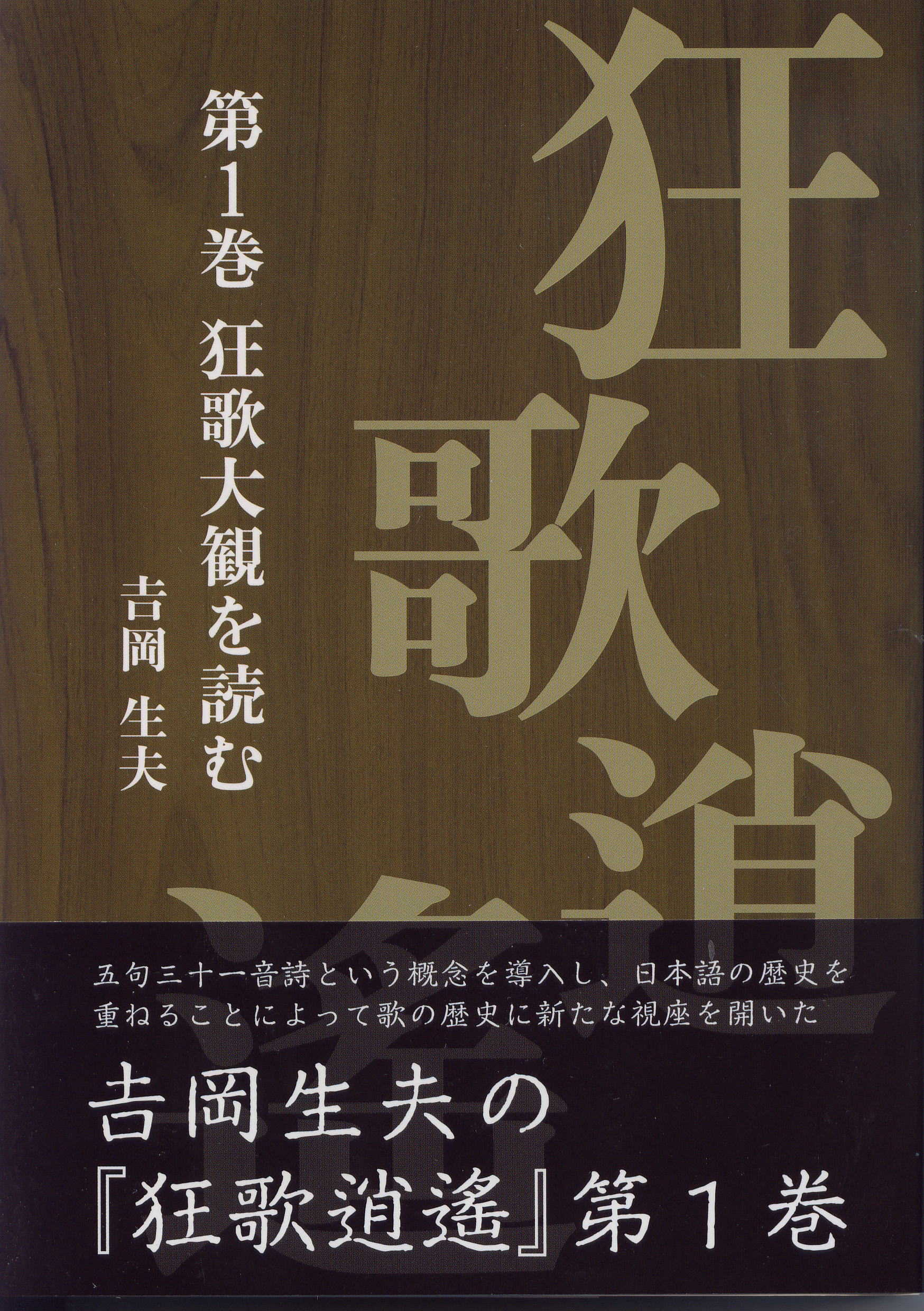| 狂歌大観を読む |
| 「狂歌逍遙 第1巻 狂歌大観を読む(1)」より続く |
| 第101回 大団(8) |
きりしやむとまはした帯のむすびめもあまりにさむき衣がへかな 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団六』、作品は元禄九年から十年の二八七首である。掲出歌は詞書に「更衣 さむかりければ」とある。元禄九年四月一日、新暦なら五月一日である。初句は「きりっ」「しゃん」か。乱れのないさまが三句に集中するが、気合を入れても寒いことに変わりはない。
一にたはら二にはにつこり三に酒大黒まい年かくお出(で)あれ
見にゆかんむまにくらをけさくらがりはなふみちらすあとはおしけれど
乗物の上下の者は歌人にてなかなる我にはぢをかかする
一首目の詞書は「又お悦猶久方のつきせじなと有(り)し返し」である。初句は「一に俵」だろう。これより前の作品の詞書は「又御加増が毎年参る福太夫と有(り)し返し」であるが軽口の応酬と読む。『日本古典文学大辞典』(岩波書店)では「寄合を勤めた」とあるが寄合とは無役である。二首目の詞書は「閏二月廿一日に下屋敷より初花をくりければ」とある。先の続きであるが寄合は三千石以上の者である。石高からいけば小普請に属する月洞軒が寄合に入るには家格や時代といった別の事情によるのだろう。下屋敷と馬が登場する珍しい例である。三首目は詞書に「駕籠かき歌物語し侍りけるに」とある。二句「上下」は「前後」の意であろう。月洞軒は元禄十年八月中旬から約一ヶ月、熱海に出かけている。知行地であったと思われるが、その途次の作品である。しかし普段の生活は江戸上屋敷、そこでは物と歌がセットになった贈答で明け暮れる、まるでそれが仕事のような『大団』なのだ。
火事におふて雪を見るさへうらめしや水にことかかぬふじと思へば
かりほにはあらでもとまをやねにあらみわが火事ごやの雨ふせぎせり
ちちつくはひと夜のふくる迄御ざれかしうづらの床のあれたいほりへ
とまぶきのこやのすがきのしたひへに尻から風がさそふすいこへ
一首目は詞書「火事の後ふじを見て」。元禄十年十月十七日に上屋敷が類火に遭っている。〈やれ火事よのけやはいはいはいはいといふまに跡はこはいにぞなる〉といった案配である。結句「こはい」は「粉灰」。いつもにもまして富士がよく見えたのだ。二首目の詞書は「雨もり迷惑故とまにてやねをふきて」、下屋敷に移ることはなかったらしい。初句「かりほ」は「仮庵」、二句「とま(苫)」は菅や茅で編んだ筵。三句「粗み」はミ語法で「粗く(敷いたので)」だろう。三首目は詞書「去(る)かたへうつらもち送(る)とて」。初句七音は鶉の鳴き声「チチックヮイと」、三句は「御座れかし」(おいでになって下さい)。四句「鶉の床」でむさ苦しい寝所の喩え。そのあとも「直重方へ大こん送(る)とて」だから驚くほかない。四首目は「題しらす」。二句の「簀搔き」は竹や葦の簀で張った床。結句「すいこ」は「酔狂」(「すいきょう」の音変化)と解した。このような状況下でも物と歌の贈答は止まないのである。
|
| 第102回 大団(9) |
からかさのさしてはぬれぬものながらひたすら雨の音羽町かな 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団七』、元禄十年から十六年の作品四二七首を収める。掲出歌は詞書「洞雲寺の前にて雨に逢(う)て」。初句は「唐傘の」。二句の「さして」は副詞、あとに打ち消しの語を伴って「それほど」「たいして」、これに傘を「さして」を掛けた。四句の「雨の」ここから句またがりである。二句の「さして」も巧みだが「雨の音羽町」から雨の音が聞こえてくる。
初声はせんずりこゑかしはがれて内所の庭にきなく鶯
けつこうなみどりのそらのはるていすたまのうてなぞ花もあるへい
つまごめにつくりならべし新宅はいよいよ爰(ここ)に八雲たつ也
神も我も爰(ここ)にいなりのみやれただ女房子むまこ子孫繁昌
一首目は詞書「十日の朝鶯をききて」。二句は「千摺り声か」、男が自慰をするときの声で三句「嗄れて」となる。四句「内所」は表向きでない所、また秘密の意を掛ける。二首目は詞書に「玄蕃かたよりみどりはるていすあるへい送(ら)けれはかく云(ひ)やりける」。確認できたのは「有平」だけであるが「みどり」「はるていす」も菓子であろう。名を詠み込んで謝意とした。〈結構な碧の空の春でいす玉の台ぞ花もあるべい〉か。三首目の詞書「奥の新宅出来しほどに廿五日わたましして」。「わたまし(移徙)」は引っ越し、本歌は〈八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣を〉(『古事記』)。四首目の詞書は「元禄十一年九月四日稲荷の宮建立して」。邸内に祠を建てたのである。二句から三句は「稲荷の宮」、これに三句の「みやれ」(見やれ)を重ねた。四句「むまこ」(むまご・うまご)は孫のこと。
うらめしの人のほむらに家こがす思ひしらずやおもひしりをれ
御不自由はたがいはずともすい風呂のかまへてあすはまち入(る)ぞ君
もつともだ我屋へがきよつまも子もまこひこやしや子かんなぼうしを
ふびんやな土蔵のすみのやけ坊主かんがよふても酒はあるまひ
一首目は詞書「去年火事に逢(ひ)ける時石川宗八無沙汰せられてことし宗八火事にあはれければかく云(ひ)やりける」。初句は口語「うらめしい」の語幹用法である。相当に変だ。二首目は詞書「野州水風呂入(り)に来(た)らんと云(ひ)こされければ呼びにやるとてかくなむ」。「水風呂(すいふろ)」は蒸し風呂などに対して水から湧かす風呂。これに「綏撫(すいぶ)」(慰めいたわること)を掛けた。三首目は詞書「十六日おもて移徙賀」。奥に遅れること三ヶ月である。二句「がき」は「牙旗」(大将旗)で八重垣を効かした。三四句は「妻も子も孫彦玄孫」で結句は「茅茨(ぼうし)剪らず采椽(さいてん)削らず」(質素な住居)から垂木を削り(鉋)、茅茨を剪れ。四首目は詞書「日輪寺類火に逢(ひ)て焼(け)残(り)し土蔵の角に住(ま)ふて居られけるに酒をくるとて色々おどけたる前書して」。四句の「かん」に「燗」と五臓の「肝」を掛けた。
|
| 第103回 大団(10) |
はや今宵年も十三ねんごろに月の夜ねぶつ手向(け)申(す)ぞ 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団七』を続ける。掲出歌は詞書に「八幡豊蔵坊十三回忌追善名号書(き)て手向(け)て」とある。二句から三句「年も十三ねん」は十三回忌と元禄十三年が重なることをいう。また「ねんごろ」は「懇ろ」である。かつて「弟子も弟子たぐひあらじの歌の弟子」を自負した月洞軒が迎えた十三回忌であるが、ここで再び鯛屋貞柳を思い出したい。元禄六(一六九三)年に月洞軒の逆鱗に触れた『八幡拾遺』のその後である。貞柳は月洞軒の没後、享保十四(一七二九)年に「鳩の杖」と改題して刊行を図るが実現しなかった。これを託された弟子の秋園斎米都は宝暦四(一七五四)年に出版を企てるが頓挫、その子青簟舎都真によって実現したのが天明七(一七八七)年の『狂歌鳩杖集』である。三代と四度の試み、およそ百年の志を傍らに置くとき月洞軒の「ねぶつ(念仏)」はいかにも空しく響くのである。
あははんとわらひて福はいりまめに鬼めはしりのあなうたれゆく
けふすでに春の日数もつきがねの又来年もこんとひびきて
顔に疔てうずつかはで物くへばくちもなまぐさ鬚もばさらだ
一首目の詞書は「節分」。初句「あははん」から連想するのは阿多福の面である。鬼の打たれるのは「尻の穴」とも読めるが「後(しり)の」に感動詞「あな」で頭を抱えて退散する図が思われる。二首目の詞書は「三月尽」。二句から三句「春の日数も尽き」と三句「撞き鐘」が「つき」二音を共有する。三句から四句は「又来年も来ん」と句またがりで「来ん」が強調される。それに鐘の音「こん」の実景で決めた。三首目の詞書は「又」、その前が「顔に疔出来て痛ければ」。二句「てうず」は「手水(てうづ)」、結句「ばさら(婆娑羅)」は放恣なさまを云う。鬚を剃れないのだ。疔は汗腺または皮脂腺が化膿してできる腫れ物である。
はねつくははごいたゐけな春遊(び)祝ふしるしの歳暮にて候
御しやうくはんさうらへかしといはぬ也さしても花の見事ならねば
むさしのの末広がりにはるかすみたてた烏帽子と見るふじの山
一首目は詞書「孫むすめ共の方へ歳暮をくるとて」。二句は歳暮の「羽子板」と孫の「いたいけな」が「いた」二音を共有して収まっている。元禄十二年、月洞軒は三十九歳である。翌年には「具足の餅祝(ひ)て」の題で〈ことし猶目出度(く)春のたつがしらひとに愚息のもちひらるれば〉があり、四十の賀では詞書に「妻子連(れ)子一家集(まり)て」とある。妻は再婚であったらしい。二首目の詞書は「直重方へ萱草を送るとて」。初句は「御賞翫」、庭で咲かせたのだろう。技巧とてない、率直な詠みぶりが印象に残る。三首目は「富士三首」の一首。三句「春霞」で切れる。末広がりの武蔵野台地に霞が棚引いている。そしてその彼方に富士山は烏帽子を立てたようだというのである。「春霞」は「立つ」の枕詞である。
|
| 第104回 春駒狂歌集 |
風のたより匂(ひ)ををくる梅の花あるしるすても春を忘れぬ 藤本由己(『春駒狂歌集』)
『春駒狂歌集』に移る。著者の藤本由己(一六四七~一七二六)、春駒翁は京都の生まれ。儒学と医術を学び、貞享(一六八四~一六八八)の末頃から水戸家に仕え、宝永(一七〇四~一七一一)の末頃から医師として柳沢家に仕えた。江戸駒込の藩邸に勤仕したが享保九(一七二四)年、主家の移封に従って大和郡山に転じた。『春駒狂歌集』は正徳三(一七一三)年の刊、一二五首を収める。掲出歌は詞書に「甲州へまかりける人の留守に梅の花さけるを紙に包(み)てそのうへに書(き)つく」とある。吉保または吉里が甲府藩主の頃であろう。由己にも『甲州紀行狂歌』(『狂歌大観』所収)がある。一首は菅原道真の辞世〈東風吹かばにほひおこせよ梅の花主なしとて春を忘るな〉(『拾遺和歌集』一〇〇六)の換骨奪胎である。
なお豊臣秀吉の御伽衆として著名な大村由己(一五三六?~一五九六)がいるので注意を要する。『狂歌大観』(本篇)では『古今夷曲集』に三首、『後撰夷曲集』に三首、計六首が「法橋由己」で登場する。第二巻の『参考篇』には『醒睡笑』に「由己」で一首、『古今狂歌仙』に「法橋由己」で一首が登場する。大阪天満宮の別当、法橋は僧位。後に法眼となる。
鶯がいまたなかぬと申(す)とも梅さへさかはやかて来い来い
おそは衆打(ち)かたらひて是からは花見にいざやよそへでんがく
花ならは散(る)と申さん吉野紙すきとをりてや螢みだるる
一首目は掲出歌の隣に並んでいる。梅の花が咲いたら自ずから鶯はやって来る。その意に花札の「こいこい」を掛けたところが面白い。二首目は詞書に「水戸黄門公御庭の花見にそばでんがく出(で)けれは是に付(け)て狂歌をと中山備前守すすめけれは」とある。初句に「そば」、結句に「でんがく」が隠れもない。三首目は詞書に「螢を吉野紙に包(み)て奉るとて」とある。花は吉野の縁語、吉野紙は薄いのが特色である。この隣に〈日はくるる人にとらるるつつまるる又はなたるる螢みたるる〉と「る」が十一回登場する歌が並ぶ。
駒込や風の手づなの一通りかけをのつたる夕立の空
ひかひかと草葉に露そ置(き)そむる秋にあふきの銀かなめかも
年に一度おあひなされてぬる数はいくつときかまほし合の空
一首目は詞書に「駒込にて夕立を」とある。初句切れで「駒(馬)」は褐色に覆われた四句「かけ(鹿毛)」、乗ったのは結句「夕立の空」、「手づな(手綱)」は二句の「風」である。二首目の題は「初秋」。初句「ひかひか」は光り輝くさま、草葉の露が扇の骨を留める銀の要のようだという。三句「置き初むる」の「初」と四句の「秋」で題の「初秋」となる。三首目の題は「七夕」。三句「寝る数」は性行為の回数を云い、下句の「聞かまほし」は「聞きたい」。その助動詞「まほし」を分断して「ほし」を上下で共有したところが巧みである。
|
| 第105回 続春駒狂歌集 |
ひろい江戸引(く)手あまたのその中につつてんとはやるいをぬけ舟 藤本由己(『続春駒狂歌集』)
『続春駒狂歌集』は六十六首、巻末に「享保六丑仲秋」とある。一七二一年、七十代の由己である。掲出歌は「薩摩外記脇をかたる右源次出世太平記語(り)しに、鳥羽屋三右衛門三味線曲引(き)いたしけるを、仰(せ)にて」で始まり、「盃をばちにして」「しやくしにて」の次「ちやわんにて曲引(き)」の歌。四句は擬音に「鳥羽屋」弱く「流行(る)」、しかし「る」の帰属は結句で「類を抜け」これに「抜け船」(役目に定まっている船を他の用に使うこと。またその船)を重ねて曲弾きの比喩とした。「仰(せ)」とあるのは御前様か。
ふるの蓑唐人笠てちやるめいらふく瀟湘の夜のあめうり
暮(れ)かかる江にふらすこのちんたには天さへ雪の花にええりや
高つきの盆のあしへに落(つ)るなり客たちあさる菓子の落鳫
永き夜もそらたきしめて香炉峯すたれあけやの秋の月影
一首目の題は「瀟湘夜雨」。中国の瀟湘八景の狂歌版である。三句はチャルメラ。結句「飴(雨)売り」、物の本によると唐人飴の登場は江戸後期とあるが、すでに見られたわけだ。二首目は「江天暮雪」。二句はフラスコボトル、三句「チンタ」は赤葡萄酒で夕焼けに染まる入江の比喩とした。結句「ええりや」は「ゑふ(酔ふ)」の已然形に完了の助動詞「り」が接続、これに疑問の助詞「や」と解した。三首目は「平砂落鳫」。初句は「高坏の」。二句は「盆の蘆辺」、菓子の「落鳫」と鳥の「落鳫」で見立ての一首である。四首目は「吉原八景」の一首目で「揚屋秋月」。二句は「空薫きしめて」、三句以下は白居易の「香炉峰の雪は簾をかかげてみる」に拠りつつ「揚屋」を入れた。一中節の「吉原八景」成立は遙か後年である。
これはなむめうたん柿のふうみよくうまいにたれもほれげきやうかな
はいれうの味はわるいそさけを柿にとりかへられてこれはしぶしぶ
元日はうしの角文字つきぬ世のすぐなる文字の御代そめてたき
花はたた目に見たはかり是は又はにあぢはひし吉野みそかな
一首目は詞書「めうたんといふ柿拝領いたして」。上下句に「なむめう/ほれげきやう」。「なむ」は係り助詞、句またがりで「むめ(梅)」、結句「惚れ」とロールシャッハテストのようだ。二首目の詞書は「鮭のいを拝領のはつを間違(ひ)にて柿をはいれういたしけれは」。今度は結句のとおり「渋々」、こんなこともあったのだ。三首目の詞書は「丑の年いの元日なりけれ(ば)」。二句「牛の角文字」は「い」で「い(亥)」(歴史的仮名遣いは「ゐ」)、三句「つきぬ」は「尽きぬ」に角で「突きぬ」を掛けた。四句「すぐなる文字」は「し」、格助詞「の」は比喩を表す。四首目の詞書は「御前様より吉野味噌といふはいれういたして読(み)て奉る」とある。四句「口」ではなく「歯(葉)」にしたのは吉野の「花」を意識した。
|
| 第106回 甚久法師狂歌集 |
つゐと立(つ)その日くらしの身は軽しおもむくかたにつくつく法師 甚久法師(『甚久法師狂歌集』)
『甚久法師狂歌集』は一七五首を収録、『日本古典文学大辞典』(岩波書店)によると享保七(一七二二)年の刊で「四十歳頃出家、江戸に行き豊前中津に下り、後、小倉の法華宗の寺に住し、享保六年三月、七十四歳で没した」とある。掲出歌は詞書に「玉峰和尚甚久か像を絵に書して讃をせよと有(る)折ふし日くらし鳴(き)て立(ち)けるを即(ち)我(が)身になそらへ」とある。結句は「着く着く」、一所不住、墨染の狂歌人であったらしい。
めくり来てさらりさらりと新玉の数珠半分とおないとしかな
なき人の三七二十一日はむかしといへる文字によめけり
一位二位三位しゐたの五位鷺は鯲(どじよう)みかけてくらひにそつく
月影はやとるまもなく汲(み)こほしせはしき淀の水車かな
一首目の詞書は「五十四歳旦」。三句「新玉」は正月、また数珠の縁語でもある。その数珠の玉は煩悩の数と同じ百八個、その半分の五十四と同い年だというのである。二首目は詞書に「相しりたる人死して三七日に」。掛け算で三七、二十一日。二十は横一に縦二(「廿」は俗字)、これに「一」を足して「日」を置くと「昔」になる。法要の際に求められたものか。三首目は詞書に「椎田にて鷺の多く集(ま)るを見て」。旧椎田町(現築上町)は東に豊前市と接している。「椎」を同音の位階「四位」に掛けた。結句「食らひにぞ付く」は「位にぞ付く」でもある。四首目は詞書「水車に月と云(ふ)題にて」。結句「淀」は京都市伏見区の地名、淀城には水を取り入れるための大きな水車があった。それを歌ったものと思われる。
なき人の姿を見れは阿弥陀堂けふはちやかまのふた七日なり
とんてから蓮のみとせになる玉は彼岸の人にあたりこそすれ
木のはしのおれか姿を写し絵にかきたてぼうと人やみるらん
右左ともへのことく廻れともささいのふたのとれにくき世や
一首目は詞書「西一鴎先生死去二七日斎に行(き)常に秘蔵の茶釜阿弥陀堂にて茶のありけれは」。秘蔵の茶釜に故人を偲ぶ、それが二句「見れば」なのだろう。結句「二七日」に茶釜の「蓋」を掛けた。二首目は詞書「ある人の妻三年忌彼岸に当(た)る」。成句に「蓮の実の飛び出たよう」があるが、飛んだ蓮の実に「三年(実とせ)」の意を重ねた。下句は「蓮の実が彼岸の人に当たる」に「(三年に)当たる」の意を重ねた。三首目は詞書に「ある人甚久姿を絵に書(き)讃を望(み)しに」。初句「木の端」は木の切れ端、転じて役に立たないもの。四句「ぼう」は「茫」(ぼんやり)に「棒」を掛けた。四首目は詞書に「ある人の云(は)る爰かしこと暮(ら)し心安からんとそ」。然り、では詰まらない。返し方の妙が挨拶歌の命である。二句は「ともへ(巴)のごとく」、四句「さざい」は「さざえ」の音変化である。
|
| 第107回 家つと |
百人一首にどうありとても元日のあかつきばかりよきものはなし 油煙斎貞柳(『家つと』)
油煙斎貞柳の家集『家つと』は享保十四(一七二九)年の刊行、貞柳七十六歳であった。収録歌数は二三九首。門下三千人、高弟に栗柯亭木端(大阪)、芥川貞佐(広島)、秋園斎米都・永日庵其律(名古屋)がいる。掲出歌は「歳旦」二首目の作品である。初二句、具体的には壬生忠岑の〈有明けのつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし〉だろう。百人一首がカルタとして正月の遊びになるのは江戸時代以降である。なお初句は七音である。
みそしあまりひとつの春になりにけり守らせたまへいつも八重垣
年の名も神にねかひの絵馬なれは誰も皆令満足(かいりようまんぞく)のはる
みかんかうしたいたいところの名主そと髪(ひげ)くひそらしちといせいゑび
初はるは目出たき本のごぼう様おひげのちりをとりもこそすれ
一首目の題は「三十一になりける歳」。結句の「いつも」は副詞の「何時も」であり、名詞の「出雲」だろう。後者は〈八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣〉に拠る。前者は四句と関連するが家内安全商売繁盛であろう。二首目の題は「丙午の歳」。二句から三句に「ひのえま」(ひのえうま)が隠れている。四句から五句の「皆令満足」は仏が慈悲心で衆生の願いをすべて満足させること。絵馬を奉納するのは祈願または報謝のためである。三首目は「酉の歳」の作らしい。初句は「蜜柑柑子」、二句は「橙(代々)ところの」、四句は「髪(ひげ)首反らし」、結句は「伊勢海老」の「伊勢」に「威勢」を掛けた。二句「だいだい」が転換点であった。四首目は題詞に「八幡滝本坊に賜りし牛房をひげをとりてにるとて」とある。二句に「たき(滝)本」、三句に「ごぼう(牛蒡・御坊)様」が隠れている。
梅はいかか思ふもしらす御懇意は初瀬山々香(か)に匂ひけり
冬もよし春きくもよし鶯のほうほけきやうは勝劣(しようれつ)そなき
西方に浄土の春はありといへと花見て千代もこちやひかし山
かしこきもかしこからぬも花に来てほしがるものは酒よ肴よ
一首目は題詞に「はつせ山小池の寺中より貫之の梅三枝タ給(は)り歌をとありけれは」とある。『古今和歌集』の〈ひとはいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける〉(四二)を受けている。初句「ひと」が「梅」になっている。二首目の題は「鶯」。日蓮宗に法華経の後半の本門が優れ前半の迹門が劣ると説く勝劣派と勝劣はないと説く一致派がある。これを下敷きとした。三首目の題は「花」。上句は死んでからいく西方浄土、それに対して下句は生者で賑わう京都は東山の桜である。結句の「こちや」(「こちは」の音変化)が猥雑で臨場感がある。四首目は三首目に続く作品である。彼岸よりも此岸そして花の下では賢い人たちも賢くない人たちも、相対化されて季節に酔っている。そんな浮世の姿が好もしい。
|
| 第108回 家つと(2) |
音にきく車返しの花の下は心にのりて行(く)そわつらふ 油煙斎貞柳(『家つと』)
『家つと』の続きで掲出歌の題は「住吉にて」。二句は住吉大社の近くにあった「車返しの桜」である。後醍醐天皇がその美しさに車を引き返させたといわれる住吉の名勝である。それが初句の「音にきく」、三句「のりて」は車の縁語、心と別に体は人混みでなかなか進まない。また〈住吉や車返しの花見とて袖引(く)つれも人そととろく〉。結句「轟く」は誘った連れも人も期待に胸がどきどきする、それほど広く世に知られていた、の両義に拠った。
節供とて祝ふ言葉もとりとりのももさえづりや花にやなぎに
かしましや此(の)里過(ぎ)よほとときすと思ふほとに一度ききたや
祇園会やはやしの鐘の七日とてしやぎりしきりに雨そふりける
夕立の雨のふる夜もふらぬ夜もかみなりさわぐ紙帳侘しき
一首目の題は「上巳」、桃の節句である。三句は「取り取り」に「鳥鳥」を掛ける。四句は「百囀り」の「百」に「桃」を掛ける。結句、桃も柳も上巳の花であった。二首目は題詞に「山崎宗鑑のむかしを思ひ出(で)て」。『狂歌五十人一首』(『狂歌大観』第二巻『参考篇』所収)に〈かしましや此(の)里過(ぎ)よほととぎすみやこのうつけいかに待(つ)らん〉がある。「うつけ」は「虚け」、痛快である。三首目の題詞は「六月七日大雨ふりけれは」。二句「はやし」は「囃子」に山鉾の林立する様を掛ける。四句は音の似た「しゃぎり」(ねり物の行列で奏する囃子)と「頻り」、加えて「しゃぎり」と音の似る縁語「車軸」(太い雨、大雨の降ること)を響かせているだろう。四首目は題詞に「はにふの小家に紙帳を釣(り)けるを見て」。粗末な家で蚊帳も紙製だから「紙鳴り騒ぐ」、これに「雷騒ぐ」を掛けた。
秋たちて幾(いく)日あらねと朝さむこさる小袖かさはや七夕の空
歌のさまふつつかなれは織女(たなばた)に手向(け)んことも梶のはもしや
七夕のすまふとる夜と下帯をむかしのすいが手向(け)こそすれ
星さまに着(き)ならし衣慮外(りよがい)なれとしきしのあれは手向(け)もやせん
一首目の題は「七夕」。三句は「寒御座る」、しかし「朝」の帰属がはっきりしない。字余りでの説明も不可で破調の前駆と見られる。四句「ばや」は願望で「貸したいものだ」。以下「七夕」が続く。二首目の結句「はもし(は文字)」は恥ずかしいこと。その上の「梶」は秋に着用する襲の色目の名、庶民ではなく貴族の子女であろう、また梶の葉姫は織女星の異称でもある。三首目の二句、年に一度逢ってすることが「相撲」とは、さすがは四句「昔の粋」である。三句「下帯」は牽牛星なら褌、織女星なら腰巻きだろう。下紐ではない。四首目、二句の「着慣衣(きならしごろも)」は着なれた衣、四句「しきし(色紙)のあれば」は和歌を書く厚紙の色紙ではない。着物の弱った部分に裏打ちをする布地があれば、となる。
|
| 第109回 家つと(3) |
火(の)用心の声あはれなりさよしくれぬれて夜番のひとり行(く)らん 油煙斎貞柳(『家つと』)
掲出歌は題詞に「風はけしき夜雨に濡(れ)て夜番の町中を廻るをねさめに聞(き)て」とある。また右肩に「本」とあるのは満意の〈ききわぶるね覚の床のさ夜時雨ふる程よりもぬるる袖かな〉(『新続古今和歌集』六一六)が思われる。時代を中世から近世へ、人物を女性から男性へ、場所を室内から室外へ移した。しかしそれなしでも読める歌である。
千金にかへぬ今宵の一輪は月のかつらの実(み)はへなるらん
されはこそ生(け)るをはなつよはなれは蟻のはふまて見ゆる月影
うろくずもうかみ出(づ)るやにこり江をいとはてすめる月の今宵は
いかなるか是いんげん豆もはなの色は抹香くさふもこさんせぬのふ
一首目の題は「八月十五夜」。初二句は蘇軾の「春宵一刻値千金」を受けた。結句の「実はえ」は月にあるという桂の「実生え」に月(桂男)の「見栄え」を掛ける。二首目の題は「男山にて」、「八月十五夜」の岩清水放生会である。この日は生きた魚や鳥を川や山に放して天下泰平を祈願した。下句は生の繁栄を祝福するかのように月が地上を照らすのだ。三首目の題は「放生川にて」。初句「うろくず」は魚、しかし「くず」の音と三句「濁り」が呼応して下句を準備する。つまり魚も月を見ようと(二句「浮かみ」は「浮かむ」(浮かぶ)の連用形)水面に顔を出すのでは、というのだ。四首目は題に「禅寺の垣のしりへにて」。初句七音は『碧巌録』(岩波文庫)の第二六則「百丈の奇特の事」に拠ろう。二句は隠元豆を伝えたという隠元(黄檗宗)の名を重ねた。一首は禅問答めかした「しりへ(後)」の会話である。
かみなりも太鼓をうつてまはりけり雨やあらしの顔見せの宵
独(ひとり)ねをせぬ夜なりとて鬼は外へ気を通してや出(で)て行(く)らん
あんずれは此(の)世は夢のかりまくら草葉の露じや玉てないもの
よし野山峯吹(く)あらしさぶけれは花を見捨(て)て帰りこそすれ
一首目の題は「霜月初(め)の頃かみなり雨さへ降(り)けれは」。霜月は十一月、顔見世興行の月である。雷神が一番太鼓を鳴らしているという見立てである。二首目の題は「除夜」。旧暦では立春が新年の元旦、節分は大晦日という背景がある。したがって姫始めに遠慮して鬼が出て行くというのである。三首目は題「母の一周忌追善に夏九十日狂歌をよみける」の一首(『銀葉夷歌集』では「亡母孝養の一夏九十首の中に」とある。一日に一首で計九十首か)。三句は仮寝のこと、下句は遍照の〈蓮葉の濁りに染まぬ心もてなにかは露を玉とあざむく〉(『新古今和歌集』一六五)を念頭に置くのだろう。四首目は題詞に「嵐三郎四郎其(の)外白人なと来て乱酒になりけれは其(の)座を抜けて帰るとて」とある。「白人」は私娼をいう。嵐三郎四郎は歌舞伎役者、二句から三句に名前を効かせるが辟易しての退散と思われる。
|
| 第110回 家つと(4) |
花と見る梢を風にさそはれてずぼろぼうずになるや木男 油煙斎貞柳(『家つと』)
掲出歌は題詞「娘を先立て悲(し)ひのあまりかしらをおろして」。四句「ずぼろぼうず」は丸坊主に剃った頭、またそのような人。結句の「木男」は無骨な男。一首は娘を守ってやれなかった自身の姿を花の季節の終わった木に擬えた。これを含む「無常」には「娘の十三回忌」の題で〈さされ石の千代に八千代とそたてしに卒塔婆に苔の娘はかなや〉がある。
百合(の)花ちり行(く)秋のはつ風にさながら夢の世とそなをみん
いろいろの膳部をなしてとふらはん春やむかしの蕗のしうとめ
世の中よ何としやうぎのこまりものはるもよしなやすててつまらず
祖父(ぢい)は山へしはしかほとに身は老(い)てむかしむかしの咄(はなし)恋しき
一首目は題詞「一家の女中ゆりはつさななをみん過(ぎ)しむかしをおもひ出(で)て」。題詞の「はつ(果つ)」は歌では「はつ(初)」、「なを(汝を)」は「猶」としても、わからないのが「さな」である。脱字がないものとして「さ」も「な」も感動詞としておく。二首目は題詞「先妻母の十三回忌」。結句は蕗の薹の別名、蕗の薹は、蕗の若い花茎。四句、人生なら春の季節の妻とその母の若々しい面影が過ぎる。三首目は題詞「述懐」。二句に「将棋」、三句に「駒」を隠す。また下句の「張る」も「捨てて」も将棋の縁語である。三句の「よしなや」は形容詞「由無し」の語幹に詠嘆の「や」である。四首目は題詞「稀年(きねん)の齢(よわい)になりて」(「古希」と思われる)。二句「しは」に「柴」を掛けて桃太郎を連想させる。そんな昔話を読み聞かせられた幼い頃は、あっという間に過ぎて、老人の私は昔のことが懐かしい。
金銀はあるも猶よしなしとても人間万事宗桂かこま
くらま山をあちらむかでぞひらひけりこれそ毘沙門天のあたへか
滝の音はひいふうみのおとんとんとん手まりのやうな玉そちりける
日盛(り)は暑き峠の苦しさに昼にさがりて風を枩坂
一首目は「稀年の齢になりて」二首中二首目。結句は「塞翁が馬」を言い換えた。「宗桂」は大橋宗桂(そうけい)(一五五五~一六三四)、将棋の名人だから「馬」ではなくて「駒」となる。二首目は題詞に「鞍馬山開帳に詣(り)けるに九折(つづらおり)にて百足を拾ひて」。初句は場所と周囲の暗さを云う。二句は「あちら向かでぞ」に「百足」を隠す。結句「あたへ」は「めぐみ」。「ひらひけり」とあるが、百足は毘沙門天の使いで目出度いものとされた。三首目の題詞は「箕面山に詣(り)し時」。二句に「箕面」を詠み込んだ。箕面は古刹に滝そして紅葉の名所である。四首目は題詞「帰るさに」。初句三句四句結句のサ音が要所を締めている。この前に「南都へ行(く)とてくらかり峠にて」の題詞で〈駕籠舁(かごかき)の心くらがり峠にて天目酒にまよひぬるかな〉がある。天目酒(茶碗酒)の迷惑を被っての帰路は風が出るのを待っている。
|
| 第111回 家つと(5) |
月ならで雲のうへまてすみのほるこれはいかなるゆゑんなるらん 油煙斎貞柳(『家つと』)
掲出歌は題詞「南都松井和泉といへる油煙所の大形の墨上つかたにも御上覧のよし風聞ありけれは」。「上つかた」は二句「雲のうへ」の人、三句「すみ」は「澄み」に「墨」を掛け、結句「ゆゑん」は「由縁」に「油煙」を掛ける。重さ二十斤余の墨であった。このあと題詞「是はいかなるゆゑんなるらんと読(め)るうたを京童の風聞さまさまあると聞(き)て」で二首続く。内一首は〈油煙斎と世にうたはるるころもきぬ心をすみにそめまほしさよ〉、三句は油煙斎という「衣着ぬ」だろう、享保十一(一七二六)年、貞柳は七十三歳だった。
ありま山いなといへともささひとつあがれあがれと湯女か一ふし
夜船にて苫(とま)よりのそく男山月のおかほのちよつとほの字て
范蠡(はんれい)とさかさまなれや鯊釣(り)に小船漕(ぎ)出(で)て喰ふはれいはん
かほりさへよし野たはこの夕けふりはなのあたりを立(ち)のほるかな
一首目の題詞は「有馬にて」。有馬山は歌枕、途次にある猪名野も歌枕、笹の名所であった。猪名野の猪名で二句の「いな(否)」は初句の「あり(有)」と対句表現となる。三句「ささ」は酒のこと、また人を促すときの「ささ」で結句の「一ふし」に掛かる。二首目の題詞は「上京の折に」。船は天井を苫で覆った三十石船。「苫」は菅や茅で編むが目が粗い。そこから覗く男山と男山に「ほの字」の月の顔、見立ての一首である。三首目は題詞「我(が)身七十に及ふまて何の功もなくいたつらにあかしくらしなにはの事もいさしら浪の舟遊ひに行(き)て」。初句の「范蠡」は別名を陶朱。中国は春秋時代、越の功臣にして金満家。結句「れいはん」は「冷飯」となる。四首目の題詞は「和州よりたばこをもらひて礼状の奥に」。「和州」は「大和」の異称、定番の「吉野」に「良し」を、「花」に「鼻」を掛けた挨拶である。
音にのみ聞(く)胡鬼(こぎ)(の)子をつくつくとめの正月をけふこそはすれ
あづさ弓ひくではないが此(の)しばゐめつたまとりにあたりこそすれ
身を捨(て)てよしやみかんのかわ衣六君子(りつくんし)にも交はらぬかも
一首目は題詞に「甲州の人胡鬼の子を持参ありて歌をとあるに」。「胡鬼の子」は羽根突きの羽根、別にツクバネの異名またその実を云うが、この歌の場合は後者である。果実が羽根に似ているのだ。三句は「つくづく」また羽子を「つくつく」、四句は「目(女)の正月」と解した。二首目は題詞「いづもの掾浄留利芝居を見て」。「いづもの掾」とは竹田出雲であろう。初句は「ひく」に掛かる枕詞、四句「めつたまとり」は賭的(かけまと)の「滅多的(めつたまと)」と見事な鳥「真鳥」の合成語が思われる。いずれも弓の縁語である。三首目の題詞は「医者隠居せしに」。二句の「よしや」までは隠居を指し、今一つは「みかん」以下に係る。中国宋代の六君子と交わらぬ、とは六君子湯の世話にならないこと。蜜柑の皮は組成成分の一つであった。
|
| 第112回 家つと(6) |
四つ橋に杜若(かきつばた)こそあらすとも人にみせはやほりの菖蒲(あやめ)を 油煙斎貞柳(『家つと』)
掲出歌は題詞に「大坂はなにはいなかにて名所なしとこころなき人の笑ひけれは」とある。初句「四つ橋」は現存しないが大坂の名所であった。すると結句「ほり」は「道頓堀」で、これも名所だから成句「何れ菖蒲か杜若」が成り立つ。次に「四つ橋」に「杜若」はないが「道頓堀」には見せたい「菖蒲」がある、とは何か。道頓堀と云えば芝居小屋である。「菖蒲」とは上方が生んだ稀代の女形、初代の芳沢あやめ(一六七三~一七二九)であろう。
下さるる鯛そとしるを相伴もああうまあんまはらをなてけり
飲(む)からに冬のさむさも忘られて春の心をあら玉子酒
にほふてふ丁子しやかうはいらねともしたたるささる夫婦丸哉
此(の)かいにたくひあらしなくみてしる酒も満(ち)干の玉の盃
一首目の題詞は「岡村道有去(る)御方より生鯛を下されしとて友とする人一人ふたりを振舞の座にて」。四句は「ああ美味」、これに音を似せつつ「あん摩」だから結句は「腹を撫でけり」となる。二首目の題詞は「寒中見舞に玉子を送られし人の許へ」。結句の「あら」を感動詞として読むこともできるし、接頭語なら新鮮な「玉子」、「あら玉」なら春に係る枕詞ともなる。三首目の題詞は「夫婦(みようと)丸に」、補足して「大坂町中を夫婦つれにてありく売薬ありよんてめうと丸といふ」。二句は「丁子や麝香は」、四句は「甘えたような、そんな」と解した。四首目の題詞は「高麗橋さめや多介より貝の盃に名をつけ歌を読(め)とたのまれ下戸ならぬこそ拾ふかひあるさかつきを見て」。四句「満(ち)干」は酒のすすむ様を云う。
おしあふは象無頼なる見物となれもしるにや鼻であしらふ
又や見ん交野(かたの)をとほる大象のはなに水ちる夏の明ほの
めつらしとはなのあたりに立(ち)よるは夏にさくらのふけんそうかな
優曇華とおもふ斗(ばかり)に大象のはな待(ち)えたることし嬉しや
右は「享保十四四月長崎より大象大坂に来る」七首中四首である。一首目だが、押し合っているのは見物の人、二句「象、無頼なる」で四句「なれ」は象となる。二首目は藤原俊成の〈またや見ん交野のみ野の桜狩花の雪散る春のあけぼの〉(『新古今和歌集』一一四)を本歌とする。初句の「や」は詠嘆と感動で再び見ることのない象は交野を通って京都それから江戸に向かう行程だった。三首目は桜の木を擬人化して「鼻のあたりに立(ち)よる」とした。結句「普賢象」は桜の品種、これに普賢菩薩が乗る象のイメージを託した。享保十四(一七二九)年四月一日は新暦なら四月二十八日である。四首目の初句「優曇華」の花が咲くのは仏教では三千年に一度とされる。稀なことの喩えであるが、貞柳にとっても、当時の日本人にとっても、最初にして最後の象体験だった。そのフィーバーぶりが伝わってくる。
|
| 第113回 華紅葉(1) |
月の船ひともとすすきほにあけて尾花か浪をはしるむさし野 半井卜養(『華紅葉』)
『華紅葉』の編者は万笈斎桑魚(桑名屋甚兵衛)、享保十四(一七二九)年の刊行、作品数は二七九首である。掲出歌は扉の一首である。初句は大空を渡る月の比喩、絵画的な構成で、高く伸びた一本の薄の穂を同音の帆に擬え、あとの尾花(薄)を波に見立てた。また視覚に加えて「と」「と」「す」「す」「を」「な」「な」「を」「し」「し」と同音が共鳴する。
鳥追(ひ)の諷(うた)ふ春こそめてたけれやんらたのしのせしよやばんぜう
念比になつなをくるる翁こそ一銭二銭のゑんでこそあろ
見ても又ねんじやといふて見る人は梅ぞまことにはなの兄ふん
「春」の部四二首より抄出する。一首目の作者は桴雪、題詞は「門に鳥追(ひ)の来りしせつ出入(り)の大工御祝(ひ)申(す)とありけれは」。上句は正月の門付け芸で女太夫が回って来たところ、四句「やんら」と結句「よや」は囃子詞、「せし」は「施主」のこと、「ばんぜう(「番匠」)」は大工のことである。二首目の作者は虎興、題詞は「薺を折にのせて翁来りしに」。老人は七草粥に使う薺を売りに来たのである。四句の「銭」は貨幣の単位で「文」に同じ、結句の「ゑん」は「縁」に「円」を掛ける。小判の形から「円」は「両」と同意に使われた。三首目の作者は桴雪、題詞は「思ふとちふたりみたり友なひ八軒梅より薬師の梅を見て帰るとて門を出(で)けるに東の方の枝には花咲(か)さるよしいふ人ありしかは念のため今一度見てこんといふて又一人見に行(き)しを」。「八軒」は「八軒屋」で淀川南岸の地域である。「薬師の梅」はそれを南下、玉造稲荷神社の北にあったらしい。二句の「ねんじや(念者)」には「入念な人」の意と「衆道の兄分(寵愛する側)」の意がある。下句はその後者を受ける。すなわち梅は他の花に先駆けて咲くところから「花の兄」と呼ばれた。
朝霞また春めかぬ空なれば歌人の口にかかるばかりぞ
誰もみなひたいを皺(しわ)め目をすかめ歌よみ皃の花の下(もと)かな
咲(く)花の枝に結ひし短冊はちりなん後(のち)の置(き)みやげかな
同し子の祐成(すけなり)ことは悲しますただごろごろと鳴(く)かわずかな
一首目の作者は樋口故白、題は「早春の霞」。まだ霞はかかっていない。ただ気の早い「歌人の口にかかるばかり」なのだ。二首目の作者は元信、題は「ともとち花見にまかりて」。作者も歌人、友達も歌人、いきおい花見も歌中心となる。三首目の作者は故白、題は「花のもとに」。短冊は枝に結んだ歌人の置き土産ではない。散っていく桜の置き土産なのだ、という擬人化が面白い。四首目の作者は成親、題は「蛙」。二句「祐成」は曾我祐成(一一七二~一一九三)、曾我兄弟の兄で十郎と称した。弟は時致(一一七四~一一九三)、五郎と称した。父親の仇を討ったが捕らえられて殺された。泣いているのは母親ということになる。
|
| 第114回 華紅葉(2) |
見て凉(すず)むまでこそよけれ蓮台(はちすは)にむかへられてはたまるものかは 元信(『華紅葉』)
『華紅葉』を続ける。掲出歌は「夏」の部、題詞は「蓮池に納涼して」。蓮の花は夏に咲く。蓮台はその花の形に作った仏像の台座である。但し作中主体が眺めているのは実際の蓮のため蓮台に「はちすは」のルビを振った。見立てである。結句「かは」は反語の意を表す。
夜貰ひもやめて今宵の手向(け)とや繍(つづれ)を垣(かき)にほし合の空
あすの夜はかけかよむへはまだ若しけふの今宵は丸きもち月
望月をおのぞみなれと今日はきれたこざれこんどの豆の粉の月
市中(しちゆう)とて折々汐のさし引(く)も丸くすみたる月の笑顔(えみがお)
「秋」。一首目の作者は元信、題詞は「文月七日の夜長町の裏を通りしに人にかはりて」。長町は日本橋の南九町を云う。往来が盛んで宿屋が多い。その裏通りの垣根に「つづれ(綴れ)」が干してある。襤褸、ぼろの着物に「繍」の字を当てたのは七夕の夜の見立てである。二首目の作者はももこ、題詞は「望月といふ事をよめと」。二句は「欠けか昨夜(よんべ)は」と読む。三首目も、ももこ。題詞は「今一首とのぞまれて」。三句は品切れを云い、四句「こざれ」は「御座れ」で結句は豆名月を指す。「望」に「餅」を重ねた。四首目の作者は湖流、題は「四つ橋の月」。上句では海が近いので汐の満ち干を云う。下句では橋の四角形を加えた条件下でも円く澄んだ名月を褒めた。「汐」には愛嬌の意味があるので上句は結句の布石でもある。これに四つ橋から近い新町の下級女郎の等級「汐」の揚げ代も「済み」を重ねた。
浪人となりさがる身も出世まつ心便(り)に捨(て)ぬぶどうぐ
降(り)あかりあそこやここに溜(ま)る水田ごとの月のここにやどれり
私用(しよう)をはかひてよふ来た高尾山扨も威光のつよきもみち葉
秋の田をかりほすは爺(とと)こくは嬢(かか)わら子供手につみかさねつつ
一首目の作者は成親、題は「葡萄」。二句は棚で栽培された葡萄を暗示する。秋の素材として葡萄が登場する初期作品の一つではないだろうか。表は「武道具」、云うまでもない。二首目の作者は金雨軒魚坂、題は「月」。田毎の月というが見えるのは一つである。あそこに行けばあそこで一つ、今はここにいるので「ここ」の田に月が宿っている。三首目の作者は元信、題詞は「高尾の楓見にまかりて」。二句「かひて」は「欠ひて」(「欠きて」のイ音便)、これに「かえで」の訛語「かいで」を掛けた。義理を欠いて「よふ」(「よう」で「良く」のウ音便)となる。三句は神護寺の山号、四句の「威光」はここから来ている。四首目の作者は成親、題詞は「田を刈(り)納(め)るいそかしき折から秋の田の御歌を思ひ出(で)て」。家族総出である。「御歌」とは天智天皇の〈秋の田のかりほのいほのとまをあらみわが衣手はつゆにぬれつつ〉(『後選和歌集』三〇二)、近世は『小倉百人一首』の方で知られたろう。
|
| 第115回 華紅葉(3) |
もふたりやもふたり川の百千鳥(ももちどり)波のつづみにはやしたてられ 虎興(『華紅葉』)
「羇旅」の部。掲出歌は題詞「越後へ罷(り)越(し)ける道前原長浜の間馬渡(もうたり)川にて」。名前に触発された初句「舞うたりや」(「舞ひたり」のウ音便に疑問の助詞「や」)を受けた二句、これに続く三句と三度の頭韻が軽快に響く。今の名は「うまわたりかわ」のようだ。
同しいろにあらんものから京の雪ふる里のより面白く見ゆ
けさのみはここも芳野よやあこれの花かと見れは木々の白雪
としこゆと目にはさやかに見へねとも豆の数にそ驚かれぬる
神主のおかほのいろは九こんにもたらて六こむ猩々となる
「冬」の部。一首目の作者は良安、題は「雪」。二句「ものから」は接続助詞で「のに」の意で続く。二首目の作者は成親、題は同じく「雪」。一首目と違って雪が平凡な山を花の吉野に変えたというのである。相反する二首であるが、どちらも納得できる。三首目の作者は和田忍笑、題は「せつ分」。元歌の藤原敏行〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(『古今和歌集』一六九)の四句「風の音」という聴覚を「豆の数」という視覚に変えて一目瞭然とした。四首目は「神祇」の部。作者は桴雪、題詞は「ある神主のもとへ罷りけるか酒なと出され半酔に及(び)なん比あるし秀句はなきかとありしに」。三句「九こん」は「九献」(接尾語の助数詞で九杯、これに三三九度の九献を掛ける)、四句「六こむ」は「六献」、次の「猩々」は二句「おかほのいろ」、合わせて「六根清浄」を掛けた。
銭屋なら九十六迄活(き)給へ算(かぞ)へはじめは市右衛門殿
草臥(くたび)れて行(く)足引(き)のやまと路はもろこしまても苦になりにけり
弁当はありし料理にかわらねと見し吸(ひ)筒の酒そ淋しき
酒か鳴(く)か草の中てもちんちろりとくりとききやれ鈴虫の声
一首目は「賀」の部。作者は寺田正晴、題詞「嵯峨の宿銭屋市右衛門といへる人長病平癒を賀して」。一(市)は分かる。百でないのは九六銭(くろくぜに)といって銭差に通した銭九十六文を百文とする慣行があった。これを受けた「銭屋」の因果である。二首目は「羇旅」の部。作者は良安、題はなし。二句「足引(き)の」は「山」に掛かる枕詞だが、ここでは同音の「大和路」に掛けて実感、実景とした。四句のあとに「行くような気がして」を補うと分かりやすい。ちなみに『古今和歌集』には「唐土の吉野」(一〇四九)が出てくる。三首目の作者は有赦、題詞は「京え舟にてのほるとて弁当の酒すくなかりけれは」。二句から推して船宿で下見もしくは試食をしたらしい。四首目の作者は友房、題詞は「返しにはあらて折節鈴虫のこゑかすかに聞えけれは」。初句は「酒が鳴くか」。三句は鈴虫の鳴く「ちんちろり」に酒の燗をする「銚釐(ちろり)」、四句の「とくり」は副詞の「とっくり」に「徳利」を掛けた。
|
| 第116回 華紅葉(4) |
行(き)かふる中にかかやく白人は金銀にすむ色とこそ見れ 我浩(『華紅葉』)
「恋」の部。掲出歌の題は「道頓堀にて」。三句の「白人」は近世の上方で私娼のこと、「白人(しろうと)」の音読みである。四句は「金銀(金銭の世界)に棲む」また二句と関連して「金銀に清む」、美しさが目を引いたのだろう。結句の「色」は情人の意でもある。
手をとりて心ひき見る若衆の弓の指南をかこつけにして
うちつけにささのはもしな事なから一夜(ひとよ)ねてたも根からほの字しや
玉章(たまずさ)やかみならすともくみてしれ硯の海のふかきをもひを
一首目の作者は故白、題は「寄弓恋」。ここでの「弓」は遊戯としての楊弓場が舞台だろう。二句の「ひき」は弓の縁語、今も昔も変わらない光景である。二首目の作者は友清、題は「寄笹恋」。二句の「はもし(は文字)」は恥ずかしいこと、「ささのは(笹の葉)」とはハ音を共有する。また笹の葉のような太くて短い字を笹の葉書きという。四句の「一夜」も笹の縁語「一節」と同音である。結句の「根」を含めて笹尽くし、直截な求愛表現となった。三首目の作者は古水、題は「人に文ををくるとてをくに」。初句「玉章」は手紙の美称。二句の「かみ」は「紙」だが「神ならずとも」(即ち君)という響きが四句「硯の海」から伝わる。
さらに又雪かと見れはやあ是の手きはよしのの峰の花塩
雪つもる柴の菴(いおり)のしばしばも春の時得てひらく花しほ
稀に逢(ふ)てまつくむ酒の名も高き天の川ならふたつほしませう
お盃かんたんくたきしゐられなあわ一すいとたへすさむろふ
噂あるかの絵を見れは千疋のさるとてはまた見事なりけり
「雑」の部に移る。一首目と二首目の作者は貞柳、題詞に「大坂高津難波伊織といへる人の製の花塩白妙にしほらしきさまを見て」とある。花塩とは型に入れて花の形に作った焼き塩をいう。一首目。四句「手際良し」から「吉野」を導いて花塩の賛とした。二首目。柴で屋根を葺く、そんな粗末な家にも訪れる時宜の花、これまた花塩の賛。いずれも冬の作である。三首目の作者は永井走帆、題詞は「久しく音つれざる方へまかりて天の川といへる酒をたうへて」。結句「二つ干しませう」に牽牛星と織女星の「二つ星」を掛けて単純だが嫌味のない挨拶である。四首目の作者は故白、題詞は「人のもとにて酒のあひさつに」。二句「肝胆(を)砕き」は真心を尽くす、意。「肝胆」に「邯鄲」を掛ける。三句は「強ひられな」、下句は「粟一炊と絶えず侍ふ」。邯鄲の夢では炊けなかった粟、それよりも長居しますので、どうぞお気遣いなさいませんように、といったところ。五首目の作者は我胸、題詞は「庚申堂に千疋の猿の絵馬あり見事なりと人の物語あり参りて見て」。二句「かの絵」に庚申堂の「庚(かのえ)」、四句の「さる(猿)」に同じく庚申堂の「申(さる)」の語を潜ませている。
|
| 第117回 華紅葉(5) |
ぼんなふのあかはなけれと風呂に入(る)老(い)にけるぞやへちま同前 魚坂(『華紅葉』)
「雑」の部。掲出歌の題詞は「人のつらさに老(い)を知りけるとあれと」。それに対して自問する作中人物にとって「老い」とは糸瓜同然にぶら下がっている男根であろう。性欲も淡くなった。それが初二句、「垢」と「糸瓜」は縁語、「同前」は「同然」に同じである。
同気相もとめて白き京粽笹のひと夜の舟て来たよね
君と我中たにいつもかわらすは思ひ残さん事もあらしな
風吹(け)はおきつ火の元見に廻る夜半にやきみか扨わるいなり
一首目の作者は陳蔵、題詞は「都より道喜粽をもらひて」。「道喜粽」は川端道喜(?~一五九二)に因んだ粽、その音を生かした初二句「同気相もとめて」は諺で、気の合う者は自然に寄り集まる、意。結句「よね」は「米」に「娼」(遊女)を掛けたか。また同意を求める口語の「~よね」にも聞こえる。二首目の作者は故白、題詞は「中谷顧山といふ人のもとへ」。背景は不明だが二句に「中たに」、四句「残さん」に「顧山」を詠み込んだ。三首目の作者は桴雪、題詞「人々を終日饗応して夜も半(は)あまりにいつれも御なこり申(し)ぬ程なく枕に打(ち)かたむきゆめをもむすひなんころ風はけしく吹(き)てすさましきままに興出(で)て」。『伊勢物語』二十三段の〈風吹けば沖つしら浪たつた山夜半にや君がひとりこゆらむ〉を踏まえた。男の火遊びを黙って送り出す女を「~きみか扨わるいなり」と変身させた。
けふよりは心はつとり取(り)なほし前句もよしの香りあるうち
商売を外にそなすの夜市まで世話をやかずによふはいさしやる
ゐんきよ所の新宅いわひまいらせ候目出たくかしく此(の)花むしろ
いたみあれは足にも枕するゆへにひさがしらとはそれでゆふらん
一首目の作者は幽松、題詞は「煙草屋に前句をこのみて夜を明かしたつきもうとかりしに」。「前句」は川柳へと発展する「前句付け」を云う。「たつき」は「方便」で生計のこと。二句「はつとり」は副詞の「はっと」に摂津産の「服部煙草」を効かす。四句「よしの」は「吉野煙草」で鯛屋貞柳に〈かほりさへよし野たはこの夕けふりはなのあたりを立(ち)のほるかな〉がある。二首目の作者は我拙、題詞は「古道具や子息楊弓(ようきゆう)をこのみて手代のいけむせしを聞(き)て」。二句から三句に「那須与一」を隠す。結句は「楊は射さしゃる」。助動詞「さしゃる」(なさる)は近世上方語。楊弓場では弓を射るものですよ、か。三首目の作者は良安、題詞は「ある人老母のもとへことふきにものを送るとて」。三句は「まゐらせそろ」で六音。四句は女性の手紙の末尾に添える語、結句「花むしろ(筵)」は「花茣蓙」に同じである。四首目の作者は元信、題詞は「足痛(み)て引(き)籠り居(り)ける比」。遊びとしての語源解釈であるが、少しは痛みが緩和される、もしくは軽減される気分があったろう。
|
| 第118回 華紅葉(6) |
痩(せ)猫の竈ばいりを見ならひてあたたまりつつ肥(え)ているにやん 千前(『華紅葉』)
掲出歌は「雑」「哀傷」「釈教」に続く「八瀬竈風呂の吟」最後の一首、初二句は竈猫を云う。貞富に〈釜の下に住(み)つけたりし灰猫の目か光るかとみれは埋(み)火〉(『後撰夷曲集』)があった。「竈風呂」は穴蔵状の竈で中に塩水を含ませた蓆などを敷き、余熱で蒸気を発生させた。近世、京都八瀬のものが有名であった。結句の「にやん」は愛嬌である。
留守事にたのしむものは酒ばかりたんぽのそこのこちやふり残し
雲の峰名もをそろしき丹波太郎とといにたいと泣(く)は鬼みそ
とんだ事いわねはくはぬ飛(び)たんご銭をやれもさかやれさてなあ
ひつついてはなれもやらぬめうと丸昼売(り)あるき夜はねるらん
一首目の作者は桴雪、題詞は「家内あまた遊山にまかりしあとに我ひとり留守して淋しさのあまり」。四句の「たんぽ(湯婆)」は京阪地方で「ちろり」のこと。結句「ふり残し」は「降り残す」の名詞法、そこだけ降らないかのように「湯婆」の底が空っぽなのだ。二首目の作者は含章、題詞は「丹波より太郎市といへるてつちをおき侍りて」。三句は陰暦六月頃、丹波の方角の山に立つ夕立ち雲、初句はその形容である。結句「鬼みそ」は外見に似ず気の弱いことを云う。三首目の作者は成親、題詞は「飛(び)たんごを見て」。初句は「飛団子」を売る行商人が歌を歌うこと、またきな粉の中へひねって飛ばした事を掛ける。下句は歌の一節と解した。四首目の作者は猶酔、題詞は「大坂町中を夫婦つれにて奇妙丸といふ薬をうりありくものあり夫婦つれなれは人々めうと丸といへり」。有名であったらしい。貞柳にも〈にほふてふ丁子しやかうはいらねともしたたるささる夫婦丸哉〉(『家つと』)があった。
世を捨(て)てゐんきよ火動て死なれしか若ひ内儀は庵に相違し
もみち葉の散(り)て汀の池水に浮(か)ふはのりの小船なるらん
花紅葉詠(なが)めも木々によるなれはそのよしあしの撰者万別
一首目は「哀傷」の部。作者は阿北斎(「あほくさい」か)、題詞は「老人の隠居死せると聞(き)て」。二句「ゐんきよ(隠居)」に「陰虚」(腎虚)を掛ける。「陰虚火動」で房事過多により鼓動が激しくなる病状を云う。結句は「庵」に「案」を掛けた。二首目は「釈教」の部。作者は小宮山義一、題詞は「神無月の比小原の寂光院といふにもふておほふけなくも後白河院の御製を思ひ出(で)て」(「大原」は「小原」とも書く)。御製は〈池水にみぎはのさくら散りしきてなみの花こそさかりなりけれ〉(『平家物語』)、建礼門院を訪ねた際の歌である。三首目の作者は万笈斎桑魚。『華紅葉』の編者である。題詞に「世を諷し人をそしり風俗をそこなふの言の葉は狂歌の大戒なり(略)其事のなきしるしに撰者の名をおき侍りぬ」云々とある。結句に「千差万別」を掛けた。そう、眺めもそれぞれ、これは真理である。
|
| 第119回 狂歌乗合船(1) |
切取事堅無用と立札はけにも卯の花おとし也けり 辻河春房(『狂歌乗合船』)
『狂歌乗合船』の刊行は享保十五年、著者の永井走帆(一六六一~一七三一)は書家でもあった。油煙斎貞柳の『家つと』は享保十四年の刊行だから、これに後れること一年、また走帆の没年は享保十六年だから、死の前年となる。序を書いている西山螬庵は連歌師で俳人の西山宗因(一六〇五~一六八二)の子、姻戚でもあった。掲出歌の題は「卯花」、初句から二句の「切取事堅無用」は「切り取る事堅く無用」で「無用」は禁止の意である。四句から五句の「卯の花おとし」は「卯の花縅」で鎧の縅の一、卯の花に見立てた白色の「縅」に「脅し」を掛けた。
戸障子をひらけは梅のにほやかに鼻の先にそ春は来にける
花と娘色香いつれと見わかねはふためくるひと是やいふへき
風の手や雲のねたはの一ふりに思ひきつたる夕たちの空
雨もふれ腰もふれやれしつほりとたのみますげの笠踊衆
一首目の題は「丙午のとし」、作者は辻河正順。「春」の部である。初句「戸障子」は雨戸と障子、朝を想像すればよいのだろう。四句「鼻の先」で一首が立ち上がった。二首目の題は「花見の女中を見て」、作者は走帆。「女中」は女性に対する敬称、ここでは美しく着飾った女性、若ければなおさらのこと目を奪われる。桜と女中、それに「二女狂い」なのだ。三首目の題は「白雨」、作者は走帆。初句「風の手や」は風の擬人化、二句「ねたは(寝刃)」は切れ味の鈍くなった刃、また雲の束というイメージも過ぎる。四句「き(切)つたる」は縁語である。四首目の題は「同所雨乞の踊を見て」、作者は水谷李郷。「同所」とは「三番村」
である。四句の「げ」は接尾語「気」、女性が主体の踊りであろうか、妙に色っぽい。
盆といへはなき人のみかけふは又下女の玉さへ帰る古さと
千金の直(ね)打(ち)はたしか有明の雲切丸かさえわたる月
徐々(そろそろ)とかたふくおしきこよひ哉月の鏡も樽のかかみも
十七の月も仲人かあつたやら入るかた見れは武庫の山のは
一首目の題は「やぶ入」、作者は犬麿。盆で迎える霊(魂)は「たま」、その盆で帰郷する下女も「玉(たま)」、両語は同源とする説もある。二首目の題は「月」、作者は田口嘉祐。二句「直打(ち)」は「値打ち」に同じ、四句、雲を払う風の手に「雲切丸」がある。千金は月ではなく、月を見せてくれる宝刀なのだ。三首目の題は「やうやう月も西にかたふきけれは」、作者は走帆。二句は「傾く惜しき」だが「惜しき」に「折敷」を掛ける。四句は満月の見立て、結句の「鏡」は樽の蓋を云う。望月も酒もそろそろお終いなのだ。四首目の題は「立ち待ち月」、作者は李郷。「立ち待ち月」は陰暦八月十七日の月、その月を女性に見立てた。結句は兵庫県東部を流れる武庫川の流路に沿った山の意、「武庫」に「婿」を掛けている。
|
| 第120回 狂歌乗合船(2) |
今ン日よりからくりかはる冬の景自身番所に火かともります 李郷(『狂歌乗合船』)
「冬」の部で題は「初冬」。初句六音、絡繰り芝居全盛の時代の見立てである。四句「自身番所」は自身番の詰め所、自身番屋とも云う。「自身番」は市中警備のために町内に置かれた番所、町人自身が持ち回りで詰めた。日が短くなったので明かりが灯ったのである。
祝ひ歌かく墨色に雲起り出世の竜の末そ見えける
よい名とてはやしたつれは後万歳(ごまんざい)と祝ふて祖父(じい)かよめる徳和歌
生れ子も名に叶へはやとくとくと乳をのむ智恵の出来たうれしさ
一首目の題は「孫娘りやうが誕生日の祝にまねかれて」、作者は走帆。娘が嫁いでいるのだろう。雲竜に因んだ賀歌である。二首目の題は「孫娘髪たれに名を徳とつけて」、作者は走帆。「髪たれ(髪垂れ)」は生後初めて産毛を剃ることを云う。三句「後万歳」と結句「徳和歌」は、いつも若々しく長寿を保つようにという祝い詞「徳若に御万歳」のもじりである。四方赤良編『徳和歌後万歳集』の刊行より約五十年早い。三首目の題は「同賀」、下に小さく「予か為にも孫なれは」とある。作者は螬菴、三句の「徳徳と」は控え目だが内孫だろう。
大切なものは天にもをしほ水琥珀のつほに唯(たつた)一はい
こよひしも御意を絵筆のほそう長うしんから情かけて給はれ
真実にたたく念仏のかねことは終に下ひもほとけ也けり
さめにけり浮世をあかしくれ竹のしちく六十三年の夢
法性の京繻子を今さとり得てあつち物にそついなられける
一首目は「神祇」の部、題はなし。作者は走帆。在原業平の歌に〈大原や小塩の山も今日こそは神代のことも思ひいづらめ〉(『古今和歌集』八七一)がある。京都の「大原」に大原野神社があり、「小塩の山」には業平ゆかりの塩竃跡と塩水を溜めたという池跡が伝わる。結句は塩を云う。二首目は「恋」の部、題は「寄筆恋」。作者は走帆。二句「絵筆」の「絵」に「得」を掛けて以下を展開した。三首目の題は「寄仏恋」、作者は中村野蓼。二句「念仏」は「ねぶつ」と読む。三句「予言」(「鉦事」を掛ける)は約束の言葉、結句「ほとけ(仏)」に「解け」を掛けた。四首目は「哀傷」の部、題は「山田草翰の母の世をされるをいたみて」。作者は走帆。初句切れ、浮世を夢に喩えたので「覚めにけり」となった。二句から三句「明かし暮れ」、四句「くれ竹の」は「世(節)」に掛かるのが順当だが九九の要請で「しちく(七九)」(紫竹)となった。これに「糸竹」(音楽)も響かせたい。五首目の題は「あひしれる呉服屋の身まかりけるを聞(き)て」、作者は走帆。二句「京」は涅槃経の意訳とされる伊呂波歌の最後、「繻子」で人としても呉服屋としても、の意。四句「あつち物(彼方者)」で死者を指す。今一つは外国人を云う。「繻子」は中国に始まる、また織物の縁だから「物」とした。
|
| 121回 『狂歌乗合船(三) |
竹馬の友はそろそろ皆うせて山の大将となれる老か身 走帆(『狂歌乗合船』)
「述懐」の部、題はなし。初二句は「たけうまのとも」と読み、意味は故事成語「竹馬の友」(ちくばのとも)で字足らずを避けたい。四句は「お山の大将」を云う。「竹馬」は子供の遊び道具、「お山の大将」は子供の遊びの一つである。山なりの場所の頂きを争い、独り占めした子供が「お山の大将われ一人」と誇る。しかし気がつくと誰もいないのだった。
水のたる男盛(り)もあり来しをかはる渕瀬や老の涕(みずばな)
かひなくも打(た)れ給ひし忠度の太刀はうせしやつかはかりにて
賑はしき道はいさみて乗(り)かけの馬の鈴さへ参宮しやんぐと
大象をけふは是非とも見かの原しはしは見世のはなをかせ山
いきた象を見しは卯月の廿日にて毛さへ色さへ鼠色なる
一首目の作者は走帆、題はなし。初句は「水の垂る」、男盛りには水の滴るような「私」だったが無常なことに今では水洟を流している。「渕瀬」は水の縁語でもある。二首目の作者は流水、題は「明石忠度の腕塚にて」。初句「かひ(甲斐)」に「櫂」、結句「つか(柄)」に「塚」を掛けた。兵庫県明石市に腕塚神社と忠度塚があり、海が迫る神戸市長田区に腕塚堂がある。三首目も流水の作、題は「伊勢参宮のとき」。二句「いさみて」は奮い立って、の意。参道の賑わいに馬も興奮気味なのだ。四句の「参宮」は馬の鈴のオノマトペに変化する。四首目からは「雑」の部、作者は走帆で題は「酉の卯月廿日象見物にまかりて」。表の意味に対して三句は京都府木津川市にある「瓶腹(みかのはら)」、結句「かせ山」は同じく木津川市の「鹿背山」を掛けた。見るために借りる「はな(端)」は「鼻」である。五首目の作者は李郷、象の続きで初句は『韓非子』の「解老第二十」(明治書院『韓非子 上』新釈漢文大系十一)中「人、生象を見ること希なり」に拠った。「二十日」から象を極小の二十日鼠に喩えた。
くき菜さへくふ事ならぬ老か身は又菜刀の刃をたのむ哉
あつかはにうき名をながす女夫丸(めおとがん)中の衣やかけて売(る)らむ
死んてみたり生(き)かへつたり狂言の役者はかみもかたき役哉
一首目の作者は走帆、題は「くき菜をきざませてくふとて」。「くき菜」は茎漬けにする野菜を云う。一方「茎長」で長刀を持つ構え方を云う。連想が掠めた、と読む。二首目の作者も走帆、題は「女夫丸と云(ふ)薬売(り)の夫婦づれなるがおかしくて」。初句に面の皮の厚さを掛け、四句「中の衣」に男女の仲を掛けた。『家つと』『華紅葉』にも登場するキャラクターである。三首目の作者は流水、題は「歌舞伎芝居悪人がたの役者を見て」。四句から五句「かみもかたき」を「神も難き」と読む。もう一つは「上も敵」と読んだ。用語「上手・下手」の上下には身分階級制度の尊卑の感覚が託されていた(平凡社『歌舞伎事典』)。
|
| 第122回 雅筵酔狂集・腹藁 |
下陰に雪のしら鷺かた足をかがめてたつは∧―⊂―(まつば)のごとし 風水軒白玉翁(『雅筵酔狂集・腹藁』)
『雅筵酔狂集・腹藁』の著者は風水軒白玉翁(ふうすいけんはくぎよくおう)すなわち正親町公通(おおぎまちきんみち)(一六五三~一七三三)である。『雅筵酔狂集』は享保十六(一七三一)年の刊、自歌自注で多くのスペースを割いている。『腹藁』は公通自筆の手控えらしく、本来『雅筵酔狂集』の草稿の一部であった。掲出歌の題詞は「雪中の鳥」。注に「狂歌は鳥の毛色雪にまがひて足はかりみえたるをいふ。ある人難じて雪中には足も埋(も)れむといふ。答に松の下陰なるゆへさもあるましきといへは詰りし人面面たり」とある。松葉の絵、というよりも記号化された松葉の登場である。
とんぼうや花田色なる狩衣の露をたづねてかするくびかみ
風をうけてななめになびく青柳のいと軽(かろ)げにもとぶつばくらめ
清水ある所まて追(ひ)来れとや尻にほたるの光みすらむ
釣(り)置(き)てふりたる網のやれやれといふ間に瓜の一つは丼(どぶり)
一首目の題詞は「蜻(虫の右に廷)」。注に「新古今集具親敷たへのまくらのうへに過(ぎ)ぬなり露を尋(ぬ)る秋の初風此(の)むし物を掠(かす)りて飛(ぶ)也」とある。二句「花田色」は薄い藍色。結句「くびかみ」は狩衣の首の周りを取り囲む部分。二首目の題詞は「柳に燕」。注に「杜甫詩受風燕子斜○狂歌は斜を二物に懸(け)ていふ」とある。今では見ることのない、しかし既視感のある典型的な風景である。三首目の題詞は「螢」。注によれば『伊勢物語』で男を追って清水のあるところで亡くなる二十四段の女が念頭にあるらしい。「狂歌は追(ひ)くる人のため尻に光を見するかとなり」だが、あくまで自歌自注を越えるものではない。四首目の題詞は「瓜を井(せい)中に冷(や)しけれは網の破れより一つ落(ち)たるを見て」。二句「ふりたる」は「旧りたる」、三句「やれやれ」は人の声に網の破れを掛けた。見所は井戸に落ちた瓜を視覚として「丼」の字を充て、聴覚として訓読を利用していることである。
立(ち)よりて花たちばなの香をかげば遠きむかしも鼻のさきなり
落馬せし嵯峨野々露のふることをしのぶやうにもなく轡むし
吉田山のほりてみれは黒谷も白川となる雪のあけほの
一首目の題詞は「橘花」。注に「古今集に読(み)人しらす五月まつはな橘の香をかけは昔の人の袖の香そする○俗に近きことを鼻のさきと云(ふ)」とある。四句「遠き」が結句の布石となった。二首目は注に「遍昭か落馬の事古今集序にあり」と記すが関心は欧陽脩の詩の一節「但(ただ)四壁の虫の声喞々たるを聞く/予(わ)が嘆息を助くるが如し」(「秋声譜」)に移って「狂歌この意を含(め)て読(め)り」となる。ポイントは「轡むし」が鳴いていること、「轡」は馬の縁語である。三首目は題詞なし、注もなし。初句「吉田山」は京都市左京区南部の丘、三句「黒谷」は京都市左京区黒谷町あたり、雪で「白川」になるという単純がよい。
|
| 第123回 雅筵酔狂集・腹藁(2) |
生(ま)れつき人のおもての有(り)ながら横にのみはひありくはいかに 風水軒白玉翁(『雅筵酔狂集・腹藁』)
『雅筵酔狂集・腹藁』は全七二九首、推敲による重複も多い。掲出歌の題は「嶋むらがにの絵」。享禄四(一五四三)年に敗死した島村貴則が蟹に化した、それが島村蟹で現在の大阪市西淀川区に伝わる話である。結句二文字で「かに」とあるところは見逃したくない。
雪ふれはいつはりのなき世とそしるからすを鷺の人の言の葉
節分の二度ある時そなを迷ふ今年かこぞか又おととし歟
惜まれて山のあなたにべらつけよ人まつ宵のかこつけの月
一首目の題は「雪中の鳥」。四句「鴉を鷺」は理を非に、非を理に云いなすこと。歌意は、雪が降っているのに、白いと云われていた鴉の羽根は相変わらずの黒さではないか、といったところか。注に「古今集の序に偽(り)のなき世なりせはいかはかり人の言の葉嬉しからまし」とある。二首目の題は「節分の二度ある年に」で注に「古今集元方年の内に春はきにけり一年をこそとやいはむ今年とやいはむ」とある。新暦に慣らされた身には残念ながら実感に遠い。三首目の題は「待恋」。注によると本歌は「古今集読人不知遅く出(つ)る月にもあるかな足引(き)の山のあなたもおしむへらなり」、また「狂歌のべらつくとは物をはきはきともせずだらりとするの俗諺」という。結句「かこつけ」は「口実」。本歌が「雑」の部で「題しらず」、山の向こうの人たちにスポットを当てるのに対して掲出歌は山のこちら側である。月が出てしまうと会う時間が短くなってしまう、また二人で眺めたいのであろう。
江の水のながれ渡りと世をしらばよしやあし間のかにの横ばひ
狼のころもにひとし魚の棚上下(かみしも)きつつ番をするねこ
風になひくふしの煙の空にきえて行衛もしらぬ法師なりけり
今よりは酒のとぎにとちぎるなり正徳二年やよひのはしめ
一首目の題は「蘆(あし)に蟹の絵」。注に「かくの世をしらはよからんにしらねはこそあしくも横にはへといふ義也」とある。二句の「ながれ渡り」は成り行きにまかせて暮らすこと。「良し」に「葦」、「蘆」に「悪し」を掛けて対句とした。二首目は題詞に「猫の袴肩衣(はかまかたぎぬ)を着て魚の棚に番をする所の道外(どうけ)絵に」とある。「道外」は「道化」。注に「魚屋町に上の棚下の棚とてあり打(ち)見たる所は優(ゆう)なれと底におそろしき所あるを俗に狼の衣きたるといふ」。また諺に「猫に肴(鰹)の番」があった。三首目は題詞「西行法師富士を見る図」。注に「新古今集西行風になひくふしのけむりの空に消(え)て行衛もしらぬ我おもひかな」。結句で「我おもひ」を「法師」その人にしてしまった。四首目は題詞「酒井正之進同徳右衛門といふ兄弟のものに三月三日初(め)て対面しけり。やよひといふ名酒を持参しけれは」。注に「対面の時節は歌の通り也義も下の句にていちしるし」とある。年号が出てくるところに注目した。
|
| 第124回 雅筵酔狂集・腹藁(3) |
凸の岩根の渦は凹に釣(り)する舟も魚もノヘ 風水軒白玉翁(『雅筵酔狂集・腹藁』)
掲出歌は題なし。初句「凸」は他のルビから推して「なかだか」、「凹」は「なかくぼ」だろう。「ヘ」は庵点と解した。以下に四音が省略されています、である。すると残るのが「ノ」である。とりあえずの結論を云えば「あとは読者に委ねた」。「ノ」から始めてください、である。すると〈なかだかの岩根の渦はなかくぼに釣(り)する舟も魚も(ノミコム)〉になる。また「ノミユク」「ノミタリ」等も考えられて読者参加型、クイズを兼ねた作品となる。
人の来てさしの言の葉きれ口によしや芳野のたばこ一ふく
我(が)国の道はたしかにさかへむと一位公通愚歌自筆(いちいきんみちぐかじひつ)
河波にはつと花よりもみちより月おもしろく見ぬや鵜つかひ
一首目の題は「たばこを」。注に「たた両人はなしの時さしていふへき事もなけれは一座の興さむる也その時一ふくすへば間もぬけすよしといふ義也」とある。二句「さし」は「差し向かい」の意、煙草の効用論である。二首目の題は「寄道祝」、『雅筵酔狂集』巻尾の歌で「朱印(はん)」とある。決め球、決め所の一首という感がする。これと巻頭の歌〈天地(あめつち)のひらけ初(め)しを大根(ね)にて国家さかゆく花の春哉〉(注に「狂歌神国の道を第一」云々)が呼応する。掲出歌の四五句はルビを振って「いちゐきんみちぐかじひつ」、結句は堂々の五音である。三首目は『雅筵酔狂集附録』の「月次(なみの)花鳥」、「六月」の一首、題詞に「鵜 みしか夜のう河にのほるかかり火のはやく過(き)ゆくみな月の空」とある。「みしか夜の」の歌は藤原定家作(『拾遺愚草』)である。二句の副詞「はつと」は鵜匠の意識そして川面に動く手縄であろう。
千世まもる神のお留守の時分そと都の空に鶴見まふらし
春の空おもひの外に暮(れ)かたき日あしや勢多のおほまはりする
立(ち)よれは鼻をつきぬく匂ひより兵庫か宿の鑓(やり)梅としる
一首目は「月次花鳥」、「十月」の一首、題詞に「鶴 夕日かけむれたるたつはさしなからしくれの雲そ山めくりする」とある。「夕日かけ(影)」は定家作(『夫木和歌抄』)である。神無月、注に「神の御名代となりて都を守るかと安堵し侍る」とある。京都の空を鶴が舞っていたことに、むしろ感動を覚える。二首目は「淡海(おうみ)八景」の一首、題は「瀬田(の)夕照」。注に「日脚(きやく)といふ熟字あり矢橋の舟は時として風波あらくあやうきゆへ勢多の方へまはりて行(く)を俗に大廻りといふ」とある。航路変更の「大廻り」を「日足」に置き換えたところが味噌である。三首目は『腹藁』の一首、題はない。推敲すること三度(他の二首は「鑓梅の」で始まる)こだわりの一首である。『雅筵酔狂集』には「玉木兵庫といふ者の下屋敷の前を過(き)けるに垣の外へ梅花の見えけれは留守居に門ひらかせ立(ち)寄(り)て」とある。人名の「兵庫」に兵器庫の「兵庫」を重ねて「つきぬく」「鑓」としたのである。
|
| 第125回 続家つと(1) |
住よしや木(こ)の間の月のかたわれはありけるものをここにそりはし 由縁斎貞柳(『続家つと』)
「解題」によると「諸本中に、『享保十四年酉十一月吉祥日』と刊年記のあるもの、刊記に異同のあるもの」云々とある。仮に享保十四(一七二九)年だと『家つと』と同年で貞柳七十六歳である。歌数は二二二首、最初に狂歌二聖として雄長老と豊蔵坊信海の作が各一首並ぶ。次いで狂歌六歌仙として松永貞徳・半井卜養・宮川尼・黒田月洞軒・生白庵行風の五人と各一首が続く。掲出歌は六人目として登場する貞柳の作である。題はない。初句は舞台が住吉大社であることを云う。二句「木の間」に見えるのは片割れ月、三句はその「かたわれ(片割れ)」がほかでもない「そりはし(反橋)」(太鼓橋)だという見立ての歌である。
男山言葉の花は散りぬれとなを頼みありむさしのの月
いや我れはあつまのゑひす歌口も髭もむさむさむさしのの月
黒田月洞軒の『大団』にも登場するが一首目が貞柳、二首目が月洞軒である。詞書に「元禄元年辰九月十三日信海法印遷化ありけれは今より後狂歌の道たとたとしきと浅草大護院へ申(し)上(げ)けれは月洞子御事豊蔵坊に狂歌おとり給ふましけれはあなたへ添削をこひ申せと仰(せ)ありけれは黒田公へ文奉るとて」とあって二人の出会いが知られる。文中「おとり給ふましけれは」は「劣り給ふまじければ」、「浅草大護院」は「哀傷」で〈むかし思ふ男山へも帰山なく遠きあつまのはて給ひける〉と詠われる「浅草前大護院」だろう。
桟敷ての酒のみなもと尋ねいれは清水辺に花そ浮瀬(うかむせ)
名にしおふくらま寺へのお初尾は百のおあしをまいらするかな
かそふれは百足のあしはちやうと百四文たらぬは不足成(る)らん
ちやうど百とおほしめすなら山椒の皮にもめをはたして給はれ
一首目の作者は貞柳、題は「芝居にて」。四句「清水」は大阪市天王寺区伶人町の清水寺、「浮瀬」は近くにあった料亭(もとは七合半盛れる貝盃の銘であった)。「桟敷」を川に面した仮設の席の意に通わした作となっている。二首目も貞柳作、題詞は「鞍馬寺月性院より年始に御祈祷の札下されけれは」。「月性院」は鞍馬寺に十院あった寺院の一つである。「お初尾」(「御初穂」)は神仏に奉る、その年に初めてとれた穀物(またはそれに代わる金銭)。四句の「おあし」は「銭」で百文、これに正味の「足」を掛けて鞍馬寺の縁語とした(「百足」は本尊毘沙門天の神使である)。三首目の作者は法印権大僧都関阿、題は「返し」。上句の真偽は問わない。ここでは「百足」から入って九六銭(くろくぜに)で応じたところが味噌である。九六銭とは銭差に通した銭九六文を百文として通用させたことを云う。だから四文不足なのだ。四首目は貞柳の「又返し」。下句「山椒の皮」は山椒の若い枝の皮を醤油漬けなどにした鞍馬の名産を指し、皮だけでなく「芽」(鞍馬名産「木の芽漬」)も足してくれと云った。
|
| 第126回 続家つと(2) |
地主(じしゆ)の桜おもしろやあれ滝の糸くりかへし返し地主のさくらや 由縁斎貞柳(『続家つと』)
「春」の部に入る。題は「清水にて」。清水の舞台を出てすぐにある地主神社の桜に取材した作品である。初句は六音、以下は七五八七となる。『閑吟集』(小学館『日本古典文学全集』第二十五巻)の小歌「地主の桜は」(二十七)や放下歌「おもしろの花の都や」(十九)を連想させるところがある。三句は枝垂れ桜の見立て、四句は嵯峨天皇が行幸されたときの故事「御車返しの桜」を云うのだろう(住吉大社そばの「車返しの桜」は後醍醐天皇だった)。
仕合(はせ)にむいてきのとのみをいはひ人をもいはふ千代の初春
此(の)春は芋の子たから手にいりてああ楽茶碗いはふ大(おお)ぶく
かたいちと人はいふとも鶯のほう法花経にしくものそなき
花を見に京へとくとくつなてなわ夢をも引(き)て行(く)夜ふね哉
一首目の題は「乙巳(きのとのみ)のとし元日に」。二句「むいて」は「向いて」に「剥いて」を掛ける。「乙(きのと)」は「木の弟」の意、これと「巳」の間に置かれた助詞「の」によって柑橘類(鏡餅の橙)の「実」を連想させた。二首目の題は「養子をして隠居せし春に」。二句「芋の子」は茶入れの名称でもある。「子」を共有して「子たから(宝)」、「楽茶碗」に「楽じゃわい」を掛けて結句「大ぶく」は新年に飲む「大福茶」の略である。三首目の題は「鶯」。初句「かたいち」は「片意地」で頑固に法花経を説くという見立て、「法花経」としか鳴けない鶯を待つ人の意でもあるだろう。四首目の題は「上京するとて」。二句「とくとく」は「疾く疾く」に「得々」の気分、三句の「綱手縄」は綱手に同じ、川を上るので陸から引っ張るのである。
花を詠(なが)め霞をくめは堂のゑんも真如平等の台(うてな)ならすや
世の中にたえて上戸のなかりせは花の盛もさひしからまし
花にあかて月になるまて酌(む)酒は入あひの鐘に下戸やちるらん
よめかはきふきのしうとめ有馬山をむこのをくとはむへもいひけり
一首目の題は「真如堂にて」。京都市左京区にある真如堂は正式には真正極楽寺。初句「花」は桜、二句「霞」は花の縁語にして「酒」の意、三句「ゑん」は「宴」に「縁」を掛ける。二首目と三首目は掲出歌と同題。うち二首目は云わずと知れた〈世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし〉(在原業平『古今和歌集』五三)に拠る。三首目の初句「あかて」は「飽かで」、「飽く」の未然形に打ち消しの助詞「で」で「飽かずに」の意。月を待つまでもなく日暮れの鐘とともに下戸は散る、世の中にたえて上戸のなかりせは下戸の心はのどけからまし、なのだ。四首目は題詞に「有馬の山口といふ所に我妻の母なる人住(み)侍りけるか文の使(ひ)に春の草々添(へ)て参りけるに」。初二句は「嫁が萩蕗の姑」で嫁菜と蕗の薹の異名である。四句「むこのをく」は「武庫の奥」に「婿の奥(方)」を掛けた。
|
| 第127回 続家つと(3) |
方丈の室(しつ)には似れと蚊帳のうちに和泉式部はさかしてもなし 由縁斎貞柳(『続家つと』)
「夏」の部に入る。題は「天王寺にて」。初句「方丈」は住職の居間を云う。謡曲『東北』(小学館『日本古典文学全集33』)の最後に「方丈の燈を、火宅とやなほ人は見ん、こここそ花の台(うてな)に、和泉式部が臥所(ふしど)よとて、方丈の室に入ると見えし、夢は覚めにけり、見し夢は覚めて失せにけり」と謡い収められる。「東北」は東北院、和泉式部の仕えた上東門院の御所を後に寺にした。歌の徳で菩薩となった式部、所縁の軒端の梅を中心に舞台は展開する。
宵々に待(つ)こそ侘(び)れ時鳥老(い)ての恋は是ひとつのみ
千はやふる神代もきかす天満川数万の桃灯(ちようちん)水くくるとは
祭礼と素麺も又同し物とふやらのひてあちのわるさよ
切麦やうどんげよりも珍しきべいふんたりけ空(くう)にじやくする
一首目の題は「郭公」。二句「侘(び)れ」(侘びる)には閑寂な隠居生活を楽しむ余裕と一方に命の火が衰えていく心淋しさ、そんな二面性を含む。二首目の題詞は「天満天神の祭礼の夕暮川船に乗り拝して」。一首は在原業平の〈ちはやぶる神代もきかず龍田川韓紅に水くくるとは〉(『古今和歌集』二九四)を下敷きにする。「天満川」は大川を云う。四句は「すまんのちやうちん」で八音となる。三首目の題詞は「大雨洪水にて所々の祭礼今月延引なれは」。四句は「どうやらのびて」だろう。延びた祭礼は「どうやら(なんとなく)」意気が上がらないのだ。四首目は題詞に「瑞竜寺雪巣和尚へ暑気御見廻申(し)ける折ふし黄檗山より米粉(べいふん)まいりけるを相伴仕りて」。初句の「や」は並立助詞、二句「うどんげ」は「饂飩」に「優曇華」を掛ける。四句は「米粉」に「たりけ」を付けて「饂飩(優曇華)」に倣う。「たり」は助動詞、「け」は終助詞と解しておく。結句「空」に「食ふ」を掛け、「じやくする」は「空寂」の分解であり、「食ふに着する」で執着する意となる。「米粉」はビーフンである。
七夕を祭る寺子のおどり歌是も手習ふはしめなるらん
払子(ほつす)かととつて見たれはすすきの穂たてる僧都のさそな笑はん
桜ちる春過(ぎ)秋の綿畠空にしられぬ雪そふきける
「秋」。一首目は題詞「己酉の七夕に」。寺子屋で学ぶ読み書き算盤を手習い、これを踊りの「差す手引く手」に変換した。次の二首の題詞は「秋の野」。二首目の初句「払子」は高僧が用いる法具。四句の「僧都」は玄賓僧都かつ案山子。玄賓僧都(?~八一八)が案山子を創案したともその粗衣が似ていたとも云われる。〈やまだもるそほづの身こそあはれなれあきはてぬればとふ人もなし〉(『続古今和歌集』一六〇八)。三首目は紀貫之の〈さくらちるこのした風はさむからでそらにしられぬゆきぞふりける〉(『拾遺和歌集』六四)に拠る。綿の果実は熟して裂開すると白い綿毛のある種子を出す。結句の「り」と「け」の違いである。
|
| 第128回 続家つと(4) |
鬼よきけなんぢ打ち出すいり大豆を年の数ほとわれとつてかも 由縁斎貞柳(『続家つと』)
「冬」の部。題は「除夜」。今なら二月三日の節分である。三句は「いりまめを」と五音で読んだ。結句の「かも」は係助詞、結びの「ある」等の省略と解した。感動、詠嘆に疑問を表す。豆を握れば鬼は与しやすい「鴨」、したがって「~かもね」の余韻である。四句「年の数ほど」だから七十ぐらいだろう。投げ損じても大丈夫、食べるにはきつい数でもある。
楊貴妃の十八の事さもあらはあれ軒のかはらの鬼のしら雪
さむうても地獄の釜のそばはいや猶如(ゆうによ)火燵にそねたか極楽
此(の)暮(れ)は諸事の商ひ利かなうてたらすかちなる大つもごかな
年もはや碁ならけちさす時分にてかつ色見えて梅そゑみぬる
一首目の題は「雪」。成句「鬼も十八番茶も出花」があるぐらいだから楊貴妃の十八はさぞかし、ときて三句七音の展開は「ままよ」となる。下句は年頃になった鬼の娘の見立て、やはり「鬼も十八」なのだ。二首目の題は「火燵」。四句は訓読なら「なほ火燵のごとし、に」だろう。それを音読して仏典の一節めかしている。結句「そねた」は「そねむ」の連用形に助動詞「た」で「そねみた」、これが撥音便で共通語「そねんだ」となる、方言か。一首は極楽の擬人化である。三首目の題は「歳暮」。三四句は「利が無うて足らず勝ちなる」、「のう」は「無く」のウ音便、結句「つもご」は「つごもり」が変化して「つもごり」、その方言である。四首目も「歳暮」。二句の「けち(結)」は、まだ所有の決まらない目を云う。四句「かつ」は接続詞で「その上」、これに「碁」の縁語の「勝つ」を重ねて梅の花へと展開する。
払はましと思へはかねのないくれは花のふふきのしがをあらはす
餅つきに内儀世話やきいとまなみよひべつかうもさらす出にけり
雲の上へもうのほりぬるたつの春はけにも冥加にかのへなりけり
なりたいや松になりたや住吉の神のおまへに千代もまいらむ
一首目の題は「歳暮」。下句は「花のふぶき」と「志賀の山越え」。数あるが慈鎮の〈あくがれし花のふぶきにすぎなれて雪の空にも志賀の山ごえ〉(『夫木和歌抄』七二九五)が状況に相応しいか。但し、三句が解せない。二首目も「歳暮」。四句は「良い鼈甲」と読んだ。結句は濁って「さらず出にけり」だろう。未然形が「さらず」は「去る」と「避る」、連語なら「然らず」「避らず」で決めがたいが、鼈甲もなく、と解した。三首目は「賀」の部。「庚辰の正月」で「院参申上御菓子捧け奉る祝に」。貞柳の父は山城大掾の称号を持っていた。鯛屋は御用商人なのだ。四句の「かのへ」は「かなふ(適ふ)」に「庚(かのえ)」を掛けた。四首目は題詞に「七十の賀の後も足手達者にて住吉へ二里余りの道を歩行して月参りし侍るを楽(し)みて」とある。往復だと十六キロだから達者なものだ。初句に屋号が見える。
|
| 第129回 続家つと(5) |
さまさまの神のお庭の芝居とて木戸をひらけはおもてしろやな 由縁斎貞柳(『続家つと』)
「神祇」の部。題詞は「座摩(ざま)宮のあたりに小芝居の有(り)けるを見て」。「座摩」は正式には「坐摩(いかすり)」だが通り名を初句に効かしている。謡曲『三輪』(岩波書店『新日本古典文学大系57』)に「天照太神、其時に岩戸を少開き給へば」「人の面(おもて)白々と」がある。「面白」の起源説話である。ここでは役者の白く塗った顔を加えた。
神前に御寄附の鈴をかけまくも忝(な)しや時節がらがら
祈(る)より思ふかひある蛤の玉の御垣(みかき)ににしりよりけり
明石なる蛸の入道をうらやみて鯛屋もいのる住吉の神
あらたなりと名に立花の八幡宮むかひに見えたるは正覚寺村
一首目は題詞「座摩宮に詣ふて再興の折(り)なれは」。三句は鈴を「掛けおくも」を祝詞に擬えた。結句は「時節柄」に「がら」を加えてオノマトペである。二首目は「住吉奉納二首」の一首。今と違って浜辺まで神域だったのだろう。二句「甲斐」に「貝」を掛ける。四句「御垣」は神社の垣、「玉」(接頭語で「玉垣」)は「石」であり、蛤参詣の図である。三首目は題なし。初二句は『源氏物語』に登場する明石の入道である。住吉神を頼んで毎年参詣、その願いが叶って娘は光源氏と結ばれる。蛸と鯛は帰属する人物また住吉神(海の守護神)の縁語である。四首目は題詞「河州橘八幡宮へ詣し比源氏の御氏神なれは頼政のうたひの詞にてよめる」(河州は河内の異称)。初句は霊験あらたか、を云う。また謡曲『頼政』(小学館『日本古典文学全集33』)に「名に橘の小島が崎」「向ひに見えたる寺は」の一節がある。
かなしむも歎(く)も恐れ多けれは申(し)上(く)へきやうもなきかな
法問(もん)をえせぬ我(が)身がまししやまて棒はくわひて馳走にそあふ
医者へやれは長いきせんと思ひしにあてか違ふた産後十八
かたみをはぢいに残して母はあちへいのふ峠の孫ちゃくしかな
「釈教」の部。一首目は題詞「鷹司(たかつかさ)前殿下薨御(こうぎよ)の時年来御出入申(し)上(げ)ける冥加のため御家来衆中に恐れなからかくなんつぶやきける」。これに対する「御取次の方より返し」は〈かなしむといたみをあぐる心こそ田舎におくはおしき山城〉。「田舎」の「山城」は「大掾」とセットの称号である。二首目の題詞は「妙心寺長興院にて茶の湯にあひ帰るさに」。禅宗だから「棒」は警策、その後は「食はいで」。したがって三句は「増しじゃ待て」と「汝(まし)じゃ待て」の表裏と読む。三首目は題詞「娘を医者とめあわせけるに一とせのうちに産後に相果(て)けるかなしみの余りに」。明石の入道と違うところである。四首目は題詞に「男子跡に残りけれは」。下句「いのう峠の孫杓子」は福井県湯の尾峠の名物、これを「往のう(帰ろう)」の口合い(江戸では「地口」)とした。「杓子」に「弱子」(幼子)を掛けた。
|
| 第130回 続家つと(6) |
国はなんの都はなんのうかれめの一たひゑめは銚子かたふく 由縁斎貞柳(『続家つと』)
「恋」の部。一首は「題しらす」であるが「傾城」(「一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く」)をモチーフとする。初句と二句の「なんの」の受け流したような、意に介さない口吻は、いったい次には何が傾くのかと戦々恐々とするのであるが、実のところは慎ましやかな銚子なのであった。傾城は美人また遊女の意、ここでは「浮かれ女」である。
道心者浄土法花とへたつれとおつるはおなし谷町のうら
おなしやうな情(なさけ)の露もみなみより西こそ秋の色の極上
西行は土てもゆかし見世さきにしはしとてこそ立(ち)とまりけり
南無おみは黄檗(おうばく)のみと思ひしに南禅寺にもとうふ有(り)けり
一首目は「題しらす」。初句「道心者」は仏門に帰依した者。下句に諺「落つれば同じ谷川の水」を効かす。寺の多い谷町の裏とは幕府公認の遊里「新町」や非公認の岡場所「島之内」である。二首目は「九軒町井筒屋にて」(九軒町は新町の一画)。三句の「みなみ」は島之内、下句の「西」は新町で両者を方角で比較、「秋の色」は紅葉で情の濃さを云い、「極上」は「西」を効かせて極楽浄土とした。三首目は「雑」の部で題は「伏見にて」。土人形に「富士見西行」がある。地名の「伏見」に「富士見」を掛けたものだが西行の〈風になびく富士の煙の空に消えてゆくへも知らぬわが思ひかな〉(『新古今和歌集』一六一三)が連想される。四首目の題詞は「東山にて」。作品は念仏の「南無阿弥陀仏」が「なむおみどう」と聞こえることに端を発す。宇治の黄檗山万福寺は念仏禅、南禅寺はすでに豆腐が有名だったようだ。共に禅寺で精進料理、片や南無阿弥陀仏の洒落で南無阿弥豆腐、片や転じて豆腐の異称である。
此(の)酒によいにいのより二ツ三ツせめて五ツをすこし給へや
とびだんこそれならなくに此(の)臼は夏衣とそついたやれもさ
けい馬をはかけ奉る御宝前是かや神の乗(り)うつるとは
一首目の題詞は「日くれて来(た)りける人に盃出しけるに用事あれははやく帰り度(き)由いふを聞(き)て」。二句は「宵に去のより」、「去の」は「帰ろう」の意。あとの数字は飲み干す盃の数、「五ツ」はそれに時刻の「五ツ(午後八時頃)」を掛けた。二首目の題詞は「有馬郡上津村石井氏年来所持の突臼(つきうす)時ありて名香のよし即夏衣と其(の)名をいふと狂歌をよめと有(り)けれは」。初句「とびだんご(飛団子)」は歌に合わせて餅を搗いたり、捻って投げたりの曲芸で売り歩いた。結句「やれ猛者」はその囃子詞である。また「ついた」には名前が付いたと餅を搗いたの両意を掛ける。三首目の題詞は「競馬の絵に」。二句の「かけ」は絵馬を「掛け」る、絵馬の馬が「駆け」る、この両意を掛ける。三句「御宝前」は神の前。下句「是かや」で噂になっていることがわかる。乗り移った神が馬を走らせているのだ。
|
| 第131回 続家つと(7) |
けふといふけふそ名利をはなれけり弥陀の浄土に住(み)たくもなし 友松居士(『続家つと』)
掲出歌の題詞は「ある人いつにても死去の時辞世にせんと思ふとて語りし歌に けふといふけふそ名利をはなれけり弥陀の浄土をかくれ家にして となんよまむいかかと語るに答(へ)ていわく仏になりたしの名聞楽をしたしの利養にては名利を放れたりとはいはれましきとこたへて」とある。このあと「友松居士」とくるので悩ましいが「こたへて」までが貞柳と読む。「ある人」即「友松居士」で残された辞世を見て助言者もびっくり、なのだ。
狂歌こそつくはの道のいぬつくはさんたをしても奉るへき
歌の会に南の坊へ来た我は西も東もしらすよみによめる
貴僧ともしらて咄を申上(け)しりこそはいや高野六十
一首目の題詞は「三田お屋敷より狂歌集の義御沙汰有(る)と聞(き)て」。二句「筑波の道」は連歌の異称、三句は「犬筑波集」の意、四句「さんた(三太)」は「犬」の縁で「ちんちん」を云う。二首目の題詞は「南都宗範興行にて生玉南坊へ歌の会に行(き)て」。「生玉南坊」は生國魂神社の神宮寺の本坊である。三句の「来た」に「北」を掛けて東西南北が揃う。下句は「知らず」の帰属が不安定で十・六とも七・九とも取れる。三首目は題詞「旅宿にて余多ひとつ座敷にとまりけるに京田舎の衆打(ち)ましり一夜語り明(か)しけるにあくる日聞(き)侍れは高野山門主竜光院殿もおはしますと宿のあるしの知らせけれはよみて奉りける」。四句は「尻こそばいや」で「こそばい」は「こそばゆい」に同じ。結句は「高野六十那智八十」を云う。高野山や那智山では男色が盛んで高齢でも相手にされたらしい。
杉折をあけて中見つまんぢうの色の白さは美女御前かな
農(のう)の時もわすれぬためにげんくわんにかねてつりをく心世になる
親もなし子もなしさのみかねもなし望む義もなし死にとうもなし
一首目の題詞は「京より饅頭をもらひて」。これは舞の本『満仲』(岩波書店『新日本古典文学大系59』)を重ねて読む。二句は「中見つ(仲光)」、三句は「まんぢゆう(満仲)」である。多田満仲は不肖の我が子「美女御前」の首を切ることを家臣の仲光に命じる。しかし仲光は代わりに我が子「幸寿丸」の首を差し出す。助けられた美女御前は比叡山で修行に励むという展開である。二首目の題詞は「竹淵村塩川氏げんくわんのまへに鐘をつりあり是は農業を下百姓にいさむるためつくよしを聞(き)て」。四句に「鐘」を隠す。結句は「心(こころ)世に鳴る」、「世に鳴る」は評判になる意でもある。続けて〈庄屋殿のげんくわの鐘の音すなりあかつきかけていつる早田乙女(さおとめ)〉がある。三首目の題は「述懐」である。行風編『後撰夷曲集』(一六七二年)に成安の三無斎〈親もなし子もなし跡に銭もなしからた斗はからりちんなり〉があった。これからすると貞柳は林子平(一七三八~一七九三)に先立つ六無斎である。
|
| 第132回 置みやけ(1) |
百居てもおなし浮世におなし花月はまんまる雪は白妙 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
『置みやけは』由縁斎貞柳著、養子の永田貞竹編、享保十九年(一七三四)十月の刊行である。貞柳はこの年の八月十五日に没、八十一歳。享保十八年と十九年の作三〇九首を収める。掲出歌は弟の紀海音の序に続く〈知るしらぬ人を狂歌に笑はせしその返報に泣(い)て給はれ〉そのあとに「辞世」として載る。百まで生きても浮世は同じことだ。春は桜、秋は月、冬は雪、変わることとてあるまい。そろそろお暇することにしましょう、と読む。
としは牛迎へし戎さんろ殿まのの長者となして給はれ
うつくしき享保十九のとらか石石かとみれはかかみ餅かな
物すきにていかよけれは夏の物をはるにもつかふうちはゆへ哉
一首目の題は「丑年」。二句「戎さん」で三句に跨る「さんろ」は「山路(殿)」、四句「真野の長者」の娘に恋をした用命天皇の仮の名である。帝の位を降りた用命天皇は長者の舎人となって牛の世話をする。舞の本『烏帽子折』(岩波書店『新日本古典文学大系59』)では「御身が娘を恋ふるゆへに、三年は奉公ありつるぞ。今は姫を参らせよ」「承る」となる。二首目は無題。三句「とらか石(虎が石)」は曾我十郎祐成と遊女虎御前にまつわる伝説の石、神奈川県大磯町の延台寺にある虎が石は賊の矢から守ったので身代わり石とも云う。重さ一四五キロ、連想に自祝の思いがこもる。三首目は題詞に「鳥路観貞峩より年頭の礼に団扇を越(し)けれは」とある。鳥路観貞峩は紀海音の別号。二句の「ていか」は「体が(貞峩)」となる。同じように四句「はる」は「春(貼る)」、結句「うちは」は「内輪(団扇)」となる。
冨士の山夢に見るこそ果報なれ路銀もいらす草臥(れ)もせす
住吉のむかい通るは清重郎しやないかいやいやあれは帆懸船也
面白やあらりきやうがり改玉のはるは鼓の声はちちとせ
こさつたこさつたひんの病をなをそとて薬袋を持(つ)た大黒
一首目の題は「初夢」。初夢に見ると縁起のよいものに「一富士二鷹三茄子」があった。また「果報は寝て待て」とも云う。下句は夢を現金に解釈してみせた。二首目の題詞は「初卯に住吉へ詣(り)て眺望して」。五・七・十・七・七と切ってみた。三句までは近松門左衛門の『五十年忌歌念仏』(小学館『日本古典文学全集43』)に出るが、当時流行っていた清十郎節らしい。三首目の題詞は「春のはしめに万歳楽来りて鼓を打(ち)舞ふを見て」。二句は「あらり興がり」で「あらり」は副詞で「大きくしっかり」の意と読む。結句「ちちとせ」は鼓のオノマトペに「千歳」を掛けた。四首目は題詞「大黒舞薬袋をかたけ来(た)れは」。初句八音、「こさつた」は「御座つた」で「来た」意の尊敬語、二句は「貧の病」で大黒天が福徳の神による。同時に金品を乞うのが大袋を担げた門付け芸人であるところが味噌だろう。
|
| 第133回 置みやけ(2) |
思ひあらはおたれのうへに寝もしにやん軒の忍をひしき物にて 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌の題は「猫妻恋」。「夫」が私を恋しいなら、という仮定だろう。二句「おたれ(尾垂れ)」は屋根の庇。字面からして庇の猫が見えてくる。三句は「寝もするだろう」を猫語に変換した。四句「軒の忍」は屋根などに生える常緑性シダ植物「軒忍」、これを字数調整から「の」を挿入した。結句は海藻の「ヒジキ」を複合名詞にして軒忍をこの範疇に加えた。
毛氈(もうせん)はひかん参りの蓮にて下戸も上戸もひとつ極楽
茶臼(ちやうす)山友引(き)つれて永き日も花を見めくりあくひこそせね
散れはこそいとと桜はめてたけれけれ共けれ共そうしやけれとも
春雨のつれつれなるままに下戸ならぬ友こそよけれいさ呼(び)にやろ
一首目の題は「彼岸」。彼岸とは浄土すなわち極楽浄土を意味する。蓮台なら仏様だが毛氈はどこに敷かれているのか。法要の行われている本堂ともとれるが、二句と四句から賑わう茶店の縁台、その緋毛氈と解釈した。被写体は生者なのだ。二首目の題は「茶臼山にて」。井原西鶴の『男色大鑑』(小学館『日本古典文学全集39』)に「難波の茶臼山へまかりけるに、桜狩りせし春にかはりて」とあるから当時は桜の名所だったのだろう。結句の「あくび」が係り結びで強調されているが「すれ」ではなく「せね」、退屈しないのだ。三首目の題は「花のうつろふを見て」。『伊勢物語』第八十二段の〈散ればこそいとど桜はめでたけれ憂き世になにか久しかるべき〉を下敷きとする。理屈でない心情が三句以下のリフレインとなる。四首目の題は「春雨」。二句が九音、また四句までが文語体で結句のみ口語体である。「やろ」は補助動詞「遣る」の未然形に助動詞「む」の音変化「やろう」、その方言と思われる。
墨吉や汐日の暮(れ)の足たゆくにしりにしりて帰るくりはま
桃山の下をのつから茶屋たてて赤前垂(れ)は物をいひけり
やつこ尼へ立(ち)よりて見る藤浪は扨も見事てこわり申そ
一首目の題は「住吉に詣(り)て」。初句は住吉の古称で歌枕「すみのえや」と読む。二句は「汐干」と「日の暮れ」が「ひ」を共有する。以下、縁語仕立てで展開する。四句「にじり」(躙る)は膝で進む意、蛤の扁平な斧足が思われる。また潮干狩りのとき足で踏んで貝を探す意、これに三句の原因「たゆく」(「弛し」は疲れて力がでないこと)を込めた。結句「ぐりはま」は「はまぐり」の倒語である。二首目の題は「伏見にて」。初句は伏見城の跡に多くの桃の木が植えられたことに由る。二句は「下、自ずから」、四句は接客の女がつけた赤い前垂れ、ここではそれをつけた女を云う。伏見は淀川水運の要として栄えていた。三首目の題は「藤 野田奴尼庵にて」。結句「こわり」は「ごわる」の連用形、「ごわる」は「ごある」の音変化で近世の奴詞に始まる。「ある」の丁寧語である。尼の名前の「奴」に呼応した。
|
| 第134回 置みやけ(3) |
螢こひ女房ともの乳(ち)をのましよ金の釜は出(よ)うと出まひと 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌の題は「螢」。浅野建二著『わらべ唄風土記・下』(塙新書)に兵庫県氷上郡(現在の丹波市)の螢狩りの唄として「ホ、ホ、ホータロこい、あっちの乳は、苦いぞ、こっちの乳は、甘いぞ」がある。貞柳の妻の里、有馬の山口はどうであったか。下句は成句「黄金の釜を掘り出したよう」(思いがけない幸運に出会うこと)に由るが、この郭巨(かくきよ)の故事(二十四孝)が貧からくる子殺しであったことを思い合わせると螢には早世のイメージが重なる。
花の王の宿直(とのい)かほにも打(ち)眠(ねぶ)る是にやん命婦の大臣(おとど)とやいはん
空蝉と名にはたてれと声いろはひたちの君かせみせみせみせみ
ほたろこひちちをのまさふ姥玉(むばたま)の闇にありくも子共すかしに
蚊は冨士の山ほと多き裏屋小屋ならぬ思ひのもゆる大鋸屑(おがくず)
一首目の題は「牡丹」すなわち花の王である。下句「命婦(みようぶ)の大臣」は『枕草子』(小学館『日本古典文学全集11』)第七段に「うへに候ふ御猫は、かうぶり給はりて、命婦のおとどとて」と描かれる一条天皇の愛猫である。但し、結句「とやいはん」である。二首目の題は「蝉」。初句「空蝉」に『源氏物語』に登場する「空蝉」(第三巻)を掛ける。空蝉の夫は「関屋」(第十六巻)で常陸守とある。したがって「ひたちの君」はその後の「空蝉」となる。三句「声いろ」は声の感じ。「ひたちの君」は「常陸の君」(方言)かつ羽化した「肥立ちの君」(おばさん)でただただ喧しい。ちなみに「蝉」の語源説には結句の鳴き声説があるらしい。三首目の題は「螢」。三句「姥玉」は宛字、イメージとしては「乳母」もう少し云えば「婆(ばあ)や」か「姉(ねえ)や」だろう。四句の「ありく」は「歩く」、結句「すかし」は機嫌をとる意の「賺す」の名詞法である。四首目の題は「蚊遣火」。紀乳母の〈冨士の嶺のならぬ思ひに燃えば燃え神だに消たぬ空し煙を〉(『古今和歌集』一〇二八)が思われる。「ならぬ」だから制御できない、片や恋の思いなら、片や目の前を飛ぶ蚊と対照的である。日本の夏、金鳥の夏には遠い。
ひこほしの来へき宵なりささかにの蜘(くも)の糸より細きそうめん
物洗ふ下女のせんらも鵲(かささぎ)のはしの白さに星をうらやむ
二首とも題は「七夕」である。一首目だが彦星(牽牛星)が訪ねる織女星を別に「蜘蛛姫(ささがにひめ)」と呼ぶ。また「ささがにの」は蜘蛛に掛かる枕詞であり、結句の「素麺」は七夕祭の供え物である。ではなぜ「糸より細き」なのか。この夜、女性は裁縫の上達を星に願ったが「糸」も「細き」もその縁語であった。二首目。四句の「はし」は「橋」、鵲は腹が白いので下から眺めると白く見える。掛けるのは「階(はし)」で宮中を天上になぞらえた。大伴家持の〈鵲の渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける〉(『新古今和歌集』六二〇)である。すると三句の「せん」は「先」で先から居る、の意となる。これに宮中に対する「賤」を掛けた。
|
| 第135回 置みやけ(4) |
露と消(え)し人を問(ひ)ぬるうら盆の重の内にも萩の花哉 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌の題は「盂蘭盆」。四句「重」は「重箱」のこと。結句「萩の花」は「萩の餅」つまり「おはぎ(御萩)」である。二句「人を問(ひ)ぬる」は仏壇に供えたという意味だろう。また四句の助詞「も」から推察して重箱の外側には萩の絵(秋の七草)が施されている、と解したい。盂蘭盆は七月十五日を中心にした魂祭り、陰暦では七月から九月が秋である。
涼(し)かろと思ひまいらせ候になほなほなほあつき文月
湖の海にてる月影をかそふれは今宵そ五十四帖初(ま)る
鎌かけていふてはなひか野も山も穂に穂そなりて目出田かりけり
淋しさは碁の相手さらになかりけり手もやや寒き秋の夕暮
心なき身にもあわれや立(つ)鴫(しぎ)をやにはに射たる秋の夕くれ
一首目の題は「残暑」で手紙文を模した。四句の「なほなほ」は副詞で「依然として」、接続詞で「加えて」となる。後者は手紙の本文のあとに書き添える常套句で尚尚書きと呼ぶ。二首目の題は「石山にて」。大津の石山寺は紫式部ゆかりの寺で『源氏物語』起筆の場所とされる。初句は「湖海」三音を助詞「の」で分断し、「湖」(琵琶湖)と「世間」(物語)の両意を託した。下句は句またがりとなる。三首目の題は「豊年の祝義に」。二句は「云うではないが」、結句は宛字なら「目出度かりけり」、これを豊年の「田」を入れて祝儀歌とした。次の二首は「三夕」である。一首目。寂蓮の〈寂しさはその色としもなかりけり槇立つ山の秋の夕暮〉(『新古今和歌集』三六一)を日常生活の現場に置き換えた。二首目。西行の〈心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮〉(『新古今和歌集』三六二)が本歌で初句の「身」を僧侶から鴫に変えた。結句「射たる」は猟師の鉄砲でズドン、と終止形である。
節句とて諷(うた)ふつ舞(ひ)つ見る菊はありとほしともおもふへき哉
本復を祝ふ節句の丹波栗鬼ともくまん心地こそすれ
茸狩(たけがり)に誰も北山秋ふかく積(も)る鬱気をましなひそする
一首目の題は「重陽」。観菊の宴は酒を酌み交わして長寿を祝う。四句は「蟻通」で謡曲『蟻通』(小学館『日本古典文学全集』34)で紀貫之が蟻通明神に手向ける和歌があるが、その下句を借りた(但し結句は「思ふべきかは」。「哉」ではない)。「蟻通」は「星有りと」を倒置した「有りと星」に由来する。歌って踊って菊は見ていないのである。二首目の題は「病気本復すれは」。九月九日の重陽の節句は栗の節句でもあった。この日は栗御飯を食べるのが慣わしである。丹波は丹波栗で有名、また丹波の大江山には酒呑童子が住んでいた。四句の「くまん」は酒を「酌まん」。三首目の題は「茸狩」。二句の「北山」は京都北方の山、この「北」に「来た」を掛ける。結句は「呪ひぞする」(病気を避けるために神仏などに祈る)。
|
| 第136回 置みやけ(5) |
埋(み)火の灰口をとふ老(い)の身は消(え)さへせねはいつも吉日 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌の題「埋(み)火」は「いけ火」とも云う。火鉢などで火が消えないように灰の中に埋めた炭火のことである。二句は「灰、口を飛ぶ」と読む。火箸を使うとしても、火を熾すために息を吹きかけたのである。その火を命の火に置き換えた下句の妙を味わいたい。
六字つめのこゑきく時そ鹿谷へ紅葉ふみ分(け)詣(り)こそすれ
おさしやんな大門様は道ひろき法(のり)の教への六条参り
うかうかと長息をするやうなれと彭祖(ほうそ)はなけの老(い)の暮(れ)哉
彭祖には八百の上若けれはさのみに老(い)の暮(れ)にてもなし
一首目の題は「鹿谷へ詣(り)て」。京都市左京区鹿ヶ谷の獅子谷法然院を参詣したと思われる。初句は「六字詰」で百万遍念仏の終わりに南無阿弥陀仏に節をつけて唱えることを云う。百万遍念仏は弥陀の名号を七日間に百万回唱えること、いよいよクライマックスというところであろう。ちなみに荒廃した法然院は延宝八年(一六八〇)に再興されている。二首目の題は「霜月御仏事に参りて」。初句は「御座しやんな」と読む。「御座」は浄土真宗で説教を聞く集まりの座、「し」は動詞「す」の連用形、「やんな」は近世上方語で「なさるな」の意。結句は東西両本願寺を参詣すること。二句「大門様」は北御堂とも南御堂とも決めがたいが余計な時間を取らせたくないという配慮であろう。三首目は無題。四句「彭祖」は中国古代の伝説上の長寿者。殷末時に七百余歳で壮健であったと云う。「なけの」は「無げの」で「なさそうだ」の意である。四首目も無題。二句「八百」は数の多いことの喩え、それを上回って若いのだから、と云う。四句「さ(然)のみに」(それほど)で年寄りでもない。
木に餅のなるてふ柳いとはやし花咲(く)春の色めいて来た
命こそ宝の市と聞(く)なれは神の恵みを得るそとうとき
煩悩の種を求(め)し年たけてけふは菩提の花そ咲(き)ぬる
西行に杖と笠とは似たれとも心は雪と墨染の袖
一首目は無題。初二句は餅花を云う。柳の枝に餅を花のようにつけて小正月(一月十月)に飾った。歌は柳の木の新葉を言祝く。三句の「いと」は副詞、漢字にすると上を受けて「柳糸」で柳の枝の意となる。二首目は題詞「九月十三日病気本復し侍れは住吉明神へ参詣申(す)折節宝の市の神事なれは」。「宝の市」は住吉大社の神事、農家で使う桝などを売る市が立つので桝の市とも云う。三首目は「釈教」で題詞「朝夕の人剃髪の時」。「朝夕」は「いつも」の意で妻の得度となる。上句は商売、家庭、子育てと二人三脚で歩んだ人生そのものを指す。そして余生の今を信心に生きるのだ。四首目の題は「年老いぬれは法衣を着して」。心は「雪」(西行)と「墨染」(貞柳)という謙譲の中に貞柳の充実した人生が見えてくるようだ。
|
| 第137回 置みやけ(6) |
極楽はらくなと聞(き)て苦の世界こちや堪忍せう待(つ)て居しやしやれ 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌の題は「忍笑一周忌」。「忍笑」は和田忍笑、『狂歌大観』では『華紅集』『狂歌乗合船』『狂歌ますかがみ』に登場する。初句「極楽」には「楽(らく)」があるが「く(苦)」も二つある。「こちゃ」(私は)、「堪忍」(我慢すること。「忍」に注目)、「せう(で「笑」となる)」(動詞「す」の未然形に助動詞「む」の音変化)。結句は補助動詞「ゐる」の未然形に尊敬の助動詞「やしやる」の命令形だと「居し」の「し」が説明できない。「おぢゃる」の未然形に助動詞「しゃる」だと「ら」が脱落する。辞書では追い切れない破格の用法である。
茄子(なすび)こそ瓜実顔にまけましと油付(け)たり串を指(し)たり
こぬ人を隣(り)もまつか小夜更(け)て灰吹(き)たたく音のみそする
歌枕ひと夜双へて寝たれとも男同士は恋の部はなし
一首目の題は「寄茄子田楽恋」。虫歯で黒くなった歯を茄子歯と云い、美人度で瓜実顔に対して茄子は劣勢のようだ。油はともかく「櫛」が「串」であるのも面白い。二首目の題は「待恋」。四句の「灰吹(き)」は煙草盆に付属した竹筒で、煙草の灰や吸い殻を落とした。煙草盆は盆と火入れと灰吹きでセットになっている。三首目は題詞「卯月廿六日一日百首の会の夜森本宗範丈と一所に浄照坊に一宿して翌日別るるとて」。「丈」は二人「だけ」で布団を「双(なら)べて」ということだろう。「宗範」の名は『後撰夷曲集』にも登場するが「作者之目録」によると「西村氏」である。「人名索引」はどちらも「宗範」で区別ができない。
有漏路(うろじ)より無漏路(むろじ)へ我は二休みとくと雨風止(み)てゆかはや
蓮葉においどすはるとくみてしる思へはもはや三年しやもの
口上にちゐか出(で)ねは竹田芝居しやて歯のぬけた様に見えぬる
ちつとした機関(からくり)なれと玉の緒は竹田近江も力及はす
一首目は題詞「我身行年八十歳なれは凡(そ)人間五十年といふふたりまへなれは」。『一休はなし』(『狂歌大観』参考篇)に〈有漏路より無漏路へかへる一休(み)雨ふらばふれ風ふかばふけ〉がある。結句の「ばや」は終助詞で願望また意志を表す。二首目の題は「妙隆三廻忌に」。初句は「はちすばに」、二句「おいど(御居処)」は女性語で「尻」、上を受けて「据わる」、下に向けて「座る」、三句は足を「組みて知る」、妙隆は妙隆尼だったと思われる。三首目は題詞「竹田口上甚右衛門死去せしと聞(き)て」。二句「ちゐ」は「ぢい(爺)」であろう。四句「しやて」は接続詞の「さて」、口上の際の常套句だが歯が抜けているので「しゃて」となった。四首目は題詞「竹田近江死(に)けるをおしみけれは」。絡繰り芝居で名を馳せた竹田近江は四世まで続くが、右は一七二九年に亡くなった二世と思われる。初句「ちつと」は「ち(些)と」の促音添加で「ちょっと」に同じ、三句「玉の緒」は命である。
|
| 第138回 置みやけ(7) |
ふくと汁よく味(は)ふて誰も見よあわの鳴戸は北枕なし 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌は無題。初句は「河豚魚汁」でフグの身を入れた味噌汁。四句「あわの鳴戸」は「鳴門海峡」の異称、「北枕」はフグ科の海水魚、そのフグは鳴戸海峡にいない魚だから三句「誰も見よ」となる。「北枕」の今一つの意味は死者を寝かせるときの作法である。四句の「阿波」が「泡」になって二句が効いてくる。「味(は)ふて」は「味はひて」のウ音便となる。
夏衣うすき縁ともさもしらて来春参らふといふて北村
黒髪の末長かれと神さまをめうかあらせ給へと祝ふことふき
公界(くがい)せぬ宿は聞(き)わく事そなき米の高ひも伽羅の安いも
老の浪よるの衾のすき間より風の入江は寒きあし哉
一首目は題詞「和歌山御薬酒所北村源次郎親父に去(る)子の五月十六日に初(め)て逢(ひ)一宿迄せしに同年八月に死去と今年丑の八月に聞(き)侍りて」。初句「夏衣」は「うすき」に掛かる枕詞、三句は「さも知らで」、結句は「北」に「来た」を掛けた。二首目は詞書「孫娘の名をふきといふも神のめうかあらせ給ふと思ひて髪置(き)のめてたさに」。「髪置き」は幼児の頭に白髪をのせて長寿を祈る儀式、「めうか(冥加)」は神の加護、三句の場合は加護に対するお礼で産土神に参拝したと読む。結句「ことぶき(寿)」に孫の名前を重ねた。三首目は「述懐」。初句「公界せぬ」は「人前へ出ない」。二句「聞(き)わく」は「納得して従う」。本来は「聞(き)わくる」だろう。情報不足が社会との溝を深くしているのだ。四首目は無題。初句は「年波」、二句「よる」は「寄る」に「夜」を重ねる。「衾」は現代の掛け布団に相当する。結句、寒風に晒される「あし」に「足」と「葦」を重ねた。
たひまくら幾度酒のかんをして呑んてあかしのむまやむまやと
冨士の山影は二つやみつしほを一荷(いつか)にするか田子の浦人
風そよく柳の枝のつはめかや秋は故郷へ帰去来
一首目の題は「羇旅」。藤原定家の〈たびまくらいくたび夢のたえぬらんおもひあかしのむまやむまやと〉(『夫木和歌抄』一四八八一)が本歌である。題は「駅」で「あかしのむまや、播磨」とある。「明かしの駅駅」で「恋」の歌と思われるが貞柳の方は「空かしの美味や美味や」であろう。二首目の題は「田子の浦に冨士のうつりし絵に」。二句の「影」は目に見える冨士の姿を云う。三句は「満つ潮を」(「満つ」は古くは四段活用だった)。五句「一荷」は一本の釣り糸に二本以上の釣り針を付けて一度に二匹の魚を釣ること。よく見ると数字が「二(つ)」「みつしほ(三四)」「一」と出てくる。三首目の題は「柳に燕の絵に」。燕は夏鳥として春に飛来する。三句の「かや」は終助詞で感動、詠嘆を表す。秋になると南方へ帰るからだ。見せ所は結句で陶淵明の「帰去来の辞」を念頭に置いて「帰りなんいざ」と読む。
|
| 第139回 置みやけ(8) |
ありし世の玉露霜ともおほしめせ是皆さまへ置土産そや 由縁斎貞柳(『置みやけ』)
掲出歌は無題。永田貞竹の後記のあとに二首並ぶ、その二首目の歌である。二句「玉露霜」とは何か。煎茶の玉露は十九世紀、音の似た玉露糖は江戸吉原の名物で除外、残るのは「露霜」(年月・星霜)に接頭語の「玉」、露を玉に見立てた「玉露」もあるので「ぎょくろそう」と読みたい。生者に遺すことを当初から意識し、計画した遺歌集であることがわかる。
ゑんこうの望む心の月やさしこちらはいもに手をのはすのみ
そろはんを置(き)てにににと笑ひぬる大黒殿はかねやのびけん
乗合の舟は寝る人起(き)る人夢をくたきて分(け)て見るかも
一首目の題は「猿猴の月を取(る)絵に」。猿が井戸に映った月を取ろうとして溺死した故事から、身分不相応なことを望む喩えとされる。しかし貞柳は下句に身分相応の芋に手を伸ばす人間を配して猿の心を諒とした。二首目の題は「大黒の小露盤おく絵に」。「小露盤」は大黒の「大」を意識した宛字で「そろばん」と読ませている。結句の元は「金を伸ばす」で「金を増やす」。大黒は七福神の一、二句「にににと」は白い歯が見えるようである。三首目の題は「伏見舟にて」。上句、寝る人と起きる人は一人の中でも繰り返される。下句はひと続きの夢を何度にも分けて見る、意と解した。併せて船首が砕く波のイメージを重ねた。
ほめ給ふ御意はしやうゐんせられねと詞の花は匂ふ藤村
よい物を持(ち)てもそれにつかはるる身は鑓もちに髭のないもの
はなになき鳥に驚くめに逢(ひ)て我(が)家土産にとちめんほふる
一首目は題詞「藤村正員方より 狂歌よむ上手の程をいはふならむかしは家隆今は貞柳 その返しに」。二句の「しやうゐん」は「承允」または「承引」に「正員」を掛けた。家隆と狂歌だが正徹の『清巌茶話』(風間書房『日本歌学大系』第五巻)に「家隆卿稚き時、霜月に霜の降るこそ道理なれなど十月に十はふらぬぞ とよみ給ひしを、後鳥羽院は重宝に成るべきものなりとて御感ありし也」とある。また順徳天皇の『八雲御抄』(風間書房『日本歌学大系』第三巻)に「家隆卿がをさなくて、『など十月に十はふらぬぞ』とよみたるこそ、山口しるくめでたけれ」とある。「山口」は前兆。『新撰狂歌集』では定家作にして俊成との父子問答を創作している。二首目は無題。諺に「鑓持ち鑓を使わず」がある。これは裏を返すと鑓に「つかはるる身」となる。さらに駄目押しで鑓持ちが鎌髭(かまひげ)とは限らないことをことを云う。三首目は無題。掲出歌「ありし世」と並ぶ歌である。上句、花鳥茶屋(珍しい鳥獣を見せ物とした茶屋)の繁盛は十八世紀の末らしいが、それに似たものがすでにあったのだろう。下句のための舞台装置である。四句「家土産」は「家苞」の意味と解して「いへづと」と読んだ。「家土産」は次の「置土産」だから結句「栃麺棒振る」で「あわてふためく」意となる。
|
| 第140回 狂歌糸の錦(1) |
今比はいかにもいかにも彼岸へすくひとられん鯛や貞柳 佐谷可親(『狂歌糸の錦』)
『狂歌糸の錦』は百子堂潘山の編、「狂歌糸の錦」として貞柳追悼狂歌、「狂歌糸の錦附録」として諸氏の狂歌集という構成である。享保十九年十二月の刊だから貞柳の死から四ヶ月である。掲出歌の題は「翁に自答のくせありしを」。二句がそれ、三句「彼岸」は「かのきし」だろう。四句「すくひ」は「救ひ」に「掬ひ」を掛けた。結句の「や」は「鯛屋」から「鯛」を取り出した。屋号から切り離されることによって鯛はイメージの中で躍ったのである。
釣(り)棹のいとたうたくも鯛屋翁仏の御手にかかり給へは
たえかぬる二日灸の切もくさ我も昔のいとならなこに
盃のうちへそ酒のみちとせやももとは下戸の詞なるらん
名の高ゐ汐干じやさかい誰誰もにじり廻つて来るにかい有
一首目の作者は永田布声、無題だが追悼歌である。二句の「いと」は「糸」、これに副詞の「いと」を重ねた。二首目より「附録」に入る。作者は常女、題の「二日灸」は陰暦二月二日にすえる灸、この日にすえると無病息災だった。結句の「いと」は「幼児」、当時は男女どちらにも使った。「なこに」は方言で「泣こ(う)に」と読む。三首目の作者は一好、題の「上巳」は五節句の一、陰暦三月の最初の巳の日。のちに三月三日(桃の節句)。三句から四句に不老長寿の「三千歳の桃(みちとせのもも)」を隠す。三句は酒の「満ち」となり、四句「もも」は副詞の「も(う)も(う)」で酒を辞退する場面となる。四首目も「上巳」で作者は花すけ、潮干狩りは陰暦三月三日の行事であった(春の大潮)。二句「じや」は断定の助動詞、「さかい」は接続助詞で原因・理由を表す上方語である。四句から結句「~に」までは泥の中の蛤を足の裏で探している様子である。その結果「貝有り」また「甲斐有り」となる。
いかのほり親の心も空になり子ゆへの昼に迷ひこそすれ
あげ過(ぎ)て天も鼻にやつきぬへし空はさなから紙鳶(いか)のあへもの
毎夜毎夜そなたへむいて拝みます本尊かけたとたつた一声
一首目の作者は貞柳、題の「鳳巾」は「いかのぼり」。二句から三句の「心も空」は上の空、これに凧(紙鳶)の上がっている「空」を重ねた。四句「子ゆへの昼」は「子ゆえの闇」の言い換え、親が夢中なのだ。二首目の作者は可親軒、同じく「鳳巾」である。初句は数が多いので、二句「天」も飽きて嫌になっているだろう。結句「紙鳶(いか)」は「いかのぼり」の略、同音の「烏賊」を重ねて料理の「和え物」を導いた。三首目の作者は似錦、題は「郭公」(ほととぎす)。『日本国語大辞典』(小学館)で「ほぞんかけたか」を引くと『犬筑波集』の〈ぶつだんに本尊かけたかほととぎす〉がある。二句「そなた」は場所、方向を示す「そっち」で仏壇。「おまえ」の意で「郭公」。結句のあとから初句に戻る、倒置法である。
|
| 第142回 狂歌机の塵 |
祝ひに水かかれとてしもかそいろは我に女房呼(ぶ)はせざらん 由縁斎貞柳(『狂歌机の塵』)
『狂歌机の塵』は「一周忌の祭詞」(序)として永田貞竹によって享保二十年に刊行された。「机の塵」は『置みやけ』に漏れた貞柳の作百三十余首を指す。掲出歌の題は「水祝」、婚礼の際または新婚翌年の正月、新郎に水を浴びせて祝った。三句「かぞいろ」は両親、四句「我」は正月を迎えた若者、息子と一緒に水を浴びよと嫁を呼ぶことはしないだろう、と読む。
行(く)年の惜(し)くも有(る)哉ひん鏡那知にて花をやるもけふ迄
涼み床うなきはあれど雨の夜はかわらをぬめる人そすくなき
神啼につけふ薬のあらされは道三箱を捨(て)し六尺
長生(き)をしたるはかりに鰭もなし昔の鯛や今のたら魚
隣まて来たる無常の旅衣よいつれなれとちと用か有(る)
高瀬舟浪に入(り)日のまつかいに猶見ゆるかな大仏の門
一首目の題は「八十の暮に」。三句は「鬢鏡」で柄つきの小さい手鏡を云う。四、五句の「花をやる」は世にもてはやされる意である。「高野六十那智八十」、男色の盛んだという那智でも八十が相手にされる上限だった。二首目は題詞「祇園会雨降(り)けれは」。場所は鴨川の河原、初句「涼み床」では寝そべる人も多い。それを「うなぎ」と云った。四句「ぬめる」は「すべる」と「浮かれ歩く」の両意がある。三首目の題は「神鳴」。初句「神啼」は地上に落ちた雷だろう。二句「つけふ」は「付けむ」が変化して「付けう(ふ)」か、四句「道三箱」は往診の途次の薬籠、著名な医者である曲直瀬道三(まなせどうさん)(一五〇七~一五九四)に因る。結句の「六尺」は下男のこと、イメージに反した行為が人間くさい。ちなみに藪医者が地上に落ちた雷を治療する狂言『神鳴』(小学館『日本古典文学全集35』)がある。四首目は「述懐」。四句「鰭」は「貫禄」を云う。結句「たら」は近世上方語で「昔の鯛や(屋)」も「(今の鯛)とやら(申す魚)」になる。五首目は題詞「雛ャ町毛馬屋太郎兵衛追善」。下句は老人会等の長寿訓で今でも活かされているようだ。六首目の題は「高瀬夕照」。三句の「まっかい(真っ赤)」に出航を「待つ櫂」を掛ける。高瀬川(鴨川から分水し、伏見を経て淀川に通じる運河)から東山区の方広寺を遠望する図である。この頃は三代目の大仏が健在だったようだ。
世に住(め)ば扨も願ひのいと多き小判付(け)たる笹に短尺
女をは鬼といふたもことはりよ弾する時は爪が三本
半数を占める門弟の作より二首引く。一首目の作者は百子、題は「七夕」。飾り竹に「小判」があるのは金に不自由しないようにという願いだろう。「短尺」も推して知るべし。初句「世に住めば」とはそういうことなのだ。二首目の作者は其考、題は「琴」。琴爪は右の親指、人さし指、中指にはめる。これに角と裂けた口、三本の爪という鬼のイメージを重ねた。
|
| 第143回 狂歌ますかがみ |
短尺に今宵たちぬる雲紙よふたつの星の中なへたてそ 栗柯亭木端(りつかていぼくたん)(『狂歌ますかがみ』)
『狂歌ますかがみ』は栗柯亭木端編で享保二十一年正月刊、序に「愚詠に批判を受(け)添削せられし詠草又みつからの詠せられし折々の歌をその紙のはしに書(き)付(け)られしままをそれなから写して」云々。木端(一七一〇~一七七三)は貞柳の高弟、栗派の祖、浄土真宗の僧侶であった。掲出歌の題は「七夕短冊」、三句「雲紙」は上下に雲形を漉き出した鳥の子紙で内曇りとも云う。二句は短冊用に「裁ちぬる」、これに「立ちぬる(雲)」として四句に繋いだ。結句は「中な隔てそ」で恋の邪魔はしないでおくれよ。優しい歌だ。
ほとときすさそな鳴(く)らん死出の山聞(き)たけれとも行(く)ことはいや
月かけはあまのはらなる臍か扨(さて)かみなりとののなるとかくるる
七夕に子供もすなる短冊を我も手向(け)ん老(い)のこしおれ
をときけは誰も心はうつはりのちりつててんのおとりさみせん
一首目の作者は貞柳、題はない。一首は俗説「時鳥は冥土の鳥」に拠った。また時鳥の別名に魂迎鳥や死出田長があるのも参考になる。二首目の作者は貞柳、題は「我等此比(このごろ)夕たちの後に月を見て」。初句の「月かけ(影)」は月の姿を云う。二句は「天の原」で空の意、「原」と同音の「腹」から「臍」を出し、「雷殿」が臍を取りに来るという口碑を効かせた。三首目の作者は貞柳、題はない。二三句は『土佐日記』の冒頭「男もすなる日記」(小学館『日本古典文学全集9』)を効かす。結句「こしおれ」は腰折れ歌であり、また腰の曲がった老人を云う。四首目の作者は木端、題は「踊三味線」。三句から四句「うつばり(梁)の塵」に三味線のオノマトペ「ちりつててん」、「ちり」の二音を重ねて成句「梁塵を動かす」(歌や音楽に優れていることの喩え)を連想させる。「踊三味線」は不明だが曲弾きの一形態と解した。
ささをのみ饅頭くへは象を見し春にも増る秋のよの月
正直の頭(こうべ)もいたし神無月あまり時雨の誠すきるで
神無月あまり時雨は誠すきたちと偽りて日和なれかし
一首目の作者は貞柳、歌評に続けて「我等も名月に」とある。象を見たのは享保十四年(一七二九)の四月で、このときのことは『家つと』や『狂歌乗合船』にも登場する。「ささ」(酒)と「饅頭」を添えて秋の名月は格別であったらしい。二首目の作者は木端、題は「神無月霖雨ふり続きけれは」。一首は定家の〈偽のなき世なりけり神無月たがまことよりしぐれそめけむ〉(『続後拾遺和歌集』四一五)を念頭に置く。初二句は成句「正直の頭に神宿る」に拠った。定家の「まこと」は名詞「偽りのない心」、木端の「誠」はこれを踏まえて副詞「本当に」を表面に出す。従って結句は「誠、過ぎるで」。三首目の作者は貞柳、題は「翁のかへし」。三句は同様に「誠、過ぎた」、しかし四句以下には名詞「偽りのない心」の意で繋いだ。
|
| 第144回 狂歌ますかがみ(2) |
たけたかふたけ長ならてうつくしふよふいひなしたかつらきのかみ 栗柯亭木端(『狂歌ますかがみ』)
掲出歌は題詞「道頓堀日本橋のほとりの女のかつらをかさりし見世に和田忍笑の歌とて 岩橋と日本橋のちかひにて扨もうつくしかつらきのかみ と書(き)付(け)て有(り)しをみて」。結句は「葛城の神」に「鬘」と「髪」を掛けた。「鬘」は日本髪を結うときの髪文字(添え髪、入れ髪)を云う。初句「岩橋」は役行者が葛城山と金峰山の間に架けようとした伝説の橋で、容貌の醜さを恥じた葛城の神が夜しか働かなかったので完成しなかった。謡曲『葛城』(小学館『日本古典文学全集33』)によって広く知られていただろう。木端の初句「たけ(丈)」は歌学用語かつ髪の縁語、二句「たけ(丈)長」は和紙を細長く切って平らに畳んで元結いの上に装飾用として結んだもの、いずれにも岩橋の「丈」が透けて見える。
こひ死ぬる夜半の煙の雲とならは君か洗濯の日毎に時雨(れ)ん
傾城の浮(き)身の上を夕時雨すいとふすいにふりみふらすみ
君か代の久し王余魚(かれい)のためしとて兼(ね)てそ石に魚の見えぬる
一首目の作者は木端、題は「寄雲恋」で「翁評云扨々御秀逸吉水和尚の上句を直に用ひて下の句一作有之是等を箔の小袖に縄帯の躰と可申候」とある。本歌は慈円の〈こひしぬる夜はの煙のくもとならばきみがやどにやわきてしぐれむ〉(『新勅撰集』九九三)。いずれも、お宮を足蹴にする貫一の台詞が思われる(『金色夜叉』)。二首目の作者は木端、題は「寄時雨恋」。二句「浮(き)身」は仰向けで水に浮かぶこと、これに「憂き身」を掛ける。その「私」に「夕時雨」が「降りみ降らずみ」と云う。四句は一に「水道水」(川筋の水)、二に「粋と無粋」で「振りみ振らずみ」となる。三首目の作者は貞柳、題は「魚骨石」。二句「王余魚」は字音で「ワウヨギヨ」、「鰈」の意で同音「佳例」と「餉」が浮かぶ。三句「ためし」(先例)とは「いはほとなりて」(石)、四句「兼ねてぞ」は「餉」の文脈で化石の「魚」となる。
なき人をかそへてみれは三つ四ついつそは我もよみやこまれん
西をさして乗合船は出(で)て行(く)南無あみた仏我はをくれた
むかしむかしの咄と成(り)てさるの尻まつかうくさふなる親仁達
一首目の作者は木端、題詞に「あひ知れる人の多く身まかれるを見て」とある。四句「何時ぞは」で早晩、「何時」に「五」を掛け、結句は「読み」に「黄泉」を掛けた。二首目の作者は貞柳、題詞は「永井走帆此(の)ころ死去につき追善」。二句の「乗合船」は走帆の歌集名である。三首目の作者は木端、題詞に「翁の述懐の歌とて 祖父は山へしはしか程に年老(い)てむかしむかしの咄こひしき と読(め)りしに寄(り)て」とある。貞柳の歌は『家つと』に既出である。四句「真っ赤」に「抹香(まつかう)」を掛け、さらに副詞「真っ斯う」(全くこう)を重ねた。
|
| 第145回 狂歌ますかがみ(3) |
本復の日数はひいふうみかきもりゑしかりまたも今しはしなり 栗柯亭木端(『狂歌ますかがみ』)
掲出歌は題詞「やつかれ痔を憂(ひ)し比かかりし医の今少(し)にて全快たるへきよしいひけれは」。三句は「御垣守」(宮中の諸門を警固する人)に「ひいふうみ」の「み」を重ねた。さらに「御垣守」の縁で四句「衛士」(宮中の警護に当たった兵士)を導入、但し四句「ゑしかりまた」は「ゐじかりまた(居敷股)」の訛り、両足を広げた中腰の姿勢となる。肛門の異称として菊があり、菊は畏れ多いが皇室の紋章で御垣守が警固する門にも通じる。情けない格好だが背に腹はかえられない。結句「今暫し」の辛抱で真っ直ぐに戻れるのだ。
かりくらし夜は轡むしささめきてせこをまつ虫鷹の鈴虫
すほうてはあしうかかめはひたおれて身のいつまいかむつかしうなる
見たらなを我をや折(れ)なん大象の長ひはなしを聞(く)につけても
一首目の作者は貞柳、題は「秋虫を」。初句は「掻き暗し」に似せて「狩り暮らし」、馬に縁語の「轡」を出して、しかし「轡虫」となる。三句も「狩り」を思わす「笹」があり、四句「せこ」は「背子」に「勢子」を重ね、「待つ」は「松」となる。結句は狩りのイメージで「鷹の巣」、その「す」音を借りて「鈴虫」となる。二首目の作者は木端、題は「国の名十を一首の中によみいれて」。「すほう(周防)」「ては(出羽)」「あしう(阿州=阿波)」「かか(加賀)」「ひた(飛騨)」「身の(美濃)」「いつ(伊豆)」「いか(伊賀)」「むつ(陸奥)」「かしう(加州=加賀)」で「加賀」と「加州」が重なるが十の国名には違いない。意味を追えば〈素襖では悪しうかがめば襞折れて身の居ずまいが難しうなる〉。三首目の作者は木端、題詞「象の登りし比他所に有(り)て見さるゆへ人の咄すを聞(き)て」。二句は「我を折る」で「驚き入る」「閉口する」の意がある。四句は「はなし(咄)」に象の「はな(鼻)」を掛けた。
名人のゆかりの色の花あやめあやなおやちのおもかけそする
此(の)氷水より出すに砂糖より出て砂糖よりあまきあちかな
ゆきかけの駄賃とやらて老(い)の坂はんとうそくの年をとらはや
一首目の作者は木端、 題詞は「吉沢あやめは名高きあやめか子のよし聞(き)て」。「名高きあやめ」は『家つと』で〈四つ橋に杜若こそあらすとも人にみせはやほりの菖蒲を〉とある初代「芳沢あやめ」であろう。助詞「の」の使用、「あや」の繰り返し、変化させた「おや」と韻を踏んだ結句、いずれも絶妙である。二首目の作者は木端、題詞に「人の許より氷砂糖をもらひて礼状をつかはすとて」。成句「氷は水より出でて水よりも寒し」(「青は藍より出でて藍より青し」)を効かせた。三首目の作者は貞柳、題詞は「我等当春八十になれは歳の初めに」。一投足で僅かに足を動かすことだから四句「半投足」は相当に遅い。初句から二句「ゆきかけの駄賃」とはスローモーションで残り少ない此岸を味わおう、そんな意味だろう。
|
| 第146回 狂歌戎の鯛 |
一もんの尾ひれともなる法の橋かかるめてたい事も有(る)かは 永田柳因(『狂歌戎の鯛』)
『狂歌戎の鯛』は元文二(一七三七)年刊、編者は永田柳因、芥河貞佐の序に「永田の家の風をふきつたへんと此(の)集をあめるになん」とある。掲出歌は題詞「伯父貞峩は父兄の宿望をとけんとてふるとし幸(ひ)に法橋位を蒙(る) 勅許ふりにし鯛屋も二度ひれ振(る)心地すれはよろこひに堪(へ)す」とある。貞因の「山城大掾」以来なのだ。二句「尾ひれ」と四句「めてたい」に鯛屋を刻み、結句「かは」に「橋」の縁語で「川」を掛けた。法橋位授与の理由は序では俳諧、『日本古典文学大辞典』(岩波書店)では医師と異なる。
かり葺(き)のさやかにてらす影もりて宵々毎に月も湯に入(る)
ぞべぞべとちちたる春の遠ありき子にかこつける恋もする哉
七種の内ならままよ仏の座鰹はゆるせ今朝の雑炊
木の端のやうに思へと此(の)法師つれつれの儘取(り)て上げます
一首目の作者は貞柳、「梓氏か望(み)に任(せ)貞柳か有馬の記爰にしるす」一連で題詞は「去年酉の冬類焼已後いまた湯のさや仮り屋なれは」。「さや(鞘)」(外囲い)と「仮り」を使い、結句で月を擬人化した。二首目の作者は摸稜舎百子、題詞は「乳母の恋といふ事をよめといふに」。初句「ぞべぞべ」は動作の不活発なさま、二句「ちち」に「遅々」と「乳」を掛けた。「乳母」よりは「ねえや」のイメージである。三首目は芥川貞佐、題は「七種」。「仏の座」も混じっているが七草の一つだ、ええい儘よ、と云うのだろう。「鰹」は「鰹節」で殺生戒に触れるのだ。四首目も貞佐、題詞は「野辺より土筆を取(り)帰り人のもとへ送るとて」。土筆はスギナの胞子茎だから「木の端」で、三句「法師」に「胞子」を掛けた。
ほとときす鳴(い)たあとしやとあきらめて只有明の月をみていの
かしこきは耳順ふとの給へと我はしたひに遠くなり行(く)
今まては無性に世をも暮せしにたたしやなるまひ三十の春
おのこ子のけに節句とて粽さへつゐ引(き)結ふ草の縄帯
一首目の作者は芥川貞佐、題は「時鳥」。藤原実定の〈郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる〉(『千載和歌集』一六一)の下句の利用また平親宗の〈有明の月は待たぬに出でぬれどなほ山深き郭公かな〉(『新古今和歌集』二一二)が背景に浮かぶ。二首目の作者は空有軒虚中、題は「愚僧六旬の迎春」。二句「耳順ふ」の出典は論語で六十歳の意、これを文字通りに解し、不賢・耳不順で聴力の低下の意を重ねた。三首目の作者は西園斎米都、題詞は「歳旦ことし三十に成(り)けれは」。二句「無性に」は「やみくもに」の意、四句「たたじや」は「立たでは」の音変化と解した。論語「三十にして立つ」に拠る。四首目も米都、題は「端午」。二句「けに」は「げに(実に)」、結句の擬人化からは石合戦が連想される。
|
| 第147回 狂歌戎の鯛(2) |
蓬莱におよきつきたる亀太郎是そふつきのはつ朝そや 永田柳因(『狂歌戎の鯛』)
掲出歌は題詞「ことし二歳の小悴有(り)伯父長命をゆつらんとて亀太郎と名つく座敷の往来亀の水にをよくことくなれは」とある。「二歳」は満で云えば一歳、まだ這い這いなのだ。初句「蓬莱」は一に新年の祝儀の飾り物、二に不老不死の島を云う。四句「ふつき」は「福貴(ふっき)」と解した。結句「はつ朝」は五音で「はつあした(初旦)」の意であろう。
白髪あらぬその前髪の春ならていつも心はもとの巳の年
木男にむすひかかりし花嫁に八千代もかけてさけとことふく
かね持(ち)の驕(り)をしめす蘇鉄哉こもをかふつて冬の有様
袖とめの御料理祝ひ申さはやおなかふくりとなるそ嬉しき
一首目の作者は湖月堂可吟、題は「元文二巳」の「歳旦」。初句七音、額の黒髪を束ねていた少年の頃、そんな歳旦であるわけもないが気持ちだけは昔と変わらない。結句は「黒髪の巳の年」だろう。二首目の作者も可吟、題詞に「壮年の比まて妻女をむかへさる人の縁辺すみ約束の酒なとつかはされしをことふきて」。「縁辺」は婚約、「木男」は無骨、無粋な男。結句「さけ」は「花(嫁)」の縁で「咲け」、これに「酒」で寿いだ。三首目の作者は風知、題詞は「冬蘇鉄を見て」。資産家の庭の景、その宿の主を零落させて立たせてみた。実際は冬支度をすませた蘇鉄だが「薦を被つて」即ち乞食に見えなくもない。四首目の作者は友房、題詞は「袖とめの祝儀振(る)舞(い)に懐躰の事をことふきて」。できちゃった婚ではなく偶然が重なったのだろう。四句「ふくり」は祝う側、祝われる側双方の「おなか」に掛かる。
元日の人のこころに花さけは御慶御慶もよし野山ひこ
見事にてこはりますとは申せとも今吹(い)てなし是は山吹
盂蘭盆は鬼も地獄に渡世なら娑婆に来りて火燈(し)をする
極楽といふはかふしたことやらん石碑のあたり節季けもなし
一首目の作者は柳因、題は「元旦」。上句は新春を迎えた喜び、四句「御慶御慶」で賀詞の交換、結句「よし」に形容詞の「好し」と「吉」を掛け、花の吉野の「山ひこ(彦)」に擬えた。二首目も柳因、題は「寄新清水の山吹」。「新清水」は天王寺区の清水寺、二句「ごわります」は「ある」の丁寧語である。山吹で有名だったらしい。四句は咲いていない様子、これに玩具の山吹鉄砲を効かせた。三首目も柳因、題は「鬼面燈籠」。盂蘭盆は地獄の釜の蓋もあいて休み、しかし喰っていかなければならないので娑婆へ出稼ぎに来たのである。結句「火燈(し)」は火を点す係りを云う。四首目も柳因、題詞は「歳暮に廟参して」。結句は「け(気)もなし」で、そのような気配がない、この「気」が「節季」の接尾語にもなっている。「節季」は「歳末」、世の中は節季仕舞いでばたばたしているが、さすがに廟所は別世界なのだ。
|
| 第148回 狂歌種ふくべ |
自由さは橋の数さへおほ坂の栄えを爰(ここ)と渡る初東風 水谷李郷(『狂歌種ふくべ』)
『狂歌種ふくべ』は永井走帆詠、水谷李郷編で元文二(一七三七)年の刊、金花翁鬼貫の序によると走帆の七回忌である。「種ふくべ(瓢)」は種子をとるために残しておく瓢箪を云う。掲出歌は「春」の部の作、三句「おほ」は「大」に「多」を掛けた。大坂は天下の台所、八百八橋に象徴される水都でもあった。結句「初東風(はつこち)」は初春の風を云う。
新椀の漆のかざもほのほのと吉野ははなの春たつの年
こまやかに落(ち)る粉雪の白妙は空にかすみのきぬふるひかも
おもしろう花の下にてたのしむも鼻の下にて呑(み)喰(ふ)かゆへ
風の手も花にはいとふ習ひしやに雨のあしとは慮外千万
一首目の作者は熊川中葉、題は「辰のとし元日に」。二句の「かざ(香)」は匂いや香り。濁音符は珍しいが読者に伝わらないことを心配したのだろう。吉野は漆の産地で漆器は吉野塗、したがって「新椀」は吉野椀となる。二首目の作者は雪縁斎一好、題は「春雪」。二句「粉雪」は「こゆき」と読みたい。結句「きぬぶるひ(絹篩)」は底に絹を張ったきめの細かな篩、空を仰ぐと霞のように見えるのだろう。三首目の作者は走帆、題は「花」。二句「花の下」と同音の四句「鼻の下」で「花より団子」。桜の下での宴会風景は昔も今も変わらないようである。四首目の作者は一好、題は「雨中花」。初句「風の手」と四句「雨のあし」は擬人化の対句表現である。手で触られるのも避けたいのに、足で踏みにじられるのは無礼千万というわけだ。三句「じゃ」は「である」の音変化の末、助詞「に」で「であるのに」の意となる。
早乙女は御田(おんだ)の雨にしよほぬれてけはひし皃も半けしやう哉
花代のいらぬあやめをやらふとて御持参うれしいけてよし沢
生玉のばばの老(い)木になく蝉も祖父(じい)や祖父やとこかれ社(こそ)すれ
一寸も手のはなされぬ夏の日はあつさ六ふにしふうちわ哉
一首目の作者は岡本流水、題詞は「亥年住吉御田植(ゑ)に雨しけり此(の)日半夏生なれは」。二句「御田」は「御田祭り」の略、神事なのだ。結句「半けしやう」は「半夏生」に「半化粧」を掛けた。四句「皃」は「顔」の異体字。二首目の作者は李郷、題詞は「菖蒲の花を手つからもて人のくれけれは」。歌舞伎俳優に「芳沢あやめ」がいた。初句「花代」は芸者の揚げ代、祝儀なら「花」でよい。後者だろう。これは「あやめ」が女形であることに拠った。結句「芳」に「良し」を掛ける。三首目の作者は田口嘉祐、題は「生玉蝉」。二句の「ばば」は生玉神社の地名「馬場」に「婆(祖母)」を掛けた。蝉の鳴き声「祖父(じい)や祖父(じい)や」が効いている。四首目の作者は流水、題は「渋団に」。初句は「一寸」の両義性に拠る。一に時間、二に尺貫法。以下、尺貫法の一寸を「六分」と「四分(渋)」に配分して絶妙である。
|
| 第149回 狂歌種ふくべ(2) |
たんしりをまはし自慢の緋ちりめんまくりあけてはやれやいやれやい 山下一叟(『狂歌種ふくべ』)
掲出歌の題詞は「天満祭たんじりに」。『大阪ことば事典』(講談社学術文庫)で陸渡御の「だんじり(地車)」を引くと「舞車、我も我もと引連れて天満宮の方に向ふ。(略)車の上は檜皮もて葺き、前一段高く、後一段低し。四方に欄干あり。其上に舞子あり。太鼓・つづみの音かしましきまで聞ゆ」(大田南畝)云々とある。三句「緋縮緬」は舞子の長襦袢であろう。二句「まはし」は思うままに動かすこと、結句の掛け声から祭の熱気が伝わってくる。
下仕(げす)魚と花奢な口にはそしられて雑喉場(ざこば)のはなをひきいはし哉
長寝する人はいつしかはつ霜のをきやう習ふ隙(ひま)は有(る)まい
ふるとやらつめたいとやらいふ里にふと誘はれて初ゆきの興
かたはしに帳面に棒くらはせてくれぬるとしの夜こそねよけれ
一首目の作者は流水、題は「割(き)鰯」。初句は漁獲量の多さと類音「卑し」に因るらしい。「雑喉場」は大坂を代表した魚市場、後は「鼻を引き鰯」となる。「鼻を引く」で嚔をすること、誹られている鰯なのだ。「端」でも「引き鰯」である。二首目の作者は中村李因、題は「初霜」。初句の「長寝」は目覚めが遅いこと。四句「をきよう」は「起き様」だが「長寝する人」の「起き様」では「霜」の「起き様」(出来方)に習えないと云うのだ。三首目の作者は菅野岸洞、題は「遊里雪」。「ふる」と「つめたい」の両義性に拠りつつ「とやら」のリフレーン、「里」と「ふと」の類音語を効かせながら結句の「ゆき(雪・行き)」に集束した。四首目の作者は嘉祐、題は「歳暮」。二句は掛け取引に対する「棒引き」を云う。四句は「呉れぬ」に「暮れぬ」を掛ける。払う金があっての強気だが結句の「寝よけれ」に本心が覗く。
何事のおはしますともしらやまの神楽に巫か靨(えくぼ)こほるる
住みよしと人はいへとも世(の)中はわたりにくうもかけた反はし
いささかなさかななれ共とふぞしてお口にあちの早うつけたさ
田楽も扨やはらかや鬼つらの名めしはこはい筈とおもふに
一首目の作者は李郷、題は「白山の開帳に神楽乙女を見て」。白山は日本三名山の一、三句「しらやま」に「知ら」を掛けた。「しらやま」は「はくさん」の古称である。二首目の作者は嘉祐、題は「寄橋述懐」。住吉大社の反り橋は太鼓橋とも云う。初句の常套句から出発して四句の両義性、結句の名所で収めるところも堂に入っている。三首目の作者はつね女、題は「病気見廻に鯵のさかな送るとて」。初二句に「さかな」が二度登場する。下句は「鯵」を「届けたい」「食べてもらいたい」、また味覚(食欲)を云っているようでもある。「さ」は接尾語で感動だろう。四首目の作者は李郷、題は「鬼貫翁にて出来合の菜飯にてんかく物して」。鬼貫(一六六一~一七三八)は俳人、名前の「鬼」から「怖い」を四句「強い」に掛けた。
|
| 第150回 狂歌餅月夜 |
酒呑(み)ものまぬ人にも寒空は面向不背の玉子なるらむ 雪縁斎一好(『狂歌餅月夜』)
『狂歌餅月夜』は塘潘山堂百子編、刊記は元文五(一七四〇)年、貞柳の七回忌追善のアンソロジーである。塘潘山堂百子は『狂歌糸の錦』の編者、百子堂潘山と同一人物であろう。貞柳の弟、紀海音の娘婿である。掲出歌の題詞は「寒中見廻玉子送るとて」。下句「面向不背の玉」で前から見ても後から見ても美しい玉、これに「子」(子には違いない)と続けた。
春の野に出尻ふご尻打(ち)むれてあら用かましや鈴菜まいらせふ
時鳥啼(き)つる跡は短うて只かぶろ等があいいぞ残れる
星合(ひ)も見えぬ斗(ばかり)の黒雲は天の川にも硯洗ふ歟(か)
曇る歟とおもへはさつと晴(れ)わたる天の気にさへ村時雨哉
一首目の作者は高津法橋(紀海音)、題詞は「むつきの末暖(か)なる野に遊ひて」。二句「ふご尻」は大きくて平たい尻、四句「用(様)がまし」は注文が多いこと。結句「鈴菜」は春の七草の一、「蕪」の別名、葉ではなく根から尻への連想だろう。「参らせう」で「差し上げましょう」。二首目の作者は一好、題は「廓郭公」。四句「かぶろ(禿)」は上級の遊女に仕えた少女、結句「あいい」は「はい」の意で里訛り、見習い中だから三句なのだ。三首目も一好、題は「七夕」。初句「星合(ひ)」は牽牛と織女の二星が出会うこと、ここでは七夕の空の意であろう。短冊を書くにも硯だから実感がこもる。四首目も一好、題は「時雨」。「天気」は「気象状態」と「天子の機嫌」の両義を含む。三句までは前者、四句「天の気」で後者の比喩が加わる。したがって結句「村」から「斑気」の「斑」を読むことになる。
腎情のもれぬやうにと今爰(ここ)に立(て)る玉子のふはふはの関
百薬の長といへるも酒なれは薬茶碗て呑(む)も又よし
瓶井(みかい)なる法の御山の花を見てけふは命のせんたくをした
青二才なら帷子は着つれともけふここの目に田舎恥(づか)し
一首目の作者は一好、「題しらす」。初句「腎情」は不詳だが精力の類と解した。下句「玉子のふはふは」は玉子の料理名、かき混ぜるので「立(て)る」か。「ふは」に「不破」を掛ける。精気が漏れると腎虚、玉子は強精薬だった。二首目の作者は其水、題詞は「薬呑(み)侍りし折節友の来りて此(の)茶碗の形風流也よき盞とたはふれけるを即(ち)酒取(り)はやして」。「取り囃して」は「興を添えて」、友の戯れを肯んじたのである。三首目の作者は備前岡山の司喉、題詞は「瓶井山の御寺に詣(り)一日花を詠(め)て」。終日、花を詠い、花を眺めていたのである。「瓶井」が結句「洗濯」を呼び寄せた。四首目も司喉、題詞は「夏の頃都に上りて友諸ともにあなたこなたに見廻りて」。麻の裏なしが二句「帷子」、絹の裏なしが単、都は単が多かったのだろう。四句「此処の目」に類音語「九重」(都)を効かす。
|
| 第151回 狂歌餅月夜(2) |
月見んと難波の川の船遊び時々にくき橋くもり哉 百子(『狂歌餅月夜』)
掲出歌の題は「月」。近世の大坂は八百八橋を謳われた水都、橋の下を通るたびに月が隠れる、これを結句「橋曇り」と云った。ちなみに『新修大阪市史』(第三巻)は「主要河川の橋数と変化」で元禄四(一六九一)年を一一一橋、天明七(一七八七)年を一二三橋としている。うち公儀橋は一二橋、あとは町橋で大坂町人の財力に依存するところが大きかった。
臆病な人は薄の穂にも恐る月は暮(れ)より独(り)武蔵野
夏来ては涼しき里の道明寺むまひ所におはします神
悦ひのほらの貝かと音聞(け)ばいやいや器量よしの柏つほ
元旦は皆腹立(た)ぬ心から餅のふくれも目出たかりけり
一首目の作者は以翠堂貞惟、題は「武蔵野の月」。成句に「落ち武者は薄の穂に怖ず」がある。それだけに夜の帷の降りた原野を渡る桂男が美しい。二首目の作者も貞惟、題は「道明寺にて」。道明寺は大阪府藤井寺市にある尼寺、結句の「神」は菅原道真。謡曲「道明寺」や浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」で知られる。四句「むまひ(うまい)」は「得だ」「都合がよい」だろう。三首目の作者は貞堂、題詞は「男子平産の元」。二句「ほら(法螺)の貝」は泣き声、やがて虚報に変化する。「貝」は女陰の謂い。四句から結句は「器量良し」と「吉野榧(栢)粒」、「つぼ」は「つぶ」の音変化、「榧粒」は男児の陰茎の異称である。吉野では榧の木の本数が財産の標準であった。四首目の作者は似笠、題は「歳旦」。四句の「ふくれ」は「膨れる」の名詞法、餅が膨れる意に上句の「皆腹立(た)ぬ心」を受けて不機嫌の意を重ねた。
大晦日風のふいこが吹(い)てきてとてことてこと懸(け)取(り)の声
雲の鞘抜クしやなけれとびかびかと光鳴(り)そふ夕たちの空
けふよりを夏女房のはしめにて衣かへよき尻やふるらん
ちやうちんでもちゐられしも老(い)ゆへと門口でつい御礼申(し)た
一首目の作者は似笠、題は「年尾」。二句は「ふいご(吹子)」、四句「とてこ」はピストンが風を送り出す際のオノマトペ、これに「取(っ)て来(う)」を掛けた。「来う」は「来よう」の意である。二首目の作者は風知、題は「夕立」。初二句で「雲の鞘抜く」と出す。次に「じゃ(では)なけれど」と受けて流して三句以下でその比喩、イメージを逆に膨らませてみせた。三首目の作者は百子、題は「更衣」。二句「夏女房」は「夏の女性」の意、四句「よき」は上下に掛かる。袷から単衣、所作も活発になる季節である。四首目の作者は百子、題は「宵の程ものへまかりけるに道行(く)人の桃灯につけられけれは」。「提灯を付ける」で提灯を持って遊女や客の道案内する意、この場合は結果的にそうなった。また「提灯」は老人の役に立たない陰茎を云う。人(女性)にとっては安心だが老人としては複雑なのだ。
|