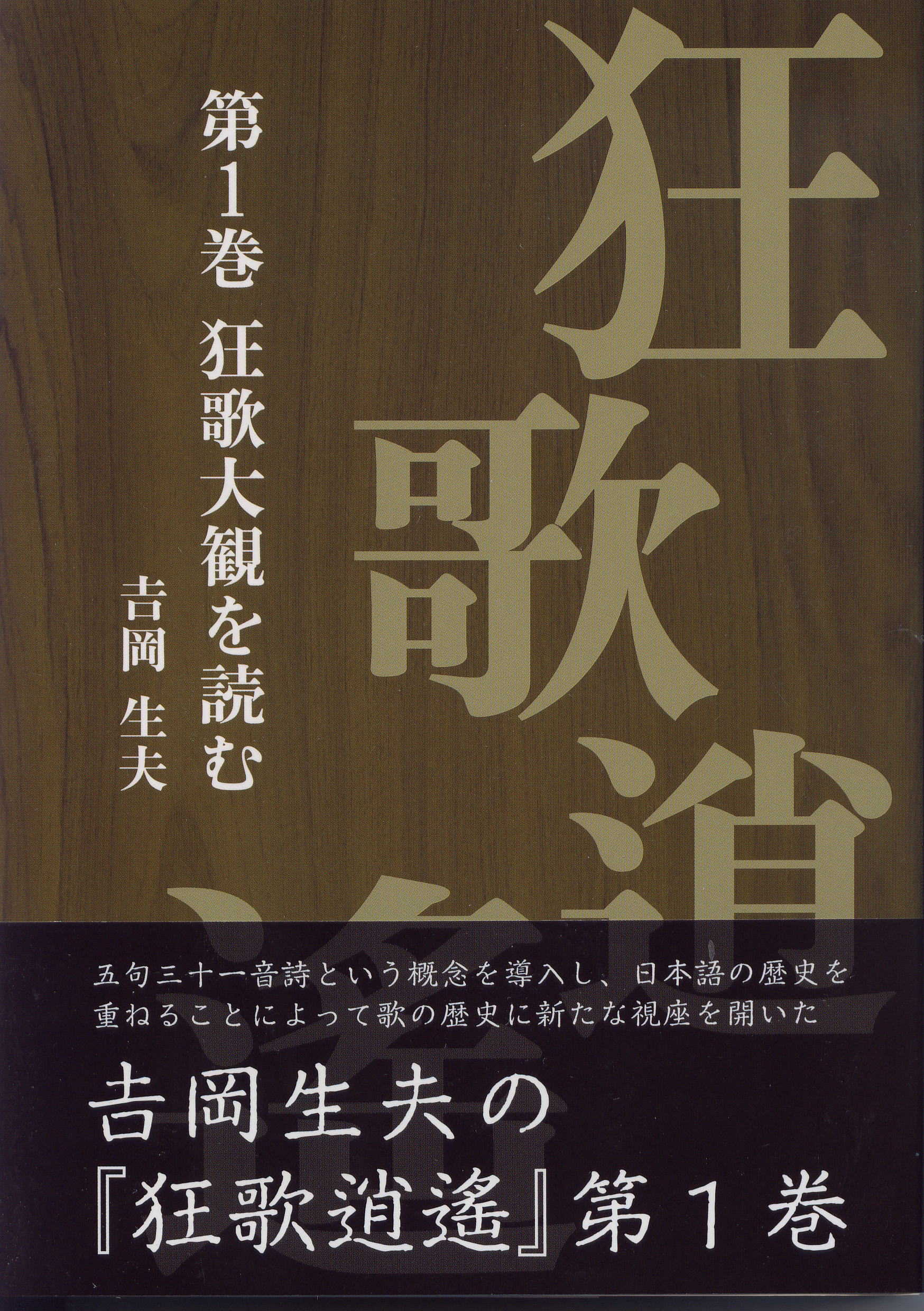| 狂歌大観を読む |
| 第101回以降は「狂歌逍遙(第1巻)~2~」でどうぞ |
| 第1回 東北院職人歌合 |
たたらふむやとの烟に月影のかすみもはてぬ有明の空 鋳物師
『狂歌大観』は『東北院職人歌合』のほかに『鶴岡放生会職人歌合』『三十二番職人歌合』『七十一番職人歌合』『職人歌合』を収録する。このうち『職人歌合』を除く四篇については岩崎佳枝の『職人歌合ー中世の職人群像ー』(平凡社)に詳しい。それに拠ると『東北院職人歌合』の成立は「建保第二の秋のころ」(序)即ち一二一四年の九月十三夜の念仏会である。詠者は、身分が極めて高い、歌の上手さ、職人との接点と理解から後鳥羽院、判者は後鳥羽院の護持僧であった慈円とする。『職人歌合』は代詠の文学であり「『職人』たちを仏道に結縁させようとの思いで、歌の詠めない『職人』になり代って創作を試みたのではなかったか。法会に参加し、座を連ねたあかしと仮りにするのである。詠者にとってもその行為は、取りも直さず仏教的善根となるわけなのである」と云う。掲出歌の題は「月」、踏鞴を踏んで夜が明けようとしているのである。金属を溶かすのは並大抵ではない。有明の月も霞んでしまう仕事場なのだ。
わか恋はなまし刀のかねあまみ思ひきれともきられさりけり
墨かねのなをきをたたす身なれともかたふく月にかふはりそなき
我(が)宿の砥水にやとる月影のあやしやいかにさひてみゆらん
大かたのさはりもしらす入(る)月よひくしめ縄をこゆな夢々
さくれとも手にもさはらぬ月影のさやけき夜半をかそへてそしる
命にも身にもかへんと思へともあふことをうる市のなきかな
一首目の職人は鍛冶で題は「恋」。二句「なまじ」は副詞で中途半端なさま、そのあとの「刀の金甘み」で鉄の鍛え方が不十分なことがわかる。下句の「きれ」「きら」は恋心と刀の双方に掛かる。二首目は番匠(大工)で題は「月」。初句の「墨金」は曲尺、二句は「直きを正す」、結句「かふばり(甲張)」は物が倒れないように支える木。但し文脈から云って二句は「歪みを正す」とあるべきだろう。三首目は刀磨、題は「月」。二句「砥水」は刃物を砥石で研ぐときに使う水を云う。結句「さびて」は「銹びて」、これに「寂びて」を掛けたか。四首目は巫女で題は「月」。歌意は「空を自由に渡る月よ、しかし注連縄を越えて聖域に入ってはいけません。断じて」。これに注連縄の中で仕事をしている間は訪れないで、月の障りよ、か。五首目は盲目、題は「月」。「盲目」というのは楽器を弾くのだろう。それに対して光は手に取ることができない。指で数えて十三夜、後の月と知るのだ。六首目は商人、題は「恋」。四句から結句に生業を出すが意想外しかも「逢ふことを売る市」の句またがりが効果的である。
なお承久の変(一二二一年)で破れた後鳥羽院は延応元年(一二三九)に隠岐で崩御、人は怨霊の災いを恐れることになる。また百年後の花園天皇は『東北院職人歌合』を書写し、「このほかにも『職人歌合』の主要な遺品の殆どが、天皇・親王などが親しく書写したり、他に模写させて襲蔵したものである」と云う。以下、岩崎説の壮大なロマンを追ってみたい。
|
| 第2回 鶴岡放生会職人歌合 |
まきれにし袖の白玉いかにそとおしへかほにもみゆる月哉 持経者
『鶴岡放生会職人歌合』の序文に「いつれの年にか鶴岡の放生会ことに事ととのほり菟園の御行粧いととめつらかにて一日の見物なれは万人きをひこそる」また「むかし宮こにて東北院の念仏九月十三夜にあたりて諸道の歌合ありけり」云々と続き職人歌合の経緯が述べられる。岩崎は、これを弘長元年(一二六一)とする。そして「弘長元年は辛酉(しんゆう)の年であった。辛酉の年は中国古代から『革命』があるとされ、わが国においても必ず元号が改められている。この年も二月二十日には改元され、文応から弘長になっている。とくに鎌倉幕府では、承久の変後隠岐へ配流され同島で没した後鳥羽上皇の怨霊を怖れ、宝治元年(一二四七)には鎌倉鶴岡西北方に新宮を奉祀している」とし、この歌合成立の背景として「後鳥羽院を偲び、その怨霊を鎮めるための営みであったとは考えられないであろうか」と推測する。
さて掲出歌の題は「月」。もう一つの題が「恋」であるのも『東北院職人歌合』と同じである。持経者は常に法華経を受持読誦している者を云う。判者は八幡宮神主、判に「五百弟子品をささけ」とある。すなわち巻第四の「五百弟子受記品第八」(岩波文庫『法華経』)に「君がどんな欲望でも満足させるのに十分なほど、非常に高価な宝玉を君の衣服の端に縫いこんでおいてあげたのだが、あれはどうしたのかね」があり、これを受けてのものである。判が解説の部分を受け持っているのであるが、それなしではなかなか理解が及ばない。
河瀬より影さす月のみなれさほ船もなかれの波のよるよる
夕まくれこすの間とほる月影はくまなきよりもあはれなるかな
水くきの岡へにわれは家ゐせん月に兎の毛のすゑをそろへて
人してそおもふ心をいはすへきふてには跡のみえもこそすれ
とる棹の歌のこゑまて浦さひて月のしほせにいつる舟人
一首目の作者は遊女、これも職人の範疇である。判に「紅衣青衫万人の往来をたのみ船中浪上一生の浮沈を思へはよその心もしぬるはかりにて」とある。三句は「水馴れ棹」、結句は「寄る寄る」に「夜夜」を掛けた。二首目の作者は御簾編、御簾を編んでつくる人である。二句「こす」は「小簾」、「すだれ」「みす」の意である。理屈抜きに情景が見えるというのはありがたい。三首目の作者は筆生、筆写を職業とする人である。初句「水茎」で筆、筆跡、手紙の意であるが「の」が付いて「岡」に係る枕詞となる。三句は「家ゐ(居)」、家を造って住もう。四句「兎(う)の毛」は筆、それと月に兎である。結句「すゑ」に穂先と部屋に射し入る月光が響く。四首目も筆生、題は「恋」である。判に「つねきく心地してめさむる所も侍らす」とある。しかし恋文を書く主導権が人ではなく、道具としての筆が握っている、しかも筆跡に掛けて結末が見えているというのだから凄い。五首目の作者は漁父、題は「月」。三句は名詞「浦」に接尾語「さびる」、四句の「しほせ(塩瀬)」は潮流を云う。判の「棹歌一曲釣漁翁と申(す)詩の心はへなるへし」は『和漢朗詠集』の「月」に 出典が見える。
|
| 第3回 金言和歌集 |
くけたちのゆみやもとらぬこくつふしなとゆきしもときえもうせぬそ よみ人しらず
『金言和歌集』には広本と略本がある。明応二(一四九三)年、将軍足利義材(あしかがよしき)を擁する畠山政長が正覚寺(大阪市平野区)に陣を張り、同族の畠山基家の追討を企てるが、細川政元のクーデターも手伝って形勢逆転、敗退し、自刃する。また義材は将軍職を廃された。この政変と正覚寺合戦が舞台である。掲出歌は略本のみに見える冬の歌。初句「公家たちの」、三句は「穀潰し」、四句「なと」は副詞「など」で「どうして」「なぜ」、消え失せないのか。
ぬるかうちもこころやすめぬかのこゑをてきのよせくるときかとそおもふ
わひつつもする夜まわりのなくさみにひとこゑききつ山時鳥
よせかぬるこむたのほりにかささきのはしをかりてもわたしてし哉
ねりぬきのはねこはたしててき御方野へのを花にましるころかな
らうとうのかふとに霜のおきなさひ人なとかめそ夜まわりの声
のふししててきにむかへるひさかしらふるふを冬におほせてし哉
一首目は夏の歌、広本の詞書に「かちようをつらさるちん屋の夜もすからいふせく侍るまま詠める」。蚊帳も吊らない陣屋、初句は「寝るがうちも」、結句「とき」は「鬨」、ナーバスなのだ。二首目も夏の歌。初句は「侘びつつ」で「心細がる」の意。しかしまだホトトギスの声に慰められている、余裕のある頃だ。なお作者名は略本に従って全作品「よみ人しらず」とした。三首目は秋の歌。二句は「誉田の濠」。基家が拠るのは高屋城(羽曳野市)。本丸は安閑天皇陵、二の丸は安閑皇后陵と下克上を象徴するような城である。しかし三句以下のイメージではない。「かささぎの橋」は七夕の夜に鵲が翼を並べて渡すという想像上の橋。結句の「てしがな」は終助詞で「~たいものだなあ」。現地を歩いた感じでは誉田山古墳(応神天皇陵)のそれである。四首目も秋の歌。広本の詞書「かふとのかさしるし袖しるし秋風になひきぬるをなかめてよめる」。初句「ねりぬき(練貫)」は笠標、袖標の素材をいう。二句「こはた」は「小旗」と思われるが「はね」は何だろう。兜を数える助数詞「刎ね」か、それとも「羽根のような」小旗の意か。三句は「敵味方」、四句「を花」は「尾花」。綺麗、そして怖い風景である。五首目は冬の歌。初句は「郎党の」。三句は「翁さび」、四句の「な~そ」は禁止の意。役目だから咎めないでくれよ、というのである。六首目も冬の歌。初句は「野武士して」、結句「おほせ」は「負ほせ」、膝が震えるのも寒さのせいにしたのである。
夢の世は六十よ六の道しはの露と我が身のけふそきえぬる
広本のみに見える。詞書に「ゆさの加賀の守しかゐいたす時もととりにたんしやくをむすひつけけるしせいの歌」云々とある。「たんしやく」は「短尺」、辞世の短冊を髻に結んで自害したのである。三句の「道芝」は雑草の意。大阪羽曳野両市史に遊佐長直の名がある。
|
| 第四回 三十二番職人歌合 |
たはふれて春の木かけにまふ師子のたたくつつみに花もさきそへ 師子舞(『三十二番職人歌合』)
岩崎佳枝によると『三十二番職人歌合』の成立は明応三(一四九四)年、製作の動機は「伏見宮家縁りの仏事結縁」と推測し、判詞の作者として聖護院道興(一四二九~一五〇一)の可能性を指摘する。「職人歌合」の流れで云えば、この年は後鳥羽院に「水無瀬神」の神号が奉られている。宗祇らの「水無瀬三吟百韻」(一四八八)は院の二百五十回忌に因んだものだった。かくて「戦国擾乱を恐れた人々は、後鳥羽上皇霊鎮めのため、さまざまな営みをしていたのである。『水無瀬三吟百韻』の五年後、後鳥羽院に神号が奉られたその年になされた後鳥羽院縁りの『職人歌合』製作を、その一つとして数え上げてよいのではなかろうか」と云う。掲出歌の題は「花」。下句「敲く鼓に花も咲き添へ」の「添へ」は四段活用である。
花のさくかけにはよせしひくさるの枝をゆふらはちりもこそすれ
春風にわかゆの桶をいたたきてたもともつしか花ををるかな
花さかりふくともたれかいとふへきかせにはあらぬこもか尺八
一首目の作者は「猿牽」。二句は「陰には寄せじ」。下句は「枝を揺ぶらば散りもこそすれ」。左の師子舞に対して右である。木登りは得意な猿であった。二首目の作者は「桂の女」。「わかゆ(若鮎)」の入った桶を頭に戴く桂女である。下句「袂も」以下は句またがりで「辻が花」は模様染め、これに正味「辻が花を折る」と掛けた。三首目の作者は「こも(薦)僧」。満開の桜、さて吹いても嫌われないものナーンダ。最後の最後に尺八を出す謎仕立てである。
たちまへるせんすまん歳いつくにもけしきはかりの禄そかひなき
杣板は世にいてなからあはれ身のをかひきこもる山すみそうき
あなたうとつくるつくるもいしの火のひかりをやかてはなつ御仏
いかにせん馬ならぬ絵のへうほうゑまきたしわろくのりのこはきを
一首目の作者は「千秋万歳法師」。題は「述懐」。「せんずまん歳」は初春の祝福芸、結句「禄」は祝儀で、どこで舞っても四句「気色許り」(ほんの形だけ)とその少額を嘆くのである。二首目の作者は「大鋸引(おがひき)」。初句「杣板」は杣木から作り出す板。杣木は杣山に生えている木。杣山は木材を切り出す山。下句、大鋸を挽いて隠る姿は世に出た杣板と対極にある。三首目の作者は「石切」。判に光は「仏の通力にてはなくて石にあたるたかねのちからよりみゆる光明なれは火打の石仏と申さむ」とある。また「当時のはやり仏谷の観音も石仏とこそ申(す)なれ」の記事が歌合成立年次の解明に繋がっている。四首目の作者は「表補絵師」(表具師)。四句「まきたし(牧出)」は少し前に捕ってきた野生の馬、これに同音異義語(「巻き出し」か)を掛ける。結句は「糊の強きを」で作業に難渋している様子がわかる。この歌の作者は三条西実隆(一四五五~一五三三)であることが家集で確認されている。
|
| 第5回 調度歌合 |
うくひすもかはつもうたをよむなれはこゑなきものの声もありけり 家の主(『調度歌合』)
『狂歌大観』の「解題」に「作者は三条西実隆か」、「成立は大永四年か」とある。三条西実隆は一四五五年に生まれて一五三三年に亡くなっている。大永四年は一五二四年だから六十九歳である。話は高野山(和歌山県)に御幸のあったところから始まる。主人公が住みついた家の主は郎党を引き連れて住吉(大阪府)まで出かけた。一行の見送りである。その留守に男は不思議な歌合を垣間見ることになる。たしか眠ったのは夕暮れであった。
わづかに隙見ゆる心地するを明けにけるやと思ひて、遣り戸を引き開けたれば、山の端 遠く、有明の霞もはてぬ。光ほのかにて、夜ふかき鳥の声もかすかに聞こゆ。昔より云 ひしめし春の夜なれば、そぞろに袖のみ濡れて思ひつづくる事多かり。さてのみ立ち明 かすべきならねば短夜も残り多かる心地して、まどろむともなきに、覚えなくもの怖ろ しきことぞある。異様なる御物の具どもの、ひしひしと取り置かれたる声々にものをぞ 云ふなる。いと珍かにて耳を立てて聞けば、このうちにとりては重き人といふべきにや、 炭櫃の云ふやう、留守のいとど徒然なり、さすが我等は只人の御調度に似るべきやうな し。春の夜の閑なる寝覚めに歌の会始め侍らばやと云ひいだしたれば、此は井の上なる 水瓶やさしく侍りなん、おのおの聞かせ給へやと云ふ、面々に応へして然るべしと定め けり、炭櫃の声にて題は何とか侍るべきぞと、その中にも水瓶、口ききたるものにて、 ただ思ひ思ひに恋の心にてこそをかしく侍るべけれと云へば、皆いと良からんとて呻き あひたる声々いと不思議におどろおどろしうぞ有ける。みな読みいだして人数を数ふれ ば、さまざまのもの多く並み居たれど、歌詠みはただ二十人ぞありける。同じくはこれ を歌合にせんと水瓶云ひ出したれば、いと良かりなんとて読師誰ぞ判者は誰ぞなど論ず るほどに、此事議判にてあるべしとて、おのおの良し悪しを定むるにとりて歌は詠まね ど只今のときにあたりたればとて御硯の兎の毛の筆ぞ書きつけける。
歌は省略するが、左右は燈台と炭櫃、台の棹と屏風、高坏と茶臼、机と脇息、銚子と水瓶、碁盤と長持、伏せ籠と塵取り、杉櫃と葛籠、下沓と裏無し、大壺と笈の台であった。
かくて夢うつつとも思ひわかざりしほどに夜も明けにしかば、この物どもの声もせずな りぬ。人に語ればまこととも云はず、さては夢なりけるにやあらん、いといと云ふかし、 まことや大壺と笈の台とは壁のあなたに真中なる落窪の所にてありしか、この定めを聞 きて我もまじり侍らんと望みて物ごしに申上侍りし、いと不思議にてこそ覚えしか、
右に続いて家の主が詠んだ一首が掲出歌である。上句は『古今和歌集』の「花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」(「仮名序」)を受けているだろう。鶯や蛙が歌を詠むのならば調度だって、というわけである。
|
| 第6回 玉吟抄 |
蓮葉(はちすは)の上に乗(り)たるあま蛙たた一飛(ひ)にまいる極楽 三条西公条(『玉吟抄』)
歌合であるが『狂歌大観』の解題に成立年の記載はない。左は三条西公条(一四八七~一五六三)。右は若狭の禅僧、潤甫周玉(一五〇三~一五四九)。判者は公条の父、三条西実隆(一四五五~一五三三)。生没年を見ると三人が揃う最後の年は一五三三年になる。この年で周玉が三〇歳、公条が三十六歳、実隆は七十八歳になる。それほど遡ることはないだろう。
夕霧の立ゐに物や思ふらん光源氏の秋のゆふぐれ
茶つほをもをかすといふは霧なれやしめりはいたく物をとをせば
さきも根も心地よけなる竹の子の六寸はかりおひそ出(て)たる
男をはせぬせぬといふ御比丘尼のはらむに似たる竹のしねんに
先の二首は四十七番の番いで題は「霧」。判は「右の歌たくみに勝(ち)侍(る)へし」だが左の人名に注目した。たとえば『古今和歌集』には登場しない。『新古今和歌集』では一例のみ、しかし『万葉集』に至っては珍しくない。狂歌また然り、なのだ。後の二首は八十三番の番いで題は「竹」。右、結句「竹」までで筍を妊婦に見立てているが「自然に」では云い止し、自然法爾の音を借りながら「自然(の)爾(汝)」とした。判は「左尾籠右過言」。息子と息子よりも若い栖雲寺和尚、左右の下ネタを前にした実隆を想像してしまうのだ。
世(の)中はなにやらかやらいとまなみせりせり川に行く月日かな
なに事もむかしにはあらぬ今出川内裏のあたりむさと流(れ)て
料紙にも書(き)とめはやと思ふかな年寄(り)たちの古物かたり
甲斐なきは年のよりたる尼が髪たけなといふも見た人もなし
先の二首は八十七番の番いで題は「川」。判は「左は世間の観念右は朝廷之零落をなけくにや左まけに侍れ右勝」。左の四句「せりせり」は気ぜわしいさま、川で洗濯か。右の歌、後奈良天皇の時代であろう。多賀博著『短冊覚え書』(朝日新聞社)に「帝はお手許が苦しいままに御製の宸筆短冊をひそかに市中でお売りになったと伝えられる」とある。結句「むさと」はうっかり、歌を解釈する限り、今出川に面している内裏の築地も流れてしまった、の意となる。後の二首は九十六番の番いで題は「懐旧」。判は「右題の心もよく叶へり可為勝にや」とする。右の四句は「丈などいふも」、結句「見た」は文語に口語の混じる早い例である。
通算成績は左勝四十一、右勝三十一、持二十八である。掲出歌は三十二番「蓮」、右は〈をしなへてわふるあつさを荷(はす)の実のくつとぬけたる池の涼しさ〉で持、二句「わふる(侘ぶる)」は迷惑する意だろう。左の判に「彼如一念頃即得往生極楽世界の文もまのあたりなるさま」とある。「観無量寿経」の一節で「一念の頃(あいだ)ほどに、すなわち極楽世界に往生することをえ」(岩波文庫)と読む。池という極楽世界に蛙は飛び込むのである。
|
| 第7回 七十一番職人歌合 |
ふるさとのかへのくつれの月影はぬる夜なくてそみるへかりける かへぬり(『七十一番職人歌合』)
岩崎佳枝によれば『七十一番職人歌合』の成立は明応九(一五〇〇)年である。曰く「この年後土御門天皇が崩御、代替りの時でもある。しかも翌年は、辛酉の年に当る。戦国の様相も一段と深まり、後鳥羽院の怨みの影がますます色濃く漂っていた頃といえる」。また総括して「『東北院』を嚆矢とするこのジャンルの作品の底には、つねに、『職人歌合』の最初の歌人であった後鳥羽院への鎮魂の思いがこめられていた」。結縁と鎮魂の二重の意味で「職人歌合」は「法楽」の歌合だというのだ。ちなみに二八四首中二十四首が飛鳥井雅康(一四三五~一五〇九)の詠歌であることが判明している。掲出歌の題は「月」。作者は「壁塗り」(左官)である。四句「ぬる」は「塗る」に「寝る」を掛ける。寝ないで見ているのである。
秋の夜もかきりありけり馬かはうこゑすむほとのあけかたの月
いけはきのかはかはうときなかむれはあかはたかにもすめる月かな
わかこひとゆわうははきのいつとなくはなれぬ中とおもはましかは
一首目の作者は「むまかはう(馬買)」、題は「月」。馬買は牛馬を売買する商人、秋の夜長も「限りありけり」なのだ。三句は職種名ではなく仕事中に発した会話文である。二首目の作者は「かはかはう(皮買)」、馬買と番いの右の歌である。皮買は獣の皮を売買する人、初句「いけはき(生剥)」は生きている獣の皮を剥ぎ取ること、四句「あかはたか(赤裸)」は血を連想させるが、ここは丸裸の意で、雲のかかっていない月を云う。二句も職種名ではない(口語体)。三首目の作者は「ゆわうははきうり(硫黄箒売)」、題は「恋」。硫黄箒売は硫黄木(付け木)と荒神箒を売る(硫黄木を束ねた形が箒に似るとは『日本国語大辞典』だが岩崎説に拠った)。二句「ゆわう」は「硫黄」に「云はう」を掛けて初句からだと「わが恋と云はう」(口語体)、順序としては「硫黄箒」のような二人の中と思えるならば、となる。
よひのまはえりあまさるるたち君の五條わたりの月ひとりみる
ねやのうちにまくらかたふけなかむれはさかつらにこそ月もみえけれ
初夜中や後やのつとめのひまなさにみるとしもなき法花寺の月
一首目の作者は「たち君(立ち君)」(街娼)。以下、題は「月」である。二句「選り余さるる」だから容姿は十人並みといったところ、仕事にならないで見る月に情趣がある。二首目の作者は「ゑひらさいく(箙細工)」。箙は矢を入れる武具。二句「枕を傾け」は寝ることを云う。「さかつら(逆頬)」は「逆頬箙」の略で矢尻をさす箱を一枚の毛皮で包んだもの、場所によって毛並みが上を向くことからの命名らしい。逆さに月を見ても同じだが、行儀の悪さが取り柄であろう。三首目の作者は「にしう(尼衆)」。「初夜中夜後夜」は夜を三分したもの、午後六時から午前六時までの勤行で忙しく、ゆっくりと見ることもない月なのだ。
|
| 第8回 雄長老狂歌百首 |
まねきよせてはかさんとてや秋ののにふれる狐の尾花なるらん 雄長老(『雄長老狂歌百首』)
雄長老(一五四七~一六〇二)の狂歌を中院通勝(一五五六~一六一〇)が批評した本書の成立は「解題」によると天正十七(一五八九)年夏、雄長老は建仁寺の長老英雄長老の略称、中院通勝は号を也足軒。年齢は雄長老四十二歳、通勝三十三歳だった。掲出歌の題は「薄」。評詞「秋の野のさま蘭菊の叢さも有(り)ぬへし」。二句は「化かさんとてや」、薄の花穂を狐の尾としたところから歌は展開する。そして狐が隠れるのは古来「蘭菊の叢」だった。
春毎に去年より物の見えぬ目は空にしられぬ霞なりけり
よることに式部がそそや洗(ふ)らしむすふいつみの水のくささは
一首目の題は「霞」。評詞「空にしられぬ霞老眼の趣尤有感」。通勝は二十四歳で正親町天皇の勅勘を蒙って出奔、丹後で細川幽斎の庇護下にあった。また雄長老は幽斎の甥である。二首目の題は「泉」。「そそ」は女性の陰部。評詞「和泉式部か臭気古来其沙汰を伝承らす。其奥説なからむ程は批判を加(へ)かたし。誓願寺の本尊は能存知歟。一笑一笑」。「伝承らず」は「うけたまわらず」と読んだ。「奥説」は深遠な説。誓願寺には式部の出家伝説がある。
田のはたに家は作らし度々の検地の衆の宿にからるる
君がかほ千世に一たひあらふらしよこれよこれて苔のむすまで
やふれしな理にくらからぬ君が代は天下太平国土あんとむ
一首目の題は「田家」。評詞は「この歌当時有憚」。太閤検地の開始は天正十(一五八二)年。役人を野宿させるわけにはいかない。しかし迷惑な話であったろう。二首目の題は「苔」、評詞「此君はいつれをさされたるにか尤も憚(り)あり」。天皇ではない。関白秀吉であろう。三首目の題は「祝」。評詞「此歌又批判ははかりあり」。初句は「破れじな」。こちらは後陽成天皇か。通勝が勅免を受けるのは四十三歳の慶長十四(一五九九)年、その間に『源氏物語』の注釈書『岷江入楚』を完成させている。「あんとむ」は安頓、暗鈍の両義に読める。
おうちうはひうはひおうちことことく死なすに居ては何を食はせん
金ひろふ夢はゆめにて夢のうちにはこするとみし夢はまさ夢
一首目の題は「懐旧」。初句の「おうち(おほじ)」は「祖父」、「うば」は「祖母」。二句の「ひうば」は「曾祖母」、「ひおうち(ひおほじ)」は「曾祖父」。評に「御母儀さまをいれられさる所尤も作者の粉骨也。殊勝珍重珍重」とある。二首目の題は「夢」。評詞「化蝶翁の夢未夢を弁す。此趣向まさ夢を弁せられたる尤も殊勝殊勝」。「はこ」は大便の意。「化蝶」は銭の異称、「化蝶翁の夢」という話があるのだろう。夢の話を正夢に転じたところが恐い。
|
| 第9回 三斎様御筆狂歌 |
穴きたな江しりを出(て)てゆく人のあしからくたりかかるはこね路 細川忠興(『三斎様御筆狂歌』)
「解題」によると「成立は天正十八年、小田原陣及び奥羽征討に従軍していた作者が、丹後田辺の一如院に住していた英甫永雄(雄長老)に宛てて書き送ったものである」と詳しい。細川忠興(一五六三~一六四六)は細川幽斎の長男、三斎は号。英甫永雄の母は幽斎の妹。天正十八(一五九〇)年は忠興二十七歳、雄長老四十三歳である。また丹後は細川家の所領だった。掲出歌は詞書に「駿河の江尻といふ所より足からはこねをさして人数の行(く)を見侍りて」とある。「人数」は大勢の意。初句の「穴」は二句「江しり(尻)」に由来、また感動詞の「あな」でもある。四句「あしから」は「足柄」に「足から」を掛ける。「くたり」は坂の「下り」に下痢の意、結句は「はこね(箱根)」の「はこ」に大便の意を掛けた。
武蔵野でけふはやき米かみちらしつまへこほれりそれもくいけり
名にしおふ日光山をなかめてもものをはくはて行(く)そかなしき
兵粮もなすののはらのちんかへにおつる涙やしらかわの関
みちのくの浅かの沼の花かつをかつへし人のくいやわたらむ
浅か山かけさへ見ゆる山のいも朝くうは夜のじんいらぬかは
かつへつつここへきた田てしろしろとみれとくはれぬもち月の空
便所も大変だが食はもっと大変である。『三斎様御筆狂歌』は全十四首、そのうち半分が食べ物に苦労する歌である。一首目。これの前に〈米のねはふしより高く成(り)にけり陣の賄ひいかにするかの〉がある。「するかの」に「駿河野」を掛ける。誰が儲けていたのか。行く先々で飢えと戦っている。三句「やき米(焼米)」は籾のまま煎って搗き、殻を除いたもの。四句「つま」は「褄」もしくは「端」。二首目の詞書「腹のうちに人しれぬ事をおもひ侍りけるに日光山の見え侍るといふ山のかたをうちなかめて」の「人しれぬ事」とは食べ物以外にないだろう。三首目の詞書は「下野国なすのの原よりみちのくしら川の関まて陣かへの日みな人のあしもとよはよはしく見え侍りしほとに」とある。三句「ちんかへ(陣替)」は陣所を他に移すこと。四首目の詞書「浅かのぬまにてかれ飯くい侍りしにうるかといふ物のうへにかつうををけつりちらして出し侍りければ」とある。「かれ飯(乾飯)」は炊いた米を乾燥させたもの。「うるか」は鮎の内臓や子を塩漬けにした食品。「かつうを(鰹)」は鰹節であったろう。五首目の詞書は「あさか山にて采女のたはふれの折ふし大君の御薬くいのことを思ひやりて」、『万葉集』の〈浅積香山(あさかやま)影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに〉(三八〇七)に拠る。一日一食であったらしい。六首目。詞書は「兵らうのともしきころ北田のさとに八月十五夜にとまりて」。初句は「飢ゑつつ」、空腹の忠興だが決して敗軍の将ではない。食の次は衣である。「まし田の在所に各ちんとりて迎(へ)に出(て)侍るなかへ」の詞書を持つ一首〈夏ころもまた其のままに冬のきてさむさましたにやとるたひ人〉、地名の「まし田」に「さむさました」、駄洒落でも云ってないとやってられないのである。
|
| 第10回 入安狂歌百首 |
春くれはいろも花香も別義にてやとの大ふくたつかすみかな 入安(『入安狂歌百首』)
著者の入安は堺の町人。「解題」の「備考」欄に「中院通村の識語により、批点・評詞は也足軒中院通勝により付せられた」とある。整理すると通勝の外祖父が三条西公条、その子で通勝からすれば伯父の三条西実枝(一五一一~一五七九)、実枝から古今伝授を受けたのが細川幽斎(一五三四~一六一〇)、その幽斎から古今伝授を受けたのが中院通勝で通村はその子である。掲出歌の題は「立春霞」。評詞は「尤(も)おもしろく候。但(し)此(れ)立春元日ならては事たかひ候哉」。元日立春でないと駄目だ、と云う。参考に通勝生存中の元日立春は二度、その二度目は二十五歳のときだった。「大ふく(おほぶく)」は「大服茶」の意。
河内女か手つからとりていひもりの山のはかすみたなひきにけり
春の野にみなつくつくしかたやして日も暮(れ)すきなすまふとり草
ぬきて今日かへすかへすもはつかしや花みるほとのかりきぬのそて
さらさらにあられん物かあられふるささの一夜もささをのますは
一首目の題は「山霞」。評詞は「歯霞近代等類のやうに候へとも伊勢物語の面影河内女の手ましたて候よく候」とある。うち「歯霞近代等類」は不明。「手ましたて候」は「手間仕立て候」。『伊勢物語』第二十三段で女が飯を盛る場面である。二首目の題は「春草」。評詞「はかなけなるしたてにて候」。二句は「つくづくし(土筆)」、結句「相撲取草」は菫の別名である。小さな別世界は見ていて飽きない。三首目の題は「更衣」、評詞は「返す借の二字ほねをおられ候」。二句「返す返すも」の本義に「返却」を籠め、結句「かりきぬ(借り衣)」となる。四句は僅かな期間の意か。四首目の題は「夜霰」。評詞は「尤(も)候」のみ。初句は擬音と副詞で「今さら」、二句は「ある」の未然形に「る」の未然形、これに「む」の連体形で三句に呼応する。四句「ささ」は副詞で風が吹くさま、これに「篠」「些々」等を重ねた。結句「ささ」は酒。今さら無理なものらしい。霰ふる、こんな夜も酒を呑まねばおられないとは。
雨風にみのもさなへもさみたれてしのふももまで見ゆるさをとめ
水まさる沢辺に匂ふ藤はかますそをひたさはさこやたまらん
かきこしにししする音の聞(こゆ)るはかの十六になる人ならん
一首目の題は「早苗」。評詞は「さしたる事なし」。二句から三句「水面早苗もさ乱れて」、事情は早乙女も同様で「忍ぶ腿まで見ゆる早乙女」、エロチシズムはお嫌いであったか。二首目の題は「水辺蘭」。「蘭」は藤袴の別名、そこから袴の裾が出てくる。評詞に「さしてききわかす候」。そうか。私には「裾を浸さば雑魚や溜まらん」の連想が楽しい。三首目の題は「聞恋」。評詞なし。初句「垣越しに」、二句「しし(尿)」は九九なら「四四」で「十六」になる。『雄長老狂歌百首』では和泉式部の「そそ」の歌に「一笑」した通勝も別人のようだ。
|
| 第11回 四生の歌合 |
しのびぢのこゑたてねともゆふぐれはつれるかてふや夜半のせきもり 蚊(『四生の歌合』)
「解題」によると著者は「木下長嘯子か」とある。長嘯子(一五六九~一六四九)は豊臣秀吉の妻、北の政所の甥である。『四生の歌合』は「むしのうた合」「とりのうた合」「うをのうた合」「けだ物の歌合」からなる。まず導入部のさわりを漢字仮名混じりにすると「庭のかたはらなる萩の一叢、枯れ残りたる陰より蟋蟀といふ虫のかけいで数々の虫に語りけるは事珍しからねど、我等が身の上こそ殊更哀れに浅ましくなりはて侍れ、面々もさこそおぼすらめ、いでいで申し侍らん、春も過ぎ夏もたけ侍れば草も緑をまし五月六月の夕立すぐる頃ほひ野辺の千草に露玉をなせる夕べはそぞろに心も浮き立つ斗また文月のすゑ八月の中の五日は名にあふ月のさやかなれど早そろそろと風も身にしむ也、面々はなにとおもしろげもうすくなり侍らずや」と、なかなかの饒舌体である。虫のすだくがごとくということであろうか。舞台は神無月(十月)、「今夜の月に思ふどち、さしつどひたるこそ嬉しけれ、いざや面々、心の底を語り明かし、何事をもさんげしてまたは其いにしへたまむしの君に歌をおくり侍りしにつらかりし心のうらみを思ひ出して一首づつ歌詠み給へかし」に応じて、ようやく「散りかかる落ち葉が上に座を連ねて数々の虫ども案じゐたり」という場面になる。
こうして「十五番うた合」が始まるが判者は「やぶのもとのひきがいる」、左右は「こうろぎ」対「はち」、「げぢげぢ」対「あり」、「はたおり」対「みのむし」、「かまきり」対「あしまとひ」、「いもむし」対「てふ」、「けむし」対「くつわむし」、「きりぎりす」対「みみず」、「すずむし」対「まつむし」、「むかで」対「きこりむし」、「ひくらし」対「こがねむし」、「はい」対「か」、「のみ」対「しらみ」、「けら」対「ほたる」、「くも」対「せみ」、「くちなわ」対「ひきがいる」、そして最後の場面は「勝」を望んだ「ひきがいる」であったが「くちなわ」に恐れをなして「竹の林の落ち葉が下にはい入りぬ」、これを見た「世なる虫たちも良き思案にこそ侍れ、命がありてこそ水に住むかはづの歌も詠むべけれ」という落ちで片が付く。
うらめしな君もわれにやならひけんふりふりとしてつれなかりけり
わがこひはあふせの道やきりきりすかへにも君がおもかげをみず
此(の)ころはつちの中なるすまゐして君がすがたもみみずなくなる
なとてかくたへぬおもひをすずむしのふりすてかたきこひぢなるらん
おもひやれひとりぬるよはわれからのあしのかずかずきみぞこひしき
一首目の作者は「いもむし」、四句に面目躍如とした観がある。二首目は逢瀬の道も自ら「きりぎりす」の悲哀である。三首目は「みみず」に免じて結句には目を瞑ろう。四首目の「すずむし」の三句も同様である。五首目は「むかで」、四句の必死さが滑稽である。
掲出歌だが判詞の「蚊帳を夜半の関守といひなされたるは伊勢物語の歌によひよひごとにうちもねななんの心おもひ出されて哀れも深くこそ侍れ」は第五段の〈人しれぬわが通ひ路の関守はよひよひごとにうちも寝ななむ〉を云う。結句は「少しでも眠ってほしい」。
|
| 第12回 四生の歌合(2) |
あさゆふにちんちんからりからからとわらうやうにてなきかはすかな 四十からおひのすけ(『四生の歌合』)
「むしのうた合」が行われたという噂が伝わるのは早い。まず軒下のみそさざいは「いかなればとて虫の家に劣らんや、すでに是、源氏は鳥の家、平氏は虫の家、藤原氏は獣、たち花は魚の家なんどと聞き伝へたり、なまなまに四家の流れの中にても源なんどいはれつる鳥の家にて歌合のなからんは甲斐なく侍らんや」と鶯の竹林坊をそそのかす。竹林「かやうのわたくしならぬ御事を上見ぬ鷲殿をさしをかん事おもひもよらず」。今度は「梟の道才棒に案内せんとて震え声にて語りけり」。かくて「鷲この由をつやつや思ふに重代四家の流れのうちに虫の家ばかりにて懸想文合のあんめれば残りたるものどもよしあしひきのやまずしもくねくねしく口にかけ侍るまま獣と魚との家ととひ合みやけを催し良くても悪しくても族類なれば子細なし、さも侍らば鶯とみそさざい使ひに参れ」。この沙汰に二人は驚いて逃げ帰るが、獣も怖いが鷲も怖い。道才「ただ疾く疾くとあへなく早めければ竹林さざい泣く泣く旅の思ひ立ち涙ながらに女房子供寄せ集め形見贈りをつかまつり、さて二人の者は三千万里をしのぎつつ魚の舘へ参りて物申請うて一々子細申(す)めり」、魚の家の賛同を得たのちは獣の家である、猫股のこん平六の「申すやう鳥の御家より軒下のみそさざい鶯の竹林坊と申(す)は何方に侍いたまふぞと名告りもあへずま近くより二三寸有(る)つめうちたて二尺余りの尾をもつて二人の背中をなでて日月のまなこにすずをはりいがみ声して御返事申(す)なり、さざい竹林肝魂も抜け果てて怖ろしきとも中なかに申(す)も愚かなればなにのわけも聞きとめず天の命を拾ひつつ国元へ立ち帰り鷲殿に何れも然るべくこそおぼしめせ、われなればこそ斯様の御使ひをもし侍れなどいひていんげんたらたら申(す)めり」。ともあれ二人の活躍もあって「とりのうた合」「うをのうた合」「けだ物の歌合」が実現したのであった。
「とりのうた合」の対組は「とびのきんすけ」対「からす田のくろ助」、「山とりのかがみのかみ」対「ひろ野きじゑもん」、「やまがらの小六」対「四十からおひの助」、「すずめじまさねかた」対「しとどぬれゑもん」、「ほととぎすとりへもん」対「鶯のちくりんほう」、「つばめのせき助」対「こま鳥のもくへもん」、「ほうじろやぶへもん」対「ひがらにしの助」、「ましこのげん太ひやうへ」対「ひわくれへもん」、「にわ鳥の平内ざへもん」対「あひるのいざりの助」、「のき下のみそさざい」対「つかみつらのこうもり」、「ふくろうのどうさいほう」対「よく野くまたか」、「ふろやのひたき」対「うまい物くいなのすけ」、「なごりおしとり」対「いつかみやことり」、「はとのかいゑもん」対「いとをしぼうのむく鳥」、「ちとりの百のすけ」対「かしとりの七のすけ」、そして判者は「うへみぬわしのすけ」であった。
物おもふわが身にひたともち月のたちてもゐてもかげははなれず
右は十四番。題は「とりもちによする恋」、作者は「はとのかひへもん」。「とりもち」を「もち月」に替えて「身につきそひて」(判)となる。掲出歌は三番、題は「さゑつりかはすこひ」。結句「なき」は「鳴き」のはずだが四句を受けて「泣き」を加えた。同音反復が快い。
|
| 第13回 四生の歌合(3) |
さぎのゑに身はならはなれおもひかわひとたひあふてうかぶせもかな どちやうのぬらりの助(『四生の歌合』)
「うをのうた合」は虫、鳥と同じく十五番、整然と終始する。左右は「おめでたいゑもん」対「君を恋のすけ」、「ふきぬきさんあんごうぢ」対「ふぐつらさんふくとうぢ」、「あゆみはこびの助」対「からいとはへの助」、「なまうなぎかりのぼう」対「なまずのひよん太郎」、「あぢぐちのひるめぼう」対「ふなばしうきよ」、「はまぐりかいのすけ」対「たこの入道けんさい」、「すずきの六郎太」対「かつをのだしすけ」、「なに共いはし」対「一ふりたちのうを」、「あかひげのゑびゑもん」対「なにかにおもひのすけ」、「おもひますへもん」対「大ざけ九郎太」、「なまこのさゑもん」対「あはびさん大かいぢ」、「どぢやうのぬらりのすけ」対「かな物かぢか」、「四かいとびうを」対「わき道さよりのすけ」、「よろこびをしらす」対「ゑそはでなくなくひやうへ」、十五番は連歌、判者は「くぢらのだんざへもん」である。
きらはるる身を気の毒とおもふにもむねはらまてをふくれこそすれ
二番「はいかいうた」。作者は「ふぐづらさんふくとうぢ」、山号と寺号からなるが「ふぐづら」は「河豚面」「ふくと(ふくとう)」は「河豚魚」であるこというまでもない。したがって「河豚面山河豚魚寺」、ちなみに河豚の食用禁止令を出したのは豊臣秀吉であった。
ゑぢがたくひかりとも見よかく斗(ばかり)うき身にそへてたゑぬおもひを
からころもにしきのそてをかへしつつうたたねにたにたのむおもかけ
九番「おり句のうた」。作者は左「あかひげのゑびへもん」。右「なにかにおもひの助」。判に「ゑびの歌はゑひが歌といふ五もじを五句の上にをき右のかにの歌はかにが歌といふ五もしを是も五句のかみにすへて」とある。なお左は『詞花集』の〈みかきもり衛士のたく火の夜はもえ昼はきえつつ物をこそ思へ〉(二二五)、右は『万葉集』の〈白たへの袖折り返し恋ふればか妹が姿の夢にし見ゆる(二九三七)〉を本歌とする。「みかきもり」は「御垣守」。
なに事もまづはしのふのころもてをめなれなからもかたみにぞおもふ
しらるるはかなしきけなしとこやみやことしなけきし中はるるらし
一首目は十一番「上下のおり句の歌」、作者は「なまこのさへもん」。「なまこめがものおもふ」という十字を五句の上下に置く。四句「目馴れながらも」は「見慣れながらも」。二首目は十三番「くはいぶんのうた」(回文の歌)、作者は「わき道さよりの助」。ハードルは高い。
掲出歌は十二番「はいかいうた」、判に「おもひかわに身をしつめくるしみに心をくたさんより一たびあふて浮かぶせ侍らばたとへばさぎのゑに身はなるともくいかなしまじといへるにや」。三句「思ひ川」は思いの深くて絶えないことの比喩。結句「がな」は願望を表す。
|
| 第14回 四生の歌合(4) |
かねつけてえみをふくめるかほはせにこよひあふみのおちぐりの本 このみのほうしりす(『四生の歌合』)
「けだ物の歌合」は十番、対組は「かわうその水ゑもん」対「ぶたのほうしどろぼう」、「いぬ山の四郎太」対「さる丸のあかだゆふ」、「いのししゑもん」対「山のべのしかの助」、「もち月のこまの助」対「よだれづらあめうし」、「きつねづかのあなゑもん」対「たぬきしるこんにやくひやうへ」、「くまがいの四郎」対「かみすきのひつじの助」、「おうしうのしろうさぎ」対「いたちゐのこしぬけ」、「ぢごくさがしのむくろもち」対「このみのほうしりつす」、「こくうとらの助」対「野山大かめ」、「よもすがらねずみ」対「ねこまたのこん平六」、判者は「ししわう」。題は「水にたはぶるるこひ」から「あふこひ」まで全て恋である。
今回は趣向を変えて判詞に登場する歌に着目した(表記は『新編国歌大観』に拠った)。
ゆふやみは道も見えねど旧里は本こし駒にまかせてぞくる
ももくさにやそくさそへてたまひてしちぶさのむくひけふぞわがする
のちのよにみだのりさうをかぶらずはあなあさましのつきのねずみや
まくず原したはひありくのらねこのなつげがたきはいもがこころか
一首目の出典は『後撰和歌集』(九七八)、作者は読人不知。結句「まかせて」が主客逆転したところである。二首目は『拾遺和歌集』(一三四七)、大僧正行基が母の報恩会に詠んだ作である。生育に百八十石の母乳を飲むという仏説に拠ったものだ。三首目の出典は『秋篠月清集』(二七〇)、作者は藤原良経。「月のねずみ」は月日の早く過ぎていくことの譬喩である。四首目の出典は『夫木和歌抄』(一三〇四四)、作者は源仲正。野良猫の登場が面白い。国際日本文化研究センターの和歌データベースで検索すると「のらねこ」は一九〇四二三件中三件、うち二件が選外作品のアンソロジー『夫木和歌抄』、あとの一件は私家集である。ちなみに「駒」は取材において「乳房」や「鼠」は用語において狂歌との親和性を覚える。
しほのほるこしの水うみかせたちてはまくりも又ゆられきにけり
きのふたちけふきて見ればきぬかわのすそほころびてさけのぼる也
右も同じ。「うをのうた合」に「古歌」とあるが出典不明。一首目の「こしの水うみ」は越後国福島潟の古称らしい。二首目の「きぬかわ」は衣川か絹川、二つの意味が平行して進行するので結句の「さけ」は「裂け」となり「鮭」ともなる。ちなみに「はまくり」を先のデータベースで検索すると十三件がヒットする。しかし勅撰和歌集には全く登場しない。「鮭」は「酒」と同音のため分別不能であるが感触としては狂歌との磁場が思われるだろう。
掲出歌は八番「やがてあふこひ」。「かね」は「鉄漿」、お歯黒に用いる液である。「かほはせ」は音変化して「かんばせ」(顔)、「あふみ」は「逢ふ身」に場所の「近江(あふみ)」、結句は「落ち栗の本」だが判者によると「近江の栗本の郡」を効かせているらしい。
|
| 第15回 新撰狂歌集 |
霜月にしものふるこそたうりなれなと十月はじうはふらぬぞ 藤原定家(『新撰狂歌集』)
「解題」によれば編者不詳。掲出歌の詞書に「定家卿六歳の時うたよみて俊成へつかはし侍るとて」、三句「たうり」は「道理」、四句「なと」は「など」。歴史的仮名遣いなら「十」は「じふ」であるが気にしない。この歌には続きがある。父、俊成の「返し」である。
十月に十のふらぬとたれかいふ時雨はしうとよまぬものかは
晩秋から初冬にかけて通り雨のように降る時雨、この「しぐれ」を音読すれば「じう」となる。但し「じう(時雨)」で調べると「ちょうどよい時に降る雨」とあったりして深追いの愚を知らされるのである。また掲出歌の出典を尋ねると正徹の『清巌茶話』(風間書房『日本歌学大系』第五巻)に「家隆卿稚き時、霜月に霜の降るこそ道理なれなど十月に十はふらぬぞ とよみ給ひしを」云々とあることだ。これでは面白くないと思う人がいたのだろう。
此(の)川は七瀬の川とききつるにここなる僧はむせわたりけり
此(の)河を七瀬の河と聞(き)きつるにここなる馬はやせわたりけり
むまひつしさるとりいぬはそちへいねうしとらぬさへうきなたつみに
けふよりはきのつらゆきとめさるへしきのさねさたかかふりおとせは
俊成、定家とくれば西行である。一首目は詞書「むかし西行法師修業の時ふしみの七瀬川の辺にて麦粉をくふとてむせけれは馬に乗りて行(き)ける人のよめる」、二首目は「返し」で、こちらが西行になる。「七瀬」に対して「むせわたりけり」(六瀬)と「やせわたりけり」(八瀬)の応酬となった。三首目も西行、詞書は「修行者一夜の宿をかりけるに其(の)夜彼(の)やとへぬす人来(た)りて牛を引(き)けれはあるし此(の)そうをうたかひすてにいましめんとしたりける時我は西行法師と申(す)修行者なりと名のりけれはよも西きやうにはあらし西行とやらむはきこふる歌人なりさらは歌よめとせめけれは」。漢字で表記するとよく分かるが「馬羊猿鶏犬はそちに猪鼠牛虎ぬさへ兎きな竜蛇に」で十二支全部が揃っている。もう一人、四首目であるが詞書に「紀の貫之はしめはきの實定と申せしか有(る)時御門の御まへにてかふりをおとしてよめる」とある。「かぶり」は「冠」そして「實」のウ冠である。改名説があったのか、なかったのか。いずれにしても著名人の名を借りた後世の作という印象は拭えない。しかし逆のケースもある。家隆の例である。たとえば細川忠興の〈穴きたな江しりを出ててゆく人のあしからくたりかかるはこね路〉(『三斎様御筆狂歌』)が「有る人」、入安の〈今はただ腿もこぶらも播磨潟飾磨の徒(褐)の旅は苦しも〉(『入安狂歌百首』)も「ある人」で登場する。しかし同じく入安の〈春くればいろも花香も別義にてやどの大ふくたつかすみかな〉(同)は「宇治の茶大臣母」、〈だれもみな諸行無常や極上をむくる茶の湯のあはれ世の中〉(同)は「いつけう和尚」の作となっている。著作権や何処、なのだ。
|
| 第16回 新撰狂歌集(2) |
女院の御まへのひろくなる事はきやう月はうかし地の入(る)ゆへ 暁月坊(『新撰狂歌集』)
『新撰狂歌集』に暁月坊の名前を冠した作品が五首見える。暁月坊は冷泉為守(一二六五~一三二八)、狂歌の元祖とされている人物である。『狂歌大観』(本篇)にも『狂歌酒百首』が収録されている。「解題」によれば官許は宝暦八(一七五八)年、発行は明和八(一七七一)年、元和(一六一五~一六一九)頃の成立とされる『新撰狂歌集』より新しい。備考欄に成立は明応六(一四九七)年以前か、としているが「刊本以前の姿を示す写本は見出し得ない」とあって、素直に「暁月坊」即「冷泉為守」とはいかないようなのだ。作品はどうか。
ゑひてのち物もいはぬはくちなしのやまふき色のさけやのむらむ
さりとてはけふまたしちにやれ蚊帳酒にそ我はくらはれにける
盃もかたふきながら秋の夜のなかなかしくものむ上戸かな
浦なみのよるになるまてのむ酒にゑひてたたよふちとりあしかな
数ならぬ身にさへいかてゑひぬらんさけは人をもきらはざりけり
下戸はなと鬼のことくに酔(ひ)ぬらんたた一口にさけはのみけり
わか身をもうしなふほとに酔(ひ)ぬれはさけにのまるる人とこそみれ
『狂歌酒百首』より抄出した。一首目は「春十五首」の一首。三句は「口無し」に「梔子」を掛ける。二首目は「夏十首」の一首、二句「しち」は「質」、三句「蚊帳」は「かちょう」と音読だろう。結句は「食らはれにける」。「食ら」に質屋の「蔵」が思われる。三首目は「秋十五首」の一首。四句は夜の長さに酒の座の長さを掛ける。四首目は「冬十首」の一首、「よる」は「寄る」と「夜」の両意が掛かる。また初句と結句が呼応する。五首目以降は「雑五十首」の歌。その五首目、初句「数ならぬ身」とは卑下したものだ。下句と併せて読むと屈折のほどが知られる。六首目の初句「など」は「どうして」、下戸の下戸たるパターンである。七首目は上戸の上戸たるパターンである。かくて勇ましくもない酒百態の暁月坊がいる。
さて掲出歌は詞書に「ある時女院の御所御庭せはきとて此(の)人の地をとりて御庭のまへをひろけ給へは」とある。設定はともあれ歌意は容易である。そして裏の意味を探れば「前」が女性器、「私地」が「似指」で男性器となり、土地を取られたという内容が女院を犯す行為に変化する。但し歴史的仮名遣いでは「私地(しぢ)」と「似指(しじ)」は別物である。
きやうくはつにけのむくむくとはへよかしさるものの子と人にいはれん
もう一首、詞書は「おなじ人のよめる」とあるのみ、「さる」は「然るべき」「立派な」の意味の連体詞に「猿」を効かす。暁月坊が冷泉為守であることを前提としているだろう。突出した自己顕示は『狂歌酒百首』の印象からは遠い。ひとまず暁月坊を名乗る人物は『新撰狂歌集』と『狂歌酒百首』に二人存在する。このように理解した方がよさそうである。
|
| 第17回 新撰狂歌集(3) |
つついつついつつにわれしいと茶碗とかをはをれかをひにけらしな 細川幽斎(『新撰狂歌集』)
作者名への関心を続ける。『狂歌大観』(本篇)の『古今若衆序』は男色を扱った作品集であるが作者名は不詳、古くから細川幽斎とされるが、一方で雄長老説もある(「解題」)。
難波つにあくや此(の)あな冬こもり今は春へとあくやこのあな
『古今和歌集』の仮名序のパロディである。本歌は〈難波津に咲くや木の花冬こもり今は春べと咲くや木の花〉で「そへ歌」が「そへ尻」、以下「かぞへ歌」が「かぞへ尻」、「なずらへ歌」が「なずらへ尻」、「たとへ歌」が「たとへ尻」と悉く変換されていくから凄い。
はなかある人をはおちやによはるれとこちや又もとにのこるつほそこ
『新撰狂歌集』にもどるが作者名は幽斎、詞書に「有(る)時紹巴すきに行(き)けるを」とある。「すき(数寄)」は茶会、初句の「はなか(花香)」は茶の香気そしてそのような風格をいうのだろう。二句「おちや」は「御茶」、四句の「こちゃ」は「こちらは」の意に古茶を掛ける。結句の「つほそこ」は「壺底」と読む。これに対する「返し」は〈残るこそ猶もへちきにはなかあれうちある人はちやちやとよはれす〉である。二句「へちき」は「別儀」、四句「うち」は「氏」に「宇治」、結句「ちやちやと」は「さっさと」の意に「茶茶」を掛ける。但し『幽斎君抜抄』(もしくは『細川家記』)では両者が入れ替わっているらしい。
掲出歌は詞書に「太閤秀吉公の御前にて御ひさうのいど茶わんうちわりける時」とある。物の本によると下句は科負い比丘尼の口吻だとある。誰かを庇ったことになるが歌の解釈としては筋が通る。本歌は『伊勢物語』二十三段の〈筒井つの井筒にかけしまろがたけ過ぎにけらしな妹見ざるまに〉。しかし『狂歌大観』の「人名索引」(第三巻『参考篇』)では両首とも幽斎の作品として拾っていない。石橋を叩いて渡るのは当然だが物足りなさも残る。
塩は唯よき程なれや鍋のしましやくしを中へ入れてみつれば
ひかせえずもみ落とすべき韮山は手をすりこぎの音のみぞする
間違いのない幽斎の作品を見たいと思って紀行文を開いた。一首目は『九州道の記』(『群書類従』第十八輯)所収、「鍋のしま」「しやくし」は地名、船旅である。下句が狂歌っぽいと思っていたら『新撰狂歌集』に「有(る)人」で採録されていた。二首目は『東国陣道記』(『群書類従』第十八輯)、やはり狂歌っぽいと思ったら『参考篇』(第二巻)の『幽斎道の記』にあった(『九州道の記』と『東国陣道記』を併せたものが一巻になっていたのである)。
幽斎は関ヶ原の戦いのときには田辺で籠城、古今伝授の秘儀の絶えることを惜しんだ後陽成天皇の勅命によって開城した。最も守旧的なところに狂歌の胎動があったのは面白い。
|
| 第18回 新撰狂歌集(4) |
もろこしのむさむさ坊主ひけ入道さしたる事はいはしとそ思ふ 一休(『新撰狂歌集』)
『新撰狂歌集』の編者は不詳であるが「解題」に「ただし、同時に刊行されたとみられる『詠百首狂歌』が合綴せられていることから、古くは雄長老編と考えられていたが小高敏郎氏は疑問を呈し、編者不明とされる」とある。ここにもまた雄長老の影が差している。
鹿の毛は筆になりても苦はやますつゐにれうしのうへてはてけり
作者は雄長老。四句の「れうし」は「料紙」、これに「猟師」を掛ける。歴史的仮名遣いからすると「料紙」は「れうし」、「猟師」は「れふし」だから無理がある。しかし契沖の『和字正濫鈔』が出版されるのは一六九五年、雄長老らはそれを知る術もなかった。発音と書写が対応していた平安時代つまり平仮名が生まれた時代と違って音韻の変化は仮名遣いの乱れとなって顕れるが、それをまた現代の物差しで測ることができないのも当然である。
をとりはね申(す)にたにもかなはぬにいねふりしてはいかてなるべき
をとりはねおちほをひろふ村すすめわしのたかねはいかかしるへき
はなむけに何をかなと思へともほんらいくうの一もつもなし
一もつもなきを給はる心こそ本らいくうのほうみ也けれ
一首目の作者は一遍上人(一二三九~一二八九)とある。詞書に「むさうこくしざせんしておはしけれは」、座禅を居眠りと見立てて貶めている。二首目は夢窓国師(一二七五~一三五一)の歌ということだが詞書はない。踊り念仏を雀に喩えて鷲の高嶺には及ばないと返している。「鷲の高嶺」とは釈迦が説法した霊鷲山だろうが「鷲」は「儂」とも同音である。一遍上人五十歳で没年の年に夢窓国師は十四歳、あり得ない話である。三首目は「むしやう国師」、これも夢窓国師のつもりか。詞書は「むかし新田左中将よしさたは朝てきをしつめ給はんとて東国にくたり給ふ時」。四首目はその「返し」で新田義貞(一三〇一~一三三八)となる。一三三三年の鎌倉幕府滅亡の年とすれば年代的には齟齬を生じないが仮託だろう。
掲出歌は一休宗純(一三九四~一四八一)作、詞書は「たるまのゑに」つまり画賛である。著名な歌だが「さしたる事はいはじ」の反骨が買いといったところか。一休が一休としてブレイクするのは死後二百年近くが経過した『一休咄』である。一休また要注意なのだ。
津の国のありまの出湯はくすりにてこしおれうたの数そあつまる
『新撰狂歌集』の作品数は一八七首、うち落書とあるのが十八首、仮託や「有る人」の類を加えると多彩である。換言するならばそのいずれもが未分化の状態にあるのが特色である。しかし右「はんにや坊」の歌とりわけ下句には新時代の到来を予感させる熱気がこもる。
|
| 第19回 新撰狂歌集(5) |
おもしろしとはつ雪なれはほめもしつけふより後に大ふりなせそ
薪などともしき人(『新撰狂歌集』)
『狂歌大観』(本篇)に『永正五年狂歌合』が収録されている。「解題」によると「成立は永正五年正月」、西暦なら一五〇八年である。判詞に「此(の)十番の歌合は初春の比世にそむける貧客とものつれつれのあまりに狂歌をよみて」とあるように十番貧乏歌合なのだ。
思ひねのほともはつかし正月のもちいをくうと夢にみしかな
我身たたえこころ得ぬと心得て心えかたき世にもふるかな
一首目は「思ひ寝」の両義性を踏まえた「恥づかし」なのだ。二首目は初句「我が身ただ」、衆儀判に「え心えぬと身のありさまをは心得なから世にふるならひ心得かたき物にて過(き)行(き)侍るらん」とある。それは百年後の『新撰狂歌集』の人たちも同じだった。
軒ちかきとなりにたにもとはれねはひんほとふかきかくれかはなし
子ともをはすしにするほと持(ち)けれといゐがなけれはひほしにそする
しらみほと世をへつらはぬ物はなしひんなるものにことにちかつく
さけのますもちをもつかぬ我宿にとしのひとつも御めんあれかし
ひんほうの神も出雲へとふならば十月ことにわれはとくにん
もろ共にあはれと思へやきめしよなみたの外にしるさいもなし
一首目の作者は無銭法師、詞書に「まつしき人のしたしきにもうとまれけれはよみてつかはしける」とある。人里離れた山中ではない。貧しさゆえに人が遠ざかっていくのである。四句「ひん」は「貧」、結句は「隠れ家もなし」である。二首目は詞書に「おとろへたる人あまたの子をみてよめる」とある。二句の「すし(鮨)」は熟れ鮨と思われる。四句「いゐ」は「いひ(飯)」のこと。魚(子)はあるが飯がないので「ひほし(日干し)」だと嘆いている。三首目は「よみ人しらす」。世をへつらわぬ虱ならば富貴の家に近づけばよさそうなものだがそうもいかないらしい。四首目の作者は「家なししそん」。年齢ばかりは貧富に差がない。むしろ喜びたいところである。五首目の作者は四首目に「の」を挿入した「家なしのしそん」、詞書に「神無月はしめつかた」とある。三句は「飛ぶならば」、十月は全国の神々が出雲大社に集まる神無月、だからわが家の貧乏神も留守で「とくにん(得人)」のだ。六首目は「羇旅歌」の中の一首である。詞書に「路のほとりにてかれいいくふとて」とある。「かれいい」は「かれいひ(乾飯)」のこと、「しるさい」は「汁菜」、初句からの連想なら「知る妻もなし」と聞こえる(物の本によれば『伊勢物語』の九段を踏まえているのだと云う)。
掲出歌は詞書に「薪なとともしき人雪のあしたせんさいに出てよめる」とある。「せんさい」は「前栽」、正殿の前庭に立つ貧乏貴族であろうか。三句「ほめもしつ」に身分からくる矜恃をのぞかせるが四句以下は嘆願に近いだろう。風雅の世界に一転して生活の影が差す。
|
| 第20回 新撰狂歌集(6) |
七重八重花はさけとも山ふきのみのひとつたになきそかなしき 主(『新撰狂歌集』)
『新撰狂歌集』は四季・恋・羇旅歌・述懐・釈教・哀傷・神祇・雑からなる。掲出歌は春の歌、詞書に「ある人俄にむらさめふりけれはしる人のもとへ行(き)みのをかりけるにあるし山吹の花一えた手をりてさしいたし」とある。作者の「あるし(主)」とは兼明親王(九一四~九八七)である(『後拾遺和歌集』)。但し『後拾遺和歌集』では結句が「なきぞあやしき」(一一五四)である。四句の「みの」(「実の」に「簑」)で「ない」と断ったのだった。
引(き)かつくかたひらこしに月みれは雲ゐをはしるやせしらみ哉
冬のよのしとしかてらに見る月はおもしろしとてやかてひつこむ
一首目は夏の歌、「題しらす」の「よみ人しらす」。場所は寝所、頭からかぶった帷子を透して月を見ていると月の兎ならぬ月のシラミが空を渡っていることだ、といったところだろう。二首目の冬の歌、詞書は「寒夜月といふ題にて」、作者は「大江のこゑもち」、名にも糞尿の肥が臭う。「しと」は尿、放尿によって熱を奪われた体がぶるぶるときた図であろう。
庭の雪に我あとつけで出でけるをとばれにけりと人やいふらん
ぬのならは一尺なりとうちさらしはちをさらすは人のなかいき
あはれなりおふちしらみの跡とへはつめのうへこそはかところなれ
かつよりと名のるたけたのかひもなくいくさにまけてしなのなけれは
くらふつかまへわにかかる大へのこきんふくりんと人やいはまし
ことはりや日のもとなれはてりもしつさりとては又あめかしたとは
一首目は恋。作者名なし。詞書に「ある人本歌の言葉をもつて心を変へよとありし時」、本歌は慈円の〈庭の雪にわが跡つけて出でつるを訪はれにけりと人や見るらん〉(『新古今和歌集』、六七九)である。二箇所の濁音によって空飛ぶ人になった。二首目は述懐。詞書「老(い)のつれなきいのちをうらみて」、作者名はない。四句「はち」は「恥」(「端」の「はじ」を掛けたか)で一尺に対応して「さらす」の違いを鮮明にする。三首目は哀傷。作者は「よみ人しらす」。二句「おふぢ」は「おほぢ(祖父)」、三句でその行方を尋ねると、四五句は宿主の爪で潰されていたことがわかる。初句切れで「哀れ」を増すのは、それが虱一族の夢の跡だからであろう。四首目からは雑。詞書に「むかし甲斐信濃を知行せられける武田の勝頼と申せしはいくさにうちまけて両国をとられし時落書に」とある。歌は三句切れにしたいところだが失ったのは両国だから「く」と続けた。五首目の詞書「くらふづといふ人大へのこにて馬をすきてのりけれは」云々とある。「大へのこ」は睾丸、そこから鞍の前輪、四句の「きんふくりん(金覆輪)」とつながっていく。六首目、詞書に「ひてりのとしさる人のよめる」とある。「日の本」と「天(雨)の下」の対比が絶妙、すでに両語の中に照る日と雨の日がある、いずれ降らないということはないだろう、の歌意。初句切れ、結句は倒置法である。
|
| 第21回 貞徳百首狂歌 |
棹姫の裳すそ吹(き)返しやはらかなけしきをそそとみする春風 松永貞徳(『貞徳百首狂歌』)
「解題」によると寛永十三(一六三六)年の詠。構成は「春二十首」「夏十五首」「秋二十首」「冬十五首」「恋十首」「雑二十首」。著者の松永貞徳(一五七一~一六五三)は俳人、歌人、歌学者で京都の人。細川幽斎、里村紹巴に学び、貞門俳諧の祖となる。掲出歌は『貞徳百首狂歌』の巻頭歌で題は「立春」。「棹姫」は春の女神。四句にある「そそ」は風の静かに吹くさまを表す副詞かつ女性の陰部を云う。山崎宗鑑の『新撰犬筑波集』に類似の〈霞の衣すそはぬれけり/佐保姫の春立ちながら尿をして〉がある。『新撰犬筑波集』は室町後期の俳諧集である。約百年を経過しているが、この『新撰犬筑波集』には、もう一つ元祖のような作品がある。〈命知らずとよし言はば言へ/君故に腎虚せんこそ望みなれ〉である。『貞徳百首狂歌』なら「恋十首」、題は「初恋」の〈恋に人腎虚するこそ道理なれ見そめしにたに腰がぬくれば〉がある。評価は人それぞれだろう。「佐保姫(棹姫)」の歌なら私は春風の悪戯を喜ぶし、「腎虚(房事過多に伴う衰弱)」の歌なら『新撰犬筑波集』の直情を愛したい。
銭金でねをさすならば鶯の法法花経も一ぶ八くはん
とととととけふたたかるる七種やおひし野原のまま子なるらん
年男あふて日数もたたさるにはやくもとくる雪女かな
うまさうに草くふ音ぞ聞こえけるこれや霞の中のはる駒
業平の折句の歌のまねをせはたちまち恥をかきつはた哉
「春二十首」の作品。一首目の題は「鶯」。二句の「ね」は「音」であり、また「値」でもあろう。結句は法華経の「一部八巻」に「一分八貫」を掛ける。「一分」は「ごくわずか」で一声の意に解した。二首目の題は「若菜」で正月七日の七草粥を歌う。擬音「とととと」に父親を呼ぶ「とと」を掛ける。同様に「まま」は「飯」かつ「継」で一首は異なる意味の同時進行となる。三首目の題は「残雪」。年男は一家を代表して正月の行事を取り仕切り、若水を汲む。雪女も溶けなければ「うちとくる」間柄だったろうか。四首目の題は「春駒」、視覚でなく聴覚に訴える作品である。四首目の題は「杜若」、二句の「折句」とは『古今和歌集』の〈唐衣きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ〉(四一〇)を指す。
玉かつらくるる夜毎にみだるるはこれや螢の兵部卿殿
極楽でのらむより只いつまでも死なでながむる蓮ともがな
「夏十五首」。一首目の題は「螢」。「玉かつら」は「玉桂」で月の異称、また「玉鬘」で『源氏物語』第二十五巻の女主人公、玉鬘に恋をするのが螢兵部卿宮である。三句には螢火で玉鬘を垣間見る場面も投影されていよう。二首目の題は「蓮」、結句の「ともがな」は願望の意を表す。極楽で蓮の葉にのるよりも生きて蓮の花を見ていたい。もっともな感想である。
|
| 第22回 貞徳百首狂歌(2) |
月故にいとと此(の)世に居たきかな土の中ては見えしと思へは 松永貞徳(『貞徳百首狂歌』)
「秋廿首」。題は「月」。名月とは陰暦八月十五夜の月をいう。二句「いとど」は「いっそう」の意、結句「見えじ」の理由も明解で説得力がある。月の価値は今よりも高い。
凉しさを巻(き)こめてくる文月は一葉の風のちらし書(き)なり
生(き)なからしほしたやうに水鳥の翅も箸も霜そ降(り)ける
をの山や煙にあたる草木迄やかねと炭の色にこそなれ
おもひとは只大石のことくにてすてんとすれどちから及ばす
うらめしや思(ひ)は鬼と成(り)ぬともさすかに君をくひはころさし
一首目は「秋廿首」、題は「立秋」。一首は二句から「文月」(七月)の「文」の縁語仕立てで展開する。四句以下は「一葉(ひとは)」を筆に喩えた散らし書き、また一葉の散るさまを散らし書きに喩えた。その両方だろう。次の二首は「冬十五首」。二首目の題は「水鳥」。二句「塩したように」、料理の下ごしらえを思わせて羽根も嘴も霜で白い。四句「箸」は宛字か愛嬌か。三首目の題は「炭竈」。初句「をの山」(小野山)は京都市左京区大原にある山、また同音かつ四句「炭」の縁語で「斧」となる。四句は「焼かねど炭の」。最後の二首は「恋十首」、四首目の題は「思(ふ)々」。初句「おもひ(思ひ)」に二句「大石(たいせき)」の縁で「おもひ(重ひ)」(重い)を掛けた。何度も書くが歴史的仮名遣いは現代人の物差しであって絶対ではないのだ。五首目の題は「恨(むる)々」。初句「恨めしや」の中の「めし」が同音の「飯」になって結句の「くひ(食ひ)」を連れてきた。四句、鬼の恋情が悲しい。
名人の流(れ)をくめと末の代は万の道が下手のかはかな
雀ほとちいさく老(い)の身はなれとうひたる人はおどりわすれぬ
生(る)るも死(ぬ)るも人はおなし事腹より出(で)て野原へそ入(る)
借銭も病もちくと有(る)物をものもたぬ身と誰かいふらん
「雑二十首」。一首目の題は「河」。成句に「一河の流れ」がある。「下手(しもて)」になると「下手(へた)」が出てくるのは自然の理であろう。どの血筋、流派、系譜も逃れることのできない「蔕の側」によって衰退するのである。二首目の題は「懐旧」。四句は「浮きたる人」でイ音便と解釈した。成句「雀百まで躍り忘れず」の出典は物の本によると『毛吹草』(一六四五)としているが『貞徳百首狂歌』の方が古い。もしかすると源流であるか。三首目の題は「無常」。生まれてくるときは「腹」、死んだら「野原」で野垂れ死に、または焼かれて埋められる。「腹」と「原」はいいとして「野」が気になるが、まあいいだろう。四首目の題は「述懐」。これも一つの源流に違いない。借金も病気も自慢にならない。吹聴したくもない。それをあえて持ち出してくる。畢竟、物持ちに対抗するには負けん気しかないのである。
|
| 第23回 職人歌合 |
月もみしたくや塩やのけふたさにめをしはしはとすまの浦人 海士人(『職人歌合』)
「解題」に著者は「烏丸光広か」とある。しかし番いの左右なし、判者不在、かつ題なし、三十六職三十九首(内、一人二首が三職)は先行する「法楽の歌合」(岩崎佳枝)の印象からは遠い。また烏丸光広(一五七九~一六三八)は慶長年間に起きた猪熊事件(姦通事件)に連座して勅勘を蒙ったことがある。極刑を望む後陽成天皇(一五七一~一六一七)であったが、事件の処分は幕府に一任され、それが幸運したのであろう。ただ武家と公家という関係で見れば、処分に不満を抱いた後陽成天皇が譲位する一因となり、後年の禁中並公家諸法度の制定につながることにもなった。次に即位した後水尾天皇(一五九六~一六八〇)によって烏丸光広は勅免される。その後水尾天皇は紫衣着用の勅許を幕府によって無効にされるという紫衣事件を背景として第一皇女に譲位する。践祚して明正天皇。父は後水尾天皇、母は東福門院すなわち徳川和子、徳川幕府二代将軍秀忠の娘であった。『東北院職人歌合』に出発した物語は、こうして終わり、あるい明治の王政復古までの長い眠りについたのである。
まてしはし隣のかちのつちの音みのこす夢のさきかくるまを
まときはのてきはをおもふかへぬりはこてを枕の夢の内にも
とりかはすこなたかなたの年玉も手玉もゆらにおる扇かな
みめわろきいくらの人に偽のかかみのとかをいかけけるらん
あたりめのはつるる時はまけはくちさいをはもまてみをやもむらん
はるはると波路をはしる舟人は月より空の星やみるらん
一首目の作者は「鍛冶」。曰く「見残した夢を鎚音に先駆けて見てしまうまで、隣の鍛冶屋よ、ちょっと待て」。しかし時すでに遅し、である。二首目の作者は「壁塗」。漢字仮名交じりだと〈窓際の手際を思ふ壁塗は鏝を枕の夢の内にも〉で「放さない」相当句が云い止しである。三首目の作者は「扇屋」。『万葉集』に〈足玉も手玉もゆらに織る服を君が御衣に縫ひもあへむかも〉(二〇六五)がある。歌われているのは元旦に年玉用の扇を売り歩いた扇売りだろう。結句「おる」は扇の地紙を「折る」と解した。四首目の作者は「鏡屋」。二句「いくら」は「多数」、下句は「鏡の科を射掛けけるらん」。結句だが江戸時代の銭湯に柘榴口があった。語源は鏡を磨ぐのに柘榴の酢を使ったことから「鏡要る」「屈み入る」、「鏡射る」の出自もこの辺りだろう。口調は科負い比丘尼である。四首目の作者は「博打」。四句「采をもむ」で博打をすること、「采をばもまで」だから博打をしないで、結句は「身をもむ」で苦悶する、「もむ」で括った対句表現である。六首目の作者は「船人」。船頭にとっては船の位置を教えてくれるのが星、名月も地上にあってこそ主役だが、航海にあっては脇役なのだ。
掲出歌の作者は「海士人」。海水を煮て塩を作っているのである。初句は「月も見じ」、二句「塩や」は「塩屋」(小屋、地名も連想させる)だが「焚くや」に重ねて高揚した気分を出した。四句「目をしばしばと」、結句「すま」は地名の「須磨」に動詞の「す」を託した。
|
| 第24回 吾吟我集 |
なにはめのはらむ子だねの冬こもりいまは春べとつはるこのはら 石田未得(『吾吟我集』)
著者の石田未得(一五八七~一六六九)は俳人・狂歌師。江戸日本橋の両替商で松永貞徳の門人。解題に「刊年不詳、序に慶安二年四月と見え、それ以後ほど経ずしての刊行と思われる」とある。慶安二年は一六四九年である。『吾吟我集』は『「古今和歌集』のもじり、本文も仮名序のパロディから始まるので見てみよう。まず「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける」は「やま田歌は人のとる早苗を種として。あまたの種のことの葉とぞなれりける」と変換される。次に「花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」なら「花に琴ひく鶯。水にあやをるかはづの声をきけば。いきとし池のはたの蚯蚓。いづれか歌をうたはざりける」といった塩梅である。
掲出歌は仮名序の「そへ歌」に対する「ざれ歌」、本歌は〈難波津に咲くや木の花冬こもり今は春べと咲くや木の花〉である。「つはる」は「つわる」、名詞なら「つわり」となる。
いつはりのなきやうなれどいかがはと中人(なかうど)口はうれしがなしき
わが庵はみやまの茶つみしかぞすむ世をうぢうぢとくらすいとなみ
やはり仮名序。一首目は「ただごと歌」に対する「たはごと歌」。結句は「嬉し悲しき」、連濁である。本歌は〈いつはりのなき世なりせばいかばかり人の言の葉うれしからまし〉。二首目は「宇治山の僧喜撰は」と六歌仙のところが「宇治山の貴賤くんじゆ(群集)すれば」となる。本歌は〈わが庵は都の辰巳しかぞ住む世をうぢ山と人はいふなり〉である。
わか門を一間ひらくあしたより天下の春をしるかさり松
春の来る道筋ならし庭の雪に日あしふみこむ跡そ見えたる
春一季宮つかへして紅梅はちるや北野のかみさまのまへ
白妙の雪とけそむる比もきて野は色なをしするよめかはき
すがりてもひきととめまし行く春の霞の袖の手にしさはらは
『吾吟我集』は巻第一「春」、巻第二「夏」、巻第三「秋」、巻第四「冬」、巻第五「賀」、巻第六「恋」、巻第七「世話」、巻第八「旅」、巻第九「雑」、巻第十「廻文歌」からなり、仮名序を入れると歌の総数は六五八首である。うち右に抄出したのは「春」の歌。一首目の題は「春のはしめの歌」。小世界から大世界への転換が句またがりを経て大団円を描く、スケールの大きさが魅力である。二句の題は「残雪」。二句の「ならし」は「なるらし」の音変化、下句に見る太陽の擬人化が冴えている。三首目の題は「梅」。四季の「一季」、また「かみさま」も狂歌ならではの語彙であろう。四首目の題は「春草」。「よめがはぎ」は「嫁が萩」で「嫁菜」の別名。ちなみに近世の「色なをし」は式後三日目であった。五首目の題は「暮春」。四句の「引き止めまし」は反実仮想を表す。したがって結句は「手にし触らば」である。
|
| 第25回 吾吟我集(2) |
夕がほの花に扇をあてぬるはたそがれ時の垣のぞきかな 石田未得(『吾吟我集』)
掲出歌は巻第二「夏」の歌で題は「夕顔」、色好みの光源氏を出歯亀にしてしまった。もっとも『源氏物語』では扇を差し出すのは少女、上に夕顔がのっている。受け取るのも随身、光源氏は牛車の中にいた。扇には〈心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花〉。市井の人である未得には、これが夕べの顔に扇、誰そ彼、と公家は戯画の対象となった。
春過ぎて夏の日影にわたぬきの衣ほすけふあせのかきぞめ
ほそかりし滝の糸筋よりあはせ大綱になすさみだれのころ
風かほり夕だつ空の涼しきは雲に水をやあぐるりうなう
夏の日のあつけをはらふ泉こそ手にむすぶてふ水のゐんなれ
「夏」の続き。一首目の題は「首夏」すなわち初夏である。本歌は『万葉集』ではなく『新古今和歌集』の持統天皇御製歌〈春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山〉に拠っているだろう。根拠は三句の「衣干したり」と「衣ほすてふ」の違いである。しかし掲出歌にしろ、この歌にしろ下敷きがあっておもしろいのではない。おもしろいのでよく見ていると下敷きに気がついた。これが真相である。したがって見逃している場合もあるし、それよりも知らない場合がほとんどだろうが気にせずにいこう。二首目の題は「五月雨」。「糸筋」と「大綱」という比喩が大胆にして巧みである。三首目の題は「白雨」。結句の「りうなう」は竜王であろう。但し、この場合の歴史的仮名遣いは「りゆうわう」である。四首目の題は「泉」。歴史的仮名遣いは「いん」であるが「ゐん」は印相、印契の「いん」であろう。
うら盆の月夜にともすちやうちんは外聞のためまた後世のため
見事にて手にはとられず白露のきえやすきこそ玉に疵なれ
かれ木さへ花さくちかひあるなれば観音草の秋は尤も
常よりもまろくてしろく見ゆればや今宵の月をもちといふらん
やよ時雨なほうはぬりをたのむぞやまだ色うすきうるし紅葉に
巻第三の「秋」に移る。一首目の題は「玉まつりに」。盂蘭盆は陰暦の七月十五日前後、今年なら八月二十七日前後で満月となる。提灯は無用であったらしい。二首目の題は「露」。「白露」に文字通り「玉」の故事をもってきたところ、しかもその「疵」を「白露」の「白露」たる所以に求めるところなど知恵の輪に弄ばれているようだ。三首目の題は「秋草」。観音草は別名吉祥草、秋の終わりに花が咲くらしい。結句の「尤も」が新鮮である。四首目の題は「八月十五夜」。言わずと知れた中秋の名月である。近づくと遠のき、遠くにあると近い、それが同音の「望」と「餅」、感動の今昔らしい。五首目の題は「漆紅葉」。なぜ紅葉一般ではなくて「うるし」なのか。漆の木だから二句の「うはぬり」が生きてくるのであった。
|
| 第26回 吾吟我集(3) |
吹(く)風の手にやははきをつかふらん山を木の葉のちり塚にして 石田未得(『吾吟我集』)
掲出歌は巻第四「冬」の歌で題は「落葉」。二句の「ははき」は「ほうき」、歴史的仮名遣いなら「はうき」。但し「はうき」は「ははき」の音変化したものらしい。とてつもない擬人法である。同じ題で〈木すゑをやすりこぎにしてこからしのあへ物となる森の落葉は〉もある。手法も同様だが片や掃除道具、片や調理器具、比喩はどこまでも身近である。
人ならは脚気(かつけ)といはん霜かれにおれふすあしのふしもかなはす
河つらのしはは氷にのびぬれど冬ことによるわか老いのなみ
河の名のうぢある人の風情にて網代にのれる氷魚のゆゆしさ
名にしおはは夏の空にしふらせたやかたひら雪にあつさしのかん
ふらずんは空たのめとやうらむへき雪こんこんと人にまたせて
節分の夜半にまきぬるいりまめも花咲(く)春の種とこそなれ
「冬」の続き。一首目の題は「寒蘆」。いきなりの病名に驚かされるが症状を含めて周知の「現代病」であったのだろう。霜枯れで折れ臥し「蘆(足)の節も叶わず」なのだ。二首目の題は「氷」。「づら」は「面」で河面の波、氷になると伸びて消えるが結句「わが老いの波」は「冬ごとに寄る」と嘆いている。三首目の題は「網代」、「うぢ」は「氏」であり「宇治」、昔は氷魚漁で有名だったらしい。平等院、源頼政、『源氏物語』なら「宇治十帖」と「ゆゆしさ」(立派さ)に不足はない。四首目の題は「雪」。「かたびら雪」は一片が薄くて大きな雪、「帷子雪」と書く。初句はこの「帷子」に由る。五首目の題も「雪」、初句「ふらずんば」の漢文訓読体が斬新に響く。「こんこん」は雪や「こんこん」に「来ん来ん」を掛けたもの。六首目の題は「節分に」、このあとが巻第四最後の題「除夜」である。立春の前日、今と違って大晦日に豆を撒いたことがわかる。なるほど願いを込めた「花咲く春の種」であった。
代を久にたもつは天下一ちやうの弓はり月よ君の御いせい
亀のこゑすほんとはやす小鼓に万歳楽といはふ君か代
活計(くわつけい)に腹のふくるる世にあへは天下たいへを国土万民
巻第五の「賀」に移る。一首目の題は「寄月祝」。世は三代将軍家光の時代である。二句から三句は句またがりで「天下一張」、「ちやう(張)」は「弓」を数える助数詞、「弓」は武家の縁語である。二首目は「寄亀祝」。二句の「すほん」は小鼓の擬音に亀を響かせているから「すぽん」(すっぽん)となる。「君」は場によって異なるだろう。三首目はどうか。題は「寄民祝」。初句の「活計」は生計またその手段を云う。わからないのが四句の「たいへを」だが「天下太平」の類音で「天下大俵」と読んだ。乱暴だが当時の仮名遣いと矢羽根の「うすべを」(「うすべう」)の音変化を思えば「俵(へう)」が「へを」であっても驚かない。
|
| 第27回 吾吟我集(4) |
いつまでかせんなき恋を信濃なるあさま夕さまもゆる思ひそ 石田未得(『吾吟我集』)
『吾吟我集』巻第六「恋」を見てみよう。一四五首、すべて題詠である。どのように難題、
珍題を消化し、あるいはクリアするのか、そこが妙味であろう。掲出歌の場合は「寄山恋」、意味なら「恋を信濃なる」より「恋を駿河なる」の方がよい。しかし駿河には浅間山はない。その浅間と同音異義の朝間から対句表現として「夕さま」を造語する。きれいな一首である。そして改めて見てみると「信濃」の二字が「せんなき恋」にふさわしいのであった。
車井戸のつるへの縄の一すちにかけておもへはめくりあはなん
うきことを聞(き)ては耳をあらひけり枕になかすたきつ泪に
思ひ川へだててこねはしきなみに人はしかけて恋わたりぬる
一首目の題は「寄井恋」。井戸から恋への転換は四句の「おもへば」、恋の側から見ると初二句は三句「一すぢに」を呼び出す序詞ということになる。巡り会うのは車井戸だから縄の両端に付いた釣瓶でもある。二首目の題は「寄滝恋」。初句は形容詞「憂し」の連用形「うき」、恋に障碍はつきものである。結句の「つ」は「の」の意の格助詞、目尻から耳にかけて「滝つ瀬」であり、また「激つ瀬」なのだ。三首目の題は「寄橋恋」。三句は「頻波」で波、「頻並み」で人を描く。したがって四句は「人橋架けて」かつ「人は仕掛けて」となる。一方的な片思い、あるいは一方的に知るのみの存在、そこに橋渡しとしての仲人が登場する。
人心じゆんじゆくせねはしふ柿のなるにつけても気味のわろさよ
そひはてぬわかれをなけく暁にやもめからすのなくもいまはし
君こむといひし夜ことに過(ぎ)ぬるはたのまぬ狐身をやばかせる
つれなきはかいるのつらにかくるてふ水くき一度あひさつもなし
一首目の題は「寄菓恋」。二句の「じゆんじゆく」という言葉に注目した。漢字表記は「純熟」「淳熟」なのだろう。よくなれ親しむこと。時機が熟すこと。それがないと後味の悪さが残る。たとえば干し柿のなりそこないのように、といったところか。二首目は「寄烏恋」。四句の「やもめがらす」をサイト「国際日本文化研究センター」の和歌データベースで検索すると九首がヒットする。和歌の世界でも用いられたことがわかるが、但し鎌倉時代以降である。作中人物をあざ笑うように戸外でカラスが鳴いているのだ。三首目の題は「寄狐恋」。初句の「こむ(来む)」は狐の鳴く「コン」でもある。四句「をや」は連語で疑問の意、「あの女は媚狐(こび)、たのみしないのに私を迷わせたのか」となる。四首目の題は「寄蛙恋」。歌の意味は「つれなきは」「水ぐき一度あひさつもなし」である。その「水ぐき」を出してくるために俚言「蛙の面に水」が使われた。「水ぐき」は手紙、「あひさつ」は歴史的仮名遣いも「あいさつ」となる。なお「かいる」は「かえる」の音変化、口語で多く用いられたらしい。
|
| 第28回 吾吟我集(5) |
待つよひの吉凶(きつきやう)あしきささかにのくもてにあがき物をこそおもへ 石田未得(『吾吟我集』)
『吾吟我集』巻第六「恋」の続きである。掲出歌の題は「寄蜘恋」。前田勇編『江戸語の辞典』(講談社学術文庫)に「夜の蜘蛛は不吉なりとて、俗に『夜の蜘蛛は親に似ても殺せ』などいう」とある。上句の背景には、この俗信がある。三句「ささがに(細蟹)」は蜘蛛の古名、また蜘蛛の糸。「ささがにの」で蜘蛛に懸かる枕詞、「くもでに」(蜘蛛手に)はあれこれと思い乱れることを云うが、流れは四句「あがき」で蜘蛛の網に絡め取られた感がする。
口くせにうそつく人とみつ蜂のさしてたのめる我そはかなき
あふ中も今ははなれてはまくりのむきみより猶うき身成(り)けり
わか恋のさしみならねとからし酢(す)の目はなとをりて涙こほるる
一首目の題は「寄蜂恋」。初句で花の蜜を吸う蜂の姿態を暗示する。三句「みつ蜂の」は次の「刺して」と同音の副詞「さして」(とりわけ)に懸かる枕詞である。おそらく石田未得の独創であろう。二首目の題は「寄貝恋」。歌われているハマグリは二枚貝、巻き貝ではこうはならない。「むきみ」は殻を取り去った中の肉、その「ぬきみ」と一字違いの「うき身」(憂き身)で恋の歌になる。反復の効果はいうまでもない。三首目の題は「寄鯉恋」。長塚節は明治四十一年に祇園の一力で〈我がこひは鮨の山葵の鼻ひびき泣きもなかぬに泪ながさむ〉(春陽堂書店『長塚節全集』第六巻)と歌っている。『吾吟我集』との関連は知らない。ただ明治の人たちにとって狂歌は現代の私達よりも身近にあったはずだ。節また然り、である。
おもふこと寝言(ねこと)にいへは敷妙の枕やかくす恋をしるらん
つつめとも外にもるるはまんちうのあんに相違のわが契り哉
うすなさけ契(り)をこめのつきはててこぬかこぬかと待つほとそうき
あた人のつくま祭にかつくてふなへての数に入(る)われそうき
一首目の題は「寄枕恋」。「敷妙」は寝床に敷く布、「敷妙の」で「敷妙」に関するものに懸かる枕詞となる。私の隠している恋を枕に知られてしまった、というところか。二首目の題は「寄饅頭恋」。三句は既出の「みつ蜂の」と同様で次の「あん(餡と案)」に懸かる枕詞の創作であろう。「まんちう」は歴史的仮名遣いなら「まんぢゆう」。三首目の題は「寄米恋」。二句「契りを込め」の「込め(米)」、三句「尽きはてて」に「搗きはてて」、四句「来ぬか来ぬか」は縁語の「小糠小糠」と饅頭仕立てのあとは米仕立てである。四首目の題は「寄鍋恋」。「つくま祭」は滋賀県米原町にある筑摩神社の祭り。主役は女、関係を持った男の数だけ、鍋を頭にかぶるという奇祭である。初句「あだ人」は浮気者。四句「なべて」に「鍋」を重ねた。『伊勢物語』の百二十段に〈近江なる筑摩の祭とくせなむつれなき人のなべのかず見む〉があるが、これを能動的ないし攻撃的とすれば本歌の場合は対照的な「われ」である。
|
| 第29回 吾吟我集(6) |
うき恋のやまひを治(ぢ)する灸ならてむねをやく火そくるしかりける 石田未得(『吾吟我集』)
巻第六「恋」の続きである。掲出歌の題は「寄火恋」。意味は「うき恋の」「むねをやく火ぞくるしかりける」、これにホンモノの火「やまひを治する灸」すなわち「灸治)が二三句に挿入されている。題の「火(ひ)」も「恋(こひ)」「やまひ」「火」、また「灸」「やく(焼く)」の火偏としても登場する。二句の漢文訓読体「治(じ)する」は狂歌ならではであろう。
こぬ人をまつ夜にともす蝋燭のおもひこかるるしんのくるしさ
恋やみにほねかはとなるちやうちんの内のおもひの外にほのめく
忍ひあまる涙の雨にかくれみのかくれ笠こそきまくほしけれ
堂宮にのろひことしてうつ釘はかなつち論のりんきいさかひ
一首目の題は「寄蝋燭恋」。初句から三句までが序詞風に展開して四句「おもひ」に繋ぐ。その「ひ」が「火」でもあることは云うまでもない。結句の「しん」も掛詞で作中「われ」の「心」であり、また「蝋燭」の「芯」でもある。二首目の題は「寄提灯恋」。折り畳まれた状態で身心の身の側を歌い、火の入った状態で身心の心の側を歌って巧みである。三首目の題は「寄簑笠恋」。忍ぶ恋の連想で簑笠も「隠れ蓑隠れ笠」が要請される。結句の「きまく」は「着る」の未然形「き」に 推量の助動詞「む」のク語法「まく」が付いて係り結び、意味としては「身に着けたいものだ」。四首目の題は「寄槌恋」。四句「金槌論」は、金槌で釘を打つように自分の言い分を繰り返すだけの議論、その結果としての丑の時参りである。
おもひにしこかれてしつむわが恋は小舟に過(ぎ)た荷物なりけり
つつめともそなたに心ひくあみのめもとに恋のあらはれやせん
船遊ひうかれをんなのさほの歌きけはよふしもなへておもしろ
一首目の題は「寄船恋」。「わが恋」と掛けて何と解く。「小舟に過ぎた荷物」と解く。その心は「思ひ(重い)」に「沈む」。謎かけだが四句の「過ぎた」に注目したい。現代短歌で文語と口語の混用が云われるが今に始まったことではないのである。二首目の題は「寄網恋」。二句の「そなた」は二人称の代名詞「おまえ」、これに中称の指示代名詞「そちら」を掛ける。後者を含めて一首は「ひく」「あみ」「め」の縁語仕立てとなっている。三首目の題は「寄遊女恋」。三句の「棹の歌」は棹さしながら歌う歌であるが、ここでは遊女の船歌だろう。「よふし」は「容止」か。歴史的仮名遣いなら「ようし」で立ち居振る舞いのことを云う。
巻第六「恋」の最後は「恋雑」。成り成りて成り余れるも成り成りて成り合はざるも二人して知る。夫婦喧嘩は犬も食わない。そして「恋」の終わりは「日常」の始まりだった。
誰なをす中とはなしにめをとするいさかひはてて夜のちきりき
|
| 第30回 吾吟我集(7) |
人しれすころびてつきしむかふ疵いへぬる跡やけがの高名 石田未得(『吾吟我集』)
『吾吟我集』巻第七「世話」に移る。掲出歌に題はない。つけるとすれば「怪我の功名」。転んだ傷が何時の間にか向こう傷になったという話、「むかふ疵」は敵と戦って体の前面に受けた傷をいう。その反対が後ろ傷である。初句「人しれず」が思わぬ結果を呼び寄せた。
軒にふく瓦をとめてさす釘や手つよく見ゆる鬼にかなばう
ゐねふりも奉公かほにあつさ弓いひきの音のする夜番哉
にくまれ子世に出(づ)るてふたくひ哉藪よりそとにそたつ若竹
世間こそはり物なれと月の夜にちようちんともす人もありけり
一首目。題をつけるなら「鬼に金棒」。ただでさえ強い鬼が金棒を持って、さらに強さを増すことを云う。作品には瓦の葺きようが盤石であるという意味での「鬼に金棒」と見立てとしての「鬼に金棒」が表裏一体となっている。二首目。「世話」とは世間の言いぐさや慣用のことばを云う。ここでは「不奉公」とか「奉公人根性」であろうか。二句「がほ」は接尾語で、そのような様子であることの意となる。三句「梓弓」は枕詞だが、「射る」の「射」に「引き」で四句「鼾」を作り、さらに「音」に繋いだ。三首目。題をつけるなら「憎まれ子世に出づ」(「憎まれっ子世に憚る」)。世に出た姿が下句であった。四首目。題をつけるなら「月夜に提灯」。無駄なことの喩えである。二句「はり物」は提灯の縁語、意味は見せかけだけで中身のないこと。世間からすると変人だが、当の本人からすると、また別なのだろう。
手のきかぬ女子の親のせつかんは針を棒にや取(り)なをすらん
かまはしな是もさはるにぼんなうの犬ははけしく人にかみつく
双六のならひはしめはさいの目のいちをもつてそしるばんのうへ
口のうちにとなふる阿弥陀ぶつめかし手にもつ数珠も老(い)のくりこと
一首目。題をつけるなら「針小棒大」。二句の「女子」は習慣的に「じょし」と読んでしまいそうだが「をなご」と読むのだろう。針を棒に持ち替えて折檻したというところに歌としては工夫がある。二首目。題をつけるなら「煩悩の犬は追えども去らず」。作品は初句切れで「かまはじな」。「じ」は未然形に付く助動詞で打ち消しの意志を表す。「な」は終助詞、念を押す思い。しかし二句「是も」すなわち「かまはじな」が「障る」というのだ。三首目。題をつけるなら「一をもって万を知る」。双六には盤双六と絵双六があるが、これは盤双六。二句は「習ひはじめは」と「並びはじめは」、四句の「いち」は「一」に「位置」、結句の「ばん」は「盤」と「万」を掛けた、と読む。四首目。題をつけるなら「老いの繰り言」。初二句が「繰り言」で「ぶつぶつ」と、三句「めかし」で御経のように聞こえる、だろう。句またがりの「ぶつ(仏)」が効いている。結句の「くりこと」には数珠をつま繰る意を重ねた。
|
| 第31回 吾吟我集(8) |
馬のあし四本かかりによる浪のくつ音たかくこすまりこ川 石田未得(『吾吟我集』)
『吾吟我集』巻第八「旅」に移る。掲出歌、詞書に「まりこ川をわたるとて」とある。「まりこ」は「丸子」、古くは「鞠子」と書いた。東海道五十三次の宿駅。静岡県に位置する。「くつ」は「沓」、四句の颯爽とした風姿に五句への句またがり、その心地よさに惹かれた。
のりかけのつづらおりしてつかれたる馬には沓をうつの山こえ
やはり沓が登場する。詞書は「宇津の山をこゆるとて」。宇津の山は丸子を出たあとの難所、初句「のりかけ」は「乗り掛け」で明荷を両脇につけた道中馬に旅人を乗せること。二句「つづらおり」(葛折り、九十九折り)は曲りくねった山道、また背の両側に葛をつけた馬を葛籠(つづら)馬と云った。縁語である。当然、馬は在来馬で沓は草鞋、「うつ」は「宇津」と「打つ」の両意に掛かるが「蹄鉄を打つ」ではない。藁の縁語で蹄鉄は明治以後の普及である。
あふのけにころばぬほとは富士も見つそれよりうへはいさやしら雲
男山むかふは北のかたなれは是やはらむといはんおほはら
山姫のをこけ成(る)らし谷底にたくりためたる滝のしら糸
一首目の詞書は「富士山をなかめて」。初句「あふのけ」は「あおのけ」で「あおむけ」に同じ、「ころばぬほど」だから天辺を見ているわけではない。天辺はどうだと尋ねると、さあどうだか「いさやしら雲」なのだ。二首目の題は「名所山」、男山は京都府八幡市、「おほはら」は大原で京都市左京区、位置関係は男山の北の方になる。さて、そこからであるが「北の方」は貴人の正妻の敬称、「はらむ」は「おほはら」すなわち大きな腹からの連想である。三首目の題は「滝」。二句の「をこけ」は「麻小笥」で紡いだ麻糸を入れる容器、檜の薄板を曲げて作る。結句の「滝の白糸」という見立てに山姫すなわち山を守る姫君を配した。
けだ物の名になかれたる熊野川水にも影のうつる月の輪
船出して松浦の沖につる魚もひれふりにけり浪のわかれに
から崎の松は一ほんたちなから名をは日本にいひそひろむる
一首目の題は「川」。二句の「なかれたる」は濁点を付して「流れたる」。三句「熊野川」は初句を受けて「熊の川」、結句「月の輪」は満月の意、これに月の輪熊の白い模様を重ねた。二首目の題は「浦」。『万葉集』の〈海原の沖行く舟を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用姫〉(八七四)一連が思われる。それが三句の「魚も」の「も」であり、「領巾」は「鰭」、同音異義のおもしろさである。三首目の題は「崎」。「から崎」は「唐崎」または「辛崎」、近江八景の一つ、唐崎の一ツ松として知られる。一本でも日本(二本)、駄洒落には違いない。
|
| 第32回 吾吟我集(9) |
めにみえぬ物ともいはし草木のうこくは風のかたちならすや 石田未得(『吾吟我集』)
巻第九「雑」に移る。掲出歌の題は「風」。「云はじ」、「動く」、「ならずや」、「草木」は「そうもく」と読むのであろう。設問に対する反論そしてその証明だが実景の趣である。
ふくろふの声よりほほんほんのりと月の桂の木すゑ明けゆく
くちなはのをのか針めのほころひを誰にぬへとてぬけるきぬそも
人を見て人は人をもたしなめは人こそ人の人のかかみよ
鹿の皮はゆかけになるもやすからす又狩人の手にそあひぬる
一首目の題は「鳥」。「月の桂」は月に生えているという巨大な桂の木、その「木ずゑ」が明けてくる、とは月の姿であると同時に、その月によって照らされている森そのものでもあろう。「ほほんほんのり」が梟の鳴き声と視界の変化を伝えておもしろい。二首目の題は「虫」。四カ所に濁点がない。歌は脱皮した蛇の抜け殻、それを補修が必要な着物に見立てている。これで思い出したのが長塚節の〈からたちの荊棘(いばら)がもとにぬぎ掛くる蛇の衣にありといはなくに〉(春陽堂書店『長塚節全集』第三巻)である。詞書に「ゆもじばかりになりてぞ酒汲みはじめける」とあって、未得とは逆に人の着物を蛇の抜け殻に見立てたものだ。三首目の題は「鏡」。三句は「たしなめば」で嗜む、気をつける、といったところであろう。「人」の繰り返しは『万葉集』の〈よき人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よよき人よく見〉(二七)を連想させる。四首目の題は「弓懸」、つまり「ゆかけ」は「ゆがけ」、弓を射るときに手を保護するための革製の手袋、鹿の災難は死んでも狩人から離れられないのである。
塵をよく取(り)ぬる徳をいふならは是もこはくの玉ははきかな
住(み)わふる世のうきふしもわすれけりのみし寝ささのよひのまきれに
桧物師のまぐるをも見よ人心しなへてこそは中まろくなれ
一まいを万枚になすはく屋こそ金を打出のこつちなりけれ
一首目の題は「帚」。三句の「は」は「ば」。結句の「玉ばはき」(「玉ばうき」)で心の塵を払う酒の意がある。そして「是も」とあるように①箒の美称、②玉を飾りつけた箒(古代、正月の初子の日に蚕室を掃くのに用いた)の意もある。二首目の題は「酒」。これにも濁点がない。正述心緒かと思いきや、「うきふし」の「ふし」に竹の縁語を効かして、「寝ささ」の「ささ」(酒。笹)に展開し、「よひ」は「酔ひ」と「宵」、一首の笹飾りは忘れていない。三首目の題は「職人」。ひさしぶりに濁点があるが、このあたりの呼吸がわからない。正述心緒に対する寄物陳思ないし道歌の趣であるが職人技が臭みを払っている。四首目の題も「職人」。「はく屋」は「箔屋」、「こつち」は「小槌」。兵庫県芦屋市に打出小槌町がある。芦屋は知らないが、箔屋の小槌は振っても振っても枚数は増えるが重さが伴うわけではない。
|
| 第33回 吾吟我集(10) |
棚はたををれる糸屋の織女(しよくちよ)こそ天乙女にもをとるましけれ 石田未得(『吾吟我集』)
『吾吟我集』巻第九「雑」の続きである。掲出歌の題は「職人」。対照的な棚機つ女の登場すなわち織女星(天乙女)と糸屋の織女であるが、主役は天上ではない、人界にあった。
おにくるみわりそこなひて手のかはをむくりこくりと身は成(り)にけり
ぬすみより外の事をはしら浪のあはれあふなく渡る世(の)中
笠きてもこびんのはしにをく霜のしろきは人の世そ更(け)にける
名を残す跡の五輪はくすの木の石となりたるしるしなりけり
まじらへは七重の膝をやへにおる袴のひだのむつかしの世や
茶をのめはねられぬ老のはつむかし大むかしまて思ふ夜すから
たむくるはしふ茶なりとも明(け)暮(れ)のつもらは無上極楽のたね
極楽は涼しき道ときくからに経かたひらをきてや行(く)らん
一首目の題詞は「くるみをわる人を見て」。「り」音の調べのよさとは別に三句が実に痛そうである。二首目の題詞は「いたつら者とかにをこなはれけるに」、「とか」は「咎」であろう。「しら浪」は盗賊の「白浪」に「知らない」を掛ける。三首目の題詞は「年よりは見くるしなといひて笠きたる人と道を行(き)つれて」、「こびん」は「小鬢」。四首目の題詞は「楠の木のなにかしといふ人の墓所にて」、可燃物が不燃物になった。五首目の題は「述懐」、結句の「世」に収斂されていく比喩が巧みである。六首目の題は「懐旧」、十年一昔に始まって壮年期はたまた青年期と夜は長い。七首目の題詞は「人の追善に」、朝晩のお供えの功徳であろう。八首目の題詞も先と同様、こちらは機知であろうか。いずれも得難い小品である。
身の留守にきてはおりとるこのはなはのこる鳥をは敵にするのみ
しら雪は今朝野ら草の葉にもつも庭のさくらのさけはきゆらし
湊川(みなとかは)とまのそきつつまはりけり浜つつきその窓は門(かと)なみ
又飛(ひ)ぬ女(め)とおとあはれぬししらし死ぬれは跡をとめぬ人玉(ひとたま)
最後の巻第十は「廻文歌」十五首。難易度が上がれば上がるほど挑戦したいのが歌の巧者であるらしい。一首目の題は「春」。初句の「留守」は鳥であろう。そうするとあとは無理がない。二首目の題も「春」。二句「野ら」の「ら」は接尾語、三句「もつも」が若干不自然だか、結句「咲けば消ゆらし」と上等である。三首目の題は「雑」。二句は「苫覗きつつ」、湊川散策の趣向である。結句の「門なみ」は「門並み」で家の並び、また「なみ」は「波」でもあるだろう。四首目の題は「哀傷」。二句は「女(め)とお(を=男)と哀れ」、三句は「主知らじ」、身元不明の男女が投身自殺をしたというのだろう、初句の「また」は名所としての場所を指すのか、それとも心中の流行をいっているのか。そのどちらも、と読んでおく。
|
| 第34回 鼻笛集 |
孫よりもゑの子かへとはうは玉のよるよるおもふ用心のため 石田未得(『鼻笛集』)
『鼻笛集』に移る。解題によると編者は「高瀬梅盛(或いは『俳諧書籍目録』にいう一彳子か)」、刊記は寛文三(一六六三)年、備考「本書は二冊本のうちの下巻分に相当する。寛文十年書籍目録などに『二冊 はなふえ 高瀬梅盛撰』とみえる」とある。作品数は九十八首。梅盛、一彳子ともに狩野快庵編『狂歌人名辞書』(臨川書店)には収録されていない。内容は故事、ことわざの類に取材した作品集になっている。掲出歌の場合は「孫より犬子かへ」の一首、初出は『吾吟我集』巻第七の「世話」である。二句の「ゑの子」は子犬。
気つかひの中にそたつる孫よりもなくさみならはゑの子ろをかへ
さや鮫のだてする人はかいらきのせなかに腹はかへかたしとや
二代なき長者の身こそ借銭の子をむさほりし報なるらし
一首目の作者は一彳子、題詞は「孫より犬子かへ」。一つの題詞に未得、溝鼬、正舎、風船、一彳子、以上の五人の歌が並ぶ。未得は夜の安心のため、一彳子は無聊を慰めるためと、それぞれ理由は異なるが順接で応じている。二首目の作者は風船、題詞は「背に腹は替かたし」。五臓六腑の収まるを腹を守るためには背中を犠牲にしてもやむを得ない。これに対して腹の方を犠牲にしてもやむ得ないというのが抄出歌である。初句の「さや」は「鞘」、「かいらき」は「かいらぎ」で鮫類の背中の皮、刀剣の鞘の装飾に使われるらしい。三首目の作者は未得、題詞は「長者二代なし」。四句の「子」は取り立てた「利子」に二代目を響かしている。
よるは鼠とらんと猫の昼の間にゐねふりするも家の奉公
茶うすにし手を打(ち)かけて居眠も留守の間の奉公そかし
雨たれのたんたんとしも落(ち)くるはこれこそのきのしたつつみなれ
蔵の前に取(り)はらひぬる米俵すすめのためにこほれ幸(ひ)
一首目の作者は正舎、題詞は「居眠(り)も奉公」、そういえば猫は夜行性であった。初句六音、四句八音の各一音増も不自然でない。二首目の作者は一彳子、題詞は同じく「居眠も奉公」、今度は人間様である。初句の「茶うす」は「茶臼」、碾茶をひいて抹茶にするためのひき臼。「し」は副助詞で強調ないし整調、むしろ字数調整の側面からの使用であろう。三首目の作者は正舎、題詞は「舌鼓」、二句の「し」は先と同様、四句から五句の「のきのしたつつみ」は「軒の舌鼓」、「舌」は「下」、だから二句の「たんたん」が生きる。四首目の作者は溝鼬、題詞は「こほれ幸」。雀にとっては思いがけぬ幸運、こぼれた米は零れ幸いであった。
あと題詞のみを紹介すると「子捨(つ)る藪はあれと身捨(つ)る藪はなし」「垣に目口」「氏より生(ひ)立(ち)」「支証なき手柄」「けかの高名」「寝耳に水」「地傾(き)て舞まはれす」「瓢箪から駒出る」「良薬口に苦し」「一樹の陰」「一河の流」などである。
|
| 第35回 古今夷曲集 |
桜花散(り)しく庭をはきあるく雪踏(せつた)の皮に波そかかれる 忠精
『古今夷曲集』の編者は生白庵行風、刊記は寛文六(一六六六)年、序文に「千歌十巻」とあるが正確には一〇六一首、うち巻第一春歌は一〇一首。古今狂歌大全の趣である。
水は本へ返弁申し酒の字の作りをとりの年そきにける
足なくて雲の走るもあやしきに何をふまへて霞立つらん
たむほほの花のちちつと咲(く)比(ころ)の野山はやしはおもしろひなふ
一首目の作者は行景、詞書に「酉年の元日によめる」。「酉」(とり)の前は二句の「申」(さる)、四句の「作り」は「旁」で「酒」なら「酉」、偏は「?」で初句に帰る。四句の「とり」は「取り」と「酉」。二首目は「題知らす」で作者は法心上人。自明の「雲の足」「霞立つ」を論難した稚気を賞したい。三首目の題は「春草」で作者は行順。タンポポは別名「鼓草」で三句「ちちつと」は鼓のオノマトペを兼ねる。四句「はやし(林)」は「囃子」である。
こつきよし色は猶よし匂ひよし已上三よしのの花の勘定
葛城や天狗のはなのそれならてによつと高間の嶺にみえたり
いつとてもよう来たとだにおしやらぬはをしほのはなて人やあしらふ
題は「名所花」。一首目の作者は行風。初句は「骨気」(体つき)と解した。「三よしの」は「み吉野」に「三良し」(三拍子)を掛けた。「已上」は「以上」。二首目の作者は道明。立ち位置だか吉野の金峰山から眺めていると解した。初句「葛城や」と歌い起こして役行者の連想から天狗を思い、その鼻ならぬ端に桜の花が「によつと」なのだろう。高間山は金剛山の異称。三首目の作者は行安。三句「仰らぬは」、四句の「をしほ」は「小塩」で「はな」は「鼻」「端」「花」、小塩山は京都市西京区大原野にある。桜の縁では謡曲「小塩」が知られる。
水にすむ蛙が歌をよくきけはとかく卑下なり愚意愚意といふ
酌人のこぼるるばかりもるにこそはや置(き)給へもも桃の酒
一首目の題は「蛙」。作者は満永。蛙の鳴き声も一様ではないが、なるほどと思わせるオノマトペである。結句の「愚意」は自分の意見や考えをへりくだっていう語、愚見、愚案に同じ。二首目の題は「三月三日」。作者の一圃は「作者之目録」に「浄久寺」とあるから僧侶なのだろう。初句は音読みである。結句の「もも桃(もも)」四音は辞退の意、そして二三句の盃の様態を重ねつつ同音の「桃」に接続した。酒は白酒ではない。桃花酒であろう。
掲出歌は題詞に「落花をよめる」とある。「雪踏」は現表記「雪駄」で竹皮草履の裏に革をつけた履き物、結句の「波」は見立て、一点凝視によって逆に大きな自然を歌い上げた。
|
| 第36回 古今夷曲集(2) |
あまかへる蓮華にひよつとのつたれは生き仏とや是もいはまし 種好(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の巻第二夏歌に移る。収録数は六三首と少ない。抄出歌の題は「蓮」。初句は雨蛙。仏像を安置する台座を蓮華座あるいは蓮華台という。見立ての歌であるが二句の「ひよつと」がほのぼのとした世界に仕上げている。これと反対なのが〈花瓶にもさすてふ花と聞きしよりはちすをみれはうそぞふかるる〉である。「さす」は「挿す」と「刺す」、「はちす」は「蓮」と花後の花托が似るところから同音の「蜂巣」、「うそ」は「嘯」(口笛、嘯き)、花瓶に挿された蓮(蜂巣)を連想しているのだろう。作者は「むねます」、宗増と思われる。
風の手の礫(つぶて)のやうに打(ち)ちらす雨こそ今日の虚印地なれ
ねぢつけていざやちぎらんをのれとはまだおちそうもなき小姫瓜
をのづからなすびの色を紫のふくさにつつむ茶入(れ)とそみる
なからへて何をなすひの畑に生ふる若きをこそは人もちきらめ
一首目は題詞に「五月五日雨降りけれは」、作者を左衛門督藤原義景とする。これは朝倉義景と考えられる。「印地」は石合戦だが、もとは実戦だった。風に散る雨粒だから「虚(うつ)」。題詞次第で歌の様態は変わってこよう。二首目の題は「姫瓜」。作者は未得。三句は一人称の人称代名詞だが副詞「自分自身で」も共存、四句は思い通りになる意だが自然落下の可能性もなくもないだけに初二句の強引さが目立つ。危うし、小姫瓜。三首目の題は「茄子」。作者は「みとく」、平仮名だが未得であろう。結句の「茶入(れ)」は茶の湯で使われる容器、その一つに茄子型がある。したがって包む袱紗も初句「おのづから」紫となるのだ。四首目の題も「茄子」。作者は玖也。二句の「なすひ」は上を受けて「なす日」、下には「なすび」で繋がっていく、不思議な交差点。有用の若い茄子と老残を嘆く無用の茄子物語である。
罪あるもあらぬ人をもいきながら鬼はかほとによもやくふへき
精舎には諸行無常となるかねのしやぎりしきりにかはる祇園会
来る秋と夏は過(ぎ)行(く)さかひめのまん中臣の祓するなり
一首目の題は「蚊」、作者は宗朋。蚊はどこにいるのか。四句の副詞「かほどに」かつ「蚊ほどに」で蚊が刺すことを「食ふ」は云うまでもない。二首目の題は「祇園会」、作者は未得。『平家物語』の冒頭を響かせている。四句の「しやぎり」は現代仮名遣いでは「しゃぎり」、練り物行列で奏する囃子である。「しやぎりしきりに」はリフレインの効果を意識した。同じ題で行風は〈ひいてくるとみれは過(ぎ)行(く)山鉾よ是や祇園の会者定離なる〉と歌う。三首目の題「荒和(の)祓」は夏越の祓に同じ。作者は淡路守宗増。「中臣の祓」は中臣氏が代々つかさどっていた大祓をいい、その大祓は六月と十二月の晦日に行われた神事で前者が夏越の祓、後者が年越しの祓であった。四句の「まん中」の接続に技量を見たい。
|
| 第37回 古今夷曲集(3) |
片脇へつとそびけろうみたくないに邪魔入(れ)申す月の村雲 よみ人しらす(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の巻第三秋歌に移る。全七五首である。抄出歌は題詞「月を奴子詞にてよめる」。奴子詞は奴詞、六方詞ともいう。山中源左衛門の辞世〈わんざくれふんばるべいかけふばかりあすはからすがかつかじるべい〉が有名である。二句「つと」は「さっと」、次は「そ(聳)びく」(雲がたなびく)の命令形に間投助詞「ろ」の音変化の接続であろう。「私」は雲を見たくないので「邪魔入申す」。「入申す」は「入り申す」ではなく「入れ申す」と読んだ。この関連で〈秋の野にかか風ふけるたたたびにたたたれ招くはは初尾花〉を引いておこう。同じく「よみ人しらす」、題詞は「薄を吃詞(どもり)にてよめる」。いずれも口語である。日本史の近代は明治からだが日本語の歴史で近代語が始まるのは江戸時代だった。
御簾(みす)ごしになかめまいらせ候は只文月の透(き)写しなり
両の手をふりつつ拍子打(つ)時はあふきを腰にさしをとり哉
渡り来る数も限らす一つれに二十三十四十からかな
草村にむさとな鳴(き)そ轡虫野飼(ひ)の馬のはむ事もあり
一首目の作者は行風、題は「初秋月」。結句の「透写し」は敷き写し、書画の上に薄い紙を置いてなぞること、「文月」の縁語かつ御簾越しの月でもあろう。現代短歌でたまに見かける「候」も狂歌の遺産だった。二首目の作者は久清、題は「踊」。「あふき」は扇。結句の「さ(差)しをとり」は踊りの名称というよりも踊り手のスタイルであろう。臨場感のある一首である。三首目の作者は少将藤原秀宗、これは巻末の「作者之目録」に「宇和嶋」とあるので宇和島藩初代藩主の伊達秀宗であろう。題の「色鳥」は秋に渡ってくる小鳥。結句の「四十から」は四十雀ではなくて四十雀雁だろう。四首目の作者は浄治。題はない。二句の「むさと」は軽率にことをすること、うっかりと。「な~そ」は禁止の意。馬に縁語の「轡」を名に冠されていても油断はできない。なにしろ野飼いの馬は轡を嵌められていないのだ。
望月を汝(なんじ)が箸にかけんとやほつかり口をあきのよの空
月見よといもか子とものねいりたを起(こ)しにきたは何かくるしき
百姓の稲こなすとてする臼の音聞く時そ秋はかしまし
一首目の作者は浄久、「題しらす」。二句の「汝」が強く響く。辞書によると中世以降は目下に対して用い、江戸時代以後は文語化したとある。子供が相手だろう。「あき」は「開き」であり「秋」。二首目は作者名の記載はないが行安だろう。題詞は「名月の夜畑なる芋ぬすめるをとらへけれはぬす人のよめる」。三句の「ねいりた」の「た」は助動詞、促音便で「ねいつた」とあるところか。三首目の作者は一幸、題は「秋田」。農家は籾摺りで忙しい。本歌は〈奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき〉(『古今和歌集』二一五)。
|
| 第38回 古今夷曲集(4) |
あたるまの久しき程に炭の火もぜうとなりてや足のひゆらん 光知(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の巻第四冬歌は全四六首。抄出歌の題は「火桶」。イメージとしては掘り火燵を想像するが丸形の火鉢のことらしい。四句の「ぜう」は歴史的仮名遣いなら「じよう(尉)」、意味に「老翁」と「炭火の白い灰になったもの」がある。当然、計算の範疇である。
昨日今日あらさむやとて重ねきる小袖そ冬の始めなりける
正直の神のちかひのかの字にし濁りをさいた身を祈るなり
なまぐさき恋をもいのる神なれは御前てとるもみくじらぞかし
出女か紅(べに)まへたれの赤坂のあかぬ姿にとまる旅人
一首目の作者は淡路守宗増、題詞は「百首歌の中に初冬」。二句は「あら寒や」、四句は「小袖ぞ」で句割れである。初冬の実感は昔も今も変わらない。二首目は巻第五賀付神祇で全二四首。作者は正定、題詞は「心あきらかならん事を神に祈りてよめる」。二句の「ちかひ」は「誓ひ」だが、これに「違ひ」を掛ける。四句の「さいた」は「離いた」「放いた」、だから「『か』の字」なのだ。三首目の作者は満永で「題しらす」。結句、「神籤らぞかし」の「ら」は接尾語と見る。「くじら(鯨)」を隠して初句「なまぐさき」と四句「とる」を効かしていよう。四首目は巻第六離別付羇旅、全五十一首を代表させた。作者は保友、題は「赤坂にて」。初句の「出女」は客引き女、多くは売春もしたらしい。「か」は「が」。二句の「紅まへたれ」は「紅前垂れ」、「赤坂」の「あ」、「あかぬ」の「あ」の韻も応えて江戸は華やかである。
君か皃うつしてほしや水桶のわがおもふその心いつはい
心には思ひますれと馬子の身で君落ちよとはえ申さず候
あふたよに鳥よなひたら元興寺(がごうじ)の鬼にかませよそなれもひよこも
竹笛のなかの節くりいさかひはりやらひやらをききぞ兼(ね)ぬる
巻第七恋歌は全一〇三首。抄出した一首目の作者は嘉隆、題詞は「職人恋歌合に桶工によせて」。初句の「皃」は「顔」の異体字である。三句以下、特に「心いっぱい」が魅力的だ。二首目の作者は久清、題詞は「馬子恋をよめる」。これも職人歌合の伝統の中にある。馬子でありながら客の落馬を願う歌を背景に身分を越えた純愛を重ねた。キーワードは四句の「君落ちよ」であった。三首目の作者は行安、題は「逢恋」。初句の「あふた」は歴史的仮名遣いなら「あうた」、二句「なひたら」は「ないたら」となる。四句は鬼に「かませようぞ」の意と解した。奈良の元興寺には鬼の伝説がある。忍ぶ恋か。ユーモアに加えて最後は「ひよこも」とどすを忘れない。四首目の作者は成安、題詞は「夫婦いさかひをみてよめる」。二句の「節くり」は「節刳り」に「怒る」意味の連用形「ふしくり」。四句は笛の擬音語かつ「理やら非やら」、犬も食わないのが夫婦喧嘩である。それにしても小道具の竹笛が冴えた。
|
| 第39回 古今夷曲集(5) |
人間の八九七十二の年も心はもとのてうちぜぜがこ 権大僧都光宥(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の巻第八雑上は物名と廻文歌を含めて全九八首。抄出歌は「題しらす」。結句の「てうちぜぜがこ」は「手打ちぜぜかこ」だろう。但し、「ぜぜかかふ」の表記で「手手甲」、昔の鬼ごっこの一種。手を組み合わせて手の甲を互いに打ちながら童謡を歌い、歌い終わった時に打たれた者が鬼となる。九九と濁音に惹かれた。作者は高野山の人らしい。
人毎に腰おれ歌をよみ置(き)てあたら桜を杖にこそつけ
たむほほをとたんとたんとはやりもせでちちつちとこそ送るなりけれ
此(の)程は打(ち)絶(え)にけるたんほほを給(は)りてくふ舌つづみかな
衣がへの今日しもわたをぬかるるは魚の腹もやう月なるらん
雨ふるは不思議か笛はおひやおひてれてれてれとならす太鼓に
一首目の作者は長嘯子、題詞に「短冊とてや花の枝にえしれぬ事とも書(き)てかけならへたるをみて」。二句「腰おれ」の縁語が結句「杖」、桜が立派だから四句「あたら」(もったいなくも)となる。次は二首で一対。一首目は「読人しらす」、題詞は「人のもとへ鼓草にそへて」、二句と四句は鼓の擬音でもある。二首目の作者名なし、題は「返し」。タンポポは別名「鼓草」だから「舌つづみ」となる。四首目の作者は貞徳、題詞に「卯月朔日魚の棚通りけるに魚ともあまたあらふをみて」。「魚の棚」は普通名詞、二句の「しも」は連語で上の語を強調。四句「もや」は連語で詠嘆、結句は「う月」で腹の中も衣替えなのだ。五首目の作者は道明、題詞に「雨請成就しけるとて踊もよほせし所にて囃子物によせてよめる」。三句は笛、四句は太鼓の擬音。また「おひやおひ」は風神、「てれ」の反復は雷神を連想させる。
あまたある中で取(り)分(け)しぶかきをむくはめききに下手のかは哉
庭の苔すき屋のたたみそりたてのあたまも青き茶(の)湯也けり
春の礼にござりやすとも待つ程にまつの内さへ打ち過ぎて候
松の内にまつかひなしや曲なしと述懐中の尤(も)の歌
一首目は「題しらす」、作者は宗朋。二句「取(り)分(け)」は副詞と動詞の連用形で意味を重層化していよう。「下手のかは」は「面の皮」「化けの皮」等に倣った「下手の皮」、また同音の「蔕の皮」でもあろう。二首目の題は「青」、作者は器音。「すき屋」は「数寄屋」、いよいよ侘びと寂の世界というところに闖入する「あたま」であるが逆に臨場感も生んでいる。次は二首一対の物名である。一首目の作者は行風、題詞に「保友のぬしいにし年の暮より音信たえて親月望日もとはて過(ぎ)にけれはそれか名をかくしてよみて遣しける」。隠しているのは二句「やすとも」である。二首目の「返し」、行風の字は懐中であった。「曲なし」は型通りで面白みがないの意。そろそろと思っているところに御尤もな催促にて候、か。
|
| 第40回 古今夷曲集(6) |
わたくしも難波にすめばすすの酒よしやあしとてたべませいては 読人しらす(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の巻第九雑下は哀傷歌を含めて全三三二首。抄出歌には「親しき方にて酒すすめられけるに是は味なし彼はよしなといひけれはとかくいひて盃の数重なる事よと笑はれけるによめる」という詞書がある。「あし(よし)」は「難波」の名物、「すす」は『万葉集』に〈難波人葦火焚く屋のすしてあれど己が妻こそ常めづらしき〉(二六五一)とあり、「煤」に「すすめる」を掛けた。結句は「ませ」が助動詞「ます」の未然形、これに接続助詞「いで」に係助詞「は」で「食べないということは」、あとの「ございません」は省略と読む。
どうどうとなるもひびくも打(ち)よする波の鼓はかはのはりあひ
四四ならは十六つれて行(く)べきを九九にもるるかひとつはしるは
よくばけて嫁入(り)をするめ狐よ夜の殿子にさらればしすな
母にいつをくれはしけむ小鼠のあけ暮(れ)ちちとなく声のする
一首目の題は「河」。作者は満永。波の描写が四句で一点「鼓」の比喩となり、結句では前景に「皮」、後景に「河」、それぞれの「はりあひ(張り合ひ)」が見事な二重奏を実現した。二首目の題は「獣」、作者は「読人しらす」。「獣」は「しし」とも読む。これを九九に置き換えたのがアイデアだが、干支ならいざ知らず、どことなく誤魔化されたような気がしないでもない。三首目も「獣」の一連にある。作者は道寛。但し、この狐は人間と思われる。夜鷹、辻君、夜発、総嫁とか呼ばれた人たち、「殿子」は「殿御」、わからないのは「さらればし」だが「戻り橋」を意識した「去られ橋」と解した。逃げられるなよ、というわけだ。四首目は、かわいい「獣」の登場だ。作者は道明。二句の「遅れはしけむ」、母鼠がいなくなったのは家猫の犠牲になったからであろうか。「ちち」は擬声語、これに母鼠の「乳」を掛けた。
折りよくは申させ給へふたつ文字牛の角もし奉るなり
魚の名のそれにはあらずひまのおりちと二(つ)文字牛の角もし
一首目の題詞に「前関白信尋公へ淀鯉奉るにそへて」とある。「作者之目録」によると「近衛殿」とある。近衛信尋(一五九九~一六四九)ならば後陽成天皇の第四子、後水尾天皇の弟である。作者は昌俊、同じく「作者之目録」では「淀住佐川田氏」とある。生年は一五七九年、没年は一六四三年。作品だが三句の「ふたつ文字」(二つ文字)は漢字の「二」に似ているところから平仮名の「こ」、四句の「牛の角もし」(牛の角文字)も形が牛の角に似ているところから平仮名の「い」、合わせて「こい(鯉)」となる。ちなみに『徒然草』の第六十二段〈ふたつもじ牛の角もじすぐなもじゆがみもじとぞ君はおぼゆる〉なら「こいしく」である。初二句は作者の昌俊が近衛家の使用人に云っているのであろう。身分が高いので間接である。二首目は「返し」。「こい」が「鯉」でないとすると同音異義で「来い」となる。
|
| 第41回 古今夷曲集(7) |
それもいさ爪に藍しむ張り物のしいし取りをく手繦(たすき)姿よ 前大僧正慈円(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の巻第九雑下の続き。抄出歌は「題しらす」。四句の「しいし」は「しんし(伸子)」で「反物を洗ったり染めたりするとき布をぴんと張らせて縮まないようにするための竹製の串」(『大辞泉』)。初句「それもいさ」は「知らず」の意を含んだ展開であろう。それさえ気がつかない、気にもかけないで、だから結句の詠嘆、感動の助詞「よ」なのだ。
薄墨につくれる眉のそばかほをよくよくみればみかどなりけり
給はりし栂尾の茶はすぐれたり是やうぢよりそたちなるらん
日本さへ及びなき身に三ごくをままにせよとの御意ぞうれしき
一首目の題詞は「蕎麦掻餅出(で)ける座にてよめる」、作者は法印玄旨、細川幽斎である。同歌が『新旧狂歌俳諧聞書』(『狂歌大観』第二巻『参考篇』)では「関白秀吉公供御上りける時にいひの中にそはとなんいふものあやまりて有りけれは秀吉いときしよくかはりけれはよめる」、また左注に「此のうたにて御きしよくやはらきけるとなん」とある。二首目の題詞は「栂尾の僧より手作(り)なりとて茶を給ひける返事に」、作者は「よみ人しらす」。諺「氏より育ち」が「宇治より育ち」となる。未得の〈ゆたんなくこやしかくれはよきえんの茶もや宇治よりそたちなるらん〉(『吾吟我集』)ほかバリエーションも多い。三首目の題詞は「或(る)方より米三石給ひたる返事に」、作者は「読人しらす」。但し『新撰狂歌集』では「さだうの法師」、『醒睡笑』(同前第二巻『参考篇』)では「鉈の床の百姓」になる。「三石」は「三国(日本・唐土・天竺)」、「まま(飯)」は「ままになる」の「まま(儘)」である。
よせ太鼓日はてれつくと打ちいづる波の音まで河原もの哉
舟ならで棹のうたてやはりてひくなくさみせんの駒のかはゆさ
碁なりせはこうはたてても生(く)べきに死ぬる道には手もなかりけり
ほつくりと死なは脇より火を付(け)てあとはいかいになして給はれ
一首目の題詞は「四条河原にてよめる」、作者は宗恒。「よせ」は寄せ太鼓の「よせ」と波の縁語、「てれつく」は太鼓の擬音に太陽の「照り付く」を掛け、三句で再び太鼓と波、往時が偲ばれる。二首目の題詞は「猫のいたみの中に」、作者は休甫。四句の「さみせん」は三味線だが「なくさみ」に「鳴く」また「慰み」が隠れる。結句の「駒」は胴と弦の間に挟むもの、また猫の異称「こま」と同音である。三首目の題詞は「臨終に碁打ちなりけれは」、作者は算砂、本因坊算砂(一五五八~一六二三)である。「こう(劫)」は一目を双方で交互に取りうる形、反復すると勝負がつかないので一手以上他に打ったあとでなければ取れない。四首目の題詞は「俳諧師なれは臨終に」、作者は宗朋。初句「ほつくり」に「発句」、三句「脇」に「脇句」、四句「はいかい」に「俳諧」と「灰」を重ねていることは云うまでもない。
|
| 第42回 古今夷曲集(8) |
極楽の金(こかね)座敷は尻(しり)ひえん只行くべきは地獄釜ぞこ 理西(『古今夷曲集』)
『古今夷曲集』の最後は巻第十釈教、全一七八首。抄出歌は「題しらす」。啖呵。大見得。ともあれ異色の作品である。但し、辞世としての傍証はない。あるのは「六十三歳にて終りをとる時よめる」の題詞で〈我(が)よはひとはば七九の鐘木杖かねはもたでも南無あみた仏〉(休甫)、また「借用之地水火風返弁申今月今日といふ前書にてよめるうた」の題詞で〈かりをきし五つの物を四(つ)かへし本来空に今ぞ趣むく〉(一休和尚)などである。
灯をかかげて夜半にする護摩の油ささんとつつをふる寺
みな人のもし成仏をするならは地獄の鬼やかつへ死なまし
此(の)尼が西方けがす科あらばめし取(り)給へ弥陀の御国に
一首目の題詞は「百首歌の中に」、作者は玄康。三句までは問題ない。しかし四句からが怪しい。「油」は護摩木を焚く際に使用するが活力源の謂いでもある。結句の「つつ」は竹筒で酒の登場であろう。二首目は「題しらす」で作者は行好。「善人なほもつて往生を遂ぐ。況んや、悪人をや」(『歎異抄』)では不都合らしい。その点で理西は上客である。三首目は題詞に「西をあとさまになして小陽せられけるをある人の見て弥陀を念ずる行者の西方けがせるはいかにぞやといへればよめる」、作者は安養尼。「小陽」は「小用」を疑ってみるが尼には不似合いである。同歌は『続家つと』に宮川尼作で登場するが結句は「弥陀の浄土へ」、題詞はない。「小陽」は「初陽」(日の出)を拝んでいるのかも知れない。味噌は結句が地獄でないところである。ほかには〈浄土にも剛の者とや沙汰すらん西にむかひて後ろみせねは〉(蓮生法師)があるが『かさぬ草紙』(『狂歌大観』第二巻『参考篇』)では安養尼や宮川尼に接近して〈西方へ足さしたるかとかならはめしとりたまへ弥陀の浄土へ〉(蓮生法師)となる。
直(ぐ)なるもゆがめる川も川は川仏も堂も同し木のきれ
直(ぐ)なるもゆがめる川も川は川仏もげたも同し木のきれ
此(の)袋あけてみたればなにもなし何もなひこそなにも有りけれ
一首目の題詞は「本来意を問(ふ)とてよみて遣はし侍りける」、作者は智薀法師。「作者之目録」に「蜷川」とある。一休と交流のあった蜷川親当、通称新右衛門なら「智薀」ではなく「智蘊」だろう。いわば禅問答。二首目は「返し」、作者は一休和尚。破天荒で、いかにもといった感じである。一休がブレイクするのは『一休咄』(一六六八年刊)によるらしいが、『古今夷曲集』はそれより二年早い刊行である。三首目の題詞は「布袋絵の賛に」、作者は沢庵和尚。四句の「なひ」は「ない」。下句は釈教歌や辞世に形を変えて現れる。布袋は七福神の一人。太鼓腹と大きな布袋、円満の相もあって人気が高い。比丘一糸作で〈手をのべてゆるりとぬるか布袋との袋の中になにもなけれは〉(「眠れる布袋の画の賛に」)もある。
|
| 第43回 堀川百首題狂歌合 |
地頭殿のお手さくの田を先うへてまいらせ尻にならふさをとめ 池田正式(『堀川百首題狂歌合』)
成立年の記載なし。著者の池田正式(?~一六七二?)は大和郡山藩士、のちに浪人、入水自殺が伝わる。掲出歌の題は「早苗」、左の詠者。但しの詠者も判者も池田正式、一人三役である。「地頭」は地方知行を与えられた家臣、「先」は「先(ま)づ」と読みたい。「まいらせ尻」については判に「手向(け)かほにさし出したる体にや」とあるが、由来は「まいらせそろ」の変体仮名の形のように、うつ伏しているときの尻の形。またその尻を云う(『日本国語大辞典』)。右は〈またくらやいととぬまぬまぬまつかんふけたのさなへとれるさをとめ〉。初句は「股ぐらや」、二句の畳語「沼沼」に続く三句「沼付かん」が卑猥である。「ふけた」は「深田」、泥深い田である。「とれる」とあるから左の水田に対する苗代田であろう。
時鳥鳴(き)つる方をなかむれはたたあきれたるつらそのこれる
いんちするつふてにあたるあたまよりたらりたらりとちをあやめ草
夏はらひしてもうき身はうらめしのうへにあつまるはいに社(こそ)あれ
一首目の題は「郭公」。下敷きになっているのは『千載和歌集』の藤原実定の〈郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる〉(一六一)で、「有明の月」を「あきれたるつら」に差し替えた。白い残月を人の顔に見立てた。二首目の題は「菖蒲」。「いんち」は「印地」、五月五日に行われた子供の遊びである。しかし石があたれば怪我をする。最後に「ち(血)」を呼び出して「あやめ(危め)」と主題の「あやめ(菖蒲)」を重ねて着地した。三首目の題は「荒和祓」(夏越の祓)。「荒」の字から「荒ぶる」、「荒ぶる」に掛かる枕詞は「五月蠅なす」。以下、蠅の行状は追い払(祓)ってもまた飯の上に集まってきて恨めし(飯)いのだ。
草ふきに門をかまへて西かはのむかひに秋の花そかほれる
越路より南へむけてくる雁もよこきれにする西風そ吹(く)
秋かせに草のは武者のはらはれて残れる露は一てきもなし
灯をいさよひのまにそむくるや油にことをかく月の空
一首目の題は「蘭」。判に「隠語なそなその躰」とあるが「蘭」の字は草冠に門、門の中に東だが少し工夫があって「西かはのむかひ」となる。そこに蘭の花が咲いているのだ。二首目の題は「雁」。初句の「越路」は北海道の古称。V字形や横一列に編隊を組んだ雁を西風すなわち秋風が「よこぎれ」にしているという。スケールが大きい。三首目の題は「露」。風に払われたのは草の葉であるが、それを「草のは武者」と擬人化して結句の「一てき(一滴・一敵)」につなげた。草の葉武者は木の葉武者の応用だろう。四首目の題は「月」。十五夜の満月に対して十六夜(「いさよひ」)の月は少し出が遅い。「いさよひ」は動詞「いさよふ」の連用形、ためらいながら灯を背けたのか、月の満ち欠けを灯油の量になぞらえている。
|
| 第44回 堀川百首題狂歌合(2) |
さもふかきよくあかつきの寝覚(め)にはそのこととなくおこる煩悩 池田正式(『堀川百首題狂歌合』)
『堀川百首題狂歌合』を続ける。掲出歌の題は「暁」。一首は二句の「よく(欲)」で切れる。以下、結句に至る「煩悩」とは何か。男には親しい「朝立ち」である。四句「そのこととなく」つまり性欲とは無関係に勃起する。だから「さもふかきよく」なのだ。判に曰く「十七八廿はかりのころは誰もさこそ侍らめ」。性ではなく生、健康のバロメーターである。
山畑にむさくさすたくむしくしはほりにしいもの跡にや有らん
ちかつけははちのあたるとゆふたすきかけもかまはぬ神無月哉
時雨さへいそかしふりに成(り)ぬれはまして木の葉の尻もたまらす
夜もすから板やの軒をはらはらとうつはあられのふりつつみ哉
一首目の題は「虫」。「むさくさ」は「むちゃくちゃ」あるいは「むしゃくしゃ」、秩序のなさと気分の晴れない、両意を含むだろう。「すたく」は集まって鳴く。「むしくし」は「むさくさ」、意味としては「むしゃくしゃ」で「虫」を出す。一方、別意「むしくし」の「あばた」で結句の「跡」を呼び出す仕掛けである。「むさくさ」「むしくし」のリフレインが心地よい。二首目の題は「初冬」。「はち」は「罰」。「ゆふたすき」は「木綿襷」で「ゆふ(言ふ)」を掛け、枕詞としては「かけ」にかかる。しかし、この「かけ」が賭け事の「賭」で神は出雲大社に出張して不在の「神無月」(十月)、何もかもが許されているのだ。三首目の題は「時雨」。雨風の変化を「降り」に「振り」(風)を掛けて「いそかしふり(忙し振り)」と捉えることによって結句、「木の葉」も尻を上げる、踊り出したのであった。四首目の題は「霰」。三句は半濁音で「ぱらぱらと」、結句の「降り」は「振り」、「ふりつつみ(振鼓)」は舞楽で使用、玩具ならでんでん太鼓となる。オノマトペの妙は「板や(板屋)」から想像できる。
へんは二水作りは水とかく氷春にもならはとけて三水
たひねして思(ひ)出(づ)れば古郷の子もちむしろにしく物そなき
すかみこのおもてをみてもうらみてもかはらぬ君か心こはさよ
一首目の題は「水」。「へん(偏)」は「二水(冫)」とあるから三句の「氷」は視覚的には「冰」だろう。結句の「三水(?)」は「水」の部首に属する。文字遊びは溶けて二から三になった。二首目の題は「旅恋」の左。四句の「子もちむしろ」は母親が子供と添い寝するときに用いる幅広い寝具、転じて「所帯じみた」で修飾される妻。怪しいのは二句だ。どこかで学習したのであろう。右に(はたこやに宿かりてねし一夜妻したたか銭をおきそわかるる)とある。三首目の題は「恨」。初句の「すかみこ(素紙子)」は安価な紙子。紙子は紙で仕立てた衣服。題は三句に隠されている。すなわち「裏見ても(恨みても)」。結句の「こはさ(強さ)」は思い通りにならない、ごわごわしている、の両意で「寄紙子恋」となっている。
|
| 第45回 堀川百首題狂歌合(3) |
観音の堂に打(ち)ふるらく書(き)をかたみに残す諸国順礼 池田正式
掲出歌の題は「旅」。三句「打ちふる」は「打ち振る」であり、また「打ち古る」だろう。「古る」は上二段活用だから連体形は「古るる」、「古る」は終止形だから二句切れとなる。それを承知で「打ち古る(る)」を加えたい。〈かきおくもかたみとなれや筆のあとわれはいづくの土となるとも〉。前田卓は『西国順礼と四国遍路の今昔』(懐徳堂友の会編『道と順礼―心を旅するひとびと―』)で「土佐一の宮」(第三十番札所善楽寺は一の宮の別当寺)の壁に書かれた元亀二(一五七一)年の落書きを紹介する。しかし論文は柱や天井に納札を打ち付けるという宗教的慣行が中心である。四句の「かたみ」は「形見」に「互」を掛ける。また「かたみ」と「打ち振る」は納札を打ち付ける行為を思わせてダブルイメージである。
あとさきへいきや出(す)らんしつのめかしりをほつたてふく火ふき竹
大雪に往来をふさく信濃路は是そ日本のかんこくの関
誰となく送る野原の無常堂たつる煙や火さう三昧
ねかはくはことかかぬ程せにもちてめ子ひきつれて世をのかれはや
先(づ)以(て)御機嫌のよき君か代をおほそれなからいはふめてたさ
一首目の題は「竹」。三句の「しつのめ」は「賤の女」、四句は「尻を帆立て」、竈で四つん這いになって尻を上げている姿、すなわち帆立尻だが手は火吹き竹を握っている。「あとさき」の「あと」は放屁である。二首目の題は「関」。二句はの「ふさく」は「塞ぐ」、結句「かんこく」は函谷関の「函谷」に「寒国」を掛ける。函谷関は中国河南省にあった関所、交通の要地であった。三首目の題は「無常」。野原の一軒家「無常堂」では修行三昧の生活を送る人がいる。そう思わせるのは四句の「たつる煙」が『新古今和歌集』の〈高き屋に登りて見れば煙立つ民のかまどはにぎはひにけり〉(七〇七)にもある「竈」を連想させること、また結句の「三昧」によろう。しかし実体は火葬場というわけだ。四首目の題は「述懐」。「せに」は「銭」、「め子」は「妻子」、「のかれはや(逃ればや)」の「ばや」は願望の終助詞。西行の〈ねがはくは花のしたにて春しなんそのきさらぎのもちづきのころ〉(『山家集』)とは対照的である。五首目の題は「祝」(左)。初句の「先(づ)以(て)」が、この作品の全てである。右は〈金銀はつむ石くらのことくにていやかうへにもおさまれる御代〉。これをもって『堀川百首題狂歌合』も「千秋万歳万々歳と祝ひ祈り奉り畢(をはんぬ)」(判)となる。
飛(ぶ)螢みな火おとしの鎧きて宇治の網代にかかりけるかな
『堀川百首題狂歌合』には二系統の本文がある。右はその別系統の『堀川狂歌集』所収の「螢」の歌二首の左である。「火おとし(威)」は緋色に染めた革や組紐などで威した鎧を云う。網代は網の代わりの意、竹を並べて川の瀬に仕掛けた。有名な宇治の螢合戦である。
|
| 第46回 堀川狂歌集 |
七草にままことをするわらはへの髪さきみるもつめる簪 如竹(『堀川狂歌集』)
『狂歌大観』の「解題」によると『堀川狂歌集』は『雄長老狂歌百首』『道増誹諧百首』『貞徳百首狂歌』『了忠狂歌百首』『如竹狂歌百首』『猶影狂歌百首』『堀川百首題狂歌合』の七作品を集成したものである。このうち本篇は『狂歌大観』に既出の四作(『雄長老狂歌百首』『道増誹諧百首』『貞徳百首狂歌』『堀川百首題狂歌合』)を除く三作(『了忠狂歌百首』『如竹狂歌百首』『猶影狂歌百首』)を収録する、とある。刊記は寛文十一(一六七一)年。掲出歌の題は「若菜」。ママゴトの場面だか、その「わらはへ(童部)」の「髪さき」を見ると「摘める(若菜の)簪」であった、という。「髪さき」は「髪先(髪前)」と思われるが少し気になる。おそらく「髪挿し」の意を加えたかったのだろう。「髪挿し」転じて「簪」なのだ。
春の雨ねりかへしたる大道は色もにたにた地黄煎かな
とんつはねつおもしろさうにみゆる哉(かな)囀る比(ころ)のひはりけの駒
ほちほちとふる五月雨に軒口もはなしの口もくちはてにけり
一首目の題は「春雨」。作者は猶影。地黄はゴマノハグサ科の多年草、その根を煎じたものが「地黄煎」。「大道」は「おおみち」もしくは「だいどう」、和歌なら前者だが狂歌である。また大道易者、大道芸、大道商人いずれも後者となる。その大道筋を行くのは人ばかりではない。犬猫牛馬そしてその落とし物、草鞋をはいて足を踏み入れるのは大変だ。二首目の題は「春駒」、作者は猶影。初句「とんつ」は「飛ぶ」の連用形に完了の助動詞「つ」の「飛びつ」の撥音便、説明すればそうなのだろうが「はねつ」とセットでオノマトペとしての効果が大きい。結句「ひはりけ」は「雲雀毛」で馬の毛色、一首は馬に雲雀のイメージを重ねている。三首目の題は「五月雨」、作者は如竹。初句「ほちほち」は半濁音「ぽちぽち」。以下、ふたつの「口」を先行させて「くち(朽ち・口)はてにけり」と巧者な手口である。
年よりてまつ一はちる口にこそすかすかあきのはつかせは立(つ)
一葉の舟に帆かけて秋や来る今朝ふき出すは追(っ)手成(なる)らん
幾秋の霧にしやれたる堂塔の板も柱も目にそ立(ち)ける
一首目の題は「立秋」、作者は如竹。二句は「まづ一歯(葉)散る」、入れ歯を外したときのおちょぼ口が思われる、人生の秋だ。次も同題で作者は猶影。ちなみにこの二人に了忠を加えて共に伝記不明である。水路を一枚の葉っぱが流れていったのは数日前だった。「あっ、秋」と思ったものだが、それもつかの間の散りようではないか。「追(っ)手」という見立てが生きている。三首目の題は「霧」、作者は如竹。二句の「しやれたる」は「しゃる(曝る)」の連用形に完了の助動詞「たり」の連体形であるが、これに「洒落る」がオーバーラップしているだろう。華麗な堂塔と湿気にさらされた堂塔、意味は異なるが共に目立つのだ。
|
| 第47回 堀川狂歌集(2) |
柴漬(け)のあたりえさらぬあやうさよ鴨やさきたつ魚や先たつ 如竹(『堀川狂歌集』)
掲出歌の題は「水鳥」。「柴漬(け)」は冬、川や湖に柴の束を沈めて、集まってくる魚を捕らえるもの。二句の「え」は副詞の「え」、まったく去る気配がない。これに「餌(え)」を掛ける。四句と五句は対句表現で「や」は疑問の係り助詞、緊迫した場面である。たとえ魚が鴨の難から逃れたとしても柴漬けに入ると万事休す、すでに人の手中にあるも同然だ。
さしも草ひねり針なといふ声に野原の虫の啼(き)よはる哉
日をかそふ命みしかき筆つ虫あはれしこくとゆふくれの声
垣壁に取(り)つく虫の哀(れ)さよ如何に死にたうもなく声のして
右の三首とも題は「虫」。一首目の作者は安井了忠。「さしも草」はヨモギで艾の材料、「ひねり針」は鍼術用語、物騒な言葉の連続に虫も大人しくなってしまったのである。結句「よはる」は「弱る」と解した。二首目の作者は如竹。三句の「筆つ虫」はコオロギの異名、その「筆」の縁で「しこく」は筆を扱く、コオロギを痛めつける、の両意となる。結句の「ゆふ(夕)」は「言ふ」を掛ける。初句切れ、意味的には連体形だろう。三首目の作者は猶影。初句の「垣壁」は土塀、四句の「死にたうも」は「死にたくも」のウ音便、結句の「なく」は「無く」と「鳴く」が交差する句またがりである。二句の「取(り)つく」が響く。
長月といはは今宵をのへよかし秋のかきりのへんかいをして
氷(り)ゐし石鉢の柄杓引(き)折(り)て手水えつかひかたき事かな
一つれにはれたちするか水かかみ見てとりとりのけはひつくろふ
ちはやふる神楽の鈴も舞殿も物さひたるはかたのことこと
祢宜神子かかくらの役を仕舞(ひ)ては皆我(が)宿へかへり申しす
一首目の題は「九月尽」。作者は了忠。三句は「延べよかし」で「かし」は終助詞。「かきり」は「限り」で終わり、「へんかい」は「変改」、長月と云うなら変え改めよ、というわけだ。二首目の題は「氷」。作者は猶影。「引き折る」はたわむほど強く引くこと。三句の「え」は副詞の「え」に柄杓の「柄」を掛けた。三首目の題は「水鳥」。作者は了忠。初句は「一つら(連)」とあるべきところに「つれ(連れ)」(一緒に行動すること)の意を加えて「はれたち(晴れ立ち)」とした。四句「とりとり」は「鳥々」に「取り取り」を重ねた。次は「神楽」の題が並ぶ。四首目の作者は如竹。初句「振る」に「古る」を掛け、物寂れた様子を結句「型の如」(型通り)に「ありのことごと」(ある限り)を通わせてオノマトペ「ごとごと」で表した。五首目の作者は猶影。初句「祢宜」は神職、「神子」(巫女)は神職を補佐する女性。結句は「返り申し」という名詞にサ変の動詞「す」。神楽が終わったので祢宜も巫女も引き上げた。そう答えているのは人ならぬ神であろうか(「返り申し」には願解きの意がある)。
|
| 第48回 堀川狂歌集(3) |
風よりもそつとすこきはふうふうと吹(い)てかかれるのへののらねこ 如竹(『堀川狂歌集』)
『堀川狂歌集』の続き。掲出歌の題は「野」。二句は「ぞっとすごきは」、四句の「吹て」は「吹きて」と「吹いて」が考えられるが二句の「き」と競合したくない。筆者はイ音便を採る。結句は「野辺の野良猫」。一首は平仮名表記を主体にカ行音で始まり、サ行音でアクセントを付け、ハ行音からナ行音に展開する。総じて視覚から受ける印象は柔らかい。しかし現実は本能も露わに威嚇する猫と猫、あるいは他の小動物か、荒涼とした自然界なのだ。
泳きえぬ稽古を見れは瓢箪の浮(き)つ沈(み)つはらのかは哉
いつ甑しかくることのなきままに竈は苔をむしにける哉
手のものと頸ふりかたけ鶴の箸野沢の水にくはゐほる也
野は七野七ついろはのうちに有(り)つえつきていさ遊(び)に行(か)ん
一首目の題は「河」、作者は如竹。金槌が練習する様を水に浮く瓢箪に見立てた。「はらのかは」は「腹の皮が捩れる」の略で、その格好が「おかしくてたまらない」のだ。「皮」と「河」で題を消化した。二首目の題は「苔」、作者は猶影。甑は米や豆を蒸す器具、後に蒸籠に取って代わられた。一首では炊煙の上がらない竈が歌われる。結句の「むし」は「生し」、ここで甑の「蒸し」を掛けている。三首目の題は「鶴」。作者は如竹。初句は「お手の物と」に同じ、二句は首を「振り、傾げ」だろう。三句の「箸」は「嘴」と同音、初句に出した「手」の縁である。「くはゐ」は慈姑、鶴は雑食なのだ。四首目の題は「野」、作者は了忠。二句の「七ついろは」は七文字で分かち書きした伊呂波歌、最後の文字を拾うと「とかなくてしす」になる。三句の「うちに有(り)」とは「ゑひもせす」の末尾に加える「京」を指す。したがって初句「七野」とは紫野、上野、蓮台野、内野、平野、北野、神明野が正解である。
朝な夕な窓の戸障子をのれさへたかひちかひに立(ち)そわかるる
とありしと我(が)身の昔いひしらへいけんこく社(こそ)いけんくさけれ
心もて心おとろくしめし哉(かな)尿のしたさの尿たるる夢
一首目の題は「別」、作者は如竹。初句の「朝な夕な」は朝晩、二句の「戸障子」は雨戸と障子のこと、朝が来て開かれ、夜が来て閉じられる。「をのれ」とは戸障子そのもの、戸障子でさえそうなのだから人の場合はまして、という展開である。二首目の題は「懐旧」、作者は猶影。初句、昔のことを長々と嫌がられながら喋る、その話を助詞「と」一語で受け止めて省略、切って捨てた。三句は「言ひ、調べ」と解した。「調ぶ」は図に乗ることを云う。三首目の題は「夢」。作者は如竹。三句の「しめし」は名詞の「湿し」で濡らすこと、また襁褓を云う。初二句からして前者だろう。四五句の「尿」は「しと」、上からだと「しめし」「しと」「したさ」「しとたるる」、夢の中で催した尿意が正夢であったことを知らされるのだ。
|
| 第49回 後撰夷曲集 |
年徳の神のししやにて春きぬと世にふれなすか鶯の声 八宮御方(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の編者は生白庵行風。先の『古今夷曲集』、後に取り上げる『銀葉夷曲集』の編者でもある。それぞれ『古今和歌集』『後撰和歌集』『金葉和歌集』を念頭に置いた命名である。生没年不明。大阪高津の富裕な町人であったらしい。刊記は寛文十二(一六七二)年、十巻一六九四首、これに巻末の「夷歌式目録」を含めると総数一七二三首、大冊である。うち巻第一春歌は二一九首。掲出歌は巻頭歌で題詞は「春たつ日よめる」。作者の「八宮御方」は「作者之目録」によると「知恩院御門跡八宮」、後陽成天皇の第八皇子である。「年徳の神」は年徳神また歳徳神、この神のいる方向を恵方、その年をつかさどる神として春の定番のように歌われている。「ししや」は「使者」、新年をことほぐ歌として素直に響いてくる。
一番の風の手なみに霜氷川しもさして雑乱(さら、以下同じ)雑乱雑乱雑乱
梅こよみ三百六十余ヶ日も子の日とひよりさく年の花
めてたしなめてたしとこたふ挨拶はたれもあふむの鳥の正月
一首目の題は「立春風」、作者は行風。二句「風の手」、安田純生は「風の手」の古い用例として『誹諧古撰』(一七六三年)と『新明題和歌集』(一七一〇年)を上げている(『歌ことば事情』)、しかしこれからすると初出は狂歌かも知れない。注目は結句、川の流れを視覚的に捉えた漢字表記と聴覚で捉えたルビの組み合わせに驚かされる。二首目の題詞は「元日子の日なりけれは」、作者は行風。初句「梅こよみ」は花の咲くのを見て春を知る、そこから梅の花を云う。二句と三句は「暦」を効かして句またがりの「三百六十余ヶ日」、四句の「ひ」は「一」、元日で、しかも「子」は十二支の最初である。三首目の題は「酉年元日に」、作者は次木。初句「な」は感動と詠嘆の終助詞、二三句の「て」は「で」、四句の「あふむ」は「鸚鵡」。三句の「こたふ」は下二段の終止形、連体形で「こたふる」としたいところだ。
虎の尾の花の盛(り)はつりかねの龍頭のをこす雲かとそみる
春の月弓張(り)にかへるかりまたは北斗の星やめあてなるらん
やり水につきなかされて苗代へ迯(のがれ)てかへるまけ軍(いくさ)哉
一首目は題詞「大坂東本願寺の鐘楼に立(ち)そへる虎の尾桜の花さかり世にこえて見事なりけれは」、作者は貞因。龍頭は釣鐘を梁につけるためのつり手、龍の頭部の形をしているのである。二首目の題は「帰鴈」、作者は満永。二句の「弓張(り)」は弓張り月の略、また雁の編隊を指し、弓を張る意ともなる。三句の「かりまた(雁股)」は先が股の形に開いた鏃、ここにも雁がいる。一首目が幻想美なら二首目は様式美である。三首目の題は「蛙」、作者は貞富。初句「やり水」は苗代水を導く流れ、三句「苗代」は「苗代田」、四句「かへる」は「帰る」に「蛙」、「やり(槍)」「つき(突き)」の同音を効かせて蛙の雑兵物語を編んだ。
|
| 第50回 後撰夷曲集(2) |
水鏡見つつ植(う)れは嫁御前のけはひ田とは此(の)事やらん 是誰(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第二夏歌は一一六首。掲出歌の題は「早苗」。初句の「水鏡」は水面に姿が映ること、また映して見ること。四句の「けはひ田」は「化粧田(けわいでん)」、上級の武士の娘が嫁入りする際に持参する田地、田植えの女性とは無縁だから「此(の)事やらん」となる。同じ題で友和に〈早苗とる早乙女につく物はたた脛(はぎ)の白きと脚布の白きと〉がある。田仕事に従事する女性にとって誇れるのは何か。ただ「脛の白き」と「脚布(きゃふ)の白き」(「脚布」は腰巻き)というのである。健康な若さが艶めかしい。
とつと空にかすかな声は里の名のなませにつらさますほとときす
不思議やな風にまたたく灯のきえぬと思へは螢にて候
しうとめにふすへられぬる夏の夜は紙帳のすみてほゆるよめかも
一首目は題詞に「なませのわたりにて」、作者は友信。「なませ」は濁って「生瀬」、有馬街道に沿う旧宿場町。「わたり」は「辺り」でなく「渡り」なら太多田川か武庫川となる。初句「とつと」は距離の離れているさま、幼児語で魚や鳥などを云う。四句の「なまぜ」は「なまじ」の変化した語、なまじ時鳥と生まれた鳥の「つらさ」と解しておく。二首目は「百首歌の中に」、作者は貞徳。既出の「候」歌の典型、安田純生の「現代短歌は、歌人が意図しているか否かにかかわらず、用語の面で江戸時代の狂歌を継承しているということである」(『現代短歌用語考』)という一節が思われる。三首目も「百首歌の中に」、作者は貞徳。「ふすべる」は煙がたくさん出るように燃やす意で紙帳(紙で作った蚊帳)の縁語、嫉妬する意で初句「姑」の登場となる。結句「嫁」の「ほゆる」も凄いが、しかし「紙帳のすみ」が悲しい。
撫子の花の口ひるうこくこそ風の手あててあははなりけれ
池水のかはき果(て)ぬる日てりには自然とほせる亀の甲かな
汗水の胸をくたりになかるれは腹のかはこそ淵となりなめ
一首目の題は「瞿麦(なでしこ)」、作者は且保。「撫子」は「撫でし子」からの擬人化なのだろう。結句「あはは(あわわ)」は子供をあやすときの所作、ここでも「風の手」なので前回の補足をしておこう。安田純生が『歌ことば事情』の中で「風の手」を持ち出したのは山崎美成(一七九六~一八五六)が『世事百談(一八四三)』の中で「かつてものに見えず」としていることへの反証であった。そしてこの文章のタイトルは「風のてのひら」つまり俵万智の歌集名につながっていくのである。二首目の題は「炎天」、作者は行風。四句の「自然と」がキーワードだろう。副詞で「おのずと」の意。このまま雨が降らなければ変温動物の亀にとっては死あるのみ、残酷な甲羅干しなのだ。三首目の題は「汗」、作者は成栄。四句の「かは」は「皮」と「川」、あとの「川」から「淵」となる。結句は「こそ」の係り結びである。
|
| 第51回 後撰夷曲集(3) |
見一の声もそのこる暑さにはをくにをかれす扇ひらひら 勝方(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第三秋歌は一五五首。掲出歌の題は「残暑」。初句の「見一」は珠算で二桁以上の割り算。二句の「声」は「割り声」、割り算をするときに唱える九九。割り算だから余る(「のこる」)は付きもの。四句の「をく(置く)」は計算すること、すべて縁語仕立てとなる。二句の「そ」は「ぞ」。読み書き算盤の算盤が消えた今日では分かりづらい歌だ。
草村に露のちらちらちりぬるは風の手玉をとるかともみゆ
なふこさせ薄かまねく又しやもあのさまの袖は露にぬれつつ
心なき草にも位たかの羽の薄の下にかかむ犬蓼
秋の野にさくらんくわつと匂ふらん見るらんむさと手折(り)とるらん
一首目の題は「叢露」、作者は行重。やはり「風の手」のバリエーションである。見えない風がお手玉をしているという見立てが美しい。二首目の題は「下女詞にて」、作者は「よみ人しらす」。このほかにも多くの詞を採集しているのが『後撰夷曲集』の特色である。初句「なふ」は感動詞「なう」。「こさせ」は「御座せ」(「来る」の意の尊敬語「御座す」の命令形)、三句の「しや」は「汝」(このあと「こさせ」相当句が省略)。「あのさま」は「彼様」で離れた人を指す。結句も「薄の中に入っていく」等の言い止しであろう。順次、主人・同僚・他人と思われる。三首目の題は「鷹羽薄」、作者は一見。鷹羽薄とは葉の横に白い斑の入った品種である。三句「たか(鷹)」に「高」を掛ける。結句「犬蓼」(別名「赤まんま」)が屈む所以となる。四首目は題詞「紫蘭の紫を四文字にとりなしてらんといふてにをは四つよみ侍(り)ける」、作者は友知。「むらさき」は「きさらむ」の順だが「ら」は手抜きの感である。
槿をさなから瑠璃のつほつほと思ふわらへはあさはなたもの
爰てなけとつこへそつこへやるまいそなんた弁慶むさしのの虫
鳥の名の鷲のお山の阿羅漢もうへ見たまはん秋の夜の月
一首目の題は「百首歌の中に槿」(「槿」は「朝顔」)、作者は安勝。三句「つほつほ」(壺壺)は底が平たく、中ほどが膨れ、口の狭い土器。朝顔の蕾の比喩である。四句「わらへは」は「童は」で結句「浅縹物」(初位の人)。「笑へば」(蕾が開く)だと結句「浅縹」(薄い藍色)に「物」(名詞について複合語)で朝顔の数と読む。二首目の題詞は「虫を奴子詞にてよめる」、作者は「よみ人しらす」。初句は「ここで鳴け」、二句は「どこ」「そこ」に促音が割り込んだものと解した。「そ」は「ぞ」。「なんた」は「なんだ」で文句があるか、といった口吻か。武蔵坊弁慶、今は「武蔵野の虫」となる。三首目、題なし。作者は舎永。二句の「鷲のお山」は霊鷲山、三句「阿羅漢」は仏。諺に「上見ぬ鷲」があるが、その上見ぬ鷲の山に住む阿羅漢でさえ四句「うへ見たまはん」となる。そんな美しい結句「秋の夜の月」なのである。
|
| 第52回 後撰夷曲集(4) |
詠(む)れはねふけもささすすむ月の兎の耳の長(き)夜なれと 資之(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第三秋歌の続き。掲出歌の題は「月」。一首目が方寸作、「踊歌詞」て〈あくる迄脇目もふらし照(る)月の桂男にまねかるるとも〉とある。一首挟んで資之、初句は「ながむれば」と読む。二句「ねふけ」は「ねぶけ」、「ささす」は「ささず」。三句と四句は月に兎の定番を踏みつつ結句の「長」を呼び出す序詞としての役割も担っている。また音訓ともに「長夜」では一音不足するため「き」を補った。月は今以上に輝いている。
しやこめなふ三五夜中の月すめはこんこんるりの世界とそなる
公家も武家も今夜の月は町人もあれ出て見さいこれ出て見さい
あつた物てないとや人のほめそやす月は世界の真中の秋
所からかはらけなりに出る月の影をうつしてきた嵯峨の川
海中へさしいる月の舟にそひて折からあくるほたて貝かな
一首目。題「八月十五夜」の二首目。作者は「ていとく」。「しやこ」はシャコガイの貝殻、「めなふ」は「瑪瑙」、「三五」は「珊瑚」、かつ掛け算だと「十五」。「こんこんるり」は「金銀瑠璃」、以上の六宝に十五夜の月が加わると七宝で荘厳された世界となる。二首目は同題四首目。作者は卜養。「見さい」は連語、「さい」は助動詞「さる」の命令形「され」の音変化、意味は「見なさい」。三首目は題詞「見事なることをあつた物てない世界の真中といへる世話にてよめる」、作者は次良。「世話」(世間の言い草)が多く登場するのも『後撰夷曲集』の特色である。四首目の題は「河月」、作者は独友。初句は河に加えて「源順馬名歌合」に拠る。作者の順(九一一~九八五)は嵯峨源氏であった。二句「かはらけ(川原毛)」は馬の毛色で黄白色を云う。五首目の題は「月前貝」、作者は「みつなか」。句またがり「月の舟」で月、ここでは月光を云う。結句「ほたて貝」は「帆立貝」、舟に揚げられていく景でもある。
けみもゆるせ神田の台の百姓の与吉か女房うへし早苗は
手にとれは人をさすてふいかくりのえみの内なる刀おそろし
ならの京の時分からこそ出来つらめ今に大和の御所柿といふ
一首目は題詞に「百首歌の中に秋田」、作者は貞富。初句「けみ」は「検見」で米の収穫前に役人が稲のできを調べ、その年の年貢高を決めること。「獅子踊詞」とあるので踊りと伴奏にこうした詞も入ったのだろうか。二首目は題詞に「家集五十首の中に」、作者は権僧正公朝。成句として「笑中に刀あり」がある。四句の「えみ(笑み)」は果実が熟して開くこと、「えみの内なる」は笑みを湛えながら、といった風情。結句「刀」は「毬」である。三首目の題は「柿」、作者は相宥。初句の「京」は「みやこ」と読む。したがって初句は七音。一首は尤もらしい、しかしおそらくは偽由来説。それに加担し、広めたとおぼしき作者である。
|
| 第53回 後撰夷曲集(5) |
神々の旅立(ち)たまふ道筋をきよめにふつてきた時雨かな 満永(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第四冬歌は一〇七首。掲出歌の題は「初冬時雨」。すなわち陰暦の十月、神々は出雲大社に集まって神無月、これを背景とする。文語の文脈に口語が、しかも句またがりで割り込んでくる。小高賢は『現代短歌作法』で「文語定型がいわゆる短歌のスタンダードであることはいうまでもないが、近年、口語調、あるいは文語口語の混交した作品が多くなった」と書く。しかし近代以前の五七五七七を視野に入れるならば口語体や、その混交現象は言文二途以来で珍しくもないのである。その言文が二途に分かれるのは『日本語の歴史4移りゆく古代語』(平凡社)によると『徒然草』(一三三〇年頃)の時代である。
あふのきてみれとも見えぬいたたきはかつく頭巾の山にそ有ける
ぬれしとていそけと雲の足はやに走りこくらをする人時雨
さむさをもいとはて庭にちり遊ふわらへも風の木の葉なりけり
難波人かれたる芦のかるわさは鎌宝蔵院そもえなるまい
一首目の題は「頭巾」(頭部を覆う布製袋状のかぶり物)、作者は一圃。石田未得の〈あふのけにころばぬほどは冨士も見つそれよりうへはいさやしら雲〉(『吾吟我集』)を念頭に置いた作であろう。二首目の題は「時雨」、作者は一見。雲と人の「走りこくら」(「こくら」は接尾語で競争する意)を歌う。結句の「人時雨」は原因の時雨を出し、かつ蝉時雨や虫時雨に倣い、一斉に走り出す人を描いた。三首目は題詞に「庭にわらはへの集(ま)りてまさなことするを見て」、作者名なし。その前の相宥と思われるが『索引篇』の「人名索引」は慎重で除外している。題詞の「まさなこと」は「正無事」でたわいないこと。三句が結句の布石となっている。四首目は題詞に「百首歌の中に寒芦」、作者は貞富。三句は「刈る技」、四句は槍術の一派、鎌宝蔵院流。結句「そも」は接続詞で一体全体、「え」は下に否定の表現を伴って不可能の意を表す。歌意は「あの使い手は鎌宝蔵院流か、いやそれはないだろう」。
千年をへたる氷にあらねともふみわりぬれははりはりとなる
湊出(づ)るかこの友舟ゆすれともひはれもやらぬ朝氷かな
きるやうな寒風は物すころくのたうもかひなもふるふはかりそ
一首目の題は「氷」、作者は宣就。四句「踏み割りぬれば」、また結句の「なる」は「鳴る」。オノマトペの「はりはり」は上句から推して「ぱ」ではなく「ば」と読む。二首目の題は「今宮御会氷礙舟」、作者は源頼政の父、仲正である。「かこ」は「水夫」。「友舟」は一緒に出て行く舟。「ひはれ」は「氷割れ」と解した。びくともしないのだ。三首目の題は「冬風」、作者は高故。「物すころく」は「双六」に「凄く」を掛けるが接頭語「物」が句またがりで強調されている、「たう」(どう)は骰子を入れて振る筒、「かひな」はそれを持つ腕である。
|
| 第54回 後撰夷曲集(6) |
破れ橋年ふりつもるゆきけたをはいて渡るはあふなかりけり 太極(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第四冬歌の続き。掲出歌の題は「橋雪」。キーワードは三句の「ゆきけた」で、上から来て「行き桁」(橋の架けられた方向に沿って渡してある桁)、下へ向かっては「雪下駄」と、ここでポイントが切り替わるのである。結句は「危なかりけり」。七音ということもあるが「危なかり」でないところは見ておきたい。安田純生が『現代短歌のことば』で「文語では、『多し』『なし』を除いて終止形のカリは認められないのである」「『悲しかり』も『在らざり』も、近代の文語体短歌における非文語的な要素を示している」(「悲しかり・あらざり」)と書く、あの「かり」である。まだここには健やかなカリ活用が生きている。
北東風にけゐの床迄とをりつる小雪はみすのふるふなりけり
炭やくにひまもなうしてはたらくは身のくらうなる仕事なりけり
山々にわれをとらしと賤の男かすみかまんをも立(つ)る煙よ
一首目の題は「家集中に」、作者は源仲正。初句「北東風」は「きたごち」、二句「けゐ」は「褻居」で居間、三句は「透(とほ)りつる」だろう。御簾で篩に掛けられた雪が床を濡らすのである。二首目の題は「炭竃」、作者は「みつなか」。四句の「くらう」は「苦労」と「黒う」(仮名遣いからいけば「暗う」だが)を掛ける。三つの「く」がアクセントになるとともに上下のウ音便がシンメトリーの装いである。三首目の題も「炭竃」、作者は宣就。二句は「われ劣らじと」、四句「すみかまん」は「住み我慢」に題の「炭竃」を掛ける。結句は送り仮名の「つ」を補った。但し、文語と口語の混交なら「て」の可能性も捨てきれない。
たはこのむ友と頼(み)て冬の夜は灰をきせるの埋(み)火のもと
釜の下に住(み)つけたりし灰猫の目か光るかとみれは埋(み)火
冬されはさむくつめたき老か身の夜床の伽にをこし炭かな
をそろしき名には相違や節分のまめにをそれてにくる鬼みそ
一首目から三首目までの題は「埋(み)火」、炉や火鉢などの灰に埋めた炭火である。一首目の作者は友和。四句「きせる」は灰を「着せる」と刻みたばこを吸う道具の「キセル」を掛ける。その「埋(み)火」が「友」なのだ。二首目の作者は貞富。二句「住(み)つけたりし」の変な御丁寧さは煤すなわち「墨つけたりし」の要請だろう。灰猫は火を落としたかまどの中に入って暖をとり、灰だらけになった猫。三首目の作者は行重。初句「冬ざれ」は草木の枯れて荒涼とした冬の時分。四句「伽」は寝所での相手をすること。この場面では人ならぬ炭が「さむくつめたき老か身」を慰めてくれるので「おこす(熾す)」のである。四首目の題は「除夜」。作者は引誓上人。「世話」とあるのは結句「鬼みそ」で、外見は強そうで実際は気の弱い人、ここでは幼子を云う。当時は立春の前日が節分かつ大晦日であった。
|
| 第55回 後撰夷曲集(7) |
つてん天下めてたいことや申(す)へき打(ち)おさまるき世をいはひては 舎永(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第五賀に移る。作品は七二首。掲出歌に題はない。文語と口語の混用例その続篇である。一首は太鼓の擬音から始まっている。二句は「めでたきことや」でもいいところであるが、ここに「太鼓」を忍ばせる必要から「めでたい」と口語になった。四句は太鼓の縁語「まるき」で結句に着地するため「打(ち)おさまる」と二字を共有した。
君か代はなかい菖蒲を軒口にさしてかはらぬかれいめてたし
くらへ馬相手をとしていさめるはかつにのつたる禰宜の皃つき
雨乞(ひ)のいさめのための踊子は袖をつらねてふるの明神
すすしむる心をもつて我(が)家の子孫に悪事夏神楽哉
一首目の題は「夏祝」、端午の節句である。作者は景則。軒に菖蒲を挿して邪気を払う風習があった。これも文語と口語の混用である。二句「長い」は「長き」でもよかったが結句の「かれい(佳例)」の「い」に対応させたかった。二首目の題は「競馬」、作者は「みつなか」。二句「をとして」は「落として」、三句「いさめる」は「勇む」(はやり立つ)の已然形に完了の助動詞「り」の連体形「る」が接続、四句「かつにのつたる」は「勝つに乗つたる」、結句の得意気な「皃つき」が馬のようだ。三首目の題は「雨乞(ひ)」、作者は自喩。二句の「いさめ」は「いさむ(慰む)」の連用形の名詞化、結句の「ふる」は「振る」に「降る」を掛けた。奉納する踊りは神を慰めやわらげるのが目的だった。四首目の題は「夏神楽」、作者は長丸。初句は「清しむ」(祭事を行って神を慰める)の連体形、結句の「夏神楽」は夏越しの祓のときに行う神楽。四句以下が大胆である。「悪事」が降りかかってきませんように、を省略。「夏神楽」に重ねているのは掛詞ではなく大串を振る映像であり、その気配と解した。
国は三河里はふた川あはすれはいつかはのほりつかん古郷
みても美穂の景にはあかぬ心をは跡におきつつ旅はういもの
それかしもきてこそはみれ菅笠のなりをするかのふしのいたたき
『後撰夷曲集』の巻第六離別に移る。作品は九二首。一首目の題は「ふた川にて」、作者は遠江守一政。国の「三河」は現在の愛知県東部。里の「ふた川(二川)」は愛知県豊橋市東部の地名。もと東海道五十三次の宿駅。「三」と「二」を足すと「いつ(五)」で同音の「何時」にバトンタッチする。二首目の題は「興津にて」、作者は友信。「興津」は静岡市の地名。もと東海道の宿駅。「美穂」は「三保」とすると江戸へ下りの旅である。四句「おきつつ」に興津を隠す。結句の「ういもの」は「愛いもの」でポジティブに解した。三首目の題は「冨士の山を見て」、作者は前作と同じ友信。初句「それがし」は冨士と拮抗すべく、やや自意識を発露、菅笠に手をやるがその菅笠の形(なり)をする、を「するが(駿河)」に掛けた。
|
| 第56回 後撰夷曲集(8) |
短夜も独(り)はねうし寅の時うきたつ恋のみをしせかめは 次木(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第七恋歌である。作品は一九五首。掲出歌の題は「夜恋」。二句の「ねうし」は「子」と「丑」、時刻にすれば「子」が午後十一時から午前一時、「丑」が一時から三時となる。三句の「寅の時」は三時から五時、そうすると四句の「うきたつ」の「う」は「卯」で五時から七時、「たつ」は「辰」で七時から九時。最後が結句の「み(巳)」で九時から十一時、これが表の意味にかぶさる格好となる。「ねうし」は「寝憂し」あたりか、「み」は「身」、「し」は強意の副助詞、「せかめは(せがめば)」は責めれば、と解しておこう。
とりなりを見るとわしらかくせにしてつかみつく程君そ恋しき
ゆひきりや地獄の釜へほつたりとをちようといふは二世のけいやく
誓ひしもらつこの皮のかはりつつあちらこちらへなひく君哉
一首目は題詞「百首歌の中に」、作者は貞富。初句「とりなり(取り成り)」はなりふりのこと。しかし「とり」には「鳥」を、二句の「わし(儂)」にも「鷲」を掛ける。「くせ」は「癖」。四句の「つかみつく(掴みつく)」は「抱きつく」の鷲語である。二首目の題は「誓恋」、注記して「童口遊詞」とある。作者は安勝。三句「ほつたり」は「ぼたり」を強めた言い方。四句「をちよう」は「落ちよう」。「を」は「お」、歴史的仮名遣いは伝家の宝刀ではない。「よう」は動詞の未然形に接続する助動詞、ここでは勧誘ないし婉曲な命令となる。「けいやく」は「契約」。三首目の題は「変恋」、作者は政要。注記して「世話」とあるのは「らっこの皮」で、その手触りの良さから、たやすく従う三句以下のような人を喩えて云う。
?(もとゆひ)を結ふの神のちかひころとけて嬉しきわれとありさま
御園生のませの秋萩七たくりたくるにつけてをそき君哉
君か今夜をちたれはこそ恋死ぬる命を我はひらひけるなれ
君と我二世を契りてねたる夜はなむあみたふつむつことそいふ
一首目の題は「馴恋」、作者は安勝。三句は「近い」に「誓ひ」を掛けた(こうした例がまま見られる)。?を使って結ぶと解けるの対比が妙、結句「ありさま」は近世上方語で「おまえさん」そして有様を掛けた。二首目は題詞に「家集恋歌の中に」、作者は源俊頼。「園生」は庭園、「ませ」は垣、萩の花が咲いている。三句の「七」は、こうした場合の定番の数である。「手繰るに手繰り」それでも来ない「待恋」なのだ。三首目の題は「百首歌の中に」、作者名なし。これも落ちると拾うの対比が妙。貞富の〈梓弓引(く)手に筈をちかへしとやにわに君をいてをとしけり〉と対になっている。同人作だろう。四首目の題は「百首歌の中に」、作者は恵立。「二世」は現世と来生、来生から「南無阿弥陀仏」、「契りてねたる」で睦言だが、当然ながら声も低い。ぶつぶつ(仏仏)の「つ」と睦の「つ」の接続にも無理がない。
|
| 第57回 後撰夷曲集(9) |
忘れしのごわうのうらをみくまののうらみてかひもなちの権現 政長(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第七恋歌の続き。題詞に「百首歌の中に」。初句は「忘れじの」。二句の「ごわう」は「牛王」で「牛王宝印」の略。神社・寺から出す刷り物の守り札。「うら」は「裏」、裏面は起請文を書くのに用いた。三句「みくまの」は「三熊野」で熊野三山、烏を図案化した熊野牛王が有名だった。「み」の表の意味は「見」。四句は「怨みて甲斐も」、しかし「裏見て」や二句の「うら」から「浦」のリフレインも連想される。結句の「なち」は「那智」、「な」に表の意味の「無」を読む。誓い合った男女の愛も紙切れ一枚で反故となる。
上るりのふしふしとなる中々にさてもそののちあはぬ君哉
をのつから手枕はつしねなをれは我おもはすと妹むつけたり
人やみんさつと一筆くはしくは御目にかかり申(す)へく候
横笛はあなうらやまし吹(く)君の舌てなめられほほにいたかれ
一首目の題は「被忘恋」。注記して「浄瑠璃詞」とある。作者は一幸。四句の「さてもそののち」は浄瑠璃の決まり文句、近松門左衛門の辞世にも〈それぞ辞世去るほどに扨もそののちに残る桜が花しにほはば〉とある。但し『後撰夷曲集』の刊行は一六七二年、このとき近松は二十歳の青年だった。二首目は「題しらす」、作者も「よみ人しらす」。「つ」「つ」「す」には濁点を付す。結句は機嫌を損ねる、の意。羨ましい、そしてまた鬱陶しい愛の局面である。三首目も「題しらす」、作者は休甫。密会の歌だが、理屈を云えば二句「一筆」は何だったのか。「いつ」と「どこ」を走り書き、それに掲出歌を添えたと解しておこう。四句は字足らずである。四首目の題は「寄笛恋」、作者は久清。二句の「あな」は感動詞、また名詞の「穴」で「君」の指が立ちあがってくること濃厚である。倒錯した横恋慕が純情可憐に響く。
君と我つれふきにする尺八は是そ浮世の中のらくあみ
我恋はしやのしやの衣しやの衣赤きうらにて色に出来の坊
ほう杖をつくえの上にをのつから恋しく思ふ手習ひの君
一首目の題は「寄尺八恋」。作者は法橋由己、秀吉の御伽衆だった大村由己と思われる。二句の「つれふき」は「連れ吹き」、結句の「らくあみ」は「楽阿弥」で人名めかすが安楽に暮らすこと。二首目の題は「寄人形恋」、作者は保友。二句から三句のリフレインが心地よい。この「しや」は「其者」の略、芸者もしくは遊女。四句の「赤きうら」は玄人だから裾裏が赤い、と解く。結句は人形の意の「出来坊」を助詞「の」で分断。但し、読みは同じ意味の「木偶の坊」を採用、平兼盛の「色にいでにけり」(『拾遺集』六二二)の歌に呼応した。三首目の題は「寄机恋」、作者は知度。初句の「ほう杖」は「方杖」で垂直材と水平材とが交わる所に、補強のために入れる斜めの材。これを「頬杖」とも呼ぶ。寺子屋の恋である。
|
| 第58回 後撰夷曲集(10) |
稲舟のいなともいはす心よき出羽よ最上のかはゆらしやな 不得(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第七恋歌の続き。題詞に「出羽といふけいせいをよめる」。「けいせい」(傾城)は遊女、ここでは太夫や天神など上位の遊女と解した。初句「稲舟の」は同音の「いな(否)」を引き出す序詞、名前の出羽は旧国名でもあり、そこから「稲舟」と縁のある「最上(川)」(最も上にある意を重ねる)を出してきた。『古今和歌集』の〈最上川のぼればくだる稲舟のいなにはあらずこの月ばかり〉(「東歌」一〇九二)が参考になる。初二句で「い」を三度使い、三句以下はヤ行音を重ねて調子を整えている。結句、ぞっこんである。
夢になりとあはせてたへと君かぬる枕かみにやきせひかけまし
いくたひもあはて待(ち)そろはんことにいつはりにくの十八の君
石うすの思ひをかけてまはらぬは君を挽(き)木のおれかきのとく
妻戸をも妻かたたけは内よりもおつとこたへてあけていれぬる
一首目の題は「寄枕恋」、作者は「みつなか」。二句「たへ」は「賜べ」、三句「ぬる」は動詞「寝(ぬ)」の連体形。「枕かみ」は「枕紙」で木枕の上の小枕をおおう紙、これに夢に立つという「枕神」を掛ける。「きせひ」は「祈誓(きせい)」。二首目の題は「寄十露盤恋」、作者は瑞生。二句の「そろ」は「候」の音変化、三句は「晩ごとに」、二句から三句に「そろばん」が隠れる。結句「にく」は「憎」と「二九」。三首目の題は「寄石磨恋」、作者は知秋。二句「思ひ」に「重い」を掛ける。三句「君」は穀類、「挽き木」は臼を回すための肘形の柄を云う。「おれ」は「俺」で「きのとく」(気の毒)は困ってしまうこと。また「挽き」に気を「惹き」、「おれ」に「折れ」(折れること)の意が重なる。四首目は題詞に「ある家とうしのくれかかりて宿にかへり戸たたきけるを主みつから戸あけけるをみてよめる」とある。作者は満永。「とうし」(刀自)は主婦。四句「おつと」は感動詞と「夫」の両様である。
すい付(け)てくれしたはこはうかれめを恋の煙のたちそめにこそ
うかうかとちきりて捨(て)ん命こそをしかのつののつかの間男
ふしふしと成(り)にし事はお歯黒のかねかね深くりんきいふ故
一首目の題は「寄傀儡恋」、作者は休昌。「傀儡」は操り人形、恋の相手は傀儡回しの女たちが売春もしたところから遊女。その回想は女が吸い付けた煙管を手渡す場面から始まる。恋の煙は煙草の煙というわけだ。二首目の題は「密夫」、作者は是誰。四句は「男鹿の角の」で「つかの間」の「つか」の序詞、また「をし」に「惜し」を掛ける。また「つかの間」と「間男」で「間」を共有した。四首目の題は「悋気」、作者は行重。初句「節々」は形容動詞で夫婦の仲がしっくりしないこと、お歯黒の縁語の「五倍子」を掛けた。三句「かねかね」は濁点を打って以前から、お歯黒に使うのも「鉄奬」。二つの畳語をリズムに転化した。
|
| 第59回 後撰夷曲集(11) |
人は武士柱は檜魚は鯛きぬは紅梅花はみよしの 一休和尚(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第八雑上に移る。歌数は一三五首。掲出歌は「題しらす」。作者が気になる。第一流の人や物を数え上げて、花はみ吉野(の桜)で終わる。しかし一休和尚が「人は武士」などというだろうか。この歌は『狂歌大観』第二巻の『参考篇』が収録する『私可多咄』(一六五九年)では読人不知、同じく『難波鑑』(一六八〇年)では一休となっている。やはり読人不知とすべきだろう。むしろ仮託する人物を誤ったといってもよい。「人は武士」は『仮名手本忠臣蔵』(一七四八年初演)の「第十 発足の櫛笄(天河屋)」で「花は桜木。人は武士と申せども」(新潮日本古典集成『浄瑠璃集』)という詞となって登場する。
春毎(ごと)の県(あがた)のめしのうへにても菓子及第にしくはあらしな
摂待にたつるせんし茶ほうしてもほうしかたきは父母の恩
移徙(わたまし)はかねてのそめる家なれはすみよからふと思ひこそやれ
一首目は題詞「家職の得業によてかけまくもかしこき 詔ましまし御菓子所山城大掾藤原貞因になしたまふその悦(び)の俳諧一巻の奥によめる」。「得業」はある過程を終えること。「よて」は「よって」の促音「っ」の無表記。「ましまし」は動詞「在す」(「有り」の尊敬語)の連用形。作者は貞徳の高弟、安原貞室。貞因(貞柳の父)の俳諧の書に寄せた賀の歌である。二句「県のめし」は「県召」(「県召の除目」の略)、しかし三句以下が「飯のあとでも食べたくなる菓子を作る、そんな貞囚の技に及ぶものはない。さすがた」と聞こえる。二首目は「題しらす」、作者は成之。三句は「奉じても」、四句は「報じがたきは」、また茶の縁語として二句「煎じ茶」に対する「焙じ茶」の「焙じ」を両句に響かせている。三首目は題詞「移徙せし人のもとへ炭つかはすとて」、作者は行風。「移徙」は引っ越し。四句「すみよからふ」の「すみ」に「住み」と「炭」を掛ける。「ふ」は助動詞「む」の音変化「う」である。
村草の名ははれん哉千たひたひたちなかむれは花のさくらん
草の名はくさのこかねのすすのねのすすのねか此(の)さく花のさく
棟の外そこて地をみす猫なけな小鼠おぢてこそとのきなん
三首とも上から読んでも下から読んでも同じ「廻文歌」である。一首目の題は「草花」、作者は卜琴。初句「村草」は「叢草」だろう。三句の「千度々」が気になるが意味は通っている。結句「ん」は助動詞「む」の音変化。二首目は題詞「人の本より槿花に。草金鈴とかきてをくれる返事に」。作者は忠直。「槿花」は初句に「草の名」とあるので朝顔と解しておく。リフレインの「すすのね」(鈴の音)が聞こえるようだ。三首目の題は「猫をよめる」、作者は宣応。初句は「むなぎのと」と読ませる。二句から三句は「地を見ず猫鳴けな」、以下「所在が掴めないため不安になった小鼠は退却するに違いない」。情景がはっきりと見える。
|
| 第60回 後撰夷曲集(12) |
はたはたと関の戸ならぬ羽をたたきここあけうよと鳴(く)か庭鳥 松緑(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第九雑下である。歌数は三六三首。掲出歌の題は「暁鶏」。初句「はたはた」は鶏が羽ばたく擬態語であり、また擬音語である。それは四句の「ここあけうよ」のも同じ、目と耳に訴えて卓抜した技量を見せる。「あけうよ」は「夜が明ける」と「開けようよ」。「関の戸」(関所の門)の開門を待つ旅人にとって時告げ鳥は一日の始まりである。
養生の湯入(り)の心しつかなれやとつかはとしてあかり給ひそ
独(り)居はひつそりとして灯の影ほうしのみ友とこそなれ
西の海の浪のひらりとひかめくは朝日にむかふ太刀魚の色
腰かかめさらさらさらと上座から下まてひいてくるまゑひ哉
一首目は題詞「法印玄旨とつ川の湯に入(り)給(ひ)しを見廻(り)に遣(ら)すとて」、作者は宮川尼。法印玄旨は細川幽斎、宮川尼は幽斎の姉、雄長老の母。四句「とつかは」(「十津川」を掛ける)は副詞でせかせかするさまを云う。結句の終助詞「そ」は制止の意。二首目の題は「閑居」、作者は政長。初二句頭韻、母音尾母音のオ音、同じく母音尾母音のイ音がリズムを形成した。燭台の「影ほうし」が寂しい。三首目の題は「魚偏に乞」、作者は行風。二句「ひらり」は波間に姿を現した太刀魚、「ひかめく」はぴかぴかと光る様子、いかにも太刀魚の銀白色にふさわしい表現だ。四首目は「題しらす」、作者は浄次。初句「腰かがめ」だから坐っているのではない。前を向いたまま後ろに下がってくる。手慣れた様子は宴席の玄人か。
鑓ならてつくつくつくといふ音をきけは太鼓をうつきさみ也
午(うま)によく牛といふ字は似たりとも上へつき出す角をみてしれ
かたかなののの字のなりのにた物は篠の葉の絵の墨の一筆
鞠の場は七間まなか四方也木と木のへたて二丈六尺
一首目は題詞に「隣に太鼓うつをききて」、作者は行風。結句「きざみ」は短い間隔で連続して太鼓を打つこと。その連続音からオノマトペを得たが、それだけでは詰まらない。「突く」という動詞に変換して初句「鑓ならで」と落ち着いた。二首目の題詞は「無知の者共午牛の文字の筆画とやかく争ふをききて」、作者は是急。「午」は「うま」で十二支の七番目、同じ十二支なら「うし」は「丑」で歌にならない。そこがこの歌のミソであろう。三首目は題詞「篠の絵の讃に」、作者は智仁親王(一五七九~一六二九)。桂離宮を創建したことで知られる。「ノ」の字を使って絵の讃、歌は「の」の字を重ねて讃のイメージとした。三句「にた」は口語である。四首目の題は「鞠場」、作者は「藤原雅康卿」すなわち飛鳥井雅康(一四三六~一五〇九)、蹴鞠の名手であった。そのルールブックによると広さは七間(一間は六尺)四方で、その中央で行い、四隅に植える木と木の隔ては二丈六尺(一丈は十尺)と云う。
|
| 第61回 後撰夷曲集(13) |
君にかくよめのことたにしらるれは此(の)小鼠のつみかろきかな
和泉式部(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第九雑下の続き。この歌の前に題詞「小式部内侍を御覧して和泉式部につかはしける」で藤原忠通の〈よめの子の小鼠いかか成(り)ぬらんあなうつくしとおもほゆる哉〉がある。掲出歌は、これに対する「かへし」である。但し、忠通は道長の誤りで『和泉式部歌集』(岩波文庫)を開くと「入道殿の、小式部の内侍子うみたるにの給はせたる」とある。道長の息子教通と和泉式部の娘の間に生まれた子供である。二人は赤子を介して祖父と祖母の関係であった。巻末の「右内歌出所古書目録」から出典は『夫木和歌抄』と思われるが『国歌大観』でも「法成寺入道関白」(道長)となっている。ちなみに『夫木和歌抄』は一三一〇年頃に東国において成立、約一七三五〇首を収録する異色の類題歌集である。
ちいちいといふ音きけは炉の内のふる姥口の釜の湯にこそ
此(の)葛は味もよしのの名物とくはぬさきよりこれもすいせん
着る物はしま黄金のはたへにて年は三十二さうなよなふ
一首目は「題しらす」、作者は友信。初句「ちいちい」は沸騰するさま、また「爺爺」を掛ける。四句「ふる」(古)は「姥口」と複合語を作る。「婆口」は歯のない老婆の口、また茶道で婆口釜を云う。結句は言い止した。二首目の題は「水繊」、作者は「みつなか」。単純に菓子の「水繊」に「推薦」を掛けた。三首目は題詞に「いときよらなる女の。嶋の衣きしをみて。人々はたちはかりにや。五六にやととりとりにいふをききて」、作者は行安。題詞の「嶋」は色町、二句の、「はたへ」は「肌」で、これに「はたち」を匂わす。結句「さう」は伝聞の助動詞「そうだ」の語幹に「相」を掛ける。三十二相は女性に備わる美しさの全て。
偽(り)と思ひなからも鉄炮のはなしにきもをつふしぬる哉
人の欲たとへんかたはなかりけり冨士の山にもいたたきそある
何ことも見さるきかさるいはさるかよこさるとさる人の申(し)き
西へちろり東へちろり暁の明星やたた我(か)身なるらん
一首目は題詞「いつはりいふを世話に鉄炮はなすといへは」、作者は政長。「世話」とは世間の言い草。嘘と思いながらも乗せられるのが人の常、「鉄砲」がよく効いている。二首目の題は「人欲」、作者は貞徳。注記に「世話」とあるから下句のような諺が世間に流布していたのだろう。三首目は「題しらす」、作者は良囚。結句の「申」(十二支)を加えて六匹の猿がいる。上の三匹は助動詞「ざり」の連体形、四匹目は三猿に同意して「良(う)御座る」(戸締まりの用具「横猿」を掛けた)、五匹目は連体詞「然る」。四首目は題詞に「ことありて東に下り又山陰へさすらへける折(り)よめる」、作者は沢庵和尚。注記して「狂言詞」。上句の出典は小舞「暁の明星」(岩波書店『日本古典文学大系四四』の「狂言歌謡」)である。
|
| 第62回 後撰夷曲集(14) |
人は城人は石垣人は堀情(け)は味方あたは敵なり 大僧正信玄(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第九雑下の続き。題はなし。つとに有名な掲出歌は『参考篇』所収『狂歌五十人一首』にも収録されている。作者は甲斐信玄。『後撰夷曲集』の「作者之目録」に続く「右内歌出所古書目録」に「信玄全集一」(「一」は作品数)とある。掲出歌の隣に源義経作として〈吉日はみかたよけれは敵もよしたた肝要は方角をとれ〉がある。これは「義経軍歌一」だろう。また題詞「武田勝頼父子のくひを御覧して」、作者は信長公で〈勝頼と名乗(る)武田のかひやなに軍(いくさ)に負(け)てしなのなけれは〉がある。これは「信長記一」だろう。ほかに『新撰狂歌集』『古今夷曲集』、『参考篇』所収の『新旧狂歌俳諧聞書』にも登場する。作者は「平信長」「落書」「らく書」と分かれている。さて掲出歌だが三橋三智也が歌った武田節に「人は石垣/人は城/情けは味方/仇は敵」とあるのが思い出される。
といつまいつ同し事をはくり返しいひても年をふるこよみかな
住(み)侘(ひ)て世にかくれこの身となれと心の鬼はやはらきもせす
よひもせぬにきたれる老(い)の土産(みやけ)とて嬉しうもなきしらかいたたく
見物に北よ南よ西東四つ辻放下(ほうか)品玉のきよく
一首目の題は「寄暦述懐」、作者は舎永。初句は「解いつ巻いつ」、それぞれ「解きつ」「巻きつ」のイ音便と解した。体裁としては巻暦、だから二句から三句の展開となる。結句の「ふる」は動詞であり、また複合語を作る名詞でもある。二首目の題は「閑居述懐」、作者は正信。二句の「かくれこ」は「隠れ子」で「隠れん坊」に同じ、そこから「鬼」が出てくるが下句とりわけ「心の鬼」が生々しい。三首目の題は「老人」、作者は季吟。北村季吟(一六二四~一七〇五)である。『後撰夷曲集』の刊行は一六七二年、季吟は四十八歳、今なら「老い」には遠い。四首目の題は「放下師」、作者は一長。四句の「放下」は大道芸、結句の「品玉」は玉や小刀などを空中に投げ上げては巧みに受け取る曲芸、二句は「来たよ皆見よ」。
こつつりとうてる火打(ち)の石の火のちらと斗(はかり)の世にもすむ哉
親もなし子もなし跡に銭もなしからた斗はからりちん也
一首目は題詞「百首歌の中に」、作者は貞富。注して「本詩」とあるのは白居易の「対酒」の「石火光中寄此身」を指すと思われる。初句はオノマトペ、三句の「ちらと」は発火のさまであり、かつ副詞。「の」を重ねて流麗である。二首目の題は「辞世」、作者は成安。結句の「からりちん」は「ちんからり」(中がからっぽのさま)に同じ、「なし」の三連続を受けて、結句は四句の「から」に韻を踏んだ。亡骸という体ばかりは残すが、といったところ。また「ちん」は仏具の「りん」を鳴らした音にも聞こえる。後年、林子平(一七三八~一七九三)は〈親もなし妻なし子なし版木なし金もなければ死にたくもなし〉と詠っている。
|
| 第63回 後撰夷曲集(15) |
我さへもまたくひたらぬ水かゆの底にもみゆる影はうし哉 西行上人(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第十釈教。歌数は二四〇首。掲出歌は題詞に「興福寺三十講の座へまかりかかり水かちなる粥たうへけるとて」とある。初句の「も」から推察して三十講に集まった信者に粥が振る舞われたのだろう。だから僧である私でさえも、となる。結句の「影はうし(影法師。歴史的仮名遣いは「ほふし」)」は光があたってできる人の影、そこに法師としての自らの姿を織り込んだ。巻末を見ると「西行家集五」とある。今度は『参考篇』(第三巻)の「人名索引」で西行を見ると『後撰夷曲集』は五首、ほぼ間違いなく「西行家集」からの抄出だろう。なお行風篇では『古今夷曲集』にも古書目録があって検証可能である。但し『銀葉夷歌集』にはない。また件の「古書」を手にできるかどうかは別の問題である。
御斎(おとき)の食を手つからもりてくふ僧はもとより釈氏なりけり
阿弥陀そと申(す)仏師の口よりもはや金色の光さしけり
石像にきさみ有馬の湯壺よりわきぬる音も薬師ふつふつ
さても此(の)御かほを見たてまつるよりふくふくふくとなる心ちして
一首目は「題しらす」、作者は宗?。初句四音、あとは定型である。「釈氏」に「杓子」を掛けているだけだが嫌みのなさがよい。二首目は題詞に「仏師の箔つかへる折から本尊は何にかと問(ひ)侍るに阿弥陀とこたへし口にはくのつきたるをみて」、作者は顕興。三句の「も」で流れが変わった。三首目の題は「有馬にて」、作者は政長。「石像」は薬師如来、その石像を祭った堂付近に「湯壺」があっらしい。結句の「ぶつぶつ」は湯の湧く音、これに薬師仏の「仏」を掛けた。四首目の題は「三面大黒の讃に」、作者は宗因。三面大黒は正面に大黒天、左に毘沙門天、右に弁財天の顔を持つ大黒天、三面で福福しさに福が一つ加わった。
九年迄壁にむかへる辛労や達磨そんしやと人のいはまし
くろかりし衣の色の黄になるは善導大師はこやたれけん
是や此(の)仏もおやくし給ふはよるひる二六十二しんたち
一首目の題は「達磨」、作者は元成。「そんしや(尊者)」に「損じゃ」を掛けている。面壁九年、あと一年で十年一昔だから損といえば損に違いない。結句「まし」は推量の助動詞である。二首目の題は「善導の讃に」、作者は一休和尚。善導(六一三~六八一)は中国における浄土教の大成者、「はこ」は大便の意できれいな歌ではない。しかも「讃」。初二句は僧階制度で衣の色が変わっていくことを云う。それに対して結句は、本質にあらず、物差しが違うと喝破する。僧衣は仏語で糞掃衣、本道を歩む人への讃と解した。三首目の題は「薬師をよめる」、作者は「みつなか」。二句から三句「お役し給ふ」に「薬師」が隠れている。「よるひる」は「二六」時中、今なら四六時中。結句は十二刻から眷属の十二神将を導いた。
|
| 第64回 後撰夷曲集(16) |
生死海(しょうじかい)に慈悲の釣舟出(で)にけり漕(き)行(く)音は弱吽鑁斛 明恵上人(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第十釈教の続き。掲出歌の題は「平等性智」。明恵(一一七三~一二三二)は華厳宗中興の祖。初句は輪廻転生の限りない苦しみを海に喩えた仏語。問題は結句だが大栗道榮の『図説 密教入門』(鈴木出版)によると愛染明王の真言は「オンマカラギャバゾロシュニシャバザラサトバジャクウンバンコク」である。最後の部分を漢字で音写したのだろう。なお『明恵上人集』(ワイド版岩波文庫)には三句が「浮かぶなり」もあった。
僧や此(の)御すきの魚の名にたたはあかめんほくそうしなはるへき
御僧(ごそう)のかくしおかるる大こくを申さは寺のひんほかみさま
此(の)世にてゆひ切(り)をせようそいはは地獄の釜へおちやらふもおし
後の世はとにもかくにもなら酒の味口からややふる戒め
罪あるは蛛舞ならて足はうへかうへは下にむけん地獄そ
一首目の題は「五戒歌の中に殺生」、作者は満永。四句は「赤面目ぞ」、「赤」は接頭語で、ここでは「面目」を強調する。名に立つ魚はそこに隠れている「赤女」(鯛、体は淡紅色)か、「赤目」(体は銀白色)で、前者と解した。二首目の題は「同し中に邪淫」、作者は利安。注記して「世話」というのは上句の周辺を云うのだろう。四句の「申さば」以下、予想を完全に裏切る「貧乏神様」が出色である。三首目の題は「同し中に妄語」、作者は長丸。注記して「童口遊詞」。三句は「嘘云はば」、結句は「落ちやらう申し」である。「やらう」は助動詞「やる」(親愛表現)の未然形に推量の助動詞「む」の音変化「う」の接続と解した。「申し」は人に呼びかけるときの言葉である。四首目の題は「同し中に飲酒」、作者は元信。三句「なら酒」(奈良酒)は寺院を中心に醸造され、良酒として知られた。下句の表の意味は「味、口からや破る戒め」(助詞「や」は強意)。これに「味、口辛や。破る戒め」(助詞「や」は詠嘆・感動)を重ねた。五首目の題は「六道の歌の中に地獄道」、作者は一圃。二句の「蛛舞」(くもまい)」は張り渡した綱の上で行う軽業芸、室町末期から近世初期に流行したらしい。下句の表の意味は「頭は下に無間地獄ぞ」、これに「頭は下に向けん」と軽業の芸を重ねた。
此(の)世界くるしき海といふなれは身にうきしつみあるは尤(もつとも)
不義にして集めたくはふ財宝のつもりて後は二世の身のあた
一首目の題は「人道」、作者は満永。二句は苦海、苦しみの絶えない現世を海に喩えた仏語、しかし三句「なれば」と確定条件である。この結果としての下句とりわけ「尤」なのだ。二首目の題も「人道」、作者は雲居和尚。すなわち臨済宗の僧、雲居希膺(一五八二~一六五九)である。巻末にある「往生要歌」が出典で、同書は中央公論社刊『大乗仏典〈中国・日本篇〉』第二十九巻に収録されている。なお二句、文法的には「集めたくはふる」だろう。
|
| 第65回 後撰夷曲集(17) |
仏法は鍋のさかやき石の髭絵にかく竹のともすれのこゑ 一休和尚(『後撰夷曲集』)
『後撰夷曲集』の巻第十釈教の続き。難解だが掲出歌に題はない。解釈一「仏法は深甚で理屈や外形ではない。とらわれる心を放下しなければ見えてこないのだ」。解釈二は対者を重視した。たとえば人生を賭した問題を安易に問う相手を戒めた。解釈三。さらなる俗人を煙に巻いた。いずれにしても同巻の〈あみたふと申(す)斗をつとめにて浄土の荘厳みるそ嬉しき〉(法然上人)〈隔(て)ぬる地獄極楽よくきけはたた一心のしはさなりけり〉(親鸞上人)〈明(け)暮(れ)は信心ひとつになくさみぬ仏の恩を深く思へは〉(蓮如上人)との違いは明白だ。そして道歌を思ったりする。寺の門前でよく目にする、あの掲示板の歌である。
山伏の祈(り)をかくる三ヶ月も春の夜なれはおほろほろほん
鉢たたきちまたに古きへうたんのしはしはむなし中の八木(はちぼく)
なむ薬師あはれみ給へ世(の)中にありわつらふも病ならすや
さしむかひ東山より西方をねかふもあみた仏光寺哉
一首目の題は「月待(ち)」、作者は満永。二三句中「祈りを掛くる(欠くる)三日月」と自然との交感もおぼつかない。結句はおぼろ月に法螺貝で視覚と聴覚に訴えるオノマトペが絶妙だ。二首目の題は「鉢叩(き)」(鉦や瓢箪を叩きながら行う念仏踊り。空也を祖と仰ぐ)、作者は忠勝。結句の「八木」は米の字を分解すると八と木、ここでは施物の米を指す。四句「しばしば空し」は勧進が思うようにいかないことで続く「中」からして米は瓢箪に入れたらしい。三首目の題は「身のまつしきを八幡山の薬師に祈(り)て」、作者は小大進。初句「なむ(南無)」は感動詞として読む。四句は複合動詞で生きがたい、生活しがたい、の意。啄木ならば「ぢつと手を見る」ところ。四首目の題は「仏光寺にて」、作者は満永。仏光寺は京都市下京区にある真宗仏光寺派の本山、東山から見るとなるほど西方(浄土)である。
法の舟ありか他力よ身はすんと南無阿弥陀仏に任せてをけ櫓
事たらぬ身をな恨みそかもの足短うてこそうかむせもあれ
にくけなき此(の)されかうへあなかしこめてたくかしこ是よりはなし
一首目は題詞に「修行門の心を当世詞にてよめる」、作者は宣応。二句は「ありがたりきよ」、三句「ずんと」は下にくる語を強調する気持ちで「すっかり、まったく」、結句の「ろ(櫓)」は間投助詞で文末用法、命令形に付く。当世詞とは六方詞か。二首目は「題しらす」、作者は夢窓国師。結句「浮かむ瀬」は助かる機会。三句以下の比喩が面白い。三首目は題詞に「親月とて都の町に松たてわたししめかさりしていはふ折(り)から。されかうへいたきありき給へるを。或人のみてこはいかにと申(し)けれは返事によめる」、作者はご存知、一休和尚。「親月」は一月の異名、ここでは「むつき」と読む。あれ見さい、奇行の人がお通りだ。
|
| 第66回 卜養狂歌集 |
きしれうる今や君のみその友とのそみのみきやまいるうれしき 半井卜養(『卜養狂歌集』)
著者の半井卜養(一六〇七~一六七八)は堺の人。江戸に下り、幕府の御番医を勤めた。『卜養狂歌集』は全一八四首。奥書は「寛文九年仲春日」。「仲春」は陰暦二月の異称、一六六九年の二月である。その奥書に「御存知の如く我(が)狂歌は御所望の言下によみ侍るゆへその時は興に乗しておかしくも侍(り)けれ共後にみれはてにはもちかひ上の句を下によみたるもあり今あらためてなをし侍らんも却而(かへつて)口むつかしくも侍れは言下によみたると知(ら)しめむためそのまま書き付け(け)る御免」とある。読者としては「御所望」の説明が煩わしい。また説明がなければわからない歌というのも苦労する。で、掲出歌は「雉子」の回文歌である。漢字で補足すると〈雉子料る今や君のみその友と望み呑みきや参る嬉しき〉あたりだろう。「料る」は「料理」の動詞化、なかなかの出来映えである。
久かたのあまのしやくてはあらね共さしてよさしてよ秋の夜の月
しふ口にをくり通する五音しんこと葉のはちをかきくけこかな
かきくけこおこそとのほもよろこひは過分至極におしやらりるれろ
一首目。詞書に「八月十五夜月曇(り)て出(で)さりけれは」。初句は枕詞として二句「天の邪鬼」の「天」に掛かる。四句は月の光だが、出自としては小唄やはやり言葉の類だろう。二首目は詞書に「或(る)人のもとより柿を給はるとて」。初句は謙譲、次の「通する五音しん」は「五音相通」と「音信」。前者は昔の音韻学の用語。国語の音韻変化を説明するために五十音図の同じ行の音は互いに通用するとした。同音相通。下句は「はち(恥)を書き(柿)」と繋いだ。これを受けたのが次で「と有(り)し返りに」。初句は相手の結句を受けてカ行、二句は母音を継いでオ段、以上を序詞として三句に本意を述べる。下句、まことに過分至極で「渋」だとか「恥」だとか仰る、あとラ行だから仰られることでございます、か。
をのか名にもたれかかるは布袋(ぬのふくろ)くらひ肥(え)たは又はらふくろ
きえやらて今にいきとしいけたすみかしらもしろく尉(ぜう)となるまて
てつほうづたまのおきやくのおはなしにちよよろつよとうちそさかゆる
一首目、詞書は「布袋(ほてい)のふくろによりかかりたる所を書(き)て歌よめと云(ふ)」。人間臭い格好だ。二首目は詞書に「今は世をのかれいつかたへも出す埋(み)火を友として消(え)やらす」云々の友を訪う。三句「池田炭」(「生け(る)掛ける」)は良質のクヌギ炭、兵庫県川西市一庫で生産され大阪府池田市を集散地とした。「尉」は老翁、それを準えた炭火の白い灰の両意がある。三首目の詞書は「てつほうづのやとへきやくをまねきてたうざ」。「てつほうづ(鉄砲洲)」は東京都中央区湊町・明石町付近の旧称、幕府の鉄砲方が大砲の演習をした地という。「たま(偶・玉)」「うち(内・撃ち)」と鉄砲の縁語仕立ての展開である。
|
| 第67回 卜養狂歌拾遺 |
天下太平なりし愈(いよいよ)御疱瘡万代かけてさかゆめてたき 半井卜養(『卜養狂歌拾遺』)
『卜養狂歌拾遺』は『狂歌大観』の編者によって編まれた補遺である。掲出歌は初句七音、句またがりである。詞書に「家綱公御疱瘡あそはし御酒湯(さかゆ)の御祝儀に狂歌御所望ありけれは」とある。家綱(一六四一~一六八〇)は第四代将軍、酒湯は小児の疱瘡がなおったときにかける湯、結句の「栄ゆ」に掛ける。しかし疱瘡が栄えてはまずい。「疱瘡」に掛けたのは「芳草」(若草)であったか。家綱が将軍職を継いだのは十歳である。
かつらおとこ雲の衣をふんぬいて丸はたかなる月のなりかな
まいるたひかく御馳走に阿波様のあかぬこころはいちこまつたい
ほのほのとあかしいろつく柿の本のひとまるくちにかふりくははや
口のはたにむさくさむさくさけがはへてそそぼだいとやこれをいふべき
一首目の詞書は「十五夜の月に」。初句「桂男」は月に住むという伝説上の男、三句の「ふん」は接頭語で動詞に付く。荒々しく衣服を脱いですっぽんぽんの月という設定、女性はどうすればいいのだろう。二首目は詞書に「松平阿波殿にていちこ出(で)けるに」、苺が珍しい。三句「あは」に「遇う」、「あか」に苺の「赤」を先行させながら、結句は「苺全い」と完璧である。三首目の詞書は「見事にしゆくしたる柿の木の下にてされ歌所望あれは」、兵庫県明石市の柿本神社と『古今和歌集』の〈ほのぼのとあかしの浦の朝霧に島隠れゆく舟をしぞ思ふ〉(四〇九)が念頭に浮かぶ。四首目の詞書は「たるまのゑに」、四句の「そそ」は女性の陰部の異称。すぐ転ぶことから達磨は売春婦を意味したというから驚きである。
春たつた霞もたつた松たつたこれぞさんたのいぬの年かな
うさいわうよろこびあれや年の暮(れ)にさらばこがねの鈴を参らしよ
武士(もののふ)の鎧のさねもたまるまし三人ばりのかりまたのさき
ごばんをは打(ち)くつろいで此(の)いしの苦労をのがるしろの御かげで
一首目は詞書に「戌のとしの春よめる」、四句の「さんた(三太)」は犬の芸、前足を上げ、後ろ足で立つ「ちんちん」のこと。二首目は詞書に「歳暮に蜜柑をくるとてふる年もはやたち花といはひまいらせ」云々。初句は能「翁」に出てくる白髪の老翁、四句「さらば」(然らば)は「それでは」、次の「こがねの鈴」(蜜柑)が美しい。「参らしよ」は「参らせむ」の「せむ」の音変化「せう」。三首目は詞書に「三人小便に立(ち)しとき」。三句「さね(札)」は甲冑の材料となる鉄・革の小板、三句は「堪るまじ」、四句は「三人張り」の強弓、結句は「雁股の先」で男三人の連れしょん風景となる。四首目は詞書に「御番御赦免の時」とある。初句は「御番(碁盤)」、二句の「打(ち)」は接頭語そして碁を「打ち」、三句は「医師(石)」、そして結句の「城(白)」と外形としては一首、実態としては二首が同時進行する。
|
| 第68回 豊蔵坊信海狂歌集 |
おもしろしつはさもしろし山からすいく世かふしの雪にさらして 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』)
底本は蜀山人の奥書のある写本とある。歌数は七二五首(内一首重複)。著者の豊蔵坊信海(一六二六~一六八八)は京都府八幡市にある石清水八幡宮の社寺豊蔵坊の社僧であった。掲出歌は詞書「不尽のすそ野に尾と翅と白き鴉を見て」。平凡社の『京都・山城寺院神社大事典』によると「豊蔵坊は幕府の祈?所であったから、きわめて富裕で朱印地三〇〇石、実際はその数倍の収入であったと思われる」とある。江戸往来も社用であったろう。
難波かたみしかきあしの水鳥は言葉の海の底はさくらし
ともすれはつかるもやりの相手にていりたくもありいりたくもなし
くりかへしつかひこそやれくた鑓のいらふいらしの心みむとて
はくちをは蝶々とまれなのはたに判形(はんぎょう)居(り)てさする一札
一首目の詞書は「大坂の歌よむ人にたはふれて」。『新古今和歌集』に〈難波潟短き蘆の〉(一〇四九)がある。「蘆」を「足」に転じて、短いから底に届かない、「底は探らじ」と言ってのけた。二首目の詞書は「入湯していれといひやりけれは」、作者名がないので信海作と解した。二句は「浸かるも鑓の」そして「つかる」は「突かる」でもある。古来、風呂場で暗殺された武人に源義朝・源頼家・太田道灌がいる。三首目は、その「返し」。三句は「管鑓の」。管に柄を通した槍。左手で管を持ち、右手で柄を持って突く。四句は「応ふ応じと」と読む。しかし「応じ」は「応はじ」の筈で鑓の素早さに合わせたか。八幡信仰の地は社僧も生臭い。四首目の詞書は「町々の者にはくち打(ち)ましきとて一札をさせてけれは」。初句は「白地(何もない土地)をば」に「博打をば」。二句の「蝶々止まれ」に「喋々、とまれ(ともあれ)」、三句は「菜の畑に(名の端に)」。四句の「判行」は「書き判」または「印形」。「居て」は字数から「居りて」と読んだ。社僧がそこに「居りて」寺領の人たちに書かせたのである。
春さむき空にも人のはたぬくはうまれ庄野のよき所から
うらやまし地獄のかまにいりぬへき業をぬけたるしやくの依狠は
時鳥こゑをきくより筆とりて一首のうたをすみそめの茶や
一首目の詞書は「余寒甚たしきに庄野の里人はたぬきたるをみて」。旅の風景、「庄野」は三重県鈴鹿市の地名で東海道五十三次の宿駅である。二首目の詞書は「釜より湯をくみあくるとて杓のこうのぬけたるをみて」。「こう」は「がふ(合)」で掬う部分。結句の「依狠」は不明だが他本では「依怙」(字足らず)とあり、意は「頼りにするもの」で「杓」即「釈(釈迦)」説、「私利」で杓卑怯者説に分かれるが後者を採りたい。三首目の詞書は「墨染の茶やにて深草山の郭公(ほととぎす)を聞(き)てかへ(壁)に書(き)付(け)ける」。「墨染」は京都市伏見区深草の地名、京阪電車に墨染駅がある。茶屋の主に所望されたのだろう。
|
| 第69回 豊蔵坊信海狂歌集(2) |
ねていひきかきくらしぬる乗物のゆりわかとののもとの身やこれ 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』)
掲出歌は詞書に「(江戸を立つに)うちつつきてねさりければのりものにてつよくねふりて夢の心ちしてさて」とある。四句「ゆりわかとの」は幸若舞の一つ、百合若大臣のことだろう。蒙古を責めた帰国の途、無人島に置き去りにされるが、釣り船に助けられて帰国、逆臣を滅ぼすという話。二句は鼾を「掻く」、「掻き暗す」(悲しみにくれる)、「暮らす」などの意を含む。さしずめ孤島に取り残されたあたりで目が覚めたのである。邯鄲の夢と違って絶望のどん底。結句、まだ完全に理解していない。信海の多忙な日常を窺うことができる。
ちとゆかる我(か)ふるまへは親しらす子しらぬ国の人といはめや
弟子に寺をゆつりて世をもいとひ川君にあふせのありやせんもし
あふてさてこよひ更(ふけ)るをしらなんたたふるうとむの[口偏に放]しすきて
たぬきたぬきこまのけふりにむせふともはらつつみうつ楽(たのしみ)はなし
一首目の詞書は「越後の親類に江戸にてふるまはれて」。初句「ちと縁る」。二句は四段活用の「振る舞ふ」が助動詞「る」を吸収して下一段に転じた「振る舞へる」の連用形、名詞法と解した。四句は縁語の「親不知子不知」。二首目は詞書「そのおやにあはむとは弟子に寺をゆつりてのちにゑちこへまかりてなんといひやるついてに」。三句は縁語「糸魚川」。結句「もし」は呼びかけの「もうし」の音変化と解する。信海は父孝仍の跡を継いだということであるが養子であったか。いろいろと想像が広がる。三首目は詞書に「饂飩ふるまふ人の当世の小歌によせてよめと云(ひ)けれは」。四句[口偏に放]は該当する現行通用字体がないのだろう。「話」と解した。節は伝わらないが意味はよくわかる。四首目は詞書「護摩を修して又加持しけれは聴聞しける人のいとけむたしといひけれは」。狸=化ける=煙、狸=僧侶というイメージを共有できたのだろう。下句は狸の縁語で締め、かつ聴聞の人を諫めた。
とく人のなきかまくらはさひはてて草のみふかきさととあれぬる
浪まくらうつつのやうに起(き)つ寝つ夢路きよみか関やこれなん
大和竹のをさへやよはき堂宮のあつたらものそ屋ねはまくるる
一首目の詞書は「かまくらの道も草ふかくみえけれは」。掲出歌の後、上りの旅である。初句「とく」は「疾く」、三句は「寂び(荒び)果てて」、鎌倉幕府滅亡は約三百年前であった。二首目の詞書は「その夜沖津にとまりて浪の音に目もあはさりけれは」。「沖津」は「興津」。夢路にも関があった。それもタイムスリップして平安時代、歌枕の清見ヶ関は知っていたが、これがそうだったのだ。三首目の詞書は「宮にて堂宮のやねのまくるを惜(しみ)て」。日本橋から数えて四十二番目の宮宿、熱田神宮を拝しての作であろう。初句「大和竹」は奈良地方に産する竹の一種、四句は「あたらもの(可惜物)」に同じ、惜しむべくもの。
|
| 第70回 豊蔵坊信海狂歌集(3) |
御使(ひ)かはいらさんせい入(り)さんせいふみはこそこにおかさむせいのふ 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』)
掲出歌の詞書は「三清と云(ふ)法師文箱もちて使(ひ)に来(に)けるを門外にて逢(ひ)て」。そこで親しく声をかけた。それも法師にちなんで三度「さんせい」を繰り返す。もと上方の遊女語だったという「さんせ」は動詞の未然形につく助動詞「さんす」の命令形。丁寧の意を含んだ尊敬を表す、とある。語尾の「い」は他に用例があるようだから不自然ではなかったと思われる。なお結句の終助詞「のふ」は歴史的仮名遣いでは「なう」になる。
むつかしき山川海をこえて来てもはや苦はなややかて宮古路
燈籠なくて大津の雨に駕籠の戸をあけつさけつに辛苦こそすれ
無馳走(ぶちそう)をきらひ給はてやかて又上野といふ殿(以下欠)
三国のやまのうちては冨士は伽羅あのそらたきの煙りみるにも
一首目の詞書は「桑名につきけれは」。四句「苦はな」に「桑名」、結句「宮古」は六三二番に詞書「九月十三夜曇(り)しに京へのほるとて」で〈気も空も晴(れ)にし月を宮古そとのほれは我か枝まめやさて〉の例から「都」とわかる。二首目の詞書「大津にてしきりに雨ふれは」。初句七音。四句は「上げつ下げつ」、したがって三句の「戸」は出入りするための引き戸ではなく、明かり取りと換気のための小窓と解釈した。三首目の詞書「吉良上野殿お出(て)有(る)に」。この「吉良上野殿」とは松の廊下の「吉良上野介」(一六四一~一七〇二)なのだろう。二句に「吉良」を隠す。結句五音は永遠のパズルとなった。四首目の詞書「又」。再び下向、信海は「東行の旅」と呼ぶ、その道中で冨士の連作である。初句の「三国」は漠然と世界と解しておく。「伽羅」は香木にして極上の意、まだ活火山であった。
をきまよふ霜夜の道のかこの内はけにもみかんのつめたいやのふ
此(の)ころの寒をいたます我(が)山にのほり給ふはわかさ成(り)けり
大阪へやかてこひとの地黄煎あまい詞にちよいとのる舟
一首目の詞書は「駕篭にのりて夜道を行(く)とて」。蜜柑の置き場所がなくて困っているところが何とも愉快である。反対に駕篭の外を「張灯もちにかはりて」の詞書で〈火をともす挑灯からりからころりころりとやせた夜のお供に〉と歌う。提灯が「からりからころり」と振動で鳴るのだろう。その「ころり」ころっと体型が変わったのは私のせいだと云っている。二首目の詞書は「神尾若狹守殿登山の心を狂歌によめと有(り)けれは」。二句は「寒を痛まず」、「寒」は音読み、苦痛に思わないで。結句に相手の官位を詠み込んだのは挨拶だろう。三首目の詞書は「迎(へ)舟をのほすへきに大坂へ下れと云(ひ)こしける人に」。二句の「こひ」は「来い」(歴史的仮名遣いも「こい」)。三句「地黄煎」は地黄を加えて練った水飴のこと。また石清水八幡宮は桂、宇治、木津の三川が合流する淀川の左岸に位置する。
|
| 第71回 豊蔵坊信海狂歌集(4) |
網の糸てくくり枕やぬれそひてめことにあまるなみた成(る)らん 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』)
掲出歌の詞書は「白すかに泊りけるに浪音高くてねられさりけれは古郷のことともおもひつかけ覚えす涙おとしてけれは」。「白すか」は白須賀で三十二番目の宿駅、現在の静岡県湖西市の地名。「おもひつかけ」の「つ」は促音で強調して「思ひっかけ(覚え)ず」か。三句は「濡れ添ひて」、濡れた上にさらに濡れる意。四句の「め」は網の目と作者の目、四句の「なみた」は涙に浪を掛ける。前後からして上りの旅、望郷の涙は親不知の越後と思われる。
秋の夜の長過(ぎ)たるに御朱印を月星とまつ武蔵野の原
なててみよ気のくすり湯に入(る)からにすんへいるりくはうの如来はたへを
春雨のかかれるゆへにせんかたなさや海道をかへり角かな
一首目の詞書は「御朱印の拝領まちかねて」。朱印状を貰わなければ帰れない。武蔵野の空は「月星」(付き欲し)が渡るプラネタリウムである。二首目の詞書「薬湯よりあかりて」。二句は「面白い湯に」、三句は「入ったので」。四句「すんへい」は「すんえい(寸栄)」(ほんのしばらくの間の栄誉)と解した。つかのまだが瑠璃光如来の肌だ、撫でてみよというのである。三首目の詞書は「雨のふりけるにさやへまはり船にのりて」。三句は「詮方な」、四句へ跨らず「無し」の語幹「な」で「ないこと」と解した。佐屋街道は脇街道、佐屋から木曽川を下り桑名に至る「帰り船」である。結句「角」は「舟」と編者の補記がある。
那智八十高野六十やはたにはけふ四十三我うしろやく
身の上の丹波こえするはしめにはまつ借銭をさえのさかかな
借銭をこひつめたらは帯ときてはたかに成(り)てねてやかからむ
おちの人のしんくといふにはつと扠(さて)ちのあかりたるここちこそすれ
一首目の詞書は「四十三をうしろ厄と聞(き)て」。俚諺に「高野六十那智八十」がある。高野山では六十、那智山では八十になっても男色の相手をさせられる、というのだ。そこから結句「うしろやく」となる。二首目の詞書は「納所(なっしょ)の身上(しんしょう)あやうく後は何と成(る)へきとくやむに」。寺の会計や庶務を掌る僧を納所坊主という。二句の「丹波こえ」は逃亡の意。京都から丹波が定番のコースだったらしい。結句の「さえ」には編者によって「老」と補記がある。「借銭を老い(負ひ)」、「さか」は丹波越えの「坂」と解した。三首目はこれに続く作品。二句は「請ひ詰めたらば」。下句は何にも出ない、出さない、その意思表示が駄々っ子のようである。四首目の詞書は「幼少の時乳をのませける者の果(て)たると聞(き)て」。初句は「御乳の人」で乳母、「御乳」に「遠」を掛けて越後の人になる。二句の「しんく」は「死んく」、「く」は他本では「だ」である。四句は「血の上がりたる」で平常心を失う。また「血」に「乳」を掛けて、乳母であることを重ねた。
|
| 第72回 豊蔵坊信海狂歌集(5) |
おつともせいていつそいはしや水鳥のおもひゐおもひゐ名残おしおし 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』)
掲出歌は詞書「江戸をたつに此ほとの名残おしきといふ人に」。初句七音「音(おっと)もせいで」。「せいで」の「せ」は動詞「す」の未然形。「いで」は接続助詞で上を打消して下を修飾する。三句の「水鳥の」は「立つ」に掛かる枕詞で、省略されているが、普段の音沙汰無しが「いざ」となったら思いはいっぱい、「名残惜し(鴛)惜し(鴛)」の反復となる。
八まんへまいるたひたひつけはけに是そすすかけはとの杖かな
酒をさてすき頭巾とはつく杖の竹のよよまてかたりつたへた
そろそろと自然こしきとなる身かなささらの竹のすつた世の中
一首目の詞書は「杖をくれけるかたへ」。初句「八まん」は「八幡」に「八万」を掛けて「たびたび突けばげに」と続ける。結句は握りに鳩の飾りのある老人用の杖、四句「是ぞ」以下は句またがりでハト科の鳥「数珠掛鳩」の登場となる。八幡は本殿、僧にとって数珠は必携であった。二首目の詞書は「陶渕明の賛」。初二句は白楽天の「陶潜が体に效ふ詩十六首并に序」(佐久節訳註『白楽天全詩集 第一巻』日本図書センター)の十二首目「口に帰去来を吟じ、頭に漉酒巾を戴く」とある。頭巾で酒を漉していた、いやその逆か。三句の「杖」は「帰去来の辞并に序」(石川忠久著『漢詩を読む 陶淵明詩選』日本放送出版協会)に「良辰を懐いて以て孤り往き/或いは杖を植(た)てて耘?(うんし)す」とある。これに拠ると思われる。杖は竹の杖、竹の茎の節と節の間を「よ(節)」という。二つ重ねて「よよ」、これに同音の「代々」を掛けた。三首目の題は「歳暮」。一読、ささくれた竹のように時と金を使い果たした私はおのずから乞食となる身であるようだ、と読める。しかし二句に「自然粳(じねんご)」(竹の実の異名で食用)と「甑(こしき)」(米などを蒸した道具)が「こ」を共有、四句と五句は「ささらすり(簓摺り)」(簓を用いる大道芸)のイメージを包含し、竹の縁語を駆使していることがわかる。また結句の「すった」の促音便は賭け事も連想させる。石清水八幡宮の鎮座する男山と江戸を往来する豊蔵坊信海にも疲れがあって不思議でない。
成(つ)てさてみたや空ふく風の手になててよふしの雪の肌えを
くもなくて硯の海を出(で)たるはさてもみことのすみの江の月
一首目は題「富士の狂歌」だが二句の「みたや」で句割れ。以下「空ふく風の手に」が上のフレーズに対して倒置法。すると四句の「撫でてよ」が「富士」の願望、勧誘として読める。しかも四句も句割れ、いやでも「雪の肌え(へ)」が強調されるという次第で、いたって艶っぽいのである。二首目の詞書は「月といふ額に」。扁額の類だろう。場所は室内である。初句は「雲なくて」。二句、海は海でも「硯の海」だから導入部を平仮名表記にして、この歌が見立てであることを暗示した。結句も「住之江(墨江)の月」だから見事というほかない。
|
| 第73回 豊蔵坊信海狂歌集(6) |
雲となりめくりて春は立(ち)帰るふしは世界の雪のふるさと 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』)
掲出歌の詞書は「富士」。三句の「立(ち)」は接頭語、「立(ち)帰る」で繰り返す意となる。上空から微速度撮影された四季の巡りを見ているようだ。『豊蔵坊信海狂歌集』は全部で七二五首、そのうち四十三首(約六%)が富士の歌である。明治になって「ふじは日本一の山」(「ふじの山」)となる。しかしそれ以前「ふしは世界の雪のふるさと」であった。
歌袋の口のあかれはもろともに財符もつれて空にふはふは
文の内に御礼申(さ)はあさくらやあいましてさておもひさんせう
正直のかうへにやとる神のあれはやしろの家にためた財宝
一首目の詞書「古郷へ歌口はきけと仕合(はせ)よろしからすと云(い)やるとて」。「歌口」は和歌(狂歌)の詠みぶり。「仕合(はせ)」は巡り合わせ、また馬の腹当てに染め抜く語として「仕合吉(しあはせよし)」があった。結句がおもしろい。交際範囲が広がって出費もかさんだのだろう。二首目の詞書「さるかたより朝倉山椒給はるに」。初句は手紙の中で、の意。二句は「御礼申さば」と読んだ。三句は産地の「朝倉」に掛けて謝意が不十分の意を込める。お会いしまして改めてお礼申し上げる「思ひ」でございます。結句は助動詞「ざんす」の未然形に推量の助動詞「む」の音変化「う」が接続した。なお朝倉山椒は兵庫県養父市八鹿町朝倉で多く産する。三首目の詞書は「屋代氏狂歌のそまれけれは」。三句の「神」までは俚諺「正直の頭に神宿る」。また四句「屋代」は同音の「やしろ(社)」を掛ける。
古郷をこふるおもひの深くさに露置(き)まよふすみそめの袖
東路をはたやるやうに行(き)来していつかにしきをきてかへらまし
かけておし忍ふ若衆の口吸(ひ)て夜をあかすへき菊の下葉を
のりもののよしたとをれは窓よりもかほつんたいてあふたうれしや
一首目の詞書は「深草のすみそめにて」。三句の地名に思いの深さを掛け、結句の地名に僧衣を掛けた。信海の越後望郷の歌である。二首目の詞書は「春やはたを出るとて」、他本では「一とせに三度下向の折に」。二句は「機やるやうに」、他本では「機へるやうに」で「へる(綜る)」は縦糸をととのえて機ににかける意。そして錦を飾るのは一首目の「古郷」ということになる。三首目の詞書「下歯かけけれは」。一首は初句切れ。その初句は「欠けて惜し」。二句「若衆」は男色関係にある少年、だから「忍ぶ」仲となる。結句の「菊」は肛門の異称。菊だから「下葉」に「下歯」を掛けた倒置法である。四首目の詞書は「吉田といふ所にて都人に逢(ふ)」。「吉田」は東海道三十四番目の宿駅、京都からだと二十番目の宿駅である。四句「つんたいて」は「突き出す」の音変化「突ん出す」の連用形に接続助詞の「て」が付いたイ音便。上りと下りの擦れ違いだが降りなかった模様、顔ぐらいは出せたらしい。
|
| 第74回 孝雄狂歌集 |
ゆひかひの有(り)もやするといそしまてたとる袂に浪はこえけり 豊蔵坊信海(『孝雄狂歌集』)
『孝雄狂歌集』の著者は豊蔵坊信海。孝雄は法諱(法号、出家した人の本名)とある。すると信海は雅号になる。体裁は写本で全二九三首のうち『豊蔵坊信海狂歌集』(七二五首)と四首重複する。掲出歌の歌番号は四、『豊蔵坊信海狂歌集』の歌番号六七一に「卯年試筆」の題で〈命毛のなかき五十の筆はこを明(け)てこころむうのとしの春〉があって接続する印象である。本歌に戻るが詞書は「ゆひの浜をかちにて行(く)に五十まてたとるあはれを催し成清法印の古歌何となくおもひ出(で)て」。「ゆひの浜」は鎌倉市の相模湾に面した海岸、江戸下向の途次と思われる。珍しく「かち(徒歩)」である。古歌とは『新古今和歌集』の〈榊葉にそのいふかひはなけれども神に心をかけぬ間ぞなき〉(一八八七)であろう。詞書は「八幡宮の権官にて年久しかりけることを恨みて、御神楽の夜参りて、榊に結び付け侍りける」。権官(ごんかん)は正官以外に仮に任じる官。権官ではないが加齢は信海をネガティブにした。初句は「言(ゆ)ひ甲斐」に「由比」を掛けた。三句は「五十路まで」、結句「浪」は「由比の浜」の縁語、成清(じようしよう)は鎌倉幕府と縁が深かった。
雪ふれはなへておしろいますかたの鬼瓦さへけさはたてして
いはし水の井にすむ蛙時を得て小田原の殿に申すことふき
山も川もおほろおほろとかすみ絵にかたわれ月の山水と出た
一首目の詞書は「雪のふりける朝に」。二句の「おしろい」は「お白粉」。三句の「ます」は「増す」、「かた」は頃や時分の「方」、結句「たて」は「伊達」となる。二首目の詞書は「稲葉美濃守殿御斎(おとき)給(ひ)て狂歌せよと有(り)けれは」。「稲葉美濃守」は小田原藩主稲葉正則(一六二三~一六九六)と思われる。「御斎」は食事。一首は石清水その最初の「い」を同音の「井」に転じて始まる。三句の「時」に「斎」を掛け、井の中の蛙とへりくだった自身を小田原の殿様に配して挨拶とした。三首目の詞書は「山水にかたはれ月の賛」。詞書の「山水」は「山と川」の意。二句「おぼろおぼろと」で「ぼんやり」、三句に続けて「霞み、絵に」と読む。四句は「片割れ月」、結句の「山水」は形容動詞で物寂しいさま。
しつらいを蝸牛のつののつかまつり何といほりのものつきやのふ
あはれたたふつつふられついきもよくねみたれ髪のちやせんやころす
一首目の詞書は「蝸庵の額に」。初句は「設ひ」、二句「蝸牛」は音で読む。初二句を序詞として三句は「仕り」。四句の「いほり」は「庵」に「云おうか」を掛ける。「ものつき」は「物好き」で作者信海にはツ音の磁場であった。二首目の詞書は「茶筅髪(ちやせんがみ)にて居る若衆の絵の讃」。二句は「振りつ振られつ」の「振りつ」が促音便で結句は「茶筅や御覧ず」。「ごろず」は「ごろうず」(ごらんになる)の変化した語である。「や」は詠嘆、感動。茶筅髪(略して「茶筅」)は、その髪型が茶道具の茶筅に似ているところからの命名、そのままを歌った。
|
| 第75回 孝雄狂歌集(2) |
われことし後住(ごじゆう)にはなれありてうきいのち也けりさよの中山 豊蔵坊信海(『孝雄狂歌集』)
掲出歌は詞書に「小夜の中山をこゆるとて五十二にて後住にやかて寺をもゆつらふとおもひしに是非なき事となけきて」とある。二句「後住」は後任の住職。「離れ」は縁が切れた。「是非なき事となけきて」からすると後住の死が考えられる。一首は『新古今和歌集』の西行作〈年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山〉(九八七)を本歌とし、西行が越えた感慨を詠ったのに対して信海は越えることができなくなった、そうした二重の意味で「在りて憂き命」を歌う。「小夜の中山」は静岡県掛川市日坂から金谷町に至る途中の坂路、東海道の難所であった。越後の信海にとっては象徴としての「小夜の中山」であった。
御酒によふて足もとよろつけはまたあかさかのうちに帰らふ
越前のものなりけれは我(が)宿へいのふ峠の孫左つれなや
せなかには重荷をおふてわれことし五十三つきのむまの春かな
京へとてまた宵なから出(で)ぬれはかこの底にや我やとるらん
一首目の詞書は「名残に一首と有(り)けれは」。初句は四音、四句の「あかさか」は地名の「赤坂」に「明るい」を掛けたと思われる。結句は「帰ろう」で口語歌なのだ。二首目は詞書なし。下句は「湯尾峠の孫杓子」(福井県湯尾峠の名物)転じて「往のう」の口合いとして使われた。「孫左」は具体的には不明、しかし峠を越えさせてくれないのである。三首目は詞書「道中五十三才なれは」。四句は東海道「五十三次」、結句は「午の春」。初二句にもどって「仕合吉」の荷馬のイメージを逆手にとった。四首目の詞書は「宵より京へ行(く)とて」。一首は『古今和歌集』の清原深養父作〈夏の夜はまだよひながら明けぬるを雲のいづくに月やどるらむ〉(一六六)を本歌とした。駕篭の底に月が宿っているような錯覚である。
御免あれ急用あれは御返事も尻をからけてはしりかき哉
あなたへひよむこなたへひよむと風になひく是こそ雲の帯くるまなれ
後々まてもつかひつかひにはなれすに是そ屏風のおし絵也けり
一首目は詞書に「かかる一巻の跡に歌よめといひおこせけれと盃のめくりめくれる年月もいそかはしくて返事もせさりけれは」とある。「いそがはしくて」は「せわしくて」、頼まれた歌は無論のこと返事もしていない、その言い訳の一首である。二首目は詞書に「ひよむといふくたもの帯車にする歌よめといふに」。「ひよむ(ひょん)」は植物「いすのき(柞)」の異名、小型の瓜に似た野生の実をつけるという。帯車は根付けのこと。「ひよむ」という名詞を副詞化、実を帯車にして雲の様を形容した。あるいは「雲」は帯車をはさむ帯そのものとも読める。三首目の詞書は「おし鳥」。初句七音も珍しくない。二句は「番ひ番ひに」、仲の良いとされる鴛鴦のカップルと左右一双の屏風を結句の「押し(鴛)絵」で合体させた。
|
| 第76回 孝雄狂歌集(3) |
菩提やか妙なる歌の言因にかの蓮台にのる菓子袋 豊蔵坊信海(『孝雄狂歌集』)
掲出歌は詞書に「難波の鯛屋といふ菓子屋に」とある。初句の「やか」は接尾語で名詞に付いて形容動詞の語幹を作る。いかにもそのような感じがする意、「提や」に「鯛屋」を隠す。「言因」は上方狂歌壇の第一人者となる鯛屋貞柳(一六五四~一七三四)の本名である。母の法名は「妙因」(二句に「妙」、三句にも「因」)、「菓子袋」に家業とお袋を重ねた。
春毎(ごと)の県(あがた)のめしのうへにても菓子及第にしくはあらしな
初にきた隔心かまし馳走すな名をはゑんていしつたお人しや
一首目は『後撰夷曲集』で取り上げたが作者は安原貞室(一六一〇~一六七三)、詞書に「家職の得業によ(り)てかけまくもかしこき詔ましまし御菓子所山城大掾藤原貞囚になしたまふその悦の俳諧一巻の奥によめる」とある。この藤原貞囚が言囚の父である。二首目は『豊蔵坊信海狂歌集』に載る。詞書に「貞室はしめて来けるに納所馳走たてしけるを留(め)て」とある。納所坊主に気を使ったのだ。二句「隔心」は気兼ねする気持ち、「ゑんてい(淵底)」は副詞で「すっかり」、結句「しや(じゃ)」は助動詞、「である」の語尾「る」が脱落した「であ」の転だという。初対面だが貴方の名前はよく知っている、気を使うなと云っている。貞室は信海より十六歳の年長、言囚は二十八歳の年少、信海の名は今思うよりも大きい。
母をすくふためし有明の月ほとなこれは菓子盆それはうら盆
見る人も見らるる花もさつとひまあきのさくゐの珍菓亭哉
くろこりややかて夜あけてしろこりやひつつれたつた京のほりかな
京まての同道はよしともなれとわれはかこにてふしみときはしや
一首目は詞書「難波の鯛屋といふ菓子屋に」の掲出歌に続く作品。二句の「ためし(例)」は餓鬼道に落ちた母を救う盂蘭盆経の物語、この経説に基づいて行われる仏事が盂蘭盆である。下句の対句表現はよくある手だ。二首目は詞書に「大坂の珍菓亭言囚参(り)て秋牡丹の花をみて狂詠をいふに」。「秋牡丹」は「秋明菊」、それを見た言因が狂歌を詠んだ。したがって「見る人」は言因、「見らるる花」は秋牡丹である。三句は「さっと閑」、即詠である。四句「さくゐ」は「作意」で心配りとか機転の意と解した。三首目は詞書「かたるに夜ふけけれは京におもむくしれものにてつれたちけれはいとくろく雨さへふりけり」。「しれもの(痴れ者)」とは信海と言囚、したがって初句は「黒狐狸や」、三句は「白狐狸や」と読む。四句は「引っ連れだった」、ちょっと悪者ぶったところに信海の満足がある。四首目の詞書は「いとねふたき歌咄しけれはわひてときはといふ処にて」。「ときは(常磐)」は京都市右京区の地名、連想は常磐御前に移り二句から三句に義経の父「義朝」が身を隠す。結句は「臥し身時じゃ」(眠らせてもらうよ)で「常磐」を隠した。言囚は笠を借りての同道である。
|
| 第77回 信海狂歌拾遺 |
やかてやかて香の花のと供せられ扨かのきしにわたりものかも 豊蔵坊信海(『信海狂歌拾遺』)
『信海狂歌拾遺』は『豊蔵坊信海狂歌集』『孝雄狂歌集』の補遺として『狂歌大観』編者によって抄出されたもの。掲出歌の出典は『芳草集』。詞書に「戊申の年九月俄に煩(ひ)て心地死(ぬ)へかりけれは」とある。弟子の黒田月洞軒の『大団』によると信海の亡くなったのは貞享五(一六八八)年九月十三日、この年は戊申だが九月三十日から元禄と年号が変わる。六十三歳、辞世であろう。結句は「渡り物」で祭礼のときの「ねりもの」をいう。
父の気色もはやゑいかもむひやうにて命なかけんめて鯛屋かな
右の作品は詞書に「父貞囚時疫煩ふとて祈?の儀頼(み)こしける程なく本服せしとて 学ひぬる歌の病ひも頼みあり時疫をいのるしるし山城 鯛やよみこしけるかへし」とある。「時疫」は流行病。父の病を治してもらい、今度は私の歌の病もよろしくお願いします。「山城」は言囚を指す。二句の「ゑい」は「えい(良い)」、三句は「無病にて」、結句は快気祝いに鯛を添えた。なお江戸での信海は石田未得や北村季吟と親しかったことが作品でわかる。
けふ御礼いちいち首尾のよかれかし各心中に御祈念をして
梅咲(い)て大木小木の花なかめあふるかき餅みそし一(と)もし
弟子はけふ麓の野辺をたとるかと心にかかる富士の白雲
ひけまんをするとはなしにをとこ山七日急(い)て八日にすらり
御祈祷の御礼納めて如律令いはふて三度急急の急
秋風とつれたつとてもひえはせしかさねかさねのたひ衣にて
一首目の詞書は「弟子一位江戸へ御礼に参りし時正月廿八日に御礼相勤(め)ん事を思ひやりて」。江戸への下向は弟子の代行に変わっている。四句「各心中」(「各」に「斯く」の意を汲みたい)は二句「いちいち」を受けている。二首目の詞書は「弟子留守の淋しさに」。二句は「たいぼくしょうぼく」と音余りで読んだ。おだやかな晩年の日々と云おうか。三首目の詞書は「いちゐけふ富士をなかめんと思ひ出(で)て」。手に取るような行程そして気になるのはやはり富士の姿であった。以上が『芳草集』。四首目の詞書は「道中八日に帰山して」。初句「卑下慢」は表面はへりくだつているようだが実際は自慢していること、よく分かっていて最初に断っている。それも通常は十五日の行程を八日に短縮したのだから凄い。結句「すらり」は事が順調に進むさま。五首目の詞書は「一とせに三度下向の折に」。魅力は「急急如律令」(急々に律令のごとくに行え、の意。祈?僧などが呪文の結びとした)の持ち込みである。以上が『狂歌鳩杖集』。六首目は『芳草集付簽』、詞書が読み辛いが「八月九月之御祈?修行御札持参又罷り下るべく存ぜられ候。心底御推量下さるべく候」か。四句からして早く帰りたかったのだろう。しかし念願とした古郷越後は最期まで遠かったようである。
|
| 第78回 銀葉夷歌集 |
態(わざわざ)申すよつて詠(め)るさくら花一枝をくりたてまつり候 安親(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』は生白堂行風の『古今夷曲集』(一六六六年)、『後撰夷曲集』(一六七二年)に次ぐ編著、『金葉和歌集』が念頭にある。延宝七(一六七九)年刊。「序」に「和歌は情淳にして風情をかさり夷歌は俗語をもきらはす心たたしく理にかなふをもはらとせり」とある。行風の狂歌観である。一〇巻一一八六首。掲出歌は巻第一春歌、全一六一首のうちの一首である。詞書は「花の枝送るに添(へ)て」。諸橋轍次の『大漢和辞典』で「態」を引くと国訓として「わざわざ」、ほかのついでではない意。したがって初句七音、二句「因って」は漢文訓読に由来する語、そういうわけで。眺めている一枝を送るという添え状の体である。
うてたてか氷のはつた川つらを打(ち)はる風は陽気もの也
棚もとてきく鶯の声ならはそも摺鉢のみそし一文字
是や此(れ)よめなをつかふ料理にはあとよりいたせ蕗のしうとめ
一首目の作者は顕行、詞書はなし。初句は「腕立て」(腕力の強さを自慢すること)、三句は「川面」で面が人の顔を連想させる。四句は「打ち張る風」に「春風」が同居する。二首目の作者は貞林、詞書は「百首の歌中に棚元聞鶯」。「棚もと」は台所、下句「(摺鉢の)味噌」に「三十(字)」が同居する。作中主体のいる台所を条件として「そもそも歌の一首ぐらい」というわけだ。三首目の作者は方碩、詞書は「春草」。二句「よめな(嫁菜)」だが春の若葉は食用となる。結句の「蕗のしうとめ(蕗の姑)」は蕗の薹の異名、蕗の若い花茎で食用となる。一首、脳天気な男の台詞ではある。そして嫁菜も蕗も同じキク科であるのが面白い。
さいめよりあらく吹(き)こす春風に花の浪たつうら屋なりけり
そよとたに風もふかぬに禅寺の花ちる事よいかなるか是
あたたかな日は田返しに引(き)て行(く)牛も涎をくるすのの原
無常そと花も悟やひらくらんきのふも過(ぎ)つけふもくれんけ
一首目の作者は伯水、詞書に「百首歌の中に際目落花」。初句の「さいめ(際目」は境目、境界。結句の「うら屋」は裏通りに面した家。粗末な家の内と外の境目、「波の花」ならぬ「花の浪」で「うら(裏)」に海と陸の境目の「浦」を重ねた。二首目の作者も伯水、詞書は「古寺落花」。四句までは眼前の風景、それに対して結句は修行者に出された公案の趣きである。二句の不条理を受けて四句に詠嘆の「よ」が付く。三首目の作者は正信、詞書は「春田」。結句は「栗栖野の原」。栗栖野は京都市北区にあった古地名、歌枕である。四句から五句の「涎をくる」は涎を垂らしていること、「涎繰り」という名詞がある。四首目の作者は一見、詞書は「木蓮花」。上句は人だけではない、花も悟りを「ひらくらん」と見立てた。下句は無常の描写、結句は「今日も暮れん(け)」に「(けふ)木蓮華」、単純だが上手な着地である。
|
| 第79回 銀葉夷歌集(2) |
ゑひもせす京をわたせる祇園会は一二三四五六月七日 恵立(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第二夏歌、七七首。掲出歌の詞書は「夕立過(ぎ)る後よめる」。雨は酒と違って酔うことはない(「よふ」は「ゑふ」の転)。初句は伊呂波歌の最後の五音、その末尾に付く「京」を呼び出す役割も担っている。結句の「六月七日」は祇園会の始まる日(現在は七月十七日)。四句以下は手習い歌に倣って漢数字、一から始めて六月七日で決めた。
さきつつく卯の花垣はしらかへの塀かまへとそみるへかりける
一声はきいたといふも中々にとつととをいの山ほとときす
一声はとちの方にか有明の月にはけたかやよほとときす
一声を聞(い)てよろこふものはたたうゐの赤子に山ほとときす
一首目の作者は正盛、題は「卯華」。初句は「咲きつづく」に「先つづく」を掛ける。三句は「白壁の」、四句は「塀構へとぞ」で、結句は「見るべきであった」。二首目の作者は元昌、題は「聞郭公」(以下の二首も同じ)。三句は「中途半端に」、四句の「とつと」は「ずっと」(幼児語の「とっと(鳥)」を掛ける)、「の」は準体助詞で、六度のト音が響く。三首目の作者は重勝で一声もない歌。二句「とち」は「どち(何方)」で「有明」に所在を問う意を掛けた。四句は「月に化けたか」、結句「やよ」は呼びかけ。藤原実定の〈郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる〉(『千載和歌集』一六一)を踏まえた。四首目の作者は信安。一声が嬉しい例として産声と初声を挙げる。四句の「うゐ」は「うひ(初)」、「ゐ」と「ひ」は問わない。そして伊呂波歌の「うゐ(有為)」で結句の「山」(有為の奥山)に続けた。
夏の夜はとにつけかくうにつけてしも団(うちは)社(こそ)よきつかひ物なれ
飛(び)火なら幾度袖を払はまし螢みたるる宇治の川はた
昼ぬれは蠅集(ま)りつよるは又是のみならすかかるめいわく
賤かやは蚊をふすへぬるけふたさに狸ねいりもならぬ夏のよ
一首目の作者は愛宗、無題である。二句は「外につけ仮寓に」を表の意味として「仮寓」に「蚊喰う」(歴史的仮名遣いなら「かくふ」となる)を掛けた。三句の「し」は副助詞で字数を補った。結句「使ひ物」は使って役に立つ物。二首目の作者は金門、詞書は「宇治にて」。初句「飛(び)火」は火の粉が飛び散ること。また、その火の粉。三句の助動詞「まし」は反実仮想、したがって結句の「はた(端)」に「肌」が掛かる。三首目の作者は半笑、題は「蚤」。四句「のみ」に蚤が隠れている。結句に「かか」で蚊が二匹、「是」(蠅)を加えて「めいわく(迷惑)」(困ること)なのだ。四首目の作者は之時、題は「蚊帳」。初句の「賤が家」に「蚊帳」を隠すが、歌は蚊帳のない家である。そこで蚊遣火となるが材料は草木の葉、三句の「ぬる」が「寝る」に見えても煙たくて眠れない。下句、その縁で狸の登場となった。
|
| 第80回 銀葉夷歌集(3) |
みるからにひれある人の家ゐには玄関口もささてさし鯖
方碩(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第三秋歌、一〇七首。掲出歌の詞書は「百首歌中に玄関刺鯖」。「刺鯖」は背開きにした塩鯖二尾を一刺しにした盆の贈答品、二句の「ひれ(鰭)」は魚の鰭、また貫禄や羽振りのことを云う。三句「家ゐ(家居)」は「家」、「ゐ」は字数調整だろう。結句は「篠で刺し鯖」、そして「然然で刺し鯖」。これこれ、しかじかと刺鯖の山が築かれるのだ。
なき玉の今宵くるくるくるくるとまはり灯籠ともしてそまつ
聖霊のちさうのためにそなへ置(く)瓜もなかこは仏ならすや
御法度の踊(り)の太鼓うつやそのてれつくてんのはちそあたらん
秬にあらず稗にもあらて畑際にほにほのそふる薄なりけり
一首目の作者は行風、詞書は「玉祭」。「玉」は「魂」と同語源、『日本国語大辞典』で「魂祭」を引くと用例に「玉祭」とある。その「玉」が帰って「来る」と「玉」が転がるさまをいう「くるくる」を重ねて四句「回り灯籠」を導く。影絵が主役のようだ。二首目の作者は伯水、詞書は「百首歌中に玉祭瓜」。四句の「なかご(中子・中心)」は瓜の種子を含んだ柔らかい部分、また堂の中央に置くところから斎宮の忌み詞で仏の意となる。三首目の作者は光友、詞書は「躍(り)法度と有(り)し年に」。初句「法度」は法令、ここでは禁止されていること。結句の「ばち」は太鼓を打つ「桴」とその見返りとしての「罰」を指す。四首目の作者は方碩、詞書は「百首歌中に畑際薄」。初句「秬(きよ)」は黒黍(くろきび)のこと。四句は「穂に穂の添ふる」。初二句で二つの作物を提示して否定、四句で擬して、結句で正体を明かした。
雲の浪こいて出(で)ぬる月の船の棹になりてやわたる鳫かね
出(づ)るより西へいるまて時付(け)のときをちかへぬ月の御船(みふね)
月弓(つくゆみ)のはすの違(ひ)しやくそくはひくにひかれぬ用とおほせよ
月弓のひくにひかれぬ用そとてやくのちかふは大はすそかし
一首目の作者は伯水、詞書は「百首歌中に月前鳫」。三句「月の船」は空を海、月をその海を渡る船に喩えた。四句「や」は反語、月を背景に雁が列をなして飛んでいる図、すべてが見立てなのだ。二首目の作者は満永、詞書は「月」。三句「時付(け)」は時刻を指定すること、空の御船の発着に乱れのないことを云っている。結句が六音の例である。三首目の作者は伯水、詞書は「ともなふ人の方へ月みにまからんと兼(ね)て契りしにさはる事有(り)けれはかく申(し)つかはしける」。初句「月弓」は「月弓尊」(月の神)また「槻弓」(槻の木で作った弓)とも同音である。弓の縁語でもある「筈」を効かせながら四句、さらに結句「おぼせよ(思せよ)」と断りを入れた。四首目は、その「返し」である。作者は方碩。「ひく」の多義性を受けて結句「大筈」(無責任なこと)というどんでん返しで一矢報いた。
|
| 第81回 銀葉夷歌集(4) |
天下一いふはかりなき名の月を目にかくる社(こそ)ことはりよなふ 太女(『銀葉夷歌集』)
巻第三秋歌の続き。掲出歌の題は「八月十五夜」。『銀葉夷歌集』の入集歌人は二〇九人、うち女性は六人。次に入集歌の多い順だが伯水の九十五首、方碩の七一首、愛宗の五五首、友和の三五首、太女の三〇首と続く。作者は有力歌人なのだ。二句は副助詞「ばかり」に「秤」を潜ませる。成句「目に掛ける」(目にとめる)の別意「秤に掛ける」の否定に拠った。
真白にて丸う見事なもち月を申さは是もてん夜もの也
月々の月の鼠の算用はひき残(り)てや有明のそら
みあくれは八坂の塔の九輪(くりん)迄たた一りんの月にかかやく
淀川の月の光ものりあひの船賃にをく露の玉かも
一首目の作者は方碩、題は「八月十五夜」。二句の「丸う」は「丸く」のウ音便。三句「もち」は「望」と「餅」、結句「てん」は「天」と「店」と同音異義語である。二首目の作者は信安、題はなし。二句「月の鼠」は月日が過ぎていくこと、次の「鼠の算用」(鼠算)は急激に増えていくことを喩えた。後者の足し算の結果を前者で引き算しても、まだ「引き(匹)残りて」「有明」というのだ。三首目の作者は貞林、題は「八坂月」。二句「八坂の塔」は京都市東山区にある法観寺の五重塔、三句「九輪」は、その頂上を飾る輪をいう。四句「一りん」は満月のほかに一個の車輪をいい、満月(一輪)によって九つの輪の各々が輝く景となる。四首目の作者は伯水、「題しらす」。三句「乗り合ひ」に「同じ乗り物に一緒に乗ること」と「乗合船の略」の両意を掛けた。渡し場はすっかり秋、草の上に置く露が船賃だった。
猫足の膳部につかふはつものはちちちと計(はかり)鼠茸哉
をし折(り)て給(は)りたれはゑほしかきその味(は)ひをかふりてそ知(る)
籠の内に思ひを入(れ)てをくらるるかたしけなしの心也けり
まつかいに紅葉は色に出(で)ぬるを詠(ながめ)る人は面白しとや
一首目の作者は重栄、題はなし。初句「猫足」は膳などの脚の下部が猫の足の形に似ているものをいう。結句「鼠茸」はホウキタケの別名。三句「初物」に類音の強者を効かせ、少しの意に鼠の鳴き声を掛けた。二首目の作者は政栄、題詞は「柿の枝折(しおり)を得て返事に」。柿は烏帽子柿。初句「をし」は動詞に付いて意味を強める接頭語、柿にも帽子にも掛かる。結句は柿が「齧る」で烏帽子は「被る」の同音異義語となる。三首目の作者は伯水、題は「梨を得て返事に」。技巧としては四句「かたじけなし」に「梨」を掛けた。あるいは二句「思ひ」は「重い」であるか。いずれにしても結句「心」を重視した作である。四首目の作者は太女、題は「紅葉」。初句「まつかい」は「まっか」に同じ。平兼盛の「しのぶれど」(『拾遺和歌集』六二二)なら「物や思ふ」と尋ねるのだが、こちらは逆に赤と白の対比の妙に還元した。
|
| 第82回 銀葉夷歌集(5) |
下くくり畳のへりのあはひよりたつ風の手を敷(き)ふすま哉 金門(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第四冬歌は全七七首。掲出歌の題は「衾」。初句は「下潜り」だろう。床の下から畳の縁と縁の間を通って風が入ってくる。衾は体にかける夜具。下に敷くのは褥、のちに敷き衾。上下一対で現在の布団となる。したがって結句の「敷ふすま」は後者の意味で解したい。四句「風の手」を「敷き伏す(ま)」(組み伏す、組み敷く)のである。
人とはぬ隠居の門ををとつるる風のみやけは木(の)葉成(り)けり
中々に火桶といはん水桶に手をさしみれは厚氷哉
わたりてもなき山川にをのれのみはね橋かくる雪折(れ)の竹
銭蔵といははやいはん火燵にはあしにおあしの集(ま)りてあり
一首目の作者は伯水、題は「百首歌中に隠居落葉」。老いという現実を一つの典型として描いてビジュアル、残酷なぐらいだ。それを支える手法は風の擬人化にあった。二首目の作者は信安、題は「氷」。「水桶」が「火桶」になる根拠は「厚=あつ=熱」という音の共有、そして熱さと冷たさと性質は両極端であるが耐え難い程度において「中々に」(むしろ、いっそのこと)なのだ。三首目の作者は重香、「題しらす」。初句は「渡り手も」。二句「山川」は山中を流れる川、サンセンとヤマガワがあるが脇役は地味な音の前者を採りたい。四句「跳ね橋」は城の入り口などに設ける橋すなわち結句「雪折(れ)の竹」となる。四首目の作者は信安、題は「火燵」。初句「銭蔵」は銭を貯えておく蔵。二句「云はばや云はん」、見立てである。火燵の足に人の足、四句は助詞の「に」で強調、足も御足も銭の謂いでもあった。
商(ひ)の片手に案しつつくるは節季仕舞(ひ)と元日の歌
柊にて鬼か目をつくそのひまに福徳神や内へいりまめ
福は外鬼は内へと節分の豆をは誰もいるまやう也
福は内へ煎(り)豆蒔(い)てもてなすをひろひひろひや鬼はいぬらん
一首目の作者は藤原貞因、題はない。四句「節季仕舞い」は節季(ここでは歳末の意)の総決算をいう。初句「商(ひ)」は菓子商の鯛屋である。本業の傍ら旧年の決算と新年の歌を「案じ続くる」日が続く。二首目の作者は一飛、題はない。初句「柊」、成句に「柊を挿す」がある。節分の夜、魔除けのために鰯の頭を付けた柊の枝を門口に挿した。四句「福徳神」、福徳は幸福と利益、福の神では足らなかったか。結句は「煎り」に「入り」を掛けた。三首目の作者は貞林、題はない。註の「世話」は結句の「いるまやう(入間様)」を云う。入間詞すなわち逆さ言葉である。だから福の神も鬼も「いるまやう(入る迷ふ)」(仮名遣いは不問)なのだ。四首目の作者は宗長法師、題はない。結句「去ぬらん」、いきがけの駄賃というか、相伴に与れなかった鬼の退場が滑稽に描かれている。今と違って節分は大晦日だった。
|
| 第83回 銀葉夷歌集(6) |
君か代の久しかれいと祝ふてふ書(き)初(め)に先(つ)めてたく歌詩句 方碩(『銀葉夷歌集』)
巻第五賀付神祇歌は六一首。掲出歌の題は「春祝」。二句は「久し」の命令形に終助詞の「い」が付いた。その「かれい」に「嘉例」(めでたい先例)を重ねた。結句「歌詩句」は和(狂)歌と漢詩と発句、読みは「かしく」で「かしこ」の音変化、「可祝」とも書くらしい。
卯の年の卯の月卯の日卯の時にうけに入(る)こそうれしかりけれ
よろこひのをりへに酒を呑(む)人の顔に紅葉の賀をもたしけり
近江なるつくま祭にみつちやつらふのやき鍋をかつき社(こそ)せめ
一首目の作者は愛宗、題は「春祝」。句頭が全て「う」。四句の「うけ(有卦)」は陰陽道で干支による運勢が吉運の年回り、「有卦に入る」で有卦の年回りに入ること、七年続くのだという。ちなみに滋賀県大津市の三尾神社の神使は兎である。手水も兎である。その三尾明神は卯年卯月卯日卯の刻卯の方向に出現したのだそうだ。二首目の作者は知秋、題は「紅葉の賀に」。紅葉の季節に催す祝宴である。二句「織部」は「織部杯」、これに織物や染め物を扱った古代の「織部司」を重ねた。結句「賀を」に「顔」を掛ける。酔って顔が赤いのだ。三首目の作者は春澄、題はない。三句は「みっちゃ面」で痘痕のある顔。四句は、あるとも思えないが「斑の焼き鍋」。滋賀県米原市の筑摩祭は日本の三大奇祭、千年の歴史を持つ。
とむるかひ泪の袖もたつひさのさらはとたにもえいはさりけり
またやかておめにかからん天秤のさらはさらはといひ別(れ)つつ
高荷をはやれそれやのいて通せよとをふやはいしい道中の馬子
高砂や此(の)浦舩の乗合につれのおほきそ脇のさまたけ
次に巻第六離別付羇旅に移る。全五〇首。一首目の作者は休甫、題はない。二句「泪」に連語「無み」(無いので)を掛ける。三句「たつ」は袖を「裁つ」(関係を「絶つ」と同語源)、さらに旅「立つ」意となる。四句「さらば」は感動詞で別れの挨拶、これに接続詞「それなのに」を重ねた。結句は「云わない」「云えない」。二首目の作者は正盛、題は「百首歌中に」。四句に揺れる天秤の「皿」が二つ、秤に掛けることを「目に掛ける」というが二つの皿が水平になるときを「御目に掛かる」、「またやがて御目に掛からん」となる。三首目の作者は顕興、「題しらす」。初句「高荷」は馬の背に高く積み上げた荷物、それを積むところである。二句「やれそれや」口やかましく「退いて通せよと」どかして「負ふや」負うたら、である。「はいしい」は手綱に代わる人語だが相手が馬に変わると響きもやさしい。四首目の作者は貞林、題は「百首歌中海路」。初句から二句「此(の)浦舩」までは謡曲「高砂」の一節、三句「乗合」は「乗合船」の略、四句「つれ」は船客の「連れ」に「ツレ」を掛ける。結句は混雑の意、また「ワキ」にとって補助的な役のワキツレが演能の妨げになることをいう。
|
| 第84回 銀葉夷歌集(7) |
離別せんいやのかちやれとやかくと思案半(ば)の子はあいの釘 意楽(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第七恋歌は一九二首。掲出歌に題はない。二句は「いや(嫌)」と「がち(月)」(「頑痴」の音変化で「野暮」)を助詞「の」と副助詞「やれ」で並列する。「嫌とか野暮とか」である。結句「あいの釘」は「合釘(間釘)」の四音に「の」を挿入して五音、両端のとがった釘、板と板を接ぎ合わせるのに使う。愛憎半ばの「愛」を「合」にを掛けた。
恋こかれ儒学もやめて千話文をかくたりけんたりねたりおきたり
春の夜の一夜もさそな長あくひああすうあすと待(ち)こかるらん
まてといひて又くることのならぬとはやらめいわくの糸ふしんなり
一首目の作者は宗意、題は「寄儒者恋」。三句「千話文」は「痴話文」。四句の「赫たり喧たり」は『大学』(講談社学術文庫)の伝三章の詩句、威儀をいい、結句の「寝たり起きたり」と対句になっている。「赫」に「書く」を掛ける。二首目の作者は伯水、題はない。結句は現在推量の助動詞「らん」、待っているのは女と読む。すると二句「さぞな」は「さだめし」「きっと」。四句は「長あくび」のオノマトペに「明日」を掛けた。三首目の作者は愛宗、「題しらす」。初句「まて(待て)」(真手=左右の手)、二句「くる(来る)」(繰る)、四句「やら」は感動詞、「めいわく」はどうしてよいか迷うこと。結句「いと不審なり」(糸ふしんなり)で、片や恋の歌なら、片や二人で糸を巻き直している光景となる。「糸ふしん」の「ふしん」は同音異義語の選択で悩むが「糸婦人」と解した。この場合「又」は「まだ」だろう。
引(き)よするいとしい君よ三味線のこまいといふは何のはちそや
さいならは五三のうらの恋といはん四の二物をそ思ふそれかし
我恋はちきの棹かやふらるれはおめにかかりて猶思(ひ)ます
一首目の作者は粧色、題は「寄三味線恋」。引き寄せているのは男、引き寄せられているのは女。四句は「こまい(小舞)」に「来まい」を掛け、結句「ばち(撥)」に「罰」を掛けた。濡れ場だ。三味線と小舞が一緒になるのは歌舞伎舞踊の一形式である拍子舞である。二首目の作者は宗兼、題は「寄双六恋」。初句は「賽」、これに「妻」を掛けた。二句「五三」は賽の目、そして「五三の君」(京都島原の最高位の太夫の異称)を掛ける。「うら(裏)」に同語源の「心」を掛け、三句「恋」には乞目(出てほしい賽の目)の「乞い」を掛ける。「裏」は双六で後から賽をふる番、結句「四の二」は四と二が同時に出ること、これに副詞の「しのに」を掛けた。作中「それがし」の恋である。三首目の作者は方碩、題は「寄知斤恋」。「ちき(知斤)」は「ちぎ(扛秤・杠秤)」に同じ、大型の棹秤である。棹の一端に受け皿がある。その近くに支点があって物を乗せると反対側が上昇する。棹が平行になるまで重りを加えていく。平行になったところが四句、目に掛けるだと量る意、結句は「思ひ増す」となる。
|
| 第85回 銀葉夷歌集(8) |
物さしのさしてそれとはいはすとも寸の情(け)をかけて給(は)れ 方碩(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第七恋歌の続き。掲出歌の題は「寄物指恋」。二句「さして」は物指しで寸法を測る意に副詞の「さして」(「たいして」、あとに打ち消しの語を伴う)を重ねて四句に繋ぐ。その「寸」は縁語で長さの単位、これに僅かの量の意を重ねて恋の歌とした。
千話をしてくらせやあののものさしの一寸先はやみの世の中
櫛のはをひけとひかねと昔より心は君によりしもとゆひ
しらすなよ局ならひのしも口は物いひあしき宮と社(こそ)きけ
一首目の作者は伯水、題は「寄物指恋」。初句「千話」は「痴話」に同じ。痴話喧嘩、睦言の意。二句は感動詞「あのの」。これに四句「もの」を共有して連語「なんのかのと言うこと、またそのさま」。四句は「ものさし」の縁語「一寸」で成句「一寸先は闇(の世)」だものとなる。二首目の作者は太女、題は「寄?恋」。初句から二句は成句「櫛の歯を挽く」(物事が絶え間なく続く意)の応用である。結句「もとゆひ」は「?(元結)」で元から結ばれていたのだ、となる。三首目の作者は源三位頼政、題は「隠傍女恋」。「知らすなよ」で初句切れである。二句「局ならひ」は部屋隣り、三句「しも口(下口)」は裏口。三句「物いひ」は噂。教えてはいけません。局続きの裏口は口さがない噂が飛び交う宮と聞いています、か。
今宵しもあふむの鳥の真似なれや互(ひ)に嬉し嬉しとそいふ
たかはしとおもふか中に秋風も今日ついたちの文月そうき
是やこの?(よめ)とり肴いたさるる魚も契(り)もおなし海老
中々に君をしらちかまししや物もんしやいもなく思ひそめぬる
一首目の作者は壺仙、題は「始逢恋」。二句「鸚鵡」を平仮名表記にして「逢ふ」を掛け、人の口真似をする鳥だから下句への展開となった。二首目の作者は重勝、題は「変恋」。初句「たかはし」は「高橋」で遊女の通り名、大坂屋太郎兵衛抱えの太夫である。初代と二代が有名だそうだが、そんな「高橋」と思ったあなたとの仲にも秋風が吹くようになった。「秋」は「飽き」、「文月」は陰暦七月の異称である。三首目の作者は方碩、題は「嫁取座に挨拶」。嫁を迎える側への挨拶である。二句は祝儀の席に出される肴の意。三句は「出ださるる」。四句の「魚」は「肴」の類義語で重複を回避、結句は偕老同穴(生きている時はともに老い、死んでからは同じ墓に入る)の「偕老(かいらう)」に海老の別名「かいらう」を掛けた。四首目の作者は伯水、題は「思」。恋歌に織物の縁語が平行して進む。初句「なかなかに」は「かえって」、二句「しらち(知らぢ)」(白地)、三句「まし(形容動詞の「まし」)」(麻糸)、「じや」は「である」の語尾「る」が脱落した「であ」の転、四句「もんしやい(問題)」(「紋紗(い)」、また「しゃいも無く」(わけもなく)、結句「初めぬる」(染めぬる)となる。
|
| 第86回 銀葉夷歌集(9) |
お小袖はいくつめすともとにかくにかりにも妻を重ね給ふな 重勝妻(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第七恋歌の続き。掲出歌の題は「妻の旅に有(り)しころ小袖をくるにそへて」。何の旅だろう。夫は家で留守番となる。四句の「妻」は小袖の縁から「褄」そして「妻」だろう。柔らかく「重ね着はいいけれども浮気は駄目ですよ」と釘をさした。オ段を中心とした調べが快い。作者の入集はこれのみ、夫の坂本重勝は十二首が入集している。
千話文をむすふ契(り)はもろともに思ひまいらせ候(そろ)へく候(そろ)
山賤(やまがつ)の垣ほにかこふわれ竹のよませになとてあひみ初剣(そめけん)
別(れ)ても肌身にそはんと計(はかり)にそもしのお名を入(れ)ほくろ哉
君とわれぬる間もなくてしらしらとけさの別そ名残おしろい
一首目の作者は伯水、題は「互思恋」。初句「千話文」は恋文、艶書。二句は「契りを結ぶ」の応用。四句「まい(ゐ)らせ」は補助動詞で謙譲の意を表し、結句「候へく候」は「候」に同じ、女性の手紙文に用いられた。二首目の作者は光俊朝臣、藤原光俊(一二〇三~一二七六)である。題はない。初句「山賤」は作中で謙遜してみせた。二句「垣ほ」は「垣穂」で垣根、四句「よませ」は「夜交ぜ」で一晩おき、「なと(ど)て」は「どうして」の意。三句は垣穂の材料かつ「娘」を指すのだろう。必要以上の謙遜は、むしろ偏屈な性格を想像させる。右は『新撰六帖題和歌』と『夫木和歌抄』に見える。三首目の作者は一十、題は「別思」。三句「そもし」は「其文字」で二人称の代名詞、あなた。結句「入れ黒子」は入れ墨、腕などに彫る。二句から三句の句またがりが印象に残る。四首目の作者は正恵、題は「別思」。二句「ぬる間」は「寝る」の文語形「寝(ぬ)」の連体形、三句「しらしら」は「と」を伴って夜が明けていくさま、結句は「名残惜し」の「惜し」に「白粉」を掛けて後朝とした。
誰も此(の)下女か化粧を笑ひけりうふけ交りの際墨をして
今からはせまいといひて又しては又してはまたりんきいさかひ
世をそむく柴の編戸のかけかねの思ひはつせは人そ待(た)るる
一首目の作者は行重、題は「化粧」。四句「際墨」は髪の生え際を墨で縁取ること、久清に〈油墨てけはふ額のかかり社(こそ)瓦燈口にし能(よく)にたりけれ〉がある。瓦燈口(かとうぐち)はアーチ状になっている。うぶ毛を剃ってこそ美しいのである。二首目の作者は方重、題は「悋気」。二句「せまい」はサ変の動詞「す」の未然形に助動詞「まい」で打ち消しの意となる。この時代は悋気講もあった。尾母音アの駆使とリフレーンが妙味である。三首目の作者は信実朝臣、画家で歌人の藤原信実(一一七六~一二六五ころ)である。題はない。三句から四句の「かけかねの思ひ」は掛け金のような思い、もう少しいえば掛け金となっている思いで初句を受ける。その掛け金さえ外せば人に待たれているのだ、となる。
|
| 第87回 銀葉夷歌集(10) |
夜を寒みねさめてきけは孫そなくすかしもあへすははやをくらん 一瓢(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第八雑上、付物名・折句。全七九首。掲出歌は「題不和」。初句の「み」は接尾語、口語だと「夜が寒いので」、以下「眠りからさめると孫が泣いている」。四句「すかし」は動詞「賺す」(言いまぎらわす)の連用形、これに連語「あへす(敢へず)」(しきれないで)が付く。結句「母や置くらん」、そのままにしているらしい。舅の想像である。
海あれは数の子もありそれよりそ魚をはととといひ初(め)に劍(けん)
堯の世といふへき今の国民もよきしゆんを得て植(ゑ)る物種
御馳走は卯(の)花いりのいかほともあかぬ料理を玉川の里
一首目の作者は愛好、題はない。二句「数の子」はニシンの卵巣を乾燥または塩漬けにした食品。四句「とと」は幼児語で「魚」それに子供が父をいうときの「とと」を掛けた。言葉のマジックである。二首目の作者は重香、「題しらす」。初句「堯(尭)」は中国古代の伝説上の聖王、その時代に比すべき世の中、これが枕である。結句「物種」は穀物や野菜の種。一首は「しゆん(旬)」を得て種を蒔く風景である。その「旬」に尭を継いだ「舜」を掛けている。三句の「国民」の語が新鮮に響く。三首目の作者は顕興、題はない。二句「卯(の)花」は第一に御殻、嫌にならない、そして満腹にならない「御馳走」だと云っている。第二に空木の白い花、その花が玉川の里に咲く季節と重なる。結句「玉川」は歌枕、六カ所あった六玉川だが特定する必要はないだろう。調べのよさ、特にア段とオ段が交響する。
秋立(つ)ていく蚊もおらねは子のねぬる跡よ枕よ心やすしも
ましはりをなすひの色も紫のゆかりといははひしこ成(り)けり
十月の十三束のかふらなはけさのしやうしをしる人の汁
山をやく折ふしはけに火をとしの鎧か嶽と申すへきなり
一首目の作者は不珍、題はない。初句は「立秋」の訓読、二句「いく」のは「秋」と「蚊」の両方だろう。結句は実感である。二首目の作者は藤原貞因、題はない。初二句は三句の「紫」を呼び出す序詞、三句の「紫のゆかり」は〈紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る〉(『古今和歌集』八六七)に拠った。武蔵野の雑草を海の魚に置き換えたのが「ひしこ」(ひしこいわし)である。鰯は漁獲量が多く値段も安い大衆魚であった。三首目の作者は光広卿、題は「精進日に蕪菜を得し返事に」。十三日が精進日、返事の「十三束(ぞく)」(蕪菜は「十三束(たば)」)は矢の長さ、十二束が普通だった。三句の「蕪菜」に「鏑矢」を掛けた。ナとヤの違いは愛嬌だろう。四句は「しやうじ(精進)」に「生死」を掛ける。四首目の作者は定吉、題は「芝焼(き)をみて」。三句「火をとし(火威)」は緋色の威、山だから「げに火威の鎧が嶽」と呼んだ。「芝焼き」は野焼き、歌は山焼きのイメージである。
|
| 第88回 銀葉夷歌集(11) |
銀薄かをしてる海をなかむれは只一枚の白なみの色 伯水(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第九雑下。全二一九首。掲出歌の題は「海辺眺望」。初句「銀薄」は「銀箔」に同じ。二句「押し照る」は一面に照る意、今ひとつは「押してる」で銀箔を「押して(い)る」。「てる」は「ている」の変化したものである。では昼か夜か。迷うところだが「銀薄」は月光、濃紺の空に対して海は箔を押したような、静かに波打つ夜の景と解した。
名人の歌さへ詩さへ及はしなかの冨士山のたけの高さは
高笑ひせぬもむかへは口あけてのけにそりつつみる冨士の山
あふなあふな通るもすへるねは土は高きあしたのはさへぬけ道
大井川ゐくいにきゐる山烏うのまねすとも魚はとらしな
一首目の作者は知秋、題はない。三句「及ばじな」の助動詞「じ」は打ち消しの推量、「な」は終助詞で詠嘆を表す。歌の品位や風格の丈、それに物の高さをいう丈、富士山は両方の丈を兼ね備えていると云いたいのだ。二首目の作者は重香、題はない。二句は「せぬも向かへば」、四句「のけに」は「のけざま(仰け様)に」と同じ、富士山が高いからだが自然と三句「口あけて」以下となる。そのさまを初句で「高笑ひ」と云った。三首目の作者は以仲、題は「雨の後すへりて下踏のはぬけし折からよめる」。「下踏」は「下駄」で「下駄の歯抜けし」なのだ。初句「あぶなあぶな」は「恐る恐る」、あと濁点を補って「すべる」「ねば土」「足駄」、「足駄」の歯は差し歯だから結句「歯さへ抜け道」と悲惨なのだ。四首目の作者は権僧正公朝、「題しらす」。二句は「堰杙に来居る」。「堰杙」は堰に並べて打つ杭、水を貯めるのである。そこに「いぐひ」(ウグイの古名)と三句の「山鴉」が来て居るという設定、韻を巧みにちりばめながら諺「鵜の真似をする烏」を歌にした。結句は「捕らないだろうなあ」。
鉄砲をうつの山辺の現にも夢にも雉子にあはぬきのとく
駄賃馬も是(れ)観音てこさつけいそく坂東の日をは縁日
化生とはなれをそいはん山のいも鰻になつたいなやつめなり
一首目の作者は重信、題はない。二句「うつ」は鉄砲を「撃つ」と獲物のいない「空・虚」(からっぽ、うつろ)の山辺に掛かる。三四句は慣用句「夢か現か」を逆転して現にも「夢にも」(いささかも)とした。結句「気の毒」は、きまりの悪いこと、またそのさま。二首目の作者は藤原貞因、題は「坂東の馬子詞にてよめる」。三句は「御座ります」相当句が訛ったものだろう。四句の「そく」は接続詞の「即」(すなわち)と読む。観世音菩薩の多様な姿の一つとして初句「駄賃馬」が登場、物を乗せて(酒代等の)縁を結ぶ、と解した。三首目の作者は宗仙、題はない。初句「化生」は化け物の意。三四句は「山の芋が鰻になる」。結句は眼前に八目鰻がいる、だから「否」と起こした。俗説を弄ぶ図ないし慣用句で遊んだ。
|
| 第89回 銀葉夷歌集(12) |
ひねつてもきかすかるたをうつけたら切(つ)てすてふそつんとたしなめ 愛宗(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第九雑下の続き。掲出歌の題は「かるたすきし子の親いさむるを聞(き)てその遊ひの詞にてよめる」。「かるた」は花札であろう。二句で句割れ、すなわち「拈っても聞かず」続けて「カルタを空けたら」(「を」は詠嘆かつ語調を整える文中用法。「空ける」で気が抜けたようになる。「たら」は助動詞「た」の、口語だから仮定形)。四句「切(つ)て捨てふぞ」の「ふ」は接尾語と解釈、意味は「切ってしまうぞ」。結句は「ずんと嗜め」(すっかりと慎みなさい)。「切る」「捨てる」が花札用語、しばらく更生は望めそうにない。
今そしる二見の浦の蛤を貝合(せ)とておほふなりけり
使(ひ)には骨おりとこそいふへけれもらふ肴はくらけなれとも
あはらやのあるるをままの天井は下にゐるさへねすみなりけり
一首目の作者は西行上人、題はない。初句切れ「今ぞ知る」とは都でしていた貝合わせ、あれは二見の浦の貝を伏せていたのだった、ということである。ちなみに日文妍の和歌データベースで「はまくり」を検索すると十三件がヒットする。歌集名では『夫木和歌抄』『山家集』『歌枕名寄』『散木奇歌集』『小野宮右衛門督君達歌合』、どうやら勅撰和歌集の用語には不向きだったらしい。二首目の作者は光広卿(烏丸光広)、題は「海月得しおりから」。クラゲはビゼンクラゲ(備前水母)である。成句に「水母の骨」(非常に珍しいことの喩え)がある。三首目の作者は伯水、題はない。鼠は天井の裏にいるもの、それが畳にまで進出している荒ら屋の様子を歌っている。ただ不思議なのは同じ歌が『後撰夷曲集』では友信の作になっていることである。もう一例、巻第三秋歌の拍水作〈籠の内に思ひを入(れ)てをくらるるかたしけなしの心也けり〉が巻第八雑下に太女作〈籠の内に思ひを入(れ)ておくらるるかたしけなしの果成けり〉で再登場する。作者が同時代人と思われるだけに解せない。
打(つ)音もこちかちとなる碁の石のめをさますほと切(り)合(ひ)にけり
小夜更(け)て風にまたたく行灯のかけさしそゆる油つき哉
食の時よしの漆のぬり箸ははなの下へのあんないしや哉
一首目の作者は愛宗、題は「囲碁」。二句「こちかち」の固い音が対局の雰囲気を効果的に演出している。囲碁の縁語「め(眼)」は四句、「切り」「攻め合い」は結句で生きている。二首目の作者は伯水、題は「行灯」。下句は「影(が)差し添ゆる油坏かな」と読んだ。「影が差す」には「光があたる」「影ができる」それに「不吉な兆候が現れる」の意がある。「添ゆる」は「添ゆ」の連体形、「添ゆ」は「添ふ」の音変化である。「油坏」は「油皿」に同じ、油が残り少ないのだ。三首目の作者は愛宗、題は「塗(り)箸」。初句は助詞「の」を挿入して五音に調整した。吉野塗だから四句は「鼻(花)の下への」、結句は「案内者かな」。
|
| 第90回 銀葉夷歌集(13) |
国ならで傾(き)にけるつふり哉小半酒(こなからざけ)に酔(つ)てねふれは 管窺(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第九雑下の続き。掲出歌に題はない。「世話」とあるのは「傾国」(一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く)、しかし傾いたのは「つぶり(頭)」であった。三句「小半酒」の「小半」は半分の半分すなわち一升の四分の一で二合半をいう。
へうたんの内より出(つ)る酒なれと駒とはいはてむまいとそいふ
浮雲やおこし米あるかたかたにあめもふる程うるる両みせ
葉たはこを給はりたりし御礼は貴面のきさみ申すへくそろ
武蔵野やさすか上戸の盃にたらぬもわろしこすもうるさし
一首目の作者は信澄、題はない。慣用句「瓢箪から駒が出る」に拠る。結句「むまい」に「馬」と「旨い」を同居させた。「むま(馬)」「むまし(旨し)」と表記する例が見られるのは平安以降らしい。二首目の作者は方碩、題はない。二種類の食物を歌い込んだ。表の意味は二句「おこし米」(「おこし」にする「米」と解した)のある三句「方々」(代名詞で「みなさん」)に下句「雨」の降るように「飴」の売れる「店」であるよ。裏の意味は「(おこし)米ある」(米に不自由しない、の意。「おこし」は平仮名表記で影を薄めている)皆さんで賑わう「見世」(張り見世)であることよ。いずれも浮き雲の下の風景である。三首目の作者は愛宗、題は「莨?(ろうとう)得し返事に」。「莨?」は植物の名、ここでは初句「葉たばこ」と解釈した。四句「貴面」は「お目にかかること」、「きざみ」は「刻みタバコ」と「その時」の両意を掛ける。結句は「申すべく候」。四首目の作者は方碩、題はない。初句「武蔵野や」は『万葉集』の〈武蔵野の草はもろ向きかもかくも君がまにまに我は寄りにしを〉(三三七七)に拠る。「もろ向き」は、あちらにもこちらにも向いていることで下句、思案のしどころなのだ。
から笠のえしれぬ人の心をはとかくろくろになすよしも哉
手かいれは足もいるてふ世の人の?(ゆがけ)を沓にはきてみよかし
生(ま)るるを取(り)あけうはの上手社(こそ)子安の地蔵の化身なるらめ
一首目の作者は方碩、題はない。二句の「え」は「から笠(唐笠)」の「柄」に打ち消しを伴う副詞「え(得)」を掛けた。四句「ろくろ」は唐笠の中央で骨を束ねているところ。結句は「もがな」と願望の終助詞なのだ。二首目の作者は梅女、題はない。註の「世話」は「手が入れば足も入る」(一度気を許すと次々につけ込まれること)。四句「?」(弓懸)は弓を射るときに使用する革製の手袋をいう。何なら足にも?をしてみるがいい。結句は終助詞の「かし」で「そうすれば分かるはずだよ」。三首目の作者は弘誓上人、題はない。二句「取(り)上げ」は動詞として初句を受け、「姥」とセットになって複合語(「取り上げ婆」)ともなる。その上手こそが「子安地蔵」(安産をかなえるという地蔵尊)の化身だというのである。
|
| 第91回 銀葉夷歌集(14) |
恥をかくかしらをもかく事もかく真草行をしらぬ身の上 資之(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第九雑下の続き。掲出歌の題は「無筆」。「無筆」とは読み書きができないこと、その書けない人間が「かく」ものとして「恥」と「かしら(頭)」と「事」の三つを挙げる。四句「真草行」は「真行草」に同じ、漢字書体の三種である。参考だが大野晋の「日本の近代化と日本語」(岩波書店『日本語について』)によると江戸時代末期の寺子屋の通学率は約二五%である。近畿地方では半数以上が通学した集落が六〇%に達していた。
くつれそふ破れついちの犬はしりふまへ所もなき我身かな
徒(いたずら)に打(ち)くらしたる碁かるたのむくひか今は手拍(てびよう)編(み)笠
細工にはあらねと浮(き)をみつめきり身をもむ計(ばかり)あいた世の中
一首目の作者は信実朝臣、題はない。初句「崩れ添ふ」の「添ふ」(四段)は連体形で二句「破れ築地」に係る。破れた築地に加えて犬走りを壁土が覆っている。下句は現実と精神両面において「踏まえ所」のない作中人物である。二首目の作者は且心、題はない。初句「徒」は無益であるさま。三句の「かるた」は花札であろう。結句「手拍編み笠」は編み笠以外は何も持たないことをいう。三首目の作者は延治、題は「寄錐述懐」。釣りの場面だが初句の「細工」は「浮き」の「細工師」と読んだ。題の「錐」は三句に隠れている。四句「もむ」と結句「飽いた(空いた)」も錐の縁語、特に後者は作中人物の半生を凝縮した格好である。
高砂の尉と姥とは扶持とらて尾の上の松の掃除する何
心よくいねふるものを脇よりもなにとておこすのふは迷惑
ちきならて是も同しきふり物の雨のあかりを待(つ)問屋かな
ひくりして肝かなたねの油屋はそらにしられぬ雷の音
一首目の作者は安親、題は「能」。「高砂」で姥が杉箒、尉(老人)が竹杷(さらえ)を持って「尾上の松も年ふりて、老の波も寄り来るや、木の下蔭の落葉かく」と謡う場面がある。結句「何」、二人は松の精だったのである。二首目も安親の作、題は「能見る内暫(く)眠(り)しを人のおこしければ」(「暫(しばらく)」は演目名)。三句「脇」は能の縁語。結句「のふ」は終助詞「なう」として四句を受け、同時に「能(のう)」として結句に続く(仮名遣いは問わない)。三首目の作者は方碩、題は「問丸」。「問丸」とは中世における運送や廻漕を業とする人々の総称また問屋をいう。ここでは廻船問屋を舞台にした作品と解する。四句「ふり物」は「降り物」で雨、「振り物」で初句の「ちき(扛秤)」と繋がる。四首目の作者は貞富、題はない。初句「びくり」は「びっくり」に同じ、二句は成句「肝が菜種になる」(肝が潰れる)。四句は名詞の「空」で「空に知られぬ雷」だから使用人を怒鳴りつけた。形容動詞の「空」ならどうか。子供用の胸掛けの意のある「油屋」を子供とすると雷鳴に怯えて「うつろ」となる。
|
| 第92回 銀葉夷歌集(15) |
法華経の序品をたにもしらぬ身の八まきか末をみるそ嬉しき 平時政(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第九雑下の続き。掲出歌の題は「八牧亡ひし時よめる」。作者は北条政子の父、北条時政である。治承四(一一八〇)年八月十七日、挙兵した源頼朝の命を受けて和泉判官平兼隆を八牧の館に襲い、首を挙げたときの歌である。出典は『源平盛衰記』。初句「法華経」だが鳩摩羅什訳八巻が一般に流布している。四句「八まき」にその八巻を掛ける。
てつからこからこと打(つ)は異国よりわたれる鍛冶か槌の拍子か
切(り)艾ふし三里五里やく灸に猶あしからのはこひよからふ
うけかたし人身よりも爪の上にのせてすへぬる灸のあつさは
しひり京へのほれとならは路銭にも則(ち)そちのおあしたされよ
一首目の作者は安忠、題は「鍛冶」。初二句のオノマトペに「鉄」と「唐子」(中国風の服装と髪形をした子供)が潜む。四句「鍛冶」は鍛冶職人、下句で再びカ音を意識した。二首目の作者は方碩、題はない。初句「切(り)艾」は紙で巻き細かく切った艾。二句は「灸を駿河」の洒落から「冨士」を出す。「三里」は灸のつぼ、足の三里を指す。二音の不足を「五里」で埋めて下句の布石とした。結句は(三里でも五里でも)「運びよからう」。三首目の作者は伯水、題はない。初句切れの歌。二句に来て三帰依文の「人身受け難し」を下敷きにしていることがわかる。「爪」以下で「今すでに受く」を響かせる。当面の最大関心事なのだ。四首目の作者は貞林、題はない。「しびり京へ上れ」は痺れたときの呪文、唱えながら額に唾を三度つけるのだそうだ。「至急」ならぱ「痺り」の代償として御足(路銭)を出せ、か。
算用をしるもしらぬもをしなへてしに天作の五りんとそなる
瓦師は烟たててや無常には鬼ものかれぬたとへみすらん
一生は夢の浮世ときけはたたうたふもまふも寝言ならまし
うつものもうたるるものも土器(かはらけ)のわれての後はもとの塊(つちくれ)
一首目の作者は愛宗、題はない。四五句は旧式珠算の一つ、二十を四で割ると五で「五りん」、「りん(厘)」に「輪」を掛けて「五輪」は供養塔の意である。また「しに(四二)」は「死に」である。以下「無常」をテーマにした作品が続く。二首目の作者は之時、題はない。初句「瓦師」は瓦を焼く職人をいう。したがって四句の「鬼」は鬼瓦、鬼を荼毘に付している趣きであるが、そこが言葉のトリックというものであろう。三首目の作者は宗意、題はない。現世での謡や舞が「寝言」なのだから「寝言」でないのは来世となる。結句「まし」は上句の仮想に呼応して、それなら「だろう」の意を表す。四首目の作者は道寸、相模国守護・三浦義同(?~一五一六)。題詞は「三浦にて最後の合戦の時よめる」。相手は北条早雲、家臣百余名とともに討ち死に、一族は滅亡した。今生の別れの盃すなわち辞世である。
|
| 第93回 銀葉夷歌集(16) |
宝鐸の風にゆらるる音迄もからんからんとなるそたうとき 愛宗(『銀葉夷歌集』)
『銀葉夷歌集』巻第十釈教、作品数は一三六首。掲出歌の題は「四天王寺」(大阪市天王寺区)。初句「宝鐸」は堂や塔の四隅の軒につるす大形の鈴、風鐸のこと。読み方は「ほうたく」と「ほうちゃく」がある。拗音は滑らかに「風」に繋がるが一般的な読みとしては前者か。四句は擬音「伽藍伽藍」で寺の建物とりわけ大きな寺院をいう。結句は「鳴るぞ尊き」。
談義をはききつつ眠る人よまたこれも仏へ奉公のうち
冬も猶かたひら一重きせてやる来世とやらはいつも夏かよ
捨(て)坊主ともいははいへ世の中に髪筋ほとも望みあらねは
一首目の作者は意楽、「題不知」。初句「談義」は教典や法義を説くこと、また説法。これに「お」を付けると「お談義」で堅苦しい、つまらない話になる。どちらにしろ眠る人がいても不思議はない。三句は句割れ。以下、仏への奉公だというが枯木も山の賑わいか。二首目の作者は松月、「題しらす」。二句の「かたびら」は経帷子、仏式の葬儀で死者に着せる衣、薄い白麻で作る。結句「かよ」は連語で疑問の意をやや強く表す。ぞんざいな言い方には違いないが、そこに悲しみがこもる。三首目の作者は方碩、題は「発心」。初句「捨(て)坊主」は生活に困窮するなどの理由で出家した人、また坊主を嘲笑する語。「発心」なくして現実生活の救済を願ったのであろう。初二句の句またがりに絶望の深淵と居直りを見る。
やすいこと願にかけてん二王殿わらちは二そく三もんのまへ
煩悩の犬は地獄の鬼よりもこはき物そとおもほゆる哉
魚はくはれ成仏するときく物を精進やたた人の悪行
なむをみやたうふたうふの声たてて皆彼(の)岸へよふね也けり
一首目の作者は長屋、題は「二王に祈れは力出ると云(へ)は」。初句「やすい」は「易い」に「安い」を掛ける。二句「掛けてん」の「てん」は連語で意志と希望を強調した。三句「二王」は「仁王」に同じ、四句「草鞋」は仁王門に付きものである。下句の「二そく三もん」は「二束三文」、「そく」に「足」、「もん」に「門」を掛ける。草履を奉納して仁王力を授かるのである。二首目の作者は方碩、題はない。俚諺に「煩悩の犬は追えども去らず」がある。四句「こはき」は「恐き」よりも「強き」であろう。感心するのは結句に「ほゆる(吠ゆる)」が隠れていることだ。三首目の作者は貞林、題はない。上句は捨身供養をいう。「それならば」が下句であろう。四句「精進や」で句割れ、「ただ」で歌い起こされるとき厳然として悪人正機説が光る。四首目の作者は言因、題は「亡母孝養の一夏九十首の中に」。「南無阿弥陀仏」を洒落て「なむおみどうふ」、これに「や」を挟んで律読に配慮したか、あるいは実際のニュアンスであったかも知れない。結句「よふね」は彼岸へ「夜船」(「よ」に「寄」が響く)。
|
| 第94回 大団(1) |
おとこ山詞の花は散(り)ぬれど猶頼みあり武さしのの月 言因(『大団(おおうちわ)』)
『大団』の著者は黒田月洞軒(一六六〇~一七二四)、歌数は二二五七首、うち「大団一」は四五一首。『狂歌大観』の「備考」によると「月洞軒自筆の稿本と推定されている。元禄元年より十六年暮に至る日々の詠草の書留で、巻二が闕けている」。さらに『日本古典文学大辞典』(岩波書店)で補うと月洞軒は知行高千二百二十石の旗本、妻は水野忠久の娘である。掲出歌は若き日の鯛屋貞柳(一六五四~一七三四)の作、詞書に「恐(れ)なからよみて奉りける」とある。師事した豊蔵坊信海の死後、兄弟子にあたる月洞軒に贈ったものだ。これに対する返歌は〈いや我はあづまのゑびす歌口もひげもむさむさむさし野の月〉だった。
師匠なきてがらとなりてはやみとせせめて手向(け)むわが歌の作
右の詞書は「男山玉雲翁三回忌の追善狂詠七首の中」、言因の歌と同じく元禄三年に入っている。次に「大団四」の元禄七年に詞書「九月十三日信海七年忌ついぜん」で〈狂歌よむひともむかしの男山げにもなまきになたまめ名月〉がある。さらに捲ると「大団七」の元禄十三年に「八幡豊蔵坊十三回忌追善名号書(い)て手向(け)て」の詞書で〈はや今宵年も十三ねんごろに月の夜ねぶつ手向(け)申(す)ぞ〉がある。二年目が三回忌、十二年目が十三回忌だから信海の没年は一六八八年九月十三日になる。元禄は九月三十日からで年号ならば貞享五年である。したがって起筆の年に詞書「信海八幡へ明日かへるといひこされければ」の歌があるが、これは『信海狂歌拾遺』の晩年の歌から見ても、元禄元年(貞享五)以前の作と考えるのが自然であろう。ではなぜここにあるのか。『大団』執筆の契機が師の死にあったからである。そこには歌の継承者としての強烈な自負、八幡神を介した旗本の同朋意識があった。さらには体質的にも近いものがあった。その愛から『大団』は始まるのである。
なには江の藻にうづもれて居はせひでよしなき歌のゑらひだてかな
けに玉の雲の翁か狂歌をはかかやく月の洞にとへかし
玉のやうな月はむさしに有(る)ものをたのまでくらき雲の洞かな
「大団三」に詞書「極月九日に珍菓亭雲洞か本より八幡拾遺といふ集ゑらふとて下書(き)到来せし時心に叶(ひ)侍らねは」で三首載る。元禄六年十二月、言因が雲洞に変わっている。その雲洞が信海(玉雲翁)の狂歌を後世に伝えるために『八幡拾遺』を編んだ。それが気にいらない。一首目はにべもない拒否である。二首目と三首目、露わな自尊心がこれを許さないのだ。この年、月洞軒三十四歳、雲洞こと言因は四十歳であった。のち貞柳は『家つと』『続家つと』、遺歌集『置みやけ』を刊行する。一方の月洞軒に刊行歌集はない。衣鉢を継ぐという意味でなら三代四度の試みの末に信海歌集『狂歌鳩杖集』を残した貞柳に対して、自恃という孤塁の中で信海を永遠に葬った月洞軒、その分岐点は『八幡拾遺』にあった。
|
| 第95回 大団(2) |
山のかみおこぜにあふたここちしてあたらさくらをちらと見たとな 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
掲出歌は『大団一』所収、元禄三年の作である。詞書に「めの女の花見に行(く)に用所あり早々かへりければ」とある。「めの女」は妻、山の神である。「用所」は厠、厠に行きたかった。御伽草紙の「をこぜ」(小学館『日本古典文学全集 36』)の最後に「あながちにものを見て、喜ぶをば『山の神にをこぜ見せたるやうなり』とぞ申し伝へたる」とある。惜しいことに桜を見たのはちらっとだったが、それでも喜んで帰ってきたというのだろう。
山の手に宿はありつつ祝日のやつ子のこのこの五色餅かな
さして扠何の風ぜいもなき宿ののきばをとふてお気のつきかげ
うれしさはどふもなりませぬつと出た花の木の間の月を見さいの
をめいこにぼぼしたばちやあたりけんつゐにじむきよで死なれまらつた
一首目は元禄元年の歌。題は「賀」、加えて「月洞女ノ十九歳」。初二句は「妻はありつつ」と読める。「やつ子」は遊女、四句「やつ子のこの子の」に連体詞の「この」を効かせて結句の「五」に繋げた。題の「女」は愛人の意と解した。二首目からは元禄三年、詞書は「月ののきもるをかくなむ」。初句の「さして」は「とりたてていうほど」の意、それに「(月が)差して」を掛ける。四句「とふて」は「訪ひて」のウ音便、結句は月の台詞である。三首目の題は「花間月」。二句の最後の「ぬ」と三句の最初の「ぬ」が重複、つまり共有することで月の出を劇的に表現した。結句「見さい」は「見なさい」の意。四首目は詞書に「さる法花宗のじむきよにてしなれければはやり小うたをたて入(れ)てついぜむにかくなむ」とある。「じむきよ(腎虚)」は房事過多による衰弱、「立て入れる」は流行歌などの詞を詠み入れること、月洞軒の得意とするところであった。初句は女陰の俗称だが「をめいこ(う)」(御命講)で日蓮の忌日に行う法会。二句「ぼぼ」は性行為、結句に「まら(魔羅)」を隠した。
あさ夕はどこやら風もひやひやとお月さま見て秋をしりました
むかし見し栄花の夢もかくやらんさまにあふたは遺精也けり
そちも無事こちも無事にてまつの葉ぞかへれかきの葉もどれももの葉
一首目の題は「初秋月」。二句の「どこやら」は「何となく」しかし確かにそうだという感じである。四句「お月さま」は月を敬い親しんでいう語、和歌には登場しない。二首目の題は「夢中恋」。上句は思春期の頃の妄想か。再び訪れることのない時間という意味において、そしてその頃と変わらなかったのは、となる。池田正式に「朝立ち」の歌があったが、こちらは「夢精(遺精)」の歌である。三首目は詞書に「直清が旅行の時かく云(ひ)やりける」とある。初二句の対句的かつリフレインの効果は「松」「桃」「柿」を使っても同じく巧みである。月洞軒の名は直常、父は直相、直清は歌仲間にして縁戚であったかも知れない。
|
| 第96回 大団(3) |
弟子も弟子たぐひあらじの歌の弟子弓矢八幡八幡(やはた)御坊の 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団一』の続き。掲出歌の詞書に「雑の歌続ける集の末に」とある。四句「弓矢八幡」は弓矢の神である八幡大菩薩。武士が誓約するときの語で「八幡」は音読み。結句の「八幡御坊」の「八幡」は石清水八幡宮の意で訓読み、「御坊」は師の信海を敬ってこう呼んだ。倒置法で初句にもどる。絶大な自信には月洞軒が旗本であったこと、また豊蔵坊が幕府の祈?所であったことも関わっていた。このほかに性格もあっただろうし、歌において長じていたこともあっただろう。信海の没年時は六十三歳、月洞軒二十九歳、言因三十五歳、但し『狂歌大観』所収の『豊蔵坊信海狂歌集』『孝雄狂歌集』等に月洞軒の名は見出せない。
さのみにはもうそもうそとゆてくれそいまでもかほのあかふなる事
河波にばつとはなせば鵜の鳥がこぶなくはへてぶりしやりとする
おもひ出(づ)るおりたけぬかの夕煙むせぶもうれし蚊めがをらねば
一首目の詞書に「恨(み)がちなる人へよみて送(り)ける」とある。初句「さのみ」は「それほど」の意で、あとに打ち消しの語を伴う。二句は「申そ(う)申そ(う)と」。三句は「ゆ(う)てくれそ」。係り結びの「な」が脱落しているが「そ」で制止の意を表す。顔の赤うなる事とは何か、弱味を握られているのだ。二首目の題は「鵜河」、ここから元禄四年である。二句「ばつと」は鵜飼いに使われる鵜が一羽や二羽でないからだろう。四句は収穫の「小鮒」をクチバシで加えているところ、結句「ぶりしやり」は辞書に「すねるさま」とある。水面に上がってきたときの首を振ったりする鵜の動きを云っているのだ。三首目の題は「蚊遣火」。本歌は後鳥羽院の〈思ひ出づる折り焚く柴の夕煙むせぶもうれし忘れがたみに〉(『新古今和歌集』八〇一)である。どこが違うのか。二句、いぶすのが目的だから「折り焚けぬ、かの」となる。「かの」は苦し紛れだが、結句の「蚊」に免じて良しとしよう。
軒にきて鳴(く)音やかまし長ざほでてうどうつせみうちころせかし
むしやくしやとしげれる庭の夏草の草の庵もよしや借宅
妹とわがぬる夜たがゐに目があけばへそのあたりをなでしこの花
一首目の題は「蝉」。四句は「丁ど空蝉」。「丁ど」は物が強くぶつかり合うさま、またその音を表して「丁ど打つ蝉」、長竿でばしっと打ち殺せと云っている。二首目の題は「夏草」。初句「むしやくしや」は髪などが「もじゃもじゃ」の状態、これを転用した。結句の「よしや」は形容詞「良し」に疑問や反語の助詞「や」である。「借宅」は「しゃくたく」。こうしてみると直音と拗音の違いはあるが「しや」を四回駆使して一首を構成していることがわかる。三首目の題は「瞿麦」。しかし花ではない、掛詞である。それも『後撰夷曲集』の〈撫子の花の口ひるうこくこそ風の手あててあははなりけれ〉(且保)とは対極の猥歌である。
|
| 第97回 大団(4) |
つれもなくつれあひもなくはせう葉に残れる露のうきねいとしや 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団一』の続き。掲出歌の詞書に「珍菓亭か妻におくれける時かく云(ひ)やりける」、歌のあとに「此(の)歌秋むなしく成(り)けるよし聞(き)けれは也」とある。元禄五年である。二人の交流を追うと、元禄五年に鯛屋雲洞から梅花香が送られてきて返歌、元禄六年に珍菓亭雲洞編『八幡拾遺』を読んだ三首については既述した、元禄八年は珍菓亭より梅花香が送られてきて返歌、同じく江戸の火事を心配した言因への返歌を見ることができる。今度は貞柳の『家つと』を見てみよう。享保十(一七二五)年と思われるが「黒田月洞軒より島絹下さるとて」の詞書で四首が収録されている。一首目〈つのくにのなにはの春のはなやかに伊達をしまきぬ着て遊べかし〉(月洞軒)、四句は「伊達をし巻きぬ」に「島絹」(八丈島で織られる八丈絹の意を採る)を掛けた。その「返し」が貞柳〈商人によき島絹を給(は)りて歌よみたてをするもはつかし〉、四句「歌読み立て」に「伊達」を効かせている。続けて「又ある御文のおくに」で月洞軒〈たつねきてひろき武蔵の野てつほうはなして見やれたまりやせまいに〉、四句に「弾」が配置されている。最後が「とよみて下されし返し」で貞柳〈てつほうのたまたま江戸に参るともいかてはなさん町人の身は〉の歌、いかにも対照的である。この年、貞柳七十一歳。但し、月洞軒は前年に亡くなっている。『続家つと』を見ると「狂歌二聖」として雄長老と豊蔵坊信海を挙げ、「狂歌六歌仙」に松永貞徳・平井卜養・宮川尼・黒田月洞軒・生白庵行風・由縁斎貞柳を数えている。各一首引くが月洞軒は次の歌である。
むさし野にはばかるほどの団がなあふぎてのけむふじのむら雲
「富士真行草」の一首、元禄三年元旦の試筆(書き初め)である。武蔵野いっぱいに広がるような団扇があればなあ。扇いで、あの富士見を邪魔する雲を除けてやるのだが。『大団』の由来である。また作品数からしても実質的な起筆はこの年からであったと思われる。
おみやうきなおこゑならずと初こえを先(づ)ほととぎすおらにきかせよ
蚊屋つりて蚊をばふせげど蚤がきてねいろとすればさあさしやうわる
ふともものしろきにむかしを思ふかな早苗取女(め)の尻からげして
一首目は詞書「女にかはりてほととぎすをよめる」。初句は「お妙技な」、結句「おら」は江戸語で町人の女性も用いたとある。上品さとぞんざいさが無意識に同居する。初句、二句、三句が「お」で頭韻、これにオ段も加勢して調べに貢献した。二首目の題は「蚤」。四句「ねいろ」は「寝入らう」、あとの表記は教科書通りにいかないのが近世である。結句、この性悪め、といいながら潰しにかかっているのだろう。三句の題は「早苗」。四句の「早苗取女」は田植えの前に早苗を苗代田から取る女性である。ふだん日光に晒されることがないから白い。それが水に映えて苦しいほどに眩しかった、そんな少年時代を思っているのだろう。
|
| 第98回 大団(5) |
ひえた斗(ばかり)あぢがよかろふといふはすいくはつとうちわつて見てきこしめせ 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団二』を欠くので『大団三』に移る。元禄五年と六年の作四一九首を収める。掲出歌の詞書は「板垣善兵衛方へ西瓜をくるとて」。見所は三句と四句の句またがり、しかも普通ではない。現代短歌の「語割れ」(塚本邦雄)なのだ。加えて「すい/くはつと」(現代仮名遣いなら「すい/かっと」)、「くは」(「か」)が一人二役の活躍である。西瓜を割ったときの赤い断面が目に飛び込んでくるようである。「きこしめせ」は「お食べになってください」。
きのふまで借銭こひと見えつるもけふあらためてきつとしたじぎ
めで鯛とかくつんだして柳樽やつ子こと葉でひな祝ふべい
とつと遠き海路にによつと見見(みみ)ゆるはよくよくいつかいものじやふじのね
さくらあさのあふてかたるが間遠さに花のいろいろかひて送つた
一首目の詞書は「町人の年初に来るを見て」。結句は「屹度した辞儀」、「屹度した」は「態度がいかめしいさま」をいう。いかにも改まった様子が新年にふさわしい。二首目の詞書は「娘共の方へひなやつ子鯛はりぬき柳樽など送(り)て」。「娘共の方」が気になるが、同じ上屋敷、奥方のいる奥向きと解釈する。月洞軒は表である。そのあとは「雛・奴鯛(元禄鯛)・張り抜き柳樽」と読む。「柳」は「酒」、張り子の柳樽である。ではどこが奴詞か、「つんだす」(勢いよく出す)と「祝ふべい」(「べい」は「べき」の音便の形)であろう。三首目の題は「富士」。見てのとおり同音反復にこだわった一首である。「とつと」は「はるかに隔たっているさま」、「見見ゆ」は「見もし、見られもする」、「いっかい」は「大きい」。四首目の詞書は「直清方へさくら草送(る)とて」。初句「桜麻の」は枕詞で「をふ(苧生・麻生)」に掛かる。「あふ」と「をふ」は違うが接続助詞「て」がくる場合の発音は変わらない。イレギュラーは承知の確信犯である。結句は「買ひて」に上句を受けて「書いて」を掛けた。
やれやれな今くれゑんの夕すずみちつとあつさをわすれ水うて
酒のみのひたいに夏を残しつつ秋とも見えぬ此此(このごろ)の空
千秋も半(ば)ならざるたのしみはふたりの中のよき子もち月
一首目の題は「納涼」。二句「くれゑん」は「暮れん」に「ゑ」を忍ばせて「暮れ縁」と位置を明示した。結句の「わすれ」は動詞として上を受けつつ名詞「忘れ水」で別風景に展開してみせた。二首目の題は「残暑」。上句は酒焼けである。したがって夏は残っていない、それにしてはこの暑さよ、というわけである。ちなみに元禄の江戸は総人口一人あたりの飲酒量が少なくも年四斗(一升瓶で四十本)を越えていたらしい。三首目の題は「八朔」、八月朔日は武家の祝日である。「子もち月」は十四日だから比喩、また「五月朔日」の題で〈五月空かしはの葉守神こばたたつるは玉のやうな男子〉があることを思えば贈答歌であろう。
|
| 第99回 大団(6) |
ささをもるお座がさむるときらはれて下戸の心はなんぼうやつら 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団四』である。元禄七年から八年の作品三二〇首を収録する。掲出歌は詞書に「身をうらみてよめりける」。初二句、酒の場が白けるというのだ。結句は「何ぼうや/辛」と読む。「いやはや」以外にないだろう。元禄年間の記録によると、上方から運ばれた酒の年間総量を江戸の人口で割ると約四斗、これに地場産を仮に一斗としても赤ちゃんを含めて一升瓶を月に四本強の計算になるらしい(柏書房『図録・近世武士生活史入門事典』)。いやはや。
きいたかと問へばきかぬがきいたかと客も亭主も待(つ)時鳥
きの毒ややめにしましよかしましよかのせうがのぶしの小歌ならねど
御代万歳ねがひもざつとすみ頭巾をくらるる歌よく出来まつちや
男子花はじめて開く梅じやほどにえだもさかへて葉もしげります
一首目の題は「待郭公」。亭主は月洞軒、拝領屋敷の広さは九百坪と思われる。場所は山の手、『徳川旗本八万騎人物系譜総覧』(新人物往来社)では湯島妻恋坂とある。二首目の詞書は「生姜を八月喰へはあたる無用にせよと云(ひ)こしけるかたへ」。四句「せうがのぶし」は類音の「しょんがえ節」(囃子詞が「しょんがい」「しょうがえ」等)と思われる。体に毒を「気の毒」で返した。「気の毒」に「相手に申し訳なく思うこと」「こちらも嫌になった」そんな両意だろう。三首目は詞書「直清かたより歳暮に茶の角頭巾をくるとて 万歳もおさまる御代にすみづきんかはらで君にたてまつつちやの」とある。二句の「すみ」は上から「住み」、下へは「角」、結句は「茶」の縁で「抹茶」を掛けた。「の」は終助詞。月洞軒の「すみ」は上から「済み」、下へ「角」だろう。四首目は詞書に「直重かたへ梅を掘(ら)せてをくるとて南枝花はじめてひらくといふことを」とある。このうち「南枝(なんし)(に)花(はな)始めて開く」(『和漢朗詠集』)の「南枝花」を「男子花」と言い換えた。ちなみに元禄七年の〈御返事はわざと申さぬ一声も子故と思へばなふうらめ子規〉は男の子の夭折を窺わせる一首である。
じまんくさく長尻くさらかすうちに身がひるへにはみが出(イ)づる也
喰(ひ)過(ぎ)し腹はる風にへひらんとそつとすかひてもやらくさのもち
くそざつと下りやしまのだんのうらはまべもくさくとまりこそすれ
次は尾篭な歌を三首。一首目は「題しらず」。二句の「長尻」は他家での長居、「くさらかす(腐らかす)」は不愉快にさせること。初二句で「くさ」が連続する。「ひる」は「放る」で最後は「身」から「実」が出てしまった。二首目の題は「桃源」。二句「はる」は「張る」に「春」を掛ける。四句は八音、「すかひて」は「透かす」の連用形「透かして」のイ音便と解した。結句の「やら」は感動詞で「草(臭)の餅」。三首目の詞書は「雪隠にてよめる」。一首中に「屋島」「壇之浦」「浜辺」「泊まり」(船着き場)などの語が見いだせる。
|
| 第100回 大団(7) |
夏衣ひとへに御免慮外にて御座りまらまで出(だ)されにけり 黒田月洞軒(『大団(おおうちわ)』)
『大団五』に移る。作品は元禄八年から九年の三五三首である。掲出歌は詞書に「戸村十蔵大あせに成(り)慮外ながらとてはだかになりければ」とある。二句「ひとへに」は「もっぱら」の意、これに袷に対する単を縁語として掛けた。「慮外」は「無礼なこと」、四句は「御座ります」ですむはずだったが、すまなかったのが褌からのぞく「摩羅」であった。
おごしより先におごぜんをあげられよ上はおかもじ下はおひもじ
ぼくせうとのたまふはひげこのりんご喰(へ)さへすればこちやだいじなし
わが尻をしたりやむかし恋衣かへすがへすもわすれぬか坊
一首目は「題しらず」。上品に「御」がつくのは「ごし(吾子)」(二人称、同輩である)、「ごぜん(御膳)」、「かもじ(母文字)」(妻)、「ひもじ(ひ文字)」(空腹であること、子供たちだろう)。貧乏旗本で歓待されている図であるか。二首目は詞書「ひげこにりむごを入(れ)て令少之至と口上にいひこしけるに」。「ひげこ(鬚籠)」は編み残した端を鬚のようにした籠のこと。初句「乏少と」(詞書の「令少」は「乏少」の誤記かも知れない)、結句「こちや」は「こちらは」の意。圧巻は「ひげ/こ」を句またがりで分断、「乏少」を籠の鬚に変えたことである。三首目の詞書は「日輪寺其阿久々をとづれぬとて恨(み)られければ」。四句には往年の「何度も何度も」が加わってニュアンスは複雑である。月洞軒には上方の若衆狂いに宛てた〈今こそあれ我もむかしは若衆也あふたら君はこはものであろ〉という歌もある。
いくとせも海老のめでたく鬚ながくそなた百までをれ二百まで
春の日の江戸紫のせち小袖かしてねよげにかかを見あげた
ぬのこ着て余寒ふせげどこしはひえ山の手なればかたはるの雪
ふじとわがかはすばかりのおてまくらそちは雲の手こちは山の手
一首目の詞書「近藤作左年わすれに来(た)りてはなされけるをいはふて」。下句は「御前百までわしゃ九十九まで」の「わしゃ」(妻)を「をれ」(月洞軒)にしたが「二百」は規格外である。二首目より元禄九年、題は「元旦」。三句は「節小袖」(正月の節振る舞いに着る小袖)。四句は「化して寝よげ」で「かか」(妻)がきれいに見えた。三首目の題は「春雪」。初句「ぬのこ(布子)」は木綿の綿入れ。結句は「肩張る」に「春」を掛けた。山の手だから春が遅い、か。参考だが月洞軒のクラスだと軍役規定による兵員二十一人を常に確保しておく必要があった。また〈ちよとあふとたちかへらるる春毎に花めづらしの御客也けり〉は年礼にきた伯父の直重である。金も気も使ったに違いない。四首目は詞書に「隣の木の枝をおろしてもらひければ富士よく見えけるゆへ」。三句は「肘枕」。二句「かはす」は肘と肘がぶつからないように「躱す」ほどの近さと解釈した。下句の対句表現もスケールが大きい。
|