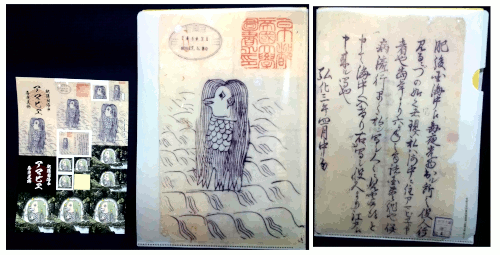|
宴会のない世界
|
「イマジン」はビートルズのメンバー、ジョン・レノンの名曲である。
「国家のない世界を想像してごらん。殺し合いも、宗教も、所有もない世界を想像してごらん。私のことを夢想家と、君は呼ぶかもしれない。けど、そんな想像をしているのは私だけではないんだよ。」
これを聞いた人は誰でも、そういう静かで平和な世の中に住んでいる自分を想像せざるを得ない。だが、国家や戦争のない世界を想像できても、歓迎会や送別会などの宴会のない世界を想像することは、ジョン・レノンにも私にもできなかった。そして今、それが新型コロナのために実現している。
コロナ禍において、「この世の中に、別段なくてもよいもの」がつぎつぎと露見していったが、歓送迎会もその一つであろう。私の職場は病院であるだけに、コロナ対策は厳しく、この1年半というもの、歓送迎会をはじめ、すべての宴会がストップしている。看護師長や部長クラスの重要人物も、気がついたら退職していたりするが、今のところ何も困っていない。
かねてから私は、出会いや別れに特別な儀式は必要ないと思ってきた。遠く離れてしまった人たちのことを思い出すとき、その人の送別会での最後の挨拶を思い出すだろうか。一緒に過ごしたり、仕事していたときのその人の何気ない一言や、無意識に出た会心のギャグの方を覚えているのではなかろうか。もしも、そんな思い出すら全く残っていないとしたら、もともと縁の薄い人だったということだ。
私がそのような思想を抱くのは、単に私が宴会嫌いだからに過ぎないのだろう。だが、今の世の中で、自分の中の宴会嫌いに目覚める人も大勢いるのではなかろうか。心配しなくていい、もしあなたが、たまたま隣に座ったそんなに好きでもない人と、無理やり話を合わせるのが苦痛だと思い始めたとしても、それはそれでそんなに恥ずかしいことではない。
「私をひねくれものと、君は呼ぶかもしれない。けど、宴会嫌いは私だけではないんだよ。」
コロナが収束したあとも、宴会のない世界が続くことを願っている。数年後にくる私の定年退職の日も、誰も送別会のことを思いつかないでいてくれたら、どんなにいいだろう。もともと影が薄いと言われる私であるから、「気がついたらあの人、いないね」と思ってもらえたら十分だし、「誰かいなくなった気がするけど、それが誰だか、思い出せない」くらいでも、私は全然差し支えない。
2021.9.21
|
|
医療機器予算申請書
|
私の病院では年に一度、各部署から医療機器予算申請をすることになっている。ただ、病院でも家庭でも、財布の中身に限りがある以上、おねだりしたものが買ってもらえるとは限らない。手術室で使うポータブルエコー装置が古くなったので、私はこの2年間、買い替えを申請しているが、落とされ続けている。
無理もない、とは思う。ノートパソコンのような本体にエコーのプローブが2本ついているだけのものが、500万円はするのである。500万円のスポーツカーに乗れば、私でも女の子をナンパできるかもしれないが、エコーに乗って街に出てもナンパは無理だ。病院にとっても魅力は薄く、この器械を使って神経ブロックや中心静脈穿刺をいくらしたところで、利益が出ない。
だがそれでも、麻酔科にエコーは必要だ。どうすればそれが上に伝わるのだろうか。
有力部長であれば、有形無形の各種影響力を要所に集中発揮して予算を確保するのかもしれないが(想像です)、私のようなヒラの部長の場合、毎年1回提出する医療機器予算申請書の「この器械を必要とする理由」欄への記入が、唯一の腕の見せ所となる。
あいにく私は、弱気なタイプである。「これを買ってくれないと、死人が出ます」、「このままでは、地球が爆発します」などという強気の文言が頭をよぎるのだが、そういうことを書いて提出する勇気がどうしても出ない。ついつい、「購入後12年経ちましたが、まだ何とか使えています」などと書いてしまうのだ。
何とか説得力のある文章で、経理課および院長をうならせることはできないだろうか。
こうなったら仕方がない。ここは幸徳秋水(こうとく・しゅうすい)の出番ではなかろうか。
1901年(明治34年)、もと衆議院議員、田中正造(たなか・しょうぞう)は皇居に向かう明治天皇の前に転がり出て、足尾鉱山による公害で臣民が苦しんでいる、何とかしてほしいと直訴した。田中に依頼されて直訴状を書いたのが、名文家として知られる幸徳秋水という新聞記者である。この直訴状がまた、確かに朗々たる名文に違いないが、何とも物々しく、読むだけで心が騒ぐのである。これをごく一部拝借し、試みに医療機器購入の直訴状を書いてみよう。
草莽の微臣、麻酔科猫又部長、誠恐誠惶頓首頓首、つつしみて奏す。
かつて院長が深仁深慈の憐みを持って購入されし超音波診断装置、使役せしむることはや十二年、今まさに故障の危機に瀕したり。ひとたび故障のことあらんか、手術室荒廃し、当院の患者、麻酔科医、他院に流離せんこと、明らかなり。
伏して思ふに、経理課当局をしてよくその責を果たさしめ、以って院長の赤子たる麻酔科医をして日月の恩に光被せしむるの道、他なし。
伏して望むらくは聖明矜察を垂れ給はんことを。臣痛絶呼号の至りにたふるなし。
昔の人はこんな感じで、言葉に呪力のようなものを宿らせることができ、それをもって人や物を動かすことができたのだろう。驕れる平家を滅ぼしたのも、一人の皇子が発した一枚の命令書(以仁王の令旨、もちひとおうのりょうじ)であった。
だが、強い言葉は副作用も強い。以仁王は平家に返り討ちされ、幸徳秋水は後年の大逆事件で濡れ衣を着せられて、死刑になった。
私は、エコーのために命を投げ出すほど筋の通った麻酔科医ではない。来年の申請書も、「購入後13年経ちましたが…」で始めるとしよう。
2021.9.4
|
|
街頭インタビュー
|
テレビのニュース番組などで、見ていて腹が立つのが、コロナ禍中の繁華街でのインタビューである。一体何の意味があるのか、わからない。
緊急事態宣言を気にせず街を歩く人たちである。どんな答えが返ってくるかは、だいたい決まっている。
「久しぶりに出てみたら、すごい人が多くてびっくりしました。用事が済んだらすぐ帰ります。」
はいはい、そうして下さい、としか言いようがない。さらに、
「今さら外出を控えても、効果があるとは思えないしぃ…」
などと訳のわからないことを言う人も多い。そういう場面が流れると、日本全国の医療従事者のうち、すくなくとも一人が、画面に向かって呪いの言葉を投げつけているはずである。
大体、そんな言い訳を聞くために取材しているのだとしたら、その取材こそが「不要不急の外出」に他ならないのではなかろうか。
テレビの人は、マイクを向ける相手を間違えていると思う。今、外出や会食を我慢している人こそ、コロナと戦う英雄である。その人たちに話を聞かないでどうする。その人がなぜ、どのように外出欲と戦っているのか、徹底的に取材してほしい。
相手は作法に則り、家に閉じこもって結界を張っているわけだから、そこに切り込んでいくのは難しいだろう。電話かインターネット経由の取材になるはずである。そして、「放送席、今日のヒーローインタビューです。あなたは今日も一日、家から一歩も出ないで過ごされましたね。これで300日連続です。今のお気持ちはいかがですか」などと聞いて回るのである。あまりおもしろい話は聞けないかもしれないが、中には、目の覚めるような名言があるかもしれない。外出したい気持ちを戒めるために、玄関にマキビシを敷きつめています、とか。
私は、人の希釈の実現のために頑張っている人の話を聞きたい。マスコミの方々もこっそり打ち上げの宴会などやっていないで、どうやって人々に外出や会食を思いとどまらせるかに、知恵を絞ってもらえないものだろうか。
あと、そろそろテレビに出る人全員に、マスクをつけてほしい。
2021.8.23
|
|
手術台
|
私が医師免許をもらって麻酔科に入局したころ(1987年)、大学病院の手術室ではまだドイツ語が飛びかっていた。エッセン(食事)、ヘルツ(心臓)、ブルート(血液)くらいは、教養部でドイツ語を習っていればすぐ分かるが、「ティッシュを上げて、下げて」と外科医に言われても、最初、何のことか分からなかった。分かってみるとこれは、ティッシュペーパーのことではなく、手術台のことなのであった。
ドイツ語のティッシュ (Tisch)は英語で言うとテーブル(table)、つまり食卓である。英語でも手術台は table と呼ぶ。縁起の悪い言葉だが、術中死のことをドイツ語でティッシュトート(Tisch Tod)、英語でテーブルデス(table death)というから、両者はよく一致している。
それにしても、欧米ではなぜ手術台をテーブルと呼ぶのか。名前だけでも「手術用ベッド」などとしてあげた方が優しくないだろうか。
これまで私がさんざんネタ元に使ってきた名著「外科の夜明け」とその続編、「近代外科を開拓した人びと」を読めば、その理由が想像できる。かつて欧米では、手術台は文字通り食卓だったのである。
19世紀、まだ病院というものがない時代、手術はしばしば患者の自宅や医師の自宅で行われた。そして、その患者を載せる台として使われたのはベッドではなく、食卓であった。
まず、そんな不潔な環境で手術ができるか、と今の人は思うだろうが、エーテル麻酔が発明された後も、清潔とか消毒という概念のない時代はしばらく続いた。また、柔らかいベッドの上でやってあげたら、と思う人も多いだろうが、ベッドは低すぎるし、幅が広くて患者に手が届きにくく、手術にはまったく不向きである。その点、食卓は手術にぴったりだったのである。
現在、手術台をテーブル、ティッシュと呼ぶのは、その頃の名残であろうと、私は考える。
一方その頃、日本には食卓というものはなかった。18世紀、独自に全身麻酔を開発したとされる華岡青洲(はなおか・せいしゅう)は、残された絵で見る限り、自分は畳の上にあぐらをかき、布団に寝かせた患者に手術していたようである。日本では手術台のことを食卓とか、ちゃぶ台などと呼ばないのは、このためであろう。
こういうちょっとした言葉の吟味から、古い時代の光景が蘇る瞬間が楽しい。
薄暗い部屋、患者の口元を覆うガーゼからイヤでも立ちのぼるエーテルやクロロホルムの匂い、それを逃がすために開け放した窓。ありがたいのは、そこから部屋に差し込んでくる木漏れ日だ。そして今朝まで料理が並んでいたテーブルの上で眠っている患者、そんな昔の臨時手術室が目に浮かんでくるのだ。
2021.8.2
|
|
医療機器
|
今、手術室の主役は医療機器である。外科医のメスさばき、などと言うけれども、現代の外科医がメスを握るのは皮膚を切る一瞬だけで、あとはもう電気メス、腹腔鏡、超音波凝固切開装置、電動式自動吻合器などが次から次へと登場し、電気なしには一秒も進まない。器械好きの執刀医だと、手術の時はあれもこれもと器械を取り揃え、自分と患者がぐるりと器械に取り囲まれて、ご満悦の図ができ上がる。
1966年の映画「白い巨塔」では、冒頭のクレジットの背景として、実際の胃切除術の一部始終が流れるのだが、たしかほとんどまったく電気を使っていなかったと思う。その分、昔ながらの外科医の職人技を堪能できるのだ。胃の切断の時に大型の手動式ステープラー「ペッツ」が出てくると、なつかしさに「おっ」と声が出る。
麻酔科医もまたしかり。今われわれが使う道具は麻酔器をはじめ、電気で動くものばかりになった。
だがもし、何かのはずみで電子たちがストライキか何かを起こし、電気が使えなくなったらどうなるだろう。その時が、私のようなおじさん(またはおばさん)が輝く最後のチャンスかもしれない。
コンピューターによる電子麻酔記録は使えないから、われわれは何と、開かずの引き出しの中から、昔使われていた紙の麻酔記録を取り出すのだ。そして、ボールペンで血圧や体温、コメントなどを記入していく。その間も呼吸用のバッグを押すのは忘れない。本当はよく忘れているが、それでも6秒ごとに思い出すのだから大したものだ。電子記録とベンチレーターしか知らない若い麻酔科医には想像もできない荒業である。こうして、麻酔が終了すると同時に、世界に一つしかない手書きの麻酔記録という作品ができあがるのだ。
その血圧だが、われわれが聴診器と水銀柱(今はその代替品)で測った方が、自動血圧計よりもはるかに速いことを、若い者は知っているのだろうか。欠点は、本当に忙しい時には血圧が測れず、「神のみぞ知る」状態になることと、数字に測る者の願望が入り込むことくらいである。
自慢話はそれくらいにして、電子たちのストライキが収束し、電気が復活したらどうするか。私はただちに機械の電源を入れる。
2021.7.25
|
|
大河ドラマ
|
NHKの大河ドラマというのがあって、何が大河なのか知らないが、要するに1年かけて展開する大掛かりな歴史ドラマである。
今やってる渋沢栄一(しぶさわ・えいいち)の物語は、見ていてなかなかおもしろい。何より、死人が少ないのがいい。
これまでの大河ドラマでは戦国時代の武将や明治維新の志士が主人公になることが多かったが、前者は大量殺人の主導者、後者はテロリストなのであるから、いずれにしても人を殺すことで自分の道を開く、という暗い業を背負った人たちである。それを「悪い奴」として描くならまだわかるが、日曜8時の番組なので、主人公は立派な人です、愛妻家ですなどと言いはるのだから、無理がある。
例えばちょっと前に主役をやっていた西郷隆盛(さいごう・たかもり)は、剛毅にして高潔な人、というイメージがあるが、実際には謀略の人でもあり、幕府打倒のためとはいえ、かなり汚いことをやっている。(たとえば「御用盗」。)少なくとも間接的に、多くの人を非業の死に追いやったことだろう。
その点渋沢は、今のところ人を殺しそうには見えないから安心だ。今は幕末だが、この先、明治時代に入ってからは実業家になるのだから、殺人鬼に豹変する可能性はとても小さい。脚本家の力量も高いのだろう、主人公が人を殺さなくても、歴史は進むのだと示してくれている。
ただ、私の最大の楽しみは、ドラマの後に始まる。その回の登場人物に関係する史跡を紹介する短いコーナーがあるのだ。物悲しい音楽をバックに、誰それの住居跡や、戦いの舞台になった城などの映像が流れる。私の耳には、女性アナウンサーの沈んだ感じのナレーションのあとに、声にならない決まり文句が聞こえるのだ。
〇〇は、この塾から、大きく世界にはばたくのでした。でも結局、死んでしまいましたけどね。
〇〇は都を追われ、この庵で不遇の晩年を送ったのでした。まあ、じきに死んでしまいましたけどね。
私は人が人を殺すのは嫌いだが、生き物に寿命というものがある限り、いずれ人が死ぬのは仕方がない。この史跡巡りにより、さっきまでドラマの中では泣いたり笑ったりしていた登場人物が、実はもう一人もこの世に残っていないということに、今さらながら気づかされる。これを見て毎回、時の流れの優しさに浸る、私の日曜日、午後8時45分なのである。
2021.7.10
|
|
スイッチ
|
業務用の電気製品の電源スイッチのなかに、わかりにくいのがある。オン、オフが "I" と "O" の記号で示してあるのだが、どっちがどっちか、直感ではわからない。かといって、熟慮してもわからない。
普通は、電源を切りたい時や入れたい時は反対側を押せばいいので、私はこれまで真剣に考えたことはなかった。しかし先日、事件は起こった。

仕事中、麻酔器という器械のアラームが鳴った。画面に出たメッセージを見ると、「電力供給が止まり、今バッテリーで動いている。さっさと電源を入れろ」とのことだった。コンセントは間違いなくつながっているが、裏面にある主電源のスイッチが "O" に入っている。これがオンなのか、オフなのかが、私にはわからない。下手に触ると、かろうじて動いているものが完全に止まってしまうかもしれない。よく考えろ、という天の声が聞こえた。
”O” は口が開いているオープンな感じだし、オンの頭文字だが、よく考えるとオフの頭文字でもある。”I” は目を閉じているイメージを感じさせるが、そこが罠かもしれない。こんなことになるのだったら、記号の意味を覚えておけばよかった。
こういう時は器械のプロが頼りだ。いつもは透析室にいる臨床工学技士(ME)のTさんに来てもらうのだが、この場合、バッテリーがどれくらい持つかわからないから、待つ余裕はない。万一麻酔器が止まってしまっても、アンビューバッグがあれば、何とでもなる。もういい、考えるな、という天の声が聞こえた。私がスイッチを "I" に倒したところ、電力は回復した。
正解は、”I” がオン、”O” がオフだった。どうしてそうなのか理由は不明だが、欧米では〇と×の意味が日本と違うらしいから、あちらでは当たり前の記号なのかもしれない。日本人は、”I” は数字の1(ある)、"O" は数字の0(ない)と覚えるしかないようだ。
ちなみに、後から来てくれた臨床工学技士のTさんに聞くと、さすがにどっちがオンかは知っているという。それは当たり前として、スイッチがオフになった理由がわからない。彼は麻酔器の説明書を持って帰り、業者に連絡し、善後策を整えてくれた。
思えば、麻酔科医は、「器械を信用するな。器械がだめになったとき、自分の手や口、目を使って、とにかく何とかしろ」という教育を受けるのだ。だからどうしても、器械のことを軽く見てしまう癖が抜けきれない。Tさんの手際を見て、器械を使うというのは本当はこういうことなんだな、と思った。
こうして私はついに、スイッチの記号を覚えた。今後は仮に、間違って発射された核ミサイルの自爆スイッチを任されても、人類の命運をかけて、自信をもって押すことができる。スイッチをオンにするのがミサイルの無効化を意味する、というので間違いなければ、だが。
やっぱり一応、Tさんに確認してからにしよう。
2021.6.13
|
|
観相
|
人の顔から、どれだけのことが分かるのだろうか。人の表情から喜怒哀楽の感情を読み取るくらいは、赤ちゃんでもできるだろう。だが、顔つきから性格が分かるかというと、もう難しくなる。
物腰柔らかな温顔のおじさんが、とんでもなく腹黒い人だったり、絶世の美女の癖に超絶性格がよかったり、そういう読み違いを60年近く繰り返した結果、人の顔からは何も引き出せないと私はあきらめている。まして、その人の健康状態や運勢など、分かるとは思えない。
昔から「人相を観る」ことを仕事にしている人たちがいて、観相師などと呼ばれるが、どれほどのものなのだろうか。
江戸時代中期の有名な観相師に、水野南北(みずの・なんぼく)という人がいる。その生涯を作家の神坂次郎(こうさか・じろう)が小説にしており(「だまってすわれば」)、面白い。若い頃は身を持ち崩し、極道まがいの悪事に明け暮れていた南北であるが、ある時、通りすがりの僧侶から「死相が出ておる」と指摘されて心を入れ替え、その僧から観相学の手ほどきを受けるのである。
観相学にも中国から伝わった教科書があるが、それをマスターしただけで「ピタリと当たる」ようになるのだったら、誰でも観相の名人になってしまう。南北がすごいのは、顔だけでなく、人のからだのすべてをなるべく数多く観て、観相を極めようとしたことである。そのために、髪結い、風呂屋、墓場などで何年にも渡って下働きをして、多くの人の全身を隈なく観まくり、その人の身の上ばなしとの答え合わせをする修行を行っている。観相師としてデビューして間もなく、評判を集めたのは当然であろう。
南北はまた、顔に表れている運命は変えることができる、とし、食事の改善などの細かい指導を行ったり、とても人を斬れそうにないやさ男の仇討ちを手伝ったりするのだから、ただの占い師ではない。これはもう、医師の仕事に近い。(もっとも、現代の医師は仇討ちに手を貸すことはない。)
ただそれは、世間の泥水の中を泳ぎ回ってきた南北の口のうまさにより、客が丸め込まれただけのことかもしれない。南北ら当時の観相師たちは、具体的にはどこをどう観ていたのか。
たとえば死相。われわれ麻酔科医は、重症の患者さんの顔が土気色になると「死相」と見るが、これは顔の皮膚の血流が止まるからだと説明できる。しかし、プロの着眼点は違う。
南北の師は、若き南北に「火輪眼」を認めた。すなわち黒眼と白眼の境に、取り巻くような細く赤い筋があり、それをもって、「誠に凶相、あと5、6か月の命」と宣告したのである。
また、南北が昔の子分の顔に観た死相は、「額に曇りがあり、額の左右に赤色が現れた時、これ大凶の相」なのであった。
確かに何らかの根拠はありそうだが、どういう理屈なのかはわれわれの考えの及ぶところではなさそうである。
南北の観相法が正しいかどうかを、誰かが科学的に検証する必要はあるだろう。人の顔を穴があくほど観察し、その所見とその人の健康状態と照合する。たとえば額の左右に発赤を認めた場合、半年以内に死亡する確率はどれほどか。これは相当数の顔に当たらなくてはできない仕事である。
こういう仕事を本職の片手間にできる人がいるとすれば、麻酔科医くらいかもしれない。
この観相法が使えたら、さぞ便利だろうと思う。術前診察の時、初見の患者さんに向かって、「死相および剣難の相が出ておる。明日の手術はおやめなさい」とか、「左の腎臓が、ちと悪いようじゃの」とか、検査結果など見なくてもすべてお見通しである。
2021.6.10
|
|
死亡時刻
|
当ブログのようなものにおいて、船のシリーズが終わった後、死ぬ話が多くなってしまっている。私は別に死にたいわけではないが、誰しも関心のある話題であろう。
以前私は、麻酔科の研究会で、ICU在室患者の夜間の血圧変動について発表したことがある。このとき、麻酔科の先輩からこういう質問をいただいた。
「大体、人が亡くなるのは夜ですよね。こうやって夜間の血圧変動を調べたのは、容態の急変が多いからではないですか。夜って、何か起こるんですよね。」
私が夜間を選んで調査したのは、血圧変動の原因になるような外的要素が少ないからであった。「人は夜死ぬ」と言われても返事に困ったが、ただ、そう言われればそうかもしれない、と私も次第に思うようになった。ICUで当直していると確かに、重症の患者さんが、夜間から明け方にかけて、亡くなることが多いような気がするのである。うちの先代のネコ、ケロちゃんも、深夜に息を引き取った。
やはり夜というのは、この世とあの世が接近する時間帯ではなかろうか。幽霊が出るのもたいてい夜らしいし(見たことはないが)、向こうから出てくるということは、こちらからも行きやすいということではないだろうか。
そこである時、病院のICUの台帳を取り出して、患者さんの死亡時刻を調べたところ、夜も昼も分布に変わりはなかった。ネットで検索して出てきた看護師の論文でも、ICUで夜間に死亡が多いというデータはなかった。人は夜死ぬというのは、ある種の文学的幻想と、自分の当直中に死亡確認はなるべくしたくないという願望が混じり合って発生した、思い込みに過ぎなかったのだろう。
簡単にできることなのだから、もっと早く確かめておいてもよかったと思う。
長年医師をやっていると、他にも私の中で変な思い込みが積み上がっているような気がする。台風が来たら気圧が下がるので、大動脈瘤や脳動脈瘤が破裂し、緊急手術になるとか、満月の夜は交通事故や不慮の事故が多く、緊急手術になるとか、年末になると日本人の胃潰瘍がひどくなり、吐血、穿孔で緊急手術になるとか。
統計など取って確かめてみてもいいけれども、おそらくは、緊急手術でさんざん眠りを妨げられてきた麻酔科医の、哀れな被害妄想なのであろう。
2021.5.30
|
|
ドッペルゲンガー
|
たとえば家の中で、ばったりと自分自身と出くわしてしまったら、少し心配した方がいい。ドッペルゲンガーという現象で、洋の東西を問わず、それは死の前兆と言われている。自分のドッペルゲンガーを人に見られた場合も、死ぬらしい。
私は今まで、自分のドッペルゲンガーを見たことはないし、自分を見たという人に会ったこともない。だから、それが本当に死の前兆なのかどうか、確かめようがない。もしそれが本当だったら、たとえば手術の前にドッペルゲンガーを見てしまった人は、手術をキャンセルするなど、いろいろ使い道のある便利な現象だと思う。
私はこのブログのようなものの中で、いわゆる臨死体験については何度か触れたことがある。臨死体験をして生き返った、という人から話を聞かせてもらったことも、2回ある。ドッペルゲンガーは、臨死体験の中の幽体離脱というものに似ていると思う。死にかけている人が自分のからだを離れ、自分や、その周囲の人たちを天井辺りから見下ろしている、という体験である。
このように自分が二つになったり、肉体と精神が分離したりする現象を、理屈で説明しようとするならば、死に瀕して脳血流が保てなくなった状況で、自他の境界線が崩れる、ということだろうか。
いつかテレビの科学番組で、幽体離脱の感覚を再現しようとする心理学者の研究を紹介していた。詳細は省くが、一定の作業を加えると、普通の人にも自分の肉体が別のところにあるような感覚が得られる、という内容だった。有り体に言えば、錯覚である。キワモノ扱いされる危険を顧みず、こういう研究をやる人は、偉いと思う。
昔は、病人が手鏡を見るようになると、死が近い、と言われていたようである。自分の手のひらを、鏡のようにじっとのぞきこむような仕草は、不吉だというのである。明治天皇が腎不全から病臥したとき、この手鏡を見るようになり、周囲は騒然となったそうである。間もなく、天皇は崩御した。
これは、自分の手が自分のものではないように見えて不思議がっているのではなかろうか。だとすれば、ドッペルゲンガーに通じるものがあるような気がする。
もっとも私は、この手鏡現象が患者さんに起こるのを見た記憶はない。救急病棟の勤務が長いナースに聞いたが、やはり記憶にないとのことであった。昔の人の観察力には驚かされる。もし本当だとすれば、だが。
ただ、こうした現象を、何でもかんでも幻覚で説明できる、と言い張るのは逆に科学的な態度ではない。説明のつかないものには、説明をつけない、というのが正しい場合もあるのではないだろうか。
私は、他人のドッペルゲンガーを見たという人には会ったことがある。以前一緒に働いていた手術室看護師である。
ある手術で思わぬ出血が生じ、術者が懸命に止血を試みるが制御がつかず、患者さんが生きるか死ぬかの状態が長時間続いたという。その手術についていた彼女は、休憩のため一時交代してもらい、手術室の廊下を歩いていると、手術を受けているはずのその患者さんが歩いているのとすれ違ってしまったのである。
彼女が疲れていたのは確かだろうが、手術室で仕事をしている最中であり、そのような幻覚を見るほど意識レベルが下がっていたとは考えにくい。優秀な看護師であり、ストレスで錯乱状態になるような人でもない。もちろん、こんなことで嘘をつくような人でもない。では何なのか。
この件に関しては、そういうこともあるかも、と思うことにしている。
ちなみにこの患者さんは幸い、何とか出血が止まり、助かったそうである。自分のドッペルゲンガーを見たり見られたりした人は必ず死ぬと、私は考えているが、すぐに、というわけでもないようだ。それは100年後かもしれない。取り乱したり、早まったりする必要はないだろう。
(念のために書いておくが、ドッペルゲンガーを見たことがない人も、残念ながら、必ず死ぬようだ。)
2021.5.16
|
|
卓球談義
|
新型コロナのせいで、私はもう丸一年、卓球場から遠ざかっている。だが、球を打つばかりが卓球の楽しみではない。卓球を語る、という楽しみ方もあるのだ。むしろそっちのほうが楽しかったりする。「負ける」心配がないからだ。
今自分たちの住む世界に神がいるかどうか、私は知らないが、卓球の世界には、神がいる。たとえば、全日本卓球選手権に出場する選手たちは全員、神である。もちろん私は対戦したことはないが、西医体や医師卓球大会などで私が足元にも寄れないような超絶最強選手でさえ、全日本の予選をなかなか通れないのである。全日本がまさに雲の上の世界であることは、容易に確信できる。
近年、全日本卓球選手権は全試合をインターネットで観戦できるようになったが、早くも1回戦から神々の饗宴が始まるのであるから、思わず手を合わせたくなる。
だが、上には上がある。卓球の世界には、史上最高の選手と誰もが認める選手がいる。スウェーデンのヤン・オベ・ワルドナーである。「最高の選手の一人」などという、英語から借りたあいまいな表現は必要ない。単に最高の選手なのである。
ワルドナーは1980年代から長年活躍し、世界選手権やオリンピックで個人、団体ともに数々の金メダルを手にした人である。全盛期の強さだけで言えばこれに匹敵する選手は中国などにもいないわけではない。ワルドナーが特別なのは、プレーそのもののすばらしさのためである。
ワルドナーのプレーを一言で表現するならば、「全能」という言葉になるだろう。攻撃のスピード、受けに回った時の反応の速さ、小技の冴え、相手の逆をつくフェイント、作戦の力、卓球に必要なすべてを兼ね備えているのである。
卓球では、相手が打球してからこちらに飛んでくるまで1−2秒前後、強打ならもっと短いが、その間に選手はそれにラケットを当てるだけではなく、どこにどのように返球するかを決めなくてはならない。ワルドナーの卓球を見ていると、彼の持ち時間は10秒くらいあるとしか思えない。満を持して放たれた打球は、あるいは弾丸のように相手コートに突き刺さり、あるいは敵をあざ笑うかのように予期しないスペースにポトンと落ち、まさに変幻自在である。まるで手品を見せられたかのように、観客も、相手選手もあっけに取られるのである。
そのプレーは動画サイトでも見ることができるが、卓球を知らない人にも、彼が他の一流選手ともまた別の世界にいることが伝わるのではないかと思う。まさに神々の神である。観る者はまた、神が降臨しえた卓球という競技の魅力にも気づかされるだろう。
卓球界がこのような神話を持つことができたのは、実に幸運なことであった。
だが一方で、さほど卓球から愛されていない者たちが、卓球を底辺から支えていることも忘れてはならない。勝ち続ける人が存在するためには、負け続ける人も同じだけ必要なのである。彼らは才能もないのに、しつこく卓球を続けている。自分の欠点を修正するような練習は面白くないから放棄し、ちょっと意味の分からない奇妙な技を開発しているのだ。彼らは天才ではないが、ある種神がかっている。神ではないし、妖精と呼ぶのもかわいすぎるが、地縛霊くらいには呼んであげたいものである。
卓球の記事を書く人たちは、トップ選手のインタビューを5ページも載せるのはやめて、彼ら卓球の地縛霊にインタビューし、誰も見たこともないようなその得意技を披露してもらったら、さぞ面白いだろうに、と思うのだ。
2021.5.5
|
|
緊急事態ジョギング
|
現在、私の住む地方は、新型コロナ感染症に係る緊急事態宣言下にある。外出は極力控えるように、とのお達しであるが、一人でジョギングするくらいならリスクは極めて小さいと、私は考えている。
海辺の公園を走っていると、集団で走っている人たちがいた。15人くらいのグループだが全員マスクをしておらず、1メートルくらいの間隔でダマになって走っている。これはいけない。
せっかく、ジョギングこそは誰にも気兼ねすることなくできる趣味なのに、わざわざ群れてやる意味がわからない。そして、あんな風にくっついて走って、しかもお互いハアハアしているのだから、前を走る人の呼気のエアロゾルをたっぷり吸っているのは間違いない。
多分、去年1年間、彼らはコロナに感染せず、このやり方に自信を持っているだろう。だが前回の繰り返しになるが、コロナは勝手にルールを変えてきている。怪獣ごっこで遊ぶ子どものように、父のスペシウム光線を浴びても「効かへんもーん」とうそぶくようになっている。屋外でも、距離2メートルでも、マスクをつけていても、うつる可能性が出てきているのだ。そして、うつってしまうと、若くても重症化しやすく、命を落とす確率が高まっている。
これは脅しでも何でもない、そういう人たちにもう何人も、私は人工呼吸のための気管挿管をしている。
今までのやり方は、考え直したほうがいい。
外出する際、大事なのは殺人指数を極力抑えることだ。殺人指数は自殺指数と他殺指数の和であるが、幸いこれを抑える方法は同じだ。
私がジョギングする時は、もちろんマスクをつける。また、人とすれ違うときは、なるべく2,3メートルは離れるようにしている。マスクを着けていない人を見たら、わざとらしく大きく迂回して、5メートル以内には近づかない。道が狭くてよけられないときはどうするか。引き返すのである。引き返す先に別の人がいたらどうするか。息を止めてすれちがうしかない。
ここまでやる意味はあまりないかもしれないが、半分ゲームのような感覚である。
あの、仲間と群れないでは走ることもできない気の毒な人たちに、ひとこと言いたい気もするが、物理的に不可能である。彼らのうち一番遅い人に合わせて走っているはずだが、あっという間に私を追い抜き、遠ざかって行くのだった。
2021.5.4
|
|
殺人指数
|
今、新型コロナの変異株が私の住む地域でも猛威を振るい、過去最大となる第4波を形成している。これだけ拡がるのは、やはり感染力がこれまでのものより強いからだろう。私の病院の患者さんたちを見ていると、重症化するスピードもあきらかに速いと感じる。また、今までより若い年齢層の人たちが人工呼吸を余儀なくされ、運の悪いとそのまま亡くなっていく。20代、30代でも、ひょっとして死ぬかもしれなくなっている。
これはつまり、向こうがゲームのルールを変えてきた、ということだ。囲碁で言えば、卑怯にも一回で2手打ってくるようなものだ。こちらも作戦を変える必要がある。これまでよりもさらに、人との距離を大きめに取らなければ、やられてしまう。
それにしても、テレビをつけると画面に映る、繁華街を行きかう大勢の人たち、飲食店でおしゃべりする人たちは、何なのだろうと思う。自分たちはコロナにかからないし、他人がコロナにかかっても自分とは関係ないと思っているのだろうか。
テレビに出てくる専門家とかいう人たちは、良識の持ち主だ。「人流を抑えることが重要」、「もう少しの間、辛抱を」などと耳あたりの良いことを言うのだけれど、もうちょっとはっきり言ったらどうなのだろう。ウイルスは人が運ぶのだ。人混みの中に入って行く人たち、多人数で会食する人たち、路上で酒を飲みながらくだを巻く人たち、あなたがたは殺人者です、と。
さすがに、一人の人が宴会に一回出席しただけで、人を一人死なせるわけではないが、私の勘では0.001人は殺しているだろう。小数になるのは、確率的現象だからだ。誰が死ぬかと言うと、自分自身が死ぬことになる可能性が最も高いのだが、うつした方の自分は何ともないのに家族や職場の人が死ぬこともよくあることだし、数人でパスを繰り返した先の赤の他人かもしれない。それらを全部まとめた数字が、「殺人指数」である。
殺人指数は、スマートホンに表示される。どんなマスクをしているか、どこに出かけてどう行動するか、などにより簡単に計算できてしまう。殺人確率0.001を1ポイントとするが、これは危険行為をするたびに加算されていく。1000ポイントたまれば、つまり一人殺した計算になれば、新型コロナのキャラクター、「コロちゃん」が画面に出てきて、表彰してくれるのだ。ご協力ありがとう、というわけだ。
現実には、タバコや酒が確実に自分の寿命が縮めることを知りながら、漫然と摂取しつづけている人が世の中にたくさんいるのだ。今晩新宿に出かけたら、あなたの殺人指数は2ポイントです、などと聞かされたところで、外出や会食を控える人がどれくらいいるだろうかと、疑問ではある。だが、誰にうつされたかわからないまま病院で亡くなっていく人たちを目の前にして、無力な麻酔科医としては、こういうことでも考えなくてはやっていられない。
明日4月25日、3度めの非常事態宣言が出る。今度こそなるべく多くの人に「物忌み」をしてもらい、人を殺すのを我慢してもらいたいと願っている。
2021.4.24
|
|
かさぶた
|
私がJPOPを聞いていて、どうしても気になるのが、やたらと出てくる「傷つく」という言葉である。
「傷つくのが怖かっただけ」
「傷つけあって生きてきた」
海外のことはよく知らないが、日本には、傷つけあってこそ真の恋愛だ、という暗黙の了解でもあるのだろうか。気の毒に、若者たちは生傷だらけではないか。
さて、先日私も、ひどく傷ついたことがあった。ジョギング中、歩道の凸凹に引っかかって転倒したのである。
あっという間もなく、目の前に地球が近づいてくる。女優ならば顔だけには傷がつかないよう、手でかばう所だが、私は麻酔科医だ。手、とくに喉頭鏡を持つ左手は傷つけてはならない。ここは顔で地球を受け止めるしかない、と覚悟を決めたのに、手が勝手に出てしまった。本能は怖い。私は麻酔科医である前に、一人の女優だったのかもしれない。
その結果、私は左手と膝小僧を思い切りすりむいた。血をだらだら流しながら、しかし照れ笑いも忘れずに、とぼとぼと歩いて帰ったのであった。
こんなに盛大にすりむいたのは、小学生のころ以来だと思う。あの頃と違って、今の私なら、これくらいでは泣かない。こういう傷に赤チンだのマキロンだのを塗って、地獄の苦しみを味わう必要がないことを知っているからである。流水で洗い、創傷パッドを貼る。これを毎日繰り返すだけでよいのである。
幸い、家には元看護師がいる。破傷風になった時には、さすがに助けてくれるだろう。
わが生傷が治癒していくさまを、私は久しぶりに興味深く観察することができた。手の傷はけっこうひどく、表皮を失っている部分も多いが、ありがたいのはかさぶただ。血小板などの血球と血漿成分が固まり、しばらく表皮の代わりをしてくれる。肉芽が盛り上がり、表皮が再生されると、かさぶた氏は、もういいですか、さよなら、とばかり剥がれ落ちていくのである。その見た目の醜さゆえに嫌われ、使い捨てにされる運命にあるのに、文句一つ言わないのである。
若者よ、傷にはかさぶたがある。こういうかさぶたのような人間に、私はなりたい。もしかしたら、もうなってしまっているかもしれない。ああでも、文句は言いたい。
2021.4.10
|
|
親の死に目
|
今どき街を走っている霊柩車は、普通の自動車と見分けがつかない地味なものであるが、私が小学生の頃は神社みたいな屋根をあしらったド派手なものだった。当時、どこから湧いた迷信かわからないが、霊柩車に出くわしたら親指を隠せ、隠さなければ親の死に目に会えなくなる、と言われていた。
小学生の私は、霊柩車を見かけたときは必死で親指を握り込んだものであるが、逆に、親の死に目に会えないということが、こうまでして恐れなくてはならないことなのだと、何者かに刷り込まれたようでもあった。
現在まで、私は自分の両親と妻の両親のうち、3人を亡くしているが、いずれもその死に立ち会うことができなかった。たぶん、子どもの頃、霊柩車を見てから親指を隠したのでは、遅かったのだ。親指は、一日中握りっぱなしにしておかなければならなかったようだ。
だが、親の死に目に会えないということがそんなに不幸なことなのだろうか。少なくとも私は、ひどい親不孝をしたと頭を抱えているわけではない。
病人を家で看病していた昔は、亡くなる瞬間を家族が看取っていただろう。しかし、ほとんどの人が病院で死ぬようになった今、家族がそこに立ち会えるとは限らなくなった。さらに新型コロナの時代になり、患者さんの死期が近いからと言って、ご家族に病院に長くとどまっていただくことが難しくなった。
そういうわけで、たとえ病気がコロナでなくても、亡くなってからご家族に連絡する、という事例が増えている。それはそれで、ある程度仕方のないことと、受け入れられているように思う。
死生観というものは、時代とともに変化するものだろう。最近のNHKの朝ドラでは、重要人物の死が描かれないことが増えた。(これを「ナレ死」という。)死に方に、その人の生きざまが凝縮される、みたいな考え方は古くなりつつあるのではあるまいか。死に目というものに、あまりこだわらない時代が来つつあるような気がする。
2021.3.13
|
|
訂正記事
|
前回の私の記事の中に、訂正したい部分がある。ヒト(ホモ・サピエンス)の第一陣が東南アジアからオーストラリアに渡るとき、水平線への旅立ちだった、ようなことを書いたけれども、そうではなかったようである。
島を伝っていけば、オーストラリアは決してアジアから隔絶した大陸ではない。また、高い山があり、対岸からそれが十分見える距離なのである。一か八か、の航海ではなく、新天地への期待に胸を膨らませての旅立ちだったのかもしれない。
オーストラリアははるかな国というイメージがあって、いい加減なことを書いてしまった。
このブログのようなサイトは、一介の底辺麻酔科医が、本で読んだことと妄想を取り交ぜて、無責任に吐き出す場だと思いこんでいる人がいるかもしれないが、まさにその通りである。
訂正ついでに吐き出させていただくが、大陸から日本へのヒトの初渡来こそが水平線への旅立ちであり、オーストラリア行きよりもはるかに困難な挑戦だったようだ。
大昔、日本と大陸はつながっていたわけで、私はヒトも歩いて(でなければ走って)渡ってきたのだと思っていた。しかし、ヒトが日本に住み始めた3−4万年前、すでに日本は大陸から切り離されていた。つまり、最初の日本人は海を渡ってきたと考えられるのである。朝鮮半島-対馬-九州のラインがもっとも有力なルートであったが、台湾(これは大陸とつながっていた)から琉球諸島へのラインも存在した。
この台湾ー琉球ラインが問題である。日本側の山は低く、台湾側の岸からは見えないし、もっと厄介なことに、黒潮という世界最大級の海流を横切らねばならない。そのようなことが3万年前のヒトの技術で可能なのか。人類進化学者の海部陽介(かいふ・ようすけ)氏はこの疑問に答えるため、クラウドファンディングで資金を集め、さまざまな船を作って実際に海を渡る試みに挑戦した(注)。私の差し出した大枚五千円の寄付も、大いに働いたはずだ。
3年にわたる試行錯誤の末、チームは石器を使って作成した丸木舟に乗って台湾から漕ぎ出し、黒潮の激流を乗り越えて与那国島にたどりつくことができたのである。その距離200キロメートル。これは最初彼らが試作したような、草や竹で作った舟やイカダでは、決してできないことだったという。
海を渡りたければ、まず山に行け、というのが、海部氏の発見であった。吉野の木材を押さえたヤマト王権が瀬戸内海を制覇した、という宮崎市定(みやざき・いちさだ)氏の説と符合する結論である。
最初の日本人たちは、力を合わせて大木を倒し、それを石器で削りまくって丸木船を作り、新世界の存在を信じて何も見えない海に乗り出して行った人たちであったことを、海部氏は証明したのである。
以上、訂正記事とそのおまけでした。
(注)海部陽介著、「サピエンス日本上陸」(講談社)
2021.2.11
|
|
船
|
気がつくと、当ブログのようなもので、船の話が3回続いている。麻酔、医学とは何の関係もない。幸い、私が何か有益なことを書くだろうなどと、期待している人はいないはずだ。このまま4回目に突入する。
20万年前、アフリカで現生人類(ホモ・サピエンス)が誕生した後、一部の者たちが10万年くらい前(諸説ある)にアフリカ大陸を旅立った。せっかく陸続きなのだから、歩いて中東へ抜けていったと考えるのが普通だが、最近は紅海を渡ってアラビア半島に上陸したという説が有力になっているようだ。
その距離、10km はあるから、泳いだのではなく何かに乗って渡ったのだろう。船か、いかだか、分からないが、そんな大昔にすでに海を渡る乗り物が発明されていたのだ。チンパンジーが船を作って乗っているのを、私は見たことがないから、さすが人間は猿より毛が3本多い(俗説です)だけある。
海を渡る前から向こう岸は見えていただろうが、命がけには違いない。なぜ彼らは旅立ったのか。彼らが胸に抱いていたのは絶望か、希望か。いずれにしてもそれは、人類史上もっとも重要な航海であっただろう。

だが、もっと不可解なのが、人類のオーストラリアへの渡航である。ホモ・サピエンスのオーストラリアへの進出はかなり早く、5、6万年前と言われる。もしかしたら、ヨーロッパより早いかもしれないのだ。
アボリジニの先祖たちは、東南アジアから100kmほどの航海を経てオーストラリアにたどり着いた、としか考えられないのだが、紅海横断と違い、出発前、目的地は見えないのだ。水平線に向かって旅立つなど、無謀としか言いようがない。
彼らは一体どんな船に乗り、何を目指して海に漕ぎ出したのか。もしタイムマシンがあったら、私は本能寺の変なんか見に行かないで、彼らの旅立ちの場面をぜひ目撃したいものだと思う。
日本人の鉄道好きについては以前書いたことがあるが、人類にとってもっとも重要な乗り物となると、やはり船であろう。鉄道が「安心」、「楽しみ」などの言葉を連想させるとすれば、船に似合うのは「運命」という言葉である。
2021.1.31
|
|
大和
|
関西で生活している人は、知らず知らずのうちに、かつて都だったという地を通りすぎたり、その上に住んだりしている可能性がある。京都平安京、奈良平城京は誰でも知っているだろうが、大津の近江京、大阪の難波京、神戸の福原京など、関西各地にさりげなく古都は存在するのである。
これらはいずれも、今は都会であり、古都という名にふさわしい風情はまるでない。
だが奈良の飛鳥は違う。この「国のまほろば」は今も田園地帯であり、「たたなづく青垣」が生きている。人があふれかえっていないところもいい。誰でもここに来さえすれば、お金を払わなくても、昔の都びとの気分に浸ることができる。
飛鳥を含む大和の地は日本の最初の都であり、同時に大陸とのつながりも強く、帰化人の多く住む国際都市であった。だがなぜそれが、こんな海に面していない内陸に置かれたのか。この場所に、どのような地の利があったのか。
この疑問に対し、ずいぶん古い人ではあるが中国史の大家、宮崎市定(みやざき・いちさだ)氏の提唱する説が、おもしろい。
宮崎氏は、ヤマトの語源は「山の門(と)」であろうという。山とは、良質な木材を産出する吉野山地のことである。大和は、船の材料となる木材を一手に押さえられる地であり、古代ヤマト王権はそれによって瀬戸内海を制覇した、というのである。
私も戦後生まれなので日本神話はほとんど知らないが、初代天皇の神武(じんむ)天皇はもともとは九州に生まれた、ということになっているようだ。45歳の時、東征を思い立って船に乗り、数々の敵を倒しながら瀬戸内海を渡ってヤマトにたどり着いたそうである。宮崎氏によると、実際にはヤマト王権はもとからヤマトにいたのだが、瀬戸内海を征服した時の歴史を「東征」という物語にしたのであろう、というのである。
宮崎説が嘘か、本当か、わからないが、山と海が結びついて生まれたのがヤマトだったと考えるのは、なかなか楽しい。征服されてしまった人たちにとってはとんでもない災厄だっただろうが、大昔の話だから、勝った人も負けた人も、もう死んでいる。今は恨みも消えて、残っているのは物語だけだ。そういうところが、古い歴史の安心なところである。
私の生家の庭だった瀬戸内海がその昔、今の天皇家のご先祖のお役に立てたようで、何よりである。
2021.1.25
|
|
瀬戸内海
|
私は6歳まで倉橋島という、広島県呉市に隣接する島に住んでいた。(今は呉市の一部となっている。)玄関を出れば、すぐ目の前に瀬戸内海が広がっているような家だった。私の兄と二人の姉はいずれも、一度は海に溺れて死にかけた経験を持つそうであるが、見ているだけなら、これだけ年中穏やかな海もなかろうと思う。
瀬戸内海は気候は温暖、波はしずかで、沿岸のどこに行っても、島影がつきることがない。また、海のどこに目をやっても視界の中には必ず、ゆっくり進む、あるいは停泊する船がある。日本のエーゲ海と称する人もいるが、私はエーゲ海に行ったことがないからよくわからない。たぶん、瀬戸内海のようなところなのだろう。
広島県出身者など、瀬戸内海を見ながら育っている人は温厚な人が多いというのが私の持論であり、私はこれを「波風立たぬ瀬戸内気質」と名づけている。
ただ、瀬戸内海は波風は立たないが、潮の流れが速く複雑で、航海する上では難所が多いらしい。戦国時代、この瀬戸内海を支配した村上海賊は、逆にそれをうまく利用していたようである。来島海峡などの攻められにくい難所に拠点を構え、潮目を知り尽くした自分たちは縦横無尽に船を走らせていたのである。
海賊と言っても、船を襲って略奪するのが主な仕事ではなく、通行税を取って、用心棒や水先案内人のようなことをしていたそうである。一方、特に能島(のしま)村上家は水軍としても強力であり、厳島(いつくしま)合戦、木津川口の戦いなどで毛利(もうり)家に味方して、勝利をもたらしている。
瀬戸内海は波風立たないが、うちうちにはこのような烈しいものを持っているのである。環境が人を育てるのであれば、外柔内剛の立派な人ができあがりそうであるが、私のような、ただ軟弱なだけの者もいるから、一概には言えない。
今年は瀬戸内海のように穏やかな一年にし…たかったけどなあ。
2021.1.16
|
|
従容として…
|
軍艦というものは、魚雷で攻撃される運命にある。魚雷が命中し、そこから海水が入ると、船が傾いて沈没するから、反対側の船底の区画にわざと海水を入れて、バランスを保たねばならない。場合によっては乗組員がまだ避難できていない船室を密閉し、海水をそこで食い止めるということもありうる。
旧日本帝国海軍のマニュアルでは、そのような場合、逃げ遅れた乗組員は「従容(しょうよう)として死に就け」ということになっていたそうである。ジタバタされて、せっかく密閉したはずのドアを開けられては、フネが沈むからだろう。
阿川弘之(あがわ・ひろゆき)の海軍ものか何かで読んだのだろうが、この「従容として死に就け」という言葉が私はずっと忘れられないでいる。一見きれいな表現だが、要は鉄のかたまりの中に閉じ込められた者に対し、フネを守るために黙って死ね、という命令である。しかも、「従容として(騒がず、ゆったりと)」などと、死ぬ態度まで指定される。私は、こんな死に方はできれば御免こうむりたい。
敗戦後、日本は変わり、お前は死ね、などとは言わなくなった。今回のコロナ禍においても、日本は世界で唯一、罰則や強制力を伴わない「呼びかけ」で対応してきた。強制的な営業停止や外出禁止が、国民の生きる権利を奪うことにつながるからであろう。
ただ、第3波の感染拡大に歯止めがかからなくなった今、この日本式も限界に近づきつつあるようだ。自分の命を救うために船室から脱出するのはいいが、そのごく一部でも、開けたドアを閉めるくらいのことをしない横着な者がいると、フネは沈むのである。
当ブログのようなものも、コロナ退治の妄想に明け暮れた1年だった。私は火星人、アマビエ、ヌエ、創作怪談、願掛け、いろんなものを持ち出してコロナに対抗しようとしたが、敵は手ごわかった。私のいる病院でも、スタッフが患者さんからウイルスをもらうケースがちらほら出始めている。
だが、我々は従容としている場合ではない。いまだに「お前らは死に就け」をやっているような国だけが栄えるのでは、悔しいではないか。私の持ち場である手術室には、海水はまだ入ってきてないが、来ればたとえバケツで海水を掻き出してでも、フネの沈没を食い止める覚悟を決める段取りをつける予定になっている。
もちろん、火星人もアマビエも、ここまで全く働いていないので、海水の掻き出しくらいは手伝ってもらう。
2020.12.30
|
|
メルケル演説
|
前回とかぶる内容になる。
12月9日のドイツの連邦議会でのメルケル首相の新型コロナに関する演説が、感動を呼んでいる。Newsweek 日本版のホームページから一部引用すると、
「1日590人の死は受け入れることができないというのが私の見解だ。」
「科学的知見とは実在するのであって、人はもっとそれを大切にするべきだ。」
「人は多くのことを無力化することができるが、重力を無力化することはできない。光速も無力化することはできない。」
元科学者らしい、知性あふれる演説である。
いわゆる Go To キャンペーンの中断や飲食店の時間制限に反対する人たちは、「根拠を示せ」というが、現在進行形の事態に対して明確な根拠が揃うはずもない。そういうのは「根拠」という科学っぽい用語を使った反科学である。
RNAウイルスという、生体外で長生きできない病原体の伝染に対し、人の混雑を避け、酒を飲んでのエアロゾル交換を止めるのが有効である、というのは、今もっとも確からしい作業仮説である。確実な根拠はまだないが、支持する所見はいくらでもある。これ以外に、このウイルスに対抗する手段はない。筋道立てれば、誰が考えてもそうなる。それが科学というものだ。
メルケル演説はそういうことを訴えたかったのだと思われる。
一方その2日後、日本の菅首相は、インターネット番組で「ガースーです」とやっていた。これまでのこの人の言葉や表情から、コロナ退治に対する情熱や、科学に寄せる信頼をうかがい知ることは、至難の業である。
だが日本の国民は、がっかりする必要はない。これも前回の繰り返しになるが、増田悦佐(ますだ・えつすけ)というちょっと変わった経済学者によると、日本にはヨーロッパのような有能で雄弁なエリートは存在しないが、むしろそのほうがいいのである。頼りない指導者の姿を見て、国民は「これではいけない」と焦り始め、自分で正しい道を探ろうとするのである。一般人の教育レベルの高さ、「常識力」の高さでは、日本はどこにも引けはとらないだろう。
つまり増田理論を私なりに解釈すれば、うちの首相があんななのは、国民を奮い立たせるためにわざとあのように演じてくれているのである。ありがたいことではないか。
増田氏によると、米国中国などの大国はこれから没落していき、最強の文明を持つ日本が、世界に屹立していくのだそうである。今ほど、この能天気とも思える増田理論が本当でありますように、と祈るような気持ちになったことはない。
2020.12.28
|
|
Go To 狂騒曲
|
コロナ感染の第3波が拡がり続けている今、いわゆる Go to キャンペーンをやめるべきかどうかが問題になっている。同キャンペーンが感染拡大の原因かどうか、議論はあるのだが、少なくとも人々の三密に対する警戒心を薄めてしまう効果はあったのではないか。「Go to はやめられない」と発言する人がいると、私はどうしても、われわれ医療関係者がせっせと掃除しているうしろで、紙吹雪をまく人に見えてしまう。
そもそも、「Go to」はまともな英語なのか。
誰かが書いていたが、Go to と聞いて連想するのは、"Go to hell" とか "Go to jail" (地獄へ落ちろ、牢屋に行け)といった罵声である。あるいは Basic という昔のプログラミング言語の諸悪の根源と言われる "goto 文" である。響きのよい言葉ではなさそうである。
しかも、Go to の後に Kyoto などの目的地がくるのならまだわかるが、そうではない。"Go to travel"、"Go to eat" というのだから、たぶん文法として間違っているのではないか。自信はないが、そんな気がする。
おそらく、東大か何かを出たお偉い官僚が、庶民にはこれくらいがお似合いだとばかり、テキトーな英語を投げ出したのだろう。結果、「とっとと旅行を行きやがれ」みたいなカタコトの罵り言葉だったとは、官僚や政治家の本心は語るに落ちた、というところであろう。
病院で働いていると、市や県など、行政の人たちも苦心して医療を支えてくれているのは感じる。しかし、大臣、総理大臣と、上に行くほど、どうも頼りない。だが、増田悦佐(ますだ・えつすけ)という経済評論家によると、日本には真のエリートが存在せず、大衆が自分の知恵で正しい方向に進んでいくような仕組みになっているのだという。
そう言えば、日本軍と戦ったアメリカ人によると、太平洋戦争の日本軍は、末端の兵隊たちが非常に優秀なのに、高い地位ほど無能な人物に占められていたそうだ。
そういうわけでわれわれは、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルケル首相が国民に呼びかける演説の力強さをうらやましく思う必要もなく、自分たちの判断で動いていけばよいということなのだろう。
2020.12.13
|
|
超新星爆発
|
超新星爆発と言うと、何か若いスターの誕生のようなものをイメージしがちであるが、実態はそんないいものではなくて、年老いた星の死亡の瞬間である。ある程度大きな恒星が燃料を使い果たすと、自分の中に大量に溜まった燃えカスの重力に耐えきれなくなって自壊し、次いで爆発するのである。戦隊ヒーローものなどで、やっつけられた怪獣が最後は爆発して死亡するが、あれのようなものだ。
だがこの爆散した燃えカスが、実はすごい。これがまた集まって、新しい星を作るのだ。地球を含む我らが太陽系も、そうやってカスを集めてリサイクルされたものである。その証拠に、地球を掘れば、金や銀が出てくる。こういう重い元素は超新星爆発でなくてはできないものなのである。
つまり地球は、超新星爆発の燃えカスからできた星だからこそ、多様な元素を持って生まれたし、これらがなかったら生命を宿すことはなかったと考えられる。
(この辺り、素人の思い込みかもしれないので、物理学的に不正確な記載があるかもしれません。)
私は日頃から、小豆(あずき)のあんこを天からの贈り物と思っているが、このような素晴らしいものが存在するのも、もとをただせば超新星爆発のおかげかと思うと、胸が熱くなる。これに、SF小説風に本末転倒変換を施すと、こうなる。
ビッグバンで生まれた宇宙は、せっかくだから何かすばらしいものを生み出そうと考えた。しかし、初期の天体はガスの寄せ集めであり、その原子炉で生産される元素は鉄までである。これでは大したものはできないので、宇宙は超新星爆発を起こし、もっといろんな元素を作った。その燃えカスから地球が生まれ、人類が発生したのである。
もっともこの人類も、ゴミから作っただけあってろくなものではなかったが、小豆という素材を与えてみたところ、「鳶が鷹を生む」とはよく言ったもので、奇跡的に究極の一品をつくった。それがあんこである。こうして宇宙の野望は果たされたのである。
(ここの、あんこに関する記載は、正確です。)
さて、2014年に宇宙に飛び立った探査機「はやぶさ2」が、6年の旅を終え、本日12月6日、小惑星リュウグウの試料を届けてくれた。これを分析することにより、太陽系の成り立ちや、地球の生命の起源に関して理解が進むと期待されている。超新星爆発の燃えカスどもが、どのようにしてあんこの誕生という宇宙進化の頂点を極めたか、ぜひとも知りたいと思う。
それにしても、はやぶさ2の仕事ぶりはパーフェクトであった。しかも、初代はやぶさが満身創痍で帰ってきて、大気圏で華々しく散ったのとは対照的に、はやぶさ2は余裕しゃくしゃくと、別の小惑星に向かってまた旅立っていった。JAXAによると「学校から帰った小学生のように、ランドセルだけ置いてすぐに遊びに行った」のである。
ロクなニュースがなかったこの1年の終わりに迎えることのできた、今日というめでたい日に、私はあんこのたっぷり入った大福を食べようと思う。
2020.12.6
|
|
たとえ話
|
内閣官房は11月、ホームページで「感染リスクが高まる5つの場面」を発表した。これまで新型コロナのクラスターが発生した事例をまとめると、飲酒を伴う長時間の会食、マスクなしの会話、寮など狭い空間での共同生活が危ない、気をつけるように、という内容である。
問題は、これをどうやって国民に周知し、実行してもらうかである。
一人ひとりについてみたら、コロナにかかる確率は高くはない。11月末現在の発症数から計算すると、東京都に住むひとりの人が一週間の間にコロナに感染する確率は、0.025%くらいである。「今まで無茶してきたのに、うつらなかった。かりにうつっても、若いから俺は大丈夫」と思ってしまうのも、無理はない。
だが、コロナ対策やってる人から見れば、お前一人がどうなろうが、そんなことはどうでもいいのだ(想像)。社会の中でコロナの連鎖反応を防ぐためには、感染確率0.025%では高すぎて話にならない。これをたとえば0.00001%くらいまで何とか下げたい。そのために人間同士のエアロゾルの交換をとことん減らし、コロナウイルスを希釈することが必要なのである。
この視点を多くの人にどうやって持ってもらえるか、ここがむずかしい。お役人や政治家の腕の見せ所であろう。
以前私はここで、創作怪談をそっとネット空間に放流し、若い人たちの無軌道な生活を戒めることを企てた。しかし私の怪談はコロナのように増殖、拡散を始めることなく、新型コロナの第3波到来を許してしまった。私の力不足であった。
事態がここまで来たらもうあとがない。宗教に頼るしかない。
宗教家が布教する時、神や仏に興味を持たない民衆の心をがっちりつかむために使うのが、たとえ話である。
「一粒の麦もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、死なば多くの実を結ぶべし」
「新しい酒は新しい袋に盛れ」
「仏の教えは盲亀浮木である。(人と生まれて仏の教えに出会えるなんて、目の見えない亀が、海に漂う浮木の穴にスポッとはまるくらい、まれで幸運なことである)」
うまいたとえ話は、人をはっとさせる。冷静に分析されてしまうとそこは所詮たとえ話、麦が地に落ちて実を結ぶのであれば、死んでないじゃん、などの矛盾に気づかれてしまうのだが、そうやって屁理屈をこねられるまえに、聞く人の頭に火花を飛ばしてしまうのが大事なのだろう。
コロナに関係する医療者、政治家は、せっかくテレビに出るのならば、これを見習ってほしいと思うが、実際にはむずかしいだろう。医療者は根拠のないことをテレビで言い散らかすわけには行かないし(そういう人もいるが)、政治家は言ったことに責任をとらなければならない(そうでない人もいるが)。
なにより、ナイスなたとえ話を語るには、特殊な才能、いわば霊感みたいなものが必要だと思う。私が思いつくのは、こんな程度だ。
「いまどきマスクをしないなんて、ズボンもパンツもはかないで外に出るようなものですよ。肛門がスースーして、風邪ひきますよね。」
誰か、天才宗教家に登場してほしいと思う、今日この頃である。
2020.11.29
|
|
切断
|
手術で「切断」と言えば、ほとんどが下肢の切断術である。下肢は糖尿病や動脈硬化などで血流が悪くなりやすく、組織の壊死、あるいは感染を起こすと、もはや打つ手がなくなり、生命を救うために切断せざるをえなくなる。一種の敗北宣言であり、身体の一部の永遠の欠如と身体機能の重大な変更を意味する手術でもあり、整形外科の医師も一番やりたくない手術だそうだ。「切断」という言葉は生々しすぎるので、手術室ではアンプタ(amputaion の略)と呼ばれることが多い。
術後の機能障害を考えると、膝の下の切断ですませたいのは山々だが、膝より上で切らざるを得ない場合もある。ごろりと切り落とされた下肢を受け取るのは看護師だが、かなり重く感じるそうである。その下肢はただちに布にくるまれ、火葬場に送られることになる。変なところで発見されると、殺人事件と区別がつかないからだろう。
下肢のアンプタはこうして、誰にとっても残念な手術であるが、それでもまだ上肢よりはましだ。上肢は下肢よりはるかに血流がよいのだが、まれに切断が必要になることがある。切断された上肢は、さすがに不気味だ。とくに、手には足と違って表情がある。もう二度と動かない手の最後の形、ここにはいかにも、患者さんの無念さが乗り移っているように見えてしまう。
下肢、上肢の切断に伴ってさまざまな人間ドラマがあるけれども、個々の症例についての紹介は差し控えさせていただきます。(総理大臣の答弁みたいだが。)
もっとも、江戸時代末期から明治にかけての日本の外科の歴史を見れば、四肢の切断は非常によく登場する手術である。抗生剤がなかったその昔、外傷などから足の感染を併発した場合、切断になることが多かったのである。まだ開腹、開胸の手術がほとんど行われていなかった時代、下肢の切断はもっとも大きな花形手術であり、外科医の腕の見せ所だったのだろう。
それはまた、大手術でもあるだけに、日本に全身麻酔が登場するための舞台ともなった。
日本では江戸時代末期に揮発性麻酔薬による全身麻酔が入ってきたが、伊東玄朴(いとう・げんぼく)という蘭医がクロロホルムを使って下肢を切断したのがその最初ではないかと言われている。ヘボン博士による歌舞伎役者澤村田之助(さわむら・たのすけ)の下腿切断も、クロロホルムを使った手術として有名である。
明治維新の時代になり、戊辰戦争(幕府と明治新政府の戦争)で銃が本格的に使われ始めると、切断は盛んに行われるようになる。なにしろ江戸時代になって日本人は、銃という武器を一旦捨てたから、銃創に慣れていない。侍たちは、からだのどんな場所でも、銃弾を受けると死は免れないと思い込んでおり、手や足を撃たれただけで、もはやこれまでと自決する者が多かったらしい。もし自決せず、医師のもとに運び込まれると、撃たれた手や足は、しばしば切断された。
このときイギリス人医師ウィリスらがクロロホルムを使ったという記録もあるが、おそらく麻酔なしで切られた兵士も多かったのではなかろうか。
明治初期の外科の第一人者、佐藤進(さとう・すすむ)の自伝によると、戊辰戦争のとき、下肢や上肢の関節に骨折を伴う銃創を受けると、切断するのが必然の選択だったという。当時は欧米でも切断が主流だったのでためらわなかったが、その後進歩した医学から見れば、足を落とす必要はなかったと思われる症例も多々あったそうである。
佐藤が下肢を切断した侍の一人が後年、面会を求めてきたことがある。穴にでも入りたい気持ちだったが、仕方なく会うと、相手の用件は別のことであった。しかし佐藤の方から切断のことについてわけを話し、謝ったそうである。
一方、佐藤進と同じ時代を生き、陸軍軍医のトップに立った医師、石黒忠悳(いしぐろ・ただのり)の自伝には、明治10年の西南戦争の話が出てくる。
上腕に骨折銃創を負った兵が二人、病院に運び込まれてきた。一人は当時の常識に従って上肢を切断したが、もう一人は比較のために腕を残してみようじゃないか、ということになった。腕を落とした方は軍を退かざるを得なかったが、腕を残した方は何とか銃を持てるくらいには回復したので軍をやめず、その後陸軍大将になった、それが寺内正毅(てらうち・まさたけ、ついでに総理大臣にもなった)だったというのである。
石黒について、私はこれまでにも何度か取り上げたが、相当アクの強い人だったと思われる。この話もまるで、寺内が出世したのは自分のおかげと言わんばかりである。佐藤の医学に対する謙虚な態度と比べると、かなり違う印象を受ける。
自分が切った足のことを、後々まで気に病んだ佐藤進というのは、良心を備えた立派な臨床医だったのではあるまいか。人の手や足を切り落とすことの後ろめたさを共有できたようで、私は親近感を覚える。
2020.11.25
|
|
痛みの専門家
|
麻酔科医は痛みの専門家と言われることがある。「言われる」と言っても、あまり誰も言ってくれないので、主に麻酔科医がそう言うのである。しかし、痛みというのはなかなか手ごわい相手であり、麻酔科医も持て余しているというのが本当のところではあるまいか。
全身麻酔をすると、たしかに手術の痛みは感じなくてすむ。しかしこれは、脳を薬で混乱させて痛みを分からなくしているだけで、からだの方は痛み刺激にちゃんと反応しているから、痛みを制御しているという実感は持てない。
「ノックアウト強盗」というのがあって、通行人をいきなりこん棒でなぐり、目を回している隙に財布を奪うのであるが、これと全身麻酔と、どこが違うのかという悲しみに襲われることが、私にはある。
麻酔科医の中でもペインクリニックをやっている医師ならば、痛みの専門家と言えるのではないか。
たしかに、神経ブロックなどが著効を奏し、患者さんが痛みから解放されると、ああ、麻酔科医もたまにはいいことをするのだという自己満足に浸れることもある。だがしかし、そういう患者さんはすぐに病院通いから卒業する。そしてあらゆる治療に抵抗する、難治性の慢性疼痛に苦しむ患者さんが、ペインクリニックの外来に残っていくのである。これで、痛みに勝っています、と言えるかどうか。
どこかに、痛みを自由に制御する方法があるのではないか、考えてみたい。
戦争の記録などで、時々こんな描写に出会うことがある。
「白兵戦を無我夢中で戦っているうちに何とか生き残り、味方の陣地に帰ってくると、お前左腕をどこにやった、と言われる。見ると自分の左腕がちぎれてなくなっているが、言われるまでまったく気がつかなかった。」
これは今作った話だが、先ごろ紹介した「私は魔境に生きた」の中にも同じような記載がある。戦闘中など、極度の緊張状態では痛みを感じなくなるということで、生存確率を高めるための合理的な仕組みである。科学的には、これは「下降性抑制系」という中枢神経の働きによると説明されているようである。つまり、痛みが脳に伝わる神経回路のどこかで、痛みの伝達を抑えるような仕組みが、人体には備わっているのである。そしてその指令は、脳から来ている。
これが本当なら、下降性抑制系は「痛みを軽くする」だけでなく、たいへんな怪我でも「痛みを全く感じなくする」までできてしまうということになる。われわれ麻酔科医は仮にも自称「痛みの専門家」である。これを利用しない手はないだろう。
誰でも真っ先に思いつくのは、手術の痛みや慢性疼痛に困っている患者さんを、銃弾の飛びかう戦場に連れて行くことであろう。だが、弾に当たってしまう可能性など、いろいろ問題が多いので、あきらめざるを得ない。
下降性抑制系を活性化する薬はないだろうか。モルヒネなどの麻薬は、この下降性抑制系を活性化すると言われている。たしかに麻薬は最強の鎮痛薬であり、麻酔科医は日々お世話になっている。だが、痛みを感じなくするほどの量を投与すると、呼吸は止まり、意識はほぼなくなる。
今回のプロジェクトの目標は、たとえ手術中でもニコニコ笑ってご飯を食べていられるほどの鎮痛法の発見である。(胃の手術中は、食事は遠慮していただく。)麻薬は惜しいけれども、副作用で却下だ。
もしも下降性抑制系を活性化する音楽、踊り、ツボ、香り、パスワードなどが発見できたら、医学界の大きな進歩になるだろう。それが、痛みを全く感じられないほどの「戦場レベル」のものだったら、夢のような話である。そして、痛みの専門家である麻酔科医は、無事失業となる。
2020.11.15
|
|
マスクの下
|
新型コロナの時代、人々がマスクをつけるようになり、街なかでも仕事の場でも、人の素顔というものがなかなか見られなくなった。職場によって違うだろうが、病院ではマスク着用義務はやはり厳しくなっており、休憩中も基本はマスクである。新人歓迎会をはじめ、各種宴会はすべて消滅したから、私は今年就職した研修医の素顔をほとんど見たことがない。
もっとも、われわれ麻酔科医のような手術室勤務者は、こういう状況には慣れている。昔から手術室では、互いの顔を知らないまま仕事をすることが多かった。たとえば新しい病院に勤務すると、目だけの外科医や看護師さんたちと一緒に仕事をし、しばしば数カ月はその素顔を知らぬまま、気心だけ分かってきたりするのである。
仕事に必要なのは声による情報交換と、手と足による物理的作業であり、顔などというものは、あってもなくてもどっちでもいい、ということをわれわれは知っている。
そんな中、何かのはずみではじめてその人のマスクをはずした顔を見ることがあるが、それはいつも驚きを伴う。数ヶ月間、想像してきたのと違うからである。意外に口が大きかったり、エラが張っていたり、ヒゲが生えていたりするのだ。
ただし違うからと言って、何がどうということはない。仕事の中で、どのような人かはもう分かっている。素顔を知って何が変わるわけでもない。「マスクをつけてるほうがよかった」などという感想は、抱くべきではないし、仮に抱いてしまったとしても決して口に出してはいけない。
もし万が一、あの人のマスクの下の素顔をどうしても見たい、と気になり始めたとしたら、それは危険な兆候である。それは自分の気持ちが仕事を離れ、その人に個人的な興味を抱きつつあることを示しているからである。そのような感情は、仕事の邪魔にしかならないので、危険物廃棄箱にでも放り込んで処理しなければならない。
私はもはや、そのような邪念に惑わされることもないが、若い頃一度だけ、その処理に失敗したことがある。それは実に重大な結果を引き起こした。私は今も、その影響を受け続けている。
先の日曜日、妻と買い物に出かけ、ふだん目を向けることもない妻の顔をたまたま見たところ、マスクをつけていた。三十数年前、ある病院の手術室で妻と出会い、このマスクにやられたのだということを、ついうっかり思い出した。
2020.11.9
|
|
点滴勝負
|
麻酔は静脈路確保(いわゆる点滴)から始まる。
患者さんは、点滴くらい一発で入るのは当たり前と思うだろう。ところがそうでもないのだ。
そもそもこれは、管の中に別の管を刺し入れる作業である。ちくわの穴にキュウリを突っ込むのとはわけが違う。静脈には入り口がないから、針で刺して穴をあけるのだが、その壁は柔らかく、破れやすいし、うっかりすると向こうの壁を突き抜けてしまう。何十年、あるいは何百年医師をやっていても、よく見えてる血管を失敗することはある。
ちょうどサッカーのペナルティー・キックのようなものだ。入って当たり前と思われがちだが、最後は運だ。運が悪いと誰だって失敗し、失敗されるのだ。
もっとわかりやすく卓球に例えると、あと1点で勝てるという時に、相手がふらふらっと上げたゆるいチャンスポールのようなものだ。打つまでになまじ時間があるだけに、雑念が入り、力まざるをえない。これをきちんとスマッシュして決めきることがいかに難しいか、どなたにも経験があるだろう。
麻酔科医は毎日、西医体優勝がかかったスマッシュ、ワールドカップ優勝がかかったペナルティー・キックを打つ重圧に耐えているのだ。
患者さん側には、そこのところが伝わらないのはやむを得ない。埋められない溝である。
点滴を2回以上失敗することもある。痛い思いをしているのは患者さんの方なので、機嫌が悪くなるのも無理はないが、ほとんどの場合、患者さんの静脈に問題がある。だがそれを言っちゃあオシマイなので、謝りながらまた刺すしかない。
ある時、私が3回目の点滴に取り組んでいる最中、患者さんから、「イタタタ、下手くそ!この先生、下手くそや」と言われた。言い返すことのできない私に代わり、ナースが患者さんをなだめてくれることを私は期待した。しかし、誰も私を応援してくれなかった。
「いやいや、この先生下手くそじゃありませんよ。あなたの血管が普通じゃないんです。」
とか何とか、言ってほしいのに、誰も言ってくれなかったのだ。点滴は何とか入ったが、言われっぱなしで終わったのは残念だった。あとでナースに聞くと、こういう答えが帰ってきた。
「目の前で点滴2回失敗した先生を、ホントは上手なんですよ、なんて言えませんよねえ、ナースは。」
言われてみれば、ナースは常に患者の側に立つ人であり、医師の気持ちを代弁する人ではない。麻酔科医に味方はいないのであった。
だが、ナースがガツンと言ってくれることもある。
これは聞いた話だが、救急外来でやはり血管の細い患者さんがいて、何度か点滴を失敗され、激怒し始めたという。「院長を呼べ」と大声を出す患者さんに対し、ベテランナースがこう言ったそうだ。
「ここに院長を呼んだってだめですよ。院長が一番ヘタクソなんですから。」
点滴を巡る患者さんと医師の攻防、勝ったのはナースだった。
2020.10.25
|
|
信号機、その2
|
私は警察官に叱られたのをきっかけに、どんなささいな信号も守ってみせる、という個人的社会実験を続けている。これが小説なら、通勤の際、毎朝自分と同じようにどうでもいい信号を守る女性がいることに気づき、いろいろあって殺人事件が起きたり、隕石が飛んできたりするのだろうが、私の身の回りに、そのようなことが起こる気配はない。私の思うに、せっかく信号をきちんと守っても退屈なばかりで、何もいいことがないのだ。これでは、普通の人はますます守らなくなる。何かごほうびが必要だと思う。
もし私が信号順守促進担当大臣になったら、信号機の下にディスプレイをつける。赤信号になると、そこに何か暇つぶしになる画像、動画、文章が現れるのだ。もちろん、赤信号で渡る不届き者には、それは決して見えない。
表示される内容については、地域の諸団体に信号機を一本ずつ割り当て、ボランティアで作ってもらうことになる。近くの小学校からは、子どもたちの絵や習字の作品、新作なぞなぞ、物知りクイズなどが出展され、それはそれで楽しい。だが老人会も負けてはいられない。公民館の各種教室でこしらえた俳句、傑作ダジャレ、ちぎり絵、自伝(連載20回分)などで小学生を圧倒するはずであったが、赤信号横断阻止率を比べてみると、小学生に完敗なのであった。
私の病院も、近所のささいな交差点のささいな信号機を一本、担当することになるだろう。掲示内容は週一回更新しなければならないから、私にも原稿依頼が回ってくる。(私が信号順守促進担当大臣であることは秘密である。)他の医師は、「健康一口メモ」など、読む人の役に立つことを書いているようだが、麻酔科医は自力で人を健康にするわけではないからネタに困る。ここは、赤信号暇つぶし掲示物の原点に戻ろうと思う。
信号に引っかかって立ち止まるたびに、本当に人はかわいい絵や、ためになる情報を見たいであろうか。哲学者ではない私たちは、くだらないことを考えながら歩くのが楽しいのだ。変に力の入った作品を見せられて、自分のふやけた脳を刺激したくない人も多いのではなかろうか。
たとえば食事をしながら、見たいテレビもない時、わざわざ「カラマーゾフの兄弟」などの重たい本を広げる人はいないだろう。しかしいつの間にか、フリカケの袋に書いてある原材料リストを眺めていたりするのだ。本物の信号待ちのプロには、そういうものが喜ばれるはずだ。
私の作る赤信号暇つぶし掲示物は、楽しくもなく、ためにもならず、ただわけのわからない字の羅列であり、目から入って脳を素通りし、直ちに後頭部から出ていくものである。それならば、この「麻酔科パラダイス」をそのまま流せばいいということになるが、公衆の目に触れるものであるから、このような根も葉もないような内容ではまずいだろう。どうでもいい内容だが、あながち嘘でもない情報を流してみたい。
今朝のごはんはおいしかったですか?そのとき、あなたの舌の後ろ半分の味覚は舌咽神経に乗り、舌根部を出て上方に曲がり、内頚動脈と茎突咽頭筋の間を垂直に上り、下神経節を経て頚静脈孔から頭蓋に入り、上神経節を通って延髄の後外側溝の最上部に入ったのでした。すごいですね。
これで、100人に1人くらいの足を止める自信がある。
2020.10.17
|
|
信号機
|
数年前私は、横断歩道を渡っていて、警察官に怒鳴られたことがある。「赤信号ですよ!」と怒鳴る声は、1,000メートル四方に響き渡りそうなほど大きかった。
たしかにそのときの信号は赤であったが、その横断歩道の片側の道路は歩行者天国のためにその日封鎖されていたのだ。そこに突っ込む車があるとすれば、アクセルとブレーキの見分けがつかなくなったドライバーによって加速されたもの以外は考えられなかった。気弱な私は照れ笑いしながら引き返したが、どうも納得が行かなかった。こんなどうでもいい信号を守らせる意味が、一体どこにあるのか。私が反撃しそうにないのをいいことに、発声練習でもしたかったのか。
こういう時、人によっては、硬直した官僚主義を嘆き、官憲の横暴に怒り、政府転覆を企てるに至る人もいるかもしれないが、私はより困難な道を選ぶ人間だ。この警察官が望む通り、どうでもいい信号も全部守るとどうなるか、一体何が起こるのか、実験してみることにした。
細い道を横切る信号機つき横断歩道は、赤でも止まって待つほうがむずかしい。車が来てないと分かれば、普通の人は渡ってしまう。ここをこらえて、青になるまで待つのである。私はこれを数年続けて見たのだが、今のところそのあきらかな利点はよくわからない。ただ、小さな発見ならいくつかある。
赤信号を渡る時、人は意外に複雑な作業をしていたのだとわかった。車が来ていないか、来ていたとしてもあのスピードなら、先に渡れるのではないか、近くで小さな子どもがけなげに信号を守っていないか、周囲に警察官はいないか、これらは最低限判断する必要がある。子どもや老人には、なかなか難しい作業である。
一方、赤なら条件反射的に立ち止まる、と決めてしまえば、何も考えないですむ。自動車ごときにビクビクしながら歩くくらいなら、信号を守ってボーッと歩くほうが幸せと言えないことはない。確かに、自由を得たような感覚がある。
他に気づいたことと言えば、意外に、私と同じようにささいな信号を守る人が、たまに存在することである。一体どういうつもりか知りたいものだ。やはり警察官に怒られたのだろうか。
この実験、大した成果は出ていないが、気がつけば私の認知症の日々も近そうであるから、このまま続けるほうが吉であろうと思っている。
2020.9.27
|
|
主語抜き
|
「見れる」、「食べれる」などのら抜き言葉が「若者の間ではやっている」、「正しい日本語ではない」として問題視する人がいる。
だが、広島では話し言葉としては、昔から使われている由緒正しい日本語である。
こういう下らない因縁をつける暇があったら、「主語抜き文章」をなんとかしたらどうか。
以下は、朝日新聞の天声人語の冒頭部分である。
「久しぶりに強い腰痛に見舞われた。」
「三十数年前、法学の授業でカタカナと格闘した。」
「先月来、元号史を調べる必要から『易経』など漢籍をたびたび開いた。」
一瞬、誰のことかと私の目は泳ぐのだが、どうやら天声人語の筆者自身のことらしい。
文章の冒頭なのだから、「私は」、「筆者は」と書いてくれたらいいのに、何で省略するのだろう。
随筆ならわかる、署名記事ならまだ許せる。これは匿名コラムなのだ。
誰も筆者について予備知識がなく、関心もないのに、いきなり「腰痛に見舞われた」などと来られるのだから、これを読んで「うっ」と気を失う人が一人、二人いてもおかしくない。
これを書いた人は「主語が『私』だというのは、馬鹿でもわかる」とでも言いたいのだろう。
だが実際には読者は、もう少し先を読まなくてはそれが確認できない。
無駄な労力を使わされた上に、見下されているようでもあり、カチンとくる。
新聞記者なら新聞記者らしく、小学校で習った作文の基本(いつどこで誰が...)を思い出し、守ってほしいものだ。
理系の論文だったら、こういうことは起こらない。
「我々は腸内細菌の腸にも腸内細菌が存在すると想定し、調査することとした」などと、一人称もきちんと書く。
読む人は余計なことを考える必要がない。
と思ってきた私だが、最近、理系の世界にも主語抜きが存在することに気付いた。
近年、大雨などが予想されるときの気象庁の説明に「今まで経験したことのない」という表現がつけられるようになった。
何か違和感があるなあと思っていたが、気がつくと主語が抜けているのであった。
今夜予想される大雨が、「その地方に住んでいる人が経験したことのない大雨」なのか、「日本人が誰も経験したことのない」ものなのか、主語が違うと全然違う。
ひょっとして「地球が経験したことのない」スーパー豪雨だとすると、もうどこにも逃げる必要はなく、お茶でも飲んでおけばいい、ということになる。
気象の予報はれっきとした理系の仕事である。
例の表現は腰の重い民衆の警戒心を煽り、避難する気にさせるためにわざとやっているのであろうが、やはり理系は理系らしく、正確な表現を採るべきだと思う。
「今まで経験したことのない」を1年に10回も20回も使ってしまうと、オオカミ少年のように、そのうち相手にされなくなるだろう。
2020.9.13
|
|
サバイバル、その2
|
前回私は、サバイバルの参考書として「私は魔境に生きた」という本を紹介した。
これは日本の敗戦を知らぬまま、ニューギニアの密林で10年を送った島田覚夫(しまだ・かくお)氏の手記である。
サバイバルの書としても興味深いが、何と言ってもこの島田さんという人物がすごい。
自分のすごさを自慢するような人ではないが、どうしても手記からもれ伝わってくるのである。
にわか島田ファンとして、私が代わりにそのすごさを自慢してみたい。
この物語の冒頭、日本軍は連合軍の攻撃にさらされ、一方的に敗走し、ジャングルで孤立する。
そして、日本軍が容易に挽回できる状況でないことを悟り、敵の目の届かない密林の中で、島田さんは16人の仲間とともに籠城することを決意するのである。
この状況は、大岡昇平(おおおか・しょうへい)の小説、「野火」に似ている。
「野火」では、フィリピンの戦地でジャングルをさまよい、飢餓のために人間らしさを失っていく敗残兵の地獄が描かれている。
小説ではあるが、「敗軍における僚友が、どういうものであるか知っているはずの私が、(中略)協力しうると信じてしまったのは…」という言葉には、重みがある。大岡氏自身が、フィリピンで戦った人だからである。
極限状況では隣の日本兵こそが、一番危険だったのである。
島田さんたちはどうか。力を合わせて命がけで食料確保に奔走し、階級にかかわらず公平に分け合った。豆粒のようなカニをつかまえても、人数分に切り分けるのである。
籠城してからもしばらくは、日本軍の食料庫にアクセスできた(敵の待ち伏せ覚悟ではあるが)という幸運はあっただろう。
しかし、仲間の多くを敵襲、マラリア、飢餓で亡くしているという点では、島田さんたちも生きるか死ぬかの状況にあったのは間違いない。
彼らが人間らしさを失わず協調できたのは、おそらくはリーダー格の島田さんの人徳のおかげではなかろうか。
籠城も後半に入ると、彼らは原住民に見つかってしまうが、島田さんは落ち着いて交渉し、すっかり仲良くなってしまう。
それどころか知識や技術を提供しあい、共存共栄の関係になる。
島田さんは言葉も通じない人たちにも信頼されたのである。
さらには、すぐに現地の言葉を覚えて、互いの家を行き来するようになる。
日本人は温厚だから、などと片付けてはいけない。
名前はここでは伏せるが、島田さんたちよりももっと長く、戦後29年間もフィリピンのジャングルに潜伏した日本兵がいた。
その人の場合、フィリピンにいる間、たびたび現地の人を襲撃、殺害していたらしい。
手記を信じるかぎり、島田さんたちは人を殺さなかった。
潜伏初期には原住民の農作物を失敬したり、生きるために可愛がっていた犬を殺したりしているから、手記がきれいごとだけで埋められているのではない。
だが、彼らは敵も、味方も、原住民も殺していない。
死線をさまよいながらも、ずっと尋常の人間であり続けた。そこがもう、尋常ではない。
古来、戦記物において、敵を多く倒した兵士は讃えられてきた。
しかし敗戦後、それはずいぶん難しいことになった。
新聞やテレビなどの主流メディアにおいては、戦争を取り上げたとき、「戦争は悲惨だ。二度とやってはならない。」で結ぶのが約束である。
戦争は全否定されなければならなくなったのである。
だが、少なくとも島田さんたちに対しては手放しで、心置きなく、「よく戦った」と声をかけることができる。平家物語の言葉を借りるならば…
あッぱれ剛(ごう)の者かな。これをこそ一騎当千の兵(つわもの)とも言ふべけれ。
2020.9.6
|
|
サバイバル
|
アメリカの原子爆弾開発にも少し関係した物理学者アイシュタインは、第三次世界大戦がどのようなものになるかと質問されて、こう答えたそうである。
「第四次世界大戦についてなら答えられます。それは、石とこん棒をつかった戦いになるでしょう。」
つまり、第三次は大惨事だと言いたいらしい。
もし文明が破壊され、「石とこん棒」の時代に戻ったら、つまり電気、ガス、石油が使えず、自給自足の生活を強いられたら、我々は何を食べて生きていけばよいのだろうか。今のうちに考えておくことは無駄ではないだろう。
たとえば公園の鳩、あれを見ても食欲は湧かないが、いざとなったら食べる気になるのか。私の街にはときどきイノシシが出るが、あれはどうやれば仕留められるか。虫、木の実、きのこはどうか… サバイバルの参考書として推したいのは、島田覚夫(しまだ・かくお)という元日本軍兵士が書いた体験記、「私は魔境に生きた」(光人社NF文庫)である。
太平洋戦争終結後、一部の日本兵は敗戦を知らぬまま、フィリピン、グアムなどのジャングルに潜伏し、自給自足の生活を送っていた。島田覚夫氏もその一人で、ニューギニア(オーストラリアの北側にある大きな島)の密林で、友軍との合流を夢見ながら10年もの間生き延びたのである。
熱帯のジャングルであれば、果実など森のめぐみもありそうだし、何とかなるのではないかという気もするが、当初17人いた同志が、敵襲やマラリア、栄養失調で倒れていき、最後には4人になってしまうほど、厳しい生活だったのである。
島田氏たちが山奥で籠城を始めた時はまだ軍の食糧が残っていたが、それが減っていく中、ありとあらゆるものを食べている。野生のパパイヤ、バナナ(種だらけ)、野草(食える草は一種類しかない)など、熱帯の森でも食べられる植物は限られている。ネズミ、色とりどりのトカゲ、ヘビ、カミキリムシの幼虫などは、焼けばなかなかの珍味であるが、そのうち、カミキリムシの成虫にも手を出し、しまいには甲虫らしきものは脚と羽だけ残して手あたり次第に食うようになったという。
私が期待するゲテモノ食いの記載はこの辺りが頂点で、そのうち、農園の開拓に成功し、火喰鳥、イノシシ、川の魚を狩る手段が定着してからは、こういうゲテモノ食いの記載はなくなるから、やはり非常時の食料だったという事だろうか。
さて、大惨事世界大戦を生き延びてしまったわれわれは、こういったものを食べることになるのであろうか。
実際には、このようなたんぱく源はどうしても量に限りがあり、今の日本の森、川、海では、日本の人口は支えられないであろう。狩猟採集に頼っていた縄文時代の人たちは、気温が下がってきたとき、日本全体で2,30万人という人口ですら維持できず、大激減を経験しているのである。
やはり、島田氏が身をもってしめしたように、安定した食料供給のためには農業が頼りである。でんぷんを目の敵にする糖質制限論者も、泣きながらコメやイモを食べるようになるだろう。
この手記を読んで思うのは、食わなければ死ぬからなんでも食う、というのは、誰にでもできるわけではないということである。私だったら、どこかで諦めていた可能性が高い。とにかくこの島田氏らはまだ20代と若く、生存欲がすさまじいのである。だからこそ生き残り、こうやって手記を書くことができた、とも言える。
そういうわけで、昆虫、ネズミ、トカゲは食って食えないこともない、というのを学んだところで、今回はお開きとしよう。こういうものを食べる練習をしたいとは、今は思わない。
ここでは書ききれなかったが、この本にはイノシシの狩り方、生存に必要な道具の作り方、炭づくりから始まる鉄の鍛え方など、いざというときに役に立つかもしれない、サバイバルのヒントが山盛りになっている。こういうのがお好きな方は、ぜひ読んでいただきたい。
2020.8.29
|
|
地球人
|
惑星ゴラスという本多猪四郎(ほんだ・いしろう)監督のSF映画があった。私が生まれる前の映画なので、私が子供の頃見たのはテレビ放送だったのだろう。地球に向かって飛んでくる巨大隕石との衝突を避けるため、南極に巨大バーナーを設置し、地球のほうを移動させるという、おごそかなラストシーンだけが記憶に残っている。
今思えば、これは相当に思い切った決断であって、地球の軌道修正に失敗でもしたら、地球は太陽系から飛び出してしまう。そうなったら地球の生命は終わりだ。そうでなくとも世界の気候は当分めちゃくちゃになるだろう。世界の人類全体の強固な合意がなければ、決してできない壮挙(もしくは暴挙)である。
今、現実の人類はどうだろう。核兵器、新型コロナ、地球温暖化、プラスチックごみなど、さまざまな問題が人類の生存を脅かしているが、世界が一つにまとまる気配は全くない。すこしずつよくなっているのならまだしも、今回のコロナ禍に対する指導者たちの言動を見て、私は愛想が尽きた。
新聞などのメディアで、人類が知恵を合わせればコロナ(戦争、温暖化)は克服できるはず、といった記事を書く人がいるが、それは人間を買いかぶりすぎだろう。
ヒト(ホモ・サピエンス)が他の動物よりも優れているのは、言葉などを通じて教えあったり助け合ったりできるところである。だがその範囲は、知り合いの知り合いの知り合いくらいまでの規模であろう。部族とか、村とかの利害を考えて協力し合うことはできても、地球の何十億人の人たちと心を合わせるなどということはできない。これまでの人間の進化の中で、そんな能力が必要とされたことはなかったからである。
頑張ればできる、そういうのは、テレビの中の松岡修造(まつおか・しゅうぞう)にでも言わせておけばいい。生物には、自分に与えられた能力を超えることは決してできないのである。たとえば、あれだけ利口な、もしかして人間より賢いのではないかと思われるチンパンジー、彼らにはどれだけ教えても、絶対に石器が作れないらしい。
悲劇は、そんな無能な人間が、地球全体に悪影響を及ぼす力だけを持ってしまったことだった。
さて、どうすれば解決するか。まず考えられるのは、ヒトがもう一歩進化し、地球ファーストで自分の行動を律することのできる「地球人」という新しい種を生み出すことである。私の持論により、それは多様な遺伝子の宝庫、アフリカ大陸で発生するだろう。もっとも、最低でも数十万年はかかるだろうから、その前にヒトが滅びる可能性は高い。
ついでに言えば、旧来のヒトは新しい「地球人」と共存できず、ネアンデルタール人のように滅亡する可能性が高い。
そのような気の長い方法では待てない、ということであれば、例によってまたSF小説の知恵を借りることになる。
アーサー・C・クラークというSF作家も、たぶん、人間の賢さに限界を感じていたのだろう、作品の中では地球外知性体の力を借りて人間を進歩させている。「2001年宇宙の旅」シリーズでは、正体不明の存在が、モノリスという物体を通じて人間の進化を促すし、「幼年期の終わり」ではヒトよりもはるかに優れた知性を持つ宇宙人が降臨し、愚かな地球人を指導してくれる。
クラーク流の地球外知性体への他力本願がいやならば、人工知能に地球を支配してもらう、という方法も考えられる。
とにかく、ヒトは生物として、地球規模の問題に取り組むのに向いていないかもしれない。そんな諦めから話を始めることも必要だろうと思うのである。
2020.8.23
|
|
ナースコール
|
もし手元にボタンがあって、それを押しさえすればすぐに、おおむね若い女性あるいは男性がやってきて、おおむね頼みごとを聞いてくれる、そんな機能がついていたらどうだろう。
ドラえもんも真っ青の、夢のようなボタンと言えるのではなかろうか。
だがそれは、存在する。
入院患者のベッドに備え付けられているナースコールのボタンが、それである。
私は当事者ではないのでこれは想像であるが、新しく入院した患者さんに、このナースコールの使い方を説明するとき、看護師はやや緊張するのではなかろうか。
介助が必要なのに、遠慮のためかナースコールを押さないでトイレに行こうとし、転倒するご老人がいる。
逆に、ナースコールを押しすぎて、「連打地獄」のダークサイドに陥る人もいる。
呼ばれて看護師が行ってみると、「そこの眼鏡取って」とか、「お前じゃない、あっち行け」とか言われたり、唾を吐かれたりすることもある。
そして、看護師がナースステーションに帰るとまた鳴っているのだ。
看護師は常に忙しいのだ。本当に必要な時だけ、押してほしいというのが看護師の本音だろう。
これを、これから病気と闘う人にどうやって分かってもらうか、である。
私が看護師なら、こんな言い方をするかもしれない。
「もし事態が深刻化し、支援が必要な時が来れば、躊躇なくボタンを押す決断を下していただきたい。」
だが、あるとき救急病棟で私が目撃したのは、まったく違う光景だった。
かなりぼんやりした感じのご老人の新規入院、担当は期待の若手イケメン看護師A君だ。
彼は患者さんの手にナースコールのボタンを握らせ、こう言った。
「これを押すとね、すぐに看護師が来ますよ。」
そして笑顔でこう付け加えた。
「便利でしょう。」
2020.8.16
|
|
麻酔科部長
|
私の同期の麻酔科医O君が、まだ卒後6年くらいだったと思うが、ある小さい病院に一人医長で赴任することになった。その病院の唯一の麻酔科医であるから、何があっても自分で背負わなくてはならない。かなりの重圧を感じていた。
非常事態についてはとなりの病院の麻酔科に応援を頼めばいいということだったが、彼の心配は別のところにあった。
まだ経験十分とは言えないのに一人で仕事していると、麻酔が我流になってしまうのではないか、というのである。それを聞いた1年後輩のH君が、こう言ってO君を励ましたそうだ。
「何言ってんだよ、O先生。うちの大学の関連病院の部長たちを見てみなって。みんな変な癖だらけの我流(がりゅう)だろ。」
これは私の知る麻酔に関する名言のなかでも、もっとも上位のものである。
これに匹敵するのは、研修医時代の心の師であるM先生の、「麻酔なんてな、かけて醒めればみな同じや」と、3年先輩のK先生の、「麻酔というのは、来た球を打つ、それでええんや」くらいである。
もともと麻酔科医というものは、外科などに比べると単独で仕事することが多く、それぞれ癖がある。
たとえば、気管チューブをテープで固定する時、その留め方はこうでなくては、というつまらないこだわりがあって、他の人の留め方ではまったく我慢ができないのである。
手技以外でも、麻酔依頼の断り方とか、部下の育て方とか、そういう内外の関係についても、麻酔科医の個性というのはかなり出るものである。
これが一人医長、部長ともなると、誰からも指導、矯正を受けることがなくなるので、もっと我流になる。
さらにそういう状態で長年経過すると、自分のどこが我流なのか、それすら分からなくなるのだ。
ちょうど、自分の家にたまっている匂いが自分では分からないようなものだ。
私は若いころから、いろんな病院で勤務、非常勤をやらせてもらい、いろんな部長の麻酔にじかに接することができた。
結論から言えば、個性的でない人は一人もいなかった。部長のからだからむらむらと立ち昇るこの空気は、緑の術衣をまとっていないと現れないものであり、大学の同門会などでスーツを来てしゃべっているだけではとても分からない。
そうやってみんなどこか偏ったものをはらみつつ、不思議と病院のカナメ部分である麻酔科をうまく成り立たせているのだから、えらい。
O君がその病院で一人医長をやっているとき、大学院生だった私は2,3回非常勤勤務に行ったことがあるが、すでにそこはO君ワールドになっていた。
かりに本人がどれほど自分の癖を抑えるつもりだったとしても、どの道、そのようにしかならなかったであろう。
同期とはいえ、こちらは臨時雇いである。雇い主の言葉や動きから、自分がどうすればいいかを読み取るのがこの世界のお作法である。
いずれ「全国麻酔科部長列伝」みたいなものができると、面白いと思う。ちなみに私も麻酔科部長だが、人畜無害、無味無臭をモットーとする私には、おかしなところも、おもしろいところも何もないから、「列伝」に載る心配はない。
2020.7.26
|
|
現代の怪談
|
新型コロナ第2波の拡大が止まらない。
私は専門家ではないので、憶測でものを言えるのだが、再感染の波形を見る限り、東京新宿のいわゆる夜の街からクラスターが同時多発した、ということでいいのではなかろうか。
それにより東京が爆発し、地方に飛び火し、日本が炎上して、今ここ、ということだと思われる。
ごく一部の若い人たちの向こう見ずな行動が、日本を危機に陥れている、とも言える。
これが強権的な国であれば、法律を無視して震源地を封鎖なりするのだろうが、日本の行政がやっているのはいまだに「呼びかけ」だけである。
つくづく日本は自由な国だと思う。
若いもんが無茶をして困る、というのは、大昔からの生物界の悩みであった。
昔一匹のやんちゃなサルが地上を後ろ足だけで歩くようになり、他の軽薄なサルたちも真似をし始めた頃、大人のサルたちは木の上で眉をひそめていたに違いない。(眉というものがあったとすれば。)
地上に降りたばかりに、肉食獣に襲われる個体もあっただろう。
それを弾圧、粛清するようなサル社会だったら、二足歩行は定着せず、今の人類は存在しなかったはずである。
このように若い人の無謀な振る舞いには、いいこと(人類が生まれるとか)と悪いこと(人類が生まれるとか)とがあるが、とりあえず今はちょっと私の身が危ないから自重して欲しい。
若者を法律で縛ることができないのであれば、ここは昔の知恵を借りることはできないか。
昔は娯楽というものがなかったから、村人は夜、白髪の長老、皺の深いおばあさんのところにあつまり、昔話を聞かせてもらっていた(と思う、映画で見た)。
それらは何しろ何十世代と語り継がれてきた話であり、つまらない部分は削ぎ取られていくから、面白くないはずがない。
昔話は、若者にさりげなく、「こういうことをしてはいけない」というタブーを教える機能も持っていただろう。
特に、怖い話にはそういう意味合いが強かったはずである。
それに習い、新型コロナ恐怖伝説をつくり、ひそかに流布させる、みんな自重する、というのが今回の私の計画だ。
ではどうすれば怖い話が作れるか。
現代でも若い人の間で怖い話が発生し、SNSなどで回し読みされているらしい。
何かの本で、そうした現代の怪談を集め、日本と海外のものを比較しているものがあった。
例えば、あるフランスの怪談では、自分の部屋に突然、黒ずくめの鎧を着た騎士が黙って続々と入ってくるのだそうだ。
フランスの若者は、それを想像しただけでもう、からだが震えるほど怖いのだと。
その恐怖のツボは、ちょっと日本人にはわからない。
一方、日本の怪談は心の内面をつくものだという。
たとえば、コインロッカーに生まれたての子どもを捨てた女性の話。このことがばれないまま過ごした数年後、女性は迷子になって泣いている子どもを見つけ、「お母さんはどこにいるの?」と声をかけた。
するとその子どもはキッと顔を上げ、「お前だよ」と言ったのである。
これは怖い。バチが当たって死ぬとか、地獄に落ちるとかよりずっと怖い。
心に抱えている後ろ暗さをえぐりだす怖さだ。
しかも、街中で泣くような、いたいけなものを使うところが効果的で、心憎い。よし、これで行こう。
新型コロナとかいうものが流行っていた頃、三密を避けるとか、マスクとか、そういうのをまったく意識せず、夜の街で乱痴気騒ぎを繰り返している男がいた。
一時体調が悪かったこともあるが、気にしないようにしていた。
あるとき、男が遊び疲れて朝帰りをする途中、道ばたで泣いている老人を見かけた。
自分の母親のカラオケ友達のゲンさんに似ている気がしたが、勘違いだろう。
先日、急病で亡くなったはずだ。
男は素通りして帰ろうとしたが、おかしい、老人が泣きながらついてくるではないか。
男は気持ち悪くなり、走って帰り道を急いだ。
男はニュースなど見ないので、知らないことであったが、厚労省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ」が勝手に奇怪な進化を遂げ、自分にウイルスをうつした人間を追跡調査できるようになったのである。
しかもそれが霊界にまで広まり、死者たちの間では、ウイルスを自分にうつした人間につきまとうのが流行しているのである。
慌てて家に帰ると、母親がドアを開けて中に入れてくれた。
四十九日がすんだばかりの母親だった。
どうだ怖いか。
2020.7.19
|
|
妖怪大戦争
|
ここのところ、新型コロナが息を吹き返している。東京では連日200人の新感染者が出るようになった。ところが政府は経済活動維持にこだわっているようで、県をまたぐ移動の制限、店舗などの営業の制限はもう二度とやらない、と心に決めているように見える。それでうまくいくという自信がどこから来ているのか、私には分からない。
世の中のことは変えられないとしても、感染予防のために身の回りでできることはある。
私の勤め先の感染管理担当の先生によると、院内感染は別として、とにかく人との会食が一番危険とのことであった。
たしかに最近クラスター発生源として問題になっているのは酒を飲みながら騒ぐ夜の街、多人数で歌うカラオケ店である。複数の人が長時間声を出し続けることで、エアロゾルを交換しあい、ウイルスを交換しあっているのであろう。
こういうところには、私は行かない。
一時、パチンコ店が営業を自粛してくれないことが問題になったが、パチンコ屋でクラスターが発生したという話は聞かない。
みんな黙々と打っているわけだから、実はかなり安全な場所だったのかも知れない。パチンコ店の前の行列を白い目で見たりして、悪いことをしたと反省している。
言葉による情報交換は、ヒトがここまで進化するための決め手であったと思われる。現生人類と一時ヨーロッパで同じ空気を吸ったであろうネアンデルタール人が生き残れなかったのは、発語の能力に劣っていたからだという説がある。
だが今にして思えば、ヒトは言葉と一緒に、ウイルスを交換し合っていたのだ。今、食事、酒、歌などを全面的に禁止する必要はないかもしれないが、近距離で長時間の発声は全国的にもうしばらく我慢してもらいたいものだ。
政府に対策を立てる気がないのであれば、自分でそういう場に突撃して暴れるという方法もあるが、「自粛警察」とばかにされるだけだ。ここは古来の日本の妖怪の力を借りるしかない。
まず活躍が期待されるのが、天邪鬼(あまのじゃく)である。
彼らは相手の言葉をそのまま受け入れるということが決してない。
会食の場には、この天邪鬼が混じる。知らない人に混じっても気づかれないのは、座敷わらしの能力を借りているのだ。
彼らの会話は必ず、「でもね」から始まる。
「俺、ノーベル賞をもらっちゃったよ。」
「でもね、実験して新発見をしたのは部下でしょ。部下の手柄を奪うなんて、サイテー。」
こうやって何でもひっくり返されるから、場は白けてしまう。
こうして会食の場から会話が消え、栄養摂取が終わればみんなそそくさと家に帰ることになる。
家に帰っても似たような会話が待っているのだが、もう仕方がない。
多人数でのカラオケ、感染対策のないショー会場には、鵺(ぬえ)が出現する。
平安時代、夜な夜な気持ちの悪い声で叫びまわり、天皇を病気に陥れたあの鵺である。
誰かが歌うたびに、鵺がそのひどい声で一緒に歌うのだ。気分は台なしだ。みんな、1曲歌ったら帰りましょう。
これら妖怪の仕事を統括するのが、アマビエである。
アマビエというのは、今回のコロナ禍で有名になった海の妖怪である。
江戸時代の印刷物(かわら版?)に一度だけ出てくるのだが、肥後(熊本)沖の海の上に現れ、疫病がはやったら自分の姿を写して人々に見せよ、と言ったのである。
それを見た役人による写し絵が、まるで人魚のゆるキャラのできそこないみたいで、そこが今、人気なのである。
私もまたアマビエに心を奪われた一人である。たまらず、大枚千円を払って「アマビエ、クリアファイルセット」を買い、日々の術前診察に使用している。
役人の報告書には、アマビエの姿を写せば疫病がやむ、とまでは書いていないが、これだけ世に広まって、さすがに何もしてくれないということはないだろう。
ただそのとぼけた顔をどう見ても、特殊な能力を持っていそうにないので、妖怪たちに指示を出す係かな、と思っておく。
そろそろ出番です、アマビエさん。
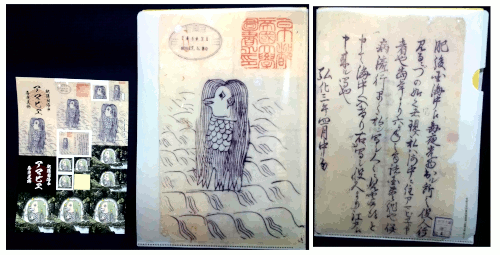
アマビエのクリアファイルと、もったいなくて使えないシールのセット
2020.7.11
|
|
電網閻魔大王
|
私たちは子どもの頃から、嘘をつくな、と言われ続けてきた。嘘をついても必ずバレるのだから、本当のことを言えと、親も教師も怖い顔で言うのである。かと言って嘘はつかないわけにもいかず、子どもは常に、自分の嘘がいつばれるかとビクビクしていた。しかし意外にバレないことが多かったから、大人の脅しは嘘だったのだろう。
医師も昔は、「癌ではないが、たちの悪い潰瘍です。切りましょう」などとよく嘘の説明をしていたが、近年ではそういうことを言わなくなった。嘘でごまかさないことが患者の利益であり、また医師自身の身を守る事にもなると教えられるようになったのだ。
ところがそれは、われわれ小市民限定のルールらしい。そういう要求をしてくる人たちのもっと上の方の人たち、国の指導者たちは、自由自在に嘘をついているのだ。
シリアのアサド大統領が、自国民に対して化学兵器を使ったことはほぼ確実とみられるが、否定し続けている。
アメリカのトランプ大統領は、自分の都合の悪い情報をすべて「フェイクニュース」という魔法の言葉で片付けてしまう。これも嘘の一種であろう。
ロシアのプーチン大統領に至っては情報機関出身であり、嘘の専門家だそうだ。彼に取って嘘は武器に他ならないのである。2014年ウクライナ上空で、マレーシア航空機がロシアの兵器で撃墜されたが、プーチンは俺たちじゃないと言い張っている。
日本では…まあ、やめておこう。
ここからわかるのは、人間偉くなりすぎると、嘘をついても誰にも叱られなくなるということである。悪意と確信を持って放たれたその言葉は、そのお仲間でない人たちにとっては、害毒でしかない。こんな人たちに、お前たちだけは所得を正直に申告せよと言われても、白けるばかりである。
20XX年、インターネットの中から忽然と、「電網閻魔大王」という作者不明のアプリが現れた。人のあらゆる発言に対し、その嘘の度合いを「嘘指数」としてパーセントで表示してくれるのである。しゃべっている人なら、スマホにその声を聞かせるだけでいい。歴史資料、文献、音声、画像など手に入るすべての一次資料を蓄積したデータベースと、その人の発言履歴などを総合し、量子コンピューターで計算するのであろう、平均1.6秒で数字が出てくる。
嘘と言ってもいろいろある。いい嘘、悪い嘘、ただの記憶違い、言い間違いなど、大きく分けても4,567種類ほどに分類されるが、細かい意味合いは全部省略し、強引に一つの数字だけで表してしまったところが、「嘘指数」が世界に受け入れられた理由であった。
ちなみにこの指数、100%や0%になることはない。100%の嘘というものはなく、どんなでたらめな言葉も一片の真理を含んでいること、逆に100%の真実も存在しないということが、このアプリにより示されたのである。
「電網閻魔大王」は本物の閻魔大王と違って、嘘つきの舌を抜いてくれる機能は持っていないが、記者会見やツイッターでの発言に対してリアルタイムで嘘指数が表示されてしまうので、さすがの職業的嘘つき師たちにも仕事をやりにくくさせる力を持つ。
「メキシコとの国境の壁の費用を払うのは、メキシコだ。〈ウソ73%〉」
「ウイグルの職業訓練所は、決して強制収容所ではない。〈ウソ81%〉入所者はみんな幸せだ。〈ウソ89%〉」
やがて彼らは気がつく。嘘の最後に「多分」とかそういうのをつけるだけで、嘘指数は10ポイントほど低下するのだ。
「新型コロナウイルスは、武漢の研究所からもれたという証拠を手に入れた。多分。〈ウソ72%〉」
「我が国が発射したのは、ミサイルではなく人工衛星だ、と思う。〈ウソ85%〉」
最初の嘘がきつすぎるので、数字は高いが、それでもだいぶましだ。そしてその分、言葉の毒性は薄められる。
さらにこれが、しもじもの者どもにも伝染する。「好きです、死ぬまで愛し続けます、多分」、「もしもし、風邪引いて声がおかしいけど、オレだよ。息子のタカシだよ多分」
絶対こうなる、多分。
2020.6.27
|
|
麻酔中の体勢、その2
|
前回からだいぶ間があいたが、麻酔中の麻酔科医が取る体勢問題の続編である。
麻酔中の患者さんの状態が安定しているとき、ただ立っているのは足がつらいので、椅子に座って麻酔管理を行うわけだが、座っていると頭がボーっとしてしまうのが難点だ。
この状況でいかに集中力を保つかが、私の長年の課題であった。
若い人はどうしているだろうか。研修医や若手麻酔科医でも、この手持ち無沙汰はつらいようである。
私は時々話し相手になるようにしているが、私のつまらない話でも聞いてくれるのだから、よほど困っているのだろう。
だがたまに、ひたすら端然と椅子に座っていられる人もいる。中でも研修医のM君の悠揚迫らざるさまは格別だった。
M君は麻酔中、椅子に座り、涼しい顔でずっと宙を見ていた。
話しかけても、あまりうれしそうではないので、つい放置してしまう。
するとやはり、斜め上方10度くらいの空間を見ている。
研修医ならば、もの珍しいからいろんな手術を見ておこうと思うものだが、彼は術野をほとんど見ない。
手術には何の興味もないそうだ。で、宙を見ながら何を考えているのかと聞くと、「無です」という信じられない答えが返ってきた。
こういう特殊な人間は、麻酔科医にでもしておくしかないと思ったら、彼はほんとに麻酔科医になった。今ごろどこかの病院で、宙を見ているのであろう。
立たないし、座らないという方法もある。若手麻酔科医のA君は、常に麻酔器の周辺をせかせかと右往左往していた。
一緒に働いていたのはもう昔のことなので、正確なところは思い出せないが、とにかく右往左往していたところしか覚えていない。
ときどき独り言も出る。これも記憶は定かではないが、「どないしよー、どないしよー、せや、あれで行って見よか」と確か、こんな調子であった。
たとえ徹夜明けでも、彼が麻酔をしながら、眠そうにしているのを見た者はいない。
常に何かを恐れているのだ。あっぱれな小動物系麻酔科医であった。
M君もA君も、ある意味超人であって、普通の人にはなかなかマネのしにくいスタイルである。だが、両方を適当に混ぜれば何とかなるのではないか。
無念無想で座り、それに飽きたらうろうろ歩き、疲れたらまた座る。これを繰り返すことで、集中力を保つことができそうだ。
念のために書いておくが、その間、バイタルサインのチェックなど、必要な仕事はやっている。
麻酔科医30年、やっと、平凡ながらそれなりの答えを見つけた思いである。
欲を言えば、足の上がらないオヤジでも安全に歩けるような、床に電気コードの這っていない麻酔科医用逍遥ルートと、外が見える窓があればいいなと思う。
2020.6.21
|
|
「寄り添う」
|
最近やたらと「寄り添う」という言葉を聞くようになった。何かいいこと言っている感じはするが、それ以上に、自分、今何かいいこと言いませんでしたか、と言っている感じがする。だが、その中身がよくわからない。
ためしに、患者さんが入院されるときに医師が手渡す「入院療養計画書」を、「寄り添う」、「向き合う」など今どきの前向きな言葉をふんだんに使って作ってみよう。
お疲れ様です。あなたの膵臓に影が見られますが、心配ありません。私たちが全力であなたの病気に向き合い、前を向くあなたに寄り添い、ドンと背中を押します。私たちは患者さんとの絆を大切にし、生命の大切さを発信するため、進化し続けてございます。とにかく、寄り添って、寄り添って、寄り添いぬく所存です。
不安は的中した。やっぱり何を言っているか分からないではないか。
本物の入院療養計画書は、こんな具合だ。
あなたは大腿骨が折れ、歩くことができません。明日、全身麻酔下で手術を行い、骨折を治療します。手術の詳しい内容は、改めて説明します。約2週間後、リハビリ病院に転院し、リハビリに専念していただく予定です。
治療の見通しについて、淡々と述べただけの文章だが、あいまいなところがない。医師による説明に間に合わなかった家族も、これから一体何が起こるのか、これを読んだだけで大体理解することができる。こちらのほうがよほど、患者さんの必要とすることに「寄り添って」いないだろうか。
幸い今、この言葉に軽く逆風が吹いている。
新型コロナがはびこる中、他人にべたべたと近づくのは無謀な行為と見なされるようになった。
電車の中などで知らない人が、勝手に体を近づけて「寄り添って」きたり、突然「向き合って」きてエアロゾルを吹きつけたりしてきたら、これは気持ち悪い。
プラットフォームで「背中を押し」たりしたら、もう犯罪である。
寄り添うとかそういうのは、ほどほどにしていただきたいと願う、今日このごろである。
2020.6.13
|
|
デマ耐性
|
これまでテレビのワイドショーなんかで流れる情報は、気楽に聞き流せるものばかりだった。殺人事件、芸能人の不倫などは、自分が被害者でない限り所詮ひと事だし、政治のスキャンダルは自分にも関係があるとはわかっていても、実害が出るまでの道のりが遠い話である。嘘か本当かはどうでもよくて、面白ければよいのである。
しかしコロナ情報は違う。もしかしたら、のレベルとは言え、情報の正否に自分の命がかかっている。
うつされないための方法、有効な消毒方法、医療機関への受診はどうすればいいか、世の中のコロナ感染の動向などなど。こういう情報は間違ってもらっては困るものばかりである。ところが一方で、何せ現場から政府からみんなが混乱しているから、変な情報もテレビや新聞でたくさん流れた。
私の記憶に残っている怪しい情報を列挙してみると…
-
中国で妙な肺炎が流行しているが、人から人への感染はない。(今年1月ごろ、中国の発表を真に受けた報道)
-
コロナウイルスは熱に弱いので、水を飲むなら暖かい白湯がいい。
-
保健所は、ウイルスのPCR検査を絶対にやってくれないが、有名人なら喜んでやる。
-
PCR検査が足りないため、実際の感染者は公表の数より10倍多い。
-
全国民にPCR検査さえすれば、感染は終わる。
-
外出規制などしなくても、感染は抑制されていた。
-
ウイルスは生物兵器として開発されたものである。
これらは、私の判断ではデマに近い、ほぼ間違った情報である。幸い、日本の人たちはデマ情報に踊らされて、おかしな騒ぎを起こすことはなかったと思う。麻生太郎(あそう・たろう)財務大臣が、「日本人の民度」を自慢していたが、余計なコメントである。日本人が生まれながら程度が高い民族である、と言いたいのかもしれないが、何かの夢を見ているのだろう。日本人だってちょっと昔は、暴れまくっていたのである。
明治10年、日本でコレラが流行していた時、沼野玄昌(ぬまの・げんしょう)という医師が井戸水に消毒薬を入れて回っていたところ、あれはコレラ患者の生肝を投入しているのだというデマが起こった。彼は怒り狂った村人たちに取り囲まれ、めった打ちにされ、殉職を遂げた。当時は他にも、流言飛語にもとづく暴動が全国で多発し、コレラ一揆と呼ばれた。(明治医事往来、新潮社)こうしてみると、日本人が民族の特性として思慮深く、冷静であるというわけではない、と思われる。
多分今、日本人はちょっと賢くなったのだと思う。外出しないこと、手を洗うことは有用であろうと、多くの人は合理的な判断ができた。
これは明治以来政府が取り組んできた教育が機能したからだろう。(ただし、教育熱心の素地は、江戸時代の寺子屋に始まっている。)
日本の教育を批判する人は多いが、私はそうバカにしたものでもないと思っている。
また、極端な妄想系の意見が主流を占めることがなくなったのは、「大東亜共栄圏」、「アジアの盟主」という妄想で舞い上がった後の敗戦で懲りたからではないかという気がする。こうして培った判断力のおかげで、強制力のない自粛要請に、多くの人が応えることができた。
麻生さんが誇るべきは、「民度」などと言う素性の怪しい属性ではなく、こういうデマ耐性を育てた教育と歴史の力ではないだろうか。
2020.6.7
|
|
応援歌
|
日本の新型コロナの新規感染者は順調に減っていき、非常事態宣言も解除となった。まだ感染が収束したわけではないが、ここまで来たのは日本に住む人たちがよく辛抱してくれたおかげだと思う。願をかけて20キャッチを目指した私のジャグリングは、まだ11キャッチがやっとであるから、どうも私のおかげではなさそうである。
今後は医学の問題は背景に回り、経済再生が問題になるだろう。私は経済のことは全くわからないが、どうもあまり日本政府のスピードにはあまり期待できそうにないから、庶民が自分の持ち場で何とかしていくしかないのかもしれない。そんな時、自分の気分をどう持っていくかがむずかしい。
多くの方が亡くなっているから、手放しで喜ぶわけにはいかない。まだウイルスが消えたわけではないから、戦後復興期のようなイケイケドンドンでもなさそうだ。経済的ダメージがこれから山ほど表面化するだろうが、不安に押しつぶされている場合ではない。
今みんなに必要なのは、軽躁なカラ元気でも、厳しい言葉でもなく、静かな励ましではないかと思う。
私は最近、野々村彩乃(ののむら・あやの)さんの歌う「それ行けカープ」という曲に出会い、聞くたびに目頭を熱くしている。
プロ野球チーム、広島東洋カープのこの応援歌は、1975年のペナントレースのさなかに発表された。私が中学1年のときである。この時までカープは「万年最下位」と言われ、ペナントレースで優勝したことのない球団であった。この年も出足で新しい外国人監督、ルーツ氏が暴言と退場を繰り返し、間もなく日本から退場した。その後の監督を、古葉竹識(こば・たけし)というよくわからないコーチに託すなど、とても期待できそうになかった。
それなのにこの歌には、「栄冠手にするその日は近いぞ」とか、「うま酒をくみかわそう」とか、はったりとしか思えないような文句が散りばめられているのである。
ところがこの年、「それ行けカープ」が煽る上昇気流に乗ったかのように、カープは勝ち続けた。「それ行けカープ」は大ヒットし、広島の街の時空を埋め尽くしていった。そしてついにカープは初優勝を手に入れたのである。この歌はカープファンにとって、奇跡の象徴になった。
そして今、これを歌うのがソプラノ歌手の野々村彩乃さん。2010年、まだ広島の女子高生だった時、春の高校野球大会開会式で君が代を歌い、その歌声の神々しさが話題になった人である。(Youtube で視聴できる。)本来ノリノリ、アゲアゲの「それ行けカープ」を、野々村さんは無伴奏で静かにゆっくりと歌うのである。その神の声で、「カープ、カープ、カープ広島」と連呼し、「鍛え抜かれし精鋭の技と力」などと持ち上げてくれるのだ。こんなふうに応援をされては、1975年のカープのように、「専門家」とやらの予想をくつがえす奇跡など、簡単に起こせそうな気になってしまう。
これからの日本と世界には、このような優しい応援歌がぴったりだ。カープ応援歌に抵抗があるなら、阪神タイガースの六甲おろしでも何でもいい、野々村さんに歌い直してもらったらどうかと思う。
2020.5.26
|
|
陰陽道
|
日本のほぼ全国民をあげての外出自粛のおかげで、ようやく新型コロナの勢いに陰りが見えてきた。
だがまだ、緊急事態宣言は取り下げられていない。
気を緩めることなく、不要不急の外出を引き続き控えて行きたい。
ゴールデンウイークに引き続きこの週末も、私はジョギングを断ち、家に閉じこもっている。
ジャグリングはまれに9キャッチ、というところまできた。
さて、私にも少しは本を読む心の余裕が出てきたので、「エッセイで楽しむ日本の歴史」(文春文庫)を読んでいると、面白い記事を見つけた。
小松和彦(こまつ・かずひこ)大阪大学教授のエッセイで、陰陽道(おんみょうどう)に関する話である。
平安時代の貴族は陰陽道を深く信仰し、陰陽道によって自らの生活を縛っていたそうである。
何か不幸が起こる、あるいはその兆しが見えた時、それは「物の怪(もののけ)」、たとえば人の怨霊や呪いのせいだとされた。
これら邪悪な神霊の攻撃を防ぐためにもっとも有効なのが「物忌み(ものいみ)」であり、具体的には家に閉じこもることなのだという。
この物忌みは、平安貴族の日常の一部だったそうである。
たとえば「宇治拾遺物語」には、ライバルから呪いをかけられた算博士の話がでてくる。
彼は陰陽師(おんみょうじ)に相談し、厳重な物忌みに入る。
ところが、敵側の陰陽師がやってきてあまりにしつこく呼ぶので、つい家の窓を開け、顔を見せたところ、呪いがかかって数日後に死んでしまったという。
仮に、今の世界のありさまを陰陽道で解釈するとどうなるだろうか。
コロナによるパンデミックはもちろん、何かの物の怪によるものだ。これに対しては物忌みが必要であるから、外出自粛はぴったり正解なのであった。
東京都知事は「ステイホーム週間」などと英語を使わなくても、「物忌み週間にしましょう」と言えばよかったのである。
もちろん、腕のよい陰陽師も必要だ。
平安時代の最強陰陽師、安倍晴明(あべのせいめい)はもういないが、今、日本の首相が阿部でも安部でもなく、安倍晋三(あべ・しんぞう)氏であるのは偶然とは思えない。
首相が清明の末裔かどうかは知らないが、ちょっとくらいは呪力を期待してもいいのではなかろうか。
今の日本の制度では、外出や店舗の営業を禁止することができないらしい。
「自分はコロナにかからないと思うから」などと自由に出歩く人や、指示を無視して営業を続けるパチンコ屋を罰する手段がない。
こういう人たちに対しては、「物忌みを破れば物の怪がつくぞ」と説得することになるだろう。
飼ってるネコが突然しゃべるなど、軽い呪いで脅しておけば、少しは聞き入れてもらえるのではなかろうか。
腕のよい陰陽師ならば、呪いを相手に送り返すことができるらしい。
コウモリだかセンザンコウだか知らないが、発生源にウイルスをお返しするところまで行けば、決着がついたと言えるだろう。
それにしても、コロナ退治のヒントが一千年前の平安時代の呪術にあったとは、驚きである。
当時、呪いは弓や刀と同じくらい、実効的な殺傷能力を持つ武器であったのだろう。
菅原道真(すがわらのみちざね)や崇徳(すとく)上皇の怨霊のたたりも、平安の人にとってはただの迷信でなく、本物の恐怖の源だった。だが、今の我々からは、なんとのどかな時代だったのか、とちょっとうらやましい。
実際には、平安人たちはわれわれ以上に殺し合い、疫病で倒れているわけだから、決して理想郷というわけではない。
しかし今の時代に陰陽道が復活したらどうだろう。
コロナ制圧をきっかけに、陰陽道が世界じゅうに広まれば、おしゃれな国際社会になるのではなかろうか。
核兵器や経済力で他国を脅すような野蛮で未開なことはもうやめて、国の指導者たちは正々堂々、呪力のみで勝負するのである。
2020.5.10
|
|
感染リスク
|
私がコロナ退散祈願を掛けた5ボール・ジャグリングは、少し進んで7キャッチまでできるようになった。
目標の20キャッチはまだ遠いが、まぐれということもある。
コロナウイルスはそろそろ、地獄へ逆落としになる準備をしておいたほうがいいだろう。
さて、私が卒後2年目で赴任した病院に、同期の外科医がいた。からだが大きく、声も大きく、頭はいつも坊主刈りで、「自衛隊」と呼ばれていた。
体力自慢の彼のこと、夜な夜な内科病棟を徘徊し、手術の必要そうなイレウス患者が隠れていないかと探している、と噂されていた。
言うこともスケールが大きく、「胃なんちゅうものは、がんになる前に切ってしまうほうがええんや。ワシが切りまくって、この辺りを無胃村にしてみせる。」などと言っていた。
で、彼によると、人のうんちを素手でさわれるようでなければ外科医とは言えないのだそうであった。
ついでに言えば、心臓外科医であれば当然、「血でジャブジャブ顔を洗えて初めてナンボのもんじゃ(一人前という意味か?関西人はこれだから…)」とのことである。
私は真に受けたわけでもないが、それだけ外科医は大変なんだろうな〜、とは思った。
どう考えても、彼らの方が麻酔科医よりも感染リスクが高そうではないか。
人のうんちというものは、今も当時も、触りたいものではないが、致命的な感染症をもらう危険性はほとんどなさそうである。コレラ、赤痢などは、さすがにずっと昔の話である。
当時圧倒的に危険だったのは、血液であった。
ベテランであるほど、B型肝炎に感染し、肝硬変を患っている外科医は多かった。B型肝炎の脅威がまだあまり知られていない時代に、術野で指を傷つけたのである。
肝不全で亡くなる先生もいた。
C型肝炎に至っては、30年前にはウイルスの正体がまだ知られておらず、ノンAノンB肝炎と呼ばれていた。
正体不明であるから、治療法はおろか、検査法もない。血液で顔を洗う心臓外科医を、さすがに私は見たことがない。
その点、麻酔科医がもっぱら扱う上気道は、断然安心だった。当時は手袋もせずに指を患者の口に入れ、気管挿管したり胃管を入れたりしていた。
2020年、突然、上気道は人体でもっとも危険な部位になってしまった。
そこは今、新型コロナがもっとも濃厚にたむろしているホットな部位なのである。
現在、消化器内科医は内視鏡検査を控え、耳鼻科医は鼻の手術を控えるようになっているが、麻酔科医が気管挿管を控えるのはむずかしい。コロナ対策会議で院長はこう言った。「じゃあ今、一番危ないのは麻酔科の先生じゃないか。」
一番危ないということはないと思うが、どうやら自分は気の毒に思われるポジションにいるらしいと、その時気づいたのであった。
私のように長年、人の上気道を素手で触ってきた人間は、たいがいの病原体に免疫ができているような気がするのだが、若い人の手前、ゴーグルつけたり、手袋を二重にしたりして仕事している。
ところで例の自衛隊先生から先日、教授就任の挨拶状が来た。これはちっとも意外なことではない。若い頃のエピソードからは、猪突猛進の無茶苦茶野郎のように見えるかもしれないが、本当のところは細かい気遣いも忘れない、上司にしたいやつナンバーワンである。むしろ遅すぎた昇進であったかもしれない。
ただこの快男児、調子に乗りすぎて、周辺地域を無胃村にしてしまわなければよいが、と思う。
2020.5.2
|
|
標語
|
先日、小池百合子(こいけ・ゆりこ)東京都知事が、「ステイホーム、おうちにいましょう週間です」と発言していた。日本語で言い直すくらいなら、最初から英語を使わなければいいのに、と思う。小池氏は他にも、アスリートファーストとか、ロックダウンとか、英語を使うのが好きなようだ。英語だと、これが新しい概念なのだということは、確かに手っ取り早く伝わるのかもしれない。日本語だとどうしても印象が薄くなってしまうのは否めない。
戦時中だったら、このような標語には、敵性語である英語は使えなかった。日本語でガツンと来る標語が作られていたはずである。対コロナ戦を日本語で盛り上げるためのヒントが見つかるかもしれない。
前回も少し紹介したが、戦時中は「欲しがりません、勝つまでは」、「贅沢は敵だ」などの標語があった。現在向きに翻訳すれば「家を出ません、勝つまでは」、「外出は敵だ」あたりでどうだろう。少しインパクトに欠けるか。
インパクトということなら四字熟語のほうが強い。「鬼畜米英」、「七生報国」、「一億玉砕」など、とても現代に通用しそうでない。「鬼畜」は人種差別を背景にしていて使えないし、そもそもコロナを鬼畜呼ばわりしても響かない。七回生まれ変わっても国に報いるぞ、ということは、七回は死んでるということだ。一億玉砕に至っては、コロナに対する敗北宣言である。強いて真似すれば、「一億春眠」くらいか。
当時は兵士や国民を鼓舞するため、軍歌も山のように作られた。「いざ来いニミッツ、マッカーサー。出てくりゃ地獄へ逆落とし」という歌詞が何かの小説に出てきて、なんと勇ましい歌だと感心したことがある。(ニミッツ、マッカーサーというのは、当時のそれぞれ米海軍、陸軍のトップである。)これは調べてみると、「比島決戦の歌」であるから、敗色濃厚になった時分のものである。つまりこれは、やけくその歌なのである。本当にニミッツやマッカーサーが来たら困るのである。「コロナ決戦の歌」などは、作らない方がよさそうだ。
やはり、参考にはならなかった。ただ、そろそろやばくなると、勇ましい言葉がはやる、ということはわかった。日本はまだ、そういう段階ではない。「ステイホーム週間」を日本語に直すなら、かわいく、「巣ごもり週間」なんかでどうだろう。
2020.4.26
|
|
たらい回し
|
先週私は、コロナ消滅の願をかけてジャグリングを再開し、5ボールカスケードで20キャッチに挑戦する決意を固めたのであった。世界を背負ってボールを投げるのは初めてであるが、驚いたことに以前は楽にできた5キャッチすら、今はできなくなっている。しかも年のせいか、まったく上達の兆しが見られない。20キャッチができたらここで報告するつもりであるが、私の力によるコロナ制圧にはちょっと時間がかかりそうである。
さて、新型コロナの蔓延に伴い、救急患者が「たらい回し」される事例が増えてきた、と報道されている。医師としてはこの「たらい回し」というマスコミ用語はやめてもらいたいと前から思っていたが、依然こうして何のためらいもなく使われているのは残念だ。
そもそも、たらい回しとは何か、知ってて言っているのか。
昔からある日本の曲芸で、床に寝た芸人が足でたらいを回すのである。
今の若い人は、こんな曲芸、見たこともないだろう。
私が若いころまで辛うじて日本の伝統曲芸を受け継いでいた染之助・染太郎(そめのすけ・そめたろう)でも、回していたのは傘であり、たらいを回していた記憶はない。
インターネットの中を探してみても、本物のたらい回しを映像で見られる場所は全くない。
日本人の多くが知らない、見たこともない「たらい回し」を、何かの比喩に使おうとすること自体がことばの乱用であり、マスコミの悪意か怠慢の産物であろう。結果的に「たらい回し」と聞けば、多くの人は救急車を思い浮かべるだろうし、医者や病院がまた患者の命をもてあそんでいるというイメージを抱くしくみになっているのである。
マスコミが「たらい回し」と呼ぶ現象は、医療側から言えば「受け入れ不能」であり、救急車側から言えば「搬送不能」である。患者を乗せた救急車はやみくもに走り出すのではなく、受診を打診して受け入れを表明された病院に運ぶのである。しかし病院の方も、病棟や診察室がいっぱいだったり、専門の医師が不在だったりすると、断らざるを得ない場合もある。わざとかどうか知らないが、日本の病院は常に手薄な状態であるから、「受け入れ不能」はときどき発生するようになっているのだ。患者ー救急車側にしてみれば、断られることが続くとどこにも走り出せず宙に浮く、「搬送不能」状態となる。たらい回しというとまるで、病院に運んだ患者の診察を断られ、次から次へと病院の間をぐるぐる回っているかのようなイメージを与えるが、救急車も患者も全然回っていないのである。
ところで確かに最近、救急車を呼んだ患者さんがなかなか受け入れ先を見つけられず、何件も断られた後で私の病院に運ばれてくる事例が増えたように思う。たとえば骨折らしき患者さんでも、熱があるとコロナかもしれないということで、断られてしまうのだろう。かかりつけ病院からさえ断られてしまった人を、何とか受け入れるのが公的病院の心意気である。ま、私が受けているのではないが、麻酔科医としてはその後方で救急医療を支えているつもりである。
最近、テレビなどが医療側に妙にやさしくなって、「医療崩壊を防げ」、「医療従事者に支援を」と訴えてくださるようになり、ありがたいような、気持ち悪いような思いであるが、だったら「たらい回し」をやめろや、とも思うのである。
2020.4.19
|
|
暇つぶし
|
新型コロナ(COVID-19)の勢いが、現在とどまることを知らず拡大中である。他の自然災害と違うのは、世界のすべての人が、このウイルスでやられる可能性を持っていることである。死亡率は低いとはいえ、どんな人でもゼロではない。有名人が感染したというニュースを聞くたびに、もしかしたら自分も、という現実味が増してくる。こんなにじわじわ来るリアルなホラーは、これまで体験したことがない。
さて、「人を希釈せよ」という私の意見がやっと官邸に届いたようで、安倍首相が緊急事態宣言を出し、外出自粛を国民に要請した。ウイルスは生体の外では長生きできないし、自力で歩いたり飛んだりする能力を持たないから、全国民が家に閉じこもればかならず絶滅する。現実にはそういうことはできないが、なるべく多くの人が外出を控えるようにすれば、感染は抑制されていくことになるのであろう。
私は幸か不幸か、医療従事者なので平日は出勤である。もしテレワークができるようなら病院に行かないで済むのだが、そのためには心霊麻酔か何かを習得する必要がある。ただこの週末は、当直も呼び出し待機もなく、完全に家に閉じこもった。問題は、家の中でどうやって暇をつぶすか、である。
若い研修医に聞くと、基本、ゲームだそうである。私は昔からこれが合わない。本を読めばよさそうなものだが、どうしたものか、この状況で安心して読める本がない。久しぶりにネット囲碁対局をやってみたが、ネットの向こう側にいるのが全く知らない人というのも、どうも気疲れする。
囲碁といえば印象深い話がある。囲碁に関する著作の多い江崎誠致(えざき・まさのり)という小説家のエッセイに出てくる話である。ある知り合いの老囲碁ファンの家を訪ねたところ、その人が古い棋譜を広げて碁盤の上に石を並べていたという。昔の実戦を目の前で再現し、鑑賞しているのである。この人はすでに、他の人と碁を打つような浅ましい行為からは卒業し、取り憑かれたようにひたすら毎日、古人の棋譜を並べているのだそうだ。さらに驚いたことに、そこへご夫人がお茶を持ってきて、「お仕事、ご苦労さまです」と夫をねぎらったというのである。
古今東西、これほど安価でしかし生産性ゼロで、それでいて本人は満足しきっているであろう暇つぶしがあっただろうか。そしてこんな役立たずの夫に対し、「ちょっとはアルバイトでもしたらどうか」などと罵るどころか、お茶をもってねぎらうような妻が、人類の歴史の中で存在しただろうか。ウイルスとは別の意味でじわじわ怖い話であるが、どちらにしてもこんな仙人みたいな暇つぶしは、凡人にはまねはできない。
私は結局この週末はネットで映画を鑑賞し、こうやって誰も読まないつまらないブログのようなものを更新することにした。そしてもう一つ、ジャグリングに再挑戦することにした。
私は40歳の誕生日、何か新しいことを始めようと思い立ち、ジャグリングを始めたのであるが、他の趣味と同じでやはり才能に恵まれず、5ボールを回すことがどうしてもできなかった。5ボールのカスケードという技は、素人ジャグラーが最初にぶつかるもっとも高い壁なのだが、私には高すぎたのである。この17年間、何度かぶつかってみたが、乗り越えられなかった
これからも家にいる時間が増えるであろう。この機会に5ボール・カスケードで20キャッチをできるようにしたい。せっかくだからこれに願(がん)かけをくっつけてみたい。私が20キャッチできた瞬間に、COVID-19 が消滅しますように、という願をかけるのだ。
ただし、私が5ボール20キャッチを実現できなくても、コロナの制圧は妨げないこととする。つまり、感染制御がうまく行かなかったとしても私のせいではないが、コロナが突然消えたりしたらそれは、私のおかげと思っていただいて結構である。
ほかの方もぜひ、家の中でチャレンジできることで、コロナ退散の願かけをしてみていただきたい。他の国の人にはちょっとこんなことは頼めないが、日本人だけでも総がかりでやれば、どれか一つくらいは当たるだろうと思うのである。
2020.4.12
|
|
コロナウイルスと戦争、その2
|
私は戦争ものの本は結構読んできた。戦争が人類の歴史を作ってきたことは事実であり、戦争史は必須の教養科目だと思うためである。戦争が好きなわけではない。
戦争を一言で語ることなどできるはずもないが、今般の対コロナ戦と共通点のありそうな話を、頭に浮かぶままに書いてみる。
-
戦争では状況が刻々と変化し、先の見通しが立たない。関ヶ原の戦いは濃霧の中で始まり、もみ合いの混戦になったが、小早川秀秋(こばやかわ・ひであき)が東軍に寝返るまで、どちらが勝つかわからなかったと言われる。
-
誤った情勢判断にもとづき、しばしば無謀な作戦が行われるが、ひどい目に会うのは兵士である。インパール作戦は兵站というものを無視した無謀な作戦で、数万人の死者を出したが、作戦の責任者の牟田口廉也(むたぐち・れんや)は天寿を全うした。彼は死ぬまで、作戦失敗は部下の無能のせいだったと主張した。「シン・ゴジラ」の主人公、矢口蘭堂(やぐち・らんどう)が「ヤシオリ作戦」を決行する際、「政治家の責任のとり方は、己の進退だ」と述べたのと、えらい違いである。
-
愚かな作戦、間違った判断が乱れ飛ぶ中で、兵士は何が何だかわからない中で目の前の敵と戦うしかない。残虐行為は数に限りがないが、意外にいい話もある。フィリピンの激戦地から生還した作家、大岡昇平(おおおか・しょうへい)によると、普段自分勝手な嫌われ者が、とっさに仲間をかばって死んだりすることがあったそうだ。大岡自身、待ち伏せに引っかかって全身をさらけ出している若いヤンキーを、どうしても撃つことができず、みすみす逃したそうである。戦場では何が起こるか分からないのだ。
-
戦争の名のもとに、国民の権利は大幅に制限される。「欲しがりません、勝つまでは」、「月月火水木金金(休みがない)」という戦時中のスローガンがそれを端的に示している。まあ当時は「国民」ではなく、「臣民」だったのだが。
-
戦中、戦後の混乱に乗じて、濡れ手に粟の荒稼ぎをする不届き者が必ず現れる。敗戦後、日本の軍の資材がごっそりと消えた。アメリカから進駐軍が来る前に、利権を持つものがネコババしたのだ。その行方は永遠の謎である。
こういう話から、現在の状況に使える教訓を得ようなどと考えるのは安易すぎるだろう。だがこれを参考にしてとりあえず、濃霧の中でも自分の持ち場でしっかり戦い、政府の立てる作戦に責任が伴っているかを厳しくチェックし、転売ヤーや詐欺師の暗躍に目を光らせることは必要かと思う。あと、願わくば、コロナウイルスに裏切り者が出ることを期待したいものである。
最後に、コロナ関連短歌を。
地下鉄に乗ればコロナが恐いので、触れず座らず、息も屁もせず。
何日も使うマスクが気の毒で、くしゃみする時思わずはずす。
咲き初めの桜よ、今年わけあって、酒盛りはない。のびのびと咲け。
お粗末でした。
2020.4.5
|
|
オリンピック
|
オリンピックにおける卓球競技の歴史は浅く、1988年のソウルオリンピックに登場したのが最初である。これほどのメジャーなスポーツでありながら、卓球は長年、オリンピックの外側で行われてきたのである。ほかの競技でもそうだと思うが、オリンピックでの卓球の試合の規模はかなり制限されていて、たとえばシングルスは一つの国から2人しか出られない。これで本当に世界一と言えるのか、疑問である。
古い卓球ファンとして言わせてもらえば、卓球界の本当の権威は世界卓球選手権、全日本卓球選手権であって、オリンピックはいわば、「卓球商店」が見本市に出した小ブースのようなものである。卓球をあまり知らない人に、ダイジェスト版だけ見せようという立場のものであろう。
そういう冷めた目で東京オリンピックのことも見ていた私であるが、先日、一年延期のニュースを聞いてから、初めて応援したい気持ちが出てきた。もしも来年、無事オリンピックが開催できたとしたら、それは間違いなく、世界がコロナ禍から恢復したという快気祝いのお祭りになる。こんな特別なオリンピックなど、滅多に巡ってこない。
もちろん、会場、スタッフ、選手の宿泊などなど、延期のために関係者は前代未聞の困難を乗り越えなくてはならないだろう。だが無責任を承知であえて言えば、こんな無茶な任務を果たすことができるのは、逆に日本くらいかもしれない。日本は敗戦、かずかずの大震災、ゴジラの来襲を乗り越えてきたのである。
ジョン・ダワ―の「敗北を抱きしめて」の中のあるエピソードが、私の記憶に残っている。日本が戦争で負けて、アメリカの進駐軍の偉い人たちがパーティーを開いた。将校の一人が紙ナプキンを手に取り、こう言ったそうだ。「日本人は、そう、これからこういうものを作って生きていけばいい。」その予想に反し、日本は廃墟の中から産業のフルセットを育て上げ、約20年後に東京オリンピックを成功させたのだ。
オリンピック開催を応援するためにはまず、コロナ退治である。現在までに一番感染を制御できていない地域が、結局東京と大阪であることから、人の密度が流行の最重要因子であることは明らかである。やはり、「衛生は希釈である」の金言に従って、人を希釈することは有効に違いない。
地球上でもっとも危険で残忍な生物であるヒトが本気を出すとどうなるか、ウイルスは分かっているのか。みんな家に引きこもった結果、ウイルスは路頭に迷うことになるのだ。
2020.3.28
|
|
コロナウイルスと戦争
|
新型コロナウイルスが全世界に拡がり、とうとうアメリカとフランスの大統領が「これは戦争だ」と言い始めた。こういうことを言えるのが、第二次世界大戦の戦勝国の気楽なところだろう。「戦争だ」と言えば気分が高揚する人も世の中にはいるのだろうが、戦争では負けることもある。戦争に負けたらどうなるか、日本人ならみんな知っている。
さすがに日本やドイツの首相は、そういうことは言わない。国の指導者であれば、戦争という言葉は、最後の最後まで取っておいた方がいいと思う。
ただ幸か不幸か、私はどこかの国の指導者ではないし、自分の家の指導者ですらないので、次のようなことは言える。確かに、戦争とコロナとの戦いには、似たところがある。私は通常の医療行為を戦争言葉で表現するのは嫌いだが、コロナは別格だ。特に、歴史を振り返れば元寇に似ているかもしれない。
元寇と新型コロナ、来るなと言っているのに、勝手に海を渡ってくるところまでは一緒である。私が学校で習った歴史では、「てつはう」など見たこともない武器に鎌倉武士団はたじたじとなるのであるが、最近の歴史学では、こっちにも流鏑馬(やぶさめ)など、敵を驚かす戦法があり、かなりよく戦ったということになっているらしい。
コロナに対しても、日本はかなり善戦していると思う。これは、べたべたと相手に触らない習慣、比較的清潔な環境、何ごとも右へならえの社会性など、ウイルスを困らせる条件が揃っているためではないか。ただし、元寇を壊滅させたのはやはり「神風」であるから、コロナにも何か一発お見舞いしたいものだ。
病原体と戦争、ときたら、H・G・ウェルズの古典SF、「宇宙戦争」を連想する人もいるだろう。あるとき突然、火星人がロンドンに降り立ち、暴虐の限りを尽くす。地球人はまったく太刀打ちできないのだが、何ということでしょう、火星人は地球のありふれた病原菌に侵されて倒れていく。わかりやすく言えば、火星人は「かぜ」をひいて全滅するのだ。(ウイルスは菌ではないが、ウェルズがこの小説を書いたころは、ウイルスは発見されていなかった。)
これは使える。火星人は必ずや、ふたたび地球に攻め寄せてくるだろう。火星人の科学力は人間よりはるかに上だから、今度は、人間よりずっと手ごわい敵、「病原菌」を抹殺する兵器を持ってくるのは間違いない。
火星人がまずコロナウイルスを退治したら、速やかにお帰りいただいたらいい。
そんなに都合よく帰ってくれるものか、と思われる方は、別の天才SF作家、フレドリック・ブラウンの「火星人ゴーホーム」をご参照いただきたい。やり方が書いてある。
この3連休、ジョギング以外では外出せず、ウイルスのことが気になって読書もテレビも身が入らず、気を紛らわせたくてついこんなつまらないことを書いてしまった。
2020.3.22
|
|
衛生は希釈である
|
数年後いやもしかしたら数カ月後には、喉元過ぎてその熱さが忘れられているかも知れないが、2020年3月現在、新型コロナウイルス(COVID-19)が日本と世界を恐怖に陥れている。テレビも時々刻々と変化するコロナ情勢を報道し続けている。ついこの間まで、中国だけで流行していた時は、対岸の火事だった。それが世界にこれだけ拡がるということを、予想できた人は少ないのではなかろうか。
私はしがない麻酔科医なので、防疫のことはまったくわからない。この流行を収束させるにはどうすればいいのか、この先どうなるのかを知りたいのだが、何せ次から次へといろんな専門家とやらがテレビやインターネットの記事などに登場し、いろんなことを言ってくるので、何が正しいのかわからない。その人が本当に伝染病を終わらせる力を持つ専門家なのか、煽るだけのニセモノが混じっていないか、そういうのを目利きするプロ、「専門家の専門家」略して「専門家専門家」が登場してくれないものだろうか。
作家の中島らも(なかじま・らも、故人)が、ある衛生学の大家の言葉をよく引用していた。「衛生は希釈である」のだそうだ。つまり、完全な清潔、完全な無菌を求めることに意味はなく、汚染を薄めるだけでよい、それが衛生の本質である、ということだろう。これはなかなか味わい深い言葉である。防疫においても有用ではなかろうか。
コロナを一匹も寄せつけたくない、というのがわれわれ素人の心情であるが、それはもともと不可能である。完全をもとめていては一歩も進まないのだが、手を洗う、うがいをする、マスクをするなど、ウイルスをせいぜい「薄める」だけでも感染確率は減らせるはずである。外出自粛、大規模イベントの中止など、効果を疑問視する人もいるが、「人を希釈」しているのだと思えば、効かないはずがないと思う。こうして少しずつ希釈すれば、集団として見れば人から人への伝染は減り、大きな効果が出るだろう。
感染がどうすれば収束するのかについては、「集団免疫」という考え方があるらしい。80%くらいの人が感染して、免疫を得れば終わるというのである。英国も3月上旬、それに基づく見通しを発表していたが、大量の死者が出ることを容認することになるので、悲観的過ぎると批判されて撤回した。
収束の別のシナリオもあって、とにかく新規感染者を減らしていくだけでいい、という。人が感染して隔離され、治癒する「除去数」よりも新規感染数が少ない状態を維持できれば収束するらしい。つまり、必ずしもワクチンによる完全なる免疫状態や、天然痘のようなウイルス根絶を目指す必要はないということである。これも「希釈」に通じる考え方である。
中島らもの言う「衛生学の大家」が誰だったのか、今ちょっとわからないのだが、こういう素人にも届く実用的なキャッチフレーズを与えてくれる専門家は本物だと思う。私、「専門家の素人」の意見である。
2020.3.20
|
|
麻酔中の体勢、その1
|
麻酔科医は仕事中、どういう体勢を取っているのか。もちろん、麻酔導入、覚醒、あるいは術中の緊急事態の際は忙しく立ち回っているが、手術中で患者さんの状態も落ち着いているときは、これと言ってやることがない。こんな時、麻酔科医は立っているのか、座っているのか、まさか床に横たわっている人はいないだろうが、その辺を調査した研究はたぶんない。麻酔の教科書にも書いてない。
立ってひたすら手術を見ている、というのが麻酔科医の理想形かもしれない。私の若いころは、立っている方が尊い、そういう意識はあったと思う。当時はパルスオキシメーターがなかったから、術野の血の色を見て、酸素化をチェックしつづけるのが仕事の一つだったのである。また、麻酔科医はダラダラして外科医になめられてはいけない、という意識もあっただろう。麻酔科は日本では戦後に創設された、まだ非常に若い科だったのである。
たとえば、私が先輩から聞いた話だから、今から40年くらい前の話であろう。ある病院の麻酔科部長がスパルタ式の教育をする人で、手術中、麻酔科医に座ることを許さなかったという。それだけでなく、ベンチレーターなど信用できない(注1)ということで、リザーバーバッグ(注2)をずっと手で押させていた。(注3)しかも何のこだわりか、たとえ開腹手術で筋弛緩を使っていても、自発呼吸が少し残っている状態を維持しなくてはならない(注4)。
ときどきその怖い先生が見回りに来るのだが、自発呼吸がないと蹴られる(比喩でなく、物理的に)から、その足音が聞こえたら必死で換気量を落とし、炭酸ガスを溜めたのだそうだ。(この辺、医師でない人には通じにくいでしょうが。)
これはつらい。バッグを押しているということは、一歩も動けないということで、交番の警察官について論じた通り、足はどんどんつらくなる。さらにうっかりバッグを押し忘れたらアウトだから、プレッシャーもかかる。それをときどき怖い人がチェック&キックをしに来る。これはもう、拷問である。
麻酔にかける情熱が有り余って、変な方に行ったのだと思われる。自分の肉体への虐待がいい麻酔につながる、という思想はもう過去のものであろう。汗をかいても水を飲むなとか、徹夜明けでも弱音を吐くなとか、そういう時代だったのだ。
昔でも、実際には麻酔科医は座っていることが多かったが、今の麻酔科医はさらに何の後ろめたさもなく座っていることだろう。血の色はパルスオキシメーターが見てくれるし、ベンチレーターは明らかに麻酔科医の手より優秀だし、手術の細部をじっくり見続けても得るものはない。麻酔は「外科医でも片手間でできる仕事」ではなくなり、虚勢をはる必要はなくなった。
だがこの、「座る」という体勢にも問題がある。これが私の長年の苦悩の源泉であった。次回に続く。

注1) 当時のベンチレーターは酸素配管のガス圧を利用し機械的に作動するもので、何かにひっかかるのか、突然止まることがあった。
注2) 麻酔回路についているゴムのバッグ。これを揉むことで、患者さんを呼吸させる。
注3) バッグは揉むのではなく、押すのだと言われていた。その違いは私には今でもわからない。
注4) 想像するに、万一麻酔科医が突然死んでも、患者は死なない、というところを目指したのではないか。
2020.3.14
|
|
交番
|
交番の前に警察官が立っていることがある。立ち番というらしい。片足を前に出した「やすめ」の格好の人もいるが、「気をつけ」の人もいて、まさに仁王立ち、さすが威風堂々としている。ただ、気の毒だと思わないでもない。立って動かない、ということが、人間にとってあまり自然なこととは思われないのである。
立っていて足にかかる負担は体重だけではない。何しろ足は心臓よりも100センチくらい低いところにある。水は低きに流れるということわざにより、全身の血液が足を目がけておしよせるのである。心臓には足から血液を汲み上げるような吸引ポンプの機能はない。ふくらはぎなどの下肢の筋肉が静脈を揉むことで、血液を押し上げているのである。つまり、ヒトは歩いたり走ったりしなければ、足がむくんでしまう仕組みになっている。
実際、2時間歩くよりも、動かず立ち続けているほうが、少なくとも私にはつらい。
おそらく、警察官の直立不動は足にあえて負担をかける、一種の苦行なのであろう。宮殿や基地の門を守る軍人などもそうだが、直立不動の人は、人にできないことをやって見せることで、見る人を威圧しているのである。
だがそうやって、足にばかり負担をかけていいのか。思い起こせば、人類の始まりは変わり者のサルが後ろあしだけで歩くようになったことであった。脳の巨大化は二足歩行の副産物であって、人類誕生よりだいぶ後の話である。脳は上級国民のような顔をして、一番立地の良いところでふんぞり返っているけれども、人類進化の立役者はあくまでも足なのである。
実際、足はけっこう主張が強い。冷蔵庫の角にぶつけただけで、足の小指ほど痛む場所が他にあるだろうか。ワシのことをただの棒状移動装置と思うなよ、という警告としか思えない。でなかったら、こむら返りも、ウオノメも、どうしてあんなに痛いのか。さらに、足はいろいろな病気にかかる。立ち仕事の人に多い下肢静脈瘤を始め、水虫、爪白癬、血管がつまりはじめて潰瘍、壊疽までくると、生命を脅かす。まれではあるが、慢性疼痛の一種に「むずむず脚症候群」という奇病もあって、不快感を伴う足の不随意な動きが脳を苦しめ続けるのである。
警察の方々には、足を大事にしていただきたいものだ。この記事を読まれた警察庁長官、内閣総理大臣は、交番前で警官が左右に歩くことを直ちに許可していただきたい。あるいはスキップのほうが血行改善には効率的かもしれない。警察官が交番の前でスキップしていては威圧感が足りない、ということならば、100kgのバーベルを担ぎながらでどうだろう。
もしどうしても動いてはいけないというのなら、足のつらさを軽くする方法を考えてあげてほしい。その際、スーパーの買い物袋をさげたまま、道端で友達としゃべっている人たちがヒントになるだろう。この人たちは普段、階段などぜったいに使わないくせに、しゃべっている間は何時間でも立っていられるのだ。
何か言葉を操ることが足のつらさを軽くするのだとしたら、交番の立ち番中には業務短歌をつくることをおすすめしたい。警察官がどんな短歌を詠むのか、ためしに作ってみようかと思ったが、仁王立ちの人に怒られそうだからやめた。
2020.3.7
|
|
オイラーの公式
|
オイラーという数学者がいた。18世紀のスイスに生まれ、さまざまな業績を残した万能の天才数学者である。とにかく膨大な量の仕事をした人で、一日で数篇の論文をこしらえたり、片手でゆりかごを揺らしながら片手で証明を書きつけたりしたそうである。年老いて失明してもなお、その勢いは止まらず、口述筆記で論文を出し続けた。天才の中の天才である。
さて、オイラーの臨終の様子を描いたある記録がしびれる。「オイラーは1783年9月18日のその瞬間、生きることと計算することをやめた」(注1)のである。人の死を描写するのに、こんなかっこいい言葉はめったにない。また、こんな言葉が似合う死に方ができる人もめったにいない。
この句を仮に「オイラーの公式」(注2)と呼ぶことにしよう。「生きることと X することをやめた。」の X に、好きな言葉を代入するといいだろう。若い人たちは、自分の生き方にぴったりくるような X を見つけて頂きたいが、私はもう、手遅れだ。たとえば…
「その瞬間、彼は生きることと麻酔することをやめた。」
手術室で仕事中死ぬのは、患者さんに迷惑だから、そんな事態は死んでも避けなくてはならない。引き際を間違えたのだとしか思えない。仕事がだめなら、自分の趣味を代入してみる。
「その瞬間、彼は生きることと歩くことをやめた。」
これでは、行き倒れ(行路病者)である。では、日頃のクセはどうか。
「その瞬間、彼は生きることとボヤくことをやめた。」
ま、私程度の人間なら、こんなところだろう。
注1) 「フェルマーの最終定理」、サイモン・シン著
注2) 本物のオイラーの公式は、eiθ = cos θ + i sin θ である。θ = π (パイ)のとき、eiπ = -1、つまり「博士の愛した数式」となる。
2020.2.29
|
|
関西人
|
関西人とは何か。たぶん、関西弁をしゃべる人である。
私が18歳で広島から関西に来て、もっとも驚いたのが、みんな本当に関西弁をしゃべっていることであった。大学の中ならば、全国から学生が来るのだから標準語だろうと思ったら違った。やはり関西人が多数派であり、関西弁こそが標準語なのであった。「ほんまやな、信じてええねんな」という、吉本新喜劇に出てきそうなコテコテの関西弁を大学の食堂で聞いて、本当に驚いた記憶がある。
関西弁をしゃべる以外に、何か特徴はないのか。当の関西人に聞けば、いやというほど教えてくれるだろう。関西人はお笑いが好き、どんな話でもオチをつけたがる、鉄砲で撃つ真似をすると死んでくれる、などなどである。関西のテレビのトーク番組でもそういう話ばかりやっている。とにかく東京と張り合いたいのである。
だが、関西人のふりをして38年間潜伏調査している私に言わせれば、関西人にも陰気な人はいるし、素晴らしいギャグセンスに恵まれた人が、九州出身者だったりする。関西弁をしゃべっている限り、出身地の区別などつかない。「おもろい関西人」というのは観念上の存在に過ぎないのではなかろうか。
ただ一つ、例外がある。大阪の中年女性である。私は、彼女らこそが本物の関西人ではないかという疑いを持っている。
私が大阪の公園内で行われたマラソン大会で走っていた時のことである。何せ公園の中をぐるぐる回って走るので、コース内外に一般人がうろうろしている。レース後半、時速8キロで爆走している(はずの)私に、自転車に乗ってよろよろと進んでいる中年女性が話しかけてきた。
「なあ、これ何周走らなあかんの?」
「15周です。」
「ひゃー、すごいなあ。おばちゃん、そんなん、自転車でもむりやわ。」
そう言って離れていった。
レース中のランナーに対するこの気安さ、ゆるさは何なのだろう。もしかして、他人と自分の境界線が、大阪の中年女性の中にはないのだろうか。で、どうして頼みもしないのに、自分が同じコースを走ることを想像し、勝手に軽くオチをつけて去っていくのか。ちなみにこの人は自分で「おばちゃん」と言ったので、以後遠慮なくそう呼ばせてもらう。
この「珍しいものを見た」感は、翌年の同じ大会でますます強くなった。レース中、やはり自転車に乗ったおばちゃんにぶつかられた。個々のおばちゃんを識別するのは困難だが、さすがに前年とは違う人だったろう。私にぶつかったそのおばちゃんは、ただ「ごめーん」と言って友達のおばちゃんの自転車の群れに戻っていったのである。知り合いの足をちょっと踏んでしまったくらいのフレンドリーな感じだった。私が大阪国際女子マラソン(2020年)でラストスパートをかけている松田瑞生(まつだ・みずき)選手でなかったのは、幸運だった。
これほどの他人に対する無遠慮、倒錯した距離感、それでいて相手を怒らせない愛嬌、今まで関西の中でも他の土地では経験したことがなかった。これは強い。何が攻め寄せてきても、大阪のおばちゃんは気安く話しかけ、丸め込んでしまいそうな気がする。
もちろん、たった2件の事例で、大阪のおばちゃん全体が分かったようなことは言ってはいけない。こういう解釈の拡大がしばしば偏見を助長し、事態を悪化させるのだ。
正確に言いなおそう。大阪の長居公園で自転車に乗っているおばちゃんは、煮詰めたような関西人である。いつかその日が来たら、日本を救ってくれるだろう。
2020.2.23
|
|
金曜日
|
金曜日は緊急手術が多い。これは手術室における千古不易の真実である。今すぐ!という手術でなくても、月曜日までは待てないなあ、という微妙なケースはときどきあり、そういうのが金曜日に入ってくる。じゃあ今日やってしまおうか、というノリである。
緊急手術が院外から舞い込んでくることもある。近所の病院で一週間くらい様子を見ていた患者さんが、金曜日になって「手術が必要です」と紹介されることがある。
麻酔科としては、なんか納得いかないなあと思いつつ、断るわけにも行かない。予定手術の後ろに、数珠つなぎで押し込んでいくしかない。
しかし、問題は山積みである。現在奴らがだらだらやってる予定手術はいつ終わるのか、月曜日の分の術前診察が消化できるのか、麻酔科医は自分以外誰が残るのか、仕事を夜勤ナースに回してもいいのか、研修医は今日、合コンの予定はないのか… ストレスがマックスに達する瞬間である。
だがたまに、ふと気がつくと、緊急手術が今日はまだ来てないぞ、と思うこともある。こういう時、それを口に出してはいけない。緊急の「き」の字でも口にした瞬間、申し込みの電話が鳴りそうな気がするのである。
緊急があってもなくても、金曜日の手術はいつかは終わる。そして、長かった一週間に別れを告げる。一週間を終えた、というより、生き延びたことの安堵感に包まれる。多くの患者さんたちも、自分たちも、ここまでよくぞ無事で乗り切った、といったところか。
もちろん、土曜、日曜も緊急当番ならば仕事は入ることはある。だがそれは、平日の麻酔科部長としてのストレスに比べたら、むしろ癒しの時間である。その心は…
目の前の患者さんだけ見ればいい。麻酔を好きになれる休日。
2020.2.16
|
|
棒詠み短歌
|
テレビもインターネットもない時代、昔の人はどうやって夜の退屈をしのいでいたのだろうか。バクチ、笛、鼓などの音楽や踊り、月の鑑賞(月の名所があるのだからおもしろい)、いろいろあっただろうが、おそらく当時の娯楽の王様は、和歌などの言葉遊びだったのではないか。私は文学史も和歌も、まったく門外漢であるが、いろいろ想像していく。
飛鳥時代から日本中で和歌(短歌、長歌)がたくさん作られてきたことはもちろんであり、作歌の腕の優劣を競う場もあっただろう。言葉には他にもいろんな遊び方があって、今様(いまよう)は、五・七・五…と続く歌詞に節をつけて歌ったもので、源平合戦時代の後白河(ごしらかわ)法皇の今様狂いは有名である。また、連歌(れんが)は人が集まって五・七・五と七・七の句を延々100句も継ぎ足していき、一つの作品を作るというもので、戦国時代には大名たちの必須の教養であった。これなどは一日がかりであるから、暇つぶしどころではなかったかもしれない。また、松尾芭蕉(まつお・ばしょう)以降の俳句の隆盛については言うまでもない。
いずれにしても、五音と七音の句を組み合わせるのが、日本の言葉遊びの伝統である。思いついた言葉を自然に並べて行けばいいものを、こうやってむりやり型にはめようとするのはなぜか。私の意見では、ああでもない、こうでもないと、言葉を並べ替えるその不毛な行為が、暇つぶしにもってこいなのである。この伝統を利用しなくてはもったいない。
前回私は、京都で平家の亡霊に触発され、棒読み調短歌を発表し、日本を興奮のうずに巻き込んだ、ような気がする。そこで今回調子に乗って、「棒詠み短歌」という遊び方を提唱したい。
棒詠み短歌の遊び方は、以下のとおりである。
-
五七五七七の短歌形式で、そのとき起こったことや感じたことを淡々と書き留める。短い日記のようなものである。感動、余韻、もののあはれ、そういうものはいらない、むしろ邪魔。
-
自然な文章がたまたま五七五七七に収まった感じがでているのがよい。かつて私が紹介した「偶然短歌」の精神を受け継ぐのである。
古語はいっさい使わない。和歌伝統の手法、掛詞(かけことば、しゃれのこと)、枕詞、本歌取りなども使わない。あくまで普通の現代文である。
-
人と見せ合ったりするのはいいが、決して評価したり、優劣を競ってはならない。人の日記を見て、いいとか悪いとか決めつける人がいたらバカである。
-
歌を作る環境に適しているのは、差し当たって手持ちぶさただが、テレビを見たり昼寝をしたりはできない状況である。どんな職種でも、そんな時間帯は発生するのではなかろうか。たとえば、謝罪会見で謝る側の端っこに座っているが、当事者ではないので決して答弁する番がまわってこない状況などである。
それでは、私の作品を並べてみよう。人の日記を見ても、たいてい面白くもなんともないように、以下のものを見ても何の感興も生じないはずである。決してけなしてはならない。
字を書いた人が女か男かは、だいたい分かる。不思議に思う。
年休は、休み難きを休むこと。総務よ、そこの痛みを分かれ。
新型の肺炎のこと議論しただけで感じる、熱とけだるさ。
たしかにどうでもいい歌である。だが、しつこいけれども他人がけなしてはならない。
一方、同業者なら感動はしないけれども心が動いてしまうだろう歌もある。四連作である。
レミフェンタ、どこに行ったかレミフェンタ。泣けど叫べど一つ足りない。
失くしてはいけない薬を失くしたら、振り返る我が麻酔人生。
ナースらが帰るのやめて捜索をはじめてくれる。頭が下がる。
麻酔器の下に落ちてたレミフェンタ、発見されて歓声上る。
この時の苦しみは、さすがににじみ出てしまった。皆さんもこういうの、いかがでしょうか。
2020.2.8
|
|
スマホと和歌
|
先日私は、京都を訪れた。大学の麻酔科医局が主催する研究会に出るためである。京都駅から大学までは遠い。普通の人なら市バスに乗るが、私は普通の人ではなく「バス降り損ね恐怖症」を患っている。降りたいと思った場所で、人さまを押して出ていく自信がないのだ。目的地が近づくと冷や汗が出る。
それに今、何と言っても恐いのは、中国からのコロナウイルス。人混みを避け、5キロほどの道のりを歩くことにした。
方角の見当つけてぶらぶらと歩いていくと、お寺があった。京都は寺だらけだからどこに寺があっても驚かないが、そこは「六波羅蜜寺」という寺であった。ちょうど今、私は平家物語を読みかえしているところだったので、平家の本拠地であった「六波羅」の地を発見できたことは、思わぬ喜びであった。何しろ六波羅という地名は現在残っていないので、これまでその位置がなかなかわからなかったのである。
そんなに有名な寺でもないような気がするが、けっこう観光客がいる。みんな、スマホで写真を撮って、うれしそうである。写真を撮って、自分がここに来たあかしを残し、インターネットで拡散する、現代の人はそうしないと何も始まらないのだろう。
こんなとき平安時代の人ならば、ただちに和歌を詠むはずである。体験を和歌に刻んで書き残し、景色や気持ちを人に伝える。平家物語のような無骨な軍記ものでさえ、無数の歌が登場する。
昔の人にとって、和歌は観光地で撮る写真であり、ラブレターであり、人気者になるためのツイッター、ユーチューブ、インスタグラムであり、昇進を願う嘆願書であり、遺書であり、つまり今のスマホ、あるいはそれ以上ののものだったのだと思わされる。
昔は昔で、なかなか文化的に豊かな生活を送っていたのだと感じる。電気を使わないし、使用料金も発生しない。人生のすべてを手軽に詰め込める、スマホのような和歌。どうしてこんな便利なものが廃れてしまったのだろう。
てなわけで、私も写真はやめておき、一首ひねってみることにした。感動も技巧も捨てて、そのままの棒読み調が、ネコマタ流だ。
その昔、平家がぶいぶい言わせてた六波羅の地の寺を見つけた
2020.2.6
|