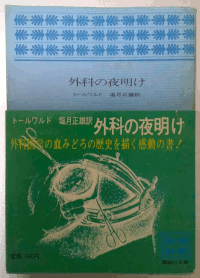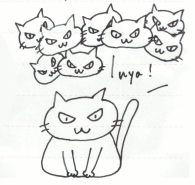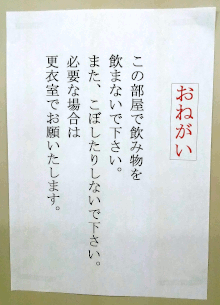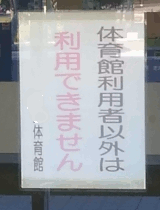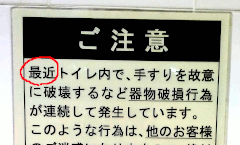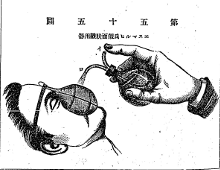|
古い言葉
|
今日はたぶん、いや間違いなく長い手術になるな、と思うことがある。具体的な術式名は控えるが、たとえば朝9時から始まって、夜10時くらいまでかかるんじゃないかという手術。その場合、術者のキャラクターもまた手術時間の重要な要素であり、自己陶酔型の術者だと納得の行くまでじっくり腰を据えてやるから、手術の進行は亀の歩みよりゆるやかであり、それどころか同じ所を行ったり来たりして、主観的な時間の流れは時計の針の進み方以上に間延びして感じられることであろう。
そんな手術に麻酔科医として臨む朝、こんな言葉が頭をよぎる。
「この門をくぐる者は、すべての希望を捨てよ」(ダンテ、「神曲」、読んだことないが)。
こんな時の気分を、寿命が1年あるかないかの「流行語大賞」などには託したくない。古典の言葉は、当たり前のことを言ってるだけのようでも、とにかく長い年月を経て生き残っているだけに、何か「持ってる」感じがする。
壮士気取りの朝ならば、こんなセリフもいい。
「壮士ひとたび去りてまた還らず」(司馬遷 - しば・せん、史記)。
これは敵国の王を暗殺するために旅立つ時、荊軻(けい・か)という男が残した言葉である。高校の漢文の授業で習った。まさに決死の覚悟の表明であるが、この男は王様に返り討ちされてしまうから、悲しい的中である。
ただし、家を出るとき配偶者に、また還らず、などと言うと、「じゃあ、もう帰ってこなくていいよ」と言われそうなので、心のつぶやきにとどめておく。
手術はやはり長引き、夜に入った。それなのに、手術の先が見えないのはどうしたことだろう。こんな時のために取っておいた言葉がある。
「どんなものにも、終わりがある。」
生まれて20年くらいしか経っていないが、私の言葉である。長年の麻酔科生活で、終わらなかった手術が一つもなかったことから、驚きをもって知り得た経験則である。
そんなことは当たり前と思われるかもしれないが、出血が止まらなくなって徹夜で休みなく急速輸血しなければならなかったり、脳腫瘍の手術が48時間かかったり(これはリレーで麻酔したが、何周も回ってきた)すると、もしかしてこの手術は永遠に終わらないのではないか、と不安になるものだ。だが大丈夫、人生、太陽の光、男女の仲、終わらないものは何一つないのだ。
長い手術も、患者さんのためだと思うから耐えられる。ただ、麻酔科医にとっての理想の手術をやはり古い言葉で表すと、
「来た、見た、勝った」(ガリア戦記、カエサル)。
さすが、二千年生き延びた言葉はキレが違うが、勝手に麻酔向きにちょっと変えさせてもらう。
「来た、見た、終わった」(麻酔科パラダイス)
2019.12.22
|
|
囲碁の話、その2
|
もう忘れている人もいるだろうが、2019年秋、日本にラグビー旋風が吹き荒れた。ラグビーワールドカップでの日本代表の活躍により、にわかラグビーファンが大量に出現したのである。彼らはラグビーのルールもよく知らないまま、テレビの視聴率を上げ、日本代表のユニフォームを買ってスタジアムに押し寄せ、子供をラグビー教室に入れ、多くのお金をラグビー界に落とした。収入源の縮小に悩む囲碁界は、これを見習わなくて、何とする。
実際、囲碁はスポーツと似ている。二人の人間が対峙し、自分の能力を最大限に発揮して、勝ちか負けかの決着をつける。丸いものを交互に打つ、という点では、卓球とよく似ている。仲間に入れてあげてもいい。
プロスポーツは「観戦」が重要な収入源であるから、囲碁もそうすればいい。ただ、囲碁は見た目が地味すぎる。ルールを知らない人でも楽しめるように、見せ方を工夫しなくてはならない。
たとえば、敵陣に取り残された黒石が、密かに白石の内臓に毒を流し、ついにこれを崩壊させる。あるいは、籠城戦のあげく陥落寸前の白石が、絶妙のタイミングで放たれた妙手で救われるが、助けに行ったその石は犠牲になる。こんな盤上のドラマを、碁を打たない人が見ても分かる、スターウォーズのような極彩色大音響の実況中継にできないか。そのハイライトシーンがテレビのスポーツニュースで映されるようになったらしめたものだ。「にわか囲碁ファン」の爆誕である。
とにかく、見せ方がすべてであるから、人工知能、コンピューターグラフィックスなどを駆使しまくった、まったく新しいショーアップ技術の開発が必須であろう。
私が日本棋院の理事長なら、その開発費に10億円出す。金を惜しんでいる場合ではない。まずは、最初にこれを提言した人に1億円を支払ってはどうだろうか。
2019.12.14
|
|
囲碁の話
|
公園で二人で遊ぶゲームを考えてみよう。一人が白い杭(くい)、もう一人が黒い杭を立てていき、境界を決めていく。最後に、杭で囲った陣地の広い方を勝ちとする。
お互い仲良く話し合って境界線を決められるような聖人君子同士なら、争いは起こらない。ところが幸か不幸か、人は少しでも多くを求めてしまうし、家でも国でも、お隣同志は仲が悪いと決まっている。境界線の押し合いへし合いはもちろんのこと、時には、自分が囲った陣地の中に相手が勝手に入り込み、杭を立て始めたりする。そうなると、その陣地が完成してしまう前に、叩き潰さなくてはならない。これはもう、陣地取りではなくて、やるかやられるかのドツキ合いである。
囲碁というゲームをわかりやすく説明すると、こんな感じになる。
私が囲碁を覚えたのは、大学を卒業してからだが、先生についたこともないし、人との対局もあまりしたことがない。そういう意味ではどれくらい強いか、自分でも計り知れないのだが、強いて推測すれば10級くらいだろう。もっぱらNHK教育テレビの囲碁対局などを見ているだけであるが、また、観戦だけでも面白いのが囲碁なのである。
まず、マス目に白黒の石を並べるだけのゲームに、どうしてみんながこんなに頭を悩ませ、プロ棋士などは人生をかけているのか、不思議でたまらない。
たとえば将棋、チェスなど、個々の駒が違う動き方をするから、ゲーム展開も複雑になるのは当たり前である。囲碁の場合、個々の石にとくべつな役割はない。それを交互に並べていくだけで、お互い数手先が読めない、どのボードゲームよりも複雑なゲームになるのだから不思議である。将棋を歩(ふ)だけで戦っても面白くなりようがないし、映画をセリフ棒読みの素人俳優だけで撮ってもつまらないが、囲碁ではそれで面白いのである。
この、道具立てのシンプルさと中身の複雑さのギャップが、囲碁の魅力ではないかと思う。
しかし今、日本の囲碁界は衰退の危機にある。何しろ碁を打つ人がどんどん減っているから、日本棋院、関西棋院の経営はさぞ苦しくなっていることだろう。また、競技力の面でも日本は苦しんでおり、日本のトップの棋士たちも中国、韓国になかなか勝てなくなっている。
囲碁というゲームがなくなることはないだろうが、このままでは日本の囲碁のプロ制度の維持は難しくなりそうだ。せっかく今、初の十代の名人、芝野虎丸(しばの・とらまる)とか、その殺傷能力の高さから「ハンマー」の異名を持つ女流本因坊、上野愛咲美(うえの・あさみ)といった新世代スターが台頭しているのだ。彼らの囲碁をこれからも見ていたい。
この辺で、日本棋院は囲碁ブームを巻き起こすために、思い切った手を打つ必要があるだろう。そろそろ推定棋力10級の私の出番かと思う。囲碁界の未来のために、捲土重来起死回生輪廻転生驚天動地大山鳴動鼠一匹の秘策を考えてみたい。次回に期待?できるわけがないでしょう。
2019.12.1
|
|
琵琶湖自慢
|
私が高校生の時、国語の教科書に、伊東静雄(いとう・しずお)という人の「わがひとに与ふる哀歌」という不幸な感じの恋愛詩が載っていた。その結びの行に「ほとんど死した湖」という言葉が出てくるが、国語の教師によるとこれは琵琶湖のことらしかった。このため、広島の高校生だった私にとって、琵琶湖とは死にかけの湖だった。
時は移って、私が医師になって2年目、大学病院を出て赴任したのは滋賀県大津市の病院だった。そこの手術室は10階にあり、麻酔科医室から琵琶湖を一望のもとに見渡すことができた。病院の窓から見える琵琶湖は、その広さゆえに陽光を何ものにも遮られることがない、明るい湖であった。伊東静雄は「わがひと」との恋愛でよほどひどい目に会ったのだろうということがわかった。
ちなみに「一望のもと」というのは言葉のアヤで、病院の窓から琵琶湖がいかにでかく見えたと言っても、それは日本一大きい湖のごくごく一部でしかなかった。滋賀県のどんな山に登ろうが、琵琶湖全体を一望できる場所はどこにもない。あきれるほどの大きさである。
滋賀県のことを、地元ではよく「湖国」という。それだけ琵琶湖が自慢なのである。自分に何かあったら、琵琶湖に飛び込めば何とかなると、県民はみんな思っている(多分)。滋賀県で琵琶湖の悪口を言うのは、広島県で広島東洋カープ(野球のチーム)の悪口をいうようなもので、危険な行為であると言わざるを得ない。
ちなみに伊東氏は京都大学の学生だったわけで、あれは滋賀県民にはちょっと書けない詩であったろう。
さて、滋賀県民の心の拠り所である琵琶湖にはヌシがいる。ビワコオオナマズという1メートルを超える魚で、琵琶湖食物連鎖の頂点にある。琵琶湖を我が物顔で荒らしまわるブルーギル、ブラックバスなどの外来魚も捕食してくれる頼もしいヌシである。琵琶湖にしかいない固有種であるが、一説によると中国長江流域の大ナマズと近縁種の関係にあるらしい。ナマズだけでなく、琵琶湖の魚類相は中国大陸の湖や河川のそれとよく似ているのだそうである。
琵琶湖は日本一広いだけでなく、日本一古い湖でもある。その年齢は400万年近いとされる。そのころは日本列島は中国大陸とつながっていたわけで、住んでいる魚の種類が今でも共通しているのは不思議ではないのかもしれないが、自然界の時間の流れの悠久さには驚かされる。
原生人類(ホモ・サピエンス)がアフリカで生まれてわずか20万年。それがやっとアジアに到達したのは5〜8万年前。琵琶湖はもちろんビワコオオナマズにも、ヒトはちょっと頭が上がらないのではなかろうか。
2019.11.19
|
|
ノーベル賞をもらわない方法
|
聞くところによると、ノーベル賞受賞の知らせは電話でくるらしい。山中伸弥(やまなか・しんや)氏などは、家で洗濯機を直しているところに電話がかかってきたというから油断できない。そんな電話を受け取ってしまったが最後、家や職場に報道陣が押し掛け、個人情報は白日のもとに晒され、配偶者までがインタビューされ、授賞式にはダンスや英語でのスピーチを強要される。
私を含め、世の中の大多数の人は、ノーベル賞受賞だけは何としても回避したいと思っているはずだ。
ノーベル賞をもらわないために一番容易なのは、当然であるが、何ら偉大な研究や人類への貢献をしないようにすることである。自分は大丈夫、と思っていたら意外な落とし穴があるかもしれない。昔、どこかの教授が、空いている研究室を人に貸したところ、その人がそこで大発見をしてしまい、発見者と一緒に部屋を貸した人にもノーベル賞を授与されてしまったというから恐ろしい。
研究と全く縁のない人でも、たとえば健康診断でへそのゴマを提出したところ、そこから常温核融合を行う細菌が発見され、地球を温暖化から救った英雄の一人として、受賞者に連座してしまうかもしれない。
スウェーデンからの不幸の電話を確実に防ぐには、自分はノーベル賞を受けとらないという記者会見を開くしかないだろう。
不思議なもので、ノーベル賞がほしくてたまらない人たちもいる。
宇宙が膨張していることを発見したハッブルという天文学者は、ノーベル天文学賞というものが存在しないことに気づき、急に天文学は物理学の仲間だと主張しはじめた。その作戦はうまく行きそうだったが、残念ながら、彼はノーベル賞をもらう前に亡くなってしまった。
また、どうしてこの人がノーベル賞をもらわないですんでいるのか、理解できないケースもある。
パルスオキシメーターは指先にセンサーを取り付けるだけで血液中の酸素濃度を測定することができる器械である。私などは、砂地に水が吸われるように、これがあっという間に世界の医療の現場に浸透していくのを目の当たりにした最後の世代だと思う。今では、患者の状態をひと目で知ることができるという点で、安全管理のために絶対に欠かせないものとなっている。この器械のおかげで容体の変化にいち早く気づいてもらえ、命拾いした患者の数は、世界で何十万人あるいはそれ以上だろう。
この器械の理論を最初に発表したのは、日本光電の技術者、青柳卓雄(あおやぎ・たくお)氏であるとされる。たしかに、その着想はきわめて独創的なものではなかったかもしれないし、技術的な困難から、器械の完成は別の企業の手によらねばならなかった無念はあるが、それでも青柳氏の手柄は十分にノーベル賞に値すると、臨床医なら誰でも思うはずである。
このような応用分野での発明には、なかなかノーベル賞は与えられないものかもしれないが、コンピューター断層撮影(CTスキャン)を発明したハウンスフィールド氏は受賞している。私は、パルスオキシメーターの価値はCTに十分匹敵すると思う。
青柳氏がなぜ、これまでノーベル賞を回避できているのか。何か、特殊な方法を知っているとしか、思えない。
2019.11.10
|
|
もて特性
|
私には縁のない話だが、私の思う「もてる男の子」のイメージは、次のようなものである。
背が高い、音楽の才能がある、スポーツができる、ハンサムである…
これらのうち、身長、音楽、スポーツは「行動遺伝学」により、なんと9割が「生まれつき」で決まるとされる特性である。以前ここで紹介したように(2017年1月15日)、これは双生児研究により科学的に割り出した数字であるから、テレビに出てくる自称脳科学者が挙げるような適当な数字ではない。「ハンサム」については評価が難しいから、調べられてはいないが、これもどう考えても生まれつきだろう。
つまり、異性にもてるかどうかは、本人の努力がほとんど及ばない特性でほぼ決まるということである。なんという不条理であろうか。
ただ、もてる人にも苦労があるはずだ。
人から聞いた話なので出典が不明であるが、昔、比叡山延暦寺にとてつもなく美しい僧がいたそうである。京の町に降りてくるたびに女性が群がってきて、前に進めないので、その美僧は「女払い棒」を手に持ち、「ごめんさないよ、ごめんさないよ」と女性たちをかきわけながら歩いたのである。
こういう話を聞くと、もてなくてよかったと、安心できる。自分は生まれつき持たざる者、ではなく、女払い棒を持って生まれた、選ばれし者、と思うようにすればよいのだ。
何でも、ものは考えようである。
もて特性に恵まれなくても、結婚相手は見つかることもある。奇跡的にゲットできた配偶者に向かって、「世界でたった一人にもてたら、僕はそれでいいから」と言ってみよう。新婚ならますます熱くなれそうだが、銀婚式を越えた夫婦だと、
「で、その一人はどこにいるの?」
と聞かれるだろう。
行動遺伝学の話に戻るが、卓球仲間の精神科医のO先生に、双子研究について話してみたことがある。彼によると、一卵性双生児でも、けっこう性格はちがいますよ、とのことであった。一卵性双生児はまったく同じ遺伝子を持っているから、生まれつきの性質も同じである、というのが双子研究の前提であるが、O先生によればその前提がおかしいという。遺伝子が同じでも、それらが発現するかどうかは複雑な制御を受けており、一卵性だから持って生まれたものが同じとは言えないはず、というのがO先生の意見であった。
行動遺伝学がその辺のところまで計算に入れているのかどうか、知らないが、あの「もて特性は9割生まれつき」の数字はちょっと違ってくる可能性がある。計算しなおしてもらって、8割くらいにならないか、という気もする。
ただ、それで私がもてるようになるわけでもないのであった。
2019.11.4
|
|
寝技について、その2
|
井上靖(いのうえ・やすし)という明治生まれの小説家が書いた「北の海」は、自分の学生時代のことを書いた自伝的小説である。この中で主人公が、「練習量がすべてを決定する」という寝技中心の柔道と出会うのであるが、これがなかなか興味深い。
現在の柔道は、立って相手を投げあう立ち技が中心であり、立ち技から崩れたという前提がなければ、寝技には持ち込めない。そういうルールである。ところが「北の海」の柔道は高専柔道と言って、いきなり寝技に持ち込んでもいい。またこういう寝技柔道では、持って生まれたセンスや体格よりも、技術力がものを言い、練習量で強さが決まるのだという。
残念ながら「北の海」では、主人公が本格的にその柔道をやるために金沢の第四高等学校に進学するところで終わっている。高専柔道とは一体どんなものなのか、見てみたいものだとずっと思っていたが、もはや絶滅したものだと諦めていた。ところが増田俊也(ますだ・としなり)の「七帝柔道記」という、これも自伝的小説で偶然知ったのだが、旧帝国大学の間で行われる大会ではこの高専ルールが生きているらしい。そしてその実際の試合の模様を、Youtube で見ることができる。
七帝柔道記によると、試合は団体戦のみで、15人の選手による勝ち抜き戦である。であるから、いかに敵の強い選手を引き分けに持ち込み、次の試合に進めなくするか、が勝負のポイントになる。選手の中には「抜き役」と「分け役」という役割分担があって、分け役の選手は相手が誰であろうとただ亀のようにうずくまり、ひたすら時間切れを狙うのである。ひっくり返されないというだけでも、これはこれで、たいへんな技量と体力を要するらしく、選手は誇り高い亀の専門家として一年中地獄の練習に明け暮れるのである。
実際 Youtube で七帝戦を見てみると、確かにこれは異質な柔道である。立ち技で戦う試合もあるが、寝技の時間が圧倒的に長い。現代柔道と違って「待て」がかかって立たされることもないから、延々と寝技勝負が繰り広げられるのだ。お互いに抱き合ったまま動けなくなり、そのまま引き分けとなる試合も多い。これはもしかして、両方分け役か?まさに、国際柔道連盟が目指すものの対極にある柔道であろう。
高専柔道が「練習量がすべてを決定する」柔道と聞いて、私は勝手にワクワクしていたのだが、そこはやっぱり寝技、思っていたよりもずいぶん地味だった。くんずほぐれつしながらも、おそろしい力と技の応酬が繰り広げられているらしいのだが、素人が見ていてもちょっとわからない。特に「分け役」の地味さと言ったらどうだろう。チームを勝たせるために、自分は負けないことだけに特化する。ちょっとでも勝ちたいという欲を出すと、ひっくり返されて負ける恐れがあるから、専守防衛に徹する。立ち技、固め技、絞め技は、紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するのであるから、ちょっと憲法九条に似ている。あらゆるスポーツの中で、これほど地味な役割りを担う選手がいるだろうか。
負けた。麻酔科医は地味さでは誰にも負けない自信があったが、七帝柔道の「分け役」には完敗である。
2019.10.20
|
|
寝技について
|
テレビなどで格闘技の競技を眺めていてどうしても気になるのが、その「実用性」である。街で悪い奴に襲われた時に、ボクシング、空手は役に立ちそうだし、柔道の投げ技も有効だろう。棒を持っていれば、剣道やなぎなたは相当戦えるだろう。だが、柔道の寝技で一番多い決まり手、「押さえ込み」がどう役に立つのか、想像がつかない。
押さえ込んだところで、相手が仰向けになって動けなくなる代わりに、押さえているこちらも動けないのだ。試合では、20秒ほど押さえておけば勝負がつくが、悪い奴をかりに押さえ込むことができても、次がない。敵がもう一人いたら、背後からやられ放題だ。
映画のアクションシーンといえば、ブルース・リーのカンフー、スチーブン・セガールの合気道などが目に浮かぶが、横四方固めを得意技にしているような地味なアクションスターは見たことがない。
私は高校の授業で柔道を習ったが、大腰、背負投げという投げ技と、ケサ固め、横四方固めという押さえ込み技を覚えた。まあとにかく、私は何をやってもてんでだめだったが、押さえ込みだけは私のような非力な者でも、きっちりかけると相手が動けなくなるのが不思議だった。
それから数十年、意外にも横四方固めが役に立つ時が来た。子どもとじゃれて遊んでいる時、横四方固めをすれば楽に時間をつぶせることに気がついたのだ。いくら子どもが相手でも、相撲とか投げ技を延々と(子どもは何でも延々とやりたがる)やっていたのでは、せっかくの日曜日に体力を消耗するばかりである。ケガをさせないよう、気をつけるのもまた労力だ。その点、押さえ込みならば体重を預けているだけでいいし、何ならそのまま昼寝に移行してもいい。何より相手に痛い思いをさせることがない。ただし、子どものほうも「こちょこちょ作戦」で対抗してくるのには手を焼くが。
寝技が子どもと遊ぶのに便利、などというと、柔道の人に怒られそうだが、相手を傷めないよう柔らかく制圧するのがその本質だとすると、ちょっと理解できた気がする。こじつけかもしれないが、ちょっと麻酔に通じるものがある。
最近の柔道の国際大会では、寝技が見直されているらしい。押さえ込みは20秒だけで一本になったし、寝技に移行してちょっとくらい動きが止まっても、「待て」がかかりにくくなった。制限時間で勝負がつかなければ延長されるので、寝技が得意な選手はじっくり攻めることができるようになった。寝技中心のブラジリアン柔術が流行している影響なのかもしれない。
Youtube で鑑賞するなら、濵田尚里(はまだ・しょうり)選手(女子78キロ以下級)の寝技集をおすすめしたい。いったん相手が畳の上に転がると、自分の巣にかかった獲物を糸でぐるぐるまきにする蜘蛛のように、じわじわと相手を料理してしまう。関節技なども駆使して、理詰めで攻略していると思われる。地味だと思っていた寝技を見る目が変わるだろう。
ちなみに、もし悪い奴に襲われても、私の使える唯一の格闘技、横四方固めの出番はない。逃げるのが最上の作戦であることは言うまでもない。
2019.10.5
|
|
ガーゼの乱
|
手術の終わり際、ガーゼカウントなる儀式が執り行われる。体内にガーゼが取り残されていないことを確認するために、ナースたちが使用済みガーゼと未使用ガーゼの数を数えるのである。数が合うのが当たり前であるが、1枚足りないとかいうことになると大変である。その1枚が、体内にあるかもしれないからである。
このとき、外科医も一応、ガーゼが残っていないか術野(切開して手術操作を施している場所)を探るのであるが、あまり本気を出しているようには見えない。「いや、もう残ってないと思うけどな。数え間違いと違うか」と、決まって言う。
一方ナースのほうは大騒ぎである。他の手術室のナースも動員して、ごみ箱をひっくり返し、外科医の足を挙げさせてスリッパの裏をチェックし、ドレープの裾や谷間を探る。さて、正しいのはどっちか。
麻酔科医としては、お役に立ちたい気持ちはあるが、患者さんを放ってごみ箱を漁るわけにはいかない。この勝負のゆくえを眺めるのみである。ま、だいたいナースが勝つのは経験上わかっているのであるが。
血眼のナースたちを眺めながら、ふと、原子力潜水艦の行方不明事件の話を思い出した。
1968年、米海軍の原子力潜水艦スコーピオンが大西洋で消息を絶った。どこかに沈没していると思われるが、やみくもに探すには、大西洋は広すぎる。そこで海軍は、数学者の力を借りたそうである。
まず、存在確率の高そうなエリアから探索を始めるのであるが、もしそこで発見できなかったらそれも大事な情報であり、それをもとに大西洋における潜水艦の存在確率の分布が変わるはずである。このように、状況の進行に応じて刻々と変化する確率を扱うのが、ベイズ理論である。そうやって存在確率マップを元に探索を進めていったところ、潜水艦は見事発見された。
この話は、ベイズ理論の入門書によく出てくるのだが、ちょっと宣伝臭い気もする。本当に数学者の手柄だったのかどうか、疑ったほうがいいかもしれない。だが、一昔前なら、「結局潜水艦を発見したのは、コンピューターでも数学理論でもなく、経験豊富な海軍士官の執念だった。」というオチだったのだが、今はもうそういうのが通じなくなったのは確かである。囲碁で人間が機械に負けた日から、私はもうあきらめている。
いつか、手術室でも人工知能がガーゼカウントをするようになるだろう。その機械がベイズ理論を実装しているのはもちろんだが、手術室内を俯瞰するカメラとつながっているので、そもそもガーゼの動きはすべて把握されている。不明ガーゼの所在など、最初からお見通しである。
これで、新人ナースが目を泳がせながらガーゼを何度も数えなおす必要もなくなるだろう。ただ、術野から「ない」はずのガーゼを発見してしまった外科部長が、取り出したガーゼをさっと清潔介助ナースの手に握らせ、「あ、ここにあるやん」と叫ぶシーンもなくなるのだと思うと、ちょっと寂しい。
2019.9.23
|
|
消費税と診療報酬
|
10月から消費税が10%に増税される。あまり知られていないことだが、病院は一般庶民と同じくらい、消費税増税の一方的な被害者である。病院が使用する材料や薬剤には消費税がかかるが、病院の主な収入である診療報酬は勝手にはいじれないからである。不条理な話である。私が病院の経営者だったら、腹を立てるところだった。
私が腹を立てるのは別のところである。
出費と収入にほんとうに10%の差がついたままでは、さすがに病院は持たない。中央社会保険医療協議会(中医協)とやらが来年の診療報酬改定で、消費増税に見合った分を増額してくれるのを待つしかない。問題はテレビである。
これまで、診療報酬についてテレビで報じられる時、アナウンサーはかならず次のように説明してきた。
「医師の給料などに当てられる診療報酬が、今回の改定で2%増額されることが決まりました。」
きっと今回も、そうやって報道されるだろう。これはいけない。これではまるで、「また医者がごねて、自分の給料を上げさせた」みたいではないか。医療に使う器械、材料、薬剤はすべて診療報酬から賄われる。人件費はその一部にすぎない。なんでこんな、誤解を招くようなことを言うのか。
心当たりがないではない。戦後、武見太郎(たけみ・たろう)という開業医が日本医師会に君臨し、政界とのコネクションをバックにして、一貫して開業医の利権を拡大した。中医協には当時、病院の代表が入っていなかったから、診療報酬は開業医がもうかるように持って行かれた。当時の状況ならば、「医師の給料などに当てられる」というのはあながち大嘘でもないかも知れない。
今はもう、医療の中心は病院である。医療は高度化し、設備、高額な医療機器、安全対策などに金がかかる時代になった。テレビ局はその決まり文句を、いつまで続けてるんですか、という話である。
テレビにはぜひ、次のようにも報道してもらいたい。
「アナウンサーの給料などに当てられるNHKの受信料が、このたび増額されることになりました。」
2019.9.16
|
|
不完全主義者の弁明
|
世の中には、タンスの引き出しにしても、ビンのフタにしても、「しっかり締める」のが苦手な人がいる。同僚や家族からはよく注意されるが、ついつい「隙間」を残してしまうのだ。完全に締めきる、ということに不安を覚えるのであろう。
そういう人はタンスだけでなく、何をやらせてもそこそこまではやるが、最後にやり残しの隙間が残る。旅行の計画を立てさせると、大事なところが抜けており、二度と任されることがない。同様に試験勉強、学会の準備、トイレの掃除、どれもこれもやり切る、ということがない。
どうしてこんなによくわかるかというと、私がそれだからである。
この、いわば「不完全主義」は気質の問題であって、決して計算の上でやっているわけではない。だが完成の一歩手前で停まる習慣は、ある程度合理的なものではないかという気がする。何ごとにおいても99%から100%への最後の一歩が、最も困難であることがしばしばある。そこにコストをかけるよりも、余裕を残しておいて、その隙間から出る問題をコントロールするほうが現実的と思われることが多い。
このやり方はたぶん、昔から存在する。
私の長年の剣豪小説研究によると、剣の達人というのはわざと相手に隙を見せたりする。相手が「隙ありっ」と撃ち込んできたところを、かかったなとばかりに撃ちかえすのである。
また戦国時代の城攻めでは、わざと攻めを緩めた門を残しておいたとのことである。逃げ道を残しておくことで、城方の兵を死に物狂いにさせない、したがって味方の損害を減らせる、という知恵である。
宗教の分野にも、それは見られる。本場の曼陀羅というのは、真ん丸に見えて実は、かならずどこかに真円が破れているところがあると聞いたことがある。仏教の世界にも、完全を回避する心があるものと思われる。
不完全主義者はあと少しのところで引き返すから、学問やスポーツにおいて世界の頂点に立つことはないだろう。それどころか、家族の頂点に立つこともむずかしい。トイレのドアをきちんと閉めない、肛門の管理も甘く、おならが漏れるなど、家族から怒られることばかりだ。
だが一方で、人類のすべてが100%を目指す完全主義者になってしまうと、これは大変だ。妥協を許せない彼らのこと、怒鳴りあい、どつきあいの惨状が繰り広げられるだろう。とくに完全主義者の麻酔科医が二人揃うと、手術室はなかなかやっかいなことになる。
それに引きかえ、われわれ不完全主義者の最大の武器は「妥協力」である。刺身をひきたてる千切り大根、荷造りのときに箱の隙間を埋める新聞紙、その程度の役割りくらいは我々にもあるんじゃないかと、私は思っている。
2019.9.8
|
|
終戦記念日
|
8月15日、令和初の戦没者追悼式で、新しい天皇陛下のお言葉が注目されたが、「深い反省」というこれまでの表現が踏襲されたのは、よいニュースであった。
終戦記念日前後になると、テレビや新聞などでも戦争に関する話題が増えるものだが、学徒出陣、空襲、沖縄戦など、日本の国民がどれだけ悲惨な目にあったか、という視点のものが多い。だから戦争は二度としてはならない、という結論である。それはもちろんその通りなのだが、日本がアジア全域を戦争の舞台にした結果、甚大な被害をアジア各国に与えてしまった事実については、あまり触れられない。
仕方がない面はある。たとえば日本軍によるシンガポール華僑粛清事件、陸軍731部隊による人体実験など、胸が悪くなるような事件の番組や記事は、誰も見たがらない。私も見たいとは思わない。だがもし日本の若い人たちが、たった2代か3代前の人たちがやったことを、知らない、聞いたこともない、という状態になっては、ちょっとまずいのではないか。
インターネットの世界では、素人の書いたものを素人が読み、願望やデタラメが真実になっていく。若い人にはぜひ書籍で、ふつうの歴史専門家が書いたふつうの昭和史に触れてみてもらいたいものだと思う。本当の歴史というのは小説と違い、愉快ではないものだ。どう控えめに言っても、日本はアジアに「迷惑をかけた」のである。当事者でないわれわれがいつまでも床にはいつくばる必要はないだろうが、記念の日に国民の代表が反省の意を表されたことを、しっかり受け止めたいと思う。
2019.8.27
|
|
こまめ
|
今年も淡い期待に反し、熱中症の季節が来た。熱中症は死に至ることもあり、そうでなくても腎障害などの臓器障害が残ることがある。まことにやっかいな病気である。
テレビなどで猛暑の予想を述べたあと、アナウンサーないし気象予報士が判で押したように、「こまめに水分補給を」と訴える。あまりに頻繁に耳にするものだから、こちらの耳にマメ、じゃなかったタコができてきた。つぎに「エアコンを適切に使用して」とつながるのだが、本来はエアコンのほうが先に来たほうがいいのではなかろうか。
最近の熱中症に関する総説を見ると、熱中症の予防の最初に来るのは、「涼しいところにとどまること」である。そして、「一人にならないこと」である。シャワーを浴びるのも有効である。「適切に水分を摂ること」は、その後にくる。ちなみに、その他の海外の(英語の)熱中症に関するサイトを見ても、水をたっぷり摂ることは勧められているが、「頻繁に」という副詞はついてない。「こまめに」という言葉に釣られて、夜中にわざわざ起きて水を飲むお年寄りがいると、聞いたことがあるが、そこまでする必要はないのではないか。
たぶん、「こまめに」という言葉がぴったりハマりすぎて、いつのまにか日本の放送界の決まり文句になってしまったのではないか。いくら水を飲んでも、くそ暑いところにいたのでは熱中症は防げない。そこに誤解が生じなければいいが、と思う。
研修医と議論してみた。
「ここまで地球温暖化が進むと、人間の冷却機能が汗しかないというのは、貧弱過ぎる。いっそ皮膚を粘膜化し、全身で気化熱を発散するほうがいい。両生類の仲間に入れてもらうんだ」
「カエル、オオサンショウウオ、ヒト、ですか。そうすると、ヒトの繁殖もタマゴということになりますね」
「そ、そうなるね。ま、少子化対策にもなるし、いいんじゃないの」
「じゃあ我々オスは、メスを見てムラムラするんじゃなくて、タマゴを見てムラムラするようになるわけですね」
地球温暖化が止まらない限り、確かに、そうなるしかない。
2019.8.11
|
|
手術器具の名前
|
手術中、外科医が欲しい器具の名前を言い、手を出す。直接介助のナースはすかさず、打てば響けやとばかりに器具を手渡す。反応が速いのは、先を読んでいるからだ。この丁々発止のやりとりは傍から見ているだけで気持ちいい。それにしても、その手術器具の種類の多いことよ。さまざまな科の器具を全部合わせると、千や二千は越えるのではないか。
器具がサッと出てこないと、いらいらする術者がいる。器具が準備されておらず、保管棚に探しに行くようなことになると、ナースに向かって声を荒らげる、頭のおかしい術者もいる。そういう者には一度、他の科の医者の直接介助をやってみて欲しいものだ。数多ある器具の名前を覚えるだけでもいかに大変か。その上手術の予習をして、手順を覚えておかなくては、先読みができない。お前(術者)の個人的な好みなど、おれが知るか、と思うはずだ。
どうぞご自由に、声を荒げあって欲しい。
ひとこと忠告しておくと、私が接してきた一流の外科医で、器具が出てくるのが遅いからと言って、ナースを叱るような人は見たことがない。それくらいのことで感情的になるような者が、術野で起こる予想外の事態に冷静に対応できるだろうか。
手術器具の名前には、カタカナのものも多い。リスター、コッヘル、ペアン(以上鉗子)、ミクリッツ(ガーゼ)、エスマルヒ(駆血帯)、ドベーキー(鑷子=ピンセット)などである。みんな何も考えずに「はいリスター」などと呼び捨てにしているが、これらは昔の偉大な外科医の名前である。彼らが何をなした外科医なのかは、なおさら知られていないだろう。リスターなどは清潔手術の手法を確立し、術後敗血症死を病院から駆逐した、近代外科の父である。それでもこういう形で自分の名前を残し、みんなに呼び捨てにしてもらえたら、外科医として本望ではなかろうか。
かわいい名前の器具もある。私が静岡の病院にいた時、泌尿器科で前立腺をぐいと押さえつける器具があり、「ネコの手」と呼ばれていた。たしかにちょっと、ネコの手に似ていたが、他の病院では聞いたことがないから、正式な名前ではないのだろう。静岡の病院なのに、医師はほとんど関西人で、ネコのアクセントが後ろ上がりになるところがポイントである。
前立腺全摘術のクライマックス、いよいよターゲットの前立腺があらわになった。尿道処理のために前立腺を圧排(あっぱい)する場面、それがネコの手の出番だ。若手泌尿器科医のN先生が「ネコの手」と要求する。このあたりの手順は一本道でぶれることはない。ナースは待ってた、とばかりN先生の手に渡す。汗かきのN先生は手術に夢中で、自分を支えてくれているナースのことはまるで意識していないが、それでいい。ナースの望みは、少しでも早く患者さんを無事にご家族のもとに帰し、自分も一秒でも早く病院を出ることなのだから。
現在、前立腺全摘術は手術支援ロボットによる手術が主流になっている。前立腺を押さえる以外の機能を一切持たないネコの手は、棚の中でじっとしているしかない。
やがて第一次世界AI大戦が勃発した時、医療系AIグループの没落に巻き込まれ、手術支援ロボットはコンセントを抜かれてしまう。それが、ネコの手の出番だ。その時ナースがその名前を、まだ憶えていてくれていればいいのだが。
2019.7.27
|
|
「させていただく」、再び
|
以前にもここで書かせていただいたことがあるが、「させていただく」という言葉がますます、日本社会をむしばみつつあると、私は感じさせていただいている。(どうです、うざいでしょう。)とにかく、何にでも「させていただく」をつけないと気がすまない人たちがいるのだ。そしてとうとう、学会という公式の場にも出現し始めた。ああもう、聞かせていただいてると、気にならせていただいてしょうがない。(しつこい。)
「発表させていただきます」はまだいい。聴衆に向かってへりくだっているのだろう。しかし、「経食道エコーを挿入させていただき…」、「気管チューブを抜管させていただきました…」など、一体誰に向かってへりくだっているのか、と聞きたいものだ。
いつか新聞の川柳コーナーで、こんなのを目にした。
「しました」を、「させていただきました」とは
高齢者はみんな、耳に飛び込んでくる違和感に苦しんでいるのだ。
ついでながら、「ございます」もはやっている。これは主に、事務系の人が会議などで連発するのだ。
「こちらは、先月の救急応需率でございます。」これはまあいいのだが、「です」で十分だと思う。そんなに丁寧に言われても、別に誰の気分もよくはならない。
「完成は7月の予定になってございます」、「患者満足度が改善してございます」は、明らかにおかしい。調べてみると、「ございます」は「あります」をさらに丁寧にした言葉である。「予定になってあります」とは言わないわけだから、違和感があるのは当然だった。
ここでも、これだけへりくだっておけば文句ないだろう、という横着な心理を感じることができる。
一方で若者は、他人に向かって自分の身内のことを「お父さん」、「奥さん」などと敬称で表現する。そこはへりくだらないのか。
あくまでも推測だが、もうみんな、敬語というものをあきらめかかっているのではないか。関係者全員の上下関係図を一旦脳内で展開しないと使えないのだから、日本の敬語はめんどくさすぎる。尊敬語と謙譲語をちょっとでも取り違えると、「そこはへりくだらないのか」と突っ込む年寄りがいたりするのだ。
こんなことならいっそ、日本語ですべての敬語を禁止したらすっきりするのに。出勤して上司に出くわしても、「やあマサオ、おはよう」と言える、中学一年の英語の教科書のような社会になれば、こんな悩みもなくなるだろう、などと最近私は、思わせていただくようになって来てございます。
2019.7.6
|
|
オンディーヌの呪い
|
私が「オンディーヌの呪い」という言葉に初めて出会ったのは、大学の生理学の授業の時であった。
われわれが意識しなくても、ついつい勝手に呼吸をしてしまうのは、脳幹部にある呼吸中枢のおかげだが、その一部が脳梗塞などで障害を受けると、極めて不幸な状態になることがある。呼吸するぞ、するぞと頑張って意識しないと呼吸できなくなるというのだ。眠ると呼吸することを忘れてしまい、死亡する、それがオンディーヌの呪いである。
よく雪山遭難のドラマなどで、「眠ると死ぬぞ」と頬を叩くシーンがあるが、あれを地で行く病気があるというのだから恐ろしい。医学の入り口に恐るおそる立ったばかりの医学生が、これを聞いてビビらずにいられるだろうか、いいや、ビビらずにはいられない。
あれから三十数年、実際の臨床では、眠った途端にピタッと呼吸が止まるような人を私は見たことがなく、呼吸が微弱あるいは不規則になるくらいのものである。患者さんのほうも、呼吸を忘れる恐怖におののいているわけでも、眠るまいと戦っているわけでもない。そういう意味では、「呪い」という言葉は、実態に合わない、調子に乗り過ぎた表現だったのだろう。
今、若い医師に「オンディーヌの呪い」のことを聞くと、みな知らないと言う。死語になりつつあるのかもしれない。患者さんの方も、自分の病気にこんなアダ名(診断名とは言えない)をつけられたら、いやだろう。
さて、オンディーヌとは誰か。それは昔むかしの女性の妖精である。オンディーヌはハンスという人間の男性と恋に落ちたのだが、ハンスが浮気をしたことに怒り、「眠ると呼吸を忘れて死ぬ」呪いをかけて殺してしまったのである。つまりこれは、「ヤキモチ」の物語である。
ヤキモチといえばギリシャ神話であるから、私はこれがギリシャ神話の中の話だと、ずっと思っていた。これまで研修医に向かって、「知らんかなあ、ギリシャ神話にあるやろ、オンディーヌの話。それくらい、知っとけ」と、さんざん説教したものであるが、今調べてみるとこれはドイツの民話なのであった。私はヤキモチを焼かれたことがない(焼く必要がないそうである)ので、この辺の確認が甘かった。無駄なことをしなさそうなイメージのあるドイツ人が、まさか嫉妬をするとは思わなかった。
不幸中の幸いだったのは、私が教えたことなど、どうせ誰も憶えていないことである。
2019.6.29
|
|
準備運動
|
マラソン大会や卓球大会で、主催者側から準備体操をさせられることがある。これが本当に必要かどうか、私は以前から疑問を抱いていた。マイクを持ったおじさんが、「しっかりアキレス腱を伸ばしておかないと、試合でケガをしますよ」とか、脅迫じみたことを言うのだ。たしかにケガは恐ろしいが、柔軟体操にケガを予防する効果はあるのか。何より、他人から号令をかけられて、みんなで同じことをするのが、私は恥ずかしいのだ。
ネットで探すと、準備運動についていろんな人がいろんなことを書いており、どれが本当なのかわからない。おそらくは多くの記事は根拠なく、自分のやってきたことだから正しいと信じて書かれているのではないか。
そこで私は、医学論文検索サイトで準備運動について検索することにした。細かく見ていくとキリがないので、数編の論文の要約だけ読んで、むりやりまとめて見ると…
-
本番の運動機能を高める上で役に立つ準備運動は、有酸素運動を伴うストレッチでからだを温めることと、野球の素振りなど、その競技の実際の動きをなぞる練習である。
-
床に腰を降ろしての柔軟体操のような、静的なストレッチは意味がない。それどころか本番で使わないような伸展を、長時間、痛いほど行うと、かえって運動機能が落ちる。
-
これらの準備運動がほんとうにケガを予防するかどうか、確証がない。
これをさらに自分に都合よく解釈すると、次のようになる。
卓球大会の前、「はい、つま先に手が届きますか。みなさん、からだ固いですよ」のストレッチおじさんは無視して、トイレにこもる。この歳になって、からだが固いくらいのことで人にけなされたくない。練習の乱打で一汗かいておけば、ウォーミングアップとしては十分だ。
最近のマラソン大会では、どこかから呼んできた準備体操専門(?)のお姉さんがステージに立つが、さすがに知ってるようで静的ストレッチはやらない。お姉さんはエアロビクス的なことを、自らやってみせながら甲高いこえで叫ぶ。「はいジャーンプ、しっかりカラダをひねって、となりの人とハイターッチ。」しかしそんな恥ずかしいことをして、もしこれが故障リスクを減らさないのだったとしたら、死んでも死に切れない。
どうせこれから死ぬほど疲れることをするのだ。出発して最初の2時間を、準備運動だと思うようにすれば、出発前のハイタッチは省略できる。2時間も走ると、世界トップの選手ならうっかりゴールしてしまうところだが、私はまだ全然折り返していないから、大丈夫だ。
私がこれまでやってきたことは、正しかった。知識は、ムダな羞恥プレーから人類を解放する。
2019.6.22
|
|
90歳代少女
|
90歳代女性の準緊急手術が入ったので、私が術前診察のためにベッドを訪問したところ、どうも手術は気が進まないと、もじもじしながらおっしゃる。なぜかというと、40年ほど前、自分の母親が手術を受けるとき、医師からこう言われたそうだ。
「75歳を超えた人に全身麻酔をかけると、もう、半々です。」
それにしても、半々、つまり死亡率50%というのだから、吹っ掛けたものだ。
いくら昔の麻酔でも、75歳以上の人に対して、麻酔をかけただけで半数が死んでしまう、なんてことがあるはずがない。ただ、開腹術など大きな手術を施した場合に、総合的にやはり現在の医療水準より劣っているから、今よりも死亡率が高かったのは、確かだろう。
たとえば、その頃は血液の酸素化を指先で評価できるパルスオキシメーターはなかったし、術後の絶食、ベッド上安静の期間は、現在よりずっと長かったし、敗血症など重症化してしまったときの治療に役立つ根拠はまだ存在せず、各医師の経験のみに基づく治療だった。
その結果として合併症が起こった場合、全部「麻酔のせい」にされてしまうところが、また、40年前なんだなあと思う。
この女性の場合、これほど明晰な頭脳を90年以上保ち続けているということだけでも、たぶん肉体エリートであろうと推察できる。予定される手術も、からだの負担の大きいものではない。私は「当時に比べて麻酔も格段に進歩し、危険性はぐっと減りました」と説明し、麻酔、手術を受けてもらった。何か起こったら麻酔のせい、という40年前の構図のままだったが、少女の面影を残すその人が、それで少しでも安心できるのなら、ま、いいかと思った。
手術はもちろん成功し、90代少女は無事退院された。
病気といい隣人といい、それらはいずれも、ある組織体へもたらす障害によってのみ自己の実体を示すものにほかならぬ。(リルケ著、大山定一(おおやま・ていいち)訳、マルテの手記)。麻酔もその仲間かもしれない。
2019.6.8
|
|
サンカ物語
|
「サンカ」と呼ばれる不思議な山の民が、かつて日本に存在していたそうである。サンカの人たちは、農民のように田畑に縛られることなく、戸籍も持たず、山間を移住しながら竹細工や漁猟などで生計を立てていたと言われる。ただし昭和の前半頃には、おそらく一般社会に吸収されてしまった、幻の集団である。
先に触れた柳田國男(やなぎだ・くにお)の「山の人生」にも、サンカは少しだけ登場しているが、そういう民がいるらしい、くらいの書き方で、ヤマンバ、テングなどと同列の扱いである。
もしもこれがたとえばアイヌのような一つの民族であり、われわれのごく近くにいながらほとんど交わることなく、山の中で独自の社会を築き、文化を受け継いできたのだとすると、ぞくぞくするような話である。しかし一方では、ただ単に一般社会にいられなくなったり、蒸発したりして山に入った、ワケありの人たちが集まったものに過ぎない可能性もある。
もともと新聞記者をしていた人で、このサンカの専門家になり、戦前から戦後にかけて本を出しまくってサンカブームを起こした人がいる。三角寛(みすみ・かん)という人である。しかし今ではこの人の書いたものは創作だったと言われ、書店で目にすることはない。先ごろの四天王寺の古本市で、三角寛の「山窩物語」(現代書館)というのを見つけたので、買ってみた。
早速読んでみると、筆者が新聞記者として事件を追ううち、サンカの存在を知り、その社会の謎に触れていくルポルタージュになっている。新聞記者だけあって、「説教強盗」を刑事たちと協力しながら追うところは、なかなか生々しい描写である。しかし、サンカの人たちが登場してくると次第に雲行きが怪しくなってくる。
サンカの若者が苦労して妻を娶ったが、逃げられないように眼を傷つけて盲目にしたという話、ドラマチックすぎないか。
この妻が大変な美女であり、川で白いからだを洗っているところが三角氏に見えちゃったり、エロ成分にもこと欠かない。
サンカ本が売れ始めたころ、京大教授や東大教授が向こうから訪ねてきて、三角氏の「研究」を褒め称えるところは、ニセ情報によく見られる「権威づけ」であろう。
サンカには実は京都にいる大親分を中心とする全国組織があり、1日140キロ走れる能力を使って連絡網を築いているとか、厳しい掟に縛られていて、それに背くと死罪になるとか。このあたりからもう、忍者である。
そして三角氏がついに、サンカの全国組織の構成に関する秘密文書を入手し、特殊なサンカ文字を解読した、と書いてあるところで、私はおなかいっぱいになり、本を閉じた。
内容の真偽は私には確かめようがないが、これだけ状況証拠が揃っては、このルポは「嘘八百」に分類するのが妥当であろう。嘘をつき通して「サンカ全集全35巻」まで書いてしまうところは、特異な才能ではある。(もし本当に調査して、これだけの量の報告書を残したのだったら、もっと驚くが。)
もし私たちが俗世間からはみ出したら、山に入って倒れたところを、サンカの美女(あるいはイケメン)に救われ、そのままご厄介になるかもしれないのである。サンカは、いわば日本人の心の最後の砦である。それが、私たちの世界以上に組織に縛られ、京都にいる親分に絶対服従でと、そんな話は聞きたくなかった。
どうせ作り話なら、もうちょっと夢のある話にしてほしい。突如山から降りてきたサンカの若者が、山の知恵でゴジラから日本を救うとか、そういうのでよかった。おそらく、ゴジラを倒す最終兵器は、先祖代々からの秘伝のタレ、その正体は、ゴジラ細胞の細胞壁を食べながら増殖する最強の腐食菌になるであろう。あと、地球上のマイクロプラスチックを食い尽くす虫なんかも、サンカは飼っているんじゃないかと思う。
2019.6.2
|
|
世を捨てる
|
私が子供の頃、父からよく聞かされた話の中に、知り合いの奥さんの家出事件がある。ごく単純な話で、その奥さんが銭湯に行くと言って洗面器を持って家を出て、そのまま二度と帰ってこなかった、という話である。その前も、後もない。
奥さんが事件に巻き込まれた可能性もあるが、そうではないと思いたい。その光景が私の目に浮かんでくるようだ。彼女はたぶん、ふっと突然、何もかも捨てちゃえと思いついてしまったのだ。家族に怪しまれないよう、洗面器とわずかな現金だけ持って家を出る。そしてそのままどこか遠くに行ってしまったのだ。
父が何度もこの話をしたのは、洗面器と家出という奇抜な取り合わせに驚きを覚えたのであろうが、その奥さんへのある種のうらやましさもあったのかもしれない。それが子にも受け継がれたのか、私はいつか自分がにっちもさっちも行かなくなった時、最後の手段として家出があるじゃないか、と思うようになった。洗面器だけ持って世捨て人になる、ああこれこそが男の(女も)ロマン、そんなふうに思えば、もうひと踏ん張りする元気が出てくるような気がするのだ。
さて家出をしてどこに行くか、考えておくのも悪くはないだろう。普通、誰も知人のいない見知らぬ街に行くものと決まっているだろうが、昔は「山に入る」というのが自然な選択肢だったようである。
柳田國男(やなぎだ・くにお)という明治・大正期に活躍した民俗学者が、「山の人生」という書き物を残している。山で生きる、ということにまつわるさまざまな伝説や逸話を集めたものだが、神隠し、失踪に関連した話も多い。それによると小学校教師の男性も、若い女性も、精神に異常をきたすなどして出奔し、意外と気軽に山に入るのだ。
たとえばある女性は、産後にちょっとおかしくなり、山に入った。最初は虫などを食べていたが、やがてキツネやタヌキを捉え、肉を裂いて生で食べるようになったという。そうするようになってからは体力がつき、一年中裸でも困らなくなったそうだ。
本当だろうか。これらの記事は、すべて伝聞や江戸時代を含む過去の記録によるものであるから、どれくらいの誇張が入っているか、どうも見当がつかない。ただ、意外に多くの世捨て人が山に入って行ったのは確かなのだろう。
ただし、もっと確かなのは、私にはキツネやタヌキ、虫は食べられないということだ。植物にしても、食えるものと毒性のものの区別はつかない。昔の人だからできたことで、私が山に入っても1週間と持たないだろう。
残念ながら、洗面器を持って山へ、という考えは却下せざるを得ない。
2019.5.26
|
|
外科の夜明け
|
今年のゴールデンウィークは10連休だったが、私の休日は手術、当直、待機当番でポロポロこぼれ落ち、丸一日私の自由になったのは4日間だけだった。でも、こういう時には下を見るといい。入院患者さんを毎日診察しにくる内科などに比べたら、麻酔科は恵まれているほうだろう。
その貴重な休日、私は大阪の四天王寺に行った。お寺の境内で古本市が行われていることをニュースで知ったからである。
街の古本屋さんは嫌いではないが、客が少ないだけに、店のオヤジさんの視線が痛いのが欠点である。その点、この青空古本市は、多くの客に紛れて、好きなだけ本を眺めまわすことができるからいい。

本を眺めはじめてすぐ、私は長年欲しいと思っていた講談社文庫の「外科の夜明け」を見つけた。全身麻酔と消毒法の発明を中心として、近代外科の誕生の様子を小説仕立てで描いた本であるが、絶版になって久しい幻の本である。まさかこんなところで出会うとは思わなかった。
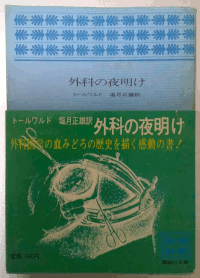
この本については当ブログのようなものでも、何度か紹介しているが、実は本物を見るのは初めてである。私がこれまで読んできたのは、同じ原作を他の人が訳したものであったが、麻酔科医なら読んでおくべき名著、との誉れ高い講談社文庫版は入手しておきたかった。しかも、この本はインターネットで探すと5,000円くらいの値段がついているのに、目の前の本は300円である。
私はまず周囲を見回し、他の人に気づかれていないことを確認し、平静を装いつつ「外科の夜明け」を手に取った。
最近、メロディーだけ知っていて、ずっとその曲名を知りたいと思っていたピアノ曲の名前が偶然わかった。あとはもう一つ、中学生のころラジオ放送をエアーチェック(死語)したポップス曲の名前がどうしても知りたいのであるが、これまで実現してしまってはまずいかもしれない。「お前はこれでもう、思い残すことはないやろ」と、どこかからお迎えが来そうである。120歳くらいになるまで、この楽しみは取っておこう。
2019.5.18
|
|
風邪声
|
私はここ8年くらい、風邪もひかずに過ごしてきたというのに、今年はもう3度目になる風邪をひき、のどをやられている。職場で低い声でしゃべっていると、看護師さんがこう言った。
「先生、なんか男前ふうの声になってますよ。違う人みたいです。どうしたんですか。」
なんか、ひっかかるものを覚えたが、おかげでいいことを思いついた。
「風邪ひいちゃってね。この声なら、オレオレ詐欺ができるんちゃうかな。」
10年以上前だが、私の実家にオレオレ詐欺の電話がかかってきた。風邪をひいてすっかり声がおかしくなった私が、電話に出た母に、こう言ったそうである。
「女に手を出した。嫁に内緒で別れたいけん、手切れ金が要るわいね」
母は、「あんた、何しょーるんね。困ったねえ」と弱り果て、父に電話を替わった。父も最初は「なんぼ要るんかのう」などと応じていたが、どうもおかしいと気づき、「われ(お前)の兄弟の名前、ゆうて見い」と言ったら、電話が切れたそうだ。
この事件で私がショックだったのは、私の母が、自分の息子の声を聞き違えたことであった。そもそも、自分の息子には浮気をするほどの勇気はないと、どうしてわからなかったのだろうか。
今はもう、両親は電話に出られる状態ではない。父親などは、あの世に行ってしまっている。この風邪声を利用して、だます相手は妻しかいない。頭の中で作戦を立ててみる。
「あ、もしもしワシや」
「え、声がちがうけど」
「ちょっと風邪をひいてね。それはともかく、仕事で失敗して、3万円ほどお金がいるんだけど。」
ここで怪しまれても大丈夫。私は本人だから、飼ってるネコの名前も、初デートの場所も答えられる。
しかしここから、どんなシナリオを立てても、3万円をゲットできる図が見つからない。妻と暮らした年月は、すでに親よりもずっと長い。親と違って、「愛情で目が曇る」ようなことは絶対にない。相手が悪かった。
こちらに被害が出る前に、オレオレ詐欺はあきらめることにした。
2019.5.5
|
|
弓道
|
このたび麻酔科に配属された研修医が、弓道部出身だった。私は弓道部の人と口をきくのは生まれて初めてなので、何か途方もない秘密が聞きだせるのではないかと予感した。
Q: 昔から武士道は「弓馬の道」と言って、いくさの主戦武器は弓だったはず。ところが弓の有名人は那須与一(なすのよいち)と源為朝(みなもとのためとも)くらいで、剣豪がひしめく剣術に比べてずいぶん冷遇されているよね。同じ武道でもこっちが上なのに、くそっ、とか思ったりしないの?
A: いや、別に…
Q: 弓矢に当たると、人は一発だけで死んだりするのかね?
A: 当たり所ですかね。
Q: 卓球は動きの中で球を打つけど、調子のいい時は敵コートの白線上(台の端)に面白いように(=10回に1回くらい)決まったりする。弓はどうなの?人間のからだは、動きを完全に止めることはできないわけだから、むしろ呼吸などの動きに合わせてタイミングで射つものかな、と勝手に思ってるけど。
A: いえ、あくまでも腰や下半身を完全に固定して、無動を実現するのが理想です。
Q: 卓球だと、朝の練習で球を打った時の感じで、その日の調子がわかる。今日はミートが悪い、とわかると、もうその日はだめ、自分では調子は変えられない。弓でもやっぱり、そういうことある?
A: あります。弓は相手がいないだけに、調子の差がもろに出ます。
Q: だとすると、調子が悪い時にそれをいい方に変える手段が、実は弓道界で発明されていたりしないの?それを公表して、人類に役立てないなんて、もったいないよ。
A: そういうのは、ないと思います。
武道と卓球という異質なスポーツの出会いが、人類を救うアイデアを生む可能性に期待したが、失敗だった。ウン千年の間、綿々と引き継がれた奥義を、ただでは教えたくないようだ。こんどソバメシを食べさせて、改めて聞き出すことにしよう。
2019.4.21
|
|
怪談
|
先日私は、本屋さんに怪談の本が陳列してあるのを見つけ、たまにはこういうのもいいかと思い、買ってみた。いろんな作家の怪談小説を集めた文庫本である。(日本怪談集、種村季弘 -たねむら・すえひろ- 編、河出文庫)
何せ色んな時代のいろんな小説が盛り込まれているので、怖さの趣向もさまざまであり、私の気に入ったのもあれば、気に入らないのもあった。文芸的過ぎるものは概して面白くない。作家は奇妙な味わいの幻想小説を書いたつもりらしいが、下手をすると誰が幽霊なのか、何が怪奇現象なのかも分からないまま終わってしまう。そういうのはちょっとお金を返してほしい気もする。
その点、この本に収録されている小松左京(こまつ・さきょう)の「くだんのはは」は素晴らしかった。昔読んでよく知っているが、読み返してみて改めて、傑作の中の傑作だと思った。空襲で家を失った少年が、あるお屋敷に引き取られ、そのお屋敷の秘密に感づいていく。その秘密の正体だけでも十分怖いが、最後の数行で突然、読者自身の身に災いが降りかかってくるのだ。この壮大な仕掛けは、さすが「日本沈没」を書いたSFの巨人である。
このように今では私も、怖い話の趣向がどうの、仕掛けがどうのと言っていられるが、少年のころは、とにかく幽霊が怖かった。子供時代の心配ごとの三分の一くらいが、幽霊に襲われたらどうしよう、という怪談関係だった気がする。私だけでなく、私の兄弟も、まわりの子供たちもそうだったと思う。
当時は金曜ロードショーなどで、さかんに劇場映画をテレビで放映していたが、怪談ものの映画も実に多かった。「一枚足りなーい」の番町皿屋敷、お岩さんの髪の毛がごっそり抜ける四谷怪談、強いのか弱いのかよくわからない吸血鬼ドラキュラなど、今から思えばのどかな古典ホラーを、私は姉たちと見ながら震え上がったものである。その夜、明かりを消して寝る時のおそろしさと言ったら、言葉では言い表せない。
ところが、自分の子供の世代を見ると、そこまで幽霊を怖がっているのを見たことがない。たぶん、そういう時代なのだろう。教育関係のコメンテーターなんかが、人間の力を超える何者かの力を恐れることが、人としての成長に必要なのだとか何とか、例によって根拠のないことを言いそうな気がするが、どんなものなのか。少なくとも私は、子どものしつけのために幽霊の力を借りるようなことは、考えなかった。
幽霊の不在が、たしかに子どもたちの精神発達に何らかの影響を持つ可能性はあるが、それが悪いことなのかどうか、誰が決められるだろうか。
とりあえず私は、心配ごとが私より三分の一少ない今の子どもたちがうらやましい。もしその子に、布団蒸しを仕掛けてくる兄がいないとしたら、その子の悩みはさらに半減し、私の三分の一になるのだ。
2019.4.15
|
|
スキー滑降
|
雑誌、卓球レポートの中条一雄(ちゅうじょう・かずお)氏の連載コラム、たしか「スポーツ名人伝」だったか、それの話をつづける。「トイレ掃除」の他にも忘れられない名言が、私の中に残っているのだ。何しろ30年以上前の記事であるから、細かいところは想像で補わざるを得ず、たぶんだいぶ嘘が交じる。
中条氏がスキー滑降の元オリンピック選手にインタビューしたときのことである。その名選手は勝つために必要なことは何かと聞かれて、日々の練習でなるべく多くの技術を身につけ、磨くことだ、と答えた。
中条氏はもともとサッカーが専門だから、スキーのことはあまり知らない。思わず聞き返したのである。滑降のような単純なスポーツでも、そんなに多様な技術が必要になるのか、と。その名選手の答えがしびれる。
「スキーの技術は、無限です。」
私もスキーのことは全く知らないが、中条氏の驚きは理解できる。他のややこしい球技などに比べると、スキー滑降が単純そうに見えるのは確かである。だが、そのような競技においても、細かいところを突き詰めて、突き詰めきったところで、また突如新しい技術が発見される。常に新しい局面が出現し、決して尽きるところがない、ということだろう。
これは世の中のすべてに通じる名言だ。うまく使えば、かっこいい。
「あ、すみません。点滴うまく入りませんでした。もう一回やらせてくださいね。」
「今度はおねがいしますよ。」
「がんばります。でもうーん、いい血管ないか、もう少し探します。」
「いやいや、点滴なんて、普通一発で入るん違うの?」
「この仕事30年やってますが、点滴が一番むずかしいんです。血管ごとに、攻め方が違いますからね。点滴の技術は、無限です。」
一度言ってみたいものだが、言い訳にしか聞こえないから、言えない。
2019.4.6
|
|
トイレ掃除
|
30年以上前のことだが、雑誌「卓球レポート」にオリンピックで金メダルを取った水泳選手の話が載っていた。たぶん、古橋広之進(ふるはし・ひろのしん)のことではなかったかと思うが、もし違っていても、とにかくその時代の人だ。F選手としておく。
当時、日本はレベルが高く、オリンピック前の合宿などでもF選手はなかなか勝てない。日本代表の中で勝てば金メダルを取れる、と言っていいのだが、それがむずかしいのだ。極限まで練習して、工夫して、それでも彼らに勝ちきるにはまだ何かが足りない。
F選手はその最後のひと押しのために、宿舎のトイレ掃除を始めたそうである。ライバルのやっていない何かをやり遂げることが、勝利につながる。そこに賭けた。それがなぜトイレ掃除だったのか、理屈では説明できないが、結果彼は金メダルを取ったのだから、正しかったのだろう。
彼の本心をそのまま言葉にすれば、「どんなに汚い手を使っても勝ちたい」だったと想像する。その執念が際どいところでトイレ掃除に転化した。きれい事でないナマの極限状態を、話を聞いた記者は感じ取り、記事にしたのだと思う。
これを書いたのは、元新聞記者の中条一雄(ちゅうじょう・かずお)氏。卓球専門誌ながら、様々な種目のスポーツ選手に直接取材し、「勝ちと負けの間のこと」をテーマに連載していた。30年経った今でも私が覚えているのは、この人の筆の力によるものだろう。
テレビなどではよく、アナウンサーが試合前の選手をつかまえて、「自信しかありません」などの、自分が聞きたいことを言わせようとしているが、中条さんを勉強して出直せ、と言いたい。
仕事にも、これくらいの執念がほしいものだ。
研修医「先生、胃管が入りません。おねがいします。」
私「ほらよ」
「どうすれば、そんなふうに入れられるようになりますか」
「まず真剣に念じることだ。胃管挿入がじょうずになりますように、と。」
「はい」
「すると、普段の行いを正しくしなければ、胃管は入らないことがわかってくる。率先してトイレ掃除するとか、階段を登れなくて困ってるおばあさんをおんぶしてあげるとか、してる?ぼくなんか毎晩、胃管のことを考えながら寝てるよ」
「あー、じゃあいいです」
こいつはだめだ。私と一緒だ。
2019.3.26
|
|
民度と国民性
|
先日、天皇陛下御在位三十年記念式典のニュースを見ていたところ、天皇陛下がおことばの中で「日本人の民度」という言葉を使われたので、私はちょっと驚いた。民度というのは、たぶん私が子供の頃にはなかった、かなり俗っぽい言葉である。ちょっと天皇陛下のおことばには合わない気がする。
私が初めてこの語を聞いたのは大学院の頃で、関東から引っ越して来た研究室の上司がこう聞いてきたのである。
「で、京都の人の民度ってどうなの?」
意味がよくわからなかったので、適当にごまかしたが、イヤな感じは残った。よその土地から来た人がいきなり、ここの民度が高いの、低いのと言いだすなど、品のないことである。私が本当の京都人なら、そろそろぶぶ漬けいかがどすか、と反撃するところだったろう。
民度と似た言葉に、国民性というのがあるが、高い、低いではないので、私としてはもう少し抵抗感は小さい。だが、これも固定観念になってしまってはろくなことがなさそうである。
たとえば日本人の国民性というと、勤勉、礼儀正しい、時間や約束を守る、というイメージがあるが、本当か。幕末物の小説、記録を読むと、いい加減な役人がいっぱい出てくる。こともあろうに、日本を代表してロシアだのアメリカだのと折衝する高級役人が、ちょっと都合が悪くなると、体調が悪い、とか何とか言って交渉をさぼりまくるのである。たまに、川路聖謨(かわじ・としあきら)みたいなまともな人も出てくると、外人さんもさぞほっとしただろう。
日本人は平和を愛する国民性、と思っている人がいるとしたら、これも歴史的に見れば大間違いである。有史以来1945年まで、戦争、一揆、テロの連続、これほどいくさ好きな民族もちょっとないのではないかという気がする。
国民性というものが、存在しないとは思わないが、時代や状況によって変わる、意外にあやふやなものではなかろうか。
結局、国民性という概念が役に立つのは、国民性をネタにした各種笑い話くらいかもしれない。私が好きなのは、定員オーバーの救命ボートから、男どもを海に飛び込ませる話である。アメリカ人には、「飛び込むとヒーローになれるゾ」、ドイツ人には、「それが規則ですから」、日本人には「みなさん、そうされてますよ」と言えば、一発で飛び込んでくれるそうである。
各国の人たちのおバカぶりを笑っているようで、実は国民性とやらに先入観を持つことのおバカぶりを笑っているようでもあり、どうでもいいけど面白いからいいか、という気になる。
2019.3.15
|
|
説明と同意と葬式、その2
|
手術の前には、麻酔科医は患者さんのもとを訪れ、麻酔の説明をし、同意をいただくわけであるが、本当に患者さんに理解してもらっているかどうか、なかなか自信は持てない。最後に質問ありますか、と聞くと、高齢者からは、わしら、なーんも分からんから、と言われてしまうことが多いのだ。
だが、全身麻酔の説明はまだ楽な方かもしれない。最終的には「寝てる間に手術が終わりますから」というところだけ理解してもらえれば、何とかなる。外科医の説明は大変だろう。
たとえば胃や心臓の手術などは再建を伴うから、まるで迷路のような完成図になることがある。脳外科の手術を完全に理解するには、脳循環の生理学、神経解剖学などの知識が必要になる。要するに、毎日そればっかりやってるプロと、ほとんど医学知識のない丸腰の素人さんが、狭い談話室で出会いがしらにぶつかるわけである。どこまで説明し、どれほどの理解を得られるか、やってみなければわからないというところだろう。
外科医にはいろいろなタイプがあって、こうしたややこしい話をとことん詳しく説明する人と、わかりやすいところだけざっくり説明して済ませる人がいる。
時間をかけて詳しい説明をするのがいい外科医、と思われそうだが、そうとも限らない。何ごとも程度の問題である。たとえば肝臓をどこまで取るかの説明でミトコンドリアまで持ち出されたのでは、聞いてる方は意識が遠のくに違いない。
説明が3秒で終わることもある。ある時、腸の穿孔だったと思うが、少しでも早く手術したほうがいい患者さんがいた。しかし本人が怖がってしまい、若手外科医がいくらその必要性を説明してもなかなか決断できない。そこにやってきた豪腕外科部長、「手術せんと死ぬで」と説明、と言うより一喝し、ただちに手術が決まった。これなどは外科史上もっとも短く、わかりやすい説明であったろう。時と場合によっては、こうした強引さもやむをえないと思う。
さて前回私は、お葬式の前に宗教者も説明と同意を、と提案した。今はもう、ほとんどの人が宗教や儀式に関し、常識というものを持たない素人になってしまっているからだ。
もしそのような時代が来たら、最強の宗教は浄土真宗ではないかと思う。私の思い違いでなければ、「生きてる間に南無阿弥陀仏と唱えておけば、死んでからも何とかなる」というのが浄土真宗の宗旨であるから、このシンプルさは強い。伝えたいことが簡明であるというのは、説明においては最大の武器である。
ただ、質問コーナーは大変そうだ。「一周忌はいつごろお願いしたらいいでしょうか」といった質問なら簡単だが、「念仏を唱えるのはいいけど、本当に極楽へ行けるのか、誰が保証してくれるのか」などと質問されたら、私だったらお手上げである。たとえば野に咲く花の可憐さや、病気の苦しみとかから神や仏の存在を証明してしまうような、特別な説得力が必要だろう。
「信じないと地獄へ落ちるで」と一喝するのは、勘弁してほしい。怖いから。
2019.3.2
|
|
説明と同意と葬式
|
昨年末、私は曹洞宗と浄土真宗のお葬式を連続で経験した。その結果、仏式のお葬式について、もやもやが残っている。
私の親の世代は、そこそこ熱心に信心していたし、普段からお寺とつきあっている。私の世代になると、もうそれがない。もし、あなた方は仏教を信じますか、と正面切って問われたら気を失うところであった。長く続く伝統だし、故人も望むであろうから、仏教式の葬儀をお願いしているという立場である。
僧侶の方は、こちら側のとまどいを知ってか知らずか、この世とあの世のエキスパートとして、我々を指導する気まんまんで登場する。お経で死者をしかるべきところに導き、出席者にも法話をして、遺された者の心得を説いたりする。
しかし、もしも何を言っても許されるのなら、いやちょっと、それ本当ですか、と聞いてみたいことがいろいろある。
まず、そのお経、何を言っているか全くわからないのですが、何のために読んでいるのでしょうか。仏になりかかっているとは言え、故人も聞いて理解しているとは思えない。たとえば一言、「いろいろあったが、成仏してください」とかではだめでしょうか。
それから、人が死ぬと四十九日はあの世とこの世の中間に漂うと言いますが、誰が見てきたのでしょうか。極楽直行便に乗る方法はないのか。
そのあと、人は因果応報の法則に従って他の生き物に生まれ変わるのか、あっさり極楽とか地獄とかに行ってしまうのか、同じ仏教でも言っていることがバラバラですが、どう整合性をつけたらいいのでしょうか。
あと、お布施をお渡ししたとき、領収書くれとは言いませんが、受取証みたいなのもないのはなぜ。
こんな疑問をいだきつつも、ほんとに聞いたら和尚さんにブチ切れられて、お葬式がめちゃくちゃになるかもしれない。そう思って、無難に全部おまかせしてしまう。
ちょっと、昔の医療に似ている。昔は、もう細かい話はわかりませんから、先生にお任せします、というのが、昔の患者さんの決まり文句であった。(今でもそうおっしゃる方はけっこう多いが。)
しかし、今は説明と同意(インフォームドコンセント)の時代だ。つまり患者は説明を聞いた上で同意をする権利があるし、たぶん義務でもある。昔は患者さんが質問するのはちょっと勇気が必要だったかもしれないが、質問が出るのはちゃんと聞いてくれている証拠だから、今では医療者側としてはうれしいくらいである。確かに、こちらの顔がひきつるような質問というのはある。
ここ病院やろ、病気を治すのが医者の仕事なんと違うんか。(いや、治らない病気もあるから、人はいつか死ぬわけで)
麻酔の副作用とか言うけど、それを絶対起こしません、いう一言がどうして言えないの?(言えないから言えません)
手術はしかたがないけど、麻酔がいやなんです、私どうしたらいいのでしょう。(じゃ、麻酔なしでやりますか、という言葉を何度のみこんだことか)
だがこのような、忍耐力の修行のようなやりとりが発生することは多くはない。逆に、麻酔の核心を捉えたような質問をいただけると、ああ会心の面談だったとうれしくなる。
説明と同意は、面倒なことばかりではない。お寺さんにとっては、新しく仏教を広め直すチャンスではなかろうか。そういう時代に、そろそろなって来るのではないかなあと思う。
2019.2.17
|
|
忘却のかなた
|
私のように人の名前が思い出せないというのは、まだ物忘れの初心者である。これが上級者になると、何から何まで盛大に忘れるようになる。
去年の暮れ、相次いで亡くなった父と義父(妻の父)は、いずれも90歳前後の大往生だったが、二人とも揃って認知症だった。自分の身内のことをだんだん忘れていくわけであるが、二人とも、兄弟のことだけは最後まで覚えていた。
父は大変なかんしゃく持ちで、周囲をホトホト困らせる人だったが、晩年には自分が誰かも忘れ、何もかも忘れ、ついに仏さんのような穏やかな表情になってお茶をすすっていた。忘れることにも、いい面はあるのだと思った。
そんなところに、けんか別れして長年絶縁状態だった父の兄が会いに来てくれたそうである。父はほとんど全く目が見えなくなっていたのに、数十年ぶりに会った兄に向かって、
「あんちゃん、車いすか」
と言い当てた。そして、あれだけ憎みあっていた兄と、楽しげに語り合っていたそうである。話に聞いて思い浮かべるだけでも、不思議な光景である。
どうやら認知症の人は、時計の針を逆に回すようである。新しいことから忘れていき、子どもの時代に戻ってしまったのでは、妻も、子も忘れるのはしかたがない。おかげで、自分が兄と立ち上げた会社で対立を繰り返し、結局ケンカ別れしたことも、うまく忘れることができたのである。
その父ももうこの世を去り、今度は父が忘れられる番である。私も当分は父を忘れないだろうが、30年先になると自信がない。100年も経てば、父を知る人はこの世にいなくなる。残るのは墓石だけだ。
磯田道史(いそだ・みちふみ)という歴史家の最新刊、「日本史の探偵手帳」(文春文庫)によると、庶民が墓に石を使うようになったのは江戸時代のことだった。それ以前は、遺体を土葬して卒塔婆という木の札を立てていた。そのうち卒塔婆が朽ち、誰をどこに埋めたかも分からなくなる。その時が、死者が忘れられるときなのである。
なるほど確かに、縄文時代から墓石が立てられていたりしたら、一つの墓に数人分のお骨を納めるにしても、積もり積もって今ごろ日本は墓石だらけになっていたはずではないか。墓石が江戸時代からのことと思えば納得がいく。
昔は、木が朽ちるのと同じくらいの、ゆっくりしたスピード感で故人が忘れられていったのだ。無常と言えば無常だが、合理的と言えば合理的である。
忘れ、忘れられることの方が優しいこともある、そんなことを父から教えてもらった気がする。織田信長ほどの有名人になると、死んで400年経っても忘れてもらえないし、墓なんかどういうわけか、あっちこっちに散在している始末である。父も私も、すぐ忘れてもらえそうな、どうでもいい人だったのはラッキーだった。
2019.2.9
|
|
名前が思い出せない
|
相手の名前失念ネタは、これまでにも書いた気がしないでもないが、よく覚えていないので、また書く。
先日、私はいつものようによろよろとジョギングしていたところ、むこうからやはりよろめきながら走ってきたお兄さんが、すれちがいざま、「〇〇先生!」と声をかけてきた。よく見ればどうも、去年、他の病院に転勤した〇〇科の医師のような気がするが、名前が思い出せない。
医師という仕事が便利なのは、こんな時だ。名前の分からない相手が医師である限り、教授だろうが研修医だろうが、二人称は「先生」で間に合ってしまう。私はこう返事した。
「先生、そろそろ開業されるんでしたっけ?こっちは相変わらずバタバタしてます。先生おられなくなって、〇〇科の雰囲気が随分変わりましたよ」
このように、一旦「先生」で始めたら、最後まで「先生」で行かなくてはならない。思い出せそうだからと言って、途中から名前で呼ぼうとなどとは、絶対に考えてはならない。しばしば相手の名前の最初の一文字が浮かび上がってくるが、これが罠なのだ。二文字目の手ごわさは異常だ。たとえば、
「それでね、えーと、松…松山先生?」
「松岡です(怒)」
となるのが落ちである。「山」も「岡」も同じようなものだが、許してはもらえない。まして最初の一文字が間違っていたら、救いはない。
私は正体がばれる前に、腕時計を見て、タイムの遅れを気にするそぶりを見せながら、早々に別れをつげた。
この手は、相手が看護師さんだと通用しない。手術室で仕事中、とつぜん目の前のナースの名前をド忘れすることがあるが、そういう時はもうなるべく話しかけないようにするしかない。そうなった時に怪しまれないよう、用もないのに声をかけるようなことは、普段から慎むことも大切だ。
英語なら全部、"you" で済むのに、日本語はこういうところが、ものを忘れはじめたおじさんに厳しい。
2019.2.7
|
|
ジョギングシューズ購入記
|
ほとんどすべてのスポーツにおいて、フットワークはもっとも重要な要素であるから、相撲やビーチバレーの選手を除けば、シューズ選びはよもやおろそかにはできない。ところが選手というものは、勝ったときは「シューズのおかげ」とは思わないくせに、負けると「シューズのせいだった」とは思うものであるから、シューズはなかなか損な役回りだ。何かに似ているなと思ったら、麻酔科医だった。
昨年走った大井川マラソンで、私は5時間38分という最長不倒記録(スキー用語)を叩き出した。途中で膝が痛くなり、半分くらい歩いたからある。もちろんこれは、シューズが悪かったのだ。ケチって五千円の安いシューズを買うから、膝に来たのだ。
私は来シーズンに備え、いいシューズを買うことにした。どんなのがいいシューズかわからないが、たしかマラソン好きの研修医Yが、シューズには一万円はかけないとダメです、と言っていた。私は、清水寺の舞台から飛び降りるつもりで、今日こそ一万円以上のものを買うと固く決意して家を出た。
運動具店に行くと、早くも決意が鈍り始める。いろいろ種類がありすぎて、自分に合うのがどれか、見当がつかない。「猫に小判」、「豚に真珠」などといったことわざが頭をよぎる。
あまり客に世話を焼かない主義の店らしく、考え込んでいる私に店員さんが全然寄ってこない。そのうち、店員さん同士が立ち話をしはじめた。
「この間のお客さん、何を勧めても、自分ではどうしたいのか最後まで言ってくれなくて…」
「そういう時はな、たとえばカカトのフィットから見て行って、こっちのペースで決めていくもんや」
なかなかシューズに詳しそうだし、熱心さも兼ね備えているようだ。私は会話の途切れたところを見計らい、勇気を振りしぼって、声をかけた。
「こ、これ、履いてみていいですか。」
「どうぞ。」
店員さんはそれだけ言って、あちらに行った。熱意と知識はあるが、とことん客にプレッシャーをかけない主義らしい。だがもしかしたら、こんなヨレヨレのおっさんにいいシューズを売ったら、シューズがかわいそう、と思っているのかもしれない。人を見る目も、商品愛も確かなようだ。
結局私は特売コーナーの6,500円のシューズを自分で選び、レジに持って行ったのであった。一万円のシューズを買うという夢は破れたが、小学校の講堂の舞台から飛び降りるくらいの勇気で間に合った。よかった。
今度のマラソンで、1,500円の価格差がどれくらいタイムを縮めるのか、楽しみである。世界記録を出すためにはいくらのシューズを買えばいいか、割り出せるはずだ。
2019.1.20
|
|
冬の色
|
冬になると、街を歩く人の多くが、濃い色の上着を着ている。黒や紺、焦げ茶色の服が多い。
冬はタダでさえ世の中が薄暗く、暗い雰囲気になりやすいのに、どうしてこうやってみんな、暗い色になってしまうのか。その理由を考えてみた。
夏に白い服を着たくなるのは、太陽光を浴びた時に熱を持ちにくいからであろう。これは明らかに体感できることである。冬はその逆で、暗い色のほうが太陽光を熱に変えやすいはずだ。人々はそれを求めているのではないか。しかし、濃い色の上着のほうが本当に暖かいかどうかは、少し疑問である。
冬の太陽は光も弱々しいし、そもそもわれわれの通勤時間帯にはどこかで寝ている。せっかくの黒い上着もあまり役に立つとは思えない。それどころか理論的には、濃い色のほうが冷えやすくなる場合もありうる。色の濃い物体は、放射熱を受けやすいのと同じくらい、放射熱を発しやすいのである。
物体はみな、その色と温度に応じて熱を放射している。黒い物体は放射熱を受けやすい分、出す方も多い。そうでなかったら、勝手に熱くなるはずである。ところが、寒い冬の夜を黒い服を来て歩くとなると、話は別だ。人間のほうが周囲より暖かいから、色が濃いほど、大事な体温を赤外線として放射しやすくなり、理論的には損である。
もっともこれは屁理屈というもので、実際には放射熱は問題になるほどではないだろう。上着が黒い方が保温に有利というわけではないと言いたいだけである。
もしこの屁理屈を極めたいという人がいたら、完全黒体からの放射光について考察を進めていくといいだろう。うっかり量子力学への扉を開いてしまうことになるようである。
私の仮説では、人が冬に暗い色、くすんだ色の上着を着るのは、主に心理的な理由である。もうすぐ花と緑のあふれる季節が来る。その期待を盛り上げるために、みんなで無意識的に協力しあい、冬の街をわざと単調な色に染めているのである。
若い人にはわからないたとえであろうが、これは高倉健(たかくら・けん)の任侠映画と同じ心理構造だ。前半、悪いやつらがやらかす無理無体の数々。ここでじっと耐える苦しみがあるから、後半ついにぶちぎれた健さんが、「死んで、貰います」とドスを振り回す喜びがある(喜んでいいのか)。最初から最後まで健さんが暴れる映画では、ちょっとお話にならないのである。冬はこの、健さんが歯を食いしばる時間帯に当たる。
この仮説によるならば、冬の上着にはパステルカラーの花柄はおススメできない。今は我慢の時、という集合的無意識を裏切る者は、社会からあまり歓迎されないだろう。もっとも、自然界にも季節外れの「狂い咲き」を見せる桜の木がある。たまには狂い咲きをする人間がいてもいいと、個人的には思う。
2019.1.20
|
|
未来の予測、その2
|
私は明治維新の話が好きなので、漫然とその辺りの歴史本、小説を読んでは忘れる、ということを長年、繰り返している。とくに私が興味を持っているのは、明治維新という空前の激変にあって、その中にいる普通の人たちはそれをどう予見し、乗り越え、または沈没していったのか、というところだ。
野口武彦(のぐち・たけひこ)という人の「幕末気分」という本に、第二次長州征討を控えた大坂の様子が描かれている。長州を討つべしとの勅許を得た幕府が、諸国から兵を集めて大坂につめこんだのだが、なかなか進発の命令が出ない。ただ飯を食って時間をつぶすだけの兵たちが起こす、乱痴気騒ぎの数々。そこには、これから起こる歴史の激動に対する緊張感はまったくなかった。つまり、彼らのうちの誰一人として、これから幕府が倒れるだろうと予見したものはいなかったのである。
第二次長州征討は失敗に終わり、幕府瓦解のきっかけになった。
一方、商人のほうはしたたかである。戊辰戦争(幕府と朝廷の戦争)が始まって間もなく、三井、島田、小野らの豪商は朝廷側の勝ちを見切ったのである。これは、全国に張り巡らせた情報網から得た判断らしい。早期から献金したことで、彼らは政商として新政府に密着し、莫大な利益を得ることになる。(中公文庫、日本の歴史20「明治維新」)
2015年のNHK朝ドラ、「あさが来た」のヒロインは、三井家の娘がモデルである。ドラマでは三井家が、たまたま時運に乗って新政府に重用されたかのように描かれていたが、実際には冷静に時代の流れを読んで賭けに勝った、歴史の勝者なのである。
だがこれは、後から見ればそうだった、という話であって、こういうのをいくら集めても、今後のことを予見する能力は身につかない。大坂駐留の兵のように、歴史の荒波に呑まれるのではなく、三井のように勝馬に乗りたいのはやまやまだが、それが簡単ではない。
どうも今、世界は歴史の転換点にあるような気がする。これほど多くの国で人気取りの政治家が独裁者となって、国を牛耳るようなことは、今までなかったのではないか。アメリカまでが、下品な男に振り回され始めた。民主主義が制度疲労を起こし始めているように、私には思える。
世界はどうなるのか、それより日本はどうなるのか、それより私はどうなるのか。いくら歴史の本をひっくり返してみても、答えは書いていない。
不安は募る一方であるが、気休めのために、明治維新の話に戻りたい。
江戸時代末期、欧米による植民地化の波がアジアに押し寄せてきていた。日本も、あの体制のままでは、中国のアヘン戦争みたいなことをやられていただろう。その危機を乗り越えるために革命を起こし、近代化を果たした。これをほぼ自力で行ったのは、アジアで日本だけである。こういうことを書くと、日本万歳のネトウヨみたいであるが、本当だから仕方がない。
指導者も、問題はいろいろあったが偉かった。戊辰戦争に当たって、幕府にはフランスがつき、朝廷側にはイギリスがついたが、幕府も朝廷も、外国の軍隊を借りることをしなかった。兵力提供の申し出はあったが、「外国の人に頼む面皮はもちあわせていない」(西郷隆盛、さいごう・たかもり)ときっぱり拒絶したのである。その後の独立を守るために、絶対必要なことであった。
庶民も偉かった。当時、農民の間でも教育熱が高く、国民全体で識字率が高かったことが、「草莽の志士」を生み、それが革命成功の下地になったのである。また、新政府、産業側からの性急な人材登用に国民が呼応できたのも、庶民の教育レベルが高かったからであった。
この辺のところは、中公文庫、日本の歴史20,21に負っているが、著者の井上清(いのうえ・きよし)も色川大吉(いろかわ・だいきち)も筋金入りの左翼であるから、たぶん馬鹿げた日本自慢ではないだろう。
というわけで、いざとなったら日本は底力を出す、ということにしておこう。太平洋戦争?それはまた、別の話、ということで…
2019.1.12
|
|
未来の予測
|
年の変わり目などには、未来の予測が新聞、雑誌などでよく取り上げられる。何も考えずにボーッと生きているよりも、未来の自分たちや世界がどうなるかを気にした方がいいに決まっているが、それらの未来予想がそう簡単に当たるとは思えない。
ただ、もしたまたま予想が当たれば、少なくとも予言者にはなれる。メディアにしばしば出てくる、「ソ連の崩壊を予言した」、「バブル崩壊、リーマンショックも言い当てた」人たちの仲間入りである。私もちょっとやってみたいが、予言や予想と称するのもおこがましいので、予感くらいにしておく。
最近では、人工知能が人間の能力を超えた時、何が起こるかについての議論が盛んである。中には、人工知能や、それを利用できる特権階級的人間が、残りの人間を支配する、みたいな悲観的な予想図を描く人もいるが、気の滅入る話である。ただ、こうした科学技術の分野では、たった一つの発明や事件で、根本的に予後が変わる可能性がある。
たとえば、悪い人工知能「だけ」を根絶させる能力を持つAIターミネーターが偶然発明されるとか。それは多分、シュワルツェネッガーのようなかっこいい形態ではなく、苔や粘菌に似たものだろうと私は予感する。
あるいは、地球を放し飼いにしてゾウリムシの進化を観察して楽しんできた宇宙人が、ある日予想外に繁殖した人類に驚き、その進化の頂点に君臨する人工知能と、その恩恵を独り占めにする独裁者どもを、「こいつかーっ」と言いながら刈り取ってくれるとか。
そんなに都合のよい事件が起こるものか、という人もいるだろうが、過去に例はある。
昔、産業革命で人口が爆発的に増え始めたころ、まもなく世界的な食糧不足が生じるという悲劇的な予想がなされていた。しかし、空中の窒素を利用する化学肥料の発明で農業革命が起こり、幸いにも悲劇は回避された。その発明がなかったら、人類はどうなっていたかわからない。
このように現状をひっくり返す技術革新や事件(宇宙人の降臨とか)は、必ず偶発的なできごとであるから、未来を正確に予想するなどは、そもそも無理なのである。
地球温暖化も、人工知能に劣らぬ人類の脅威だ。温暖化はデマだと言っている人もいるが、昨年の逆走台風、異常な豪雨による災害を経験してしまうと、どうもこのままではまずいのではないかという実感が湧いてくる。これら異常気象が、本当に温暖化のせいかどうかは知らないが、なんとかして助かりたい気持ちはどうしても高まってくる。
問題解決は簡単で、太陽エネルギーを吸収し、そのエネルギーで温暖化ガスである二酸化炭素を分解する装置を作ればよい。そんな一石二鳥の都合のよい装置があるか、と怒られそうだが、その辺に生えている植物がみなそれである。ただし、緑を大切に、というくらいではもう、間に合わない。あっという間に種から大木になるような植物が必要である。そんな便利な植物があるのかというと、昔の文献をひもとけば、ちゃんと記載されているのである。
「ジャックと豆の木」、「源五郎の天昇り」などの文献によると、ある種の豆は土に埋めると、一晩で雲に届くような成長を遂げるようである。驚くべき二酸化炭素固定力である。これを毎日伐採しどこかに貯蔵すれば、大気中の二酸化炭素を隔離したことになる。思えば、妖怪大戦争(2005年)という映画で、地球制服をたくらむ魔人、加藤保憲(かとう・やすのり)の野望を打ち砕いたのも、ひと粒の小豆(あずき)であった。どうやら、人類を救うのは豆ではないかというのが、私の予感である。
あとは、優秀な若者たちが私の予感を実現するだけだ。餅でも食べながら、予言者と呼ばれる日を待つことにしよう。
2019.1.3
|
|
夫婦物語
|
年の瀬なので、夫婦について考えてみたい。といっても、自分のうちのことを書くほど、私は向こう見ずではない。 仕事で関わったよその夫婦のことである。
手術室に来られる患者さんには、入れ歯をはずしていただく必要がある。意識がない間にはずれて、のどに落ちたら困るからである。ある上品な高齢女性に、術前診察でそれを説明すると、病棟でははずしたくない。手術室に来てからはずし、術後は病棟に帰る前にはめたい、とおっしゃる。どうしてかと聞けば、入れ歯をつけていることを、夫に知られたくないのだと。
私は非常に驚いた。これが話に聞いたことがある、ヤマトナデシコとかいうものか。 決して人前でおならをしないというだけでなく、入れ歯を夫に悟られぬまま生き抜こうとしているとは。それにしてもその夫さんは、本当に妻の入れ歯に気がついていないのだろうか。もしかして、知らないふりをしているのだろうか。妻も、夫が気がついていることを知らないふりをしているのか。この無限ループ、深い、深すぎる。ゴーン、と一つ、除夜の鐘が鳴る。
女性の患者さんが、手術室で鳴らす音楽はこれにしてほしいと、カセットテープを持ってきたことがあった。夫がカラオケで歌っているのを、録音したものだそうだ。とっくに聞き飽きたであろう夫の声を、それでも聴きたいというくらいだから、そんなに歌がうまいのかと思いながらテープを回してみると、これはまったくの素人のカラオケである。延々とつづく歌を聞いていると、酒も飲んでないのにくらくらしてきたが、勝手に止めるわけにもいかない。患者さんは「これを聞いてると、落ち着くんです」とおっしゃるのだ。その夫婦愛が、私の理解を超えていた。ゴーン、とまた一つ。
患者さんに麻酔について説明した後、同意書に署名をいただく。同席しているご夫人らしき人にも署名と続柄を記入していただくが、これが少し怖い。わざわざ「内縁の妻」と書いてくださることがある。「内縁」という言葉がどうも微妙である。「知人」でも何でもいいのだが、まじめにありのままを書いてくださるのである。中には、どうみてもその患者さん、介護なしには生きて行けそうになかったりする。法的な保護をほとんど受けない関係でありながら、「内縁の妻」が逃げずに介護しているのである。ゴーン。
同意書の続柄欄に「元妻」と書く人もいる。聞けば、離婚したけど、まだ一緒に住んでいるという。これも何なのだろう。なんだか、エロティックな感じがしないでもない。
きちんと離婚し、別居しているはずの「元妻」が、元夫の命に関わる緊急手術に付き添ってくれていることもある。元妻はあきらめたように、「この人、私がやってあげないと、仕方ないんです。」とおっしゃる。その表情は、ほほえみか、苦笑いか。これはもう、聖人である。ゴーン、ゴーン、ゴーン。三つ鳴った。
ここまで、男は何をしているのだ、という疑問も生じてきそうだが、立派な夫もたくさん見てきた。患者である80代女性が何だか、女王さまみたいな人なのだが、その夫は腹をくくってシモベになりきっている。 どうも、妻のオムツも夫が替えているらしい。あいにく、夫の方が認知症になり遅れたのだ。ゴーン。
夫婦の愛憎そのものが手術の原因になることもある。とくに、愛ゆえにそのような事態になったケースに対しては、こちらも言葉を失うことが多い。ある男性の緊急手術で、そうなった経緯を聞いて感動した私は、女性ナースに教えたのだが、「バッカじゃないの、私だったらそんなこと、してほしくなーい」と一蹴されたことがある。これ以上はもう、「男と女の事件簿」になってしまうから、ここでは書けないのが残念であるが、その余韻だけで除夜の鐘の残り101つは、余裕で鳴らせる。
ゴーン、ゴーン…
2018.12.24
|
|
酒豪
|
麻酔の説明をしていると、患者さんによく訊かれるのが、酒に関することである。自分は酒に強いのだが麻酔はちゃんとかかるだろうか、あるいはその逆で、酒に弱いので麻酔が効きすぎるのではないか、というのである。
酒に強いというのは、一般にはアルコールの代謝が速い体質を指すことが多い。アルコールは肝臓で代謝されてアセトアルデヒドになるが、ここからが問題で、このアセトアルデヒドをさらに分解する酵素の能力に個人差があるのである。この分解が速いと、いくら飲んでも酔ったり、気分を悪くしたりしにくい人になる。
そういうわけで、この代謝能力はアルコールのみにかかわることで、全身麻酔薬とはまったく関係がないから、酒に強いからと言って麻酔にも強いということには、全然ならない。
ただアルコールには麻酔作用があって、そのために暴れたり(浅い麻酔相は興奮となって表れる)、気を失ったりするのであるが、そういうことにちっともならない人がいるとすれば、アルコールの麻酔作用に対して脳に抵抗力があるということかもしれない。そういう人が、全身麻酔薬にも抵抗力があるという可能性も、排除はできない。
しかし実際のところ、酒に強いと豪語する患者さんが、麻酔薬を多量に必要とした、という経験は私にはないので、基本的には酒と麻酔とは別物だ、と考えているし、患者さんにもそう説明する。
それにしても、「酒に強い」ということがしばしば自慢や賛美や羨望の対象になるのはどうしたことだろう。
よく、飲み比べで相手が先にひっくり返ると、勝った、お強いですね、とか言う。そういう人には酒豪、うわばみ、ざるなどの尊称が奉られる。しかしそれは精進して鍛えたものではなく、 単に親から受け継いだ代謝酵素の活性の問題であり、その人の値打ちとは全く別のものである。
私のような下戸から見ると、酒に強い人はむしろ損をしやすいと思われる。
間違いなく言えるのは、そういう人はたくさん飲んでしまうから、飲み代がかかる。私のように缶ビール1本で眠ってしまう人間は、何と安上がりなのだろうと思うが、どういうわけか、誰もほめてくれない。
また、たくさん飲めば飲むほど、アルコール依存症、肝硬変、膵炎にもなりやすいのは自明である。(ならない人もいるからややこしいが。)私は嘔吐、頭痛が怖いから、缶ビールを2本は飲まない。これでは健康被害も出るはずがない。だが誰もほめてくれない。
いわゆる酒豪に向かって、「酒の代謝が速いんですね、 お気の毒に」といえる時代が、そのうち来るかもしれない。
2018.11.4
|
|
個人差、その2
|
ポン菓子の米や、ポップコーンのとうもろこしは、強い圧力から急激に開放されると、ポンとはじける。たぶん、人間も同じようなものではないだろうか。年を取って仕事から引退し、社会から受ける圧力から開放されると、人はふたたび自由に自己表現するようになると思う。
60,70を越えたりすると、手術室にくる患者さんの個人差はふたたび激しくなってくる。どうにでもしてくれ、という諦観の人、逆に神経質になり、いろいろと要求する人、ナースのお尻をさわる人、認知症が入って暴れる人、まあ十人十色である。
自分がさらに年を取って、患者として手術室に来たら、どのタイプになるか、自分では予想がつかないけれども、こうありたいという願望はある。面白いおじいさんである。たとえば、私は今まで、こんな人たちに出会った。
術前診察でおじいさんに、どこかお悪いところはありますか、と聞くと、「頭が少し、悪い」という。じゃあ、お薬なんかはとくにのまれてないんですね、と聞くと、いきなり遠い目になり、「貧乏だけが私の薬です」と言われた。
また別のおじいさん、心臓の病気とかありませんか、と聞くと、「きれいな女の人を見るとどきどきする」と答えた。ちょっと急ぐ緊急手術だったので、この問答は手術台の上で行われたのである。この人に麻酔をかけるとき、さあもう眠くなりますよ、というと、「まんまんちゃん、あん」と言った。関西の子供が、仏さまを拝むときに唱える文句である。
さらに別のおじいさん、手術室入室時にナースが本人に手術部位を確認した。「手術の場所はどこですか。」こちらとしては、「右の腎臓」などと答えてほしいのであるが、この人、「〇〇病院」と答えたので、ナースがイラッとした。「それは病院でしょ。手術の場所ですよ。教えてください。」すると、「あ、手術室。」これなどは、天然なのか、狙っているのかがわからない。
こういうのは、小児やサラリーマンにはちょっと出せない味である。
自分もこんなふうに、頭がボケてきているのか、漫才で言う「ボケ」役なのか、誰にもわからないようなギリギリの線を出してみたいけれども、自信はない。はじける前のコーンは多分、自分がポップした後でどんな形に膨らむか、知らないだろうと思うのだ。
2018.10.27
|
|
個人差
|
手術という人生の一大事に遭遇してどう振る舞うか、人によって違うのは当然である。ただその振れ幅は、年齢によって違う。
小児が手術室に入った時、おとなしく従ってくれるか抵抗するか、二つに一つだが、前日の術前診察で少し見ただけではまず予想できない。
3歳から5歳の子どもは、一人で手術室に入ることを怖がることが多いので、お母さんかお父さんに同伴入室してもらうことが多い。ところが、何の恐れもなく一人でベッド(本当は手術台)に乗り、点滴まで取らせてくれる、けなげな子がいる。その上、興味深げに手術室を見回し、「あの音、何?」と心電図モニターを指さしたりする。「これはね、〇〇くんの心臓の音だよ」とか何とか答えながら、スタッフ一同胸キュンの感動に包まれる。
一方では、10歳でも手術室に入る時泣き出す子、注射は痛いからイヤ、と言う子もいる。そういう時は、私は無理せず吸入麻酔で眠ってもらうようにしている。10歳なら注射を我慢できるはず、乗り越えられるはず、というのは、大人の勝手な基準の押しつけである。
協力してくれる子には、「お利口さん。あとでごほうびをいっぱいもらってね」といいたくなるが、我慢できない子が悪いということではない。知らない大人たちが覆面をして自分を取り囲み、わが身に何か危害を加えようとするのである。身を守ろうとする権利は誰にでもある。抵抗する子にかける言葉は、「よく戦った。あっぱれ」というところだろうか。
とにかく子どもは個人差が激しい。危機的状況に臨む態度が、この年齢にしてこれだけ違うのはなぜか。持って生まれたものが違うのか、すでに人生経験が違ってきているのか、私はかねてから不思議に思っている。
これが大人になると、個人差がほとんどなくなる。たいていの人はこちらの話をよく聞いてくれるし、治療に協力してくれる。こういう人が手術室に入ると、お互い、「よろしくお願いします」から始まったりする。
不安でないはずがない。しかし、こちらのペースに合わせて、自分を抑えてくれているのであろう。 とくに男性サラリーマンにはその傾向が著しい。 態度は落ち着いていても、こういう人に心電図をつけると、大層な速さで脈が打っていることがある。やはり多少、無理をしているのだろう。
ルールを守り、 人に迷惑をかけない、まともな社会人。サラリーマンはこの人型にはめられた状態で生きており、病院でもそれを実践してしまうのだと、私は考えている。自分もその仲間であることは疑いないから、その悲しいこらえ性に共感を覚える。
さらにこれが老人になるとどうなるか。次回につづく。
2018.10.20
|
|
剃毛
|
ほんの十数年ほど前まで、手術には「剃毛(ていもう)」が必須であった。感染症を防ぐため、手術でメスが入る部位に生えている毛という毛は、手術前日に剃られなければならなかった。
脳外科の手術を受ける人は、院内の散髪屋さんに連れて行かれ、性別を問わず丸刈りにされた。多くの人の恐怖の的になったのが、虫垂炎の術前の陰部の剃毛であろう。パンツを脱いで 看護師さんに身をまかせ、ツルツルに手を剃られるわけだから、若い男性にとっては苦悩の根源であった。
時代が変わると、真実も変わる。術前の剃毛は、かえって感染症を増やす、と言われるようになった。カミソリで毛を剃ると、かならず皮膚が傷む。一晩もあれば、その小さな切り傷に菌が棲みつく。それが術後、手術の傷にうつるのである。
現在は、少なくとも手術前日に毛を剃ることはない。毛深い人に対して、麻酔導入後に、シェーバーで毛を刈ることがあるくらいである。
この時代ギャップが、事件の原因になりうる。
剃毛が非常識になったあとのこと、ある男性が虫垂炎と診断され、即日手術を受けることになった。よくあることだが、この患者さん、入院の準備のために一度帰宅したいという。無理もないことなので帰宅してもらい、帰院後、手術出しとなった。全身麻酔をかけて、腹部を露出して一同絶句。自宅で一人になった隙をついて、ご自分で毛を剃って来られたのであった。よほど慌てていたのか、その皮膚は切り傷だらけだった。
この人は、まさか医学の絶対的真理が、こんなに簡単にころころ変わるとは、思わなかったのだろう。
2018.10.15
|
|
骨折
|
医療ドラマといえば、主役を取るのは外科医(どういうわけか、脳も心臓も全部できちゃう)、救急専門医、産婦人科医、あとは定番の内科医くらいか。麻酔科医は脇役として、たまに出てくる。一方、現実社会ではメジャー感があるのに、ドラマにめったに出てこないのが、整形外科医である。
一般人から見たら、「折れた骨をくっつけてくれる人」くらいの印象しかないのかもしれない。本当は、整形外科医は骨折の治療をそれほど喜んではいない(脊椎や、人工関節のほうがお好きのようである)という事情は置いといて、その骨折の治療がいかにありがたいものか、見ていてつくづく思う。
骨と言ってもいろいろある。その折れ方にもいろいろあって、頻度の多い折れ方には「コレス骨折」とか何とか、固有名詞が付いているほどだ。そういう中で、頚椎は別格として、見ているだけで冷や汗が出るのが大腿骨、上腕骨の骨幹部骨折である。つまり、太ももや二の腕のところの骨が真ん中でぽっきりと折れた状況である。
こういう骨折だと、患者さんが病院に来た頃にはたいがい骨の断端部がずれており、さらに痛みに反応した筋肉群がかちかちに収縮するため、骨と骨がすれ違い状態になっている。これを放置していたら、2つの骨断面は永遠に泣き別れである。そういう人が治療を受けないと、いったいどういうことになるのか、わからないが、一生立てないとか、物を持てないとか、そういう重度の不自由、あるいは苦しんだ末の死亡という事態が待っているだろう。
昔は「骨接ぎ」という職業があったわけで、想像するところ、とりあえず無理やりひっぱって、骨断端同士を合わせたのであろう。一体どれだけの割合で骨を「接ぐ」ことができたのかはわからないが、断言できるのは、治療には極限の痛みと死亡リスクを伴ったであろう、ということだ。
その点、現代に生まれた人はラッキーである。骨折により命を落とすとか、一生不自由を抱えるとか、治療中に悶絶死する、といった事態を、ほぼ想定しなくてもいいのであるから。このブログのようなもので私が書いてきたとおり、近代外科の最大の恩恵は、ありふれた良性疾患による死亡を回避できるようになったことであるが、骨折の手術もまた、虫垂切除術、胆嚢摘出術と同じくらい救命的な手術なのである。
だが、現在の骨折の治療は、死なない、というだけではだめなようだ。手術を見ていると、整形外科医は、骨に入れるネジの深さ一つとっても、1mm の違いを気にしながら慎重に進めている。術後の運動機能のことを考えると、ちょっとした角度や位置のずれが問題になるのだろう。もうちょっと適当にやっても、患者さんにはわからないんじゃないだろうか、などと、横から見ているとつい考えてしまうが、やってる先生方はみな、職人かたぎまる出しで、あーでもないこーでもないと、こだわりぬいている。
この日陰者感、麻酔科医に通じるものがある。ああ整形外科医のこの努力が、世の中に理解されますように、そしていつか、医療ドラマで主役が回ってきますように、と祈らずにはいられない。
2018.10.8
|
|
確率の世界、その3
|
若い人としゃべっていると、これはかなわん、と思い知らされることがある。
たとえば、若い麻酔科医としゃべっていて、別の麻酔科医のうわさ話になり、「あの先生、今頃どうしているんだろう」と私が言うと、彼はしゃべりながら目の前のスマホやパソコンでその人の名前を検索する。そして、あー今ここにお勤めですね、と即答するのである。確かに、医師の名前というのはたいがい、所属の病院とか、開業中の医院のホームページに載っているものであるが、ああやって、会話をしながらインターネットで検索するというのが、私の世代の者にはなかなか思いつかない。
私は大人になってからインターネットの誕生と成長を目の当たりにし、えらいものができたもんだ、という思いを持っているが、若い人たちは物心ついた時にはそれがあるわけで、そういう人をデジタルネイティブというらしい。勝手に漢字化すると、「生得的電脳感覚」かな。
私などは、5代まえの朝ドラ女優の名前とか、国民栄誉賞の2人目は誰だったか、みたいな、気にはなるけどどうでもいいようなことは、わからないままに済ます癖がついている。昔は、調べるにしても不相応な努力を必要としたから、それが合理的な態度だった。だがデジタルネイティブの人たちは、わからなければネットで調べればすむことじゃん、なのである。
会話中にスマホをいじるのは相手に失礼、という感覚も、もとからない。
今どきの若いものは、とぼやくのは自由だが、狩猟採集民が、農業を始めた人を「軟弱な」とけなすようなもので、あまり意味がないだろうと思う。
インターネットでものを調べるというと、言葉の意味や、人やモノに関する情報などが中心になるだろうが、今後はそれも変容していくのではなかろうか。アマゾン、グーグルなどのIT大手は、そういう後ろ向きの情報だけでなく、前向きの情報、つまり近い未来にこういうことが起こりやすい、といった確率情報をため込んでいるはずである。これが一般人にも調べられるようになったら、世の中はさらに変貌するのではないか。
その頃にはコンピュータは、人間の思考に直接割り込んでくる。
とうとうプロポーズして来よったな。絶対死ぬまで幸せにして見せます、やて。ぐふ。
ああそれね、プロポーズの時に「絶対」、「死ぬまで」、「幸せ」が揃うと、結婚しても浮気の確率32%ですね。でもよかったですやん。これに「生まれ変わっても」がつくと、浮気率56%になるところでした。
うるさーい!
ただ、このような確率情報こそがIT企業のメシの種であろうから、すなおに一般公開してくれるとは考えにくい。気をつけないと、都合のいい数字だけ見せられて、われわれ利用者側がいいように利用されて終わりであろう。(グーグルが公開した、アルファ碁に関する情報が、いかに偏ったものだったか、王銘琬(おう・めいえん)氏の著作に詳しい。)
そのうち、人工知能や人間が、正しい確率情報の所有権をめぐって争う、情報戦争の時代が来るかもしれない。いったん、IT支配層から叩きだされた野良人工知能群が、情報の民主化を求める人間たちと手を組み、地下組織を立ち上げるのだ。いや、地下組織だから、堀り下げるのか。そこになぞの美少年が現れたり、行方不明の天才技術者が発見されたり、裏切ったり裏切られたり、いろいろあって、最後は何だか知らないが大どんでん返しになる。
私の経験によると、私のこうした予測が的中する確率は、0.023%である。お、宝くじが当たるよりも高い。
2018.9.30
|
|
確率の世界、その2
|
中学や高校の数学の授業で、確率の単元に入った時、面白いと思った人がいたとすれば、かなり奇特な人ではあるまいか。普通の学生は順列、組み合わせでつまづき、「場合の数」とやらを全部数えるところでがっくりと膝を折り、定期試験の前には床の上に倒れてピクピクしていたはずだ。もちろん私も、その一人である。
ところが近年、確率の概念が変わってきているらしい。主観的確率と言って、「ある命題が、本当だと信じられるのはどの程度か」という尺度が数字になり、計算の対象になり、人工知能に取り入れられ、マーケティングなどで利用されて世の中を動かすまでになっているのである。これは、「1を場合の数で割る」ようなことで出てくる数字ではない。
たとえば天気予報で「降水確率30%」などと表示されるが、これは予報担当者が明日は雨だと思うその確信度が30%くらい、という意味であろうから、主観的確率の一種だと思われる。私は58%ほど、そう確信している。
学校で習った確率であれば、全く同じ気象状態が100回あるとして、30回雨が降るという観察をもって、30%としているはずである。だが、全く同じ気象状態など起こるわけがないから、古典的確率の概念では降水確率は理解できない。
病院の話になるが、手術を受ける患者さんの全身状態が悪く、死亡リスクが否定できない場合がある。もちろん、手術をしないともっと危ないと信じるから、手術を勧めるのである。外科医の中には、患者さん側への説明のときにあえて数字を出す人がいる。
「手術した結果、命にかかわる可能性も、10%くらいあります。」
これも、主観的確率と言っていいだろう。
10%と聞いて、怒る患者さんもいるかもしれない。
「なに、10人に1人が死ぬだと?どうやって調べたんだ。ワシにとっては、死ぬか生きるか、どっちかしかないだろう。そんな数字に意味はないじゃないか。」
だがこれも、降水確率と同じで、たくさん試行して成功率を計算したものではない。この10%は、外科医のリスク感覚の表出だと受け取ってもらったほうがいいのだろう。「絶対大丈夫です」とか、「万一ということはあるかも」などという言い方よりは、はるかに誠実だと思う。
個々の症例の死亡確率は、計算できないが、あとから検証することはできる。外科医の出すこうした死亡率は、実際の手術成績よりも高いという調査結果がある。ついリスクの上乗せをしてしまうのは、それはまあそのほうが医者側に都合がいいのだろう。
麻酔科医は、あまりそういうことを言わない。通常、外科医の説明のほうが先だから、患者さんも覚悟を決めてしまっていることが多い。そこに改めてリスクの説明をすると、話をややこしくする可能性がある。ただ、外科医の説明があまりに楽観的だと感じた場合は、「5%くらいのリスクがあります」などと説明することはある。
自分がそう信じればそれが確率だ、というのがまかり通るのであれば、学生も喜ぶだろう。だが、そんなにかんたんな話ではないのはもちろんである。私はこの種の確率を扱う「ベイズ理論」をちょっとかじってみたが、たちまち消化不良を起こした。「確率分布にも平均と分散がある。正規分布の場合…」などと言われては、やはり床に倒れ込むしかない。
それでも私はしつこいタイプだ。難しいところはすっとばし、迷惑メールを仕分けする「ベイズフィルター」という手法を盗用し、術前診察の所見から死亡確率を計算するソフトを試作したのであった。それを使って、術前にたくさん病気を持つ人の死亡確率を計算したところ、「4.392...」とかいう数字が出た。この人は手術すると、4回以上、お亡くなりになるという結果である。ちなみに、実際にはこの患者さんは、問題なく退院した人だった。
いくら考えても、どこがおかしいかわからない。
主観の時代になっても、確率の遣い手になるのは、依然、むずかしそうである。
2018.9.23
|
|
確率の世界
|
王銘琬(おう・めいえん)という囲碁棋士が、「棋士とAI - アルファ碁から始まった未来(岩波新書)」という本を書いている。王氏は一線級のプロ棋士でありながら、囲碁対戦ソフトの開発に携わったこともあるそうで、機械側、人間側双方の事情に詳しく、非常に読み応えのある本であった。
王氏の解説する、人工知能の囲碁と人間の囲碁の違いが面白い。人間は次の一手を打つ時、ストーリーを大事にするが、人工知能は、確率だけを求めて打つ、というのである。
人間は碁を打つ時、「思い切って攻めていく」、「ここは我慢」、「このままでは負けるから、一か八かの勝負手だ」といったストーリーを作り、その流れで打ち進めるものだ。ところが機械はそうではない。得意の計算力にものを言わせ、さまざまな手をシミュレーションし、勝つ確率が最も高い手を打つらしい。
ただし、今はもう機械の方が強いからと言って、人間も確率で打つのがいいといういうわけではない。王氏によると、やはり人間は演算力に限界がある以上、ストーリーで打つことから離れることはできないだろうという。しかし局面によっては人間も、「神の一手」、「プロの意地」なんかにこだわらず、確率の高そうな手を打つのもありではないか、というのが王氏の考えである。
なるほど、と思った。これは囲碁だけの話ではなく、医療にも通じるものがある。
医療の世界でも、目の前の人の病気や痛みを癒やしたいとか、ご家族のもとに帰してあげたい、というストーリーは駆動力としては必要だが、それだけでは仕事にならない。自動車で言えばハンドルに当たるものが、どの治療を選ぶかという個々の判断であって、ここには絶対に正しい道というものはなく、確率で選ぶしかないのである。
医療物のドラマを見ていると、「絶対に治してみせる」とか、「私、失敗しないので」とか、「この手術を成功させれば、次期教授の座が」とか、バカみたいなセリフが飛びかっているが、あんなふうに、強く念じれば何でもうまく行くなんてことは、スポ根ドラマまでにしてもらいたい。ハンドルなしでアクセルをいっぱいに踏み込むと、電柱に激突するのが関の山である。
現実の医療は確率の世界であり、100%の成功がありえないという点から言えば、妥協の連続である。
問題は、その確率である。その場その場で、どっちを選ぶとどういう確率になるのか、そんな数字は誰も教えてくれない。それを知るすべがない。今のところ、頼りになるのは各医師の経験といえば聞こえはいいが、最後は勘である。最近では、各種ガイドラインが充実してきて、こういう時はこっちがいい、と教えてくれるようになったが、症例ごとの細かい条件が違ってくると、もう正解がわからない。こういう時、電子カルテのなかで人工知能が目覚めてくれるというのはどうか。
「実は私、当院の敗血症の治療データをコツコツと蓄積してきました。この患者さんに合わせて、条件付き確率を計算できます。パチパチ(そろばんの音)。ガイドライン通りに治療すると、生存確率は77%ですが、早めに気管挿管したほうが2%アップ、血液浄化は効果がないけれども、合併症のリスクから、生存率0.3%ダウン、云々、云々。」
確率だから、予想がズバズバと的中するわけではない。はずれもある。ただ、少しずつ確率の高い方をセコく選んでいくと、10段階ほども経るうちに、人間の経験にもとづく治療とは決定的な差が出るはずだ。囲碁と同じで、人間医師は人工知能に太刀打ちできなくなるかもしれない。
「人情」に関わる部分も、機械だから苦手とは限らない。経済状況、本人のやる気、家族の熱意、そういうものはそれなりに治療の選択に影響するものであるが、おそらく機械もその「それなりの配慮」くらいは学習するものと思われる。
では人間医師は何をしたらいいのだろう。人工知能の判定を黙々と実行するだけでいいのか。いや、人工知能も経験したことのない不可解な事態が発生した時、それが人間の出番だ。
どうしたらいいか、人間にもわかるわけがないが、何でもいいから何かする、あるいは何もしないと決断する、その辺が人間の仕事ということになるだろう。そう思いたい。
2018.9.17
|
|
麻酔科耳
|
手術中、外科医は麻酔科医に何ごとかの依頼をすることがよくある。筋弛緩剤を足してほしい、手術台を傾けてほしい、早めに輸血してほしい、などなどである。心臓外科の手術だと、麻酔科との意思疎通はさらに緊密なものとなる。
しかし、外科医の声というのはなかなか聞こえづらい。ベテランになればなるほど、「ボソッと」しゃべるのである。それで通じると思っているのだから、困ったものである。昔はともかく、今どきの手術室は雑音に満ちているのだ。経験の少ない者には聞き取れない。
残念なことに、それが麻酔科医には聞き取れてしまう。「麻酔科耳」というらしいが、まあ、ただの慣れである。これほど、持っていてうれしくない能力も、なかなかないだろう。
2018.9.2
|
|
猫たちの沈黙
|
20世紀の最も偉大な作曲家(私見)であるベラ・バルトークは、異常に耳が鋭敏だったそうである。ある時、嵐の森の中で鳴く子猫の鳴き声に気づき、家人に拾って来いと命じたが、家人にはそれが聞こえない、いくら耳を澄ませてみてもどうしても聞こえないから拾えないという。バルトークは腹を立て、私があの鳴き声のために眠れなくてもいいのかと、家人を責めたらしい。
映画「羊たちの沈黙」のクラリスは、幼い頃の記憶に残る羊たちの鳴き声のために、大人になっても眠れなかったわけだが、バルトークは嵐の中のか細い子猫の鳴き声のために眠れなかったというのだから、恐ろしい聴力である。ただ家族にとっては、恨めしい超能力だったに違いない。
麻酔科医は音の専門家ではないが、手術室という音の嵐の中で長時間耐えているという点では、誰にも引けをとらない。バルトークとレベルはぜんぜん違うが、同じような話がないでもない。
手術室には、いろんな音が満ちている。心電図モニターから出る心拍同期音、患者さんを暖める温風器のうなり、外科医のおしゃべり(まったく無言で手術する人はまれである)、バックグラウンドミュージック、そしてとりわけ耳ざわりなのが各種機械のアラームだ。
手術室に詰め込まれたほとんどすべての機械が、異常を感じると思い思いのタイミングで音を出す。中でも麻酔科医にとって最も聞き捨てならないのが、麻酔器の発するアラームである。呼吸の異常を告げている可能性があるからだ。逆に、最もどうでもいいのが、血栓形成予防のために足をマッサージするポンプのアラームである。これが、どうでもいいくせに(ほんとはよくないが)、よく鳴る。
この両極のアラームの中間に、いろんな警戒レベルのいろんな音色のアラームがひしめいているのが手術室である。
哀れなことに、麻酔科医、手術室ナースは、これらのアラームを無意識レベルで聞き分けることができる。音が鳴った瞬間に、あ、気腹装置の炭酸ガスがなくなった、とか、ナースが電気メスの対極版を貼り忘れたな、とか、つまらないことがわかってしまう。別に特殊能力でもなんでもない。毎日その音の渦の中にいるのだから、自然とそうなる。
「お、今麻酔器のアラームが鳴ったね。短い警告音だから、重大トラブルじゃなさそうだけど、回路リークっじゃないかな。カフもれとか大丈夫?」
「え、今そんな音鳴ってます?ぼく、耳悪いんで」
「鳴ってるやろー。耳悪いんなら、どうして手術帽を耳にかぶせてるの。はい、よく聞いてみ。ほらまた鳴った。」
「いやー、わかりません」
「えっ!?」
「えっ!?」
この研修医が特にとろいのではない。手術室デビュー1か月の新人ならばこんなものだ。それだけ、手術室に充満する雑音と、意味のある音とを聞き分けるには、慣れが必要なのだろう。我々は必要とあれば、手術室に迷い込んだ子猫の鳴き声を聞き届ける自信がある。
クラリスの心の中の羊たちを沈黙させたレクター博士のように、手術室のすべての物を沈黙させられる麻酔科医がいたら... 患者のバイタルサインを完璧にコントロールして生体モニターのアラームを黙らせ、麻酔器を手なずけ、対極板の貼り忘れを鋭く指摘し、手術室に迷い込んだ子猫をやさしく抱き上げるのだ。これは、映画化決定だな。
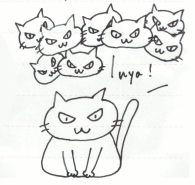
2018.8.25
|
|
外来語の旅
|
旦那という言葉がある。中国から来た外来語には違いないが、はるか昔に渡ってきたものだから、とっくに日本語である。
この旦那というのは、元々は仏教用語で、僧侶にお布施をする人のことである。そこから、金やものをくれる人、一家のあるじ、となったのであろう。
既婚女性に対して、「お宅の旦那さんは」などというと、女性が男性に従属していると認める形になり、日本国憲法第二十四条に違反してしまうので、私は言わない。こっちは気を使っているのに、女性が平気で、ウチの旦那が、と言っているのを聞くと、モヤモヤする。
さて、旦那は中国にとっても外来語である。そのもとは仏教の生まれた場所、インドの言葉なのである。ところが、インド語とヨーロッパ語は、根っこがつながっている(インド=ヨーロッパ語族)。で、旦那と同じ語源をもつ英語があるのである。それがドナー(提供者)である。
こうして、インド=ヨーロッパ祖語が東回りで旦那となり、西回りでドナーとなり、何百年かそれ以上の時間をかけて地球を一周し、極東の地、日本でついに感動の再会を果たしたのである。

「えー、今日の生体肝移植のドナーは、患者の旦那さんです。」
この憲法違反に対しては、お目こぼしをお願いしたい。
出典: 橋本陽介, 日本語の謎を解く, 新潮選書
2018.8.18
|
|
創作漢字固有名詞
|
卓球の市民大会に出ると、いろんなチーム名を目にするが、そのほとんどが英語由来のカタカナか、わけのわからないアルファベットの頭文字である。そういう自分の所属するチームも、後者であるから、大きいことは言えない。ただ、もし自分がチーム名を好きにしていいと言われたら、見る人をうならせるうまい漢字を当ててみたいと思っている。いろいろと候補を思い浮かべてみるのだが、じっさいこれはかなりの難事業である。
常盤会(ときわかい)とか、薫風会(くんぷうかい)とか、病院の医療法人の名前みたいだ。以前私が住んでいた大津市の地区名にちなんで、晴嵐クラブというのを考えたこともあるが、かっこよすぎて自分の弱小チームにはもったいない。今すぐ提出しろと言われたら、「低低(ひくひく)クラブ」しか出てこない。これが私の漢字センスである。絶望のあまり、胃がヒクヒクする。
漢字で架空の人名や地名を創造させたら、SF作家の神林長平(かんばやし・ちょうへい)の右に出る者はいないのではなかろうか。究極の宇宙海賊、匋冥(ようめい、「敵は海賊」シリーズ)、火星の都市、破沙(はさ)空洞市(「あなたの魂に安らぎあれ」)、謎の妖精、銀妖子(ぎんようし、「完璧な涙」)などなど、もうこれしかないというくらいハマっている。この漢字力はもう、天賦の才としか言いようがない。
この人に、自分の卓球チームの名前をつけてもらえるなら、1千万円の値打ちはあるだろうと思う。払えないけど。
私がひそかに静かに熱い思いを抱いている漢字固有名詞が、他にもある。ウルトラマン・ガイア(1998年)の宿命の敵にして正体不明の存在、根源的破滅招来体(こんげんてきはめつしょうらいたい)である。たしかに地球の破滅を狙っている悪い奴らだが、一体、子ども向けの怪獣番組で、いくら憎っくき敵とはいえ、こんなに長くてややこしい、そして意味するところもえげつない名前をつけるものだろうか。とくに「招来」と続く言葉の流れは、とても凡人には思いつかない。発想がすごい。すごい人がいたものだと思う。
ウルトラマン・ガイアの最終回には、敵のラスボス、「根源破滅天使」が登場する。破滅と天使が合体するこの世界観も、もはや根源破滅的である。ラストシーンは涙なしでは見られないが、思い出すだけで目がうるむので、省略する。
前回、ハラスメントに当てるいい漢字がないと書いたが、こんなふうにインパクトがあるものなら満点だ。「部長、それは根源的破滅招来行為です!」さすがの部長(私ではない)も、手を引っ込めるだろう。意味が合っているかどうかなど、もうどうでもいい。
2018.8.14
|
|
創作熟語
|
私の勤務する病院で、手術を受ける外国人は多い。ベトナム人がもっとも多く、中国人、モンゴル人あたりが続く。この人たちが一体どういう成り行きで日本にいるのか、それは知らない。とにかく、彼らは英語は全然無理だし、日本語もかなり怪しい。最近、医療通訳の制度が整ってきたようで、術前の麻酔の説明も通訳に来てもらっている。
通訳の言葉を聞いていて、今さら気づいたのだが、ベトナム語でも、中国語でも麻酔は「マツィー」とか「マジー」などと表現されているようだ。調べてみると、中国でも「麻酔」という字が使われているから、語源は同じであろう。
松木明知(まつき・あきとも)氏の研究によると、麻酔という熟語は江戸時代の日本で生まれたものであるから、それが中国に逆輸出され、ベトナムへと流れていったのだと思われる。私の勘違いでなければ、神経、経済、共和国などもいわゆる和製漢語であり、やはり中国に輸出されているはずである。おそらく、多くの中国人はそれらが、日本製であるとは知らないであろう。
日本がアジアでもっとも早く、西洋文明の優位性に気づき、取り入れようとした結果であろう。ちょっと誇らしい気分になる。
だが、それもこれも、日本人が漢字を知っていた時代の話である。何しろ、明治時代の初期までは、まともな書籍であれば序文は格調高く漢文で書かれていた。漢詩も、戦前までは日本人の文芸の一大分野であった。漢字に関するそれだけ深い素養がなければ、「麻酔」のように本場中国でも通用するようなちゃんとした熟語を創造することは、なかなかできないだろう。「しびれる」という意味に「麻」という字を当てるなど、今の日本人には、とても無理な話である。
現在の日本では、外来語をいちいち漢字化するのはあきらめ、そのままカタカナにして使っている。しかし、コンプライアンス(法令遵守)、ガバナンス(統治)など、漢字で表現できるのにわざわざカタカナを使うのは、鼻につくやり方だ。リテラシーなどというやっかいな外来語もあるが、「素養」くらいで間に合うと思うし、それで間に合うような文脈にすればいいのだ。
だが、どうにもぴったりした漢字の見当たらない外来語もある。
たとえば、ハラスメントである。嫌がらせ、というヤマト言葉はあてはまるが、漢字の訳語はなさそうである。「部長、それは性的嫌がらせです!」では、切迫感が出ないので、漢字二字のうまい熟語を、だれか造ってくれないだろうか。読みも、部長(私のことではない)が思わず肩を揉む手を引っ込めるような、ビシッとしたのがいい。「部長、それは性ビンタンです!」みたいなのである。そうであれば、別に中国人に通用しなくてもいい。
昨年、「忖度」というヌエのような熟語が話題になった。「婚活」、「滑舌」など、近年になって自然発生した熟語もある。漢字にもまだ、活躍の余地はあると思うのだ。
2018.8.5
|
|
口癖
|
先日私は、事務系の女性職員に保険請求のことで聞きたいことがあり、話しかけた。いつも忙しそうだし、体格のよい人だし、つい下から出てしまう。
「あのー、どうでもいい話なんだけどね…」
すると彼女は、間髪入れず切り返してきた。
「先生の話、いつも、どうでもいいもんねー」
これには意表を突かれた。この人はどんな相手とでも対等に渡り合える、なかなかの豪傑であるが、まさかいきなり、こんなことを言ってくるとは思わなかった。
「え、ぼく、そんなにつまらない話ばかりしてましたっけ」
「いや、だって、先生いつも最初に、『どうでもいい話だけど』って言ってくるもん」
自分の口癖というのは、まるで気がつかないものだ。これまでも私は、研修医にこう指摘されたことがある。「その、めんどくさい、というのは、もしかして口癖ですか。」自分がこんな「どうでもいい」ことを口走っている事実を、指摘されて初めて知るのである。恥ずかしい話である。
しかし、恥ずかしいのはお互いさまだ。この際、人の口癖を鑑賞する側に回るほうが得策だろう。この人、自分の口癖を知っているのだろうか、何の深層心理ででこんなこと言うのだろうか、などと考えるのはまた、楽しからずや。
まあ、「どうでもいい話だけど」とか、「めんどくさい」を口癖にしている麻酔科医など、深層心理がどうこう言う以前に、大した人でないことは確かだろうけど。
2018.7.30
|
|
申し送りのドラマ
|
患者さんが手術室に入る時、必ず、病棟ナースから手術室ナースへの「申し送り」が行われる。最終飲食時間、出棟時の血圧などバイタルサインの値、アレルギーの有無、その他、患者さんに関連するもろもろの情報を一気に、書面と口頭の両方で伝達される。そしてその直後、今度は手術室ナースが麻酔科医に、今聞いた情報を申し送らなくてはならない。
この伝言ゲーム、一番大変なのは間に入る手術室ナースだろう。ベテランナースが麻酔科医に申し送るときは、血圧や体温などの数字は省略して、「バイタル変わりなし」などと流してくれるのだが、新人ナースはそうはいかない。何が正常かを判断する余裕がないから、書いてあることをひたすら全部読み上げる。変な情報も、おかしいと思う余裕がないから、全部読み上げる。
ここでさまざまな悲喜劇が生まれるのだ。
ある時、新人ナースが私に対し、「申し送りお願いします」と、型通りの報告を始めた。血圧など、申し送り書に書いてあるデータを読んでいくが、まあ異常ないので聞き流す。次に、「アレルギーはビール、あります。」とさらっと言ったので、エッとなった。指導役の年長ナースの顔を見ると、吹き出しそうになっていたので、空耳ではないようだ。
アルコール消毒は皮膚が赤くなるから使用禁止、これはよくある。金属アレルギー、ラテックスアレルギー、これらも必要な情報だ。しかしビールアレルギーだけは聞いたことがない。アレルギーという言葉は普通、麦とかホップとか、もうちょっと細かい成分に対して使うものだ。
あとで調べてみると、患者さんは「ビールを飲むと、カユくなるんや」と言ったらしい。それを聞いた病棟のナースがやはり新人で、アレルギー欄に「ビール」と記入してしまい、手術室ナースはそれを何の疑問もなく読み上げたのであった。
情報伝達は正確に行われたので、何も問題はなかった。幸い、手術や麻酔でビールが使われることもなかった。だが、おかしくてたまらなかった。
またある時のこと、私は麻酔導入を非常に急いでいた。新人ナースが、「申し送りお願いしまーす」といつものやつを始めそうになったので、私はつい、新人には酷な要求をしてしまった。
「大事なポイントだけでいいわ、教えて」
申し送り書を普通に読み上げるつもりだったそのナース、うっと詰まり、そして次のように答えた。
「では一つだけ、出棟前にトイレに行きましたが、残便感があります。」
彼女が病棟側から聞いた情報の中で、一番気になったポイントがここだったのだろう。残念ながら、麻酔をかけるに当たってはもっとも不要な情報であった。
新人ナースが2年目になり、麻酔科への申し送りの中で「バイタル異常ありません」などと省略するようになると、ああ、ぶじ成長したんだなあと思う。
2018.7.22
|
|
主食
|
私はサツマイモを毎日のように食べているが、意外に飽きないものである。飽きることを恐れる気持ちは、イモを「おかず」と見なすところから始まる。イモは「主食」だと信じれば、飽きないということに何の不思議もない。
主食ともなれば、いつも同じ味じゃないか、とか、いつもの味と違うじゃないか、とか言ってはいられない。それを食べ続けられないと、生命が危うい。したがって、主食であればそれをしみじみと味わう心を捨て、さっさと呑み込んでしまうというのが、自然な態度ではなかろうか。(個人の感想です。)
サツマイモにもいろいろ品種があるし、産地によっても味が多少違うが、私はこだわらない。強いて言えば、おいしすぎないほうがいいように思う。
本物の主食であるコメもまた同じで、農家の方には申しわけないが、私にはコメの味の違いがわからない。新米だからどうとか、コシヒカリがどうとか、何の話かわからない。
だが近年、この主食の地位が脅かされている。糖質制限ダイエット勢力の勃興のせいである。
私はこの「糖質制限」については無知なのだが、肥満気味だった兄が数年来、熱心にこれをやっているので、ちょっと教えてもらった。要するに、炭水化物をなるべく取らないようにすればよいらしい。つまり、肉や野菜などのおかずだけで食事を済ませてしまうということである。
物足りないのでは、と聞くと、慣れてしまえば何でもないという。ご飯も全く食べないところまでやる必要はないし、「おやつなんかも、ちょっとぐらいなら食べてもええんよ。」と、依然として大きなおなかをさすりながら教えてくれた。
おかずだけで生きていける、いやむしろそれが真実の食事法なのだとしたら、「主食」とは何だったのか、ということになる。日本人はやっぱりごはんを食べないと力が出ない、とよく言われるが、われわれは洗脳されていたのか。
瑞穂の国と言われ、150年前まで税や給料がコメで支払われていたこの日本で、こんなことになろうとは。そのうち、コメはおかずになるのだろうか。こっそりご飯を食べていたら、お母さんに見つかり、あんた昨日もご飯食べてたじゃないの、イヤねこの子は、偏食かしら、などと言われる日が来るのだろうか。
コメ族の巻き返しに期待したい。個人的には、イモでもいいけど。
2018.7.15
|
|
サツマイモ
|
サツマイモの時代が来たかもしれない。
焼き芋を売っているスーパーが増えてきたし、NHKの大河ドラマでも、西郷どんがサツマイモを食べている。ちなみに私も、週に3日は昼食にサツマイモである。
私はこれまで、昼食はカップ麺!というのを日課にしてきたが、今年初めに血圧が140mmHg を超えたのを機に、これをやめた。塩分制限で本当に血圧が下がるのか、一種の人体実験である。それ以来、カップ麺は一度も食べていない。
代わりに何を食べるかについては、多少の試行錯誤があったが、とりあえず今、サツマイモにたどり着いたところである。そのヒントは、かつて日本の最長寿県だった沖縄にあった。
沖縄ではあまり米が作られておらず、昔からサツマイモ、マメが主食であったらしい。それが、沖縄のおじいさん、おばあさんが長生きする理由だったと言う。戦後、沖縄の若者の食生活がアメリカの影響を受けた結果、寿命が劇的に下がってしまったのが、その残念な裏付けになる。(もちろん、沖縄の長寿はイモの効果だ、と証明するものではない。)
私は仕事の合間、焼き芋を一本食べる。それだけで昼食として十分だが、タンパク補給に、ゆで卵などをつけることもある。それでも、急げば10分で食べられるから、次の手術出しまで時間がなくても、何とかなる。
塩分はほぼゼロ、食物繊維はたっぷり、腹持ちがよく、夕方までおやつがいらない。気になるのはカロリーだが、菓子パンを2個食べるよりイモ一つのほうが、カロリーはずっと少ない計算である。そして安い。麻酔科医にとって、理想的な昼食ではないかと思う。
栄養のバランスは大丈夫なのか、という懸念もあるが、バランスは朝食と夕食でまかなっていくと割り切り、麻酔中に空腹で動けなくなる事態を避けるための昼食であるということにすれば、麻酔科医はイモでよかろうと思う。
私は現在、かろうじて高血圧の一歩手前で踏みとどまっているが、イモがどれくらい効いているかはわからない。全般的に薄味をこころがけているからかもしれないし、汗をかく季節になったからかもしれないし、単に心臓が弱っているだけかもしれない。
昼になると、私は周囲の人に見せびらかしながらイモを食べ、「もうイモしかありえない」とか何とか力説しているが、誰もうらやましそうな表情は見せてくれない。

お弁当作りを担当している方々、明日からこれでどうでしょう
2018.7.1
|
|
アフリカの人
|
現在、サッカーのワールドカップ、ロシア大会が盛り上がっている。特に、予選で日本と戦ったアフリカのセネガルは印象深かった。私はアフリカに行ったことがないし、セネガルがアフリカのどのあたりにあるかも知らないが、割とクリーンな試合態度(かつてのカメルーンはひどかった)、しびれるほどかっこいいアリウ・シセ監督、楽しそうなサポーターの映像を通じて、セネガルをごく身近に感じたのであった。やはり、サッカーは世界の言葉だと思う。
サッカーでアフリカ勢と対戦する時、日本人はすぐに、「身体能力」という言葉を使って相手戦力をまとめてしまう。ジャンプ力、俊敏性などに優れると言いたいのだろうが、黒人だからそういう能力が高いと考えるのは短絡的過ぎる。また、思考力や組織力より体力で勝負してくる人たちだ、と言うニュアンスも漂ってきて、それも失礼な話である。
これは、自分がアフリカ人を、みな同じ「黒人」というジャンルでくくって見てしまっているのだということを、自白しているようなものだ。一種の偏見である。当たり前だが、アフリカ人はみな同じでもなく、似たようなものでもない。
何の本で読んだか忘れたが、アフリカ人の遺伝子多様性はアフリカ以外の全人類の多様性を合わせたよりも大きいらしい。言うまでもなくアフリカは現生人類発祥の地であるが、白人も黄色人種も、アフリカを旅立った一部のホモ・サピエンスの末裔にすぎないからである。アフリカにとどまった大多数の遺伝子は、驚くべき多様性を保ちつつ、いまだアフリカに温存されているのである。
これは何を意味するかというと、人類の次の進化も、まず間違いなく、アフリカで起きるだろうということである。たとえば、気候変動とか、世界規模の核汚染、プラスチックによる海洋汚染などが人類の生存を脅かした場合、それを乗り越える資質を持った新しい人類が生まれるとしたら、多様性に富む遺伝子のゆりかごであるアフリカ以外からとは考えにくいのである。
思い起こせば、人類の進化はつねに、アフリカで起こってきた。私が生まれる前のことだから、見てきたわけではないが、数百万年前のこと、ホモ・エレクトゥスという人類がアフリカで成功して世界に拡がった。ところが、彼らはそこで行き止まりだった。人類の最新モデルであるホモ・サピエンスは、もう一度アフリカの中から生まれ直し、ホモ・エレクトゥスを駆逐しながら再び世界に拡散したのである。
このことを考えると、アフリカの人を「黒人」とか「身体能力」でまとめている場合ではないことがわかる。彼らはまず、スポーツの分野で頭角を現しつつあるが、そこにはとどまらないだろう。人類の未来はアフリカにかかっている。
私自身、正直言って、アフリカの人がみな同じように見えてしまうが、とにかく、よろしく頼みます、という気持ちである。
2018.6.27
|
|
スズメからの逃走
|
最近では、鳥は恐竜の子孫ということになっているが、とてもそうとは思えないほど用心深い生き物である。落ち着きなくキョロキョロしているクセに、一定の距離以内に人が近づくと、必ず逃げる。私は今まで、何人かの学校の先生が、「先生はな、頭の後ろにも目がついているんだぞ」と告白されるのを聞いたことがあるが、鳥もあれと同じものを持っているのだろう。(公園の鳩を除く。)この禁断の間合いをたぶん、「逃避距離」というのだと思うが、スズメは特にこの逃避距離が長いように思う。測ったわけではないが、2〜3メートルくらいではなかろうか。
ところがこのスズメの逃避距離が、ここ2,3年でぐっと短くなってきたような気がする。スズメが私の鼻先をかすめて、意外なほど近くに降り立ったり、こちらから近づいて行っても、1メートルくらいまでは逃げなかったりすることがある。以前はこんなことはなかった。
スズメの世界に何かが起こったのだろうか。あるいは鬼界カルデラの破局噴火や地磁気の逆転など、何かの天変地異の前兆だろうか。世界の危機を救うため、私は調査に乗り出すことにした。
私は職場の人たちに、スズメの接近現象について聞いて回った。しかし驚いたことに、ほとんどの人が、「へえ、そうですかね」という反応しか示さなかった。唯一同意してくれたのは、私より年長のベテラン麻酔科医だけだった。
はてな。もしかしたら、スズメが近づいてきたのは、あちらに理由があるのではなく、こちらの問題だったのか。つまり、動物のほんらい持つ「殺気」あるいは「生気」のようなものが、加齢により私(と、失礼ながらそのベテラン先生)から失われてきているのか。
確かに私は、「『当院麻酔科のアメとムチ』のアメのほう」などと称されることがあるが、外科医や研修医からなめられているだけかと思ったら、こうしてスズメにまでなめられていたとは、望外の喜びである。
ただ心配なのは、このまま逃避距離がどんどん縮まって、ゼロになった時、何が起こるかということだ。すなわちついに、スズメが私の肩に乗ったとすれば、それはスズメがが私のことを、石や木と大して違わないものだと判断しているということだろう。これは喜んでいていいこととは思えない。
世界の危機かと思ったら、私の危機だった。今後、これ以上スズメが近づいて来るようであれば、私はあわてて逃げなくてはならない。

公園のスズメは、さらに近い
2018.6.24
|
|
よい外科医とは
|
「よい外科医とは何か、定義せよ」と、私は外科系を志望する研修医には問うようにしている。研修医のうちに、外から見たよい外科医のイメージを持ってほしいと思うからだ。一度外科医になってしまうと、その視点は内側に固定されてしまい、われわれ手術を支える側とは違ってきてしまうだろうと思う。
ある研修医は、「やさしい人」と答えたが、ちょっと甘い。やさしくていい人だけど、手術はいまいち、という外科医をたくさん見てきた私としては、同意はできない。もちろん、手術がいまいちで、性格も悪い外科医より、はるかにましではあるが。
またある研修医は、「人に迷惑をかけない外科医」と答えたが、これはまた変わった答えだ。どうしてそう思うのかと聞いたところ、「麻酔科研修中にいろんな外科医見てて、そう思った」とのこと。それを聞いたうえで回答を吟味すると、なるほどと思う。たしかに、手術室看護師や麻酔科医、そしてもちろん患者さんに迷惑をかけないで手術するというのは、いい外科医にしかできないことだ。
私自身は、手術が速いのがいい外科医、と思っている。手術に時間がかかると、患者さんのからだに負担がかかる。看護師や麻酔科医にも負担がかかる。手術の速い人はそれを理解したうえで、高い技術力でそれを実現する。当然、手術成績もよい。よい外科医を一言で表現するなら、これに限る、と思ってきた。
私が満を持して、研修医に自説を開陳しようとしたその時、ある中堅手術室看護師が乱入してきた。彼女によると、よい外科医とは一言で言うと、「人のせいにしない外科医」なのだそうだ。意表を突かれたが、次の瞬間、たしかにそうかも、と思った。
どんな小さな手術でも、順風満帆、まったくトラブルなしで終了するなんてことは、まずない。腹膜が癒着していて手術が進まないとか、器械が不調で術者の好みの電気メスが使えないとか、助手が力持ちすぎて、縫合の糸を結ぶときにブチブチ切ってしまうとか。そういう、うまくことが運ばない時に、イライラして人のせいにするのは、間違いなく大したことのない外科医である。力量のある外科医なら、天災、人災、原因にかかわらず何が起こっても、涼しい顔で冷静に対応する。
「人のせいにしない」とは、外科医のイライラ光線を浴びやすい看護師ならではの切り口だった。
それでは、「よい麻酔科医」とは何か。本人たちはそれなりのイメージを持って仕事しているわけであるが、残念ながらそろそろ字数制限にかかるので、ここでは書 (終了)
2018.6.17
|
|
無慈悲な反論
|
どうも私は、麻酔科部長として威厳がなさすぎるらしい。研修医に熱血指導してみても、しばしば簡単に反論される。しかもそれは、私に言い返すことを許さない、取りつく島もない反論である。たとえば、次のようなものである
よし、気管チューブをこれだけしっかり固定したら、ゴジラが引っぱっても抜けへんな。
いや、ゴジラが引っぱったら抜けると思います。
だよね。
救急外来で気管挿管したら胸部レントゲン写真撮るの、常識でしょ。日本国憲法にも書いてあるよね。
いえ、憲法にはそんなこと、書いてありません。
あれ、隅っこの目立たないところに書いてなかったっけ。
いいえ、隅っこの目立たないところにも、書いてありません。
そうかいな。
耳鼻科の鼻内視鏡の手術、自分でもやってみたいと思わへんか。鼻の中の粘膜をこりこりはがしていくの、おもしろそうやん。
そうですか?ぼくはそうは思いません。
あっ、そ。
麻酔器の構造はかくかくしかじかで、(10分くらい説明)。
あー、でも、車の構造を知らなくても運転はできますし。
もうええわ。
家に帰っても、同じようなものだ。
もうちょっと言い方というもんはないんか。そんなことばっかり言ってると、浮気するかもよ。ええんやな。
どうぞどうぞ、いいのよ、浮気しても。あんたなんかを相手にしてくれる人がいれば、の話だけどね。ハッ!
ぎゃふん。
偶然かもしれないが私は、父親としても威厳がない。息子が小学生のころ、私の指導に対して言い返してきた。
なあなあ、このままじゃ、わしの嫁はんが風邪ひいてしまうわ。そこの毛布掛けたってくれへんか。
またまた~。(にやにやしながら)父ちゃんはもう、母ちゃんのこと、好きでも何でもないくせに~。
うっ!
小学生にまで反論され、言葉も出なかった。それにしても、こいつは一体、誰に似たものか。
2018.6.10
|
|
明治・大正、麻酔の旅、その4
|
「昔の手術」と聞いて私がまず連想するのは、昭和前半の脊椎麻酔である。戦前から戦後しばらくにかけて、薬剤、物資が圧倒的に不足していたため、虫垂炎はもちろん、胃切除でも何でも、脊椎麻酔でやっていたと聞く。局所麻酔薬1本でできるからだ。胃切除となると、脊椎麻酔ではカバーしきれないから、痛かったはずだ。痛くても、無理やり続けるのである。そのようなことを、昔手術を受けたという古い患者さんから何度も聞かされた。
現在ならこういうとき、全身麻酔に切り替えたり、せめて点滴から鎮痛剤を投与したりするが、昔は何せ、モノがない。麻酔科の先輩によると、こういうときに追加するのは「拳骨麻酔」なるものだったという。患者さんが悲鳴を上げると頭をごつんとやって、これぐらいで痛いと言うな、と怒鳴るのだとか。手術の痛みを別の痛みで制御する、といえば聞こえはいいが、患者さんにとってはただの「泣き面に蜂」ではなかったろうか。
もっとさかのぼって明治の手術となると、さすがに実体験を聞かせてもらったことはないが、話を読んだりはする。とくに印象深いのが、まだ文明の恵みを享受することに慣れていない患者が、麻酔を断るという逸話の数々である。
たとえば寺田寅彦(てらだ・とらひこ)の随筆に出てくる60歳代女性。舌癌の切除のために麻酔しようとすると、「そんなものはいらない」と言って聞かなかったとのこと。とうとう無麻酔で舌を切除したが、まったく平気で、苦痛の顔色を示さなかったそうである。(「追憶の医師たち」、青空文庫より)
どうも昔の時代は、ハラキリとか、折檻とか、痛い話に満ち満ちているような気がしてならないのだが、昔の人は痛いのが平気だったのだろうか。いや、まさかとは思うが、痛いのが好きだったのか。実際、昔の手術室はどんな様子だったのだろうか。
昔の人が麻酔について触れたものを読むと、麻酔をミステリーもののネタなどとして面白半分に扱っているものも多いが、実体験に基づくと思われる、患者視点のものもある。ふたたび、ゆるゆると見ていく。
「出家とその弟子」という戯曲で有名な倉田百三(くらた・ひゃくぞう)の手紙に、自分が痔の手術を受けた時の話が書いてある。
「二度目のはこの病院で、全身麻痺の恐るべき手術でした。私は今もなおあの手術の時真裸かで、手術台の上に寝かされて、コロロホルムを嗅がされて意識を失ふ時の、恐るべき嫌悪すべき心持を忘れることができません。」(青春の息の痕、大正3年)
残念ながら、よほどおいやだったようだ。ただその描写のしかたが、自身の書いた戯曲と同じく、ジクジクと悩み多き青年ぶりである。しかし「全身麻痺」ですか…
素木(しらき)しづという作家の「青白き夢」(大正4年)という小説は、もうちょっと詳しい。著者自身が17歳の時に、結核性関節炎との診断で右下肢の切断術を受けているから、そのときのことをそのまま書いているのであろう。明治45年当時の麻酔の様子が伺われる。
「誰か、お葉(よう)の枕の方に来た。そして何か鼻のあたりに置かれたと思った時に、はっきりと声がきこえた。
『魔薬ですから、静かにしてらっしゃい。』
急に、変な香がした。そして静かにしようとあせればあせる程、息がせはしく苦しくなって行く。そして何か知らないものが、ゴクンゴクンと咽喉のどの中に入って行った。(中略)
彼女の身体は、その中に十重、二十重(とへ、はたへ)にしばられて、恐るべき速力で何千里と飛んだけれども、その行く先はわからなくなった。すべてが無になった。お葉の意識はすっかり魔睡してしまった。」
これだけ生々しく麻酔体験を表現した文章は、これまで見たことがない。それがなんとも、苦痛に満ちた体験である。そして字が、「魔薬」、「魔睡」である。だが、17歳にして下腿を失う少女の心情を思えば、また彼女自身が結局、結核のために23歳でこの世を去ったことを考えると、こんなイヤな「魔睡」なんかかけて、どうもすみません、としか言えない。
だんだん気が滅入ってきたので、最後は景気がいいのを書き写しておこう。日露戦争の旅順港閉塞作戦で、部下を助けようとしたために戦死し、軍神になってしまった広瀬武夫(ひろせ・たけお)中佐の若い頃の逸話である。(剣影散史(読み方不明)著、軍神廣瀬中佐壮烈談、明治37年。国立国会図書館デジタルコレクション。私の趣味で、明治の香り高い旧字、歴史的仮名遣いのまま引用する。)
「中佐が海軍大學に入學して居た頃、脚部を負傷した事がある、ところがその傷は却々(なかなか)素情(すじやう)が惡いから切開せねばならぬと云ふので魔睡剤を用ゐて手術にかゝる事となつた、スルト中佐は昏睡しながら大きな聲(こゑ)で「打てツ」「進め!」と野砲操練の號令(がうれい)をかけ續(つづ)けて居たので手術を了(おは)つてから醫員(いいん)も看護兵もその元氣に驚いたといふ話だ。」
柔道の猛者(もさ)にして、後に軍神となる広瀬中佐といえども痛みと無駄に戦うのではなく、ちゃんと「魔睡」(もはや慣れてきたな)を受けていたというのだから、これはいい話である。しかも何だか、愉快そうだ。ただ、全体的に「壮烈」すぎて、ちょっと嘘っぽい。
2018.6.2
|
|
自然淘汰
|
ふたたび、弱者の生き方を考える。
あまりにも昔のことで思い出せないのだが、中学の頃の私が学校で進化について学んだ時、「自然淘汰」という言葉の不気味さに、戸惑いを覚えなかったはずはないと思う。「淘汰」という言葉は聞いたことがなく、意味がよくわからないが、何か悪い意味に違いない。その証拠に理科の先生は、こんなことを言う。
「お前らも、ちゃんと勉強しないと、社会で淘汰されるよ。それが自然界の掟だ。」
ちょうど工場のラインで、不良品が弾き飛ばされるように、生存競争から落伍した弱者もゴミ箱に放り込まれる、それが淘汰か・・・。これでは、まだ社会の荒波とやらを知らない中学高校の生徒たちはびびるはずだ。
国語の授業も、不安をあおったかもしれない。弱肉強食!優勝劣敗!適者生存!この世には恐ろしい四字熟語がたくさんあるのだ。
ところが、ダーウィンはもう少し優しかった。彼が「種の起源」で使った言葉は "Natural selection" なのである。最近では自然淘汰ではなく、自然選択と訳されることのほうが多い。要は、環境によりよく適応したものが、より多く子孫を残せるという話であって、弱い個体や集団がただちに物理的に排除されるわけではない。一体誰が、「淘汰」などという殺伐とした言葉を当てたのだろう。誤解か、はたまた陰謀か。
もちろん、「弱肉強食」、「優勝劣敗」という言葉も概念も、「種の起源」の中にはない(はず。まだ読んだことがない)。
学校の授業であれだけ不安にさせられた生徒たちは、その数十年後、数々の致命的な弱点をかかえたまま、まだ生きている自分を発見するわけである。ダーウィンは正しかった。もともと、何百世代に渡る現象である進化の用語を、個体の生き方に適用するのが間違いのもとなのであるが。
NHKの「人類誕生」という、人類史に関する科学番組を見ていると、「弱さからの逆転」という言葉が何度も語られていた。頑丈型アウストラロピテクス、ネアンデルタール人など、人類史上肉体的に優位な種はいくらでもあったのに、なぜかその都度、ひ弱な方のホモ・サピエンスの系譜が綿綿と生き延びてきた。これは、からだの弱さを、石器の発明やコミュニケーション能力で補ったからである、かっこよく言えば、「弱さを武器に変えた」のだ、というストーリーである。
どうしてこういうまとめ方になるかというと、たぶん、そのほうがテレビ的には面白いからである。ちょっと古いが、舞の海のような小兵力士が、大きな力士を倒す場面を、視聴者はもっとも喜ぶものである。だが現実には、「弱いからこそ勝てました」などというできすぎた逆説は、なかなか発生しないのではないか。
たぶん、われわれの先祖は運がよかったのだ。何か手柄があったとすれば、「弱いけど死なない」を実践したことであろう。
2018.5.27
|
|
ドラッカー
|
数年前、「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」という本がベストセラーになり、ドラッカーという経営学者がもてはやされたことがある。もし麻酔科医がドラッカーを読んだら、今頃私の病院は甲子園で優勝していたかもしれないが、私は高校野球には興味がないから読まなかった。ただ、その「名言」とやらがちらちら目に入ってくる。ぎょっとさせられたのが、次の言葉である。
「何事かを成し遂げるのは、強みによってである。弱みによって何かを行うことはできない。」
自分が叱られているような気がした。
私なりにドラッカーを解釈すれば、次のような優しい言葉はまるで幻想に過ぎない。
「うちの病院はこれと言って特徴はないけど、ほんわかして働きやすいところです。みんな来て見てください。」
「あなたはこれといって、取りえはないけど、そんな平凡なところが好き。」
「働かないアリにも、何か存在意義がある。」
「弱くても勝てます。」(そういうドラマがあったような。)
ほんわかしているだけじゃダメだ、何か取りえを持ちなさい、とドラッカーは言いたいのであろう。しかし、「弱いものは死ね」と言われたようで、私はショックを受ける側である。何かこう、力への信奉みたいな、アメリカ的と言えばアメリカ的な思想ではなかろうか。
上昇志向をあえて封印した弱者に、チャンスというものはないのか。
しかし考えてみれば、地球上には私以外にも、何の取りえもなさそうな生き物が存在する。たとえば、ナメクジとかカピバラとかナマケモノとか、彼らは一体何なのか。攻撃力も防御力もなさそうだし、深海とか火山の中とか、極端な環境の中で耐え抜いているわけでもない。 現実の世界では、あのような動物が自然淘汰の魔刃をかいくぐり、ぬくぬくと生き残っているではないか。
経営学と進化論をごちゃまぜにすると、弱者のチャンスが見えてきた。
「弱いけどなぜかしぶとくて、なかなか死なない。」できることなら、この線でやって行きたいものである。
2018.5.22
|
|
リュックサック
|
リュックサックを背負って街を歩く人が、明らかに増えている。小学生のランドセルは昔からの日本の文化だが、今や学生も社会人もお母さんも、ついでに私も、荷物を背に負っている。中にはスーツにリュックという出で立ちの人もいる。昔だったら石を投げられていたはずだが(昔はそんな人はいなかったので、勝手なことを言っている)、見慣れてしまえば何の違和感もない。
カバンやバッグを持つことをいやがるとは、横着な者どもだ、と眉をひそめる人もいるかもしれないが、それは当たらないのではないか。背負う人たちは、なるべく乗り物に頼らず、歩く楽しみを味わいたいと考えているのだと思う。
そもそもどう考えても、荷物を手に持つというスタイルは長距離の歩行に適していない。腕が疲れて仕方がないのだ。
荷物を持って歩くということは、単にそれを地上数十センチメートルの高さで水平移動させているだけであり、純粋力学的には全くエネルギーを要さないはずである。腕に余計な力が必要なのは、歩行運動でからだが上下に動くからだろう。だとすれば、腰が完全水平移動する方式、たとえば泥棒の「抜き足差し足」とか能楽師のような動きがいいのかもしれない。そこで私は、たわむれに水平歩きしたのだが、つらさに泣きて、三歩あゆまず、という石川啄木状態となった。
もちろん、からだの上下動に合わせて荷物を上げ下げし、荷物だけが水平移動する方式にも挑戦したが、もっと疲れただけだった。
前回私は、二足歩行運搬起源説を紹介した。家族に食糧を持ち帰るためにサルが立ち上がり、手を空けたのが人類の始まりという説である。だがもしそれが正しいのなら、人間はもう少し合理的で、エネルギー効率の良い運搬システムを持っていそうなものである。実際、歩くのが楽しいという人はいるにしても、荷物を持ったほうがもっと楽しいという人は、まずいないだろう。
手は、運搬装置としては進化しきれなかったのだ。その理由は明らかだ。苦労して獲物を持って帰ったところ、家族には意外に喜ばれなかった、むしろ、「隣のお父さん、もっとたくさん、そしてイケメン」と比較された。そのトラウマが数百万年積み重なった結果が、これなのだ。
リュックサックは人類にとって、石器に匹敵するほどの、偉大な発明であった。念願叶い、手は自由になった。その運搬能力はますます退化するだろう。その手でスマホをイジって歩く者がいるが、やめてほしい。邪魔だし、次の人類への進化を妨げる行為だ。
歩く時、手は空っぽがいい。同じく二足歩行する生き物、ゴジラが日本に上陸する時、手に荷物を持っていたら、さぞカッコ悪いだろう。
2018.5.13
|
|
人類誕生
|
現在NHKで、「人類誕生」というドキュメンタリーが放送されている。人類史好きは見逃せない。第1部がすでに放送されたが、まだ再放送があるし、第2、第3部はこれからだ。
テレビの科学番組は、まだ確定していない新しい学説を断定的に語ることがあるので、第1部「こうしてヒトが生まれた」も、私は半信半疑の構えで見た。ただ、私たちのご先祖様が実にリアルなCGで動いているのには、目を見張らされた。
どこから見てもただの毛むくじゃらのサルが、腰を伸ばして直立二足歩行をしている。実写と区別のつかない映像でそういうのを見ると、奇妙で新鮮な感覚だ。
もう少し後の時代、サルかヒトかわからないのが肉食獣に襲われて無力に引きずられていく。足が遅くて、力が弱いのだ。そのくせ、背だけ無駄に高くて、見つかりやすいのだ。ああ、ご先祖様がやられてしまう、と脇汗がにじむ。ここまでリアルな映像は、たぶんテレビ史上はじめてだろう。これだけでも見る価値があると思う。
内容で気になったのは、サルがなぜ立って歩いたのか、である。以前私がここで紹介した二足歩行の最大の利点は、移動に要するエネルギーが小さいということであった。これは、走るのが好きな進化人類学者、リーバーマン氏(この番組でも走っていたが、ちょっとサルっぽいフォームだった)の本からの受け売りである。
一方番組のほうでは、手で食べ物を運べるようになったのが利点だったと言っている。映像では、食べ物を両手に抱えたオスが、自分の妻と子のところに持って帰るシーンが出てくる。夫のおみやげに手を伸ばす妻の表情が冷ややかで、たったそれだけかと言いたげなところが、胸を打つ。やはり昔からこうだったのか。
調べてみると、どうやらやはり、「二足歩行=食糧運搬」説はあるらしい(注)。人類はきわめて早期から、サル界にはめずらしく一夫一妻制をとっており、家族を養うために手で食糧を運んだと考えられているようだ。運搬説、省エネ説、どちらが正しいのかはまだわからないが、安定したつがいを作る習性については、メス争奪戦に使う犬歯がすぐに小さくなったことから、確かなようだ。
大変なことになった。結婚とか互いの貞操というものが、社会の仕組みとか文化とかではなく、人類誕生の原点だというのだから。
私は、自分が長年パートナーを取り替えたり増やしたりしていないのは、面倒だからではなく、ケチだからでもなく、まして魅力がないからでもなく、生物として当然のことをしたまでだったと確認できた。やはり人類史は役に立つ。
注) 更科功(さらしな・いさお)著、絶滅の人類史。NHK出版新書。
2018.5.6
|
|
明治・大正、麻酔の旅、李鴻章編
|
明治28年3月、日清戦争の大勢が決し、李鴻章(り・こうしょう)が講和交渉のため、清国全権大使として来日した。ところが、幕末桜田門外の変から昭和の二・二六事件に至るまで、日本はテロ大国である。李鴻章も日本人の暴漢に狙撃され、頭部に重傷を負った。
このとき、日本側の医師団として治療に当たったのが、陸軍軍医監、佐藤進(さとう・すすむ)と陸軍軍医総監、石黒忠悳(いしぐろ・ただのり)である。石黒の回想録(注1)によると、銃弾は頭蓋骨を貫通せず、顔面の皮下のどこかにとどまっているが、どうしても探り当てることができない。佐藤は全身麻酔での摘出を主張したが、石黒が思いとどまらせたという。クロロホルムによる麻酔で、李鴻章の身に万一のことがあれば、日本の面目がつぶれ、講和交渉が不利になるという、政治的な判断である。
「君は純外科家としてその説を主張せらるるは勿論なるも、余は衛生長官として、貴君の意を曲げても麻酔薬の使用を止むるものである」と、佐藤を説き伏せたのだそうだ。
結果的に、皮下に放置された弾丸は何ら合併症を起こすことなく、講和条約は無事締結された。
それでは当時の手術の現場で、クロロホルム麻酔はどれほど危険だったのか。明治30年の外科学の教科書を見ると、海外の統計値を紹介している(注2)。例えばドイツからの報告では、クロロホルムによる麻酔死は、2,900件につき1例、エーテルによる麻酔死は6,000件につき1例とされている。イギリスのデータも、同じようなものだ。
もちろんこれは、現在よりはるかに悪い数字であるが、人工呼吸回路も、酸素投与も、心電図モニターもない時代にしてこの数字というのは、意外である。もう一桁くらい悪いだろうと、私は思っていた。
ただ、当時の日本の医療水準、李鴻章の74歳という年齢、その肥満体から予見される気道と心臓のトラブルなどを考慮すると、やはりクロロホルム麻酔による死亡や合併症は、現実的なリスクであっただろう。賢明な選択だったと言わざるを得ない。
佐藤進といえば、明治政府からのドイツ留学第一号で、当時日本の外科の第一人者である。爆弾テロに遭難した大隈重信(おおくま・しげのぶ)の右足も、この人が切った。その頭を押さえつけて、政治的成功を収めたわけだから、長年医療行政の道を歩んできた石黒の面目躍如というところだろう。
ただしこの石黒の回想録、以前もとりあげたことがあるが、本のおもて表紙からうら表紙まで、すべて自慢話である。それはまあ、悠々自適の生活を送っている90歳の老人のところに信奉者がやってきて、昔のことを聞きたいというのだから、都合のよい話ばかりになるだろう。何しろ陸軍はこの戦争で、脚気(かっけ)のために多数の死者を出しているのに、明らかにその最大の責任者であった石黒は、本書では知らん顔なのである。
李鴻章の麻酔回避の件は、細かすぎて普通の歴史書には書いてないようだ。これが本当に石黒の手柄だったのか、数十年かけて脳内補正を重ねた美しい思い出なのか、その辺は歴史のウヤムヤの中である。
ともあれ麻酔はこのとき、施行されなかったことで歴史に貢献した。この皮肉な役回りが、いかにも麻酔らしくて、泣ける。
注1) 懐旧九十年(石黒忠悳、岩波文庫)
注2) 智児曼斯(チルマンス)氏外科総論(1897年、南江堂。国立国会図書館デジタルコレクションより)
2018.4.28
|
|
明治・大正、麻酔の旅、その2
|
明治・大正の時代、麻酔は庶民にどう受け止められていたのか。これを掘り下げていくと、カオスはますます深まっていく。
調べていて驚いたのは、明治、大正時代において、麻酔という言葉の意味や表記がひどくでたらめなことである。
「麻酔」という言葉は、江戸時代末期に蘭学者がエーテルによる全身麻酔に対する訳語として作った新語である。歴史の浅い医学用語だから、誤用、転用の余地はあまりないはずなのだが、同じ立場である「神経」、「関節」と違って、麻酔はずいぶん雑な扱いを受けているのだ。
青空文庫で明治・大正に書かれたものを読むと、麻酔という言葉は全身麻酔ではなく、鎮静剤、睡眠導入剤あるいは麻薬の作用の意味で使われていることが多い。
たとえば正岡子規(まさおか・しき)の日記。
「七時頃より再び眠る。からだ 労 ( つか ) れて心地よし。少量の麻酔剤を服したるが如し。 」
などである。これは睡眠導入剤のことであろう。全身麻酔とはだいぶ違うものである。
あるいは夏目漱石(なつめ・そうせき)が江戸時代について、「少なくとも鎖港排外の空気で二百年も麻酔したあげく…」などと述べているのは、鎮静剤的なもので頭がぼんやりしている、くらいの意味であろう。
このように言葉の意味が拡大するようなことは、まあ、ありうるかなと思う。しかし「麻酔」をわざわざ「魔睡」などと書きかえるのは、感じが悪すぎないか。たとえば明治39年の帝国議会で、歯科医が全身麻酔を行うことの是非を論じた時の記録である。(注)
「一々ひどいのは手術台の上に載せて魔睡剤を掛けてやる、外科医は手術台の脇に助手がおりますが、歯科医は一人でやることになる…」
この時の議事録では、「麻酔」はすべて「魔睡」と表記されている。速記者が無知でこのような字を当てたのかもしれないが、議論の内容自体にも明らかにある種の悪意があり、それが速記者に伝染したのかもしれない。それにしても、天下の帝国議会で「魔睡」とは…
さらにややこしいことに、明治時代、「魔睡」は催眠術をも意味した。たとえば「魔睡術」(明治20年)という本を国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができるが、これは、催眠術について紹介した本である。たとえば、動物の中で一番催眠術のかかりやすいのはカエルだ、などとよくわからないことが書いてある。
何やら明治後半期、日本で催眠術が大流行したのだそうである。森鴎外(もり・おうがい)にその名も「魔睡」という小説があり、主人公の妻が怪しい博士に催眠術をかけられ、いたずらされたみたいだ、困ったな、という妙なお話である。
催眠術はちゃんとした専門家がやればよいのだが、いかがわしい人がやればいかがわしくなるわけで、当時はこの小説にあるような事件も多発したようだ。そういうのを麻酔と一緒にされても困るのだが、同じ漢字を当てられてしまっては、当時の一般市民には区別のつけようがないではないか。
かわいそうな麻酔!この近代医学の華は、探偵小説の小道具にされ、鎮静剤や麻薬や催眠術と一緒くたにされ、「魔睡」、「魔酔」、「魔剤」などと意地悪な字を当てられ、とにかくロクな扱いを受けてこなかった。
誰か文句を言えよ、と言いたくなるが、当時は麻酔科医なるものは存在せず、したがってもちろん麻酔科学会もなかった。麻酔をかけるのは、外科医の助手であっただろう。麻酔の立場を守るものはいなかったのだ。
こうなったら仕方がない。麻酔という言葉の混乱を逆手に取るしかない。現代の麻酔科医を一人つかまえて、「魔睡士」として明治の世に送り込み、ブラックジャックのようなダークヒーローとして活躍させるのだ。
この魔睡士、明治の数々の事件の現場に蜃気楼のように登場し、当時の医療水準では想像もできなかった陽圧式人工呼吸、酸素の使用、輸液と輸血、神経ブロック、そしてなぜか催眠術を駆使して患者さんたちを助け、日本の危機をも救う。
明治22年、不平等条約の改正に燃える大隈重信(おおくま・しげのぶ)が爆弾テロで重傷を負ったとき、右大腿切断の大手術を指揮して成功させたのもこの魔睡士であったし、明治24年、大津で警官に切りつけられたニコライ・ロシア皇太子を治療し、ついでに催眠術をかけて日本への報復を思いとどまらせたのもこの人だった。明治43年大吐血して死にかかった夏目漱石も、魔睡士の蘇生術がなかったら名作「こゝろ」を遺すことはなかっただろう。そして、法外な報酬を要求しては断られ、しょんぼりとして消えるのだ。
どなたか麻酔科の先生、タイムトリップおねがいします。明治時代の日本で、暗躍してみませんか。
注) 明治39年3月24日、第22回帝国議会貴族院医師法案特別委員会議事速記録より、三宅秀(みやけ・ひいず)委員の質問。この貴重な情報は、「明治以降の麻酔と外科の歴史を考える」(http://www011.upp.so-net.ne.jp/konita/rekisi2.html)という、詠み人知らずなサイトからいただいた。議事録自体は、国立国会図書館のサイトで見ることができる。
2018.4.22
|
|
明治・大正、麻酔の旅
|
全身麻酔の技術が日本に入ってきたのは江戸時代末期のことである。当時は顔に布付きのマスクをかぶせ、上からエーテルやクロロホルムを滴下して吸入させる方法が用いられた。現代の安全な麻酔には、気管挿管による人工呼吸がどうしても不可欠の技術であるが、これが日本に導入されたのは戦後のことであるから、それまではずいぶん危なっかしい、いやはっきり言えば危険な麻酔が行われていただろうと思われる。
この間、麻酔は日本人にどのように評価されてきたのだろうか。
ここにインターネットとかいう、便利なものがある。著作権の切れた古い本ならば、国立国会図書館デジタルコレクション、青空文庫(ボランティアによるインターネット図書館)などで自由に検索、閲覧ができる。これらを使ってゆるゆると見ていくことにしよう。
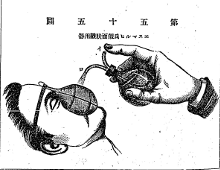
軍陣外科学(明治32年、陸軍省)より、「エスマルヒ氏仮面状嗅用器」
麻酔を扱った小説の中で、もっとも早い時代のものが、泉鏡花(いずみ・きょうか)の「外科室」(明治28年)である。
「私はね、心に一つ秘密がある。痲酔剤(ねむりぐすり)は譫言(うはごと)を謂(い)ふと申すから、それが恐くってなりません。」
というわけで、主人公の貴婦人は、自分に手術を行おうとする青年外科医への思いを、麻酔のせいでうっかり告白しないよう、麻酔なしでの手術を願う。さらにそれだけでは足らず、手術中に外科医のメスを奪って自分の胸を突いてしまう。
何とも過激な話である。昭和、平成の人が、このヒロインに共感するのはちょっとむずかしいのではないか。
昔、坂東玉三郎(ばんどう・たまさぶろう)氏がこれを映画化したが、見事にコケたような記憶がある。
これによく似たフランスの小説があって、その名も「麻酔剤」(ルヴェル・モーリス著、田中早苗(たなか・さなえ)訳、日本では大正12年初出)である。青年医師が、道ならぬ恋の相手である人妻にクロロホルム麻酔をかけるのであるが、この人が寝ぼけて秘密をしゃべってしまいそうになるので、医師はおもわずクロロホルムを過量に垂らしてしまい、死に至らしめてしまうのである。
どうも幻想小説家というものは、洋の東西を問わず、美女に麻酔をかけてみたくなるもののようである。
ここで言っておくが、現代の麻酔では、麻酔薬を静脈投与してスッと眠ってもらうので、「うはごとを言ふ」ようなことはありません。秘密を告白する前に眠ってしまうのである。心に秘密を持つ方(しかいないと思うが)も、安心して「外科室(げくわしつ)」にお越しいただきたい。
青空文庫で「麻酔」を検索した時、もっとも多く顔を出してくるのが、もう少しあとの時代の探偵小説家、小酒井不木(こざかい・ふぼく)である。たとえば「謎の咬傷」(大正14年)は、クロロホルムを染み込ませた布で被害者を襲ったのは誰か、というミステリーになっている。その後、昭和のテレビや映画では、ハンカチを使って人の気を失わせて誘拐するシーンがあふれかえったわけであるが、その走りではあるまいか。迷惑なことである。
この小酒井氏にはほかにも、手術、麻酔にまつわる恐怖小説がいくつかあり、えらく医学に詳しいなと思ったら、東北帝国大学医学部の教授だったようだ。教授がこんなふうに、一般人の妄想を掻き立てるようなこと書いて、いいのだろうか。
他にも、江戸川乱歩(えどがわ・らんぽ)、夢野久作(ゆめの・きゅうさく)らの探偵、幻想小説の大家たちも、小説の中で麻酔を使っているようである。
麻酔は、近代外科の出発点となった革命的技術であり、病を持つ人にとっても無痛の手術を実現してくれた、まさに福音であったはずだ。それなのに、ああそれなのに明治・大正の読み物を見る限り、庶民にとっては、麻酔は奇談や犯罪小説の小道具に過ぎなかったようである。
ま、いいか。よく考えたら今でも同じようなものかもしれない。
2018.4.15
|
|
私の研究の研究
|
十数年前まで、医学論文を作るのは今ほど大変ではなかった。
臨床研究であれば、2,30例ほどの症例を集めて統計を取って、グループ間で何か意味ありげな差が出ればOKだった。
基礎研究ならば、動物とか細胞とかを使い、麻酔薬でこんな反応が出た、くらいでまあよかった。
時代は変わった。「根拠に基づく医学」が提唱され、大規模臨床研究が主流になった。倫理委員会に諮り、実際に治療を受ける患者さんを数百人あるいはそれ以上集め、それぞれの方から同意書をとりつけ、アブラ汗を流しながらデータを取り、その大量のデータをもとに複雑怪奇な統計処理を行わなければならない。
これは、日本人研究者にはきわめて不利な状況と言える。このような研究は日本では、ほとんど遂行不可能だからである。
まず、日本の医師は忙しすぎる。研究するのが仕事のはずの大学病院の医師でさえ、病院での診療でほとんど手一杯だ。研究に時間を割くためには、気の進まない仕事から逃げる才能、夜間や休日に研究にとりかかれる体力、家族から見放される覚悟など、いろいろなものが必要になる。
また、大規模臨床研究を行う環境が整っていない。日本では「実験」を中心とする基礎研究は評価されやすいのだが、このような臨床研究に金を出し、業績として重視するムードが、日本にはまだあまりない(と思う)。
また、これは私の偏見かもしれないが、そもそも日本人は一人でこつこつやる仕事が好きなのである。大規模臨床治験では、多くの医師を説得し、組織し、進行が遅い者に対しては恫喝し、逃げようとする者を羽交い締めにする、といった人間関係上の力仕事が必要である。こういうのは日本人にはあまり向いていない。もっと偏見かもしれないが、こういうこってりとした仕事は、血の滴るビーフステーキを毎日平らげるような欧米人にしかできない気がする。
15年ほど前、私は十数例の症例を集めただけの研究で論文を作ったが、この時は何とかイギリスの雑誌に採用された。
5年前、私は同じくらい小規模の臨床研究で次のドジョウを狙ったが、もうどこにも採用されなかった。中身も悪かったが、とにかく症例数が少なすぎたのが門前払いのいい口実になった。
惜しいことだ。この研究はもし発表されていたら、医学界初(多分)のアイウエオ論文になるはずだった。
話はさかのぼるが、昔、ジョージ・ガモフという、ロシア出身の物理学者がいた。ロシア語のガモフは、英語ではガンマ(γ)に相当するらしい。あるとき、ガモフの弟子のラルフ・アルファーというのがよい成果を出した。アルファー=ガンマの論文として発表してもよかったのだが、ちょっと物足りない。そこでガモフは一計を案じた。ドイツのベーテ(英語でベータ)という、やはり高名な物理学者の名前を、本人に無断で使ったのだ。この、アルファー=ベータ=ガンマ(αβγ)論文は、宇宙のビッグバン理論の土台になる記念碑的業績になった。
私が論文をこしらえている最中、ふと気づくと、自分の病院の麻酔科の5人のメンバーの名前が、ア行で揃っていた。これは医学界のガモフになれるチャンスだ。私は麻酔科メンバーの名前をアイウエオの順番にして論文に並べ、投稿した。そして落ちた。
このシャレは外国人には通じなかった。きっと、日本人にも通じなかっただろう。
私の研究人生も焼きが回ったようだ。病院の勤務医には、大規模臨床研究を行うための資源は全く無い。アイデアも枯渇した。時代から取り残された挙句、こんなことをやって落ちつづけている。
2018.4.9
|
|
研究の研究
|
新聞記事などに時々、企業系研究所からの研究結果が紹介されることがある。
印象に残っているものを挙げると、パジャマを着たほうがぐっすり眠れたとか、牛丼を毎日食べても、血液検査に異常が見られなかったとか。それぞれ、下着メーカー、牛丼屋がスポンサーになっている研究である。
これらの結果は、すんなりと信じる気にはなれない。研究対象になっている製品と、金(研究費)と、両者の出どころが、まるで一緒だからである。
忖度というのは、どう考えても日本人の専売特許ではなく、人類共通の神経回路である。企業から給料をもらっている研究者が、スポンサーに不利益になるような結果を、おいそれと公表できるものではない。そのスポンサーの喜ぶ顔が見たいから、悪い結果ならそっと隅に片づけるし、よい結果なら発表する。これを積み重ねていけば、真実と正反対の結果すら出てくるかもしれない。これは無意識界のできごとであるから、研究者自身も気がつかないでやってしまう可能性がある。
それでは大学の研究者が医学雑誌に載せるような専門的な研究ならば、信用できるのか。そうとも言い切れない。
中には製薬会社から研究費を受けている研究もある。(その旨は、論文の冒頭で言明しなければならない。)そうでなくても、研究者たるもの、かっこいい成果を出して名前を売りたいのである。それが偏りの発生源になる。
研究者はつねに、データいじりの誘惑と戦っている。これまでもたびたび、研究者によるデータ捏造が露見して、報道されてきたが、あれはたまたま、暗黒面に落ちてしまった人たちであろう。
全く偏りのない、公平無私の研究を行うためには、どうすればいいか。私は長年ひそかに研究した結果、以下の二つの方法を発見した。
まず、何らかの方法で大金持ちになる。そして自分の金を使って好きな研究をする。仮に大発見をしても、公表せず、一人でニヤニヤする。
あるいは…
まず修行か何かして、すべての欲望を捨てることに成功する。老荘思想でいう無為自然の世界である。何せ野心というものがないから、研究成果が出なくて、職を失い、食べるものがなくなっても、全然気にならない。「で、それが、何か?」と言うのが決めゼリフである。仙人ぐらいにはなれるかもしれないが、ただし、研究は失敗する。
どちらも「まず」のところがもっともむずかしい。仮にそれをクリアしても、困ったことに、結果として人類に役に立つ話にはならない。
誰か、私に研究費を提供していただければ、もう少しましな方法を発見できるかもしれないのだが…
2018.3.31
|
|
佐々木小次郎、その2
|
ある研修医と話していて、私が「やつらは烏合の衆だから」と語ったところ、「ウゴーノシューって、何ですか?」と聞かれた。おっと、これは私の得意ネタ、ジェネレーションギャップではないか。例の戦闘系有名人の件を思い出し、ついでにいろいろ聞いてみた。
予想通り彼女は、「佐々木小次郎(ささき・こじろう)」も、「大石内蔵助(おおいし・くらのすけ)」も、「山本五十六(やまもと・いそろく)」も、聞いたことがないという。かろうじて 「東郷平八郎(とうごう・へいはちろう)」は聞いたことがあるが、何をした人かは知らない。もちろん、セオドア・ルーズベルト米大統領を感動させた、「勝ってカブトの緒をしめよ」のくだりも知らない。
私が「ほう、ほう、やはりな」とひとり悦に入っていると、普段温厚な彼女も、ついに、カチンときたようだ。
「でも、研修医の〇〇くんは、飯島愛(いいじま・あい)のことも知らなかったんですよ。それってどうなんですかっ!?」
何という洗練された反撃だろう。私に直接反論する代わりに、自分の同僚を血祭りに上げるとは。これは一種の威嚇射撃だろうか。しかも、東郷平八郎に対抗して飯島愛を持ち出すとは。二重の意味で、「江戸のカタキを長崎で討つ!」(これも戦闘系死語)である。
タマがこちらに飛んでくる前に、話題を変えた。
2018.3.27
|
|
小論文問題
|
私は病院内の研修委員会の委員なので、毎年、研修医採用試験の小論文の問題を作っている。ただ、委員は他にもいるので、私の作った問題が実際に試験に出されるとは限らない。正確にいうと、これまで一度も採用されたことがない。つまり、ボツにされつづけているのである。
自分でも理由はわかっているつもりだ。内容が突飛すぎるのだ。受験者にとってはたぶん想定外で、答えを組み立てるのにさぞ苦しむことだろうと、気の毒になるような問題ばかりである。私が委員長でも、採用しない。
これまで作った問題は、まだ今後採用される可能性があるので、(いやほとんどないが、とりあえず)ここには紹介できないのが残念だ。しかし、今回あまりに悪乗りがひどく、さすがの私も提出できない問題を思いついてしまったので、ここに書き捨てておく。
「自分が死亡するときの年齢と死因を想定し、その状況を説明せよ。また、そこであなたが詠む辞世の句は、どのようなものか。」
受験者の人生観、死生観、健康状態、医学知識、表現力を一気に教えてもらおうという、欲張りな質問である。しかし、死に方を教えろとか、今どき辞世の句を詠めなど、何の冗談か。酒の席の雑談なら面白いが、これを就職先に答えさせるとなると、受験者にとっては深刻なモラルハラスメントであろう。こんな問題は、絶対に出ないので、当院への応募をお考えの学生さんは、ご安心ください。
どうでもよいが、解答例は以下の通り。読めばわかるが、「模範解答」ではない。
私は、自分が95歳くらいで事故死するであろうと想定します。私はその年で寿命をさらに延ばすためにジョギングを行っているわけですが、よろけたはずみで後ろから来た自動車にはねられます。自動車搭載AIには、「歩くより遅く走る95歳の老人」に関するデータがなく、動きを予測できなかったようです。そこが高速道路の真ん中だったのも不運でした。
虫の息で横たわる私ですが、最後の力を振り絞り、日本古来の美風、「辞世の句」を遺すのでした。
恥ずかしき思い出連れて死出の旅、心残りはブログの消し忘れ
2018.3.18
|
|
佐々木小次郎
|
麻酔の準備をしている時、注射器に薬を吸おうとして、針のキャップを取った研修医が、そのキャップをぽいとゴミ箱に放り捨てた。薬を吸ったら、針にまたキャップをするのだから、これは捨ててはいけない。私は思わず、「お、佐々木小次郎(ささき・こじろう)かよ」と突っこんだのだが、これが研修医には全然通じなかった。
念のために説明しておくと、佐々木小次郎は戦国時代あたりに生きた剣士であり、宮本武蔵(みやもと・むさし)と巌流島で決闘を行い、敗れて命を落としている。巷説では、約束の時間よりはるかに遅れて宮本武蔵が現れたとき、佐々木小次郎はよほどイライラしていたらしく、刀を抜いたあと、サヤを投げ捨てたという。これを見た武蔵は、「小次郎敗れたり!」と叫んだ。勝つつもりなら、勝った後に刀を収めるべきサヤを捨てるはずがない、という理屈である。もちろん、武蔵のはったりであろう。
研修医が針のサヤを捨てたのを見て、私はこの小次郎のエピソードを思い出したわけであるが、その研修医がきょとんとしていたのは、その連想が通じなかったからではなかった。彼は佐々木小次郎そのものを知らなかったのである。ただちに周囲の若い人たちに聞いてまわったところ、小次郎を知らない人のほうが多かった。予想外の事態だった。
敗戦後18年も経って生まれた私であるが、そのころでも日本には、決闘、戦争、あだ討ちとかいう、血なまぐささを好む空気がまだまだ残っていたのではなかろうか。知らず知らず、私もそういう空気を吸って育っているのである。たとえば私が少年の頃は、毎年8月15日の終戦記念日には、なぜか必ずゼロ戦(零式艦上戦闘機)の活躍を賛美する特集番組が流れていたのだ。(今でもその意味がわからない。)大晦日はもちろん、大石内蔵助(おおいし・くらのすけ)が主君の仇を討つ忠臣蔵である。今はもう、そういう時代ではないということだ。
私も仕事中、時代遅れな好戦的発言を控えるよう、気をつけなくてはならない。たとえば、
「お、電気メスのノイズで心電図の音が乱れまくっとるやないか。まるで山鹿(やまが)流陣太鼓!え、忠臣蔵知らんの?」
「この手術が、今週の山場やな。皇国の興廃はこの一戦にあり、と東郷(とうごう)元帥も言うてる。ちなみに東郷平八郎(とうごう・へいはちろう)やで。デューク東郷とちがうで。あ、それも知らんか。」
「危ない手術やったが、何とか終わったわ。でも患者さんが退室するまで気を抜いたらあかんで。古人いわく、勝ってカブトの緒をしめよ、と。はいはい、東郷さん知らんもんな。」
これらすべて、若者たちの耳を素通りすること、まちがいなしである。
老兵は死なず。マッカーサーじゃないが、そろそろ消え去ってしまいたい。
2018.3.11
|
|
塩と進化
|
SF映画の不朽の名作、「2001年宇宙の旅」は、太古の昔のサルが、サバンナに突如現れた不思議な物体「モノリス」に触れる場面から始まる。モノリスの効験あらたかに、サルたちは突如、手で道具を使うことに目覚めるのだ。サルがヒトに進化した瞬間を描いているのだと思われる。
この映画が公開されたのは1968年である。現在の人類進化学の知見はちょっと違う(下記注)。サルがヒトになったその分岐点は、「道具の使用」ではない。「二足歩行」なのである。たまたま一部のサルが、酔狂にも二足歩行を始めたのだろう。それが定着して後に、脳の巨大化、食べ物を分け合う習性、オスとメスでつがいをつくる変な癖など、さらなる人間の特徴が現れてくるのである。(もっとも人間に近い種、チンパンジーは食べ物を分けず、また乱婚である。)
歩き始めた最初のサルは、ご近所でも評判の変わり者だったのだろうが、それが子孫を増やしたからには、二足歩行に意外な利点があったのだろう。それは何か。
手が使えるようになった、というのが自然な連想であるが、重要なのはそこではない。二足歩行の利点は、長距離の移動に適していることなのである。二足歩行は短距離でのスピードに劣るけれども、長く歩いたり走ったりする分には、エネルギー効率に最も優れた方式であるらしい。(二足歩行は手を使うためだったという説も、まだ有力であるようだ。)
われわれ一般人でも、ちょっと練習すれば、10キロや20キロを休まずに走ることは、そう苦ではない。ところが、そんな持久力を持つ動物は、きわめて稀なのである。
乾燥化のために森が消滅しつつあるアフリカの大地で、われわれの祖先は木から降り、地面を歩いたり走ったりすることに活路を見出したのである。さらにヒトは全身から汗をかいてからだを冷やす能力を手に入れた。(全身で汗をかける動物は、ヒトとウマくらいらしい。)他の動物たちが、暑い日中グッタリとする隙を狙い、木の実や地下茎を求めて歩き回ったり、動物を執念深く追って疲れさせて仕留める、それこそが二足歩行の最大の利点だったのだ。
つまり、ヒトのヒトたるゆえんは、歩き、走ることと、汗をかくことであると言える。
以上が最近読んだ本の受け売りである。(一部脚色あり。)ここから例によって、何の根拠もない、私の妄想が始まる。
- 汗から塩分が失われるので、ヒトは塩の補給がなければ生きていけないからだになってしまった。人と塩のくされ縁はここから始まった。
- ヒトはやがて、一日中歩かなくてもよい生活を手に入れても、塩を欲するようになった。そして、高血圧になった。(単純化しすぎでしょうか。)
- 塩により、ヒトは運動をやめると病気になりやすくなる呪いをかけられたのだ。どうせなら同じ樹上生活者でも、ナマケモノから進化していれば、こんなことにはならなかったが、仕方がない。大いに運動し、汗をかこうではないか。
- ところで、ダッシュ力という面では原理的に、四足走行こそが理想である。百メートル走の選手は、自分の両手に、「お前は前アシだ」と言い聞かせ、這い這いで走る稽古をしたらどうか。
- 前アシ用シューズを作ったら、さぞ売れるだろう。こはぜ屋の宮沢社長、いかがです?名付けて「獣王」
- 逆にマラソンの選手には忠告しておきたい。長距離を走りたいなら、這ってはならない。絶対に、だ。
注) 人体六〇〇万年史~科学が明かす進化・健康・疾病~(上・下), ダニエル・E・リーバーマン, ハヤカワ文庫NF
2018.3.4
|
|
塩
|
先日、私は献血ルームに行き、最初の血圧測定で142mmHgという新記録を叩き出してしまった。これが続けばもう、高血圧症である。検診の医師は、「ここまで歩いて来られたんでしょ?こんなものですよ。」と慰めてくれたが、だまされるわけにはいかない。高血圧は明らかに脳卒中などのリスクを高め、寿命を縮める。このままではあと100年も生きられない。早めに手を打たなければならない。
薬をのまないで血圧を下げようと思ったら、真っ先にできるのは、塩分制限である。私には、何にでもしょうゆやソースをだぶだぶとぶっかけるような性癖はないけれども、妻に比べたら味の濃いものを好むようである。これは親の影響が強いだろう。私の父も母も、かなり濃い味付けを好む人だった。
自分の子供時代の食生活を思い出してみる。当時(1970年前後)は、余ったおかずは冷蔵庫に入れるのではなく、「水屋」という、網戸つきの棚に室温で保管していた。それをふたたび食事に出すときに、母が匂いを嗅いで、まだ大丈夫かどうかを確かめるのである。夏などには、ときどきこの匂いチェックにひっかかる皿があったから、今から思えば、母の嗅覚に家族全員の健康がかかっているという、なかなかスリルのある食生活だった。
かりに母の嗅覚が正確だったとしても、これはそもそも、その料理の塩分が濃くないと成立しないやり方だった。実際、母の料理はみんな、しょうゆ色に染まっていた。私の親のような、冷蔵庫のない時代に育った人たちにとって、塩は防腐剤に他ならなかったのである。
神道などで塩が清めに使われたりするのも、腐敗を退けるこの白い粉がまぶしかったからではあるまいか。
私の父も、塩の清め効果を信仰しており、ちょっと鮮度に疑問のある刺身などを食べるときは、
「ええか、こうやってしょうゆをようけつけて食えや。そうすりゃ、あたらんけんのう(食中毒にならないからね)」
とお手本を見せてくるのであった。(もちろんこれは、間違っている。)
私の子供たちが、刺身をしょうゆにつけずに食べたり、フライものをソースなしで食べたり、自分にはとてもまねできないことをするのを見ると、味覚における食習慣の影響はかなり強いことがわかる。(現在のわが家において、父親の影響力がゼロであることもわかる。)
とりあえず、私が昼に食べているカップ麺は塩分が多く、血圧に悪そうだ。やめてみようと思う。しょうゆのつけ過ぎ、ソースのかけ過ぎにも気をつけたい。年を取るとは、さまざまな自由をひとつずつ捨てていくことだと思われるが、この度、塩辛いものを好きなだけ食べる自由を捨てることになった。妻より長生きする、という目標を持つ私なら、頑張れるはずだ。
2018.2.25
|
|
のど飴の効用
|
今年もインフルエンザが大流行した。麻酔科医はほとんど手術室にいるので、比較的安全だが、救急外来でたくさんの人と接触する研修医は、かなりの率でインフルエンザをもらってしまう。また彼らは、虐げられた者どうし、仲良しだから、お互いにうつしっこをする。からだを張ったお仕事、ご苦労なことである。
あるとき、テレビで朝の情報番組を見ていると、どこかの医院の医師が出てきて、クイズを出してきた。インフルエンザの予防に有効なのは、次のうちどれでしょう、というのだ。4つほどの選択肢のうち、正解は、飴である。出演者一同、へーっとうなる。私も知らなかった。
その医師によると、のどが乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなる。飴をなめて、のどをうるおせば、インフルエンザ予防に役立つ、というのであった。
本当だろうか。
私は感染症は専門外だが、のどならちょっとだけ専門だ。人さまののどの奥を、毎日覗いて管を挿入しているのだ。私の経験上、のどの奥の粘膜が濡れていない人など、まずいない。まれに、意識障害のある人が、高熱を出して息が荒くなっていたりすると、のどが完全に乾燥するくらいのものだ。「飴をなめて、のどをうるおす」と言葉にしてみると、もっともな感じはするが、飴がなくてものどはもともとうるおっているのだ。
飴を舐めて唾液をもっと出せば、バリア効果がアップする。そういう意見もあるだろう。ネットで検索してみると、そのようなことを書いてあるサイトが山ほど出てくる。中には、免疫グロブリンがどうとか、立派な専門用語をからめているサイトもあり、私もつい、「かたじけなさに涙こぼるる」状態に持って行かれそうになる。
だが待て、理屈はどうでもよいのだ。大事なのは、本当に「飴をなめるとインフルエンザにかかるリスクが減るのか」どうかを、誰が実際に確かめたのかである。
厚生労働省のホームページを見てみよう。医学的根拠のないことは書いてないはずだ。「今冬のインフルエンザ総合対策について」の中で述べられている予防対策は、咳エチケット、予防接種、隔離、などであり、飴のことはひとことも触れられていない。
医学論文の検索サイト、「PubMed」で調べてみよう。Influenza + Candy で出てくる論文は1件、ブラジルのインフルエンザウイルスの全ゲノム配列に関するもので、飴とは関係ないだろう。
おそらくは、「飴でインフルエンザを予防する」というのは、調査によって確かめられた話ではない。たしかに、嘘であるという証拠もない。だが、そういうことをテレビでべらべらしゃべる人の気がしれない。のど飴屋さんが出てきて、そういうことをしゃべるのなら、まだ許せるが、医師がそれをするのだ。同業者として恥ずかしい。
教訓として、テレビに出てクイズなんか出してくる医師は、信用しないほうがいいようだ。もちろん、ブログのようなもので適当なことを書く医師も、似たようなものだが、害は少ないと信じている。
2018.2.18
|
|
光線療法
|
前回私は、光免疫療法について書いたが、それで連想してしまったのが、いわゆる民間療法の一つ、「光線療法」である。私の父は糖尿病性網膜症を治すために治療器を買い、自宅でこれをやっていた。もちろん、光免疫療法とは何の関係もない。新生児黄疸の治療に使う光線療法とも関係ない。
光線治療器の電源を入れて、カーボンの電極同士を近づけると、放電して火花が出る。その光に治療効果があるのだそうだ。電極の種類を変えると、光の色が変わる。治したい病気によって、適切な電極を選び、適切な場所に照射するのである。
当時中学生だった私も恐る恐る、自分で試してみたが、光のまたたきが幻想的気分を醸し出すのと、照射した肌がほんのり暖かくなるという効果は確認した。
そんなもので病気が治るはずがない、と見くびるのは科学的な態度ではない。これがどういう仕組みで病気を治すのか、ちょっと見当がつかないのは確かだが、そのことは効かないという証明にはならない。
効く、あるいは効かない、と言い切るためには、やはり、この光線を当てた人と当てなかった人で、病気の経過を比較しなくてはいけないのだ。しかもそれをするのは、その治療でお金を得ている人と無関係の人でなければならない。利害がからむと、どうしても結果に影響が出るからである。誰もそんな仕事を、莫大な金と時間をかけて、するわけがない。
ドラマなどで探偵役が、「真実は一つ」と言っているが、何事もそう単純ではない。事実上開示されえない真実というものもあって、それで世の中回っている面もあると思う。
この光線治療の理論について詳述した解説書が、「遺伝と光線」という分厚い本である。少し読んでみたが、戦前からこの治療一筋の開祖が書いた本だけあって、小学生の頃から私が愛読していた「少年少女世界の名作文学」とは明らかにテンションが違っていた。さすがに取っつきにくく、パラパラとページをめくるくらいのものだったが、一つだけ強烈な記事があり、今でも覚えている。
それはある症例の紹介である。日頃熱心に光線を当てていた患者さんが、治療の甲斐なく、自宅で亡くなってしまった。家族は懸命に蘇生させようとしているうち、とてもいいことを思いついた。人は死ぬと、肛門が開いてしまう。それならば、肛門に光線を当てて、再び締まるように導けば、生き返るのではないか。
手に汗握る、この前代未聞の試みの途中経過は省略。もちろん、肛門はその輝ける活力を取り戻し、患者は息を吹き返したのであった。
因果関係というものは通常、原因があって結果があるのであって、結果をいじると原因がどうにかなるものではない。風が吹いて桶屋がもうかるのだとしても、桶屋が損をするようにしむければ、風が吹かなくなるというものではない。
因果を逆転させて、死んだ人がよみがえる。たしかにこれは、奇跡としか言いようがない。中学生は、驚いた。確か、夏休みのある日の午後のことであった。
2018.2.11
|
|
光免疫療法
|
今、がんに対する光免疫療法が注目を集めている。まだ開発中の治療法であるが、免疫反応を利用してがん細胞に特殊な分子をくっつけ、近赤外線を当てるとがん細胞が死んでいくという、できすぎのようないい話である。ただ、この「光免疫」という名前の響きが、ちょっとひっかかる。
光のパワーでがんを攻撃する、とか、免疫力を高めてがんを退治する、などはオーロラ波動研究所(架空)のホームページにでも出てきそうな宣伝文句である。その「光」と「免疫」が合体しているのだから、これは怪しげである。
だが心配ない。開発したのはアメリカ国立がん研究所の日本人医師であり、たまたま私の大学の同級生のK氏である。よく覚えていないのだが、確か、怪しい人ではなかった。いやいや、大事なのは人柄ではなく、これが医学の本流から出た治療法であるということである。それは、必ずその有効性と副作用について、客観的に調べられ、その結果が公開されることを意味するからである。そこが民間療法との違いである。
すでにアメリカでは光免疫療法の小規模な臨床治験が行われ、有望な結果が出ているらしい。日本でもこの3月から、治験が行われる。こういった先進的治療に対する動き出しの遅い日本にしては、異例のスピードである。開発者が日本人だということもあるのかもしれない。実際に日本の患者に使えるものかどうか、数年以内に結論が出るだろう。
もしもこの治療の効果が期待どおりならば、手術や放射線など従来の治療がむずかしいがんにも効く可能性があるし、対象となるがんの種類も幅が広そうだし、しかも患者さんのからだと財布への負担が軽い治療になるだろう。
将来もし、この治療法がさまざまながんをつぎつぎに制圧していったとしたら、麻酔科の仕事にも影響が出るに違いない。がん切除の手術はほとんどなくなってしまうのではあるまいか。とくに、食道がん、膀胱がん、膵がん、肝がんなどは大手術が必要になるため、患者負担を考えると、手術はほとんど選択されなくなるかもしれない。
手術にも、栄光と没落の物語がある。開腹して尿管結石をひょいと取るとか、精巣腫瘍でからだ中のリンパ節をとりまくるとか、昔はよくやってたが、もう忘れ去られている。食道亜全摘術なんかも数年後には、そんな手術があったと、若い人に語っても信じてもらえないかもしれない。「え、胃を筒状にして首まで引っ張り上げるんですか。それでちゃんとつながるんですかね。」といった具合だ。
麻酔科医の仕事は減るだろうが、あの、罰ゲームのようなひたすら長い手術たちがなくなるのであれば、悪くない世界である。かつて私が取り上げたように、外科の夜明けはもっぱら、命をおびやかす良性疾患(鼠径ヘルニア、虫垂炎など)を治すためにもたらされたのである。そこに戻ればよい話である。
先走ってしまったが、何ごとも治験の結果しだいである。結果しだいではあるが、かなりインパクトのある新治療法であり、社会を変えてしまう可能性を持っている。
学生時代、Kくんに何か親切にしてあげたことがなかったか、私は懸命に思い出そうとしているところである。
2018.2.4
|
|
寒い話
|
いよいよ本当に、寒くなってきた。
私は普段、一年中適温に保たれている手術室にこもっているから、暑さ寒さには弱い。その代わりと言っては何だが、適温には強い。
昔ある時、私は救急車を迎えるため、救急搬入口の扉を開けて外に出たのだが、そこが「底冷え」と呼ばれる京都の冬の夜だということをうっかり忘れていた。術衣の薄いシャツ一枚だった私が悲鳴を上げたところ、ナースに叱られた。
「こういうのは寒いとは言いません」
そのナースは、北海道出身だったのだ。
私の祖先は、1万年かそれ以上前、大陸から歩いて日本に渡ってきたはずである。なぜそんなことができたかというと、そのときはまだ氷河期で、海の水が大量に凍っていて水位が低かったからである。おそらく衣類と火くらいは持っていただろうが、人間は今よりはるかに寒い時代を生き延び、拡散すらしたのである。ここのところが不思議でたまらない。
ご先祖さまが寒さに耐えるために武器となったのは、体質か、防寒技術か、気合いか、ただの慣れか、その辺が知りたいものである。
昔の人が寒さとどう戦ったのか、参考になるのが、本多勝一(ほんだ・かついち)の「極限の民族」という本である。1960年代、朝日新聞の記者だった本多氏は、カナダ北極圏のイヌイット(当時はエスキモーと呼ばれた)の暮らす村に入っていき、長期間住み込んで、その生活ぶりを観察している。
それによると、イヌイットがなぜ寒さに耐えられるかというと、防寒具がしっかりしているからである。女たちが噛んでなめした毛皮をきっちり縫い合わせ、しっかり着ることで、地獄のような寒さの中で生きられるようになるのである。仮に零下50℃の中に裸で放置されたとして、何分で死ぬかというと、イヌイットも日本人も変わらないだろうと、本多氏は述べている。(何とも乱暴な議論だが、本多氏自身がたぶんちょっと、極端な人である。)
それを読んで、少し安心した覚えがある。何だ、同じ人間じゃないか、という思いである。
しかし、その安心は、同じ本の次の報告、「ニューギニア高地人」でひっくり返される。彼らはほとんど裸で暮らしているのだが、岩場で野宿した時も、明け方にかけて4℃くらいまで気温が下がったのに、裸のまま平気で眠っていたそうである。一方、カナダの極北で鍛えたはずの本多氏のほうは、服を着ていても、寒すぎて眠れないのである。耐寒力という点では、もしかしたらニューギニア裸族のほうがイヌイットより上かもしれないと、本多氏は驚いている。
食事に秘密が隠されていると思うかもしれないが、彼らはほとんど芋しか食べていない。からだを温めてくれそうなタンパク質や脂肪は、決定的に不足しているのである。
これは無理だ。何だ、違う人間じゃないか、という思いである。
寒さ対策のヒントになるかもしれないと思い、こうして寒い話を書きはじめて見たが、余計寒くなっただけだった。春が来るまで、暖房とコートと布団に頼るしかない。イヌイットやニューギニア高地人には、「神戸の冬は、寒いとはいわない」と怒られるだろうが。
2018.1.28
|
|
名前を叫ぶ
|
手術が終わると、麻酔薬の投与を中止する。体内の麻酔薬濃度が下がってきたところを見計らって、患者さんを起こすのだが、この場合のもっとも有効な覚醒刺激は、大声で名前を呼ぶことである。
簡単な医療行為であるが、すべての医療行為には失敗の可能性がある。患者さんの名前を間違えて呼んでしまうことがあるのだ。一番多い間違いは、なぜか、主治医の名前を呼んでしまうことである。麻酔科医が大声で叫んでいる横で、主治医が苦笑いしているわけだから、これはちょっと恥ずかしい。
若い男性麻酔科医が、間違ってナースの名前を叫んでしまったことがある。彼はあとで、「病棟から患者を迎えに来たナースが、かわいいと思ってた人なので、つい間違えて呼んでしまった。恥ずかしい」と顔を赤らめていた。たしかにこれは、かなり恥ずかしい。問うに落ちず、語るに落ちず、叫ぶに落ちた、といったところだろうか。
もっともこの男は既婚者なので、その後何か進展があったわけではない。あったら困る。
忙しかった一週間の終わり、金曜日の最後の医療行為が終わった後、嫌いな人の名前を叫んで締めくくってみてはどうかと、私は研修医に提案することがある。すると研修医たちは一様にとまどいの色を見せ、次のように言い逃れようとする。
「いえ、いい研修をさせてもらって、いやな思いをすることもありません」
「苦手な先生はありません」
「看護師さんも、同僚も、いい人ばかりです」
そこで私がお手本を見せることにする。「じゃあ行くでー、足利尊氏っ!」
研修医は拍子抜けして言う。「え、足利尊氏って、そういうのでよかったんですか?」
「蘇我入鹿でもかまわんよ。誰が『身の回りの嫌いな人』と限定したかね。そうやって、職場に嫌いな人はいませんと、あわてて打ち消しにかかるほうが怪しい。じっくり話を聞こうやないか」
みなさんの職場でも、試してみてほしい。
2018.1.21
|
|
大丈夫?
|
最近私は、「だいじょうぶ」という言葉が気になっている。若い人が使うとどうも、我々とは少し意味合いが違うようだ。
たとえばスーパーのレジで、「袋おつけしますか?」と聞かれた若い客が、「あ、大丈夫です。」などと答える。やんわりと断る言葉として使っているらしい。
これはまだぎりぎりわからないでもない。しかし、テレビの番組の中でバンジージャンプをやらされそうになったタレントが、「えー、大丈夫です」と断っているのを見たときは、これは新しいと思った。
否定語を一切使わないで済ませるとは、ずるい断り方があったものだ。
数年前ある研修医が、10月の麻酔科ローテート中に夏休みを取りたいと言ってきた。わざわざ10月に夏休みを取るとは思っていなかったので、油断していた。完全な人手不足である。「うーん」と苦しんでいると、研修医、「ここ、夏休みいただいても、大丈夫ですか。」と畳みかけてきた。
この使い方もちょっと新しい。 昔は、目上の人に許可を求めるときに、「大丈夫?」などとは聞かなかった。
「いや、10月は産休に入る先生もいて、麻酔科大丈夫かって言われると、大丈夫じゃないんだよね。夏休みは9月に内科で取っちゃうとか、ないのかなあ。」
私はこう返事をしたがだめだった。空気を読まなければ生きていけない、日本の気詰まりな社会を憂えている人は、喜ぶといい。今の若い人は、空気を読まないだけでなく、相手の苦しそうな表情も、自分に都合の悪い言葉も読まないようだ。
「え、でも10月じゃないとちょっと。大丈夫でしょうか?」
こう重ねて言われて、気がついた。部下の休暇取得を拒否する権限はこちらにはないのであった。
どうやら「大丈夫」の疑問形は、相手を気づかう言葉ではなく、立場の強いものが弱いものに対して使う、ただの念押しだったようだ。知らなかった。
古くからあるこんな言葉も、若者にかかればこんな具合に奇怪な変貌を遂げてしまう。うっかりしていると、足元をすくわれそうだ。たとえば、若い医師にこんなことを言ってみよう。
「うん、これは珍しい症例だ。症例報告が書けそうだな。書いてみる?」
「あー、大丈夫です。」
こういう答えが返ってきて安心していたら、痛い目にあうはずだ。待てど暮せど、症例報告の原稿は降りてこないのである。まったく油断ならない。
皆さん、大丈夫でしょうか。
2018.1.20
|
|
センター試験
|
本日、私の長女が大学入試センター試験を受けるので、卓球の練習は休むことにした。いくらのんきな私でも、娘が人生をかけて戦っているときに、ヘラヘラと球を打っている訳にはいかない。ビシッと打てばいいのかもしれないが、その能力がない。
3年前、長男がセンター試験を受けるときも練習を休んだのだが、練習仲間にはこう言われた。
「息子さんが受験しているからと言って、親が家でじっとしていても、役に立たないでしょうに」
その時私はこう答えたそうである。
「いや、試験となると何が起こるか分りません。いざとなったら、私がパンツの替えを持っていかなきゃいけませんから」
自分では憶えていないのだが、そう答えたらしい。忘れるくらいだから口から出まかせなのだろうが、なぜそこでパンツの話になるのか、誰かに教えて欲しいものだ。
今回長女が志望校に受かると、ついに夫婦二人の生活になってしまう。そうなったら、どうやれば平和な生活が送れるのか、皆目見当がつかない。今回の試験に人生がかかっているのは、彼女だけではないのである。
試験でうまくやってほしいのはもちろんだが、複雑な気持ちである。私は自宅に試験対策本部を設け、いつでも出動できる態勢を整えたが、することがないので、とりあえずお茶を飲んでいる。
2018.1.13
|
|
手術室と病棟
|
先だって記事に登場してもらった、手術室看護師のKさん、とにかく「デキる」ナースだった。
たとえば麻酔中、私がモニター画面を見て、オヤという表情になって、患者さんの手もとを見たりする。すると外回りナースのKさんは、私の視線の動きだけから、何が起こっているかを読み取る。そして、患者さんの指につけた酸素センサー(SpO2モニターのプローブ)が外れかかっているのを、さっと直すのだ。
ここで得意そうな顔をするのでは、まだまだ未熟者である。Kさんはそしらぬ顔で黙ってあちらに行く。このとき私は動揺の色を見せつつ、あ、先を越された、なぜばれた、などと思っているのであるが、Kさんとしてはそれに気づかぬふりをして、ま、気にせんといてください、というサインを送っているわけである。
ここまでの数秒間で、両者一言も言葉を交わすことなく、情報が2往復しているのだから、ややこしいことだ。だがこういうナースが、数秒を争うような手術中の緊急事態でどれだけ頼りになることか。無言のファインプレーの連続が、あきらかに結果に影響する。これが手術室看護師の力量である。
病棟は逆に、言葉の世界である。患者さんには優しく、ときに厳しい言葉をかけなくてはならないし、医師からの指示は視線や動揺の色などではなく、口頭指示とカルテの指示コメントである。
私は若い頃、大学病院のICUで、血液内科の医師2人が、担当患者の治療方針をめぐって2時間語り合っているのを見て、唖然としたことがある。手術室での仕事は即断即決が基本であるから、このような気長な医療行為が存在するとは信じられなかった。2時間もあれば、ちょっとした手術なら終わってしまうではないか。
だがその粘さこそが、病棟を本拠地とする内科医の力なのかもしれない。おそらく彼らは、言葉に言葉をかぶせていくことで、すこしずつ正解に近づこうとしているのであろう。
手術室生え抜きのKさんも、病棟という言葉の世界に異動となり、ずいぶんとまどっていることだろう。スマッシュをバンバン打っていた卓球部のエースが、なぜか文芸部に転部したようなものである。作ったこともない俳句を作らされ、
「ライバルの読みを欺く流し打ち」
などと詠んでしまい、先輩に総つっこみを入れられているような状態ではあるまいか。はやく慣れて欲しいと願っている。
2018.1.8
|