|
映画の中の麻酔、その2
|
私はそんなに映画を観る方ではないが、たまたま観た映画に麻酔がでてくると、やはり気になる。麻酔が、かなり気になる使い方をされてしまうことがある、と言った方がいいかもしれない。
ひどかったのは、たしか「彩り河」という、20年くらい前の映画である。ヒロインの名取裕子が身内のかたきをたくさんパーティーにおびき寄せ、飲み物の中にドロレプタンを入れて飲ませる。全身麻酔のときに補助的に使うメジャートランキライザー、鎮静薬の一種である。すると驚くなかれ、かたきどもが全員ふらふらとなり、名取裕子の命令に従うようになる。彼女がベランダから飛び降りるように命令しただけで、彼らは列をなしてつぎつぎと飛び降りていくのであった。
これを観た一般人は、世の中には人を思い通りにあやつれる、そんな薬があるのかと驚いたはずである。そして、自分がそれを手に入れたあかつきの、その使い道についていろいろ想像を巡らせたことだろう。いやいや、ドロレプタンはそんな便利な薬ではないのですよ。飲ませてもただ、ぐったりとなるだけだ。
人間を薬で思いどうりになどできないというのは、人類にとってはありがたい話であろう。
それから、最近あまり見なくなったが、映画の中で悪い奴が人を誘拐する時にかならず使っていたのが、相手の口をふさぐとたちどころに気を失ってしまう魔法のようなハンカチである。その作用機序から想像すると、それは揮発性全身麻酔薬、なかでも即効性の高いクロロホルムを染み込ませたハンカチなのだろう。
クロロホルムは不整脈を起こすというのではるか昔に臨床使用からはずされてしまった危険な薬である。食事して間もない人であれば、嘔吐による窒息も怖い。そんな薬を、数秒で失神するほどの高濃度で使うのであるから、3回に1回くらいは被害者が死んでしまってもおかしくない。犯人達はそれくらい覚悟して誘拐を計画しているのだろうか。
映画やドラマを作る人が、都合のいい時だけ麻酔を魔術のように使うのは、勘弁してほしいものだと思う。へんな人がへんな妄想を抱かねばよいが、と心配になる。
2009.12.4
|
|
午後の曳航
|
「麻酔とは」コーナーを書き足していて思い出したのが、「午後の曳航」という映画である。30年くらい前の外国の映画だが、原作は三島由紀夫らしい。この中の「麻酔」シーンが素人さんの麻酔観を表していて面白い。
古い映画なのでネタバレも許してもらえると思う。多感な少年が主人公のこの物語は、少年が友人たちの力を借りて母親の恋人に麻酔薬を混ぜた紅茶を飲ませ、生きながらの解剖を始めるところで終わる。その結末の強烈さについては置いといて、問題は経口投与した麻酔薬で生体解剖、つまり手術が可能かということである。
この麻酔薬は、医師宅から盗んできたものだが、ちょっと眠くなるくらいの量を飲ませても、手術などは絶対にできない。メスを入れた途端に目を覚まし、
「何するんじゃ」
と子供たちを怒鳴りつけるはずである。
ではたくさん飲ませたらいいのではないか。紅茶が苦くてバレバレだろうが、それでもなんとかだまして飲ませたらどうなるかというと、呼吸が止まってそれだけで死んでしまう可能性が高い。死なないけど、切っても動かない分量をきっちり飲ませる、そんな芸当は少年たちには無理だろう。私にもできない。胃や腸からの吸収は不確実、不安定で、麻酔薬投与の経路としては全く適さないのである。また、人工呼吸の技術なしにそれだけの麻酔を与えることもむずかしい。現在の麻酔では、麻酔薬は静脈(つまり点滴)と気道(つまり吸入)を使って投与し、人工呼吸を行う。だからこそ安全に行えるのである。
世界初の全身麻酔とされる華岡青洲の麻酔は、経口投与だったようである。これは神業的さじ加減だったと言わざるを得ない。しかし、本当に現在の全身麻酔のような完全な無意識、無痛のものだったかどうか、それは分からない。また、実験台となった妻が失明したように、麻酔が多過ぎての失敗もなかったはずはなかろうと思う。
30年経っても私が覚えているくらい、非常に印象的な映画だった。その現実離れした内容から言っても、思春期の少年の心のどろどろに形を与えてみたという映画なのだろう。そんな映画の中で麻酔が便利な小道具として使われていたので、ちゃちゃを入れてみたくなった。
2009.10.10
|
|
業務日誌
|
大津赤十字病院は私の麻酔科人生の原点である。私の研修医当時の部長、N先生はかなり個性的な「濃い」麻酔科医だったが、私にとってはよい上司であり、いろんな意味でもっとも影響を受けた先輩である。その後の私の麻酔科医としてのスタイルはN先生とは違うものになってしまったが、今でもしばしば、私の中でN先生がぬらりひょんのようにお茶をすすっておられるところに出くわすのである。
N先生はその日の手術がおわってもすぐには帰らず、いつも自分の机に向かって何かノートに書き付けておられた。一日の手術室を振り返って、起こったことを逐一記録しているのだろうと思った。普段は「麻酔が命」という感じではなかったが、こういうところはきっちりしておられるのだと、ひそかに感服していた。
 さて時が経ち、私が気楽なヒラ麻酔科医生活に別れを告げて、麻酔科の長として部下を持つ身になったとき、自分などが麻酔科を一つ預かってしまってよいのだろうかと、ずいぶん緊張した。こういう時に頼りになるのが、自分の中に住んでいるN先生である。机に向かうあの後ろ姿を思いだし、よし形から入ろう、業務日誌をつけるのだ、と思いついた。別に麻酔科を仕切ることと業務日誌は直接の関係はないのだが、N先生の後ろ姿こそが私にとっての麻酔科部長の姿だったのである。
さて時が経ち、私が気楽なヒラ麻酔科医生活に別れを告げて、麻酔科の長として部下を持つ身になったとき、自分などが麻酔科を一つ預かってしまってよいのだろうかと、ずいぶん緊張した。こういう時に頼りになるのが、自分の中に住んでいるN先生である。机に向かうあの後ろ姿を思いだし、よし形から入ろう、業務日誌をつけるのだ、と思いついた。別に麻酔科を仕切ることと業務日誌は直接の関係はないのだが、N先生の後ろ姿こそが私にとっての麻酔科部長の姿だったのである。
後年、N先生にお会いしたときに、
「私も先生を見習って業務日誌をつけています。」
と言ったところ、思わぬ返事が帰ってきた。
「ああ、あれはただの日記や。前の晩にどこに飲みに行ったとか、何を食ったとか、そういうことばかりで、仕事の話なんか書いとらん。」
偉大なり、N先生。自分ではまったくその気がないのにもかかわらず、後ろ姿だけで後進を導いていたのであった。
業務日誌は今も続けている。
2009.9.13
|
|
「お疲れさまです」
|
病院の廊下で職員とすれ違うとき、
「お疲れさまです」
と声をかけてくれることがある。一日のうち何度顔を合わせても、毎回これを言ってよこす律儀な研修医もいる。が、実は私は、これにはどうもなじめないでいる。
昔からこうだっただろうか、いや違う気がする。朝は「おはようございます」だが、それ以降は黙って会釈だけだったと思うし、それでいいじゃないかと思う。インターネットで「お疲れさま」を検索してみても、最近この挨拶が増えて気持ち悪いとブログで嘆く中高年の方が幾人もおられるので、最近の風潮であると言っていいと思う。
私の感覚では、「お疲れさま」は、自分や人が帰宅するときにかける言葉であり、仕事中の人にかける言葉ではない。休憩中にこう言われるのならまだわかるが、日中に廊下を歩いているときに言われるのは残念である。ましてや、仕事の連絡だと思ってとった院内PHSから、いきなり「お疲れさまです」という声が飛び込んできたら、思わず通話終了のボタンを押しそうになる。つまり、こちらが気を張って仕事している最中に、「疲れてますよね」と疲労感を自覚させてどうするんだ、ほっとけよ、といいたいのである。
「お疲れさまです」を英語に言いかえてみると、
”You must be tired"
である。ケンカを売ってるようなものである。
ただの挨拶なんだから意味なんかない、と本人たちは思っているようだ。だが、「こんにちは」や「さようなら」ほどこなれていないこの挨拶には、やはり十分意味が残っていると思う。その意味に込められるのは、相手を気遣って見せることでちょこっとポイントを稼ぎたいという意識下の心理なのではないだろうか。考えすぎかな。そしてあいさつを受けたわたしの残念な気持ちの中には、通りがかりの人に気遣われてしまったという軽い失望も含まれているのだろう。これはひがみすぎか。
 さて、そのあいさつにどう返すかがむずかしい。
さて、そのあいさつにどう返すかがむずかしい。
「お疲れさまです」は意地でも言わない。
「あのね、この朝っぱらから疲れてるわけがないでしょう」と一度言ってみたいところだが、そこまで因業なおやじにはなれない。そんな暇もない。
例の研修医に、一日なんども挨拶するな、と言ってみたが、「いやあ、癖ですから」と軽くいなされて終わってしまった。
しかたがないから、「…でーす」とか、「うーす」とかいってごまかしているのである。トホホ。
2009.9.11
|
|
臨死体験その2
|
臨死体験の話はとにかく放っておけないので、つづくのである。
全身麻酔中の体外離脱は自分の臨床経験の中にはないが、臨死体験をしたことがある、という患者さんに出会ったことは2、3回ある。いずれも術前の診察やペインクリニックで問診をしたときに出てきた話である。そういうときは、くわしく話を聞かせてもらうことにしている。
たとえばある女性は、薬のアレルギーを起こして家で意識を失っている間に、それはそれはきれいなお花畑のようなところにいったという。するとすでに亡くなっていた妹が出てきて、
「あんたはまだこんなところに来たらあかん。帰れ。」
ときつく言われて戻ってきたとのことである。まさに典型的な臨死体験である。
ただ、私が話を聞いたいずれの方も、心臓が一旦止まってご臨終ですと言われるほどの臨死ではなく、単に血圧が下がって意識をうしなっていた状況と思われた。私の感覚で言えば、医学的に死と言えるほどの状況に陥って体験した話ならば、魂がそういうところに行ったのかな、と納得するのだが、血圧が下がっただけで魂が浮いてしまったりするものだろうか、と疑問を感じるのである。逆に、明らかに心臓が止まってしまってから蘇生した人の中からそういう話を聞いたことは、私はない。(もちろん立花隆の本の中には出てくるが)
これはやはり、脳の血流が低下したときに見る夢や幻覚のようなものと考える方が自然ではなかろうか。完全に心臓が止まってしまっては、夢は見られないということではないだろうか。
私が臨死体験の話に惹かれる理由の一つは、それが、人間はからだが滅びても霊魂が生きつづけるということの科学的な証明につながる可能性をもつからである。しかし理系人間のはしくれとしての私が自分のまわりで見聞きする範囲では、霊魂の存在を証明しうるような事例はひとつもない。もしそれが、20年の臨床経験でも出会わないほどのものだとすると、臨死体験は科学の対象にするにはまれすぎる。科学の本質は再現性、つまり誰がやっても同じ結果や結論が得られるという点にあり、起こるか起こらないか分からない、まれすぎる現象は科学の対象にはなりえないのである。
本当は霊魂の実在を証明する必要などないのであろう。死に瀕した人が美しい体験をする、それだけでいい、臨死体験の話はきわめて興味深い。
2009.9.5
|
|
臨死体験
|
「腰麻サロン」で少し触れたが、十数年前に立花隆(田中角栄を首相の座から引きずりおろしたジャーナリストね)が「臨死体験」という番組を作りNHKで放送し、話題になった。文春文庫からも分厚い本が出て、大変興味深く読んだ。
臨死体験とは、死の間際まで行って生き返った人が語る体験談で、体外離脱、まばゆい光、その後のお花畑、すでに亡くなっている近親者との出会いなど、文化の違いを超えてかなり共通した内容をもつとされる。本当に魂がからだから抜け出してそういう体験をするのか、血圧が低下して脳血流が下がったときにそういう幻想を見ているのにすぎないのか、立花氏もそこのところは分からないとしている。そういうところは、さすがにそこらへんのオカルト愛好家とは違うのである。ただ、体外離脱して上から自分や自分のまわりをみたという人の中に、本当に上から見たのでなければ知り得ないようなことを言うという事例を、立花氏は熱心に紹介しているから、魂が存在する方がうれしいという気持ちはあるのだろう。
 その体外離脱話の中に、麻酔科医としては聞き捨てならぬ話がいくつか出てくる。
その体外離脱話の中に、麻酔科医としては聞き捨てならぬ話がいくつか出てくる。
一つは、心臓外科の手術中に上から自分の心臓を見て、意外に白いなと思ったという話。素人なら心臓は赤いと思っているはずだが、実際には脂肪に覆われて白いわけで、それを知り得たというのはほんとに見たからじゃないかというのである。外科医のしぐさもただしく指摘したらしい。心臓外科の手術というのはたいてい心臓を止めて手術しているわけで、それが死に近い状態だからというので体外離脱してしまったのかもしれないが、心臓を止める度にそんなことが起こったらわれわれとしてはちょっと困る。実際、心臓外科の患者さんから術後にそういう指摘をされたことが私は一度もない。もしそういうことが起こるとすれば、きわめてまれな事例ということになる。
もう一つは、患者さんが頚部の手術を受けている最中に自分の手術を上から眺めており、あ、そこは危ないと思った瞬間に頚動脈から大出血したという話。これなどは、大出血するまえは死の手前でも何でもなくただの全身麻酔状態であるから、そんなのでも「上から目線」になってしまったというのだから恐ろしい。ところがやはり、私はこれまでに1万件を超える全身麻酔に関わっているはずだが、そのような報告は受けたことがないのである。その中には、真に死線を越えかかってしまったケースも数え切れないほどあるのだが、そういう人たちからもそんな話は聞いたことがない。全身麻酔中の体外離脱というものがあるとすれば、心臓外科のそれよりさらにまれな事例と思われる。
この番組を見てしばらくは、麻酔中にふと天井を見上げて「あの辺かな」などと目を凝らしてみたこともあるが、いまではすっかり諦めてしまった。
それにしても、この道20年の私が出会ったことのない奇跡的な事例を、立花隆はどうやって集めたのだろうか。それが不思議だ。
2009.8.29
|
|
脊椎麻酔伝説
|
脊椎麻酔で気になっていることをもうひとつ。
麻酔を予定された患者さんには、前日に診察と麻酔の説明を行う。脊椎麻酔を予定された患者さんに対しては、
「背中から注射しますので、そのときだけちょっと痛いですよ。」
と説明するのだが、4人に1人くらいの方からつぎのような言葉が返ってくる。
「あれ、相当痛いんでしょ。その麻酔されたことのある知り合いが言うてましたわ。」
と、なぜか顔までしかめているのである。きっとその知り合いは、顔をしかめながら教えてくれたのだろう。
 たしかに脊椎麻酔の針がなかなか入らず、結果的に痛い思いをさせてしまうこともたまにあるのだが、脊椎麻酔が痛いと教えられる人のほうがはるかに高率であるという印象を抱くのである。なぜそうなるのか、考えてみる。
たしかに脊椎麻酔の針がなかなか入らず、結果的に痛い思いをさせてしまうこともたまにあるのだが、脊椎麻酔が痛いと教えられる人のほうがはるかに高率であるという印象を抱くのである。なぜそうなるのか、考えてみる。
一つは、昔はかなり太い針(22-23ゲージ)を事前の局所麻酔なしで使っていたという事実がある。しかも昔の医者は偉かったから、「動いたらあぶないよ」とこわいことをいうことがあった。これはほんとに痛かっただろうと思う。だから、「20年前に盲腸の手術で脊椎麻酔を受けた」という人の体験談は、今はあまり参考にならない。
もう一つは、こういう話は大きくなりやすいということである。自分でもちょっとめずらしい体験を人に話すときは、ものの数などはたいがい倍になってしまうから、痛みも倍や三倍になってもおかしくないと思う。
もし自分に時間と根性があれば、その「知り合い」の方をかたっぱしから訪ねあてていろいろ聞いてみたい。いつの時代のことか、ほんとに痛かったのか、どれくらい痛かったのか、その経験をこれから手術を受けようとする方に顔をしかめながら(想像ですが)説明するのはどういう親切心からなのか。ちょっと残念な気持ちがはいりすぎでしょうか。
2009.8.23
|
|
腰麻サロン
|
足や下腹部の手術でよく使われるのが脊椎麻酔である。背中から注射針を穿刺して脊髄を浸す脳脊髄液の中に麻酔薬を注入し、下半身だけを無感覚、不動にする方法である。日本麻酔科学会はいつの間にか”脊髄くも膜下麻酔”という呼称を使うようになっているが、言いにくくてしかたがないし麻酔科以外では通じないので、どうしても脊椎麻酔、腰椎麻酔あるいは略して腰麻(ようま)と呼んでしまう。
さて面白いことに、脳には影響がない麻酔のはずなのに、この麻酔を受けると何割かのかたが手術中に眠ってしまう。とくにご老人では多い。しかもこれがかなり気持ちよさそうな眠り方で、手術が終わって呼びかけてみると、
「ああ、なんか眠ってしもうてた」
と、すこし名残り惜しげに目を醒まされる。
なぜ眠るのか、はっきりした理由は分からないが、下半身の感覚が消失することで意識を保つのに必要な刺激がたりなくなるのであろう。暗い、暖かい部屋で理解できないスライドを見せられると私などは直ちに入眠してしまうが、それと同じ原理だと思う。
立花隆の"臨死体験”という本の中で、似たような話が紹介されている。ある変わった研究者が、肉体の受けるあらゆる刺激を遮断しても意識というものが残るのかどうか、突き止めようとした。魂が肉体から独立して存在しうるのかどうかという哲学的な問題に挑戦したわけである。その研究者は生温かいどろどろの液を満たしたカプセルの中に入り、音も光もさえぎって、自分の意識に何が起こるかを試した。その結果はたしか、意識の体外離脱感や幻覚などが体験されたという話だったと思うが、それが、スライド中に居眠りしながら私が見る短い夢とどう違うのか、私にはわからない。自分の魂を見てやろうという人がカプセルの中に入るのであるからいろんなものが見えるのかもしれないが、私だったらやはりまっすぐに入眠すると思う。
 腰麻も薬の量しだいでは胸まで麻酔が効いてしまうことがある。さらに上位まで効くと全脊麻といって、意識を失うと言われている。これはまさに、その無刺激カプセルと同じ効果ではあるまいか。とすればこれを目的とした麻酔もありじゃないかという邪念が頭を横切るのである。駅前に「腰麻サロン」なるものを開業し、
腰麻も薬の量しだいでは胸まで麻酔が効いてしまうことがある。さらに上位まで効くと全脊麻といって、意識を失うと言われている。これはまさに、その無刺激カプセルと同じ効果ではあるまいか。とすればこれを目的とした麻酔もありじゃないかという邪念が頭を横切るのである。駅前に「腰麻サロン」なるものを開業し、
「究極のリラクセーション、魂との出会い」
などと宣伝するのである。お客様にはしっかり腰麻を効かせ、心地よい音楽のなかで横たわっていただく。世の中には好みのビタミンを補給できる点滴パーラーみたいなのがあると聞くし、腰麻サロンだってあってもいいんじゃないか。
ま、よくないわな。
2009.8.13
|
|
麻酔科医は変人か
|
麻酔科医には変人が多いというイメージが、どうも強いようである。人を眠らせることを職業にするなんて、よほどの変人や人間嫌いではないか、などと思われるらしい。一般人が漠然とそう思うのならしかたがないが、他科の医師からもそう思われているふしがある。人間としゃべるのが嫌だと思う人が麻酔科を選ぶんでしょと、外科医に面と向かって言われたこともある。
人間嫌いというのはいわれなき誹謗である。麻酔科医だって術前診察で患者さんとしっかり喋らなくてはならないし、外科医や看護師とのコミュニケーションが上手にとれないようでは、麻酔科医としての能力に問題がある。しかし、麻酔科医が変人かどうかというと、ちょっと否定しきれない気持ちが、自分の中にはある。
大体、医師が自分の専門を選ぶことに何の制約もないのに、なんで「患者さんを治す」ほうでなく「眠らせる」ことを選んでしまうのか。若い医師が麻酔科を志望すると聞いたら、つい、ちょっと変わった奴、と思ってしまう。自分が麻酔科を選んだのは、人の生命活動をそっくり預かってしまうという仕事におもしろさとかっこよさを感じたからであるし、今でもその選択に納得しているが、みんなが当たり前のように歩く道を自分は選びたくないという生来のへそ曲がりも、その選択に影響していたことは間違いない。
麻酔科こそ病院の根幹、ドクター・オブ・ドクター、医師の王道だ、という主張をするひともあるし、それも一理あると思う。しかし、私自身はそのような麻酔科像に自分をあてはめる気にはどうもなれない。麻酔科医たるもの、ちょっと変わっていると思われているくらいでいいのではあるまいか。「治す」人たちと少し違う視点を持ち、そこから見える景色を提供できる存在、そういう麻酔科医像のほうに魅力を感じてしまうのである。
水族館でイワシなどの群れる魚を見ていると、ときどき一斉に泳ぐ向きを変えるのであるが、だれがどう指揮をとっているわけでもなさそうである。わたしの想像だが、群れの動きを決めるのは先頭中央にいる一匹の号令でなく、はぐれかかった一匹のちょっとした動きなのではないか。人間界でも、麻酔科医のような少しずれた人の意見が集団に決定的な方向性を与えるということは、大いにありうると思うのである。
集まれ、変人!
あ、普通の人もね。
2009.7.18
|
|
ホームページを見てもらうには
|
何でもやってみないとわからないもので、自分のホームページを見てもらうのに努力が必要なものだとは思わなかった。つまり、ホームページの検索サービスというものがある以上、自分のつくったものがどんなにマイナーな分野のものであっても、興味が一致しさえすれば検索で当ててもらえるはずだ、そう思っていたのである。具体的に言うと、神戸西市民病院麻酔科に興味がある研修医、ネコマタと一反もめんの交友関係に興味がある人、こういう人がたまたま検索サイトを通してわがホームページを訪れるという奇跡のような出会い、そういったものを期待していたのである。これはまったくの幻想であった。
このホームページを開設して4ヶ月近いが、どんな検索サイトでやってみても、自分のホームページは全く当たらないのである。Googleは登録申請した当初は検索できるようになっていたのだが、だんだん当たりにくくなり、とうとういかなるキーワードを用いてもヒット不可能になってしまった。他の検索サイトなど、最初からかすりもしない。今のところこのホームページを世間に知らせる努力は全くしていないため、誰かがここにたどり着くためには、まったくの偶然でWebアドレスをタイプしてしまう以外にはありえない。船が通りかかるのを待つロビンソン・クルーソーのようなものである。
それにしても、検索サイトというものはどういう仕組みになっているのだろう。検索ロボットとやらが無差別にWebアドレスを拾いまくって検索用データベースを作るのだと聞いていたが、どうも違うのではないか。無差別だとすると、いったんこのホームページを登録した Google が、ふたたび登録からはずすということはしないはずではないか。とすると、内容とかヒット数とかその他一般人にはわからない何かを元にして、ホームページを選別しているということになる。ただ便利に使っていただけの検索サイトだが、いろいろウラがありそうである。
それはともかく、ホームページというものは見てもらうために存在するものであるから、さすがに多少は営業活動も必要かと思い始めた。かといって知り合いにアドレスを知らせて、「見てください」というのは気がひける。とりあえず、プロバイダーの会員サイト紹介に登録してみよう。
2009.7.3
|
|
学会発表について
|
自分の学会発表くらいで世の中が変わるものではないと分かってはいるが、せっかく発表するのであれば聞いてくれる人に感心してもらいたい、せめて、「へえ」くらいは言ってもらいたいのが人情である。そのためにめんどくさい準備だってするのである。だから、発表のときに何が悲しいといって、会場から質問も意見もなにも出ないことくらい悲しいことはない。
そういうときは司会の先生が、なんとか絞り出すようにして何か質問を出してくださるのであるが、その1回のやりとりだけで司会の先生も会場も、これで義理は果たしたという安堵の色を隠そうともせず、「では次の演題に」とやられると、ますますがっかりする。
ポスターセッションなどは、よほどおもしろそうなテーマのものでなければ、どうせ発表者とその知り合いだけがあつまってお互いの発表を聞き合うのであるから、もうすこし仲間意識みたいなのがほしい気がする。自分の発表が済んでも、セッションが終わるまで帰らないのは当然として、なるべく質問を出し合うようにすれば、セッションが盛り上がって発表準備の苦労も報われるというものではないだろうか。
反対に、学会をはなからバトルの場として設定するのも面白いかもしれない。適当に似たテーマ同士の発表で対戦させて、勝ちか負けか、審判員が判定をくだす。勝てばもちろんうれしいし、負けても、「あんな卑怯な手を使いやがって」とか何とか、打ち上げ会で負け惜しみをいう楽しみがある。今の世の中はなんでもランキングだから、麻酔科学会のランキングもできるだろう。ランキングを少しでもあげるために、ポスターのデザイン技法、印象的な発表法の勉強はもとより、あげあし取り、ギャグ、聞こえないふり、メーキャップなど、小技の練習にも日々精進がかかせない。
これは麻酔どころではないな。
2009.6.21
|
|
血液型性格判断
|
血液型から性格を判断しようなどというのは、もとより医学的にはまったく根拠のないエセ科学の最たるものである。私はむかしから、この話題になると、「はあ」とか「そうですかね」くらいしか返事をしないことにしている。ところが、科学者のはしくれであるはずの医師のなかにも、この手の話が好きな人は意外に多いのである。
先日、シニアクラスの医師同士の酒の席に出席したところ、やはりこの血液型の話になり、私以外の人たちは結構もりあがっていた。医師だけに変なところに診断能力を発揮し、
「あの人はA型だけど、ちょっといい加減なところもあってO型寄りだから、遺伝子的にはAO型じゃないかと思う。」
などと、想像をふくらませたりしている。こういった議論を黙って聞いていると、どの血液型にもこれぞ何型、という典型例があるらしいのだが、そうでない亜型もかならず存在しているようで、むしろどっちかというと亜型のほうが多いように感じられ、そんなこと言い出すとなんでもありじゃないか、と私などは思うのだがどうでしょう。
 まあもしかしたら、酒の席を手っ取り早く無難にもりあげるには、血液型ネタはもってこいなのかもしれない。つまり、みんなぜんぜん信じていないけど、信じているふりをしているし、それをお互いわかってやっている、というわけである。
まあもしかしたら、酒の席を手っ取り早く無難にもりあげるには、血液型ネタはもってこいなのかもしれない。つまり、みんなぜんぜん信じていないけど、信じているふりをしているし、それをお互いわかってやっている、というわけである。
たしかに、仕事中に血液型性格判断を活用している医師は、私はいまだ見たことがない。私の尊敬する麻酔科のある大先輩も、あらゆる人物の性格、行動パターンを血液型から完璧に説明してしまう名人であるが、それほどの血液型の大家であれば、輸血の際に患者さんの性格から血液型を診断することなど何でもないことであるはずだ。だがそうはされないところをみると、あれはただの趣味だということか。
やっぱり、みんな、うそとわかってて楽しんでいるのである。ただ人の噂話がしたいだけなのである。ああなんと、大人というのは奥が深いのだろう。わたしにはとてもまねできない。
2009.5.30
|
|
医師の悪筆
|
医師には悪筆の人が多い。忙しい中でカルテや処方箋になぐり書きしているうちに習い性となり、乱暴な字が手に染み付いてしまうのではないだろうか。字がきたないどころでなく、ほとんど社会に対する挑戦としか思えないような、判読不可能な字を書く人もいる。なかでも横綱級だったのが、以前勤務していたある病院のI先生だった。
カルテの字が読めない、これはよくあることである。自分が読めればいいという油断がどうしても入るからである。しかし、I先生の場合他科への依頼箋、つまり他の医師へのお願いの手紙、これも読めなかった。字がすべてつなかっていて、文字数すら判然としない。それでも長いつきあいのなかでところどころは解読できるようになるので、わからない部分を想像で埋めていくことはできる。だが、どうしてもお手上げだったのが数字である。検査データとか、日付とか、こればかりは想像で埋められるものではない。それなのに、やはり全部つながっていて、読めないのであった。
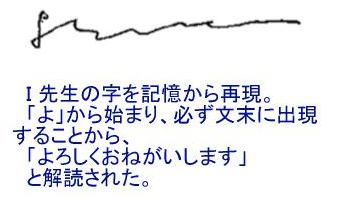 その病院が電子カルテ化したとき、I先生の書いた依頼箋がスラスラ読めるようになったという現実にはなかなかなじめなかったものである。
その病院が電子カルテ化したとき、I先生の書いた依頼箋がスラスラ読めるようになったという現実にはなかなかなじめなかったものである。
I先生の字にはずいぶん悩まされたが、ご本人はたいへんさばさばしていい先生だった。他にも、すべての面で尊敬に値するすばらしい医師が、ぐちゃぐちゃな字を書いたりするケースはけっこうある。逆に、字は美しいがあまりお近づきになりたくない医師もいる。
こうして見ると、字を見てその人の人間性とか値打ちとかを判定したりなど、しないほうがよさそうである。「字は人をあらわす」というのは、子供にきれいな字を書かせたい大人が言う、脅し文句に過ぎないという気がする。
2009.5.16
|
|
全人類単一クローン化計画
|
麻酔科医にとって、患者さんの体質の個人差は大敵である。同じ麻酔を行っているのに、人によって妙に醒めにくかったり、おかしなことがおこったりすることがある。麻酔科医の仕事を楽にするために、じゃなくて、安全な麻酔管理のために、患者さんの個人差をなくす方向で考えてみたいものである。そこで、全人類を単一クローン化してはどうだろう。
手段は思いつかないが、麻酔にかかりやすく醒めやすい人を選び、世の中をそのクローン人間ばかりにしてしまうのである。すべての人間が同じ体質であるから、ラクチンなこと、じゃなくて安全なことこのうえない。あのひとも、このひとも、みんな同じ顔だから面白みのない世界になるかもしれないが、安全な麻酔のためならやむをえない。
わたしのほら話を聞いてくれたある研修医、こう忠告してくれた。
”でも、ウイルスとか何かの病気が流行したら、いっぺんに人類滅亡しますよ”
なるほどすべての人が同じ体質だから、そういうことになるわけである。こうして、私の野望は打ち砕かれたのであった。
2009.5.3
|
|
麻酔科医の喜び
|
”麻酔科医として一番うれしいのはどういうときですか?”
と、研修医から聞かれたことがある。科を選ぶときの参考にしようというのであろうが、なかなかこしゃくな質問である。そのとき答えたのは、
”人がやってできなかった手技を自分が成功させたときかな。その手技に命がかかってくることもあるしね”
というような内容だったと思うが、どうもあまりいい答えではない。若気のいたりである。今同じ質問を受けたとしたら、迷わず、
”仕事が終わって帰るとき”
と答えるだろう。
麻酔科医は、手術を受ける患者さんを無事病棟にお帰しするのが仕事であるから、何かすごいことをして評価されるのではなく、何も起こさなかったことで評価される、そういうたぐいの仕事をしている。なにかつまらない仕事のようにも聞こえるが、手術や麻酔というのは言ってみれば患者さんのからだにとってはピンチの連続であり、それを”何ごともなかったかのように”切り抜けるために、一言では言えないが麻酔科医は冷や汗かきながらまあいろいろやっているのである。一日の仕事が終わって、特に心配事が残っていないとすれば、麻酔科医としてはでかしたと言えるのである。帰るときに、やれうれしい、と思うのは自然なことだ。
こうして、一日一日、きっちりと仕事を終えることができるのは、麻酔科の魅力でもある。
ところで、他の科の先生方は患者さんが退院されるとき、”ありがとうございました”と感謝されるときがうれしいのだと聞く。しかし、退院の時に麻酔科に挨拶に来られる患者さんはまずないし、仮に来られたとしても私が治したわけではないから、照れくさいばかりである。
くだんの研修医氏、参考になるでしょうか?
2009.4.19
|
|
麻酔科医とは何者か
|
わたしが麻酔科に進むといったとき、父は驚いて言った。
「患者をむりやり眠らせて手術するんじゃろうが。そがいな殺生な仕事するやつがおるか」(広島弁)
麻酔を殺生な仕事と言われたのはこのときが最初で最後であるが、父のような一般人からは麻酔科医というのがわかりにくい、不気味な仕事と受け取られるのは無理もないことであろう。
麻酔科医というのは医師のなかでも特殊な職種である。診断もしないし、治療もしないように見える。本当は分単位、秒単位で診断と治療を繰り返しているとも言える仕事であるが、周囲がそう思っているかどうかは別の話である。手術のお膳立てという裏方仕事の、何が楽しいのだろうくらいに思われているのではあるまいか。裏方も必要だからやっているのだ、という麻酔科医もいるかもしれないが、そういう自己犠牲の精神ばかりではこの仕事はとても続けられないだろう。やはり、自分では気づいていないかもしれないが、麻酔科医はそれなりに仕事を楽しんでいるのだと思う。
というわけで、このホームページの中では気が向いたときどきに、麻酔科医という職業を私なりに解説してみたいと思う。リクルート目的というにおいも漂うが、まあ許してください。
2009.4.12
|


 さて時が経ち、私が気楽なヒラ麻酔科医生活に別れを告げて、麻酔科の長として部下を持つ身になったとき、自分などが麻酔科を一つ預かってしまってよいのだろうかと、ずいぶん緊張した。こういう時に頼りになるのが、自分の中に住んでいるN先生である。机に向かうあの後ろ姿を思いだし、よし形から入ろう、業務日誌をつけるのだ、と思いついた。別に麻酔科を仕切ることと業務日誌は直接の関係はないのだが、N先生の後ろ姿こそが私にとっての麻酔科部長の姿だったのである。
さて時が経ち、私が気楽なヒラ麻酔科医生活に別れを告げて、麻酔科の長として部下を持つ身になったとき、自分などが麻酔科を一つ預かってしまってよいのだろうかと、ずいぶん緊張した。こういう時に頼りになるのが、自分の中に住んでいるN先生である。机に向かうあの後ろ姿を思いだし、よし形から入ろう、業務日誌をつけるのだ、と思いついた。別に麻酔科を仕切ることと業務日誌は直接の関係はないのだが、N先生の後ろ姿こそが私にとっての麻酔科部長の姿だったのである。 さて、そのあいさつにどう返すかがむずかしい。
さて、そのあいさつにどう返すかがむずかしい。 その体外離脱話の中に、麻酔科医としては聞き捨てならぬ話がいくつか出てくる。
その体外離脱話の中に、麻酔科医としては聞き捨てならぬ話がいくつか出てくる。 たしかに脊椎麻酔の針がなかなか入らず、結果的に痛い思いをさせてしまうこともたまにあるのだが、脊椎麻酔が痛いと教えられる人のほうがはるかに高率であるという印象を抱くのである。なぜそうなるのか、考えてみる。
たしかに脊椎麻酔の針がなかなか入らず、結果的に痛い思いをさせてしまうこともたまにあるのだが、脊椎麻酔が痛いと教えられる人のほうがはるかに高率であるという印象を抱くのである。なぜそうなるのか、考えてみる。 腰麻も薬の量しだいでは胸まで麻酔が効いてしまうことがある。さらに上位まで効くと全脊麻といって、意識を失うと言われている。これはまさに、その無刺激カプセルと同じ効果ではあるまいか。とすればこれを目的とした麻酔もありじゃないかという邪念が頭を横切るのである。駅前に「腰麻サロン」なるものを開業し、
腰麻も薬の量しだいでは胸まで麻酔が効いてしまうことがある。さらに上位まで効くと全脊麻といって、意識を失うと言われている。これはまさに、その無刺激カプセルと同じ効果ではあるまいか。とすればこれを目的とした麻酔もありじゃないかという邪念が頭を横切るのである。駅前に「腰麻サロン」なるものを開業し、 まあもしかしたら、酒の席を手っ取り早く無難にもりあげるには、血液型ネタはもってこいなのかもしれない。つまり、みんなぜんぜん信じていないけど、信じているふりをしているし、それをお互いわかってやっている、というわけである。
まあもしかしたら、酒の席を手っ取り早く無難にもりあげるには、血液型ネタはもってこいなのかもしれない。つまり、みんなぜんぜん信じていないけど、信じているふりをしているし、それをお互いわかってやっている、というわけである。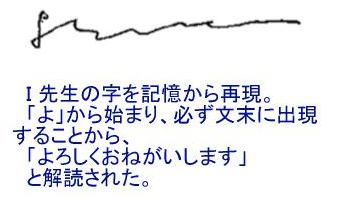 その病院が電子カルテ化したとき、I先生の書いた依頼箋がスラスラ読めるようになったという現実にはなかなかなじめなかったものである。
その病院が電子カルテ化したとき、I先生の書いた依頼箋がスラスラ読めるようになったという現実にはなかなかなじめなかったものである。