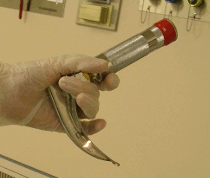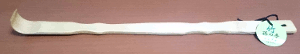こぼれ話集
新人の時から8年間、手術室ひと筋で勤務してきたKさんという優秀なナースが、この秋、他の病棟に異動した。この人は、ここで以前紹介した「笑う業務日誌」(2017/1/14)のきっかけを作ってくれた人だったので、私は自分の8年間の業務日誌の中から、ちょっとおもしろいこぼれ話だけ集めて、小冊子にしてプレゼントした。
2017.12.31
鉄道愛
恥ずかしながら、帰ってまいりました(45年前の流行語)。弁明も口上もないまま、年末みなさんが忙しい時をねらって、ひっそりと再開します。どうか、誰にも気づかれませんように。
汽車が山道をゆくとき
朔太郎はたった3行で、鉄道の楽しみを大体語り尽くしている。少なくとも大正時代にはすでに、鉄道は日本人の心だったことがわかる。
2017.12.29
ボールペンのゆくえ
医師にとって、ボールペンは欠かせない商売道具である。電子カルテの時代になっても、最後は麻酔同意書を作るときに、こちらと患者さんのサインが必要だから、ボールペンを使う。
2017.7.30
お知らせ
当サイトの更新をしばらく休みます。飽きが来たというか、ネタ枯れというか。再開するとしたら1ヶ月後か、1年後か、自分でも予想がつきません。1万年後ではないことを祈ります。
2017.6.25
家族欄
カルテに記載される個人情報の中で、宗教と並んでもっとも重要なものが家族構成である。その患者さんのキーパーソン(最初の連絡先)が誰か、という情報は、主治医や病棟の看護師にとっては欠かせないものである。
2017.6.25
老人力
私はこの春、麻酔科医になって30年目を迎えた。誰かがお祝いとか、ごほうびの金品などをくれるかもしれないと待っていたが、誰も何もくれなかった。
2017.6.11
握手の風格
日本人は普段、めったに握手などしないものである。ビジネスの世界のことはよく知らないが、たぶん、名刺の交換とかで握手の代わりにしているのではなかろうか。
2017.6.4
卓球の風格
昔は卓球の動く映像をいくら見たくても、泣こうがわめこうが、見る手段がなかった。テレビで確実に放送されるのは、毎年1月の全日本選手権大会のみだったので、番組が始まるのをテレビの前で正座して待ったものである。今はインターネットで見たい放題だ。いい時代になった。
2017.5.28
秘密の花園
麻酔科医としての経験上、人体には危険なゾーンがある。手術操作がそこに及ぶと、何となく見ているこちらが胸騒ぎがする、そんな場所である。中でも危険度が高いのが、膀胱の裏側の一帯である。
2017.5.21
ウサギとカメ、その2
前回私は、走ることよりも歩くことのほうが、人間が生きていく土台として大事ではなかろうか、と書いた。これは麻酔科医としての経験を漫然と、うすらぼんやりと思い返した結果であって、なんら客観的な根拠に基づくものではない。
<文献1> Walking and running produce similar reductions in cause-specific disease mortality in hypertensives. Williams PT. Hypertension. 2013; 62: 485-91.
2017.5.14
ウサギとカメ
私が高齢の方の麻酔を担当するとき、術前診察で必ず質問することがある。普段、どれくらい歩けてますか、ということである。
2017.5.7
廊下受診
医師が家に帰ると、その家庭に最低一人は医師がいるわけである。ただそれが、頼りになるものではないことは、前回説明したとおりである。
2017.4.30
一家に一人
一般の方は、自分の家族に医者が一人いるとどれだけ便利か、と思われるかもしれない。これが、そうでもないのだ。
2017.4.23
偶然短歌
このところ、偶然短歌なるものを、ネット、新聞記事で見かける。これはウィキペディアのようなサイトの中の文章をコンピュータで分析し、偶然五七五七七の言葉の並びになっている部分を抽出して面白がる、というものである。
念仏で救済される喜びに衣服もはだけ激しく踊り
アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、中央アジア、およびシベリア
郡山(こおりやま)、大和小泉、法隆寺、王寺、三郷(さんごう)、河内堅上(かわちかたかみ)
電信隊浄水池女子大学刑務所射撃場塹壕赤羽の鉄橋隅田川品川湾
2017.4.16
手術室一斉放送
「今は昔」コーナーで書いたように、私がいたころの大学病院(2001年まで)では、各医師はPHSもポケットベルも持っていなかった。したがって研修医が麻酔中、部屋を離れている指導医を呼ぶ時は、手術室内一斉放送をかけるしかなかった。何しろ大学病院の手術室は広いから、個々の医師の局在を探すのは容易ではないのである。
2017.4.9
スパゲティ症候群
麻酔中の患者さん、あるいはICUで集中治療を受けている患者さんには、たくさんのライン(点滴などの管や電線)がつながっている。麻酔中であれば患者さんがまったく動かないはずなのに、それでもなぜか、油断するとラインはどんどんもつれていく。
2017.4.2
漢方
先日、久しぶりに会った麻酔科の後輩U先生が、漢方薬の専門家に転向していたと聞いて驚いた。
2017.3.26
ほめる
私が麻酔科医として駆け出しだったころ、叱られた思い出はたくさんあるが、ほめられてうれしかったこともちょっとはある。それらのおほめの言葉は、へこたれがちな新米麻酔科医への最高の気力回復剤となり、その後も心の支えになってきたと思う。
2017.3.20
宝くじの買い方
私は宝くじで千一円以上当てたことが一度もない。その私が、宝くじのかしこい買い方を提案するのであるから、今回の話でも誰も得をしないことは、胸を張って約束できる。
2017.3.11
宗教欄消滅
紙カルテから電子カルテに移行した時、患者基本情報のページから宗教欄が消滅していたことに、最近になって気がついた。どうしてこんなことになったのか、システムを作った業者に聞かなくてはわからないが、まあ想像はつく。昔に比べて空欄のままにされていることが増えていたからだろう。日本人の宗教離れが進んでいるように思える。
2017.3.6
宗教欄
昔の紙カルテ(電子カルテになる前)の2ページ目には、患者さんの基本情報が書き込まれていた。職業、過去の病気、家族構成などである。その中に「宗教」の欄もあった。
2017.2.26
五線の肩ツキ
去年2016年は囲碁ファンにとって、つらい年であった。世界トップレベルの棋士、韓国のイ・セドル氏がアルファ碁とかいう人工知能に負けたのである。
2017.2.19
ガウン・テクニック
病院の中でももっとも清潔でなければならない手術室という空間にも、非常に不潔なものが存在する。医師と看護師である。この要素は他の手術器材のように、120℃の蒸気やエチレンオキサイドガスで滅菌できない。かわりに滅菌した手袋とガウンを着用することにより、清潔とみなすのである。これをガウンテクニックと呼ぶ。
2017.2.12
探偵ナイトスクープ
「探偵ナイトスクープ」という関西のテレビ番組がある。視聴者から寄せられた依頼を、芸人迷探偵が解決するという趣旨の人気番組である。この中で多い依頼が、自分の特技を取材してほしい、〇〇に挑戦させてほしい、といった、自分アピールものである。
2017.2.5
双子あれこれ
先に取り上げた「行動遺伝学」では、双子をたくさん集め、一卵性と二卵性とを統計学的に比べることによって、遺伝子の力を数字で評価しようというのであった。
(1) Cognitive Functioning after Surgery in Middle-aged and Elderly Danish Twins. Dokkedal U, et al. Anesthesiology. 2016 Feb;124(2):312-21.
2017.1.29
音楽と素質
私は小さい頃、ピアノを習っていたことがあるが、非常にできの悪い生徒だった。先生のお宅に行っては、本棚から勝手にマンガや本を引っ張りだして読んでいた記憶しかない。素質の欠如というものは、まずそういう形で姿をあらわすのであろう。とにかく、白と黒の鍵盤をたたくことに、何の面白さも見いだせなかったのだ。長続きしなかったのは、関係者すべてにとって幸いであった。
2017.1.21
知能と素質
人の頭のよしあしは、生まれつきの素質で決まっている、などと大声で言ったりしたら、危ない人だと思われるかもしれない。からだは親からもらったものだが、頭脳に関しては本人の努力次第でどこまでも上昇できる、というのが世の中のタテマエというものだ。しかし今、「行動遺伝学」という耳慣れない学問が、「生まれつき」理論を主張して話題になっているらしい。そこで、専門家である安藤寿康 (あんどう・じゅこう)という人の本を読んでみた。(日本人の9割が知らない遺伝の真実、SB新書)
2017.1.15
笑う業務日誌
おととしの手術室忘年会で私は、あるナースから、今年一番面白かったことは何でしたかと聞かれて思い出せず、窮地に追い込まれたのであった。そこで私は心に誓った。毎日つけている業務日誌には、何よりも、その日おもしろいと思ったエピソードを書きとめようと。
2017.1.14
新年のあいさつ
新年、初出勤すると、職場でいろんな人から、「あけましておめでとうございます、本年もよろしくおねがいします。」と言われる。もちろんこちらもあいさつを返すが、「おめでとう」と「おねがいします」のところで2回お辞儀をしなければならないのがストレスだ。
2017.1.9
麻酔と遅刻
麻酔科医がいないと、手術が始まらない。にもかかわらず、寝坊して、遅刻する者がいる。 さすがに本物の麻酔科医はそういうことをしないが、麻酔科にローテートしている研修医が、ときどきやる。
2016.12.31
「この世界の片隅に」
「この世界の片隅に」という映画が大好評を博しているというので、見に行った。何しろ私の故郷の呉(くれ)が舞台なのであるから、見に行かないわけには行かなかった。レ ク レ~ レ~ ク 、ク レ、ク レ
2016.12.23
「戦犯」について
戦犯、という言葉が、スポーツ新聞、低俗週刊誌などで使われているのを見ると、私は実に腹立たしく感じる。
2016.12.21
食わない殺生
日本の民話の中に女マタギの話があって、印象に残っている。このすご腕の狩人は、山の中の沼に君臨する大ガマと出会い、死闘の末にみごと撃ち止める。だが彼女は「食わない殺生(せっしょう)をすると、罰が当たる」と言って、あえてこのガマを煮て食い、あっけなく死んだのだ。
2016.12.16
自転車外傷
自転車に乗るのは楽しい。両足は地から離れ、からだは風に浮く。ちょうど空を飛んでいるような気分である。ペダルを漕いで加速するのが離陸の喜びならば、そのあとの慣性運行は滑空の爽快さである。
2016.12.3
スポーツ外傷
私などのように一日のほとんどを手術室で過ごしていると、世の中のスポーツや遊びを、「外傷のリスク」という色眼鏡で見るようになる。健康的とか、かっこいいとか、そういうイメージとは裏腹に、スポーツは意外に危険なのだ。
フットサル。ぶつかったり、急にひねったりするためか、じん帯損傷、鎖骨や下肢の骨折が意外に多い。サッカーで骨折するのはたいがい中高生であり、名誉の負傷として扱われるだろうが、フットサルで負傷するのはまず会社員だから、その立場は微妙だろうと想像する。
柔道、ボクシングなどの格闘技全般。ラグビー、アメフトも、ケガの内容、発生機転から見て同類と言える。 まあ本人も、多少のケガは覚悟の上かもしれないが、頚椎の骨折だけは、試合に敗けてもいいから全力で回避してほしい。
スキー、スノーボード。命に関わるほどではなくても、脚の骨が真ん中(骨幹部)で折れるなどの長期入院コースものの重傷が多い。競技人口減少に悩むスキー場関係者には申しわけないが、受験とか就職とか、人生の節目を控えた人があえてやるべきスポーツではないと、私は思う。
小学校の組み体操。とくに、ピラミッドの一番上に登る子が落ちて、腕の骨を折る。昔から危ないと思っていたが、このごろやっと世の中に認識されてきた。こんなことなら私も、もっと前から警鐘を鳴らしておけば、組み体操問題評論家としてテレビに出られたかもしれない。
クライミング。高いところに登ると、誰でもたまには落ちる。猿も木から落ちるらしいし、仕事中に落ちたトビ職人の麻酔も、私は何度か経験した。いわんや趣味で絶壁に登る人においておや。高所恐怖症の私から見ると、まことに不思議な趣味である。
自転車。これはスポーツというよりも、交通手段の一つであるが、これもけっこう危ない。これはまた、回を改めて書いてみたい。 2016.11.27
事故報道
私たちはニュースなどで毎日、事故の報道に接している。「心肺停止状態」とか「意識不明の重体」などと聞くと、見知らぬ人とは言え、何とか生きのびて欲しいと祈らずにはいられない。
2016.11.20
山の辺の道
10月のある平日、私は今年はじめての夏休みをいち日だけ取り、ひとりで奈良を訪れた。かねてから、「 山の辺(やまのべ)の道」を歩いてみたかったのだ。 その歴史的意義はよく知らないが、とにかくとても古い街道であり、歩いていくだけでいろんな神社や史跡を巡ることができるらしい。私を破局から救った、山の上の蕎麦屋さんの大雑把な地図看板。実際はこのように、登り切ったところには人気(ひとけ)があった。
2016.11.13
シンゴジラ、その2
映画「シンゴジラ」でもう少し遊ばせてもらう。もし、シンゴジラの運命をまだ知りたくない人がおられたら、この先は読まないで、DVDの発売をお待ちいただきたい。
2016.11.6
シンゴジラ
「君の名は」と来たら、つぎはゴジラである。
2016.10.30
君の名は…
患者さんが手術室に入室するとき、必ず行うのが氏名の確認である。病棟の看護師と、手術室の看護師がともに患者さんに向き合い、氏名を尋ねる。看護師から「○○さんですね」と問うのではだめである。ぼんやりした人だと別人の名前でもうんと言ってしまうからである。患者さん自身に名乗ってもらうのが基本である。
2016.10.23
スーパープレー、その3
昔のことである。外科の手術中、外科部長が清潔介助のナースに、骨ろう(コツロウ。骨の断面に塗りつける、粘土のようなもの)を丸めて渡すよう要求した。
2016.6.19
スーパープレー、その2
以前、スーパープレーについて書いた後、自分にも仕事上のかっこいいプレーの一つや二つ、あるはずだと考え、懸命に思い出そうとした。そして、何も思い出せなかった。
2016.6.12
切腹
歴史書、映画、小説などで見る限り、日本の武士は、しばしば切腹したようである。ただし、一人一回までである。
2016.6.4
子育て麻酔科医
麻酔科医の中には子どもを持つ女性も多い。大学医局の人材派遣機能が低下し、麻酔科業界の人手不足がつづく中、子育て中の女性麻酔科医にはぜひとも働いてもらわなくてはならない。多くの病院ではそういう医師を対象に、時短、週3日の出勤などの軽減勤務制度を提供している。
2016.5.29
スーパープレー
今はどんなマイナーなスポーツでも、インターネットの動画サイトに行けば、いつでもその映像を観ることができる。いい時代になったものだ。
2016.5.22
息づまる戦い
私は先ごろサンダーバード(国際救助隊ではなく、JRの特急の方)に乗り、久しぶりに金沢を訪れた。日本医師卓球大会に出場するためである。
2016.5.15
さかあがり
緊急手術に呼ばれて休日出勤したあと、まっすぐ家に帰るのもアレだから、公園で缶コーヒーを飲むことにした。本に飽きて遠くを眺めていると、中学生くらいの子たちが跳ねるようにして公園に入ってくるのが目に入った。彼らはそのうち鉄棒に目をつけ、さかあがりをし始めたようだ。
2016.5.7
痛みの定義
痛みとは何か、定義を述べよ、と研修医に言うと、目を白黒させる者が多い。彼らは医師国家試験をパスしたばかりであるから、ベーチェット病の診断基準とか、肺がんのステージ分類とかはたぶんすらすら答えられるのだろうが、われわれ人間にとってもっともなじみ深い「痛み」という生理現象を、言葉にするとなるとみな四苦八苦である。
* "An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage."
2016.5.1
座右の銘
転勤した時に新しい職場で、自己紹介の文を書かされることがある。その中に「好きな言葉」の欄があったりすると、私はたいてい、「人畜無害」、「犬も歩けば棒に当たる」などの、人畜無害意味不明な言葉を記入するのだが、あるとき奮発して、「圧力と時間」と記入したことがある。あとでそれを見た人から、これはどういう意味か、と聞かれた。
2016.4.23
基礎医学
4月14日に熊本地震が発生した。私はこのふざけたブログのようなものを書いている場合ではないな、と思ったものの、サッカーの本田圭佑(ほんだ・けいすけ)選手が「自粛すべきではない」と言っているようなので(何のことを言っているのかは読んでないが、このサイトのことかもしれない)、今週も地震に負けないで書くことにした。
2016.4.18
アンパンマン
私は、大学院での研究を薬理学教室でやらせていただいた。こちらの教授は、麻酔科のM教授と正反対の人柄であったが、やはり偉大な人物であった。
2016.4.9
博士号
私のこのブログのようなものの入り口のページに、アクセスカウンターが置いてある。年々、一日あたりのアクセス数が増えてきていたが、去年後半から減り始めた。
2016.4.3
合理主義、その2
前回私は、今は亡きM教授の合理主義について語ったけれども、人間も、人間社会もそもそも合理的でないから、そんな中で合理主義をまっすぐに貫くと大変なことになる。「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。(中略)とかくにこの世は住みにくい。」との夏目漱石(なつめ・そうせき)の言葉は、まことに名言である。M教授はまさにその、角が立つ人の代表選手であった。
2016.3.27
合理主義
その昔、医師は祈祷師、呪術師の仲間であったと思われるが、現在は科学者の仲間だと、自分たちでは思っている。(科学者の方でそう思ってくれているかどうかは不明である。)だから、根拠に基づく合理的なものの考え方を重んじているつもりである。
2016.3.20
脳ブーム
テレビでよく見かけるようになった「脳科学者」、あれは一体いかなる人たちなのだろうか。そもそも「脳科学」という言葉自体が耳慣れないものである。
通勤中はかわいいものを見つけるようにするとよい
右脳を鍛えるには、利き手でないほうで歯を磨くとよい
マンネリを避けて、いつもとちがうことをしよう 2016.3.12
小関越え、その2
前回述べたように、私は真夜中の小関越えを繰り返す中で、一度も怪異現象に遭遇することがなかった。怨霊のたぐいはめんどくさそうなので遠慮したいが、害のない妖怪のようなものであれば、出会ってみたかった気もしないではない。
2016.3.5
小関越え
私は京都の大学院で研究していた頃、大津から通っていた。京都府と滋賀県のともに県庁所在地であるが、隣り合った市であり、通勤にはまったく不自由しない距離である。
2016.2.27
手術室の窓、その2
外科医のからだの仕組みが、私にはいまだによくわからない。
2016.2.20
手術室の窓
手術室は閉ざされた空間であり、外界と接する窓はない。雨が降るのを見てもの思うとか、道を行く人の生活を想像するとか、そういうことは手術室ではできない構造になっている。
覗かれ窓
2016.2.13
アミノグリコシド・トリック
10年ほど前までのテレビ界では、2時間ドラマなるものがやたらはやっていて、毎晩どこかのチャンネルでこれをやっていた。そのほとんどがサスペンスもので、まず冒頭で人が死亡し、途中いろいろあって、最後は探偵が犯人を断崖絶壁に追いつめる。動かぬ証拠をつきつけられた犯人は、がっくりと膝を折るのであった。
2016.2.6
孫の手
本日とうとう、当直明けの帰り道で百円ショップに寄り、「孫の手」を買った。
2016.1.31
ジギタリス
昔読んだミステリーやショートショートなどに、ジギタリスなる不思議なくすりが出てきて、医学生になる前の私の好奇心を刺激した記憶がある。何でも心臓の悪い人がのめば薬になるが、健康人がのめば毒になるというのである。これほど見事に逆説的な性質を持つ薬が実在するのなら、ネタに困った小説家の心をくすぐるであろうことは、想像に難くない。
2016.1.30
走者の下痢
公園には1級と2級の別がある。トイレがついているのが1級、ついていないのが2級である。知らない人が多いのも無理はない。私が決めた基準だからである。日頃から、自分の行動範囲内の公園については、1級か、2級か、よく把握しておくことが重要である。いつトイレのお世話になるかわからないからである。
2016.1.23
デジタル・ゾンビ
歩くことが人類の最大の娯楽の一つであることは言うまでもないが、その楽しみに水をさすものがある。タバコ、スマホ、歩道を我が物顔で走りぬける自転車である。驚いたことに、この3つを同時にやる人もいる。VIDEO
2016.1.17
初ランニング
今年の元旦、気がつくと家の者がみんな外出してしまい、一人取り残されていた。仕方がないので、走ることにした。私にとって、もっとも安上がりな暇つぶしの手段である。性懲りもなく3月のフルマラソンを申し込んでしまったので、そろそろ距離に慣れる必要もあり、20キロコースを走ることにした。灘の酒蔵一帯を通り抜けるルートだ。
2016.1.9