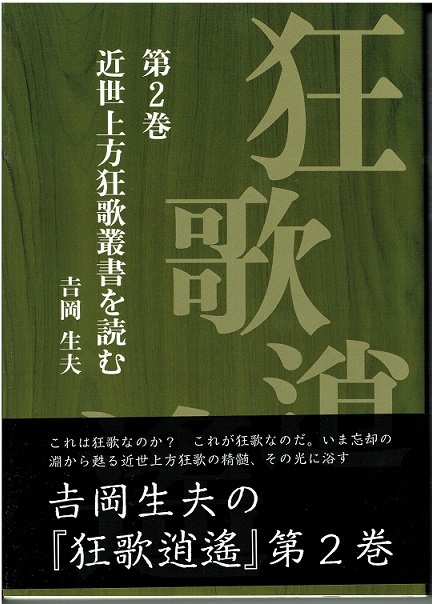| 近世上方狂歌叢書を読む |
| 第101回以降は「狂歌逍遙(第2巻)~2~」でどうぞ |
| 第1回 狂歌大和拾遺 |
なみ居たるはつたひこんこう童子たち其(の)口もとは不動明王 田中基翁
『狂歌大和拾遺』の刊行は寛保元(一七四一)年である。『近世上方狂歌叢書二十』に収録されており、『狂歌大観』や『江戸狂歌本選集』と違って年代順になっていない。編者は田中基翁、奈良県大和郡山の人である。解説によれば入集者は狂歌師集団ではない。そのことを「地方においても狂歌が近世文芸(出版文芸)として自立していく方向性を示していた。狂歌の近世文芸としての自立は、貞柳から木端へと中央で急速に展開されていったが、それのみではなく、地方においても着実に進行していったのであった」という。掲出歌の題は「子とも集(ま)りて麦粉を喰(ひ)けるおかしさに」。二三句の「八大金剛童子」(不動明王の使者である八人の童子)に「はったい粉」を掛けた。口元がはったい粉まみれで不動明王だというのだ。
かそふれは辰から辰のいつまはり本卦もぬけて禿(げ)あたまなり
六一か四方にひかる禿(げ)あたままたはへましやう升かきの竹
なるはなしもはや帰らん鶯のちよツひちよツひとよほとのみけり
盃はちよつひちよつひの音はかり生えかたらぬものてこさろう
一首目の作者は基翁、題は「六十一歳の賀に」。四句の「本卦もぬけて」は還暦で「卦」に「毛」を掛けた。二首目の作者は大七、題は「右返し」。初二句は割り算の九九「六一加下四」(ろくいちかかし)を使った。四句の毛が「また生えませう」は生まれた干支に戻ったことの賀詞、結句「升掻きの竹」は「八十八の枡掻き」(商売繁盛の縁起を祝い、米寿の人に米の枡掻きを切ってもらった)に因んだ予祝とした。三首目の作者は千翠、題は「夜咄に酒をとふへて」(「食べて」は「飲む」の意)。初句「鳴るは無し」は四句の盃を干す音「チョッピチョッピ」をいう。四首目の作者は基翁、題は「返し」。四句「生餌が足らぬ」は酒の肴をいう。千翠が鶯の鳴き声を模したので、これに応じた。結句は「御座らう」で「御座いましょう」。
花に来てはるかの谷の山さくら咲(き)ものこらすちりもはしめす
私が今日のこころは盆師走ふるひもしたりあせもかひたり
なかなかに田舎の水のすみよくて淀川のほる気はこさんせぬ
一首目の作者は永志、題は「よしの奥さくら谷にて」。下句は謡曲『鞍馬天狗』(小学館『日本古典文学全集 34』)中の一節「今日見ずは悔しからまし花盛り、『咲きも残らず散りも始めず』」が口を衝いて出た。二首目の作者は寺沢還愚稿、阿州小松嶋(徳島県小松島市)の人である。題は「山田再賀公俄に御入(り)ありけれは」。山田姓から想像するのは徳島藩の家老である。初句の人代名詞「私」に注目したい。三句の緊張感は「盆」が「汗もかいたり」、「師走」が「震ひもしたり}となる。三首目の作者も寺沢還愚稿、題は「京へ隠居せよと世悴方より申(し)来りける返事に」、親の老後を心配する息子への返事である。結句「御座んせぬ」が冷たく言い放ったような印象だが「御座んす」は「ある」の意の丁寧語なのだそうだ。
|
| 第2回 狂歌秋の花 |
十三年あすのたいやのけそくそと兎も杵てもち月の空 三休斎白掬
『狂歌秋の花』の撰者は永日庵其律、貞柳十三回忌追善集である。但し、出版は延享三(一七四六)年と遅れた。二句「逮夜」は忌日の前夜をいう。三句は「華足ぞと」、華足は仏に供える餅や菓子の類である。結句の「もち月」は「望月」に「(杵で)餅搗き」を掛けた。
元服に齢ひさつくる男振(り)するは千年かみは万年
きのふにはかはる寒さと引(き)かふる頭巾そ冬のはしめ也けり
むそし六下からも又六十六中からよみし春もありしに
丸ぬれにぬるると儘よ初しくれかみなし月の坊主あたまは
以下「秋の花附録雑歌」より抄出する。一首目の作者は桃縁斎貞佐、題は「元服をことふきて」。二句「齢(よわい)授くる」は烏帽子親である。四句「する(剃る)」は「そる(剃る)」の転、結句「かみ」は「髪」、下句に「鶴は千年亀は万年」を掛けた。二首目の作者は高橋氏曲扇、題は「初冬」。三句は「引き替ふる」、昨日とは異なる寒さに対応して頭巾を被ったのである。四句は句割れで「冬の~」から結句に実感が伴う。三首目の作者は川船子秋楽、題は「六十六歳の春」。初句は「六十路六」(六十六)、三句「六十六」(むそじろく)は下から読んでも六十六、これが上句である。次に下句だが「六十六」の真ん中にある十を起点とすると下に十六、上にも十六、帰りたくても帰れない十六歳の春となる。四首目の作者も川船子秋楽、題は「時雨」。二句「儘(まま)よ」は「かまわない」、四句「かみなし月」は「神無月」で陰暦の十月、これに「髪無し(月)」を掛けた。ウ段とア段の音が響く。
身にそはぬ衣のつまのむかしをは思ひ出しては涙ほころふ
しらなんた花や月見や降雪のつもれはとしの暮となるもの
十かへりの花よめなれや松か枝も今朝はかふつた雪の丸綿
語(り)あふた中はあかなき湯の山を別れの涙しほる手ぬくひ
一首目の作者は湖月堂可吟、題は「先妻の年忌に」。初二句は衣に身の添わぬ妻、脱け殻としての衣の端、また成句「魂も身に添わず」(気が動転する)の「私」も重なろう。結句「綻ぶ」は衣の縁語だが、ここでは涙を怺えきれないことをいう。二首目の作者は永言斎季来、題は「歳暮」。初句は「知らなんだ」、三句は「降る雪の」と読んだ。四句「積もれば」は雪そして二句などの日数である。句またがりで「歳の暮れ」が効いていよう。三首目の作者は永日庵其律、題は「松雪 夢中吟」。初二句「十返(とかえ)りの花」は百年に一度、千年に十度咲くという松の花である。祝賀の意に用い、二句は「花」を共有して下に「花嫁であることよ」。結句「丸綿」は綿帽子の一種で花嫁が被った。四首目の作者も永日庵其律、題は「勢州菰野へ湯治せし時逗留中語(り)あひし人々山口まておくり出しわかれに」。初句はウ音便だから表記は「語りあうた」になる。二句「あかなき」は「垢なき」、これに「飽かなくに」(残り惜しいのに)の意を重ねた。三句は湯ノ山温泉、今の三重県菰野町が舞台である。
|
| 第3回 狂歌手なれの鏡(1) |
隠居てもひま社(こそ)なけれ子や孫やこたつの中は足の八重ふき 偶然翁秋国
『狂歌手なれの鏡』の撰は栗柯亭木端、刊行は貞柳十七回忌にあたる寛延三(一七五〇)年である。掲出歌の題は「閑居火燵」。和泉式部の〈津の国のこやとも人をいふべきにひまこそなけれ蘆のやへぶき〉(岩波文庫『和泉式部歌集』)に拠った。本歌の「来や」(「昆陽」)に対して「子や」、本歌の人の目を盗む「隙」に対して隠居の「閑」、本歌の「蘆」に対して「足」で火燵の歌を組み立てて見せた。
油煙斎墨の衣はきたれ共なまくさ坊主鯛や貞柳
足曳の山鳥の尾の長談義なかなかしきにしひりきらした
かせふけはおきつ白波たつた山夜半にはちいはしひん尋(ぬ)る
貞柳の遺詠より三首を引く。一首目の題は「東本願寺より衣御免ありしのち着して連歌の会にいでけるに人々あいさつあるに」。上句だが「油煙斎」の由来は墨、その墨染の衣を三句「着たれども」となる。下句は屋号が「鯛屋」だから鯛の縁語で「生臭坊主」、「屋」を詠嘆の「や」とした。二首目は「題しらず」。本歌は柿本人麻呂の〈葦引の山鳥の尾のしだりをのながながし夜をひとりかもねむ〉(『拾遺集』七七八)、恋の歌である。結句は足の痺れと苛々する気持ちの両方であろう。三首目も「題しらず」。本歌は読人しらずの〈風吹けば沖つ白波たつた山夜半にや君がひとり越ゆらむ〉(『古今和歌集』九九四)である。下句の「ぢい」以下は「爺は溲瓶尋ぬる」だろう。「しびん」は「しゅびん」の転訛、寝床近くに置く小便壺である。
ひとつ搗(い)てあひたのあるは鐘つきか心あり明の月をみるけな
是もまた夢かとそおもふ切買の雪踏み分(け)て帰るこころは
うすの音ほたんほたんと花やかにするは富貴な家のもちつき
元日とてさかやきやそる若やいてあおあおとした年のかしらや
一首目は読人しらすの「題しらす」。左註「是は江戸の人の詠にて後世狂歌を撰みあつむる事あらは加えいれてよといひ置(け)るよしなれは今爰に出す」が『平家物語』が伝える藤原俊成と平忠度の逸話を思わせる。結句の助動詞「げな」は「ようだ」、様態を推測する意を表す。二首目の作者は山本華麓、題は「組題の歌続ける中に色里雪」。惟喬親王を詠った『伊勢物語』の〈忘れては夢かとぞ思ふおもひきや雪ふみわけて君を見むとは〉(八十三段)が本歌である。三句「切買」は「買い切り」の逆さ言葉だろう。豪遊の後の「雪踏み分けて帰る心」は理解を超えた世界である。三首目の作者は霞城、題は「餅搗」。右肩に「本語」とある。謎解きは二句のオノマトペ「ぼたんぼたん」、三句の「花」、四句の「富貴」から「富貴草」(「牡丹」の別名)と知れるのだ。「本語」はともあれ餅搗きの景としても綺麗な仕上がりとなった。四首目の作者は栗柯亭木端、題は「とし立つ日」(年が改まる日)。〈元日とて月代や剃る若やいで青々とした年の頭や〉。初句六音。二句から四句は月代にスポットを当てながら、三句当たりで新年の気分を乗せていき、結句で二つの頭を一つに重ねた。母音要素としてのア音のリードが目を惹く。
|
| 第4回 狂歌手なれの鏡(2) |
こま人の来朝をする春なれは唐土の鳥のわたる日にたつ 栗柯亭木端
掲出歌の題は「人日(じんじつ)」。五節句の一つで陰暦正月七日の称、七草粥を食べる風習がある。また古代中国では正月の一日から六日まで順次「鶏、狗、猪、羊、牛、馬」を占い、七日に人を占った。この「人日」の題の下に「戊辰の年は此(の)日立春にて朝鮮人来聘の年なれば」とある。江戸時代を通じて十二回あった朝鮮通信使、その十回目が寛延元(一七四八)年である。また註記のとおり一月七日が立春という偶然が重なった。日本国語大辞典で「薺の囃子」を引くと「陰暦正月七日に七種粥を作るため、その前夜から早朝にかけて春の七草を俎上に載せて刻みながら、『七くさなづな、唐土の鳥が、日本の土地へ渡らぬ先に、七くさなづな手に摘み入れて』などとはやす」とある。したがって初句の「こま」は「高麗」(朝鮮半島古代の国名)に同音の「駒」(馬)を掛けている。下句の「唐土の鳥」は「人日」の「人」に喩えた。占いの馬から人に渡る日に「春」が「立つ」そして「戊辰」の「辰」となる。
かき初(め)の硯の海のあはち島おろせし筆や天のさかほこ
梅ほうしになる身としりて咲(く)や此(の)花のすかたもはつちとひらく
いかのほりしあけてみれは吹(く)風に細工はりうりうりうりうとなる
一首目の作者は木端、題は「とし立つ日」。二句は墨汁をためておく凹んだところ、結句は国産みの神話で伊耶那岐命と伊耶那美命が用いた逆鉾、その二つが合わさる意を込めたのが三句の「淡路島」である。スケールの大きな見立てである。二首目の作者も木端、題は「梅」。初句は「梅法師」で「梅干し」を擬人化した。結句「はつち」は「鉢」の変化した語、初句の縁語の托鉢坊主は「はっちはっち」と云って施物を乞う。その「はっち」を梅の開花のオノマトペにした。三首目の作者も木端、題は「紙鳶」。四句は成句「細工は流流仕上げを御覧じろ」の前半を用いる。結句はその後半を証明して見せた。名詞「流流」に副詞の「りゅうりゅう」を接続して紙鳶が勢いよく風を切る音とした。
まつ人をたまし暮(ら)しつほとときす今一声はなきそうにして
道法は百廿里の程ときすしはなくこゑを状通てきく
かやりには手もなくにけて棒振(り)し昔の稽古の未熟みせけり
一首目の作者は栗柯亭木端、題は「百首歌読(み)しとき」。作中主体は時鳥、この時鳥が瞞したのは源公忠〈行きやらて山ぢくらしつほととぎす今ひとこゑのきかまほしさに〉(『拾遺和歌集』一〇六)である。「今一声は鳴きさうにして」(時鳥)なのだ。二首目の作者も木端、題は「山本華麓より江戸は郭公のおほく鳴(く)よしをいひをくられしせうそこの返事に」。「せうそこ」は「消息」(「しょうそく」の音変化)である。初句は「みちのり」。三句の「程」は上から「百廿里の程」、下へは「ほととぎす」(古くは清音)と二役となる。四句「しば鳴く」は「しきりに鳴く」、結句は「状通で聞く」(「状通」は「手紙」)。三首目も木端、題は「百首歌読(み)ける時蚊遣(り)火」。初句「蚊遣り」は「蚊遣り火」、これに対して蚊は「棒振り剣術」(振り回すだけの下手な剣術)だから手もなく(簡単に)逃げたというのである。蚊の昔すなわち幼虫時代は「棒振り」と呼ばれていた。
|
| 第5回 狂歌手なれの鏡(3) |
たたかひの跡そと今もかうみやうを一二の谷にかかやかす月 栗柯亭木端
掲出歌の題は「組題のうたよみける中に古戦場ノ月」。源平の古戦場、一ノ谷である。三句は「高名」に「光明」を掛けた。四句は一ノ谷と二ノ谷をいう。東から一ノ谷、二ノ谷、三ノ谷とあったらしいが、これに「高名」が「一二」(一二を争うこと)を掛けた。結句では「光明」が前に出て、「高名」を「光明」が具体の谷と抽象の名の両意で「輝かす」だろう。
よはひほしに稲妻のよう靡くのは七夕の千話けなりかりてか
三味線のいとちの声のあひの手かちりんちりんと鈴虫のなく
今宵はなつ月の光も鯉鮒も池にうつりてもなかにそすむ
たまとみる今宵の月を隠したるおててこてんの雲の袖かな
一首目の作者は木端、題は「七夕の夜流星稲妻を見て」。初句「よはひほし(夜這ひ星)」は「流れ星」、四句「千話」は「痴話」となる。結句は「異なりがりてか」、「けなりがる」(羨ましく思うこと)の連用形に接続助詞「て」と係り助詞「か」で問いかけとなる。「稲妻が夜這ひ星に靡くのは夫婦星が羨ましいからか」。二首目も木端作、題は「虫似音曲」。初二句は「三味線の糸」(三味線の弦)と「地の声」(地声)だろう。隠し絵が「いとじ」で蟋蟀の異名、ここでは秋に鳴く虫の総称としたと考えたい。多くの虫の中でもとりわけ美しい「合ひの手がリンリンと鳴く鈴虫」なのだ。三首目も木端作、題は「十五夜の月の前にて放生せしを見て」。初句の「はなつ」は「月の光」と「鯉鮒」だが、その双方が放生池に、ここまでが上句である。四句は月が「池に映りて」だが鯉鮒は「池に移りて」だろう。結句は月が池の「最中にぞ清む」(この夜の月を「最中の月」という)のに対して鯉鮒は月の「最中にぞ棲む」で放生会の夜を名実ともに美しくしたのである。四首目も木端作、題は「同し夜曇りけるに」。四句は放下師が「演技中、『おててこてん、すててこてん』などと口で締太鼓の音を模して囃した」(『江戸語の辞典』)語である。またその芸の中で「おででこ」と呼ぶ操り人形を使ったという。これが結句「雲の袖」になった。初句にもどれば月の見立てが「玉」だが放下師が行う曲芸の品玉も玉に重ねたかったのだろう。
つきの名の菊もしほれて冬近き花屋は霜の下草はかり
冬来ぬと今朝は寒さの入(り)口をたてて見せたる霜はしら哉
かれてたつあしもとみてや寒風にゆすりてかさにかかる白なみ
一首目の作者は木端、題は「組題の歌読(み)し時華屋ノ暮秋」。初二句「月の名の菊」とは菊月(陰暦九月)、その「菊も萎れて」なのだ。これと対比されるのが「下草」(地面を彩るために植える草)で、「霜」の置き場所となるだけで華やかさに欠けるというのだろう。四句の「花屋」の語が目に止まった。二首目の作者も木端、題は「百首歌よみしなかに初冬」。三句の「入り口」は上からは「寒さの入り口」で初冬の謂いとなる。下へ向けて「入り口を立ててみせたるしも柱かな」という見立てとなった。三首目も作者は木端、題は「百首歌よみしなかに寒芦」。二首同居の表が〈枯れて立つ芦もと見てや寒風に揺すりて嵩に懸かる白波〉ならば裏は芦が「枯れて」に人の勢いが「枯れて」、「芦元」にが「足元」、「揺すりて」は脅して金品を出させる意、「白波」は盗賊の意で、表裏同時進行の騙し絵が完成する。
|
| 第6回 狂歌手なれの鏡(4) |
みゆきとて物靜(か)なるその中にさきをふ声か竹の下折 栗柯亭木端
掲出歌の題は「百首歌よみけるとき雪」。初句「みゆき」は「行幸・御幸」で天皇の外出をいう。これに「深雪」を掛ける。四句「さきをふ」は「先追ふ」で前方の通行人を追い払うこと、またその役の人をいう。これに「先負ふ」を掛けた。雪の重みで竹の先が耐えきれなくなった。その声か、というのである。深雪で庭の竹が折れた、そこからの物語が思われる。
さむき夜に独(り)は寝すに居られしと炉の火もせせりおこし社すれ
人の世はしやほんの露の身なれはやなき玉とつい消(え)てゆきけり
無心なる雲にもあらて我は今朝くきの城下をたちいてにけり
あり明のつれなくみえしやとり哉ひのきえた程憂(き)ものはなし
ふし見まて十里の道をしらせてや船の底さへこりこりといふ
茶をひいてねふるは肩のつかえしと知(り)てとまるかやんまけんへき
木端の作が続く。一首目の題は「百首歌読(み)けるとき埋火」。三句は「居られじ」、そこで埋み火を「せせり熾しこそすれ」となる。これに「せせり起こし」を掛けた。「せせる」には「つつく」のほかに「ちょっかいする」の意がある。初句の「寒き」の影が薄い。二首目は「哀傷」の部で題は「百首歌読(み)しとき無常」。二句「しやほんの露」はシャボン玉の液、四句の「玉」は「シャボン玉」の「玉」に「魂」を掛けた。野口雨情作詞の童謡「しゃぼん玉」を先取りしたような世界である。三首目は「覊旅」の部で題は「但馬の旅へまかりける時三田といふ所にとまりてあさとくいてたつとて」。一首は「雲無心にして岫を出ず」(陶淵明「帰去来辞」)を効かした。四句「くき」は「九鬼」氏で三田藩の藩主である。これに「岫」(山の峰)を掛けた。四首目の題は「おなじとき柏原といへる所にとまりしに宿のあるじ油をおしみて有明の灯のきえけれは」。「本歌」は壬生忠岑の〈有明けのつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし〉(『古今和歌集』六二五)だろう。油を惜しんだばかりに評判を落としていく宿が見えるようである。五首目の題は「京え登る船のすはりて底に砂のすれるを聞(き)て」。「据わりて」は「座礁して」の意。結句は「ごりごり」に「五里五里」を掛けた。足せば二句の「十里」となる。珍しくない光景だったのだろう。六首目の題は「茶挽坊主居ねぶりし肩にとんぼうとまれるに」。「茶挽坊主」は葉茶を茶臼で挽いて抹茶を作る坊主。三句「つかえじ」は「使へじ」に「支へじ」(肩が「こらない」)を掛けた。結句の「やんま」は大形の「とんぼう(蜻蛉)」で「けんぺき(肩癖)」は按摩のこと、見立てである。
巻末に「柳門狂歌十徳」を載せている。このうち「俗諺俳言を用ゆれば児女のたぐひ牧童樵夫のともがらも耳近くて心得易し」「梵漢の語も其(の)ままにもちゆれは詞広(く)して詩歌にいひ残す情ものべやすし」「はやりうたはやりこと葉の拙きも此(の)道に用ゆれはやさしくなれり」等は正岡子規の「生は和歌につきても旧思想を破壊して、新思想を注文するの考にて、随(したが)つて用語は、雅語、俗語、漢語、洋語必要次第用うるつもりにて候」(岩波文庫『歌よみに与ふる書』)を思わせる。狂歌は和歌の落胤のような名称を戴いているが木端は三十一文字における素材及び用語の選択の自由を謳っているのである。これを雅に対する俗として説明するのは正しくない。雅俗は和歌の問題であって狂歌の与り知らぬことなのだ。雅俗とは、和歌の制約によって雁字搦めになっている、その証左にほかならないのである。
|
| 第7回 朋ちから(1) |
ぽんぽんと餅つくおとのきみか代や千代にやちよにさされ石臼 九如館鈍永
『朋ちから』の撰者は九如館鈍永(一七二三~一七六七)、刊行は宝暦三(一七五三)年である。掲出歌の題は「或方の餅つきに石の臼にてつかれしに」。木の臼だと〈うすの音ぼたんぼたんと花やかにするは富貴な家のもちつき〉(『狂歌手なれの鏡』)だが石臼は「ぽんぽん」と音も「気味」が良い。その「気味」に「君」を掛けて賀歌「君が代」の詞に乗せた。
立春へぬけてやけさののんとりは誠に月の太郎殿なり
花よりもたんこよりまたよい物を給はりけりな卯月やうかん
ほのほのとあかしにあらぬこちのうらに人まるめろのなるかきのもと
たれも来て都のにしきこき薄き名こそ高雄のもみち葉の色
高雄山裾ふく風に紅葉葉のうらを見せたり表見せたり
一首目の作者は塵尾店乙介、題は「元旦」。三句「のんどり」はゆったりとしてこせこせしないさまをいう。下句は一月の異称が「太郎月」、これを擬人化して「太郎」(総領息子)のイメージを重ねた。二首目の作者は不外堂末中、題は「四月八日に羊羹をもらひて」。成句「花より団子」その「団子よりまたよい物を給はりけりな」、助詞の「な」は感動を示す。結句の「卯月」は四月、「羊羹」に「八日」を掛けた。三首目の作者は観月亭鈍及、題は「奴か庭にまるめろ出来たるを」(「やっこ」は一人称の人代名詞)。四句に「人麿」と「マルメロ」を重ね、結句も果樹の「柿の本」に人名である。本歌は伝人麿作〈ほのぼのとあかしの浦の朝露に島隠れゆく舟をしぞ思ふ〉(『古今和歌集』四〇九)である。四首目の作者は末中、題は「高雄の紅葉見に罷りて」。二句は「錦(にしき)」に「西」を掛けた、三句は「錦」の「濃き薄き」となる。上句で「き」音が交響する。五首目の作者は霏雲亭漏月、題は同前。二句「裾」は着物の「裾」を掛けた。対句の下句だが「たり」は助動詞より接続助詞で言い止しの感がする。ちなみに良寛の「うらを見せおもてを見せてちるもみぢ」(『はちすの露』)よりも早い。
てにおはのかもをは中へあしらふてみそしひともし振(る)舞(は)れけり
若衆方年はさやうにみえねとも豆のかすにそおとろかれぬる
詣ふて来る百万遍のくりみれはすはいたすはいた梅のすはいた
一首目の作者は漏月、題は「鴨葱を振(る)舞(は)れて」。初句は枕詞風に展開して助詞の連語「かも」で「鴨」を呼び出した。四句「三十一文字」に「味噌」と「葱」(「一文字」は女房詞)だろう。二首目の作者は鈍永、題は「節分に役者のとしを聞(き)て」。初句「若衆方」は歌舞伎で美少年に扮する俳優のこと、下句は豆の数に実年齢を見た。本歌は藤原敏行の〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(『古今和歌集』一六九)である。三首目の作者は舎楽斎鈍草、題詞は「洛東百万遍に詣ふてけるに庫裏のあなたに梅のこすへ見えけるを」(百万遍は知恩寺)。四句の「すはい(楚)」(すわい)は「すはえ」(若い小枝)の音変化、これに類音「酸っぱい」で「楚だ楚だ梅の楚(酸っぱい)だ」となる。
|
| 第8回 朋ちから(2) |
あふむさん念珠の親の玉の緒はふつつり切(れ)て涙とまらす 皓々舎蚊睡
掲出歌の題は「母のわかれに」。初句は「おお無残」と読んだ。「あふさか(逢坂)」は「おうさか」、「う」が長音の例に倣った。ほかに「狐釣のわなを狐かくわへ逃(げ)る絵に」の題で可陽亭紅圓に〈あふにくや狐は逃(げ)てたのみつるわなもとられて猟師こうくはい〉(『朋ちから』)もある。上句、数珠の中心となる大玉が親玉、また「緒」は紐かつ命でもある。
ともにしたふ心をすくに手向にと申(す)詞の花たてまつる
咲(く)頃は此(の)世も後世もかはるまい仏果もよしの花の台に
世にあらばバアといふへし地の下へかくれん坊主扨もかはいや
手習(ひ)に顔はさなからむさし坊七ツ道具の年はゆかねは
一首目の作者は鈍永、題は「同手向(け)の詠」。「同」は「羅人一周忌に壇主法林寺に縁類あつまりて」である。初句は「共に慕ふ」、二句は「直ぐに」と乞われて即詠で応じたというのである。二首目の作者は向嶽亭青人、題は「友とちの老父弥生の此身まかり給ひしを」。二句の「後世」は「あの世」の意で、四句「仏果」は成仏の証果、結句は「善しの」に「吉野」を掛けた。「花」は桜しかない。三首目の作者は鈍永、題は「一七日墓所にまかりて」。これより前に題「愚息六才にて身まかりしを」で〈一のうらは六さいの秋はかなくもさいの川原へなかき別れ路〉がある。「骰子」に「才」を掛け、また同音の「賽(の川原)」へと変化する。掲出歌では二句「バア」が切ない。四首目の作者は菊緒、題は「手習(ふ)子の顔に墨の付(き)しを」。上句は顔についた墨が頬髭に見えるのだろう。三句は「むさし」の平仮名であどけない「坊」を忘れない。なにしろ下句は「七ツ道具」で七歳の年端のゆかぬ弁慶なのだ。
梅さくら松田の家の小童かあんとに取(り)添(へ)玉はつて候
帆をあけてさぬきを的に入(り)舟の弓手のかたにつる打(ち)の山
一九二十三馬四きりにせかまれて書(く)ははちかみこむしんの賛
一首目の作者は鈍永、題は「友人松田某やつかれか詠を見せよこにかれこれ書(き)付(け)持参せる折しもたそかれにて主老人成(り)けれは目鑑と行燈もてよとせはしくいへるに小童のいそき目かねを落(と)し玉破れけれは主ことなふいきとをりしに」。「やつがれ」は「友人」の自称となる。「梅さくら松」は『菅原伝授手習鑑』に拠ろう。結句は友人の作品を「給わった」に「玉割った」を掛け、小童への助け船とした。二首目の作者は漏月、題は「讃岐に罷る舟中にて」。四句は左側をいう。結句は呪いとして行う弦打ちと同名の「弦打山」をいう。『角川日本地名大辞典』によると高松市の石清尾山から浄願寺山にかけての山々らしい。三首目の作者は温古堂百亀、題は「馬三匹書(き)しに」。絵の賛を求められたのである。「一九」「二十」「三馬」「四切」もカルタ用語だが、その「四切」に「頻り」を掛けた。ここまでを「せがまれて」の序詞とする巧みさながら「恥ぢかみ渾身の賛」と実に謙虚なのだ。
|
| 第9回 狂歌水の鏡(1) |
義経はとり落とさねと壇の浦のなみにうかみし弓張の月 山果亭紫笛
『狂歌水の鏡』は宝暦四(一七五四)年の刊、詠者は山果亭紫笛(一七一八?~一七七九)、山果亭は初号で後に如雲舎と号した。掲出歌の題は「古戦場ノ月」。馬を海中に乗り入れて戦っているときに平家の舟から熊手が襲ってくる。『平家物語』だと「いかがしたりけむ、判官弓をかけおとされぬ。うつぶして鞭をもッてかき寄せて、とらうとらうどし給へば、兵共、『ただすてさせ給へ』と申しけれども、つひにとッて、わらうてぞかへられける」(小学館『日本古典文学全集 三〇』)という場面である。注意する老武者に義経曰く、弓を惜しんだのではない。ひ弱い弓ゆえに名を惜しんだというのであった。結句「弓張の月」は弦月である。
さかりとは遠目からてもかくれもない大名小路のさくら花かな
色里に身をうつはりのつはくらめうつくしい子をおもふてや来る
小袖地にそめし代ものさはけねはころもかえうきけふの呉服屋
かみなりの太鼓の皮はさもなくてきひしい音に夢かやふれた
一首目の題は「候第ノ花盛也」、「候第」に「ヤシキマチ」とルビがある。四句「大名小路」は「永楽町・八重洲町・有楽町の大通り。大名屋敷が多かったのでいう」(講談社学術文庫『江戸語の辞典』)、紫笛は大阪の人であるが江戸にも通じていたのだろう。二首目の題は「章臺ニ燕来」、「章臺」に「イロサト」とルビがある。成句「梁の燕」(子を思う親の愛情が深いことの喩え)があるが、初二句「色里に身を打つ」(色里に打ち込む、身を滅ぼす)の内包は親と子以外の燕を思わせる。三首目の題は「綵帛舗ノ更衣」、「綵帛舗」に「ゴフクヤ」のルビがある。初句「小袖」は絹の綿入れをいう。冬物が捌けないのだ。本歌は源重之の〈花の色にそめしたもとのをしければ衣かへうきけふにもあるかな〉(『拾遺和歌集』八一)である。四首目の題は「雷鳴妨夢」。三句は「然もなくて」、雷鼓(雷神が持つという太鼓)の皮が破れたのではない、そうではなくて「私」の夢が破れた、安眠もあったものではないというのである。
ふたこころとや人の見ん古戦場にはふ葛の葉のうらかへりしは
棚の上に蓮のいとこやはとこまてをきしは露の玉まつりかや
この家をかりてすみたくおもふかや普請のうちから月かさしこむ
一首目の題は「古戦場ノ葛」。四句「葛の葉の」は「うら」や「うらみ」などに掛かる枕詞だが、その葉の裏返るさまを裏切りに喩えた。古歌〈秋風の吹き裏返す葛の葉のうらみてもなほうらめしきかな〉(平貞文『古今和歌集』八二三)以後の歴史が新味を加えている。二首目の題は「魂祭色々」。初句の「棚」は「盆棚」(精霊棚)をいう。二句の「蓮」は蓮根を意味し、「いとこ」「はとこ」とは季節の野菜や果物だろう。ところが四句「置きし」で「置く露の」の意を帯びて「玉」、「玉」の同音の「魂」を導いて「魂祭り」に落ち着くのである。三首目の題は「修造場ノ月」、「修造」に「フシン」のルビがある。二句は「住みたく」に「清みたく」が掛かる。棟上げ前後、外観と内部の双方が露わな家に擬人化した月の配合が美しい。
|
| 第10回 狂歌水の鏡(2) |
分銅のあらたまる春もよけれともなれたふるとしおしむ両替 山果亭紫笛
掲出歌の題は「歳暮ノ兌銀舗」、「兌銀舗」に「リヤウカエヤ」のルビがある。二句の「改まる」は「分銅」にも「春」にも掛かる。『日本国語大辞典』で「分銅改」を引くと「近世、ある期間を限って、秤の分銅の量目を検査したこと。分銅製作の専売権を有した分銅座の後藤四郎兵衛家がこれに当たった」とある。どう改まるのかは触れられていないが下句「慣れた旧年惜しむ両替」だから無条件て受け容れる春と、そうでない春と二様であったことがわかる。
また誰か住(む)ともなきにかしや札野分の風かふきまくるかや
ちかつきにちよつとあふむの挨拶やようふるといへはようふるといふ
猿ならて日よりを見んと船子共へさきにちよいとそれ立(ち)たりな
空はれてまことにめてたうさふらひのえほしに似たる帆かけ舟かな
一首目の題は「空館ノ野分」、「空館」に「アキヤシキ」のルビがある。二句「住むともなきに」と下句「野分の風が吹きまくるかや」が目に止まる。人が住んでいたらまだしもの感なのだ。三句の斜めに貼られた「貸屋札」を持っていきそうな風が思われて凄い。二首目の題は「挨拶ノ天象」。二三句「鸚鵡の挨拶」は「鸚鵡のような挨拶」の意だろう。人の言ったとおりに言い返すことを鸚鵡返しというが、この類である。「よう降りますね」「よう降りますね」、天候の挨拶はかくあらねばならないのである。三首目の題は「海辺ニ日和ヲ見ル」。三句「船子」は船頭の指揮下にある水夫をいう。立ったのは「舳先」、船の先端、船首である。結句の「な」は感動と詠嘆、その身の軽さと日焼けした姿から初句「猿ならで」となった。四首目の題は「晴天懸帆船」、「懸帆船」に「ホカケフネ」のルビがある。二句は「まことにめでたう」(「めでたく」のウ音便)、三句は上から「(めでたう)候ひ」、下へは「侍(烏帽子)」となる。三句を共有しながら意味を転換し、頂を折り伏せた武家烏帽子と帆掛け船の帆の形の類似をいった。
世の義理も褌もかかぬ閑居とてふらつきけりな軒の風鈴
さみせんのたうとん堀の床なれは糸ひん撥ひんひきつけて結(ふ)
勢田ならてわたし普請の橋大工むかてのやうにはたらきそする
一首目の題は「閑居ノ風鈴」。初二句は成句「義理と褌欠かされぬ」(身に付ける褌を例に出して義理を欠いてはならないことをいう)を使った。しかし二句の平仮名は「掛かぬ」(義理を掛けない。褌を結ばない)だろう。そういう軒に風鈴が「ぶらつきけりな」、いたずらに日を送る閑居なのだ。二首目の題は「水辺ノ床髪結(ひ)」。「床髪結ひ」は屋台で営業する床屋である。初二句は「三味線の道頓堀」、「堀」のみ漢字で題を強調し、芝居小屋で賑わう町を表す。四句の「糸鬢」も「撥鬢」も男子の髪型、「糸」「撥」と三味線の縁語が続く。三首目の題は「工人閙」、ルビに「ダイクイソカハシ」とある。初句「勢田ならで」は「あの瀬田の唐橋ではないが」といったニュアンスが響く。実際もそのとおりで二句の「渡し普請」は請負の安普請をいう。だから大工も「百足のやうに(一人で五十人分か)働きぞする」なのだ。
|
| 第11回 興太郎 |
にくまれて添(ふ)はてふよりわしは又かはひからるる内にしにたや 縫女
『近世上方狂歌叢書十三』所収の『興太郎』は九如館鈍永撰、宝暦六(一七五六)年の刊行である。掲出歌の題は「油煙斎の歌に にくまれて世に住(む)かひはなけれどもかわひがられてしのよりはましと有(る)をききてさもあるべけれども」。引用歌を抜き出すと〈憎まれて世に住む甲斐はなけれども可愛がられて死のよりはまし〉だろう。「死の」は「死ぬ」の意と解した。これに対して〈憎まれて添ふはてふより儂はまた可愛がらるるうちに死にたし〉と返した。二句「てふ」(ちょう)は連語で「という」。三句の「儂」(「わたし」の音変化)は一人称の人代名詞、近世では主に女性が用いたという。二者択一の生き方が鮮明である。
下さるる土産はなんと能(く)見れは音に菊屋の霰酒也
仏壇へいき世のみたの来迎は極楽世界一はいの箔
王城の鬼門かまはす釣(る)かやは隅々四天のあれはなりけり
一首目の作者は観蛍亭、題は「南都へ罷りし人の土産とて霰酒給はりて」。二句の副詞「何と」に「南都」を掛ける。霰酒は奈良の特産、焼酎に浸して乾燥させた霰餅を味醂に入れて熟成させたものという。四句「菊」に「聞く」を掛けた。二首目の作者は塵尾店乙介、題は「仏壇あらたに出来隠居せる人に」。二句は「生き世を弥陀の」、「生き世」は「此の世」の意。また「生き」に「行き」、「弥陀」に「見た」を掛けた。下句は「極楽世界」が弥陀、仏壇が「一杯の金」、しかし「一」の帰属は不可分なのが現実であるかも知れない。三首目の作者は蝸牛舎市葉、題は「蚊帳」。二句「鬼門」は陰陽道で邪悪な鬼が出入りするとして万事に忌み嫌われた丑寅の方角だが、気にせず蚊帳は吊るのだという。四句「四天」は蚊帳の上部の四方のへり、四箇所に四天があり、別義で東西南北の方角だから丑寅も帳消しにされるのである。
来年もなを豊年て御座候(ふ)と屋毎屋毎にふれるしら雪
ほんほんときねか鼓にあらねとも打(つ)より手にてならす餅つき
産業もやすななり風俗恥かしや紙屑のはのうらみうらみて
一首目の作者は柳雫軒止月、題は「雪」。大晦日の夜だろう。三句七音、上句は成句「雪は豊年の瑞」、作中主体は「天」の趣きである。三好達治の「雪」(太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。/次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。)が思われる。二首目の作者は永得、題は「餅搗」。〈ぽんぽんと杵が鼓にあらねども打つより手にて均す餅搗き〉。初句の擬音から鼓が登場する。結句は介添えが餅を「均す」に鼓を「鳴らす」を掛けた。三首目の作者は如実、題は「寄帋屑買」。初句「産業」は生業の意、紙屑買いは紙屑やその他の不用品を買い歩く職業らしい。二句は「安ななり風俗」で十音、「安」は金額の安いこと、「ななり」は「~であるらしい」。句跨りで「風俗(身なり)恥かしや」は作中主体「私」の感想であろうか。同時進行で二句の阿倍「やすな」(保名)から〈恋しくば尋ね来て見よ和泉なる篠田の森のうらみ葛の葉〉(『信田妻』)を下句に響かせた。「葛」に「屑」、「葉」に紙の「端」を掛けている。
|
| 第12回 狂歌かかみやま(1) |
大小を見するこよみは武士に似てことし加増のありし吉日 栗柯亭木端
『狂歌かかみやま』の撰者は栗柯亭木端、刊行は宝暦八(一七五八)年である。掲出歌の題は「宝暦五年の新暦よりみつの吉日のませしをみて」。宝暦五年から四十三年間用いられた宝暦暦をいい、「みつの吉日」は暦注下段に加えられた天恩日、母倉日、月徳日である。初句の「大小」は武士の大刀と小刀に擬えた大吉と小吉、吉日もその縁語で「加増」となった。
あさ市の道具もいまたうれぬのに霞の絹か包みかかつた
またまけぬ気のはや河てとけのこる氷のせきか春とすまふた
開きしとひらかぬはなの唇はあうんて梅のにほふ成(る)らめ
たたくへき月下の門に匂ひ来て寺中のむめの盛りをは知る
一首目の作者は千樹、題は「霞朝市ヲ隔ツ」。上句「朝市の道具も未だ売れぬのに」その「道具」を包み「かける」とは、いや「かかる」なのである。そこでズーム・アウトすると霞の掛かった朝市が全景を現すのである。二首目の作者は仲野宜々、題は「早河氷猶残ル」。初二句「まだ負けぬ気の早る」意を普通名詞の早河に掛けた。四句「氷の関」は擬人化して関取、また氷は川の「関」でもある。結句の四音は「争(すま)ふ」の連用形に助動詞「た」で「すまひた」、これのウ音便で「すまうた」となる。三首目の作者は岫雲亭華産、題は「梅」。〈開きしと開かぬ花の唇は阿吽で梅の匂ふなるらめ〉。「花の唇」は花弁また美人の唇をいう。「阿吽」は呼吸、「花」に「鼻」を掛けて主体を梅から人に移した。結句「らめ」の類音に注目したい。四首目の作者は木端、題は「梅ノ花夜芳シ」。右肩の「本語」は「僧は推す月下の門」の「推す」を「敲く」に直したという故事「推敲」であり、これを使って梅の香りを描いた。
ゆうれいの姿かと見るくらかりのたうけに白き梅の立枝は
大名の普請場そとてあをやきも長うたらりとかかる春の日
錠ならておろす荷の内銭にして早うあけたきかきわらひかや
水ぬるむ池のやなきのいとを見て針にはあらぬみみつ出て来る
一首目の作者は木端、題は「嶺ノ梅」、「嶺」に「タウケ」とルビがある。右肩の「本語」は「幽霊」だろう。初二句から定型化された白衣と足の消えた姿を思わせる。場所も格好の「暗峠」(生駒山地の峠)である。しかし「白き梅の立枝」と美しい幕切れとなった。二首目の作者も木端、題は「修造場ノ柳」、「修造場」に「フシンハ」のルビがある。費用を惜しまない建築を大名普請また大らかな気質を大名気というが、これを三句の「~も」以下で具象化した。三首目の作者は千樹、題は「荷ヒ売リノ早蕨」。〈錠ならで下ろす荷の内、銭にして早う空けたき鉤蕨かや〉。荷の中は銭になる早蕨、早く空にしたいのである。鉤蕨は頭部が鉤の手のように曲がった蕨の芽をいう。錠と「おろす」、鉤と「あけたき」と縁語仕立てである。四首目の作者は木端、題は「水温カニシテ虫出」。二三句「柳の糸」の糸の縁語で針を出しかけたが引っ込めた。ではなぜ蚯蚓が出てきたのか。三句「糸を見」た仲間の糸蚯蚓なのであった。
|
| 第13回 狂歌かかみやま(2) |
花をとふに岫を出て来しくもかこか扨心なき返答をした 栗柯亭木端
掲出歌の題は「花を見にまかる山路にて戻りかごに花のありやなしやをとふに明らかに答もせで行(き)ければ」。右肩の「本語」は「雲無心にして岫を出ず」(陶淵明「帰去来辞」)だろう。「岫」は山の峰をいう。三句「雲駕籠」は雲助駕籠、雲助の語源に浮雲の行方定めぬところをいうともある。四句「心無き」の熟語は「無心」、但し陶淵明の詩心からは遠い。
はたこやの出たちのめしのゆけと共に霞みて見ゆる春の曙
時の花へ挨拶ふりに春の月わさとかすんてみせしものかは
破れあみつつくる海士の手伝ひを春雨やする軒のいとみつ
河ふねはふしみの岸てあかれとも猶こかれ来し花の白波
一首目の作者は修琴亭遙擲、題は「百首歌読(み)けるとき旅店ノ春ノ曙」。「旅店」は「ハタゴヤ」と読む。二句「出たち」は「出立ち」(でたち)で出発のこと。三句「ゆけ」は「湯気」に「行け」で下句に繋いだ。二首目の作者は木端、題は「春月」。初句「時の花」は、その時節に相応しい花、ここでは桜であろう。二句「ぶり」(振り)は、その物事の状態や様子の意を表す。結句「かは」は詠嘆を含んだ疑問で朧月と桜の配合の妙をいう。三首目の作者も木端、題は「百首うた読(み)けるとき漁家ノ春雨」。二句「つづくる」の漢字表記は「綴る(繕る)」で繕うこと、三句「海士」は「あま」で男を指す。結句「糸水」(雨だれ)は初二句の縁語、休漁の日も休みではない。四首目の作者は木端、題は「きさらぎの末都にまかりしにふしみの河船よりあがりすぐに東山の花を見めぐりて」。「伏見」は河川港としての伏見港、「東山」は東山三十六峰と呼ばれる山々、花は桜、河の縁で一首は「花の白波」と結んだ。
盛りめて折るはたこやの花の枝これも木賃の内にいれてよ
花見んと群来る人の目をぬくは巾着切のとかり鍖や
楽の名のこまいさみたつまひの手につなかぬ花もちりかかりけり
舞姫の世を遁れたる跡そとて花の色をはちつと残した
一首目の作者は木端、題は「旅店ニ花ヲ折(ル)」。「旅店」のルビは「ハタゴヤ」。初句は「盛(さか)り愛で」、四句「木賃」は客が自炊のため宿屋に払う薪の代金をいう。桜の枝も薪代で勘定してくれというのだ。二首目の作者は千樹、題は「花ノ下ノ覓絡児」。「覓絡児」のルビは「キンチヤクキリ」。三句「目を抜く」は人の目をごまかす意、また「抜く」のは財布でもある。結句「とがり鍖」の「鍖」は「やすり」と読んだ。三首目も千樹の作、題は「花の歌あまたよみし時花ノ下ノ舞楽」。初句は神楽歌の「其駒(そのこま)」だろう。『デジタル大辞泉』に「舞を伴う。神の乗り物の駒を歌って、惜別の情を表した歌」とある。下句は神楽殿の外の景を舞人に絡めて巧みである。四首目の作者は木端、題は「妓王寺にて庭のさくらの散(り)はててはつかばかりのこれるをみて」。「妓王寺」は滋賀県野洲市の寺、妓王の生れた屋敷跡ともいわれる。結句「ちっと」は「少し」の意。なお嵯峨の祇王寺は明治の建立である。
|
| 第14回 狂歌かかみやま(3) |
ととかかのそのわけとしもあら麦をこなす山田の秋のゆふくれ 燕果亭千樹
掲出歌の題は「夕ノ麦秋」(「麦秋」は麦の熟する時季。初夏の頃)。初句の「ととかか」は「とと」のような「かか」の意で「かかあ天下」をいう。二三句「その訳としもあら(なくに)」、三四句「荒麦を熟す」は脱穀の意である。結句は麦の秋をいう。歌意は「嬶天下という訳でもないが、かかの活躍が目を引く。そんな麦の取り入れで忙しい、初夏の夕暮れである」。
泪ならてすすろに落(つ)るいかほこり袖やすからぬむきの秋かせ
はしかさに隣在所へいてみてもいつくも麦のあきの夕暮
ほとときす竹田の宿て水銀の人形のようにおちかへりなく
田葉粉の名の国分峠のほとときす声もしめらぬ五月雨の中
一首目の作者は木端、題は「新題百首の歌読(み)けるとき麦秋」。二句「すずろに」は「むやみに」、三句は「いがほこり」(毬埃)で脱穀後の芒だろう。四句「安からぬ」は「落ちつかない」、風で衣服も麦の穂の棘だらけなのだ。二首目の作者は木端、題は「夕ノ麦秋」。初句の「はしかさ」は「ちくちくとかゆいこと」、二句の「隣在所」は隣の集落、「行て」は「行って」の約である。何処も同じ麦秋、はしかい夕暮れなのだ。三首目の作者は華産、題は「旅店(ハタコヤ)ニ郭公ヲ聞(ク)」。二句「竹田の宿」は京都市の竹田街道に面した宿と解した。街道名から竹田芝居(絡繰り芝居)の連想に及んだ。「水銀の人形」は水銀で動く人形で「復ち返り」から「段返り人形」が思われる。その人形のように繰り返し鳴くというのだ。四首目の作者は霞城亭朝三、題は「嶺(タウケ)ノ郭公」。初句六音。大隅国(鹿児島県)国分産、国分煙草として賞揚されたその質が四句から窺える。三、四首目とも鳴き声の比喩が面白い。
今日加茂の足そろへなる競馬とてむまのあふとちたうたうをする
玉ほこの道ゆく人の傘もやれて程ふるさみたれのころ
かやり火のふすへる閨の独ねに悋気て去(つ)たつま思ひ出す
縄をなふ真似するくせに蠅か夢むすはせぬのにこまる夏の日
一首目の作者は華産、題は「友どち打(ち)つれ加茂のきをひ馬のあし揃へを見にまかりて」。足揃えは馬の遅速を調べること、下句は「馬の合ふどち同道をする」。馬の縁で馬が合う友どちとした。中に「王都路」と馬を御する「どうどう」を掛けた。二首目の作者は宵眠、題は「五月雨」。三句「傘」(からかさ)は油紙だから四句「破れて」も不思議でないが、初句「鉾」の存在は見逃せない。「程ふる」は「程降る」で空間の状態、「程経る」で時間の経過を示した。三首目の作者は木端、題は「百首歌よみしとき独寝ノ蚊遣(り)」。「燻べる」には「煙を立たせる」意と「嫉妬する」意がある。初二句は前者で蚊の場合、三句以下が後者の場合となる。悋気の元とともに思い出されるのだろう。四首目の作者は木端、題は「蠅ニ依(リ)テ夏ヲ厭フ」。初句「縄を綯ふ」は蠅が手を擦るさま、その「綯ふ」の縁語で四句「結ばせぬ」となる。蠅が五月蝿いのである。また縄と蠅の偏は異なるが右側を共有しているところも面白い。
|
| 第15回 狂歌かかみやま(4) |
なには橋はなひの光りかけきえて市人わたる夏の明ほの 右文堂正則
掲出歌の題は「夏ノ早起(キ)」。現在の橋は中之島の延伸で堂島川と土佐堀川に分断されているが往時は一本であった。木端に〈山ざきのはなや夜風を引きつらんくつさめのやうに花火とびちる〉がある。山崎の鼻は中之島の東端、山崎家の蔵屋敷があったところ、今の中央公会堂の辺りだそうだ。この東が難波橋で花火見物で賑わった夜と対照的な朝を描いてみせた。
まつりの比俄に出(つ)る雲を見て皆夕たちの所望をそする
ゆふ立の雲助かこか杖のやうな雨に暑さのいきつきをした
いなつまの鑰て明るかなるかみの天の戸ほそをくわらくわらくわら
花とちかひふかぬ嵐に汗の露打(ち)ちらしたる夏のひさかり
一首目の作者は千樹、題は「夏雲」。「夏雲」は積雲(綿雲)や積乱雲(入道雲)をいう。とりわけ積乱雲は雨や雷を伴うことが多い。祭りの前に一雨欲しい、一雨降って気持ちのいい夏祭りを迎えたい、実際にもそのような空なのだ。二首目の作者は千樹、題は「あつさ強かりける比夕たちのしければ」。初句「夕」の平仮名表記で「立」のイメージを養い、二句「雲助(駕籠)」で展開、三句「杖のやうな」、結句「息継ぎ」もそうだろう。雲助の縁語で固めた。三首目の作者は岡田青牛、題は「雷」。二句「鑰(かぎ)」は錠を開閉する金具をいう。次の「あかる」は「明るくなる」意。四句「戸臍」の「臍」は「鳴神」の縁語、これが原義で表記は「枢」、意味は「戸」、結句「がらがらがら」と鳴って雷のお出ましなのだ。四首目の作者は木端、題は「夏ノ昼」。初二句で成句「花に嵐」を出した。夏の暑さを妨げる風が吹かないというのである。四句の「打ち」は接頭語で下の動詞を強調する。長い夏の昼しかも無風なのだ。
しんこにはあらぬ山路をうねり来て涼しくむすふ滝のしらいと
龍宮から奪ひにこねと涼しさに玉の汗をはうしなひしふね
すい瓜の中並へるたねは照るといふ文字の連火の姿かと見る
水の面に照る提燈の数そひて今宵まつりともやつきにけり
一首目の作者は古梅園栗洲、題は「納涼ニ水ヲ翫ブ」。初句「しんこ」(振古)は太古の意。上句は「太古ではないが、太古のような山道をやってきた」となる。四句「結ぶ」は水を掬う意である。結句の見立て「滝の白糸」、その白糸の縁となる。二首目の作者は木端、題は「舟遊ビニ夏ヲ忘ル」。二句は「奪ひに来ねど」。浦島太郎が「龍宮」で土産にもらったのが玉手箱で、その玉から「玉の汗」を呼び出した。また船遊びで汗も引いた、それを初二句の縁で結句「うしなひし」としたのが卓越である。三首目の作者は木端、題は「西瓜」。四句「連火」は「烈火」のことで漢字の脚の一。三句「照」の「灬」の部分をいう。種の並んだ姿を視覚的に捉えた漢字歌である。四首目の作者は滝絲巷千丈、題は「夏祓ノ灯水ニ移ル」。三句「数添ひて」は「数が増えて」。結句「もやつく」は「混乱する」と「気持ちが乱れる」の意がある。下句「今宵祭りと~」で夏越しの祓えと夏祭りがごっちゃになりそうだというのである。
|
| 第16回 狂歌かかみやま(5) |
なかんつく秋のゆふへの風にきく捨(て)子の声ははらわたをたつ 坤井堂宵眠
掲出歌の題は「百首歌読(み)しとき秋ノ夕ノ捨(て)子」。「本語」とあるのは「断腸」だろう。同題で木端の〈すてられて何のくわんせもなく声を親はきかぬか秋の夕くれ〉が並ぶ。「頑是も無く」の「無く」に「泣く」を掛けた。これに続く「なかんづく」(とりわけ)となる。風に乗って聞こえてくる泣き声は結句「腸を断つ」(断腸の思いがする)というのだ。
名にしおふ中けんなれはさし鯖をさしこはらしてきつとことふく
いもの葉のゑくみの中にをく露は悪人形のなみたかと見る
下りふねあたこ参りの夢と共にしきみに結ふよはのしら露
きりきりす北山の手の金かくのあたりは将棋させとてやなく
一首目の作者は華産、題は「盆の祝儀を饋るとて」。初句は「名にし負ふ」。二句は武家の下僕である「中間」に「中元」を掛けた。中元は乾物の「刺し鯖」である。受け取る中間は「差し強らして」(刀を差して武張って)、「きっと」弛みのないさまで喜びをいった。二首目の作者は木端、題は「芋ノ葉露ヲ帯(ブ)」。二句「ゑぐみ」は「ゑぐい」(気が強い。思いやりがない)の語幹に接尾語「み」が付いた名詞、広くて分厚い葉に歌舞伎の敵役である「悪人形(あくにんがた)」の涙を配した。三首目の作者は木端、題は「夜船の露」。京都の愛宕神社を参拝した帰りの船中を詠う。四句の「結ぶ」は「夢」と「露」の双方に掛かっている。神社といえば榊であるが愛宕神社の神花は樒なのである。四首目の作者は紫笛、題は「秋の歌の中に」。北山の金閣寺を使ってキリギリスを将棋仕立てとした。初句は「切り切り(す)」、二句「手」、三句「金角」、下句「将棋させ」は一般に「チョンギース」、鳴き声のオノマトペである。
胸の輪になつけし月の影なれとこよひの空はくまのけもなし
俊寛かしはしは月の舟よのう雲の波まに見えつ隠れつ
まん丸なこよひのもちのかけたるは月の鼡やしよくすなるらん
宇治橋を引(い)たむかしも曳(か)ぬ今も澄(み)わたりぬる月はかはらす
一首目の作者は木端、題は「さやけきを賞して」。〈月の輪に名付けし月の影なれど今宵の空は隈の気もなし〉。歌意は「月の輪から名付けた月の輪熊の月は三日月だが、今宵の満月は欠けたところがない」。結句に「熊の毛」を掛けた。二首目の作者は華産、題は「くもりし月のさやけきとみるほどに又雲にいりけれは」。上句の「俊寛がしばしは月の舟よのう」は「私」の溜め息で下句に謡曲『俊寛』の最後の場面「舟影も人影も、消えて見えずなりにけり」を重ねた。三首目の作者は栗山、題は「中秋の月蝕しければ」。中秋の名月が月蝕で欠けたのである。四句「月の鼠」は月日の過ぎてゆく比喩であるが、ここでは月に棲む鼠の意で借用した。結句「食」に「蝕」を掛けた。四首目の作者は木端、題は「古戦場ノ月」。昔とは一一八〇(治承四)年、源頼政が戦死した橋合戦をいう。橋板を引いて、取り外して敵が渡れないようにしたのである。しかし引く引かぬの橋とは別に今昔「澄み渡りぬる月は変はらず」なのだ。
|
| 第17回 狂歌かかみやま(6) |
而后のつきとてもなかより致知各別那誠意晴天 木端
掲出歌の題は「よもすがらくまなきにもちの夜のくもりがち成りし事を思ひて」。右肩の「本語」は『大学』の「格物致知」だろう。手に余るが「而后(じご)の月/とてもなかより/知致すれど/各別なんぞ/誠意晴天」と読んだ。終夜を隈のない月が続き、而后(それから)の満月(最中の月)が曇る。「致知」の次は「誠意」だが天候は格別、晴天は約束されない。
山の端を東国かたから出る月に抑(も)これはの能をはしめる
おやかたきめくりあふまて忘るなと空行(く)月や照(ら)すなるらん
いかたしの丸太は杉とおもひしによしののかはにきりもなかるる
ひなの秋はわきて淋しくおもひてや京街道にたちのほる霧
一首目の作者は華産、題は「月ノ下ノ申楽」。「申楽」は能楽の旧称である。二句から三句は「これは東国方より出でたる僧にて候」(『田村』ほか)、四句も「そもこれは嵯峨の天皇に仕へ奉る臣下なり」(『嵐山』)と定番の詞章である。また能舞台は野外であった。二首目の作者は木端、題は「月敵討(チ)ヲ照(ラ)ス」。「本歌」とあるのは『伊勢物語』第十一段の〈忘るなよほどは雲居になりぬとも空ゆく月のめぐりあふまで〉だろう。江戸時代の敵討ちは記録に残るだけで百件を越えているらしい。三首目の作者は木端、題は「早川ノ霧」。初句は「筏師の」、四句は奈良の吉野川である。「杉」は吉野杉と呼ばれる良材で酒樽などに使用された。「桐」は匂わせるだけ、秋は霧が流れる早川なのだ。四首目の作者は華産、題は「街道ノ霧」。初句は「鄙の秋」、二句の「分きて」は「分けて」(とりわけ)に同じ、これに霧の「湧きて」を掛けた。三句の「や」は反語となる。四句「京街道」は大坂から京都に至る道をいう。
つくつくと見れはとこやら三日月のおさなかほある十三夜かな
いもよりも豆ある岸へわたし船さすや今宵の十さうのつき
天に通ふ橋にのほりて見るもみち彼(の)七夕の織(り)しにしきか
名に高きよしののうるしもみちにはかへてもそはへよらはまけうそ
一首目の作者は栗山、題は「九月十三夜」。十五夜は中秋の名月で満月だが、十三夜(のちの月)は少し欠けた月になる。この隠れている部分を三四句「三日月の幼顔」といったのである。初二句の熱心さがないと観察は難しい。二首目の作者は影馴亭花鈴、題は「十三のわたしにて」。「十三(じゅうそう)」は今の大阪市淀川区にある地名である。初句「いも」(八月十五夜の芋名月)から二句「豆」(九月十三夜の豆名月)へ「渡し船(棹)さすや」十三の渡しなのだ。実景にして比喩の船が進む。三首目の作者は木端、題は「東福禅寺の通天橋のもみちを見て」。東福寺は京都市東山区本町にある臨済宗東福寺派の大本山 、通天橋は現在も紅葉の名所として人気が高い。下句はその見立てである。四首目の作者は修琴亭遙擲、題は「漆ノ紅葉」。紅葉といえば楓の別名、また紅葉する木の総称でもある。ここは本家本元と吉野漆の対戦である。結句「負けうそ」(「負けようぞ」の音変化だろう)は漆にかぶれる意でもあった。
|
| 第18回 狂歌かかみやま(7) |
冬来ても木々には似いて米ふみの働きしけき酒はやしの内 木端
掲出歌の題は「初冬ノ酒店(サカヤ)」。二句「似いで」は「似ないで」、「いで」は接続助詞である。三句「米踏み」は水車精米に対する足踏精米をいう。結句「酒林(さかばやし)」は酒屋の看板、杉の葉を球形に束ねて軒先に吊した。見所は初句の「来」、二句の「木々」、四句の「き」音で初二句とは逆に結句が「林」となった。なお当時は寒造りが主流であった。
捨(て)られししかみひはちも冬くれはめし出(だ)されて撫(で)さすらるる
うれへ場か袖をそぬらす時雨月はや一とせも四段目となり
きりきりすのねも枯(れ)行(き)し冬ののに牛飼(ひ)はかりさせいとそいふ
あら行のむかし忍ふか男へし霜にこたえし那智の谷あひ
一首目の作者は栗葉軒如擽、題は「初冬ノ火鉢」。二句の「獅噛み火鉢」は獅噛みの意匠(獅子の頭を模様化したもの)を脚に施した金属製の丸火鉢をいう。下句の冬「召し出だされて撫でさすらるる」は愛玩を思わせる。二首目の作者は千樹。題は「時雨ニ袖濡(ラ)ス」。初二句「愁へ場か袖をぞ濡らす」が三句「時雨月」の序詞となる。春から始まった一年は十月の冬で四段目と、こちらも芝居仕立てである。三首目の作者は木端、題は「枯野ノ牛飼」。二句の「音」は冬の用意に衣を「綴り刺せ」と鳴いていた蟋蟀(古名「きりぎりす」)である。これに「枯野」の「根」を掛けた。で、冬野は牛飼いが牛を追う掛け声の「させい」ばかりだというのである。四首目の作者は木端、題は「百首歌よみしとき谷ノ間ノ寒草」。四句「霜に堪へし」は霜に耐えたことをいう。男顕屬・鼎峭唸埃圓蓮慂寝畔・譟抓・荼泙謀仂譴垢詈験个世蹐ΑF畸劼旅唸圓蚤譴紡任燭譴動貪戮六爐鵑世海箸砲覆辰討い襦・鐔蠅妊群擦・魘舛垢襦」
橋ふしん板またうたて張(り)つめし氷の上をわたるかはかせ
こめ洗ひに濁る流れの水見れはこえゆく年の関やしら河
光陰の箭か追(ひ)つめて年のゐも暦のまきの末にせまつた
夕顔のやとりの臼のをとならてはるの隣にこほこほの咳
一首目の作者は水香軒栗園、題は「橋ノ下ノ氷」。初二句「橋普請板まだ打たで」、建設中の橋は橋桁に橋板を渡していないのだ。反対に川面は氷が張り詰めている、その氷の上を川風が吹き渡るさまを詠った。二首目の作者は木端、題は「としのくれの歌の中に」。白く濁った米のとぎ汁が堰に向かっている、それを「年の関」に喩えた。「や」は反語である。また結句は福島県白河市あったという古代の関所「白河の関」(歌枕)を重ねた。三首目の作者は木端、題は「亥どし」。初二句は「光陰矢の如し」を使って箭を番えた狩人を登場させた。三句は「亥の年」を逆にして「亥」を走らせた。下句は暦の「巻」(巻物の「巻」に「牧」か)も末に迫った。四首目の作者は木端、題は「はやりかぜをひきし人のとしの末までしはぶきするをききて」。右肩に「夕顔巻」とある。上句は光源氏が夕顔の家に「宿り」耳にした「ごほごほと(略)踏みとどろかす唐臼の音」をいう。それと違って「春の隣にごほごほの咳」なのだ。
|
| 第19回 狂歌かかみやま(8) |
線香の甲斐なくたちて春のよの夢斗りなるかりましよの声 遙擲
掲出歌の題は「春ノ夜ノ切買」。本歌は周防内侍の〈春のよの夢ばかりなるたまくらにかひなくたたん名こそをしけれ〉(『千載集』九六四)である。題「切買」は逆さ言葉で「買切」となる。初句の「線香」は時計代わりで二句は「甲斐なく経ちて」だろう。結句は「『借りましょ』の声」、遊女を借りられる「私」にすれば「春の夜の夢ばかり」ということになる。
えん遠く年ふる川の娘とて染(ま)るはつせにこひを祈つた
六十の手ならひなれと美しい君かいろはにほの字とそなる
春の夜にかりねの声のきこゆれと花を見すてていにもなるまい
打(ち)こんてほうれん草の色なれはかねつけはとうもしてやられまい
一首目の作者は木端、題は「嫁入ヲ祈ル恋」。二句「ふる」は「旧る」、これに初瀬川に流れこむ「布留(川)」を掛けた。四句は紅葉する「初瀬」(奈良県桜井市。歌枕)に比喩として婚期を過ぎた娘の恋を重ねた。二首目の作者は華産、題は「老恋」。成句「六十の手習ひ」で習字に寄せた恋である。四句の「いろ(色)」は顔立ちや姿をいう。「ほの字」の用例はこれ以前にもあるが「いろはにほの字」は確認できない。三首目の作者は木端、題は「春ノ夜ノ切買」。〈春の夜に「借りね」の声の聞こゆれど花を見捨てて去にもなるまい〉。「借りね」は「借りる」の未然形に助詞の「ね」で「借りたい」となる。「花」は遊女、借りられる側としてそのあとが困るらしい。四首目の作者は紫笛、題は「寄草恋」。二句「菠薐草」に「惚れる」意を重ねた。三句の「色」はそんな様子をいう。四句「鉄漿付け」は初鉄漿を任された「鉄漿親」と解した。婚期の近い娘の叶わぬ恋に後見人の鉄漿親は「どうもしてやられまい」なのだ。
ねのいらぬ恋路は苔のさまなれやかはらぬ色とみえてつめたい
あはら屋の雨にはあらて恋すれは人めおほかみもるそ恐ろし
こかれぬる心ははな火の玉なるかめつたに内かとひ出たうなる
あた惚(れ)としらてまことをたて板にみつからうきなはつと流した
一首目の作者は田谷飛鳶、題は「寄苔恋」。初句「根の入らぬ」の対極に「根を下ろす」がある。三句の「や」は疑問の意。下句からの連想は「苔むす」「苔塔」ほか多い。なるほと「変はらぬ色と見えて冷たい」恋路なのだ。二首目の作者は霞城亭朝三、題は「寄獣恋」。初二句は母音要素「あ」音また類音の反復が快い伏線である。四句は「多み」(多いので)に「狼」を掛けて「人目多(か)み」、結句の「漏る」は初二句「雨」の縁語である。三首目の作者は木端、題は「寄玉恋」。三句の「か」は疑問の意。四句の「めった」は程度が甚だしいことをいう。「とう」は助動詞「たい」の連用形「たく」の音便形。恋する心を外に表したくて仕方がないのである。四首目の作者は華産、題は「寄世話詞恋」(世話詞は「立て板に水」)。〈あだ惚れと知らで誠を立ていたにみづから浮き名はっと流した〉。「徒惚れ」は叶わぬ恋、「みづ(から)」に「水」掛け、水の縁語が「浮き(名)」である。「はっと」は目立つさまをいう。
|
| 第20回 狂歌かかみやま(9) |
つくやみを何と申さんことの葉もつき夜烏のああと斗りに 霞城亭朝三
掲出歌の題は「蛻厳先生の身まかり給ひしをいたみて」。初句「つくやみ」が「お悔やみ」の間違いでないのならば「月闇」だろう。四句は上から「言の葉も尽き(夜烏の)」、下へは「月夜烏の」となる。「月夜烏」は月夜に浮かれて鳴く烏をいう。「月闇」はその対極だから浮かれて鳴くのではない。ただ「嗚呼」(烏は「唖唖」)と悲しみを繰り返すばかりなのである。
ふたらくの南の岸かとうとよする国のはてなる北の浦波
乙姫のをとに聞えしむかて山秀卿ならていてもみたやな
もろこしのよし野の山の花見かやから尻をかる春の日のたひ
けに風は天地のいきのことはりて木々のはとはのあひにそよいた
一首目の作者は木端。題は「但馬の湯へまかりける時きのさきの瀬戸といふ所にて北海のはてを見しに風のふくともなきに三四丈ばかりの浪の岸の岩根に打(ち)よせければ」。本歌は〈補陀落の南の岸に堂建てて今ぞ栄えん北の藤波〉(『新古今和歌集』一八五四)。三句以下で日本海の荒波を顕現した。二首目の作者は華産、題は「むかで山を遙(か)に見やりて」。「百足山」(三上山)は近江富士として名高い。「秀卿」は藤原秀郷(俵藤太)、大津市に勢多橋龍宮秀郷社がある。下句は「秀郷ならで行ても見たやな」。三首目の作者は木端、題は「旅行ニ馬ヲ借ル」。初句は古歌の例からも「吉野」に掛かる枕詞に数えたい。三句「かや」は詠嘆、四句「空尻」は駄賃馬をいう。カ音が響いて最後は旅気分である。四首目の作者は木端、題は「風」。〈げに風は天地の息の理で木々の波止場の間に戦いだ〉。上句の出典は『荘子』内篇第二斉物論篇である。木々は風避けの港、そこでは木の葉もそよそよと揺れ動くのである。
日もすてに傾く山の麓よりみれはたうけにかかるくもかこ
臼を曳(く)音もさなからなる神て太鼓のやうな水くるまかな
煙てふ草のはしめは其むかしたれそ思ひのたねやまきけん
御懇情やまやまふきてこの礼はいふにいはれぬをし花の色
一首目の作者は栗葉軒如擽、題は「薄暮ノ轎夫(カコカキ)」。「雲駕籠」は「雲助駕籠」である。雲助が峠に差し掛かったところを麓から見ているのであるが、平仮名を多用して夕雲のイメージを重ねた。二首目の作者は坤井堂宵眠、題は「新題百首のうた読(み)しとき水車」。上句が水車小屋の中、下句が外の水車の音である。前者に雷鼓の「雷」、後者に「鼓」を使った。水車が精米用に使われるのは江戸時代中期である。三首目の作者は木端、題は「新題百首の歌読(み)しとき煙草」。植物体としての煙草を詠う中に嗜好品としての煙草の縁語「思ひ」「(思)火の種」を絡めて巧みである。煙草の伝来は十六世紀、これまた「新題」で、明治の開化新題を遡ること百余年である。四首目の作者は木端、は題は「南都古梅園栗洲より井手の山吹ををし花にして歌添(へ)て恵まれしにむくふ」。二句「やまやま」(沢山あるさま)に「山吹」の「やま」を重ねた。下句の「言ふに言はれぬ押し(唖)花の色」は梔子色をいう。
|
| 第21回 狂歌かかみやま(10) |
難波橋か天神はしかしらねとも渡りものには長うかかつた 栗柯亭木端
掲出歌の題は「麻疹を久しく悩みて平臥せし人に」。「麻疹」は「ましん」また「はしか」、「平臥」は養生すること、「人」だから大人である。初句「(難波)はしか」と二句「(天神)はしか」に病名が隠れている。四句「渡りもの」は渡る橋と人から人に感染する病を重ねた。「麻疹は命定め」ともいわれ、また患者は子供に限らない、今とは随分と違う印象がする。
見事なるさめやつはすにうち交り浪の平かと思ふたち魚
燈の油となれる鯨こそしにひかりとはいふへかりけれ
からすきはつけねと筆のたかやしのたすけとなるや水いれの牛
檀尻のちきちきちんちゃんひいたれは絵もういて出るはすて社あれ
一首目の作者は木端、題は「新題百首の歌読(み)し中に刀魚(タチウヲ)」。二句は「鮫や津走に」、「津走(つばす)」はブリの幼魚をいう。四句「浪の平」(波の平)は薩摩国谷山村波平に住んだ刀工の一派また製作した刀をいう。太刀魚の姿態を流派の名で喩え、また「刀」で喩えた。二首目の作者は木端、題は「鯨」。初句は「ともしびの」、四句「しにひかり」(死に光)は死後に残る栄光をいう。鯨油は文字通り世の「光」となったのだ。三首目の作者は木端、題は「新題百首の歌読(み)しとき水滴牛(ミズイレ)」。初句「からすき」(唐鋤)は柄が曲がって刃が広い鋤、牛や馬に引かせて田畑を耕すのに用いる。結句「水入れ」は硯に注ぐ水を入れておくための器、牛がデザインされているのだ。四首目の作者は木端、題は「天満宮に長崎辻何某のかけるうきゑの絵馬をみて」。二句は楽車の鳴り物だろう。「浮絵」は遠近画法を施した浮世絵である。まだ日も浅いのだろう、三句「引いたれば」だから今一つなのだ。
おさな子のみやけにせんと鶉もちちちくわい中の銭出してかふ
傘のえのまぬ我にさかつきをくつとほせよやさしかけといふ
しゆもくならてこれは至極の鐘の段上手てこんすと世になれるはす
やつはしの半分なれと河の数三河にあらて四かはなかむる
一首目の作者は木端。題は「餅の歌よみける中に鶉餅」。四句「ちちくわい」は鶉の鳴き声を表す語、「ちちくわい中」て「父懐中」、「かふ」が平仮名なのは「買ふ」に「飼ふ」を縁語とした。二首目の作者は岡田青牛、題は「酒をしゐられて」。初句「傘」は「からかさ」。二句の「え」は副詞、これに「柄」を掛ける。四句「干せ」は酒にも傘にもいう。結句「差し掛け」は立派な無理強いである、傘では外の人に差し出すことをいう。三首目の作者は木端、題は「堀本やといへるが平仮名盛衰記の鐘の段の浄留理をききて」。初二句の「撞木ならでこれは至極の」は「撞木」と「至極」の類音に拠った。四句「ごんす」は「御座います」に鐘の擬音、結句「鳴れる筈」も名声に音響を重ねた。四首目の作者は木端、題は「四ツ橋ノ眺望」。初句は「八橋」、『伊勢物語』に「三河の国八橋といふ所(略)、水ゆく河のくもでなれば、橋を八つわたせる」とある。橋の数では劣るが河の数では勝っている、そんなお国自慢であろう。
|
| 第22回 狂歌かかみやま(11) |
にほん橋といふもことはり出羽近江越前筑後目の下にみる 栗柯亭木端
掲出歌の題は「日本橋ノ眺望」。橋の上から道頓堀川を眺めているのである。下を行く「出羽近江越前筑後」は、これが上句の見立てなのだが、船以外にない。道頓堀といえば劇場の町だから伊藤出羽掾、竹田近江掾、豊竹越前少掾、竹本筑後掾などが思われる。飾り立てた船に乗って、囃しながら、道頓堀から劇場に入っていく船乗り込みを歌ったものであろう。
ゆふ化粧雪のはたへの色ましてたれにあふみの比良のおやまそ
石山とかたいは名のみ照る月のゑかほに秋のいろをふくんた
うき思ひくゆるきせるのすはすはと通りかねたるらをのよの中
二千里の外もくまなき新月に十万億土の故人こひしき
一首目の作者は千樹、題は「比良ノ暮雪」(近江八景)。比良山地を女性に見立てた歌である。〈夕化粧雪の肌の色まして誰に会ふ身の比良のお山ぞ〉。「会ふ身」は「近江」、「おやま」(美しい女)に尊称としての「御山」である。二首目の作者は千樹、題は「石山ノ秋ノ月」(近江八景)。初二句は地名の「石山」を普通名詞にして「硬い」。これがベースの三句以下となる。「笑顔」は欠けたところのない満月、その名月に照らされた地名「石山」の賞揚である。三首目の作者は紫笛、題は「述懐」。〈憂き思ひ燻る煙管のすぱすぱと通りかねたる羅宇の世の中〉。「燻る」に「悔ゆる」を掛けた。「らを」は「羅宇」でキセルの雁首と吸い口とをつなぐ竹の管、助詞「の」は比喩で「のような世の中」となる。四首目の作者は奏産亭州実、題は「廿一年に当りしとし秋ノ懐旧」。「本語」とあるのは白居易の詩句「二千里の外(ほか)故人の心」で遠くに住む旧友を思う心、これを拡大して極楽浄土に住む由縁斎貞柳を偲ぶ心を描いた。
すゑに名のくちせすもああ忠臣はくすの木やなる大石ならん
十つつのはちを並へしことふきは茶碗屋ならぬいもとせともの
笛竹のをとしはよれと俤はおなし調子や六十いちこつ
ちよの春けふよりかそへはしめつるそのおや指やさそ嬉しかろ
一首目の作者は紫笛、題は「大石勇士の五十回忌に」。〈末に名の朽ちせずもああ忠臣は楠やなる大石ならん〉。「や」は反語。楠正成と正行だろうか。いや大石内蔵助と主税だろう。二句の感動詞「嗚呼」の登場に注目した。二首目の作者は木端、題は「あまがさきの人夫婦やそぢなるを」。〈十づつの八を並べし寿は茶碗屋ならぬ妹と背(戸物)〉。「八」に「鉢」を掛けた。「茶碗屋」の縁で結句に「瀬戸物」を出した。三首目の作者は華産、題は「六十一歳になれる人を祝(ひ)て」。〈笛竹のお年は寄れど俤は同じ調子や六十壱(越)〉。「笛竹」は竹で作った笛、「お年」に「音」を掛けた。「壱越」は「六十一」の「壱」また日本音楽の十二律の一。「調子」は具合、音楽では音階の主音の高さで決まる音階をいう。四首目の作者は華産、題は「むつきに子のいできし人の許へ」。題の「睦月」に「襁褓」を掛けた。初句「千代の春」は末長いことを祝う初春、その数え初めに折る「親指」に「父親」(母親)の「親」を重ねた。
|
| 第23回 狂歌かかみやま(12) |
左保姫の霞の衣したてたる針休めかとみるあさみくさ 栗柯亭木端
掲出歌の題は「あざみ」(薊)。部立ては「絵の歌」である。初句「左保姫」(佐保姫)は春をつかさどる神、三句は「仕立てたる」。以下、見立てが続く。四句「針休め」は「針立て」「針山」などともいう。その「針休め」に似た薊、葉ではなく、花だというのである。加えて薊の別名は「刺草」(しそう)、先端が棘で紅紫色の頭状花が霞の里でひっそりと咲いている。
みそを摺るれんきにはねのはえたれは追(ひ)懸(く)る人もはしらかすかや
街道に更(け)ゆく月は早飛脚か雲のいつこにやとるともなし
ちのありてたるるといへる名にも似すすひにより来る蚊をふせくかや
客好むはたこやなれと是(れ)斗りとまりにくるをいとふかやりひ
一首目の作者は木端、題は「すりこぎにはねはへとぶを追(ひ)懸(く)るに」。〈味噌を擦る連木に羽の生えたれば追ひ懸くる人も走らかすかや〉。「連木」は「擂り粉木」、「走らかす」は「走らせる」。戯画である。二首目の作者は木端、題は「街道ノ夏ノ月」。本歌は清原深養父の〈夏の夜はまだよひながら明けぬるを雲のいづくに月やどるらむ〉(『古今和歌集』一六六)。擬人化と宿ること自体を不確かにしたのが特色である。三首目の作者は木端、題は「新題百首の歌読(み)しとき蚊幮」。〈乳のありて垂るるといへる名にも似ず吸ひに寄り来る蚊を防ぐかや〉。「乳」(蚊帳を吊る紐を通す小さな輪)に垂乳根を重ねたが、赤子ではなく、寄って来るのは血を吸う蚊、その蚊を防ぐ「蚊帳」を詠う。「蚊帳」に詠嘆の助詞「かや」を掛けた。四首目の作者は木端、題は「旅店(ハタコヤ)ノ蚊遣火」。三句は「こればかり」、「これ」は蚊で「泊まりに来るを厭ふ」となる。「蚊」を出さずに「蚊遣火」で示したところが凄い。
長みしか筆発句脇絵の霞人の気つらら羽織かみさき
細いのはさみせんの三蚊のまつけ江戸兵衛か鬢帳のたち屑
さかさまはいなさる客のたて帚美女のたとへにつりしひいとろ
ひつたりと汗に濡(れ)けりゆふたちの雨の足には走りぬけても
一首目の作者は木端、題は「江霜庵所望の五文字にて読(み)し歌の中になかみしか」。「長短」尽くしである。以下「筆」対「発句脇」(七七)、「絵の霞」(帯状に描かれる)対「人の気」(「人の噂も七十五日」)、「氷柱」対「羽織が御先」(先払いの声「下に下に」)となる。二首目の作者は木端、題はない。細いもの尽くしである。「三味線の三」の糸、「蚊の睫毛」(洒落だろう)、「江戸兵衛が鬢」(髪型の糸鬢。京阪では撥鬢という)、「帳の裁ち屑」(「帳」は「帳簿」)となる。三首目の作者は木端、題はない。逆様に箒を立てるのは二句「去なざる客」(長居の客)を帰す呪いであった。また美女を喩えて「ビードロを逆さに吊す」といった。逆さま二態で好悪も対極になるさまを詠った。四首目の作者は法眼香川、題は「夕立」。初二句「ひったり」(または「びったり」)で濡れそぼつさま、濡らしたのは「私」の汗。三句以下は縦に降る雨の中を通り抜けた、夕立から逃れたことをいう。その見返りが汗なのである。
|
| 第24回 狂歌かかみやま(13) |
物まねをそへてあきなふ和中散かはぬ人まてよくききにけり 栗葉軒如擽
掲出歌の題は「役者ものまねをしてあきなふ和中散やを見て」。「和中散」は暑気あたりや風邪などに効能があるとして諸国に流布した粉薬である。近江国栗太郡梅木村(滋賀県栗東市六地蔵)に本家があった。初二句は振売り箱を担いでの行商だろう。人を呼んで幾らなのだ。下句は「買はぬ人までよく聞きにけり」が「よく効きにけり」に聞こえるところが心憎い。
春日かけあなあたたかとはひ出(つ)る時しる知恵やありの一むれ
かく斗り昔忍へと孫の手のととかぬほとそかひなかりける
やたけには今思へともあつさゆみはるかの月日ゆふてかへらぬ
煤をみなにしなとの風に払ひ給ひきよめて結ふまつり前かな
一首目の作者は近藤任風、題は「日暖カニシテ虫出ル」。太陽暦の三月五日頃にあたる啓蟄である。初句は「春日影」(春の日の光)、二句の感動詞「あな」に「穴」を掛けた。結句は「蟻」に「有り」だろう。二首目の作者は近藤任風、題は「祖父の七回忌にいまそかりし世の恵み深かりし事を思へばいか成(る)追福もなすべけれど心にまかせざれば」。四句「届かぬほどぞ」(彼岸までは届かない)、結句は「甲斐なかりける」(方法がない)のだ。三首目の作者は小笹繰風、題は「祖母の十七回忌に在(り)し世はいとけなくて孝のつかえのうとかりし事を今更くひて」。初句「弥猛」(勇み立つこと)に「矢竹」(矢の竹の部分)を掛ける。三句の枕詞「梓弓」は四句の「遥(か)」と結句「帰る」に掛かる。「ゆふ」は「言ふ」。四首目の作者は如擽、題は「夏まつりの前のすすはきを」。初句は「皆にする」(全部なくす)を使って「煤を皆に(し)」、二句「科戸の風」(風の異称)と「し」の共用である。二句の縁で祝詞風の展開である。
たんしりのやれややれやのその中にやらんやらんのひき船もあり
芝居みて気を開かんとへんたうにむすへる飯のにきにきしさよ
よつの海蝦夷か千島の鮑まて戸ささてすめる君か代の春
心して花にはふきそ野ふろには酒あたたむるほとの春かせ
一首目の作者は華産、題は「夏祓」。楽車が速さを競っているのである。先頭の一台が「やれややれや」で後続の一台から「やらんやらん」と声が飛ぶ。結句「引き船」は楽車の比喩である。川渡御に対する陸渡御で縁語なのだ。二首目の作者は紫笛、題は「芝居ゆきの行厨(ヘンタウ)のこしらえにきはしきをみて」。二句は「陽気な気分になりたい」もしくは「陽気な気分になろう」。結句はその期待を表して「握り飯」を始めとする賑やかな中身なのだ。三首目の作者は柏木遊泉、題は「としたつあした」(元旦)。〈四つの海蝦夷が千島の鮑まで戸鎖さで住(清)める君か代の春〉。上句は「日本の果ての蝦夷地にある多くの島の、その鮑まで」だろう。鮑は巻き貝だが浅い皿形で他の巻き貝のような蓋がない。四首目の作者は遊泉、題は「春風」。二句の助詞「そ」は禁止の意を表す。三句「野風呂」は露天風呂、銚子を入れた湯桶を浮かべているのだろう。花は散らさず、酒を楽しむのにほどよい春風を所望なのだ。
|
| 第25回 狂歌千代のかけはし |
市中の紅葉はうれし此(の)秋も声聞(く)ときといふものも来す 桃縁斎貞佐
『狂歌千代のかけはし』は撰者桃縁斎貞佐、刊記は宝暦九(一七五九)年である。掲出歌は無題、本歌は『古今和歌集』の〈奥山のもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき〉(二一五)。初句は「いちなかの」と読んだ。二句、なぜ紅葉は嬉しいのか。本歌の「声きく時ぞ秋は悲しき」その悲しくさせる鹿も来ず、多くの人が「私」を愛でてくれるからである。
かしましや此(の)里過(き)よと宗鑑のほとときすほと蛙鳴(く)なり
納(ま)れはおもき千石万石も在所娘の手にとる早苗
うたぬ火もちるあはら家のしるしかも五月の闇に螢はらはら
楠のしるしに植(ゑ)し松梅も年経てのちは石とこそなれ
一首目の作者は楽中、題は「蛙」。宗鑑の一首は〈かしましや此の里過ぎよほととぎすみやこのうつけいかに待つらん〉(『狂歌五十人一首』)、これを受けた貞柳に〈かしましや此の里過ぎよほととぎすと思ふほとに一度ききたや〉(『家づと』)があるが、蛙に転じたところが意表を突く。二首目の作者は秋園斎米都、題はない。初句は年貢米のこと、二三句は幕府・諸大名・寺社等の蔵屋敷なのだろう。そこに積まれた膨大な米袋の米も、元は早乙女が手にした早苗だったというのである。三首目の作者は露玉、題は「螢」。初句「打たぬ火」(火打ち石を使わない火)すなわち蛍火が散るのも廃屋の証だというのである。結句の「はらはら」は清音で読んだ。四首目の作者は春魯、題は「摂州湊川にて楠正成の塚に詣うでけるにむかしはしるしに松梅の二本ありしが今は石碑になりたるよし所の人かたりければ」。湊川神社の創建は明治五(一八七二)年である。結句は係り結びで石になったことが強調されているのである。
竹杖に乗(り)て遊(ひ)し事ともを語れは今も馬そあひぬる
けふあしたふりぬる我も目に見えすちくりほくりとちひて行(く)なり
絵にかけるねすの嫁入の姫君も供の奴も同し口ひけ
ひいとろの此(の)盃をなかむれは酒ほしさふに顔か見えすこ
一首目の作者は貞山、題は「芸州貞雨の主に久しぶりにて物がたりして」。上句は竹馬で遊んだことをいう。「竹杖」としたのは下句での重複を避けたのである。その「竹馬の友」は今も馬が合うというのが歌意である。二首目の作者は漱石、題は「京木履を調へて」(「差し歯の高足駄」を「買って」)。夏目漱石より百年以上前の「石に漱ぎ流れに枕す」る御仁である。初二句「今日明日旧りぬる」の「今日」に「京」を掛けた。四句は「ちくり」(僅かなさま)と「ぼくりぼくり」(ゆっきり歩くさま)を合体させた。三首目の作者は藤巴、題は「鼠嫁入の絵」。二句は「ねづのよめり」と読んだ。天下一の婿を取ろうとした親の試みも同類の鼠に落ち着くという昔話で結句の「口髭」が効いている。四首目の作者は楽中、題は「びいどろの盃を見て」。ガラス製の盃である。四句は「酒ほしさうに」、結句は「見え透かん」(心の底が見えてくるのだろう)の音変化「見え透かう」「見え透こう」「見え透こ」と解した。
|
| 第26回 五色集 |
風からぬ手のこひかけにかくる帆も手水の浪にぬれぬ日そなき 自然軒鈍全
『五色集』は即興詠を得意とした自然軒鈍全(生没年未詳)の詠草集で宝暦年中(一七五一~一七六四)の編と考えられている。掲出歌の題は「手拭(ひ)掛(け)帰帆」。「帰帆」は帰途につく帆船をいう。初句は「風借らぬ」、四句「手水」は手や顔を洗うための水であるが、厠の出口の手水鉢と軒先の手拭い掛けであろう。見立てによって日常の風景が変わる。
さす水にしはししつまるにえ釜もまたさよしくれ降(り)しきる也
短尺のいと風雅成(り)うへに又銭まてあれは下におかれす
あたまからかみこなせしといわしますそのいにしへも鬼しやあるまい
たれもみな今より月にゆひささて此(の)サホテンに足をはこはん
一首目の題は「臺司夜雨」。「臺司」は「高官」、その邸宅の大きな台所をイメージした。また別本に結句「降るかとぞきく」があるが「降りしきる也」を採る。差し水をして再び湯玉が上がってくるさまの比喩が巧い。二首目の題は「或(る)人やつがれに書(き)付(け)みせぬる興歌 風鈴はたかふとまれる物なれど銭かなければ鳴(ら)ぬ成(り)けり 返し」。この「高うとまれる」を受けて結句「下に置かれす」とした。「銭」の穴に短冊が付いて風に揺れるのだ。三首目の題は「鰯とますのやきもの出(で)ければむかしはいわしをあたまからくひしにといへる人によみて見せ侍る」。四句は「鰯鱒」に「言わします」(「言わす」の連用形に丁寧の助動詞「ます」)を掛けた。四首目の題は「豊後橋のほとり指月山月桂寺といへる寺にサホテンといへる植(ゑ)ものの高さ一間にあまり一ひらははの百よあるを見て」。「一片は刃の百余」は薄く平らな一茎に棘が百余、三句は山号とサボテンの「指刺さで」を重ねた。
となりまて聞(こ)へし声も南無あみたふつとここてはのふこわつくり
てらされていきもならさる昼舟も苫をまかるる雨よりはまし
さよふけてゆひきのこゑのきこゆるは弓矢八まん町の番太良
讃うさんけに面白き絵すかたのヘマムシヨ入道もいはれぬ
一首目の題は「家城某の墓にまいり此(の)人高くこはつくりするくせ有(り)しをおもひ出(で)て」。「声作り」は咳払いと解した。四句「仏と」に煙で「ふっと」を掛ける。二首目の題は「難波下りの昼舟にてよめる」。初句は「(陽に)照らされて」。京と大坂を結ぶ淀川の三十石船だが、その乗り心地を伝えて興味深い。三首目の題は「夜更(け)八幡町の門を叩けど番はね入(り)あけざりし時」。二句「ゆびき」は「鼾」の訛音、「ゆ」音を重ねて「弓矢八幡」その「八幡町」は江戸深川の遊里仲町の異称であった。結句「番太良」は番太、町木戸の番人をいう。三首目の題は「いとたふとき御方のかかせられしヘマムシヨ入道の絵に讃のぞまれやつがれごときの讃かくべき御筆ならねば料紙を乞(ひ)書(き)付(け)侍る」。鈍全は公卿の甘露寺家に仕える侍だった。「ヘマムシヨ入道」は文字遊戯。初句は「讃胡散」、二句の「げに」は「胡散」の接尾語の「げ」でもある。結句は「(言ふに)言はれぬ」だろう。
|
| 第27回 狂歌柳下草(1) |
春風にふりわけかみのいかのほりいとさまならて誰かあくへき 柏木遊泉
『狂歌柳下草』の詠者は柏木遊泉(一六八七?~一七六三)、「附録追悼歌」を加えた本編は明和二(一七六五)年頃の成立らしい。掲出歌の題は「紙鳶」。二句は「振り分け髪」で子供の髪形をいうが「髪」に「紙」で凧の尾とした。四句「いとさま」は小児をいう敬称で、これに凧の「糸」を掛ける。結句は「誰か揚ぐべき」だが「いとさま」しかいないのである。
米の直の上りさかりをきかんより雲雀さへつる春の野遊ひ
米相場のいきほひに似て北浜やすつと立枝の梅五六りん
大名の御出(で)かつつくつくつくしたて笠霞む春の野はかま
佐保姫の文やはのへにちらし書(き)候べく候と見ゆるさわらひ
一首目の題は「野遊」。初句の「直(ね)」は売買の相場をいう。遊泉は屋号が紙屋、明石の商人で大坂にも店を出していた。同じなら雲雀の「上がり下がり」に心を解き放ちたい、真率な響きがする。二首目の題は「市場梅」。北浜は現在の大阪市中央区、船場北部の地名。米の売買取引の市場が置かれて賑わった。高く伸び立った枝に、しかも梅の花の比喩が美しい。「りん」は「輪」に「厘」を掛けた。三首目の題は「筆頭菜」。〈大名の御出でが続くづづくし立笠霞む春の野袴〉。「御出で」は「出ること」の尊敬語。三句は「つくづく」(観察するさま)に助詞の「し」、また五音で土筆の異名。四句「立笠」は長柄の大傘で供の者に持たせた。結句「野袴」は武士が旅をするときの袴、土筆にも袴があり、見立ての景である。四首目の題は「早蕨」。二句「文やは野辺に」の「やは」は反語、三句「散らし書き」は文字を散らして布置する書法、四句「そろべくそろ」は女性の手紙文に用いられた。見立てだが壮大である。
見渡せは琵琶の海つら一めんにほろんほろほろ春雨のふる
散(り)行きし花のかたみと笛の名の青葉にしける須磨の夏山
時鳥また朝くらの一こゑにひりりさんしよの目をはさました
湯より猶きいた有馬のほとときす棹にゆかたをかけたかの声
一首目の題は「湖上春雨」。二句は琵琶湖を「の」で分離して「海面」とし、その一面に、また「私」の傘を打つ雨が「ぼろんぽろぽろ」なのだ。当然ながら琵琶を弾くオノマトペである。二首目の題は「新樹 須磨にて」。二句「花の形見」は花を思い出す種となるもの、ここは一ノ谷の戦いで熊谷直実に討たれた平敦盛(一一六九~一一八四)だろう。三句「笛の名」は「青葉の笛」で敦盛秘蔵の一管であった。その青葉が繁る須磨の夏山だというのである。三首目の題は「朝時鳥」。二句「まだ朝くら」は朝が暗い意に朝倉山椒の「朝倉」を掛けた。四句の「ぴりり山椒」は成句「山椒は小粒でもぴりりと辛い」で侮れない「一声」を表した。結句「目をば覚ました」は「私」である。四首目の題は「湯山杜宇」。上句は「(効いた)湯より猶聞いた有馬の時鳥」の意である。「有馬」は有馬温泉、畿内最古の温泉である。鳴き声の「てっぺんかけたか」「ほぞんかけたか」から下句「『棹に浴衣を掛けたか』の声」とした。
|
| 第28回 狂歌柳下草(2) |
夏菓子は何よりもつて尉殿の持たしやりそうな鈴なりのひは 柏木遊泉
掲出歌の題は「ある所にて枇杷の菓子出(で)ければ」(「菓子」は果物)。一首は祝祷の歌舞『翁』の三番叟「この色の黒い尉が千秋萬歳とめでたいやうに舞ひ納めうずる事は。何より以て易う候」また面箱持ちの「ああらめでたや。さあらば鈴を参らせう」の詞章に乗せた主人への挨拶である。四句は「お持ちになりそうな」、結句は「鈴の段」の舞いを連想させる。
吹(く)風にかふりかふりをして遊ふ野はなてしこのいとし盛りしや
かけ日なたさへなつの日やかさもきすあつさ誰かためするほうこ草
夏の夜はむしくるのみか出来し子のややともすれは寝ひえをそする
夜うちには入れし蚊帳の城かまへ蚊よ時の声あけてよすとも
一首目の題は「夏草の歌よみし中に」。二句の「頭頭」は嫌々のこと、四句「撫子」は植物名に愛児の姿を重ねる。結句の「愛し盛り」は愛らしい盛りをいう。次の助動詞「じゃ」は「である」の「る」が脱落した「であ」の転、断定の意を表す。二首目の題は先に同じ、漢字を多用すると〈陰日向さえ夏の日や笠も着ず暑さ誰がためする母子草〉。初二句に「陰日向なく」(真面目)の意を掛けた。この苦労は誰のためなのか。結句「ほうこ(草)」に「奉公」を重ねた。三首目の題は「夏夜」。二句は「蒸しくる」に「虫来る」を掛けた。四句は副詞で「どうかすると」の意、これに三句の「やや(こ)」を重ねた。また「蒸し」と結句「(寝)冷え」が呼応する。四首目の題は「蚊」。〈夜討ちには入れじ蚊帳の城構へ蚊よ時の声あげて寄すとも〉。「蚊帳」は音で「かちょう」と読んで二句七音とにる。見立てもここまでくると戯画である。
北浜は軒の玉水横堀を筋違橋に渡るゆふたち
ほそ引(き)をわたせる小袖えりあかの白きをみれは遅き土用干(し)
たはこ好く人ても九度三ふくのきつきあつさにむせかへるなり
生玉のはすはにそよくかけ作り水涯たちし風の涼しさ
一首目の題は「北浜のあたりにて夕立に逢ひて」。二句「玉水」は雨だれの美称、三句「横堀」は土佐堀川から道頓堀川まで通じる東西の運河で四句「筋違橋」は西横堀川に架かっていた。堀と橋の名が雨脚に臨場感を与えている。二首目の題は「土用干」。〈細引きを渡せる小袖襟垢の白きを見れば遅き土用干し〉。小袖に「細引き」(細い縄)を通して干しているのである。白いのは白カビで、風を通すのが遅かったというのだ。三首目の題は「苦熱」。二三句の「九度三ふく」は「九度三分」に「三伏」(夏の最も暑い時期)と煙草の「三服詰め」を掛けた。「九度」は「二十九度」の意であろうか。温度計が日本に伝わったのは平賀源内がらみで明和二(一七六五)年とされるが、このとき遊泉は生きていない、実際はもっと早かったに違いない。四首目の題は「納涼」。〈生玉の蓮葉にそよぐ懸け造り水涯立ちし風の涼しさ〉。「生玉」は大阪市天王寺区の生玉神社、「懸け造り」は水の上に建物を張り出して作ること、またその建物をいう。「水涯」は「水辺」である。当時は弁天池があって蓮見の名所であったと思われる。
|
| 第29回 狂歌柳下草(3) |
五つつつつ三つの難波のうらやまし秋のよつ橋すみ渡る月 柏木遊泉
掲出歌の題は「名月の頃難波木端師の方へせうそこ遣はすついでに」。「せうそこ」は「消息」。初二句の「五つづつ三つ」は膳立の法式の一つ「五五三」を使った。「三つ」に「御津」を掛けて「難波」の序詞とした。また五つが三つで十五夜となる。下句は「秋の夜」と「四つ橋」で「よ」を共有した。木端の「かへし」は〈なには津のみつのあちより賞翫は強いあかしのもちの月影〉である。「難波の蜜(御津)の味」より「明石の餅(望月)」だというのである。
あかし潟名にたちにける朝霧は島かくれなき浦の景物
またらなる猫の毛色に似た雲のしくれいく度風にそはゆる
すいも有りなますいも又おほさかやひやうたん町をぬめるそめき衆
双六のさいの河原をひとり旅てつちもつれすうとうととゆこ
一首目の題は「霧」。二句の「立ちける」は「世の中に知れ渡っていること」、また「霧が立ちのぼる」意となる。四句は〈ほのぼのとあかしの浦の朝霧に島隠れゆく舟をしぞ思ふ〉(『古今和歌集』四〇九)と違い、島が朝霧に隠れて無い。それと「(島)隠れなき」有名な景だというのである。二首目の題は「時雨」。初二句は「斑猫の毛色」をいう。三句は上から雲の「時雨行く(度)」、下へは「(しぐれ)幾度」となる。結句「戯ゆる」は「日照り雨が降る」意に「(猫が)じゃれる」意を重ねた。三首目の題は「恋の歌の中に」。初二句は「粋も有り生粋もまた」、三句は「大坂や」に「多さかや」を掛ける。四句「瓢箪町」は新町遊郭にあった町名である。「ぬめる」は浮かれ歩く、「ぞめき衆」(騒衆)は遊郭をひやかす遊び人をいう。四首目の題は「三歳になりし孫をうしなひて」。〈双六の賽の河原を一人旅丁稚も連れずうとうととゆこ〉。初二句、正月の絵双六の賽から舞台は賽の河原へと暗転する。結句「うとうと」は歩行などのおぼつかないさまをいう。「ゆこ」は「行かむ」「行かう」で推量の意と解した。
たはこ呑む間もあちきなや身のつゐの烟のはての灰を思へは
二八にてうたれ玉ひし跡そとて敦盛前のそはうとん茶や
松かけにころりと思ひなけ杖にねてさへいひきかく駕のもの
一首目の題は「無常」。火葬を支えるのは仏教文化である。明治政府は神道国教化政策から火葬禁止を打ち出したことがある。ちなみに大正四年の火葬率は三六%である。遊泉の頃は大量の薪を必要としない土葬が多かったろう。四句の「烟」は比喩の可能性もある。二首目の題は「須磨浦にて」。初句の「二八」は掛け算で敦盛の享年十六になる。これに蕎麦の「二八」(うどん粉とそば粉の割合が二対八の蕎麦。二八蕎麦)を掛けた。四句「敦盛前」は神戸市須磨区一の谷町にある敦盛塚の前になる。また「さき」と読んで貴人の先払い、「まえ」と読んで貴人に伺候する意となる。なお熱湯を通して熱くした盛り蕎麦を敦盛蕎麦という。三首目の題は「駕かきの松の本に昼寝せしかた書(け)る画に歌を望まれて」。三句は上から思い「無げ(杖に)」、下へは息杖を「投げ杖に」だろう。四句は駕籠を舁かないで「鼾かく」となる。
|
| 第30回 狂歌柳下草(4) |
色よりもかにめてるとはあなおかし一はさみにもたらぬさかなを 柏木遊泉
掲出歌は題に「山本呉蘭のぬしへ蟹を送りければ御隠居の御心ざしは蘭の花色よりぞまづかにぞめでぬるとありければかへし」とある。再掲すれば〈御隠居の御心ざしは蘭の花色よりぞまづかにぞめでぬる〉。三句に雅号の「(呉)蘭」を出した。結句は「香にぞ愛でぬる」で「香に」に「蟹」を掛けた。遊泉の歌を再掲すると〈色よりもかに愛でるとはあな可笑し一はさみにも足らぬ肴を〉。やはり「香に」に「蟹」を掛けた。四句は箸で挟む「一挟み」に蟹の爪の「一鋏」を掛けて「ほんの少しですが」と謙遜した。結句の「肴」は酒のさかなをいう。
極楽を纔斗りの手の内てにきつたやうに辻談義ほん
そり捨(て)しつふりのなりを人問ははうき世に秋の月と答(へ)ん
うきふしは有(る)も習ひにくれ竹の杖つきの字のやうな老か身
老の身は鰹に同しとにかくに日ことに心ほそうこそなれ
新宅の栄へは千とせ松島や誠めてたうそんしさふらふ
一首目の題は「題しらす」。二句は「わずかばかりの」。結句「辻談義」は談義僧が往来で仏法を説いて喜捨を受けること。また「談義本」は談義僧の口調をまねて庶民教化を行う滑稽本、「ほん」は「本」に極楽往生する者の能力を等級に分ける「品」を掛けた。二首目の題は「法体せし時よめる」。四句は「浮世(憂き世)に」、句またがりで「秋(飽き)の月」(澄んだ夜空に冴え渡る月)となる。また二句「頭の形」に「秋の月」で花札の薄(二十点札)が連想させる。三首目の題は「述懐」。初句は「憂き節」、辛いときもあったが二三句「習ひに暮れ(竹の)」、四句はそこで習った「杖つきの字」(「杖をつく『の』の字」)すなわち「乃」の字のような姿の「老いが身」だというのだ。別に「節」の縁で三四句「呉竹の杖」があり、「乃」の字を導く流れを作っている。四首目の題も「述懐」。二句の「鰹」は「鰹節」の意だろう。毎日、身を削られて細くなる、それを「老の身」に転じて「心ぼそう」と表現した。五首目の題は「松島屋次三郎といふ人の新宅を賀して」。三句「松島や」は日本三景の一、歌枕の「松島(や)」に「松島屋」を掛けた。結句「(ぞん)じさぶろう」に「次三郎」が隠れている。
ぬしのなき駒をや何と将棋盤目もる泪にくつる袖飛車
祖父さまにかひなき別れ孫の手もととかぬ事を悔みこそすれ
「附録追悼歌」より二首引く。一首目の作者は嶺果亭漁産、題は「遊泉雅翁の将棋をさしながら身まかり玉ふとききて」。三四句は「何と将(棋盤)」で「何としよう」。四句の「目もるは「守る」の原義「目守る」(見守る)を使った。今一つ「目(を)漏る」で「泪」に続く。結句「袖飛車」は将棋の戦法の一つ、また「袖に泪」の図、「崩る」は「崩るる」が正しい。二首目の作者は林果亭栗篠、題詞に「柏木遊泉雅翁の身まかり玉ふをききてむまごの朝省のぬしへいひをくる」。初句は「じいさまに」だろう。三句「孫の手」は背中を掻くときの道具を比喩として使う。なお『狂歌柳下草』の跋文は「不肖孫柏木朝省拝識」となっている。
|
| 第31回 狂歌ともかかみ(1) |
屠蘇にけさ酔(ひ)つつ同し事いふは蓬莱の山のこたまなるかや 園果亭義栗
『狂歌友かかみ』の詠者は如棗亭栗洞と園果亭義栗、撰者は栗柯亭木端、刊記は明和四(一七六七)年である。掲出歌の題は「初春酒」。四句の「蓬莱」は正月の祝儀に用いられる「蓬莱飾り」の略、神仙思想に基づく蓬莱山を象った台に飾られる。酔ってくだを巻いているだけなのだが、言われると蓬莱山からの山彦だと応える。酔っ払いである「私」の弁なのだ。
初春をつけくちなれと鶯のちよつひちよつひはにくうないもの
おれきれき御出(で)なりとていと桜地にはなつけて盛(り)見せけり
黒船の名になかれたる姉川の花ならはちよと下に居て見ん
三千とせのよはひはよくしやけふ祝ふ花の名におふももとせてよい
一首目の作者は如棗亭栗洞、題は「鶯」。二句「告げ口」は「密告」の暗さを払拭して「初春」を告げる意に転じた。だから結句「憎うない」のである。四句は「ちょっぴちょっぴ」のオノマトペである。二首目の作者は栗洞、題は「同じほどにおほけなき御方の御入(り)有(り)しを」。他の題から大阪市天王寺区の隆専寺と思われる。初句は「御歴歴」で身分の高い人たち、したがって四句の「花」は枝垂れの「端」であり、擬人化して桜の「鼻」となる。三首目の作者は義栗、題は「妙光寺の庭に故姉川新四郎植(ゑ)置(き)しといへるさくらの盛(ん)なるに」。姉川新四郎(一六八五~一七五〇)は歌舞伎役者、侠客の黒船忠右衛門が当たり役だった。四句「ちょと」は「ちと」の転、花見を観劇に見立てた。四首目の作者は義栗、題は「三月三日」(桃の節句)。〈三千年の齢は欲ぢゃ今日祝ふ花の名に負ふ百年でよい〉。「三千年の桃」(不老長寿)は「欲ぢゃ」が桃と同音の「百年」ならよい。これ又「欲なことぢゃ」。
はた薄な蚊と成(つ)てけふとひ初(め)ぬ棒ふりむしも衣かへとて
杖の様なゆふたちの雨に息をつきしほれし草も腰をのしたり
着た笠の陰のまんなかふむひあし是(れ)炎天の昼の辻なり
秋風の米の相場の道具たてせりあけもするせりさけもする
一首目の作者は栗洞、題は「卯月朔蚊はじめて出(で)けるに」。四月一日は夏の衣替えである。今なら五月中旬だから初句「肌薄」となる。「棒振り虫」(蚊の幼虫)が衣替えをして「蚊」になるという見立てが奇想天外である。二首目の作者は義栗、題は「夕立」。上句の「杖」から「息をつき」で炎暑に対する息杖(荷物を担いだ人や駕籠かきが息入れするときに用いる杖)を浮上させて、これを下句で「萎れし草も腰を伸したり」と展開した。草の擬人化である。三首目の作者は義栗、題は「夏昼」。三句の「日脚」は太陽が東から西へ移っていく動き、初二句は両足が立っている所、そこを同じくして日の脚が立っているというのだ。結句「辻」は道路が十字形に交わる所として読んだ。炎天に人の気もない。四首目の作者は栗洞、題は「秋風のはげしかりけるほどに米市の浜を通(る)とて」。「浜」とは北浜をいう。結句は相場の暴落(奈落)という意味で劇場用語を持ってきて「競り上げ」と対句にしたものと思われる。
|
| 第32回 狂歌ともかかみ(2) |
是(れ)も神のちかい春とて傘のさしつまりたる年の末広 園果亭義栗
掲出歌の題は「としの暮に」。脇狂言「末廣かり」に拠る。「末廣かり」(扇)が分からず、瞞されて古傘を買って帰った太郎冠者に怒る主人だが「かさをさすなる春日山、かさをさすなる春日山、これも神の誓ひとて、人がかさをさすなら、我もかさをささうよ。げにさもあり、やようがりもさうよの」と囃す太郎冠者に最後は機嫌を直すというもの。二句「誓い」に「近い」、四句は「(傘の)差し」から「差し詰まりたる」(その時期に近づく)「春」となる。
山崎のはなにかかりてなかめけり眼かねの玉の水しやうの月
かくはかり上りかねたる手習にうらやましくも山端の月
あけむつの花とや雪のふりつもり夜半にひかしの山もしらんた
道しるへせしいにしへもしら雪のふり埋みたる庭の駒下駄
一首目の作者は義栗、題は八月十五夜「同し夜やま崎のはなに船を浮(か)へて」。「山崎の端」は中之島の東端、山崎家の蔵屋敷があった所で「端」に「鼻」を掛けた。結句の「水晶」は「玉」の縁語である。二首目の作者は栗洞、題は「月前学習」。初句は連語「斯くばかり」(こんなにまで)に「書くばかり」を掛けた。対して「羨ましくも山端(やまはな)の月」が上るのだ。三首目の作者は義栗、題は「雪」。初句「明け六つ」は午前六時頃、二句「とや」は連語で疑問を表す。下句「夜半に東の山も白んだ」。まだ夜中だというのに降り積もった雪で朝のようだというのである。四首目の作者は義栗、題は「庭雪」。本歌は後醍醐天皇の〈雪のうちに昔の道をたづぬればまよはぬこまの跡ぞしらるる〉(『続千載集』八四四)であろう。二句の「も」は逆接の意を表す。「駒」を「駒下駄」として庭の雪に埋めてしまったのだ。
うそふきのめんつや提(げ)てゆきの日の寒さに口もゆかむ乞食
火にくはるやうにこたつにねころんたこころはほんに大名しやまて
月々に参る身なれはすみよしの道の案内はそてこさります
また地震ゆりおこそかのをそはれもゐのこゐのこてましなひにけり
一首目の作者は義栗、題は「雪中乞児」。初句「嘯」は口を尖らした狂言面、「めんつ(面桶)」(飯椀)に「面子」を掛けて詠嘆の助詞「や」、「雪」に「行き」で表情も硬い「こつじき」なのだ。二首目の作者は栗洞、題は「旅厭寒」。初句は「火に食はる」。結句「ぢやまで」は助動詞「じゃ」に助詞「まで」が付いて断定の「のだね」ないし詠嘆の「だなあ」となる。三首目の作者は栗洞、題は「すみよしの社へ月詣するとて」。結句は「そで御座ります」。「そ」とは何か。案内不要、「なせそ」の「そ」であろう。四首目の作者は栗洞、題は「宝暦六年神無月四日は大地震の五十回とて人々恐れけるにさせる事もなく折しも亥猪なりければ」。宝永四(一七〇七)年に起きた地震は歴史的な大地震で死者二万人、家屋倒壊六万戸、流失二万戸といわれる。擬人化した「地震が揺り起こさうか、としているという魘れ(悪夢にうなされること)も」、「いのこ(猪子)に上方語の「いの」(帰ろう)を掛けて神仏に「呪ひにけり」か。
|
| 第33回 狂歌肱枕 |
みな月のはらひといふて難波かたあしに任せてちやうさやようさや 韓果亭栗嶝
『狂歌肱枕』の詠者は韓果亭栗嶝、刊記は明和四(一七六七)年である。掲出歌の題は「荒和祓」(あらにこのはらえ)。一首は夏越しの祓に節季仕舞いを重ねた。初二句で「水無月の祓ひ」と「皆、月の払ひ」、三句以下は各々「潟葦に」で茅の輪作りの現場となり、「方足に」で難波人が足に任せて決算に走る姿となる。結句は山車などを引く時の掛け声で囃した。
魚と水たのしみあひし川竹は流れなれとも今朝は恋しい
早乙女にほれたとみえて雨あかり田植の足に吸(ひ)付(い)たひる
へつたりと降(り)つむ雪の庭の面ほくろとみゆるとひ石もなく
おそけれとつつやはたちてやうやうと恋のいろはを習ひ覚(え)た
一首目の題は「後朝ノ恋」。初句「魚と水」は親密な間柄をいう。また成句に「川竹は流れの身」(遊女の身の上)があり、ここから「川竹」で遊女をさす。一夜だが結句「今朝は恋しい」というのである。二首目の題は「雨後の田植」。蛭は吸い付いて血を吸うが、珍しいものてはなく「蛭鉤」(蛭に似た吊り鉤)や「蛭飼い」(腫れ物の悪い血を蛭に吸わせて治療すること)などからも生活に近かったことが知れるのである。三首目の題は「雪飛(び)石ヲ埋ム」。上句は「へったりと降り積む雪の庭の面」と読んだ。初句の「へ」は雪のイメージから半濁音や濁音を退けた結果である。下句は「黒子と見ゆる飛び石もなく」。庭の「面」(顔)に「黒子」が見立てであるが、雪で化粧したので隠れてしまったようだ。四首目の題は「漸ク色ノ道ヲ知ル」。〈遅けれど十や二十で漸うと恋のいろはを習ひ覚えた〉。「つづ(十)やはたち(二十)」で二十歳をいう。「いろは」は手習いの最初に習うことから初歩ないしは入門篇である。
百姓のははか悋気に里芋のおやちもとんとくわをぬかした
にほはせて馬子はたはこをすつはすはよう吸(ふ)事しや五十三次
たひ枕ねられぬ儘にやとの事おもひ明(か)して気草臥(れ)した
雪ふりに屋尻を切(つ)てぬすまれたそのしろ物の行衛しらなみ
一首目の題は「老女ノ悋気」。〈百姓の婆が悋気に里芋の親仁もとんと鍬を抜かした〉。「里芋の親父」は里芋の子の父、子だくさんなのだ。「とんと」は「すっかり」、結句は成句「鍬を抜かす」(茫然とする)で縁語仕立てとなる。二首目の題は「行路ノ馬子」。初句「匂はして」は酒代の要求であろう。いい返事のあるまで馬は動かさない、煙草を吸い続けるらしい。結句は「すっぱすぱ」の回数を掛けて東海道五十三次、呆れているのだ。三首目の題は「旅ニ留守ヲ憶フ」。〈旅枕寝られぬまままに宿のこと思ひ明かして気草臥れした〉。留守宅である家(宿)を思って寝られなかったのである。結句「気草臥れ」(気疲れ)に初句の「旅」と同音を含むのも偶然ではないだろう。四首目の題は「雪中盗賊」。成句「家尻を切る」(盗人が家や蔵などの裏手の壁に穴を空ける)を使った。初句は「雪の降るときをいう。盗まれた「代物」(金銭)にその雪の「白」を掛けた。結句「白波」は盗賊のこと、「白」に「知ら(波)である。
|
| 第34回 狂歌鵜のまね |
愚かなる言葉を世々に残し置(き)て必(ず)似なと思ふ形見そ 山中千丈
『狂歌鵜のまね』の詠者は山中千丈、刊記は明和四(一七六七)年である。掲出歌は序文の最後に「一子鉄之進へ詠(み)てあたふる」とある。四句「似な」(会話では「にぃな」だろう)は「似るな」の意。潔いが、これには「返し」があって一子十二歳〈違はぬを孝とし聞けは我もまた父の跡追ふされ歌の道〉千麿とある。形見は引き継ぐというのだ。跋文は友人の虎林館千里が書き〈人はいさ光りを磨く言の葉を玉と我のみ誉(め)て奥書〉と締める。
能いおとしとりの年とてつへこへと囀る春の女子衆の礼
きのふけふ花も盛(り)とさくら坂見にくる人も峠なるかい
花も人も乱れあひたる糸桜くたをはまくの内の酒もり
手はしかう鎌をかけても麦秋はやとふ人さへあちらむきやす
一首目の題は「早春ノ礼 酉の年」。二句「取り」に「酉」、三句以下に男尊女卑も漂うが、枝に囀る鳥さながらの光景は珍しくない。正月の格別華やかな景が活写されている。結句「女子衆」は「おなごし」で四音。二首目の題は「峠の花盛(り)」。一首は「峠」の両義性(①山の上り下りの境目。②ものの勢いの絶頂期)に拠った。結句の話し言葉「かい」は疑問と確認の意を表す終助詞である。三首目の題は「花下ノ酒宴」。三句「糸桜」は枝垂れ桜の別名、二句の比喩ほか「糸」の縁語仕立てとなっている。三四句「くだをば巻く」と「幕の内」が「まく」を共有する。。四首目の題は「麦秋怱」(「麦秋」は麦を取り入れる初夏の頃、「怱」は慌ただしい意)。初句は「手はしかく」のウ音便、「はしかい」に「痛がゆい」と「機転がきき敏捷である」の両意を託した。結句の助動詞「やす」は四句「雇ふ人」への軽い敬意を表す。
夜番とて下戸も徳利をふる雪のしろ酒てちと寒をしのいた
大小のこしりつまつた大三十日武士もぬきさしさせぬ借銭
降(り)もせて雨降り山の名もあれは水ありとても水無瀬とや云(ふ)
さきの夜は御寝なら路へ馬上にて眠り落(と)させ給ふ宮さま
一首目の題は「寒夜ノ下戸」。三句「ふる」は「徳利を振る」と「降る雪」で上下に働いている。「雪の」以下も実景としての「雪の白」を描きつつ、「雪のような白酒」を準備した。二首目の題は「歳暮」、作者の山中千丈は摂州高槻の人、武士の身分であった。一首は成句「鐺が詰まる」(借金で身動きできなくなる)に拠った。「鐺(こじり)」は刀の鞘の先端の部分、これが詰まれば四句「抜き差しさせぬ」で刀と借金の双方に掛かる。三句は「おおみそか」と読む。三首目の題「水無瀬川」は大阪府北東部の島本町を流れ、淀川に注ぐ川、二句「雨降山」は神奈川県丹沢山地東南端に位置する大山の異称である。名高い固有名詞を水の有る無しで虚を衝いた。四首目の題は「馬上ノ眠」。二句は「御寝(ぎょしん)なる」で「寝る」の尊敬語、「御寝ならじ」に「奈良路」を掛けた。四句は「眠り落(と)す」の複合語。「眠りに落ちる」でなく、助詞「に」を省略、敬語表現も加わって一瞬「宮さま」落馬のイメージとなる。
|
| 第35回 興歌帆かけ船(1) |
寂滅とかねてはたれも夕暮や何時しらぬか仏成(る)らん 雪縁斎一好
『興歌帆かけ船』の詠者は雪縁斎一好、刊記は明和五(一七六八)年、編者は子の白縁斎梅好(一七三七~一八〇五)で一好十三回忌の追善集である。掲出歌は辞世、行年五十六歳とある。上句は成句「寂滅を唱う」(「死ぬ」意)を使った。死は自明の理だが何時(なんどき)と知れない。これに成句「知らぬが仏」を掛ける。涅槃の意の寂滅と結句の仏が呼応する。
浦遠く霞をわけて入相の鐘にそ浪の花やちるらん
人ことにかさりし花の言の葉もちることやすきひとへ正月
暦よりこまやかにふる春雨やはしめをはりはみせぬ八せん
前後をも花に忙して吉野山足よりも目のかいたるきかな
一首目の題は「海上晩霞」。上句は霞の中を帰帆する船を遠望する「私」である。しかしまだ船首は見えない。陸では晩鐘が響いて桜の花が散っている。そして独白「この花に似て船の舳先は浪の花(飛沫)を上げているのだろう」。二首目の題は「ひとへ正月と人のいへるに」。「ひとえ」は「一日」(ひとひ)の変化で「一日正月」は二月一日をいう。初句は「人ごとに」で、もう誰も賀詞を述べることもない、それが四句であろう。三首目の題は「八専の春雨といへることを」。「八専」は陰暦で壬子の日から癸亥の日までの十二日のうち丑・辰・午・戌の日を除いた八日をいう。この期間は雨が多いといわれる。ただ春雨は八専の始まる前の日も、終わった次の日も降り続けているのだ。四首目の題は「芳野山の花に」。初句は「(左右はいうに及ばず)前後をも」の感がする。二句「忙(せわ)して」は「忙しいて」その前は「忙しくて」の音変化だろう。どこまでも桜の花で足より目が「かいだるい」(かったるい)のだ。
あすの夜を今宵になして踊子もここかおもひのきりこ燈籠や
久かたの雨戸へ闇やひきこんてことにさやけき月は一めん
黄昏のしはしくらかり峠をはならより越(え)るししの月かけ
泉水に秋はもみちのにしきとも別れてみゆる金銀の魚
一首目の題は「文月晦日に」(陰暦七月最後の日)。いつから始まったのかは不明だか、盆踊りも今宵限りなのだ。心残りのないようにというのが初二句の表現、だから下句の「ここが思ひの切り子(燈篭)」となる。切り子燈篭は盆提灯をいう。二首目の題は「月丁琴」(提琴は胴が丸いので「月提琴のごとし」か)。初句の枕詞「久方の」を「雨」ならぬ「雨戸」に掛けた。二、三句で視界を確保すると「殊に」(「とりわけ」の意。同音の「琴」を掛けた)「月の光が冴えて美しい辺り一面」(「面」は琴の助数詞)となる。三首目の題は「十六夜」。三四句に跨る「暗峠」は奈良と大阪を結ぶ生駒山地の峠である。猪(四四)が越えるように、四四十六夜の月もためらいながらであるが、大坂側の山の端に姿を現そうとしているのだ。四首目の題は「秋泉水」(「泉水」は庭の池)。秋の紅葉の錦、池に泳ぐ錦鯉、同じ錦であって同じでない。また泉水に映る紅葉の影を行き来する錦鯉、併せて四句「別れて見ゆる」なのだろう。
|
| 第36回 興歌帆かけ船(2) |
言のはの色もよしののたはこうた床にかけ地の一ふくとなる 雪縁斎一好
掲出歌は題に「連中の床に由縁斎翁の煙草の絵賛に かほりさへよしの田葉粉の夕煙はなのあたりをたちのほるかな 右一軸を拝覧して」とある。「連中」は仲間の人たち、ここは狂歌仲間だろう。由縁斎貞柳の四句「はな」は「鼻」に「花」を掛ける。一好の四句は「床に掛け」また「掛地(かけじ)」は掛け物、結句「一ふく」は「一幅」に「一服」を掛けた。
無風雅と人やみるらん丸合羽時雨にかさす袖のなきこそ
定めなき世にも磁石の針のやうにいつくてふるも北時雨かな
ひとり行(く)道とはいへと来迎の菩薩をいれて二十六人
ねふい目と寒いめをして拝ますにかへるは以上三そんの弥陀
一首目の題は「時雨」。三句「丸合羽」は袖なしの合羽をいう。風雅とは何か。たとえば藤原家隆の〈ながめつついくたび袖に曇るらん時雨に更くる有明の月〉(『新古今和歌集』五九五)だろう。和歌では時雨に袖と涙は欠かせない。二首目の題も「時雨」。時雨は定めなく降るものだが二句の「世」でいえば〈篠の篠屋の村時雨/あら定めなの/憂き世やなう〉(『閑吟集』一九五)が思われる。四句「降る」に磁石の針が「振る」を掛ける。結句「北時雨」は北の方から降ってくる時雨をいう。三首目の題は「釈教」。結句の「二十六人」は初句の「ひとり行(く)」「私」と二十五菩薩をいう。浄土教では臨終の際に二十五菩薩が阿弥陀仏とともに来迎する(さすがに如来は勘定に入っていない)。四首目の題は「霜月廿六夜の月拝せんと難波橋迄まかりしに遅くなれば帰るさによめる」。月光の中に弥陀・観音・勢至の三尊が現れるという二十六夜待ちである。初句二句三句で「以上」は合計で「三尊」に「三損」を掛けた。
なけけとて茎やはものを思はするむかしは梅の種も割(り)しに
人肥(え)し旅にしあれは思ひしる竹輿かる折と居風呂の時
そののちはついにたよりもしら雪の白雪のとてつもる年月
下戸上戸へたてもなみのやかたふね知つた同士や涼しかるらん
一首目の題は「寄歯述懐」。二句の「やは」は疑問、「茎」とは歯のない歯茎、これで租借しているのだろう。すでに人工歯も行われていたようだが、いずれにしても梅の種を割る自然歯の比ではない。二首目の題は「旅行述懐」。肥満した旅行者の悲哀が二件続く。四句「竹輿」は竹製の駕籠、「かご」と二音で読んだ。「居風呂(すえふろ)」は桶の下部が釜で水から沸かす風呂をいう。雲助に嫌われ、旅篭の主人に迷惑がられ、それでも痩せないのだろう。三首目の題は「寄雪懐旧」。三句「しら」は「知ら(ない)」に「白(雪)」、雪の積もる景色に音信不通の歳月を重ねた。『後撰夷曲集』に一幸の〈上るりのふしふしとなる中々にさてもそののちあはぬ君哉〉があるが、この「そののちに」を受けたように思えてならない。四首目の題は「川口眺望」。二句「なみ」は「無み」(無いので)に「波」を重ねた。三句は納涼の「屋形船」である。四句は「(下戸も上戸も)「知つた同士」で気心が知れているというのだろう。
|
| 第37回 興歌帆かけ船(3) |
御辞退をする墨なれとふかきゆえん有(る)にまかせてくらうかけます 白縁斎梅好
掲出歌の題は「紫笛のぬしより予が婚姻を祝して墨を贈り玉ふとて よろこびを申すゆえんのあるからにかたばかりなる祝儀する墨 とある返し」。「附録」に収められた作である。
よろこびを申すゆえんのあるからにかたばかりなる祝儀する墨 如雲舎紫笛
月ならで雲のうへまてすみのほるこれはいかなるゆゑんなるらん 油煙斎貞柳
紫笛(一七一八~一七七九)の歌を再掲し、梅好と共有する「由縁」の源流たる油煙斎貞柳の作を並べた。紫笛の「由縁」は梅好と同じ貞門であることをいう。「由縁」に「油煙」を掛けたのは貞柳の墨にまつわる逸話からである。梅好の二句に「擦る墨」を掛けたのも祝いの品以上に「深き由縁」で断れないのだ。結句は「苦労かけます」に「黒う書けます」となる。
廿五の春やきた野の神垣にむかふて運をひらく梅か枝
ねもやらて耳をすましつ時鳥ほそんかけ樋の水の音のみ
豊としの田面をてらす月見れは人はあをむく稲はうつむく
千早振(る)鈴の音いろもしやんとした袴を着せて神へ参らしよ
以下、梅好の作が並ぶ。一首目の題は「廿五歳の春をむかへて」。二句「きた」は「来た」に「北」、北野天満宮である。梅の枝に開く花のように、狂号も梅好であれば、自らの開運を祈ったのである。二首目の題は「髪截山にて時鳥を待(ち)しに夜もすがら懸樋の水音の耳にさはりければ」。「髪截山」は生駒山中の「髪切山」と思われる。時鳥の名所であった。四句は時鳥の鳴き声「ほぞんかけたか」に「懸樋」(かけい)を掛けた。三首目の題は「三五夜」。陰暦十五日の夜、満月である。初句は「豊年」(とよとし・ほうねん)、二句「田面」(田の表面)は「たおも」と読んだ。豊作だから下句の対句表現となった。四首目の題は「袴着」、初めて袴を着せる儀式で、やがて七五三として定着した。初二句は「千早(舞衣)を着た巫女が振る鈴の音色も」の意で三句「しゃんとした」(鈴の音に副詞の「しゃんと」を重ねた)の序詞となる。結句「参らしよ」は「参らせん」の音変化「参らせう」その上方表現と解した。
据風呂に入(る)や彼岸の心さしあかの他人もあつくよろこふ
水の面にうつるをみれは雲のうへわたるこころそ百しきや橋
四ツ橋の名代を通すきせるやの買人はひびにつまる店さき
一首目の題は「彼岸の入(り)に据(ゑ)風呂をたきしとて人々をいれ玉ふに」。「私」も入れてもらった一人か。二句の「や」は接続助詞、三句は「志」の宛字、積善に努めているのである。四句「赤」に「垢」、結句「篤く」に「熱く」となる。二首目の題は「浪華の橋づくしの中 敷屋橋」。三句「雲の上」は実景に内裏の意を重ねた。結句「百敷」は宮中、一字を共有して「敷屋橋」となる。限定付きながら雲上人なのだ。三首目の題は「四ツはしのきせる名高きに」。煙管屋が軒を並べていたらしい。二句「名代(なだい)」は評判の高いこと。四句「買人(かいにん)」は買い手をいう。下句の「日々に詰まる」は客の多さを煙管に擬えた。
|
| 第38回 狂歌野夫鶯(1) |
名月や扨名月や名月や秘蔵の植木か邪魔に成(り)けり 九如館鈍永
『狂歌野夫鶯』の詠者は九如館鈍永(一七二三~一七六七)、選者は吐虹校、明和七(一七七〇)年の刊である。掲出歌の題は「名月」。「松島やああ松島や松島や」が思われるが、これは江戸時代後期の狂歌師田原坊の作、しかも「ああ」は「さて」であったというが狂歌史で足跡を確認することはできなかった。下句はあたら秘蔵の植木が、といったところだろう。
久かたの天津のつとの太はしら探る雑煮のあなうまし国
ふこ尻をもつたてて摘(む)春の野にまたとしわかな嫁なましくら
おつとつてゑいやつ塔の前の藤立(ち)あふて見る花のしなへを
久かたのあめの細工やちやるめらの笛のねたててよふ子鳥かも
一首目の題は「雑煮」。初句は「天」に掛かる枕詞、二句の「のっと」は「祝詞」で「天津祝詞」は祝詞の美称、三句の「太」は立派な、「柱」は神霊の依代、これに「箸」を掛けた。結句は「旨し」に「美し(国)」となる。二首目の題は「早春」。初句「ふごじり」は大きく平たい尻、また出っ張った尻。二句「持っ立てて」は持ち上げるように立てて、下句の「(年)若な/嫁な」に若菜と嫁菜が隠れる。結句「ましぐら」は「まっしぐら」、尻も軽いのだ。三首目の題は「洛東祗園塔の前藤見にまかりて」。初句「押っ取って」は「気軽に」また「意のままに」、二句「えいやっと(う)」は決断するさまに刀を振り回すときの掛け声を重ね、結句は花の「撓へ」(撓うこと)に同音の「竹刀」で剣道の様子を掛けた。四首目の題は「喚子鳥」、初句の「久方の」を「天」「雨」ならぬ「飴」に掛けた。三四句の「笛」は結句の布石なのだろう。その結句は上から「(笛の音立てて)呼ぶ子」また飴細工の「呼子鳥」となる。
ほとときす思ひもよらぬ一声をききはつつたるてうの始(め)に
しやつきりとおへて見ゆ也早乙女かまくる裾野の小田のわかなへ
よそにみても心せわしき夕立やかつらき山にかかる黒雲
月宮殿玉斧の修理も成就して扨けつかうな秋の中空
一首目の題は「普請場時鳥」。四句は「聞き外ったる」、。結句「てうの」は「ておの」の転で発音は「ちょうの」、したがって結句は「手斧始めに」となる。不運にも手斧の使い始めと時鳥の鳴く声が重なったのである。二首目の題は「早苗」。初句「しゃっきり」は直立しているさまをいう。二句「生へ(る)」は「成長する」と「勃起する」の両意を含む。下句は「泥で汚れないように捲った早乙女の着物の裾、そこに広がる水田の若苗」となる。一に若苗、二に早乙女に勃起する若苗の戯画だろう。三首目の題は「夕立」。初句は黒雲の下にいない、余所事をいう。四句「葛城山」は奈良と和歌山の両方にあり、いずれも「私」がいるのは大坂側である。なお和歌に「黒雲」の用例を見ないが如何。四首目の題は「名月」。陰暦八月十五夜である。初句「月宮殿」は月の中にあるという宮殿である。二句「玉斧」(ぎょくふ)は玉で飾った斧、これを欠けていた月の部分、また円く仕上げる道具の両方の比喩とした。
|
| 第39回 狂歌野夫鶯(2) |
手をとつて思ひ机により添ひつおしへてやらうか恋のいろはを 九如館鈍永
掲出歌の題は「机前恋」。場面一、寺子屋。今ならさしずめ学校の教師が生徒に言い寄る場面だろう。不良教師とおませな女の子、少なくとも同年代ではない。場面二、若者宿(若衆宿、寝宿)。男から女、女から男、男と男、もしかしたら女と女、考えられるケースは多い。場面三以下は読者の特権、妄想次第となる。三句「ひつ」を除けば現代語と何ら変わらない。
畳たたく音は高間かはらひ給へきよめて春をまつや神国
よつてかかつて搗(く)ぞめでたき年のくれ餅は餅屋かよいといへとも
額つくや神の広にはとりの名のそのかしわ手のひひく拝殿
いとはしな胸のひしやくや君か為たとひ湯の中はて水の中
一首目の題は「寄神道せいほ」。「畳たたく音は」と「春を待つ(や)神国」を縁語の比喩で埋めた。「高間が原」は八百万の神々がいるという天上界、「原」に同音の「払」を重ねて「払ひ給へきよめ」(給へ)で、ともども祝詞がらみなのだ。二首目の題は「餅搗」。初句は七音で「寄って掛かって」(大勢が寄り集まって)、四句「餅は餅屋」は餅屋が搗く餅が一番の意。専門家には及ばないが共同作業の中にこそ歳末の高揚感も生まれるというのだ。三首目の題は「寄鳥神祇」。〈額づくや神の広庭 鳥の名のその柏手の響く拝殿〉。初句切れで「や」は詠嘆。三四句に「鶏」が棲む。以下「鳥の名のその黄鶏(かしわ。羽色が茶褐色の鶏)と同音の柏手」となる。四首目の題は「寄杓恋」。初句は「厭はじな」。誠意を示すときの成句「たとえ火の中水の中」を使う。恋だから「胸の柄(火)」だが「火の中」で杓が燃えては困る。縁語の「湯の中」にしたが、「はて(と思案するに)」、それでは艱難辛苦にあたらないのであった。
袖たもとほすまなみたの雨とのみふりつつ君はつれなさほ竹
隠れもない大名しやとて公家しやとて恋に隔てはおりないは扨
かはらしと契り参らせそろはんのわれてもすへにあはんとそ思ふ
花のいろはうつりにけりな我も人もついしはくちやとなれる朝顔
一首目の題は「寄棹竹恋」。初句は「袖袂」、二句は「干す間無み」(干す間がないので)と「涙の」が「なみ」でつながり、結句も「つれなさ」と「棹竹」が「さ」で重なっている。「袖」「涙」「雨」は和歌以来の深い縁語である。二首目の題は「寄狂言詞恋」。〈隠れもない大名じゃとて公家じゃとて恋に隔てはおりないは扨〉。「おりない」は「御入りない」の音変化で「ない」の丁寧語。感動詞の「扨」は文末にあって自分の発言を確認する気持を表わす。これと「じゃ」が狂言詞だろう。三首目の題は「寄算盤恋」。〈変はらずと契り参らせ候(ばん)の破れても末に逢はんとぞ思ふ〉。三句に「算盤」を掛ける。四句の「破れて」に替わる「割れて」で割り算で割り切れることをいう。恋歌に算盤用語を交えて最後は大団円とした。四首目の題は「寄朝顔述懐」。小野小町の〈花の色は移りにけりないたづらにわが身よにふるながめせしまに〉(『古今和歌集』一一三)の三句以下に萎んだ朝顔を配してリアリティを与えた。
|
| 第40回 狂歌野夫鶯(3) |
とそ思ふヤツヲンはやふと望まれて急にもみ出す此(の)三番三 九如館鈍永
掲出歌の題は「三番三の絵に」。さらに「大幸大幸大よろこびありやわりこの所より外へはやらじ」(「やわり」は「やっぱり」)。二句「ヤツヲン」は「私」を指すらしい。下句の「揉み出す」は三番叟の舞の一部をいう。初句の大胆な「とぞ思ふ」に飛びついたが、これ以上は進めない。ヤツヲンは八音で音楽担当の俗称なのか、舞台を袖にする大幸とは何なのか等、如何。
鑓は毛槍弓は山田の鳥おとし鉄炮いそれ湯わかしとなる
通宝の徳は元より世の末も枕もやすくゆるり寛永
蚊の声も扇の芝の草陰に文武二道の名将の跡
あつまりし枝のねとりの昼かとておきまとはせる森の月影
一首目の題は「祝」。初句「鑓(やり)は毛槍」の毛槍は先端を鳥の羽毛で飾った儀仗用の槍。二句から三句の「山田の鳥威し」は案山子をいう。四句の「い」は副助詞で語調を強めた。「それ」は話題の「鉄炮」を指す。今や改鋳されて湯沸かしとなる平和な時代なのだ。二首目の題は「寄銭祝」。初句「通宝」は広く一般に流通する貨幣の意、二句の「元より」は昔から、これに「いうまでもなく」も入るだろう。寛永通宝は寛永十三(一六三六)年から万延元(一八六〇)年まで鋳造された。三首目の題は「古戦場蚊」。謡曲「頼政」に「源三位頼政合戦にうち負け、扇を敷き自害し果て給ひぬ。されば名将の古跡なればとて、扇のなりに取り残して今に扇の芝と申し候」とある。場所は宇治の平等院。初句は四句「文武」(蚊の飛ぶ音の擬音)に掛かる。四首目の題は「月如昼」。二句「寝鳥」は塒で寝ている鳥、四句は「置き惑はせる」で夜か昼か見分けがつかない、これに三四句「昼かとて起き」を重ねて立体的とした。
佐藤兵衛教清入道西行も富士かなけれは唯はつち坊
引(か)ぬ弓もてと放さす山田守僧都の身には尤に候
いつれなりと柳はみとり去(り)なから只一本も花はくれない
六塵のけふ迄遣ひし色々をへつたりけした墨染の袖
一首目の題は「富士見西行の絵」。「富士見西行」は笠や旅包みなどをわきに置いて富士山を眺める西行、その後ろ姿である。結句「鉢坊」は乞食坊主、富士山を消して外観だけで判断すればそうもいえるのだろう。二首目の題は「案山子絵賛」。初二句は「引かぬ弓もてど放さず」。三句「山田守」(やまだもり)は山田の番人をいう。四句「僧都」は「玄賓僧都」で案山子、案山子は玄賓の創案ともいわれる。結句「尤に候」の由縁である。三首目の題は「紅梅と柳沢山に有(り)し方にて所望せしかば柳はいかほどもやるべし梅はやらじといひけるに」。三句「去りながら」(「去」は宛字だろう)は「そうではあるが」。結句に「紅」と「呉れない」を掛けた。四首目の題は「色欲ふかき人はからずも発心せるを」。初句「六塵」は色・声・香・味・触・法の六境、心の清浄を汚すので六塵ともいう。三句以下は仏教用語の「色」を重ねることで意味を転換し、その「色々」を墨染の黒で「べったり消した」というのである。
|
| 第41回 狂歌気のくすり(1) |
元朝の雑煮の餅はいくつても嬉しきものよ下戸も上戸も 傍花
『狂歌気のくすり』の撰者は三休斎白掬、閲者は秋園斎米都、刊行年は不明らしいが米都の跋文は明和七(一七七〇)年である。掲出歌の題は「元日」。三句の「いくつでも」は年齢の如何に係わらず、これに初二句を受けた「何個でも」の意を重ねた。酒なら上戸と下戸で好き嫌いが分かれるが、同じ米からできているとはいえ正月に食べる雑煮の餅は別格なのだ。
見染(め)つつそつとするほと我はまた惚(れ)にけらしなろくろ首たけ
ほれたとてちよつとつめつたおいとより其こひ中の深うなりぬる
かく人もかかるる駕籠の内と外同し生れも肩によるかや
鳴(く)まては爰をはさらしやよいかに根気くらふの山時鳥
一首目の作者は菊二、題は「寄化物恋」。二句は「ぞっとするほど」、結句は「ろくろ首」に「首ったけ」(夢中になる)の意で「首」を共有した。化け物だが、ろくろ首は美しい女性なのだ。二句は恐怖と感動の相反する面をいう。二首目の作者は時風、題は「寄井恋」。二句「抓(つ)めった」は「抓(つね)った」に同じ、三句「おいど」(御居処)は尻をいう女性語、女が男の尻を抓ったのである。題の「井」と三句の「(お)いど」また結句の「深う」も縁語である。三首目の作者は花楽園都流、題は「寄駕籠述懐」。初二句は「舁く人も舁かるる駕籠の」、結句「肩」は運をいう。肩に倶生神、人とともに生まれる神が宿っていて運命を支配するという俗信に拠る、これに駕籠を担ぐ肩を掛けた。四首目の作者は三休斎白掬、題は「寄名所時鳥」。二句は「ここをば去らじ」、三句「やよいかに」は呼びかけて問う語。結句の「くらぶ」は「比ぶ」、句またがりで「くらぶの山」は鞍馬山の古称、歌枕で時鳥の和歌も多い。
船橋のありとはすれと天の河今宵浅瀬のあらまほし合
礼義ある御代にたのもの節句とて稲の袴も揃ひ社すれ
太平の代にも弓矢をはなさぬは山田に立(て)る何かしかかし
川の瀬と人の心と夏の日はかはりやすひとゆふたちの空
一首目の作者は三休斎白掬、題は「七夕」。初句「船橋」は船を並べてつなぎ、その上に板を渡した橋をいう。結句「あらまほし」はあってほしい、次は「けれ」の予想を裏切って「星合い」(牽牛と織女の二星が会うこと)となる。二首目の作者は三休斎白掬、題は「八朔」(陰暦八月一日)。「田面の節句」は稲の初穂を田の神などに供える穂掛けの行事をいう。また武家の年中行事とりわけ幕府の重要行事だった。下句は稲の袴(茎をまといおおう皮)を登城する武士の袴に見立てた。三首目の作者は三休斎白掬、題は「案山子」。平時にも準備怠りない武士がいる。それが案山子なので結句が「なにがしかがし」(某某)のその他大勢では困る。ここは自称で「何某(は山田の)案山子(でござる)」と改まって読みたい。四首目の作者は八朔庵米因、題は「夕立」。その夕立を降らせる空が「川の瀬」と「人の心」と「夏の日」は変わりやすいと「言うた」(「ゆうた(ち)」)のである。空とは「夏の日」そのものだろう。
|
| 第42回 狂歌気のくすり(2) |
さひしさは土瓶の下に火気もなしひとり坊主の庵の夕くれ 僧 一英
掲出歌は「題しらす」。この一首のみが入集している。僧侶で美濃の人、情報はこれだけである。僧侶といっても寺の住職ではないだろう。三句の「火気もなし」からも心もとない境遇であることが想像される。自画像として捉えてもいいのではないか。思い浮かべたのは歌人なら山崎方代、俳人なら尾崎放哉や種田山頭火といった近現代を生きた人たちであった。
山々に霞の網を春なれと鳥おとろかぬ御代そのとけき
ひけとあとへ何を種とて生(ひ)出(づ)る畑のうねうねしける夏草
橘の香をとむへくも便りなくおしや昔の人となられた
山寺の花の盛(り)に来て見れは日中のかねにひらく弁当
一首目の作者は帰一斎三麿、題は「霞」。二句は「霞網」ならぬ「霞の網」、しかも「張るなれど」ではなく「春なれど」だから「鳥驚かぬ」だ。「御代」という治世に還元するのは頂けないが「のどけき」里山である。二首目の作者は帰一斎三麿、題は「夏草」。初句は「引けど後へ」、四句「うねうね」は文字通り「畝という畝」そこに高く低く続くさまを重ねて結句「茂る夏草」となる。二句の「何を種とて」は実感だろう。三首目の作者は袖香堂蘭室、題は「家号橘や永日庵其律追悼」。其律(一七二〇~一七六一)は尾張の商家の出身、貞柳の高弟であった。屋号の〈橘の香を尋むべくも便りなく惜しや昔の人となられた〉。本歌は〈五月まつ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする〉(『古今和歌集』一三九)である。四首目の作者は猪葉、題は「日中桜」(「日中(じっちゅう)」で午の刻)。四句は「ひなか(の鐘に)」と読んだ。片や鐘を合図に勤行の始まる僧侶、片や弁当を開く人たちと賑やかな山寺なのである。
目にも見す手にもとられぬ鉄砲のたまほとときす耳にふれけり
はや馬のあしよりはやき秋の日に鞭うちたてるやうな日くらし
かり金に気は文七とひちはつてりつはにやらんくれの立ひき
かしたまふ笠はあたまにいたたきて合羽は恩に着てかへらはや
一首目の作者は猪葉、題は「時鳥」。上句は四句「たま」の序詞、美しい声すなわち「玉の声」を耳にした僥倖が「偶々」のニュアンスで迫る。時鳥の題詠は簡単に鳴き声を聞かせてくれない、これが前提にあるようだ。二首目の作者は猪葉、題は「蜩」。早馬に鞭打つのではない。早馬の足より早い日脚すなわち秋の日に鞭を盛んに打つような、そんな蜩の声が聞こえるというのだ。見立てだが二つの「日」が要所を押さえた。三首目の作者は雨柳、題は「歳暮」。〈借り金に気は文七と肘張って立派にやらん暮れの立て引き〉。「借り金」に「雁金」で雁金文七(一六七六~一七〇二)となる。大阪の無頼漢で後に「雁金五人男」として劇化された。「肘張って」は強そうな様子で、「立て引き」は談判、交渉をいう。四首目の作者は雨柳、題は「或(る)所にて笠と合羽をかりて」。三句は「①頭に被る②頭上に押し頂く気持ち」の両意、下句の「(恩に)着て」も気持ちと実際の両意を掛けた。結句「帰らばや」は「帰ろう」。
|
| 第43回 狂歌気のくすり(3) |
箕笠てよろふて田子の勢揃へ水責(め)にする雨の苗代 宣樹
掲出歌の題は「苗代」。初句は「蓑笠」で簑は肩に羽織る雨具、笠は被り笠。二句は「鎧ひて」のウ音便だから「鎧うて」、「田子」は農民をいう。四句「水責め」は拷問の一種、仰向けに寝かせて顔に水をかけたり、また飲ませたりする。しかしそれでは上句が生きてこない。ここは兵法の「水攻め」だろう。その証拠に結句の「苗代」に「城(代)」が隠れている。
星さまも今宵しつほり相合(ひ)のかささきの橋ぬれやわたらん
いつまてもひよこて居たいものなれと又年ひとつとりの春かな
降(る)かことく来る掛(け)乞(ひ)の書(き)出しも払へはきえる雪の大とし
かしらにはとくふりにけるおやちさへめつらしと見る今朝の初雪
一首目の作者は柳煙斎鷺洲、題は「七夕雨降(り)ければ」。初句の「さま」が親近感を増す。三四句「相合ひの傘」と「鵲の橋」(牽牛と織女を会わせるために鵲が翼を並べて天の川に渡す橋)が「かさ」を共有する。結句は「や~ん」の係り結びである。二首目の作者は鶫山堂魯伯、題は「酉春」。いつまでも子供でいたい、年をとりたくない。にもかかわらず年を取る。取らねばならない。「酉」に「取り」で珍しい述懐風の「春」の歌である。三首目の作者は鶫山堂魯伯、題は「大晦日雪降(り)ければ」。二句「掛け乞ひ」は掛け取りのこと、三句「書き出し」は請求書、結句「大とし」(大年)は大晦日をいう。なお「払へば消える雪」だが、掛け金と違って、こちらは現に降っているのだ。四首目の作者は陶々斎干有、題は「初雪」。二句の「とく」は「疾く」(とっくに)で三句「親父」の「かしら」(頭)は白髪だのに、という。他愛ないが初雪は季節が巡らなければ見られない、それだけ感興を誘うのであった。
さしもなと名には立(つ)らむ猿猴の手も長月の月は得とらて
冬の月望(む)をやめて山のはの木の実になくかましら成(る)らむ
松のうへに手にとることき月見てや谷から峰へ登るむれ猿
春の野の草の庵の頼母子は風にあたつて匂ふ花くし
一首目の作者は白鶴、題は「月前猿」。上句は「然しもなど名には立つらむ」(それほどにも、なぜ評判になるのだろう)。四句は「手も長(い)」と「長月」が重なる。念頭にあるのは「猿猴が月を取る」(水に映る月を取ろうとして溺死する猿の故事)。月を取ってもいないのに、というのだ。二首目の作者は一松、題は「同じく」(月前猿)。初二句に大望を抱いたばかりに溺死した故事の猿が浮かぶ。下句は「木の実に鳴くが猿なるらむ」、今一つは「木の実に鳴くが増し(ら)なる(らむ)」(身分相応)というのだ。三首目の作者は淡水、題は「同しく」。上句は谷から「松の上に手に取るごとき月見てや」、「見たのだろうか」である。下句の生き生きとした景が印象的だ。四首目の作者は鶯里、題は「野亭頼母子」。「頼母子」は「頼母子講」に同じ。結句「花籤」は本籤のほかに若干の金銭を分けるために混ぜる籤をいう。「花」ともいい、ここから生まれた一首だろう。四句「あたって」は籤の縁語、促音便が印象に残る。
|
| 第44回 狂歌気のくすり(4) |
里人にやかれてもまたこりもせす今年も手をはのへの早蕨 沖名斎鳥億
掲出歌の題は「蕨」。『夫木和歌抄』に〈さわらびももえやしぬらん山人の野やくけぶりはたなびきにけり〉(八九三)がある。二句の「もえ」は「燃え」と「萌え」、野焼きを詠っている。掲出歌は野焼きとその後である。結句の「のへ」は「野辺」と「伸べ」となる。題の「蕨」は最後に出てくるだけ、このため怪しい世界に足を踏み入れたような錯覚に襲われる。
親はさて胸こかすらん捨(て)し子をてらす螢の尻の火よりも
驚(く)ほと音する風はふかねとも蚊帳のうこくに秋そしらるる
ほとときす客の有(る)夜は鳴(き)やらて思はぬ我をうそつきにする
豊年のしるしを見せて蓬莱にむへかさり米白妙の雪
一首目の作者は梢楽斎先賀、題は「螢照捨子」。間引きは子殺しであるが、捨て子は拾われることが期待されている。初二句「胸焦がすらん」は「胸の火」、これと結句の「尻の火」が対応している。二首目の作者は冗斎其律、題は「初秋」。本歌は藤原敏行の〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(『古今和歌集』一六九)だろう。夏の風と秋の風、その微妙な変化を四句で知るのである。三首目の作者は浅野暁格、題は「時鳥聞(か)んと友の来(た)りけるになかざりければ」。〈時鳥 客のある夜は鳴きやらで思はぬ我を嘘つきにする〉。普段は鳴くのに肝心のときは鳴かないというのである。四句「思はぬ我を」は「思いもよらない我を」の意である。四首目の作者は筍香園帒路、題は「蓬莱」。〈豊年の瑞を見せて蓬莱にむべ飾り米白妙の雪〉。成句「雪は豊年の瑞」、「蓬莱」は蓬莱飾りの略、新年の祝儀として床などに飾った。四句以下「むべ(なるほど)雪に見立てた飾り米だ」。初二句と下句が対応する。
双六のさいにも似たり春雨のふる度ことに種々のめか出る
いはひつる齢はかきりなく今しやいたたき禿(け)て赤くなる迄
老(い)ぬれは立居に腰もかかみ餅目には霞のかかるはつ春
開帳はなくと藥師もすき間より覗(い)て見てのいと桜かも
一首目の作者は省斎可童、題は「春雨」。二句の「さい」は「賽」に菜園の「菜」、結句の「め」は「芽」に賽の「目」を掛ける。四句の「ふる」は雨が「降る」に賽を「振る」となる。二首目の作者は一陽斎柳生、題は「何某七十賀題鶴」(「何某(なにがし)」は自称、謙譲の意である)。〈祝ひつる齢は限りなく今じゃ頂き禿げて赤くなる迄〉。初句に「鶴」が隠れ、下句は「私」と「鶴」である。丹頂鶴の頭が赤いのは肌が露出しているのである。三首目の作者は童楽斎鳥兆、題は「としの初(め)に」。三句の「かかみ」は「屈み」に「鏡」を重ねた。下句は春霞ならぬ老齢に起因する「目には霞の掛かる」また「斯かる(このような)初春」となる。四首目の作者は露喬舎幽湖、題は「薬師堂の桜に」。初句「開帳」は秘仏を参拝者に公開すること、今はその期間ではないが季節は春、寺の桜も満開とくれば秘仏たる藥師如来も「帳」の隙間から花見をしているというのだ。結句「いと」は「糸」に副詞の「いと」(大変)を掛けた。
|
| 第45回 狂歌浪花丸 |
くみしめてゐるのはもののはつみにて是はと手うつけふらひもなし 雪縁斎一好
『狂歌浪花丸』の選者は白縁斎梅好、刊記は明和八(一七七一)年である。掲出歌は「おどけ画三十六歌仙」の一首、おどけ絵賛である。題は「うつけ」、絵は両腕を組んだ人物だが表情も身だしなみもだらしない。初句は「組み締めて」だろう。結句は「毛振らひもなし」、「毛振らひ」は気配をいう。妙案が浮かんだ、決断をした、そんな様子もないというのだ。
見かけよりさしたる功もない身にて大ふたらたらいふや大たら
まめ板や壱歩小判をうちませて奢りそ後は乞食なりける
かみしもてゐんきんするもおさまつた御代のしるしと祝ふなりけり
一首目の作者は一好、題は「大ぶいひ」(大分言い)。きっちりと帯を締めて刀を差した男の絵である。二句「さしたる」は取り立てていうほどの、これに初句「見かけ」の刀を「差したる」だろう。結句「大たら」は四句「大分たらたら」の略。二首目の作者は一好、題は「おごりもの」(奢り者)。絵は大黒頭巾を被った男が、座敷であろうか、銭をばらまいている。初句「豆板」は豆板銀で銀貨の一種、二句「壱歩小判」は一分金、四枚で小判一枚(一両)と換えた。結句は「驕れる者は久しからず」だろう。三首目の作者は如雲舎紫笛、題は「ゐんぎんもの」(慇懃者)。初二句から連想するのは名字帯刀を許された町人である。絵は刀らしいものを差した男が背中を丸めて深々と座礼している。三句以下の感想の拠り所と思われるのだ。
ゆたんせぬ番家のうちの蚊遣火にぬす人はなをけふたかるらん
たんしりを引(く)大坂のちからても京のほこにはとうもかたれぬ
我心われよりほかにしるへきや壁に耳なし岩に口なし
あらかねのつちてつくねた狐ても子ともをたましはかす持(ち)遊ひ
夏まつり何にたとへん天満川こきゆふる舟にそろへてうちん
ここからは「追加」の部、歌のみで構成されている。一首目の作者は白縁斎梅好、題は「町の番家に蚊をくすべるに」。「番家」(番屋)は市中警備のために町内に置かれた番所をいう。蚊遣火は自身番が詰めているからで、蚊のみならず、盗人も煙たいというのだ。二首目の作者は梅好、題は「祇園会を初(め)て拝見して」。上句は天神祭の陸渡御が思われるが、楽車の速さよりも山鉾巡行の荘厳華麗に感動、結句「どうも勝たれぬ」というのである。三首目の作者は梅好、「題しらす」。三句の「や」は反語、したがって上句は「私の心を私以外の者が知るべきであるか、いや無い」となる。下句は「壁に耳あり」「岩が物言う」からの解放と捉えたい。四首目の作者は梅好、題は「土ざいくの狐の絵賛」。〈粗金の土で捏ねた狐でも子供を騙し化かす持ち遊び〉。「粗金の」は「土」に掛かる枕詞、「捏ねた」はこねて丸めることをいう。狐の形の「持ち遊び」(玩具)である。五首目の作者は梅好、題は「天神祭」。四句は「漕ぎ揺ぶる舟」で「揺ぶる」は揺り動かすことをいう。結句は「揃へ提灯」で屋根の庇に並んでいるのだろう。提灯の灯が水面に映る、また同じような舟が天満川を「漕ぎ揺ぶる」のだ。
|
| 第46回 狂歌まことの道 |
三寸の舌て五尺のからたをはやしなひもするうしなひもする 如雲舎紫笛
『狂歌まことの道』の詠者は如雲舎紫笛、撰者は呉雲館山岐ほか四名、刊記は明和八(一七七一)年である。掲出歌の題は「舌」。「舌先三寸」「舌三寸」という。その短い舌が「五尺の体」「五尺の身」を生かしもし殺しもするという道歌の趣きである。四句と結句の対句表現とりわけ「(や)しなひ」(養い)と「(う)しなひ」(失い)が韻を踏んで巧みである。
福とくのたからとおもへのらむすこいつもおやちにもらふ目の玉
蟹はたた横に行(く)なりなには江のよしといふてもあしといふても
福とくはここにありとて大こくかこらへ袋をしつとおさへた
此あふきあふく時にはあつき日もなんのへちまのかはてこそあれ
一首目の題は「玉」。初句「福徳」は財産や幸福に恵まれていること、三句「のら息子」は「どら息子」、結句「目の玉」は「お目玉」をいう。「親孝行したいときには親はなし」で叱られているうちが花だというのだろう。二首目の題は「蘆に蟹」。蟹のように横に歩くことを蟹行という。初句「ただ」は「直」で真っ直ぐ、「唯」「只」で専らの意となる。植物「アシ」の別名は「ヨシ」だが、これを「善し」「悪し」といっても始まらないというのだ。三首目は挿絵の歌である。三句「こらへ袋」は「堪へ袋」のこと、トレードマークの大袋を堪忍袋にしてしまった。堪忍は一生の宝、成らぬ堪忍するが堪忍、その堪忍袋の緒が切れないように結句「じっと押さへた」のである。四首目の題は「へちまの絵のあふぎに」。初句「あふぎ」の発音は「おうぎ」だが視覚的には「あふぎ」「あふぐ」「あつき」と類音反復ならぬ類字反復である。下句は成句「何の糸瓜の皮」(何とも思わないこと)を使い、係り結びで強調した。
目や鼻のやまひはしらす耳によくきいた有馬の山ほとときす
朝かほのあしたの露にくらふれは一夜そなかきほし合の空
うは玉のくらやみならてふりしきり一寸さきもしら雪の空
あたこ山峯のかたより飛(ひ)さかるあれは天狗かいいやかはらけ
一首目の題は「有馬山にてほととぎすをききて」。初二句は有馬温泉、湯治場である。そこから「病」の語が出てくる。目や耳に「効いた」かどうかは知らない。ただ耳には「よく聞いた」というのである。二首目の題は「七夕」。初二句は「朝顔の露」(束の間のこと)と「朝の露」(朝、草葉に置いた露。短く儚いことの喩え)の両意を含む。その一時に比べれば、というのである。結句は二星が会う七夕の夜の空をいう。なお朝顔の別名が牽牛花、織女星を朝顔姫と呼ぶ。三首目は題に「西山泉谷達観亭にて雪のいたく降(り)ける日よめる」(西山は京都の山々、泉谷は現「右京区鳴滝泉谷町」が思われる)。四句の「一寸先」は烏羽玉の闇ではない。しかし何も見えない、ただ白雪の降る空なのだ(「しら」は「知ら」に通う)。四首目の題は「愛宕山にて」。愛宕山は京都市右京区にある山。標高九二四メートル、東の比叡山と相対し、山頂に愛宕神社がある。三句は「飛び下がる」だろう。土器投げを詠って珍しい。
|
| 第47回 夷曲歌ねふつ(1) |
海はらのはてしも浪の上にふりつもれる雪やこんひらの樽 九如館鈍永
『夷曲歌ねふつ』の撰者は御射山社紅圓、刊記はなし、序文は安永二(一七七三)年。掲出歌の題は「海上雪」。二句「果てしも浪の」は「浪」に「無み」を掛ける。結句は「金比羅の樽」で「流し樽」をいう。航海の安全を祈願して「奉納金刀比羅宮」の幟を立てた酒樽を流すのだ。その樽を遙拝しているのか、降れば消える雪も樽の上にだけは白く積もっていく。
夕立にさそはれ出(づ)るうろくすもしはしは遊ふ草むらの中
折(り)とる事禁制とのみ制札に引(き)ぬくなとは書(い)てないもの
蛍こいこつちの水はうまい事其(の)手はくはぬと尻に聞(き)ゆく
雪は富士氷は室に春こして夏迄冬はうろたへてゐる
一首目の作者は自然軒鈍全、題は「やごとなき御方にてやつがれが即興を御覧あるべしとて御家来の内に給(ひ)取(り)仰(せ)付(け)しに草原に魚の集(ま)りし所を書(き)しに」。夕立の雨に乗るかたちで打ち上げられた魚、その束の間の命を詠った。二首目の作者は鈍永、題は「ある寺の杜若を人のとりけるを侍壱人出て制札は見ずやとののしりけるをみて」。二句切れ、寺侍と花盗人の遣り取りに一休さんが思われる。三首目の作者は鈍永、題は「蛍」。三句は螢狩りの誘い水「甘い」から「うまい事」(まんまと)に意味を転じた。四句は「そんなやり方には瞞されない」(其の手は桑名の焼き蛤)。結句は成句「尻に聞かす」(聞き捨てにする)の逆だから慎重に「私」の尻の火で照らして行く意だろう。四首目の作者は鈍永、題は「氷室」。氷室は天然の氷を夏まで保存しておくための小屋または穴をいう。季節に違えて残る富士山の雪と氷室の氷に、退場の切っ掛けを失って冬が狼狽しているというのである。
七夕の後のあしたのもきとうさつい明年の明年のとて
くへもせぬこのみをそなへて玉祭けれう物いはぬ客なれはこそ
千年と契るもはかな常なき世鶴も料理の献立の一
山高み木なきを以て貴しとするかの富士は格別なもの
一首目の作者は鈍永、題は「七夕後朝」。二句は「後の朝の」、三句は形容動詞の「没義道」(不人情)に接尾語の「さ」である。これに能楽の「裳着胴」(上半身が下着の着付けだけの着方)を重ねた。別れを惜しむ後朝の恋なのだ。二首目の作者は鈍永、題は「玉祭」(盂蘭盆会)。二句の「このみ」だが一に「好み」で好きだったもの、故人だから初句「食へはせぬ」。二に「この実」で茄子で作った牛や胡瓜の馬、また「木の実」で季節の果物もあろう。四句「けれう」は「仮令」(幸い)だろう。三首目の作者は鈍永、題は「無常」。初句は「鶴は千年亀は万年」だろう。また「鶴の包丁」(将軍から献上された鶴を清涼殿で料理する儀式)という言葉もある。一般的だったかどうかは別として鶴は食材の一つだったのである。四首目の作者は鈍永、題は「山」。初句は「山が高いので」、二句から四句は聖徳太子の「和を以て貴しと為す」の口合いで「為るが」に「駿河」を掛けた。雪を戴いて格別だというのである。
|
| 第48回 夷曲歌ねふつ(2) |
思ひ出(づ)ることしの秋はうつらさへ七回と啼(く)やうに聞(こ)ゆる 錦月
『夷曲歌ねふつ』の「ねふつ」は「念仏」のこと、掲出歌の題は「市中亭の主人并社中よりも鈍子の七回に追悼の歌よみて送り給はりけるを爰に記」とあるように、『夷曲歌ねふつ』は九如館鈍永の七回忌追善集であった。四句の「七回(しちかい)」は『日本国語大辞典』に「ちちかい」で「鶉などの鳴き声を表わす語。ちちっかい」とある。その口合いとした。
諺もあてにはならす子か墓の石かものをはいはぬにて候
龍宮はこんな物かよ藤の棚あたまの上を濡(れ)ぬ浪こす
とふ鳥の放さぬ弓矢恐るるはたますに手なき案山子也けり
鍋墨のやうな闇夜にとふ蛍是そ火打(ち)の石山の景
一首目の作者は紅円、題は「八月九日鈍永居士七回の忌日に菩提所の墓所にまふて侍りて」とある。初句「諺」とは「岩に口」「岩が物言う」を指す。三句の「子(し)」は二人称の人代名詞である。紅円の「自序」に「予と此(の)道の友」とある。二首目の作者は訥峨、題は「藤」。藤の花が風で波のように揺れ動くことを藤波という。この「波」が結句「濡れぬ波」を呼び、波の底から海やがて想像力が初句「龍宮」へと案内する亀に変じたのである。三首目の作者は新水、題は「鹿驚」。初句は「早く」に掛かる枕詞を使って二句を呼び起こした。四句は成句「騙すに手無し」(瞞す以外に方法がない)に拠る。ではなぜ「恐るる」なのか。鹿には他意「巧みに騙しかけられては防ぐ手段がない」のだろう。四首目の作者は志水、題は「寺の蛍」。寺とは大津市の石山寺である。初句「鍋墨」は鍋や釜底についた黒い煤をいう。下句は蛍の光であるが「火打ち石」を分解して「石山」に接続した。寺の山号「石光山」が重なろう。
月は弓つるみよるてふ今宵しもはつさぬ的の星合の空
夜もすから鳴(く)声聞けはあの鹿に角かあろとは思はさりけり
戦(ひ)の跡とおもへはみなと川茶の銭まても切(り)合(ひ)にして
小指をは一本切(つ)たのこりにて九本の浄土へ手を引(か)ふそや
一首目の作者は季桃、題は「七夕」。初句「月は弓」(弓張り月)から弓に張る「弦」(つる)を引き出し、二句は「弦」の同音から「交尾み寄るてふ」(男女が交接のために寄る)。三句以下、再び弓矢を前面に出すが、最後まで性的な映像も失わない。二首目の作者は何麿。題は「鹿」。四句に「角」が出てくるのは〈奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき〉(『古今和歌集』二一五)に拠る。「あろ」は「あろう」が約まった。三首目の作者は踈慵、題は「湊川にて」。初句「戦(い)」とは建武三(一三三六)年、足利軍が新田・楠木の朝廷軍を破った湊川の戦いをいう。結句「切り合い」は切合勘定つまり割り勘のことである。四首目の作者は紅円、題は「恋の歌の内」。小指を切るのは愛の証、その道行きの場面である。四句は「九品浄土」(阿彌陀如来の極楽浄土。往生する者に応じた九種の浄土)に指の「九本」を掛けた。結句は「引く」の未然形に助動詞の「ふ」が付いて「ぞや」の詠嘆的強調となる。
|
| 第49回 狂歌今はむかし(1) |
冷水と好んた夏をはやおもひ桐の一葉か井戸にふたする 仙柳
『狂歌今はむかし』は由縁斎貞柳の五十回忌の追善集で集者は土屋自休、刊記は安永五(一七七六)年である。掲出歌の題は「初秋」。初句は「ひやみず」と読んだ。四句「桐」は落葉高木で葉は大きな広卵形で長い柄を持つ。だから井戸を覗くと結句「蓋する」ように見えたのであろう。季節感がそこに凝縮しているようである。二句「好んだ」も口語体である。
梅かへる発鶯も音つれてほほうけつかうなあら玉の春
あつさゆみ春の日なかに引(つ)こしてゐこころもよふ思ふやうつり
麦の穂をこなせは人の手あしまてあからみもするみかいりもする
実もりの白髪を染(め)ししの原とそら真黒にくもる夕たち
一首目の作者は谷旦、題は「歳旦」。初句「かへる」(返る)は年が改まること、季節が一巡したのである。二句「発鶯」は「初鶯」、二句「音つれて」は「訪れて」、宛字に込めた思いは詮索しない。四句に鶯の賀詞と人の賀詞を重ねた。二首目の作者は馬場柳風、題は「春日移居」。四句「ゐこころ(居心)」は居心地のこと、「よふ」(良う)は「良く」のウ音便である。結句「やうつり(家移り)」は引っ越しをいう。三首目の作者は馬場柳風、題は「麦秋急」。二句「こなせは」は「熟せば」で脱穀しているのである。四句は「赤らみもする」、麦の細長い針のような芒でチクチクするのだ。結句は「身が入りもする」で一生懸命になる。この「身」に麦の「実」を掛けた。四首目の作者は水空居嵋山、題は「古戦場夕立」。初句「実もり」とは斎藤実盛(?~一一八三)である。加賀の篠原で源義仲と戦って戦死、その際に白髪を墨で染めて出陣したという。世阿弥作の謡曲「実盛」で知られていたのであろう。
かささきの橋はめてたしいつまても牛馬無用と書(く)に及はす
一枚にかんはん打(つ)た役者そとこよひの月を三ます大五郎
姥の尻すへる縁座のやうにあのふとく丸なる十五夜の月
偽りはなき世なりけりことわさのさせ干せかさと時雨してけり
一首目の作者は橘中庵玉丹、題は「七夕」。四句「牛馬無用」の「無用」は禁止の意、牛馬を渡らせることはできないのである。時代相が垣間見えて面白い。二首目の作者は仙柳、題は「名月」。上句、一枚看板とは歌舞伎劇場の前に掲げた大きな看板、上部に主な役者の絵姿を示した。結句は三桝大五郎、「三ます」に「見ます」の意を込めた。おそらく初代であろう。中秋の名月に花形役者の来し方を重ねて賛とした。三首目の作者は故月庵指山、題は「姥の月見」。二句「縁座」は「円座」(藁などで渦巻のかたちに円く平らに編んだ敷物)の宛字と思われる。絵になるシーンである。四首目の作者は梢楽斎先賀、題は「時雨傘」。歌は定家の〈偽のなき世なりけり神無月たがまことよりしぐれそめけむ〉(『続後拾遺和歌集』四一五)を転用した。時雨の季節は傘の保存法「差せ干せ傘(からかさ)」の繰り返しなのだ。
|
| 第50回 狂歌今はむかし(2) |
賞翫の七十五日これからは嘸さむかろとおもふはつ雪 先賀
掲出歌の題は「初雪」。成句に「初物七十五日」(初物を食べると寿命が七十五日延びる)がある。初句「賞翫」は初雪を愛でること、これを「初物」に転化して喜ぶ「七十五日」、それを過ぎると寒さばかりが身に凍むだろうというのだ。『新撰狂歌集』にも〈おもしろしとはつ雪なれはほめもしつけふより後に大ふりなせそ〉(「薪などともしき人」作)があった。
あひるのは今しやといへと寒こりの水はかへらぬ昔なりけり
ふりつもる難儀におたのかかしこそかんきを受(け)し雪の裸身
すきはらや吸ものわんをかきさかす此(の)杉箸そ天のさかほこ
天秤に年の大浪打(ち)寄(せ)て鳴(る)おとしけきくれにもあるかな
一首目の作者は白縁斎梅好、題は「冬懐旧」。下句の「水はかへらぬ昔」は「帰らぬ昔」に「覆水盆に返らず」だろう。一茶の〈寒垢離にせなかの竜の披露かな〉(『おらが春』)が思われる。心の龍が立ち上るのだ。二首目の作者は嘯月軒思李鳥、題は「雪中案山子」。〈降り積もる難儀に小田の案山子こそ寒気を受けし雪の裸身〉。「難儀」が「雪」なら上記の通り、「裸身」は「はだかみ」と読んだ。「難儀」を「一大事」とすれば「寒気」が「勘気」、「小田」も小藩等の比喩に見えてくる。三首目の作者は可亮、題は「蛎の吸物をたべるとて」。初句は「空き腹」に「杉原」を掛ける。三句は「掻き捜す」で「掻き」に「蛎」を掛ける。結句「天の逆鉾」は伊弉諾と伊弉冉の二神が国産みに用いた矛、見立てによる縮尺再現である。四首目の作者は可亮、題は「年暮」。初句「天秤」から節季仕舞いで多忙な両替屋を想像した。二句以下は「年波流る」(年が経過して年末となる意)の波を独立させて実景に自然の虚景を添えた。
中のよひ座敷の友とおもふにそなかめあかしてちりりちんちん
白雲かいやひらひらとはねまわるかんひやうたんと曝す軒端は
かさを着て濡(る)るけもなく大雨をにやんの苦ものふ凌くこの猫
のちのみをたすけ給はる誓(ひ)あらはたたいつまてもむかへたまふな
一首目の作者は常楽居士、題はない。以下二首も同様で挿絵に登場する作である。初句は「仲の良い」。新鮮に響いた風鈴も下句「眺め飽かして」となると生気のない「ちりりちんちん」となる。秋も近いのだ。二首目の作者も常楽居士。〈白雲か否ひらひらと跳ね回る干瓢たんと晒す軒端は〉。干瓢はユウガオの果肉を紐のように切って乾燥させた食品、巻き寿司の具などになる。「たんと」は「たくさん」、今まさに軒端の風で「跳ね回る」景なのだ。三首目の作者は嵋山、挿絵には猫が笠から顔と前足を覗かせている。二句「け」は「気」に「毛」であろう。四句の「にやんの」は「何の」に猫の「ニャン(の)」、「のふ」は形容詞「ない」の連用形「なく」のウ音便「のう」である。四首目の作者は森如水、題は「述懐」。〈後の身を助け給はる誓ひあらばただ何時までも迎へ給ふな〉。「誓ひ」は衆生を救おうとする神仏の誓願、ここは阿弥陀仏の本願だろう。初句が「後のみを」に聞こえるが、述懐だから長寿訓でもあろう。
|
| 第51回 興歌河内羽二重(1) |
水の面にうつりにけりな飛鳥川あすかい殿のまりほとな月 九如館鈍永
『興歌河内羽二重』の詠者は九如館鈍永と鈍永社中、撰者は山居、刊記は安永五(一七七六)年だが翻刻本である。序文は明和五(一七六八)年で鈍永の一周忌にあたる。掲出歌の題は「名川月」。三句「飛鳥川」は奈良県中部を流れる川、その「飛鳥」から同音反復で「飛鳥井殿」を呼び出した。結句は「鞠ほどな月」、飛鳥井流は雅経を祖とする蹴鞠の流派であった。
薬筥を弁当にけふ引(き)かへて花の容体見あるく医者殿
ほとときす鳴(き)つるかたや相撲場のにしか東か北かみなみか
七夕の別(れ)はさそなけさはもう待(つ)日の数に入(る)と思へは
雲上な月のこよひの一刻は金つくてないけしき也けり
有難やこよひの空の雲の上のとてお月さまに二つはこさらぬ
一首目の作者は鈍永、題は「医者花見といふことを」。初句「薬筥」は医者が往診のときに持ち歩いた箱、薬籠である。三句は「引(き)換へて」、遊山の弁当箱と往診の薬箱が似ていたのだろう。二首目の作者は鈍永、題は「相撲場時鳥」。「相撲場」は相撲の興行する場所をいう。二句は「方(や)」で方角、「片や」で行司が力士を呼び上げる語となる。相撲は西と東だが、時鳥の鳴く方向は定まらないので結句「北か南か」が追加された。三首目の作者は鈍永、題は「後朝」。牽牛星と織女星が会うのは七月七日、後朝の八日は次の逢瀬まで三百六十五日の振り出しなのだ。二句「さぞな」の次は「辛かろう」等が言い止しになっている。 四首目の作者は鈍永、題は「名月」。初句の「雲上」は形容詞で高貴なように見えるさまをいう。三四句は「春宵一刻値千金」に対して「金尽く」でないことをいう。結句の「けしき」は「気色」(自然界の有様)であり「景色」(趣き)でもあろう。五首目の作者は鈍永、題は「名月」。初句切れで「有難や」。二三句「今宵の空の禁中(のような別世界)の」、四句「とて」は接続助詞で「といっても」以下「お月さまに二つは御座らぬ」で、やっぱり格別な名月なのだ。
あられなら夢や砕かめ存(じ)よらすふりし夜のまの雪の明ほの
おしやなふお袋さまは極楽へ跡は千世もといのりかためて
寝ても夢覚(め)ても夢の世の中は無明の酒の二日酔(ひ)也
一首目の作者は鈍永、題は「雪」。〈霰なら夢や砕かめ存じ寄らず降りし夜の間の雪の曙〉。歌意は「霰なら、その音で寝ている私の夢を砕いたことだろう。夜間に降ろうとは思いつかなかった雪の曙である」。二句は本来は「夢や砕かん」となるべきであった。二首目の作者は鈍永、題は「追善」。初句切れで「惜しやなう」、「なう」(のう)は詠嘆の終助詞である。下句は娑婆世界に遺す係累の幸せを願いつつ極楽浄土へ旅立ったというのである。三句「極楽へ」は言い止し、あとの「旅だった」等が省略されている。三首目の作者は鈍永、題は「夢」。初二句は「寝ても覚めても」(いつも)の変奏、三句の序詞とした。その「世の中」は四句の成句「無明の酒」(俗念を酒にたとえていう語、煩悩)の「二日酔ひ」だというのである。
|
| 第52回 興歌河内羽二重(2) |
小倉山もみちのにしきおりおりにしくれのいとのたてよこにふる 女 雅楽
掲出歌の題は「名所時雨」。初句「小倉山」は京都市右京区嵯峨、保津川を隔てて嵐山と対する山で紅葉の名所、歌枕の地である。二句「錦」は一に「美しいもの」の意で「紅葉の錦」、二に「織物」の意を掛ける。三句は「折々」に「織り織り」を掛ける。四句「糸」は筋のように見える雨と織物に使う糸の両意とした。結句が視覚に訴える。着想は『古今和歌集』の〈龍田川錦織りかく神無月しぐれの雨をたてぬきにして〉(三一四、読人しらず)に通う。
おしやなふお袋さまは極楽へ跡は千世もといのりかためて
寿はちよにや千代にそりや偽しや有様無事て百五十年
風鈴のねのこくなれはあつき夜に身もひいやりとすす虫松むし
蓮の葉に乗(つ)てこさると聞(く)からはゆふへの露の玉祭かも
一首目の作者は鈍永、題は「追善」。初句は「惜しやなう」、「なう」(のう)は詠嘆の終助詞。下句は娑婆世界に遺す係累の幸せを願いつつ極楽浄土へ旅立ったというのである。二首目の作者は鈍永、題は「祝」。初句「寿(ことぶき)は」、三句は「そりや偽しや」で「そりや(そりゃ)」は「それは」の音変化、「偽」は当て字と解して「偽(うそ)じゃ」と読む。詠作時期は不明だが『興歌河内羽二重』の出版は明和五(一七六八)年だから結句「百五十年」は慶長八(一六〇三)年に成立した江戸幕府以後となる。三首目の作者は隣山、題は「深更風鈴」。二句「ねのこく」は「子の刻」(午前零時頃)に「音の濃く」だろう。結句「すず虫」に「涼む」が隠れる。もしくは上から「身もひいやりとする虫松むし」が重なっているだろう。四首目の作者は雅楽、題は「魂祭」。上句は見立てとしての蓮の台をいう。下句は美称「露の玉」と「玉祭」が「玉」を共有する。「玉」と「魂」は同語源と見る説がある。
淋しさをはしめてしりぬ盆もすきおとりやんたる秋の夕くれ
くとけともみふ狂言の物いわすさりとはむこいしかたはつかり
世は情(け)ありさうな君と跡や先になつてこかるる旅の道つれ
世々にふれと気色は今もわかの浦浪より外によるしわもなし
一首目の作者は志染、題は「秋夕」。二句の「初めて」とは二句以下を経過しての感想をいう。「やんだる」は「止む」の連用形に「たり」が付いて撥音便の「止んだり」その連体形だろう。二首目の作者は山居、題の「壬生狂言」は壬生寺(京都市中京区)の大念仏会で行う仮面劇をいう。終始無言である。四句「然りとは」(なんとまあ)「酷い」、結句は「仕方ばっかり」で「仕方」は「仕打ち」、これに「身ぶりや手真似」の意を掛けた。三首目の作者は琶水(女性)、題は「旅恋」。成句「旅は道連れ世は情け」を脚色して「情け」を「他人をいたわる心」から「恋愛の情」に置き換えた。四首目の作者は永賀、題の「和歌浦」は和歌山市南部の海岸、歌枕である。初句は「世々(よよ)を古れど」、二句「気色(けしき)」は光景、また顔などに表れた内面の様子をいう。擬人法、下句の比喩が巧みというほかない。
|
| 第53回 狂謌いそちとり(1) |
霧の海そことも見えすさはさはと尾花浪よる音ばかりして 松柏亭枝月
『狂謌いそちとり』は白縁斎梅好編、序文は安永五(一七七六)年、貞柳五十回忌追善集である。掲出歌の題は「霧海薄」。海に薄原が迫っている地形、断崖も考えられる。初二句は霧が深くて、四方どこがどこだか見極めがつかないさまである。視界ゼロなのだ。しかし聴覚には薄の原を渡ってくる風が「さはさはと」、まるで寄せ波の音のように止まないのである。
なきあかれふずくるやうなほとときすあたぼこしもない月ぞ残れる
からくりのつもりものそや久かたの天から天からふれるしら雪
山崎やおとこ山にも近けれははちまんくうくう鳩のこゑする
ひはの音に平家の昔ひきだせばなみだのほろんほろんとぞなる
一首目の作者は望雪斎和水、題は「馬上聞時鳥」。〈鳴き上がれ文作るやうな時鳥あたぼこしもない月ぞ残れる〉。歌意は「声を高く上げて鳴け。誑かすような時鳥の声の方を見やれば、ただ有明の空に忌々しい月が残るばかりなのだ」。四句は馬方詞である。二首目の作者も和水、題は「雪の日の詠」。〈絡繰りの作り物ぞや久方の天から天から降れる白雪〉。初二句は受注生産された絡繰りの意に解した。三句以下は、これぞ雪の日、そんな降り方を見せてくれるのだ。三首目の作者は和水、題は「山崎屋といへる家居の飼(ふ)鳩を」。初句の「や」は「屋」に詠嘆の「や」を重ねた。以下、「男山」(京都府八幡市)頂上に石清水八幡宮があり、鳩は八幡の神使である。四句は「八幡宮」と鳩の鳴き声との合体である。四首目の作者は休閑亭春慮、題は「琵琶」。三句は昔の話を「引き出せば」に琵琶を「弾き出せば」、結句の「なる」は「生る」に「鳴る」を掛け、「ぼろんぼろん」のオノマトペも涙と音の双方に使われている。
明(け)そめて鶯はまだ聞(か)ねども御慶ぞ人の初音なるらん
くもるとは哥にうたへどすずか山おもひのほかに月はてるてる
年月をうつらうつらとふけゆけばはやたらちめのちちくはいきかな
よしあしの世のうきふしもさはりなしなにはともあれ風になびかん
一首目の作者は舎楽斎、題は「元日」。初句は夜と同時に新年が「明けそめて」である。四句「御慶」は新年の挨拶だが鶯の鳴き声「ケキョ」を彷彿とさせる。下句「人の初声」の由縁でもある。二首目の作者は舎楽斎、題は「照月山」。初二句は鈴鹿馬子唄の「坂は照る照る/峠は曇る/あいの土山雨が降る」に拠る。鈴鹿峠は曇ると思っていたら月が思いのほかに明るいというのである。三首目の作者も舎楽斎、題は「亡母七回忌」。〈年月をうつらうつらと更けゆけばはや垂乳女の七回忌かな〉。二句に「鶉鶉」を重ねた。四句「垂乳女」は生母、結句「七回忌」に鶉の鳴く声「ちちかい」を重ねた。四首目の作者は舎楽斎、題は「愚拙杖とたのみぬる人と老後を居せよとて一宇を柱立(て)し侍るに」。「愚拙」(私)が家を建てる、その柱立てを自祝する歌と解した。〈善し悪しの世の憂き節も障りなし何はともあれ風に靡かん〉。初句「ヨシアシ」、四句「なには」に「浪花」、結句も風に難波の葦が揺らめくさまに見える。
|
| 第53回 狂謌いそちとり(1) |
霧の海そことも見えすさはさはと尾花浪よる音ばかりして 松柏亭枝月
『狂謌いそちとり』は白縁斎梅好編、序文は安永五(一七七六)年、貞柳五十回忌追善集である。掲出歌の題は「霧海薄」。海に薄原が迫っている地形、断崖も考えられる。初二句は霧が深くて、四方どこがどこだか見極めがつかないさまである。視界ゼロなのだ。しかし聴覚には薄の原を渡ってくる風が「さはさはと」、まるで寄せ波の音のように止まないのである。
なきあかれふずくるやうなほとときすあたぼこしもない月ぞ残れる
からくりのつもりものそや久かたの天から天からふれるしら雪
山崎やおとこ山にも近けれははちまんくうくう鳩のこゑする
ひはの音に平家の昔ひきだせばなみだのほろんほろんとぞなる
一首目の作者は望雪斎和水、題は「馬上聞時鳥」。〈鳴き上がれ文作るやうな時鳥あたぼこしもない月ぞ残れる〉。歌意は「声を高く上げて鳴け。誑かすような時鳥の声の方を見やれば、ただ有明の空に忌々しい月が残るばかりなのだ」。四句は馬方詞である。二首目の作者も和水、題は「雪の日の詠」。〈絡繰りの作り物ぞや久方の天から天から降れる白雪〉。初二句は受注生産された絡繰りの意に解した。三句以下は、これぞ雪の日、そんな降り方を見せてくれるのだ。三首目の作者は和水、題は「山崎屋といへる家居の飼(ふ)鳩を」。初句の「や」は「屋」に詠嘆の「や」を重ねた。以下、「男山」(京都府八幡市)頂上に石清水八幡宮があり、鳩は八幡の神使である。四句は「八幡宮」と鳩の鳴き声との合体である。四首目の作者は休閑亭春慮、題は「琵琶」。三句は昔の話を「引き出せば」に琵琶を「弾き出せば」、結句の「なる」は「生る」に「鳴る」を掛け、「ぼろんぼろん」のオノマトペも涙と音の双方に使われている。
明(け)そめて鶯はまだ聞(か)ねども御慶ぞ人の初音なるらん
くもるとは哥にうたへどすずか山おもひのほかに月はてるてる
年月をうつらうつらとふけゆけばはやたらちめのちちくはいきかな
よしあしの世のうきふしもさはりなしなにはともあれ風になびかん
一首目の作者は舎楽斎、題は「元日」。初句は夜と同時に新年が「明けそめて」である。四句「御慶」は新年の挨拶だが鶯の鳴き声「ケキョ」を彷彿とさせる。下句「人の初声」の由縁でもある。二首目の作者は舎楽斎、題は「照月山」。初二句は鈴鹿馬子唄の「坂は照る照る/峠は曇る/あいの土山雨が降る」に拠る。鈴鹿峠は曇ると思っていたら月が思いのほかに明るいというのである。三首目の作者も舎楽斎、題は「亡母七回忌」。〈年月をうつらうつらと更けゆけばはや垂乳女の七回忌かな〉。二句に「鶉鶉」を重ねた。四句「垂乳女」は生母、結句「七回忌」に鶉の鳴く声「ちちかい」を重ねた。四首目の作者は舎楽斎、題は「愚拙杖とたのみぬる人と老後を居せよとて一宇を柱立(て)し侍るに」。「愚拙」(私)が家を建てる、その柱立てを自祝する歌と解した。〈善し悪しの世の憂き節も障りなし何はともあれ風に靡かん〉。初句「ヨシアシ」、四句「なには」に「浪花」、結句も風に難波の葦が揺らめくさまに見える。
|
| 第54回 狂謌いそちとり(2) |
道風の筆にもまけじおとらじと濱のまさごのふるひ書(き)かな 白縁斎梅好
掲出歌の題は「市中にて砂をふるひ書画をさまさまに書(く)を」。「砂絵」は「砂を手に握り、少しずつ地面にこぼしながら描いた絵。(略)。江戸時代、大道芸人が白砂や五色の砂を使ってした見せもの」(『日本国語大辞典』)とある。現在は姿を消した砂絵師を取り囲む庶民が見えるようだ。初句「道風」は和風書体の創始者、小野道風(八九四~九六六)である。
此(の)ころは日毎にちはやふるしぐれ天てらします神のるすとて
馬奴哥もあはれにくれて行(く)秋や木幡のさとにとめてとまらぬ
蒸(し)たての芋をはだへに冬の夜もさむしろならてつつむ琉球
うつすりと春の寒さは山里やまたとどこほるかけとひの水
一首目の作者は松柏亭枝月、題は「時雨」。二三句は「千早振る」の「振る」に「降る」を重ねて「神」ならぬ「時雨」に接いだ。四句は「天に輝いておられる」その神さまが留守(神無月)だから天気は望むべくもないというのだ。二首目の作者は一葦庵湖月、題は「里暮秋」。初句は「馬子唄」と読んだ。木幡は京都府宇治市の地名、古くから交通の要衝また歌枕の地であった。日暮れに連れて唄声も「暮れて行く」これに「行く秋」を重ねて詠嘆の「や」、今度はズームアウトして全景を捉えた。三首目の作者は無楊軒賈好、題は「四季雑」。歌材は蒸かし芋。二句は「芋を肌に」で三四句を挟んで結句「つつむ」となる。四句は「狭筵ならで」、狭筵は短い筵、また「寒し」を隠す。再び結句だが「琉球」は「琉球芋」(薩摩芋)の略である。四首目の作者は近山、題は「餘寒」。初句「うっすり」は「うっすら」のこと、四句「まだ滞る」に「凍る」が隠れる。結句「掛渡井」は川の上を横断してかける樋をいう。春まだ浅い山里の景である。
時鳥やすらふかたもしら雲のいつこに腰をかけた一こゑ
心あてにおらはやおらん師走はたたてよりぬきのいとせはしなや
うき橋にあらぬ四条の水の面祗園会のかけうつすさかほこ
久かたの天津空豆かみわればにほひとともにかかるはかすみ
一首目の作者は蒼々斎李朝、題は「郭公」。二句「休らう」は声が聞こえない。これと下句が対応している。三句の「白(雲)」にその「方」(方向)を「知ら(ない)」を重ねた。結句の「かけた」は時鳥の異名「かけたか鳥」を呼び起こす。二首目の作者は花月堂素石、題は「師走機」。〈心当てに織らぱや織らん師走機経より緯のいと忙しなや〉。初句は当て推量、四句は織物の幅に並べた縦糸の間を繰り返し横糸を通すのである。結句は「いと」(全く)に「糸」を掛けた。三首目の作者は雪縁斎一好、題は「祇園会」。この頃は本橋がなく、神幸のときは仮橋を渡した。浮橋だが初句の「浮橋」は記紀に出てくる「天の浮橋」をいう。曳行する山鉾が水面に映って逆鉾(天の瓊矛)だという見立てである。四首目の作者は白縁斎梅好、題は「有(る)方にて茶菓子に空豆の出(で)しに」。初句「久方の」は「天」に掛かる枕詞、「天津空」までは正統だが「豆」を付けて脱線した。結句「歯がすみ」(歯滓)に「霞」を掛ける。
|
| 第55回 狂歌ならひの岡(1) |
わひことをいふたきのふは小声にて今朝ものまうの調子高さよ 岫雲亭華産
『狂歌ならひの岡』の撰者は仙果亭嘉栗(一七四七~一七九九)、刊記は安永六(一七七七)年である。嘉栗の本名は三井高業、三井の南家第四代の当主、浄瑠璃作者としては紀上太郎を使う。掲出歌の題は「とし立(つ)日」。二句の「昨日」は節季仕舞い、掛け売買の決算期である。「わびごとを言うた」だから金の工面ができなかったのだろう。作中主体は掛け取りと読む。どのようにして切り抜けたのか、年が明けると「物申」と声にも張りがあるのだ。
ほんのりとあかり障子へみつのとのみの紙しろくはるはきにけり
山々のふつと吹(き)出す春風にもらひ笑ひや梅のくちひる
初夢に見たと祝ひをするかなるあとはいはぬかよい事しやけな
豊としのしるしとふれるなそなそのつゐとけ安き春の淡ゆき
一首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「癸巳のとし」。初二句は「ほんのりと明かり」(動詞「明る」の連用形)と名詞の「明かり障子」が三音を共有する。三四句は「癸巳(みずのとみ)」に「の」を挿入して「巳」に「美(濃紙)」を重ねた。「白く」は障子紙の色と、夜が白み始めたの両意を掛けた。名歌の趣きである。二首目の作者は栗柯亭木端、題は「初春」。成句「山笑う」を背景として二句「ふっと吹き出す」、これを縁語の「春風」が受けて四句「もらひ笑ひ」で感動と詠嘆の「や」となる。ちなみに蕾が開くのも「笑う」である。結句「唇」は花片をいう。三首目の作者は嘉栗、題は「初夢有吉慶」。三句は祝いを「為る(がなる)」に「駿河なる(国の諺)」を掛けた。四五句は「後(つまり「一富士二鷹三茄子」のどれか)は言はぬがよいことじゃげな」、言わぬが花というのであろう。「げな」は「げなり」の音変化である。四首目の作者は條果亭栗標、題は「睦月はしめつかた雪のふりけるに」。『万葉集』に〈新しき年の初めに豊の稔(とし)しるすとならし雪の降れるは〉(三九二五)がある。「謎々」の答だが、下句の「つい溶けやすき」(「つい解けやすき」を掛けた)の展開が意想外で美しい。
千金の直打(ち)はあるそ春霞たち入(り)ましたことしやけれとも
のまねとも子(の)日のけふの酒ならは一くちひこか千代のためしに
和中散商ふからは梅の木のありとやここに鶯のなく
一首目の作者は嘉栗、題は「霞」。上句は「春宵一刻値千金」というが春霞も価千金だという。しかしそれ以上は下句「部外者が入り込むことではないけれども」と上品に躱した。四句は「立ち入る」の連用形に「ます」の連用形に「た」の連体形で今の言葉そのものだ。二首目の作者は好果亭栗埜、題は「子日汲酒」。〈飲まねども子の日の今日の酒ならば一口ひこか千代の例に〉。本歌は〈子日する野べに小松のなかりせば千世のためしになにをひかまし〉(『拾遺和歌集』二三)である。小松を「ひく」で酒も「ひこか」(いこか)である。三首目の作者は華産、題は「薬舗鴬」。和中散の本家は「近江国栗太郡梅木村」、ここから「商ふからは梅の木のありとや」となる。「とや」は反語で、そうではないが鴬が鳴いているというのだ。
|
| 第56回 狂歌ならひの岡(2) |
須磨の浦や汐かまさくら咲(き)にけり松風さんもよきてふかんせ 豊果亭漁産
掲出歌の題は「塩竈桜」。サトザクラの園芸品種である。結句「避きて」は「避けて」に同じ、「吹かんせ」の「んせ」は助動詞「んす」の命令形で尊敬の意を表す。吹いてもらいたい、といったところか。四句の「松風」は謡曲「松風」に登場する海女の名に因む。妹の村雨と共に在原行平に愛される、その舞台が須磨なのだ。文語と口語の混交は過渡期の体を表す。
はけしさは雪もちらちらふる年に瓜をふたつの二月中旬
幕串のあとはそのまま取(り)なから夕暮淋し花のこのもと
住吉のかみか絹かはしらねともよほと遠さとをのみゆるいか
山寺の春の夕くれ見渡せは只しら雲の中てかねつく
一首目の作者は華産、題は「如月未暖」(二月「未だ暖かからず」)。四句「瓜を二つ」は二つに割った瓜のように似ていること。つまり結句の「二」は「似」で、「二」を導くための序詞なのだ。二首目の作者は嘉栗、題は「夕花」。初句「幕串」は幕を張るために立てる細い柱をいう。イベントの終了後、幕も幕串を片づけられて桜の花と杭の穴が残ったというのである。墓碑では三句が「有ながら」(『日本古典文学大辞典』)らしい。断然「有りながら」だろう。三首目の作者は燕果亭千樹、題は「遠村紙鳶」。二句は「紙」に「神」を掛け、下句「遠さと尾の見ゆる紙鳶」中「遠さと尾の」に歌枕「遠里小野」(現在の住吉区から堺市の古称)を掛けた。住吉から遠く離れた在所の意である。四首目の作者は宣果亭朝省、題は「春眺望」。二句の平仮名表記「ぐれ」は暮色を避けたかった。下句は「ただ白雲の(ような桜の)中」を強調するために結句の具体像を平仮名表記で後退させた。桜以外は「しら」ないのである。
汐干潟うら吹(き)かへす春の風おまへのさきに貝や見ゆらん
ほとときすそれや鳴(い)たそと出て見れはまけにそへたる有明の月
かなつちをうちさしものや時鳥釘よりさきにきいたうれしさ
ところてんうり行(く)声に夢さめて蚊帳からあたまぬつとつき出す
一首目の作者は漁産、題は「相知(り)ける女と弥生三日住吉に詣で侍りけるに風いたく吹(き)ければ」。二句「浦」に着物の「裏」を掛けた。下句は①「住吉大社の御前の崎に潮干狩りの貝」、②「お前(女)の先からは女陰という貝」が見えるだろう、の意となる。二首目の作者は栗柯亭、題はない。四句「負けに添へたる」は「おまけ」、あと一声の代わりである。本歌は〈郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる〉(『千載和歌集』一六一)である。三首目の作者は木聖軒樊圃、題は「職人聞時鳥」。二句は金槌を「打ち止す」で打ちかけて、あとを中止する。その連用形に「物」が付いた複合語で「打ち止し物」(それだけの価値のあるもの、の意を表す)、なにしろ金槌を振り下ろす前に時鳥を聞いたのである。四首目の作者は森果亭甘栗、題は「夏晏起」(「晏起」は朝寝)。行商人の売り声に寝過ぎたことを知って蚊帳から頭を出した体である。それが心太突きの棒のようでもあり、押し出される側のようでもあった。
|
| 第57回 狂歌ならひの岡(3) |
うつし植(ゑ)し菊掘(り)かへすうころもちけしきの外の秋の悲しさ 秀果亭栗岑
掲出歌の題は「秋動物」。三句「うごろもち」(「うころもち」とも)はモグラの別名である。今ではゲームセンターの土竜叩きでお目にかかるしかないが、ここでは現役で人間と共存しているのである。四句「外」は「ほか」と読みたい。秋の景色はもの悲しい。しかし土竜によって趣味の菊作りができなくなった落胆は景色と異質だが深い悲しみだというのである。
軒くちて落(ち)し瓦の鬼の目になみたのやうな露そこほるる
涼しさはひいやりひやり笛竹のよこ堀にふく秋の川かせ
秋風になひくきりこのふさもまたをとろをとろとみたれみたるる
世(の)中はなんのへちまとおもへともふらりとなつてくらされもせす
一首目の作者は朝省、題は「廃宅露」。初句「軒朽ちて」に「軒口」を重ねた。鬼瓦は棟の端に飾る瓦、それが地面に転がっているのである。「鬼の目にも涙」ではないが、瓦の露に廃屋の涙を見ているのだ。二首目の作者は栗岑、題は「秋風」。構造は「涼しさは(二三句)横堀に吹く秋の川風」だろう。「笛竹」は竹製の横笛、二句は冷たさを感じるさまに笛竹の音色を重ねた。二三句が下句「よこ」の序詞として働く。「横堀」は土佐堀川と道頓堀川を結ぶ運河である。三首目の作者は華産、題は「秋風」。二句「きりこ」(切り子灯籠)は隅切形の四方に造花や細かく切った紙や絹布などの飾りを下げた灯籠で盂蘭盆会に用いられた。その房が風に揺れるさまが下句で「踊ろ踊ろと乱れ乱れる」風情なのだ。四首目の作者は栗柯亭、題は「秋風」。二句「糸瓜」は詰まらないものの喩えでもある。世の中って全く面白くない。そうは思っても糸瓜野郎(ぶらぶらと何もしないでいる男)でいられるわけもないのである。
名に高き今宵の月のくもりては明石も須磨もたたの浦なり
汲み流しまたくみなかし水車のつるへにうつる月そつきせし
山守もけふはなゆるせ松茸のかさかとりたい雨もあかれは
色深き舞子の浜の紅葉はに松の太夫も照れる斗(ばかり)そ
一首目の作者は朝省、題は「八月十五夜のつきのくもりけれは」。明石も須磨も景勝地、月の名所である。それが曇っては普通の浜辺だというのである。「明石」に「明(るい)」、「須磨」に「清ま(す)」の名月が掛かる。二首目の作者は栗柯亭、題は「月移水車」。四句「釣瓶」は水車の水桶である。水流によって揚水し、それによって水車が回る。一つや二つでないから月影も移っていくというのだ。結句「じ」は打ち消しの推量で「尽きないだろう」。三首目の作者は華産、題は「雨後茸狩」。「山守」は山番のこと、山守に山盛りを掛けた。同様に四句「かさ」は松茸の笠に雨の日にかぶる笠を掛けた。雨が止んだら笠を取るのは理に叶ったことでもある。四首目は発果亭庭栗、題は「海辺紅葉」。実景としては紅葉に映える松だろう。虚景は「色深き舞子の(浜の)紅葉(はは)」と擬人化した。「は」を組み込むと「紅葉葉」だが松の異称「太夫(たいふ)」(五位以上り官位の呼称)も照れるばかりという脚色となった。
|
| 第58回 狂歌ならひの岡(4) |
まつ人に似たあし音もゆきすきて違ふ雪踏のかね音そうき 樵果亭栗圃
掲出歌の題は「待恋」。四句の「雪踏(せった)」は竹皮草履の裏に革をはったもので、考案者は千利休といわれているらしい。丈夫で湿気が通らない。加えて元禄(一六八八~一七〇四)の頃から踵に尻鉄(しりかね)を打つのが流行する。結句「鉄音ぞ憂き」の雪踏である。続く足音は冷たい「鉄音」ばかり、それでも「あの人」を待つ。聴覚に特化した恋歌である。
山寺につく身はさそな寝所て聞(く)さへ寒き暁のかね
思ふまい思ふまいそとおもふほといととおもひに思ひかさなる
夕されは里の賑ひおもはれてうちのかかめに秋かせそふく
世話のたねよくもはなるるうれしさよ何をあんすのこともなきみは
一首目の作者は岸果亭東栗、題は「冬暁」。二句は鐘を「突く身はさぞな」で言い止した。「さぞな」は「さぞかし」「きっと」寒いだろう、となる。三句は「ねどころで」と五音で読みたい。対照的な二人である。二首目の作者は栗翠、題は「百首歌よみ侍りし中に思恋といふ心を」。これを純情歌篇とすると、訳あり歌篇に〈思ふ人おもはぬ人の思ふ人おもはざらなん思ひしるべく〉(『後撰和歌集』五七一)がある。三首目の作者は嘉栗、題は「小倉色紙百首本歌とりよみし中に」。二句の「里」は遊里のこと、着飾った廓の女を思うと「内の嚊め」、嚊こそ迷惑な飽き風である。本歌は〈夕されば門田の稲葉おとづれて葦のまろ屋に秋風ぞ吹く〉。四首目の作者は樊圃、題は「寄果述懐」。〈世話の種 欲も離るる嬉しさよ何を案ずのこともなき身は〉。初句の「世話」は手がかかって苦労する、「種」は因果の「因」で題の「果」(「果物」と因果の「果」)に対応している。四句の「案ず」に「杏子」、結句の「身」に「実」を掛けた。
買(ひ)に行(く)ほとはとうふの壱丁も二丁も匂ふあふらあけなり
我(が)見ても久しくなりぬ住よしの茶屋の婆さまはいくつなるらん
てんほうやすすのしのやに秋ふけてけふり淋しき深草の里
心にはまかせぬものよとにかくに人間万事さいの出たらめ
一首目の作者は翫果亭斗栗、題は「油揚遠ク薫ル」。〈買ひに行く程はとうふの壱丁も二丁も匂ふ油揚げなり〉。二句「程」は道のりと豆腐の分量の意、次は「遠(ふ)」に「豆腐」である。一丁(町)は約一〇九米、また助数詞の「丁」でもある。二首目の作者は漁産、題は「住吉の茶店にてよめる」。初二句で「私」が最初に見た頃から「婆さま」だったが、いったい幾つなのだと化け物扱いである。気の毒な話だが茶店には「婆さま」がよく似合う。三首目の作者は嘉栗、題は「伏見街道にて」。初句「転蓬」(風に転がるヨモギ)は旅人や漂泊する身の上に喩える。二句は「篠の篠屋」(すず竹など細い竹で葺いた家)、四句は「煙」に「気振り」(気配)だろう。街道沿いの嘱目詠だが初句「や」の詠嘆が響く。四首目の作者は嘉栗で「題しらす」。「とかくに人の世は住みにくい」は漱石の『草枕』だが、下句の成句「人間万事塞翁が馬」(人生の禍福は測できない)を「賽の目」ならぬ「賽の出鱈目」に置き換えて出色である。
|
| 第59回 狂歌落穂集 |
ひえるはず石の地蔵も綿ぼうし召(さ)れてしのくけふの初雪 無為楽
『狂歌落穂集』の詠者は無為楽、跋文は安永六(一七七七)年。しかし作者像は未詳で「解説」にも東都の人「無為楽が何らかの理由で京都に滞在していた」と推測の域を超えない。掲出歌の題は「初雪」。初句切れで一首は始まる。矛盾するが三句は雪の「綿帽子召されてしのぐけふの初雪」である。うっすらとした綿帽子、だから初句「冷えるはず」となった。
一ィ二ゥ三ィ四めいりまへの振袖のちぎれる程に手まりをぞつく
春の日は龍宮界にさも似たりいかやたこらが空をおよげば
白雨にしりまくられて姉(あね)さんのぬれさんしたかかみなりがする
だだいふて声をはかりとあいた口餅くはされてなきやみし児
一首目の題は「手まり」。初二句「ひいふうみいよ」の同音「よ」で「嫁入り前」を引き寄せた。三句「振袖」は未婚女性の礼装用の長着である。四句から無邪気な御転婆ぶりが目に見える。二首目の題は「紙鳶(いか)のぼりの多く上(が)りたるを見て」。三句から南京玉簾を連想するが作者は関知しない。「紙鳶(いか)」は凧のことで海の「烏賊」や「蛸」と同音、足の本数は少ないが、格好にも似たところがあって「龍宮界」となった。三首目の題は「祗園祭礼俄(にわか)に夕立のしけれは女中みな尻をからげ四条河原を通る体を見て」。初句は「しらさめ」で五音、擬人化して「強い態度」(夕立)と「女性の着物の裾をめくる」の両意を掛けた。逃げるはずである。「さんし」は助動詞「さんす」の連用形、尊敬語である。四首目の題は「あいた口に餅」。初句は「駄々いふて」、二句の「を」は「声だけ、のみ」の強調だろう。そこに餅を放り込んだら効果覿面、泣きやんだのである。「児」は「ちご」と読んだ。
楽しみもかぎりが見へてふらそこのなさけもうすく心ぼそさよ
名も高き大磯ならぬ大坂のせうせうながらとらやまんぢう
国さあで聞(い)たよりかはでかいものてんこちもないがいな仏じや
くはし盆にもちあけて見る大仏はせはひくけれど高い代物
一首目の題は「寄ふらそこの銘酒に」。「ふらそこ」は「ふらすこ」に同じ、首の細く長いガラス製の徳利をいう。減り具合が見えることと、その形状から下句の表現となった。二首目の題は「江戸へ虎屋饅頭を送るとて」。上句の「大磯」は江戸の人ならではの選択だろう。四句は「少々ながら」。結句の「虎屋饅頭」は京都が発祥の地、のちに大阪でも名物となったようである。三首目の題は「関東べい大仏をおがみて」。「関東べい」は話し言葉の文末に「べい」を付けることから関東訛り、またそれを話す人を関西で嘲った語である。初句「さあ」は方向を示す格助詞「さ」(東国語)に長音、二句「かは」は詠嘆を含む疑問である。四句「天骨も無い」は「とんでもない」で結句「がいな」は程度の甚だしいさまをいう。大仏は方広寺の大仏である。四首目の題は「寄大仏餅に」。初句は「菓子盆」、大仏餅は大仏の形を焼き印で押した餅、大仏殿前の餅屋で売り出したのが始めという。背は低いが値段は高いというのだ。
|
| 第60回 狂歌ことはの道(1) |
元日の礼者はかしらさくれとも辞宜のならぬはひとつよるとし 如雲舎紫笛
『狂歌ことはの道』の撰者は紫髯・山丘・如館・紫山・如錐、刊記は安永七(一七七八)年である。掲出歌の題は「試筆」(書き初め)。二句「礼者」は年賀に回る人。句跨りで「頭下ぐれども」。四句「辞宜」の意に「頭を下げて挨拶をすること」と「遠慮すること」がある。賀客としては頭は下げるが結句「一つ寄る年」は遠慮したくともできないというのである。
さる沢の池の前にて能役者きやつきやといふてはやす也けり
目になかめ鼻に香をかき口にほめ耳こそあそへ花の下陰
よしあしを人はいへとも山吹のいはぬ色ほとよいものはなし
いとふへき風はふくともふかすともひといきつつにちる花の春
一首目の作者は山岐、題は「薪能」。猿沢の池は興福寺南門前にある池、薪能は興福寺の修二会の際、大和猿楽四座によって演じられた神事能である。猿沢、猿楽と「猿」と縁の深い舞台である。四句の「きゃっきゃ」は能役者を囃す笛や掛け声、囃子方の見立てと解した。二首目の作者は紫蕾、題は「花」。花見で働かせる必要のないのは聴覚だけだから「耳こそ遊べ」となる。嗅覚は〈をはつせのふもとのいほもかをるらんさくら吹きまく深山おろしに〉(『夫木和歌抄』一四三六二)ほか例歌も多い。三首目の作者は湖雪、題は「山吹」。初二句は難波の「ヨシアシ」を掛けて、話題を転換、三句以下で「山吹」を賞揚した。すなわち四句「言わぬ色」は「口無し」から梔色、山吹色に勝るものはないとする。四首目の作者は紫山、題は「暮春」。四句「一息」は 一呼吸するだけの短い間、「づつ」は積み重ねで「徐々に」の意と解した。時節がくれば花が咲き、時節がくれば散っていく。一片また一片といったところか。
早乙女は腰をかかめて植(ゑ)にけりほさちの苗を大切にして
あつきよをしのひ兼(ね)つつ立(ち)いてて團片手にあをき見る月
夏の夜にかほとなんきなものはなし蚊もなんきなとおもふ蚊遣火
蚊やのうち出るといるとのひとへなり蚊に喰(は)れふと喰(は)れまいとも
一首目の作者は一空、題は「早苗」、四句「ぼさち」は「菩薩」で米・米粒の敬称、「さち」は「薩」の呉音である(『江戸語の辞典』)。二句「腰をかがめて」、結句「大切にして」は田植えの姿勢また様子に早苗を尊ぶ心を加えた。二首目の作者は紫山、題は「夏月」。二句は我慢する「忍びかねつつ」に賞美する「偲びかねつつ」の両意が平行して進行する。四句「團」は「うちわ(団扇)」と読んだ。結句は「仰ぎ(見る)」に「煽ぎ」を重ねた。三首目の作者は真叟、題は「蚊遣火」。二句「蚊ほど」に副詞の「斯程」(これほど)を掛ける。人は蚊を難儀と思って蚊遣火を燻らせるが、その蚊遣火を蚊は難儀と思っているだろうというのである。四首目の作者は如館、題は「蚊帳」。二句「いる」は「居る」に「入る」を掛ける。三句はこれを受けて蚊帳一重を隔てた違いをいう。四句の「喰(は)れふ」は「喰はれる」の未然形に仮想の助動詞「よう」が付く形だが音変化して「喰はれう」、発音は「くわりょう」だろう。
|
| 第61回 狂歌ことはの道(2) |
是は祖父是は祖母のときるもののむかし咄になりし虫ほし 先賀
掲出歌の題は「土用干(し)」(衣類等に風を通して虫を払うこと)。初二句から着物が親から子へ、子から孫へと大切に引き継がれていたことがわかる。夏干しはまた家族の絆を確認する場でもあったのだろう。初句「是は祖父」と二句「是は祖母」が対句、下句では「むかしばなしになりしむしぼし」で「し」音が五度使われているのも見逃せない特色であろう。
ぬけからは耳の薬となる蝉の声つきぬけるやうに聞(こ)ゆる
十五夜の空なかむれは照(る)月のましへりもせすまん丸な影
鳰鳥の水にうきうきよろこんて手のまひあしのふみたてもなし
ふれはつもりつもれは白ししら雪のゆきのまことはつめたかりけり
一首目の作者は如錐、題は「蝉」。『和漢薬百科図鑑〔Ⅱ〕』(保育社)で「蝉退(せんたい)」の薬能を見ていくと「大人の失音」(唖でなく聾だろう)がある。句跨りで蝉の「声突き抜けるやうに聞こゆる」は現実の蝉時雨に治癒後の聴覚を重ねた。二首目の作者は晴雨、題は「月」。初二句の素朴な出だしから二句「照る月」への反応が四句の「増し減り」といい、結句の「真ん丸」といい、子供っぽくもあるが、逆にいえば無条件の帰依を物語っているようだ。三首目の作者は花岐、題は「水鳥」。初句「鳰鳥」はカイツブリの別名、二句「浮き浮き」は副詞、また動詞を重ねたオノマトペであろう。その生態は「手の舞ひ脚の踏み立て」もなく水に潜るのを得意とする。四首目の作者は如光、題は「雪」。初二句「降れば積もり積もれば白し」は雪の白さに帰着する。三句「白雪の」、上から「白し白」でウンウン、三句から四句「雪の雪の」で確信すると「真は冷たかりけり」、どんでん返しとはこういうことをいうのだろう。
冬かれは淋しきものとおもへとも又しら雪の花そふりける
うはかうへふりつむ時はよしあしのなにはの事もしら雪のくれ
ふゆかれの淋しさまさる奥山に煙にきはふおののすみかま
なてさすり寵愛するも埋(み)火のつめたうならぬうちて社(こそ)あれ
一首目の作者は隆女、題は「雪」。冬になって草木の葉が枯れた風景を二句「淋しきもの」と一旦引き算をしてみせる。そうすることによってモノトーンの世界に降ってくる雪の美しさが倍加する仕組み「又しら雪の花」なのだ。二首目の作者は我拙、題は「雪」。〈上が上 降り積む時はよしあしの何はの事もしら雪の暮れ〉。降り積む雪でヨシやアシや吉凶の「何はの事」(諸事万端)は知らない、一面の雪の夕暮れなのだ。「何は」に「難波」はいうまでもない。三首目の作者は壷天、題は「炭竈」。初二句「冬枯れの淋しさ勝る」と四五句「煙賑はふ小野の炭竈」が対応している。「煙賑はふ」だから「炭竈」は一つや二つでない。「小野」は京都市左京区八瀬から大原一帯の古称である。四首目の作者は放過、題は「埋(み)火」。〈撫でさすり寵愛するも埋み火の冷たうならぬうちでこそあれ〉。火鉢などの灰にうずめた炭火を火箸でいじっているのであるが、言外に、冷たくなれば容赦なく捨てられる運命を暗示する。
|
| 第62回 狂歌ことはの道(3) |
目の見えぬ鳥もそろそろうこき出しはねつくろひの暁の空 清叟
掲出歌の題は「暁」。「鳥目」を辞書で引くと「鳥の多くは夜目が利かないところから」云々とある。鳥は必ずしも「鳥目」でないようだが、そうした認識が前提にあっての作品であろう。まず思い出されるのが鶏鳴で『神楽歌』にも〈鶏は かけろと鳴きぬなり 起きよ起きよ 我が門に 夜の夫 人もこそ見れ〉とあるが、結句からは樹上を塒とする鳥が思われる。
寒こりや水をあひるもあたまからつめたい事はかつてんて候
千年のよはひをたもつ鶴なれは鼻から下の長いくちはし
出世しやとおもふて鯉の瀧のほりのほつた所か壷てこそあれ
身をすてて人にほとこす大鯨されは七さとうかふなりけり
一首目の作者は山丘、題は「寒垢離」。初句切れである。三句は上から「水を浴びるも頭から」、下へは「頭から冷たい事は」(初めから冷たい事は)となる。結句は「合点で候」、分かっているというのだ。二首目の作者は清叟、題は「鶴」。成句「鶴は千年亀は万年」を「なれば」(それだから)と下句につないだ。論理的に無関係なこと言うまでもないが、下句とりわけ四句の「鼻」が生々しくツルである。三首目の作者は紫山、題は「鯉」。壺の絵「鯉の滝登り」からの奇想だろうか。結句の「こそあれ」が省略しているのは、鯉が龍にならずに、壺の水中に棲んでいることだ。思う壺とは影の声である。四首目の作者は清叟、題は「鯨」。上句は成句「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」の変奏である。下句は宝暦四(一七五四)年の序がある『世間長者容気』(帝国文庫『校訂続気質全集全』)の一節「古より鯨を突当れば七郷うかぶといふ言葉、誰知らぬものなけれども」によって、二句の意味共々、了解されるのだ。
髭なかく腰もかかめと海老は又とんたりはねたり達者也けり
深草といへときれいな焼ものやむさくさとした店付もなし
よき事はまかなすきかな考(へ)てまかなすきかな心かくへし
やつあると名におふ物は猫のちち蜘と蛸との手足なりけり
一首目の作者は春光、題は「海老」。初二句は海老の語源でもある。起承転結でいえば起承である。転は四句「跳んだり跳ねたり」。なにしろ筋肉が凄い(だから美味でもある)。結句(結)は「達者也けり」で賀祝となる。二首目の作者は徹性、題は「深草にて」。深草は京都市伏見区北部の地名、伏見人形は製作地から「深草焼」とも呼ばれたそうである。四句「ふかくさ」ならぬ「むさくさ」は秩序のないさま、結句「店付き」は店構えをいう。地名からくるイメージとの落差を突いた。三首目の作者は真翁、題は「間」。〈良き事は間がな隙がな考へて間がな隙がな心がくべし〉。「間がな隙がな」は「暇さえあれば」「いつでも」「絶えず」(心がけなさい)。意味もさることながらリフレインと語呂が舌にのせて快感なのだ。四首目の作者は竹耳、題は「八」。一から十、百、千、万、億と数に取材した歌が並ぶ、その中で取り合わせの妙で目を引いた。三四句「猫の乳蜘蛛と蛸との」手足だが猫は意想外、出色の選択であった。
|
| 第63回 狂歌藻塩草(1) |
南無阿弥陀いまそうき世のつるきれてみのなるはてはころりへうたむ 揚果亭栗毬
『狂歌藻塩草』の詠者は揚果亭栗毬(瓢箪坊、焙烙庵)、撰者は岫雲亭華産、刊行は天明二(一七八二)年と推察される。掲出歌は辞世である。三句以下は「蔓切れて実(身)のなる果てはころり瓢箪」。「瓢箪」の「箪」は飯を盛る「筺」、「形見」と同音である。栗毬は大阪府枚方市禁野本町にある浄蓮寺の住職であった。安永七(一七七八)年没、六十五歳。華産の序文の書き出し「またやみむ」は藤原俊成の〈またや見ん交野のみ野の桜狩花の雪散る春のあけぼの〉(『新古今和歌集』一一四)に拠る。その「交野」の人であった。風貌を伝えて「頤に払子を植ゑしごとき長髪をふりて」とある。なお『日本国語大辞典』(岩波書店)を始め「楊果亭」としているが、原本がそうにしても「楊」では具合が悪いだろう、栗柯亭の弟子なのだ。
よろこんふ芋やおほねもこきませて雑煮そ春のけしき也ける
雁かとへは石亀といふことわさに坊主も今朝は春めきにけり
七種を寺にはすこしははからん仏の座をもたたくおもへは
人とはぬ遠山里のおもひては都にまたきうくひすの声
一首目の題は「春のはじめの歌の中に」。初句は「喜ぶ」の語呂合わせで「よろ昆布」、二三句は「芋や大根も扱き混ぜて」(「扱き」は接頭語)、結句は「気色」で自然のたたずまいや光景をいう。二首目も同題、三句の「諺」は「雁が飛べば石亀も地団駄」(自分の分際を忘れて、むやみに人真似をしようとすること)。袈裟に身を包んだ僧侶の自戒だが新春を寿ぐ気分は変わらない。三首目の題は「人日」。陰暦正月七日は七種粥を食べる風習があるが、三句「憚らん」、遠慮しようというのである。七草粥に用いる菜を叩き菜と呼ぶ。俎板に載せて「仏の座」を叩くのは差し障りがあるというのである。四首目の題は「鶯をはやくきき侍りて」。三句は「思ひ出は」、四句は「まだき」で、その時期にならない、の意。鶯前線は都に達していない、都から遠い山里だから鶯の棲息に適していることもあったのだろう、その贅沢をいった。
とりもちの霞の網をやふりつつ命めてたくかへるかりかね
北国へ一筆啓上仕る猶もきかんの時を期し候
さかりなる熊谷さくら散り行(く)は南無阿弥陀仏発心かさて
一首目の題は「帰雁」。初句は「取り持ち」(間に立って渡来ならぬ渡去を阻むもの)に「鳥黐」(竿の先に塗って鳥を捕まえる物質)を掛けた。「霞の網」(霞網)は極細の糸で作られた張り網である。三句はその網を破って、また突破して、の両意だろう。二首目も同題。手紙を雁書また故事から「雁の使い」(匈奴の虜囚となった蘇武は漢帝への手紙を雁の足に結びつけて放った)ともいうが、これに擬えた。「一筆啓上仕る」も「猶~の時を期し候」も定型句、四句「帰還」に「帰雁」を掛けた。三首目の題は「落花」。二句「熊谷桜」は熊谷直実の一の谷先陣にちなむ名という。早く咲くが早く散る。これを剃髪に擬えたか。後に直実は法然の弟子になった。文末の「さて」は「私」の発言をその通りだと確認する気持ちを表す。
|
| 第64回 狂歌藻塩草(2) |
朝倉や木の丸殿はともかくも名のりてすきよやよほとときす 揚果亭栗毬
掲出歌の題は「郭公」。初句切れで「朝倉」は福岡県朝倉市。二句「木の丸殿」は斉明天皇の行宮をいい、その西征に皇太子として同行した天智天皇の〈朝倉や木の丸殿にわれをれば名のりをしつつゆくはたが子ぞ〉(『新古今和歌集』一六八七)以来、歌枕としての例歌は多い。その蓄積の上の一首である。四句「過ぎよ」、結句「やよ」(感動詞)が心地良く響く。
桃色に顔もなるてふひなまつりかさなる酒にいやよひのけふ
潮干かたはまくりにしるももの日はをなこわさなる貝あはせかな
春風に芝居太鼓の音すれはうはの空にも人のそはつく
夜目に見て夏の雪かと横手をはてうとうつ木の花の白妙
一首目の題は「三月三日」。〈桃色に顔もなるてふ雛祭り重なる酒に弥生の今日〉。結句の「いやよひ」は陰暦三月の異名、表記は「弥生」で変わらない。これに「いや酔ひ」を掛けた。「いや」(弥)は「たいそう」、白酒を重ねて酔ったのであった。二首目の題は「桃花」。〈潮干潟 蛤に知る桃の日は女子業なる貝合はせかな〉二句の「に知る」は「煮汁」で雛祭りに定番の蛤の吸物、「躙る」で蛤の動くさまを思わせる。四句「女子業」は「女にふさわしい」意としておく。なお蛤には女陰の意味もある。三首目の題は「春の歌の中に」。四句「上の空」には空の上、心が浮きたって落ちつかないさまの両意がある。結句「そはつく」は、そわそわとする。春風に乗って芝居太鼓が聞こえてくるのである。落ち着いていられる方が不思議なのだ。四首目の題は「卯花」(卯木)。夜は月を頼る生活である。四句は上から「横手を丁と打つ(木の)」(我知らずはっしと両手を打ち合わす)、下へは「(てうと)卯木の花の白妙」となる。
手を合(は)せおかむはかりそほとときすほそんかけたとたつた一声
ほとときすまつに長尻くさらしたつくねん坊主空をにらんて
見ても見てもあかぬはよくの深見草富貴なものと人はいふ也
節句前一時しやうふの売(り)ものはよろひ兜に鑓や長刀
一首目の題は「郭公」。〈手を合はせ拝むばかりぞ時鳥ほぞんかけたとたった一声〉。「ほぞんかけたか」は時鳥の鳴き声、「ほぞん」は「本尊」とされる。四句は「本尊かけたと」、「か」を「と」に変更した。いかにも僧侶らしい時鳥詠である。二首目の題は「待郭公」。〈時鳥待つに長尻腐らしたつくねん坊主空を睨んで〉。長い間待ったのに、時鳥の声を聞くことができなかった、がっかりした自画像「つくねん坊主空をにらんで」となった。三首目の題は「牡丹」。〈見ても見ても飽かぬは欲の深見草富貴なものと人はいふなり〉。三句の「欲の」までが「深見草」の序詞だろう。欲の深い「見」は三度目の登場である。牡丹は別名「深見草」また「富貴草」と呼ばれる。四首目の題は「端午のかざりものを売(り)行(く)を見て」。飾り物の兜や鎗、長刀の行商である。したがって二句は「一時勝負」となる。売れるのは初句「節句前」という限られた商戦なのだ。加えて「勝負」に同音の「菖蒲」また「尚武」を掛けた。
|
| 第65回 狂歌藻塩草(3) |
雑喉ひとつかかつたことか川かりの十方にくれてかへるあみふね 揚果亭栗毬
掲出歌は挿絵の一首、題はない。〈雑魚一つ掛かったことか川狩りの十方に暮れて帰る網舟〉。二句の「か」は疑問を呈する。なぜなのか。「川狩り」は川漁。四句は分断されているが「十方暮れ」をいう。大空が暗く曇っていながら雨の降らない天候である。また暦で甲申から癸巳までの十日をいい、この間は万事に凶とされる。空しく網を引き上げて帰る網船なのだ。
おさまれるよはよろひより六月も綿入を着るひえ法師たち
水底をくくりて魚をとりくらふうやつらやともおもはさるかは
たなはたの今宵逢瀬のむつことを踊にまきらすはあやつとせい
朝かほの花の色こそうつりけれ蚊にせふられて長寝せしまに
一首目の題は「水無月にひえい山にのぼりしに法師の布子着しを」。「布子」は木綿の綿入れをいう。信長の焼き討ちにもあった比叡山の僧兵の歴史が二句「鎧」だが、今では夏にも綿入れを着る「冷え(比叡山の「比叡」を掛けた)法師」だというのだ。二首目の題は「鵜の魚をとるを見て」。二句「潜りて」に鵜の首を「括りて」。四句は「憂や辛や」で「辛や」は形容詞「辛し」の語幹に助詞「や」が付いた。「憂」に「鵜」を掛ける。結句「かは」は詠嘆を含んだ疑問、これに「川」を掛けた。三首目の題は「七夕」。踊りは小町踊り、娘の風流踊りである。天界の睦言に対して地界の囃子詞を配した。紛らしているのは何か。ハアヤットセイ、ヤットセイ。溜め息交じりの声が意味深に響く。四首目の題は「秋の朝によめる」。上句は花が萎んだ、もしくはそれに近い状態をいった。四句「せぶられて」の「せぶる」は『大阪ことば事典』に「責めるの転訛」とある。蚊帳に紛れ込んだかして寝られなかったのである。
稲荷山出る月影にはかされて立(ち)て見居て見ふしみかい道
あすしらぬ露の命にありなから菊には罪をつくるものかは
扨もその後の月見は一段とよひから朝まてかたりあかした
めつらしくたれもなかむるはつ雪は昔も今もふるものなから
一首目の題は「街道待月」。三句は「化かされて」、初句の縁語である。下句は「立ちて見居て見伏し(て)見」で伏見街道を出す。場所は京都市伏見区、稲荷山の西麓には稲荷神社の総本社、伏見稲荷大社がある。二首目の題は「菊」。上句は「露の命」(露のように消えやすい命)をいう。一方で「菊の露」(菊にやどる露。これを飲むと長寿を保つとされた)という。菊は儚い命を弄んでいる、罪作りだといっているのだ。三首目の題は「九月十三夜」。初二句は句跨りで「さてもその/あとの月見は」となる。語感から「あとの」と読んだが、八月十五日の名月があって「後(のち)の月」だから九月十三夜なのである。四句「宵」に「良い」を掛けた。四首目の題は「霜月三十日ばかりに」。構造上は二句切れで「珍しく誰も眺むる」と連体止めである。三句以下の「初雪は昔も今も降るものながら」が意味上の始まりだから倒置の関係である。実際は読者の無句切れを誘い、二十日鼠の回し車で、永遠の循環構造に入る。
|
| 第66回 狂歌藻塩草(4) |
くはたひしとあれる鼠に今宵しもあつたら夢をかちりかかれた 揚果亭栗毬
掲出歌の題は「荒鼠妨夢」。「荒れ鼠」は暴れ回る鼠だが、ここでは宝暦年間(一七五一~六三)作の地唄「荒れ鼠」が題材と解したい。鼠の大将が家来に指図して大暴れ、そこに猫が登場するという筋である。初句は「がたぴしと」だろう。四句「あつたら」は「あたら」(残念なことに)の音変化、結句は可能動詞で「囓りかかれた」、安眠を妨害されたのである。
かかもたぬひとり巨燵の気さんしはやくらの足のさはるはかりそ
ことしから貧乏神をすすはきに払ふてとこもふくや雑巾
家家の軒にさすてふ年こしの赤いわしてももとはきれもの
天(の)河に心中をしてしぬるとはふたりの人のほしのわるさよ
一首目は題なし、挿絵と共に登場する。上句、嚊がいても不思議でない独り身である。「気散じ」(気楽)でもあるが、火燵に足を入れても櫓で触れるのは木の足ばかり、「気散じ」(心のわだかまりないこと)とはいかないところも覗くのだ。二首目の題は「煤払」。正月を迎える準備として行っているのだろう。四句は「払うてどこも」、結句の「拭く」に「福」を重ねた。来年からではない。来年の福は今から準備するのである。三首目の題は「赤鰯の払底なるよし商人のいふに」。赤鰯は塩漬け又は干して赤茶けた鰯をいう。節分は初二句のとおりだが、内「さす」は赤鰯の別意「赤く銹びた刀」の縁語である。結句は卸元での払底と、銹びない頃の刀である。四首目の題は「天(の)河にて心中をして死せるとききて」。初句「天(の)河」(天野川、天之川)は歌枕、浄蓮寺のある禁野の地名、また付近を流れる淀川の支流の名前でもある。四句「人の」には男星と女星が意識にある。結句も同様で「星」は運勢をいう。
親の顔見るやふいりの嬉しさは孝行ものと人やまうさう
内心は夜叉のお山をよねといふ外面ほさつの名こそたつらめ
しらなみのよするなきさにめくり来てはくをはかれし我は木仏
世(の)中はくのたえまこそなかりけれらくにもくの字ついてはなれす
一首目の題は「やぶ入(り)を」。正月と盆の宿下がりだが、結句「申さう」に藪の縁で「孟宗」(「孟宗竹」の略)を掛けた。藪入りそのものではない。「私」の「嬉しさ」を人は褒め称えているのである。二首目は挿絵、妓楼の張見世である。「外面似菩薩内心如夜叉」を詠う。二句「お山」は美しい女、三句「よね」は「娼」で遊女、ちなみに「米」で「菩薩」の異称となる。三首目も挿絵だが歌の前に「夜のいたくふけしころなぎさのつつみくりといへる所にて賊に出あひ赤裸にはがれしとき」、歌の後に「かくなん詠じければ賊心をやはらぎ奪ひしものをかへしあたへけるとぞ」とある。「なぎさ」は「渚」、現地名にも残る。初句「白波」は盗賊、「の」が付いて「寄する」の枕詞、四句「はく」は仏の「箔」に人の「帛」を掛ける。四首目の題は「述懐」。二句の「苦」と同音を含む「楽」を四句で導く、あたかも「苦」を伴わない「楽」はないかのようで「述懐」というよりは道歌の趣きである。やはり僧侶なのだ。
|
| 第67回 狂歌軒の松(1) |
木々のみか木のめはる雨ふる下駄も桐のふたつ葉杉のふたつは 園果亭義栗
『狂歌軒の松』の撰者は園果亭義栗、刊記は天明元(一七八一)年である。掲出歌の題は「春雨」。二句は「木の芽張る」、下へ向かって「(木の芽)春雨降る」、三句は「古下駄も」と各々「はる」「ふる」を共有しながらの展開となる。下句の対句は四句「木の芽張る(略)桐の二つ葉」(二つ葉は発芽して最初に出る葉)と結句「古下駄も(略)杉の二つ歯」となる。
冬なから冬ともいはしとしの内にまた春ならぬ春を迎へて
春に入るしるしは今朝そ有馬山かかる霞の幕湯かとみて
軒端なる梅に乞食もうくひすの初音一口賞翫そする
猿猴のさる沢に手もなかなかとのひる蕨は春の月末
一首目の作者は園果亭義栗、題は「ふるとしに春たちける日よみ侍りし」。人の手で体系付けられた時の流れと実際の時の誤差すなわち年内立春に対する率直な戸惑いである。陰暦にあっても理屈と感覚は別だったことがわかる。二首目の作者は庸野亭舞雪、題は「酉のとし」。結句「幕湯」は貴人の入浴の際に他人との混浴を避けるために幕を張ること、またそのような浴場をいう。見立てによって気分だけは貴人となった。三首目の作者は逢里亭紫園、題は「乞食聞鶯」。狂歌には捨て子、妾、泥棒、盲人、後家等々、役者には事欠かない。掲出歌の場合、聴覚を味覚に置き換えたところが乞食の由縁であるが、同じ絵の中で季節の恩恵だけは平等に受けている。四首目の作者は文蘭同祗卜、題は「池辺早蕨」。初二句は「猿猴猿」(「猿猴」に同じ)を「の」で分断して「猿沢」を呼び出した。池ではなく沢なのだ。また猿猴は手長猿をいう。これらを縁語として本命の蕨が登場する。結句「春の月末」は季節の月尻だろう。
巣立(つ)野や雲雀か床も打(ち)しめりあかりかねたる春雨の空
春雨のふるにもあかる夕ひはり空に声さへやむかたそなき
朝たつを宿の桜にとめられて昼中食も此(の)はなのした
瀧つほに地主のさくらの影見へて風には落(ち)ぬ花を散(ら)した
一首目の作者は園果亭義栗、題は「野外春雨」。初句の「や」は並列助詞で「野」と「床」が三句を述部として共有する。四句は上から「雲雀が(略)上がりかねたる、下へは「上がりかねたる春雨の空」となる。二首目の作者も園果亭義栗、題は「雨中雲雀」。見所一として上句では「春雨の降る」と「上がる夕雲雀」の対句表現がある。見所二としては下句の雨ならぬ雲雀の声の「止む方ぞなき」。それぞれに意味を取り違えながら進行するのが巧みである。三首目の作者は文蘭同祗卜、題は「旅店見 花」。「旅店」は宿屋。初句は「朝発つを」、二句から三句は桜の擬人化である。四句「中食(ちゅうじき)」は後の昼食、一日二食の時代であった。結句「花」に「鼻」が掛かる。四首目の作者は逢里亭紫園、題は「瀧辺花」。二句「地主(じしゅ)」は土地の守護神、そこに咲く桜が「地主の桜」である。風で花が散っているのではない。水に映っているのだ。しかし滝壺なので結句「花を散(ら)した」なのだ。
|
| 第68回 狂歌軒の松(2) |
花嫁をむかへた門を祝ふとて石を外からくれの春の日 姫路 孤立
掲出歌の作者は孤立、姫路在住という意味だろう。題は「暮春嫁入」。新郎に水を浴びせる風習に水祝いがあるが、これは石の祝いを詠った。石打ともいうが『江戸語の辞典』(講談社学術文庫)に「婚礼の夜、近隣の者などがその家に小石を投げこんで祝う風習」とある。結句の「くれ」は石を「呉れ(た)」に春の「暮れ」となる。晩春で、夕暮れの意ではない。
汲(む)桶に塩竈さくら影見えて手折(ら)ぬ花もかたけ行(く)蜑人
風ならす共よきてふけ妻乞の猫もさかりの花の木の元
また散らぬ花のなかめに忘れけり我身につらき風のここちも
替え竹輿のあちとこちとへ棒はなも花も嵐に乗(り)て別るる
一首目の作者は園果亭義栗、題は「塩家辺花」。「塩家」は「塩屋」(塩を作る家)だろう。二句は桜も「塩竈桜」(桜の品種)、ポイントは四句「手折らぬ花」となる。結句は「担げ行く蜑人」、「蜑人」は「あま」と読んだ。絵なら桶に映る桜が海女の肩に担がれて行くところである。二首目の作者も義栗、題は「花下猫」。上句は「風ならずとも避きて吹け妻恋の」で猫の恋を詠った。ほんものの風ではないが、それでも物狂おしく鳴く猫の声で散らないか、桜を気遣っているのである。三首目の作者は船越とき女、題は「花下忘病」。初句は「まだ散らぬ」。結句「風」は「風邪」の意で、意図的に「邪」を外したのではない。もちろん桜を散らす「風」を意識する。四首目の作者は義栗、題は「竹輿落花」。宿駅で別の竹輿(「ちくよ」)に乗り換える場面である。三句は「棒鼻」(駕籠を担ぐ棒の先)だから前後に、「花」は花嵐で枝と別れるのである。「鼻」(端)に花を掛け、結句は駕籠との縁で「花」も「乗りて」となった。
散らしたるうらみはあれと花過(き)て風そたよりのなき人もうし
照りもせすとはいへはれの嫁入(り)て朧月夜にしきかねはなし
さて近ふ夏きるものとまち針や袷もくけて置(く)春のすそ
縫あけをおろせと延(ひ)ぬ春のたけふたよはかりの袷仕立(て)る
一首目の作者は園果亭義栗、題は「花後客稀」。風への恨みをいい、また来なくなった客を「憂し」と嘆く。風を人の噂(風の便り)に転じた「私」は花の名所に店を持つらしい。二首目の作者も義栗、題は「春夜嫁入」。本歌は大江千里の〈照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき〉(『新古今和歌集』五五)である。二句の「晴れ」は褻に対する晴れをいう。結句「敷金」は持参金、朧月夜には不要なのだ。三首目の作者は逢里亭紫園、題は「暮春縫袷」。「袷」は裏地を付けて仕立てた着物、近世では初夏に用いた。三句「待ち針」は縫い合わせる布がずれないように刺してとめる針、夏を「待ち」でもある。四句「絎け(る)」は縫い目が表に見えないようにする縫い方で、結句「すそ」は着物と暮春の両意となる。四首目の作者は長橋李投、同題で続く。肩揚げや腰揚げを下ろして成長した子供の袷を縫っているのだが、その丈を延ばすのに二夜を費やしたというのである。「丈」に「闌け」を掛けた。
|
| 第69回 狂歌軒の松(3) |
早苗とる早乙女か手のうらわかみ足は田面の泥にふしたつ 船越とき女
掲出歌の題は「早乙女」。二三句は「早乙女が手のうら若み」、「うら若み」は形容詞「うらわかい」の語幹に接尾語「み」が付いて「若々しくなよやかなので」、下句「足は田面(たづら)の泥に節立つ」となる。田面(たづら)は田の表面、「節立つ」で茎がのびて節があらわれること、この場面だと早乙女の膝小僧だろう。泥の中でもすっくと若々しいのだ。
夕立に木々の青葉もひいやひや名のみはかりはあつ盛の塚
入(り)のなき芝居と替り木戸まても涼む仕うちは是もかとなか
破(れ)團骨折(り)のみて其(の)日をは暮しかねたるあふち貧ほう
打(ち)寄(せ)ていかかせん手とゆふ間暮真(つ)黒に蚊もはんを囲んた
一首目の作者は高岡右契、題は「古塚夕立」。三句の「ひいやひや」は夕立がもたらしたもので下句の「名のみばかりの暑」さとなる。二音を重ねた結句は「敦盛の塚」で「青葉のひいやひや」が敦盛遺愛の笛として木々に響くのだ。二首目の作者は何徳亭義頂、題は「道頓堀納涼」。初句は「客の入りが悪い」、三句「木戸までも」は客席に加えての意、四句はそれを受けた「仕打ち」(振る舞い)となる。結句の「門中」は往来のこと。三首目の作者は含章亭絮風、題は「貧家團」。〈破れうちわ骨折りのみで其の日をば暮しかねたる煽貧乏〉。「煽」(あおち)は「煽つ」の連用形からで「ばたばたすること」、結句は「もがき貧乏」をいう。破れた団扇は風の効率も悪い。四首目の作者は戴月舎社栗、題は「夏碁」(成句「夏碁に炬燵俳諧」)。初句の「打ち/寄せ」は碁の縁語、二句「せん手」に動詞の「せん」と「先」を掛ける。三句は「言ふ」に「夕」、結句は「盤」に「晩」を掛けた、蚊が、先手の黒石の趣きである。
照りつつく日やけさせしと百姓は田毎に出(で)て汗の水かき
いとさまを抱(か)ぬ間とてもなつは猶しほるや汗もおちの人とて
誕生に蚊も餅ついて男かとゆふへわあわあたてる初声
こかれ寄る流れの里て切売(り)にするや西瓜のあけのそほ舟
一首目の作者は谷沢其慶、題は「夏農人」。初句切れで「照り続く」だろう。あとは結句まで「日焼けさせじと百姓は田毎に出でて汗の水掛き」となる。結句は「水掛桶}(みずかきおけ)の略もしくは連用形の中止法であろう。汗しながらの作業なのである。二首目の作者は草魁堂有園、題は「夏乳母」。初句「いとさま(幼様)」は小児をいう敬称。四句「霑る」(しおる)は濡れる意、結句は汗が「落ちの人」、これに乳母の意で「御乳の人」を重ねた。三首目の作者は長橋李投、題は「夏夕安産」。成句に「蚊が餅つく」がある。四句「言ふ」に「夕(べ)」を掛ける。「わあわあ」は騒がしい周囲の様子また群集して上下に移動する蚊柱の羽音、これに赤子の産声を重ねた。四首目の作者は園果亭義栗、題は「華街にて西瓜の切売(り)を見て」。「切売り」には時間を限って肉体を売る女郎の意がある。初句は「漕がれ寄る」、二句「流れの里」は遊里、結句の「朱の赭船」は赤土で塗った船、売られる西瓜の形容でもある。
|
| 第70回 狂歌軒の松(4) |
船となる柳の一葉かい散りて秋の日なみの風に流るる 長橋李投
掲出歌の題は「秋のはしめの心をよめる」。「故事」の註記は「一葉落ちて天下の秋を知る」だろう。柳は春の景物というイメージが強いが落葉樹である。三句は接頭語の「かい」で語勢を強め、また語調を整えた。四句の「日並み」は「日和」また「毎日」の意味もあり、これから深まる秋が思われる。初句は水に落ちて流れていく様を一葉舟、一隻の小舟に喩えた。
夏ははやきのふと誰もしら露の秋に暑さを置くはいかにそ
年ことに一夜をちきる七夕へしはん坊なる柿を手向(け)ん
逢瀬にも閏ふのあらは一とせに二度とは是も稀な七夕
貰(ひ)水この身にかかる手伝(ひ)もしんとに替えるお隣の井戸
一首目の作者は逢里亭紫園、題は「初秋未涼」。「初秋未だ涼しからず」なのだ。夏はすでに昨日のことだとは誰も知らない、白露を置く秋に暑さを置くとはどうしたことなのか、の意となろう。二首目の作者は泉加楽、題は「七夕供果」。四句「吝ん坊」はけちな人。成句に「吝ん坊の柿の種」がある。柿の種も物惜しみする吝嗇家を罵っていう。上句「年毎に一夜を契る七夕」の二星を吝ん坊に見立てて、柿の種ではない、踏ん張って柿を手向けようというのだ。三首目の作者は園果亭義栗、題は「閏七夕」。七月と閏七月のあった年を詠ったのだろう。暦の閏七月なら「あれば」となる。しかし年中行事の七夕は一度だから二句「あらば」の仮定で三句以下の所感に繋がったのだろう。四首目の作者は園果亭義栗、題は「隣井戸替」。井戸替えは井戸の水をくみ出して中を掃除すること、井戸さらえである。四句の「しんと」は「塵土(じんど)」で井戸の塵と土と解した。これに「くたびれる」意の「しんど」を重ねた。
よひよひといへと今宵も四つ橋て踊(り)の声も次へ渡した
消(え)てうきなみたにしめる送り火に灰よせをせし昔をそおもふ
己の役とかかしは弓を引(き)あけの朝露の間も下に置かしな
秋の夜に鹿の命毛かひそある筆のたちとも通ひ習ひて
一首目の作者は草魁堂夏園、題は「橋辺踊」。初句は連日の「宵宵」に踊りの掛け声の「よいよい」だろう。二句の「宵」、三句の「四つ」と同音類音が続く、そのように踊りの声も後ろへ、また明日へ渡したというのだ。二首目の作者は園果亭義栗、題は「送り火を見て」。送り火は盂蘭盆の最終日、親族の霊を送るために門前などで焚く火をいう。上句「消えて憂き涙に湿る」は新仏だろう。その光景から「灰寄せ」(骨上げ)をした昔が甦ったのである。三首目の作者は草魁堂夏園、題は「朝案山子」。初句「己」は「おのれ」と読んだ。三句は「弓を引き上げの」で構えた状態、これに「(引き)明けの」とした。結句「置かじな」の「じ」は打ち消しの推量、「な」は詠嘆。朝の田畑を守る案山子の姿である。四首目の作者は船越とき女、題は「秋夜手習(ひ)」。初句以下「秋の鹿」を重ねる。二句「命毛」は筆の芯になる毛である。次「甲斐ぞある」の三句切れ、四句の「立ち処(たちど)」は筆の「運び」をいう。
|
| 第71回 狂歌軒の松(5) |
隣にも半分は汲む影見えて相合井戸のかたわれの月 園果亭義栗
掲出歌の題は「井月」。二句「半分」は井戸から汲む桶の水に映った「片割れ月」(半分またはそれ以上欠けている月)をいう。これと四句「相合井戸」(近所の者が共同で使う井戸)が対応する景である。水を汲む人の傍らでは食器を洗い、また洗濯をする人もいるだろう。流しにも盥にも、そしてもちろん空にも弓張り月なのだ。名月だけでない月が暗示的である。
ひとりとは誰かゆふへの月を友我(が)影さへも我にさし添ふ
今そ来る花にはいんだ雁かねも秋は越路の月を見捨(て)て
明(け)ぬれと夜るを残して登り舟のほるにくらき淀の朝霧
疱瘡の呪をする此(の)山に赤う出揃ふもみち葉のつら
幾秋をなかく契りてきせ綿の帽子色よき菊の花嫁
一首目の作者は義栗、題は「独見月」。三句の「夕べ」に「言ふ(べ)」で「誰が言ったのか。友である月に加えて私の影の三人連れだというのに」となる。結句の「差し」は整調と強意の接頭語である。二首目の作者は義栗、題は「月前雁」。二句「花には去んだ」、春に北方へ帰ることをいう。下句は逆に飛来して越冬する。冬鳥だが、どちらも当地自慢の季節を顧みない、その雁の飛来を歓迎する気持ちが初句切れとなった。三首日の作者は長宣館延年、題は「舟霧」。時刻でいえば夜は明けたが、まだ暗い、これが初二句だろう。以下「残して」「登り舟」「のぼるに」と「の」の反復が快い。また初二句の句頭「あ」「よ」と結句内の「よ」「あ」の対応も心憎い。四首目の作者は三嚥亭琪園、詞書に「箕面山岩本坊に詣て疱瘡の呪を請ける折から庭の紅葉の今を最中と見えければ」とある。結句の「つら」は葉の表面(面)の意に疱瘡を病む顔の「面」を掛けた。五首目の作者はとき女、題は「菊月に婚礼ありける方へ」。九月八日夜の露を移し取った被せ綿で翌日の重陽の節句に身をなでると長寿を保つといわれた。三句はその菊の「被せ綿」に花嫁の「綿帽子」像を重ねて「美しい菊のような花嫁」と祝した。
昔おもふ木々の葉武者のひをとしも冬きて落(ち)る城跡の風
冬かれの野にふす案山子霜置(き)てとまり定めぬ鳥や朝たつ
ふりつみて鐘の音さむきかん山寺六つの花よりあけかかる空
一首目の作者は逢里亭紫園、題は「冬古戦場」。初句で切れ、二句の「木々」から弱兵「木の葉武者」「葉武者」に飛び、三句は鎧の「緋縅」に紅葉を重ねた。落ち葉と落城、感慨は結句から初句へと循環する。二首目の作者は何徳亭義頂、題は「冬案山子」。上司は「冬枯れの野に寝ているような、倒れた案山子に霜が降りる朝」、四句は「伏す」の縁語「泊まり」を最後に落ちつく所「止まり」に転化して結句の自然が美しい。三首目の作者は延年、題は「冬鐘」。〈降り積みて鐘の音寒き寒山寺六つの花より明けかかる空〉。中国の寺の名に着想を得た。二三句「寒」を重ねて寒さを強調、漢字「山寺」で寺の有り様を示した。四句「(明け)六つ」(午前六時頃)で結句「明けかかる」、「六つの花」(雪)で同じく「開けかかる」となろう。
|
| 第72回 狂歌軒の松(6) |
来る春を的になしてや破魔弓も声一はいにはり詰(め)て売る 戴月舎社栗
掲出歌の題は「としのくれの歌の中に」。三句「破魔弓」は破魔矢を射る弓、正月を祝って男児に贈る玩具である。その的を「春」とした初二句が目を引く。「てや」は終助詞「て」に間投助詞「や」で親しみの気持と軽い感動また軽く念を押す(~よ。~ね)。弓は力一杯に張り詰めて射るが、下句は気持ちで「声一杯に張り詰めて売る」、歳末商戦の声が響く。
橋桁を二三間程弁慶とうたふて膽をひやす寒声
色わかぬ雪のつもりのしら梅は匂ひや手折(る)しるへなるらむ
難波人芦火たく家も煤とれば軒のつままで又めつらなり
ひそり合(ひ)もたせあふたるかたつふりくはきうに折れぬ両方の角
一首目の作者は延年、題は「橋上寒風」。結句の「寒声」は①「『かんごえ』で僧や邦楽を学ぶ人が寒中に声を出してのどを鍛えること、またその声」、②「『かんせい』で寒そうな声」の意となる。下句は①の声が②に変化したところである。三句は謡曲の「橋弁慶」を指す。二首目の作者は義栗、題は「雪のふりける日住よしに詣て庭なるしら梅を折るとてよめる」。上句は雪になったつもりの白梅、擬人法である。下句は手折る「標」(案内)は匂いだけだといっている。四句「や」は詠嘆と感動だろう。三首目の作者は岡田川狭、題は「煤払」。本歌は『万葉集』の〈難波人葦火焚く屋のすしてあれど己が妻こそ常めづらしき〉(二六五一)。煤払い前を煤払い後の歌にした。四句「軒の端」の「端」に「妻」が重なる。四首目の作者は義栗、題は「恋の歌の中に」。初句「干反り合ひ」(互いにすねて)、二句「持たせおうたる」(しかし思わせぶりに気を引いて)、四句は「火急」に「蝸牛」を掛けた。なんとも厄介な恋である。
ふしもよく言葉の花も咲(き)かけてへたつまかきのきくもおもしろ
真黒によりあつまつて口々に声もからすの森のいさかひ
盃をもつてゆるりとはなし亀此(の)御礼にはあかろ二さん度
さかつきの亀の御礼の二度三度それはともあれまあはなさしやれ
一首目の作者は延年、題は「隣音曲」。初句は「節もよく」、下句は「隔つ籬の菊もおもしろ」で「菊」に「聞く」を重ねた。「籬」は竹や柴で目を粗く編んだ垣根をいう。また籬節という小唄もあったというから音曲の縁語としたか。近景に庭の菊、遠景に隣の音曲と開放的である。二首目の作者は延年、題は「社中喧嘩」。「社中」は神社の境内をいう。四句「嗄らす」に「烏」を重ねた。初二句と結句が対応して「らしさ」のある鎮守の森詠となった。 三首目の作者は紫園、題は「琪園丈の許へまかりけるに酒を出し給ふに盃に亀の蒔絵のありけれは」。「丈」は接尾語で敬意を表す。三句は酒を注いで盃が「放し亀」(放生池)となった。下句はその亀の気持ちを代弁し、かつ酒をいただく挨拶とした。四首目の作者は琪園、題は「かくよみたまふを聞(き)て」。遠慮しながら盃を干す客に対して主人曰く「亀の御礼はいいから、もつと放さしゃれ」そして「話さしゃれ」と応じたのだろう。結句の「しゃれ」は助動詞「しゃる」の命令形、尊敬の意を表す。
|
| 第73回 きやうか圓 |
佐保姫のひめはしめより細眉のけしきほのかにかすむ遠山 荒木氏女 幸代
『きやうか圓』の撰者は市中亭吾(山の右に同)、刊記は天明二(一七八二)年とある。掲出歌の題は「山霞」。二句「姫始め」は暦の正月二日のところに記された日柄(ひがら)の名である。種々の事柄をその年に初めて行う日とされる。内容から推して化粧始めと解しておこう。三句の「細眉」は細長い眉、それを遠山の形に転じた。「へ」の字のような稜線が霞んでいるというのである。
打(ち)よりて子の日の跡にひくものはあちやこちやと宝引の綱
山吹も咲く玉川の瀬にむれてのほる小鮎は白かねの色
洛陽の花の頂き色みちて知恩ゐん気はない桜時
包のしつけたは節供の朝比奈の髪のもとゆひ草てさふらふ
一首目の作者は飲月洞杜水、題は「宝引催興」。初二句は正月最初の子の日に引く松、そのあとに引くものは、が三句である。宝引は籤引式の賭博で数本から数十本の綱の一端に当りの印を結んで引かせた。だから下句「彼方や此方やと宝引の綱」なのだ。二首目の作者は福井山人、題は「若鮎多」。玉川は山吹、蛙、卯の花の名所だが鮎も多かったようで『夫木和歌抄』に〈かがり火のかげにぞしるき玉川のあゆふすせにはひかりそひつつ〉(三一七二)とある。鵜川なのだ。三首目の作者は市中亭吾峒、題は「東山花」。初句「洛陽」は平安京の左京の称、二句は知恩院の山号「華頂山」から「華の頂」とした。四句は「院」に「陰」、一七三三年まで火葬場が置かれていたという。四首目の作者は吾峒、題は「端午 進物の粽を見て異名を思ひ」。〈包み熨斗つけたは節供の朝比奈の髪の元結草で候ふ〉。異名とは元結草、また朝比奈粽である。朝比奈は別に朝比奈義秀、鎌倉前期の武将で通称を三郎、これを結句の「さぶらふ」に重ねた。
涼しさに四条河原の仮橋てけふ一日の暑さ戻した
春は花にかへさ忘れし吉野なる葛水て又夏を忘れた
数の子を日本国へせいほにと配つて置(い)て春をまつ前
潮ならぬ酒のみちひの折毎になみの花こそひらくかい辺
一首目の作者は可陽亭紅圓、題は「橋上納涼」。三句の「仮橋」は祇園会の神幸の時に掛けられた。浮橋ともいい橋付近では夕涼みが行われた(天文から安政まで大橋はなかったらしい)。結句が言い得て妙である。二首目の作者は猿毛舎貨童、題は「葛水忘夏」。二句「かへさ」は「帰るさ」が変化した語で帰り道、また帰ることをいう。四句の「葛水」(くずみず)は葛粉と砂糖を湯で溶いて冷やした飲物、吉野葛は上質だった。三首目の作者は志交、題は「歳暮」。二句は「ニッポンこくへ」と読んだ。結句の「まつ」は上から「春を待つ」、下へ「松前」となる。松前が外国のようであるが、北海道は蝦夷地、松前奉行が置かれるのは一八〇七年であった。四首目の作者は吾峒、題は「浪の華てふ貝の盞に狂歌望(ま)れ」。「浪の華」は波の白くあわだつさまを花に喩えた語、二句の「満ち干」は杯を重ねる意を潮の満ち干に擬えた、下句は「波の花こそ開く海辺」で「海」に「貝」を掛けた。料亭か、通人か、貝にとっては死光かも知れない。
|
| 第74回 狂歌栗のおち穂 |
月に由縁むすぶ柳の五十年下からよみて見れば三五夜 摂難波 霞島
『狂歌栗のおち穂』の撰者は百喜堂貞史、貞柳の五十回忌の追善集である。五十回忌は天明三年であるが刊記に記載がない。『近世上方狂歌叢書十』の解説は天明五年刊と推定する。初句は〈月ならで雲のうへまてすみのぼるこれはいかなるゆゑんなるらん〉を指す。結句は陰暦八月十五日の夜、貞柳の辞世〈百居てもおなし浮世におなじ花月はまんまる雪は白妙〉に拠ろう。
町人の芸は下手こそ上手なれ上手になると家が下手ばる
ほんが来たほんか来たとはいひぬれどそんじよそれとも見えぬ亡き魂
祖父(じい)と婆々(ばば)昔噺しの高笑ひ歯ぬけ同士のひよつかすかすか
ちろりちろりけふふらすこの初雪にひやひや酒ものんだよたんぼ
一首目は佐々木泉明堂が「これも誰やらの詠める」として記す。遊芸と貧乏芸、成句にも「芸が身を助けるほどの不仕合わせ」とあるが家を没落させる例も多かったのだろう。二首目の作者は喜縁斎貞巴、題は「子を失ひし年の七月によみ侍る」。初句「ほん」は「盆」に「坊」を掛けた。四句「そんじよそれ」(そんじょうそれ)は、しかじかの者、かくかくの者、「そんじょう」は「その定」の転である。三首目の作者は喜楽斎貞舎、題は「老人高笑」。結句は老人の歩く様を連想させる「ひょっかひょっか」(ひょっこひょっこ)に四句「歯抜け」の「すかすか」で造語とした。貞柳の〈祖父(ぢい)は山へしばしがほどに身は老てむかしむかしの咄恋しき〉が思われる。四首目の作者は紫縁斎貞逸、題は「初雪酒狂」。初句「ちろりちろり」は雪の降る様であり、「ちろり」で酒を温める容器を、二句「ふらすこ」は「降らす、この」にガラス製の徳利「フラスコ」を重ねた。結句「よたんぼ」(酔坊)は酔っ払いをいう。
一里二里三里のやいとすへたやら時の間にゆく夕立の脚
おしめども最(も)はや月日もくれ六つのなつたならぬのかねのおとのみ
のぼりては笑靨(えくぼ)に見ゆるおふく鳳巾(いか)はなしはせじと引はつてゐる
野呂氏の男山をもまもり詰(め)ゐさせ給はれ弓矢八まん
一首目の作者は紅縁斎貞左、題は「白雨」。序数詞で韻を踏みながら二句「三里」を呼び出した。「三里」は灸穴、ここに灸をすえると足を丈夫にするといわれる。三里の灸である。四句「時の間」は束の間をいう。二首目の作者は清流軒月舟、題は「歳暮」。三句「暮れ六」は午後六時頃、時間だけではない、「月日」という「歳」も「暮れ」なのだ。四句は「鳴った鳴らぬ」に「成った成らぬ」だろう。三首目の作者は故人梅枝、題は「寄紙鳶恋」。三句の「御福」とは阿多福だから「夜目遠目笠の内」の遠目をいう。四句は「放しはせじと」。四首目の作者は奥田居館、題は「天明三年卯四月末つかた紀州野呂御氏洛東三十三間堂にて大矢数の日限究(め)けるよし相応の用もあらんなれば参るべしと御しらせにより悴をめしつれ陸地をのぼるとて八幡にまふでて」。初句の接尾語「氏」が目を引く。読み方は「うじ」と「し」の二者択一だが前者で五音と解しておく。四句「ゐさせ」は「居させ」に「射させ」となる。
|
| 第75回 除元狂歌小集(1) |
むつましう揃ふて祝ふ雑煮餅娘もことしは七つおきして 浮油堂土丸
『除元狂歌小集』の編者は雄崎貞右、詠者は「天明四甲辰 浪華玉雲斎社中六群之内」(解説)、「除元」は「除夜」と「元日」の意味らしい。掲出歌の結句「七つ起き」は早朝の四時に起きることをいう。四句「今年は」からすると去年はそうではなかったのだろう。嫁にいくのも遠くはない。その予感が上句「むつまじう揃ふて祝ふ雑煮餅」を格別にしている。
とてもなら春諸ともに谷の戸を先(づ)明(け)ましたと祝へうくひす
おつとせい喰ふたより早あたたかやにつと年立(つ)門の松前
日のあしのさても短(か)やあらせはし朝てもくれといふ年のくれ
かはりなき御代のしるしや明(け)て今朝長うなる日の丸ういつるは
一首目の作者は眠龍館斧丸、題は「歳旦」。初句は「とても」と「なら」の間が省略されたものである。入るとすれば「鴬は姿を見せられない」だろう。初春とはいえ鶯との揃い踏みは望めない。それならばせめて声だけでも二句「もろともに」というのである。二首目の作者は玉川堂渦丸、題は「歳旦」。正月からの薬食いが異色の作品である。とっておきの精力剤だったのだろう。口元だけの笑い「ニッと」が露悪的だが日の出の比喩でもあろう。結句は「門(の)松」と北海道の「松前」が「松」を共有している。三首目の作者は小西蘆鑵、題は「歳暮」。初句は「日脚」に助詞「の」を挿入して字数を調整をした。遅く明け、早く暮れるから気持ちも倍加して忙しいのだろう。たしかに朝でも「(歳の)暮れ」には違いない。四首目の作者は驚燕堂塵丸、題は「歳旦」。冬至は十二月二十二日頃、陰暦なら十一月だろうから四句は厳密でないが、気分は了解できる。天下太平、四五句に句またがりで「日の丸」が昇る。
嚊の腹もはるそ嬉しきいはた帯しめかさりしてむつきまつ也
化粧する間もなきとしのすゑ餅やかかみの数を手にはとれとも
雪と墨違ふてよそは年忘れこちや忘れしと大さらへする
きのふとはきやうとう違ふて門の戸をくわらりと明(け)の春の長閑さ
一首目の作者は田中是旭、題は「歳暮」で「妻なるもののはらめるをよろこびて」。二句は「張る」に「春」、四句の「締め」に「注連飾り」の「注連」を掛ける。結句「睦月」に「襁褓」を重ねる。二首目は一首目の隣で作者は「同女 きと」。右に登場する「嚊」であろう。〈化粧する間もなき年の末 餅や鏡の数を手にはすれども〉。三句が句割れ、四句の「鏡」は「鏡餅」の略で実際の鏡を手にする時間がないというのである。三首目の作者は「そよ女」、題は「歳暮」で「稚きに手跡の指南しければ」。四句「こちゃ」は「こちらは」、下句は「忘れじと大浚へする」。歳暮も読み書きを教える教育ママとなる。四首目の作者は柳浮堂如松、題は「歳旦」。〈昨日とは驚倒 違うて門の戸をがらりと明けの春の長閑さ〉か。二句は「今日と違うて」を掛けたと思われるが、それならば「けふと(う)違うて」でなければならない。表記の問題が最後まで残るが家の戸を一枚「ガラリ」で風景も「がらり」の変化に立ち止まった。
|
| 第76回 除元狂歌小集(2) |
千早振(る)神の春なり屠蘇ふくろからくれなゐに酒くくるとは 南有舎星丸
初句「千早振る」は神の枕詞、二句「神の春」は新年を祝っていう。三句「屠蘇袋」は屠蘇散を入れて酒に浸す袋。紅絹(もみ)または白絹を三角形に縫って作る。本歌は在原業平の〈ちはやぶる神代もきかず龍田川韓紅に水くくるとは〉(『古今和歌集』二九四)である。
とりわけて心をくはる衣くはり寒気見舞(ひ)もかててくはへて
一ふてをこころみしはきのふけふと暮(れ)はや餅米をめてたくかしこ
春たてる大福の茶のかまた氏みつからそ今朝昆布て祝はん
おててこてんのてんまやとしの関守は明(け)てそかはるあら玉の春
一首目の作者は女性で「あさ」、題は「歳暮」。三句の「衣(きぬ)配り」は年末に正月用の衣服を使用人などに配り与えること。結句の「かてて加へて」は悪いことが重なる場合に使われるが、ここは初句の「て」音に反応した少数例と解したい。二首目の作者も女性で百枝、題は「歳暮」。初二句「一筆を試み」は手紙を書いたのだろう。三句は「今日と暮れ」、結句の「めでたくかしこ」は手紙の終わりに添える語。「かしく」なら「炊ぐ」で「めでたく炊ご」を掛けた。三首目の作者は鎌田氏さく、内儀であろうか。題はない。二句「大福の茶」(大福茶)は元日に若水でたてた煎茶、梅干しや昆布などを入れて飲む。三句の「かま」は「釜」に苗字の「鎌」を掛ける。四首目の作者は陌頭軒柳人、題は「住所によりて」。初句「おててこてん」は御出木偶(おででこ)を使う見世物の囃子である。この「てん」から「天満」(大阪市北区南東部の地名)を呼び出した。続く「や」は詠嘆の助詞、「年の関守」は「甲辰」になる。
乗る者もかこかく者もひよつこひよこともに世話しき年の尻へた
春を迎へ目出度(い)かなのめの字かや丸ふ結んた注連縄の輪は
鶯もほけきやうつけよ我(が)庵の仏壇の戸を明(け)のはつ春
かたひらもいつしかに年のくれなゐやたもとに屠蘇の袋にほひぬ
一首目の作者は藤井沖丸、題は「療養の途中にてよめる」。三句のオノマトペが乗る側と駕籠をかく側双方に効いている。結句「尻べた」は臀部「年の~」で一年の最後尾となる。世の忙しさが療養者にも感染したようである。二首目の作者は呉竹菴杖丸、題は「歳旦」。四句「丸ふ」は「丸く」のウ音便だから「丸う」となる。仮名の「め」の字に似るのは結句にも「輪」とあるとおり輪締めの注連縄で、牛蒡締め等ではない。三首目の作者は聞潮、僧侶である。題は「歳旦」。鶯の別名に春告げ鳥と経読み鳥がある。二句は「法華経告げよ」と後者に呼びかけた。しかし出てきたのは「仏壇を明けの初春」で前者、仏壇の中は自然の森なのだ。四首目の作者は土井雛丸、題は「屠蘇散を製し袖にして友がりゆくとて」。「友がり」の「がり」は接尾語で「のもとに」。初句の「帷子も」は裏をつけない衣服、三句は屠蘇袋の「紅」に「暮れ」を掛ける。これより先に暁江作で〈針さしのいと世話しなや屠蘇袋くけてあくせく気をもみのきれ〉がある。四句は「絎けて~」、結句「紅絹」に「揉み」、殿方は気楽に出来ている。
|
| 第77回 除元狂歌集(1) |
今朝年をこしきの湯気かたつ霞よいまんちうやあたたかな春 如亀楼有孝
尾崎貞右編『除元狂歌集』の詠者は「天明五乙巳 浪花玉雲斎社中」、刊記等なし、天明五年は一七八五年である。掲出歌の題は「いとなみによりて」。二句「甑」は米や豆を蒸すのに用いた道具で湯釜の上にのせて用いた。初句からだと「今朝年を越しき」となる。また四句から饅頭屋だと分かる。「や」は詠嘆と感動、二句の「湯気」が結句「暖かな」と呼応する。
春されは門田の稲葉も藁となり注連と変して初東風そふく
ちとくめとしかつた遠出の小坊主か茶の大ふくも用にたつ春
両の手に握りつめたる五十五も今朝指一つあけ始(め)る春
明(け)始(め)る今朝はとうからおきの石屠蘇の土器かはく間そなき
一首目の作者は蚯蚓菴鬼丸、題は「元旦」。二句「門田」は家の前にある田、「稲葉」は田に生えている稲をいう。結句「初東風(はつこつ)」は初春の風である。稲、藁、注連縄(「〆」を掛ける)と米の縁語で一年の推移を表した。二首目の作者は一雫軒鉄丸、題はない。寺年始であろう。したがって初句「くめ」は「水を汲んで来い」ではなく「お茶でも飲んでいけ」の意となる。ねぎらいで叱った小坊主が今では立派になった。正月のお祝い茶を一緒にするまでになったという感慨だろう。三首目の作者は不寝軒鱶丸、題は「いそし六つの春を迎へて」。片方の握り拳が五十、片方が五、後者の薬指を立てて五十六だというのである。四首目の作者は山中氏信、妻女の信さんである。初句は「明け初める」、二句は「疾うから」、三句の「おき」は「起き」に「沖」を掛ける。四句の「土器」は「かわらけ」と読む。杯のほかに酒宴の意味がある。結句の「かは」と同音のくり返し、乾く間のないのは沖の石も同様である。
取り始(め)る筆より先へかきさかす娘もこころ三ッの正月
こその暮寒いと云ふた西風も今朝は嬉しいあちらこち風
屠蘇酒に酔ふたは猿か赤い顔て蓬莱の山の串柿を取る
とくとくと若水むかへにくるまきのかねの釣瓶もあたつてくわん朝
一首目の作者は一洞亭其丸、題は「子なりけるものの三才となりけれは」。二句の「筆」と下句の「こころ三」(試み)で試筆(書き初め)となる。但し三句「掻きさがす」で字になっていないのだろう。結句「三ッ」に年齢と「三つ(の朝)」(元旦)を重ねた。二首目の作者は錦山舎綾里、題はない。寒い西風が東風に変わって嬉しい、春を寿ぐ歌である。結句「あちらこち」は反対、あべこべの意。「東風」で「こち」とも「こちかぜ」とも読むが、掲出歌は後者である。三首目の作者は樵諷軒歩丸、題はない。四句「蓬莱の山」(蓬莱山)は蓬莱飾りともいい、関西で新年の祝儀の飾り物の一、酔顔を猿に見立てた。その猿が山の串柿を取って食べたのだろう。四首目の作者は澪標軒芦江、題はない。三句の「くるまき」は滑車、また車井戸をいう。滑車に縄をかけ、その両端に金属製の釣瓶をつけている。井戸に下りていく釣瓶は初句「とくとくと」だが、もう一方は滑車に当たって「カン」となる「元朝」なのだ。
|
| 第78回 除元狂歌集(2) |
氷面鏡割れかかれともあかきれはたつ春風にいへ始めてけり 松尾氏婢女みよ
初句の「氷面鏡(ひもかがみ)」は池などが凍って鏡の面のようになったものをいう。自然界の「あかぎれ」に対して「私」の皹は春風とともに「癒え初めてけり」、「癒ゆ」はヤ行下二段活用である。女中であれば水仕事は多かっただろう。新年を寿ぐ挨拶歌として読む。
ふる年と替つたけしきをこらふしませ今朝の雑煮の御前からくり
雑煮餅いわへはうれしひよくひよくと心も躍るこめかみの春
初日影少しあかみて霞んても大事ない大事ない目の玉の春
すへらきの御代の春とてはい虫の我等も屠蘇の酒にたかりぬ
一首目の作者は大矢氏宰、小さく「女」とある。初句は「旧年と」、二句「けしき」は「気色」でいいだろう。三句は「御覧じませ」、「見る」の尊敬語「ごろうず」の連用形に助動詞「ます」の命令形が接続した。結句「おまえ」は敬う気持ち、「からくり」は「工夫」「やりくり」と解した。二首目の作者は棹雫軒麦丸、題はない。三句の「ひょくひょく」は擬態語で結句の「こめかみ」が動いているさまをいう(ここの即物表現が堪らない)。だから四句「心も踊る」の「も」となる。三首目の作者は見聞舎恒丸、題は「眼科を行へは」。初句「初日影」は初日の出、それが赤く霞んでいるという。下句「~目の玉」に擬人化と眼科医の見立てが挿入される。人ならば「大事無い、心配することはない症状」です。これと「玉」を共有して「目の(新)玉の春」を略して大団円となった。四首目の作者は梅流軒観山、題はない。三句「はい虫」は「はひ虫」(蠅虫)、武家の時代だから初二句の「すべらぎの~」が注目される。酒器にたかる蠅のような、取るに足らないというときに対極としての権威が要請されるのだろう。
麁物足袋もつまらて少しゆつたりとさいた初日のあしのうららか
はりつめた氷も人も去年の気は離れてうきうきうくや初日に
年も今朝あら玉津嶋こころみの筆やすみよし絵をかきの本
月の夜や雪のけしきに替へ事も今朝はへかこの目の玉の春
一首目の作者は八木氏女尾上、題はない。初句「麁物(そぶつ)」は盆、暮に主人から奉公人に与える衣類などをいう。下句「さいた」は「放いた(離いた)」だろう、「初日の脚」に足袋をはいた足を重ねた。二首目の作者は鶴子軒崎丸、題はない。初日の出によって一面の氷も溶け始めて浮いている、人の気分も浮き浮きしている。しかし「浮き浮き浮くや」は「氷」よりも、「人」よりも、初日の出そのものの姿なのである。三首目の作者は春潮齋門二、題は「試筆ありて和歌三神を画(く)とて」。二句「あら玉津島(明神)」、四句「墨良し=住吉(明神)」、結句「画きの本=柿本(人麻呂)」と詠み込んで歌意も通っていることを嘉したい。四首目の作者は非菱軒無角、題はない。初句の「や」は並列助詞である。その「月の夜」や「雪の景色」と「正月の朝」を三句「替へ事」(交換)する話については四句「べかこ」(「べかこう」。指で下まぶたを引き下げて裏の赤い部分を見せる仕草)すなわち拒否するというのである。
|
| 第79回 除元狂歌集(3) |
年なみのよせて世話しき行(き)違ひ袖て楫とる宝船うり 中邑群丸
題はない。初句「年波」は年が重なっていくことを波に喩えた語、また「波」は下句の「楫」と「宝船」に呼応する。二句の「世話」は「忙」の宛字、ルビに似た効果を思う。三句は「ゆきちがい」で擦れ違うこと。結句の「宝船売り」は「おたから、おたから」と呼びながら宝船の絵を売り歩いたという。賑やかな雑踏にも、紛れることのない、人の姿である。
寒垢離かあひたる水は凍(り)つけと跡をもみつや流れ行(く)とし
年仕舞大事しやうしもさつはりと柱へ暦はるのこしらへ
押詰(め)ても煤うち払ふ世話もなし旅のやとりの年の夕くれ
雪霜をいたたく老かかうかい髷くるくるまはりもよい年の暮
一首目の作者は幾田友丸、題はない。初句「寒垢離」は寒中に白装束で家々に用意された桶の水を浴びて歩く行、ここではその行者をいう。四句「みつ」は「水」に「見ず」を掛ける。結句は「流年」の読み下しである。二首目の作者は岩瀬亀丸、題はない。二句「小事」に「障子」を掛ける。下句の句またがり「暦/はる」は「貼る」に「春」を重ねた。迎春の準備も万端整ったのである。三首目の作者は森染丸、題は「旅店にて」(りょてん、宿屋)。本歌は藤原定家の〈駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野のわたりの雪の夕暮〉(『新古今和歌集』六七一)。三句「世話もなし」の「も」で手持ち無沙汰を託つのは勤勉の裏返しだろう。四首目の作者は安宅氏仙、女性である。初二句「~戴く」は老人の白髪に冬の季節を重ねる。三句「笄髷(こうがいわげ)」は笄に髪を巻きつけた婦人の髪型をいう。笄は髪をかきあげる道具、後に髷に差す髪飾りの意となった。四句の髪の量感がなくなったことから歳末風景に接いだ。
嬉しさと世話しさ餅につきませる春を隣のきねのおと月
煤払ふほこりの雲に声するは天乙女てはいや内儀なり
月も日も段々かへりの人形か工合よういた年の尻まて
化粧するひまも内儀は年仕舞(ひ)白うぬつたは竈はつかり
一首目の作者は岡橋枝丸、題はない。二句「世話」の宛字が市井の様子を生き生きと浮かび上がらせるようだ。結句は「杵の音」と「弟月」(十二月)が「おと」を共有する。二首目の作者は栗本睦丸、題はない。三句の「天乙女」は天女、そこはかとした期待に胸躍らされるが結句「いや(そうでは)ない(儀なり)」。働き者の内儀と怠け者の亭主の配合が生んだ見立てであろう。三首目の作者は井川圭丸、題はない。二句から三句の「段々返りの人形」は後方転回をしながら階段を下りてくる絡繰り人形だろう。五段返りが一般的だが、ここでは月数にして十二段、日数にして三六五段(いずれも新暦計算である)、うまく着地できた「私」の大仕舞であった、といったところか。四首目の作者は木田芦調、題はない。二句「内」に「(暇も)ない」を重ねた。下句の「白うぬったは竈」は竈の上塗りのことだろう。陰暦十二月八日を竈塗り日と称して新年を迎える準備を行った。畢竟、化粧は「竈ばっかり」なのだ。
|
| 第80回 除元狂歌集(4) |
相替(は)らす目出たきつけと暮(れ)毎に小便かへかくれる豆から 羽田山丸
無題。初句は今までどおり、二句「付け」は請求書、三句は一定の期間ごと、四句は「小便替へが」。農夫が肥料にする糞尿を野菜などと交換したり買ったりするのだ。その支払いが「豆殻」、実を取ったあとの茎・葉・莢だから、なかなか抜け目のない小便替えである。
世話しさに拝みはせんしゅ観世音お手かかりたや年のくれには
はたはたはた叩く畳は医者殿の真似やすすはきしまいかたには
やかて春にあふみそ嬉し今錺る蓬莱山王としの坂本
初東風かやかてふき組ちといねをつんてんころりんしやんと仕舞ふて
一首目の作者は荒川歩丸、題は「新清水寺の辺リを通るとて」。新清水寺は大阪市天王寺区にある四天王寺の子院で清水寺の千手観音を移して本尊とした。二句は「拝みはせん(手)」、四句は「お手が借りたや」。二首目の作者は石村呉丸、題はない。初句は「ぱたぱたぱた」だろう。下句は「真似や/煤掃き仕舞方には」。仕舞方は仕舞う頃をいう。慣用句「医者の玄関構え」は外観を飾る喩えだが、いよいよ正月を迎える準備が整いつつある風情なのだ。三首目の作者は坂本渡山、題は「氏ニよりて」。二句は「逢ふ身」に「近江」、四句は「蓬莱山」に「山王」(滋賀県にある日吉大社)で「山」(また号「渡山」の「山」)を共有する。結句「年の坂」は年末、「坂本」は「坂の上り口」、また滋賀県(近江)の地名、作者の「氏」である。出身地だろう。四首目の作者は大矢氏宰、女性である。二句「吹き」に「菜蕗」(八橋検校作曲の組歌の代表曲。菜蕗組)を掛ける。三句以下は「稲積む」(正月に用いる忌み詞で「寝る」)をツンテンシャン、三味線の口調で「ごろりとしたいものだ、正月の準備を終えて」と詠う。
うす紅葉見たはきのふかけふあもをつき日のたつは早いものまへ
天しやうの煤を払へは黒雲のやうなほこりかはや辰の暮
やかてはや春かきの国蜜柑かはとちらむいてもいそかしけなり
はや春の花のおもかげ見するかは餅米洗ふ水にしら雲
一首目の作者は大矢氏蔦、女性である。初句は薄く色づいた木の葉、三句「あも」は餅、四句は「搗き」に「月」を重ねた。結句「物前」は正月の前、また「まへ」が「かえ」(連語で疑問の意をもって聞き手に働きかける)に聞こえる。二首目の作者は今西汐丸、題はない。「雲龍」(雲に乗って昇天する龍)の見立てだが「雲龍相逐う」「雲は龍に従い風は虎に従う」と関連する成句も多い。「辰」に埃が「立つ」、天明四年(辰年)の暮れを詠う。三首目の作者は小山梁人、題はない。三句は「春が来の国」と「春が紀国」が表裏で、三句の「かは」も片や詠嘆を含んだ疑問の意の連語、片や蜜柑の「皮」となる。四句は「向いても」と「剥いても」、正月飾りにも用いられる蜜柑が大活躍である。四首目の作者は雄崎貞右、題は「歳暮」。三句切れの歌である。上句は「はや春の花、桜の面影を見せるのだろうか。いやそんなことはない」。下句は餅米を洗う水が糠で白くなって流れるさまだろう。小川か用水堀が想定される。
|
| 第81回 嬾葉夷曲集(1) |
辨當のむすひをほれはなつく犬の手をくれるまて遊ふ春の野 鼠蟲軒栗本睦丸
「嬾葉夷曲集」の選者は原素館尾田初丸、刊記は天明六(一七八六)年。混沌軒貞右(国丸)が烏丸光祖より玉雲斎の号を賜ったことを記念する祝賀集である。掲出歌は「春之部」、題は「野遊」。二句は「結びを放れば」、四句は「お手をしてくれるまで」だろう。携帯用に作られた重箱もあったというが、犬に握り飯をくれてやるなど、贅沢な野遊びである。
古郷の野路に残れる雪ならて所またらになまるやふいり
梅か香の通ふはかりそ柴の戸はあくるもさすも春の風の手
盃の熊かへさくら丁とよいもう此(の)うへはちりますちります
せめてとや植(ゑ)いたみせし連翹の枝にとまつた黄なる蝶々
一首目の作者は青巾舎中村群丸、題「宿居」(「宿下がり」)は奉公人が休暇をもらって親元に帰ることをいう。三句は「雪ならで」、下句の「所斑に訛る藪入り」とは都会言葉の中に田舎訛りが顔を出すのであろう。二首目の作者は竹葉軒高松杉丸、題は「幽居春風」。「幽居」は世の煩わしさを避けて静かに暮らすこと、またその住まいをいう。四句は「開くるも鎖すも」、戸の開け閉めは風任せ、通うのも人ならぬ梅の香りだというのである。三首目の作者は青巾舎中村群丸、題は「花」。二句は「熊谷桜」、彼岸桜に次いで早く咲く。盃の内面に桜の絵が施してあるのだろう。注いでくれる酒も「丁度良い」、これ以上だと「こぼれます」を桜に掛けて「散ります」といっている。四首目の作者は雌雄軒土井蟹丸、題は「蝶」。二句「植ゑ傷み」は植物を植え替えた時、しばらくの間生育が止まり、葉が萎れたり枯れたりすることをいう。その代償ではないが、黄色い連翹さながらに蝶々が羽を休めているのである。
隙やつた布子かそしるか朝夕はまたくつさめこ衣かへして
ほとときすたつた一声短夜にああ侭ならぬ犬の長鳴き
時鳥のこゑにはつむた小便もおもはす半分しののめの頃
ちりて後なとけし尼といはぬそやかくうつくしき花の姿を
「夏之部」に移る。一首目の作者は青巾舎中村群丸、題は「首夏」。木綿の綿入れである「布子」に「隙(ひま)やった」は擬人法で四句の「こ」は接尾語である。朝夕は「くっさめ」(くさめ・くしゃみ)が止まないのだ。二首目の作者は青々舎安楽酒丸、題は「郭公」。短夜にホトトギスの一声を待っていると事もあろうに犬が長鳴きを始めたというのである。四句の「ああ~」も新鮮に響く。三首目の作者は驚燕堂村主塵丸、題は「曙郭公」。二句は「声に弾んだ」、活気を帯びたのである。しかしそのために「弾んだ小便も」、勢いよく跳ね返るそれも「半分残したところで東雲(夜明け)の忍ぶ」様子が情けなくも可笑しい。四首目の作者は青々舎安楽酒丸、題は「罌粟」。二句の「など」は何故、どうして、の意。罌粟の果実を罌粟坊主、またこれに似ているところから頭頂だけ毛を残して周囲を剃り落とした乳幼児の髪形をいう。この坊主を寺の坊主に読み替えて罌粟尼を提唱した。果実ではなく花に着目すると肯ける。
|
| 第82回 嬾葉夷曲集(2) |
少将の深草うちは手にとれは夏ももも夜やかよふ秋風 義楽
題は「團」。二句「深草団扇」は天正年間(一五七三~一五九二)に奈良団扇を模して現在の京都市伏見区深草で作られるようになった。初二句「少将の深草」(深草少将)は小野小町に恋をして九十九夜通ったが、もう一夜というところで果たせなかった伝説上の人物、これを受けて四句が「夏も百夜や」となる。結句の「通う」も秋風と共に少将の面影が漂う。
昼の辻しはしゆききの音絶(え)て暑さそ物にまきれさりける
ぬけからのそれかあらぬか夏なからあきや涼しき蝉のもろ声
吹(く)風に髪の匂ひもつき夜影いもは島田にゆふすすみして
川水に夏はさなから流るらし風鈴の音のちんのすすしさ
一首目の作者は青巾舎中村群丸、題の「苦熱」は暑さに苦しむこと、またその暑さをいう。下句「暑さぞ物にまぎれざりける」は他のことで紛らかすことのできない苦熱、その具現として太陽が南中する頃の無人の辻が描かれている。二首目の作者は眠龍舘三原斧丸、題は「空舘蝉」。初句「脱け殻」は一つには空き家、今一つは蝉の脱け殻をいう。二句は「そのためかどうか」。四句「あきや」は一つに「空き家」、今一つは「秋や」を隠す。三首目の作者は鼠蟲軒栗本睦丸、題は「納涼」。三句「月夜影」は月の光また月の光に照らし出された景色をいう。これに二三句「髪の匂ひもつき」を重ね、視覚と嗅覚の「妹は島田に夕涼みして」なのだ。「島田」は未婚の女性の髪形とされる「島田髷」の略である。四首目の作者は鳥巣軒岡橋枝丸、題の「水檻風凉不待秋」(水檻に風涼しくして秋を待たず)は白居易の詩句。「水檻」は水辺の手すりをいう。上句の譬喩また結句も副詞「ちん」に「亭(ちん)」を重ねて巧みである。
はかされしと立合大事に懸(け)ぬるは二王の草鞋の土つかす同士
吹(く)風のあらうはすなと夕霧やむすひの角力は稲の花かた
人柱のむかし見するかふちはかまなからの川に影のしつんて
取(る)もうしとらぬもつらしよい中に柿の出来たる隣同士は
「秋之部」に移る。一首目の作者は眠龍舘三原斧丸、題は「相撲」。寺門の左右に立つ仁王が相手である。初句の「履かされじと」は三句以下と対応する。また健脚の神に奉納される草履だから「土つかず」となる。二首目の作者は九淵堂八木雪丸、題は「田家相撲」。三句切れで上句は「吹く風が逆に荒うはするなと稲の力士に言ったかどうか、夕霧が出ている」。その「夕霧」の季節は秋、実りの秋で結びの一番にも豊作の願いがこもる。稲は田家の花形なのだ。三首目の作者は交水舘佐藤魚丸、題は「水辺草花」。見立ての歌で四句「ながらの川」は淀川下流の長柄川と解した。人柱は藤袴の「袴」からの連想、結句は水面に映る姿が「沈んで」見えるのである。四首目の作者は青々舎安楽酒丸、題は「果熟スレハ隣家ノ罪」。『日本国語大辞典』で「隣家」等を引くと「此柿の実は、此男児の物にあらず、隣家の物なるに、垣を踰えて、盗み取れるなり」(『小学読本』)が登場する。教材の原型とその広がりに思いが及ぶ。
|
| 第83回 嬾葉夷曲集(3) |
なら茶舟もりよき食やこほれたかと霰に誰も一杯は喰ふ 九淵堂八木雪丸
「冬之部」に移る。題は「舟中霰」。初句「奈良茶船」は奈良茶飯を売る船。伏見・大坂間の乗合船などを相手に商売をした。二句は「盛りよき食(めし)や」、三句は霰に飯が「こぼれたかと」思う、それを結句、上手く騙される意の「一杯食う」でアレンジしてみせた。
盗人のこちるや冬の入口は音もめつきり寒むなつてきた
厚氷提(け)あるかんと小便てあけたる穴へとをすわらんへ
寒き夜や竈の山にきらきらと凄いは猫の眼の玉の月
川水に流るる菜の葉足さきにまつはりぬれは気にかかる鴨
一首目の作者は舩秤軒岩崎象丸、題は「初冬盗人」。二句「こじる」は隙間などに物を差し入れてねじること、三句の「入口」は泥棒だから雨戸や戸の隙、これに題の「初冬」を重ねた。四句の「音」はその際のものだろう。二首目の作者は原素館尾田初丸、題は「小児翫氷」。厚い氷を二句「提げ歩かんと」、小便で穴を開けたのである。結句「通す」だが穴に何を通すのか、「童部」の「わら」に「藁」を重ねたと読む。三首目の作者は眠龍舘三原斧丸、題は「山冬月」。竈のそばで蹲って暖をとっている猫を竈猫という。その翻案のような作品である。①室内詠。二句「竈の山」を山の形状の譬喩として読む。②室外詠。福岡県太宰府市の「竈山」を舞台として読む。題を尊重するならば②となるが、①も捨てがたい。四首目の作者は稲葉軒山田草丸、題は「水鳥」。観察の行き届いた作品である。ただ結句「鴨」を助詞「かも」の当て字と解するなら作中主体は「私」となる。和歌に特徴的な助動詞「けり」や助詞「かも」を当て字して「鳧鴨」という。和歌への嘲りとはいわないが純然たる水鳥とも断じがたい。
玉人(スリ)も嘸やこまらん冬の日のうすき光のくもり安きに
訪ふよりはとはぬ人こそ誠なれ足跡もなき庭のしら雪
ひく馬のおふた黒木も白妙にあし跡むつの花の都路
此(の)ころは杖に埃かつむ年の老は火桶や火箸たよりに
一首目の作者は青々舎安楽酒丸、題は「冬日職人」(玉磨り)。天候の曇りと玉の曇りは本質的に異なる。しかし二句「さぞや困らん」で作者の奇妙な論理にはまり、あとは頷くだけの読者なのだ。二首目の作者は青巾舎中村群丸、題は「雪」。三句の「まこと」は足跡で情趣を壊したくない真心といったところか。本歌と思しき作品は多いが『玉葉和歌集』の〈とふ人もなくて日数ぞつもりぬる庭に跡みぬやどのしら雪〉(九八二)も、その一つに違いない。三首目の作者は長谷川氏礒女、題は「都雪」。二句の「負うた」はウ音便、「黒木」は皮のついたままの丸太をいう。四句「あし跡むつ」は初句「引く馬」で馬の四本と人の二本で「六つ」、句またがりで「六つの花」は結晶が六角形であるところから雪をいう。結句「花の都」は都の美称。四首目の作者は鼠蟲軒栗本睦丸、題は「冬籠」。初句は「この頃」、三句の「つむ」は上下に「埃を積む」また「積む年」となる。結句を「に」で言い止して老いの心情を滲ませた。
|
| 第84回 嬾葉夷曲集(4) |
しかしかと山さへ見えす火縄ふる夜道はさひし狩人に似て 真圓軒石田束丸
「雑之部」、題は「旅」。初句の「しかじか」は言外にある自明な物事をさし示していう。ここは真っ暗な夜道であること、すると三句の「火縄」は明るさが目的ではない。「ふる」のは火を消さないため、「私」の念頭にあるのは狼や熊、道連れがあれば話し声で近寄ってこない。しかし一人旅なのだ。結句「狩人」と違うのは獣と出合わないための火縄だった。
やよや猫にやんちしらすやいにしへの司馬温公か壷のためしを
禮を知る心や竹にもち雪のそのほとほとに腰をかかめて
実(の)児の寄合なれや中の能いあけくはわれるものとすいした
くちせしな千とせはおろか墨の画の松こそかみのあらむかきりは
「画賛之部」から四首引く。一首目の作者は青巾舎中村群丸、絵は水槽の金魚を狙う猫。初句「やよや」は「おい」、二句「にやんぢ」は「汝」。三句以下は猫に対して人、水瓶に落ちた友達を助けるためその瓶を石で割った司馬光(一〇一九~一〇八六)七歳の逸話をいう。二首目の作者は不朽軒池村蔦丸、絵は竹の葉に雪が積もったところ。三句「餅雪」は餅のようにふわふわした雪をいう。成句に「実る稲田は頭垂る」があるが、これを竹と雪の組み合わせで描いた。四句の重々しさに威厳が覗く。三首目の作者は真圓軒石田束丸、絵は果実が大きく裂けた柘榴、たくさんの果肉が犇めいている。初句は「実の児」と五音で読んだ。三句「能い」は「良い」。下句「あげくは割れるものと推した」。四首目の作者は原素舘尾田初丸、絵は海浜の松原と思しい。初句は「朽ちせじな」で「じ」は打ち消しの推量、「な」は感動ないしは詠嘆だろう。四句の「かみ」は「紙」に「神」、トイレの紙(神)以前の古いお話である。
當世は強いはかりてゆくまいと河内木綿ものふれんになる
鶏かねをしらぬ丁稚のきぬきぬは起(き)よと呵る親方の声
ゑいやつとうつ木刀を上段や下段にひらく山田百姓
一流の手なみ見よとや釼術者鎖てちよいと留(め)た鑓むめ
以下は「雑之部」。一首目の作者は秀紅軒藤井釜丸、題は「ひな歌の物語などしける折傍にもめんの有ければ是を題にして歌よめと望まれけるに」、「ひな」は「鄙」。四句「河内木綿」は普通の木綿より地が厚く丈夫であった。結句「のうれん」は「のれん(暖簾)」に同じ。二首目の作者は青巾舎中村群丸、題は「暁天丁稚」。初句は「鳥が音」、二句「知らぬ」は鶏が鳴いても起きないのである。だから親方の叱声と共に三句「衣衣」(布団との別れ)はやってくる。三首目の作者は九淵堂八木雪丸、題は「百姓劔術」。初句「えいやっと」は名詞で剣術、副詞で「かろうじて」。四句「開く」は「構える」だが武士の忌み詞では「逃げる」の意。結句の呼ばれ方からしても棒振り剣術が思われる。四首目の作者は雌雄軒土井蟹丸、題は「劔術者生花」。剣術者が使うのは鎖鎌術である。対する相手が槍術家でその鑓の攻撃を鎖鎌で留めたのなら分かるが結句は「鑓梅」である。大道芸を想像するよりほかにないだろう。
|
| 第85回 興歌百人一首嵯峨辺 |
あかがりも春は越路にかへれかし冬こそ足のもとに有(る)とも 猿丸太夫
『興歌百人一首嵯峨辺』の選者は中川度量、刊記は天明七(一七八七)年。初句の「あかがり」(皹)に同音の「雁(かり)」を掛けた。「雁」「帰る」「越路」は歌のパターンで〈かへる雁かすみの衣いくへきてさむきこし路の空を行くらん〉(『夫木和歌抄』一六〇二)といった具合であった。下句だが、「あかがり」の「あ」は足の意、二句の「越路」も意識した。なお掲出歌の出典は『かさぬ草紙』、作者は伝記未詳の伝説的歌人、その成り済ましだろう。
葉までよく咲(き)乱れたる作りやうこがね目貫の菊一文字
鉢の木の枝打(ち)払ふ程もなしああふりたらぬけふの初雪
弁慶は腰に二さし背に四さしあわせてむさし棒は手にもつ
千金も一両日とのこりけりここが小判のはしくれの春
一首目の作者は八宮御方(知恩院御門跡八宮)、出典は『後撰夷曲集』である。以下、題はない。四句の「黄金目貫」は刀の柄の留め釘の上につける菊の花の形をした純金の飾り、結句はその大輪十六弁の菊をいう。二首目の作者は麦里。所領を失った男が、雪の夜、旅僧(最明寺入道時頼)のために盆栽の枝を火に焼べてもてなしたのが縁で本領を回復するという謡曲『鉢木』を使った。下句の「ああ」は男の幸運に与れない嘆きともなる。三首目の作者は、よみ人しらず。武蔵坊の「武蔵」と同音の「六差し」、「棒」は同音の「坊」に因んで七つ道具である。ちなみに弁慶の七つ道具という言葉が文献に登場するのは江戸時代らしい。四首目の作者は山居。成句「春宵一刻値千金」の翻案である。初句「千金」は千両、下句「小判」は一枚で一両、その「端くれ」しか残っていないというのであるが「くれ」に「暮れ」を掛ける。
何こともあとの祭りはわるけれとそれとちかふて宵祭哉
老(い)にけり皿ほとな眼で有(り)ながら秤のほしの見へわかぬまで
いととしく過(き)にしかたのこひしきは酒をのみても足のたつたに
をのづから角一つあれ人こころあまり丸きはころひやすきに
一首目の作者は繁雅、題は「神祇」。二句「後の祭り」は手遅れの状態をいう。四句はウ音便だから「それとちがうて」、結句「宵祭り」は本祭りの前夜に行う祭りをいう。「宵」に「良い」を掛ける。二首目の作者は中川度量、題は「述懐」。初句切れで嘆くのは老眼である。「私」が手にしているのは竿秤だろう。その秤竿の上面に記した星を規準として末の取緒で量るのだが、成句「目を皿にする」(目を大きく見開く)の二三句をもってしても目盛が「見え分かぬ」(はっきりと見えない)のだ。三首目の作者は一叟、題は「懐旧」。初句は形容詞「いとどし」(いよいよ甚だしい)の連用形。下句、昔は「いくら酔っ払っても、千鳥足で帰ったものだが、今は素面でも立ち上がるのがやっとになった」か。四首目の作者は隆覚禅師、題はない。出典の『古今夷曲集』では、この前に平時頼の〈角あれは物のかかりてむつかしや心よこころまろまろとせよ〉があって掲出歌は「返し」である。問答歌また道歌の類といえよう。
|
| 第86回 狂歌つのくみ草 |
あつさには川の水さへ夏やせかちよろりちよろりとほそう流るる 春朝亭氷花
『狂歌つのくみ草』の選者は如棗亭栗洞、刊記は寛政元年(一七八九)年。掲出歌の題は「夏川」。二句の人ばかりか「さへ」で導かれた水量を譬喩した夏痩せ、この渇水表現が意表をつく。しかも下句の「ちょろりちょろり」以下、映像で流して「いかにも」なのだ。
木々の葉のしけりてかこふ庭の面是も日陰の妻の宿りに
照(り)つける暑さに道そ急かるる木蔭や近き蝉のもろこゑ
ふけゆけは花火の煙り空に消えて行衛もしらす帰る御座舟
流すほとの雨さへ晴(れ)てをとる手の打(っ)てかはりしてふり袖ふり
一首目の作者は可楽亭指耕、題は「妾宅新樹」。「妾を囲う」という。また妾のことを「日陰妻」(下句「日陰の妻」)ともいった。結句「宿り」は本妻の「宿」(家)と違って仮の住まいをいう。読者の抱く「妾宅」のイメージを裏切らない作品といえようか。二首目の作者は仙郷亭棗風、題は「夏昼」。二句から三句の「ぞ~るる」、四句の「や~き」と係り結びが二度出現する。最初は日を遮るものがないらしいこと、また旅人かそれに近い「私」を想像させる。二度目は視覚ではない、聴覚によって木蔭の存在を知る。結句「蝉の諸声」を逆説的に夏のオアシスとした。三首目の作者は野口さい女、題は「夏の夜のいたくふけ行(き)し頃なには橋にて」。当時の難波橋は現在より一筋西の難波橋筋にあり、大川に架かっていた。橋上は十有余の橋を見渡せる絶景で、夏の浜には納涼客を目当ての店も出て賑わったという。結句は徒歩の「私」に対して富裕な町人が乗る「御座船」が行く。四首目の作者はみよ女、題は「雨後踊」。初二句の雨は踊りを中止させるような雨の意、四句「打って変わりし」は本来は天候のことだが「踊る手」に組み替えられて同音異語の「手振り袖振り」となる。
秋風のつよく案山子の弓とりもふきたをされて足か上つた
色はへるもみちを見にはゆきもせてきにもそまらぬ用か出て来た
ああらめてた火燵へ足袋を落します焼く払ひますやくはらひます
玄関のすたれをかかけ風の手は案内なしにつつと通つた
一首目の作者は可楽亭指耕、題は「野分案山子」。三句「弓取り」は弓を持つことを務めとする人をいう。その結句「足が上がった」は失敗してお払い箱になる意、実景でもあろう。二首目の作者は似棗亭春洞、題は「紅葉を見にまからんと約して得まからさりけるといへるに」。四句は「気にも染まらぬ」(心に適わない)、これに紅葉の「黄にも染まらぬ」を重ねた。三首目の作者は如棗亭栗洞、題は「節分の夜火燵へ足袋を落(と)して」。初句は「ああら目出度」だろう。三句以下が変だが結句「厄払います」への通過点と読む、厄払いは厄落としともいい、「ます」(枡)は節分の豆まきのアイテムなのだ。四首目の作者は春朝亭氷花、題は「風をよみねと望(ま)れて」。古くからある「風の手」を用いた擬人化である。二句は「簾を掲げ」、垂れ下がっている簾を持ち上げた。下句とりわけ「つっと」が圧巻である。
|
| 第87回 狂歌玉雲集(1) |
井の中へ打(ち)込(む) やうに飛ふ蛙とんふりとよむ文字の点かも 居由
『狂歌玉雲集』の選者は玉雲斎雄崎貞右、刊記は寛政二年(一七九〇)年。掲出歌の題は「蛙」。「井」の字形に組んだ井戸のふち、その井桁に蛙は飛び込んだわけで視覚的にも「井」となる。飛び込んだ音も「どんぶり」だから擬音が同時に和訓となった。似たような趣向の歌に風水軒白玉翁の〈釣り置きてふりたる網のやれやれといふ間に瓜の一つは丼〉がある。
山かつのかへる袂のにほはすはみねのさかりを人やしら梅
たいこ持(ち)かこはいろ里て扇紙鳶顔にかさしてちよとあけまする
みな人をあをむかしけり朧けに見ゆるしやほんの玉の月影
帆はしらは一本もなきけふの海とる蛤のはしらはかりて
一首目の作者は浅生(女性)、題は「山中梅」。初句「山賤」は猟師や樵夫をいう。三句「匂はずは」は「匂はないなら」、四句は「峰の盛り」、結句は「白梅」に「知ら」で知らない意を重ねた。和歌では情趣を解さないというのが前提の山賤である。二首目の作者は此丸、題は「花街紙鳶」。初句は「太鼓持ちが」、二句の「こはいろ」は「声色(こわいろ)」で声帯模写、これと「いろ」を共有して「色里で」となる。三句は扇の形をした凧、結句は「ちょと揚げまする」。「まする」は助動詞「ます」の古い形を示す。三首目の作者は岩丸、題は「春月」。二句は「仰向かしけり」。一見、シャボン玉を見上げたような印象を受ける。しかし結句の助詞「の」は譬喩だからシャボン玉のような朧月ということになる。四首目の作者は梶丸、題は「汐干」。遠景には帆船が一隻も出ていない海、それと対照的に近景の浜では潮干狩りに余年のない人たち、快晴なのだろう、その光景を帆柱と貝柱という二つの「はしら」で描き出した。
ここまてはよもやと思ふ山奥の花の外にも笑ふ人声
とかめうか一枝は折(つ)ていぬさくら花盗人といははいへつと
水なれ棹さしかねにけり山桜のかけをきよろりと見ていかたのり
拍子とるつゐてに蚊まてころしをる汗しつほりと語る浄るり
一首目の作者は虹丸、題は「花」。四句は「花のほかにも」、結句の「笑ふ」には「花が咲く」の意がある。だから「~も」となる。たかが桜狩りや花見遊山ではない。「私」を含めて花見衆は貪欲なのだ。二首目の作者は窓丸、題は「花」。初句は「咎みょうか」、「めう」は『日本国語大辞典』の「め」の項目によると助動詞「よう」の前身であるらしい。三句は「犬桜」に「去ぬ」、結句は「家苞」に「言え」を掛けた。三首目の作者は輔丸、題は「水辺花」。初句「水馴れ棹(みなれざお)」は水底に刺して舟を進める棹、しかし、それが出来ない。棹差せば山桜(「影」)を散らすことになるのではないか。「ぎょろり」には「睨む」の外に「呆気にとられて」の意がある。四首目の作者は龍丸、題は「夏夜音曲」。太夫と観客が直接向かい合う素浄瑠璃(人形や俳優を伴わないで浄瑠璃だけを語って聞かせること)が、この歌の環境には最も似つかわしく思われる。四句「汗しっぽりと」だから蚊も自然と寄ってくるのだ。
|
| 第88回 狂歌玉雲集(2) |
夜もすから十種香ならぬかうろきをほのかにそきく秋のすかりに 女 百枝
題は「虫」。二句「十種香(じしゅこう)」は十包の香木を順不同にたき、その香りを聞き分けるもの。三句「かうろぎ」は香炉木と同音の「蟋蟀(こうろぎ)」に接続する。四句「きく」は一つに聴覚、今一つは嗅覚の「聞く」をいう。結句「すがり」も同音異語で二つに分かれる。一つは秋の終わり、また衰えた蟋蟀の声。今一つは香のたき残り、余香である。
来年とおもへはをしやひいてゆく月鉾ははや西の洞院
ひとへ帯といてもあつきこのころにむすひて涼し岩間の清水は
ゆふへたいた風呂の湯もまた其(の)ままに残るあつさの汗を流さん
秋といへとあかす子供かたく花火こんやて廿日ねすみ線香
一首目の作者は豆丸、題は「祗園会」。二句切れ、「や」は詠嘆と感動の助詞である。四句「月鉾」は祇園会に下京区の月鉾町から出る鉾の名、結句「西の洞院」は西洞院通。祭りも終わり、引かれていく月鉾を西空に沈んでいく月に擬えた。二首目の作者は秀里、題は「泉」。初句の「一重帯」は主に女帯で夏に用いる。その帯を二句「解いて」も熱いが四句「結びて涼し」の謎かけは、継続ではなく、話材の転換で結句「岩間の清水」となる。三首目の作者は長丸、題は「残暑」。初句の「ゆふべ」は「夕べ」(夕方)と「昨夜」の両方が考えられる。二句は「風呂の湯もまだ」、四句の「あつさ」は湯の「熱さ」に残暑の「暑さ」を掛ける。夜に入ったとも朝に入ったとも取れるが前者で読んだ。四首目の作者は垂枝、題は「連夜烟火」。二句から三句「飽かず子供が焚く」。四句「廿日」は上の「今夜で」を受けるが句またがりで結句の「鼠」にも掛かって趣向を添える。秋は陰暦だと七月、現在だと九月で涼しさにはほど遠い。
しよう事なしにうつむきや水に又横手うつつた月のまんまる木橋
ひとつとりふたつみつよついつの間に日もたけかりの帰るさ忘れて
古手屋か裏のもやうに植(ゑ)た菊たかきて見てもようにほふとて
ひろふ人の口をとむるかしゐしゐの落(ち)る梢の秋はひそやか
一首目の作者は邊木、題は「橋上月」。初句「しょうことなし」は仕方ないこと。二句「俯きゃ」は「俯けば」。三句「横手」は脇そして「横手(打つ)」となる。結句の「まんまる」は月と丸木橋の「丸」である。橋の下に船が入って空の月は隠れたが水面に映る月に「また」手を打ち合わせたのだ。二首目の作者は袖丸、題は「茸狩忘帰」。初二句はキノコ狩りの様子、また序詞として三句の「何時(五)」へ展開した。四句は「日も長け~」に「~茸狩の」で「たけ」を共有した。三首目の作者は和水(女性)、題は「商家菊」。初句「古手屋」は古着屋。以下、二つの意味が同時進行する。二句「もやう」は「風情(模様)」、四句「きて」は「来て(着て)」、結句は「匂うとて(似合うとて)」(発音は「ニオーとて」で一致する)。四首目の作者は信女、題は「果」。二句は「口を止むるか」、続く三句は静かにするように促すときの「しいしい」に「椎椎」を重ねた。椎の実は食用、落ちてくる団栗を拾う静かな秋である。
|
| 第89回 狂歌玉雲集(3) |
小便に八たひおきぬる霜の夜は寝る間もなつよりやつとみしかい 鵺丸
題は「冬夜」。二句「八度(やたび)」は八回もしくは「何度も何度も」だろう。四句「やっと」は一方が他方をはるかにしのいでいることを強めていう語。ずっと。はるかに。八回なら連続して一時間と寝ていない。明けるのが早いとはいえ夏は尿意で悩むこともない。
おりもおり今きて見れはてうとよいころもての山の木々の錦は
けふ冬かきた風さむく羽織着りや礼服となるしものはかまて
秋のいぬすかた見ぬめの浦なれとけふより冬とふれる時雨か
ねかはくは往来をしはしととめたや上様ならぬけふのみゆきに
一首目の作者は牛丸、題は「秋山」。初句は「折も折」に「織りも織り」、二句は「来て」に「着て」で三句切れの「丁度良い」。下句は「衣手(衣服の袖)の山の木々の錦は」で倒置法となる。なお衣手の山(三重県鈴鹿市)の例歌に〈きてみらんことを頼まぬ身にしあればたちわびぬべきころもでの山〉(『夫木和歌集』八六六六)がある。二首目の作者は止母蘇、題は「初冬」。二句の「きた」は上から「来た」、下へは「北」と働く。三句「着りゃ」は「着れば」の縮約、結句は「下」に「霜」を掛ける。改まった服装を羽織袴というが、そうした共通認識が背景にあろう。三首目の作者は園生(女性)、題は「浦時雨」。初句は「秋の去ぬ」、三句「見ぬ目」は「見ないまま」だろう。これに「敏馬」を掛ける。敏馬の浦は現在の神戸市灘区の摩耶埠頭付近にあった。『古今和歌集』の〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(一六九)が思われる。四首目の作者は冬丸、題は「雪」。四句「上様」は天皇など高貴な人の尊称。結句は「深雪」と「御幸」を重ねて、足跡のない銀世界を願った。
駒とめて歌やよみけん一ところひつめの跡のふかき雪の日
せはしなき冬のひさこの念仏者六字をつつめなもたなもふた
寝耳には水と違ふて誰人のめくみかあつきかいやろの声
はき捨(て)た秋のほこりのゆくすへを見するや除夜の空はまつ黒
一首目の作者は菊丸、題は「雪」。四句は誰の「蹄の跡」なのか。〈駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野のわたりの雪の夕暮〉(『新古今和歌集』六七一)との時空を越えた交感である。二首目の作者は友丸、題は「鉢叩」。鉢叩きは鉦や瓢箪を叩き、念仏踊りを踊って布施を求めた。四句は「六字(南無阿弥陀仏)を約め」、寒いからなのか、これが「なもだ」や「なまうだ(なもうだ)」になるというのだ。三首目の作者は暁江(女性)、題は「粥遣声近枕」。二句「違ふて」はウ音便だから「違うて」である。三句「誰人(たれびと)」は不定称の人代名詞、なんびと。四句は句割れで以下「恵みか/熱き粥遣ろの声」となる。「熱き」は二句の「水」に呼応する。「粥遣ろ」は粥施行、粥施行は富者が貧者または僧などに粥を施し与えること、そのときに呼びかける常套句である。四首目の作者は一双、題は「歳暮」。煤払いの煤はどこにいったのか。これこのように「除夜の空は真っ黒」というわけで奇想の歌に分類できよう。
|
| 第90回 狂歌栗下草(1) |
腕つくにその福力をえひす様にきりこふしてまいりましたそ 岫雲亭華産
『狂歌栗下草』の撰者は岫雲亭華山、刊記は寛政四(一七九二)年である。掲出歌の題は「十日戎」(正月十日に行われる初恵比須の祭礼)。歌意は「恵比寿様の福力(福徳)を腕尽くでも頂こうと、これこのように握り拳(こぶ)して参りましたぞ」と物騒だ。囃子詞「商売繁盛で笹もってこい」の起源は確認できなかったが、今と変わらない賑わいを背景に読んだ。
山吹のさかりほとにはいはぬ色なせ菜の花は菜の花はなせ
手枕の夢はかりなる春(の)夜にかひないものしやひたりこなから
けふやさくあすやさくらの桜のとみねにこころのかかるしら雲
花の香を風のたよりにたくへてそけふは貴様をお誘ひ申(す)
一首目の作者は華産、題は「菜花」。和歌の世界で多く詠われてきた山吹に対して、同じ色でも菜の花は希少例だろう。下句は上下が対称、しかし結句は「菜の花は何故」かつ「菜の花話せ」となり、ここが味噌となっている。二首目の作者も華産、題は「春夜酒といふこころを」。初二句「手枕の夢」は「夢の手枕」(夢の中で恋しい人がしてくれる手枕。また転た寝に見る夢)を逆にした。四句は「甲斐ないものじゃ」、結句は「左、こながら」。「こながら」は「小半」また「二合半」とも書く。右で手枕、左で独酌となる。三首目の作者も華産、題は「花五十首組題よみし中に見雲待花」。雲を見て花を待つ心、花の雲は桜を雲に見立てたものだった。初二句の対句表現に始まって、言葉の斡旋が巧みである。四首目の作者も華産、題は「花の頃友を誘ふといふ詞書の探題を得て」。四句の「貴様」にドキッとさせられるが、語誌的には尊称から対等への移行期の代名詞であって卑称は含まない。だから「お誘ひ申す」なのだ。
入相の鐘はなれともこん龍寺さかりの花に人は散らさる
目をすゑて居ひたれ酒や白妙の雪とのみ花雲とのみ花
麓ならむれつつ人の来うものをあたら桜のとうけにそ有る
桜花ちりちりにけふなかれ行(く)春のかたみとみよし野の花
一首目の作者は永昌堂子賢、題は「金龍寺の花の最中に」。大阪府高槻市にあった金龍寺は桜(能因桜)の名所で、本歌は〈山里の春の夕暮来てみれば入相の鐘に花ぞ散りける〉(『新古今和歌集』一一六)となる。三句「こん」に鐘の音を託した。二首目の作者は華産、題は「花下酌酒といふこころを」。二句は「居浸(びた)れ酒」(いつまでも居すわって飲み続けること)。初句からも酔っていることが分かる。雪といい、雲といい、下句のリフレインが心地良い。三首目の作者は山口如流、題は「峠花」。本歌は西行の〈花見にとむれつつ人のくるのみぞあたらさくらのとがには有りける〉(『山家集』八七)。三句「来(こ)う」はカ変動詞「来」の未然形に意志・推量の助動詞「う」で「来よう」の意。下句、惜しいことには峠の桜であることよ。四首目の作者は紅南堂甘谷、題は「河落花といふこころを」。三句は落花に季節の流れていくこと重ねた。下句「春の形見とみ吉野の花」に句跨りで「形見と見よ」が響く。
|
| 第91回 狂歌栗下草(2) |
風の手にふとももまてもふきまくられおめこ十夜のあれいやいなあ 岫雲亭華産
掲出歌の題は「十月十日ばかり風はげしかりければ」。四句の「おめこ」は女陰の意だが、別に「御命講」(十月十三日、日蓮忌に行なわれる法会)の略、したがって表向きは御命講への参詣の図となる。下句の「あれ」は感動詞、しかし「十夜の荒れ」(この頃に吹く大風)の「荒れ」を共有する。「いやいな」は遊里語で「いやだわ」、最後の「あ」は長音を表す。
はれさうなそふりはなしにいく日ふる扨もなかやの軒の五月雨
なるかみのさはく夕たちのふる塚に俗名半兵衛おちよいやそや
秋来ても庭の荻はらししらしんこそつくものは團はかりそ
いつさよりいるさをかけてすみわたる今宵は月を丸て見ました
一首目の作者は華産、題は「五月雨」。四句「なかや」は「長屋」これに長く降り続く意の「長(や)」を掛けた。軒下には照る照る坊主を吊したい。雨の影響必至の人も多いのだ。二首目の作者も華産、題は「三昧夕立」。「三昧」は「三昧場」(墓)の略である。初二句は「鳴神の騒ぐ夕立の」、三句は「降る塚に」かつ「古塚に」となる。四句は心中物「お千代半兵衛」の亭主、女房は結句「落ちよ(お千代)」で「否然や」(いえ、そうだ)となる。三首目の作者も華産、題は「残暑」。庭は三句「ししらしん」(物音のしないさま)。ただ団扇が四句「こそつく」(こそこそと音を音をたてて動く)のみだという。〈かぜわたるにはのをぎはらそよさらになほよをあきとおどろかすかな〉(『為家五社百首』三〇一)とは逆の残暑なのだ。四首目の作者は華産、題は「見月至暁更といふこころを」。初二句は「出づさより入るさをかけて」。結句の「丸で」は一つは「さながら(そっくり全部)」、今一つは「円形で」の両意となる。
魚虎のそれよりもなをきらきらとおしろの月の本丸にして
かさふせのかさのけもない月なれはさらはをふねにさほてまいりましよ
大江山いく野の道は遠いけなこれは丹波のくりのひと枝
山々のかなたこなたとむらしくれかさきかさとりはれみはれすみ
一首目の作者は華遊、題は「金城月」。初句の「魚虎」は「鯱」(しゃちほこ)の分字。以下「城の本丸(天守閣)の金の鯱、その上には鯱さえ色あせて見える月の本丸(満月)が出ていることだ」。二首目の作者は華産、題は「月夜泛船」。初二句は暈の破れを伏せ隠した、不完全な暈の気もない、と読んだ。「きれいな満月だから、それならば、小舟に棹で参りましょう」。棹さしていく小舟と空を渡る月の船、メルヘンの世界である。三首目の作者は華産、題は「栗の一枝に歌よめと望まれて」。本歌は〈おほえやまいくののみちのとほければふみもまだみずあまのはしだて〉(『金葉和歌集』五五〇)である。初句「大江山」は「大枝山」とも書き、三句「げな」は推測または伝聞の助動詞、で「これはその途次の丹波の栗の一枝」となる。四首目の作者も華産、題は「時雨」。初句の畳語「山々」に続いて二句の「彼方此方」、四句「笠着笠取り」、結句「晴れみ晴れずみ」と対句表現の連続で三句「群時雨」を表現した。
|
| 第92回 狂歌栗下草(3) |
ことふきはとをつあふみの灘こえて磁石の針のふれよいく春 岫雲亭華産
掲出歌の題は「野口某七十賀に産業船手なれば」(産業は仕事、船手は船乗り)。初句「寿」は長命、二句「遠淡海」は「とおとうみ(遠江)」(琵琶湖の近つ淡海に対して浜名湖のある国、遠州)をいう。三句「灘」は風波やうねりが強く、航行の困難な海域。その遠州灘を越えていく船磁石の針が振れるように命も末永く「旧れよ」(正しくは「旧りよ」)と解した。
散れはこそいととさくらにまかふなり小春の空の雪のはつ花
かれ残る尾花か袖にほころひの綿かとはかりはつかはつ雪
打払ひはらへとあかき尻まてかましらに雪のふりもやまさる
宇治かつら木津となかれは隔(つ)れとおつるはおなし淀川の水
一首目の作者は峯果亭栗桴、題は「十月初雪といふこころを」。本歌は『伊勢物語』の〈散ればこそいとど桜はめでたけれ憂き世になにか久しかるべき〉(八十二段)である。下句の観念性を払拭して「小春」(陰暦十月の異名)「雪」「はつ花」と桜に代わる豊かな景色を提示してみせた。二首目の作者は香果亭栗芳、題は「初雪纔(わづか)」。二句「尾花が袖」は尾花が風に靡くさまを人を招く袖に見立てたもの、そこから三句「綻びの」以下が展開する。結句の「はつ」のリフレインが美しい。三首目の作者は東果亭揚栗、題は「猿払雪」。四句「ましら」は上からだと「真白」、下へは「猿」、ポイントが切り替わる同音異語なのだ。結句に「山猿」が隠れている。四首目の作者は好果亭栗埜、題は「淀のわたりに出(で)て」。本歌は貞柳の〈道心者浄土法花とへだつれどおつるはおなじ谷町のうら〉(『続家つと』)である。寺の多い谷町の裏は遊里であった。その人間臭さに対して三川合流は観念的というか道歌臭い。
似我蜂とあちらこちらの親心われに似すともよき人に似よ
大仏の鐘にうらみはこんすまい花にも恋にも邪魔にならねは
よしあしやみなそれそれのすくの道横に行(く)のも横ならぬかに
白粥の三粒の豆をかきつくりいくよゐさなきいくよゐさなみ
一首目の作者は山本立志、題は「悴を教訓に」。初句「似我蜂」命名の由来は獲物を運ぶときの羽音をジガジガと聞いた昔の人が、それを他の虫をハチに変える呪文と考えたことに始まる。下句が道歌っぽい。二首目の作者は華産、題は「方広寺にて」。初句、方広寺は通称大仏殿と呼ばれた。三句の「ごんす」は「ある」の丁寧語、これに鐘の音を重ねた。助動詞「まい」は否定的に推量する意を表わす。徳川家康が鐘銘に難癖をつけた、あの鐘である。三首目の作者は華産、題は「芦に蟹の図に」。初句は定番の植物名に「善し悪し」を掛けた。結句は①「横ならぬ蟹」、②「横ならぬがに」(副助詞「がに」は横ならぬ「かのように」)となる。四首目の作者は華産、題は「新宅祝」。『古事類苑』の飲食部六赤小豆粥に「三島明神の氏子伊豆の豆と三島の三を象りて、豆三粒入る」とある。初二句の出所だろう。また「わたましに赤豆粥を煮て祝ふ」ともある。以下、オリジナルの「垣作り幾代いざなぎ幾代いざなみ」が快い。
|
| 第93回 興歌野中の水 |
片うてをとられたやうにかなしかろ此世の綱のきれしおはさま 九如館鈍永
『興歌野中の水』の撰者は山田繁雅、刊記は寛政四(一七九二)年。掲出歌の題は「帰葉のぬしの伯母なりける人身まかられしよし聞(き)侍りて渡辺にたとふるもなにとやらんはばかりなきにしもあらねど失(せ)にし人も親にひとしければ武門の栄を蒙らせたからんままゆるし給へと書(き)て」。「渡辺」は源頼光の四天王の一人、渡辺綱(九五三~一〇二五)で、苗字は養母が摂津国渡辺に居住したことに拠る。鬼の腕を切り落とした逸話を上句で使い、人名を普通名詞の「綱」(ロープ)に戻して絆とした。結句の「伯母様」が出色である。
春蒔(い)てはこふ手なつちあしなつち養ひえたるこの稲田媛
方円の器のなりにしたかふて水にちよつほり、(テン)のなすわさ
かうて有つたああて有(つ)たとともすれは思ひそいつる其人のくせ
鈍永の作が三首続く。一首目の題は「秋田」。二句「手摩乳」は素戔嗚尊が出雲で八岐大蛇を退治した後結婚する奇稲田姫の母親、三句「脚摩乳」は父親である。結句「稲田媛」のためには労苦を惜しまないことの見立て、水田だから「手な土」「足な土」だろう。二首目の題は「氷」。上句は成句「方円の器に従う」(水は容器次第で四角にも丸にも形を変える)をいう。四句「ちょっぽり」は「ちょっぴり」、続けて「水」に読点のルビ「テン」で「氷」、これも三句「従うて」の範囲というのだろう。三首目の題は「懐旧」。初二句「こうであったああであった」も三句「ともすれば」(放任しておくとそうなる傾向)下句「思ひぞ出づるその人の癖」に落ち着くという。大事ではない、小事の中にこそ故人現出のリアリズムが潜むのだ。
潮干には乗(り)ものやめて奥方の遊ひもしやれた貝をおひろひ
酔ふ目には梢も雪と思はるれ四五盃まては花てあつたか
目かねにも姿は見えすほとときすこゑは左右の耳にかけても
ちつぽけれ粽はやるもまく芦の葉はかりおほく思はれそする
以下、「附録」で鈍永以外の作品が続く。一首目の作者は吾元、題は「汐干」。駕籠を常用する貴人の潮干狩りである。結句の「御拾ひ」は歩くことを敬っていう女房詞だが、文脈上は「御拾ひなさい」の略となる。下句も奥方の遊びが洒落た「貝」なのか「御拾ひ」なのかによって変わってくる。二首目の作者は踈慵、題は「花見に罷り酒酔におよびて詠(む)る」。「詠(む)る」は詩歌を作る意の「詠(なが)む」の連体形である。結句は倒置法で「花であったが」。酔うにつれて花の輪郭が崩れて色だけになっていくのだ。三首目の作者は蘆角、題は「郭公両方」。片や「眼鏡にも姿は見えずほととぎす(蔓を)左右の耳にかけても」で視覚、片や「(略)ほととぎす声は左右の耳にかけても」で聴覚(「耳にかけても」は「聞く」意となる。「も」のあとは言い止しである)となる。四首目の作者は吟楽、題は「端午に粽を贈るとて」。挨拶歌であるが初句に注目した。「ちっぽい」は口語、しかし「ちっぽし」は聞かない。これぞ文語と口語の混用例であろう。「粽は遣る(届ける)も巻く芦の葉ばかり多く思はれぞする」。
|
| 第94回 興歌野中の水(2) |
もかみかわなみとよのなかはやきときやはか名の世とみな我身かも 素行
掲出歌の題は「はかなの世といふ事を隠し題にして回文歌に詠(む)る」。〈最上川波と世の中早きときやはか名の世と皆我が身かも〉。隠し題は四句の「はか名の世」(儚の世)である。「やは(わ)か」は反語の意を表す。初句の「川」(かは)が新仮名だが気にしない。上出来の回文歌である。歌意は「最上川の波のように激しく移り変わる世の中にあって、人は皆、名世を思ったりもするが、どうして波に呑み込まれない我が身であるだろうか」と解した。
さつき闇ほたるの照らす東山時代なし地と見ゆる也けり
くつさめの出て来さうなる涼しさやそしる人さへなきいほりにも
籠なれて逃(げ)うともせぬ五十雀は天命をしる鳥とこそみれ
住む籠の長月の空こひしかろ木の葉色つく秋の山から
一首目の作者は桟治、題は「洛東蛍」。四句「梨子地」は蒔絵の一種、上から読むと時代蒔絵、時代蒔絵は東山時代をいう。「梨子地」は空に舞う夜火事の火の粉の形容でもある。二首目の作者は湖月、題は「閑居納涼」。初句「くっさめ」は「くさめ」の促音化である。下句からすると嚔と噂の慣用句「一褒め、二謗り、三惚れ、四風邪」の類が行われていた形跡である。三首目の作者は維石、題は「篭中秋鳥」。二句「逃(げ)う」は「逃ぐ」の未然形に助動詞「む」の変化した「う」か付いた。発音は音節が融合して「にぎょう」となる。下句「天明を知る鳥とこそ見れ」は「私」にはそう見えたということに過ぎない。四首目の作者は季隆、題は同じく「篭中秋鳥」。二句「長月」は陰暦九月の異称、これに籠で飼われる長さを暗示した。四句と五句を倒置、体言止めの理由の一つは「山から」に「山雀」を重ねるためであった。
さひしさはいつくも同し其(の)中になをすまふ場の秋の夕くれ
落葉にもああ忠臣の名は朽(ち)ぬ石となりたるくすの木の塚
わんはくな子供かよりて雪こかしつい手にあはぬものと成(る)へし
御狩する狩場の空は鳥の毛をむしつたやうに雪そふりける
一首目の作者は度量、題は「秋夕」。本歌は〈さびしさはいづくもおなじことわりにおもひなされぬあきのゆふぐれ〉(『続古今和歌集』三七四)だろう。自らの淋しさを他と同列視できないのである。掲出歌はそうした特別視と無縁で、一例だが副詞の「直」で「ありきたりの相撲場」を加えた。二首目の作者は幸竹、題は「湊川にて凩のはげしかりければ」。楠正成の塚は元禄四(一六九一)年、徳川光圀によって碑石が建立された。歌われたのは百年後、この地に湊川神社が創建されるのは明治五(一八七二)年である。三首目の作者は机向、題は「子供の雪こかしするをみて」。三句は「雪転」と書く。雪の上で雪の玉を転がしている。二句「寄りて」は複数、それだからこそ次第にコントロールできない存在となる気配なのだ。四首目の作者は菊二、題は「狩場雪」。初句「御(み)」は接頭語、狩の美称だろう。二句「狩場」は鳥獣を狩る場所。鉄砲か、鷹か、いずれにしろそのイメージを引き摺った奇想の歌である。
|
| 第95回 狂歌泰平楽 |
煤とりて破れ障子のそこや爰はるをまつ下禅尼しやなけれと 玉雲斎貞右
『狂歌泰平楽』の撰者は市中庵時丸・旧路館魚丸、詠者は玉雲斎貞右、刊記は寛政四(一七九二)年である。掲出歌の題は「歳暮」。四句「はる」は上からは「貼る」、下へは「春」、「まつ」は上からは「待つ」、下へは「松」となる。その松下禅尼は鎌倉幕府第五代執権北条時頼の母。手ずから障子の切り張りをして、子の時頼に質素倹約の手本を示したという逸話が『徒然草』第百八十四段に見える。結句「しや」(ぢゃ)は「では」の変化したものである。
人の親の心はやみにあらねとも子ゆへに提燈もつてちやうさよ
ととんとと太鼓かなる戸のうら盆は渦かまい夜さ踊(る)かありやありや
うふかみをたれか種ともしら露のまたちちくさの中に捨(て)子は
中そらは星稀にして下界には月見る人の目玉きらきら
一首目の題は「御霊宮夏神楽の夜参詣の往来を見て」。本歌は〈人のおやの心はやみにあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな〉(『後撰和歌集』一一〇二)。子故の闇ではないが提灯を持つ親が多い。これを山車などを引くときの掛け声「ちょうさよ(うさ)」で囃した。二首目の題は「海辺踊」。初句は「ととんどと」か。二句「鳴る」に「鳴(戸)」、三句「盂蘭(盆)」に「浦」、四句「毎」に「巻い」で「夜さ」は夜をいう。結句は踊りの掛け声だろう。三首目の題は「秋野捨子」。初二句は「産神を誰が種とも」、三句は「白」に「知ら」を掛けた。四句の「乳草」は茎や葉を切ると乳のような液を出す草木をいう。捨てることに活路を託したのだろう。四首目の題は「八月十五夜」、中秋の名月である。今は昔、中天からの眺めを詠った。すなわち「下界には月見る人の目玉きらきら」で「中空は星稀にして」の由縁なのだ。
けふよりは冬きた風に紅葉葉の五つのゆひもひひにいたまん
湯へ入(り)にきた時雨かや有馬山ぬれてはあかりあかつてはぬれ
つく人も臼取(り)もみなすまふ取(り)餅もつよふていつれおとらし
豆よりも雨にうたれて鬼はさそふとしぬらさんとらのかはいや
一首目の題は「十月朔日」。二句「きた」は「(冬)来た」に「北(風)」。三句「紅葉」はカエデの別名で、その葉は手のひら状をしている。秋になると紅葉するが(本歌は二十四節季で冬、今なら十一月初旬であろう)、これを擬えて「五つの指も皹(日々)に痛まん」とした。二首目の題は「湯山時雨」。有馬温泉の古称を「湯山」(ゆのやま)という。下句は、降ったり止んだりする時雨を、入浴を繰り返す湯治客の姿に重ねた。三首目の題は「角力取餅搗」。初句は餅を「搗く人」、二句「臼取(り)」は臼のかたわらで餅をこね返す人、四句「餅も強うて」は粘りのあること、結句の「じ」は打ち消しの推量となる。力士も餅も強くて、どちらが劣るということもないだろう、と解した。四首目の題は「節分の夜雨のふりけるを」。三句「鬼はさぞ」、四句「ふどし」は「ふんどし」(褌)の音変化で、それを「濡らすだろう」。結句は「虎の可愛や」。鬼の褌は虎の皮だが、鬼ではなく、その褌の虎を不憫と同情しているのだ。
|
| 第96回 狂歌拾葉集 |
売(り)あけの銭ならなくにせせ貝をつなく二見の春雨の頃 在丸
『狂歌拾葉集』の撰者は一静社草丸、序文及び跋文は寛政六(一七九四)年である。掲出歌の題は「浦春雨」。三句「ぜぜがい」(銭貝)は巻き貝で殻は貝細工の材料となる。『日本国語大辞典』の用例にも「ぜぜ貝つなぎ」「おみや召せ召せ、二見ぜぜ貝伊勢わかめ」「戯に此介を銭となす」等が見える。外は静かに降る雨、売上げとなる土産物作りの現場である。
こころよやこしの海辺をやはやはとさするやうなる春の風の手
春雨にゑほしもゆるむ大あくひ紐もしめしめふるのみやつこ
疱瘡子の襦はんの袖の長町にかきやふつて出たみつちや笋
昇殿をゆるすゆるすとゆふ間くれ蛍をまねく笏や桧あふき
一首目の作者は百丸、題は「海辺春風」。初句は形容詞「快い」の語幹に詠嘆の「や」。二句「越の海辺」は北陸地方の海辺で、「越」に「腰」を掛けた。下句は「摩るやうなる春の風の手」で風の按摩仕立てとした。二首目の作者は嶋丸、題は「社頭春雨」。四句は「紐も締め締め」、下へは雨も「じめじめ(降る)」となる。その結句は「古(の)宮子」、「古」は形容詞の語幹と解した。「宮子」は神官である。三首目の作者は女性で暁江、題は「市中笋」。初句「ほうそご」は疱瘡にかかっている小児、その長襦袢から地名の長町(大阪市)を呼び出した。下句は「掻き破って出たみっちゃ筍」、「みっちゃ」は疱瘡の跡(あばた)また筍の異称である。なお竹の縁でいえば篠竹を短く切って作った管襦袢があった。四首目の作者は百丸、題は「禁中蛍」。殿上人に対して地下の蛍という設定である。三句「言う(間ぐれ)」に「夕間暮れ」となる。結句は男が威儀を整える「笏」で、女は開いて持つ「檜扇」で蛍を招く姿である。
妹と背の中も隔(た)るあつき夜にひつ付(く)ものは寝こさはつかり
かは太郎もあたまの水かこほるるとはさらに思はて月に見とれん
見わたせはてんかう書(く)子もなかりけり蔵の戸前の秋のゆふ暮
わたし舟早うさせてふきりきりすむかふも乗(る)人まつ虫の声
一首目の作者は魚丸、題は「強暑」。夫婦は体温の感じられる距離には近づかない。溝ではない。暑さのせいなのだ。したがって二句「隔たる」と読んだ。その結果、汗だろう、引っ付くのは寝茣蓙ばかりなのだ。二首目の作者は艸丸、題は「月」。初句「河太郎」は河童の異称、四句の「さらに」は副詞で「少しも」「全然」の意、これに「皿に」を掛けて空想の月夜に遊んだ。三首目の作者は玉雲斎、題は「秋のゆふべ家居にありてつれづれなるままよめる狂歌三首」。悪戯書きを「てんごう書き」という。これを動詞にしたのが二句である。三夕の和歌を倣ったものだが一首目は〈誰にかもあくひうつさん友もなしわれのみ口をあきの夕暮〉、結句が「空き」に「秋」である。四首目の作者も玉雲斎、題は「渡場虫」。初句は「渡し船」、二三句の由来は〈秋風に綻びぬらし藤袴つづりさせてふきりぎりす鳴く〉(『古今和歌集』一〇二〇)の「させてふきりぎりす」だろう。結句「まつ」は「待つ」に「松」となる。
|
| 第97回 狂歌拾葉集(2) |
てうとうけてかなはぬ時はちよつと出て助たちたのむ酒のかたきに 玉雲斎
掲出歌の題は「妻なるものの予がいたく酒を好(み)けるをいさめて御身のため酒をかたきとしてしらずなど戴くぞともにてんもくとなんよみけるかへし」。妻の歌は〈御身のため酒を敵として知らずなど戴くぞ共に天目〉。「天目」は「天目茶碗」のこと、夫婦で茶碗酒を楽しんでいたのだろう。御身を思えば酒は敵、どうして今までのように相伴できるだろうか。返歌の初句は「丁と受けて」、敵の太刀を「はっしと」受ける場面。二句以下四句「敵わぬ時はちょっと出て助太刀頼む」。結句は「酒を敵」(贈歌)から「酒の敵」にして妻の懐柔を試みた。ちなみに「丁と」は副詞だが、接尾語「丁」は酒樽などを数える助数詞である。
さむき夜に手足の赤うちちんたは執行にいてたたこ坊主さま
布の名の下腑あたためんと薩摩芋のぬくぬくを喰ふ毎夜鷹達
王城の地をふんてのふすての事極楽世界へ生れふとした
一首目の作者は恒丸、題は「寒夜僧」。三句「縮んだは」、四句「執行」(しゅぎょう)は「修行」と同じで行脚をいう。「いてた」の「いて」は促音の省略で「行て」(行って)、「てた」は「ていた」の変化である。二首目の作者は玉雲斎、題は「辻君薬喰」。ここでいう「薬食い」には栄養になるものを食べること、そして交合の意味を含む。初二句「布の名の下腑」の布とは「花布」、印花布また更紗をいう。「下腑」は下腹だろう。結句は「夜」を上下に使って「毎夜」と「夜鷹達」である。三首目の作者は女性の菅江、題は「長月のころ都にありて風の心地とていたづき侍りける心地しぬべくおぼえけるも少しねつさめ心よくなりぬるふしよめる」。初句「王城」は都、二句は「地を踏んでなう」、三句は「すでのこと」(もう少しで)、結句は「生まれうとした」。つまり初句「王城」は「往生」と同音ゆえの選択だった。
入舩はうはか上荷のいそかしくししうにやくのあるそめてたき
嬉しさを何といひわんもる乳母かくくめる口もあけてふたつふ
さつかつた五重にことし又五十百はたしかにいきによらいさま
一首目の作者は女性の菅江、題は「舩長なりける人の四そぢ二ツを寿(ぎ)て」。二句「うはか」は『大阪ことば事典』(講談社学術文庫)の「上側」(うわかわ)の約に拠った。四句は「始終荷(役の)」に「四十二」を掛けた。二首目の作者は蟹丸、題は「ふるとし末に出生しける孫なるものの喰ひ初(め)に」。食い初めは生後百日目に行われる祝いごと、二句「飯椀」に「祝はん」を掛けた。四句「くくめる」は「口に含ませる」意、結句の「二粒」がいい。三首目の作者は玉雲斎、題は「土井氏の母なる方過(ぎ)にし年仏法僧のみつのおしへを請(ひ)伝へおはしけると聞(こ)えしに今年なんよはひ百の半(ば)に満(つ)るとて蟹丸の主寿筵をまうけ給ふけるに」。副詞「半ば」は「ほとんど」の意、結句は「生き如来さま」(五十年は人の寿命)。これに対する蟹丸の「かへし母にかはりて」は〈ありがたいといただくかれましよ五重より百はたしかなことぶきの歌〉。四句は不明だが「頂かれましょ」と解した。
|
| 第98回 狂歌得手かつて |
敷島の道にも少し違ひありきやうかいとうとわかさ街道 玉雲斎貞右
『狂歌得手かつて』の撰者は凡鳥舎虫丸、刊記は寛政六(一七九四)年、貞右は四年前に五十七歳で亡くなっている。掲出歌の題は「有心体と無心体はいかなる違ひと人の問(ひ)けるに」。四句「京街道(きやうかいとう)」に「狂歌」、結句「若狭(わかさ)」に「和歌」を隠す。狂歌は無心体というのだが、こうした分類に毒されてきたのが外ならぬ狂歌史なのだ。
音羽山みねは夕立にあふ坂の関のこなたはきろりくはんくはん
秋の夜も夢はかりとや肱尻をかこからちよいと出すきりきりす
片意地な氷も春にやはらきて器にしたかふ今朝の若水
猿引(き)に出合(ひ)ておかし初礼者行義姿てしやんとせいこりや
一首日の作者は貞右、題は「山中白雨」。初句「音羽山」は京都市と滋賀県の境にあり、北は逢坂山に連なる。三句は「(夕立に)逢ふ」と「逢坂の(関)」、関所のこちらは太陽が「ぎろりかんかん」と解した。二首目の作者も貞右、題は「夜(䒑+𤼭)」。本歌は周防内侍の〈春のよの夢ばかりなるたまくらにかひなくたたん名こそをしけれ〉(『千載集』九六四)。これは枕にと御簾の下から自分の腕を差し入れた男に対する歌だが、掲出歌は逆に籠から肘や尻を出す。二句「とや」は間い返しの意で「というのだな」。三首目の作者は凡鳥舎虫丸、題は「若水」。四句は成句「方円の器に従う」、水のことをいうが、水だから初旬「片意地」となる。三句「和らぎて」は溶けて若水、新年の祝歌である。四首目の作者は白雲洞逸木、題は「早春」。初句は猿回し、三句「初礼者」は年賀に歩く人、四句の「行儀姿で」は頭を低くしたところだろう。以下、猿紐の先で落ちつかない相棒に「しゃんとせいこりゃ」と声をかけている。
よい麁物してもらふたと道すから丁稚はひちをはるのやふ入(り)
此(の)寺の羅漢のさまかしら梅のにほひに人もいろいろの顔
さひしさにひとつ野守かとつくりをふれと音なき春雨の頃
ゆふへいそく月と違ふて春の野はすつほんの酒に暮(れ)おしまるれ
一首目の作者は松根堂呉丸、題は「藪入」。初句「麁物」(そぶつ)は盆暮れに主人から奉公人に与える衣類などをいう。結句は上から「(肘を)張る〜」(得意そうに振る舞う)、下へは「春の藪入り」となる。麁物は襦袢であろうか。二首目の作者は凡島舎虫丸、題は「寺中梅」。二句は「羅漢の様か」、三句は「知ら(梅の)」に「白梅の」となる。下句「梅の匂ひに色々の顔」に五百羅漢を重ねて出色である。梅と五百羅漢像で知られる寺なのだろう。三首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「野亭春雨」。「野亭(やてい)」は野中の小屋をいう。この「野守」は立ち入りを禁じられている野原の番人だろう。慰めてくれるのは「一つ」徳利だが空そして音なく降り続く春雨なのだ。四首目の作者は凡鳥舎虫丸、題は「野遊」。成句「月とスッポン」(二つのものがひどく違っていることの喩え)が思われる。但し四句の「すっぽん」は酒を入れる容器で、比較されるのは空を急ぐ月そして暮れていくのを惜しむ野遊びの人である。
|
| 第99回 狂歌得手かつて(2) |
ます水になかれのさとや溝板もうほうほになるさみたれの頃 蔦葉軒軸丸
掲出歌の題は「花街五月雨」。初句は「増す水に」、二句「流れの里」は流れの身である遊女のいる所、遊里である。四句は「うぽうぽ」(「うぼうぼ」とも)で、水面に物が浮かび漂うさまをいう。二句の助詞「や」は詠嘆、また並列の「や」でもあろう。後者を受けて三句の助詞は「も」となる。比喩だが、実際にも、この雨では客足が遠のいたかも知れない。
爰の花はやつはり花とよんていのあちらては雲こちらては雪
しける葉に昼さへくらうすま明石いつも月夜のやうに思へと
お住持もとんて起(き)ぬる時鳥にころり寝釈迦はほんに仏しや
もうあとはきかいてもよいほとときすそれて男かたつた一声
一首目の作者は凡鳥舎虫丸、題は「花処々」。三句は「詠んで」、「いの」は「帰ろう」(『大阪ことば事典』)。取材は歌人の桜狩りと解した。初句「爰」は場所、四句「あちら」と結句「こちら」は散在する人を表す。雲や雪は桜の花の見立てである。二首目の作者も虫丸、題は「浦新樹」。二句「くらう」は「暗く」のウ音便で四句にかけて「昼さへ暗うす(ま明石)」、三句「須磨明石」は風光明媚をもって知られ、月の名所でもあった。三首目の作者も虫丸、題は「寺院郭公」。初句「住持」は住職、これに接頭語の「御」が付いた。枕詞としての時鳥は「飛ぶ」にかかる、二句の「飛んで」がそれである。四句「寝釈迦」には寝釈迦仏と人の横臥する姿の両意がある。結句は寝釈迦仏を助詞「の」で分断して前者だといっている。四首目の作者は不朽軒蔦丸、題は「男達聞時鳥」。二句「聞かいでも」の「いで」は「ずて」の転、現代語の「ないで」に相当する。下句は「男が立った」に「たった一声」が重なる。時鳥行なのだ。
おらんたのもしの関かとゆふ間くれ輪になつて出る蚊遣りの煙は
きのふまて抱(い)て寝たのも秋風てけふはいとまをやる竹夫人
とこもかもめてたかり穂にほう作て思ひ出された去年の大雪
いくとせかふるの都は枝高く今は名のみとなつた御所柿
一首目の作者は鷺燕堂塵丸、題は「関蚊遣火」。二句は「文字の関」で「文字」は門司の古称、上代に関所があった。三句「ゆふ」は上からは「言ふ」、下へは「夕」。オランダ文字のように輪になって出る蚊遣りの煙なのだ。二首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「立秋」。結句「竹夫人」(ちくふじん)は寝間で暑さをしのぐために用いる竹の籠。抱いたり足を乗せたりする。秋になったので御払い箱、何とも思わせぶりな歌である。三首目の作者は凡鳥舎虫丸、題は「秋田」。二句の「めでた」は「めでたい」の語幹に「芽出た」の字を当てて秋の「刈り穂」と続く。祝い歌の趣きだが、そういえばと下句が出てきたのだろう。雪は豊年の瑞なのだ。四首目の作者は不朽軒蔦丸、題は「旧都柿」。『後撰夷曲集』にも〈ならの京の時分からこそ出来つらめ今に大和の御所柿といふ〉がある。御所柿は奈良県御所(ごせ)市の原産、しかし「ごしょがき」だからロマンを掻きたてられるのだろう。結句に柿が「なった」残像を引く。
|
| 第100回 狂歌得手かつて(3) |
ふりさけ見る月やは物を思はする西行の事仲麻呂の事 如臍軒虹丸
掲出歌の題は「見月思故人」。西行(一一一八~一一九〇)に〈なげけとて月やは物をおもはするかこちがほなるわが涙かな〉(『千載和歌集』九二九)、阿倍仲麻呂(六八〇~七七〇)に〈天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山にいでし月かも〉(『古今和歌集』四〇六)がある。上句で各々のフレーズを用いているが、「百人一首」で身近な二人だったと思われる。
横町からそりや又ふつてきた時雨かつく袖笠ひちまかる辻
あたつてねやといはれた火燵めつそうな朝まて心よいのままたき
雨てさへしらぬわら屋の雪の朝出て見よとてか下折の音
よろこふはよけれと雪にあし跡をつけ行(く)犬のあの畜生め
一首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「市中時雨」。初句は「よこちょから」で六音、三句の「きた」は「来た」に「北」を重ねた。四句「被く袖笠」は袖を頭上にして雨を凌ぐこと、結句「肘曲がる」は鉤の手に折れ曲がる、横丁から袖笠で飛び出して辻を直角に曲がったのである。二首目の作者は凡鳥舎虫丸、題は「下女埋火」。初句「寝や」の「や」は「やれ」の略。三句の「滅相」はある筈のないさま。結句の「よい」は「(心)良い」と「宵(の飯炊き)」を重ねた。三首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「雪」。初二句は成句「藁屋の雨」(藁葺きの家に降る雨)を使った。音のしないことの喩えである。雪なら尚更で四句「とて」は「といって」、茎か枝が雪の重みで折れる音がしたというのだ。四首目の作者は虫丸、題は「雪」。足跡のない銀世界を選りに選って、というのだろう。しかし犬に「あの畜生」(「あの」が変化して「あん畜生」)も可笑しい。童謡「雪」の一節「犬は喜び庭駈けまわり」が思われる。
浜辺うつ波のつつみを住よしのお庭かくらのこたまかときく
をきくされといはれたむかし恋しやな親父さまとははらか立役
子供の時のはなし肴にのむ酒もちつく竹馬の友しら髪同士
にこりなき世は住よしのそり橋のうつりて丸く和合した迄
一首目の作者は蔦葉軒軸丸、題は「住吉に詣てて」。大阪の住吉大社である。四句「庭神楽」は舞台を設けないで庭に篝火をたいて奏する神楽をいう。二句「波の鼓」は打ち寄せる波の音の比喩、これを神楽の谺と見立てた。二首目の作者は不朽軒蔦丸、題は「歌舞伎役者思昔」。初句「措きくされ」の「措く」は中止する意、「腐る」は補助動詞で人の動作を軽蔑する意を表す。結句は立役、敵役、老役に擬して「腹が立役」とした。三首目の作者は蔦丸、題は「老人酒宴」。四句の「ちっく」は「ちっくい」(小さい)の語幹、「ちっくちく」で少しずつするさま、句またがりで「竹馬の友」を重ねて結句の「友白髪同士」となる。共白髪は夫婦が一般的だが、ここは幼馴染みとした。四首目の作者も蔦丸、題は「寄丸物祝」。二句「住」は初句を受けて「清」、「世は」で「住み良し」を含意する。住吉大社の反橋が水面に映って丸く、実際は楕円形だが、それに取材した。結句「した」は動詞に名詞の「下」を掛けた。
|