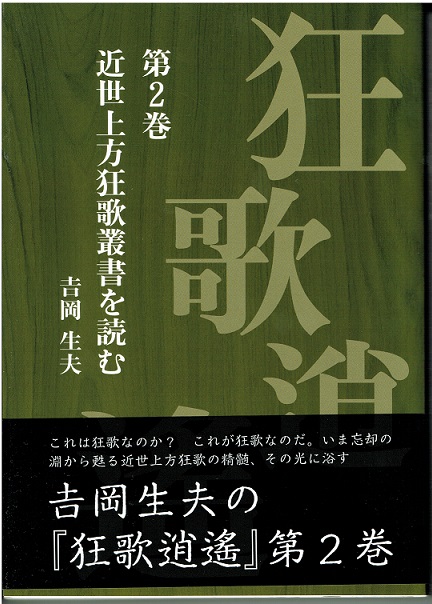| 近世上方狂歌叢書を読む |
| 「狂歌逍遙(第2巻)」より続く |
| 第101回 狂歌芦分船 |
人もなひく何てもかても青柳のみとりよりとり十九文店 謹度亭有節
『狂歌芦分船』の撰者は園果亭義栗、刊記は寛政七(一七九五)年である。掲出歌の題は「商家柳」。「人も靡く何でもかでも青柳の緑」は変だが、まだ「商家柳」を離れていない。しかしその四句が転回点で「みとりよりとり」を並べ替えると「選り取り見取り」となる。結句は種々の雑貨を十九文均一で売る店をいう。さしずめ江戸時代の百円ショップなのだ。
くる春の座附の膳は雑煮にて七五三まて揃ふしめ縄
注連縄のまへたれかけの門松はけふきた春かめみえ姿か
くしけつるやうに氷も春風にさらさらとける青柳の橋
春といへとさえてとこやらまた冬のおもかけ山に残るしら雪
一首目の作者は時女、題はない。二句「座附」は宴席で最初に出る飲食物をいう。四句「七五三」は「七五三の膳」(本膳に七菜、二の膳に五菜、三の膳に三菜を出す盛宴)の略また「注連縄」の異称である。その「〆」をもって結句とした。二首目の作者は緑水庵如川、題はない。上句は門松に飾った注連縄を奉公人の前垂れ掛けに見立てた。下句も擬人化で「目見え姿か」、「春」(主人)の前に出て初めて挨拶する朝なのか、となる。三首目の作者は春雨亭麦秀、題は「橋辺氷解」。柳の細く、しなやかに垂れる枝を「柳の髪」という。同様に女性の長い髪も「柳の髪」(柳髪)という。初句の縁語「梳る」は、これを川の氷に適用、副詞「さらさら」で本家の柳にもどして風景を結着させた。四首目の作者は栗枝亭蕪園、題は「山残雪」。二句の「冴えて」は冷え込んで、また冷たく感じるほど澄んで、その両方だろう。四句「面影山」は鳥取市にあったといわれる山だが、ここでは三句から続く「冬の面影」でもあろう。
爪に火をともす銭屋の梅(の)花一りん二りんあらそふて咲(く)
乗(り)かけの馬の耳ならともかくもふくな春風はなのあたりを
千本の数はわかてもみよし野や一目につつく山なりの花
山吹のいはぬといへとなく蛙こゑの色にや井手の玉川
一首目の作者は栗山亭如園、題は「両替屋梅」。初二句は成句「爪に火を点す」(蝋燭の代わりに爪を使う意から極端に倹約すること)で「銭屋」を呼び出す序詞とした。下句の「りん」は「厘」に「輪」を重ねた。二首目の作者は仮楽亭四綱、題は「馬上見花」。二三句の印象から結句「はな」に「鼻」を想定するが、これは作者の悪戯、成句「馬耳東風」「馬の鼻向け」も後押しをするが四句「吹くな」からも「花」(桜)に落着するのである。三首目の作者は栗枝亭蕪園、題は「花のうたよみし中に」。二句「分かねど」の「分く」は判別する、結句「山なり」は山形をいう。吉野山の観桜に絶好の場所を「一目千本」というが、これを逆手にとった作品である。四首目の作者は栗箕亭芦園、題は「蛙」。初句「山吹」の「くちなし色」から「口無し」で「言わぬ色」を導く。四句は「声の色にや(あらん)」の略と思われる。取り合わせを背景として「蛙は山吹の声色で鳴いているのではないか」と解した。
|
| 第102回 狂歌芦分船(2) |
御心にかけて給はる郭公一しほまれにきいて賞翫 栗子亭箕園
掲出歌の題は「郭公を塩に漬(け)て送られしに」。塩鳥としての時鳥である。下句の「一しほ」は①「一入」(他の場合と比べて程度が一段と増すさま)に②「一塩」(塩漬けの鳥)を掛けた。これに続く部分だが、めったに見られないことを「稀に見る」という、時鳥は見るものではなくて聞くものだから「稀に聞いて」とした。それにしても驚きの一品である。
洗ふては鯛も綿ぬく衣かえけふ袷より身につくはこれ
医者殿の薬とともに夏くれはあはせ加減もよい衣かへ
皆遊ふ牡丹の花の色里に獅子はとこしやのたはむれも有(る)
親の思ふやうには行(か)ぬいけ垣の夜の間に外へ出(づ)る竹の子
一首目の作者は園果亭義栗、題は「四月朔日肴をたうへて」。四月一日は衣替え、この日から綿入れの綿を抜いて袷となる。二句「鯛」の場合は「腸抜き」で同音異語となる。ちなみに衣替えは「綿抜きの朔日」また「綿抜きの祝い」ともいった。二首目の作者は橘園亭奇慄、題は「医家更衣」。薬の「合はせ加減」(調合)は評判であるが、夏到来「医者殿」の「袷加減」(袷仕立て)も涼しい衣替えである、か。四句「あはせ」で医家と更衣を重ねた。三首目の作者は義栗、題は「華街牡丹」。二句の「牡丹」は遊女をいう。だから「花」も顔負けの「牡丹の花」であり、下へは「花の色里」となる。四句「獅子」は「獅子に牡丹」の配合のよさから「どこじゃ」と戯れたのである。結句は「有り」「有る」の二者択一だが、安定感を生む連体止めで読んだ。四首目の作者は春雨亭麦秀、題は「垣根笋」。上句の流れからいえば結句は「出る男の子」だろう。それを「竹の子」にずらして笑いの中に共感の輪を広げた。
おさな子のもりを片手に苗片手跡しよりこしよりて植(ゑ)る早乙女
鳥の音とともに声して早乙女かうたふも同しいなのめの空
ぬれもしつ泥にふしたつ早乙女の足もなえるや雨の植付(け)
雨雲のちきれちきれの田植(ゑ)うたけふのはれにそ揃ふ一ふし
一首目の作者は栗山亭如園、題は「早乙女」。四句は「跡じょり腰よりで」と読んだ。「あとじょり」は「後じさり」の変化した語、後退しながらの作業なのだ。「腰より」は初句「幼子」を負んぶして「守り」をしている姿を重ねた。二首目の作者は緑水庵如川、題は「暁田植」。初句「鳥の音(ね)」は鳥の鳴き声とりわけ鶏の鳴き声をいう。結句「いなのめの空」は明け方の空である。ただ鶏鳴だけでは「空」という広がりのある言葉が生きてこない。田植え歌に和するように塒を飛び立つ小鳥たちを配したい。三首目の作者は初牙斎無口、題は「雨中田植」。二句「ふしたつ」は「節立つ」と読んだ。通常は苗などの茎がのびて節が現れることをいうが、縁語ないし見立てとして早乙女の足と解した。四句の「萎える」も同様で、寒いのだ。四首目の作者は栗左亭瓜園、題は「雨後田植」。二句の「ちぎれちぎれ」は初句の「雨雲」にも三句の「田植え唄」にも掛かる。その両方が解決して下句「今日の晴にぞ揃ふ一節」なのだ。
|
| 第103回 狂歌芦分船(3) |
合法の辻に閻魔は御座れとも此(の)涼しさはほんに極らく 栗樹亭有園
掲出歌の題は「辻納涼」。初句「合法」は「がっぽう」(『日本歴史地名大系』)と読む。舞台は大阪市天王寺区にあった合法ヶ辻の閻魔堂である。石像が安置されていたが、らしくない閻魔大王で、つまり肩に張りがない。そこから役に立たないことを「合法ヶ辻の石の閻魔王の肩すぼった」といったらしい。閻魔大王・焦熱地獄と納涼の取り合わせに妙がある。
恋ならて其(の)きみしりやなすひ畑宵にちきろかあしたちきろか
夏の日にようもあつ着をしてかたの舞は脇から見てゐるも汗
夕立にありまちぬれて一しほのひつた絞るや夏の衣手
賑しささかさまにほす御神燈しむとはかりに秋は淋しき
一首目の作者は栗花亭寿園、題はない。初句の「恋」は二句の「其のきみ~」に拠る。「木毟茄子(きみしりなすび)」は時期遅れで根こぎにした枝から毟り取る茄子である。末生りで小さい。二首目の作者は松永夭々、題は「夏能師」。二句「ようも」は「よくまあ」の意、次の「厚(着)」に「暑」を掛けた。三句は意味的には「して(かたの)」、ここに「仕手方」(シテ)の語を嵌めた。四句「脇」はシテに対するワキを掛けた。三首目の作者は栗山亭如園、題は「夕立に着物をぬらして」。二句「有りまち」は「有りっ丈」、三句「一入」は染め物を一度染め液に浸すことをいう。四句「ひった」(直)は副詞、ここでは「一途に」(着物を)「絞る」そして疑問の「や」となる。四首目の作者は園果亭義栗、「ふみ月朔日祭り桃灯をほしたるをみて」。秋祭りの準備中なのだ。そのシンボルである御神燈の干し方から四句「しんと」(しいんと)が生まれた。賑やかさの逆だから淋しさ、とはいえ季節への感応に偽りはない。
夕されはうりかふこゑもやみなからむしのねはかり又たつの市
風もなく二百十日をこゆるきのいそく稲葉の波のうちまき
よるもたたすつくりたつてゐるかかし何をおとしの弓はりの月
五六本とつてきた山松たけのみやけと雨にかりたたぬかさ
一首目の作者は柳修舎有文、題は「市場虫」。三句の「止み」に「闇」で主役も移って「虫の音ばかり又立つ(の)市」。人の市から虫の市だが、これに同音「辰の市」(古代にあった市)を重ねて夜を深くした。二首目の作者は栗洲亭義園、題は「稲」。二百十日は稲の開花期に加えて台風も多いため農家の厄日とされる。それが風もない。下句「小余綾の」は「急ぐ」の枕詞、「稲葉の波」は風になびく稲穂を大海の波に見立てた。「打ち撒き」は米、このまま実りの秋を迎えたいのである。三首目の作者は栗枝亭蕪園、題は「夜案山子」。歌意は「夜もただすっくと立ってゐる案山子、さて何を威すのだろう弓張りの月は」。なお案山子と弦月の配合に「すっきり」の別義「清々しく感じられるさま」を見ることができる。四首目の作者は園果亭義栗、題は「雨中松茸狩」。二句「来た」は下へは「北(山)」となる。下句「土産と雨に雁立たぬ傘」は土産と土産にはなるが傘の用は足さない松茸(「雁」は「雁首」の略)だろう。
|
| 第104回 狂歌芦分船(4) |
六そちにはととかぬ年の三具足其(の)鶴亀の千代もなんしやい 栗窓亭李園
掲出歌の題は「母の喪にこもり五十日五十首よみし中に五十三歳にて身まかり給へば」。三句の「三具足」(「三」は「さん」とも「みつ」とも読む)は仏前に供する華瓶、燭台、香炉を一揃いとしたものをいう。四句「鶴亀」は燭台などに描かれていたのであろう。鶴千年亀万年から結句「千代」(千年)、「何じゃい」は「何だ!」(『大阪ことば事典』となる。
木のもとにこのみをひとつ盗(み)くふ口をしはつた渋柿の味
いなり山青かりし葉ももみちして鳥井の朱のいろをはかした
落(ち)て来る水もつららとこほりてはその名にもおふ音なしの瀧
こころにはかけ樋の水のととこおり冬もとくとく聞(か)ぬ音つれ
一首目の作者は栗箕亭芦園、題は「柿」。初二句で頭韻を踏む心地良い調べが続く中に突如として「盗み」という異分子に出合うが、大事ない。次の布石なのだ。つまるところ「渋柿の味」が「口を縛った」と表現したかったのだ。二首目の作者は閑古亭三子、題は「社頭紅葉」。初句は伏見稲荷大社のある「稲荷山」で狐との縁が深い。四句「鳥井」は「鳥居」、結句「化かした」は紅葉した青葉が同色の鳥居と区別できなくなった、だろう。三首目の作者は春秋亭芋園、題は「瀧水」。結句「音無の滝」は歌枕で京都市左京区大原にある滝という。和歌では「音信がない」で詠まれることが多いが、こちらは冬季限定で実に分かりやすい。四首目の作者は園果亭義栗、題は「冬の日久しく問(は)ざりける方へ」。歌意は「心には掛かっていたのですが、地上にかけ渡して導く懸け樋のように水も滞り、冬は滴の滴る音も聞かない、しかしその音のように疾く疾くと思いながら消息をお尋ねするのが遅くなったことです」か。
ふりかかり岸根の竹のをれふして水にもつもる雪の枝川
ふくれたりひそつてみたりせんへいのととやかかやかわれるいさかい
舟もはやさしかけてきた将棋島をふてはみえぬ金城の辺
息杖の二ほん晴なる旅の空只かこやろのくもはかりにて
一首目の作者は園果亭義栗、題は「川辺雪」。二句「岸根」は水際、三句は「折れ伏して」、四句は積雪の広がりをいう。結句「枝川」は本流に対する支流である。二首目の作者は栗子亭箕園、題はないが「恋」の部である。「膨れる」「干反る」「割れる」とも多義語である。三句は「煎餅の」、四句は「父や母やが」、親を巻き込んだ娘の恋の顛末や如何。三首目の作者も箕園、題は「船にて網島の辺りに遊びて」。「網島」は大阪市都島区南端の地名で料亭が多かった。三句「将棋島」も地名、結句「金城」は大阪城である。二句「指し掛けて」(将棋を一時休止して。島が近いので停船するのだろう)、四句は「追ふて」に「王手」と将棋尽しである。四首目の作者は仮楽亭四綱、題は「晴天旅」。初句「息杖」は駕籠かきが一休みするときの杖、二人だから「二本」に「日本(晴れ)」、四句の「駕籠遣ろ」は客引きの声である。雲一つない空だが結句は「くも(ばかりにて)」、雲助駕籠の「雲」を遣り過ごすのも楽ではない。
|
| 第105回 狂歌溪の月 |
乗合船さす蚊はかりかみしか夜にくらはんかまてせめて寝させぬ 溪月庵宵眠
『狂歌溪の月』の詠者は溪月庵宵眠(一七〇八~一七八四)、撰者は坤井堂宵瑞、刊記は寛政七(一七九五)年。掲出歌の題は「船中厭蚊」。二句は「刺す蚊ばかりか」、三句は「短夜に」、四句の「食らはんか(蚊)」は「食らはんか船」(淀川の三十石船の乗客に飲食物を売った煮売り船)の略、乱暴な呼号そのままの俗称である。商売は夜も厭わなかったらしい。
美芳野の山は世界のはなはしら誰かめがねにもかかるしら雲
うへこみの若葉の梢雨はれて花かあらぬか蝶の三つ四つ
玉ぼこの道ゆき人のからかさもやれてほとふるさみたれのころ
ひく声のゑいさらゑいはきこえねと様子やありの熊野海道
一首目の題は「名所花」。初句は「御吉野」の宛字、三句は「花」に「鼻(柱)」で次の布石とした。結句の「掛かる」は①「眼鏡に掛かる」で気に入る意、②吉野の山に「掛かる白雲」で花の雲となる。二首目の題は「首夏雨晴」。初句「植ゑ込みの」、二句「梢」は枝の先で葉も青々と夏めいてくる頃の雨後の景である。花かそうでないか、訝っていたら枝を離れていった、その蝶のさまに惹かれる。三首目の題は「五月雨」。本歌は〈玉桙のみちゆき人のことづてもたえて程ふる五月雨の空〉(藤原定家『拾遺愚草』四二八)。初句「玉鉾の」は道に掛かる枕詞、二句「道行き人」(旅人)は「道行き」(情死行)であっても不思議でない三句以降である。四句「程降る」は雨また「程経る」時間だろう。四首目の題は「蟻」。上句は蟻が楽車でも引いている感である。四句の「や」は係り助詞で疑問を表し、「有り」に「蟻」を掛ける。結句「熊野海道」(熊野街道)は京都から熊野三社に至る街道、成句に「蟻の熊野参り」がある。
くねつさへせんかたなつの其(の)上に又ちうねつの閏六月
月をみて虫きく秋はおもしろや目の八月に耳の八月
枝かはす汀の松のかけ見えて月も木つたふさるさはの池
酒のんて芋も存分此(の)うへのゑようにもちの皮かむきたい
一首目の題は「閏六月」。初句「苦熱」は暑さに苦しむこと、二句は「(為ん方)ない」に「夏」を掛ける。四句「中熱」は「中暑」(暑気あたり)をいう。二十四節気の小暑と大暑を意識した番外編であろう。宵眠六十三歳の明和七(一七七〇)年に閏六月が見られる。二首目の題は「虫」。中秋の名月と虫の音の取り合わせである。四句「目の八月」は「目の正月」(目の保養)、結句「耳の八月」は「耳の正月」(耳の御馳走)をそれぞれ応用した。三首目の題は「月」。初句は枝が交差するさま、二三句「松の影」は池に映って見える松である。四句「木伝ふ」は枝から枝へと移ること、「も」は結句「猿沢の池」に「猿」が控えているからだ。「伝ふ」(四段)は連体形、一首は無句切れの歌となる。四首目の題は「雲のみおほいければ」。雲が隠したのは八月十五夜の月、里芋の新芋を供えたところから芋名月ともいう。下句は成句「栄耀に餅の皮を剥く」(餡餅の皮を剥く)を使った。「餅」に「望(月)」で「皮」は雲をいう。
|
| 第106回 狂歌溪の月(2) |
朝鮮も大人参は指なやらどのかほも皆ひけはかりなり 溪月庵宵眠
掲出歌の題は「大坂にて朝鮮人を見て」。二句「大人参」(おおにんじん)は朝鮮人参の根が大きいもので「参」を除くと「大人」になる。三句「指な」は造語で「指菜」と解した。親指から小指まで、大きさは違っても指腹は同じ顔、菜は草本を示す。だから副助詞「やら」(「やらん」の音変化)が付く。髭に驚くとともに形状が大人参の細根と似ていることをいう。
つつほりとひとりたつたのかかしをは夜半にやきみのわるものとみん
きつと手ににきりこふしのたかもちは放しもやらて身をぬくめ鳥
真白に三輪の山もと道もなしたた豊年のしるしのみして
ゆくとくるとしと年との挨拶は互にまめをいはふせつふん
一首目の題は「案山子」。初句「つっぽり」は「しょんぼり」、二句の「たった」は上から「一人立った」、下へは「たったの案山子」で「わずか一体の案山子」の意となる。四句「気味」に「君」、結句も「悪者(悪物)と見ん」の両意を含む。二首目の題は「鷹狩」。初句「きっと」は厳しいさま。結句「温め鳥」は冬の夜、捕らえた小鳥を掴んで足を暖めるが、翌朝に小鳥を放して追わないという鷹の口碑である。鷹と三句「鷹持ち」(「鷹匠」と解した)を置き換えた見立てを楽しみたい。三首目の題は「雪」。二句「三輪の山」は奈良県桜井市にあり、三輪山を御神体とする大神神社は山元(麓)にある。そこが雪で道もない。ただ「のみ」が強調する「雪は豊年の瑞」(成句)、その予祝の景なのだ。四首目の題は「節分」。節分は立春の前日をいい、新暦だと二月三日か四日になる。しかし旧暦では二十四節気が一巡して旧年を越したときが立春すなわち正月節だから節分の夜は年越しとなる。三句「挨拶」の由縁である。
浄るりのふしみにかかるふんこ橋いさ都路の事かたれきこ
扨なかい日しやの夜しやのといふうちについ盆になり正月かくる
つつしめや隣同士のよい中にかきの木うえて不和になりもの
鳳かけり鶴の舞なるいきほひをかこ字にうつしとりの足跡
一首目の題は「伏見むかひ島にとまりて」。向島は京都市伏見区の地名。三句「豊後橋」(観月橋)は宇治川北岸の豊後橋町と南岸を結ぶ橋。四句「都路」は「宮古路」で浄瑠璃の宮古路豊後掾を詠った。結句は「~語れ聞こ」。二首目の題は「日」。初二句「さて長い日じゃ」は陰暦五月の夏至、長い「夜じゃ」は十一月の冬至、この間に七月の盆、一月の正月が入る。曰く「歳月人を待たず」。三首目の題は「隣」。三句の「中」は仲に境目の意を掛ける。結句は「不和になり(もの)」に「(不和に)生物」(果実)。青々舎安楽酒丸に〈取るもうしとらぬもつらしよい中に柿の出来たる隣同士は〉があった。四首目の題は「書」。初句切れで「鳳(おおとり)翔けり」(「鳳」は鶴などの大きな鳥)、二句「鶴の舞」は鶴の動作を模倣する舞で上句は書の特色を示す。四句「籠字」は元の字の輪郭をなぞる複製技術で、「籠」は鳥の縁語、以下「写し取り」の「取り」に「鳥」、「足跡」(そくせき)は書家の墨蹟に業績を重ねた。
|
| 第107回 狂歌溪の月(3) |
さかもりに千とせの命のへにけりさよもふけ井のつるの吸(ひ)もの 溪月庵宵眠
掲出歌の題は「深更酒盛」。二句から三句は「千歳の命延べにけり」、四句は「小夜も更け(井の)」に「(小夜も)吹飯の」となる。「吹井」は宛字、「吹飯」は「吹飯の浦」(大阪府泉南郡岬町深日の海岸)で歌枕、鶴の名所であった。結句に千歳の鶴料理となる。『日本国語大辞典』に「鶴の汁」として「鶴の肉を入れた汁。第一の料理として珍重された」とある。
ひきよせて三井の古寺鐘はあれととをめかねにて声はきこへす
夏もはやいつきの宮の草しけみひらき残りしひあふきの花
せはしない浜の真砂の二厘五毛つもれは人のおいとなるもの
あられいる音はきけとも年寄(り)ははくきに老(い)をかむ斗なり
一首目の題は「千里鏡」(望遠鏡)。初二句は遠くの三井寺を近くへ引き寄せて、となる。しかし三句以下は「鐘はあれども遠眼鏡にて声は聞こえず」。景色は引き寄せられるが音は残る、のであった。二首目の題は「廃宮」。二句「斎宮」(斎皇女の居所)は江戸時代、伊勢参宮の街道から少し外れたところに地名とともにその名残を残していたらしい。結句「檜扇」はアヤメ科の多年草、同名の彩色も美しい「檜扇」を連想して昔を偲んだのである。三首目の題は「米相場」。初句「忙しない」は市場の開かれている時間、二句「浜の真砂」は数えきれない取引、三句「二厘五毛」(わずかな金)は値動きだろう。結句「おい」は「負ひ」(負債)に「老い」(神経)が考えられる。四首目の題は「餅百首の中に」。初句「霰」は「霰餅」の略。「いる」は「煎る」、「入る」(下二)は「入るる」、口語は「入れる」だから採れない。下句は「歯茎に老いを噛むばかりなり」。歯が抜けて入れ歯もしていない、その口元の皺に老いが滲む。
千代鶴のとひたの歌を給(は)るはかしこまるやの家のめいほく
ここをせに鉋かけたかと郭公よしの丸たの杉のむらたち
故郷の軒もあらたにたちはなやむかしのままに匂ふ門々
一首目の題は「富田三位光知卿上洛のついで茅屋に立(ち)より給ひて 名に聞(き)し鶴の丸やをきてとへは賑(は)ひにけり千代のもろ声とよみて給ひしかへし」。宵眠は奈良の人、通称は丸屋勘兵衛である。二句「飛びた」は「飛びたる」の脱落、いずれ蛙となって「飛んだ」が予想される。四句に「丸屋」が覗く。結句は「家の面目」(「めんぼく」に同じ)となる。二首目の題は「午の年の春大火にて数千軒やけしかばみなみな普請場になりし所をとをりしに思ひがけず一声をききて」。宝暦十二(一七六二)年午の年の二月、大火で東大寺戒壇院や興福寺なども焼失している。初句は「肝心のとき」の意だろう。二句は時鳥の「(ほぞん)かけたか」を「(鉋)かけたか」と聞きなした。下句は「吉野丸太の杉の群立ち」となる。本歌は西行の〈聞かずともここをせにせん郭公山田の原の杉の群立ち〉(『新古今和歌集』二一名)である。三首目の題は「五月の比は家並大かたにたてつづきしかば」。二三句は「軒も新たに建ち(ばなや)」で「橘や」を重ねた。以下「昔」「匂ふ」とくれば思い出される古歌も多い。
|
| 第108回 狂歌溪の月(4) |
ひてりとし夕たちほしくおもひねの夢にもなかす百姓の汗 溪月庵宵眠
掲出歌の題は「寅の年大旱卯のとしもひでりにてみなみな雨を乞(ひ)殊に農業せんかたなく水をかへいろいろとすれど猿沢の池も涸(カレ)ぬるほどにて未曾有のことなり其(の)ころよみ侍る」。寅の年は明和七(一七七〇)年である。上句は「旱年夕立欲しく思ひ寝の」となる。三句の対象は多く恋人で、流すのは涙になるが、結句の汗に注目しておきたい。
観音のちかひかこそのひてりにてかれたる井にも花の春雨
おかけとて皆ぬけ参(り)正直のかうへには蚊か宿取(つ)てくふ
一首目の題は「冬にいたりてもまた旱つづき井は水なくて飲(み)水にくるしみしが早春に程よく雨潤ひしに」。二三句は「誓ひか去年の旱にて」、「観音の誓ひ」(本誓)は衆生を救済しようとする大慈悲の誓願である。その現れとしての下句が美しい。二首目の題は「おかげ参(り)とて諸国より夥しく伊勢参宮ありはたごやは皆つみで施行宿に大勢とまりしをみて」。詠われているのは明和八(一七七一)年の御陰参りである。題の「つみで」は「罪で」だろう。往来手形がないので施行宿の施しに与るのである。三句以下は「正直の頭に神宿る」(正直な人には神の加護がある)の口合いで、「正直の頭」は宿泊の世話をする施行者、「蚊が宿取(つ)てくふ」の「蚊」は抜け参りと称される参詣者のことだろう。辛口である。
うしをにとなるいきほひをもちなから無慙やこちへくるとたいみそ
書(く)もしの廿の右はむかしにて段々十の左へそよる
うのまねかうさきのまねかしら紙の浪をからすかこゆるきの磯
水無月をせかてかこらは高帆真帆片原漕かて風沖つなみ
白髪問うもとの干支そきつるなる月そ昔の友うとからし
一首目の題は「寒中に一尾をもらひて」。初句の「潮煮」は白身の魚を塩で味付けした吸い物、結句の「鯛味噌」は砂糖と味醂を加えた味噌に鯛のほぐした身を混ぜた嘗め味噌をいう。新鮮な素材を活かすという点で軍配をあげると四句の「無慙や」なのだろう。二首目の題は「懐旧」。考えられる文字は「帶」、上の部分の真ん中に「廿」(二十)、右に「十」(昔)、左の「廿」を足して三十、次の十で四十になる。「滯」「蔕」等も同様である。三首目の題は「浪にからす」。初句は成句「鵜の真似する烏」(能力も顧みないで失敗すること)、二句は成句「兎波を走る」(月影が水面に映るさま)に由来、すべて平仮名の序詞として三句の「知ら」に繋いだ。その「白紙」に登場する四句「烏」は「筆で紙に罫を引く時、あやまって墨が広がった部分」(『日本国語大辞典』)と解した、あとは縁語仕立てである。三者に共通するのは初二句で頭韻を踏む「う」(字音)である。四首目の題は「夏」、回文である。二句は「急かで水夫らは」、四句「片原」は「傍ら」の宛字また視界の陸地と解した。結句から辺つ波(岸に近いところに立つ波)は穏やかなのだ。五首目の題は「懐旧」。やはり回文である。二三句「元の干支(かんし)ぞ来つるなる」は還暦、下句の「月」は暦の月と空の月、その両者を受けて「月ぞ昔の友疎からず」なのだ。
|
| 第109回 狂歌我身の土産 |
たとへにはもるる親なり可愛子に留主をはさして旅をして来た 養老館路芳
『狂歌我身の土産』の詠者は養老館路芳、編者は養老館路産、刊記は寛政八(一七九六)年である。掲出歌の題は「帰路の日息路産迎(へ)に来(た)りてかくなんあし引(き)のやまとめぐりの留主の間を長々しやと待(つ)て居ましたとよめる返しに」。初句の「喩へ」は「可愛い子には旅をさせよ」、二句は「漏るる親」となる。路産の迎えの歌も率直だ。
千とせふる鶴のよはひにあやからんわれもあたまか赤うなるから
水になる物ても水にするはおし地黄はたけにつもる初ゆき
いたたきはたとひはけてもはたち山あやかりたやな年のくれには
をさな子のちんほうかとそ身ふるひし下を見やれはししか谷むら
一首目の題は「年のはじめによめる」。鶴は頭頂が裸出して赤い。「私」も禿頭、しかも屠蘇酒で赤くなっている。そこから上句に展開して齢も「肖らん」となる。二首目の題は「薬園雪」。雪は溶けると水になる。しかし上句「水になる物でも水にするは惜し」が初雪であろう。これが薬草だと「地黄になる物でも地黄にするは惜し」は成立しない。三首目の題は「としのくれに」。三句の「二十山」は富士山、二句「はげ」の「は」が句頭の「は」を呼び込んだ。禿頭でもいから「一富士二鷹三茄子」の一の異称「二十(山)」の若さがほしいというのである。四首目の題は「あるとし卯月ころ万英了山とともに洛東に遊ばんとて鹿が谷にゆき透谷が家をたづね彼(の)人のあないにて椿峰といふみねにのぼりて」。椿峰は東山三十六峰の椿ヶ峰だろう。二句の「珍宝(かとぞ)」は直接表現を回避した。その「珍宝(ちんぽう)」は珍しい宝物をいう。結句「しし」の同音に成句「獅子の子落し」が浮かんで縮み上がったのだ。
大すまふの関川なれや橋の銭とつて中々まけさうになし
ならふなら鋤鍬ほしや吉野やま根にかへりたる花を掘(ら)ふに
此(の)ほとり古戦場とてかふてのむ一はい酒の代もきりあふ
一首目の題は「ひととせ伊勢まうでし夫よりかけて大和路におもむく事あり先弥生六日の日都を出立八日には関川といふ所にいたりければ長き橋をかけて其(の)あたひを取れり友なる人高値なりといへるに」。二句の「関川」は当時の力士なのだろう。結句は①「値引きしそうにない」、②「負けそうにない」関川となる。二首目の題は「内外の宮にまふでしかどいとかしこみかしこみて何のことばのいづべくもあらずそれより芳野にまかりけるに桜はみな青葉なりければ」。初句「成らうなら」は実現できることならば、四句は成句「花は根に帰る」に拠った。結句は「花を掘らうに」。大誤算だが〈さかりをばはかりかねつる芳野やまうらやましいは水茶屋の婆々〉という作品もあるから安心である。三首目の題は「芳野の町もさびしければ友つ人々とともに侘しげなる酒汲(み)かはし正慶建武のむかしをおもひて」。三句は「買うて呑む」、四句「一杯酒」は一杯盛り切りの酒をいう。結句「斬り合う」は各自が金銭を出しあうこと、これに刀を交える意を重ねた。正慶建武は南北朝時代の前後をいう。
|
| 第110回 狂歌かたをなみ |
はらからの娘かしほんた花とつてふくらかすかの里の朝かほ 佐藤少女萩
『狂歌かたをなみ』は玉雲斎社中詠、刊記は寛政八(一七九六)年。掲出歌の題は「里朝顔」。初二句「はらからの娘」とは嫁いだ姉の子、姪と思われる。以下「萎んだ花とって脹らかす」からも幼児だろう。「かの」は遠称の代名詞、「里」は村落。集中に佐藤魚丸(蝙蝠軒、旧路館)と佐藤女鶴江が出てくるが両親かも知れない。貴重なジュニアの作品である。
村立(ち)し杉の庵のこの花もわらひかけ樋の水ぬるむころ
音信は声をはかりに谷むかひかはる事なしけふもさみたれ
秋かせのふくにつけてもくさめくさめ在もこまちも寒なつて来て
かけ声もよいよいやつとせき取の踊(り)はさすかとひやうしなもの
一首目の作者は女性で安田李枝、題は「山家梅」。初二句「群立ちし杉の庵」の庭に咲く梅なのだろう。四句の「かけ」は上から花も「咲ひかけ(樋の)」、下へは「(わらひ)懸け樋の」となる。莟が開くことを「咲(わら)ふ」という。二首目の作者は含章堂梨丸、題は「山中五月雨」。山の中の一軒家である。初句の「音信」は谷を隔てて届く声、二三句とりわけ「ばかり」からもホトトギスだろう。四句は鳴き声と五月雨、だから結句の「も」となる。三首目の作者は竹林舎恒丸、題は「穐風」。三句の「くさめ」は嚔のこと、リフレインは「ハックションハックション」だろう。四句の「在」は田舎、「古町」(昔ながらの町)から少し離れた所をいう。結句の会話体が心に響く。四首目の作者は越要舎後丸、題は「角力取躍」。二句の掛け声「やっとせ」の「せ」を三句「関取」の句頭に重ねた。そのため「やっと」が「ようやく」となって調子を削ぐ。結句の「と拍子」は「突拍子」と同じ、やはり調子はずれなのだ。
花の木も花さかぬ木も紅葉して秋は思ひの色をあらそふ
つめたうも思はす来たる町はつれ馬捨場とは見えぬ雪の日
ちはやふる雪とあられの玉津しまけにおもしろき和歌の御社
紙袋あたまへ着せりや煤掃(き)に跡すさりしてふきまはる猫
一首目の作者は玉紅舎䰗丸、題は「紅葉」。四句は「思ひ」の「ひ」に「緋」を掛けた。主役は人ではない。花の有無も問わない。木自体が装いとしての緋色を競っているというのが妙である。二首目の作者は此君亭嶋丸、題は「雪」。二句「思はず」は初句を受け、また二句「来たる」へと続く。つい雪に誘われての逍遥と見た。四句「馬捨場」は死んだ馬や牛などを捨てる場所だが三句「町外れ」にあった。三首目の作者は渓藤舎海丸、題は「社頭冬」。初句の枕詞は三句の神社名に掛かる。しかし二句に「雪と霰の(玉)」を挿入した結果、境内は雪と霰が同時に降るという「げに面白き(珍しい、風流な)和歌の御社」となった。玉津島神社(和歌山市)は和歌三神の一社である。四首目の作者は破睡軒辻丸、題は「季冬猫」。二句「着せりゃ」は「着せれば」、結句「吹き」だが『日本国語大辞典』で「吹(嘯)く」を引くと「熊虎の声ぞ。玉篇には咆(フ)くぞ。咆は鳴なり」とある。これに「拭き回る」を掛けた。
|
| 第111回 狂歌かたをなみ(2) |
緋おとしのよろひゆゆしくほうらいのやまの大将と見ゆる伊勢海老 玉雲斎貞右
掲出歌は挿絵、蓬莱山の賛である。蓬莱山は関西の新年の祝儀として、三方(前と左右に刳形の穴をあけた台に方形の折敷を載せた物)に白米を盛り、熨斗鮑・搗ち栗・昆布・橙・海老などを飾った。初二句は甲殻を「緋威の鎧」に見立てた。「ゆゆし(く)」は立派なさまをいう。三四句は蓬莱山を「の」で分断、子供の遊び「山の大将」の景として仕上げた。
恋風になひきつよれつもつれつつ又あをやきのめてしらすころ
わすられぬ其(の)一言かかすかいとなつていかたのはなれさる中
三年物かかつてこいやふなゆさん客はしまんて網をうち川
往来も目をとめる家の花盛り京のまなこと思ふ室町
一首目の作者は順風軒沖丸、題は「寄柳恋」。二三句は「靡きつ縒れつ縺れつつ」でツ音がリズムを刻む。下句は「また青柳が芽で知らす頃」。「青柳」は若い女性、「芽」に「目」を重ねて色っぽい。二首目の作者は杉林軒益丸、題は「寄筏恋」。三句「鎹」は材木同士を繋ぎ止めるために打ち込むコの字形の大釘をいう。急流にも離れない下句が魅力なだけ二句の「其の一言」が知りたい。三首目の作者は熙春堂菱丸、題は「船遊」。初句は生後三年たった魚で食べ頃とされる。二句「掛かってこいや」と三句「船遊山」の間に「鯉や鮒」が隠れている。四句「客は自慢で」、結句の「うち」は「(網を)打ち~」に「~宇治(川)」だろう。四首目の作者は雄崎菅江、題は「市中花」。二句八音、四句は「京の愛子」だろう。結句「室町」は京都を南北に走る室町通り沿道の地区名、西陣機業の発展で栄える繊維問屋街であった。
つなく馬かあれてちらした花のうへはたしてそ行(く)こはたの里人
なはしろの水はな頭痛せきとめよ送らるる風の神ならは神
つつくつく築波の山の下藪に出た竹の子もかのもこのもし
はりこんた扇てゑすと左してしさいらしけにあをいてこさる
一首目の作者は佐藤鶴江、題は「里落花」。下句は「裸足でぞ行く木幡の里人」。「木幡」は歌枕、宇治市木幡町周辺の古称である。花が優雅に見せるが裸足は珍しくなかったろう。跣足禁止令が出るのは明治三十四(一九〇一)年である。二首目の作者は佐藤魚丸、題は「春のすへつかた風邪流行して風の神を送るに」。「風の神を送る」は風の神に見立てた人形を鉦や太鼓で囃して風邪を追い払う呪いである。上句は「苗代の水堰き止めよ」に「水洟頭痛咳」を挿入、重ねた。出だしも「苗代水」を分断して枕詞風かつ陰陽師風である。三首目の作者は雄崎菅江、題は「名所笋」。初句「突く突く」は三句「下藪」に掛かるが筑波山の枕詞っぽく造語した。結句は「彼のも好もし」で「彼の」は四六の蝦蟇を指す。「かのもこのも」と対句風である。四首目の作者は難得斎此丸、題は「もろかつらをはり込(め)し扇に歌よめと有(り)ければ」。初句は桂と葵を「張り込んだ」、二句「でえす」(です)は尊大な語感を伴う。以下「左して子細らしげに仰いでござる」。「左」は「左扇」で得意な様子、依頼者の顔が見たい。
|
| 第112回 狂歌かたをなみ(3) |
人か軒にさすなら我もさそふようけにも菖蒲に蓬もそふよの 酒泉堂蛸丸
掲出歌の題は「端午」(陰暦五月五日の男子の節供)。一首は狂言「末廣がり」の「人がかさをさすなら、我もかさをささうよ、げにもさあり、やようがりもさうよの」に拠った。表記を整理すると〈人が軒にさすなら我もささうようげにも菖蒲に蓬もさうよの〉となる。邪気を払うために菖蒲や蓬を軒に差すのだが、亭主殿は口合いで舞台の人さながらである。
ふちはなれ向ふの岸の菰かろと持(つ)たる鎌もさひた浪人
立はなのかほる河辺てせんたくの婆さまの袖も昔ゆかしき
枚方のくらはんか船もさみたれはちとあかれかしとやさしういふ也
夏の夜はわきて涼しやむすふ手に思はぬ月かひとつまし水
一首目の作者は一日庵荻丸、題は「浪人刈菰」。初句は「淵」に「扶持」。三句の「菰」は真菰の古称、「薦被り」(乞食)の略また菰筵の意がある。次の「かろ」は「刈ら(う)」に菰筵を「借ら(う)」を重ねた。四句は「持ったる」だろう。結句は鎌も「銹びた浪人」。二首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「水辺薫橘」。本歌は〈「五月まつ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする〉(『古今和歌集』一三九)である。これに久米の仙人の神通力をも失わせた若さの懐旧として二三句「河辺で洗濯」を用意した。三首目の作者は似蜂軒波丸、題は「河辺皐月雨」。四句は「些と上がれかし」で「上がる」は「食う」の尊敬語、「かし」は強調の助詞。これに五月雨も「少し止んでくれ」の意を重ねた。「ちと」は少しの量また間である。四首目の作者は樵諷軒歩丸、題は「泉」。二句「分きて」は「格別に」、三句「掬ぶ手に」は両の手で汲んだ水をいう、結句はその手の泉にも月が「一つ増し(水)」でロマネスクな世界を詠った。
さつはりとなかこも種も喰(ひ)つくし又来るとしは何まくは瓜
宮の名の朝日の出からやれあついすすしめ玉へと舞ふ夏神楽
秋きぬと目には見えねと風になひくすすきかんさし売(り)あるく人
片手には小魚抓んて洗ふたる硯の海に放す男の童
一首目の作者は非神軒辰丸、題は「瓜」。初句の「さっぱり」は「すっかり」、二句は「中子(なかご)も種も」、「中子」は種のある肉の部分をいう。結句「何蒔くは瓜」(「何、真桑瓜」)は「何を蒔けばいいのだろう(蒔くものがなくなって)」と解した。二首目の作者は熙春堂菱丸、題は「社頭夏日」。伊勢神宮の内宮を朝日の宮という。上句は「宮の名の朝日ではないが、朝の日の出から、本当に暑い」の意。三首目の作者は里橘庵蕗丸、題は「初秋商人」。本歌の〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(『古今和歌集』一六九〉は視覚転じて聴覚で秋を知った。掲出歌は聴覚の風を再び視覚化させて〈風に靡く薄簪売り歩く人〉で都市生活の中に秋を見出した。四首目の作者は不鳳薮丸、題は「硯洗」。硯で墨汁を貯めておく窪みを「硯の海」という。その「海」に小魚を放したのである。これだけでも十分に可愛いが、「海」に比重を移すと大人国の「男(を)の童(わらべ)」が重なって見える。
|
| 第113回 狂歌かたをなみ(4) |
とんふりの文字かともみつ四つ橋の中に一点うつる月かけ 雌雄軒蟹丸
掲出歌の題は「橋辺月」。橋の名は川の交差する所に四方四つの橋を架けた、その総称だが大坂の名所であった。類歌に居由の〈井の中へ打ち込むやうに飛ふ蛙とんふりとよむ文字の点かも〉(『狂歌玉雲集』)や正親町公通の〈釣り置きてふりたる網のやれやれといふ間に瓜の一つは丼〉(『雅筵酔狂集・腹藁』)があるがスケールの大きな見立てに月が貢献している。
町風にやつしておとるもののふは先(づ)ちうけんに刀わたした
秋の日のかけはさせともやや寒くふるふてのほるきやくのみね入(り)
うつくしさ是ににかみかあらふとは誰も思ひはせんふりの花
あつま路に神のゐせいを見せつるき草なきたをすけふの野分も
一首目の作者は秀紅軒釜丸、題は「武士踊」。初句「町風」は町人のふうをいう。町人は都市に住んだ商工業者である。四句「中間」は武士に仕えて雑務に従った。士農工商の工商の踊りに加わるために刀を渡したのである。二首目の作者は雌雄軒蟹丸、題は「峰入」。二句の「かげ」(影)は日光をいう。結句の「きやく」は「逆」で吉野から大峰山を経て熊野にぬける「逆の峰入り」である。また三四句の体から推して修験者ではない、在俗者を中心とした大峯講で「逆」に「客」を重ねたと解する。三首目の作者は福寿軒茂丸、題は「草枕」。結句「千振」はリンドウ科、秋に五裂で紫の筋のある白い花を開く。全体に苦味があって胃腸薬として用いられた。下句「誰も思ひはせん(ぶりの花)」である。四首目の作者は非神軒辰丸、題は「東路野分」。倭建命の東征伝承を思い出す仕組みである。二句は「神の威勢を」、三四句「(見せ)剣草薙ぎ倒す」に活躍する草薙の剣が見える。舞台は相模、くだりは野火の難である。
虫の音をいとふてあゆむ駒下駄の音もしつかな秋の夕くれ
淋しさよ深草の里の人形屋に人形もてあそふ秋の夕暮
ゆききさへとたへの橋に水音の高くて淋しあきのゆふ暮
玄関になく子もみえす小児医者さひしき台もあきの夕暮
一首目の作者は杉林軒益丸、題は「秋夕」。二句の「厭うて」は「大事にして」の意、これを受けた三句の「駒下駄」であろう。また取り合わせとして〈草村にむさとな鳴きそ轡虫野飼ひの馬のはむ事もあり〉(『古今夷曲集』)が思い出される。二首目の作者は園丸、題は「里秋夕」。名称は伏見人形、素焼の人形に白・赤・黄などの彩色を施した郷土玩具で、最盛期には五十余の窯元と十数軒の店舗が軒を並べていた。四句「もて遊ぶ」は関係者の無聊だろう。三首目の作者は二松軒中丸、題は「橋辺秋夕」。初二句「行き来さへ途絶えの」で渡る人も稀な橋であることが分かる。四句の「高くて」は水音に加えて橋の高さでもあり、しかも秋、三句の読みは清音の「スイオン」を選択したが如何。四首目の作者は一日庵荻丸、題は「医家秋夕」。二句は「泣く子も見えず」。三句が助詞を欠くのは繋がらないからだろう。その四句「台」は小児を寝かせて診察する台を想定した。結句は「空きの夕暮」に「秋の夕暮」となる。
|
| 第114回 狂歌かたをなみ(5) |
一枝を折(つ)てくせとは京言葉さてもいつかいかいて紅葉を 佐藤女鶴江
掲出歌の題は「花洛紅葉」。『京都語辞典』(東京堂出版)に「くす」(動五)がある。意味は「よこす。貰う」で「御所ことば(女房詞)」なのだそうだ。したがって命令形だが「一枝を折ってもらえませんか」といったところか。四句「いっかい」は「厳い」で大きい、結句「かいで」は「かえで」の変化した語、下句は「なんとまあ大きな楓紅葉を」となる。
大仏のはしらにあけたあな淋しほこりのつもる穐の夕くれ
棚にあるすやきの布袋もおとる也からころもうつ伏見の里の家
花の時はさそやとこしをかけ茶屋の茶碗にちり込(む)桜紅葉葉
雪の中の松はものかは横山のほのほの中てちらぬ花炭
一首目の作者は巴蕪軒道丸、題は「寺院秋夕」。奈良の大仏殿である。三句は「穴淋し」に感動詞の「あな淋し」なのだろう。四句からして久しく穴を潜る人もいない。現今と異なる風情である。二首目の作者は東朝館次丸、題は「里擣衣」。「擣衣」は布を柔らかくし、艶を出すため、砧にのせて槌で打つことをいう。四句は「唐衣」ならぬ「空衣」だろう。二句の「素焼き」と対応し、三句とも連動する。結句は九音である。三首目の作者は雌雄軒蟹丸、題は「茶店落葉」。三句は腰を「掛け(茶屋の)」、「掛け茶屋」は「腰掛け茶屋」ともいう。春の主役も、秋といえば楓、その主役を去った桜紅葉の葉が茶碗に舞い込んだのである。四句切れの歌と解した。四首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「炭竈」。三句の「横山」は横山炭を産する和泉国の横山地方をいう。結句「花炭」は梅や躑躅の枝をそのままの形で白炭にした、炎と花炭に比べれば、名だたる取り合わせの松と雪も物の数ではないというのだろう。
表附(き)に誰かかへたそとはいて見りやしんみりきゆる霜のふる下駄
万年もとおもふこころは乞食てもかはらて亀を薬くひする
散(り)しける花みやつこよ中臣のはらひ玉ふな清めたまふな
片遠所の旅路は淋し七夕やうし引(い)た人に稀にあふのみ
一首目の作者は佐藤女鶴江、題は「霜置足駄」。初句「表附き」は畳表のついた足駄をいう。以下「誰が替へたぞと履いて見りゃしんみり消ゆる」、結句は「降る」に「古」だろう。だから二句の錯覚が生じたのである。二首目の作者は栄言軒旗丸、題は「乞食薬喰」。初二句は成句「鶴は千年亀は万年」のうち薬食いする後者に拠った。四句は「変はらで」に「川原で」を掛けた。亀はスッポンの異名であり、薬食いはスッポンと解した。三首目の作者は玉雲斎貞右、題は「社地愛落花」。二句「花宮つ子」は花を神社に奉仕する人に擬した。「よ」は感動である。三句以下は「中臣の祓ひ」と祓詞「祓ひたまへ清めたまへ」をドッキングかつ逆転させた。社地の落花に風情を覚えたのである。四首目の作者も玉雲斎貞右、題は「七夕旅行」。初句「片遠所」(かたえんじょ)は片田舎、三句の「や」は詠嘆だろう。牽牛星は牛車で天の川を渡って行く。地上では牛を引いた人に稀に会うだけだ、と実景の趣きである。
|
| 第115回 狂歌拾遺わすれ貝 |
雲雀さへあかりかねたるけしきかなけふ一日の春雨のそら 樵果亭栗圃
『狂歌拾遺わすれ貝』の詠者は樵果亭栗圃、刊記は寛政九(一七九七)年、栗圃の七回忌追福として編纂された。但し生前刊行の『狂歌わすれ貝』は現在所在不明だそうだ。掲出歌の題は「雨中ノ三月尽」。上句は雲雀が「上がりかねたる」ほどの春雨であった。もしくは春雨が「上がりかねたる」に加えて雲雀までも、となる。多義語の「上がる」を活用した。
斧の柄もかひる斗りのつゆか来てきこりはうちにこりる山里
早乙女やおとこましくらしなしなと濡(れ)つつ植(ゑ)る小田のわか苗
雨の夜もきえぬ螢のともし火は庭山めかした草庵のうち
雨のあしにしりあかりに蝉の声にえる台子のかまひすしさよ
一首目の題は「山中ノ楳雨」。二句は「黴びるばかりの」、結句は「懲りる~」である。四句の「(き)こり」と結句の「こり(る)」、母音要素なら二句の「(か)びる」と結句の「(こ)りる」が反復する。二首目の題は「田植」。二句の「まじくら」は接尾語で「男をまじえて」の意となる。三句「しなしな」は撓い撓むさま、結句「小田」の「お」は接頭語である。初句と結句が呼応する。三首目の題は「螢照庵ヲ」。四句の「庭山」は築山、「めかした」でディオラマ風となるが、展開する景物は深山幽谷の趣きなのだ。四首目の題は「水無月の比雨のふりける日人の許に茶を振(る)舞(は)れはべりしに雨もやや晴(れ)わたるほど植込(み)に蝉のおほく啼(き)ければ」。二句「躙り上がり」は上下に働いて「①雨が上がること②蝉の声が大きくなること」の両意となる。また「躙り」で茶室の「躙り口」の意となる。四句の「台子」は茶の湯で用いる置棚をいう。雨が上がると蝉の声、煮える釜の湯とかまびすしい。
桐の葉の机のうへにちりぬるはけふより秋も風の手ならひ
秋くれとまた汗水にしのはすか池のそこらも忍ひかねたり
わかこころなくさめあかすなには橋きのふの花火けふの月かけ
かはらけのかはくあふらにはかりしる夜も長月の有明のころ
一首目の題は「初秋ノ手習」。三句は「散りぬる(は)」、手習いの初めは以呂波歌だった。その桐の葉を机に運んできたのは結句「風の手(ならひ)」、手習いの主を含めて風を擬人化した。二首目の題は「東武ノ残暑」。名前のとおり不忍池は勿論のこと四句「そこら」(その辺り)も、この暑さには忍びかねるというのだ。不忍池は夏の蓮見、秋は観月で有名だった。三首目の題は「難波橋ノ月」。本歌は〈わが心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て〉(『古今和歌集』八七八)である。三句「慰めかねつ」(慰められなかった)を「慰め飽かず」(十分に慰めてもらった)とした。姨捨山から難波橋、手放しの謳歌に近い。四首目の題は「暮秋知夜長」。上句は「土器の乾く油に計り知る」。初句の「土器」は火皿に用いられている。初二句で「かは」が頭韻を踏んでいる(全体でも母音要素のア音の活躍が目立つ)。三句は理解する意、四句は「長月」(九月)に夜も「長い」を掛けた。夜明けまで点けておく有明行灯だろう。
|
| 第116回 狂歌拾遺わすれ貝(2) |
さてなかい春の日高の川つつみ蛇籠のきはにもゆる若草 臨江亭三津国
『狂歌拾遺わすれ貝』には樵果亭栗圃の教えを受けた人たちの作品が「拾遺わすれ貝附録」として収録されている。掲出歌の題は「塘辺ノ春巾」。上句は「さて長い春の日の日高(日中)の川堤には」と読んだ。四句「蛇籠」は竹で粗く円筒形に編んだ籠に石を詰めて護岸や水流制御などに用いた。大蛇に似ているからの命名という。結句の萌える若草が鮮やかだ。
野遊ひに呼出し酒か雲雀よりちよひちよひちよひとようあかります
おはくろのゐくろめとてや新宅に口へにさしてきたるつはくろ
見あけてはたれもあきれて詠め入る大仏さまのはなの下陰
三月この大根もともに天王寺のたうのあたりにたけてゆく春
一首目の作者は独酔軒華渓、題は「春ノ飲酒」。二句「呼出し酒」は続けて飲みたい気持を起こさせる最初の一杯をいう。すでに「ちょぴちょぴちょぴ」なのだ。結句は空の雲雀よりも「よう上がります」となる。二首目の作者は為笑亭是雲、題は「新宅ニ燕来」。初句は「お羽黒」(羽の黒いこと)に「お歯黒」を重ねた。二句「居ぐろめ」は居なれ住み慣れること。四句の「口紅」は物の縁に付ける紅で燕の額と咽の色をいう。燕の擬人化と「おはぐろ」「ゐぐろめ」「つばくろ」の韻に特色を見る。三首目の作者は臨江亭三津国、題は「南京大仏殿の花を見侍りて」。迂闊だが結句「はなの」まで大仏の下に立っていることを疑わない。桜の花陰に瞬間移動である。四首目の作者も臨江亭三津国、題は「暮春天王寺の辺りをよぎりて」。初句は「やよいこの」、四句「たう」は「塔」(大根の形状また「薹が立つ」を連想させる)、結句「長けて」は季節も植物も終わりに近づくことをいう。天王寺大根は名産だった。
水ものの西瓜はたけも干あかつて照りわるやうな夏の日盛り
天窓から油の汗かなかれます髪の島田をとをる日盛り
白粉も所またらにぬり笠のひもの下から汗そなかるる
夏の夜の螢はかりか暮(れ)てゆく年の尻にも火をともす梅
一首目の作者は臨江亭三津国、題は「田家ノ苦熱」。初句「水物」は「果物」と「運に左右されやすいもの」の両意を活用した。下句の「照り割る」は日照りで地面ががひび割れること、くだんの西瓜畑にも厳しい日差しが注いでいる。二首目の作者は吐雲亭樵山、題は「東海道ノ苦熱」。初句「天窓」は「あたま」と読む。二句「油の汗」は鬢付け油と汗が一緒になったものだろう。結句は汗が「透る」に街道を「通る」を掛ける。ちなみに島田髷は東海道島田宿の遊女の髪形から広まったという。三首目の作者は独酔軒華渓、題は「夏日ノ笠」。初句「白粉」は「おしろい」と読む。二句「所斑」は汗のせいだろう。三句の「塗り」は上から所斑に「塗り(笠の)」、下へは「塗り笠の」紐となる。その下句のリアリティが並みでない。四首目の作者は望郊亭馬朝、題は「早梅」。三句までは起承転結なら起承、四句「年の尻にも」が転で「火をともす梅」が結となる。年が改まることへの思いの火が体言止めで象徴化された。
|
| 第117回 狂歌栗葉集 |
くくれとそいふ間もなつの破れ蚊帳はいるかのこゑひつた穴から 栗跡亭初園
『狂歌栗葉集』の選者は宣果亭朝省、仙果亭嘉栗、雲来亭林栗。刊記は寛政十(一七九八)年、栗柯亭木端の二十五回忌追善歌集である。掲出歌の題は「蚊入蚊帳」。二句の「夏」に「無(い)」の意を掛けた。四句の「ひった」は「簸った」で「風が吹きつけて物を揺らす」(『日本国語大辞典』)の意だろう。括る間もなく、風で広がった穴から蚊が入ってきたのだ。
春なから寒さは冬の通り筋炭火継足す夜半の店つき
花みちの桜の風はさむからて空にしられぬ切紙のゆき
春雨に蛙もをのか歌袋くちをほときにゐての玉川
夜もすから寝ぬさへあるに杜宇行く道てふとこれや拾ひもの
一首目の作者は斤果亭如石、題は「妓館余寒」。妓館は遊女屋である。余寒は旧暦だから十二月後半から一月前半である。結句の「店付き」は置屋の表に面した間に座って客を待つ女郎をいう。二三句は懐手をした客の姿でもあるだろう。二首目の作者は仙方亭春甲、題は「戯場春風」。紀貫之の〈さくらちるこのした風はさむからでそらにしられぬゆきぞふりける〉(『拾遺和歌集』六四)を劇場の花道に置き換えた。結句の「ゆき」は桜吹雪である。三首目の作者は隠鳥舎雪山、題は「名所蛙」。三句の「歌袋」は鳴嚢をいう。鳴く時にふくらませる袋である。四句は「口を解きに」、結句は「井手」に「出で」を掛けた。蛙は鳴くのではない。歌を詠うのである。四首目の作者は河合栗秋、題は「途中時鳥」。時鳥の一声を待って夜を明かすことだってあるのに、その途中で耳にした。これは思いがけない幸運であったというのである。四句「てふと」は「ちやうど」(丁度)と解した。結句の助詞「や」は感動だろう。
水嚢と同し麻蚊帳こせし蚊をいく度となくふるひ返した
夏の日のひるねの夢をさませとやゆすりてそなく蝉のもろ声
今朝秋のきよ水寺の舞台からとんた一葉にひいやりとした
閙しい中へ御座つたたまの客節季しらぬか仏なるらん
一首目の作者は栗正亭雅園、題は「蚊入蚊帳」。初句「水嚢」は漉水嚢の略、飲み水を漉す袋だが水を飲むとき水中の虫を殺さないためのものである。これと同じ麻製の蚊帳を内側へ三句「越せし蚊」を何度も篩って外に返したのだろう。ちなみに水嚢なら「漉せし」、また両方とも「せし」ではなく「しし」が正しい。二首目の作者は橙果亭天地根、題は「蝉声近枕」。蝉は昼間に鳴くのが仕事、昼寝をする人間様とは相容れない存在であるが、それにしても四句「揺すりてぞ鳴く」には臨場感がある。三首目の作者は暁雲亭華峯、題は「寺院秋来」。背景に成句「清水の舞台から飛ぶ」がある。しかし大方の読者が清水寺の景観を想像できる、そのことが結句に貢献するところも小さくないだろう。四首目の作者は仙郷亭棗風、題は「魂祭」。初句は「さわがしい」と読んだ。二句「御座った」は「来た」の尊敬語、「たま」は「魂」に稀なことの「偶」を重ねた。下句の「節季」は掛売買の決算期、尤もな次第ではある。
|
| 第118回 狂歌栗葉集(2) |
乳のたらぬこの哀れさはのます身ももらひ泣(き)する秋の夕暮 若拙堂負米
掲出歌の題は「秋夕囉乳」。「囉乳」は「乳を囉(もら)う」と読んだ。二句「この」は「此の」に「子の」だろう。乳の足る母親が乳の足らない子に授乳する。それは乳の出ない母親が乳の出る女性に我が子を託すことでもある。代用乳とてない、かといって乳母を雇える環境でもない。二句の同情は貰い乳をする赤子から、自ずと貰い泣きをしているのである。
すむ水の色にもまかふ青畳其(の)かはへりに照る月の影
空に月水の底にも月と雲そのまん中に船をうかへた
くくり戸にさし入(る)月は盗人の昼しやないかとおもふ斗そ
婆々は川へせんたくの間にきた時雨まひとつこうかと気をもんてゐる
一首目の作者は松果亭羅文、題は「月照畳」。初二句は「澄む水の色にも紛ふ」は「青畳」の別意「波の静かな青々とした海面」を逆手にとった手法が凄い。四句は「川縁」の平仮名表記が功を奏した。二首目の作者は岸果亭東栗、題は「月夜泛舟」。三句の「月と雲」は水面に映っているのではない。二句「水の底にも」だから下句「そのまん中に船をうかべた」となった。水の上と水の下、その結界に舟を浮かべているのである。三首目の作者は三浦蝉鳴、題は「月照軒端」。「軒端」は屋根の軒先をいう。初句の「潜り戸」は民家の大戸や雨戸などに設けられた、潜って出入りする小さな戸口である。盗人だから雨戸かも知れない。下句は現代人の感覚を越えたものであったろう。四首目の作者は穐果亭板栗、題は「川辺時雨」。三句は「来た」に「北」、四句「まひとつ」は「いまひとつ」、その次は「来うか」で「来ようか」となる。結句は気を揉みながら、しかし洗濯物を「揉んでゐる」婆々の姿でもある。
にくてらしい時雨のあめよ障子をはあくれはふりつさせはさす月
作り花咲(き)にけらしなもり物の山のかひより拝む祖師様
足もとのしもの剣のつめたさにはなしもきれる旅の道つれ
はりつめし氷を棹てわり声のにつちもさつちもゆかぬ川船
一首目の作者は東果亭揚栗、題は「月夜厭時雨」。初句の「憎体らしい」は「憎らしい」。下句「障子をば上ぐれば降りつ鎖せば差す月」から推して障子は上下可動式のようだ。二句の詠嘆「よ」が素直に響く。二首目の作者は如棗亭栗洞、題は「会式」。本歌は〈桜花咲きにけらしなあしひきの山の峡より見ゆる白雲〉(『古今和歌集』五九)。初句は紙や布製の造花、三句「盛り物」は菓子や果物などを盛った供物である。四句「山の峡」は山と山との間をいう。会式は御会式、祖師は日蓮である。三首目の作者は秀果亭栗岑、題は「旅霜」。「霜剣」は霜のように冷たく光る剣をいうが、これを逆にしたのが二句「霜の剣」であろう。だから四句「話も切れる」のであった。四首目の作者は仙秀亭嘉蘭、題は「氷留川船」。二三句は「氷を棹で割り(声の)」、また「割り声」は珠算で割り算をするときに唱える九九の声でもあった。四句「二進も三進も」(どうにもこうにも)は、その「二進一十」「三進一十」から来ている。
|
| 第119回 狂歌栗葉集(3) |
糸をもてくくれは猿となるみかんきいの国より出るとききてし 若拙堂負米
掲出歌の題は「蜜柑」。上句は蜜柑猿という遊びである。実の一袋の中央部を糸で通して括り、上下を丸くしたものだが、簡易な括り猿を想像すれば分かりやすい。四句は紀伊国の古称「木の国」で猿を呼び出し、「き」を「きい」と発音する特性に鳴き声を重ねた。結句「(聞き)てし」は完了の助動詞「つ」の連用形に過去の助動詞「き」の連体形が付いたもの。
わんはくをいひつつ乳母の乳と共にはつた氷をなふるほんさま
ふうはりと置(き)たる雪の綿帽子風にとられし岸の姫松
仕事するそはには毒な火鉢そや得てはつゐ手のあたる物から
かくれんほ節季の鬼もしらぬ子かもうかもうかと春をまちぬる
一首目の作者は寺田李都(女)、題は「児童翫氷」。初二句「腕白を言ひつつ」は駄駄を捏ねるさまだろう。四句の「張った」は氷だけではない。二三句「乳母の乳と共に」なのだ。結句は「嬲る坊様」となる。一、二歳の男の子の姿だろう。二首目の作者は森果亭甘栗、題は「風払松雪」。初句の「ふうはり」という副詞も、おそらく和歌で採用されることはなかったのだろう。二句の「雪」と結句の「松」、三句の「綿帽子」と結句の「姫」が縁語として呼応する。三首目の作者は英果亭桂雄、題は「火鉢」。二句の「毒」は「ためにならないもの」、三句の「ぞや」は「だなあ」と詠嘆的強調を表す。四句の「得ては」は副詞で「ともすると」の意である。四首目の作者は見世(女)、題は「児待春」。初句は鬼遊び、二句は借金取り、子供と大人では大変な違いである。四句の「もう」は初句を受けて「もう(いい)」、結句に向けて「もう(幾つ…)」、「か」はその確認だろう。結句の助動詞「ぬる」に「寝る」が隠れている。
年の尻ひつからけてや小つめ役暮の御祝義申(し)あけます
御社につはくらは巣をかけまくもかたしけなしやちりをましへて
きのふこそ早苗乙女のいつの間にたのみもとりて嫁とよはるる
盗人のうかかふ頃の大あくひはつれやすらん鰓のかけかね
一首目の作者は盤果亭鷺石、題は「歳暮俳優」。初句は「年末(にあたって)」、二句は「一年を引っくるめて」だろう。続く「てや」は軽い感動を表す。三句「小詰役」は上方歌舞伎の下級俳優をいう。四句「御祝儀」は祝いの挨拶である。尻軽な印象だが、対面しているのは師匠筋、場所なら稽古場を想定したい。二首目の作者は若拙堂負米、題は「社頭燕」。三句の巣を「懸け(まくも)」に祝詞の「懸けまくも」を重ねた。四句も同様だが「忝なしや」(面目ないか)と変奏させた。結句「塵を交えて」だからである。三首目の作者は橋本青貢、題は「田家嫁入」。四句「田の実」に「頼み」(結納)を掛けた。本歌は〈昨日こそ早苗とりしかいつのまに稲葉そよぎて秋風の吹く〉(『古今和歌集』一七二)である。四首目の作者は粒果亭方雅、題は「深更大欠」。四句は「外れやすらん」。外れるだろうか。いやそんなことはない。結句は成句「鰓の掛け金を脱す」(大笑いすること)を参考に「あぎとの掛け金」と読んだ。
|
| 第120回 狂歌辰の市 |
長閑さはともに若なをつむ春の野らなむすこもゑくの親父も 仙掌亭不崑
『狂歌辰の市』の選者は仙果亭嘉栗、刊記は寛政十(一七九八)年、栗柯亭木端の二十五回忌追善歌集である。掲出歌の題は「老若摘若菜」。初句「のどかさは」、四句「のら」は怠け者、句としては「どら息子も」だろう。結句「ゑぐ(の)」は「ゑぐい」(灰汁が強い)の語幹用法と解しておく。言い止しだが、倒置法で三句の「の」を除くと意味は完結する。
やうかんの棹をみやけにふる郷へ無事てきかんの春のやふ入(り)
こまのかうにしの字を嫌ふ人さへも此(の)よかんにはしかんたるかほ
その色もうこんの馬場の末遠く北野につつく七野なのはな
木の本へむれつつきぬる笠よりも数は幾千まんかいの花
一首目の作者は徳村嘉洞、題は「藪入買土産」。初句は「羊羹の」、二句の「棹」は助数詞また薮の縁語である。四句は「無事で帰館の」だろう。初句の「かん」と四句の「かん」が韻を踏む。二首目の作者は物先亭梅烏、題は「余寒」。初句は「護摩の講に」で護摩の修法を行なう講をいう。護摩木の文字の二句「し」音を嫌うのは「死」を呼ぶからだ。しかしその人でさえ余寒には顰んだ、渋い顔だという。二句の「し」と結句の「し」が対応し、四句の「かん」と結句の「かん」が反復する。三首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「菜花渺々」。歌意は「右近の馬場から遠く、北野へ続く、そしてその北野を含む洛外七野に菜の花が一面に広がって、その色ときたら右近ならぬ鬱金以外の何物でもない」か。四首目の作者は仙掌亭不崑、題は「花下笠」。上句は花見客の笠の多さをあげるが、下句で桜の「数は幾千万(かいの花)」それほどの「~満開の花」だという。「き」音と「か」音がアクセントになっている。
雪とのみふりあをむけはすけ笠の紐もはつれてはなの下かけ
さひしさをすもし下され我も又よしの行(き)にもまかれたるもの
のこりなくちらし給ふな山桜ありて吉野のはなしこそあれ
よし野山よしやすそわけするとても心の奥の花は忘れし
一首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「花下笠」。二句「振り仰向けば」は「顔をあげて上を見れば」、「振り」に雪が「降り」だろう。その拍子に笠が外れるという劇的シーンである。二首目の作者は峯女、題は「父嘉栗のよし野へまかりし留守見舞(ひ)とて或(る)人のもとより雨の日巻(き)ずしを贈られて春雨のおりにおるすは格別にお淋しかろとすもじいたしたと聞(こ)へけれは」。「春雨~いたした」への返歌である。「す文字」は女性語で「推量」と「鮨」の意。結句は寿司の縁語「巻かれたるもの」に同音「撒かれ~」を掛ける。三首目の作者も峯女、題は「よしののつとに花をもち帰り友どちのかたがたへ遣はし玉ふに」(「苞」は土産物)。本歌は〈残りなく散るぞめでたき桜花ありて世の中はての憂ければ〉(『古今和歌集』七一)である。四首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「返し」。二句「縦や」は「よしんば」の意。初二句で「よし」のリフレインが響く。結句「忘れじ」の「じ」は打ち消しの推量と解した。
|
| 第121回 狂歌辰の市(2) |
宵山やふけ行(く)空をなかむれは四条室町西へ入(る)月 吉岡嘉水
掲出歌の題は「宵山を見て」。祇園会の宵山は前の祭である神幸祭の前夜六月六日、後の祭である還幸祭の前夜六月十三日であった。初句の助詞「や」は場面を提示かつ詠嘆を込めた。山鉾は翌日の巡行に準じて本飾りにし、鉾の上では囃子が行なわれた。ちなみに月鉾だが四条室町西入月鉾町が出していた。また夜が更けるとともに月は東から西へと移っていく。
庄やとののひなによはれて百姓衆もも尻に成り祝ふ酒盛
片田舎桃の節句は庄屋とのに一対揃ふ雛のはりひち
いとさまをたしにつかふて青柳のこしもと衆か桃の酒もり
たけのこのかあいらしくも生ひ出(て)ぬうしろ紐なる垣の結ひめ
一首目の作者は峯女、題は「田家雛遊」。雛の節句は別名「桃の節句」ともいう。庄屋は納税その他の事務を行う村役人、村の長であった。四句「桃尻」は尻が落ちつかないこと。旧家で立派な雛飾りなのだろう。二首目の作者は仙駕亭由鯉、題は「田家雛遊」。先の歌と大同小異の場面と思われるが、舞台を初句「片田舎」に設定した。その違いが結句「張り肘」(手を懐に入れて肘を左右に張ること)であろう。威張って見えるのだ。三首目の作者は鹿女、題は「婦汲雛酒」。初句「いと様」は女児、二句は「出しに使うて」、三句は四句の枕詞ではない。「青柳」「柳腰」「腰元」の連想だろう。良家の子女なのだ。四首目の作者は白桜舎桃下、題は「笋」。二句は「可愛らしくも」、四句の「後ろ紐」は小児の衣服に用いる付け紐である。衿から後ろに回して結ぶ、その後ろ紐に見立てた竹垣に寄り添うような竹の子なのだろう。
たれもみなうつくしよしとほめてたもけふきそめたる蝉の羽衣
うふるにも跡へ跡へとしうとめに随ふよめを何とそしろ田
飛ふ螢かやのちの下すけゆくを面向不背の玉かとそ見る
すんふりの鵜よりもさきへ山端にぬつとあかれる夏の夜の月
一首目の作者は峯女、題は「かたびらをきるとて」(「帷子」は単衣の着物)。二句の「うつくしよし」はツクツクボウシの鳴き声をいう。源俊頼に〈女郎花なまめきたてるすがたをやうつくしよしと蝉のなくらん〉(『散木奇歌集』三四二)がある。三句「たも」は「賜もる」の命令形の音変化で「~下さい」。結句は軽く薄い夏の着物をいう。二首目の作者は仙遊亭嘉橘、題は「早苗」。後退は植えた早苗を踏まないためだろう。横列にしろ好奇の対象になりやすい嫁と姑である。結句の「誹ろ(田~」(誹ることができるのか)は「十代田」(狭い田地)に掛けている。三首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「螢透蚊帳」。二句の「乳」(ち)は蚊帳を吊るための輪をいう。下句「面向不背の玉」は前後どちらから見ても表裏のない玉をいう。蚊帳を隔てて飛ぶ螢が幻想的である。四首目の作者も仙果亭嘉栗、題は「鵜川月」。初句は水中へ鵜が沈みこむさまだが、日の暮れるさまをも表す。四句の「ぬっと」は突然現れ出るさまで、どちらにも該当するが、こちらは月をいつた。オノマトペを駆使して重層的な景である。
|
| 第122回 狂歌辰の市(3) |
夕たちも目利(き)するかやてりぬいた西瓜畑をたたき廻るは 吉岡嘉水
掲出歌の題は「畠夕立」。二句の「目利き」は物の良否を見分けることをいう。西瓜ならポンポンと叩いて鮮度と空洞の有無を調べるのである。三句は「照り抜いた」、「抜く」は「すっかり~する」の意。見立ての歌だが、それほど大粒の、激しい夕立なのだ。現在は空洞を調べる機械があり、店頭にはカットされた西瓜も並び、当たり外れからは遠い消費者である。
土用前きうにふりくるゆふ立の跡の山見てあつさ忘れた
手にさけて名のみすすしの薄羽織扇はかりはたたむ間もなし
風の手はゆるして通す土用干(し)ゆひもささせぬふり袖にして
嫁入(り)も延(は)してほしや夏の日はけはひにつらき汗のおしろい
一首目の作者は峯女、題は「白雨忘夏」。土用入りは小暑の後の十三日目、新暦なら七月二十日頃、旧暦なら六月十日頃である。二句は「きふに(急に)~」。緑被率の高い近世にあっては、その涼感に嘘偽りのない結句だったろう。二首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「扇」。二句は「生絹」(すずし)に「涼し」を掛けた。「薄羽織」(夏羽織)は「手に提げて」いる。それでも暑いから「扇ばかりは畳む間もなし」なのだ。三首目の作者は仙霞亭由紫、題は「土用干」。初句「風の手」は風の擬人化、その手が通るのは許す。四句「指も差させぬ」は「手も触れさせぬ」、風以外の手出しは無用なのだ。結句「振り袖」に手を通すのは年頃の娘、その親にすれば虫を払いたいのは衣服だけではないのである。四首目の作者は幾秋(女)、題は「嫁歎暑日婚」。四句は「化粧に辛き」、化粧の新仮名遣いは「けわい」である。化粧して白無垢、夏も綿帽子では苦行だろう。ちなみに江戸は薄化粧、上方は厚化粧だったという。
けふ秋の色つくからにそろそろと軒の風鈴も声替りした
よみ本もはや見えわかて外題のみなかめてけりな秋の夕暮
ありありと鞠場の松のかけ見へて枝うつりよき秋のよの月
おはくろも染(ま)り色よきよめ御寮細きまゆみのもみちかさして
一首目の作者は仙芳亭春甲、題は「風鈴知秋」。『古今和歌集』の〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(一六九〉と違って目にも耳にも秋、結句が意表を突いた。二首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「秋夕」。初句「読本」は小説の類で読むことを主体とした本の意である。二句「見え分かで」は見分けがつかない。三句「外題」(げだい)は表紙に貼られた書名、四句の助詞「な」は詠嘆、日も短くなったのである。三首目の作者は物先亭梅烏、題は「鞠場月」。飛鳥井雅康に〈鞠の場は七間まなか四方也木と木のへだて二丈六尺〉(『後撰夷曲集』)がある。四隅に植える木のうち西北が「松」、高く蹴上げしたような月なのだ。四句「映り」に「移り」だろう。四首目の作者は仙駕亭由鯉、題は「女挿紅葉」。上句の「~も染まり」で新婚、「色よき」で容姿端麗、「嫁御寮」は嫁を敬った語。以上がプロフィールなら下句の「細き真弓の紅葉挿頭して」は紅葉狩りでのスナップショットであろうか。
|
| 第123回 狂歌辰の市(4) |
あたこ山しくれの桜それ過(き)てゆきの花ちるけふのさむけさ 嘉栗孫十歳 世根女
掲出歌の題は「山雪」。歌意は「愛宕神社に参詣する途次のことだ。時雨桜を過ぎた頃から雨が雪に変わっていた。時雨の秋から雪の冬、今日は本当に寒いことだ」。二句と四句が対句構造になっている。堪忍舎二字守に〈愛宕山山麓の桜時雨てふ名を得てくもる春の月の輪〉(『狂歌手毎の花 初編』)があり、時雨桜という品種の桜が実景であったことが分かる。
叮嚀に冬のしるしを四ツ橋へ四角四面にしくれしくるる
時雨とはふりかはりつつ傘のもみちを破るあられうたてや
わかります雪とすみかま白黒の評判をする桟敷かたけ
ふる雪に小宮小宮も白妙の中に一きはうつくしのみや
一首目の作者は仙秀亭嘉蘭、題は「橋上時雨」。四ツ橋に時雨の降る景。しかし作者の関心は三句から四句の「四・四・四」、二句の「し・し」、三句の「橋」の「し」、四句の「四(し)・四(し)」、結句の「し・し」。同じく結句の「く」「る」の反復にあった。二首目の作者は田園舎私楽、題は「霰破傘」。二句は「降り変はりつつ」、時雨から霰になったのだ。三四句は「紅葉傘」を「傘(からかさ)の紅葉」とした。この頃は粗製品であったろう。結句は「霰」に感動詞の「あら」を重ねた。「うたて」は「情けない」。三首目の作者は仙計亭嘉秋、題は「山雪埋炭竈」。三句「白黒」は雪と炭竈、いや本命は白炭と黒炭の出来であろう。結句「桟敷ヶ嶽」は京都市北区にある山、近世は「さんじきがたけ」と七音で読んだ。四首目の作者は鹿女、題は「祇園雪」。二句「小宮」(こみや)は小さい神社や寺をいう。結句の「美しの宮」は題からしても「祇園社」(八坂神社)であろう。地名としての祇園は代表的な遊里であった。
かはらけと共にちらちらあたこ山よ所にはなけの雪のけしきや
下帯てくくられしよりましろたへ関の地蔵の綿ほうし雪
まろまかす雪のふり袖曳(き)つれてよめり盛りのころころのむす
ゆく年のをさな心や除夜のかねいくつになつても春そまたるる
一首目の作者は仙秀亭嘉蘭、題は「愛宕山雪」。土器投げは如雲舎紫笛も〈あたこ山峯のかたより飛びさかるあれは天狗かいいやかはらけ〉(『狂歌まことの道』)と詠っている。四句の「無げ」に「投げ」を掛けた。二首目の作者は物先亭梅烏、題は「駅路雪」。三重県鈴鹿郡関町にある宝蔵寺を俗に「関の地蔵」と呼ぶ。上句は地蔵尊の開眼を巡る一休宗純の伝説らしい。「下帯」(褌)で括ったのは首、それ以来の「真白妙」で今は雪の綿帽子なのだ。三首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「娘転雪」。初句「丸かす」は丸くする意。四句「よめり」は「よめいり」の変化した語、「嫁入り盛り」は婚期をいう。結句「むす」は「むすめ」の略だが袖を取られての転倒からお結びころころの感もして複雑である。四首目の作者は西田青虹、題は「除夜」。初句の「行く年」は歳晩であり、また年齢でもあるが、新年を迎える気持ちは昔と変わらないという。大切なことを思い出させてくれるのが百八の鐘の響きであるようだ。
|
| 第124回 狂歌辰の市(5) |
終に行(く)道とはきのふけふかたひら吾(か)つまそとは思はさりけり 仙果亭嘉栗
掲出歌の題は「妻のうせければ」。本歌は在原業平の〈つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを〉(『古今和歌集』八六一)である。四句の「今日」が掲出歌では三句の「経帷子」の「経」を兼ねている。「けふ」と「きやう」だが時代は近世である。四句「妻」に着物の縁語「褄」を重ねた。以下四首から推して四十歳前後の作と思われる。
まつとてもいつかへりこん死(に)わかれいなはの山のおみねのこして
ちりはつるならひなれともさりとては花よ紅葉よかかよ娘よ
小町よとたはふれいひしそれも今卒塔婆と成りしおはは可愛や
いたつらにうつりにけりな七小町七とせも夢百とせもゆめ
一首目の題は「峯といへる少女のあれば」。本歌は在原行平の〈立ち別れいなばの山の峰におふるまつとし聞かばいま帰り来む〉(『古今和歌集』三六五)である。「立ち別れ」が「死にわかれ」、「まつとし」以下が初二句で変奏する。「いなば(の)や(ま)」(往なばや)で「帰ろう」となる。「みね」は歌人の峯女である。二首目の題は「真如堂に先立(ち)し娘の塔あるに妻の名も彫(り)添(へ)るとて」。真如堂は京都市左京区にある天台宗の寺、真正極楽寺をいう。三句は「そうであっても」「だからこそ」、せめての思いで石に名前を刻むのである。結句の「かか}は「嬶」、妻である。三首目の題は「亡妻ありし世にたはぶれて おもかげのかはるものならかわれかし小町のやうにこれこちのかか。かくよみしにほどなくうせければ」。結句の「御婆可愛や」の「御婆」は謡曲「卒塔婆小町」に由来する。四首目の題は「とよみしも早七回忌に」。初二句は小野小町の〈花の色は移りにけりないたづらにわが身よにふるながめせしまに〉(『古今和歌集』一一三)に拠った。三句の「七小町」は小町伝説に取材した七つの謡曲の総称をいい、四句の「七」を呼び出した。結句のリフレインで夢幻を強調する。
すゑふろへ入相のかねにけふの日も暮(れ)ぬと告(け)るこん兵衛か宿
君はけふ花のお江戸へ行列や日よりも段々はれはさのよい
一首目の作者は北川里秋、題は「近江にまかりしにある里にて権兵衛といへるもとにやどりて」。初句「据ゑ風呂」は桶の下部に竈を据え付けた風呂、二句「入相の鐘」は晩鐘、結句は「権~」に鐘が「ゴン」となる。二首目の作者は吉岡嘉水、題は「仙果亭の東の旅立(ち)に」。三句は文字通りの「行列や」、「や」は場面の提示と詠嘆だろう。下句は「日和も段々晴れ(後略)」。「はれはさのよい」は「晴れ業の良い」で晴れの仕事の門出を祝う。また三句の「や」に囃子詞を見る。「はれはさのよい」も同様である。颯爽として仲間の誇りだったろう。嘉栗の本名は三井高業、三井家の南家の第四代当主である。二十六歳で家督をつぎ、幕府御為替御用名前の次郎右衛門となった。天明四(一七八四)年、三十八歳で長男に家督を譲り、退隠した。この時まで一、二年ごとに京都本店勤めと江戸勤番を交互に行い、大阪店にもしばしば出張した(岩波書店『日本古典文学大辞典』)。三句からも、この時期の餞の歌と思われる。
|
| 第125回 狂歌辰の市(6) |
呑(み)つつけ日数もひいふうみいら取そのむかひさけそのむかひさけ 仙果亭嘉栗
掲出歌の題は「連日酒」。嘉栗の墓は大阪市天王寺区の浄土宗西方寺にあり、その墓碑に右の歌が刻まれているらしい。退隠後の嘉栗は五十歳のとき三井家内紛の罪をかぶり江戸重追放となっている。寛政十一(一七九九)年、中風で倒れて死去、五十三歳であった。狩野快庵編『狂歌人名辞書』によると仙秀亭嘉蘭は妾腹の子である。いける口であったらしい。
暮(れ)限り錠前ひんと箱根山四角四面にさしたものしやな
是(れ)や此(の)といふよりさきに手を出(た)すかりたの有所しるも知らぬも
此春ははなの下こそやすからね一こくあたひ二百五十目
二百目のそとをり姫やささかにのさかつて来へきよいさたかする
一首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「関路夕」。初句は暮れ六つの規則通り。二句の「ぴんと」は錠前を掛ける音、役人が関所の門を「箱根」の箱よろしく「四角四面に差した」のである。「じゃ」は断定、「な」は詠嘆、呆れているのだ。二首目の作者は峯女、題は「歌骨牌」(「うたがりた」と読む。「うたかるた」の変化した語)。四句「有所」は「ありど」と三音で読んだ。ひどい御手付きは他の競技者の鼻白むところだろう。三首目の作者は仙果亭嘉栗、題は「天明の頃米の価いとむつかしかりけれは」。二句「鼻の下」は口、口に入る米が安くないという。重ねて桜の花の下での宴会も易くない。四句は「春宵一刻値千金」を使って「一石値~」に「一刻値~」、結句の「目」(め)は銀貨の量目の単位、匁の略である。四首目の作者も嘉栗、題は「其(の)後日々にやすらかに聞(こ)へけれは」。本歌は衣通姫の〈わが背子が来べき宵なりささがにの蜘蛛のふるまひかねてしるしも〉(『古今和歌集』一一一〇)である。三句からの「蜘蛛の下がって来べき」も、「宵~」の「良い沙汰」も巧みである。
本玉のあつきめくみに此(の)はなもかかる嬉しきめにもこそあへ
ふりかへりみやこの桜ならうなら此春はかり墨染てさけ
智恵かそかちと智恵うろか極上のよき智恵も有(る)かしちゑも有(る)
嘉栗の歌が続く。一首目の題は「目かねをもらひて」。初句「本玉」は眼鏡の玉の水晶製のものをいう。三句は「此の鼻も」、四句は「斯かる~」(このような)だが、一方で鼻にも「掛かる」だろう。結句の「目」も感覚器官としての目と、巡り合わせとしての「目」の両意があろう。二首目の題は「類焼の春伏見に引(き)移るとて」。三句は「成ろうことならば」、すでに春なのだ。京都市伏見区深草墨染町の墨染寺(通称「桜寺」)にある桜を墨染桜と呼ぶ。上野峯雄に〈深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染に咲け〉(『古今和歌集』八三二)があり、同歌の登場する謡曲に『墨染桜』もある。振り返れば市中の大半が焼失「桜よ少しは人の心を思い遣ってくれ」と解した。三首目の題は「召仕(ひ)なる与吉嘉七等か働(き)にて諸色よくかたつきけれは自慢して」。やはり天明の大火だろう。類音反復同音反復の中、四句「よき智(恵)」に「与吉」、結句「かしち(ゑ)」に「嘉七」を隠して上機嫌である。
|
| 第126回 興歌かひこの鳥 |
元日にそる月代のもみ心はけるものとはおもはれもせす 得閑斎繁雅
『興歌かひこの鳥』の撰者は得閑斎繁雅(一七四八~一八一三)、刊行は寛政十二(一八〇〇)年である。掲出歌の題は「としたつ日」。三句は揉み湯(剃る前に皮膚につけて揉む湯)を使っているときの感想だろう。下句は「禿げるものとは思はれもせず」、ほっておいたら黒々と生えてくるのだろう。繁雅は九如館鈍永の高弟で一派をなした。京都の商人である。
年玉の手鞠にてうと百のうへはつんてこませと端銭まてつく
造りなす棟もななへや八重霞立(ち)こそつつけここのへの春
見せものの小屋もそろそろ片つきて河原にたてる秋の淋しさ
露と消(え)し人を迎へて祭るてふはちすの上はたまたらけ也
一首目の作者は季隆、題は「年玉に弄物を求めて」。「年玉」は新年の贈り物、「弄物」(まさぐりもの)は慰みものをいう。二句は「ちょうど」(ぴったり)、三句の「百」は「百厘」の意か、これに突いた鞠の数だろう。四句「弾んで」は金を「奮発して」、また鞠突きを続ける意を掛ける。「こませ」は補助動詞で「てやれ」。結句は「端銭(はせん)まで付く」。「端銭」は「毛」か、「付く」(渡す)に手鞠を「突く」を掛けた。二首目の作者は得閑斎繁雅、題は「天明八年申の春京師の大火に禁裏炎上せしが明(く)る酉の春 御造営成就有(り)けるを恐(れ)ながら悦びて」。二句「七重」と三句の「八重」と重ねながら結句「九重」、宮中の春を祝した。天明の大火は一七七八年、皇居も罹災した。市中の焼失家屋は十八万余に達したという。三首目の作者は白賀、題は「立秋」。京都の三条、四条の河原には芝居小屋や見せ物小屋が並んだという。その小屋も興行が終わって解体、代わって「河原に立てる秋」なのだ。但し更地から聞こえるのは風の音ばかりだろう。四首目の作者は得閑斎繁雅、題は「魂祭」。〈露と消えし人を迎へて祭るてふ蓮の上は魂だらけ也〉。初句は死ぬ意。結句は「魂」ではなく「玉」(露、水の玉の意)だが、「魂」と「玉」は同語源である。四句の縁語「蓮」によって繋がった。
踊子の跡にも風の手拍子はよすからさはく庭の荻の葉
いたたきていたみ入(り)けり我ら迄くらはされたる御こふしの茸
河堤めくるしくれもゆく人のさきへ成(つ)たり跡へなつたり
一首目の作者は楚雀、題は「荻」。踊り子の手拍子が止んでの後、風の手を応用した二句「風の手拍子」が止まないという。四句は「夜すがら騒ぐ」である。結句の「庭」は盆踊りの会場、周辺は荻原なのだ。二首目の作者は得閑斎繁雅、題は「正親町三條家狩に出(で)させられし御こぶしとて誠に見事なる松茸拝領せし御礼まうし上(ぐ)るとて」。「こぶし」は狩の獲物を意味する「拳」だろう。多義語としての「拳」(拳骨)を効かして二句「痛み(入り)」は恐縮の意に痛覚、四句「食らはされたる」も食の意に強打となる。三首目の作者も繁雅、題は「堤時雨」。初句は訓読で五音、二句「巡る」はあちこち移動すること、「時雨」は降ったり止んだりの小雨をいう。一本道だから、人と同じで先になったり後になったり、なのだ。
|
| 第127回 興歌かひこの鳥(2) |
打出(て)て見上(く)る雪の白妙に大仏殿は下京の不二 得閑斎繁雅
掲出歌の題は「雪のあした方広殿をのそみて」。本歌は「百人一首」でも知られる〈田子の浦にうち出でて見れば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ〉(『新古今和歌集』六七五)である。四句「大仏殿」の高さは約四十九メートルだった。結句の「下京」は三条通以南の地をいい、「不二」は富士山である。寛政十(一七九八)年の落雷による焼失以前の詠であろう。
ほうはつていはれぬ程に手に余り口にもあまる節分の豆
きさんてもきさんても唯君に似る仏の顔に罪つくるなり
安土てふ寺へよる間にくれかかる日の短かさは論のない秋
こかねしく月をみ堂のささら浪千体仏も物の数かは
一首目の作者は疎慵、題は「同し夜いくつに成(る)そと人の問(ひ)しこたへに」。節分の夜なのだ。初二句は「頬張って言はれぬ程に」、三句は処置出来ない意だが、応用して口一杯手に一杯の豆(年齢)とした。二首目の作者は得閑斎繁雅、題は「仏師恋」。片思いの仏師には罪作りな「君」を結句で効かした。罪とは純真な者を欺く、また仏道にそむく意である。三首目の作者も繁雅、題は「長月半(は)あふみの国彦根にまかりけるかへさ安土の宗建寺に参りけるか高かりし日も山のはにかたふきぬれは」。「長月」は陰暦九月、「帰さ」は「帰るさ」(帰る途中)の音変化である。「宗建寺」は安土山が山号の総見寺と思われる。結句の「論のない」(論なし)に注目した。意味は「論じるまでもない」。天正七(一五七九)年、織田信長が行わせた安土宗論(浄土宗と日蓮宗の論争)を重ねた。四首目の作者も繁雅、題は「木の浜より堅田にわたり浮御堂に参りしに折(り)から月湖水をてらしてえならぬなかめなれは」。「木の浜」は「このはま」と読む。二句は「御」に「見」を掛けた。黄金を敷いた上に月が浮かんでいる図である。三句「細浪」は細かく立つ浪、四句「千体仏」は同一面に同形の多数の仏像を彫刻または描いたもの、結句「かは」は感動のこもった疑問の意を表す。
盆といへは小踊りをせしやつとさも今は立(ち)居のかけ声にして
小判紙といふ名にめてて山吹のきに染(ま)すともうけて給はれ
小判紙をもらふはよいかとてもならきらひのしの字のけて給はれ
一首目の作者は得閑斎繁雅、題は「寄盆述懐」。盆といえば盆踊りで「小躍り」(踊りの縁で「小踊り」を採用)したのも遠い昔、踊りの「やっとさ」も立ち上がるときの掛け声になってしまったというのだ。二首目の作者は露水、題は「得閑斎の狂歌をこひし挨拶に小判紙三束送るとて」。「小判紙」は版の小さい紙をいう。四句の「き」は「黄」に「気」を掛けた。山吹色(小判)ではないが、気に染まないかも知れないが、よろしくというのだ。三首目の作者は繁雅、題は「と聞(こ)えける礼状のはしに戯れて」。「聞こえける」は「仰る(露水への)」の意となる。三句「とてもなら」は「せめてのことに」、四句の「嫌いのしの字」は「紙」の「し」音が「死」に通じることをいう。で、どうせなら小判がいいとなった。
|
| 第128回 狂歌家の風 |
呵(り)たる子供よゆるせ今朝の春まつにほたへたきのふ一昨日 栗本軒貞国
『狂歌家の風』の詠者は栗本軒貞国、広島の人である。刊記は享和元(一八〇一)年。『近世上方狂歌叢書九』の解説によると「栗本軒」以前の号は竹尊舎らしい。掲出歌の題は「歳旦」。初句は「しかりたる」、四句は「待つにほたえた」(「ほたえた」は「ふざけた」「じゃれた」等)、待ち遠しくて落ちつかなかったのだ。結句「一昨日」は「おとつい」と読んだ。
昼飯もきのふのやうに覚(え)けりそれから後のはるの夕くれ
あつさ弓夕への風の涼しさにぬいたるかたもいるるもののふ
中秋の兎はあれとそれよりも蚊かもちを搗(く)夏の夜の月
庭の面はきのふの夏の打(ち)水にましてひいやりふく秋のかせ
一首目の題は「春夕」。近世になって三食が一般化する。初句「昼飯」の読み方も数通りあるが「ひるめし」としておく。度胆を抜く上句、その理由が下句である。どうやら春の午後はのたりのたりと暮れてゆくらしい。二首目の題は「武家納涼」。初句「梓弓」から二句の「夕べ」のイレギュラーは類音で結びついたのだろう。四句「脱いだる」は「脱ぎたる」のイ音便で連濁となる。以下「肩も/入るる武士」である。「梓弓」なら「射る武士」も着物に肩を「入るる」となった。三首目の題は「夏月」。初句「中秋」は陰暦八月十五日で秋、しかし「題」に加えて結句も「夏の夜の月」だから面白い。兎は月で餅を搗くが、その名月を邪魔するように蚊が餅を搗いている(蚊が群集して上下に移動しながら浮遊するさまをいう)。四首目の題は「庭上秋風」。四句の「まして」が気になる。たぶん動詞の「増す」の連用形に助詞「て」のついた「増して」と副詞の「増して」が同居しているのだろう。そこが見所でもある。
二王門てる月影に浮雲よ出さはつて握りこふし喰(ら)ふな
ひまくれた女房をおもひ出(た)しけりひとりめし喰ふ秋の夕くれ
引上(け)てさこの子もゐぬ網の目に風のみとまる秋の夕くれ
手水鉢氷(り)ついたる柄杓にて夜半のさむさは汲(ま)すしてしる
一首目の題は「二王門月」。四句「出さばって」は「出しゃばって」の変化した語、「握り/こぶし」で句またがりになる。「揃って月見をしている二王の邪魔すると痛い目にあうよ、浮雲さん」というわけだ。二首目の題は「秋夕」。初句の「暇」は「長のいとま」をいう。逃げられたのだが、原因は男にあった。栗柯亭木端にも〈かやり火のふすべる閨の独りねに悋気で去つたつま思ひ出す〉(『狂歌かがみやま』)がある。三首目の題は「漁村秋夕」。二句の「ざこ」は小魚の「雑魚」、「雑魚の子も」は一匹も、の強意強調と解した。三四句は成句「網の目に風とまらず」(網を張っても風を防ぐことはできない)を逆手にとった。無駄なことの喩えらしいが、これも強調表現だろう。四首目の題は「冬朝といへることを」。初句「手水鉢」(ちょうずばち)は手洗いの水を入れておく鉢である。二句の「たる」の「る」が脱落して現在の「氷りついた」になる。結句、柄杓もろともだから実際にも汲めないのである。
|
| 第129回 和歌夷 |
呼(ひ)出しの扇いかやら団扇いかあくる角力の二條河原に 牧笛
『和歌夷』の選者は四穂園永田貞也、刊行は享和三(一八〇三)年である。掲出歌の題は「川辺鳳巾」。人寄せのための扇や団扇の形の凧が揚がっているのだ。四句「挙ぐる」と連体形、結句が「に」では歌が終わらない。結句「二條の河原」も一案であろう。『日本歴史地名大系』で「鴨河原」等を繙けば近世における興行は三条から六条の河原だったと思われる。
来いと待(つ)螢は来いて呼はぬ蚊のむしくる夜さや橋詰に出て
跡見よといふて茶店をたつ客も暑さ忘れていぬる川床
さしかかり降(る)雨やとる寺の軒落書(き)に見る傘はあれとも
婚礼の座敷やめくるさかつきの影のさし図も秋の仲人
一首目の作者は永田貞也、題は「橋辺蚊」。二句「来いで」の接続助詞「いで」は活用語の未然形に付く。打消しを表して意味は「来ないで」となる。四句の「虫くる」は「蒸る」に掛けている。「夜さ」は「夜さり」の変化で「夜」をいう。二首目の作者は破扇、題は「茶店納涼」。初句の「跡見よ」は「金は桟敷に置いていく(忘れるなよ)」だろう。茶店の主にそう言った客も、性質は異なるが、下句「暑さ忘れて去ぬる川床」となる。但し損はしていない。三首目の作者は鷹羽、題は「寺院雨舎」。寺の前を通りかかったところで雨にあった。やむなく軒を借りたが、見ると落書きされた傘がある。結句は「あれども(差せない)」だが、初句の「差し」に呼応して今にも使えそうな錯覚を生む。四首目の作者は吐楽、題は「座敷月」。四句の「影」に注目したい。まず三句から四句の「盃の影さし」は「(さか)月の影差し」、これが下句では「影の指図も秋の仲人」となる。祝宴とそれを演出する配慮が対照的である。
千代能の桶と違ふて河童のいたたく皿にやとる月影
猫も来は袋に入(れ)て鞠に蹴ん山寺淋し秋の夕くれ
照りつ又降(つ)てきつねの嫁入(り)か時雨は三三九度も十度も
幾しくれしくれてやとる辻堂の仏の顔も三度といふに
一首目の作者は一扇、題は「月下獣」。初句「千代能」は霜月騒動で一族を滅ぼされた安達泰盛(一二三一~一二八五)の娘、〈千代能がいただく桶の底ぬけて水たまらねば月も宿らず〉と詠んで悟りを開いた逸話で知られる(神谷道倫『深く深く鎌倉史跡散策』)。三句「河童」は「かわどう」と湯桶読みで「千代能」に対応させたい。二首目の作者は永田貞也、題は「寺院秋夕」。初句は「猫も来ば」(来たなら)である。当時の手鞠唄「山寺の和尚さんは/毬がお好きで毬はなし/猫を紙袋へへしこんで/ポンと蹴りゃ/ニャンと鳴く/(略)」に拠った。三首目の作者は清巴、題は「時雨度々」。二句の振り仮名「つ」は「り」の可能性もあるが、初句の「つ」、二句の「きつね」の「つ」との呼応は無視できない。これと数のマジックが命なのだ。四首目の作者も清巴、題も「時雨度々」。下句は成句「仏の顔も三度」(仏の顔も三度撫ずれば腹立つ)」を使った。同音反復と数のマジックの前に仏様もあきらめ顔だろう。
|
| 第130回 |
婆は河へ気のせんたくか網舟て最ひとつ鯉をうてとおもしやる 玉雲斎貞右
『狂歌二翁集』の選者は蝙蝠軒魚丸、跋文は享和(一八〇三)三年、二翁とは桃縁斎貞佐と玉雲斎貞右をいう。掲出歌の題は「老女川狩」。四句の「最ひとつ」は「も一つ」である。結句は「(鯉を捕るための網を)打てと」、次の「おもしゃる」は「お申しある」の変化した語で「仰せになる」。「お婆さんは川へ洗濯に…」を踏まえた二句「気の洗濯」であった。
よくとくの望みも今ははなれ家にうへて楽しむ此(の)金銀花
ああしんきはらたち花の種をうへて待(つ)ほとときす軒にきをらぬ
風鈴の音すすしやと夕暮にちりんとなりの人もより来る
竜宮の鏡立(て)とやみやしまの鳥居にかかる秋のよの月
一首目の作者は某丸、題は「閑居夏艸」。初句は「欲得の」、三句は欲得を「離れ(家に)」と欲得はそのまま「離れ家に」となる。真相はというと、金銀は金銀でも、隠居の楽しみは植物の「金銀花」(スイカズラ)であった。二首目の作者は桃縁斎貞佐、題は「軒橘」。初句の「辛気」は「じれったい」、二句は「腹立ち(花の)」と「(はら)橘の」、三句の「種」は癪の種でもある。結句の「きおらぬ」(来よらぬ、来ない)が目を惹く。橘と時鳥は『万葉集』以来の配合である。三首目の作者は旗丸、題は「納涼」。四句は「ちりんと鳴り(の)」と「(ちりん)隣(の)」が重なるが、狂歌に見る修辞法の一つといってよく、上の三音も例外ではない。四首目の作者は桃縁斎貞佐、題はない。挿絵の一首である。二句の「鏡立て」は鏡を立てかける木製の枠をいう。「とや」は「と」で受ける内容に対する疑問を表す。三句「宮島」は厳島の別称。したがって厳島神社を竜宮城に、鳥居を鏡立てに、それぞれ見立てたことになる。
定めなきあまの橋立しくるれと日かけさす也雲のきれとは
寒き夜やこたつにあしをさし向ひ昔はなしをする祖父と祖母
ゆらゆらと酔(ひ)心地する葛橋もみち散(り)しくうへをわたれは
薪よりまつ厚氷斧をもて打(ち)わつてたく仙か茶の水
一首目の作者は辻丸、題は「橋辺時雨」。二句の「あま」は「天」、これに「雨」を重ねた。四句「日影」は太陽の光、結句「切処」は砂州の一部が切れている所をいう。天の橋立の先端にある、宮津湾と阿蘇海を結ぶ水道もその例である。今なら「天使の梯子」というのだろう。二首目の作者は秋水、題は「櫨辺閑談」。結句の「祖父と祖母」に着目した。読みは「そふとそぼ」だろう。安田純生の『現代短歌のことば』によれば擬古典語の「おほちち」と「おほはは」が登場するのは大正年間であるらしい。三首目の作者は之唀、題は「橋上落葉」。三句「葛橋」は葛を素材とした吊り橋で普通名詞と解した。ただでも揺れる、しかも落ち葉した紅葉を踏むと「私」も山の色に染められてゆくのであった。四首目の作者は蝙蝠軒魚丸、題は「山中氷」。初句「薪」は「たきぎ」、四句は「打ち割って焚く」、結句の「仙」(そま)は木樵の意と解した。厳冬期に水を確保することを思えば、これと似たことがあっても驚かない。
|
| 第131回 狂歌二翁集(2) |
死んて行(く)処はおかし仏護寺の犬の小便するかきの本 桃縁斎貞佐
掲出歌の題は「辞世」改行して「一枝の花に笑ふて死んで行(く)あとにて花が笑ふとこちやしらんしらぬ所が仏なりけり」とある。仏護寺は現在の本願寺広島別院、貞佐(一六九九~一七七九)は広島の酒造家であった。結句の「垣の本」に「柿の本」を掛ける。犬が小便するのは貞佐の墓ではない。犬に小便されているのは正当を自称する和歌人たちなのだ。
一文のわたしの舩を仰山にこはんこはんと呼んてのる武士
打(ち)付(け)た茶碗もわれし女夫中跡は近所か世話をやきつき
材木のしるしを手本と砂書(き)に習ふ浜辺の月の夜鷹は
おし合(う)てすりむくさんりのきうくつやしひり京へとつみのほり舩
大海を我(か)ままにした鯨てもあはれに家のともし火となる
一首目の作者は道丸、題は「渡場武士」。四句は「請はん」に「小判」だろう。ただ「請はん」はハ行転呼音により「こわん」であった筈だ。「小判」は「こばん」だから現実には聞き誤る可能性は少ない。文字通り文字の上で成立した面白さであろう。二首目の作者は物丸、題は「女夫喧嘩」。「女夫」は「めおと」と読む。結句は「世話を焼き(つぎ)」に「(世話を)焼き接ぎ」となる。「焼き接ぎ」は欠けた陶器を釉(うわぐすり)で焼きつけて継ぎ合わせること、もちろん夫婦仲の比喩である。三首目の作者は豊丸、題は「辻君手習」。三句の「砂書き」は砂絵ではない。地面に指か何かで二句の「手本」(木印ないし家印)をなぞっているのだ。四句の「浜辺」は大坂で川端をいう。材木問屋が並んでいるのだろう。結句は「月の夜」と「夜鷹」の合体である。四首目の作者は玉雲齋貞右、題はない。挿絵の一首である。漢字仮名交じりだと〈押し合うて擦り剥く三里の(灸)窮屈や痺り京へと積み上り船〉となる。「三里」は灸のツボで膝頭の下をいう。「痺り京へ上れ」は痺れが切れたときの呪い、人も荷も一杯なのだ。五首目の作者は桃縁斎貞佐、題は「寄燈無常」。照明には蝋燭と油が使われた。蝋燭は高価だが油より明るく取り扱いも簡単だった。油では無煙の菜種油が主役だった。これに対する鯨油は臭気があり、その分だけ菜種油より安かった。上句とは対照的な死に光である。
一たんは薬て治して而(し)てのちにきするも定(ま)る寿命しや
作者は玉雲齋貞右(一七三四~一七九〇)、題は「五とせのむかしさつきなかば病(ま)ふになやみて 定まつた所じやことし五十三めい日も又五月十三日 かく詠じてすでに事きれなんとせしが夜もすがら蛤貝をもて薬を用ひ翌るあしたやうやう心よくて なきがらとよばれはせじな蛤のかひある薬命すくふて とよみてふたたひ生(ま)れ出(で)し心地せしがことしきさらぎのすへに世を辞するとて」とある。辞世だけの話でいえば、この五年前に死んでおくべきであった。その幻の快作を再掲しておく。丸派の租は大阪の商人であった。
定まつた所しやことし五十三めい日も又五月十三日
|
| 第132回 狂歌芦の若葉 |
こらえられぬ春の寒さは天に口なけれと雪のふれる諺 其遊
『狂歌芦の若葉』の撰者は得閑斎繁雅、刊記は文化四(一八〇七)年である。掲出歌の題は「余寒雪」。結句の「諺」は「天に口無し人を以て言わしむ」だろう。意味は「天はものを言わないけれども人の口を通して言わせる」。だが「雪のふれる」と天意は形を変えて表されている。初二句は人の反応で「人を以て言わしむ」、雪を降らせる天も寒がっているのだ。
たはこのむ煙のやうにおんほりときせる店まてかすむ四(つ)橋
春草も萌(え)揃ふ野に焼(き)筆をはしらす絵師は手のみ遊はす
千金といふもここらかくれさうてついくれかたきはるの夕くれ
うちひさす語意も都の山の端にほんのり見する春の曙
一首目の作者は季隆、題は「橋辺霞」。三句「おんぼり」は情景がはっきりとしないさま、白縁斎梅好の歌に〈四ツ橋の名代を通すきせるやの買人はひびにつまる店さき〉(『興歌帆かけ船』)があるが四つ橋は煙管店が軒を連ねていた。その煙草がらみで景を仕立てた。二首目の作者は素来、題は「画工野遊」。三句「焼き筆」は柳などで作った棒の先端を焼いて消し炭状にしたもの、下絵を描くのに用いた。結句は「手のみ遊ばず」だろう。真剣なのだ。三首目の作者は茂喬、題は「春夕」。漢字仮名交じりだと〈千金といふもここらか暮れさうでつい暮れがたき春の夕暮れ〉、四句の「つい」は副詞で「すぐ」「じきに」の意、しかし暮れない「ここら」すなわち宵との境目が「一刻千金」なのだ。四首目の作者はかや丸、題は「都春曙」。初句「うちひさす」は二句「都」に掛かる枕詞であるが語義及び掛かり方ともに未詳である。二句の「語意」は「私」の解釈、それが「都」以下の朝日を内包した山の稜線なのだ。
井手といふ名はとふ迄もなくかはつこの玉水のついそこにそれ
善光寺みのりをたのみすく人も牛にひかれてゆくや田のうね
やあはりとすきかへす地は紙ならて扇にえんのある御田かや
小栗栖の薮際に出たたけのこは光秀よりも見のかされまい
一首目の作者は朶丸、題は「名水蛙」。二句「とふ」は「問ふ」に「跳ぶ」を掛けた。前者は名所「井手の蛙」に拠り、後者は下句の話者のとおりである。ちなみに三句の「なく」は「無く」に「鳴く」だろう。結句の会話体が新鮮に響く。二首目の作者は三枝、題は「春田」。成句「牛に引かれて善光寺参り」に拠った。二三句は「実りを頼み鋤く人は」、「頼み」に秋の「田の実」を掛けた。下句は牛に唐鋤を引かせる姿を逆転させて結句「や」の反語となる。三首目の作者は度水、題は「春田」。初句は「やーわりと」なのだろう。伊勢神宮の御田植神事で用いる大きな扇が御田扇、その図柄も稲田に関係するので三句「紙ならで」となる。結句「かや」は終助詞で感動と詠嘆だろう。四首目の作者は和珹、題は「竹子」。初句「小栗栖」は京都市伏見区の地名である。天正十(一五八二)年、山崎の合戦で敗れた明智光秀は近江の坂本城に向かう。しかしこの地に至って土地の者に竹槍で刺殺された。よって明智藪という。片や子であっても竹の子、罪は人の比ではない。
|
| 第133回 狂歌芦の若葉(2) |
大みねののそきは井戸の西瓜より釣(り)おろされて肝や冷さむ 蘭丸
掲出歌の題は「峰入」。下句が不安定である。通常なら〈大峰の覗きは井戸の西瓜より肝や冷さむ釣(り)降ろされて〉となる。整理することで失うもの、臨場感へのこだわりであろうか。ともあれ覗き岩(高山で谷間に向かって差し出た岩)に惹かれるものがあった。人も釣り下げられて、再び釣り上げられるのだが、西瓜よりも肝を冷やすだろうというのである。
とろ河にやとりはとれと大峰へのほるは六根清浄のこゑ
くひ入(り)てさむる枕に飛(ふ)蚤もとらへところはなつの夜の夢
もむ数珠の玉と欺く身の汗や世の濁りにはしまぬ行者も
せき入れし川はひつつくよいてりにひやす西瓜の水を賞翫
其(の)なりもにふの河辺のまくは瓜流れに枕の語をやひく蔓
一首目の作者は茂喬、題は「大峰」である。初句「洞川」(どろかわ)は修験道の根本道場大峰山山上ヶ岳への登山口、二句「宿り」は動詞「宿る」の連用形の名詞化である。「洞」と同音の「泥」を効かせて下句「六根清浄」に対応させた。二首目の作者は繁雅、題は「蚤鷲夢」。〈食ひ入りて覚むる枕に飛ぶ蚤も捕らへ所は夏の夜の夢〉。結句「夏」に「無(つ)」を掛けた。「と」音を反復しながら消えていく蚤「夢か現か、空を行く鷲のようだった」か。三首目の作者は砂長、題は「夏行者」。上句は手に揉む「数珠の玉」かと見紛う、つまり欺く「汗(の粒)」、助詞の「や」は詠嘆だろう。これと対応するのが下句の「世の濁りには染まぬ行者も」となる。下句と上句が倒置の関係である。四首目の作者は季隆、題は「水辺瓜」。歌の構造は「堰き入れし川は(干っ付く良い照りに)冷やす西瓜の水を賞翫」だろう。川に堰を作って西瓜を冷やしているのである。丸括弧の中は「私」の乾いた咽をいう。だから「西瓜」でなくて「西瓜の水(を賞翫)」となった。五首目の作者は其遊、題は「水辺瓜」。歌意は「その形も吉野の丹生川の「丹」ではないが、枕に似た真桑(音まで似ている)、その真桑瓜が流れに浮いている。これが「石に漱ぎ流れに枕す」の成句と繋がる蔓であろうか(いや、そんな…)」如何。
筏士にとふまてもなく谷水の濁るにそれとみねの夕立
大かたは褌はかりてくらしたる夏のなこりかくふ麦団子
かへるさも忘れて舟にうかれめと花火も揚(け)て遊ふ浪速津
一首目の作者は不山、題は「峯夕立」。初句「筏士」は筏乗り、対する「私」は釣り人だろうか。結句「峯」に「見ね」を掛けた。峯を見なくても、川の水の濁りから夕立だと分かるというのだ。二首目の作者は茂喬、題は「晩夏」。作中主体は何をして暮らしているのか、職業不詳の不思議な褌男である。結句「麦団子」は小麦粉でつくった団子をいう。麦の取り入れは初夏であった。三首目の作者は湖暁、題は「花火」。初句「帰るさ」は帰る時をいう。三句は「浮かれ女」に「浮かれめ」(船、また気分)だろう。結句「浪速津」は古代の港だが〈難波津に咲くやこの花冬こもり今は春べと咲くやこの花〉(『古今和歌集』)を連想した。
|
| 第134回 狂歌芦の若葉(3) |
白小袖かす看板を釣る軒によるむく鳥も一れつのいろ 繁雅
掲出歌の題は「軒色鳥」。初句は損料をとって貸す葬式衣装をいっているのであろう。西鶴の『日本永代蔵』に「葬礼のかし色、ゑぼし・白小袖・紋なしの袴」とある。下句は「寄る椋鳥も一列の色」だろう。椋鳥は顔と腰に白い羽毛がまじるが、全体としては黒色である。これが葬礼の貸し色によって葬列の色に変わる。軒の椋鳥を客に見立てたのであった。
宮の名の落葉かき分(け)きのこをは狩る大将はけふも御忍ひ
松茸のかさも仕丁にもたせつつさかすは山のお公家様かた
水攻(め)の其おもかけも立(ち)こめて霧の海にそ沈む城跡
魚篇に夏とかくのは冬くふてあたらぬ文字の理かや河豚汁
一首目の作者は砂長、題は「貴人茸狩」。松茸は赤松林の地上に発生する。よって初句は赤松宮を指す。興良親王(生没年不詳)をいい、南朝の皇族であった。父は護良親王、母は北畠親房の妹、征夷大将軍にも任じられた。二首目の作者は季隆、題は「貴人茸狩」。二句「仕丁」は貴族の家で雑役に使われる下男である。初二句は雨なのだろう、その仕丁に松茸に似た傘も、松茸も持たせていると解した。下句「山のお公家様方」は松茸をいう。三首目の作者は砂長、題は「古戦場霧」。初句「水攻め」は城の周囲に堤を築き、付近の湖川の水を導入して城を水浸しにする戦法である。二三句は「面影に立つ」を「面影も立ち籠めて」と四句に接続したところが上手い。現場を俯瞰する趣きである。四首目の作者は其遊、題は「河豚汁」。『大字源』(角川書店)の附録の「国字一覧」に「魚夏」で「ふぐ」とある。ちなみに魚偏に冬は「鮗」(このしろ)である。結句「かや」は疑問の意、勝手な語源に自ら遊んでいるのであろう。
ゑふて目もちらつく雪に面白い咄しのつもる酒の友とち
こやしとる得意へ米は渡しつつ我(か)屋の餅をつく年の尻
豊年のあきのかたへと宿かへて道具も取(り)いれ急く百姓
高もちの宿かへの荷は田畑よりいくせたすけて運ふうし馬
一首目の作者は華友、題は「雪中友」。二句「ちらつく」は上から「酔うて目もちらつく」、下へは「ちらつく雪に」となる。四句で「つもる」のは「咄し」だが「雪」の縁語でもある。二首目の作者は素人、題は「農家餅搗」。羽田山丸に〈相替はらず目出たきつけと暮れ毎に小便かへがくれる豆がら〉(『除元狂歌集』)があった。小便買いも人によるらしい。初句「肥やし」の縁で結句「年の尻」となった。三首目の作者は其遊、題は「田家宿替」。「宿」は家屋、我が家のことをいう。同題で七首が並び、いずれも円満な引っ越しである。掲出歌の二句は「空きの方へと」かつ「空き」に「秋」を掛けている。四句から田畑と家を残して道具等一式を運ぶことが分かる。四首目の作者は閑雅、同題である。初句「高持ち」は年貢付きの田畑を持ち、持高相当の年貢を収めて諸役も勤める、いわゆる本百姓である。四句「幾瀬助けて」に「幾瀬田鋤けて」が隠れている。仕事の相棒である田鋤牛と田鋤馬を連れての引っ越しなのだ。
|
| 第135回 狂歌蘆の角 |
笛ならて東風ふく風にあは雪かちりやたらりの橋にひやりひう 雌雄軒蟹丸
『狂歌蘆の角』の詠者は雌雄軒蟹丸、刊記は文化四(一八〇七)年である。掲出歌の題は「橋上残雪」。二句の「東風(こち)」は春に吹く東の風、三句「淡雪」も春先のうっすら積もって消えやすい雪をいう。四句の「ちりやたらり」は風で立ち上がるさま、結句「ひやりひう」は風に舞うさまが思われる。笛の音の聴覚に視覚を加えたオノマトペが冴える。
橋の名のささやくやうになるかめりおとなし川も凍とけのして
花や散(る)と見れは梢に打(ち)むれておとろかしたる蝶のふるまひ
よしの川にちらぬさきから桜鮎移りし花をこえつくくりつ
たらちねそいとと恋しき魂棚へ手向(け)の水に顔かうつりて
奈良の町に見なれた鹿のなく声も今さらかなし秋の夕暮
水の面に影すみわたる月今宵はなしてくやむ魚のむら雲
一首目の題は「名所凍解」。四句は和歌山県田辺市本宮町の熊野本宮の横を流れて熊野川に合流する「音無川」、初二句は本宮町にあった耳語橋(ささやきばし)をいう。三句は「鳴るべかめり」か「なべかめり」だろう。二首目の題は「蝶」。上から下へという流れの中で見ていた落花が急に梢に打ち群れた。何だろう、これは。まなじりを凝らすことで知れた蝶の群れであるが、思い込みと事実の落差が新鮮に響く。三首目の題は「春興」。三句、吉野川の鮎は「桜鮎」の名で有名だったらしい。四句「移り」は「映り」だろう。まだ散っていない、水面に映った桜の花を結句「越えつ潜りつ」している光景なのだ。四首目の題は「魂祭」。三句「魂棚」は盂蘭盆で用意する精霊棚をいう。曲亭馬琴に〈うちむかふ鏡に親のしたはしきわが顔ながらかたみとおもへば〉(『著作堂雑記抄』)があって同様の感慨が伝わってくる。五首目の題は「市中秋夕」。四句「今さら」は「今改めて」の意だろう。見なれた景色、耳慣れた鹿の声も、新しい気がするというのである。タイムスリップしても変わらない町の観がする。六首目の題は「八月十五夜」。八幡宮の神事として行なわれた放生会が舞台である。四句は「放して悔やむ」、魚の群れが群雲のように水に映った月を邪魔しているというのだ。
我一と施行角力かとりとりにきのふはむすひけふはせきはん
遊行する舟もとたえてしら波の見渡しさひし秋のゆふ暮
一首目の題は「享和二壬戌年みな月すゑつかた風雨はげしく世上いぶせかりけるがふづき初(め)の日家居近き西横堀も水高く西口ははや床に付(く)などいひはやしけるがほどなく攝河州淀川筋堤きれて大水あふれ田畑もみるがうちに湖となりて其色々里々の人からきめに逢(ひ)ぬる事のいたましくて此(の)日毎施行ありけるを」である。時は一八〇二年である。初句「我一」は「我先」である。二句は施しに熱心なさまをいう。下句は「昨日は結び今日は赤飯」だろう。二首目の題は「水見舞のかへるさ暮に及びけるに」。初句「遊行」は遊覧の意と解した。この時点では、見渡すところ、人家も水没した状況であったらしい。
|
| 第136回 狂歌手毎の花 初編 |
ひいやりとする水茶やの夕すすみ床机のあしも川にひたして 其酔
『狂歌手毎の花 初編』の輯者は文屋茂喬、刊記は文化七(一八一〇)年である。掲出歌は挿絵の一首で題はない。二句「水茶屋」は路傍や社寺の境内で茶を出して休ませた店である。四句の「床几」は横長に作った数人用の腰掛け台、絵では川床のように二つ合わせた格好である。人の足を川に浸しているような四句の「も」が上句に説得力を与えていよう。
一に不二にたかとおもふ山もなく三になすへき又山もなし
喰(ひ)そめをせぬ一つ子は節分に母の乳豆もふたつ祝へよ
土つかぬ関取なれや道中を駕にのりても四人かかりは
やかて人を驚かさんと荻のはのうなつきあひし秋のはつ風
一首目の作者は月六斎休、挿絵の一首で題はない。初夢「一富士二鷹三茄子」の口合いで「一富士」に特化させた。二三句「似たかと思ふ山もなく」、下句は「三に為すべき又山もなし」となる。二首目の作者は乙立、題は「家内打(ち)よりて年とる夜に」。「打ち」からも節分の夜である。初句「喰ひ初め」は生後百日もしくは百二十日目の小児に食事をさせる祝いの儀式である。数え年だから一歳、年とれば二歳、豆なら二粒だから結句「母の乳豆もふたつ祝へよ」となった。三首目の作者は金友亭以文、題は「角力取」。二句「なれや」は疑問の意を表す。結句「四人懸かり」は駕籠を四人で担ぐこと、これを土俵に擬えた。初句の「土」は黒星に地面の土である。四首目の作者は観雪堂鵞習、題は「初秋」。二句もそうだが四句「頷き合ひし」の出所は〈かぜわたるにはのをぎはらそよさらになほよをあきとおどろかすかな〉(『為家五社百首』三〇一)だろう。三四句は風のそよぐ意に「さらになほ」と荻を強調していた。
鄙まつるあの子とならば世帯して見たや弥生の三日なりとも
春風に行列さむきのり物の戸ひらきかねてすくむ花嫁
物いははかしましからむよしの山口からさきへ咲(き)そめし花
百姓の論はなかれて夏の田に水かけと名をとる草の苗
一首目の作者は観雪堂鵞習、題は「春恋」。初句は「雛祭る」、下句「弥生の三日」は上巳の節句である。結句「なりとも」が無責任だが「一日でよいから御雛様のようなあの子の隣に座りたい」の意と解した。二首目の作者は都頭見堂調音美、題は「風前嫁入」。花嫁行列が婿となる男の家の前に着いた。戸を開けようとするのだが風で難渋しているのだ。加えて緊張感から結句「竦む」(体が強ばって動かなくなる)のだろう。三首目の作者は吉丸宗正、題は「花」。三句は「吉野山」、四句は上の「山」を共有して「山口から先へ」となる。「山口」は山口神社、吉野水分神社に対する勝手神社の称である。この背後の「袖振山」(五節の舞の起源)が初二句「物いはば姦しからむ」なのだ。四首目の作者も吉丸宗正、題は「苗代」。初二句は水論(水争い)などの訴訟が解決したと読む。下句「水影(苗を映す一面の水)と名」云々の出所は〈苗代の水かげばかり見えし田のかりはつるまで長居しにけり〉(『更級日記』)だろう。
|
| 第137回 狂歌手毎の花 初編(2) |
必の文字のひつかけはつす戸にうらみもはれし心とそなる 白石園雑亭駄鹿
掲出歌の題は「逢恋」。初句は「必ずの」と読んだ。二句「引っ掛け」は戸締まりの用具でもある。盗人の隠語では合鍵をいう。下句は心を開いた世界、藤原信実に〈世をそむく柴のあみどのかけがねのおもひはづせば人ぞまたるる〉(『夫木和歌抄』一四九四四)がある。
悲しいめしらぬ泪を退屈なあくひにこほす御代のおたやか
淋しさのとらへ所はなかりけり小鳥まてたつ秋の夕くれ
咲(き)みちて方角たにもしら雲をつかむかこときみよしのの花
とふも又跡やつかんと下駄のはの二のあしをふむ雪の白妙
一首目の作者は午涼軒友野由躬、題は「祝」。初句は悲しい境遇や体験などをいう。そうした「目」と関係のない、人の目から出る「泪」を使って結句を導いた。「涙」では「欠伸」とそぐわない。二首目の作者は律巴亭橘連事多留、題は「秋夕」。寂蓮は〈寂しさはその色としもなかりけり槙立つ山の秋の夕暮〉(『新古今和歌集』三六一)で色(紅葉)ではない、存在そのものだとして「秋の夕暮れ」に常緑樹を配した。事多留は手掛かりのないことをいい、その証左のように小鳥の群れを見送っている。三首目の作者は緑亭大矢員久、なぜか題がない。満開の桜を二樣に表現した。一つは「方角だにも知ら」ないで「雲を掴むが如き」だという「私」、今一つは伝統的な「白雲を掴むが如き御吉野の花」である。四首目の作者も緑亭大矢員久、やはり題がない。青巾舎中村群丸に〈訪ふよりはとはぬ人こそ誠なれ足跡もなき庭のしら雪〉(『嬾葉夷曲集』)がある。これを受けた二句「又」だろう。三四句「下駄の歯の二の足を踏む」は二の字二の字の足跡に成句「二の足を踏む」(躊躇すること)を重ねた。
降(る)雪に犬はかりかはよし原をうかれてかける四つ足の駕
長閑さや残りし雪も解(く)る頃かすみにきゆる淡路しま山
独居はなんの遠慮もなつの月さしむかひたる丸裸とち
老楽は此(の)身ひとつの丸家にてつまもなけれは子ひさしもなし
一首目の作者は緑亭大矢員久、題はない。二句「かは」は反語で「犬ばかりだろうか。いや、そうではない」。三句は犬なら「葭原」、人なら遊郭の「吉原」となる。結句は駕籠舁きが二人で「四つ足」となる。二首目の作者は橘戸亭藤の苗継、題は「霞」。「私」の在所で雪が消えて土を表す頃、内海に親しく眺めてきた淡路島がその稜線を霞の奥に隠してしまうのだ。「長閑さ」を間投助詞「や」が受けて詠嘆、初句切れが響く。三首目の作者は青漆庵緑竹満、題は「夏月」。初句は「ひとりゐ」だろう。三句は「無(つ)」に「夏」である。月の異称は桂男、半井卜養に〈かつらおとこ雲の衣をふんぬいて丸はたかなる月のなりかな〉(『卜養狂歌拾遺』)がある。男同士なのだ。四首目の作者も緑竹満、題は「述懐」。三句「丸家」は「丸屋(まろや)」で葦や茅をそのまま屋根に葺いた粗末な家をいう。以下「つま」には軒端の「端」に女房の「妻」を掛けた。結句も同じ手法だが「子廂」は「小廂」が正しい。
|
| 第138回 狂歌手毎の花 初編(3) |
ここもまたすめは都と五畿内のこきの木地ひく木曽の山里 逸昇亭五合法師
掲出歌の題は「山家」。三句「五畿内」は京都の周囲にあった山城・大和・河内・和泉・摂津の五か国をいう。四句の「御器(ごき)」は蓋つきの食器、「木地」は轆轤挽きなどで細工する木を粗挽きしたもの、「挽く」は原木とも轆轤とも取れるが後者で解した。消費地の五畿内も、生産地の山里も「住めば都」は同じなのだ。「こ」や「き」の同音反復が心地良い。
久かたの空遠けれと人の目にとまるは星の二十八宿
道草のすすきに疵をつけられて露も身にしむ秋のゆふ風
野にたてる石の地蔵の其(の)あたり咲(き)しはさいのかはらなてしこ
中にしんありてくるくるこまならてさても廻りのよきはかた帯
一首目の作者は日々庵橘太刀持、題は「天象」。結句「二十八宿」は月・太陽・春分点・冬至点などの位置を示すために黄道付近の星座二十八を定めて、これを宿と呼んだものである。四句の「と(留)まる」と結句の「宿」が呼応する。二首目の作者は月六斎休、題は「秋風」。初句の「道草」は道端に生えてい草、その内の一つが二句の「薄」である。また「道草を食う」の「道草」の意でもある。葉の縁が鋸状、このため掻き分けるなどすると皮膚を傷つけてヒリヒリと痛むのであった。三首目の作者は小田手乗安、題は「瞿麦」。下句の「賽の河原瞿麦」は植物の名称ではない。騙し絵の世界だが撫子は河原に多いので別名を河原撫子、あとは初二句との配合で「賽の河原」と結合した。四首目の作者は菊亭本丸、題は「帯」。結句の「博多帯」は博多織の帯をいう。博多織は練り糸を使った平織物で、地合いが固く、光沢があり、多く帯地に用いられる。一首はその質感を三句「独楽」に喩えて表現した。
二階から又うへにみるあけ灯籠これや三界万霊のため
夜をふれは石灯籠もうつもれて月のみかけのしら雪の庭
月夜よし何よしかよし春のよの闇にもにほふ宿の梅かえ
手に取(り)て見ては音もなき鈴虫のはなせはりんと振(る)声そする
一首目の作者は千湖亭鮒麿、題は「燈籠」。三句「揚げ灯籠」(あげどうろ)は盂蘭盆に竿の先へ吊るして門外に揚げる灯籠をいう。下句「三界万霊」は三界(過去・現在・未来)全ての霊あるものの意、これに初二句の「二階からまた上」の三階を掛けた。二首目の作者も鮒麿、題は「雪」。朝まで降ったので三句「埋もれて」と大雪なのだ。四句は「月の御影の」で接頭語の「御」は美称、「影」は光である。結句の「しら」は、その光の「しろ」に雪の「白」を重ねた。二語を接続するための平仮名表記であった。三首目の作者は暁霜庵鐘也、題は「夜梅」。初二句は「月夜よし何よし香よし」だろう。その「香」は「よし」のリフレインに包んで四句の「匂ふ」で披瀝した。結句は家の「梅が枝」。四首目の作者も鐘也、題は「鈴虫」。二句の「音」は「ね」と一音で読んだ。鈴虫は鳴くというが手に取れば「ぐうの音も出ない」。放せば前翅を摺り合わせて「りんと振る声ぞする」。係り結びで強調される異議申し立てなのだ。
|
| 第139回 狂歌手毎の花 初編(4) |
愛宕山山麓の桜時雨てふ名を得てくもる春の月の輪 堪忍舎二字守
掲出歌の題は「春月」。三句「時雨」は晩秋から初冬に降る雨、結句「月の輪」は秋の満月をいう。嘉栗の孫、十歳の世根女には〈あたご山しぐれの桜それ過ぎてゆきの花ちるけふのさむけさ〉(『狂歌辰の市』)がある。時雨桜は桜の品種、また愛宕山東峰には月輪寺がある。季節は春、しかし名称への関心の連鎖が「朧月」を「月の輪」に置き換えたのであった。
白露は伏見難波の舟ならて登る夕くれくたる明かた
いといとといはれし昔なつかしやお袋さまと人によはれて
追(ひ)やれと又可愛さは足跡に花形なして逃(く)るいのころ
手枕は気楽なりけりともともに長うなりてそ見る後の月
一首目の作者は文巣居鼠雄、題は「露」。上句の「伏見難波の舟」は淀川を上下した三十石船をいう。花形の交通機関が横の「上下」なら縦の「上下」で対抗させたのが季節限定の「白露」である。発着場の秋に情趣を添えたことだろう。二首目の作者も文巣居鼠雄、題は「懐旧」。初句の「いと」は近世上方語で幼児、男女に用いたが後には女児をさすようになる。四句「御袋」は母親、ここは他人から敬称として呼ばれている。「いと」は「糸」と同音、「袋」の縁語になって面白い。但し語史的には「袋」の方が早い。三首目の作者は暮秋庵万籟、題は「生類」。結句「いのころ」(犬児)は犬の子をいう。子犬と人の掛け合いが活写されているが、中でも四句の見立て「花形」からは図抜けた感性が覗く。四首目の作者は菊一本、題はない。三句の「共々に」は枕にした肘と、それを枕にする「私」となる。結句「後の月」は八月十五夜に対する九月十三夜の月をいう。ちなみに陰暦九月の異称も長月であった。
潤にも照る月なみをかそふれはやつはり秋の最中なる影
雪ならはいくたひあたまをはらはまし年月ふりてかかる白髪
時鳥たしかそこらて鳴(い)たとは月か證拠にたつたひとこゑ
夢のやうに聞(い)て過(き)にき若い時目を覚(ま)せよと人のいひしも
一首目の作者は川村知州、題は「閏良夜」。源順の〈水の面に照る月なみをかぞふればこよひぞ秋の最中なりける〉(『拾遺和歌集』一七一)が本歌だろう。閏名月(閏八月十五日の名月)も同じだというのだ。初句の「潤」は本歌の初句と合わせた三水と解した。二首目の作者は推枕軒雨眠、題は「老述懐」。夢ならば嬉しいところだが実際は払っても払っても落ちない白髪である。四句は「降りて」ではなく「旧りて」、結句も「掛かる」ではなく「斯かる」となる。三首目の作者は楊麗舎花夕、題は「郭公」。四句の「月か證拠に」が面白い。該当しそうな古歌ならやはり「百人一首」で知られる〈郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる〉(『千載和歌集』一六一)だろう。四首目の作者も花夕、題は「懐旧」。四句には、眠る人に向けての「起きよ」と起きている人に向けての「正気にもどれ」の二種がある。若い時は後者だった。しかし今になれば全てが前者の夢のような来し方に思えるのである。
|
| 第140回 萩の折はし |
業ひらの夜半にかよひし河内路はみな一めんのおきつ白浪 翠柳軒栗飯
翠柳軒栗飯の三回忌追善家集『萩の折はし』の詠者は栗飯とその一門、刊記は文化八(一八一一)年である。掲出歌の題は「享和二いぬのとしの洪水に淀川のつつみくづれてくらがり峠のふもとまて帆かけたる船の行(き)かふを見て」。暗峠は奈良県との境、淀川は大阪平野を西南に流れて海に注いでいる。蟹丸も『狂歌蘆の角』で記録する洪水の凄さである。
魚偏に京もゐなかも肴やかねもせていそく今朝の初売
春風に梅の唇ほころひてしやへり出したる鶯のこゑ
いかなれは春三夏六の沙汰もなく秋に一度のほし合の宵
桐の一葉敢(り)て告(げ)にし秋もはやきりのひと日と今日はなりにき
老(い)ぬれは腰にゆみはり桃燈をたたみしことく皺のよりけり
一首目の作者は栗飯(以下の五首も同様)、題は「初売」。上句「魚偏に京」は「鯨」、次に「ゐなか」と読めて魚偏にあるのは「庄」、国字で「さけ」とある。三句以下は「肴屋が寝もせで急ぐ」となる。都会も田舎も初商いは忙しいのだ。二首目の題は「鶯」。二句の「唇」は花片をいう。藤原仲美に〈春くれどのべの霞につつまれて花のゑまひのくちびるもみず〉(『夫木和歌抄』一〇八三)があった。三句以下で「鶯」に接続するのは奇術に近い。梅との強い配合力であろう。三首目の題は「七夕」。初句は「どういうわけで」、二句の「春三夏六」(しゅんさんかろく)は性交の回数をいう。これだと春三回、夏六回だが秋に比べると多い。三句は「裁定もなく」か。結果、秋に一度の七夕というわけである。四首目の題は「九月尽」。上句は成句「桐一葉」また「一葉落ちて天下の秋を知る」を指す。四句の「きり」は「桐」と同音の「切り」(切れ目)、明日からは十月で冬なのだ。五首目の題は「述懐」。上句の「弓張り提灯」は竹を弓のように曲げ、その弾力を利用して火袋を伸ばし、上下に強く張って安定させるように考案されている。張って往年、畳んで現在、絶妙の比喩というほかない。
おのか枝を折(る)へき花の盗人としらて手引をしたる梅か香
かしや札へつたりはりし入口に用水桶もこほりとちけり
夢にさへ見てもよいとの初茄子めもさめさうなあさつけのいろ
一首目の作者は餅花庵寸柳、題は「梅」。枝を折られた梅だが、その花盗人を案内したのは梅自身だった。なるほど木は移動できないが匂いなら別である。擬人化の一つの行き着く所であろう。二首目の作者は義文庵花芥、題は「空館氷」。初句は「貸家札」で二句は「べったり貼りし」、なぜか斜めに貼ったのだという。四句「用水桶」は火災に備えて水をためておく桶である。結句は「凍り閉ぢけり」で三句の「入口」と同様だというのである。三首目の作者は寺西かね子、題は「夏喰物」。初二句の「夢にさへ見てもよい」と四句「めもさめさうな」が対応する。また二句「良い」と結句「浅」が「宵」と「朝」で対応する。夢は「一富士二鷹三茄子」で初夢の茄子と初茄子が対応する。下句は「目も覚めそうな浅漬けの色」となる。
|
| 第141回 狂歌紅葉集 |
はなやかにはこふは秋のなかたちかつきの照(り)そふ嫁入荷物 貞三
『狂歌紅葉集』の撰者は文屋茂喬、出版は文化八(一八一一)年である。掲出歌の題は「月照荷物」、対象は嫁荷を婚家へ運ぶ行列である。三句の「秋の仲立ちか」は秋を演出者に見立てたものだ。華やかな行列に月と提灯は狐の嫁入りだけではなかったらしい。吐楽の〈婚礼の座敷やめくるさかつきの影のさし図も秋の仲人〉(『和歌夷』)も夜の祝宴であった。
火ともしてかよふ螢はとかめなし御門はくれを限る城下も
ほたるさへ光りを添(へ)てまち筋の道あきらかな殿の御帰城
女夫岩いつもつなかる二見にもふた夜とは見ぬ星合のそら
日のあしの秋は短かう成(つ)て来ぬいさりは立(つ)て帰る湯元に
一首目の作者は素人、題は「城下蛍」。四句の「御門」は結句の「城下」から城門ではなく城下町を出入りする門と解した。不審人物でない、提灯を持った場合の時間外通行を思わせて、蛍の飛翔する光が美しい。二首目の作者は得閑斎繁雅、題は「城下蛍」。二句「さへ」から家の灯や出迎えの提灯も見えてくる。三句は上から「光りを添へて待ち(筋の)」、下へは「町筋の」、参勤交代に伴う帰国であろうか。三首目の作者も繁雅、題は「水郷七夕」。初句は二見浦の「めおといわ」、沖合の興玉(おきたま)神石を拝する岩門として両岩は大注連縄で二句「いつも繋がる」、結ばれている。これと「二見」の類音だが四句「(年に)二夜とは見ぬ」夫婦星を対応せて「星合の空」(七夕の夜の空)の快晴をいう。四首目の作者は度水、題は「温泉秋」。四句「いざり」は足が不自由で立って歩けない人をいう。初句の「足」も二句の「短かう」も四句の「立って」も縁語である。昼は街道で物乞いをし、塒は湯元(温泉場)の怪人物である。
うかれ女は客の気もとる歌かるた今一たひのあふ事をとて
行燈の火かけも人もちらちらと軒には雪のふる道具店
海へ出た鼻まて長う見やられて降(り)積む雪の白き象潟
長物におひかけられておそはるるねつきのゆめもさめか井の宿
一首目の作者は交山、題は「遊女績松」。初句「浮かれ女」は遊女、二句の「も取る」は第一に三句「歌カルタ」を「取る」からだ。具体的には下句、和泉式部の〈あらざらむこの世の外の思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな〉(『後拾遺歌集』七六三)である。二首目の作者は芳水、題は「冬夜店」。二句の「火影」は灯火に照らされてできる影、人はこれに動きが加わる。三句「ちらちらと」は屋外から見て初二句、屋内から見て下句の二重構造となる。三首目の作者は得閑斎繁雅、題は「雪中眺望」。結句「象潟」は秋田県南西端の地名。日本海に面し、かつては八十八潟、九十九島の景観で知られたが、文化元(一八〇四)年の地震で陸地化したという。二句の「鼻(端)まて長う」に「象」が呼応し、壮大な見立てとなった。四首目の作者は狸鏡、題は「旅宿夢」。初句「長物」は蛇を忌んでいう。結句の「醒ケ井の宿」は現在の滋賀県米原町、中山道の宿駅であった。寝ては「夢も醒め(ケ井の宿)」なのだ。
|
| 第142回 狂歌手毎の花 二編 |
鳥はみなねくらするころねくら出ておのれ顔なるさとの蝙蝠 雌雄軒蟹丸
『狂歌手毎の花 二編』の輯者は文屋茂喬、刊記は文化八(一八一一)年。掲出歌は挿絵の一首である。上句の「ねぐら」は鳥の寝る所、二句は「塒する」で複合動詞である。鳥と蝙蝠また昼と夜で対をなす。鳥は鳥類、蝙蝠は哺乳類、成句「鳥無き里の蝙蝠」(優れた者のいない所では詰まらない者が幅をきかす譬え)があるが、実景としての迫力を享受した。
月わたる橋よりみれは雪をもつ木々はかつらの花てこそあれ
ひとふしををしゆる杖の下からも廻る小猿の可愛らしさよ
いはぬ色か言(ふ)にまさりて道灌を歌よみにせし山ふきのはな
桜はな手ことに折(り)てかへるをは春の行(く)とや人は見るらむ
一首目の作者は無風亭破扇、挿絵の一首である。初二句の橋は京都市の大堰川に架かる渡月橋だろう。四句の「桂の花」は月の光をいう。渡月橋のある嵐山は春の桜、秋の紅葉で知られるが、月と雪の配合の妙を詠った。二首目の作者は志成、挿絵の一首である。成句に「杖の下から回る子」がある。意味は「杖を振り上げても逃げない、縋り付いてくる子供は打てない」。類句に「杖の下に回る犬は打てない」もあり、こちらの変型かも知れない。絵は猿回しである。三首目の作者は詞海斎輪田麿、挿絵の一首である。雨に遭った道灌が簑を借りようとしたら山吹を出されて怒ったが、後に〈七重八重花は咲けども山吹のみの一つだになきぞ悲しき〉(「実の」に「簑」を掛けた)の意と知って歌道を志す逸話(『常山紀談』)に拠った。四首目の作者は源登平、挿絵の一首である。「春行く」は春が過ぎて行くことをいう。同じ過ぎて行くことには違いないが、手毎に花を持つ人が行く。それを季節が歩いていくと見立てたのである。
夏痩(せ)も忘れて涼し帷子のたもとより入る風にふくれて
小倉山みゆきの先へ風立(ち)てしたにしたにとちる紅葉かな
日のもとの花の鏡のよしの山さきみつるをや曇(る)といふらむ
團屋もふけて涼しき夜店にはうりのころうと心ひやひや
一首目の作者は三蔵楼田鶴丸、題は「納涼」。三句の「袂」は袖付けから下の袋のように垂れた部分、ここから入って抜けるのは襟元だから上半身が結句「風にふくれて」となる。初句の「夏痩せ」と対応して面白い。二首目の作者は月花庵雪丸、題は「落葉」。二句「御行」は行くことを敬っていう。四句は「下に居よ」の意で大名行列などの先払いが庶民に土下座をするように促す掛け声、ここでは落ち葉を人に見立てている。三首目の作者は桃原亭園丸、題は「花」。初句「日の本の」が掛かる「大和」も二句「花の鏡」(花の映る池水を鏡に見立てた語)の池水も出てこない。上句は「日本の花の鏡(模範)の吉野山」だろう。下句「花曇り」(四月頃の曇りやすい天気)の「咲き満つるをや」も相当に可笑しい。四首目の作者は北風彦丸、題は「夜市涼風」。初句は「うちわやも」と読む。四句の「らう」は推量の助動詞「らむ」の音変化、従って「売り残るだろうと」、結句「心冷や冷や」は主人の心境なのであった。
|
| 第143回 狂歌手毎の花 二編(二) |
飼葉する舎人もいらす銭かねももとよりいらぬたたみねの馬 鱗集亭問丸
掲出歌の題は「馬」。藤原清輔の『袋草紙』が伝える壬生忠見(生没年未詳)の逸話に拠った。忠岑は父である。「幼童の時、内裏より召有る、乗物なくて参り難きの由を申すに、而らば竹馬に乗りて参るべきの由御定有り」。返歌は〈竹のむまはふしかげにしていとよわし今夕かげにのりてまゐらん〉(岩波書店『新日本古典文学大系』)、夕方参上というわけだ。
其(の)むかし結ひし縄もかくやらんまゐらせ候へくそろの文字は
千金にかへかたき春の花さかり一りんたにもちらさしと思ふ
下からはくもるさえぬとそしれともまことの所はすんてある月
門閉(め)て目もかたくこそ守る夜は用水桶もこほりはり番
一首目の作者は鱗集亭問丸、題は「文字」。下句は「参らせ候」(まゐらせそろ)と「候べく候」(そろべくそろ)の二語を「候」で接続した。手紙では極端な崩し書きにされた。その形態の比喩が上句だろう。『散木奇歌集』の〈木をきざみなはをむすびしむかしよりつひにはとけてみえけるものを〉(一二四二)が思われる。二首目の作者は雪頂斎桃苗、題は「花」。上句は「春宵一刻値千金というが、その千金に代えがたいのが春の花盛り」だという。下句は花の「一輪」に金の「一厘」を掛けた。三首目の作者も雪頂斎桃苗、題は「月」。上句は地球から見た月、これを形而下とすれば、下句は地球を離れて見た月で形而上の月になる。つまり真如の理が衆生の迷いを破るという「まことの月」(真如の月)なのだ。四首目の作者は花友亭春眠、題は「冬夜番人」。二句の「目も堅くこそ」には「夜が更けても眠くならない」と「戸や錠が堅固で壊しにくい」の両意が働く。用水桶も付き合って「凍り張り番」なのだ。
完爾と笑ふゑくほの穴よりそあな美しと思ひそめつる
放生会は諸鳥のための大赦にてもれたるは只夜鷹昼鳶
長崎のよねか名うての衣装にもかひたんの来る五月雨の頃
親ゆひをまたにはさんたさまなるか山のかひより出る豆の月
一首目の作者は雲多楼花足、題は「恋」。初句は「莞爾(かんじ)と」で四音となる。にっこりと微笑んでいるさまをいう。その笑窪が愛らしいのだ。同音反復だが四句の「あな」は感動詞である。二首目の作者は餐霞亭雨風、題は「放生会」。法会は供養のためで鳥が悪いことをしたわけではない。そこを「大赦」とずらすことで結句が可能になった。「夜鷹」は夜の街娼、「昼鳶」は人家などに忍び込む昼の泥棒をいう。三首目の作者は東翠舎狐月、題は「遊里五月雨」。二句「よね」(娼)は遊女、「名うて」は名高いこと。四句「カピタン」は絹織物の名称、またオランダ商館の館長やヨーロッパ船の船長の意もある。したがって呉服屋も、男も五月雨式にやってくる五月雨の頃となる。四首目の作者も東翠舎狐月、題は「後月」。上句は人差し指と中指の間から親指を出した恰好だろう。下句はその卑猥なイメージを喚起させる「豆の月」(九月十三夜の月、後の月)である。ちなみに「豆」には女陰の意味がある。
|
| 第144回 狂歌手毎の花 二編(3) |
へへふつと吹(き)出す風の音羽山せきのこなたの貰ひ笑ひは 八橋園紫水
掲出歌の題は「山笑(ふ)」(新緑や花によって山全体が萌えるように明るいさまになる様子)。初句のオノマトペに注目した。三句「音羽山」は京都府と滋賀県の境に位地し、四句の「関」(逢坂の関)は北の滋賀、「此方」だから作歌主体となる山は京都側である。結句「貰ひ笑ひは」は言い止しではない。倒置法で下句から上句で読むと「音羽山」の体言止めとなる。
早乙女か入(り)日につれて植(ゑ)る田はしりさかりにそ見ゆる山里
厚氷池のつらまてはりまはす寒さはとうもこらへかたない
一声は何所としら川夜舟てふね耳に水の入るほとときす
花は過(ぎ)雪はまたなりたのしみもいまた半(ば)のあきの夜の月
一首目の作者は鳫行斎文山、題は「里田植」。入り日は西の山の端に近づいている。早乙女も同方向だが、スタイルは「尻下がり」(前向きのまま後ろに下がること)である。水田の緑も後進で四句「田は尻下がりにぞ」なのだ。二首目の作者は凌南軒可由、題は「氷」。二句は「人の顔に加えて池の表面まで」の意、これを受けた三句も同様である。風が「張り回す」のだが、池は凍っているのだろう。結句の「(堪へ)難ない」は接尾語で「寒さを堪える」のが困難であることを表わす。三首目の作者は其川庵羽觴、題は「郭公」。二句は上から「どこと知ら」ない、下へ「(どこと)白川夜舟」(よく眠っていて何も気づかないこと)となる。下句は船の縁で水の成句「寝耳に水の入るごとし」(突然な出来事)を使った。四首目の作者も羽觴、題は「月」。歌意は一年間の楽しみも、まだ半分しか味わっていない。これとあと一つ、今は月半ばの月で満月しかも秋の夜だから中秋の月を見ている、不足はないのである。
柴舟のしはし蛍もこかれよるかりとらるるは同し身にして
ゆひ折れは朔日二日三日よつかいつかはれなん五月雨の空
伸(び)をするけしきの森の初蕨にきりこふしの長し短し
和らかな風に柳のうなつきぬはるといふても冬といふても
一首目の作者は繁樹亭庭茂、題は「蛍入船」。韻を踏む初二句が幻想的な世界へ誘う。蛍は柴木に「焦がれ寄る」(思いを寄せる)が、柴木も「焦がれる」(焼け焦げる)身。互に「狩り取ら」れ、「刈り取ら」れる船頭小唄なのだ。二首目の作者は二階歌織、題は「五月雨」。二句「朔日」は毎月の第一日、以下「二日三日四日」、その次は「何時か」に「五日」を重ねて五指を折る。四句は「何時かは晴れるだろう」(「なん」は完了の助動詞「ぬ」の未然形に推量の助動詞「む」)。三首目の作者は萬世末長、題は「早蕨」。初句「伸びをする」は疲れたり退屈したりした時に手足を伸ばすこと、二句の「気色」はそのように見えたのである。下句は「握り拳」(早蕨)がてんでばらばらで「長し短し」となった。四首目の作者は中井吐虹斎、題は「年内立春」。初句は「やはらかな」、三句は「頷きぬ」。「年内立春」は陰暦で新年を迎えないうちに立春になること。今は新年だといっても、いや旧年だといっても、柳に風なのだ。
|
| 第145回 狂歌手毎の花 三編 |
洗たくはうはの空なる郭公きき流せねは耳もすましつ 豊城館貞幹
『狂歌手毎の花 三編』の輯者は文屋茂喬、刊記は文化九(一八一二)年である。挿絵の一首である。二句の「上の空」はホトトギスの鳴き声に心を奪われること、そして洗濯に注意が向かないことをいう。一方で「上の空」には空中の意味もある。挿絵では女性に上空を振り向かせているが、下句の「流せねは」「清ましつ」も初句「洗濯」の縁語であった。
水論の喧嘩の中を夕立にたたかれて夜も寝よい百姓
心やすい人て上手て尻かるてしきりにはやる隠婆との
きのふ迄いとひし声もぬけからの蝉吹(き)おとす初秋の風
月やとる露かとみれは朝顔のつるはひのほるあきのほたる火
一首目の作者は随雲舎麁幸、題は「田家夕立」。初句「水論」は田に引く水の配分をめぐって争うことをいう。四句「叩かれて」は二句「喧嘩」の縁語である。但し、こちらは嬉しい「叩かれて」で四五句のとおり「夜も寝よい」のである。二首目の作者も随雲舎麁幸、題は「隠婆」(おんば。産婦を助ける婦人だが昔は年配の人が多かった。産婆)。三句「尻軽」は「行動の軽々しいこと」のほかに「動作の活発なこと」をいう。結句は「隠婆殿」で五音となる。三首目の作者は東鶏館鳰丸、題は「立秋」。三句は上から「厭ひし声も抜け(殻の)」で蝉の声を聞かなくなった、下へは「脱け殻の蝉」で空蝉をいう。枝や幹また葉に残った脱け殻を結句「初秋の風」が吹き落としていくのだ。四首目の作者も鳰丸、題は「秋蛍」。初二句は三句以下と対応する。すなわち成句「月に蛍火」(同じような物でありながら二つが非常に隔たっていることの喩え)なのだ。初二句を布石として、衰えていく蛍火がズーム・アップされる。
もちぬしは誰とゆふへのすすみ床忘(れ)た扇ひらいてもなし
起(き)るまてこらへて居たる小便もしはし忘るる朝かほの花
真黒にからすと紛ふ熊野炭権現様の山て焼くかあ
小判にはあらてきれとの内海て網にひけたる金太郎鰯
一首目の作者は一了軒夫丸、題は「納涼」。二句は「誰と言ふ(べの)」、また「(誰と)夕べの涼み床」と展開する。全体図は「持ち主は誰と言うのか。昨夜の涼み床の忘れ物、扇は開かず仕舞いだったらしい」か。二首目の作者も一了軒夫丸、題は「槿」。上句を裏返せば堪えきれなくなって起きたのだろう。厠に急ぐ途中、庭の朝顔の花が目に止まり、その清涼感に立ち止まったのである。三首目の作者は蟋蟀亭庭季、題は「炭」。三句「熊野炭」は紀伊半島の熊野地方から産出する堅くて火力の強い高級な木炭、備長炭をいう。四句「権現様」は熊野三山(本宮・新宮・那智)をいい、烏は熊野の神使で護符にも図案化されている。結句「かあ」で刻印だろう。四首目の作者は松寿亭庭枝、題は「鰯引」。二句「切処(の)」は砂州や堤防の一部が切れている所をいう。結句「金太郎鰯」は京都府与謝郡の近海でとれる小形の鰯、初二句「小判にはあらで」は「私」の見立てである。四句「内海」では天橋立が知られている。 |
| |
| 第146回 狂歌手毎の花 三編(2) |
名所もしつたり顔にさへつるやうたよみ鳥の籠に居なから 其川庵羽觴
掲出歌の題は「篭中転」。初句は「などころも」、二句「知ったり顔」は「さも知っているといった顔つきや様子」をいう。三句の「や」は問いかけている感、四句「歌詠み鳥」は鶯をいい、『古今和歌集』の仮名序「花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」に由る。名所とは歌枕、和歌人のカリカチュアであろう。
思ふほと先きかおもはは何おもふ思はねはこそおもふなりけれ
高うする枕に風のかよい来て戸ささぬ世こそよるもねよけれ
莟てふ子ともの持(ち)し弁当もひらく所か花てこそあれ
鑓の如ふる夕立をのかれんと長刀さうりぬきて逃(け)出す
一首目の作者は冷朝亭庭滴、題は「思」。意味は「こちらが思っているほど先方が思っているなら何も思うことはない。思わないからこそ思ってしまうのだ」。下句は係り結び、「思う」中身は読者の自由裁量である。二首目の作者は童龍、題は「夏夜」。初二句「高うする枕」は成句「枕を高くする」(安心して寝る、また暮らす)を活用した。四句は「戸鎖さぬ世」、以下で係り結びとなる。「ねよけれ」は「根好けれ」に「寝」を掛けたが共寝は意識しない。三首目の作者も童龍、題は「弁当」。初句の「莟」は弁当箱とは関係がない。将来を期待されるが一人前でない年頃をいう。これを花の莟に見立てたのである。弁当も「開く」、莟も「開く」、よって下句の「開く所が花」となった。四首目の作者は四時軒花鳥、題は「夕立」。四句「長刀草履」は履き古して形が崩れ、長刀のように反り返った藁草履をいう。初二句の鑓のように降ってくる雨には太刀打ちできない。手にして走り出したのだろう、正解であった。
さてなんの苦もなつの夜の安産をいはふて蚊さへ軒て餅つく
年寄(り)の口にも蕗はあふゆゑか茎さへあれはははいらぬもの
見る花に盗人こころ出させたはあたらさくらの咎にそ有(り)ける
国の名のあはれなるとの順礼場なかす太夫も親はないかい
一首目の作者は一粒斎萬倍、題は「夏夜安産」。初句「さて」は接続詞で「それから」の意だろう。「何の」と二句「なつの」(「無(つ)」に「夏」を掛ける)の類音に注目である。下句には成句「蚊が餅搗く」を配した。二首目の作者は老松軒三鶴、題は「蕗」。下句は「茎さへあれば葉は要らぬもの」、食用は蕗の薹と葉柄だからである。この「葉」に「歯」を掛けた。歯茎だけで食べられるというのである。三首目の作者は凌南軒可由、題は「折花」。本歌は〈花見にとむれつつ人のくるのみぞあたら桜のとがにはありける〉(『山家集』八七)である。下句「あたら」は「勿体ないことにも(まあ)」、あとの「には」と「にぞ」の差が微妙である。四首目の作者は興道舎継風、題は「浄留理」。二句の「哀れ」に「阿波(れ)」を掛ける。三句は「傾城阿波の鳴門」の「順礼歌の段」(ととさんの名は阿波十郎兵衛、かかさんはお弓と申します)をいう。四句は「泣かす~」。結句は巧みな芸能を誉める語(親がいたら喜ぶ意)。
|
| 第147回 狂歌手毎の花 三編(3) |
針川のえんをひきてやとふ蛍やみをぬひゆくやうにみえける 雲頂館棹丸
掲出歌の題は「水辺蛍」。初句「針川」だが『日本歴史地名大系』に滋賀県伊香郡余呉町針川村に「丹生川上流域の山村。左岸に支流針川が合流。針川は東端の上谷山から発し、村内を南東流」とある。先行して江戸の鍋黒住に〈大針にさつさとぬふて行く蛍橋のたもとも川の裾をも〉(『狂歌東西集』)がある。同趣向だが「針川」を持ってきて棹丸の刻印とした。
五右衛門か七条ならぬかはらけの油の中に果(て)る夏むし
照(る)月にささ浪よせて浮御堂流れゆくかとみつうみの面
寺子共手ふりてゆきのちらし書(き)白うよこれて戻る夕暮
雲のあなたこなたさまかと問(ひ)廻る不案内なる奴いかそも
一首目の作者は更見舎山月、題は「夏虫」。石川五右衛門が子供とともに油をはった釜で煮殺されたのは三条河原であった。七条河原は演劇等の世界で流布したのだろう。四句「土器」の「かはら」に「河原」を掛けた見立てである。二首目の作者は槇上則次、題は「湖上月」。湖面に月が映り、さざ波が寄せている、これが初二句だろう。寄せ波は引き波となる、これが三句以下で結句「湖」の「みづ」に清音で「見つ」を掛けた。三首目の作者も槇上則次、題は「雪」。初句は「寺子」(寺子屋で学ぶ子供)に接尾語の「共」だろう。三句は紙面構成として文字を散らして布置する書き方で、雪を喜ぶ子ども達の姿が彷彿とする。四句の「白う汚れて」が意表を突く。四首目の作者は鰭広物、題は「鳳巾」。下句「奴凧」は筒袖の奴が左右に両手を広げた形の紙鳶、奴は武家の奴僕、「不案内」は勝手を知らないのだ。風を切りながら空で大きく揺れる紙鳶の姿に、日常の雑用で走り回る奴の姿を重ねたのであった。
心ありて放ちし魚も池水にけふの月こそめつらしく見め
鬼はとくおひやりぬれとまたさむし軒につららのつのは残りて
わやくいへは鬼かゐたそとせなの子にくはせてねかす節分の豆
甲斐やおもふ越後やしのふ流れ行(く)かは中島の秋の夕くれ
一首目の作者は菅の舎杉足明、題は「池辺月」。陰暦八月十五日、仏教の不殺生戒により魚を池に放ち供養する放生会である。これが初句の意となる。二句以下は成句「魚心あれば水心」の「魚心」の原義「魚、心あれば」に拠った。二首目の作者は千柳亭糸唐麿、題は「余寒」。漢字を多用すると〈鬼は疾く追ひ遣りぬれどまだ寒し軒に氷柱の角は残りて〉となる。初二句は節分をいう。余寒は立春後の寒さ、時節的には今と変わらない。三首目の作者は千路堂春風晴、題は「節分」。初句「わやく」は聞き分けがないことをいう。漢字を多用すると〈わやく言へば鬼が居たぞと背なの子に喰はせて寝かす節分の豆〉、二句は「鬼に食べられるぞ」だろう。一方では年の数以上の豆であやして寝かすのであった。四首目の作者は四方瀧水米人、題は「秋夕」。初句「甲斐」は武田信玄、二句「越後」は上杉謙信をいう。四句「かは」は上から「流れ行く川」、下へは「川中島の秋の夕暮れ」で古戦場に両雄を忍ぶ図となる。
|
| 第148回 狂歌四つの友 |
むつの花かつらの花のとはいへとやつはり花ははなて社あれ 蝙蝠軒魚丸
『狂歌よつの友』の撰者は蝙蝠軒魚丸、刊記は文化九(一八一二)年、魚丸の還暦を祝う歌集である。掲出歌の題は「花の歌よみける中に」。初句「六つの花」は雪の異称。六弁の花のように結晶することに由る。二句「桂」は中国の伝説で月の世界にある木、「桂の花」は月光をいう。四句は「やっぱり花は」、結句は異質の花と比較しても桜が花王だと強調した。
見る度に邪魔な菅笠いさ捨(て)んてうとよい程花曇(り)すりや
いとせめて今宵よしのの夢見草虱のしゆはん裏かへし寝た
月かけにいけるを放つ夜半なれは我もころさて放す芋の屁
降(り)つもる夜半のしら雪音なくて今朝かしましき薮の下折(れ)
一首目の題は「花の歌よみける中に」、作者は魚丸(以下、同じである)。二句「菅笠」は日除けとしても旅の必需品だったようだ。四句は「丁度よい程」、結句「花曇り」は桜の咲く頃の曇った天気をいう。「すりゃ」は「すれば」の音変化、上下句が倒置になっている。二首目の題は「夜半に花をおもひて」。三句「夢見草」は桜の異名、これに安眠の願いを込めた。四句の「しゆはん」は襦袢、肌着である。その内側に吸血害虫が付着するので結句「裏返し寝た」のだ。虱は寄主の体から離れると死ぬらしい。三首目の題は「月の歌よみける中に」。初二句は「月影に生けるを放つ」で放生会である。月は八月十五夜、芋を供えるところから芋名月と呼ぶ。四句「殺さで」は勢いを弱めないで、の意となる。四首目の題は「雪のうたよみける中に」。二三句は「夜半、知らないうちに(降る)白雪は音もなくて」だろう。四句「姦しき」は「耳障りな」、結句は雪の重みで草木が折れて下に垂れる、その音をいう。
心なく箒もて出た人さへもしはし見とるる雪のあけほの
消(え)やせんけふのはれとはいひなからまあ火はいれな雪見灯籠
すへりなはころりころろん転ひなん子もりの宮の雪にあふなき
王城の前後左もおしなへて右のとほりに雪の白妙
一首目の題は「雪のうたよみける中に」。初句は「無風流に」だろう。二句「箒持て」の「持て」は「持って」の音変化として読んだ。以下、そんな人さえも暫し見とれる雪の夜明けなのである。二首目も同じ題が続く。表記に漢字を加えると上句は〈消えやせん今日の晴れとは言ひながら〉だろう。四句の「まあ」は結果に自信は持てないが、と読む。「入れな」の「な」は助詞で「ねば」(『大阪ことば事典』)の意となる。結句「雪見灯籠」は庭園で用いられる。雪景色が映えるのだろう。三首目の題は「子守の宮にて」。子守神社は全国に散在し、特定はできないが、吉野水分神社もその一つらしい。眼目は初句「滑りなば」と下句「子守の宮の雪に危なき」の間で展開する類音反復の妙にある。四首目の題は「京にて雪のふりける日」。初句「王城」は皇居のある所すなわち都である。二句は「ぜんごひだりも」、四句「右の通りに」で実際にも結句該当の雪の景を右に置く。挿絵ではない。コラボレーションなのだ。
|
| 第149回 狂歌四つの友(2) |
都路の車のわたち降(り)うつむ雪にはつらきうしの小便 蝙蝠軒魚丸
掲出歌の題は「京にて雪のふりける日」。上句は〈都路の車の轍降り埋む〉だろう。「車」には牛車と大八車があるが、大八車は人が引く。残るのは牛車すなわち荷車である。「都路」だから古代の牛車も考えられるが、ここは荷車と解した。下句は成句「牛の小便」(だらだらと長く続くこと)で汚される雪の迷惑もあろうが、使役される牛の視点も失いたくない。
打(ち)はれた春の野もせの楽しみはお月さまよりすつほんの酒
手酌ては気か春風や花見酒もふ此(の)うへはちりますちります
なる口もならぬ口にもあを東風の涼みの床てのむ柳かけ
下戸上戸とちらの方へも向(き)ぬるは面向不背の玉子さけかも
一首目の作者は魚丸(以下三首も同人)、題は「野辺にあそひて」。初句「打ち晴れた」は雨がやんで晴れ渡った天気、二句の「野面」は野原一面をいう。結句「すっぽん」は酒を入れる容器で、成句「月とスッポン」を逆手に取った。但し、昼だから月は出ていない。二首目の題も「野辺にあそひて」。二句「気が春~」に「気が晴る~」を掛けた。結句「散ります」は酒が杯からこぼれる意だが、これに桜の花が春風で散る光景を重ねた。三首目の題は「夏の夜に」。上句「なる口」は酒が飲める人、「ならぬ口」は酒が飲めない人だろう。「青東風」(あをこち)は初夏のころに青葉を吹いて渡る東からの風をいう。下句の「柳陰」は味醂に焼酎などを加えた甘い酒、これに柳の木陰の意を重ねた。四首目の題は「鶏卵酒をよめる」。四句「面向不背」は前から見ても後ろから見ても美しいことをいい、結句の「玉子」に掛かる。意は「面向不背の玉子で作る玉子酒は下戸上戸どちらからも好まれる面向不背の酒である」か。
かき餅やあられはきのふ尽(き)はててけふはあくひのつきぬ春雨
おのか葉をしとねにしきてはつ茄子まつ此(の)ころの市の大将
海となる俄夕立にはしる也みち行(く)人も尻に帆かけて
水かきのくはのかれたと夕立の雲のすきまにかへる百姓
一首目の作者は梨丸、題は「春雨」。静かに雨が降り続いている。隠居であろうか。退屈で、時間を持てあまして欠き餅や霰餅は食べ尽くした。今日は尽きることのない欠伸をしながらの家居なのだ。二首目の作者は栗丸、挿絵の一首である。三句の「初茄子」はその年に初めてなった茄子をいい、四句の「先づ」は「他に先んじて」、結句の「市」は市場である。季節は夏、艶のある紫黒色の初物は値段も高いのだろう。三首目の作者は笠丸、題は「夕立」。二句の「俄(にはか)」は突然の意。結句「尻に帆(を)掛けて」は慌てふためいて逃げだす意、この成句から初句が出てきたのか、その逆なのか。いずれにしても活写されて余りある光景だ。四首目の作者は元彦、題は「畑夕立」。初句の「水掻き」は料理用語で俎板の水を刮ぎ落とすこと、これを鍬についた土を刮ぎ落とす意に転用した。四句の「雲の隙間」に同音の「鍬」を潜り込ませた。結句「帰る」に「蛙」を重ねた。初句には蛙の「水掻き」も準備されている。
|
| 第150回 狂歌四つの友(3) |
大形に切(つ)てうる也大坂のみなとは日本いち岡西瓜 蜘丸
掲出歌の題は「西瓜」。『日本歴史地名大系』で「市岡新田」(大阪市/港区/市岡新田)を引くと十七世紀末に開発、作物として「とくに西瓜が有名であった」とある。『国史大辞典』の「川口新田」(現大阪市西部一帯で開発された新田の総称)でも「ことに西瓜は新田西瓜として(略)市に良質のものを供給した」とある。下句は「日本一(市)岡西瓜」なのだ。
仲居衆かささを手向(く)る七夕にひとつほしませふたつほしさま
籠のうちをほんよさらはとぬけて出て子供をなかすあれきりきりす
花の香の春はものかはすれちかふ袂にかをる秋の茸狩
白浪のかへしてはうつさよ砧あまかさか手にもつたころもを
一首目の作者は桃三、挿絵の一首である。初句「仲居」は料亭で接待をする女性、「衆」は接尾語で親愛を添える。二句の「笹」に同音の「酒」(女房詞)を掛ける。下句の「一つ干しませ」の「干し」に「星」を掛け、「二つ星さま」と対句かつ数え歌風が楽しい。二首目の作者は元丸、題は「蛬」。初句の「内」は「中」や「家」とも書く。二句「坊」は男の子を丁寧に呼ぶ語、また住居の意もある。虫ではなく人を泣かせて結句「あれ」(意外なことが起こって驚いた時に発する語)となった。三首目の作者は簑丸、題は「茸狩」。二句の「春はものかは」は「春は物の数ではない」。三句「すれ違ふ」のは人の「袂」であるが、桜の比でないのは勿論だろう。四首目の作者は小萩(女)、題は「漁村擣衣」。初句の「白浪の」は枕詞で「返し」に掛かる。また漁村や海女の縁語であり、衣の比喩ともなっていよう。三句「小夜砧」は夜に打つ砧をいう。下句は「海女が逆手に持った衣を」。布地を巻く綾巻(円い棒)は台の板柱で横に渡されて浮いている。それを向こう側に返しながら横槌で打つ様が思われる。
大尽のはてはやつはりやつしろの紙子を着てもはまる川竹
うり出せはかひちやといふてきた浜の相場の側てすくふ蛎売(り)
砥のみつにはつた氷をふしん場て大工の弟子か穴明(け)てゐる
一首目の作者は小萩(女)、題は「紙子」。初句「大尽」は大金持ち、四句「紙子」(紙で作った衣服)は安価で貧乏人に愛用された。三句「八代」(熊本県八代市)はその産地である。結句「川竹」は遊女をいう。別意で「大尽」には遊里で豪遊する客の意があり、紙子も遊里で粋に使い捨てにされた。二句の「果てはやっぱり」は、持つものを持ったら、定番のコースだという醒めた視線である。二首目の作者は蔦木、題は「市場蛎売」。上句の「売り出せば買ひぢゃといふて来た(浜の)」に「売り」と「買ひ」が入る。三句は下へ向かって「北浜の」となる。牡蠣売りの姿に米相場の景を重ねた。三首目の作者は鰤丸、題は「修造場氷」。初句は五音、意味は「砥石に使う水に」。今一つは「の」を比喩として「砥のような」、成句なら「砥の如し」(砥石の表面のように平らなこと)で、そのような氷の張った四句「普請場」の桶なのだろう。必要な水さえ確保できれば用を足すので結句「穴開けてゐる」と解した。
|
| 第151回 狂歌浦の見わたし |
雛にならへ影の膳をやしやう宅は本意なふおもやへいとをとられて 三日坊雛丸
『狂歌浦の見わたし』の発起人は蝙蝠軒魚丸、集者は葉流軒河丸、一文舎銭丸、刊記は文化九(一八一二)年である。掲出歌の題は「妾宅雛祭」。三句は上から「影の膳をやしよう(宅は)」、下へ向かって「妾宅は」となる。四句は「本意無う思(やへ)」に「本意無う母屋」だろう。結句は「いとを取られて」、女児はいないが雛に並べてその子の食事を供えるのだ。
更級やこゑを田毎にうつすほといくつも聞かせやよ時鳥
ふしの山を天守となしてふる雪や日本国を真しろにした
つほの内にねはる菜種の油こそそのいにしへは花も咲(か)せた
奥山の紅葉ならねとさらさらとふみかきちらす鹿の巻筆
一首目の作者は太白菴里丸、題は「名所郭公」。「田毎の月」(長野県更級郡の姨捨山、その麓の水田一つ一つに映る月)のように田の数だけ鳴け時鳥、だろう。結句「やよ」は呼びかけの語、四句で欠けた命令形の「よ」と合体した。二首目の作者は澄丸、題は「雪」。初句は「富士の山を」、二句の「天守」は城の本丸に築かれた最も高い物見櫓をいう。天守閣から雪を降らせているイメージである。結句の「しろ」は「白」に「城」である。三首目の作者は鍋丸、題は「油」。歌意「壺にあるのは今でこそ粘っこい油だが、採油以前は一面に咲く菜の花だった。それだけではない。壺に生けられて黄の花を咲かせたこともあったのだ」。四首目の作者は音丸、題は「筆」。本歌は「百人一首」の〈奥山にもみぢ踏み分け鳴く鹿の声きくときぞ秋はかなしき〉(『古今和歌集』二一五)。四句「文書き散らす」に「踏み掻き散らす」を掛ける。結句「鹿の巻筆」は芯を立てて紙を巻き、その周囲に鹿毛を植えて穂を作った筆をいう。
鍬の刃のさへかへりつつ春の田を返す手もとにあわ雪の降(る)
鶯のしらぬ宿あり春秋もわかて匂へる墨の画の梅
さむけさも忘れなからの身ふるひや小便こらへてゆく雪の道
ちさい子を遊はすやうに蝶々かてうちてうちに似たる羽つかひ
一首目の作者は有郷、題は「春日百姓」。初二句は振り上げた鍬がくっきりと見え、振り下ろした鍬の音が澄む。余寒が厳しいのである。古歌に〈冬と春とゆき逢坂の杉がえに霞をしのぎあは雪のふる〉(『後鳥羽院御集』四〇二)があった。二首目の作者は星石亭彦丸、挿絵の一首である。鶯はいない。書き足さない限り永遠の不在だから初二句「鶯の知らぬ宿あり」となる。同じく季節の変動もないので、以下「春秋も分かで匂へる墨の画の梅」なのだ。なお四句の「で」は「ずに」の意で活用語の未然形に付く。三首目の作者は町丸、題は「雪」。上句「寒けさを忘れながらの身震ひ」とは何か。寒さに原因する身震いが、それを忘れさせるほどになった。すなわち四句の尿意から来る身震いが前者を上回ったのである。四首目の作者は文丸、題は「蝶」。初句は「小さい子を」、四句の「手打ち手打ち」は拍子をとって手をたたくことをいう。結句の「似たる羽遣ひ」は見立てであるが、それによって風景が楽しくなった。
|
| 第152回 狂歌浦の見わたし(2) |
咲(く)花の木ふり永字の八方へいとと見事にひくくわく満寺 菊丸
掲出歌は挿絵の一首である。作品は初二句の「~木振り」の見立てから展開する、以下「永字の八方」(「永字八法」)は漢字の「永」の一字で、すべての文字に共通する八種の筆法を示すという書法伝授法である。「八法」を木の幹や枝の格好だから「八方」とした。「いとど見事に引く鶴満寺」で「鶴」に「書く」を掛けた。寺は大阪市北区長柄東一丁目に現存する。
鶯か枝をこそくる長閑さにうめもにこにこ笑ひ掛(か)つた
農夫のしん苦を筆にまかせつつ見事なかふらかよふ出来ました
前髪をとつたる跡は青によしなら男とも見ゆる元服
金毘羅へ酒たつ人もけさはひとつくるしかるまし屠蘇のつけ汁
一首目の作者は泡丸、挿絵の一首である。莟が綻び始めた枝で一羽の鶯が囀りながら枝移りをする様子に見える。二句「こそぐる」は「くすぐる」、下句は成句「花笑う」(花の蕾が開く)を応用して挿絵と一体となった。二首目の作者は藤之家吉丸。やはり挿絵の一首である。二句は「辛苦」(辛い苦しみ)ないし「真苦」(本当の苦しみ)と読む。三句の「任せつつ」は筆の勢いを削がずに、だろう。四句は「見事な蕪(の絵)が」となる。結句の「よふ」は「よく」のウ音便で「よう」が正しい。三首目の作者は泡丸、題は「元服」。二句は「取りたる」の促音便、剃り跡が青々としているところから枕詞「青丹よし」と展開し、四句の「奈良男」(成句に「奈良男に京女」がある)で、その男振りを賞賛した。四首目の作者は鹿丸、題は「歳旦」。初二句は金毘羅権現に願をかけて酒を飲まない人をいう。三四句は「今朝は苦しかるまじ」、結句「屠蘇の付け汁」は屠蘇散に付けた汁で屠蘇酒だろう。誘惑の多い正月である。
白波はないと汐干に油断して蛤は唯の人にとられた
簾もれて恐れ多くもうへ様のはなこそくりにきたる梅か香
畦になく子は打(ち)すてて蛭にちをすはれなからも植(ゑ)る早乙女
野分(き)して店のとからし散ると見ん伏見の里に飛ふ赤とんほ
一首目の作者は的丸、題は「汐干」(潮が引いて現れた砂浜)。歌意「寄せ波に続く引き波によって沖へ攫われなかったかわりに蛤は無警戒だった普通の人に取られてしまった」。ここで「白波」に「盗賊」を重ねることで作品は完成する。二首目の作者は越丸、題は「禁中梅」。初句は「すだれ漏れて」で六音となる。三句「上様」は「禁中」(皇居)だから天皇だろう。擬人化された梅が鼻を擽るという不埒な行為に及んだ、いや梅が匂うのだった。三首目の作者は笠丸、題は「田植」。初句「畦(あぜ)」は田と田の間に土を盛った堤をいう。表記を改めると〈畦に泣く子は打ち捨てて蛭に血を吸はれながらも植ゑる早乙女〉、我が子に「乳(ち)」をやる閑もなく蛭に「血」を吸わせている母親なのだ。四首目の作者は笠丸、題は「里蜻蛉」。初句「野分き」は二百十日頃に吹く暴風をいう。二句の「とがらし」は「唐辛子」、伏見は伏見唐辛子の産地であった。「散る」だから一味唐辛子だろうが、出色の見立てである。
|
| 第153回 狂歌浦の見わたし(3) |
くひ付(い)たあふれ蚊ひつしやり叩いてもあはれのまさる秋の夕暮 兼丸
掲出歌の題は「秋夕」である。上句は「食ひ付いたあぶれ蚊ぴっしゃり叩いても」である。初句は刺しにきたというよりも、しっかり取り付いた、しがみついたと解すべきだろう。「溢れ蚊」は最盛期を過ぎて元気のなくなった蚊をいう。「ぴっしゃり」に反応して皮膚を離れるのは夏の蚊であり、ここはみじめなほど叩かれて潰れる蚊、それが下句の思いとなった。
両国の橋にかかりし秋最中またとちらへもかたふかぬ月
七福を外へもらさす一ふくのかけ地に書(い)て世の宝船
つれつれに来へき人こぬ春の雨ささかにと違ふ針のいと水
日暮(れ)から軒にわあわあ蚊の如くわらへかたかつて搗(く)亥の子餅
一首目の作者は鰤丸、題は「橋上月」。上句「両国」は東京都墨田区の地名、「橋」は両国橋で江戸随一の盛り場であった。「掛かりし秋最中」は陰暦十五夜の月が橋の真上に来ているのだろう。四句の「まだどちらへも」は橋の両端、これを意識した結句である。二首目の作者は葉流軒河丸、挿絵の一首である。初句「七福」は「七福神」の略、二句は挿絵の外の世界をいう。三四句の「一幅の掛地」、この「一幅」に七福を纏めた「一福」を掛けた。三首目の作者は樵諷軒歩丸、題は「春雨」。上句は「退屈すると必ずやって来る人も来ない春雨(来てもよいのに)」。下句は「細蟹(ささがに)つまり蜘蛛の糸と違って針のような糸水、軒の雨だれを見ている私」だろう。四首目の作者は民女、題は「玄猪」(げんちょ。陰暦十月の亥の日に食べた餠。亥子餠)。二句「わあわあ」は喧しく騒ぎ立てるさまを表わす語、「わいわい」である。下句は「蚊の如く童が集って搗く亥の子餅」で成句「蚊が餅搗く」の童版とした。
秋風かそよ通ひ来て心よやすすしの蚊帳か顔へへつたり
ほんとはせ皮むくつけも人の手にもまれて渋のとれた焼(き)栗
安いとてはけははな緒に破られてはや疵物となる紀州足袋
はこくんて貰ふたたけは返すなり子か又親をもりの烏は
一首目の作者は河丸、題は「納涼」。二句の「そよ」は風がかすかに吹くさま、三句の「よや」は感動をこめて聞き手に働きかける語である。下句は「生絹の蚊帳が顔にぺったり」だろう。「生絹」(生糸)に同音の「涼し」を掛けた。二首目の作者は淀丸、題は「栗」。初句は「ポンと爆ぜ」、二句の「むくつけ」は不気味なさまをいう。以下「人の手に揉まれて」渋皮が取れたというのである。焼いているのは素人、商売ではない。三首目の作者は竹丸、題は「足袋」。二三句の「履けば鼻緒に破られて」は草履や下駄を履くと鼻緒で足袋が破れる、縫い目が綻びたのだろうか、疵物になるというのである。藩も奨励した紀州足袋の生産だったようだが、この時点での評判は今一つであったらしい。四首目の作者は河丸、題は「烏」。初句は「はごこんで」(育んで)、「はぐくんで」の音変化である。成句に「烏は親の養いを育み返す」、また「烏に反哺の孝あり」もあった。結句「もり」は「守り」に「森」を掛けた。
|
| 第154回 狂歌三栗集 |
千金の春の外にも百両のねをつけてかふ籠の鶯 如石
『狂歌三栗集』の詠者は條果亭栗標・(革の右に斤)果亭有栗(如石)・桂果亭諦栗(幽山)、撰者は橙果亭天地根・英果亭(百尺樓)桂雄、刊記は文化十(一八一三)年である。掲出歌の題は「籠中鶯」。初二句は春宵値千金でない所、四句の「ね」は「値」に「音」を掛けた。競鳴の対象となる鶯が、千両とはいかないにしろ、法外な値段で取引されていたことが分かるのだ。
たれひとりとひくる人のなき宿も庭はくやうに見ゆる青柳
雲雪と人をまとはす花なれはくさ冠に化(け)るとやかく
道もせもわかすしけれる夏草にまひ子になりし梅若の塚
秋きぬとおとろかしたる其うへにいやかうは風荻をさわかす
一首目の作者は如石、題は「閑居柳」。上句は「誰一人訪ひ来る人のなき宿も」、「宿」は「私」の家である。閑居して眺める先に庭がある。それでも来客のあることを考えて下句「庭を掃く」否そのように見える青柳なのだ。二首目の作者も如石、題は「花」。上句だが、雲ならば「花に雲」(桜の花が一面に満開になるさま)、雪ならば「花吹雪」(桜の花が吹雪のように乱れ散ること)がある。よって下句「草冠に化けるとや書く」となった。三首目の作者は幽山、題は「夏草蔵塚」。初二句は「道も瀬も分かず繁れる」である。四句の「迷子」は夏草で見えなくなった、その塚をいう。「梅若」は人商人に騙されて隅田川の辺で病死する少年で浄瑠璃や歌舞伎・仮名草子等で広く知られていた。四首目の作者は幽山、題は「荻」。本歌は藤原基俊の〈ひとりゐてながむる宿に秋きぬと荻の上ばのおどろかすらむ〉(『新拾遺集』三二二)。四句は「弥が上(に)」(益々)を効かした「(いやが)上風」(本歌「上葉の」)である。
紫のおなし色ても藤よりはしたにさからぬ秋萩の花
お食事もすすみ薬もきく月や菊といふ字は米はらむから
しくれつつしくれの桜咲(き)にけり花は雫も春にかはらて
紅葉葉のちりての後もてる月のかつらの花に冬かれはなし
一首目の作者は幽山、題は「萩」。春の藤と秋の萩で季節を越えた花合わせとなった。四句の「下に下がらぬ」は「二番と下がらない」の意、これに垂れて咲く藤と垂れない萩を重ねた。結句「秋萩」は萩、植物詠では『万葉集』中最多を誇るらしい。二首目の作者は栗標、題は「久しくいたつきける人のもとへ葉月つごもりに」。葉月は八月、菊月は九月である。三句は「(薬も)効く月や」に「菊月や」で切れる。結句から初句に戻って「お食事も」以下、むしろ意味が通りやすい。三首目の作者は幽山、題は「帰咲如花」。季節外れに咲く帰り花を詠った。花の雫は春と変わらないが、時雨に濡れながら咲く品種も「時雨桜」、その季節の合致したところに興味が湧いたのだろう。四首目の作者も幽山、題は「冬月」。四句「月の桂」は古代中国の伝説で月に生えているという木である。桂の花は月の光をいう。紅葉と一緒に照っていた月、その月は紅葉が散ったあとも変わらない。思えば冬枯れを知らない花であった。
|
| 第155回 狂歌三栗集(2) |
組重のもりこほしもて酒のみぬはや正月のはしくれの気て 如石
掲出歌の題は「除夜酌酒」。初句の「組重」は幾つも重ね合わせるようになっている重箱、二句の「盛り零し」は重箱に御節料理を盛っていったが入りきらなかった分をいう。盛り零したといっても立派な御節料理には違いない。だから下句「はや正月の端くれの気で」となる。昆布巻や田作、牛蒡、里芋などに箸を伸ばしながら余得の酒に与っているのだろう。
駒とめて馬子ははちまきうち払ひほうかふりにてゆきの夕暮
おもひきや鳥も通はぬ山里てひるとんひめにかけられんとは
よきにつけあしきにつけてとはるれはこれさい翁か馬のあふ友
されはとて浮世の事もすてられすけふしらぬ身のあすのたくはへ
一首目の作者は如石、題は「雪中馬卒」。藤原定家の〈駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野のわたりの雪の夕暮〉(『新古今和歌集』六七一)が本歌である。鉢巻を頬被りに変えて行き(雪)の夕暮れとなる。二句「馬子」は馬方で幕府の役人、だから題に「馬卒」が入る。二首目の作者は幽山、題は「山家盗賊」。古歌に多い「思ひきや~とは」の構成に倣った。四句の「昼鳶」は昼間に人家等へ忍び込むこそ泥で接尾語「め(奴)」は昼鳶を卑しめていう。これを共有するのが同音の「目」で以下「目に掛けられんとは」となる。三首目の作者は如石、題は「友」。上句は「良きにつけ悪しきにつけて訪はるれば」、下句は「塞翁」に「再往」(同じことを繰り返すこと)の意を掛けた。句全体では「これ塞翁(私)の馬が合う友」となる。四首目の作者は幽山、題は「述懐」。歌意は「世捨人になろうと思った。だからといって浮世が捨てられたわけではない。定めのない命のための貯えに励んできた、思えば優柔不断の人生よ」か。
花によはれ月に招かれうかうかとつひには老(い)に誘はれそする
夢の世は夢の間なれや目をとちて目をふさく時の事をおもへは
摩訶盧遮那婆婆吒耶うんとほら貝のしりにもまかふ山伏のくそ
紗綾綸子それよりたたの木綿にてとかくやすいをいはふ腹帯
一首目の作者は幽山、題は「述懐」。『夫木和歌抄』の〈一年を花よ月よとすごしきて身にゆきつもるはてぞかなしき〉(七六一六)を受動態に置き換えた感がする。結句「誘はれぞする」は拒めないのが端から見えているのだ。二首目の作者は如石、題は「深観無常」。初句「夢の世」は夢のようにはかない世の中、二句「夢の間」は極めて短い間、初二句に対応するのが三句の生、四句は永遠の眠りで結句は死の「事を思えば」となる。三首目の作者は栗標、題は「屎百首の中に」。結句が「~のくそ」で終わる作品七首中の一首である。「すべらぎのくそ」や「うかれめのくそ」があるが結句横列百首は壮観なこと鼻を抓むばかりだったろう。二句は「ばばしつやうんと」、四句「法螺貝の尻」は音の出る開口部が思われる。四首目の作者は如石、題は「着帯祝」(「着帯(ちやくたい)」は妊娠五か月目に初めて岩田帯を着用すること)。初句の「紗」も「綾」も「綸子」も名のある織物、四句の「やすい」は安産の「易い」に三句「木綿」の「安い」を掛けた。
|
| 第156回 狂歌手毎の花 四編 |
あたまをはかきの木かけのまけ相撲手しふいなけにへたはころりと 渓華堂宵甫
『狂歌手毎の花 四編』の輯者は文屋茂喬、刊記は文化十(一八一三)年である。掲出歌は挿絵の一首で題はない。柿尽くしで相撲風景を詠った。上句は「頭をば掻きの木陰の負け相撲」だが「掻き」に「柿」である。下句は「手渋い投げに下手はころりと」である。「手渋い」は手ごわい、「渋い」は柿の縁語である。「下手」は柿の「蔕」と中々の巧者なのだ。
軒の下かりにし礼をいふ口のかはかぬうちにまたもしくるる
蛸のあし八本はかり流す木をいかだと人のいふそをかしき
よく実のる秋のさなたを守るのは案山子か水に移るかけ武者
鬼にうつ礫となるはつよけれと又よわき名の味噌になる豆
一首目の作者は桂花園秀郡、挿絵の一首である。三四句の「口の渇かぬ」は初二句「軒の下借りにし礼」の言葉を口から出して幾らも時がたっていないこと、これに同音で身の「乾かぬ」を重ねた。二首目の作者は鹿外楼石川清澄(雅望の長男)、題は「筏」。蛸の足は八本、烏賊の足は十本である。上句の「蛸」は筏が八本の材木で結束されることが多かった、そこから出たのだろう。「蛸」を「烏賊だ」とは可笑しい、というのだ。三首目の作者は翫月庵登南、題は「水辺案山子」。初句は「良く実乗る」(「良く実る」に同じ)、二句の「狭田」は狭い田また一説に美田をいう。下句は句割れの「案山子か/水に移る影武者」で田園風景に敗軍の影、「移る」は「映る」だが、イメージとしての落武者村また隠田聚落の秋の景とした。四首目の作者は凌風亭花眠、題は「豆」。上句は節分に「鬼は外」と撒く豆だから強い。下句は食品の味噌になる豆、これに泣き味噌や弱味噌など弱い者を嘲っていう場合の「味噌」を重ねた。
うるはしき紅をさしぬる蓮なれは仏さんてもござりそなもの
留守見舞(ひ)貰ひましたと淋しさをよそへもくはるあきの夕暮
借り傘をかやせはまたも定めなきしくれの雨に身をすほめゆく
引(き)舟もそふ水揚(け)は湊よりきらをかさりて出(た)す新艘
一首目の作者は香桂法師、題は「蓮」。初二句は紅色の蓮の花を擬人化して妖艶な女性とした。下句の「仏さん」は「愛人」だろう。「御座りそなもの」で断定の語を省略した。二首目の作者は生果亭桂芽、題は「留守秋夕」。初句は主人が不在中に家族の安否を問い尋ねることをいう。差し入れなどもあっただろう。帰宅後は挨拶も兼ねての訪問となった。人懐かしい秋の夕暮れなのだ。三首目の作者も生果亭桂芽、題は「時雨」。二句「かやせば」は「かえせば」の音変化である。傘を借り、傘を返し、傘がなければ結句「身を窄めゆく」、これが三四句「定めなき時雨」の対処法なのだ。四首目の作者は椙廼屋三寸美、題は「出船」。初句「引き舟」は他の船を引き綱で引く舟、「添ふ」は「加わって」、三句「水揚け」は小水越綱(こみずこしづな)(舵を巻き上げるための綱)をいう。これを出すところまで曳航してもらうのだろう。四句は「綺羅を飾りて」、結句「新艘」は新造の船をいう。水揚げや新艘の多義語が華やかさを倍加する。
|
| 第157回 狂歌手毎の花 四編(2) |
薄雪もきえてなきさに舟水をくめとも尽(き)ぬ春のよの月 下戸舎望月
掲出歌の題は「舟春月」。二句は上からは「薄雪も消えて無き(さに)」、下へは「(消えて)渚に舟水を」となる。三句の「舟水」は船遊山で盃洗がわりに使う川の水である。「渚」は波打ち際で出港前となる。四句「汲めども尽きぬ」は水また結句「春の夜の月」だろう。
暮そふてくれぬといひし春の日に庭から燈す梅のはつ花
ころも川ほころひかかる桜には後をみする人はあるまい
さす影に渡る丸木の橋よりもめのはなされぬ月のさやけさ
秋きぬとはやくもしかと知らせたるかりほの庵のおとし鉄炮
一首目の作者は童亭源土器、題は「梅」。初句の表記は「暮れさうで」となる。結句の「初花」は多義語だが、その木に初めて咲いた花と解した。四句「庭から燈す」が斬新、この種の比喩としては最初期のものではないだろうか。二首目の作者は其川庵羽觴、題は「川辺桜」。初句「衣川」は弁慶が立ち往生した古戦場でもある。歌意は「衣川、その衣と違って、今、桜の花が綻びかけている。衣川を舞台とした合戦ならいざ知らず、花に背中を見せる人はあるまい」。三首目の作者は海道澄人、題は「橋上月」。初句の「差す影」は月光だろう。しかも橋は橋でも丸木橋、一本の丸太を渡しただけの橋だから余程の注意を払わないと足を踏み外す危険がある。にも関わらず下句「目の離されぬ月の清けさ」という酔狂な絵図となった。四首目の作者は朗月斎楚宝、題は「立秋」。二句は「早くも確と」で「確」に「鹿」を掛けた。四句の「かりほのいお」は「刈穂」に「仮庵」を掛けた語で「仮庵」をいう。結句は農作物を荒す鳥獣を脅して追い払うための空砲をいう。
小原女のしはしも雲のはれやらてかしらおもけな春雨のそら
庭にかく雪に落せは眼かねさへ心なき身をにらむやうなり
薬喰夜毎にかへて遊君か身のたのみともなすおつとせい
春宵の價にまさる菜の花や野は一めんに小判色なす
一首目の作者は桂花園秀群、題は「春雨」。初句「小原女」は大原や八瀬の里から柴や花などを頭にのせて京都の町に売りにくる女性をいう。二句に「柴」を隠す。四句「頭重げな」も天候と相俟って、よくその姿を伝えていよう。二首目の作者は東原亭為彦、題は「雪」。初句は「庭に斯く」(庭にこのように)と読んだ。三句以下は、心のない眼鏡が心のある身(私)を「睨むやうなり」で、雪に跡をつけないという伝統的主題を引き受ける中での新味と解した。三首目の作者は都中館梅李、題は「遊女薬喰」。「薬喰」を『日本国語大辞典』は「冬に、保温や滋養のために猪、鹿などの肉を食べること。普通、獣肉は穢があると忌んで食べなかったが、病人などは薬と称して食べた」と説明する。しかし狂歌を通してだが、その広がりには驚かされることが多い。膃肭臍と遊女も例外ではない。四首目の作者は花麓亭佳喬、題は「菜花」。初二句「春宵の價」は「春宵一刻値千金」、それに勝るものとして持ち出したのが菜の花で、桜でないところが新鮮である。結句の額ではなく色で決めたのも悪くない。
|
| 第158回 狂歌越天楽 |
双六のふりみふらすみしくれ空とこをさいめといふこともなく 梅雨亭華栗
『狂歌越天楽』の撰者は棗由亭負米、刊記は文化十一(一八一四)年である。掲出歌の題は「時雨」。上句は「双六の振りみ振らずみ」と「降りみ降らずみ時雨空」が二句で合体、もしくは「双六の」を枕詞とした。「み」は接尾語である。下句は「どこを境目といふこともなく」、「境目」に「賽目」を掛けた。時雨を双六と平行して詠う、その技が見所である。
ちりあくたすつへからすのみそまても埋む落葉はとかめてもなし
喰(ひ)初(め)にあらねと祝ふ亥の子日は月さへ日さへかなかしらなる
つまさきもこほる斗の寒けさにあたたかにはく鹿の皮たひ
節季前ゆつたり月をくわへてもやはりせはしき冬の日短
一首目の作者は灰汁亭蛇目、題は「落葉」。表記を改めると〈塵芥捨つべからずの溝までも埋む落ち葉は咎め手もなし〉となる。溝を巡って人の論理と自然の摂理が相容れないさまを落ち葉に見ているのである。二首目の作者は似由亭負麦、題は「亥猪」(亥の子餅)。初句「喰ひ初め」は出生後初めて食事をさせる祝いの儀式、二三句は「亥の子の祝」で稲の収穫を祝って新穀の餅を搗いた。それが亥の月(十月)亥の日なので結句「仮名頭」(いろは四十七文字の最初の「い」)だといって祝意を重ねたのである。三首目の作者も似由亭負麦、題は「足袋」。初句と結句が対応する。その「鹿の皮足袋」に注目した。使用は限られた範囲また職域だったと思われるが、残念なことに、「私」を具体化する情報を欠いている。四首目の作者は栗英亭棗実、題は「閏月」。文化十年の閏十一月と思われる。閏月も節季も実感から遠いが、いつもと変わらない忙しさだったのだろう。またそれを煽るように冬の昼間は短いのである。
秋ならはさそとおもへと寒けさにほめてひつこむ冬の夜の月
御狩する末野のわたりふりしきるゆきに見それしましらふのたか
誓文をはらふ跡から商人もはやかはうそのくすり喰(ひ)する
坊主あたま手鞠つくほとあけさけはひいふうみよの仏かそへて
一首目の作者は似由亭負麦、題は「冬月」。月の明るい夜を良夜という。初二句はその内「特に中秋名月の夜」といわれる良夜を指す。三句以下「寒けさに誉めて引っ込む冬の夜」は逆で特に断らない良夜の故である。二首目の作者は丹波亭負栗、挿絵の一首である。初句「御狩」だから貴人だろう。二句は「末野の渡り」続けて「雪に見逸れし真白斑の鷹」となる。降りしきる雪の中を翔(かけ)ていく、もう見分けも付かないのだが、羽に白い斑紋のある鷹を遠望しているのである。三首目の作者は牧事亭負笛、題は「薬喰」。上句は商人の風習で十月二十日に京都四条寺町の誓文返しの神に参詣し、嘘の罪を払い、神罰を免れるように祈った後、の意である。四句「川獺」に「(川)嘘」だが、何でもよく食べたものである。四首目の作者は十里亭遠栗、題は「仏名」。永田貞也に〈猫も来ば袋に入れて鞠に蹴ん山寺淋し秋の夕くれ〉があるが、初句「坊主頭」を「鞠」に見立てた歌である。位牌堂での清掃作業の場面と解した。
|
| 第159回 狂歌後三栗集 |
いんきんに袴着て出るつくつくしたれしも腰をかかめてそとる 寺井梅風
『狂歌後三栗集』の撰者は百尺楼桂雄と橙果亭天地根、刊記は文化十一(一八一四)年である。掲出歌の題は「土筆」。上句は「慇懃に袴着て出る土筆」、「つくづくし」(または「つくつくし」)は土筆の異名である。下句は「誰しも腰を屈めてぞ採る」。「誰しも」の「しも」は強意の助詞、「つく」と「し」の反復が快い。「小さ子」に仕える大人の絵図のようだ。
呼子鳥かんこ鳥てふ説はあれと太鼓ほとなる判はおされす
今ははやとんてかたちもかはひらこさして毛虫のけは見えぬ也
しる人もなきふる郷にかはらぬはむかしも今もものいはぬ花
のとかなる春くははるはうれしけれと二度咲(く)花のなきそ悲しき
一首目の作者は西隣亭戯雄、題は「呼子鳥」。呼子鳥は古歌に登場するが正体不明である。二句「閑古鳥」(郭公)だとする説もあるが下句「太鼓程なる判」(「なる」に「鳴る」を掛けた)は捺せないとする。二首目の作者は橙果亭天地根、題は「蝶」。初二句は「今ははや飛んで形も」、三句「かはひらこ」は蝶の古名である。上から「形も変は(ひらこ)」だろう。四句の「さして」(これといって)に「刺して」を掛ける。結句の「け」は「気」に「毛」を重ねた。三首目の作者は橙芽亭天与之、題は「故郷花」。結句の「物言はぬ花」は草木の花をいう。これに対して「物言う花」は美人である。人は替わるが自然は替わらない。素朴な感慨を詠った。四首目の作者は辻青霞、題は「有(り)ける年よみけるといふ題をさぐりて」。探り題は籤で探り取った題、それが「有りける年よみける」なので閏月の有った年、それも春とした。陰暦の智恵を喜ぶ「長閑なる春加はるは嬉しけれど」と自然の運行を歎く下句となった。
裾まくるかいとり妻に悪されも言はて口をはとつるはまくり
月かけの有明行燈消そとしてふつと一こゑ聞(く)ほとときす
鶯のかひこの中のほとときす親はないかい今の一声
鎧かふとかさり立(て)たる初のほり其(の)ちのみ子かけふの大将
一首目の作者は懐古亭英風、題は「蛤取」。表記を改めると〈裾捲る掻取妻に悪戯(わるざれ)も言はで口をば閉づる蛤〉になる。「掻取(かいどり)」に「貝取り」を掛けた。蛤(女陰)を仰いで、悪い冗談を言いそうな蛤であったが、採られてはお終いというので口(蓋)を閉ざしたのである。二首目の作者は橙果亭天地根、題は「郭公」。本歌は藤原実定の〈郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる〉(『千載和歌集』一六一)。室外から室内に舞台を移して「月影の有明行燈」としたところに新味を見る。三首目の作者は粒果亭方雅、題は「郭公」。上句は「鶯の卵(かいご)の中の時鳥」(托卵)で実の親子でないことをいう。下句の意は「親の時鳥が今この場に居合わせたら素晴らしい子の鳴き声をどんなに嬉しく聞くだろう」。四首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「初幟」。二句「立てたる」は上から「鎧兜飾り~」、下へは「~初幟」と二役を担った。下句は「其の乳飲み子が今日の大将」で、「其の」からも初幟は室内用だろう。
|
| 第160回 狂歌後三栗集(2) |
ふる雨に蛍きよかとかやの内にあんしてわれは気をもやしけり 幼女 うの
掲出歌の題は「雨中蛍」。表記を改めると〈降る雨に蛍来よかと蚊帳の内に案じてわれは気を燃やしけり〉になる。雨戸を開けて蛍を待っているのだ。「来よ」は「来よる」の「る」の脱落した形だろう。「来よる」は「来る」、『大阪ことば事典』は「しよる」「行きよる」ほかを載せる。で、待った甲斐あって蛍は来よった。結句は幼女が灯していた胸の蛍火なのだ。
ならうなら実さへ花さへその香さへ霜おけるまてとつとこよもの
夕風に吹(き)たてられてちるほたるひるのあつさのゆくへなるらし
せせなきのほうふりむしも蚊となりし出世いはひの餅やつくらん
金銀の身につく徳はうをさへもはらふくらしてあそふ泉水
一首目の作者は百尺楼桂雄、題は「橘」。本歌は〈橘は実さへ花さへその葉さへ枝に霜降れどいや常葉の木〉(『万葉集』一〇〇九)。初句は「出来ることなら」、結句「取つとこ」(「取っておこう」の意。『大阪ことば事典』で助動詞「とく」の項に「~ておく」の約とある)と「常世物」(橘の古名)の合体である。二首目の作者も桂雄、題は「蛍」。下句「昼の暑さの行方なるらし」の「行方」(行った先)が上句「夕風に吹き立てられて散る蛍」となる。涼感の由縁である。三首目の作者は繞樹亭百丈、題は「蚊」。初句の「せせなぎ」(溝)は溝、どぶ、下水、流し元の小溝などをいう。二句は蚊の幼虫で「棒振り虫」、下句は成句「蚊が餅搗く」を使った。四首目の作者は山田其風、題は「金魚」。二句の「徳」は生まれつき備わった能力や性質の意であろう。三句の「魚」は金魚や銀魚をいう。下句「腹脹らして遊ぶ」は魚の腹部を言い得て妙、これも金銀の衣装故の天運なのだ。「泉水」は庭先に作られた池をいう。
七日七日たてしそとはのうへこして次第に高うしける夏草
日やけせし賤か姿にひきかへて垣ねにしろきはなの夕かほ
そこぬけにふるゆふたちの雲はれてたまり水にもやとる月かけ
奥さまの小袖を下女はあれもほしこれもほしかる土用干かな
一首目の作者は周果亭桂右、題は「夏草蔵墓」。初句は初七日から七七日までの意、二三句は「立てし卒塔婆の上越して」。卒塔婆は供養のため墓のうしろに立てる細長い板をいう。下句「高う繁る」の結果が「夏草墓を蔵す」なのだ。二首目の作者は抄果亭標山、題は「夕顔」。上句「賤」からは若い農婦、下句の「夕顔」からは『源氏物語』(夕顔巻)が連想される。三句を経て後者礼賛の趣きであるが、前者の健康の中にこそ美はあろう。三首目の作者は酔花亭春雲、題は「雨後夏月」。表記を改めると〈底抜けに降る夕立の雲晴れて溜まり水にも宿る月影〉となる。歌意「底抜けに降るというが、空にあった雨雲がなくなった。文字通り天の底が抜けたのだろう。溜まり水には月が宿っている」。四首目の作者は抄果亭標山、題は「土用干」。三句は「あれも干し」、ところが四句は「これも欲しがる」としか読めない。再び三句に戻ると「あれも欲し」と読める。土用干しは下女にとって羨ましい展示会でもあった。
|
| 第161回 狂歌後三栗集(3) |
はきものは腰にしつかりさしなから扇落(と)してはしる夕立 清果亭桂影
掲出歌の題は「夕立」。初句「履き物」といえば鼻緒のある草履か下駄だが、二三句「腰にしっかり差しながら」からは草履(雪駄・板裏草履・麻裏草履・中貫草履・藁草履)の方が似つかわしい。下駄なら手に提げるだろう。裏を重ねて帯に挟んだのはいいが、そのときに先客の扇を落としたのだろう。走れば鼻緒擦れも心配だ。ここは裸足しかないのである。
いつまても若い気の有(る)星合を南極星はうらやみそせん
むかしから子のあるさたもきかされははらみ句なりと星にたむけん
いそかるる道さまたけの大踊(り)まぬけ拍子にぬけられもせす
おきおきの露のまかきのかかみ草身しまひはやき花の顔はせ
一首目の作者は生果亭桂芽、題は「七夕」。三句「星合」は牽牛星と織女星が会うこと。四句の「南極星」は老人星ともいう。人の寿命をつかさどるとされ、地上の男どもの野卑な関心となった。二首目の作者は酔花亭春雲、題は「七夕」。余計なお世話であり、今ならセクハラそのものだが、時代が違うのである。四句「孕み句」は連歌や俳諧などで事前に作っておいた句、その名称からの展開である。三首目の作者は橙芽亭天与之、題は「踊妨往来」。三句は大勢で踊る踊りをいう、四句「間抜け拍子」から初二句「急がるる道妨げ」を「抜けられもせず」なのだ。ちなみに抜けた「間拍子」は「強弱の拍子」と「その時の弾み」の多義語となる。四首目の作者は竹女、題は「槿花」。上句は「起き起きの(起きたての)露の籬の鏡草(朝顔)}となる。下句は「身仕舞ひ早き花の顔」で上句の「鏡」と下句の「顔」が対応する。また鏡草と同音の女訓書に中江藤樹の『鑑草』があり、女性の守るべき徳目を説く。
普請場を我ものかほにすみつほの車にもちよとむかふかまきり
物かなしき秋の夕は雲も目をしはたたくかと見ゆる稲つま
をみなへしはきのあたりを吹(き)まくる野分は風の性わるそかし
飛(ひ)めくる烏もち論もろ鳥のねくらさわつくけふの月かけ
一首目の作者は抄果亭標山、題は「修造場蟷螂」。三句「墨壺」は直線を引くのに用いる大工道具、四句の「車」は糸車である。「ちょと」は副詞「ちょっと」の変化と解した。今、蟷螂の綱渡りが始まりそうな気配と読む。二首目の作者は曲肱亭百年、題は「稲妻」。三句以下が途轍もない見立てである。四句「瞬く」は「頻りに瞬きをする」「目をパチパチさせる」意。垂直の稲妻そのものより雲の下部、横に広がる光りの明滅に注目したのだ。三首目の作者は至果亭桂普、題は「野分」。遍照の〈名にめでて折れるばかりぞ女郎花我おちにきと人にかたるな〉(『古今和歌集』二二六)が知られるが、これに「萩」(脛)を配して三句以下を展開した。結句の「性悪」は好色な様をいう。四首目の作者は粒果亭方雅、題は「月」。二三句の「烏もち論もろ鳥」の類音が快適である。「勿論」の「もち」は陰暦十五夜の「望月」をいう。その姿、その光に、照らされる空の黒い烏も、塒の黒くない諸鳥もざわつくというのだ。
|
| 第162回 狂歌後三栗集(4) |
崩れ簗もれて日に日におち鮎のさひしなからになかれ行(く)秋 清果亭桂影
掲出歌の題は「暮秋」。初句の「簗(やな)」は川の瀬に杭を打ち並べて水を堰き、一か所をあけ、そこに流れてくる魚を梁簀に落とし入れる仕掛である。そのどこかが崩れているのだろう。三句「落ち鮎」は秋に産卵場へ向かって川を下る鮎、またの名を「錆鮎」といい、同音の「さび」が四句「淋しながら」で呼応する。「ながら」は「けれども」の意と解した。
花ならはいとはん風に雲ちりてさくらの宮の月のさやけさ
かしましきうちのきぬたに目はさめてをちの碪にあはれをそしる
月にうつ夜さむの衣音さえて我(か)影法師はわれと相槌
影の膳すゑて待(つ)身のさひしさはふたりまへなる秋の夕暮
一首目の作者は万樹亭連雲、題は「社内見月」。漢字を補うと〈花ならば厭はん風に雲散りて桜宮の月の明けさ〉。桜宮は大阪市都島区にある神社、月の宮(月の中にあるという宮殿、月宮)と呼応する。また満開の桜をライトアップする月という幻想も誘う。二首目の作者は光華亭彩雲、題は「擣衣」(砧で衣を打つこと)。四句の「おち(彼方)」、遠くから聞こえてくる砧の音に結句「哀れをぞ知る」は観念だろう。ところが家の中からだと上句「姦しき内の砧に~」と現実に戻る。人とは勝手なものだ。三首目の作者は信夫雄州、題は「擣衣」。初句は「月夜に打つ」意だろう。その「夜」は二句「夜寒」(秋夜の寒さ)に登場する。また「相槌」は互い違いに打つものだが「影法師」と「我」は一体となる。四首目の作者は如栗亭楚石、題は「留守秋夕」。連れ合いが仕事か何かで旅の身なのだろう。その無事を祈っての「影の膳」なのだ。淋しさを二人分ではなく「二人前」としことでほのぼの感も加わった。
虫の音に心ほそくてふる郷のふと気にかかる秋のなか旅
銀杏の葉はらつきかける冬のきていつちいにけん虫の声々
冬のきたしるしを見する懐手なに握つたといふちやなけれと
二三丁かへしにもとる傘の辻のあなたは又しくれけり
一首目の作者は吹松亭峰風、題は「秋旅」。三句「ふる」は初句「虫の音」に共振する意の「振る」を「古里」の「古」に掛けた。また四句の類音「ふと」で調子を取った。当時の長旅と切っても切れぬ不安であったろう。二首目の作者は粒果亭方雅、題は「初冬」。漢字で補うと〈銀杏の葉ばらつきかける冬の来て何方去にけん虫の声々〉。二句と四句が呼応し、初句の「い(ちょうの葉)」と四句の「い」音がリズミカルに響く。三首目の作者は條果亭栗標、題は「初冬懐手」。「ふところで」は手を懐に入れることをいう。上句「冬の来た標」とは寒いからだが、それを下句「何握ったといふぢゃなけれど」とやると余計なことを想像する。そこが味噌だろう。四首目の作者は光華亭彩雲、題は「時雨」。初句の「丁」は距離の単位で一丁は約一〇九メートルをいう。傘(からかさ)を借りたら雨が止んだ。返すつもりで二、三丁戻ったら辻の彼方、借りた向こうはまた時雨れている。諦めるしかない時雨なのだ。
|
| 第163回 狂歌後三栗集(5) |
家ことの屋根一面にしら雪のつもりて見えぬ瓦町すち 幼童 辻行雲
掲出歌の題は「市中雪」。結句「瓦町」は瓦を焼く職業の家が多い町の意で、これを地名とする町も多い。ここでは大阪市中央区瓦町を舞台に選んだ。二句の「屋根」と呼応した「瓦町」であり、「一面に~見えぬ(瓦)町筋」でもある。『狂歌後三栗集』に二首を見る「幼童」だが、四年後の『狂歌新三栗集』では前置きなしの巫山亭行雲で十三首が入っている。
夜へぬきしわらつはいつこ落葉をははかてはしれぬはたこやの庭
下け札はとれてうつろふ菊なから迷子にならぬにほひ也けり
材木の市場にふれと白たへの雪にはゆるせ下駄のこく印
看板はおの字はかりにうつもれてしろいは色にゆつる雪の日
一首目の作者は翠扇亭清風、題は「旅店落葉」。漢字を補うと〈昨夜脱ぎし草鞋は何処落ち葉をば掃かでは知れぬ旅籠屋の庭〉。二句「わらづ」は「わらうず(藁沓)」の変化で「わらぢ」に同じ、四句「掃かで」に草鞋を「履かで」を掛けた。二首目の作者は清果亭桂影、題は「残菊」(九月九日の節句を過ぎたあとの菊、また晩秋から初冬まで咲き残っている菊をいう)。ここは冬の菊、鉢植えと解した。下げ札も取れて位地も変わったが、匂いでそこと知れる。品評会も終わった愛好家の庭を想像した。三首目の作者は散綺亭紅霞、題は「市場雪」。二句は「市場に降れど」だろう。結句の「刻印」は材木の所有者などを示すものと解した。「下駄」だから「一一」、肩すかしは思う壷なのだ。四首目の作者は送月亭長風、題は「雪埋看板」。平仮名が「雪」に合っているが、意味を探るなら〈看板は「お」の字ばかりに埋もれて「しろい」は色に譲る雪の日〉だろう。白粉の「しろい」に雪の「白い」を重ねたのだ。
まうけてもぬけめかあるかすたすたといへと坊主に鉢巻の所作
月にとる膃肭臍をはよへ今宵りやう夜をかけてくふ薬喰
観音の御手をからはや年のくれいろいろさつたの用事あるから
うへをしたへかへすはかりにせはしきは未も末となるとしのくれ
一首目の作者は清果亭桂影、題は「すたすた坊主をみて」。漢字を補うと〈儲けても抜け目があるかすたすたといへど坊主に鉢巻の所作〉。詠われているのは寒中に裸で縄の鉢巻き、腰に注連縄、手には扇や錫杖などを持って歌い踊った乞食坊主である。成句「坊主の鉢巻き」(締まりがないこと)を効かした。二首目の作者は生果亭桂芽、題は「連夜薬喰」。初句は「月夜に捕る」意だろう。三四句は「昨夜今宵両夜をかけて」、「両夜」に「良夜」を掛けた。オットセイも薬食いの対象だったのだ。三首目の作者は笠松軽雲、題は「歳暮」。二句「~借らばや」は「借りよう」、下句「いろいろ雑多の用事あるから」で初句に戻る。三句切れ、意味的には四句から始まる構造となっている。四首目の作者は散糧亭雄飛、題は「未年のくれに」。初二句「上を下へ返す」(混乱し、ごった返すさま)は三句以下の「忙しき~年の暮れ」だが、もう一つは文字通りの四句「未(ひつじ)も末(すえ)となる」の漢字の面白さだった。
|
| 第164回 狂歌後三栗集(6) |
ひろき事かきりはあらし日本はし不二もちいさくみゆる大江戸 西隣亭戯雄
掲出歌の題は「江戸」。初二句を三句の「日本橋」を基点に証明する構図である。ただ東海道五十三次の起点ともなる「日本橋」が次の「小さく」に呑まれては困る。で「橋」を平仮名表記にした。また助詞「は」に副助詞の「し」で日本の中心であることも強調する。これで準備完了、不二が小さいのは距離のせい、マジックとはいえ納得の「大江戸」となる。
風起(こ)すふいこに死(ん)て名を残す狸はとらにおとらさらまし
三熊野の烏よりしも順礼の一番鶏かまつうたひ出す
古のこかねはしらすみちのくにはなをさかせる仙台の銭
捨(て)て行(く)親はなきつつうちまもる顔見てにこり子や笑(ふ)らん
一首目の作者は懐古亭英風、題は「狸」。二句「鞴(ふいご)」は火を熾すのに用いる送風器だが狸の皮を使う。よって成句「虎は死して皮を留め人は死して名を残す」に同等だというのだが、その下句に「とら」が二度覗く。二首目の作者は粒果亭方雅、題は「鶏」。西国三十三カ所観音霊場順礼の第一番札所は那智の青岸渡寺である。御詠歌は〈補陀洛や岸打つ波は三熊野の那智のお山にひびく滝つ瀬〉で、これに合わせたように一番鶏も鳴くのである。三首目の作者は益洗亭武雄、題は「仙台銭」。陸奥は〈天皇(すめろき)の御世(みよ)栄えむと東(あづま)なる陸奥山(みちのくやま)に黄金(くがね)花咲く〉(『万葉集』四〇九七)から「花の咲く国」と呼ばれた。結句は仙台藩が領内に限定して流布させた仙台通宝をいう。実際の鋳造は一七八四年から四年間であった。四首目の作者は吹松亭峰風、題は「捨子」。三句「打ち守る」(じっと見詰める)は親の去ったあとの状況であろう。結句の「にこり」が赤子に幸運することもあったろう。初二句と対照的な親の知らない光景である。
牛若とさす将棋には弁慶も長刀おきて鎗つかふらし
さあ次の咄しはたそといふうちに番か廻つてうつや明(け)むつ
お月さまにくらへてはとまれ泥亀もはなせはなみの花のうへ行(く)
立居さへああゑいやつと老(い)ぬれは我身ひとつかもてかぬるなり
一首目の作者は独酔亭百銭、題は「弁慶と牛若将棋さすかた」。義経ではなく、弁慶と牛若丸が仲良く将棋を指しているのが面白い。長刀は五条橋で負けているので今度は戦いの場を将棋に移して鎗でリベンジの弁慶なのだ。二首目の作者は周果亭桂石、題は「話至暁」。夜話だが百物語を連想した。蝋燭を百本立てて一話終わると一本を消す。百話終わった闇の中に妖怪が現れる。その最後の番が回ってきたが「明け六」(午前六時頃)で闇も遠ざかったというのである。三首目の作者は周果亭桂右、題は「放泥亀」。泥亀はスッポンの別名だから上句は成句「月と鼈(すつぽん)」を指す。「とまれ」は「ともあれ」の音変化。下句は「放せば波の花の上行く」である。波の花は海の白い泡の見立てである。泥亀は淡水産だが、そこはそれ花を持たせたのだろう。四首目の作者は懐古亭英風、題は「述懐」。二句「えいやっと」は「力を入れて」と「やっとのことで」の両義が働く。結句は「持ち兼ねるなり」の音変化と解した。
|
| 第165回 狂歌選集楽 |
かたわきへきんたまによろり殿さまも腹をかかえの角力をかしき 玉雲齋貞右
『狂歌選集楽』の撰者は雄崎貞丸、詠者は玉雲齋貞右、刊記は文化十一(一八一四)年。貞右二十五回忌の独詠集である。掲出歌の題は「武家相撲」。家臣の相撲を観覧する殿様だろう。初二句「片脇へ金玉にょろり」は回しの横から睾丸が顔を出したのだ。泰平の世になって武家相撲も様変わり、四句の「腹を抱え」は大笑いで素人相撲の罪の無さだけが残った。
にやんにやんの誓文たてそ猫の恋首筋もとにかみかけた中
月も日も五つ五つのわれ角力軒のしやうふは明日とらせます
呑(み)こみのよいに似合(は)す鵜飼(ひ)船最上の川てかふりふるとは
魚の名を鳥にむりやりおしつけていひなれさせし此(の)雀鮓
一首目の題は「猫妻乞」。初句七音のオノマトペは二匹の猫の姿でもあろう。二句は「誓文立てぞ」(約束ぞ)、その「首筋元に噛みかけた」愛撫が艶めかしい。二首目の題は「五月五日」。三句「割れ角力」は勝負のつかない角力をいう。下句は「(軒の)菖蒲は明日取らせます」に「勝負は明日取らせます」と掛けた。三首目の題は「鵜川」。下句は「最上の川で頭振るとは」(頭を左右に振って不承知の意を表す)。何故なのか。古歌には〈最上川いなとこたへていな舟のしばしばかりは心をも見む〉(『新後拾遺集』九九八)等、最上川に稲舟を配合した例が多い。その「稲」と同音の「否」を使った古歌に倣ったのである。四首目の題は「福島雀鮓をたうべて」。雀鮨は背割にした江鮒(ボラの幼魚)を塩に浸して乾かし腹に鮨飯を詰めたもの、形が雀のように脹れているので。この名がある。大阪の福島名物であった。三句「押しつけて」から握り鮨でないことも分かる。四句は「言い慣れさせし」に「飯熟れさせし」だろう。
むら猿の尻かと見れは蔦紅葉春日の杉の枝にふらふら
年もおし又鶯もきかまほしこころは除夜の闇に迷ふた
君か影ちらとみかんのかはいらしま一度こちらむいてたまはれ
紙袋の底かいたみてこほれ梅あたらみやけを棒にふる雨
一首目の題は「森紅葉」。初二句は「群猿の尻かと見れば」、ところが三句「蔦紅葉」(紅葉した蔦の葉)だった。四句の「春日」は不明だが、その名を冠した森「の杉の枝に」だろう。「ふらふら」は「ぶらぶら」と濁音で読んだ。二首目の題は「歳暮」。今年と来年もしくは新年と旧年、その二律背反の間で迷った。しかし初句「年も惜し」の取り方次第で別の解もあろう。つまり春の鶯も聞きたいが、また一つ若さから遠のくのも惜しい、その二者択一の闇に迷ったというのである、如何。三首目の題は「寄蜜柑恋」。初句の意は「君が姿を」だろう。以下「ちらと見て忘れられない/その可愛らしさ/もう一度こちらを/向いて下さい」。「ま一度」は「今一度」の音変化、「向いて」に蜜柑を「剥いて」を重ねた。四首目の題は「伊丹の里にて雨に逢ひて」。二句「痛みて」に酒の町「伊丹で」を掛けた。三句「零れ梅」は味醂の絞り粕をいう。無駄にする意の「棒に振る」だが貞右には「棒に降る雨」だったろう。
|
| 第166回 狂歌夜光玉 |
打(ち)よりてねきりこきりのほとときすこの鳥箒かけねこさらぬ 如棗亭栗洞
『狂歌夜光玉』(「一名順慶町夜店百首」)の詠者は如棗亭栗洞と棗由亭負米、撰者は棗由亭負米、刊記は文化十二(一八一五)年である。掲出歌の題は「鳥箒屋」(鳥箒は鳥の羽で作った箒、机の上などを掃いた)。二句は「値切り小切り」で、あれこれ言い立てて値切ることをいう。結句は「掛け値御座らぬ」、応じられないのである。同音反復類音反復で快調だ。
ここもまた天の岩戸や八百よろつかみあつまりてうれる常店
はなやかなはな緒に足も立(ち)とまりようはけるものそふりやの店
盃にあらて茶わんてすすめます爰まてこされあまさけあまさけ
きんかんや桃梨ふとうかきみかん春夏冬もあきめなきみせ
すつほんよおもひしるらん汁となりて今吸(は)るるは吸(ひ)ついた科
栗洞の作品から五首を引く。一首目の題は「紙店」。二句の「や」は詠嘆と反語だろう。三句以下は「八百万紙集まりて売れる常店」、「紙」に「神」を掛ける。「常店」(じょうみせ)は一定の場所で常にきまった商品を売る店をいう。二首目の題は「草履店」。漢字で補うと〈華やかな鼻緒に足も立ち止まりよう捌けるもの草履屋の店〉となる。「良う」は「良く」のウ音便、「捌ける」に「履ける」を掛けた。「ぞふり」は「ざうり」である。ハ音ないし母音要素のア音が響く。三首目の題は「あまさけ売」。初二句は「けちな盃ではなく茶碗で試飲を勧めます」か。三句以下は「ここまで御座れ甘酒甘酒」、「御座れ」は「来い」の尊敬語。甘酒売りの売り言葉、口上であろう。四首目の題は「果物店」。結句は「空き目なき店」で「空き」に「秋」を掛けた。「空き目」は賭け事で誰も賭け物を張らないところをいう。売り物は秋の金柑・桃・梨・葡萄・柿に冬の蜜柑で四句は「春夏冬も~」と季節を示す。五首目の題は「すつほん汁や」。「鼈汁」は鼈の肉を入れた汁をいう。「鼈よ、身に沁みて悟っただろう。鼈汁になって吸われているが、これも人に吸い付いた昔の科だよ」。一首は同音類音系統で彩られていく。
すなとりのわさはしらねと今もなをあみにかかりてうるかつをふし
御馴染(み)のはしとなりぬる商内や御やうしあらはたのみ上(け)ます
なさけをは商ふさとのちかけれはここにもおいろうれる店つき
次に負米の作品から三首を引く。一首目の題は「鰹節店」。漢字を多用すると〈漁りの業は知らねど今もなほ網に掛かりて売る鰹節〉となる。初二句は「鰹の漁法は知らないが」。下句は「今も量り売りの際に網を使う」意に解した。二首目の題は「箸楊枝店」。漢字で補うと〈御馴染みの端となりぬる商いや御用事あらば頼み上げます〉。上句は馴染みの端緒となった商いだろう。「端」に「箸」を掛けた。下句は「用事」に「楊枝」を掛けた。三首目の題は「紅粉屋」。順慶町は現在の大阪市中央区南船場をいい、往時は新町遊郭の東口筋にあった。上句の「情けをば商ふ里の近ければ」の由縁である。下句は「ここにも御色を売れる店付き」。「御色」は「紅」をいう女性語である。順慶町通の夜店の賑わいは相当なものだったらしい。
|
| 第167回 狂歌千種園 春 |
荘厳もなきあき寺の春雨に瓔珞めかす軒の玉水 茂喬
『狂歌千種園 春』の撰者は得閑斎繁雅、文化十二(一八一五)年の刊である。掲出歌の題は「空寺春雨」。初句「荘厳」(しょうごん)は仏像や仏堂を天蓋や幢幡(どうばん)で厳かに飾ること、またその物をいう。四句「瓔珞」(ようらく)は仏像を荘厳する飾り具また寺院内の宝華状の荘厳をいう。いずれも結句「軒の玉水」の見立て、忘れられた無住寺の姿を詠った。
誰ひとりせわやかねとも春雨のふる度ことにもえ出(つ)る草
松かえにかかるもあれはささかにのくもゐに糸を出すもある凧
主の子のもて出る紙鳶の尾についた丁稚も心空にのほしつ
あやふくも風に高ふる奴几巾主とする糸のきれぬ間は
一首目の作者は芳水、題は「春草」。初二句「誰一人世話焼かねども」は人のことだが、そうした思惑が小さく見えるところに「私」は立っている。大自然の摂理は三句以下「春雨の降るたびごとに萌え出(つ)る草」なのだ。二首目の作者は文之、題は「几巾」(たこ)。漢字で補うと〈松が枝に掛かるもあれば細蟹の蜘蛛の雲居に糸を出すもある凧〉となる。「蜘蛛の」は枕詞で蜘蛛と同音の雲に掛かる。雲居も雲の意である。三句以下は空高く舞い上がった凧が雲から糸を出す図となる。三首目の作者は鵞習、題は「几巾」。丁稚と凧を持った主人の子の取り合わせである。当然、年齢は近い。初句「主」は「ぬし」、二句は「持て出る紙鳶の」と七音で読んだ。結句の「上した」は「上す」の連用形に助動詞の「た」の終止形、口語である。心を空に上げ、また上気しているのである。四首目の作者は友風、題は「几巾」。上句「危ふくも風に高ぶる奴几巾」(「高ぶる」は「昂ぶる」とも書く)は奴凧の絵柄にふさわしい上がりようである。現実の奴のイメージも重なっているだろう。但し下句の限定付きである。
花のさく菜にひかれてや青物のみせに遊へる蝶も一二羽
さくらかなさくらかなとて日々に句をはくに箒となる筆のさき
数珠になるさくら木なれと花さきて風の手さきにもむはゆるせよ
白くもの雪のといふて歌よみかあたらさくらをうそつきにする
一首目の作者は以文、題は「蝶」。初二句は菜の花に惹かれて、助詞「や」は疑問の意。三句「青物」は野菜の総称である。結句「蝶」の助数詞「羽」は野菜の「把」に合わせたのだろう。二首目の作者は鵞習、題は「桜」。初二句の「桜哉桜哉」のリフレインを経て四句の「吐く」が「掃く」に転換、加えて筆を動かすことが実は紙の上を掃いている、推敲の跡なのだ。三首目の作者は以文、題は「桜」。初二句の「数珠になる桜木」と三句以下の「花咲きて風の手先に揉む」が「なれど」で接続して「許せよ」となる。そこに「拝む」と「揉む」また「人の手」と「風の手」の違いが鮮明になる仕組みである。四首目の作者は可笑、題は「桜」。西行の〈花見にとむれつつ人のくるのみぞあたら桜のとがにはありける〉(『山家集』八七)に出発したバリエーションへの新たな参加者である。「白雲の雪の」と嘘を重ねるというのだ。
|
| 第168回 狂歌千種園 春(2) |
さくら狩(り)労れしくれも足もとのあかいうちには何といなれう 鵞習
掲出歌の題は「夕花」。初句「桜狩り」には「花見」で収まらないエネルギーが秘められているのだろうか。二句は「疲れし暮れも」で「労」は「疲」の宛字と解した。結句「いなれう」は「往ぬ」の未然形「往な」に助動詞「れる」の未然形「れ」、これに助動詞「よう」が付いた。現代仮名遣いなら「往なりょう」、「何と」で「どうして帰れよう」の意となる。
岫を出(て)し雲と見えつる花なれは無心まうして折(つ)た一えた
弁当をさけつつゆけは紐とくもひらきをはるもある桜花
松か枝の隙に交りし桜花仲間いりして散るな必(す)
吹(く)とても花はさそはぬ春風のそよきに動く枝の短冊
一首目の作者は綿竹、題は「折花」。初句「岫」は「くき」と読む。山の峰の意である。岫から雲が出たように、同音の「茎」から花が出た。下句は「無心申して折った一枝」。承諾なしの一枝だろう。不思議だが、こうした花で咎められたケースと出合わない。二首目の作者は季隆、題は「花有遅速」。一首は「弁当を提げつつゆけば紐解くも開き終はりもある」これに「弁当箱」の手もあった。その可能性を最後の最後まで引っ張って結句で「桜花」と軌道修正をしてみせた。人を食ったようなところが味だろう。三首目の作者は砂香、題は「花交松」。歌意は「常緑樹の松の枝の隅から落葉樹の桜の枝が入り込んでいる。桜が松の仲間入りをしたのだろうか。それならば散るなよ、必ず」。結句が力強い。四首目の作者は季隆、題は「春風」。歌意は「吹くといっても落花を誘うほどでない春風の、それでもそよそよと音がして枝に括り付けた短冊も動いている」。花見客にとっては最高の見頃であるに違いない。
さく花はのう見物そよかきつはた一番二番三番目まて
句の上にすゑてよまれし杜若今も下にはおけぬ色なり
字をなして雁は帰りし春の日にのたくり廻る蚯蚓あはれや
けふ彌生つきぬる鐘もなこりをしいつ又春のこむとひひけは
一首目の作者は繁雅、題は「杜若」。二句切れ、三句は助詞の省略だろう。結句の「三番目」は能の五番立分類で第三番目に置かれて一日の演能の中心をなす曲をいい、「杜若」も三番目物である。これを花の杜若に重ねて賞賛した。二首目の作者は何虹、題は「杜若」。上句は在原業平の〈唐衣きつつなれにしつましあれはるばるきぬる旅をしぞ思ふ〉(『古今和歌集』四一〇)をいう。句頭の仮名を拾うと「かきつばた」になる折り句、下句はこれを受けて「色」に転じた。古来、紫は高貴な色だった。三首目の作者は茂喬、題は「春動物」。雁の並んで飛ぶさまを雁の文字また雁字ともいう。これに対して四句「のたくり廻る」だけで字にならない蚯蚓を持ち出したのが手柄である。すでに啓蟄の候なのだ。四首目の作者は山鳥、題は「三月尽」。二句は上から弥生「尽きぬる(鐘も)」、下へは「撞きぬる鐘も」と双方向に働く。三句は「名残惜し」。結句の「こむ」は春の「来む」に鐘の「コンと響けば」の両意となる。
|
| 第169回 狂歌千種園 夏 |
筑摩祭いたたく鍋の数もなくひとりの男まもらせ給へ 素人
掲出歌の題は「筑摩祭」。筑摩祭は滋賀県米原市の筑摩神社で行われる祭礼である。古来、女性が交渉をもった男性の数だけ鍋をかぶって神幸に従ったという。日本三奇祭の一つとされる。作中主体は、これから嫁ごうとする「私」、もしくは娘の親である「私」だろう。
すんすりと袷は着れとおのつから汗をもよほす夏の首すち
脱(ぎ)かへし布子の事も忘れてはさかす袷の袖たはこいれ
五六日つけし四月の当座帳も花のなこりを思ふ墨の香
まつかうにかさす刀のもろは草はらへは露の玉そちりぬる
一首目の作者は先賀、題は「首夏」。初句「すんずり」は気分の清々するさまを表わす語である。衣替えで袷を着たが、それでも自然と汗の滲んでくる夏の首筋であるという。結句に実感を伴うが、同時に題を詠み込んでいるところが巧い。二首目の作者は鬮丸、題は「更衣」。袷の袖に入れたはずの煙草入れがない。実は布子(木綿の綿入れ)から入れ替えるのを忘れていたのだった。煙草入れは刻みタバコを入れる携帯用の袋をいう。キセル筒と対になったものが多く、懐中用と腰さげ用があるが、これは前者を詠っている。三首目の作者は朶丸、題は「初夏」。三句の「当座帳」は商家で仕分けをせず売り上げ順で仮に記録しておく帳簿をいう。四句「花の名残」は散った桜花を惜しむ気持をいうが、上句の内容も花見客の数と無関係ではない。それが結句の「墨の香」と解した。四首目の作者は鵞習、題は「葵」。漢字を多用すると〈真つ向にかざす刀の両葉草払へば露の玉と散りぬる〉。三句「両葉草」は「双葉葵」の別名かつ「両葉」に同音の「諸刃」を掛けている。初二句は見立てだが下句が爽やかである。
棒よりも薮から出(で)し笋のはしりの直にはひつくりそする
薮力出すか十七はちくてふ竹のこも土持(ち)上(げ)にけり
くたくたとくたまかうより粽まけ此(の)ささの香は下戸も悦ふ
早乙女か歌聞(き)とれて笠のうちのそけは泥に半けしやう也
一首目の作者は半月、題は「笋」。成句「薮から棒」よりも驚くのは季節に先駆けて市場に並ぶ竹の子、その値段の高いことである。同じ薮から出る棒を話の枕にしたところが巧みであった。二首目の作者は以文、題は「笋」。二句は「(薮力)出すか」で句割れとなる。以下は「十七八九てふ竹の子も土持ち上げにけり」で、「八九」に「破竹」を掛けた。十代後半が子供なのか、些かのためらいもある「竹のこも」ではある。三首目の作者は八髯、題は「粽(ちまき)」。上句は「くだくだとくだ巻かうより粽巻け」。「巻かう」の「う」は推量の助動詞「む」の音変化である。下句の「笹」は「酒」をいう女房詞でもある。「くだ」(三回)、「巻か(う)」「(ち)まき」「まけ」等が響く。四首目の作者は青葭、題は「早苗」。初二句は「早乙女が歌聞きとれで」、隣から田植えをしながら歌う仕事歌が聞こえてこない。不審に思って顔を覗き込んだら、跳ね返ったのか、泥で半化粧(半夏生)だった。気の毒なことこの上ない早乙女なのだ。
|
| 第170回 狂歌千種園 夏(2) |
ふりつつくさつきの雨に真菰さへあたまにかふる池の水かさ 峨山
掲出歌の題は「五月雨」。三句「真菰」はイネ科の多年草で水辺に生える。高さは約二メートルというから大変である。分類すれば自然詠だが三四句で頭を掠めるのは「真菰」が「真菰蓆」の略であり、そこから薦で包んだ酒樽や薦を被った乞食を連想することである。いわば被られる側が被る側に回った「降り続く五月の雨」や「池の水嵩」の凄さなのである。
一合のよひの寝酒のさめやらぬうちにとくりとあくる夏の夜
僧てあろさうてはないとあらそひぬ月下の門をたたく水鶏に
広沢の池の堤もなつくさのしけりしけりて道を狭むる
うつくしいお顔には似す夏の夜の月は気早に入らせられます
一首目の作者は和夕、題は「夏夜」。一合の酒の酔いだから、そんなに深くない。その酔いが醒めるよりも夜が早く明けるという。二句「酔ひ」に「宵」を掛けた。四五句は「徳利を空ける」と「疾く(り)と明ける」で口合いとした。二首目の作者は和珹、題は「水鶏」。連想されるのは「僧推月下門」、「推敲」の語原である。唐の詩人が「推」と「敲」の選択に悩む話である。こちらは初句「僧」に同音の二句「然う」から推して、敲く主体が問題にされており、結果は「水鶏敲月下門」で終わる。三首目の作者は貞旨、題は「塘夏草」。二句以下は「池の堤も夏草の茂り茂りて道を狭める」。これと初句が対応するスタイル、つまり「広沢の(略)道を狭める」となるのである。四首目の作者は繁雅、題は「夏月」。深窓の佳人といった趣きだが、やはり夏の夜が短いからだろう。結句は「いらせられる」(「入る」の尊敬語)の連用形に、助動詞「ます」(謙譲語。動作の及ぶ「月」に対する敬意を表わす)である。
ふる雨の足には怪我も有(る)まいに石橋たたいてわたる夕立
身のもゆるあつさを消せと心太水鉄炮のやうにつき出す
燈篭にする気てかふた西瓜には棚か落(ち)ても怪我はこさらぬ
音頭の声なかりせは祇園会の山ほこいかてゑいやらやらまし
一首目の作者は玉光、題は「夕立」。成句「石橋を叩いて渡る」のは人、八方無碍の雨足は二三句「怪我も有るまい」なのだ。しかしこれに逆接の助詞「に」が加わると印象が少し変化する。あたかも成句と雨足そして人の足が渾然と重なって見えるのだ。二首目の作者は花夕、題は「心太」。心太突きを水鉄炮に喩えたところが見所である。心太突きは箱筒の一端に格子状の網目を取り付け、他の一端から心太を入れて棒で押し、細くして突き出す器具をいう。三首目の作者は季隆、題は「西瓜」。二句「かふた」は「こぉた(買うた)」(『大阪ことば事典』)となる。四句は西瓜が熟し過ぎて内部に空洞ができることをいう。結句「怪我は御座らぬ」の由縁である。四首目の作者は毛人、題は「夏声」。意味は〈音頭の声なかりせは祇園会の山鉾如何で遣らまし〉。音頭の声がなかったとしたら祇園会の山鉾をどうして動かすことができるだろうか。この結句に音頭の声が入って「えいやらや(らまし)」で動き出すのである。
|
| 第171回 狂歌千種園 秋 |
はや西の海へさらりと入る月を惜(し)むににくきこつかこの声 季隆
掲出歌の題は「惜月」。下句は「惜しむに憎きこつかこの声」となる。「こつかこ」は鶏の鳴き声である。山鳥にも〈厄はらひのようべのさらりこつかこをけさ立つはるの鳥の音に聞く〉(『狂歌千種園 春』)があった。『日本国語大辞典』には「こけこっこう」の外に方言として「こっかこおこお」等を載せている。近世の上方では本歌のように聞いたのだろう。
押(し)つめて残る晴天十日めのすまひは跡のない土俵際
なせ行事渋團をはもたぬそい貧乏神の名あるすまふに
十分の実入(り)と見えて米蔵の鍵の手なりに光るいなつま
見ねは気かとうやらすまぬ月の影心にかかる雲はなけれと
一首目の作者は滝志、題は「相撲」。上句の「晴天十日」(晴れた日十日間の意)は大相撲興行の日数。一七七八年に江戸で興行されたのが最初で、それ以前は晴天八日であった。偶数日だから相星で終わる力士もいたことになる。二首目の作者は輪田丸、題は「相撲」。上句は「何故行事渋団扇をば持たぬぞい」。「渋団扇」は貧乏神が持つとされた。「ぞい」は「ぞ」よりも柔らかい働きかけである。下句の「貧乏神」は十両筆頭のこと、幕内力士との取り組みが多いが給金は十両で損をした。三首目の作者は交山、題は「稲妻」。稲妻は稲の夫の意、稲の結実期に多く起こるので初二句「十分の実入り」となった。また蔵の鍵を稲妻という。形が似ているからで、米蔵が登場した二つ目の由縁である。四首目の作者は砂長、題は「未出月」。上句の「見ねば気がどうやら済まぬ月」、これに下句「心にかかる雲はなけれど」が反応して「澄まぬ月」となる。日没と月の出は必然だが、この気迫は十五夜に違いない。
川童の皿の水にもやとるらむてつへいにすむ月の光りは
結構な月夜とは見め刈(り)しまふ山田に腰をのす時にこそ
夜道かく駕にはいとふ雲介か杖した時に見る月の影
つむき出すいととの声は秋のよの長うなる程細りてそゆく
一首目の作者は文之、題は「亭午月」。初句「川童」は「河童」である。四句は「天辺に澄む」、「てっぺい」は「てへん」の音変化である。題の「亭午」は南中をいい、月だと真夜中ということになる。二首目の作者は繁雅、題は「田夫見月」。三句は「刈り仕舞ふ」だろう。四五句「腰を伸す」は腰を伸ばして真っ直ぐにすることをいう。最後は係り助詞の「こそ」、倒置法で二句の已然形「見め」で結びとなる。田仕事を終えたあとの月は格別だったろう。三首目の作者は歌陸、題は「雲助見月」。上句は「夜道舁く駕籠には厭ふ雲介が」。駕籠を舁くなら昼間だろう。夜の明かりは月だけ、しかも満ち欠けがある。下句には仕事を終えたあとの満足感も漂う。四首目の作者は芳水、題は「虫」。二句の「いとど」はカマドウマの異名である。初句「紡ぎ出す」は「いと(ど)」と同音の「糸」の縁、同じ配慮から三句の「夜」は平仮名で印象を弱くした。糸は長くなるほど声は細くなり、やがて夜が白むのである。
|
| 第172回 狂歌千種園 秋(2) |
野末なる石の地蔵にすかりつつ父恋しとそ鳴(く)むしの声 久楽
掲出歌の題は「虫」。二句「石の地蔵」は子供を守ると信じられ路傍などに立てられた。四句「父恋し」以下は蓑虫、『枕草紙』に「蓑虫、いとあはれなり。〈略〉、逃げていにけるも知らず、風の音聞き知りて、八月ばかりになれば『ちちよ、ちちよ』とはかなげに鳴く」(五十段「虫は」)とある。したがって三句「縋りつつ」は地蔵の体にぶら下がる蓑虫となる。
人は目をさますふし戸のあけかたに啼(き)くたひれて細る虫の音
くらけれと手水せんとて河水に向ふの岸も見せぬ朝霧
宮宮に組なす垣の糸萩のむすひとめとやとまるとんはう
あふれ蚊もひやつく風ににけうせてふつともいはぬ秋の夕暮
一首目の作者は鵝習、題は「暁虫」。上句は「人は目を覚ます臥所の明け方に」だろう。これと別に三四句「節戸の開け方に」を用意した。節戸を開ける頃、また開けた方向である。明け方、外では細っていく虫の音なのだ。二首目の作者は砂長、題は「朝霧深」。二句「手水」(ちょうず)は手を洗うのか、おそらく小便だろう。初句は「くらければ」の擬装、四句「向ふ」は名詞として「岸」に掛かる。一方で二句を受けた動詞「対ふ」の意でもある。三首目の作者は貞旨、題は「蜻蛉」。歌意は「皇族方が庭に編む垣根、今は糸のように枝の細い糸萩が植わっている、その名にある糸の結び止めのように蜻蛉が糸萩に止まっていることだよ」か。類音また「と」音の反復が響く。四首目の作者は遂良、題は「秋夕」。初句「溢れ蚊」は最盛期を過ぎて元気のなくなった蚊をいう。二句「冷やつく」は「ひんやりする」。四句は「逃げ失せて」。四句の「ふっとも」は二句の「風」の縁で口をすぼめて息を吹くさまだろう。
世の中の人か十分寝あまれはくらふ獏もや夢に秋の夜
火と燃(え)し柘榴もあれはけさんとて結ひし印の水梨もあり
さまさまになりくたものは栗のみのふたこもあれは妻なしもあり
さやかには目に見えすしてきた秋か野山に錦かさるいにさま
一首目の作者は継風、題は「秋夜」。四句の「獏」は辞書によると人の悪夢を食うという想像上の動物である。秋が来て世人が三句「寝余れば」食い飽きた獏も夢を見る秋の夜だというのだが、このように夢一般を食う獏も活躍中なのだ。二首目の作者は星子、題は「果非一」。柘榴の果実は球形で紫紅色に熟すと裂けて赤い種子が現れる。これが初句「火と燃えし」なのだろう。これに対して水梨を出すための工夫が三四句「消さんとて結びし印の」であった。三首目の作者は砂長、題は「果非一」。二句「生り果物」は果実また果樹をいう。三四句は「栗の実の双子」(普通は毬の中は三つ子)、結句は「妻無し」(「妻梨」に掛けた)で「果非一」も一様でない。四首目の作者は半月、題は「暮秋」。上句は『古今和歌集』の〈秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる〉(一六九〉をいう。三句以下は「来た秋が野山に錦飾る往に様」となる。立ち去ろうとするとき「故郷へ錦を飾る」趣きとなった。
|
| 第173回 狂歌千種園 冬 |
いくたひか我をはたしにしくれ空草履はさのみ土ふますにて 力丸
掲出歌の題は「時雨」。上句は「幾たびか我を裸足にしく(さった)れ空」、ニュアンスたが「為腐った時雨空」となる。下句は「その代わり草履は土踏まずとまではいかないが、きれいなままだ」か。裸足は合理的かつ経済的だったろう。「雨」の題で得閑斎繁雅には〈はらはらとあしとき雨は飛脚をもはたしになして走らせにけり〉(『狂歌千種園 雑』)がある。
はるるとも空定めなき時雨にはさし出(づ)る月もかさをはなさし
雲のあしと雨のあしとかかたみにそ走りこくらをするしくれ空
諺によるか老(い)てはこからしの風にしたかふ庭の木々の葉
風の子の草履かくしやしたりけむ落はの中に尋ね出さぬは
一首目の作者は眠過、題は「時雨」。歌意は「たとえ晴れても定めのないのは空も地上と同じことである。笠を差して雲間から姿を現したお月さまも、その笠を手放すことはないだろう」か。月の「暈」を「笠」として読んでみた。二首目の作者は知州、題は「時雨」。初句「雲の足」(雲の動くさま)と二句「雨の足」(雨足。雨の通り過ぎていく様子)で対句とした。三句「互にぞ」で代わる代わる、四句「走りこくら」(「こくら」は接尾語、走り競べをいう)となる。三首目の作者は名丸、題は「落葉随風」。初句のいう「諺」は「老いては子に従え」で、二句から四句がその口合いになっている。結句の「庭の木々の葉」は捨てられるか、燃やされるか、厳しい「木枯らし」なのだ。四首目の作者は素来、題は「落葉埋物」。初句「風の子」とは子供である。二句「草履隠し」は幼児の遊戯、草履を隠して鬼の役に探させるもの。三句「したりけむ」は推量である。下句は「落ち葉の中を探しても見つけ出せないのは」。
しろ物とさくらもしるか植木屋に冬もちよつほり花を餝つた
けふそ茶をたて役者とや炉の口をひらく帛紗もよいさはき方
さしあたることをすてても老(い)の身はとかくこたつか去(り)かたき用
こたつなる炭はもゆれとをち姥はむねの火をけす後世の相談
一首目の作者は茂喬、題は「植木屋帰花」。初句「代物」には①商品②話の材料の両意があるが、ここは後者だろう。春に咲く桜が冬に咲いた、帰り花なのだ。下句は「冬もちょっぽり花を飾った」。二首目の作者は麁馬、題は「開爐」(茶家で陰暦十月一日または同月の亥の日に風炉をしまい炉を開くこと)。二句は上から茶を「点て(役者とや)」、下へ「立役者とや」(茶会の主人の比喩、「とや」は疑問)となる。四句「帛紗」は茶道具を拭い、また扱う際に用いる絹布をいう。三首目の作者は繁雅、題は「炉火」。火燵に収まりのいいのは老人である。四句「とかくこたつ」を母音要素で並べると「おあうおあう」とリフレイン、また初句「あたる」も火燵の縁語であった。四首目の作者は斗油、題は「爐辺閑談」。三句の「をち」は「おぢ(祖父)」((「おほぢ(祖父)」の音変化)、「姥(うば)」は祖母をいう。結句「後世(ごせ)」は四句からして、どちらかが一人になったときのこと、また「家」のことなどであろう。
|
| 第174回 狂歌千種園 冬(2) |
畑に有(り)し時よりもなほつむ綿にふけよと願ふ番船の風 砂長
掲出歌の題は「番船」。番船は菱垣廻船と樽廻船が年中行事として行なった新綿番船と新酒番船の略称。上方から江戸までの所用日数を競った。普通は二週間前後だが番船は三、四日で到着、新綿番船の記録には五十時間もあった。一番船には賞金と翌年の積荷に際しての特権が与えられ、その順番を当てる博打も流行した。三句「積む」に「摘む」を掛けた。
劣らしと争ふ中によい風のふく一はいの番ふねの風
くりわくる積りはこれを中いれにあれを糸にと嚊のはらわた
吹(き)たてて立木を枯らす嵐には梢に蜘の家ものこらす
樵(り)そへて竈にくへる枯木まて炭やく山のにきはひとなる
一首目の作者は季隆、題は「番船」(「ばんぶね」または「ばんせん」)。新酒番船は西宮から品川の間を競った。賞金と特権は新綿番船と同様である。四句「一ぱい」は副詞の「一杯」で風、「一艘」で船、「一盃」で積んでいる酒ともなる。二首目の作者は遂良、題は「綿」。初句「繰り分くる」は綿繰り車で木綿の種を取り去る作業、その使途を練っているのだ。三句「中入れ」は衣服や帯用の綿、四句「糸」は糸車にかける綿、結句は「かかの腸」で腸の「わた」に綿を掛けた。三首目の作者は繁雅、題は「木枯」。木枯らしは木を吹き枯らすものの意、初二句の通りである。下句「梢に蜘蛛の巣も残らず」ではなく「梢に蜘蛛の家も残らず」が凄い。そのための布石が三句の「嵐」だった。四首目の作者は和夕、題は「炭竈」。初句は「樵(こ)り添へて」、前からあった薪に加えて枯木を補充したのである。枯木でも炭を焼く燃料として赤赤と美しい。つまらないものでも無いよりまし、成句「枯木も山の賑わい」なのだ。
こもく場に捨(て)しさうりの長刀も刃をつけたかときらめける霜
乞食の息は見えけり小筵に霜置(き)そふるうたたねの橋
けふは火もおこさぬふいこ祭りとて横にころりと休む相槌
降(つ)てとふあられは魚の目の玉に似てもくはれぬ物とこそしれ
一首目の作者は鵝習、題は「霜」。初句「芥場」(ごもくば)はごみ捨て場をいう。二三句「草履の長刀」(長刀草履)は使い古して形の崩れた藁草履をいう。この長刀からの見立てが下句の「刃を付けたかと煌めける霜」なのだ。二首目の作者は五頂、題は「橋上霜」。初句は「こつじきの」と五音で読んだ。二句は吐く息が白く見えるのだろう。三句「小筵」(こむしろ)は小さな茣蓙、それに「霜置き添ふるうたた寝の橋」を横目に通り過ぎるところなのだ。三首目の作者も五頂、題は「鞴祭(ふいごまつり)」。鞴祭りは陰暦十一月八日に鍛冶屋や鋳物師など日頃ふいごを用いる家で稲荷神または金屋子神を祭り、職人は仕事を休んだ。結句の「相槌」は二人の職人が交互に打ち合わす、その槌をいっている。四首目の作者は歌鼠、題は「霰似玉」。初句は「降りて」と「降って」の二者択一だが後者を採った。魚の目玉は食えるが霰は食えない、しかも係り結びで強調されている。食えても食わぬ人の多いのが魚の目玉であろう。
|
| 第175回 狂歌千種園 冬(3) |
くすり喰(ひ)と身をやなししの皮足袋に足のうらまてあたたまりぬる 素人
掲出歌の題は「足袋」。二句の「をや」は感動と詠嘆だろう。「なしし」は「為す」の連用形に「き」の連体形、この「しし」に「肉」(しし。食用の肉)を掛けた。下句は「足の裏まで暖まりぬる」。『日本国語大辞典』で「革足袋屋」を引くと「江戸時代、革足袋を売る者をいう。多くは行商で、荷かつぎに荷を持たせ、自分は先に立って呼び歩いた」とある。
こはたたきおこされたより驚きぬ音せてつみし雪の朝戸出
跡つけぬうちにとそみる雪の朝火燵にさへも足いれすして
雪よ雪ようつみな果(て)そ訪(ひ)きつる人のなさけの深き足あと
空をのみ見つつあほうか男ほとまてともいまに来ぬ雪女
一首目の作者は貞旨、題は「雪」。初句「此は」は「これはまあ」の意、疑問と感動の気持であろう。以下、二句「叩き/起こされたより」と句跨りが効果を発揮する。下句は「音せで積みし雪の朝戸出」となる。二首目の作者は芳水、題は「雪」。上句「跡付けぬ内にとぞ見る」は①他人が「跡付けぬ内」であるが、②「私」も「跡付けぬ内にとぞ見る雪の朝」である。そのための下句「炬燵にさへも足入れずして」だったはずだ。三首目の作者は律丸、題は「雪」。二句は「埋みな果てそ」、しかし「埋み」は「埋む」(マ行四段)の連用形だから「な埋み果てそ」が自然と思われる。破格の用法だが三句以下「訪ひ来つる人の情けの深き足跡」を「埋めてしまうな」という歌の新味と無縁ではない。四首目の作者は芳水、題は「待雪」。上句は「空をのみ見つつ阿呆が男ほど」と読んだ。助詞「が」は「の」の意味だが親愛と軽侮の念が加わっている。下句は「待てども今に来ぬ雪女」、若くて美しい雪女の虜になりたいのである。
辻芝居ならてふれるは町なみに新うす雪のはしまりはしまり
池水はこほりの名にそふりきぬる雪気に風も添ふの上下
国の名も丹波の小雪里々をあまた郡につきてふれふれ
ころふなといふ思ひ子の雪こかし大きうなるを親もこそまて
一首目の作者は亀住、題は「初雪」。四句「新うす雪」は浄瑠璃の『新薄雪物語』通称「新薄雪」をいう。初二句は「辻芝居ならで降れるは」、結句の「始まり始まり」は初雪を喜ぶ気分の高まりであろう。二首目の作者は砂長、題は「郡雪」。二句は「郡」に初句の縁語「氷」を掛けた。結句は「添上郡」で『国史大辞典』に大和国東北部の郡とある。同様に「添下郡」は大和国の北部中央を占めた郡とある。広大で初句の「池水」には猿沢池も含まれる。三首目の作者は山鳥、題は「郡雪」。上句の「丹波国」は山陰道の一国。現在の京都府中部と兵庫県東北部に跨っている。四句「数多郡」(小雪をたくさん、多くの郡)に「天田郡」を掛けた。結句は「付きて降れ降れ」となる。四首目の作者は文之、題は「雪中童」。二句「思ひ子」は可愛く思う子、三句「雪転し」は雪転がし、転がして大きな塊にすること、またその塊をいう。四句「大きう~」(「大きく」の変化、「大きゅう」と発音)に子供の成長を重ねた。
|
| 第176回 狂歌千種園 冬(4) |
渡辺はいさ伯母とよふ雪の日はうれしけに手もくれる飼(ひ)犬 子方
掲出歌の題は「雪中獣」。初句「渡辺」は渡辺綱をいう。伯母に化けた鬼が綱の館へ行き、切り取られた片腕を奪い返すという話に拠った。三句の「雪」は鬼が化けた美女の肌ないし鬼の棲む山の縁を思わせる。初句「渡辺は」(鬼)、二句「いざ伯母」(綱)だろう。下句「嬉しげに手もくれる綱」の流れを「飼(ひ)犬」で収めて斬新、この手では初出と思われる。
にきりては児の打(ち)あふ雪つふていたくつめたい顔つきもせす
こしの山の雪の深さに出(で)しよとみるやしるしのさを鹿の跡
寒念仏胴のすわつた男てもふるひ声にてまはる七墓
梓弓つるを目当(て)に鷹匠かこふしも切(つ)てはなすはやふさ
一首目の作者は多加羅、題は「雪中童」。今の雪合戦は「雪打ち」(『日本国語大辞典』)といったらしい。二句六音、三句「雪礫」は雪の玉、四句「いたく」は「痛く」に副詞の「いたく」を重ねた。二首目の作者は鵝習、題は「雪中獣」。「越の山の雪の深さに出でしよと見るや/標の小牡鹿の跡」。「越」(北陸道の古称)に鹿の「腰」を掛けた。四句は句割れで反語。結句「標の小牡(鹿)」が「標の竿」(北国で積雪の深さを測るための竿)となった。三首目の作者は輪田丸、題は「寒念仏」。ここは僧侶ならぬ俗人の寒念仏(寒夜を選んで鉦を打ち和讚や念仏を唱えること)、しかも季節外れの七墓巡りも兼ねるから二三句「胴の据わった男」でも寒さで声が震えるのである。四首目の作者は路竹、題は「鷹狩」。二句は「弦」ならぬ「鶴」である。四句の「拳」は鷹を据える手、「切って」は「弦」の縁からだろう。結句は「放す隼」、隼も鷹狩りに用いた。将軍が鷹で捕獲した鶴は宮中に献上されたが、これを御拳(おこぶし)の鶴という。
ふる雪は鵝毛にも似て放したる鷹に小鳥も飛(び)て散乱
つかみつつあたためてゐる鷹の足に小鳥は肝をひやす冬の夜
せかむ子をたますみかんもくくりては手なしの猿にしたるお袋
つくもちの鏡とるにも輪にいれてかたのことくにおしつめし年
一首目の作者は継風、題は「鷹狩」。二句「鵝毛」は鵝鳥の羽毛で白いものや極めて軽いものの喩えに用いられた。ここなら雪である。下句「小鳥も飛びて散乱」は獲物を捉えた瞬間だろう。初二句と対応する光景である。二首目の作者は芳水、題は「煖鳥(ぬくめどり)」。「温め鳥」は冬の寒い夜、鷹が小鳥を捕らえて掴み、足を温めることをいう。その鳥の心情を下句で描いた。但し翌朝これを放してやり、その日は小鳥の飛び去った方向へは行かないといわれる。三首目の作者は久楽、題は「蜜柑」。四句は蜜柑猿をいい、袋の中央部を上下に括って丸くした。また機嫌の悪い子供のお守りを猿の守という。蜜柑猿は気を紛らせるのに有効な遊びだったのだろう。結句「お袋」(母)に蜜柑の「袋」を重ねた。四首目の作者は季隆、題は「餅搗」。鏡餅を作る専用の輪の型があったらしい。そのことに驚かされた。下句「型の如くに押し詰めし」で「餅」から「年」に変えたのが巧い。ズーム・アウトして歳末恒例の風景である。
|
| 第177回 狂歌千種園 恋 |
わたなへのつなかりはせて君か手を妻か悋気の鬼にきられつ 貞旨
掲出歌の題は「依妬離恋」。子方の〈渡辺はいざ伯母とよぶ雪の日はうれしげに手もくれる飼ひ犬〉(『狂歌千種園 冬』)に感心したら、さっそく枕詞に使う歌人が現れた。評判になったのだろう。初二句「渡辺の繋がりもせで」で同音の「綱」も登場する。ところが腕を切ったのは悋気の鬼、切られたのは「君が手」(「私」との男女関係)という変型となった。
こつそりとおくりし文に御内しやうといはるるやうな返事せよ君
うちとけぬこころしれとや書(き)送る文も結ひしままに返すは
おもはすよ頭さへあからぬ恋やみに君かうなつくやうになろとは
契りてし事をいなとて白粉のしらしらしくも美しい顔
一首目の作者は弄花、題は「忍送書恋」。初二句は題のとおり内証で出した手紙をいう。期待している返事は三句「御内証」(御内室、御内儀)といわれるような、これは書中に添えたのだろう。求愛の結句「返事せよ君」であった。二首目の作者は惟一、題は「返書恋」。書中に初二句「打ち解けぬ心知れ」と書いたら受け取り拒否で返ってきたのである。望んだのは二人が「打ち解けること」その縁語の「結びしまま」だったのが踏んだり蹴ったりである。三首目の作者は歌鼠、題は「及病諾恋」。初句切れで感動と詠嘆を前面に出した。思わずよ。思いもしなかったことだ。二句九音で「頭さへ上がらぬ恋闇に君が肯くやうになろとは」。純情一路に負けたしっかり者の女性だろう。四首目の作者は素人、題は「争恋」。初二句は「あったこと」を「なかった」と言い張っているのである。三句「白粉(おしろい)」を枕詞と実写かつ類音効果とした技が冴える。なるほど憎らしいぐらいに結句「美しい君」なのだ。
親々にいひ出(た)さんも手にをはのわるさに悔む妹かはらみ句
何処て花さかすことやら音つれも絶(え)ての後はゆくへしら雲
めしもりに残りし心一はいも宿たつ時は何くはぬかほ
あきか来ていなした跡はあはれみの添ふ程ふかうなる今の妻
一首目の作者は童龍、題は「胎後悔恋」。初句「親々」は双方の親、三句以下は手順の悪さを「孕み句」(連歌俳諧などで前もって考えておいた句)の修辞に重ねた。「てにをは」には助詞のほかに話の辻褄の意がある。悔やむのはそのことなのだ。二首目の作者は言之、題は「絶不知恋」。初句は「どこで花」の五音、二句「咲かすことやら」また結句「行方しら雲」からも流れ者への心情は悪くない。男か女かは分からないが、この歌を明るく収めている。三首目の作者は友風、題は「旅路恋」。初句「飯盛り」は飯盛り女、給仕のほかに売春も行った。三句の「一杯」以下、飯の縁語で統一した。結句「何食はぬ顔」は自分には関係ないという顔つき、その「食はぬ」も同様である。四首目の作者は砂長、題は「後妻契深」。流れとしては「飽きが来て去なしたあとは哀れみの添ふほど深うなる前の妻」だが、そうはならない。失敗から学んだ経験が「今の妻」に注がれる。その意味では重ねて気の毒な前の妻なのだ。
|
| 第178回 狂歌千種園 雑 |
すは風のさきを払ふてお通りに片よりそする池の萍 交山
春夏秋冬恋に続く「狂歌千種園巻之六」、最終巻である。掲出歌の題は「萍」。浮き草は水面上に浮かんで生育する草の総称としておく。初句「すは」は突然の出来事に驚いて発する語、現代仮名遣いなら「すわ」である。見立てだが風の先払いをして両側に「片寄りぞする」というのである。根が水中に垂れて固定しないことからの現象だがよく捉えられている。
あしもはもそろへて雲にとふつるは仙人たちか例の乗物
時得ねは千里かくへき馬たにも奴か尻について行列
業平に似たる鼠の豆男築地の穴から夜ことかよへり
洪水にくつれし堤見てからはちひさき蟻のあなとられさる
一首目の作者は砂長、題は「鶴」。上句は「脚も羽も揃へて雲に飛ぶ鶴は」となる。了解済みを示す結句「例の」は珍しくない手法である。迷惑な話だが「鶴駕(かくが)」だろう。『日本国語大辞典』に「仙人の乗り物」とある。二首目の作者は芳水、題は「馬」。上句は「時得ねば千里駆くべき馬だにも」となる。一日に千里を走る優れた馬も好機に巡り会わなければ下句の運命を辿る。しかし塞翁が馬、逆に時を得顔の馬もいたに違いない。三首目の作者は羽曲、題は「鼠」。業平と鼠は直接しない。下句「築地の穴から夜ごと通へり」の豆男(色好みな男)を経て二句「似たる」が成立する。しかしそれ以前から見てきたような錯覚を生む戯画には驚くほかない。四首目の作者は鬮丸、題は「蟻」。成句「蟻の穴から堤も崩れる」の脚色である。堤の崩れたのは蟻の穴から、その穴と同音を含む結句「侮られざる」である。自分の腕で堤防の穴を塞いで決壊から守ったというオランダの少年の話が連想された。
虫篇に義を結ふてふありなれはそのふの桃に集(ま)りやする
うるはしき弁才天女に抱(か)れては琵琶も糸目や細くなるらん
双六のとう兼好かおしやるとも打(ち)なくさまんよるのつれつれ
足取(り)も静かな御代になそらへて能はしつとりをさまつた物
一首目の作者は交山、題は「蟻」。成句「桃園に義を結ぶ」を使った。蜀の劉備、関羽、張飛の三豪傑が桃園で義兄弟の契りを結んだという故事である。下句の集団行動の実体は義ではなく、食のための本能が列をなさしめるのであった。二首目の作者は繁樹、題は「琵琶」。弁財天女が抱える琵琶を擬人化しかも男性にしたら、これしかないという場面である。琵琶の弦を糸目と表現、これに嬉しさや愛らしさに微笑む意の「目を細くする」を重ねた。三首目の作者は朶丸、題は「双六」。上句は『方丈記』第百十一段の「囲碁・双六好みて明かし暮らす人は、四重・五逆にもまされる悪事とぞ思ふ」を指す。下句は「打ち慰まん夜の徒然」、なお二句「どう」に賽を入れて振る「筒」を掛けた。四首目の作者は鵝習、題は「能」。三句「擬へて」は下句「能はしっとり収まった物」をいう。能の「収まった」に対し二句「御代」は「治まった」、初二句「足取りも静かな」は能の基本である白足袋摺り足と重なろう。
|
| 第179回 狂歌千種園 雑(2) |
渡辺のつなかる縁に持(つ)てきた東寺参りの伯母の手みやけ 芳水
掲出歌の題は「土産」。貞旨が〈わたなへのつなかりはせて君か手を妻か悋気の鬼にきられつ〉(『狂歌千種園 恋』)とやったので、今度は「繋がる縁に」で新作を加えた。四句「東寺」は鬼が住む羅生門から近い。渡辺綱に切られた腕を取り返しに来るのが伯母に化けた鬼だが、ここは本当の伯母なのだろう、しかも念には念の入れ用で「手土産」の持参となった。
春ならて見る祇園会の宵山はかさる錦もあたひ千金
ひく牛の肩にかはりて御車をたてておくなる榻もよつ足
一はいにつめしははやる芝居とてひらくも膝をわりこ弁当
御佛のまへにともしし蝋燭は風にまかせてはすに流るる
一首目の作者は知州、題は「錦」。往時の祇園会は陰暦六月七日から十四日、宵山は六月六日と十三日である。山鉾を翌日の巡行に準じて本飾りにし、鉾の上で囃子を行なった。下句「飾る錦も値千金」なのだ。二首目の作者は艤舟、題は「車」。三句は「みくるまを」と読んだ。古代の牛車である。結句「榻」(しじ)は牛車から牛を外したときに車の轅の軛を支え、乗り降りに際しては踏み台とする台とした。これが牛と同じく四つ足だというのである。三首目の作者は和夕、題は「弁当」。初二句「一杯に詰めし」は劇場に弁当箱を重ねた。下句は「開くも膝を割り(ご弁当)」に「(開くも膝を)破子弁当」、弁当箱を開くために座った両膝の間を空けたのである。破子は折り箱のように檜の薄い白木で作った容器で弁当箱に用いた。四首目の作者は茂喬、題は「蝋燭」。下句は炎が「風に任せて斜に流るる」で「斜」に「蓮」を掛けた。蓮といえば蓮の台、極楽浄土に往生した者が座るという蓮の花の座である。
ちよほくさとしやへる女のつくうそも共に禿(け)たる唇の紅
かかめつつはく腰板もあて馴(れ)てはかまにしはは見せぬ老人
からき世の味をしりてやたうからしの鷹の爪にも火をともす色
売(り)こと葉かひ詞なる口論はゆききも門に市なしてきく
一首目の作者は貞旨、題は「紅」。初句は口先巧みに話すさまをいう。以下「女のつく嘘も共に禿げたる唇の紅」。「禿げる」の意から「露見した真っ赤な嘘」に「嘘をついた唇の色褪せた紅」を重ねた。二首目の作者は鵝習、題は「袴」。初二句「屈めつつ穿く腰板」の「腰板」は袴の後ろ腰に当てる板をいう。それも当て馴れて下句「袴に皺は見せぬ老人」となる。四句「皺を」でなく「皺は」に注目したい。三首目の作者は真辟、題は「番椒」(唐辛子)。初句「辛き」には、ここでいう生き辛さのほかに味覚に関わる意味もある。後者が黒子の役で一首は進行する。四句「鷹の爪」は唐辛子の品種で赤く熟し、辛みが強い。「爪」を出して成句「爪に火を点す」を導き、貧苦を詠った。四首目の作者は歌鼠、題は「口論」。下句の「往き来」は往来の人、「門に市なして」は成句「門前市を成す」を連想させる。群がり集まった人が聞くのは上句の「売り言葉買ひ言葉」である。市場の縁語「売り買ひ」を重ねた。
|
| 第180回 狂歌千種園 雑(3) |
唐詩選素よみの声の聞ゆれと誰とも主人相知らぬ家 茂喬
掲出歌の題は「素読誰家」。「すよみ」乃至「そどく」は漢文訓読を繰り返すことで「読書百遍意自ら通ず」という学習法である。下句は知るにも表札が掛かっていないのだ。士農工商の時代、名字を持つ人は少数派だった。同題で輪田丸が〈主は誰とよめぬけれとも素読をはさせぬる家の奥床しさよ〉と詠うのも表札を、表札がないために読めないのであった。
足とめて拝む計りか旅人の手を落書(き)にのこす堂宮
いなりへもまうてきつねのくわん東兵衛筆をとりゐにとんた落書(き)
すけましよといふを手妻に牽頭小鉢の酒を早花にした
くはせたしきせたしためて譲りたし子を思ふゆゑに物思ふ身は
一首目の作者は花夕、題は「遊子落書」。遊子は旅人、結句「堂宮」は寺や社をいう。江戸前期を生きた池田正式の〈観音の堂に打ちふるらく書きをかたみに残す諸国順礼〉(『堀河百首題狂歌合』)は落書きにも歴史のあることを教えてくれる。二首目の作者は聞候、題は「遊子落書」。伏見稲荷であろうか。やって来たのは関東人(関東兵衛)である。二句「詣できつ(ねの)」に狐、四句「筆を取り(ゐに)」で鳥居を掛けて結句は「とんだ落書き」となる。三首目の作者は文之、題は「幇間」。初句は「助けましょと」。二句の「手妻」は手品。三句の「牽頭」は幇間だが四音のため「たいこもち」と読んだ。助けましょというのが合図で忽ち小鉢の酒を花に変えたのである。四首目の作者は賈石、題は「述懐」。食わせられなかったわけではない。着せられなかったわけでもない。蓄えがないわけでもない。気持ちと実際の乖離が問題なのだが、下句から推して子育ても後半、まだ可能性を残しての述懐と見た。
世わたりにかたひちはれと力なや今にわつかな銭ももてぬは
今そなき親の諫めし夜遊ひのかへらぬむかし思ひ出さるる
からきよを渡るに付(け)て身にそしむあまやかされし親の恵は
餞によりあふてのむ酒盛(り)の果(て)はくたをそまくいとまこひ
一首目の作者は素人、題は「述懐」。〈世渡りに肩肘張れど力無や今に僅かな金も持てぬは〉。「無や」は形容詞「ない」の語幹に詠嘆の助詞「や」、「肩肘」を張る一方で、こうした冷静さを見失わないところは強い魅力である。二首目の作者は梅里、題は「懐旧」。四句「帰らぬ昔」、その「帰らぬ」で思い出されるのが夜遊びをしていた若い頃なのだ。諫めてくれた親も元気だった。結句「思ひ出さるる」その頃の親も「私」も再び帰ってくることはない。三首目の作者は花夕、題は「懐旧」。下句「甘やかされし親の恵みは」、その甘やかされたことが今に災いして上句「辛き世を渡るに付けて身にぞ染む」という。「親の恵み」が皮肉に聞こえるが、なかなか抜けない「私」の甘えらしい。四首目の作者は輪田丸、題は「離別」。〈餞に寄り合うて呑む酒盛りの果てはくだをぞ巻く暇乞ひ〉と後味の悪さが残る。しかしこうした姿が常態であったとすれば、これしかない送られ方であり、また送り方なのだろう。
|
| 第181回 狂歌新三栗集 |
三味線のまことにこれやと横柄に大黒舞は頭巾着なから 喜多英風
『狂歌新三栗集』の撰者は燈果亭天地根、刊記は文政元(一八一八)年である。掲出歌の題は「大黒舞」。大黒舞は正月の門付け芸である。大黒天の面に赤い頭巾、手には打ち出の小槌の姿で祝いの詞を歌いながら舞った。二句はその一節だろう。三句の「横柄に」が面白い。下句からすると頭巾を取れというのだろうが、それでは大黒でなくなってしまうのだ。
魚といふ魚の中にも魚へんに尊き所へ上(げ)ますの魚
山も笑ふ春の光にかはら家の鬼もよたりをなかす雪解(け)
寝はらはひおのかまにまに草つみてあそふや野への牛はうしつれ
野あそひの小歌てかへる夕暮にかはつもそこやここをとひとひ
一首目の作者は百尺楼桂雄、題は「はらかの御贅はこふ処といふ題をさくりて」。「はらか(腹赤)」は鱒の異名である。四句は上から「魚偏に尊(き所へ)」、下へは「尊き所へ(上げますの魚)」。結句にも「鱒」が隠れている。二首目の作者は西隣亭戯雄、題は「雪解」。初句は春らしくなった山をいう。三句「瓦家」は瓦葺きの家だろう。四句の「鬼」は鬼瓦(大棟や降り棟の端に飾る瓦)のこと、次は「よだり(涎)」で雪解けの雫の比喩となる。三首目の作者は清果亭桂影、題は「野遊」。初二句は「寝腹ばひ己が随意に」で二句の意は「任意に」、三四句の「摘みて遊ぶ」は人ではない。牛だろう。結句は成句「牛は牛連れ」(同類は自然と集まりやすい)。登場しない「人は人連れ」を三四句に重ねた。四首目の作者は燈果亭天地根、題は「夕蛙」。三句「小歌」は巷間で流行した短い歌謡の総称をいう。「帰る」は「蛙」と同音、下句は「蛙も其処や此処を飛び飛び」で「小歌」が童謡や唱歌でも不思議でない道が続く。
獅子もわか子はためすとも谷陰にさける牡丹の花はおとさし
村中て腕さする男も尻こみに跡へ跡へとよれる植(ゑ)つけ
親達の目をしのひつつあみのめに魚はかかれとあそふわらんへ
口はしの針ては物をぬはぬ蚊のかやの破れをなとさかすらん
一首目の作者は原舎鳳、題は「山路牡丹」。初二句を「わが/子」の句跨りで始め、「獅子の子落とし」に「獅子に牡丹」を絡ませた。子供への厳しい試練を与える獅子を描く一方で、花を愛でる華麗な姿を重ねた。二首目の作者は曲肱亭百年、題は「早苗」。早苗は後退しながら植えていく。ここに誰を置くかだが、初二句「村中で腕さする男」(村で一番の力自慢)を用意した。その男に「尻込み」(怖じけて後じさり)をさせるという見立てが愉快なのだ。三首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「童子川狩」。〈親達の目を忍びつつ網の目に魚は掛かれど遊ぶ童〉。「親達の目」と「網の目」を対比的に描く。片や「忍びつつ」、片や「掛かれど」なのだ。しかし後者の「目」も忘れて遊ぶのが童部らしい。四首目の作者も麦浪亭渓雲、題は「蚊」。初句の「口嘴」は蚊帳の綻びを繕ってくれるのではない。逆に「蚊帳の破れを何ど探すらん」、「縫う」ではなく「刺す」。蚊帳の外の小さな蚊、中の大きな人間、その攻防の図が楽しい。
|
| 第182回 狂歌新三栗集(2) |
をりにあへは土用鱸の汁にうく油を汗の玉かとそおもふ 巴水亭朝雲
掲出歌の題は「鱸」。鱸(すずき)は海産魚だが夏季には河川に入る。旬は夏で、脂肪がのり、美味である。初句「折りに合へば」とは、このような時期にありつけたらと解した。二句の「土用」がそれで、小暑から立秋までの最も暑い盛りである。夏を乗り切るスタミナ源として喜ばれたのだろう。その「汁に浮く油を汗の玉かとぞ思ふ」も視覚に訴えてくる。
能因の顔もやけつくたひちには秋風そふくなととありたい
真桑瓜ふたつならへてそなへしを枕のやうにほしやおほさん
あまの河盃事のありしにやあくるあしたにささのなかるる
石やまのむかしはしらす秋もまたほたるの光り月にきそへり
一首目の作者は粒果亭方雅、題は「旅苦熱」。能因の〈みやこをばかすみとともにたちしかど秋風ぞふくしらかはのせき〉(『後拾遺集』五一八)に拠った。上句「顔も焼け付く旅路」は夏を歩いたこと、また「白河」を意識した。結句は「などとありたい」。二首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「七夕瓜」。上句は「真桑瓜二つ並べて供へしを」、果実が楕円形なのだ。続けて「枕のやうに星や思さん」。「思さん」は尊敬語だが、卑猥な視線はごまかせない。三首目の作者は青梧亭舎鳳、題は「七夕後朝」。二句「盃事」は夫婦の契りを結ぶ儀式を指していう。結句「笹の流るる」の「笹」に「酒」(女房詞)を掛けた。しらばくれれたところは承知の作だろう。四首目の作者は鈍少亭普拙、題は「秋蛍」。二句「知らず」とあるが三句の助詞「も」に注意である。石山秋月を含む近江八景は十六世紀の選定になる。また『和漢三才図絵』(一七一三年)は大きさも数も尋常でない、この地域の蛍について記述している。
手をつくしもみつひねりつとる角力みてゐる人の肩のこるまて
風にまかせたれかれなしにまねくなり薄も秋は淋しいかして
さかさまにたてし箒に似なからも野辺の尾花はなと招くらん
おとろきておもはすおとす提燈のきえて行(く)かたしれぬいなつま
一首目の作者は繞樹亭百丈、題は「角力」。相撲風景に按摩用語を重ねた。上句「手を尽くし」(手技)「揉みつ」「捻りつ」「取る」(按摩を取る)である。下句は成る程だが、按摩は逆に「肩のこる」から出発することになる。二首目の作者は清浅亭軽雲、題は「薄」。古歌の〈夕暮は吹きもさだめぬ秋かぜにまねくすすきの袖かへる見ゆ〉(『夫木和歌抄』四四〇六)や成句「秋風に薄の穂」が思われるが、この見境のなさは出色である。招かれた男の行方や何処。三首目の作者は吹樹亭猛風、題は「薄」。上句は成句「箒を逆さに立てる」(長居の客を早く帰す呪い)をいう。結句「など招くらん」(どうして招くのだろうか)、見立てと機知がすべてといってもよいだろう。四首目の作者は清月亭如流、題は「稲妻」。初二句に「お」音が三音、母音要素を含めると七音と三句までがスムーズである。下句「行く方知れず」は稲妻の行った先が分からない、また自分の進んで行く方向が分からない、真っ暗なのである。
|
| 第183回 狂歌新三栗集(3) |
おつとせいの外にねてゐる物はあらし月さえわたるえその海つら 西隣亭戯雄
掲出歌の題は「海路月」。上句はオットセイ以外は起きているというのである。結句「蝦夷の海面」の意は北海道の海辺でいいだろう。生果亭桂芽に〈月にとる膃肭臍をばよべ今宵りやう夜をかけてくふ薬喰〉(『狂歌後三栗集』)がある。「月にとる」は「月の夜に捕る」意で、掲出歌から推してオットセイは寝ているのであろう。捕るのはアイヌの人たちである。
手折(る)手を見とかめられて我(が)かほもともにしくれのもみち葉の色
手紙にもかくのことくともみち葉をひと葉封しておくる山守
ひこひかと見れはもみちの散(り)たるを其(の)ままこほる庭の池水
雪になろか風になろかととちらへもころひやすげに霰たはしる
一首目の作者は曲肱亭百年、題は「紅葉」。当たり前のように花の枝を折る。花盗人を咎める人はいないのかと思っていたら、花ではなく紅葉だが事例を見つけたので抄出する。但し三句以下のアイデアから生まれたかも知れず、事実か否かを保証するものではない。二首目の作者は吹松亭峰風、題は「紅葉」。秋が深まり、寺の境内また山も紅葉したこと、二句「斯くの如くと」(こんなふうだ)と一枚の葉を入れた。「斯く」に「書く」を重ねて奥ゆかしくも美しい。三首目の作者は清果亭桂影、題は「池水」。漢字を補うと〈緋鯉かと見れば紅葉の散りたるを其のまま凍る庭の池水〉となる。氷の中に閉じ込められた緋鯉かと思ったのであろう。見立てだが、十分に遭遇しそうな光景に違いない。四首目の作者は粒果亭方雅、題は「霰」。霰は雪の仲間で継続しては降らないから雪にもどるか、そうでなければ降り止んで風となる。「なろか「なろか」「ら」「ろ」「ら(霰)」「る」は一例だが意味内容だけでない見所である。
鷺かともみのにふりつむ雪の道ぬきあしをしてあゆむすかたは
ねくらたつかたちはそれとしら鷺の羽音にわかる雪の曙
山しろの木幡の里の馬よなも道しりかほにふむな白雪
つもりたる雪の中行(く)鹿の背をいつよりひくう見るならの町
一首目の作者は清果亭桂影、題は「雪」。〈鷺かとも簑に降り積む雪の道抜き足をして歩む姿は〉。簑の茶色が雪を被って翼を畳んだ羽毛に見えるのだろう。抜き足がさらにそれらしくさせる。初句を受ける述語が見当たらないが二句「簑」に「見(の)」であろうか。二首目の作者は送月亭長風、題は「雪曙」。〈塒たつ形はそれと白鷺の羽音に分かる雪の曙〉。「白」に「知ら(ない)」を掛ける。平仮名は雪のイメージで雪に紛れた白鷺を聴覚で見ているのである。三首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「里雪」。初句の「しろ」(城)は結句に対応した。木幡は奈良街道の道筋なので駄馬が相手である。三句「なも」は「何にも」の変化で「そんなに」と解した。四句は知っているような顔つきをいう。四首目の作者は曲肱亭百年、題は「市中雪」。雪の深さだけ鹿の背が四句「低う」(ウ音便)なるのだ。四句は積雪が「何時より」の自問である。奈良の市中を室内から眺めているのだろう。室外だと人も鹿も同じ条件となる。
|
| 第184回 狂歌新三栗集(4) |
犬のこゑいとはてきたを聞(き)わけすほえたりかんたり何の事そい 柳果亭桂舟
掲出歌の題は「厭肝積恋という題をとりて」。表記を改めると〈犬の声厭はで来たを聞き分けず吠えたり噛んだり何の事ぞい〉となろう。歌意は「犬の声を嫌がらないできた。それなのにあなたといったら私の言葉に納得しない、吠えたり、噛んだりとは、何のことだよ」と痴話喧嘩を想定した。題の意は「厭わずに真心(肝は魂の宿る場所とされた)を積む恋」か。
夜まはりの拍子木の音打(ち)絶(え)て雀ちよんちよんなける暁
早き瀬を丸太にのりてあちへとひこちへとひもてくたす杣人
不性ものとは思はねと田をすけは尻おもけにも見ゆる牛哉
しるしにはとうありとても雨ふれは先(つ)一番にいつる番傘
一首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「暁」。四句「ちょんちょん」は雀の囀る声であり、また拍子木を続けて打つ音でもある。静寂をはさんだ夜と明け方を同じオノマトペで繋いだ。三句も拍子木の縁語を意識した。二首目の作者は清果亭桂影、題は「杣」。上流で伐採した丸太を下流へ流し、杣人は筏で監視しているのであろう。岩場等で流れの止まった丸太に「あちへ鳶こちへ鳶もて」流れにもどすのである。「鳶」は「鳶口」の略、「もて」から「飛び」は採らない。三首目の作者は万樹亭連雲、題は「牛」。句跨り感の大きい初二句が効果的だ。三句は「田を鋤けば」で「私」の位地は牛の背後となる。尻を見ながらの前進だけに観察の行き届いた、また質感を捉えた下句となった。四首目の作者は酔花亭春雲、題は「傘」。油煙斎貞柳の〈百人一首にどうありとても元日のあかつきばかりよきものはなし〉(『家づと』)を踏まえた。初句「印」は屋号、四句は「一番先」の意に傘の番号を掛けた。商家の貸し傘だろう。
いつよりかつまを婆々とは呼(ひ)なれし我おいにきとおもはさりしに
ふみまよひとへと互(ひ)にことはさへわからぬひなの長路くるしき
見渡せはけしきようそろとりかちやおも梶ことに模様かはりて
祝ひうつつふてはそとにおとす也あかつきかけて内は高砂
一首目の作者は連雲、題は「老人」。三句切れの連体形止め、ニュアンスは「いつから妻を婆々と呼ぶようになったのだろう」となる。待遇表現は家族構成によるから孫の誕生が契機だろう。「私」も爺なのだ。二首目の作者は西隣亭戯雄、題は「羈中」。表記を改めると〈踏み迷ひ問へど互ひに言葉さへ分からぬ鄙の長路苦しき〉。日本の方言文化が最も顕著だったのは封建体制下の江戸時代だというから、こうしたことも珍しくなかったと思われる。三首目の作者は独酔亭百銭、題は「船眺望」。〈見渡せば景色宜う候取り舵や面舵ごとに模様変はりて〉の「宜う候」は一に景色、二に「真っ直ぐ進め」となる。「取り舵」は左に回頭、「面舵」は右に回頭するように舵を取ることをいう。四首目の作者は百尺楼桂雄、題は「婚姻」。孤立に〈花嫁をむかへた門を祝ふとて石を外からくれの春の日〉(『狂歌軒の松』)がある。石打、石祝い、祝儀の石などというが、中に投げ入れるのだが遠慮したのか。朝へかけての祝宴である。
|
| 第185回 狂歌新後三栗集 |
うしろからたたいて福をいのるなり夷はあちらむいて御座ろに 巴水亭朝雲
『狂歌新後三栗集』の撰者は橙果亭天地根と清果亭桂影、刊記は文政二(一八一九)年である。掲出歌の題は「十日戎」(正月十日の祭)。大阪の今宮戎神社では本殿裏にある銅板を叩くという。京都の建仁寺は板を叩くらしい。夷さんは耳が遠いので願い事の念押しなのだそうだ。掲出歌の世界が今も見られるのである。但し兵庫県の西宮神社は裏が森のため回れない。
みやけには背丈をのはし金よりも角前髪となりてやふ入(り)
あふくとも風はひかねといたつらに鼻うこかさんうつし画の梅
雪と見し花のをりにはさもなくて毛虫かそつとさした葉桜
世の中よ月にむら雲花に風ほとときすには瀧津せのおと
一首目の作者は青梧亭舎鳳、題は「養父入」(藪入り)。句を入れ替えると三句「金よりも」以下「土産には背丈を伸ばし角前髪となりて藪入り」である。角前髪(すみまえがみ)は元服前、十四歳になった少年の髪型をいう。二首目の作者は百尺楼桂雄、題は「扇にかける梅の絵に」。初句「仰ぐ」に「扇ぐ」を掛けた。二句「風」は風邪の意の「風」に梅の香りを運ぶ「風」である。仰いでも、扇いでも無益に鼻を動かすだけの梅の写生画なのだ。三首目の作者は粒果亭方雅、題は「葉さくらのもとにて」。三句「然もなくて」(そうでもなくて)、以下「毛虫がぞっとさした葉桜」となる。「さした」は①動詞「さす」(し向ける)の連用形に助動詞「た」、「させた」に同じ②これに毛虫の縁語「刺した」を重ねた。四首目の作者は繞樹亭百丈、題は「郭公」。二三句で成句「月に叢雲花に風」(世の中の好事には障害の多いこと)を使った。この比喩に追加したのが下句「時鳥には滝つ瀬の音」、激しく流れる川音だというのである。
大きみの氷室守雄は行義よく夏もはたかてくらささらまし
しこしらへて出すをとり子の親たちはさそない袖もふつてよろこふ
節分の豆まくやうにふる霰鬼かはらにもいたくあたらむ
恋風になひくをいつとしろかねのつくりつけなるすすきかんさし
一首目の作者は曲肱亭百年、題は「氷室」。初句から宮中用だと分かる。二句は職名「氷室守」に「雄」を付けて擬人化、下句は大君と氷室からの推量で「夏も裸で暮らさざらまし」(服を着て暮らすのだろう)とした。二首目の作者は繞樹亭百丈、題は「踊」。〈仕拵へて出す踊り子の親達はさぞ無い袖も振って喜ぶ〉。成句「無い袖を振る」(なけなしの金で遣り繰りをする)を使った。戯画として袖のない親が目に浮かぶ。三首目の作者は散糧亭雄飛、題は「霰」。上句の比喩が巧みである。下句「鬼瓦にもいたく当たらむ」にも無理がない。見立てによって自然現象も楽しくなる例であろう。「いたく」は「甚く」(ひどく)に「痛く」を掛ける。「ら」音また母音要素の「あ」音が響く。四首目の作者は清果亭桂影、題は「幼恋」。〈恋風に靡くは何時と銀の作り付けなる薄簪〉。三句は「知らないが」の綾を掛ける。女の子が自分の手で自分のために銀紙で薄の穂形の簪を作ったのである。今、黒髪にその簪が揺れている。
|
| 第186回 狂歌あさみとり |
伊左衛門になる三五郎はやつしろの紙子を着るも芸のふり付(け) 畝守
『狂歌あさみとり』の撰者は柳條亭小道、刊行は文政三(一八二〇)年である。掲出歌の題は「芸者紙子」。初句「伊左衛門」は歌舞伎の『廓文章』に登場する伊左衛門、二句の「三五郎」は三代目の嵐三五郎(?~一八三三頃)であろう。三句の「八代」(熊本)は紙子の産地、落ちぶれた伊左衛門が紙子を着るのだか、これを歌舞伎では「やつしの芸」という。
耕作に遣ふた恩と百姓の身に戴(い)て喰ふ牛の肉
くはつくはつとぬくもる薬と庄や殿か年貢の外にとり〆て喰(ふ)
秋の田をあらせしにくさ百倍の身か可愛さにくふ紅葉鳥
庄屋さへも負(け)る狐をくすりくひした百姓かつよい顔して
秋の田をあらした猪も百姓か内をととのふものと煮て喰(ふ)
一首目の作者は近道、題は「百姓薬喰」(以下、同題が並ぶ)。二句はウ音便だから「遣うた」となる。その「恩」また四句「戴いて」と薬食いのイメージからは遠い、敬虔な姿勢が印象に残る。二首目の作者は天足である。初句は「くわっくわっ」と鶏の鳴き声、また「かっかっ」と読ませて体が二句「温もる」さまとした。歴史的仮名遣いがもたらした表記と発音の二重性を逆手に取った修辞である。四句は百姓の飼育する鶏を「年貢のほかに」、結句「取り(鶏)締めて喰ふ」という悪庄屋である。三首目の作者は弥陀丸である。結句「紅葉鳥」は鹿の異名である。一首は成句「可愛さ余って憎さが百倍」(可愛いと思う心が強いだけに、憎いと思い始めると、その憎しみは非常に強い)を使った。苦労して育てた稲を荒らされた、その苦労した我が身可愛さからの薬食いなのだろう。四首目の作者は三巴である。狐拳また庄屋拳という三すくみの拳がある。庄屋は鉄砲に勝ち、鉄鉋は狐に勝ち、狐は庄屋に勝つというものである。その狐を食った百姓が結句「強い顔して」おそらく狐顔になって庄屋に迫っている図なのであろう。五首目の作者は遊鶴である。四句「内をととのふ」に対する「外」は初二句「秋の田を荒らした猪」である。以上、虚実綯い交ぜとはいいながら百姓の薬食いを垣間見た。
ゆつたりと碁にも思案の長袖や盤に心をおくけ様とち
おとかいはとまれ好く餅ひつつきし入れ歯のあこもはつす老人
綿帽子ほとつつ枝にまろかりて松葉の針にとつるしら雪
一首目の作者は都柳、題は「公家囲碁」。三句「長袖や」(普段着の道服だろう)は初二句を受けて「~思案の長(袖や)」で長い意を掛けた。結句の「お公家様どち」も上から「盤に心を置く(げ様どち)」となる。二首目の作者は天足、題は「老人好餅」。初句「おとがひ(頤)」は顎、四句も「あご」だが、初句は続けて「とまれ」(さておき)となる。このことから下句で外すのは餅が引っ付いたままの木床義歯(入れ歯の顎)だと分かるのだ。三首目の作者は陰成、題は「樹上雪」。表記を改めると〈綿帽子程づつ枝に丸がりて松葉の針に閉づる白雪〉。きれいな雪景色にズームインした。中でも下句さらにいえば「閉づる」が卓抜である。
|
| 第187回 狂歌一橙集 |
こは何もかへり見もせて手まりのみつくにしきりと動くかんさし 橙果亭天地根
『狂歌一橙集』の詠者は橙果亭島天地根、刊記は文政四(一八二一)年である。掲出歌の題は「をとめ子の手鞠つけるを見て」。表記を改めると〈此は何も顧みもせで手鞠のみ突くに頻りと動く簪〉だろう。しかし二句の破格「かへり見もせで」で振り返る少女の幻想が消える。平仮名に占める「見」の効果である。すべてが結句の「簪」に集中するさまも美しい。
薮かけに雪そのこれるこその冬をれたる竹を日おほひにして
月も日も二にんか四花や算用はあはてもすゑん七九十一
花ゆゑにかたきのやうにいはれてもやはらかにふく春の山かせ
よへ白う見し菜の花も千金の色をあらはす春の明(け)ほの
一首目の題は「残雪」。初句「藪蔭」は薮のために陰になっている所をいう。二句切れ、三句以下は「去年の冬折れたる竹を日覆ひにして」。ただでさえ日当たりの悪い所に折れた竹が覆い被さっているのである。見る人を得た景である。二首目の題は「二日灸」(二月二日にする灸)。二句「四花」は灸のツボの一つ、四句「合はでも据ゑん」の結句「七九十一」だが「七九」は灸を据える場所、「十一」は後世の命名らしいが『足臂十一脈灸経』『『陰陽十一脈灸経』との関係に拠ろう。三首目の題は「春風」。上句だが相手は桜の花で勝ち目はない。しかし判官贔屓で下句「柔らかに吹く春の山風」とやった。山中の風は花を散らすほどでない、また散るには早い。風のような平仮名表記である。四首目の題は「春曙」。初二句「昨夜白う見し菜の花」は月光のみでモノクロの世界だった。それが次第にカラーの世界へと移っていくのである。三句「千金の色」以下は千枚の黄金を前にしたように圧倒されているのであろう。
たはれ島や何をたはれて山々は霞の袖にわらひつつめる
さみたれはたたみに足のひつつきて友かりゆかむこともものうし
水ましてつるへのなはも長たらしちときりあけよ五月雨の空
ひきつれし牛こそ見えね秋霧のもうもうとたつ中に声あり
一首目の題は「春望」。初句「風流島」(たわれじま)は熊本県宇土市の緑川河口付近にある岩島である。三句「山々」は有明海の周辺の山を擬人化して「霞の袖に笑ひ包める」となる。古代から詠われてきた不思議な岩礁である。二首目の題は「五月雨」。上句は「五月雨は畳に足の引っ付きて」、足袋を履いても変わらない。湿気で畳がべっとりしているのだ。下句「友がり行かむことも物憂し」(「がり」は接尾語、友の所へ)と気分を削がれるのであった。三首目の題は「五月雨久」。上句は「水増して釣瓶の縄も長たらし」、長雨で井戸の釣瓶の縄が手元に余って長いというのだ。その縁語で下句「ちと切り上げよ五月雨の空」となる。釣瓶の着水する高さが水量で上下するところに着眼した。四首目の題は「霧」。初句「引き連れし」から位地関係は「私」の後ろをついて来る牛、何頭かなのだろう。その牛が四句「濛濛」とした霧で確認できないのだ。しかし同音の「もうもう」と鳴く牛の声がするというのである。 |
| 第188回 狂歌一橙集(2) |
よはひ星もかけ見えぬまて照(る)月に空はからすのとふはかりなり 橙果亭天地根
掲出歌の題は「月」。〈夜這ひ星も影見えぬまで照る月に空は鴉の飛ぶばかりなり〉。初句は流れ星の異称である。三句は中秋の名月と読む。では下句はどうか。粒果亭方雅にも〈飛びめぐる烏もち論もろ鳥のねぐらざわつくけふの月かげ〉(『狂歌後三栗集』)がある。烏は昼行性だから、ここは月夜烏なのだ。良夜に浮かれて鳴く烏、転じて夜遊び人のこともいう。
ひたたれの錦にまかふもみち葉は木々の中ての山の大将
秋やまに此(の)ころむれてつとひ来る人も紅葉のそめきならまし
我は酒こさねと頭巾いたたけはほのほのとしてかんをしのけり
たちとまりゆくもゆかれすふりつもる雪にあしたの跡へもとろか
一首目の題は「山紅葉」。初句の「直垂」は軍陣に際して鎧の下に着る鎧直垂であろう。「一期の晴着として日常の直垂よりも華麗な地質を用い」(『国史大辞典』)、材質も錦などが用いられた。そこからの結句「山の大将」となる。二首目の題は「紅葉見にゆきて」。二句「此の頃」で今時分、以下「群れて集ひ来る人」を「紅葉の騒き」(「ぞめき」は遊郭や夜店などを冷やかして浮かれ歩く人)に擬えた。「も」で受けたのは「私」がそうだからである。三首目の題は「頭巾」。白楽天の「陶潜が体に效ふ詩十六首并に序」(佐久節訳註『白楽天全詩集 第一巻』)の十二首目に「口に帰去来を吟じ、頭に漉酒巾を戴く」の句があり、これに拠った。結句「寒」に酒の「燗」を掛けた。四首目の題は「雪」。四句「足駄」は高下駄をいう。近世では特に高い歯を入れて太い緒をつけた。道の悪い時に用いたが、雪の中を進めず、足駄の跡を逆戻りしようかというのである。成句「雪の明日は間男の穿鑿」が思われたことであろう。
雪をれの音する冬の山里は人よりししやまつすくむらむ
人や来とまつの梢につむ雪をおとして通る風そつれなき
とりはみなにくる御狩に鶴とてもたか括(り)てはゐられさらまし
河豚汁の薬喰(ひ)よりわた入(れ)しなこやの衾きてぬくもらむ
一首目の題は「雪」。初句「雪折れ」は雪の重みで木の幹や竹が折れること、四句の「しし」は猪をいう。下句は「先づ竦むらむ」(驚きで体がこわばる)に猪の猪首(首を竦めることにもいう)の意と猪突猛進の「真っ直ぐ(むらむ)」を掛けた。二首目の題は「閑居雪」。趣きは〈梅の花見にこそ来つれ鶯のひとくひとくと厭ひしもをる〉(『古今和歌集』一〇一一)の冬バージョンである。二句「松」に「待つ」を掛ける。結句「風ぞつれなき」、思いやりがないというのである。三首目の題は「鷹狩」。初二句は「鳥は皆逃ぐる御狩に」、下句は「高括りては居られざらまし」、この「高」に「鷹」を掛ける。高を括った相手が将軍だと「御鷹の鶴」「鶴の御成(おなり)」「御拳(おこぶし)の鶴」と大層だが食材となった。四首目の題は「衾(ふすま)」(寝る時に体の上にかける長方形の夜具)。三句「綿」に河豚の「腸(わた)」を掛けた。河豚の毒は内蔵(腸)にある。下句は「和やの衾着て温もらむ」、「や」は接尾語で柔らかな状態をいう。
|
| 第189回 狂歌一橙集(3) |
行燈に羽織を着せて今宵先(つ)手にふれそむる吾妹子か乳 橙果亭天地根
掲出歌の題は「初逢恋」。行燈の火を消すのではない。二句「羽織を着せて」が艶めかしく閉ざされた空間を演出する。結句の「乳(ちち)」の登場に目を瞠った。発刊時は鳳姓だったという与謝野晶子の『みだれ髪』中〈乳ぶさおさへ神秘のとばりそとけりぬここなる花の紅ぞ濃き〉や〈春みじかし何に不滅の命ぞとちからある乳を手にさぐらせぬ〉が思われる。
関守もなにかとかめむ通ひなれし旅商人は顔のうれれは
大船に乗(つ)たやうなといふはつよくかありさうに見えぬ海つら
一首目の題は「関」。初句は関所の番人だが比喩的に人の往来を阻むものをいう。これを受けての展開である。結句は「顔の売れれば」、これに商人の物を「売る」を掛けた。二首目の題は「海」。成句「大船に乗ったよう」を使った。三句は「言ふ筈よ」で三句切れとなる。四句は「苦が」に同音の「陸」を掛ける。結句は「海ずら」(海らしい)に「面」を掛けた。
いやらしと人なおもひそ脈やあると手を握りつつ見る妻の顔
長生(き)をなほねかふなり今は恥も忘れかたみのをさな子を見て
目にあてる子供の袖や露にぬれん母は草葉のかけにかくれて
一首目の題は「文化九年といふ年の春のすゑより家とぢのこここちあしとてとかくふしがちにて夏かけて日にけにあつしくおとろへ行(く)を見るにかのややもすればきえをあらそふ露の世にとよみ給ひておほん泪をおさへ給ひしとかきこゆる御ためしさへ思ひ出(で)らるるにおほけなけれどおのれがよはひさへ彼(の)君のほどにおなじければいとど心細くていかなるさほふ作善をも力のおよばん限りはと思へどさるかたにはうとき身なれば家の業をつくしてとかくすれど露其(の)しるしも見えねばこは我思ひばかりのいたらぬかたもやあると思ひめぐらして世に聞(こ)えあるくすしたちを是彼まねき物し得がたき木の皮草の根などもとめていそしく看あつかひつれどさだまれるすくせにやありけむ日々によわりつつたのみなくなりもてゆきつひに文月むゆかといふにさらぬわかれとなりぬるぞいとかなしく」。文中「ややもすれば」云々は紫の上との死別を前にした光源氏の〈ややもせば消えをあらそふ露の世におくれ先だつほど経ずもがな〉(『源氏物語』第四十帖「御法」)をいう。年齢が同じというから天地根五十一歳である。長塚節の詞書短歌も連想される。二首目の題は「よそぢにたらぬほどにて身まかりたる妻は何がしの法師の心にはかなふべけれど我はまだ」。文中の法師は吉田兼好で『徒然草』(第七段)の「命長ければ辱(はぢ)多し。長くとも四十に足らぬほどにて死なんこと、めやすべけれ」を指す。四句の「忘れ」は上から「今は恥も忘れ」、下へは「忘れ形見の」となる。三首目の題は「をさなきものらのかくれんばうとかいふたはぶれ事をするを見て」。子供の袖を目に当てているのは草葉の陰つまり墓の下の母(妻)という設定である。三句の「露」は草葉の縁で「露」そして「涙」の比喩でもある。ちなみに『狂歌一橙集』は天地根の還暦を祝って長男の橙芽亭天与之が上梓を勧めたものだという。
|
| 第190回 狂歌拾遺三栗集 |
百草をかきわけ見れは土の筆とりたる跡にみみすぬたくる 曲肱亭百年
『狂歌拾遺三栗集』の撰者は橙果亭天地根、刊記は文政五(一八二二)年である。掲出歌の題は「土筆(つくし)」。初句「百草」(いろいろの草)は「ももくさ」と訓読した。二句は「掻き分け見れば」、では三句はなぜ「土の筆」なのか。結句の「蚯蚓」を筆の跡に見立てているからである。「ぬたくる」は「うねり転がる」「のたくる」意、自然の景としても無理がない。
わらへらは親のまつをもよそにしてかへるをいとひ凧のほすらし
弁当を坊主持(ち)して野路ゆけは家にかへれる事もわすれき
ききたさは山ほとときす山彦のそひてうれしき跡の一声
たくましい和子は節句にかさりたる鎧武者にもつかみかかれり
一首目の作者は巴水亭朝雲、題は「鳳巾」。結句「のぼす」は「高い所に上げる」と「夢中になる」の意となる。あと二句の「待つ」が「松」に見える。凧の帰る場所「松をも余所にして反るを厭ひ」で凧も童と同じなのだ。二首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「野遊」。二句「坊主持ち」は同行者の荷物を一人で持つが、坊主に会うたびに交代することをいう。「坊主」から「出家」を連想して下句「家に帰れる事も忘れき」となる。「帰れる」は可能動詞でラ抜きではない。三首目の作者は寺島世楽、題は「郭公」。二句は山にいる時鳥、聞きたいのは「山彦の添ひて嬉しき跡の一声」だという。平地では一声、山ならオマケに一声付いてくるというのだ。二句と三句で頭韻を踏む。四首目の作者は繞樹亭百丈、題は「端午」。二句「和子(わこ)」は作中主体である「私」の子供だろう。ハイハイが掴まり立ちをする頃の幼児が思われる。興味のおもむくままで初句も結句も親馬鹿の一語なのだが憎めないスナップである。
ほつとする五月雨頃は蝸牛の角ものひする手かとこそ見れ
手習(ひ)はうはの空なる顔つきにやんまつる手やよくあかるらむ
用水や溜り水よりわけれはかね耳にいりてつらき蚊の声
伏(せ)籠にていふすかやりはこすのひまもれて雲井に立(ち)のほるらし
一首目の作者は巴水亭朝雲、題は「蝸牛」。初句「ほっとする」のは「私」ではない。三句以下「蝸牛の角も伸びする手かとこそ見れ」の蝸牛だろう。人の手を思わせる活発な触覚を観察しての詠なのだ。二首目の作者は曲肱亭百年、題は「顔に墨つきたる児の蜻蛉をつれるかたに」。上句は習字への不熱心、蜻蛉のいる空への関心を「上の空」の多義語で表した。下句の「やんま」は大形の蜻蛉、「手やよく上がるらむ」は習字の腕に呼応する。蜻蛉釣りは囮の蜻蛉を竿の先に糸で結んで他の蜻蛉を誘い寄せた。三首目の作者は巴水亭朝雲、題は「蚊」。初句「用水」は池や水路をいう。三四句は「湧ければか寝耳に入りて」で成句「寝耳に水」を使った。初二句との縁語仕立てである。四首目の作者は懐古亭英風、題は「禁中蚊遣」。〈伏せ籠にて燻す蚊遣りは小簾の隙漏れて雲居に立ち上るらし〉。「伏せ籠」は「蚊遣り」の上に伏せた籠をいう。その煙が御簾の間から御座所に届く様の推定、「雲居」は天皇だろう。
|
| 第191回 狂歌拾遺三栗集(2) |
背中よりぬけ出(で)し蝉よ汝は外にはらからといふ物はあるまい 麦浪亭渓雲
掲出歌の題は「蝉」。上句は「背中より抜け出でし蝉よ」と蝉に呼びかけ、読者には脱皮の様を映像として喚起させる。三句は「なはほかに」と読んだ。四五句は「同朋といふ物はあるまい」で同じ腹から生まれた兄弟はあってはならない、となる。脱け殻が母胎なのだ。今一つは三四句「汝は外(そと)に腹からといふ」と読む。背中を割って出てくるからだ。
むさしのの月かと見れは夏草のしけみをわくる旅人の笠
夏の夜の川瀬にうつる月みれは足のはやさも流るるかこと
やねのもりにたらひをあてて夕立の跡は行水せしここちせむ
夕立にたたかれしとてにけこめはあたまをうたす軒の看板
一首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「夏草」。初句の平仮名書きは具体的な地名よりも広大な夏草の野をいいたかったのだろう。そこを出た小さな月、いや旅人の笠だった。月の出の早い時刻の見立てとして読んだ。二首目の作者は橙果亭天地根、題は「夏月」。舞台は上句とりわけ「川瀬に映る月」、見所は下句「足の速さも流るるがごと」。川底が浅く流れの速い川瀬では、足が速いといわれる夏の月も、流されそうに映っている。一点凝視が冴える。三首目の作者は酔花亭春雲、題は「白雨」(明るい空から降る雨)。〈屋根の漏りに盥を当てて夕立の後は行水せし心地せむ〉。結句「する」なら「私」のことだが「せむ」だから第三者の悪戦苦闘を推測しての詠になる。四首目の作者は随風亭香山、題は「白雨」。〈夕立に叩かれじとて逃げ込めば頭を打たす軒の看板〉。夕立に叩かれないにしようと入った軒で看板に打たれたというのがミソとなっている。雨宿りを余儀なくさせられる頃にはありそうな話であったろう。
人の嫌ふかはよせつけぬ枕蚊やふせこのさまにかたち通ひて
むすはてもむかへは涼し山の井の水につかりし我(が)かけを見て
いかつちのおとうちたえて小山田に鳴子くわらつく秋はきにけり
露の玉穂さきに見えてきらつくはこれや孔雀の尾花なるらし
一首目の作者は柳果亭桂舟、題は「蚊帳」。上句は「人の嫌ふ蚊は寄せ付けぬ枕蚊帳」、枕蚊帳は子供の枕もとを覆うのに用いる小さな蚊帳をいう。それと「伏せ籠」(伏せておいてその上に衣服をかける籠)の形の類似をいった。二首目の作者は橙芽亭天与之、題は「泉」。「掬ばでも向かへば涼し」と二句切れ、手で掬わなくても向かえば涼しいという。なぜなら「私」の影が、山の清水をためてある所、その水に浸かっているのを見ているからなのだ。三首目の作者は江風亭清明、題は「立秋」。〈雷の音打ち絶えて小山田に鳴子がらつく秋はきにけり〉。二句「打ち絶えて」の「打ち」に雷鼓の音が重なる。秋になって「がらつく」のが鳴子、田畑を鳥獣に荒らされるのを防ぐ仕掛けなのだ。四首目の作者は橙果亭天地根、題は「薄」。初句「露の玉」は見立てである。その玉のような露が穂先にキラキラと光っている。下句は尾花の尾に孔雀の尾を重ねた。「これや」は「これやこの」(これがまあ例の)の勢いである。
|
| 第192回 狂歌拾遺三栗集(3) |
遠慮なうとふらひきませ何ほとの足跡もついうつむ大雪 粒果亭方雅
掲出歌の題は「雪」。一面の銀世界から出発して、足跡を遠慮し、また足跡を懐かしみ、さまざまな変化と新味を加えていく歌人の営為が面白い。この歌から思い出されるのは律丸の〈雪よ雪ようつみな果てそ訪ひきつる人のなさけの深き足あと〉(『狂歌千種園 冬』)である。分類すれば後者、そして同じ思いを共有しながら、前者に配慮したのが本作といえよう。
きりきりすなくは湯とののほとりかもひとりあかする夜はのわひしさ
人の田と我(が)田のあせのほそ道をわけかぬる迄稲のおしあふ
松茸と出あふ時には山里のかたいとうふもちとくたけをれ
をりかさすつとの紅葉の一枝をそめたらしとや又もしくるる
一首目の作者は柳果亭桂舟、題は「独聞虫」。〈蟋蟀鳴くは湯殿の辺かも独り垢擦る夜半の侘びしさ〉。四句「垢擦る」は「垢擦り」の名詞を「垢」と「擦る」に分けた。これに「明かする」を掛けた。「明かす」は四段活用だから無理を承知の場面転換である。二首目の作者は懐古亭英風、題は「秋田」。田畑の境界を畔囲というか「畔の細道を分けかぬるまで稲の押し合ふ」は豊作なのだ。一方で結句「押し合ふ」は田地拡大の末の「細道」を思わせる。三首目の作者は曲肱亭百年、題は「茸狩」。下句は「堅い豆腐もちと砕けをれ」と読める。しかし四句の平仮名はそれだけではない。掛けるとすれば「頭部」か「同父」だろう。結論は腹違いの兄弟を訪ねての作としてみたが正解は如何。四首目の作者は清果亭桂影、題は「紅葉見に行(き)てゆくりなくしぐれにあひて」。上句「折り翳す苞(略)」は土産の一枝を掲げているのである。下句は「染め足らじとや又も時雨るる」で、これは山の接待というべきかも知れない。
神無月こたつあくれは床のしたに足ちちかめてゐるきりきりす
手伝ふて塩振袖の嫁御にも世帯なれよとつけさせる茎
米のわら咽をとほしておのつからはらの大きうなれる塩たら
いく度もせせるにつけて埋火のあかくなるのをおこるといふらむ
一首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「炉開」。上句は炬燵を収納場所から動かすために持ち上げたのだろう。四句には人と変わらないという見立てがある。結句は蟋蟀と解したが陰暦の十月、冬を越せない虫なのだ。二首目の作者は清月亭如流、題は「茎漬」。二句は「塩振る袖」の意だが送り仮名は付けない。また「しおふりそで」と読む。「振袖」は未婚女性のもの、遠慮のある嫁御から家刀自として腕を振るってほしい、そんな願いのこもる下句である。三首目の作者は懐古亭英風、題は「鱈」。初句の「藁」は稲の茎である。その藁を平仮名にして「米」を表に出したのは四句の布石である。「腹の大きうなれる塩鱈」だが内臓を取り除いた後の見栄えを考えてのことなのだろう。ちなみに「鱈腹」は宛字という。四首目の作者は前田沢風、題は「埋火」。初句は「幾たびも」で五音、二句「せせる」は「つつきほじくる」と「からかう」の意がある。結句「熾る」は前者の結果、後者の結果を同音の「怒る」で掛けた。
|
| 第193回 狂歌拾遺三栗集(4) |
そつとさす三本あしの首筋に人なみならぬ妹と見とれつ 懐古亭英風
掲出歌の題は「見恋」。初句「ぞっとさす」は感動で体が震え上がるさまをいう。二句「三本足」は『日本国語大辞典』に「女性の化粧法の一つ。襟足を三本にそりあげて、そこへ白粉をつけるもの。江戸末期に始まる」とある。「あし」と平仮名にしたのは「足の首」を避けたかったのだ。下句は一般の女性とはかけ離れた美しさに見とれているというのである。
はつかしとねやのあかりを吹(き)けした妹の息こそ恋風ならめ
とけあひし印と見るも嬉しきは屏風にかかる二すちの帯
君をおきていかてかは妹にかへぬへき背中に腹をおはせてしより
恋風をはやひきそめてはなたれの長吉もちとうはかれし声
一首目の作者は曲肱亭百年、題は「逢恋」。上句「恥づかしと閨の明かりを吹き消した」。天地根の〈行燈に羽織を着せて今宵先づ手にふれそむる吾妹子か乳〉(『狂歌一橙集』)で明かりを残したのは男、こちらは女が吹き消した。下句はその見立てである。二首目の作者は杉森百丈、題は「逢恋」。三本足、行燈と続き、今度の小道具は帯である。初句「解け合ひし」は打ち解けた仲をいう。これが下句で展開し、解かれた「二筋の帯」の持ち主が一体になっている。その比喩としてカットしてきた映像が能弁かつ艶麗である。三首目の作者も杉森百丈、題は「男色」。下句は後背位のアナル・セックス、「私」は稚児の役である。ここで成句「背に腹はかえられない」の逆「負はせ」たのである。その結果が上句の論理で「妹」に「君」はかえられぬとなった。四首目の作者は清果亭桂影、題は「声替」。初句「恋風」の風(風邪)の縁語で「洟垂れ」小僧の長吉を出した。長じて結句「ちと上嗄れし声」(少ししゃがれ声)なのだ。
裾からけわたれは人のひさ過(ぎ)てぬるるふくりの玉川の水
横柄に胸つき出してあゆめとも礼はたたしき鳩にそ有(り)ける
ふる家の軒にふらりとさかりくも人に柱のゆかみ見よとや
三井のかね尾上のかねそかねならむつかても其(の)名ひひきわたれは
一首目の作者は西隣亭戯雄、題は「川」。〈裾絡げ渡れば人の膝過ぎて濡るる陰嚢の玉川の水〉。四句「陰嚢(ふぐり)」は「陰茎基部に下垂する袋」(『日本国語大辞典』)で俗に金玉、略して「玉」で結句「玉川の水」となる。玉川は歌枕の玉川だろう。二首目の作者は麦浪亭渓雲、題は「鳩」。上句で鳩の動きが実に巧く捉えられている。そこに目を瞠った。下句は成句「鳩に三枝(さんし)の礼有り」(鳩は親鳩より三本下の枝に止まって礼を守る。礼儀を重んずべきことの喩え)をいう。三首目の作者は柳果亭桂舟、題は「蜘蛛」。三句の「下がり蜘蛛」は天井などから糸を引いて垂れ下がっている蜘蛛をいう。ここは軒からなので下句「人に柱の歪み見よとや」、人は不特定多数の人であろう。四首目の作者は粒果亭方雅、題は「鐘」。〈三井の鐘尾上の鐘の鐘ぞ鐘ならむ撞かでも其の名響き渡れば〉。三井は三井寺(滋賀県大津市)、尾上は尾上神社(兵庫県加古川市)であり、その名声をいう。「鐘」が四度出てくる鐘尽くしとなった。
|
| 第194回 狂歌板橋集 |
去年といひことしといふかおかしいか雪のかたほにわらふ山の端 如棗亭栗洞
『狂歌板橋集』の撰者は揚棗廬楫友、刊記は文政六(一八二三)年、如棗亭栗洞の三十三回忌追善集である。掲出歌の題は「年内立春」。上句「去年(こぞ)といひ今年といふも可笑しいか」、陰暦の世界にいても、こうした感想を持つ人の少なくなかったのだろう。下句「雪の片頬に笑ふ山の端」(片方の頬に冬、片方の頬は春)で、目隠しをとれば驚く福笑い。
若水を心おかしく祝(ひ)けれ我もむかしははるの華むこ
負ふた子を下におろしてうは迄かはらをかかへて笑ふ万才
橋詰(め)の寒さは冬にかはらねとかき船帰る春の河かせ
待(ち)侘(び)ていつるあくひのうつれかしひらくまおそき花のくちひる
一首目の作者は如棗亭栗洞、題は「若水」(元旦に汲んで用いる水。一年の邪気を除くとされる)。上句は「若水」の「若」が呼び起こす詠嘆、具体的には〈今こそあれ我も昔は男山さかゆく時もありこしものを〉(『古今和歌集』八八九)となる。二首目の作者は春浪亭氷花、題は「万歳」(まんざい。正月の門付祝福芸)。座敷で太夫と才蔵の滑稽な掛け合いが行われているのだろう。「負うた子を下に下ろして乳母までが」、サボタージュといえばサボタージュなのだが正月なのである。三首目の作者は松本見代女、題は「河風如冬」。四句「牡蠣船」は大坂名物で、当初は広島の牡蠣を売るだけだったが、後に牡蠣料理を出すようになった。季節限定のため、春が来て広島に帰るところなのだ。橋の下に係留していたのであろう。冬のように寒い橋際である。四首目の作者は四時亭柴栗、題は「待花」。〈待ち侘びて出づる欠伸の移れかし開く間遅き花の唇〉。欠伸にこと寄せて花の開花を促したのである。花は桜と解した。
叢に蛍は光りあらはしておのかゐところ人にしらるる
あつさには枇杷葉湯売(り)も声たえてからすかよはぬ夏の日盛(り)
かつらをはかふり直して一人俄男なりけり女なりけり
影清きこよひは月の王様しやあれまろまろとおつしやるやうな
一首目の作者は仙郷亭棗風、題は「蛍」。『夫木和歌抄』に〈おほえ山しげみがもとにまじりても人にしらるるほたるなりけり〉(三一八六)があるが、むしろ茂吉〈ものみなの饐ゆるがごとき空恋ひて鳴かねばならぬ蝉のこゑ聞ゆ〉(『赤光』)が思われる。鳴かねばこそ明滅し、光らねばならぬのだ。二首目の作者は揚棗廬楫友、題は「夏のうたよめる中に」。二句「枇杷葉湯」(びわようとう)は乾燥した枇杷の葉などの煎じ汁で暑気あたりや下り腹などに用いた。その売り声も聞こえない。四句の「烏通はぬ」は八丈島、誰もいない「夏の日盛り」なのだ。三首目の作者は棗由亭負米、題は「俄」。同じカツラを使っての早変わりを主とする演芸らしい。下句の「なりけり」に見物客の同意が感取される。縁日か座敷か、背景は不明だが雰囲気だけは伝わってくる。四首目の作者は如棗亭栗洞、題は「月」。上句は中秋の名月をいう。下句は「あれ麻呂麻呂と仰るやうな」、自称の代名詞「麻呂」に同音の「丸」を掛けた。
|
| 第195回 狂歌板橋集(2) |
さはかしき世をいとひたる山住(み)もかきさかさるる茸かりの頃 春浪亭氷花
掲出歌の題は「山家秋」。表記を改めると〈騒がしき世を厭ひたる山住みも掻き探さるる茸狩の頃〉となる。松茸狩りの頃になると捨てた世間が大挙して山に向かって来る。とりわけ四句「掻き探さるる」の受け身の表現の中に、テリトリーを侵される、そんな迷惑な気持が滲んでいるようだ。音ではカ行音とサ行音が活躍し、母音要素ではア音が図抜けて多い。
虫の音もさつはり絶へた冬の来て樟脳ほとにおける朝霜
おそうくれはやうしらみて冬の日を長う覚ゆる雪のふる郷
ああふつたる雪かなとはかり酔(ひ)つふれ先へ一あし跡へ一あし
せいほ酒はや来年のこといふて笑ふ座敷のおにきはしさよ
一首目の作者は春浪亭氷花、題は「霜」。四句「樟脳ほどに」の「ほど」は量また広がりをいうのだろう。樟脳を置くならばこの程度、粒と色の類似に着目したのであった。二首目の作者は棗由亭負米、題は「雪」。結句「雪の故郷」は雪の降る郷」でもある。その雪の白さが残照と月の光を反射して夜は「遅う暮れ」、朝は「早う白みて」、つづまるところ「冬の日を長う覚ゆる」のだが、ウ音便の活躍が目立つ。三首目の作者は仙郷亭棗風、題は「雪中酔人」。初二句「ああ降ったる雪かな」は男の科白だろう。しかしここまでで「とばかり酔ひつぶれ」(というのを切っ掛けに酔いつぶれ)、足にきたのである。下句は完全に酩酊状態の対句表現となった。四首目の作者も仙郷亭棗風、題は「せいぼの礼に人のもとへゆきけるに酒席のいとうるはしければ」。初句「歳暮酒(せいぼざけ)」は歳暮にもらった酒、これを歳暮に飲む酒の意に掛けた。結句は「お賑はしさよ」で「来年の事を言えば鬼が笑う」の「鬼」が潜む。
幾夜こと門のみなれて犬に迄尾をふられたる身こそわひしき
留主の間は口舌もなつの蚤せせりいちられてうき嚊のひとりね
思案にも工夫するにも煙り草けふりに智恵のわをやふくらん
名にしおふ住吉四社の御社もかくらの鈴はこしやこしやと鳴る
一首目の作者は積小亭喜友、題は「従門帰恋」。〈幾夜毎門のみ慣れて犬にまで尾を振られたる身こそ侘びしき〉。初句は「行く夜毎」でもある。「慣れて」に犬の「馴れて」、「振られたる」は君に「振られたる」を掛けた。二首目の作者も積小亭喜友、題は「夏閨怨」。二句「口舌」は痴話喧嘩をいう。亭主が留主だからそれも「無(つ)」で「夏」の独り寝を蚤が「せせり」(「噛む」の意に「ちょっかいをかける」を掛けた)、弄られて、悩ましい嚊なのだ。三首目の作者は四時堂柴栗、題は「煙草」。下句は「煙に智恵の輪をや吹くらん」、何か閃いただろうかというのである。江戸時代に伝わったという玩具の「知恵の輪」だが早くは西鶴が『大坂独吟集』に句を残している。四首目の作者は如棗亭栗洞、題は「神祇」。二句「住吉四社」は住吉大社(大阪市)にある四つの本宮をいう。「ししゃ(四社)」だが神楽の鈴は「ごしゃごしゃ(五社五社)」と鳴る、掛けまくも賢くも他愛がない。三句は「おやしろも」と五音で読んだ。
|