放課後。
不利な条件でも上級生をこてんぱんに打ち負かしたリョーマではあったが、『新入部員』という待遇に変わりのない今は、初心者の一年生に混じってランニングや素振りというメニューを黙々とこなす。
それでも、そう言った基礎練習の間、リョーマはさりげなく視線を流して、部内の様子を観察していた。
特に、レギュラーの様子を。
(確か、あの人が『不二周助』)
手塚が気をつけろと忠告してくれた、男。
(普通っぽいけどな…)
不自然にならない程度に不二を観察していて、まず思ったことは、それだった。
どちらかと言えば線の細い身体で、パワーというよりテクニックやセンスが、他の部員に比べて群を抜いている。表情も常に穏やかで、口調もやわらかい。
テニスの実力がずば抜けていることを除けば、ごく普通の生徒に見えた。
(なんで、部長はあんなのを警戒しているんだろう)
よっぽど桃城の方が『クセモノ』に思える。
(でもきっと何かあるんだ。部長が、ああ言うんだから)
自分でも不思議なくらい、リョーマは何の疑いもなく手塚のことを信じている。
その実力を目の当たりにしたわけでもないし、人柄が特に優れているというわけでもない。
むしろ人間としてはどうかと思うような言動もしばしば見られる。
なのに、惹かれている。
冷たく感じるほど透明な瞳は、手塚の心に曇りがないとも言えるし、自分の非をあっさりと認めるあたりは、とても潔く感じる。
ロボットであったなら怪我などしないだろうにと言った手塚の言葉は、裏返せば、「ロボットじゃないから、自分も傷つくことがある」と言っているように、リョーマには聞こえた。
(それに、部長の唇、すごくあったかかった)
ランニングをしながら、リョーマはそっと、舌先で自分の唇をなぞる。
たとえ情報伝達の手段であっても、手塚の唇が自分の唇に触れ、自分の唇が手塚の唇に触れることを許されたあの時間は、リョーマにとっては至福の時間だった。
おそらく、暫くの間は手塚との仕事の会話はあの状態で行うことになるのだろう。
迂闊に外せない襟元のマイクや、その他にも設置されているであろうカメラやマイクを警戒する以上、あの方法が一番手っ取り早くて確実に互いの意志を伝えられるからだ。
(でも、誰かに見られないように気をつけなきゃな)
とはいえ、手塚の制服にマイクを仕掛けた人物は、手塚とリョーマが「そう言う関係」であると思っているのだろう。
だからこそ、もしも、手塚とリョーマの関係が噂になったとしたら、その噂を遡っていけば、マイクを仕掛けた人物に行き着くということにもなる。
リョーマとしては、手塚とキスのような行為を何度も出来れば嬉しいことこの上ないが、そこには、様々な思惑が絡み合っていることを考えると、複雑な気分にもなる。
(ま、こんな状況じゃなきゃ、あの人とキスなんて一生できないんだし)
自分はラッキーなのだと、リョーマは思うことにする。
「あと一周、ラストスパートいくぞ!」
先頭を任されている同級生が、精一杯の声を張り上げて檄を飛ばす。
「青学、ファイオー!」
周りにあわせて適当に声を出しながら、リョーマはもう一度、不二に視線を向ける。
「あ」
不二と目が合い、リョーマはさりげなく視線を逸らす。
一瞬目が合っただけなのに、リョーマは自分が小さく動揺していることに気づいた。
(あの目……なんか…ヤバい感じ…)
何がどう、というのではなく、リョーマの本能の深いところで、微かに警鐘が鳴った。
もう一度、帽子の影から不二を見ると、すでにいつもの穏やかな微笑みに戻って仲間と語らい合っていた。
(気をつけよう、あの人には、特に…)
リョーマはグンとスピードを上げ、最後尾からトップに躍り出てフィニッシュした。
それから暫くは特に変わったことのない平穏な日々が続いた。
だが、「特に何もない」ことを伝えるだけでも、リョーマは手塚に唇を寄せた。
「………」
触れ合っていた唇をそっと離し、リョーマはすぐに手塚から顔を逸らした。
(赤くなってる顔なんて見せられない)
手塚は何とも思っていないであろう行為を、リョーマの方が気にしていると知られてしまったならば、もしかしたら、今後はこの方法を使ってくれなくなるかもしれない。
(そうしたら、二度とこの人には触れられなくなる)
仕事だと割り切っている手塚だからこそ、自分も割り切っているのだと振る舞えば、こうして堂々とリョーマからも触れられるのだ。
「…そうか」
ぼそっと小さく呟かれ、リョーマは自分の心の声が手塚に聞こえてしまったかと、一瞬ドキッとした。しかしそんなはずもないと思い直し、平静を装って手塚を見上げる。
「部長からは、何も言ってくれないんスか?」
「ん?……ああ…」
まるで甘い囁きをねだっているような言葉で、その後の経過はどうだ、とリョーマは訊いた。
手塚は小さく頷き、カメラを意識してか、優しくリョーマの髪を撫でた。
「……いよいよ校内ランキング戦が始まる」
「は?……ああ、そっスね」
「気を抜くなよ?」
リョーマの瞳をじっと見つめながら話す手塚の言葉の意味を、リョーマは推し量る。
手塚が言う「気を抜くな」は、単に試合に負けるなというだけの意味ではないのだろう。
ランキング戦が始まれば、部員たちの意識は試合が行われるそれぞれのコートへ集中する。だがその間、試合に出ていない者へは、意識はほとんど向けらない状態になるということだ。
(向こうもオレたちに探りを入れてくるとしたら、ランキング戦の最中かも)
「………っス」
しっかりと手塚の瞳を見つめ返してリョーマが頷くと、手塚ももう一度小さく頷いた。
「ねえ、部長」
「なんだ?」
「私服でデートとか、してくれないんスか?」
「え?」
「や、いいっス、今のナシ、ウソ」
手塚の眉間に小さく皺が寄ったのを見たリョーマは、慌てて自分の誘いを撤回した。
「じゃ、もうオレ、教室に戻るっス」
小さく苦笑してリョーマが手塚に背を向けようとしたその時、いきなり腕が強く掴まれて引き止められた。
「いっ……痛…」
「ランキング戦のあとなら……」
「え……」
リョーマが目を丸くすると、手塚も一瞬ハッとしたように目を見開き、強く掴んでいたリョーマの腕を放した。
「……ランキング戦のあとなら、時間を作る」
「マジ…?」
「ああ」
至極真面目な顔で頷かれ、リョーマは「ああ」と理解した。
(なんだ、仕事の話がしたいだけか)
「じゃあさ、オレがブロックで全勝したら、なんかご褒美くれる?」
「褒美?」
「そ、ご褒美。約束っスよ?じゃ」
困惑した手塚から拒絶の言葉が出る前にと、リョーマは急いで踵を返して屋上を後にした。
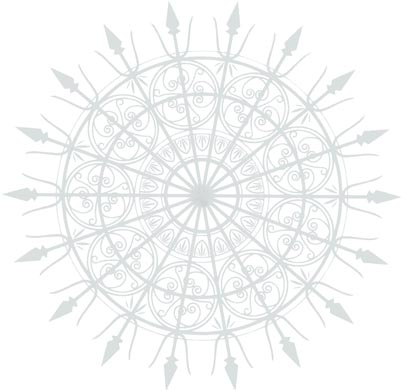
青学テニス部校内ランキング戦は、リョーマが想像していたのよりもずっと大々的に行われた。
「Dブロック、越前リョーマ、6ー0っス」
試合結果を副部長に報告し、次の試合に備えて身体を冷やさない程度に休憩を取る。
「スゴイね、リョーマくん、6ー0なんて!」
「べつに」
ランキング戦開始から同級生三人がリョーマに貼り付き、どこに行くにもついてくる勢いだ。
まさかリョーマを見張っているわけではないのだろうが、この状況では迂闊に他のレギュラーに注視することも出来ないし、手塚の元へ行くことも出来ない。
(部長も全部勝つんだろうな)
報告がてら視線を走らせたホワイトボードには、すでに手塚の勝利が書き込まれていた。
(あの人はあの人で、着々と自分の仕事をこなすんだ…)
誰にも頼らず、自分だけの力で。
確かにリョーマも自分の力でレギュラーの座を勝ち取るつもりではいるが、どうしても手塚の行動が気になるし、その姿を探してしまう。
頼っているわけではないと思いたいが、そう言い切るには、自分にとって手塚の存在はあまりに大きいと、リョーマは思う。
(ま、だからこそ、あの人に見限られないように、きっちり仕事はこなさなきゃね)
ふぅと大きく溜息を吐くと、背後でクスクスと笑う声が聞こえた。
「ぁ、不二先輩!」
傍らにいた同級生が、少し緊張した声を発した。
(不二、周助…)
リョーマはチラリと背後に視線を走らせ、適当に、軽く会釈した。
「調子はいいみたいだね、越前」
「まあまあっス」
穏やかに話しかけてくる不二を、内心ではひどく警戒し、表面では飄々として、リョーマは答える。
「確かキミ、今日の最後の試合は、海堂と当たるんだよね」
「はぁ」
「楽しみにしてるよ」
「ども」
終始笑みを絶やさないまま、不二はその場を立ち去った。
肩越しに不二の背中を見送り、リョーマは小さく眉を寄せる。
(やっぱりスキがない)
会話の途中で一瞬でも表情の変化があれば見逃さない自信がリョーマにはある。だが不二の表情は、一瞬たりとも崩れる気配がなかった。
だが、だからこそ、その笑みが『完璧に作られた仮面』である気がしてならない。
(だとしたら、不二周助は、このランキング戦の最中は、動かない)
敵に油断が生じるかもしれない時だからこそ、敢えて、その隙をつくような画策はしない。
不二周助という男をよく知っているわけではないが、リョーマには、そう感じ取れた。
「ホント、気が抜けないって感じ」
ボソッとリョーマが呟くと、すぐ隣にいた同級生が目を丸くした。
「当たり前だろ、越前!大体なぁ、一年生が一学期のランキング戦にエントリーされるってことだけでもすごいことなんだぜ!」
「………」
すぐ隣にいるというのに大音量で話すのが「堀尾」という名前だというのを、リョーマは真っ先に覚えた。これだけ目立つ言動の人間も珍しいと思う。
(そのくせ案外小心者で)
リョーマがじっと見つめると、堀尾は困惑したようにモゴモゴと何か呟きながら視線をずらす。
(これが演技だったらスゴイよな…)
リョーマはキャップを深く被り直して表情を隠しながらクッと小さく笑った。
(心から信じられるのが部長だけって……思っていたよりしんどいな…)
この『仕事』を選んだ時から覚悟はしていた。これほど多くの同年代の者に囲まれながら、そのほとんどには心を開いてはいけないということを。
アメリカではずっと大人たちに紛れて育ってきたから、友人がいない孤独感など、今さら感じることはないのだと思っていた。
だが、ただ『友人がいない』のと、『友人を作ってはいけない』のとでは、感覚も感じ方も違ってきてしまう。
寂しい、などと甘ったれたことを言うつもりはないし、そんなふうに心に隙間を作るのは致命傷に繋がりかねないこともわかっている。
だが、人間の心を捨て切れているわけでもない。
(ホント、まだまだのまだ、ってヤツか…)
父によく言われた台詞を心の中で、自分に向けて言い放つ。
(部長は……あの人は、もう、全然平気なのかな…)
ふと、コートの奥に視線を向けると、二年生同士の試合を真剣に見つめる手塚の姿が目に留まった。
(いや、もしかして、アンタも………)
そう思おうとして、リョーマは小さく苦笑した。
(それはオレの願望、か…)
手塚の心に少しでも人の温もりを恋しいと思う隙間があったら。
いや、ほんの少しでもそんな隙間があってくれたら。
自分が埋めてやるのに、と。
(ヤバいな……もう、こんなにハマっちゃってる……?)
何度も唇に触れてしまったせいなのか。
想いが、抑えきれないほど熱を伴って溢れ出てくる。
信頼、という言葉だけでは言い表せない想い。
憧れ、という域を超えてしまった想い。
「マジでヤバい」
ぼそりと呟いたリョーマの言葉は、誰の耳に届くこともなく風にかき消されていった。
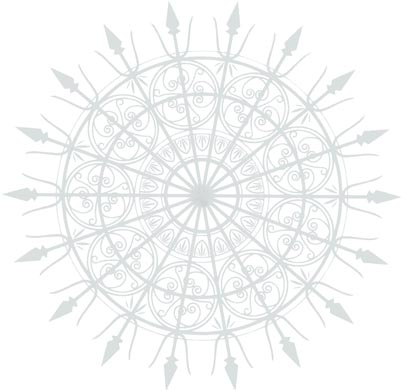
数日間に渡った校内ランキング戦が終わった。
その日のうちに新レギュラーが発表され、リョーマは晴れて、青学レギュラーの一人に名を連ねることとなった。
「全勝したっスよ」
部員がいなくなった頃を見計らって部室に引き返してきたリョーマは、案の定一人居残っていた手塚にいきなりそう切り出した。
「ああ。よくやった」
部の日誌を書いているらしい手塚は、肩越しに振り返ってそう言うと、少し沈黙してからまた口を開いた。
「……どこか行きたいところはあるのか?」
「へ?」
「だから、私服で出かけたいのだろう?行きたい場所を考えていなかったのか?」
「あ……えーと」
リョーマが口籠ると、手塚はやれやれというように深く溜息を吐いた。
「その件で引き返してきたんじゃないのか」
「いや、そ、それは、そ…う、なんスけど…」
まさか手塚の方からデートの話を切り出してくるとは思わなかった。おかげでリョーマはかなり動揺してしまっている。
そんなリョーマを暫し見つめてから、手塚は徐に視線を手元に戻した。
「ぁ……あの…」
「もうすぐ終わる。そこで少し待っていろ」
「ういっス」
リョーマはドアに寄りかかると、小さく小さく、溜息を吐いた。
(「今日は帰れ」って、言われるかと思った)
あの屋上での『約束』が有効であることを確かめられたらそれだけでいいと思って、リョーマはここに戻ってきた。
それなのに、『有効』どころか、この雰囲気ならば待ち合わせ時間や、デートのコースまで決めることになるかもしれない。
(部長とデート…)
リョーマは思わず口元を綻ばせ、だが、そんな自分の表情に気づいて慌てて俯いた。
(ヤバい……嬉しい…)
俯いているせいではなく、どんどん頬に熱が集まってくるのがわかる。
(部長は仕事だから仕方なく付き合ってくれるにしたって、オレはちゃんとデートのつもりでいればいいんだ)
そうすれば、その日一日がどんなに楽しい時間になることだろう。
「やった…」
「………」
小さく小さく呟いたリョーマの言葉に、手塚の肩が微かに揺れる。
だが俯いたままのリョーマは、それに気づくことはなかった。
家に帰り着いたリョーマは、自室に駆け込み、制服のままベッドにダイブした。
暫く俯せのままじっとしていたが、時折両脚をパタンパタンと動かし始め、やがてパタパタと、バタ足をするようにリズムを上げてゆき、またピタリと動きを止めた。
枕を抱え込んで、ごろりと仰向けになる。
頬は上気し、瞳がわずかに潤み、口元は柔らかく綻んでいる。
「やった……明後日、部長とデートだ……」
呟いてククッと笑い、枕をギュッと強く抱き締めて今度は横向きになる。
「青龍…」
リョーマはゆっくりと目を閉じて微笑んだ。
ふわりと、ついさっきまで一緒にいた手塚とのやり取りが蘇る。
「明後日でいいか?」
日誌を書き終えた手塚が、レギャラージャージを脱ぎながら唐突にそう言った。
「え?」
「何か予定があるのか?」
「い、いや、べつにないっス」
ブンブンと首を横に振るリョーマを一瞥して、手塚は淡々と続ける。
「ならば明後日の………そうだな……、十時くらいでいいか」
「ぁ、ういっス。待ち合わせとかは……」
「お前の家の最寄りの駅でいい。改札に十時、だ」
「ういっス」
リョーマがニッコリ笑って頷くのと、手塚の着替えが終わるのはほぼ同時だった。
「帰るぞ」
「日誌はいいんスか?」
「明日の朝、先生に渡すからいい」
「ふーん」
「……ああ、そうだ」
「え…」
リョーマの傍で立ち止まった手塚が、いきなりリョーマの肩を抱き寄せ、唇を寄せてきた。
「わっ、んん……っ」
手塚の唇がリョーマの唇に触れながら、ゆっくり動く。
ランキング戦の間変わったことなかったか、と訊かれた。
(あ、そうか、制服着てるから…)
リョーマはそっと手塚の身体を押し返し、視線をずらして首を横に振った。
「………嫌だったか?」
「え?」
「ここではしたくなかったか?」
「ぁ……」
言うまでもなく、この部室にもどこかにカメラは設置してある。しかも、屋上にあるものよりも距離が近い分、その表情や視線の動きなども鮮明にわかることだろう。
だから、今リョーマが「言葉で」答えずに「首を横に振った」という行動の意味を、カメラの向こうの存在に納得させなければならない。
そうでなければ、二人が唇を寄せ合っていた行為が、「キスではない」ことがバレてしまうからだ。
「ぁ、ごめ……そうじゃなくて……え、っと……」
「ん?」
「い、いきなりだったから……ビックリしただけ……」
「そうか……すまなかったな…」
「べ、べつに……」
しどろもどろにリョーマが答えると、手塚がもう一度リョーマを引き寄せ、だが今度は額に口づけてきた。
「わ」
「いちいち驚くな」
「だ……って、こんなの、慣れてなくて……」
「じゃ、断ればいいんだな。キスするぞ」
「え……」
手塚の両手で頬を包まれ、まるで本当に口づけを交わすようにそっと唇が押し当てられる。
だが、唇から伝わってくるのは、甘い想いではなく。
『古い資料を見ていて気づいたことも明後日教える』
『外だと、そう言う話はマズいんじゃ』
『ああ、だから本当の待ち合わせは、別の場所にしよう』
一旦唇を離し、見つめ合う。
そうして今度はリョーマから唇を寄せた。
『ウチに来ますか?』
手塚が小さく目を見開いた。
『いいのか?』
唇を触れ合わせながら、リョーマは小さく頷く。
『ウチならセキュリティも完璧だし、明後日はウチに誰もいなくなります』
『……わかった。尾行を撒いて九時半頃にお前の家に行く』
『オレも九時くらいに一旦家を出て、尾行を撒いてすぐ家に戻ります』
『出来るのか?』
小さく眉を寄せる手塚に、リョーマはムッとして唇を離す。
だが小さな溜息をひとつ零してから、手塚を引き寄せるようにして唇を寄せた。
『それくらい出来なかったら、アンタのパートナーには選ばれないでしょ』
それだけ言って唇を離し、手塚に向かってニッと笑ってみせると、手塚も小さく溜息を吐いてから微かに頷いた。
「………帰るか」
「ういっス」
ドアを開けて二人は外に出る。
もう少しで完全に沈む夕日から放たれる、柔らかな橙黄の光に背後から照らされて、足下には二つの長い影が伸びる。
(久しぶりに長く話しちゃったな)
端から見れば、長い長い口づけに見えたことだろう。
唇を触れさせるだけのキスではなく、唇を動かして、まるで濃厚に舌を絡め合っているかのように見えたかもしれない。
(本当のキスって、どんな感じなんだろう…)
チラリと、リョーマが手塚に視線を向けると、手塚は「なんだ?」という顔で首を傾げた。
「や……べつに……」
ぎこちなく笑うリョーマに、手塚は訝しげな視線を向ける。
だが、その先を、手塚は訊いて来ようとはしない。
リョーマが心の扉を閉じてしまえば、その扉を無理矢理こじ開けて踏み込んでくるようなことを、手塚は決してしないのだ。
(これが、今のオレたちの距離、か)
隣を並んで歩いていても、唇を触れ合わせることはあっても、その心は決して触れ合うことはない。
「いつか……アンタと手、繋いで歩いてみたいな」
「え……」
「デートで」
「………」
黙り込んでしまった手塚の表情は、きっとどのカメラにも捉えられてはいない。そのおかげで手塚は素直に心情を表情に表せているのだろう。
驚きと、困惑と、微かな嫌悪と─────様々な思考が絡み合った複雑な表情は、「恋人」から「手を繋ぎたい」と言われた時のそれとはほど遠いものだ。
だが制服に取り付けられているマイクは、その表情を、音声だけを聞いている者たちへは伝えない。
だから手塚は、言葉ではいくらでも「リョーマの恋人」を演じることが出来る。
「……じゃあ明後日、手を繋いで歩けばいい」
「あは、マジ?やった!」
マイクでも弾んだ声が拾えるように、リョーマは少し大袈裟に喜んでみせる。
街を歩くことのない『デート』で、いつ、どこで「手を繋いで歩く」ことがあるのだろう。
「オレ、まだこっちに来て美味しいアイスとか食べてないんだよね。部長、どこか美味しいところ知っていたら連れて行ってくれません?」
「ああ。…俺もあまりそういう店は詳しくないが、探しておく」
「ありがと、部長」
リョーマがニッコリ笑いかけると、手塚はまた小さく眉を寄せた。
(表情も演技してくれればいいのに)
リョーマの微笑みが苦笑に変わると、手塚は小さく溜息を吐いて視線を逸らした。
「明後日楽しみっスね」
「ああ、そうだな」
(あ…)
言葉でだけなら、少し「恋人気分」を味わえることにリョーマは気づいた。
(そっか、「表情」見なきゃいいんだ)
「アメリカにいた時なんか毎日アイスとか食べてたっスよ。でもあっちのアイスは甘過ぎて、暫く食べてると気持ち悪くなってきたりしてさ」
「向こうのは色もすごいからな」
「そうそう。ブルーのケーキとか、蛍光色のクッキーとかあるんだから……怖くて食べたことないけど」
「俺もごめんだな」
「だよね」
クスクス笑いながら手塚の方を見そうになり、リョーマは慌てて視線を前に戻す。
(うん、部長の顔見なければ、案外幸せなシチュエーションだ)
そう考えると、手塚の制服にマイクが仕掛けられたことはラッキーだと思えてくる。
そのマイクのおかげで唇を触れ合わせて「会話」をしなければならなくなったのだし、今も、こうして言葉だけの「恋人ごっこ」も出来る。
何でも物事を前向きに考えるのは、リョーマの得意技のひとつだ。
(私服じゃなくて制服でデート、とか言えばよかった)
そうすれば、ずっと恋人気分でいられるのに、と。
(ぁ、それじゃ「仕事」になんないじゃん)
自分の思考回路の矛盾に気づき、なんだかおかしくなってきてリョーマはぷっと吹き出した。
「…どうした?」
手塚が柔らかな声音で尋ねてくる。
「……オレ、ずっと独りだったから、誰かとこんなふうに楽しい会話が出来るのって、なんか嬉しくて……変なこと考えそうになっちゃった」
「変なこと?」
「また怒られそうなこと。ぁ、アンタは気にしなくていいから」
手塚の方を見ずにリョーマがそう言うと、手塚が小さく溜息を吐くのが聞こえた。
「越前」
「はい?」
前を見たまま返事をすると、いきなり腕を引かれて手塚の方を向かされた。
「な…」
「キスするぞ」
「え?ぁ………んんっ」
いつになく乱暴に唇が押し当てられる。
「?」
だかしばらくしても、手塚の唇が、言葉を伝えてはこない。
訝しく思ってリョーマが目を開けると、眉をきつく寄せた手塚に見つめられていた。
(部長?)
リョーマが困惑していると、手塚がゆっくりと目を閉じた。
そして。
『仕事に集中しろ』
と。
それだけを一方的に伝え、リョーマを突き放すようにして身体を離した。
「……誰かに見られたらどーするんスか」
そんな険しい表情を。
どう見ても恋人とキスをしたようには見えないその表情を、他の組織の連中に見られたら、今までの苦労が水の泡だ。
(アンタが、オレのこと好きじゃないのがバレちゃうじゃんか)
「………すまない」
リョーマに背を向けたまま手塚が呟く。
「べつに。オレは嬉しいからいいけど」
「……」
リョーマはクスッと笑って、手塚の横を擦り抜ける。
「そろそろバス来るんじゃないっスか?行こう、部長」
「………ああ」
手塚がまた溜息を吐く。
(オレといると、ホント、溜息ばっかだね、部長)
長く伸びる二つの影に視線を落として、リョーマも小さく溜息を零した。
それからバスの中も、駅に着いても、ホームで電車を待つ間も、電車の中でも、二人は一言も言葉を交わさなかった。
だが別れ際に手塚が小さく呟いた。
「……褒美は何がいいのか、明後日までに考えておけよ」
「え?」
「全勝したら、何か褒美が欲しいと言っていただろう」
「ぁ……ういっス。考えときます!」
手塚を真っ直ぐに見上げてリョーマが嬉しそうに微笑むと、手塚の表情がほんの一瞬和らいだ。
「じゃあな」
「はい」
リョーマがホームに降り立つとすぐにドアが閉まり、手塚を乗せた電車がゆっくりと動き出す。
車内の奥にいる手塚の姿はホームからはもう見えなかったが、電車が見えなくなるまで見送り、リョーマはゆっくりと踵を返した。
「ホントにご褒美くれるのかな」
呟いてみて「まさか」と自分で否定する。
それでも、束の間、恋人のような会話ができたことが、今日はとても嬉しかった。
(そうだ、アンタといっぱい話せるように、オレももっと気合い入れていろいろ探ってみるか…)
どこから手をつければいいのかは、今は思いつかないけれど。
仕事絡みだろうとなんだろうと、少しでも長く手塚と二人でいられるなら嬉しい。そうして、その時にほんの一瞬でもあの柔らかな微笑みを向けてもらえるなら、何だって出来る気がする。
「よしっ」
リョーマは小さくガッツポーズを取ると、改札へ向かって走り出した。
「そうだ、もっと頑張んなきゃ」
ぼそりと呟き、リョーマはガバッと身体を起こした。
「オレに出来ることは限られてるだろうけど……」
自分だからこそ出来ることだってあるはずだ、とリョーマは思う。
「さしあたっては、テニス部にいる他の組織のヤツらのあぶり出し、かな…」
少しでも手塚が動きやすくなるように、相手の動きを探ってみようと思う。
「よし、なんか書くもの…」
ベッドから降りて筆記用具を出そうとバッグを漁る。
「?」
そのバッグの奥の方に、一通の封筒を見つけた。
「なんだ?これ」
宛名はリョーマの名前になっている。差出人の名は、ない。
「ふーん…」
リョーマはまず証明に透かして封筒の中身を探る。
「特に妙なものは入っていない、か」
封はされておらず、だがリョーマは注意深く中の便せんを取り出して広げた。
「なに…」
そこにはこう書かれていた。
『手を引かなければ大事なものを壊す』
ゴクリと、リョーマの喉が鳴る。
「キョーハク状、ってヤツ…?」
いつバッグの中に入れられたのだろうかとリョーマは考える。
だが、ざっと考えただけでもうんざりするほど、リョーマのバッグにこの封筒を入れるチャンスがあったことを思い出す。
部活中はコートに出ている間バッグは部室に無造作に置かれていたわけだし、授業中だってバッグを教室に置いたまま別教室に移動したこともある。
乱暴に言ってしまえば、誰にでもこの封筒をリョーマのバッグに入れるチャンスがあったということになる。
「ふーん…」
リョーマはひとつ溜息を吐くと、口元を歪めてニィッと笑った。
「いいじゃん。こーゆーシリアスな感じ、気合いが入るね」
手塚のことを考えていた時とはまるで別人のような顔つきで、リョーマはその「手紙」を見下ろした。
気高き白い虎が、その牙を表し始めた。
TO BE CONTINUED...
20090615
|

