<2>
好むと好まざるとに関わらず、自分は『諍いの女神』に見入られているのではないかと、リョーマは思った。
手塚に屋上で釘を刺されたその日のうちに、リョーマはまた、放課後の部活で例の荒井と無許可の『試合』をした。
テニス部員どころか、グラウンドで練習していた他の運動部の連中も騒ぎを聞きつけてコートの周りに集まり、存外大騒ぎになってしまった。
(ヤバい……また怒られる…)
目立つ行動はダメだと、頭ではわかっていたことだが感情が言うことを聞いてくれなかった。
リョーマのラケットが隠され、使い物にならないような古びたラケットを使えと言われた。
理不尽な条件を突きつけて自分を貶めようとする相手を、リョーマは許すことなど出来なかった。
もちろんリョーマは圧倒的な実力の差を見せつけて勝利し、テニス部員のみならず、校内でも一目置かれる、ちょっとした有名人になってしまったことだろう。
(嫌われるかな…)
忠告を無視して────無視したつもりはないが、無視するような形になってしまって────手塚が怒らないはずがない。
(謝っておいた方が、いいよな…)
罰としてその場にいた全員でグラウンドを走らされながら、リョーマは眉を寄せて奥歯を噛み締める。
(怒らせたいわけじゃないのに…)
自分が手塚を信頼するのと同じくらい信頼して欲しいとは言わないが、その半分でも、いや、四半分でもいいから信頼して欲しいと思うのに、うまくいかない。
(とにかく謝って、もうしないって約束して、それから……)
グルグルと手塚の許しを請う手順を考えていて、リョーマはハタと気づいた。
(……らしくないな、オレ…)
思わず苦笑が漏れる。
今まで、父親やいろいろなことを教えてくれた『教師』たちには、ひどく怒られたとしても、こんなにも言い訳めいたことを考えたり、必死に取り繕う方法を悩んだりしたことはなかった。
これほど、関係の悪化を、恐れたことなどなかった。
おそらくは、自分が今まで生きて来て初めて、心の底から「嫌われたくない」と思っている人物に出会ってしまったのだろう。
(絶対、アンタが必要としてくれるような男に、オレは、なってみせる)
だから。
どうか、見限らないで欲しい。
女々しく追い縋るつもりは毛頭ないけれど、もうこれ以上、迷惑は掛けないから。
(部長……いや、青龍…)
心の奥で、リョーマはその名を何度も何度も呟いた。
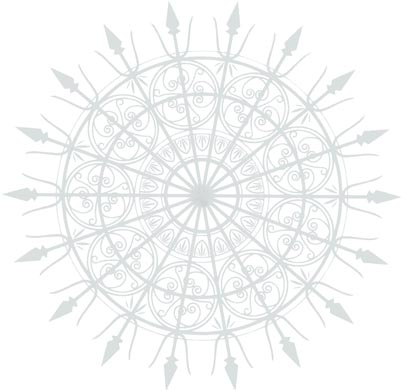
「……すみませんでした」
翌日になって、昼休みにリョーマの方から手塚を屋上に連れ出し、開口一番そう言って頭を下げた。
結局昨日は、罰走としてグラウンドを走った後、手塚と二人きりにはなれなかったのでちゃんと謝れなかった。
「………」
手塚はリョーマに背を向け、腕を組んだまま何も言わない。
暫くそのまま二人の間には沈黙が流れ、他に誰もいない屋上には、まだ少し冷たい風が通り過ぎる音だけが静かに響いた。
「……俺が一年の時にも、俺のことが気に食わないと言って、何かと絡んでくる先輩がいた」
「え…?」
間違いなくまた小言を食らうだろうと覚悟していたリョーマは、ポツリと、手塚から意外な話を切り出されて目を丸くした。
「その先輩から試合を申し込まれて……俺なりに目立たずに穏便に済ませようと思っていろいろ考えたんだが、結局はその先輩の怒りを買う形になってしまった」
「そ、それで…」
「試合のあと、ラケットで殴られた」
「!」
手塚がゆっくりと自分の左腕を、特に肘のあたりを、そっと撫でる。
「左腕をやられて……案外重傷で…もうテニスは出来ないかと思った」
「そんな……ぁ、でも、今もテニス続けていられるってことは、治ったんスよね?」
手塚は短く沈黙し、溜息を吐いてからリョーマを振り返った。
「あの時……もしもお前のように俺も全力で戦っていたら、先輩の怒りを買うことはなかったのかもしれないな」
「…部長…」
スッと、手塚がリョーマから視線を逸らす。
「俺は、他人の『感情』というものに関心がない。他人が何を考え、俺に対してどんな感情を持っているかなど、仕事に差し支えがないなら、どうでもいいことなんだ」
「……」
「組織の先輩たちに、そんな俺がなんて呼ばれているか、知っているか?」
リョーマは俯き、一瞬躊躇ってから静かに首を横に振った。
「ロボット」
「……」
「俺には血も涙も感情もなく、ただ指令を受け、それを忠実にこなすロボットなんだと」
「そんなこと…っ!」
「そうだな。本当にロボットならば、ラケットで叩かれたくらいで怪我もしないだろうに」
「そう言う…意味じゃなくて…」
「越前」
手塚は、揺るぎのない瞳で、リョーマを、見た。
「お前の行動は、俺から見たら無駄が多くて、突発的で、感情的で、非論理的にしか見えない」
「ぅ……」
「だが……お前には、人を惹き付ける何かがある」
「え…」
「俺にはない不思議な力を、お前は持っているようだ」
笑みこそしなかったが、とても柔らかな瞳で手塚にそう告げられ、リョーマはふわりと頬を染めた。
「だからお前は、今のままでいいのかもしれない」
「……」
「…今後は、俺が指示するまで、お前は一切動くな」
「え…?」
「お前は当分、テニスだけに集中していろ」
「そ、それって、どういう意味っスか!」
(暫くこの仕事から外すってこと?)
必死に食い下がるリョーマに、手塚はほんの一瞬だけ、小さく小さく、微笑んだ。
その次の瞬間。
(え?)
リョーマの身体はいきなり手塚に引き寄せられ、昨日のように、いや、昨日よりも近く、顔を寄せられた。
「ぶちょ…」
「…読み取れよ」
こんなに近くでも聞き取れないほど小さな声で囁かれ、両頬が手塚の手に包まれた。
「え?ぁ………んぅっ???」
(な…っ?)
リョーマの頭の中が、一瞬真っ白になった。
(キス……?)
手塚の唇が、リョーマのそれに優しく触れている。
思わず、リョーマはギュッと目を瞑った。
(ど、して…?)
バクバクと心臓が高鳴り、耳鳴りが起きたかのように周囲の音が聞こえなくなる。
だが。
「?」
手塚の唇が、少し奇妙に動いた。
(え?)
手塚の唇が、リョーマの唇に触れたまま、動く。
(なに、これ……まるで、なんか、喋ってるみたいな……「喋る」…?)
リョーマはハッとして目を見開き、手塚の瞳を見つめた。
唇を触れ合わせたまま、手塚が小さく頷く。
(『読み取れよ』って、唇を、読めってことか)
リョーマも頷き、なんとかして心を落ち着かせ、そっと目を閉じて手塚の唇の動きに集中する。
(「あ」「さ」「れ」「ん」「の」「と」「き」「せ」「い」「ふ」「く」「に」「ま」「い」「く」「つ」「け」「ら」「れ」「た」)
『朝練の時、制服にマイクつけられた』
思わずリョーマは目を見開いて手塚の身体を押し返した。
「ぶちょう…?」
(誰に…っ)
「すまない、もう少し…」
そう言って手塚がまた唇を寄せてくる。
(「ぎゃ」「く」「に」…)
『逆に利用して、相手を油断させる。話を合わせろ』
伝えられた手塚の言葉に、リョーマはコクコクと頷く。
「………」
手塚は、ゆっくりとリョーマから唇を離した。
「……上からの指示も、当分はお前には伝えない。お前を巻き込みたくないんだ。わかってくれ」
演技だとわかってはいるが、リョーマの心臓は早鐘のように激しく鳴り続け、頬も、火が噴きそうなほど熱くなっている。
(仕事だからって、コンナコトまでして口に出せない『方針』を伝えるなんて……この人はやっぱ、プロなんだ…)
自分ならこんな真似は出来ないとリョーマは思う。
先日も生徒会室でこの方法を試みようかと思ったが、『見られてると恥ずかしい』という言葉に置き換えて、大まかな意志を伝えるに留めてしまった。
だが手塚は、あっさりと、冷静に、この方法を選んで実行できている。
(やっぱ、すごい人だ……青龍…)
感心するとともに、リョーマの心に切なさが込み上げて来た。
(じゃあ、ここに来てからの部長の話は、全部、演技……)
先輩から暴力を受けた云々は本当のことかもしれないが、自分にはないリョーマの不思議な魅力に惹かれた、というような言葉は、全部演技だったのだろう。よく考えてみれば、唐突に手塚がそんなことを言い出した時点で、「おかしい」と思わなければいけなかったかもしれない。
(でも、嘘でも嬉しかったな…)
嘘でも、演技でも、あの柔らかな瞳をもう一度見ることが出来て、とても嬉しいと感じた。リョーマの個性を受け入れると言ってくれた、その言葉に心が震えた。
(あの言葉が全部本当だったら、今頃きっとオレは……この人と…)
もしも、手塚が自分を求めて来たら、求められただけ与えてしまっていただろうとリョーマは思う。
(オレ…って……こういうヤツだったっけ…?)
手塚と一緒にいると、自分がどんどん変えられていく気がする。
(オレにとってこの人は、何、なんだろう…)
リョーマがじっと手塚を見つめていると、手塚がまた唇を寄せて来た。
思わず甘い声をあげそうになってしまい、リョーマはまたギュッと目を閉じて、吐息さえも零さないように堪える。
「………」
どこか躊躇うような間を開けてから、手塚の唇が動く。
『上からの指示は、直接、俺がお前に伝える』
リョーマはまた頷く。
手塚はまだ離れない。
『先生にも、お前を暫く仕事から外すと伝えておく』
リョーマは目を開けて、怪訝そうに手塚の瞳を見つめる。
『なんで、オバサンに言わない?』
今度はリョーマから尋ねた。
手塚は一旦唇を離し、小さく眉を寄せた。
「……このことは、俺とお前だけの秘密にしてくれ。誰にも邪魔されたくない」
リョーマはドキリとした。
仕事のことを言っているのはわかるが、手塚の言葉が、そのまま二人の『甘い関係の始まり』を意味するものであればいいと思ってしまう。
(やっぱオレ、『そう言う意味』で、この人に惹かれてる…んだ、な…)
しかし。
ふと気を引き締めて手塚の言葉の意味を考え、リョーマは眉を顰めた。
(今の言い方だと、オバサンのことも疑ってるってこと?……この前は信頼してるって、はっきり言ってたのに…?)
背伸びしてリョーマから唇を寄せていき、手塚にそう尋ねてみると、手塚は少し考えてから『今はまだわからない』と言った。
(何か、あったのかな……)
つい先日も竜崎と話をしたが、リョーマの前では、竜崎の態度に変なところはなかった。
むしろ、竜崎は『上』の方針には同意しかねていて、手塚の身の潔白をリョーマとともに証明したいと思っているような口ぶりだった。
(でも、この人がオバサンにも黙ってオレに行動させるって言うんだから、きっと、オバサンにも不審なところが何かあるんだ)
手塚の言葉を、態度を、方針を、リョーマは疑うつもりは微塵もない。
(オレは、アンタのこと全部信じるって決めてるんだ)
納得したという意味を込めてリョーマが頷くと、手塚がまたリョーマの唇に触れてくる。
『とにかく、お前は暫く待機状態だと思わせることにする。その間に、お前にはやってもらいたいことがある』
手塚のその言葉に、リョーマは瞳を輝かせた。
間近で見つめる手塚の瞳が、一瞬、戸惑うように見開かれる。
『……細かい指示は追々出すが、まずは暫く桃城や不二、その他にも、妙な動きをする者がいないか見張れ』
手塚の指示に、リョーマは素直に頷く。
『アンタはどうすんの?』
『俺はもう一度古い資料の洗い直しをする』
そこでやっと二人は唇を離した。
自分の唇に手塚の唇の感触や温もりが残っていて、リョーマは思わず赤面して俯く。
「……いきなりすまなかった。気持ち悪かったか?」
手塚が親指でリョーマの唇をグイッと拭ってくれる。
まるで自分が触れて、リョーマの唇を穢してしまったと言うように。
「そんなこと…」
何度も唇を拭ってくれる手塚の手を、リョーマは両手で包み込んだ。
「ビックリしたけど、アンタならいい」
「………」
手塚の手が微かに揺れ、その心がほんの少し動揺したのがリョーマにはわかった。
「オレはアンタのこと、全面的に信頼してるって言ったでしょ。アンタになら、何されてもいい」
「………」
困惑したような瞳で、手塚がじっとリョーマを見つめている。
リョーマは、そんな手塚にふわりと微笑みかけた。
「でも、こんなに長い時間キスしたのは生まれて初めてっス」
「初めて、だったか?」
手塚がハッとしたように尋ねてくる。
「……オレがどこで生まれたと思ってるんスか。オレの唇なんて、記憶にない赤ん坊の頃にとっくに奪われてるっスよ」
「………」
「じゃ、オレ、そろそろ教室に戻ります」
「ああ…」
手塚に小さく笑いかけ、リョーマはゆっくりと踵を返す。
「越前」
すぐに手塚に呼び止められ、リョーマは振り返った。
「明日は、昼に委員会があるから都合が悪いんだが、明後日…また昼にここで会えるか?」
「よろこんで」
ニッコリ微笑んでリョーマが頷くと、手塚は少し硬い表情で頷いた。
「また、キスしてね、部長」
「………ああ」
手塚が頷くのを確認してから、リョーマは屋上をあとにした。
(キス、しちゃった…な…)
階段をゆっくり下りながらリョーマは自分の唇に指先で触れてみる。
(キス…じゃ、ない、か…)
ぐっと、胸の奥に重い塊が込み上げて来た。
「苦し…」
手塚には平然と振る舞ってみせたが、アメリカで育ったからと言って、キスに慣れているなんてことはない。
マウス・トゥ・マウスのキスは、好きな人とだけしたいと思っていた。
そして好きな人とするキスは、きっと優しく甘い味がするのだろうと思っていた。
女の子ほどではないが、それなりに、いろいろなシチュエーションを夢見ていた。
「最初のキスが、仕事絡みって、……きついね」
何より切ないのが、相手に何とも思われていないことだ。
(オレは、あの人のこと大好きだけど……あの人は、きっとオレのことなんか…)
はぁ、と、深い溜息が零れた。
(明後日、また、部長とキスするのかな…)
胸の奥が痛くなるような、想いの通い合わない、冷たいキスを。
「オレも、まだまだ、だね…」
もう一度短く溜息を吐き出し、数段残った階段を、リョーマは一気に飛び降りた。
TO BE CONTINUED...
20090224
|

