<1>
いつ来てもいいと言われたので、早速翌日リョーマがテニス部を覗きに行ってみると、その日はちょうど手塚も含めたレギュラーたちが他校に遠征に出かけて不在で、コートは閑散としていた。
だがそこでリョーマは、二年生の桃城という男に会った。
「かよわい新入生をカモっちゃーいけねぇなあ、いけねーよ!」
リョーマの同級生たちをカモにしていた上級生部員を適当にあしらっている時に、桃城は現れた。
(あ…)
リョーマがこの男と会ったのは、ここが初めてではなかった。
先程リョーマは、下駄箱のところでこの男にコートへの行き方を尋ねたのだ。
もちろんリョーマはコートの場所など知っていたが、この男の、不思議な雰囲気に興味を持ったから声を掛けたくなった。
(やっぱこの人、ニヤニヤ笑ってんのに、瞳の奥が、全然笑ってないんだよね)
人当たりよく、軽い口調で話している割に、男の目が笑っていないことに、リョーマは少々関心を持った。
(ヘーキでウソ教えるし……どっかの「組織」の人かも)
生徒を疑い始めればキリがないとは思うが、この男だけは、「間違いない」と、リョーマの本能が訴えてくる。
(気をつけないと…)
成り行きで桃城と試合することとなり、コートで対峙しながらリョーマはじっと桃城を観察する。
桃城もレギュラーらしいが、今回は足の怪我のために遠征には出かけなかったようだった。本人は隠しているようだったが、微かな湿布薬の匂いで、リョーマにはすぐにわかった。
「バアさんから聞いたんだけど…ツイストサーブ打てるんだって?」
「!」
リョーマは小さく眉を寄せて桃城を見上げる。
(オバサンが、オレのこと、話した…?)
ツイストサーブという言葉にどよめく面々をよそに、リョーマは桃城から視線を外さない。
(あのオバサンだって、一応組織の上の方の人なのに……オレに興味を持たせるようなこと、言うのかな…)
「中学生じゃ、まずこれが出来る奴はいねーよ…、なっ」
意味ありげな視線を向けられて、だが、リョーマはその視線を受け流した。
「いーから早くやろうよ」
「あいよ」
(「どっち」の組織なんだろう…)
桃城はどういう立場でリョーマの前に立ち塞がるのか、あるいは立ち塞がることなく、違う態度で接して来るのか。
とりあえずは手塚にも話し、様子を見てみようとリョーマは思った。
早速翌日の昼休み、リョーマは弁当を持って手塚のクラスを訪れ、さりげなく手塚を数学準備室に連れ出して昨日の出来事を話した。
桃城が「組織」の人間ではないかということも含めて、桃城とのやり取りを逐一話すと、一通り話を聞いてから、手塚は静かに溜息を吐いた。
「……断定は出来ないが、俺も、桃城には注意している」
「やっぱり!」
リョーマは得意顔で頷き、手塚と同意見であるという嬉しさを隠さずに微笑んだ。
「だが越前」
喜ぶリョーマを見つめて、手塚は小さく眉を顰める。
「テニス部員に対して、あまり『そう言う意図』で接触するな。お前が警戒しながら近づくと向こうにも『何かある』と勘付かれる可能性があるだろう」
「ぁ…」
リョーマが小さく目を見開くと、手塚はまた溜息を吐いた。
「いいか。部員ともめ事を起こすな。…お前はただでさえ目立つだろうから、大人しくしていろ」
「え…オレ、目立つっスか?」
怪訝そうにリョーマが尋ねると、手塚は一瞬口を噤んでから溜息混じりに言う。
「………一年生のくせに態度がでかい。三年の教室に平気でやって来る一年など、お前くらいしかいないぞ」
「ふーん?そうなんスか」
リョーマがきょとんとしたまま手塚を見つめていると、手塚はやれやれとばかりに肩を竦めてまた溜息を吐く。
「あ、そうだ、部長、お昼食べました?」
ふいに思い出して、リョーマが瞳を輝かせる。
「いや…」
「一緒に食べません?」
「………いや、俺は生徒会室に行く用事がある」
視線を逸らされ、素っ気なく言われてリョーマは唇を尖らせる。
「なーんだ。せっかく親睦深めようと思ったのに」
「お前はまだそんなことを……」
「だってオレは、アンタのことをもっと知りたいっス」
「俺のことは、もういろいろ聞いて知っているんじゃなかったのか?」
「そういう誰でも知っていることじゃなくて、オレしか知らないアンタの顔とか、声とか、癖とか、知りたいなーって」
「………」
眉を顰めて黙り込んでしまった手塚に、リョーマは慌てて言葉を付け足した。
「いや、あの、今のはオレがそうしたいなって思ってるだけなんで、アンタが嫌がることを無理にしたりはしないっス」
「………お前は、いつもそうなのか?」
「は?」
「いつもそうやって、気になる相手には警戒なく近づいて、あっさりと自分を曝け出すのか?」
「べ……べつに……誰でもってワケじゃ…」
「もっと他人を警戒しろ」
「……さっきは警戒しすぎるなって言ったくせに」
プウ、とリョーマが頬を膨らませて唇を尖らせると、手塚はもう何度目になるかわからない溜息を吐いた。
「それとこれとは意味が……まあ、いい、ならばさっきの言葉は撤回する。お前は警戒しなさすぎだ。もっと緊張感を持って仕事しろ」
「はーい」
「…………」
間延びしたリョーマの返事に、手塚がきつく眉を寄せて口を開きかけたところで、部屋のドアがいきなり開いた。
「おや、また来てたのかい」
リョーマがデジャヴを感じて苦笑すると、手塚は「今、話は終わりました」と言って竜崎と入れ違いにさっさと部屋を出て行ってしまった。
「……ちょうどよかったよ、リョーマ。ちょっといいかい?」
「?」
ニッコリ笑う竜崎を見て、リョーマは怪訝そうに首を傾げた。
「どうだい、この学校は?」
「はぁ、まぁ」
弁当を食べ始めたリョーマにほうじ茶を差し出しながら、竜崎は笑った。
「まだ入学してから間もないからねぇ…」
そう言って、自分で淹れたほうじ茶を飲み、竜崎はフゥッと、小さく溜息を吐いた。
「………ちょうどよかったって、オレに何か用があったんじゃないんスか?」
「ん?ああ……」
リョーマに言われてやっと思い出したかのように竜崎は頷いて、湯のみを机に置いた。そうしてとても自然な仕草で、机の横の「スイッチ」を確認する。
(やっぱ、仕事の話、か)
リョーマはもぐもぐと口を動かしながら、視線を竜崎に向ける。
「アタシは反対したんだけどねぇ…」
「?」
唐突な竜崎の言葉にリョーマは眉を寄せる。
「でも確かに、アイツの行動はたまに読み切れないこともある……」
「…何のコトっスか?」
「………」
竜崎は暫し沈黙してから、呟くように話し始めた。
「手塚もお前さんと同じように、二年前……一年生の時にこの学園に新入生として入学してきて、先輩と組んで仕事に取り組んでいたんだが…」
「え、部長が一年の時から、この仕事に取りかかっていたんスか?」
小さく溜息を吐いてから竜崎は頷いた。
「ここに来て最初に組んだのが、当時のテニス部の部長でね。そりゃもう、手塚はその男のことを心から信頼していたものさ」
「へぇ…」
リョーマの胸の奥がちくりと痛んだ。
「?」
(なに、今の…?なんで、胸の奥が、痛いんだろ…)
「その時その男は三年生だったから、卒業という形で表向きはこの件から外された形になったんだが、そいつ、個人的にもこの仕事に興味があったみたいでね……」
「……つまり、組織に関係なく、独自に調査を始めた、って?」
「それだけならいいんだよ。個人がいろいろ調べたところでたかが知れてる。でもそいつは、自分を高く評価してくれる組織に、鞍替えしたんだ」
「え…じゃあ…」
リョーマが目を見開くと、竜崎は苦々しそうに眉を顰めて頷いた。
「学園側に付いて、『宝探し』を今も続けてるのさ」
「ぁ…」
(だから、学園側には部長の『正体』がバレちゃってたんだ)
「まあ、あからさまに敵対しているわけじゃないんでアタシも放っておいたんだが……上の連中が、あろう事か、手塚のことを疑い始めた」
「なにそれ」
リョーマは持っていた箸を乱暴に机の上に置いた。
「まさか、部長も同じように裏切るんじゃないかとか、思ってるわけ?」
「………」
「部長は……あの人は、そんなことしない!」
「わかってるよ。アタシも手塚のことは信頼してる」
「じゃあ、オバサンから上の奴らに言えば…」
じっと、竜崎に強い瞳で見つめられ、リョーマは口を噤む。
「証のないものを、疑心暗鬼で凝り固まった上の連中が信じると思うかい?奴らが一番信じていないのが、『人の心』なんだ」
「そんな…」
唇を噛み締めて、リョーマは俯いた。
そして、ここに手塚がいなくてよかったと、心の底から思った。
あんなにも組織に忠実に『仕事』をこなしている手塚のことを、上層部の連中が信頼していないなどと知ったら、どんなに落胆するだろう、と。
「証が、あれば、いいんスか?」
「え…」
ゆっくりと顔を上げ、リョーマは竜崎の瞳を真っ直ぐに、見た。
「オレが、部長はそんなことする人じゃないってのを、証明するっス」
「………どうやって?」
「それは……今は、思いつかないけど……絶対、オレが、あの人の潔白を、証明してみせる!」
きっぱりと、はっきりと、リョーマが揺るぎなき瞳で竜崎に宣言すると、それまで硬かった竜崎の表情が和らいだ。
「お前さんなら、そう言ってくれると思っていたよ」
「………」
「上の連中は、最初からお前に手塚を見張らせるつもりでここに寄越したんだ。奴らの指示に従いつつ、鼻を明かしてやるってのも気持ちいいだろうさ」
ニヤリと笑う竜崎に、リョーマは大きく頷いてみせる。
(親父が「組織」を嫌ったのも、なんかわかる気がしてきた……)
再び箸を取って弁当の残りを黙々と平らげると、リョーマは「お茶、ゴチソウサマっした」とだけ言ってから、数学準備室をあとにした。
「よし」
チラリと腕時計に目をやり、まだ五分くらいは昼休みがあることを確認してから、リョーマは生徒会室へと駆け出した。
「まだ何か用か?」
生徒会室を訪ねると、手塚に素っ気なくそう言われた。
「ちょっと話、いいっスか?」
めげずにリョーマがそう尋ねると、手塚は短く沈黙してから、仕方ないというように溜息をついて小さく頷いた。
「……ここでいいのか?」
リョーマが話し始めようとするのとほぼ同時に、手塚がそう尋ねて来た。
その意味を、リョーマはちゃんと理解した上で、答える。
「ここで話した方がいいと思うんで」
「?」
怪訝そうに眉を顰める手塚に、リョーマは小さく笑ってみせた。
「さっき、アンタがこの学校に入学した頃の話を聞いたんスけど」
「……」
「その時のアンタの先輩に当たる人が、『向こう側』に付いてるって…」
そう言ってリョーマは、自分たちのものではないカメラがある方向を見上げ、笑みを消して睨みつける。
「………それで?」
静かな手塚の声に、リョーマはまた視線を手塚に戻した。
「そのせいで、アンタのことが『向こう』にバレてるんスよね。それ聞いて、オレ、なんかすごく、腹が立ったっていうか」
胸のモヤモヤを手塚にどう伝えればいいものかとリョーマは口を噤む。
だが手塚はそんなリョーマをチラリと一瞥してから、小さな溜息を吐き捨てるように零した。
「だから何だと言うんだ。そんなこと、この世界にいれば、そう珍しいことでもないだろう」
「な……」
窓際の会長席に戻り、手塚は読みかけだったらしい書類に視線を落とす。
「話というのはそれだけなのか?だったらさっさと教室に戻れ。もう予鈴が鳴るぞ。一年の教室はここからでは遠いだろう」
「………」
こちらを見ようともしない手塚を見つめ、リョーマはキュッと唇を噛む。
「……オレは、アンタの先輩だった人が許せないっス」
「………」
「アンタの信頼を踏みにじるようなコトして……オレは…」
「俺が気にしていないことを、なぜお前が気にする必要があるんだ」
書類から視線をあげずに、手塚が溜息混じりに言う。
「…っ」
「それにあの人は……違う……」
「え…」
「……この話はもうしない。…教室に戻れ」
手にしていた書類をきちっと揃えてから机の上に置き、手塚が立ち上がる。
「今日は俺も練習に参加する。仮入部だからといって甘やかさないからそのつもりで来い」
「………」
「返事」
「……ういーっス」
不貞腐れたようにそう言って、リョーマは手塚に背を向ける。だが、ドアに向かって数歩歩いたところで、もう一度手塚を振り返った。
「アンタが気にしてないことだって、オレは気にするっス」
「……」
「だって、今のアンタのパートナーは、オレなんスから!」
手塚の目を真っ直ぐに見て、リョーマがきっぱりと言い切る。
だが、手塚の表情は全く変わらず、リョーマは胸の奥をギュッと掴まれたような苦しさを感じた。
「……失礼します」
返事を待たず、リョーマは生徒会室から飛び出した。
(よろしくって、言ったじゃんか…)
柔らかな瞳で右手を差し出して来た手塚が脳裏に浮かび、静かに消えてゆく。
(もう…すごい昔のことみたい…)
いや、あの時の手塚とのやり取りは、自分の願望が見せた夢ではなかったかとさえ思えて来た。
(こんなんで…部長の潔白を証明することなんて、出来んのかな……)
深い溜息を吐き、一歩踏み出したところで予鈴が鳴り始めた。
リョーマはチラリと生徒会室のドアを振り向き、もう一度小さく溜息を吐いてから、自分の教室に向かって歩き出した。
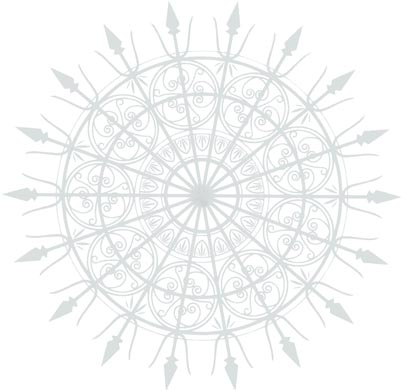
「あれほど、もめ事は起こすなと言っておいただろう」
「………」
部員全員が揃っての初めての部活動の日に、リョーマは上級生とちょっとした問題を起こした。といっても、リョーマは何も言わず、ただ上級生に因縁を付けられ、胸ぐらを掴み上げられただけだ。
それでも、そうやって目立つ行為を、手塚は咎めた。
「自分の立場をわかっているのか?」
今日は数学準備室ではなく、屋上に連れて来られた。
(昼休みにいきなり教室に来るから何かと思ったら…)
お説教か、と、リョーマは心の中で溜息を零す。
手塚は声を荒げることはないが、手塚の瞳が出会ってすぐの時のような冷たい色に見えて、その気分をひどく害してしまったのだろうということが、リョーマにはよくわかった。
「以後気をつけマス」
言ったことのない言葉だったが、手塚には素直に使えた。
だが、あまり「悪いことをした」という気はしていないせいか、それが顔に出てしまったらしく、暫しリョーマを見つめていた手塚が深く溜息を吐く。
「でもあの人、たぶんまたちょっかいかけてくると思うっス」
「………」
リョーマが少し唇を尖らせてそう言うと、手塚はチラリとリョーマを見遣ってから、もう一度小さく息を吐いた。
「……確かに……荒井は上下関係には特にうるさいヤツだからな」
どこかうんざりしたような手塚の言い方に、リョーマは思わず「プッ」と吹き出した。
「なんだ?」
ギロリと、手塚はキツイ視線を向けてくる。
「だって、部長、上下関係にうるさいヤツって……そういう言い方するって思わなかったから」
そう言ってクスクスとリョーマが笑うと、手塚は無表情のままリョーマをじっと見つめ、苛立ちを隠すかのように前髪を掻き上げた。
「とにかく」
一旦言葉を区切って、手塚はリョーマに釘を刺す。
「二度ともめ事は起こすな。荒井が何か仕掛けて来ても相手にするな。それでもしつこく絡んでくるなら、俺に言え。対処する」
「ういーっス」
間延びした声で適当に返事をすると、また手塚が眉を顰めたが、リョーマは気にしないことにした。
「それにしても部長、なんで今日はココなんスか?」
確かにこの屋上には人気はなく、どこかに盗聴器が仕掛けられていたとしても風の音まで拾ってしまって役には立たないかもしれない。
だが、だからといってこの場所が『安全』かどうかはわからないはずだ。どこかにカメラがあってもおかしくはない。
「……竜崎先生のところにそうそう入り浸るわけにはいかないし、生徒会室も、今日は他の役員がいる」
少し間を置いて、手塚はそう答えた。
確かに、いくら部活の顧問だと言っても、そうたびたび教師を訪ねていくのは不審がられるだろうし、まださほど親しくもないはずの部長と新入部員がしょっちゅう一緒にいるのを見られるのも本意ではないのだろう。
「それに、」と、手塚は続ける。
「俺の見たところ、ここには情報収集用の機器はない。あったとしても、超小型のカメラが給水タンクあたりにあるくらいだろう」
(やっぱカメラはあるかもしれないんだ)
うんざりして、リョーマがチラリと視線をタンクに向けると、手塚はまた溜息を吐いた。
「……ただでさえお前はこれから目立つようになる。今から上級生部員の反感を買うような真似はやめておけ」
「え…なんでオレが目立つようになるんスか?」
「近々、校内ランキング戦がある。通例では、一年生はこのランキング戦に参加することはないが……」
すべては言わずにじっとリョーマを見つめる手塚に、リョーマは合点がいったというように頷いてみせた。
「了解っス。オレからは波風立てないようにしますんで」
ニッと笑いながらリョーマが了承すると、手塚はまた小さく息を吐いて頷いた。
「俺の話はそれだけだ。教室に戻っていい」
「はーい」
「越前」
ドアに向かいかけたリョーマを、手塚が何か思い出したように引き止める。
「なんスか?」
手塚は、タンクにあるかもしれないカメラの死角に入るように、自然にリョーマに歩み寄った。
「え…」
思いの外顔を近づけられ、リョーマの頬が薄く染まる。
「ぶちょう…?」
リョーマの顔のすぐ横に、手塚の顔がある。
「不二という男には気をつけろ」
「は…?」
だが、声をひそめて告げられた手塚の言葉に、リョーマの心に込み上げて来た甘い感情が、一気に冷めてゆく。
「ふじ…?」
「テニス部の、レギュラーの一人だ。アイツは、桃城以上に厄介な相手かもしれない」
「じゃ、もしかして、埋蔵金を狙ってる奴らの…?」
「断定は出来ない。だが、絶対に、ヤツの前では気を緩めるな」
「ういっス」
リョーマがしっかりと返事を返すと、手塚もしっかりと頷いた。
「じゃ、教室、戻りま…」
手塚に視線を向けて改めてリョーマは、手塚と自分の距離があり得ないほど近いことに気づき、思い切り赤面してしまった。
唇が、手塚の頬に届いてしまいそうで、はっきりと動揺する。
「え…ぁ……すまない」
手塚もリョーマの動揺を見て初めて二人の距離の近さに気づいたのか、小さく目を見開いてから、スッと離れていった。
「ぁ…いえ、その…べつに…」
「………」
「失礼します」
どうにも頬の熱さがひかなくて、リョーマは手塚を見ずにそのままドアへと向かう。
その直後。
「…」
(え…?)
背後で、手塚が溜息を吐いた。
その溜息の意味を考えそうになり、リョーマはギュッと両手を握り締めた。
(部長……オレと一緒にいると、溜息ばかりだ…)
そっと盗み見るように手塚を振り返ると、手塚は空を見上げてまた溜息を吐いていた。
(オレ……負担になってるのかな……)
いたたまれなくて、逃げるように屋上をあとにし、きつく眉を寄せたまま教室へと戻る。
(もう、あの人の足を引っ張らないようにしないと…)
自分の席につき、頰杖をついてぼんやりと手塚の顔を思い出す。
すぐに思い浮かぶのは、きつい瞳でじっとこちらを見つめてくる手塚の厳しい顔。そしてそれを打ち消したくて、握手を求められた時の柔らかな表情を、無理矢理思い出す。
(あの時、あの人の瞳が、すごく綺麗に見えた…)
薄く頬を染めて、リョーマは胸に込み上げて来た甘い何かを、唇から吐息とともに吐き出す。
(そういえば、さっき…)
あり得ないほど近くで手塚と見つめ合ってしまった。
事故のようなものだったが、あの瞬間、リョーマの心の中は、甘い歓喜が、確かに存在した。
(ドキドキしたりして……オレ、あの人のこと、『そう言う意味』で好きなのかな……)
アメリカで生まれ育ったリョーマは、同性のカップルを目にすることが日本よりは多かったせいか、抵抗や嫌悪感はほとんど抱いていない。
リョーマが目にしたゲイのカップルは、皆とても自然で、幼いリョーマにも、お互いを大切に想い合っているのがよく伝わって来たからだ。
だからといって自分がそうなるとは思っていないが、『誰かを想う心』には、人種も、性別も、年齢も、一切関係ないことをリョーマは知っている。
先程、手塚をとても近くに感じてひどく驚いたが、それ以上に心の中が光に満ちるような、そして甘い熱に包まれるような、幸せな感覚があった。
あのまま見つめ合っていたなら、絶対に自分は、手塚の頬に唇を寄せていただろうと確信できる。
(それって、キスしたかったって……こと……か……)
「ぅ、わ…」
頬の熱が一気にぶり返し、真っ赤になったリョーマは机に突っ伏した。
「越前?どした?具合悪ぃのか?」
クラスメイトの堀尾が心配そうに声を掛けてくる。
「なんでもない」
突っ伏したままくぐもった声で答えるリョーマに、堀尾は肩を竦めて、あっさりと離れていく。
(確かに青龍には憧れてるけど……キスしたいとか、思ったことなかったのに…)
実際に会って、最初は失望して。
でも、意外に素直なところもあって、本当はとても綺麗な瞳をしているのだと知ってしまったあの時から、『憧れ』が、何か違うものに変化し始めている気がする。
「ヤバい」
仕事上のパートナーを、しかも同性を、好きになるなんて許されるわけがない。
(だいたい、失恋決定してるし)
自分と話している時の手塚の表情に変化はないし、瞳の色も、あの握手した時以外は、和らぐことはない。
だから、自分と手塚が恋愛関係になってしまって問題が起きるということはないのだろうが、自分がしっかりしないと、手塚に大きな迷惑がかかる気がした。
(いや、オレの方だって、まだこれが恋愛感情だって確定したわけじゃないし)
グルグルといろいろ考えている間に予鈴も本鈴も鳴ったようで、教室に教師が入って来たのを見てリョーマは慌てて教科書とノートを机の上に出した。
(とにかく、部長に迷惑だけは掛けないようにしないと)
リョーマはぐっと唇を引き結んで、心の中で「よし」と気合いを入れた。
TO BE CONTINUED...
20090207
|

