学校の敷地内にあるすべての建物を案内され、各校舎、教室、特別棟などの位置と構造、そして其処此処に設置された小型カメラやマイクの位置すべてをリョーマが頭に叩き込み終えたのは、もう夕暮れに近かった。
「ぅ……」
昼食さえ摂っていなかったことを思い出し、校門の前でリョーマは腹を押さえて呻いた。
「……腹が減ったのか?」
「減ったっス」
ハァーッと、リョーマが盛大に溜息を吐くと、手塚も小さく溜息を吐いた。
「今日は学食は開いていないんだ。すまなかった、説明に集中していて、食事を忘れた」
綺麗な眉を顰めて呟くように謝る手塚を見て、リョーマは小さく笑った。
「なんだ?」
「え?ぁ、いや、自分の非は意外と素直に認めるんスね」
さらにクスクスリョーマが笑うと、手塚は一層きつく眉を寄せて、吐き捨てるように、短く溜息を吐く。
「……俺は今まで自分より下の人間と組んだことがないんだ。だから、どうも、ペースがわからない」
「下とかって、やっぱ、はっきり言うっスね」
「事実だから仕方がないだろう」
「ま、そのうちオレの実力はちゃんと証明してみせますんで」
「………」
手塚はリョーマをじっと見つめ、小さく溜息を吐いて、リョーマの挑発的な言葉をあっさり無視した。
「駅前のファストフードでよければ連れて行くが?」
「…いいっスね。ゴチソウしてくれるんスか?」
「店に案内するだけだ。俺は帰る」
「なにそれ。親睦深めようとかしないんスか?」
「……俺には必要ない。仕事は仕事で完璧にこなすまでのこと。人付き合いには興味はない」
「………」
唇を尖らせるリョーマをチラリと見遣ってから、手塚はサッと踵を返す。
「俺のやり方が気に入らなければ、別の仕事に回してもらえ。お前なら、組みたいと申し出る人間はたくさんいるだろう」
「……べつに。オレはアンタ以外とは組みたいと思わないけど」
「え…?」
リョーマの言葉が意外だったようで、手塚は小さく目を見開いて振り返った。
「なぜ……初対面の俺と…?」
「確かに今日が初対面だけど、オレは、アンタのことはずっと前から知ってるっス」
「?」
訝しげに眉を寄せる手塚に、リョーマは薄く頬を染めて告げる。
「オレはずっとアンタに憧れてた。親父や、オッサンたちからアンタの話を聞くたびに、どんな人なんだろう、いつか一緒に仕事できるのかな、って」
「………」
「アンタに会うのが楽しみで仕方がなかった。今回の話だって、アンタがいるって言うから、初仕事をここに決めた」
(あれ?なんかこれじゃ、愛の告白してるみたいじゃん)
言いながらどんどん自分の頬が熱くなるのがリョーマにはわかる。
「アンタの役に立てたらいいと思った。アンタがオレのことを必要だと言ってくれるようになるまで、オレは弱音は吐かないっスよ」
「………」
言いたいことを粗方言い終えて、リョーマは真っ直ぐに手塚を見た。
手塚は、だが、特に心を動かされたという表情はしていなかった。
リョーマはほんの少し動揺して、さらに言葉を続ける。
「今日初めてアンタと会って、最初はきつそうな人だって思ったけど、きっとこの世界にいればそれくらいは当然だろうし、だから、オレに厳しくしてくれるのは、オレのためを思って…」
「勘違いするな」
リョーマの言葉を遮って、手塚は冷ややかな声でそう言った。
「寝言は寝て言え。必要以上に人と関わろうとするな。これは忠告だ」
「……っ」
「駅前に出ればすぐにファストフード店も見つかる。気が変わった。一人で行ってくれ」
そう言い残して手塚はリョーマに背を向け、さっさと歩き出した。
「ど、どこ行くんスか?」
「俺にはまだやることがいろいろと残っている。お前は帰れ」
取りつく島もなく、手塚は校内に姿を消した。
残されたリョーマは、暫くその場に立ち尽くしたまま、動けなかった。
◆
「寝言って、あんまりじゃない?」
ファストフード店で一人ヤケ食いをしてから家に帰り着いたリョーマは、愛猫のカルピンを抱え上げて、ブツブツと愚痴を零す。
「あんなにカッコいいくせに、中身はスッゲェ冷徹で、潔癖で、完璧主義ってどうよ?」
カルピンはじっとリョーマを見つめたまま、時折ぱちくりと瞬きをする。
「『必要以上に人と関わろうとするな。これは忠告だ』だってさ。もうあんなヤツになんか関わってやんないもんね」
愛猫に向かってベーッと舌を出してみせると、カルピンは興味なしとばかりに、するりとリョーマの腕を抜け出し、床にトン、と降り立った。
「…お前もオレにキョーミなし?」
カルピンはチラリとリョーマを振り仰いで、独特の声で小さく鳴いてから、階下へと下りて行ってしまった。
リョーマは盛大に溜息を吐き、ベッドに仰向けに倒れ込んだ。
「やっと、会えたのに……青龍……」
ゆっくりと目を閉じ、小さく眉を寄せる。
途端に、今日何度も自分に向けられた手塚の冷ややかな瞳が浮かんできた。
(そりゃ、友達作りに来たわけじゃないんだってのはわかってるけど……もっとこう、なんていうか、優しく、してくれたって、いいじゃん……)
何度も何度も、繰り返し浮かんでは消える手塚の冷たい目がいたたまれなくて、リョーマはスッと目を開ける。
「……絶対、アンタに、オレが必要だって言わせてやるから!」
覚悟してろよ、と口の中で呟いて、リョーマは勢い良く身体を起こした。
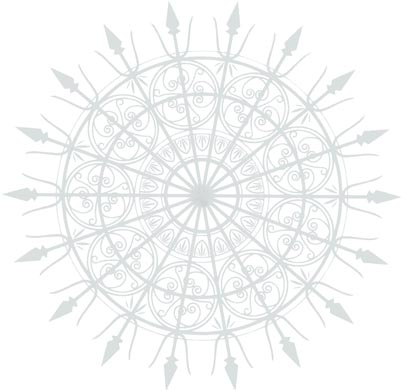
翌日。
暫くは待機、と竜崎から密かに指示を受け、リョーマはとりあえず放課後に、テニス部の入部届けを持って手塚の元を訪れた。
だが三年の教室を訪ねると手塚は生徒会室に行ったと教えられ、リョーマは昨日覚えたばかりの記憶を辿って生徒会室に向かった。
迷うことなく生徒会室に辿り着き、早速コンコンコン、とノックをしてみたが応答はなかった。仕方なくリョーマはそっとドアを開けながら「失礼しまーす」と声を掛ける。
ぐるりと視線を巡らせると、部屋の中には人の気配がなかった。ただ、ついさっきまで誰かがそこにいた証のように、湯気のたつコーヒーカップが窓際の机の上にひとつ置かれていた。
「部長?」
念のため呼んでみるが、やはり応えは返って来ない。
「どこ行っちゃったんだ?」
とりあえず中に入ってドアを後ろ手に閉め、コーヒーカップが置いてある窓際の机へと近づく。
(トイレ、とか…?)
だが窓のすぐ傍まで来たリョーマは、ふと立ち止まり、背後に神経を集中させる。
(………?)
視線のようなものを、感じた。
(そう言えば、この部屋にもカメラがあるんだった)
昨日の手塚の説明───というより「仕草」───では、この生徒会室にもカメラが一台と、盗聴マイクが二カ所設置されているようだった。
(昨日の説明じゃ、カメラはこっち側にひとつあるだけだって……)
リョーマは少し考え込んでから、昨日の手塚の説明にはなかったカメラがあると想定して、そのカメラの死角に入るように、さりげなく移動を始めた。
(窓の方のカメラの位置があの辺だとして、もうひとつのカメラはたぶん、こういう角度に向けられているだろうから……この辺はカバーしづらいんじゃない?)
そのかわり、カメラの死角と思われるリョーマが進む方面には、高性能の超小型盗聴用マイクが仕込まれているはずだ。
それを理解した上で、リョーマは囁くように呼びかける。
「……仕事柄、ノゾキが趣味なんスか?部長?」
マイクで拾えるギリギリの小声で話す。
「昨日アンタはわざと説明しなかったんスね。オレのこと試してるつもり?……アンタは昨日、この部屋にはカメラが一台とマイクが二台って教えてくれたけ
ど、本当は、この部屋にはカメラが二台とマイクが三つ、いや、四つ。それと、カメラの死角に当たるこの壁の向こうに、校内の監視用カメラのモニター室があ
る。……違う?部長」
手塚が聞いていると確信して、リョーマは話した。
案の定、すぐにカタンという小さな音が壁の向こうから聞こえ、壁だと思われたその一部が薄く開いた。
「みーつけた、部長」
「………なかなかいい観察力だな」
少しも動揺した様子もなく、薄く開いた壁の向こうから手塚が現れた。
「オレ、合格っスか?」
「とりあえずは、な」
ニヤリと笑うリョーマに、手塚は小さく肩を竦めてみせる。
「この部屋も、『仕事の話』して大丈夫なんスか?」
「まあな」
「ふーん」
改めてリョーマは部屋の中を見回し、ある一点を見つめて小さく眉を寄せる。
「どうした?」
「……べつに」
(カメラ……もう一台、ウチのじゃないのがありそうだね…)
手塚が気づいているのかいないのかは不明だが、自分が気づけた程度のモノに、あの青龍が気づけないわけがないとも思う。
(わざと気づいていないフリをして相手を油断させてるわけか)
そうであるなら。
この部屋で『仕事』の詳細を語り合うのは危険極まり無い。たとえ声をひそめたとしても、『マイク』で聞こえない会話も唇の動きだけで内容を知ることが、プロであるならば可能だからだ。
さらには、カメラが一台でもあるということは、『筆談』も危険だ。手元を映せるほどのズーム機能がついていないとも限らない。
だが、そんな状況でも、ひとつだけ、唇を読ませない方法が、ある。
「部長」
「なんだ?」
「あー………、やっぱ、いいっス。『見られると恥ずかしいことなんで』」
言いながら、手塚の瞳をじっと見上げると、手塚は小さく目を見開き、微かに頷いた。
二人きりでいるのに『見られると恥ずかしい』、つまり、他にも見ている者がいることを、リョーマは密かに言葉に交えて手塚に伝えたのだ。
手塚もすぐにその言葉に反応し、頷いてくれた。
「……そうそう、これ、入部届けっス」
「ああ」
ポケットから、少しシワになった紙を取り出して手塚に渡すと、手塚はまた頷いてその紙を受け取った。
「…顧問は数学の竜崎先生だ。これから俺も行くんだが、一緒に行くか?」
「ういっス」
わざわざすでに知っていることを、まるでリョーマが知らないことのように聞かせるということは、竜崎の正体については、「敵」も知らないことなのかもしれない。
リョーマが頷くと、手塚も頷き、入部届けを丁寧にたたんで上着のポケットにしまった。
「部長、コーヒー、飲まなくていいんスか?」
「………一度目を離したコーヒーなど、飲めたモノではない」
「ふーん。なるほど、ね」
手塚の慎重さに、リョーマは内心驚きつつも、感心した。
いくら自分で用意した飲み物であっても、一度目を離したものは口にしない。たとえ、傍にいたのが「味方」であったとしても。
組織に属して教育を受けたわけではないリョーマは、そんなふうに具体的に教わったことはないが、たぶん、基本的な「鉄則」なのだろう。
(それにしても、この部屋にカメラやらマイクが仕込んであるってことは、この人の正体は「敵」にはもうバレてるってことか)
だから、カメラがあるのに、手塚は壁の奥の部屋に潜んでみせた。
「行くぞ」
手塚に促され、生徒会室をあとにし、数学準備室へと真っ直ぐ向かう。
二人並んで無言で歩き、数学準備室に入った途端、リョーマはハーッと、詰めていた息を一気に吐き出した。
「………よく気がついたな」
リョーマほどではないが、手塚も小さく息を吐いてから、口を開く。今は、竜崎はいない。他の数学教師も出払っていた。
「ま、素人じゃないんで」
「試すような真似をして悪かった」
静かな口調で謝罪され、リョーマは小さく目を見開いた。
(ああ、またこの人は…)
「いいっスよ。パートナーの実力は、誰だって把握しておきたいっしょ」
「………」
仕事に対して冷徹でストイックな手塚は、しかし、人としては意外に素直なんじゃないかとリョーマは思う。
(オバサンが言っていたこと、ちょっとわかってきたかも)
案外いいヤツだ、と竜崎は言っていた。
昨日はその言葉を一瞬疑ったけれど、きっともっと手塚と付き合いが深くなれば、竜崎の言葉に心から納得する日も来るだろうと思えてきた。
(それにしても…)
「ねえ、もしかして、アンタの正体って、『向こう』にバレちゃってるってこと?」
「ああ、そうだと考えて間違いない。お前の情報もすでに回っているだろう」
平然と答えてから、手塚は徐に窓際まで行ってカーテンを閉めた。そうして竜崎の机の横にある目立たないスイッチを「ON」にする。
「念のためジャミングシステムを作動させた。これで盗聴も盗撮も、この部屋では機能しない」
「へえ」
感心するリョーマにチラリと視線を向けてから、手塚は改めて口を開く。
「生徒会室にあるモニタールームはダミーだ。だから、こちらがどこにどんな情報収集機器を設置しているかは、『彼ら』は正確には把握できていないだろう」
「その『彼ら』ってのは?」
「……正確には、一部の組織は完全なる敵とは言い切れない面もある。時には情報を提供し合って協力態勢をとることもあるくらいだからな」
「ふーん?」
「我々の組織は情報収集が主な目的で、その情報を元に我々が直接何らかの行動を起こすことはあまりない。だが今、この学校に我々同様潜伏
している組織は、どちらかと言えば、手に入れた情報を元にして、時には警察や政府と連動し、あるいはその組織単体で、その組織自体が直接何らかのアクションを起こすことを主たる目的としている」
(つまり、オレたちより荒っぽい連中が妨害してくる可能性があるってことか…)
「だから情報収集能力に長けたオレたちとたまに手を組むこともあるわけっスね。じゃ、オレたちのお客さんになるコトもあるんだ?」
「ああ。稀にはあるようだ。俺が教育を受け始めてからは、一度もないが」
ふーん、と頷いてから、リョーマはじっと手塚の顔を見つめた。
「で、さ。今回の仕事、大まかにしか内容把握してないんスけど、アンタはもちろん詳しいこと知ってるんだよね?」
少し踏み込んだリョーマの質問に、手塚は静かに頷く。
「オレのとこには、この学校の運営資金に不正があるって…」
「まだ未遂だがな」
「未遂?」
もう一度頷いてから、手塚は腕を組んだ。
「……この国には埋蔵金があると、聞いたことがあるだろう?」
「埋蔵金……って、徳川とか豊臣の?」
「ああ。その埋蔵金が、どうやらこの学校の敷地内にもあるらしい」
「ウソ!マジでっ?」
驚いて目を丸くするリョーマに、手塚は表情を崩さずに頷く。
「本来ならば、埋蔵金の類いを発見した場合は国の機関への届け出が義務づけられているんだが、その埋蔵金を密かに調査し、万が一にも発掘できた暁には、届け出はせずにすべてを学園の運営資金か、あるいは理事長の懐にしまい込むつもりなのだろう」
「ふーん、埋蔵金、ねぇ」
リョーマは、その、どこか夢物語的な話に、拍子抜けした。
(なんかもっとこう、重要機密とか、陰謀とかが絡むかと思ったのに…)
そんなことを内心で思い、小さく溜息を吐くと、手塚にジロリと睨まれた。
「簡単な仕事だと思うなよ?これはかなり深刻な問題に発展する要素だって含んだ仕事なんだぞ」
「え?」
「いいか?この学園に埋蔵金があって、それをこの学園側が着服することになったとする。コトがそれだけですめば、公金横領罪などで、この件に関わった学園側の責任者が罰せられるに過ぎない。だが、それは、埋蔵金が、そのまま学園側に渡れば、の話だ」
手塚の言葉に、リョーマはクッと眉を寄せる。
「どういう意味っスか?」
「……今回、この埋蔵金の件には、複数の組織が首を突っ込んできている。単純に、学園側に雇われて埋蔵金を調査し、発掘しようとしている者。もうひとつ
は、埋蔵金の調査とともに、学園側が横領しないように阻止しようとしている我々、そして、もうひとつ、発掘された埋蔵金を手中に収めようと、虎視眈々と狙
う奴ら」
「………」
なるほど、とリョーマは思った。
(単なる宝探しじゃないんだ)
手塚があげた最初の組織については、さほど危機感もなく、それこそ宝探しゲームのような感覚で調査を進めているかもしれないが、問題は、最後にあげた組
織。それが、どのような組織なのかはわからないが、もしも手に入れた資金を、戦争の道具にするような組織だとしたら、その組織には絶対に埋蔵金を渡すわけ
にはいかない。
「……結構、しんどいっスね」
唸るようにリョーマが言うと、手塚は大きく頷いた。
「最後にあげた組織については、未だ未知なところが多い。俺の調べたところでは、生徒会室に仕掛けられているカメラやマイクは学園側のものだ。だから生徒会室では、向こうに知れている情報を巧く使って、逆にカムフラージュに使わせてもらっている」
「じゃあ、その最後に言った組織には、アンタの正体は知られていないってこと?」
「さあな」
手塚は小さく溜息を吐いて、窓に寄りかかった。
「とにかく、この学園で信用できるのは、竜崎先生しかいないということだ」
「ちょっと待って」
リョーマが唇を尖らせると、手塚は怪訝そうにリョーマを見た。
「オレのことも信用してよ。アンタのパートナーなんだから」
「………」
手塚はリョーマを見つめたまま暫し沈黙し、もう一度深く溜息を吐いた。
「……お前こそ、そんなに俺のことを信用していいのか?本当は俺がその厄介な奴らの回し者かもしれないんだぞ?」
「それはないっしょ」
「なぜ、そう言いきれる?」
きつく眉を寄せて、手塚が呻くように問う。
リョーマは、ただ真っ直ぐに、手塚を見た。
「まあ……オレのカン?」
「勘、だと?」
手塚は思い切り顔を顰めると、勢いよくリョーマに詰め寄った。
「寝言は寝て言えと言っただろう。思い込みや感情だけで判断するな。もし俺がお前を利用して事を成そうとしているとしたらどうするんだ」
「アンタはそんなことはしない」
「……っ」
淡々と、至極当たり前のことを話すようにリョーマが言うと、手塚はどこか苦しげに口を噤んだ。
「オレは、パートナーのアンタを信じるっスよ。なにがあっても、どんな状況になっても、オレは、アンタのことだけは信じるっス」
「なぜ……そこまで……」
苛ついていたような手塚の瞳が、だんだんと困惑へと変わってゆく。
「あのさ、寝言って、その人の本当の気持ちを言ってることが多いでしょ?だから、オレが言ってる言葉が寝言に聞こえるんなら、アンタは、オレの、本当の気持ちを聞いたってコトっスよ」
「…っ!」
手塚が、ハッとしたように目を見開いた。
そうして、そのまま暫し黙り込み、やがて。
「……お前のような人間は、初めてだ」
クッと、吹き出すようにして手塚が笑い始めた。
(わ、笑った!)
だがリョーマが心の中で歓喜したのも束の間、手塚はすぐにいつものポーカーフェイスに戻ってしまった。
「いいだろう。お前の『寝言』はしっかりと聞いた。改めて、よろしく頼む、越前」
スッと右手を差し出され、リョーマは大きく目を見開いた。
「ぁ……はい!よろしく、お願いしますっ!」
手塚の右手をしっかりと握り、煌めく瞳を真っ直ぐに手塚に向けた。
見下ろしてくる手塚の瞳は、今までとは打って変わって、穏やかで優しげなものに変わっている。
(キレイな……瞳、だったんだ……)
手塚の手を握りしめたままうっとりするように手塚の瞳を見つめていると、その手塚の瞳が一瞬、困惑したような色を浮かべ、スッと逸らされた。
「…仮入部はもう少し先だが、部の方へはいつでも来てくれて構わない。俺が委員会などでいない時でもわかるように、副部長の大石という男に話しはしておく」
「はい」
「越前」
「はい?」
「手を離してくれ」
「あ!」
ガッチリと握り締めてしまっていた手塚の手を慌てて離し、リョーマは頬を真っ赤に染めて苦笑した。
「す、すみません」
「いや…」
それきり妙な沈黙が流れ、どうにかしようとリョーマが口を開きかけたところで、いきなりガラリとドアが開いた。
「おや、来てたのかい?」
「お留守にすみません」
「いや、べつに構いやしないよ。………ところで、『それ』、どうかしたのかい?」
竜崎の目がおもしろそうに細められ、二人の顔を交互に見る。
リョーマは自分の頬が紅いことを言われたのだと思ったが、竜崎の視線が手塚にも向けられていることに気づき、そっと、盗み見るように手塚を窺ってみた。
(え?なんで?)
手塚の頬も、薄く色がついている。
竜崎が来るまでは、こんな赤みは差していなかったのに。
「…ぶちょう?」
「!」
手塚は小さく目を見開くと、「今日はこれで失礼します」と、少し早口で言ってから部屋を出て行ってしまった。
残されたリョーマはポカンと口を開いて手塚の消えたドアを見つめている。
「………ずいぶん手塚と打ち解けたようだね、リョーマ?」
「はぁ……」
「何かあったのかい?」
興味津々と言った様子で竜崎に尋ねられ、リョーマはまた少し頬を赤らめる。
「寝言……聞いてもらっただけっス」
「寝言?」
不思議そうに目を丸くする竜崎に、ニッと笑ってみせてから「失礼します」と言ってリョーマも部屋を出た。
先程知った仕事の重大性よりも、手塚の笑った顔が、ずっとリョーマの頭の中に浮かんでいた。
TO BE CONTINUED...
20090123
|

