頬に何かが触れた気がして、少年は目を開けた。
「桜…?」
昨夜は少し興奮してしまい、ベッドに入ってもすぐには眠れなかった。そのせいで、今になってひどい眠気に襲われていた。
「あれ?」
辺りに溢れていた人影が見当たらない。
まだまだ余裕があると思っていた時間はあッと言う間に過ぎていたらしく、少年は腕時計を見て「ヤバっ」と叫んだ。
飛び跳ねるように立ち上がり、枕代わりにしていたバッグを肩に担いで勢いよく走り出す。
(初日から遅刻したんじゃ、あの人に呆れられちゃう)
もう一度腕時計に目をやり、少年はニッと笑う。
「でも二分あれば充分」
少年はグッと顎を引くと、ググン、と加速した。
グラウンドの端から、ほぼ対角にある講堂へ向けて、一気に駆け抜ける。
その姿はまるで風のごとく、地を走るというよりは、空を翔るように、軽やかでしなやかで、美しくも見えた。
少年の名は越前リョーマ。
今日から、ある使命を受けてこの青春学園中等部に通うことになった、若き「戦士」。
そう、彼は、ある組織に所属する駆け出しのエージェントだった。
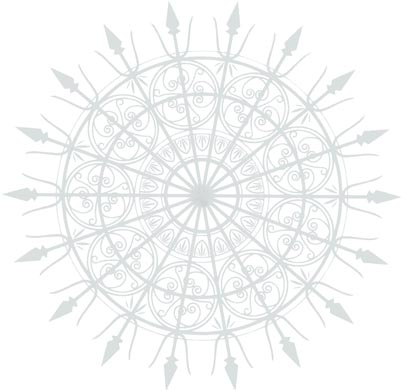
「よく来たね、リョーマ」
入学式やら教室でのオリエンテーションを終え、漸く解放されたリョーマは、真っ直ぐ数学準備室へと足を運んだ。
そこにいた数学教師、兼、テニス部顧問の竜崎スミレに、用があったのだ。
「本日付けで配属になりました、越前リョーマっス」
「まあ、そう緊張しなくていいよ。肩の力を抜いて、頑張るんだよ」
「ういっス」
一応そう返事はしたものの、緊張など最初からしていない。退屈な時間がやっと終わり、むしろ今はさらにリラックスしているほどだ。
それを感じ取ったのか、竜崎が柔らかく微笑む。
「ま、お前さんは緊張なんてするタマじゃなかったかねぇ。親父と同じで」
「親父は関係ないっス」
少しムッとして竜崎を睨みつけると、竜崎は小さく目を見開いてから、ククッと笑った。
「いい目をしてるね。お前さんが『白虎』を継ぐのは、案外すぐかもしれないね」
「………」
リョーマは竜崎を睨んだまま、口を噤んだ。
(べつにオレは『白虎』になりたいわけじゃ、ない)
唇から零れそうになる言葉を奥歯で噛み殺し、竜崎から視線を逸らす。
そんなリョーマを一瞥してから、竜崎は「ああ、そうだ」と口調を変えた。
「もうすぐここに『青龍』が来るから、ついでに挨拶するんだね」
「えっ!」
竜崎の言葉に、リョーマの表情が一変する。
「ウソッ、マジで、もう会えるんスかっ?」
「ん?」
瞳を輝かせて詰め寄るリョーマに、竜崎は一瞬呆気にとられたような表情をする。
「………なんだい、お前さん、本当に噂通り、青龍に…」
竜崎の言葉の途中で、コンコン、と、ドアがノックされた。
「どうぞ」
「失礼します」
竜崎の許可が下りると、ドアの向こうでよく響くテノールの声が聞こえ、静かにドアが開いた。
「遅くなって申し訳ありません」
部屋に入る前に一礼し、その男は真っ直ぐ竜崎の前に進み出た。
竜崎の横でぽかんと口を開けて目を見開いているリョーマをチラリと見遣ってから、男は口を開く。
「……ご用は?」
「ああ、まずはこいつを紹介しておきたくてね」
「?」
ノンフレームの眼鏡の奥で、男が訝しげに眉を寄せる。
「こいつは越前リョーマ。今日からこの学園に入学してきたルーキーだ。面倒見てやっとくれ」
「越前?」
「ぁ…ういっス、よろしくお願いします!」
リョーマは姿勢を正してからペコリと頭を下げる。だが男はリョーマは眼中にないらしく竜崎から視線を外さない。
「まさか、越前南次郎さんの…?」
「ああ、息子だよ。蛙の子は蛙、やっぱり同じ世界に入ってきちまった」
「………そうですか、あの、『白虎』の……」
そう言って、やっとその男はリョーマに真っ直ぐ視線を向けた。
「俺は手塚国光。ここでは三年、今は生徒会長も務めている。よろしく頼む」
ニコリともせずに自己紹介され、リョーマはゴクリと小さく喉を鳴らした。
手塚と名乗ったその男は、身長が180近くあり、均整の取れたスラリとした体躯で、モデルかと思えるような綺麗な姿勢で立っていた。
ノンフレームの眼鏡の奥の瞳は案外鋭く、端正な顔立ちはほんの少し色素の薄い髪と相俟って、全体的に仄かな光を放っているような錯覚さえ起こさせる。
「ぁ…の、えっと、もしかして、アンタが、『青龍』?」
「……」
手塚は答えずに小さく眉を寄せると、竜崎に視線を戻した。
「彼の教育は、どこの機関で?」
「アメリカだよ。だが特にひとつの機関で教育を受けたわけじゃない。こいつは南次郎から直接、徹底的に仕込まれた、いわば、ちょっとした異端児なんだよ」
「組織の教育を受けていない?……では今までの任務は…」
「今回が初仕事だ」
「………」
手塚はきつく眉を寄せて一瞬黙り込み、小さく溜息を吐いた。
「……確かに、今回の件は命に関わるようなものではありませんが、他の組織に先を越されないためには、迅速かつ的確な行動が要求されます」
「何が言いたい?」
竜崎が穏やかな表情のまま、声のトーンを少しだけ下げて問う。
「足手まといなら応援はいりません。俺一人で結構です」
「ちょっと」
竜崎が口を開く前に、リョーマが堪えきれずに口を挟んだ。
「何それ、オレが足手まといだって言いたいわけ?」
「………」
チラリとリョーマを見遣り、手塚はまた小さく溜息を吐く。
「オバサン、オレのデータ、ないの?」
「…これのことかい?」
竜崎からA4サイズの茶封筒を渡され、リョーマは中を確認してから手塚に差し出した。
「これ見てよ。身体能力なら、アンタにも引けを取らないけど?」
差し出された茶封筒を受け取り、手塚は中の書類に目を通す。
「なるほど。確かに、データとしての能力は、思ったよりも上だな」
「でしょ?」
「だが俺が言うのは、実践能力の話だ。本番で力を100%発揮できる者は少ない。特に新人は、な」
「…っ」
ムッとしたリョーマが反論しようと口を開きかけたところで、竜崎が笑いながら「まあまあ」と、割って入った。
「記録には残っていないが、こいつは親父の仕事に同行したことが何回かあるんだよ。だから、まるきり素人同然、というわけじゃない。その辺は、アタシが保証するよ」
「……そうですか。それならいいのですが」
「……」
リョーマはギッと手塚を睨んでから、スッと視線を外した。
(これが、『青龍』……?)
その人物に、リョーマはずっと憧れていた。
初代『青龍』は女性だったと聞くが、その跡を継いだ二代目は、初代を上回る実力の持ち主で、その仕事は迅速かつ正確で、非の打ち所のない完璧な仕上がりだという。
それだけではなく、ひとつの指令に要する時間、費用など、細かな予測もほぼ完璧で、手塚の実力を妬む者からは「アイツはロボットなんじゃないのか」とまで言われているらしい。
(オレの親父とは正反対なんだ)
リョーマの父・越前南次郎は、『白虎』というコードネームを使い、裏の世界では知らぬ者がいないほど名の通ったエージェントだった。
だがその仕事は自由で気ままで、その奔放さから、最後まで決まったパートナーを持たず、『白虎』というよりは『一匹狼』のようでもあったと言う。
その父は、リョーマがまだ幼い頃に突然引退を決め、業界から忽然と姿を消した。それでも、仕事が仕事だっただけにしっかりと監視がつけられ、どこへ行くにも『お供』がついてきた。
だが南次郎は、その監視員たちとさえも打ち解け、終いにはリョーマの『教育』を手伝わせたりもしていた。
(やることがムチャクチャなんだよ、あのクソ親父は)
だから、父と正反対に完璧に仕事をこなす男がいると聞いて、興味を持った。さらにその男が『二代目』であり、歳も自分とさほどに変わらぬことを聞き、驚きとともに憧れを抱いた。
(ずっと、会いたいと思っていたのに…)
リョーマはまたじっと手塚を見つめ、そうして小さく溜息を吐いた。
(なんか……想像していたのと違う…)
確かに、この短いやり取りでも、手塚が仕事に対してとてもクールで、何事も冷静に処理できるのであろうことはわかった気がする。
ロボット、と。
そう言われているのも、リョーマにはわかる気がした。
「じゃあ、手塚、とりあえずこいつに校内の案内をしてやってくれるかい?アタシはこれから職員会議なんでね」
「……わかりました」
「職員会議って?作戦会議のことっスか?」
リョーマが目を輝かせると、竜崎は声を立てて笑った。
「いいかい、リョーマ。この学校はべつにスパイ養成学校じゃない。普通の子が通う私立の学校だ。そしてそこに勤めるアタシは、普通の、ちょっとテニスが巧い数学の教師なんだよ」
「はぁ…?」
「お前さんの本当の正体を知っているのは、アタシと、この手塚だけだ。だからリョーマ、他の生徒や教師たちには、アンタが特殊な教育を受けて、特殊な目的でこの学園に来たということを秘密にしなきゃならないんだ」
スッと笑みを消した竜崎の目を見て、リョーマは表情を引き締めた。
「わかってるっス」
真剣なリョーマの表情を見て、竜崎は大きく頷いた。
「とりあえず、お前さんはまだ『見習い』扱いだ。先輩である手塚の言うことをよく聞いて、勝手な行動はするんじゃないよ?」
「……ういっス」
少し不貞腐れたようにリョーマが返事をすると、竜崎は笑いながらリョーマの頭を撫でた。
「…案外いいヤツだよ、手塚は。そのうちお前さんにもわかると思うけどね」
リョーマにだけ聞こえるようにそっと囁かれ、リョーマは眉をきつく寄せて顔を上げた。
「……そうは思えないっスけど」
ムッとしてそう答えると、竜崎はまた笑った。
「じゃあ手塚、あとは頼んだよ。……リョーマ、とりあえず今日は校内の構造と特別教室の配置を、よく頭に叩き込んでおきな」
「ういーっス」
竜崎は笑いながら机の上にあった書類の束を抱えると、手塚に目配せをしてから部屋を出て行った。
しん、と、部屋の中が急に静まり返る。
「……まさかとは思うが、この学校の構造を全く知らないわけではないだろうな?」
「は?」
「前もって調べていないのか?」
きょとんと手塚を見上げるリョーマを、手塚は思い切り呆れたような瞳で見下ろす。
「……ここへは仕事で来たのだと、わかっているのか?」
「もちろん」
口をへの字に曲げてリョーマが頷くと、手塚は短く沈黙してから溜息を吐いた。
「……今から校内を案内してやる。要所要所には超小型カメラやマイクを設置してあるから、それも教える。一度しか言わないから、しっかりと覚えろ」
「ういっス」
「それから、ここでは主任のことは『竜崎先生』と呼べ」
「はーい」
どうでもいいとばかりにリョーマが気の抜けた返事をすると、手塚がきつく眉を寄せた。
「……そして、竜崎先生は言わなかった大事なことがひとつ」
「え…?」
「竜崎先生は、この学校で俺たちの正体を知る者は竜崎先生以外にはいないと言ったが、それは正しくもあり、間違いでもある」
手塚の声のトーンが下がり、リョーマはこれから告げられることの重要性を直感的に感じ取る。
「この学校には、俺たちの他にも、俺たちと同じ世界の人間が、すでに何人か入り込んでいる」
「え、それって…」
目を見開くリョーマに、手塚は小さく頷いてみせた。
「迂闊なことはこの部屋以外では口にするな。どこで聞かれているかわからないからな」
「………」
ゴクリ、とリョーマの喉が鳴った。
「だから、仕事の話はこの部屋だけでする。それと、コードネームについては一切口にするな。初対面の相手にいきなりコードネームを聞こうとするバカなマネもやめておけ」
「ぁ……」
リョーマは先程、いきなり手塚に「青龍か」と尋ねてしまった失態を思い出した。
「す、すみませんでした」
「わかればいい」
手塚は小さく溜息を吐いて、ゆっくりと腕を組んだ。
「俺は、お前の父親のことはとても尊敬している。だが、だからといってお前を甘やかすつもりはない。俺について来られないと思った時は早めに言ってくれ。お前の代わりの者は、いくらでもいる」
「!」
手塚の言葉に、リョーマは大きな衝撃を受けた。
(オレの代わりは、いくらでも、いる…)
「…今から校内を案内し、カメラとマイクの位置も同時に教えるが、さっきも言ったようにいちいち言葉に出して教えるわけにはいかない。だから、俺が立ち止まった位置で眼鏡に触れたならカメラの設置場所、襟に触れたならマイクの場所、と覚えておけ。いいな?」
「…ういっス」
俯いたまま頷くリョーマを一瞥して、手塚はまた小さく溜息を吐く。
「……テニス部のことは、竜崎先生から聞いているか?」
「ぇ…あ、はぁ」
「………」
曖昧な返事をするリョーマに、手塚は冷たい視線を向ける。
「なぜ俺たちの仲間が、副業としてプロテニスプレーヤーになるか、知っているか?」
「ぇ…さぁ…?」
「プロになると、年間様々な国での大会に参加することになる」
「あ!…もしかして、怪しまれずに、いろんな国へ移動するため、っスか?」
手塚は表情を変えずに静かに頷いた。
「少しは頭の回転もいいようだな。各国で開かれる大会への参加のためであるなら、短期間に点々と移動を繰り返しても怪しまれることはないからな」
手塚の言葉に少しムッとしながらも、リョーマは大きく頷いてみせる。
「だからといって、誰でもがプロテニスプレーヤーになって活躍できるというわけではない。仕事のこともあるが、お前には、テニスの才能もあると見込まれて、この学校へ派遣されたのだということを、理解しておけ」
「どういうことっスか?」
「この学校はテニスの強豪校としてもある程度名が知れているところなんだ。両立は難しいだろうが、仕事もテニスも、しっかりついてこい」
「ぁ………はい!」
「あとで入部届けを持ってこい。俺は、テニス部の部長もしている」
「スゴイっスね、大役をいくつ掛け持ちしてんスか?」
リョーマが目を丸くすると、手塚は小さく肩を竦めた。
「どうということはない。……だがテニスは、ハマるぞ」
「え…」
ふわりと、小さく微笑まれて、リョーマはさらに目を見開いた。
(うわ…なに、この人……?)
リョーマの心臓が、いきなり加速を始める。
「よし、そろそろ行くぞ。何か質問はあるか?」
「ぁ……あの、オレは、アンタのこと、なんて呼べばいいっスか?」
なぜかもつれそうになる舌をなんとか動かしてリョーマがそう質問すると、手塚は短く思案してから「部長とでも呼べ」と短く言った。
「いくぞ」
「ういっス」
静かにドアを開ける手塚の背中を、リョーマはじっと見つめた。
(やっぱり、アンタは、オレの『青龍』だ)
ほんのりと頬に熱が集まるのがわかる。
(アンタに失望されないように、ちゃんと仕事してみせるから)
前を歩く手塚に小走りして追いつき、横に並ぶ。
「部長、これから、よろしくお願いします」
「………」
短く沈黙してから、手塚は小さく「ああ」と言った。
少し開いていた廊下の窓から、春の薫りを纏った風が舞い込んでくる。
(手塚、国光……か…)
リョーマの胸にも、爽やかな、そして心の奥をくすぐるような、一陣の春の風が、舞い込んだ。
TO BE CONTINUED...
20090116
|

