|
救急隊員
|
119番に電話すると、救急車に乗ってやってきてくれるのが救急隊員である。その中でも「救急救命士」という国家資格を持つ人はある程度の医療行為も許されており、一定の条件のもとに気管挿管を行うこともできる。
この人たちに、「救命救急士さん」と呼びかけてみよう。そうすると、「いいえ、救急救命士です。」という返事が返ってくるはずである。国家資格であるから、ことばの順番もおろそかにはできないのである。どっちが正しいかとても憶えられないよ、とお嘆きの方は、「QQQ命士」と憶えていただくとよいだろう。(私も彼らをローマ字で呼んでいるが、たぶんばれていないだろう。)
彼らは気管挿管の実習を受けるなどの目的で病院の手術室を訪れることがあり、そこに麻酔科との接点がある。いろんな人と知り合いになったが、もっとも印象深いのは「方向音痴」の救急隊員である。この人は麻酔科の控え室から手術室に向かうとき、たいてい反対方向に行きかけてしまうのである。しかも、その癖は3日たっても直らなかった。救急車という特権的乗り物と、方向音痴の救急隊員という取り合わせが、妙におかしかった。
もちろん、仮にこの人が救急車を運転するとしても、ナビゲーターがつくので迷子になる心配はない。このナビゲーターは助手席の人間である。救急車ではいわゆるカーナビに頼るよりも、助手席の人間が地図とにらめっこしながら指示を出すほうが速くて正確なのだそうだ。
彼らは自治体消防局に就職した人たちであり、もと消防隊員という人も多いようである。消防隊員と同じ訓練(よく知らないが、走ったり登ったりするのだろう)をこなし、体格もよい。このような、われわれ医師、看護師とはかなり違う入り口から入った人たちと、「救命」の部分で協力しあう関係になる、そういうところにも医療の仕事の面白さがあると思う。
2013.12.28
|
|
人気の職業
|
よくテレビなどで、子供の将来つきたい職業人気ベストテンを目にするが、その中に医師は入っていても、麻酔科医が挙げられているのを見たことがない。もしかしたら11位くらいにつけているのかもしれないが、ベストテンに入るには、仕事の内容が少しわかりにくいように思う。麻酔科医は患者さんを眠らせるのが仕事だが、その患者さんを治すのは外科医だから、その分業の構造が子供には理解されにくいのだ。
他の人気職業を見てみると、サッカー選手=「蹴りこむ」、教師=「導く」、ケーキ屋さん=「余ったら食べる」など、一語か二語で最終目標を表現できる、わかりやすい職業ばかりだ。これでは麻酔科は勝てない。
 私も、自分の子供に麻酔科医の仕事を理解させるのに苦労した。
私も、自分の子供に麻酔科医の仕事を理解させるのに苦労した。
たとえば、上の子は幼稚園の頃、私の知人にこう説明した。
「おとうちゃんの仕事はね、病院で看護婦さんに注射して眠らせることなの。」
その知人が看護婦さんだったから無事ですんだが、警察官やマスコミの人だったらヤバいところだった。
下の子とも、こんな会話がかわされた。
「おとうちゃん、きょう日曜なのに電話で呼ばれたのは、なんの手術やったん?」
「オチンチンにケガした人の手術やで。」
「ふうん、オチンチンの手術したん。ほんでおとうちゃん、手がくさくなった?」
「違う!手がくさくなったのはおとうちゃんじゃない、ヒニョーキカの先生や。」(泌尿器科の先生ごめんなさい。)
自分の子供がこれだから、他人の子供にわかってもらうなど夢のまた夢だ。
この際、迷える幼稚園児と小学生のためにわかりやすくまとめる。麻酔科医の仕事を一言で説明すると、「患者さんを守る」だ。
2013.12.22
|
|
2つの無人航空機
|
私はSFの熱心な読者でもないのにこんなことを言うのは何だが、仮に世の中に完璧な小説はないとしても、完璧なSF小説は存在すると思っている。「戦闘妖精・雪風」(神林長平、1984年、ハヤカワ文庫)がそれである。
地球防衛軍のエースパイロット深井中尉とその愛機、雪風は、突如地球に侵攻してきたなぞの機械生命体であるジャムと戦っている。雪風は最高レベルの電子武装を通して深井中尉の戦技を吸収し、防衛軍最強の存在となっていく。ところが地球軍の戦術コンピュータ群は、この戦いには人間は不要であるかのような振る舞いを見せ始める。そしてついに、雪風も無人機として自由にジャムと戦わせるべし、という決定がくだされてしまう。物言わぬ雪風は人間の味方か、敵か、迷いが生じる中でジャムとの決戦のときが迫る。
人間よりも機械に親和性を持つゆえに地球軍に送られた深井中尉だが、雪風にはおれが必要だ、と信じ、裏切られていく深井中尉の葛藤は、やはり人間のものである。読者もまた雪風に対し、愛情と憎悪と2つの感情を抱いている自分に気づくのである。
「雪風」を初めて読んだ30年近く前には、まさか現実の世界を無人航空機が飛び回るようになるとは思わなかった。アメリカの無人攻撃機ドローンである。しかもそれは、SF小説よりもはるかに醜悪な構図の中で飛んでいる。
もともとは人間同士の戦いだったはずなのに、一方が金と技術にものを言わせて、人間と機械との戦いにすり替えてしまった。殺人マシーンとまともに戦っても人間に勝ち目はない。しかも多数の民間人が巻き添えになっているという。これまでの人間の歴史になかったタイプの理不尽な死に方だ。アムネスティが報告したように、これは戦争犯罪と言っていい。
こんなに趣味の悪いSF小説をうっかり買ってしまったとしたら、ただちにページを閉じて、ゴミ箱に入れるだろう。
2013.12.20
|
|
麻酔科医の急所
|
強い者、優れた者にも弱点がある。アキレウスのかかと、弁慶のむこうずね、クレヨンしんちゃんの風間くんの耳の穴、などなど。そこを攻められると、あんなに完璧であると見えた人たちがたちどころに窮地に陥ることになっている。これを「急所」と呼ぶ。
私はもともと強くないので、私に勝つためにどこが急所かを調べてもらう必要もないのだが、興味本位で知りたいと思う人がいるかもしれないので書いておくと、一番の急所は「左手の小指」である。これがないと、麻酔科医として満足に仕事ができなくなるからだ。
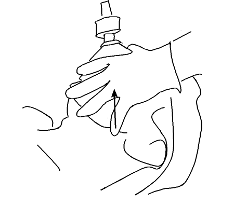 「介抱講座」で述べたように、舌根沈下による気道閉塞に対しては、「下顎挙上」がもっとも有効な手段となる。麻酔においても、全身麻酔をかけてから気管に呼吸のための管を挿入するまでの数分間、下顎挙上が必要になるが、麻酔科医はこれを左手小指の先端だけで行っている(図参照)。万一この指を失ったら、他の指では代用がきかないのである。たとえば、左薬指や右小指ではだめなのである。
「介抱講座」で述べたように、舌根沈下による気道閉塞に対しては、「下顎挙上」がもっとも有効な手段となる。麻酔においても、全身麻酔をかけてから気管に呼吸のための管を挿入するまでの数分間、下顎挙上が必要になるが、麻酔科医はこれを左手小指の先端だけで行っている(図参照)。万一この指を失ったら、他の指では代用がきかないのである。たとえば、左薬指や右小指ではだめなのである。
患者さんの中で、なんらかの事情により左小指の先をなくしている方をときどき見かけるが、そのたびに背筋が寒くなる。私だったら「そこだけは勘弁して」と言わなければならないところだ。
この秘密は、絶対に人に教えないようにしていただきたい。
2013.12.15
|
|
手術室の挨拶
|
あまり知られていないことだが、手術を開始する時、外科医はかならず「お願いします」と挨拶する。これは全国共通だと思う。麻酔科医、看護師などに向かって、手術のサポートをよろしく頼みます、という意味だ。
テレビドラマなんかだと、外科医が、「これより○○の手術を始める。麻酔科、用意はいいか」などと威張っているが、悲しくなるほどありえない光景だ。現実世界では、どんなに腹黒くて傲慢な外科医でも、「お願いします」と言ってから執刀するのである。手術を始めてしまった外科医は、赤ん坊のように、周囲からいろいろなことを手伝ってもらわないと何もできない生き物になってしまうからだ。
脊椎麻酔(下半身だけの麻酔)で手術を受けたある患者さんは、この挨拶を聞いて、「あらまあ、なんだか感動的よね」と感心してくれたものである。
研修医には、次のように指導している。
「外科医がお願いしますと言ったら、麻酔科としては何と答える?」
「お願いします、と言います。」
「それでいい。だがその意味は、『せいぜい頑張って、さっさと終わらせてくださいよ、お願いしますよ』ということだから、勘違いしないでね。」
「え、なんか上から目線ですね。」
「そうよ。じゃあ、手術が終わった時には必ず『ありがとうございました』と言われるけれども、これにはどう返事する?」
「もちろん、『ありがとうございました』です。」
「感謝してどうするっ!。ここは『ごくろうさまでした』だろうが。『さまでした』はつけなくてもいいくらいだ。この手術が終わったら言ってみるように。」
「えー?ぼく、麻酔科のあと、外科にローテートするんですよね。あ、そろそろ筋弛緩剤を追加しないと」
と、ごまかされる。
手術が外科医だけのものではないということを感じていただければ、幸いである。
2013.12.14
|
|
麻酔科医による酔っぱらい介抱講座、その3
|
前回までのあらすじ。酒を飲み過ぎて意識を失った課長。かろうじていびきは聞こえるから生きているのだろうが、いくら呼んでも起きないし、ときどきいびきが止まるし、危ない予感がする。あなたは2年前の食い物の恨みを一時的に忘れる決意を固めた!
人は人差し指一本でどれほどのことを成し遂げられるでしょうか。指一本では、ハエを捕まえることも、配偶者にコーヒーをいれさせることもできませんが、残念ながら核ミサイルのボタンを押すことはできます。そんなつまらないことに使うよりも、人の命を自分の指一本で助けてみたいと思いませんか。それは、非常に限られた特殊な状況で可能なのです。(自由に条件をつけられるなら何だって可能なのです。)
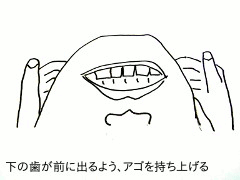 目の前で泥のように眠っている課長、舌根沈下を起こしてすごいいびきですが、ときどき気道閉塞に陥っているようです。普通に眠っている人でもそういう人はいますが(睡眠時無呼吸症候群)、アルコール、薬物、脳卒中などによる気道閉塞だとしたら呼吸が再開しないでそれっきりになる可能性があります。どうすれば舌根沈下を防ぐことができるでしょうか。
目の前で泥のように眠っている課長、舌根沈下を起こしてすごいいびきですが、ときどき気道閉塞に陥っているようです。普通に眠っている人でもそういう人はいますが(睡眠時無呼吸症候群)、アルコール、薬物、脳卒中などによる気道閉塞だとしたら呼吸が再開しないでそれっきりになる可能性があります。どうすれば舌根沈下を防ぐことができるでしょうか。
誰が発見したのか知りませんが、それは「下顎挙上」によって実現できます。文字通りあごを持ち上げるのです。たとえば両手で課長のあごのエラを持ち、下の歯が上の歯より前に出るくらい、天井方向に持ち上げます(上の図)。あごの関節は前後にも動くので、そういった「ずらし」が可能なのです。これでたいていの舌根沈下は退治できます。ほれ、課長の呼吸がすーっと楽になりましたね。
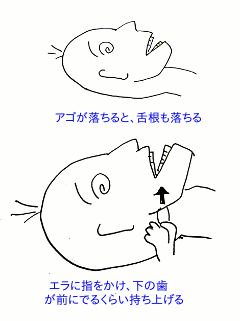 コツをつかめば、これが指一本でできるようになります(下の図)。これが、「指一本で人の命を助ける方法」なのでした。かっこいいでしょう。麻酔科医は麻酔導入時にこれを左手の小指でやっているので簡単にできますが、一般の方はすこし練習をする必要があるかもしれません。家族にいびきのひどいオヤジなどいれば、練習台にしてやりましょう。
コツをつかめば、これが指一本でできるようになります(下の図)。これが、「指一本で人の命を助ける方法」なのでした。かっこいいでしょう。麻酔科医は麻酔導入時にこれを左手の小指でやっているので簡単にできますが、一般の方はすこし練習をする必要があるかもしれません。家族にいびきのひどいオヤジなどいれば、練習台にしてやりましょう。
ただし、手を離すとすぐにまた、舌根沈下に戻ります。ずっと課長のあごを持っているのが嫌ならば、末尾の追補をお読みください。(面白くなさそうなので、後ろにまとめました。)
「指一本でいびきを止める、かっこいい技」を紹介したかっただけなのに、行きがかり上、3回にわたり長々と、「酔っぱらい介抱講座」などという大それたものを書いてきました。本サイトは、役に立たない話ばかりを書きつづる場であったはずなのに、ちょっとは読む人のためになることを書こうとしたばかりに、大変疲れてしまいました。後悔しています。
次からはまた、誰のためにもならない話に戻ります。それでは。
<追補:気道閉塞を起こしている人の介抱のしかた>
-
一般の方が意識のない人の介抱をする場合は、横向きに寝かせておくのがおすすめです。舌根沈下や嘔吐による窒息を起こしにくいからです。
-
長時間横向きに寝かせておくと、腕や足の血流障害、神経障害を起こす可能性があります。体位を変える必要がありますが、そもそも何時間も寝返りも打たないほどの昏睡であれば病院に連れて行くべきです。
-
仰向きで舌根沈下を起こす場合、「肩枕」が有効な場合があります。ざぶとんを2つに折ったくらいのものを肩の下に敷き、頭がすこしのけぞるようにして見てください。これで呼吸が楽にならなければ、もとに戻しましょう。
-
嘔吐してしまったが自分で吐き出せない、というほど弱っていたら、口の中の吐物を指で掻きだしてやらなくてはなりません。まさに酸鼻ですが、何か楽しいことを考えながらやりましょう。お年寄りが餅やパンをのどに詰まらせたとしても同じで、背中を叩いたり励ましたりするよりも、指で取るほうが確実です。これが、「指一本で命を助ける」もうひとつの方法です。
-
暖かいところに寝かせてください。昏睡状態の人は自分の体温を管理できなくなっていますから、路上に放置しておくと夏でなければ凍死の危険性があります。すでにからだが冷えきってしまっている場合、以前書いたように理想の復温方法は「裸で添い寝」ですが、いろんな意味で間違いが起こる可能性がありますから、電気毛布やストーブで代用してください。
以上
2013.12.8
|
|
祝福の言葉
|
手術室のある看護師さんが結婚したので、その同僚たちから、メッセージ書き込み用の色紙を渡された。そこで私は、
「いやになったら別れろよ。」
と書いておいた。
これは私が考えた言葉ではない。私が結婚した時、ある口の悪いおばさんからかけられた言葉である。そのおばさんは、戦死した恋人に操を立てて、独身のまま助産師として働き抜いた人であった。その、愛の大先輩がどういう意味でこう言ったのか。たぶん、いやになったら別れろよ、という意味だろうが、とにかくそう言われてみると意外にうれしかったのを覚えている。あ、それでいいのか、という、荷が軽くなった気分だった。
どんな契約でもクーリングオフ制度で解約できる今の世の中、結婚にだけは「一生添い遂げます」という覚悟を求められたりしたら、危なくてやっていられない。「死ぬまで君を守り続ける」とかそういうストーカーみたいなのは、歌の中だけにしてほしい。
いつでも解約できると思えば、理想的とは言いがたい相手とも、結婚してみようかという気になるはずだ。少子化対策担当大臣には参考にしてほしい。
2013.12.1
|
|
麻酔科医による酔っぱらい介抱講座、その2
|
前回のあらすじ。逃げ遅れたあなたは、酔っぱらって道路の真ん中に横たわる課長(50歳)の肩をどんどんと叩きながら名前を叫んだが、何の反応もない。もしかして死んでいるのかも、と心配になり、課長が息をしているかどうかを確かめることにした。
若い麻酔科医に対して、「五感を使って仕事せよ」と教える指導者がいます。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、あらゆる感覚を使って患者の状態を把握せよ、という意味です。でも「味覚」はどうやって使うのでしょうか。私は今でも想像がつきません。(というより、想像したくない。)「五感を使え」などとかっこよく見えをきった人は責任をとってほしいものです。また触覚と嗅覚も、酒で正体をなくした50歳課長に対しては行使したいとは思いません。五感の中で頼りになるのは、やはり聴覚と視覚でしょう。
まず、呼吸を耳で確認してみましょう。いびき、規則正しい寝息、寝言、うわごと、こういったものが聞こえたら、呼吸をしている何よりの証拠です。酔いもこの程度ならば、家に連れて帰って様子を見ても構わないでしょう。なお、酔っぱらいの口元に耳を寄せすぎると、危険なものが飛んでくることがありますので気をつけましょう。
いびきの音が時々止まるようなら、注意が必要です。もともといびきとは、舌根沈下と言って空気の通り道(気道)が狭くなったときに出る音ですが、これが完全閉塞すると音が止まるのです。さっきまでうるさかった豪快ないびきが止まっているとしたら、目が覚めたのかもしれませんが、気道閉塞に陥っている可能性もあります。そんなときどうするかは、次回「実技」でお話しします。
もしも、周囲がうるさくて音がよくわからない、口元に耳を寄せても寝息が聞き取れないといった場合は、胸の動きを目で確認します。分厚い上着は脱がせ、できれば仰向きにさせ、胸とおなかが同時に見えるようにします。男性は腹式呼吸をするので、胸だけではわからないことが多いのです。それではよーく観察しましょう。胸と腹が同じタイミングで上下していたら、たぶん呼吸しています。
プロの技その2。呼吸の確認はまず音で、よくわからなければ胸の動きをおなかとセットで観察。
ただ、呼吸の観察は実際にはむずかしい作業です。
私たち麻酔科医は、呼吸の視認に関しては自信を持っています。正常な呼吸のほか、シーソー呼吸、陥没呼吸、下顎呼吸、チェーン・ストークス呼吸、過呼吸、脳圧亢進に伴う大呼吸など、名前だけ聞くと怪しい想像をかき立てそうなさまざまな呼吸パターンを見分け、お望みとあらば実演してみせることだってできますが、そんなことをしても誰にも感心してもらえないのが残念です。そんな我々でも、状況によっては、目の前の患者さんの呼吸が十分かどうか、さっぱりわからんことがあるのです。とくに、「虫の息」でかろうじて生きている人は、音もしなければ胸の動きもわかりにくい。こういう人が、昔は自分のお通夜の最中に息を吹き返し、「オレの悪口を言ったな」と起き上がったのだろうと思われます。
 結局、課長の意識がない、呼吸しているかどうかもわからない、という時は救急車を呼んでもらうしかありません。救急車には呼吸モニターと気道確保に精通した救急救命士が乗っていますから。
結局、課長の意識がない、呼吸しているかどうかもわからない、という時は救急車を呼んでもらうしかありません。救急車には呼吸モニターと気道確保に精通した救急救命士が乗っていますから。
最後に、万一、課長のからだが完全にだらんとして、胸の動きも何も、ピクリともしないとすれば、心臓が止まっていると考えなくてはなりません。もしかしたら課長の魂はちょっとだけ浮いて、あなたを軽く見下ろしているかもしれません。救急車が来るのを待たず、一秒でも早く心マッサージを行う必要があります。「恥ずかしい写真を撮っておこう」などと、スマホを取り出すような段階ではありません。やったことがない?自信がない?その場合は、周囲に助けを求めてください。AED(自動体外式除細動器)も、近くにあればぜひ使用してみてください。
くれぐれも、日頃の恨みは、忘れることです。
あとで恩を売る楽しみだけを考えてください。
次回はいよいよ実技編です。愛と感動の大団円があなたを待っている、のだといいですね。
2013.11.24
|
|
吸湿発熱繊維
|
「そろそろヒー○テックの下着を買いに行かなきゃ」とうわごとのように言っている人がわが家にいる。
近年はやっているこの「吸湿発熱繊維」、人間の発する湿気を吸収して発熱するというのであるから、うっとりするほどすばらしい大発明のように見える。
 しかし、理系の人間ならば違和感を覚えるはずだ。37℃の水蒸気それ自身にはエネルギーや化学的な活性はほとんどない。繊維の側も、燃焼などの化学変化を起こしているのではないだろう。その両者が合体して熱を産み続けるわけがない。エネルギー保存の法則に反している。発熱現象はおそらく溶解熱の一種だろうが、いずれにしてもごく一時的なものに過ぎないはずである。(ネットで調べた所では、ものの3分。)
しかし、理系の人間ならば違和感を覚えるはずだ。37℃の水蒸気それ自身にはエネルギーや化学的な活性はほとんどない。繊維の側も、燃焼などの化学変化を起こしているのではないだろう。その両者が合体して熱を産み続けるわけがない。エネルギー保存の法則に反している。発熱現象はおそらく溶解熱の一種だろうが、いずれにしてもごく一時的なものに過ぎないはずである。(ネットで調べた所では、ものの3分。)
使い捨てカイロはまったく違う。鉄の酸化という化学反応を利用している。分子の持つエネルギーをゆっくり取り出すので持続的に発熱するが、それだけに再生はできない。同じ原理で発熱する衣類を作れる可能性はあるが、1回着るとカチカチかボロボロになるので、もちろん使い捨てだ。
服を売っている業者の広告を見ると、そのへんのところは巧妙に回避している。消費者が、「まるでカイロのようにからだを温め続ける魔法の服」という幻想を持つことを邪魔しないようにしているのだろう。
このことをわが家のヒート○ックファンに言っても、「それは屁理屈よっ!」と斬られて終わるだけなので言わない。
2013.11.24
|
|
麻酔科医による酔っぱらい介抱講座、その1
|
忘年会シーズンが近づいてきた。忘年会でやっかいなのが、見た人にトラウマを残す隠し芸と酔っぱらいだ。騒がしい酔っぱらいも迷惑だが、昏睡状態まで進んだ酔っぱらいはさらに迷惑だ。こういう人を放置すると死亡する恐れがあるので、介抱しないわけには行かないのである。統計をしらべたわけではないが、急性アルコール中毒の主な死因は窒息と低体温(凍死)であると思われる。
何の因果かわからないが、麻酔科医は生死の境目に関する専門家である。専門家としてアドバイスするとすれば、仲間の中で酔いつぶれた人が出た場合、まだ人が多いうちに全力で姿を消すのがよい。が、不幸にして逃げ遅れて自分とその人だけになってしまった場合は腹をくくるしかない。
災難としかいいようがないが、ここは気の持ちようである。この迷惑な酔っぱらいから学べることもある。酔っぱらいの介抱には、意識を失った重症患者への対応と共通するものがあるのだ。万一大事な人が急に倒れたら、という場面を想定して、目の前の大事でない人で練習させてもらう気になれば、少しは腹の虫もおさまるかもしれない。
以下、麻酔科医による、倒れてる人の介抱講座である。
この講座では、さっきからそこで倒れているだけと思っていた人が、気がついたら死んでいた、という気まずい事態を避けるための知識と技術を学んでいただきます。麻酔科医のプロの技をこっそり教えますので(堂々と教えられるとつまらないから)、あなたもこっそり学んでください。
目の前に倒れている人(酔っぱらいを含む)がいる場合、まず、意識の有無を確認しましょう。普通に呼んで返事があれば、たぶんまだ生きています。もし返事がなかったら、肩を強くたたきながら大声で呼んでください。麻酔科医は、全身麻酔から患者さんを覚ますときにいつもやっていますが、これが一番強い覚醒刺激なのです。映画などでよく顔をたたくシーンがありますが、効果は高くないし、無駄にエラそうに見えるだけですのでやめておきましょう。「火事だ!」とか「奥さんが来たぞ!怒ってるぞ!」とかは、意識のある人には強い刺激になるかもしれませんが、もうろう状態の人には通用しません。
プロの技その1。肩を叩きながら、耳もとで大声で呼ぶ
なんだ、そんなのプロでも何でもないじゃないか、と思われるかもしれませんが、ぐでんぐでんの人に返事をさせるためには、腹の底から声を出す必要があります。麻酔科医は患者さんを醒ますとき、「えーっ、まだ醒めへんの、早く部屋を片付けたいんだけど。」というナースの冷たい視線の中で、毎日必死になって声を振りしぼっているのです。私自身、しんどいので若い研修医にやらせているほどです。その苦労を思えば、あなたも、命がけで声を張るくらい何でもないはずです。
命がけで呼んでも、うんともすんとも言わない場合、結構これは危険です。気持よく昏睡しているだけかもしれませんが、ひょっとして死にかけている可能性、いやすでに死んでいる可能性すらあります。すぐに、この人が息をしているかどうかを確認する必要があります。
呼吸の確認、これはかなり難しい技術です。難しいので次回にまわしますが、次回が来るかどうかは私にもわかりません。来るといいですね。
2013.11.23
|
|
「グルメ」研究
|
グルメという言葉が街にあふれている。「グルメ情報」、「グルメ番組」、「人気グルメ」などなど。グルメと聞いただけでよだれが出そうだが、本来「グルメ」とは美食家のことであり、人間であるから食べることはできない。
かねてより私はグルメなるものに、微妙な関心を抱いてきた。スーパーで売っている塩サバやいかの塩辛に美味の頂点を味わってしまう私には、その辺にあるものでは満足できないであろうグルメのその気持ちがどうも理解できないのだ。
たとえば、私の仄聞するところでは、グルメはとにかく味に厳しいので、一口食べて席を立ったり、店主やシェフを呼んで叱ってみたり、フトコロから自分専用のソースを取り出してかけてみたり、お母さんにばれたら間違いなく怒られるようなことをするようである。私はこういう人たちと一緒に食事をしたいとは思わない。
中島らもという作家はこういうタイプのグルメに対してかなり手厳しく、「口が卑しいだけの人が、どうしてあんなにいばるのか」と書いている。あ、言っちゃった、という感じだ。ただし、彼は「まずいものを出す店のランキングを作るべきだ。」などとも書いているから、どこか倒錯しているのかもしれない。
気難しいのがいやだからと言って、テレビのレポーターみたいなグルメも困る。一口食べるたびに身悶えして喜ぶような人とも、居合わせたくはない。こっちが恥ずかしい。
我慢強くもの静かなグルメとなら、ぜひご一緒したい。たとえば、ジュール・ベルヌの小説、「八十日間世界一周」の主人公フォッグ氏である。英国紳士の権化とも言えるフォッグ氏はインドのレストランでうさぎ料理を食べ始めたところ、肉の硬さに気づき、すぐに給仕を呼んだ。
「このウサギは殺される時にニャーとは鳴きませんでしたか」
「誓って申し上げますが、これはウサギですからニャーとは鳴きません。」
「誓ってもらわなくて結構。ただ、かつてインドでは猫は神聖な動物だったということだけは覚えておいていただきたい。それは実に、いい時代でした。」
こう指摘しおえてからフォッグ氏は悠然と夕食を続けたのであった。
食品偽装は昔から世界中で行われていたもののようである。気がつかないほうが幸せだろうが、気がついてしまったら、こうありたいものだと思う。
2013.11.17
|
|
ネコマタ解題
|
当サイトには、ネコマタのイラストがついている。
ネコマタを見たことがない人のために説明すると、ネコマタとは、猫が10歳以上になって人語を解するなどさまざまな力を身につけ、ついには妖怪と化したものである。ちなみに私も見たことはない。そうした猫の尾は2つに裂けているという。恐ろしいことである。
ネコマタのイラストのモデルになったのが、ケロちゃんという、となりの家の子が拾った猫である。事情があって(その家はすでに、数十匹のいろんな動物を飼っていた)、うちに迎えたのであった。雑種で、茶色のシマ模様の、何より掃除機を恐れる、何の変哲もない猫だったが、長年一緒に暮らすうちに12歳を超えた。つまり、いつネコマタに化けてもおかしくない状態になった。
ネコマタになれば、ふすまを開けて通った後、閉めるようになるはずである。だがなかなかそこのところは見せてくれなかった。人語を解するというからには、私が面白いことを言った時に「ふっ」と笑うはずであるが、これも用心深く笑いをかみ殺していたのか、表に出すことはなかった。もっともこれは、私のギャグが人間だけでなく猫にも理解されなかっただけという可能性がある。
 そうこうするうち、ケロちゃんは原因不明のけいれんに悩まされるようになった。いよいよ弱ってきたとき、明るいところに連れて行こうとすると、最後の力を振り絞って抵抗した。そして、とうとう望み通り暗いところで真夜中に息をひきとった。妖怪になる前に仏様になってしまったのである。
そうこうするうち、ケロちゃんは原因不明のけいれんに悩まされるようになった。いよいよ弱ってきたとき、明るいところに連れて行こうとすると、最後の力を振り絞って抵抗した。そして、とうとう望み通り暗いところで真夜中に息をひきとった。妖怪になる前に仏様になってしまったのである。
しばらくして、猫にとりつかれた私たちは新しい猫を探すことにした。世の中には奇特な方々もおられるもので、行き場のない猫たちを保護し、責任ある飼い主に譲る活動をしている団体があるのである。
この度は「西神地域ねこの会」(ホームページあり)にお世話になり、右のイラストのチョコちゃんを迎えた。次のネコマタ化は9年後を予定している。
2013.11.16
|
|
卓球と顕微鏡
|
卓球の試合においては、人が普段見せるのとは逆の人格が出てくる。簡単に言えば、人格の逆噴射である。全国の卓球関係者を敵に回したくないので、私と私の周囲ではそうだということにしておく。手術室においても、ある種の手術に同じような現象を認めることがある。
整形外科のN先生は、怖いので有名だった。怖そうな顔をして実はやさしいとか、何も考えていない、というのはよくある話だが、この人は本当にいつも不機嫌でイライラしていて気が短く、よく看護師や若い医師を叱っていた。笑っているところを見た記憶がない。
ある時、切断指をつなぐ手術がはいり、N先生が手術に入った。指の再接着術は、細い血管同士を顕微鏡のもとで縫い合わせるという、技術と根気のいる手術である。N先生の手術は骨折、関節置換などの大きなものしか見たことがなく、顕微鏡下手術などというものを、こんなに気の短い人がちゃんとできるのだろうかと心配した。途中で「いーっ」となって手術を投げ出したりしたら大変である。
ところがそれは、素晴らしい手術だった。姿勢が崩れず、手が震えず、運針にまったくよどみがなく、怒鳴ることもなく(顕微鏡を覗きながら怒鳴ると手術にならない)、必然的に短時間で終了した。顕微鏡を覗いている間だけ、これまで見せたことのないような辛抱強さを発揮したのである。意外だった。
顕微鏡下の血管吻合をもっとも得意とするのは形成外科であるが、そういえば形成外科の先生が言っていた。形成外科の中でも気の短い人(関西弁でいうイラチ)のほうが顕微鏡手術に向いているのだそうだ。理由がわからないが、現実そうなっているのだ。N先生の手術を見て、はじめてそのことを思い出した。
顕微鏡には卓球と同じように、人を別世界に導く魔力があるのかもしれない。N先生とは逆のパターンもある。普段とてもきさくで紳士的な脳外科の先生が、顕微鏡に向かったとたん暴君に豹変し、助手に向かって、「君のはアシスタントではない、レジスタントだっ!」などとののしったりするのであった。この人の場合は手術をとめて怒鳴るので、麻酔科としては困惑させられたものだ。
N先生に関しては、以後、黙って血管吻合をしているところだけを見たいものだと思ったが、そんな機会にはついぞ恵まれず、その後も相変わらず手術中不機嫌光線乱反射を浴びさせられたのであった。
2013.11.9
|
|
卓球と性格
|
このたび、卓球王国という雑誌の紙面とホームページで活躍されている伊藤条太氏のブログで、当サイトを紹介していただいた(http://world-tt.com/blog/johta/)。私がひそかに師と仰いできた方なので、まことに身に余る光栄である。
それを記念して、卓球の話から始める。
卓球には、他のスポーツでは考えられないほどの多様なプレースタイルが存在する。専守防衛から攻撃一辺倒まで、闘志むき出し型から完全ポーカーフェイスまで、とにかく、選手ごとにプレーぶりが違う。そして、私のみるところ、多くの場合において選手のプレースタイルは実生活での性格とは逆に出るのである。
普段おとなしい人が、ラケットを握ると凶暴な野獣になったり、いつも後輩に怒鳴っている怖い先輩が、実は我慢強く球を拾うカットマンだったり、どこから見てもアホとしか言いようのない後輩がとつもなくクレバーな卓球をしたり、不思議なことばかりだ。しかも、いったん身についたプレースタイルはまず死ぬまで変わることはない。たとえば私の場合、50歳になって年相応の枯れた卓球に変えたいのに、力まかせの卓球がどうしてもやめられないのである。
実生活では、自分の性格をひとつのパターンに定着させておかないとまともな人間として扱ってもらえない。しかしそんなことをしてしまった反動で、そうでない自分が出口を求めた挙句、卓球とかそういうものに発現してしまうのだろう。出口が卓球でよかったと喜んでいるのは私だけだろうか。
つまり、卓球とはやむにやまれぬ人間性の発露であり、その意味では矯正のしようのない、自分でもどうにもならない、手のつけられないシロモノなのである。(やっぱり私だけだったりして。)
こんなことを書いても、卓球しない人にとっては何の意味もないかもしれない。だが、抑圧された「自分」の出口は卓球ばかりとは限らない。たとえば、同じような現象は手術室でも見られることがあるのである。次回につづく。
2013.11.8
|
|
精神科の力
|
昔、クッキーを焼くのが得意な研修医がいた。男性である。ときどき、リボン付きの袋にクッキーを入れて、周囲の人に配っていた。私ももらったことがあるが、その時抱いた感想といえば、「変わった奴だなあ」、「でも、おやつ代が浮いた」くらいだった。
しかし、専門家はそこから別の結論を導く。その話を聞いた精神科の先生は、いつものようにソフトな口調で、「あ、それはマザコンですね。」と断定されたのであった。
 それが当たっているかどうかは別にして、このような、帽子の中から鳩が飛び出すような離れ業を目の当たりにする瞬間が、なんとも言えない。
それが当たっているかどうかは別にして、このような、帽子の中から鳩が飛び出すような離れ業を目の当たりにする瞬間が、なんとも言えない。
2013.11.3
|
|
放射線科の力(2)
|
放射線科講師のI先生は、画像診断の中でも「肺」ひとすじであった。学生時代に講義を受けた時の印象が強烈で、挨拶も自己紹介もなく、放射線の話も何もなく、いきなり肺の解剖、つまり肺動脈、肺静脈、細気管支の微細構造を黒板に書き始められたのには驚いた。この3者はこういう順番で並んでいく、だからレントゲン写真ではこう写る、とかなんとか、肺だけで講義の時間を使いきってしまった。今から思えば独創的なアイデアに満ちた素晴らしい講義であったはずだが、当時の私にとってはにあまりにも理解不能だった。次回の講義はさぼってしまったが、きっと肺で始まり、肺で終わったはずだ。
麻酔科医になって、そのI先生に手術室で再会することになろうとは思わなかった。何しろ、自分が肺のCTで所見をつけた患者が手術を受けるときは、かならず手術室に現れるのである。そして、切除標本(主に肺がんの病巣部)が出てくると、その標本を受け取って眺め、触れ、自分でそれを切り出して病理部に送り、術中病理診断の連絡が来るのを待つ。いわば答え合わせである。
驚くべきはその正答率で、術前のCT画像から、患部が悪性か良性かはもちろん、腺癌、扁平上皮癌など癌の組織型(種類のようなもの)まで予想し、ほとんどはずすことがなかった。どこを見ているのかと問うと、腫瘍に入っていく血管の巻き込まれ方でわかると言っておられたような気がするが、相変わらずまったく理解できなかったのでここでは省略せざるを得ない。
あれだけ当たるのだから、もう手術場に来てまで答え合わせをする必要はなさそうな気もするのだが、肺が好きでたまらぬのでやってくる、という様子だった。放射線科の医師のなかでも、あそこまで自分の仕事(兼趣味?)に打ち込む人は見たことがない。研究機関でもある大学病院だからできたことでもあるだろう。
 小柄ながら筋肉質、まゆが太く、メガネのフチも太く、見た目は頑固な偏屈おやじであったが、実際にはとても気さくでやさしいひとであった。(いやなやつだったら、そもそも私の文章には登場しない。)ICUで撮った胸部写真を見てもらった時、とても親切に読んで下さったことは忘れない。胸部外科の医師からも激しく愛されていて、肺やリンパ節をどこまで切除すべきかを、手術中にしばしば相談されていた。
小柄ながら筋肉質、まゆが太く、メガネのフチも太く、見た目は頑固な偏屈おやじであったが、実際にはとても気さくでやさしいひとであった。(いやなやつだったら、そもそも私の文章には登場しない。)ICUで撮った胸部写真を見てもらった時、とても親切に読んで下さったことは忘れない。胸部外科の医師からも激しく愛されていて、肺やリンパ節をどこまで切除すべきかを、手術中にしばしば相談されていた。
後に北陸の大学の教授に栄転された。かの地でも、さぞ、人を驚かせたことだろう。そう思うと、縁の薄い私でも同門のよしみでちょっと得意な気分になったりする。そういう先生だった。
2013.10.26
|
|
放射線科の力(1)
|
一般の方にとって、放射線科というのは麻酔科以上に得体のしれない存在かもしれないが、医師にとっては、病院機能の鍵を握るとも言える、非常に重要な部門である。画像診断、カテーテル治療、放射線治療など、さまざまな専門に分かれているようだが、麻酔科医にとってなじみが深いのはX線写真やCT(コンピュータ断層撮影)に放射線科医が所見をつけてくれる画像診断の部門である。
CTなんかは人体を輪切りにした図が誰の目にも見えるようにしてくれているわけで、何がどうなっているのか、見ればわかると思われるかもしれないが、プロには全然違うものが見えているのである。
たとえば、発熱と臓器障害でICUに入室させた人の病因がまったくわからず、放射線科の先生に腹部CTを読んでいただいたことがある。するとその先生、画像を2ー3分眺め回した後、はっきりした声で診断を下した。「うん、腎臓が正常よりすこし大きい、それからこことここのリンパ節が腫大している。だから、悪性リンパ腫のほにゃらら型が疑われます。うん、たぶん間違いないでしょう。血液内科にコンサルトしてください。」
もしかしたら、これくらいのことは放射線科医としてもっとも基本的な能力なのかもしれないが、医師の中でもとりわけ画像診断にうとい麻酔科医たちにとっては、これは神技である。「今、目の前で偉大なことが行われた!」という感動に、一同しばし浸ったものである。
 画像診断は囲碁、将棋に似ている。これらは「完全情報ゲーム」といって、競技者がすべての情報を知りうる状況にあり(麻雀やポーカーは違う)、したがって勝敗は運よりも「読みの深さ」で決まるというものである。
画像診断は囲碁、将棋に似ている。これらは「完全情報ゲーム」といって、競技者がすべての情報を知りうる状況にあり(麻雀やポーカーは違う)、したがって勝敗は運よりも「読みの深さ」で決まるというものである。
他の科であれば、麻酔科における麻酔薬の使い方、消化器内科における内視鏡など、師弟関係の中で一定の訓練を経なければ身につかない、いわば独占的な技術を使って仕事をしている。一度それらを身につければ食っていくのに苦労はしないから、ある意味安直な生き方である。しかし、放射線科医はそのようなツールをもちいることなく、誰もが同じものを見ているという状況で、「読みの深さ」だけで勝負しているのである。それだけに、彼らのワザはわれわれには実に不思議で鮮やかなものに見える。ちょうど囲碁のプロ棋士が、死んでいるはずの石を生き返らせたり、攻めているはずの石を取り囲んで全滅させたり、魔術のような芸当を公衆の面前で行なって見せるのに似ている。
そういうわけで、放射線科の先生に対しては、「かっこええなあ」という憧れを持ち続けている。
大学病院ではいろいろな放射線科医にお世話になったが、とくに想い出深いのはI先生である。この人は、正真正銘の「肺オタク」であった。次回につづく。
2013.10.19
|
|
内科の力
|
医師は、国家試験をパスして医師免許を取得した時点では、その能力はみな一緒だ。つまり、ほとんど何もできない。しかし、特定の診療科に進んで経験を積んでいくに従って、専門的な能力をどんどん高めていく。その結果、他の科の医師がとてもまねできないようなことを平気でやってしまうようになる。
もちろん、専門以外のことができなくなる、いわゆる「専門バカ」に対する批判はあるし、その反省から幅広い知識と診療能力を持つ「総合診療医」の存在がクローズアップされている。しかし、その道一筋の切れ味にも捨てがたいものがあるのだ。これまで、他科の医師の能力にドギモを抜かれたことが何度かあるので、紹介していきたいと思う。
もう15年くらい前の症例である。ICUに意識のまったくない救急患者が運び込まれてきた。頭部CTでは何も異常はない。こういう時は鎮静剤などによる急性薬物中毒を疑うが、患者の配偶者はそれを強く否定した。そんなことをする理由がまったくないというのである。意識が回復する気配はまったくない。命に危険はなさそうだったが、原因がわからないのではICUの麻酔科医はお手上げである。
すると、担当をお願いした神経内科医が何度目かの診察のあと、こんなことを言われた。
「足関節にミオクローヌス(カクカクとした小さな動き)が見られます。これはある鎮静剤(名前は忘れた)の大量服用で起こることがあるとされています。」
数日後、ようやく血液の薬物濃度検査の結果が返ってきた。血中から検出されたのは、神経内科医の指摘した薬物だった。やはり、薬物中毒だったのだ。
内科医というのは、知識の量をもって自らをたのむ人たちである。特に神経内科というのは、時間をかけて診断し、診断がついても場合によっては何十年もその患者とつきあうという気の長い科である。一方麻酔科医は、目の前で起こる事態に即座に対応できる反射神経を重んじる人たちであるから、内科医に対しては、ま、知識だけでもあかんわな、診断だけできて何になる、というコンプレックスの裏返しのようなものを抱いているのである。しかし、このときばかりは内科医の知識量の力と、見逃されやすい症状を診断に結びつける力の凄さを思い知らされたのであった。
あ、内科医もかっこいい、と思った。
2013.10.14
|
|
薬には勝てない
|
この世の中は、楽しいことに満ちあふれている。しかし、楽しいことは長続きしないか、依存症(いわゆる中毒)を起こしやすいかどちらかだ。一方、苦しいことは依存症は起こさないものの、長続きしやすい。したがって、こんなに楽しい世の中にあって、人生は苦しいことのほうがやや多くなるようにできている。
依存症を起こしやすいものとしては、パチンコなどのギャンブル、ゲーム、インターネット、ジョギング、卓球などいろいろあるが、やっかいなのはやはり薬物だ。たばこ(ニコチン)、アルコール、麻薬、覚せい剤、シンナーなどは身体的依存と言って、やめようとすると離脱症状が出て、大変な苦痛を伴うのだ。
気が進まないながら、ときどき事件として新聞に載ることなので書いてしまうと、麻酔科医の中に、ある種の麻酔薬を自分で使用する者がいるようである。そんなものを使って何がどういいのかは知らない。これは、どんな事情があろうと、決して許されてはならない行為である。発覚したら確実にクビになるが、それがわかっていてもやめられないところが、薬物依存の恐ろしさなのだろう。
日本麻酔科学会も数年前にこの問題の存在を認め、対策を打ち出して対応を始めている。
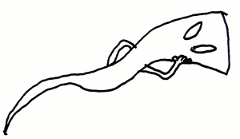 薬物依存から離脱するのはむずかしいが、依存症にならないようにすることは極めて簡単である。「試してみようと思わないこと」である。ある薬理学の教授の言葉を借りれば、「人間は薬には絶対に勝てない」のである。一度だけ試して、すぐにやめよう、という考えは、薬物という魔物には通用しない。自分を買いかぶってはいけないのである。
薬物依存から離脱するのはむずかしいが、依存症にならないようにすることは極めて簡単である。「試してみようと思わないこと」である。ある薬理学の教授の言葉を借りれば、「人間は薬には絶対に勝てない」のである。一度だけ試して、すぐにやめよう、という考えは、薬物という魔物には通用しない。自分を買いかぶってはいけないのである。
私は自分の弱さには自信がある。何しろ、仕事中ミントタブレットを頬張るのがやめられないのだ。たばこや麻酔薬に手を出したらとんでもないことになるだろう。
強い刺激、めくるめく快感などは人生に必ずしも必要ない。目先の小さい楽しみを大切にすることで、普通の人は十分に生きていけると思う。
2013.10.13
|
|
脳死について
|
唐突だが、脳死について。最近、芸能人が脳死宣告された後に意識を取り戻したという、まあ「イカニモ」といった感じのスポーツ新聞情報が出回ったので、一般の方の誤解を解きたいと思い、書かせていただく。
結論から言えば、正しく診断された脳死ならば意識を回復することはありえない。すくなくとも、日本の脳死基準を満たした人が意識を回復した事例はない。もし例の芸能情報のために、脳死による臓器移植に対して疑いを持たれた方がおられたら、その芸能情報のほうは忘れていただきたい。医師が根拠なく「脳死」と口走ってしまったか、患者さんの側が何か聞き違えたかのどちらかだろう。
言いたいことはこれだけだが、ちょっとした知的好奇心と時間がある方のために、どうして脳死が絶対に回復不能なのか、説明してみたい。意外に簡単な理屈なので、安心してください。
脳死への過程はまず、脳圧の上昇から始まる。重度の脳出血が原因となることが多い。なにぶん脳は頭蓋骨の中に閉じ込められているため、圧が上がってもそれを逃す方法が存在しない。やがて脳圧が血圧を超えてしまうと、決定的な事件が起きる。脳に血液が全く流れなくなるのだ。脳血流の途絶は必ず脳の神経細胞の全滅をもたらす。これが脳死である。他の臓器にはみられない現象であり、脳を守るはずの頭蓋骨が攻撃する側に立つという、脳だけの悲劇である。
神経細胞は決して再生しないから、脳死状態になればもとには戻らないし、意識も戻るはずがない。
ただし、脳圧が血圧を超えるというのは、簡単に起こることではない。通常の脳出血では、出血部位周辺の脳を傷めるだけである。脳死はきわめてまれな事態であると考えてよい。
それから、一般の方はご存じないだろうが、そもそも脳死を判定し、死亡として診断するのは、臓器移植を前提としたときのみである。それ以外の場合は、たとえ医学的には脳死と考えてよいような場合でも、脳死をもって人の死とすることは法的に許されていないのである。
このように、脳死は医学的にも法的にも厳密に定義されたものなので、医師も患者さんの側の人たちも、軽々しく「脳死」という言葉を使うべきではない。もちろん、スポーツ新聞もだ。
それにしても、一般の方にとっては、知っておいてこれほど役に立ちそうにない情報(あるいは役に立ってほしくない情報)もめずらしいのではないだろうか。
2013.10.7
|
|
論文掲載への道
|
医学雑誌にもいろいろあるが、やはり日本語の雑誌よりは、海外の英文雑誌のほうが格が高い。麻酔業界で言えば、Anesthesiology や Anesthesia and Analgesia などは歴史が古いだけあってもっとも尊重される。こういう雑誌に自分の投稿した論文が掲載されたら、大学の研究者であればポジションの確保に有利だし、そうでない人でもまあ心の支えくらいにはなる。誰でもタダで投稿できるが、当然ながら、投稿した論文が受理される確率は相当低い。
よくわからない方は、「欽ちゃんのドーンと行ってみよう」というテレビ番組に自作のコントを書いて送るようなものだと考えていただければ、わかっていただけるだろうか。分かっていただけたとすれば、あなたは45歳以上だと推定できる。
では、どうすればこのような雑誌に論文を受理してもらえるのだろうか。
もっともよいのは、文句のつけようのない独創的な研究をすることである。そこを押しただけで麻酔がばっちり醒めるツボを発見したとか、体表に噴霧しただけで深部まで無痛状態となり、全身麻酔の必要性がなくなる画期的な局所麻酔薬(ついでに麻酔科医もいらなくなる)の発明とか、そういう論文ならば採用されるであろう。(独創的すぎて無視される可能性もある。)
だが現実には、中身だけで勝負というのはむずかしい。もし読む人が腰を抜かすほどの研究でなかったら、文章力で査読者にアピールしなくてはならない。私に論文の指導をしてくださったある先生は、次のように言っておられた。
「ええか、ここの一文の出来次第で、レフェリー(査読者)がたばこの火を消すかどうかが決まるんや。レフェリーをじっくり読ませる気にさせることができたら、こっちの勝ちやからな。」
たばこのくだりが、吸ったことのない私にはよくわからないのだが、つまり、査読者が自分の論文を読む光景をイメージしながら文章を練れ、最後のひとひねりを絞り出せ、ということだろう。この先生は、数多くの論文を一流誌に載せ続けられたが、研究の値打ちが高いのはもとより、表現にも力を入れる姿勢がその業績に寄与していたことは間違いないだろう。日本人はつい、「いいものなら黙っていても分かってもらえる」と思いがちだが(多分)、海外の人と勝負するならば表現力も、多少のハッタリを含めて、必須であろう。
さて、文章力の平凡な人が、平凡な内容の研究を仕上げてしまった時はどうしたらいいだろう。その辺は、私の得意分野である。受理されなかったらあきらめる、でいいのだが、粘りさえあれば運が味方する場合もある。
 2つほどの雑誌から拒絶された論文を持て余したときのことである。私はこれをイギリスのややマイナーな雑誌に投稿し直したが、数ヶ月経ってもまだ受け取りの通知が来ない。しかし私はあえてこれを放置した。1年を過ぎたあたりでそろそろかと腰を上げ、問い合わせの手紙を送ったところすぐに返事が来た。論文を見落としていた、すぐに査読に回す、とのことであった。この時点で、私は「これは行ける」と思った。相手が恐縮しているのを感じたからである。論文はすんなり受理された。
2つほどの雑誌から拒絶された論文を持て余したときのことである。私はこれをイギリスのややマイナーな雑誌に投稿し直したが、数ヶ月経ってもまだ受け取りの通知が来ない。しかし私はあえてこれを放置した。1年を過ぎたあたりでそろそろかと腰を上げ、問い合わせの手紙を送ったところすぐに返事が来た。論文を見落としていた、すぐに査読に回す、とのことであった。この時点で、私は「これは行ける」と思った。相手が恐縮しているのを感じたからである。論文はすんなり受理された。
もし今度、論文を投稿するようなことがあったら、たぶん同じように見落とされてしまうだろうから(内容の薄さ、インパクトの弱さには自信がある)、今度は10年くらい放置してみようかと思っている。
自分で忘れてしまうというオチが待っていそうだが。
2013.9.28
|
|
手術室看護師列伝(4)
|
かつて大学病院手術室の看護師長をされていたKさんは、男性だった。看護師長が「婦長」と呼ばれていた時代だったので、この人は「看護長」と呼ばれていた。私が個人的に知っている限り、男性の看護師長はこの人ひとりだけである。しかも、師長と言っても部下と必ずしもしっくり行っている人ばかりとはかぎらない中で、この人は看護師、医師を含めたスタッフから絶大な信頼を得ていたように思う。
男社会の中で女性が出世するのがいかに大変か、という話はよく聞くけれども、女社会で男性が出世するのもたぶん、同じくらい困難だと思う。たとえば、女性同士では次のような場面が発生する、らしい。
「あんた、怒られたからゆうて泣いても私には通用せえへんで。涙が落ちると器材が不潔になるやろ。落としないや。」
「つわりがひどいゆうても、妊娠は病気じゃないさかいな。出てきいや。」
なんだか、語尾の「や」が怖い。男としては、こういう話を聞くだけで失禁しそうになる。こんな世界を、Kさんは萎縮することもなく渡ってきたのだから、ただ者ではないだろう。
どのような秘訣があったのか、わからないけれども、少なくとも権威と威厳で部下を導いていたのではないことは確かである。小柄でいつもニコニコしていたし、人をしかりつけていた場面も記憶にない。おそらく、包容力とユーモアが決め手だったのではないかと想像する。私達麻酔科医も、手の空いているときなどにこの人としゃべるのが大好きだった。
今でもよく思い出すのが、オウム真理教の教祖が逃走の末、ついにどこかの屋根裏からひきずり出されて捕まった時のことである。
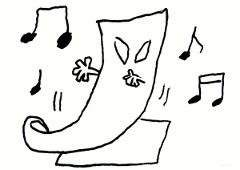 「わし、尊敬してたのに、残念やな。はは。」
「わし、尊敬してたのに、残念やな。はは。」
2つのサリン事件の主犯がこの教祖だと判明して以来、オウム憎し一色だった日本の中で、こんな力の抜けた冗談が言える人はそうはいなかったはずだ。やはり、ただ者ではなかったと思う。
2013.9.21
|
|
手術室看護師列伝(3)
|
Mさんと同じ病院の手術室の主任さん、こちらもかなり背が高く、押しが強く、あらゆる意味でMさんと並んで手術室のツインタワーといった風情であった。この人による、脊椎麻酔の介助は見ものであった。
脊椎麻酔とは、背骨(腰椎)の隙間から針を通して脊髄の周囲に麻酔薬を注入し、下半身にだけ麻酔をかける方法である。背中から注射をしなくてはならないので、患者さんには手術台の上で横向きになり、背中を丸めてもらう必要がある。その間、動くと危ないし、のけぞると針が通らないので、両手で患者さんのからだを支えるのが看護師の重要な役割りになる。今わざとやさしい表現をしたが、からだが動かないように押さえる、というのが本当のところかもしれない。主任さんはその名手であり、長い腕で患者さんをがっちり抱え込んで、「動きたくても動けなく」してくれるのであった。柔道の「押さえ込み」に似ている。麻酔科医としては実に頼もしい介助者であった。
あるとき、若手麻酔科医が患者さんに脊椎麻酔を施行しようとすると、これがたいへん敏感な方で、背中を指で触れただけで「ぎゃっ」とのけぞるので、なかなか針の穿刺まで持っていけないことがあった。介助していた主任さん、さらに腕に力を入れ、麻酔科医に目くばせをした。マスクをしていたから口元は見えなかったが、何の合図かは明らかだった。
「やっちまいな。」
 気迫に押された麻酔科医は、今度は何とか穿刺し、麻酔を成功させたのであった。
気迫に押された麻酔科医は、今度は何とか穿刺し、麻酔を成功させたのであった。
こんなことを書くと、極悪非道なことをしているように思われるかもしれないが、さっさと終わったほうが患者さんも楽だし、終わってしまえば「実はそんなに痛くはなかった」と言ってもらえることがほとんどだから、ひと思いに「やっちまう」ことは患者さんへのやさしさである、とご理解願いたい。
今でも、この主任さんのことを思い出すと、聞こえたはずのない「やっちまいな!」という言葉が頭にこだまするのである。存在そのものがパワースポットだと言えるだろう。もし再会したら、一度押さえこんでもらいたい気がする。
2013.9.14
|
|
手術室看護師列伝(2)
|
ある病院のベテランナース、Mさんの話である。この人はバツイチで子持ちの独身女性、スラリと背が高く、声がでかく、しかも有能な手術室看護師である。一言でいうと、怖いものなしであった。
あるとき、直腸の手術で出血が止まらなくなった。直腸周囲は静脈が多く、出血しだすと厄介なのだ。外回り看護師(つまりその手術室の支配者)をしていたMさんは、全く動じることなく、ガーゼカウントし、清潔介助の若手ナースを励まし、輸血の手配をし、と獅子奮迅の活躍をしてくれた。
 ガーゼカウントというのは、手術終了時に体内にガーゼが残らないよう、使用済みのガーゼを集めて数える作業であり、どんなに忙しくても、清潔ナースと声を合わせて数を照合しつづけなくてはならない。一旦数が合わなくなると、いつどこで無くしたのか、追跡不能になるのだ。
ガーゼカウントというのは、手術終了時に体内にガーゼが残らないよう、使用済みのガーゼを集めて数える作業であり、どんなに忙しくても、清潔ナースと声を合わせて数を照合しつづけなくてはならない。一旦数が合わなくなると、いつどこで無くしたのか、追跡不能になるのだ。
出血はなかなか止まらない。いらだった外科部長が、ドスの効いた声でMさんに因縁をつけてきた。
「おい、ガーゼカウントなんかやっとる場合か。見たらわかるやろ。」
手術帽を脱げばパンチパーマだし、小指があるのが不思議なくらいのコワモテの先生である。しかし、Mさんは「これが仕事ですから。」と全く取り合わない。私から見ても、ガーゼカウントをこなしながらもMさんの仕事は完璧で、とくにあれほど的確に輸血の手配をしてくれていなかったら(結構むずかしい仕事だ)、相当危なかったと思う。外科部長がなぜ文句をつけてきたのか、よく分からない。
2時間くらいかかっただろうか、ようやく出血が収まった。外科部長はまだ怒っていて、何やら捨てゼリフを残して去って行ったが、Mさんは全然平気だった。「よく血が出たっけだよー」と、あっけらかんとしている。
終わってみて分かったのは、駄々っ子とお母さんでは最初から勝負にならないということだった。
私は、「患者さんが助かったのはMさんのおかげですよ。」と言おうとして、やめた。地上最強の生物に、ほめ言葉はいらないと思ったからだ。
2013.9.8
|
|
手術室看護師列伝(1)
|
麻酔科医以上に世間の注目を浴びにくい手術室看護師(以下、オペ看)であるが、もちろん、その持ち場で華々しく活躍し、存在感を見せる人たちがいる。彼女ら・彼らの放つ光芒が手術室の外に伝わらないのはいかにも残念だ。少しずつ紹介していきたい。
あるとき、私は手術室コントロールルーム(看護師のリーダーさんが手術症例の出し入れをコントロールする、管制塔のような場所)で鉛筆立てをつつきながら、あるものを探していた。すると、たまたまそこにいた3年めの看護師が、「これですか。」と言って別のところからペン型修正液を出してくれた。私の探していたものである。
私は小心者なので、理解できない状況に遭ったとき、まず自分の身を守る行動をとる。この人は他人の考えが読める、超能力の持ち主である可能性があった。私がまっさきに行ったことは、自分の頭の中に住んでいるいろんな邪念を追い払うことだった。次に、彼女に聞いた。「え、どうして分かったんですか。」
彼女によると、私がペン立てから青いペンを取ってすぐに戻したのを見て、自分も以前そのペンを修正液と間違えたのを思い出したのだそうだ。超能力ではなかったようだが、おどろくべき推理力である。
そもそも、私はいつものように気配を消して(私の場合そこに努力はいらない)、人に迷惑をかけないように探し物をしていたのである。自分の背後でかさこそとゴキブリのような音を立てる私の存在に気づき、その手の動きを見て意図を汲み取る、これこそは優秀なオペ看のみがなせるすご技であった。
新米のオペ看はまず、清潔介助と言って外科医の手術の介助から仕事を覚え始める。メス、攝子(ピンセット)など、外科医に言われてから器具を渡すのでは全然だめで、手術の進行状況や術者の手の動きを判断し、つぎはどの器具が必要かを先読みしなくてはならない。それができるようになると外回りと言って、その手術の全般を仕切る仕事を任せられる。行動の舞台が術野だけでなくなり、麻酔科医の補助、手術室全体を仕切るリーダー看護師との連携、電話を介した外部との調整と、大量の情報から適切な判断を行い、予測し、直ちに必要な行動を起こす必要がある。
したがって、オペ看はあるレベルに達してしまうと、普通の人が見逃すようなささいなことからでもつい「気づいて」しまい、「先読み」してしまうようになるのだ。「これですか」の看護師はそういえば、手術室でもたびたび心を読まれているような気にさせられる人だった。やはり、ある種の超能力と言える。
 後にこの人が結婚すると聞いたとき、美しい人でもあったので、相手の男性をうらやましく思うと同時に、同情の念も禁じえなかった。お釈迦様の手から孫悟空が逃れられないのと同じくらい、こういう人の目はごまかすことはできないからだ。
後にこの人が結婚すると聞いたとき、美しい人でもあったので、相手の男性をうらやましく思うと同時に、同情の念も禁じえなかった。お釈迦様の手から孫悟空が逃れられないのと同じくらい、こういう人の目はごまかすことはできないからだ。
たとえば、何かの会費を郵便局で振り込んで、給与口座を押さえているオペ看妻に請求したとする。
「この振込みの控え、どうしてコピーなの?」
本物は職場に提出し、経費からも落とすために取っておいたのだが、あわててカバンから取り出す。
「あ、なんでコピーなんか出しちゃったんだろうね。」
とか何とか言いながら。
まるで見てきたような生々しいシーンであるが、あくまでも例え話である。あしからず。
かの人の夫よ、お察しします。
2013.9.7
|
|
ゴッドハンド麻酔科医
|
前回、「仕事柄、器用さに敏感」と書いたが、それは以下のようなことである。
麻酔は穿刺、挿管など、物理的手段に訴えて患者さんのからだの機能にアプローチする仕事だが、それでも手術に比べれば必要とされる技術の幅は狭い。麻酔科で後進を指導していて思うことだが、器用な人のほうが技術の習得が速いのは確かだが、2年もやっていれば不器用な人も追いついて大きな差はなくなってしまう。結局みんな、普段の診療には全く困らないレベルになる。
臨床で一番大事なのは、器用で習得が速いかどうかではなく、一度手に入れた技術を確実に発揮できるかどうかである。
ただし、本心を言えば、やはり腕の差というのはどこかに残っていてほしいとも思う。いまここで成功させなければならないときに、一発で決められるかどうか、その辺で麻酔科医としての力が試されることがある。たとえば、手術中に予想外の出血が発生したときに、唯一アクセス可能な静脈をきっちり確保するとか、全身麻酔は絶対に避けたい患者さんの脊椎麻酔を普通に成功させるとか、そういう場面である。
そういう意味では、若い麻酔科医が手先の器用さを追及するのは悪いことではないと思う。
だが、麻酔は器用さだけでは十分でない。ここで、若い麻酔科医とそれ以外の人たちのために、私の敬愛する先輩を紹介しよう。
昔、大学病院に、仲間から「ゴッドハンド」と呼ばれる麻酔科医O先生がいた。この人は本当に手先が器用で、たとえば私が誤って粉々に割ってしまった麻薬のアンプル(薬剤部に返却しなければならない)を、鼻唄を歌いながら接着剤を使ってもとの形に戻してくださったことがある。麻酔の技術もあっけにとられるほど鮮やかで、手術室で何か困ったことが起こればすぐに呼ばれていた。O先生は呼ばれてもいやな顔ひとつせず、さっと問題を解決して、得意げな顔ひとつ見せず、引き揚げて行かれたものである。
あるとき、幼い子が耳に何か突っ込んで取れなくなったということで、耳鼻科が全身麻酔を依頼してきた。O先生が麻酔をかけ、手術をセッティングしたものの、肝心の耳鼻科医がなかなか手術室に現れない。そこで手持ち無沙汰のO先生は耳の中を覗き込み、奥からその異物を取り出してしまった。しかし、それでは耳鼻科医の立場がなくなる。O先生はその異物を、耳の穴の入口のところにそっと戻したのであった。
ゴッドハンドと呼ばれたのは、手先のことだけではなく、そのおしゃれな仕事っぷりを愛されたからでもある。ぜひ参考にしていただきたい。
2013.9.1
|
|
利き手
|
医療機械というのは右利き用に作られている。海外には左利き用の道具があると聞くが、私は日本では見たことがない。
麻酔科でも、たとえば気管挿管に使う喉頭鏡は左手に持つように作られていて、微細なコントロールを必要とする挿管操作は右手で行うようになっている。麻酔器は右側と決まっているし、とにかく右利き有利なのは間違いない。
しかし、左利きの医師を気の毒に思い、左利きは大変ですね、というと、結構な確率でこういう答えが返ってくる。
「あ、いや、右手も使えます。両手利きなんです。」
うらやましいと思う一方、ちょっと心配もある。両手が同じくらい使えると言いたいのだろうが、両手とも同じくらい「利いていない」可能性も排除できない。ストレートに言えば、不器用ということだが、本人は気がついていなかったりする。だから、「両手利き」とはあまり言わないほうがいい気がする。
仕事柄、人の器用、不器用には敏感なもので(自分のことは置いといて)、ちょっと辛口になりました。
2013.8.31
|
|
人間臨終図巻、その三
|
大岡昇平の「武蔵野夫人」は、戦後間もなくの武蔵野を舞台とする恋愛小説である。例によってストーリーはあまり覚えていないが、結末だけは印象に残っている。道ならぬ恋に悩むヒロインが大量の睡眠剤をのんで、一時は持ち直すものの、やがて再び「呼吸が弱くなって」、亡くなってしまうのである。亡くなったのは病院ではなく、自宅だったと思う。
なぜ印象に残っているかというと、人工呼吸さえしていればこのような死はおそらく避けることができたのに、その技術がなかったばかりに若く美しい女性が亡くなったのを残念に思ったからであり、また、人工呼吸の歴史がこれほど浅いということを再認識させられたからだ。
で、なぜこのようなことを書くかと言えば、重症患者への人工呼吸について書けば書くほど、現在の医療に批判的な人たちを勢いづかせるような気がするからだ。
「大往生を邪魔するのは医者だ。医療に近づくな。」
「治療が人を殺している!」
だが、人工呼吸により急場をしのいで助かっている人がたくさんおられるのは事実である。武蔵野夫人は、現在であれば助かっていた可能性が高い。命を預けられた医師としては、その可能性のほうに賭けないわかにはいかない。
もちろん、誰にでも無差別に人工呼吸を施すわけではない。がんや慢性呼吸不全の末期など、回復可能性のない方、高齢の患者さんで、ご家族からこのまま見送りたいと申し出られたような場合などは、人工呼吸は行わない。それくらいの良識はある。
一方で、人工呼吸により死の尊厳が損なわれているのでは、という弱気もまた、持ち合わせ続けたいと思う。
よい知らせもある。近年、呼吸不全に対して、気管挿管を必要としない人工呼吸法が増えてきている。非侵襲的陽圧換気(NPPV)といって、密着型のマスクを顔に当て、酸素で加圧するのである。徹底した治療を望むならば気管挿管の方が有利と思われるが、NPPVでもかなりのところまでは行けると考えられるようになってきた。薬石効を奏せず、という場合も NPPVのままで最期を看取る、ということが増えてきている。
これならばしゃべることができる。こんな状況で、とっておきの最後の言葉を遺すのは実際には非常に困難だが、少なくともそのチャンスは、患者さんの手の中にあるのである。
戦後、「人間臨終の図」はずいぶん変わったかもしれない。しかし、もともと、「納得のいかない死に方」ばかり小説に書き続けてきた戦中派作家山田風太郎ならば、「なーに、さして変わりはないさ」と、我々にとって少しは気休めになるようなことを言ってくれそうな気もする。
2013.8.27
|
|
人間臨終図巻、そのニ
|
ICU や救急外来などで、患者さんの命を助けるために行う気管挿管だが、本当にいいことをしたのか、わからなくなることがある。そのまま亡くなってしまったような場合である。挿管してしまうと声が出ないし、またその後は鎮静剤を使い続けるから意思表示もできなくなることが多い。最後に言いたいことがあったのではないか、その最後の言葉を奪ったのは自分ではないかと気に病むのである。
自分が患者だったらどう思うだろう。助かる可能性があるのなら、治療はしてほしい。だがその結果、もしだめと決まったら、その時は教えてほしい。覚悟を決めたら、走馬灯のように自分の人生が目の前でくるくると再現されるのではなかろうか。走馬灯の実物を見たことはないが、恥ずかしいシーンは早送りできるくらいの機能はついているだろう。最後の言葉も言わせてほしい。聞いてくれる人がいればの話だが。
だが、一旦挿管してしまうと、そのように引導を渡し、渡されるようなことは難しくなる。それなら挿管の前に、こう聞かれたらどうだろう。
「何か言い残すことはありませんか。」
この時点ではまだまだ助かる可能性があるのに、こんなことを言われたら、それだけで逝ってしまいそうだ。
結局、なかなかうまく行かないのである。挿管されたまま亡くなるケースは実際にはまれである。だが、自分の言葉を確実に遺したい人は、いま注目の「エンディングノート」のようなものを活用したほうがいいだろう。
私も文具屋でコクヨのエンディングノートを買い、隠し財産も隠し子もないことを婉曲に表明したが、肝心の「大切な人へのメッセージ」欄にはいまだ書き込めないでいる。もしも私がここに偽りなき本心を書き込んだりしたら、取り返しのつかないことになるかもしれない。まだ私が元気なうちに「どれどれ」などと読まれたりしたら、笑われるか、激怒されるか、どっちかしか想像できないのだ。
目の前に走馬灯が現れた頃に書くことにしよう。
2013.8.24
|
|
人間臨終図巻
|
山田風太郎(1922年−2001年)は、忍法帖シリーズや明治もので戦後に一世を風靡した小説家である。医大を出ているが、医師として仕事をしたことはないはずだ。この人の膨大な著作の中でも奇書と言われるのが「人間臨終図巻」である。歴史上の著名人、芸術家の死に際の言動の記録を、洋の東西を問わず手当たりしだい蒐集し、機械的に死亡時年齢順に並べていったという本である。
内容はあまり覚えていないが、偉大な人物があまりかっこよくない死に方をしたり、悪人がみごとな散りぎわを見せたり、そういう場面を無造作に並べていけるところは、この天使的に非人情な大作家の面目躍如といえる。
さて、臨終の場面の中でも、特別の重みを持つのはやはり最後の言葉である。本人はそのつもりはなくても、周囲があれこれ考えてしまう。ゲーテの「もっと光を」は、もうちょっと部屋を明るくして欲しかっただけという説もあるが、ゲーテが言ったのだから深い意味がある、でいいのだ。板垣退助の「板垣死すとも自由は死せず」というのは、後からの創作と言われるが、それでもこれだけで一幕のドラマを見たかのような思いにさせられるのだから、名セリフである。(もっともよく考えれば、彼はこのときの襲撃を生き延びているから、最後の言葉ではなかった。)
私も、何かかっこいいことを言って死にたいが、あまりに強く日頃の思いを込めようとすると、「もっとおこづかいを」などと口走ってしまうおそれがある。「あ、どうも。(がくっ)」などと、聞いた人が顔を見合わせるくらい意味不明なほうが自分らしくていいかな、と思う。
ただ、現代の病院で死を迎えるにあたっては問題が出てくる。ごく一部の重症患者さんに限るが、人工呼吸のために気管挿管されている場合、最期の言葉を伝えたくても声が出ないのだ。「あ、どうも」など、かねてから練りに練った言葉が不発に終わったりしたら、無念極まりないのではなかろうか。
私はこれまで麻酔科医として、手術患者だけでなく、人工呼吸目的の重症患者にも数え切れないくらいの気管挿管を行ってきたが、このことをけっこう気に病んできたのである。
次回につづく。
2013.8.18
|
|
麻酔科医と手術、その弐
|
前回書いたことと矛盾するようだが、実は麻酔科医が見ていて、あ、やって見たいと思う手術もある。人によって違うだろうが、私のベスト3を挙げると、次のようになる。
第3位。膀胱結石を砕く手術。
これは、膀胱にできた結石を内視鏡で見ながら、これにワイヤーのようなものを当て、衝撃を与えて砕くという手術である。あたかもゲームセンターで戦闘機から機関銃を射っているかのような、タッタッタッという小気味よい音とともに、結石が崩れて行くのである。
「楽しそうですね。」と泌尿器科の先生に声をかけると、
「そう見えますけどね、根気がいるし疲れるんですよ、これ。」と、苦しそうな顔でおっしゃる。たぶん、演技だろう。
第2位。鼻内視鏡。
副鼻腔炎、いわゆる蓄膿の手術と言えば、昔は、鼻の奥とか我々素人にはよくわからない場所から骨に穴をあけて、ヤスリのようなもので何やらごりごり穴を広げる痛そうな手術という印象があった。今は違う。太いまっすぐな内視鏡を、どこかわからないが鼻の奥に突っ込んで、骨とか粘膜とか鼻茸とかを見える範囲で剥がしまくり、掻き出しつくす手術なのである。この術式になって、副鼻腔炎の手術は非常に満足度の高い手術になったらしい。
麻酔から醒めたばかりの患者さんに、耳鼻医が、「もうこれですっきり通りますよ。」と断言するのを聞いて、ああ、うらやましいと思った。麻酔でも手術でも、治療直後にこんなふうに勝利宣言できることはまれである。
もし自分にまかせてもらえるなら、ペンペン草も生えないほどに、と夢想はするものの、本当は解剖(からだの構造)が分かっていない者がやみくもに突き進むと向こうの壁を破って、出てきてはいけないものが出てくるらしい。所詮素人にできる手術ではないのだ。
第1位。抜歯。
同業者には説明不要だが、一般人のために解説する。
あらゆる麻酔合併症のなかで、気管挿管のときに歯が抜けてしまうほどショッキングなものはない。抜けた歯は、決してもとには戻らないからだ。もし許されるなら、そのままへなへなと床に崩れ落ちたくなるほどのショックなのである。だから、挿管のときに注意力と心配力の半分は、歯に注がれる。
それほど麻酔科医を苦しめる歯であるが、歯科の先生はそれを患者さんに頼まれて、白昼堂々と抜くのである。見ている我々のねたましさはもはや頂点である。全身麻酔での抜歯は、難しいオヤシラズが多く、とても真似できないけれども、中には未治療のぐらぐらになった歯を片端から何本も抜くだけという手術があり、それなら自分にもできるのに(勝手な思い込みです)と思うと、もはやため息しか出ない。
歯科の先生に聞くと、抜歯する瞬間はやはり、少し気持ちいいそうである。くそっ。
それにしても、こうして並べてみると、砕くとか、掻き出すとか、抜き去るとか、効果音つきのオオワザ系の手術にばかり目が行っていることに気づく。手術で難しいのは、術後の機能回復である。腸の手術なら、食べられるようにならないと意味がないし、骨の手術ならその手や足を使えるようにならなければ意味がない。取ってしまえばおしまいという大雑把な手術(あくまで思い込みです)にしか魅力を感じない私は、やっぱり外科医には向いていないということだろう。
麻酔科でよかった。
2013.8.10
|
|
麻酔科医と手術、その壱
|
胃切除術が着々と進行している。麻酔科A医師は術野を覗き込み、外科医に話しかけた。
「ほう、吻合はビルロート I 法ですか。リンパ節郭清もしっかりしたし、今日の手術は完璧ですな。」
…
などという光景は実際にはまずない。大抵の麻酔科医は手術の細部には驚くほど無関心である。どんな吻合法で胃と腸をつないだとか、リンパ節をどの範囲まで取ったかといったことは、術後早期の患者さんの全身状態とはほとんど関係ないからだ。麻酔科を長くやっていて思うことだが、手術中に起こることの中で患者さんのからだの負担(手術侵襲という)と関係があるのは、手術時間と出血量、この2つだけである。短時間で少ない出血量で終えることのできた手術ほど、術後の経過がよいのである。
術中、むずかしい顔をして麻酔管理している麻酔科医の心の中を覗いてみれば、そこにあるのはただ一言、「さっさと終わってくれへんかな」、だったりする。
まじめにやれ、と言われてしまうかもしれないが、手術に夢中になる人と、少し引いたところから全体を見る人と、2種類あったほうがバランスがよいのである。 ものの見方の違う者同士が力を合わせて働く。そこに手術室の仕事の妙味があると思う。
2013.8.9
|
|
理想的加温装置
|
全身麻酔がかかると、ほとんどの場合、患者さんの体温は低下する。体温調節をつかさどる脳の機能が落ちるからだ。まして腹部の手術となると、術野から熱を奪われるので、余計体が冷える。近年では温風を使った加温装置があるから以前よりはましだが、それでも麻酔中は体温が下がることが多く、いったん冷えたからだをもとの体温に戻すにはかなりの時間がかかる。何かいい手段はないだろうか。
1890年(明治23年)、オスマン帝国(大体今のトルコ)の軍艦が和歌山県串本町沖で沈没し、多くの犠牲者を出した。エルトゥールル号遭難事件である。このとき、村民が村を挙げて船員の救出に努め、冷え切った生存者のからだを温めるために裸になって添い寝したという。男同士(たぶん)だからちょっと異様な光景だったろうが、一説には、それは昔から村に伝わる、溺水者蘇生のもっとも有効な手段だったという。
たしかに、技術の進歩した現在にあっても、この人肌加温はメリットが多く、魅力的な方法だ。
まず絶対にヤケドしない。これまでにあった手術用加温装置はつねに、ヤケドのリスクという問題を抱えてきた。しかし人肌なら安全だ。他人の肌に触れてやけどさせられる人がいるとすれば、熱病にかかって死の床についた平清盛くらいであろう。(そばに置いたお椀の水が沸騰したそうだ)
熱伝導効率という面でも人肌は理想的だ。温風加温装置の場合、空気から肌に熱を移動させることになるので、スピードが遅い。人肌ならば水からの熱伝導と同程度と考えられるので、加温はずっと速いはずだ。(缶ビールを冷やすなら冷蔵庫より氷水のほうが速いのと同じ。)人の代わりに猫をあてがうのはどうかという提案に対しても、この理由で却下できる。猫の周辺で温かいのは猫自身のみであって、毛皮に含まれる大量の空気のせいで、人を温める能力では「毛なし」の人間には遠く及ばない。さらに、猫にはひっかく、噛む、立ち去るなどの副作用があり、とても採用できない。
エコロジーという面でも優れている。この装置のエネルギー源は、ごはん、ラーメン、たこ焼きなどである。化石燃料を使わない(あえて使うと故障する)から、人は温めるが地球は温めない。
この理想的な加温装置を臨床応用しない手はない。手術が済んだら医者が二人ほど術衣を脱ぎ、患者さんをはさんで川の字になるとよいのではないだろうか。からだを張った治療である。ただ、患者さん、医師いずれかに女性が混じると途端にややこしいことになる(私の首が飛ぶ)から、考えないことにする。
麻酔中の患者さんの体温が下がってしまったとき、研修医にこの感動的な話を教える。そして、部長として厳しい口調で指示をするのだ。
「えーと、もし恥ずかしかったら、あっちを向いておくけど?」
今まで、無視されなかったことはない。
2013.8.1
|
|
最期の閑談
|
私もかつて人並みにフェイスブックに参加して、つまらない話や写真を見せられたり、つまらない話や写真を載せたりしたものであるが、あるときやめたくなったのでやめることにした。
やめるのは意外に簡単だった。何の前触れもなく単純にアカウントを削除しただけである。何が起きたかというと、全く何も起きなかった。現実世界で顔を合わせている人たちから、「やめたんですか、戻ってこないんですか」などと言われるのかと思ったが、ただの一回も聞かれなかった。
SNSが苦痛になってきている人たちの参考になればと思い、書かせてもらうが、誰かがネット上の社会から蒸発したところで、誰も困りはしないし、心配もしないのだ。
というわけで、「麻酔科パラダイス」も蒸発の時が来た。(「入り口」参照あれ)
医療という題材が題材だし、なによりも私は現役医師なので、無邪気に好きなことを書きちらすわけにもいかず、内容にはけっこう気を使った。このサイトの維持は楽しみでもあったが、心配やためらいもあった。そもそも誰のために何を書いているのか、自分でもよくわからなかったが、メールをくださった方が3人あったのと、自分で読み返してみたらそれなりに面白かったということもあって、4年ほど続けることができた。そろそろこの辺でよか、というのが現在の気分である。
ちなみに、「そろそろこの辺で…」というのは、西郷隆盛が部下に介錯を促す最期の言葉である。そんなに好きな人物ではないが、この言葉は和風でよい。「海底二万里」のネモ艦長の最後の言葉、「全能の神よ、もうたくさんだ。」の絶望に比べ、余韻に味わいがある。
そう書いてしまうと、このサイトの最期の言葉も気の利いたものを選びたくなるが、あえて普通に終わらせていただく。2012年4月6日の「閑談」からの引用。
「また、ご縁がありましたら。」
2013.7.3
完
|
|
新人の心のケア
|
新人研修医は大変だ。それまでの気楽な人生から一変し、就職するやいなや非常に思い責任を負わされる。責任が重いだけに、最初は怒られてばかりだ。(こちらは注意しているつもりだが、あちらは怒られていると感じるらしい。)いつ、心身のバランスをくずすかわからないので、周囲は気をつけてやる必要がある。
私:「どう、ストレス溜まってる?」
研:「同僚や上の先生との人間関係がややこしいです」
私:「そういうときは、その人の悪口を言うのが最強最善の解決法だよ。今ここで言っていいよ、聞いてあげよう。」
研:「いや、それはちょっと」
私:「もっと高度な技として、めんどくさいと思っている相手に直接相談してみるというのもあるよ。うちの下の子が幼稚園の頃、お風呂の中で兄に向かって言ったんだ。『おにいちゃん、相談があります。おにいちゃんがいじめてくるんです。どうしたらいいでしょう。』幼稚園児でもできるんだから、先生にもできるかもね」
研:「そんなことできませーん」
あとで考えなおしてはっとした。その研修医は私に対して、すでにそれを実践中だったのかもしれない。心のケアはむずかしい。
2013.6.22
|
|
配偶者呼称問題
|
たいしたことでもないのに、頭の中でひっかかりがちな問題というものがある。病院前で患者さんが吐き出す煙草のけむりをどうやって回避するか、このまま順調に禿げあがって頭髪がなくなった場合、手術帽は免除してもらえるのか、そういうささいなことである。相手や自分の配偶者をどう呼ぶか、という問題もその一つだ。
このサイトが、ささいな、どうでもいいことのみを取り扱う場だからよかったようなものの、そうでなかったら無視されるような問題である。
女性と話しているとき、その夫のことを普通、「ご主人」、「旦那さん」などと呼ぶ。これは多分、夫が家長として絶対的権力を保障されていた戦前のなごりであろう。しかし現在、そのへんの子供に、「お父さんとお母さん、おうちではどっちが偉い?」と聞けばすぐわかるように、これらの呼称はすでに実態を表していない。夫婦間の平等を保障する憲法24条を振り回す人がいるとすれば、それは今や夫のほうだ。「憲法に保障してもらってよかったね」と言われるだけであろうが。
ただ、テレビで田嶋陽子氏などの言動を見るにつけ、女性がいまだに不当に虐げられていると主張している人がいるらしいのが心配だ。そういう人に向かって、「あなたのご主人」、「旦那さん」などと言ったら怒鳴られるのではないだろうか。田嶋陽子氏に面と向かって怒鳴られたら怖そうだ。ではどう呼ぶか。これがいい言葉がないのだ。
「夫」、「配偶者」では無骨すぎる。「夫さん」はコッケイだ。「お相手」では何の相手かわからない。唯一納得できる呼称が「ご夫君」という言葉で、故人となった中島らもという作家がエッセイなどで使っていた。この人は無頼派なのに、妙に律儀なところもあるのだ。ただ「ゴフクン」と言われて通じる人のほうが少ないと思うだけに、会話の中で実際に使う勇気はない。
医師は患者さんに対して、ある程度常識的な振る舞いをすることが期待されているから、診療では結局、「ご主人」という言葉を使わざるを得ない。相手が女性医師の場合はあえて「夫のかた」などと不自然な日本語を使ってみたりするが、その女性が「うちの旦那が」とか「主人は」などというので、私の苦労はここでも報われることがないのであった。
やっぱり、誰にとってもどうでもいいことだった。
2013.6.15
|
|
麻酔科医の眼力
|
数年前に「医龍」という医療ドラマがあったが、そのなかに出てくる麻酔科医荒瀬が麻酔を極めた男で、たとえば患者や同僚の体重をぴたりと当てるという能力を持っているのであった。これを見てあせった私は、患者さんの体重を見た目だけで推定することに凝ったものであるが、私のような平凡な麻酔科医でもけっこう近い数字は言い当てられるものだと分かった。
しかし、体重を当てるならば麻酔科医よりも体重計のほうが信頼できる。本当に麻酔科医の眼力を証明したいのであれば、術前診察で初めて対面した患者さんの見た目から健康状態を言い当てるほうがかっこいいし、実用性も高い。プロとして当然、と言いたいところだが、これはそう簡単ではない。カルテで病歴や検査結果を見たり、ご本人と話をしてみて初めてわかることも多く、むしろ見た目から先入観を持ってしまうと判断を誤るケースもある。たとえば重症敗血症なのに顔色がよく、高齢ながら意識がしっかりされているような場合があり、見た目に頼りすぎると楽観から対処が遅れてしまうのである。シャーロック・ホームズのようには行かないのが現実である。
もしも、自分は患者を一目見ただけで病状がわかる、などという医師がいたら、その人には占い師のほうが向いているだろう。
健康状態よりもさらに判断の難しいものがある。女性の年齢である。患者さんの年齢はさすがにあらかじめ知っているから間違えることはないが、患者さんに女性の家族が付き添っていると、いきなり厳しい状況に追い込まれる。その女性が患者さんの妻か、母親か、兄弟か、ひょっとして娘なのか、皆目見当がつかないのである。こんなとき、当てずっぽうはまずい。
「えっと、奥さんです…よ…ね」
「いえ、娘ですが」
などという事態は絶対に避けなくてはならない。私は何度かの失敗の末、この件に関しては完全に諦めており、「お家のかた」、「ご家族」と呼ぶことにしている。
女性の年齢判定問題は、麻酔科医の眼力が到底届かない場所にあるのである。
2013.6.8
|
|
散髪
|
散髪するとその次の日、手術室で数人のナースから、「散髪したんですね」と声をかけられる。なぜそのようなどうでもいいことをわざわざ指摘するのか、不思議で仕方がない。もし、散髪した理由を質問してくれれば、「失恋したので気分転換に」とか、「おじいちゃんの遺言なので」などと答える用意があるのに、質問はしてくれない。単に指摘するだけなのだ。
最も不可解なのは、声をかけてくる人全員が、「素敵ですよ」を付け加えるのを忘れることである。
2013.5.28
|
|
口渇
|
戦時中の話や映画などで、重傷を負った兵が水を欲しがり、うっかり水を与えると兵が「うっ、がくっ」と死んでしまう場面が出てくる。逆に軍医が、「飲んだら死ぬぞ」みたいなことを言って激しく拒む場面もある。これがどういうことなのかがわからない。
外傷時に口渇を覚えるのは、合理的である。出血に対して循環血液量を確保するため、からだが水分を欲するのは当然だ。
現在の医療ならば、出血に対しては輸液を行う。たしかに輸液のほうが飲水よりも効果が早いし、腸管損傷があった場合の体内での水漏れや、肺への誤嚥を気にする必要がない。だが、輸液の準備がないという状況で、唯一の補液手段である飲水を禁じる合理性がどこにあるのか、わからない。水を飲んだくらいで死んでしまったとしたら、たぶん、水を飲まなくても早晩死んでしまう人だということではあるまいか。そういう人は仕方がないのだとして、まだ生きられそうな人に水を与える意義は大きいはずだ。そういう極限状況の話は、現在の教科書には書いていないのである。医学論文検索サイトで調べてみても、わからなかった。
これは、医療の発達していない過去の話とばかりは言い切れない。大災害などあれば、多数の負傷者に対して輸液の備蓄が足りなくなるということはあり得る。その際もし、重傷の患者から水を要求されたら、昔の軍医のように「飲むな」と叱る理由がない。しかし、負傷者が水を飲んで死んでしまうシーンが頭をよぎったりすると、飲水はさせるべきだと言い切る自信もない。
麻酔科の同僚に聞いてみたが、やはり首をかしげるばかりであった。ただ、一つの有力な意見として、次のようなものがあった。
「よく、冬山遭難のシーンで、寝たら死ぬぞ、なんて言いますが、あれは逆で、死にそうだから寝てしまうんじゃないかと、前から思ってたんです。それと同じでしょう。水を飲んだから死んだのではなくて、死にそうだから水を欲しがるのかもしれません。それならば、末期(まつご)の水を我慢させるのはかわいそうじゃないですかね。」
なんとなく説得力のある説明だった。自分がもしそんな場面に出くわしたら、水を飲ませてあげそうな気がする。もっと確信を持って言えるのは、自分が重傷を負って水を欲したら、どうか飲ませて欲しいということだ。
2013.5.25
|
|
そばめし
|
当院麻酔科に神戸の外からのお客さん(麻酔科に見学に来た学生さんなど)があれば、近くのお好み焼き屋から「そばめし」を取り寄せることが多い。ご存じない方のために説明すると、焼きそばにご飯をまぜて炒めたもので、神戸発のB級グルメである。
これは、恐ろしい食べ物である。
 その発泡スチロールのパックの重みに動揺しつつも、食べ始めると、うまい。これは誰もが認めるところである。だがここからが長い道のりだ。
その発泡スチロールのパックの重みに動揺しつつも、食べ始めると、うまい。これは誰もが認めるところである。だがここからが長い道のりだ。
いくら食べても、なかなか減らない。量が多すぎるのだ。当たり前のことだが、味は最後まで微動だにせぬソース味だから、味わいを楽しむ段階は前半で終わり、後半はもう、完食への義務感で箸を運ぶ状況である。なんとか食べきった後、がぶがぶお茶を飲みながら(塩分もすごい)、いろんなことが頭をよぎる。
「一体どれくらいのカロリーがあるのだろうか。普段の節制が台なしだ」
「誰がこんな、でんぷんのカタマリのような料理を注文するのか。自分だが」
「もうこの先1年は、食べないでいいな」
こうやって、甘酸っぱい後悔にしばし浸るところまでが、そばめしの味わいのうちである。塩辛さのあとに甘酸っぱさを引き出すところは、もはやB級グルメを超越している。
そして、その固い決意もむなしく、またお客さんが来たら、つい注文してしまうのである。
お客さんのほうも、おしゃれ(そう)な街神戸に来て、まさかこんなものを食べさせられるとは思わなかっただろう。
2013.5.22
|
|
ろくなもの
|
アメリカの何かの小説の中に、こんなセリフがあった。
「この世の中に、ろくなものは何一つないが、アスピリンだけは別だ」
アメリカ人のアスピリン好きは有名だが、それにしても世の中を語る場面で唐突に鎮痛剤の名前が出てくるところはさすがである。この、ひねくれもの(としか思えない)の中年男を、アスピリンだけは満足させていたのであろう。
ペインクリニックなどで痛みの治療をしていて思うことだが、痛みが取れるというのはかなり劇的な体験である。痛みは生命への脅威を知らせる危険信号であり、したがって常に不快でいまわしいものとして感じられる。気持ちの良い痛みというものは原則としてない。したがって、痛みが取れる、しかも薬や神経ブロックなどで急速に痛みが止まるという体験は、危機から逃げおおせたという、本能的な喜びをもたらすようなのである。慢性疼痛の治療はなかなかうまくいかないことも多く、ストレスを感じることがしばしばであるが、時に痛みが取れる瞬間を患者さんと共有できることがあり、文字通り「痛快な」気分である。
手術室での麻酔はちょっと違う。最初から痛みを感じないですむように、神経をブロックしたり、全身麻酔で眠ってもらったりする。痛みからの開放という劇的瞬間は訪れない。手術を受けられる患者さんの中で、麻酔科医の存在感が薄いのは必然であろう。麻酔科医は自分の心の中で「痛快さ」を味わうしかない。
「この世の中に、ろくなものは何一つないが、麻酔科だけは別だ。」
と言っている人がもしいたら、そいつは麻酔科医だ。
2013.5.16
|
|
瀉血
|
「フェルマーの最終定理」、「暗号解読」(いずれも新潮文庫)などで知られるサイモン・シンは、おそらく現代最高のサイエンスジャーナリストだろう。その最新作が、「代替医療のトリック」(共著、新潮社)である。この本の中で、あらゆる医療行為は「臨床試験」によってその効果を確かめられるべきであることが、医学の歴史を踏まえて説き明かされている。そして鍼(はり)治療、カイロプラクティック、ホメオパシーなどの代替医療(通常医療に代わる医療)をこの「臨床試験」という試練にかけた結果、ほぼ全滅であると宣言している。つまり、ごく一部の治療効果(ある種の痛みに対する鍼の効果など)を除き、これらにはプラセボ以上の効果がほとんど認められないというのである。
この本では「通常医療」、つまり病院などで健康保険の中で行われている医療がしばしば引き合いに出され、ほとんどの場合において通常医療の側に軍配をあげている。ある意味では意外性のない結論であるが、このような本はお金儲けにつながらないため、めったに目にすることがない。「医療にかかわるな」とか、「医者に殺されない…」とか、「がんが消えた」とか、鬼面人を驚かすような本が横行する世の中にあって、さすが科学者の良心に恥じない本を書く人であると感銘を受けた。
ただ、こんなテーマで本が売れるのだろうかという懸念はある。これまでのシン氏の本のように文庫化されるかどうか、たぶん微妙な所だろう。
この本の中でもっとも刺激的なのは、現代の代替医療の話ではなく、過去の欧米の正統医学のなかでも王道の中の王道、瀉血(しゃけつ)の話である。トルストイの「戦争と平和」などにも、たしか、気分を悪くされたご婦人を治療するために医師が瀉血を行なう場面があり、以前から気にはなっていた。この瀉血、過去の欧米では、香港におけるタイガーバームのように、あらゆる病気に対して効く万能の治療法だったようなのである。「悪い血を抜く」くらいの意味合いであろうが、現在ではうっ血性心不全など特殊な症例を除いては有用性が考えられない治療である。驚くべきはアメリカの初代大統領ワシントンの最期で、彼は具合が悪くなった時に次々にいろんな医者にかかり、そのたびに瀉血されたため、おそらく失血死したのであろうということである。
やがて勇気ある医師たちが、瀉血を行う患者と行わない患者に分けて、治療効果を比較したところ、瀉血群の死亡率が圧倒的に高いことが証明された。人間の思い込みや直感というものがいかにあてにならないものか、効くと信じられている治療でも、それを実証することがいかに大事なことか、考えさせられる。
臨床医学では、いまだに臨床試験を経ていない慣行的治療は多く残っている。たとえば、帝王切開や心筋梗塞などの危機的な状況では酸素を投与するのがよいと信じられてきたが、最近では特にその必要性はないという研究が出てきている。また、そもそも臨床試験の不可能な分野もある。開腹手術に本当に麻酔が必要なのか、麻酔なしでやるとどうなるのか、ちゃんと調べられていないだろうが、こんな試験に参加する被験者がいるわけがないから、検証は不可能だ。
せめて、自分たちのやっていることを疑う謙虚さを忘れないようにしたいものだ。
(ちなみに、いくら謙虚になったからといって、以前ここで取り上げた「医者に殺されない…」の近藤誠氏の肩をもつことはできない。医療批判の一部には正しい部分はあるものの、「がんは放置せよ」との決めゼリフはいくら何でもひどすぎる。がんの種類によるが、本当に放置なんかしたらどんなことになるか、反証となる実例をいくらでも挙げることができる。これは臨床試験以前の問題だ。)
2013.5.11
|
|
エリート
|
医師が事件を起こしたり、巻き込まれたりすると、週刊誌などで「エリート医師がなぜ?」などという見出しをつけられてしまう。(ちなみに、看護師だと無条件で「美人ナース」である。)だが、医師だからと言ってエリートとは限らないはずだ。
エリートというのは辞書によると、優れた資質を生かして指導的地位についている人を指すようである。この「指導的地位」というのが重要で、高いところから人に命令するのが仕事ということだろう。医師はちょっと違うような気がする。それは、私がスーツを買いにデパートに行った時の、店員さんとの会話を聞いていただければわかるはずである。
店「スーツはお仕事で着られるのですか?」
私「いや、仕事中は作業服(術衣のこと)だし、通勤もスーツじゃないですね」
店「じゃあ、どういった時に?」
私「会議のときだけ(学会のこと)ですから、年2回くらいですかね。」
ここから分かるように、医師は本質的に現場労働者である。厳密に言えば、少なくとも神戸に住むある麻酔科医は現場労働者である。その人は、大工さん用の作業靴「親方満足」を履いて仕事をしているほどだ。
もしエリートというものが、現場を離れて命令だけしているような人なのだとしたら、気の毒な人もいたものだ。
2013.5.4
|
|
お気遣い
|
緊急手術で自宅から呼び出され、術前診察で患者さんを訪れると、患者さんのご家族から、「まあお休みのところすみません。」と声をかけていただくことがある。こういうお気遣いはまことにありがたい。
医者なんだから夜間休日も働くのは当たり前、と思っておられる人が多いのではないだろうか。そうでもないのです。麻酔科が毎日一人は院内で当直している、などという病院は多くはない。普通の病院では、必要が生じた時に自宅や外出先から呼び出されているのである。麻酔科医どうしで話し合って呼び出し待機当番を決めるのであるが、当番できる者が2人しかいなければ2日に1回まわってくる。(麻酔科医1人の病院だったら、そもそも呼び出しを受ける体制をとるべきではない。)
きらいな仕事だったらとても持たないところだ。逆に言えば、自分は緊急手術が好きだ、という暗示をかけておく必要がある。おっ、緊急が来たか、よし麻酔ができるぞ、と思えるようになったらしめたものだ。だが実際には、呼び出されるタイミングや体調によっては、がっかりしながら出勤するのである。
そういうときに、「お休みのところ…」とねぎらっていただくと、正直ほっとするのである。
ただ、どう考えても、緊急手術を受ける患者さん側のほうが、寝入りばなを起こされた麻酔科医より大変な状況である。さすがに患者さん本人からこんなことは言われないが、ご家族でもこんなことが言えるのはすごいことだと思う。たいがい、老婦人である。年を重ねるのも悪くないものだ。敬意を表したい。
2013.4.30
|
|
超緊急帝王切開
|
緊急手術の種類は数あれど、超緊急帝王切開ほど急を要する手術はない。赤ちゃんが胎内にいるのに胎盤が急に子宮から剥がれたり、へその緒がねじれたりすると、赤ちゃんへの血流が減少し、生命の危機に陥る。(もちろん、極めてまれなことですよ。)どうしてそれがわかるかというと、赤ちゃんの心拍数(お母さんのお腹の上から超音波で測る)が急激に落ちるからである。これが胎児低酸素のサインだ。この場合、1分でも1秒でも早く帝王切開を行い、赤ちゃんを外に出してあげる必要がある。これをレッドカイザーと呼び、院内のすべての業務に優先する、緊急事態爆走状態(てんやわんや)となる。ただし、最善を尽くしても助かるかどうかは神のみぞ知る、である。
あるとき、休日に超緊急ではない帝王切開があり、私はその麻酔をかけていた。ちょうど手術が終わった頃、産科病棟で胎児心音が低下したという連絡があり、産婦人科の先生が病棟に見に行った。そして、ただちに患者さんとともに手術室に帰ってきた。レッドカイザーだ。病棟ナース、助産師、当直看護師長、小児科医、産婦人科医が術衣への着替えなしで手術室になだれ込んでくる。私が全身麻酔をかけると同時に術者が切開を始め、2−3分後には赤ちゃんを取り出す。赤ちゃんはおぎゃあと泣いた。何事にも動じなさそうに見える中年ナースたちが、思わず一斉に歓声を挙げ拍手したほどの元気な泣き声だった。
当院では麻酔科医、小児科医、2人目の産婦人科医(手術には普通は2人必要)は病院に常駐していない。大病院なら当直ローテーションを組むだけの数を揃えられるが、普通の病院には不可能なのだ。このときはめぐり合わせのすべてが赤ちゃんに味方した。この赤ちゃんは実に強運の持ち主だったと見える。
産科医療はときどき、こんな感じである。
2013.4.27
|
|
医師および忙しい人のためのジャグリング入門
|
40歳になったとき、これからの自分の人生は下り坂をころげおちるのみであると悟り、老化へのささやかな抵抗としてジャグリングを覚えることにした。大道芸などでよく見る、3つ以上のボールや棒をくるくる投げ回すあれである。やってみて分かったのは、ジャグリングは医師にとって理想の趣味であるということだった。その理由は、
-
好きな時間に練習できる
-
やれば必ず上達し、達成感がある。いったん会得した技は練習不足でも忘れることはない。そこは自転車や水泳に似ている
-
無限の技があり、やりつくすという事がない
-
宴会などで芸を強要されても、慌てずにすむ。誰か私に強要してくれないだろうか
-
放物線をコントロールする快感に目覚め、ゴミを離れたところからゴミ箱に放り込むようになる。ただし、成功するまで繰り返されることになる
-
ほとんどお金がかからない。例によって、ここが最重要ポイント
これだけではジャグリングの魅力は伝わらないと思う。3つのボールを投げるだけで、何が面白いのかと疑う向きも多かろう。そういう方には次の動画を見ていただければと思う。
→ Chris Bliss 氏の動画へ
また、ボールを4つ、5つと増やしてさらなる高みを目指すこともできる。
もし、我も、と思われたら、ネット上にジャグリング入門のサイトがいろいろあるので見てもらってもよいし(「Juggling Donuts」の「ジャグリング教本」がおすすめ)、ちょっとお金を出してもよいという気になったら、ナランハという専門ショップ(http://www.naranja.co.jp/)で入門書とボールを取り寄せるとよいだろう。(アマゾンでも入手可能。)
私は職場でも、さまざまな人にジャグリングを勧めている。手術室にある適当なものを使ってジャグリングを実演し、お古のジャグリング用ボールを贈呈し、なだめ、すかし、パワハラを行使し、セクハラは我慢し、それでも私のあとに続く者が一人もいないのはどうしてだろう。よほど私の技が凄すぎて挑戦意欲をなくすのか、お粗末すぎて挑戦意欲をなくすのか、どちらかだろう。
どっちなんだろう。
2013.4.21
|
|
紅茶と健康
|
日本紅茶協会のホームページを見ると、紅茶の健康への効能が紹介されている。紅茶にはポリフェノール、テアフラビン、カテキンなどが含まれているため、酸化防止、がん予防、殺菌効果などが期待できるというのである。しかし、そもそもこれらが何ものなのかが私にはわからない。ポリビニール、てんびん、ぞうきんなどと区別をつけるのはむずかしい。仮にこれらがからだにいい物質なのだとしても、通常の紅茶の飲用量で効果があるという保証はどこにもない。
たとえば、エチルアルコールは優れた消毒薬であるが、いくら酒を飲んで体内のエチルアルコール濃度を上げても、肺炎やインフルエンザなどの感染症を防ぐ効果はない。
現在の医学の考え方では、薬、食品、治療法の効果を証明できるのは対照研究のみである。紅茶をよく飲む人の健康度を、飲まない人と比べればよいのである。医学論文データベース「Pubmed」で調べてみると、コーヒー、紅茶、緑茶の健康への影響は非常に熱心に調べられており、たしかにある種のがんや心血管系の病気を減らす効果はあるとする結果が多いようである。日本紅茶協会も、どうせ載せるならこういうデータを出せばいいのにと思う。
ただ、目の前で効果の出る薬ばかり扱っている麻酔科医としては、そういう食品の長期間摂取の効果を見せられてもなかなかぴんと来ない。実際のところ、これらの研究を詳しく見てみると、飲む人と飲まない人とでは生活の背景が違う(コーヒーを飲む人はタバコを吸う人が多いなど)ため、単純な比較はできず、両群の背景を揃えるためにさまざまな統計学的操作を加えている。ここまでやられてしまうと、結論を信じていいのかどうか、直感的には分からなくなるのだ。
麻酔科医として信じられる紅茶の急性効果は、多尿(有効成分は水)と不眠(同じくカフェイン)であるが、健康に役立っているのかどうか、定かではない。
つまるところ、紅茶、コーヒーは好きだから飲むのであって、健康のために飲むのではない。これらを飲む人の健康が優っているとしたら、その理由はポリフェノールなんかではなく、くつろぎの時間だという可能性は否定できない。
2013.4.20
|
|
紅茶の楽しみ方
|
理想の喫茶店が遠い過去にしか見当たらないため、自宅で紅茶を楽しむことが多い。もともとはコーヒーが好きだったのだが、年を取って胃にこたえるようになってきたため、紅茶派に転向した。紅茶はコーヒーに比べると味や香りが地味であるが、これはこれで、楽しみの多い飲み物である。
ガラスのポットに茶葉を入れ、沸騰したての湯を注ぐ。すると、まず湯の表面近くに浮き上がった葉が、沈んだりまた浮いたりと、各自思い思いの昇降運動にふけるようになる。なかなか幻想的な光景だ。(これが人間社会の浮き沈みに似ていると気がついてしまうと、なかなか哀切な光景だ。)やがて運動に疲れた葉がぐったりとなってあらかた沈んでしまうと、その時が飲みごろである。このような視覚的な癒し効果は、コーヒーには期待できないだろう。
おいしい紅茶の飲み方について、いろんなうんちくをお持ちの方は多いだろうが、私の意見は以下のとおりである。

-
先に述べた、ホッピングとかジャンピングとかいう現象が、おいしい紅茶を淹れるために必須であるとよく言われるが、本当だろうか。私は、そういう紅茶とティーバッグで淹れた紅茶とを区別できない自信がある。(前回書いたように、大きなポットにティーバッグ一つでは、さすがに分かる。)
-
本場イギリスでは、ミルクを入れたカップに紅茶を注ぐほうがよいと主張する人がいて、その逆の手順で用意した紅茶と飲みくらべて判別することができるそうである。これは、逆手順でミルクが急激に加熱されたときに生じる酸味のせいだというが、もちろん、私にわかるわけがない。
-
紅茶をスプーンで混ぜるときに、右回しがよいとか左回しがよいとかいう論争があるそうだが、右回しのほうがよいのは明らかだ。右利きの人間が左回しを行うのは骨が折れるからだ。もっとも私は、洗い物をふやさぬよう、スプーンの使用は控えている。
-
私の経験では、同じように淹れた紅茶でも、まずく感じる時と、すばらしい香りを楽しめる時とがある。たぶん、紅茶の味わいを最も左右するのは淹れ方ではなくて、飲む人間の体調ではないだろうか。したがって、湯の注ぎ方とか、蒸らす時間とかにこだわるよりも、紅茶をおいしく飲める体調を整えるほうが効果的だ。ただ、どういうときに紅茶向きの体調を迎えられるかは、不明である。ちょうど、同じだけお酒を飲んでも二日酔いになるときとならないときとがあるのに、そんなことを全然気にせず飲んで悪酔いするのと同じだ。
-
結局、確実に紅茶の味わいを高める方法は一つしかない。家に誰もいない時に淹れることだ。
2013.4.13
|
|
理想の喫茶店
|
私がたまに喫茶店に行くのは、雑用や人間関係から逃れ、好きな本でも読みながらゆっくり過ごしたいからであるが、その目的に達することは稀である。大抵何か、私がくつろぐのを邪魔するものが待っている。
たとえば、タバコの煙(自分以外の全員がタバコを吸いはじめた時の絶望よ)、大声でしゃべる中年女性(それはしばしば店のおかみである)、陰気で何を考えているかわからない隣の席の中年男性(向こうもそう思っている)などなど。
飲み物も問題だ。明らかに温めなおしたと思われるコーヒーが出てきたり、本格的にポットで出された紅茶が妙に薄味なので中を覗いてみるとティーバッグが沈んでいたりする。幻滅だ。店の人がこだわりすぎるのはもっと困る。どうだ、とばかり濃く淹れたコーヒーは胃が苦しくなるだけだし、ミルクなしで味わってくださいどうしても欲しかったら呼んでください、という忠告のもとに出される紅茶は渋すぎて楽しめない。
だが、一番大事なのは読み物だ。持参の本は2、3ページ読んだら飽きるのだから、自分ではなかなか買う気にならないような週刊誌をぜひとも用意しておいてほしいのだ。どうでもいい芸能界やスポーツ界の裏話を、実在の疑わしい匿名者が記者に打ち明けるといったような、どうでもいい記事を読みたい。有意義な時間よりも「無意義」な時間を喫茶店に求めるのは、私だけではないだろう。
「大人の〇〇」を連発する高級月刊誌しか置かない店があるが、「オペラ鑑賞入門」とか、「ブルゴーニュワインの味わい方」なんかを喜んで読むような客が自分の店にふさわしいと思っているのかもしれない。どうやら私は、ふさわしくないようだ。
こんなわけで、私の希望を満たすようなちょうどよい喫茶店はいまだに見つからない。私の要求は厳しすぎるのだろうか。学生時代によく行った、大学の近くの喫茶店が、今思えば理想の店だった気がする。コーヒー一杯でいくら長時間漫画を読もうが、気にもされず、気にもしなかった。
2013.4.6
|
|
由井正雪の最期
|
前回書いたように、高校時代の授業では三角関係や下駄について貴重なことを学んだ。他にもある。高校の日本史のM場先生の授業では、由井正雪の最期について教わった。ちなみに、由井正雪とは、江戸時代に幕府転覆を企てた男である。
おおむねつぎのような話だったと思う。
「反乱の計画が露見して幕府の役人に取り囲まれたとき、由井正雪は変わった方法で自殺しました。何かの拍子に心臓がつまづくような感じがすることがあるでしょ。このちょっとしたリズムの狂いを、自分でどんどん乱して大きくし、立ったまま心臓を止めたんです。由井正雪が死んでいることに役人たちが気づいたのは、みんなで飛びかかって取り押さえたあとでした。」
私は、人間、その気になればこんなオカルト的な死に方ができるのかと心底驚いたものである。一方、忍者や修験者でもなさそうな由井正雪が、どうやってこんな技を習得できたのか、練習中になぜうっかり死ななかったのか、最期にこの技を使ったことを誰がどうやって知り得たのか、など、さまざまな疑念にも苦しめられた。
医学的には、このような現象は自律神経と関係があるように思われる。自律神経ならば麻酔科医に任せていただきたい。麻酔中は患者さんの自律神経もある程度コントロールする必要があるのだ。麻酔科医は主に薬剤によって、自律神経の活動に介入している。由井正雪はこれを意志の力で行ったということかもしれない。
自律神経は交感神経系と副交感神経系の2つのシステムから構成されている。交換神経を極度に緊張させることで不整脈や脳出血を導くことは可能かもしれないが、不確実だし苦しそうだ。どちらかといえば副交感神経のほうが目的にかなっている。臨床的には「血管迷走神経反射」といって、なんらかの刺激によって副交感神経が活性化すると、反射性に高度の徐脈が発生することがあるのだ。極めてまれに心停止にまで至ることもある。
しかし、薬物や反射ならともかく、自分の自律神経を自在にあやつるなどということは、考えられないことである。そういうことができるなら「自律」とは言わないのである。ヨガの行者なんかだとある程度のことまではできそうな気もするが(根拠なし)、それでも心臓が止まるほどの極度の副交感緊張を誘導できるとは考えにくい。
一番腑に落ちないのは、その授業以外の場で、由井正雪が自分で心臓を止めたという話をまったく聞かないことだ。普通の歴史の上では、自刃したということになっているようだ。また、他の誰かが意図的に自分の心臓を止めることに成功したという話も聞いたことがない。憶測であるが、M場先生は講談とか小説本で聞きかじった話を生徒に聞かせていたのではあるまいか。だとしたら人騒がせな話だ。
そういうことだから、よい子はこんな技を試して見ようなどと思わないでいただきたいものである。
2013.3.31
|
|
師の言葉の重み
|
前回、大学時代の講義で聞きおぼえていた言葉を書き留めてみたが、このような雑談の部分は覚えていても、肝心の学問的なところは全然思い出せない。私が自分の経験からざっと見積もったところでは、これまで聞いた講義のうち99.99%は忘れてしまっており、覚えている0.01%はすべて雑談部分であった。
例えば、高校時代の数学の授業、「三角関数を略して、三角関係という。あれ、全然略してないのう」とか。
同じく高校の化学の授業、「今日11月11日は何の日か知っとる?下駄の日なんよ。下駄が踏んだあとは、2本線が2つできとるじゃろ?」とか。
どうでもいいことばかりだ。学生を授業に引きこむために、先生たちが知恵を絞ってはさんだ雑談が、結果的に学生の記憶のすべてになるのだから、わが恩師たちの無念は察するにあまりある。
これはしかし、人ごとではない。
先日、久しぶりに会ったある後輩がこんなことを言った。
「先生、麻酔中によくいろんな話をしてくれましたよね。僕結構覚えているんです。」
麻酔中、患者さんの状態が落ち着いていたら、指導する方もされるほうも、お互い手持ち無沙汰だ。そんなときは将来ある後輩に、ためになる話をするよう、心がけているのだ。
「たとえば、医者は年取ってくると、結局女に走るか、金に走るか、どっちかしかないと言われてましたが、あれ、どういう意味ですか。」
私は動揺した。どういう意味も何も、そんなことを言った記憶が全くないのだ。しかも、後輩にこんなことを教える意味が自分でもわからない。第一、この年になって女性にもお金にも縁がないのは他ならぬ自分である。
彼が他にも挙げた私の発言のすべてが、私の記憶に残っていなかった。私は一体、若いもんを相手に何を言い散らかしてきたのかと恐ろしくなった。どうせ自分を恐れるのならば、自分の才能を恐れたかった。
師の言葉はこんなにも軽い、場合もある。あまりわが恩師に同情する必要はなかったのかもしれない。
2013.3.24
|
|
時間と麻酔
|
学生時代、麻酔科の講義で、助教授が「急性内科」と板書されたことをよく覚えている。麻酔科の本質をこう表現したのである。つまり、現在進行中の事態に対し、限られた時間の中で内科的な手段で介入を行い、ただちに効果を得るのが麻酔科の仕事という訳である。私が麻酔科に進むためのきっかけになったキャッチフレーズであった。
たしかに、麻酔の仕事で時間が関係しないものはほとんどないと言ってよい。薬物の効果、呼吸や血圧の管理、出血への対応などはすべて、数十秒から数時間のオーダーの話である。患者さんを麻酔から無事に覚まし、病棟に帰した時点で、麻酔の結果はほぼ出そろっている。(本当はあとから出る副作用への警戒も必要であるが。)この歯切れのよさが、麻酔という仕事の魅力の一つである。同じ患者さんと何十年も付き合うことがあるという内科の先生方の話を聞くと、私などは気が遠くなる。
そういえば生理学の講義では、生理学の助教授が、「生理学は時間軸の上で組み立てられる学問である」と言われたが、麻酔は生理学の臨床応用版といえるから、この言葉は麻酔にもあてはまる。「麻酔は時間軸のうえに成り立つ診療科である」と言ってみると、哲学の香りがするではないか。
どうしてそんな30年近くも昔のことを覚えているかというと、その二人の助教授はやたらとかっこよかったからである。私が麻酔科勧誘の殺し文句のつもりで研修医に同じことをささやいてみても、研修医は数秒で忘れてしまうだろう。ところで教授達は何をされていたのだろう。
麻酔科医になって数カ月もすると、みな時間に鋭敏になる。血圧低下時の薬物の投与、気管への挿管、徐脈発生時の術者への手術中断コールなど、麻酔は「今すぐ」の連続である。その結果、麻酔科医はほぼ例外なく「せっかちな人間」になってしまう。仕事中、相手が「ええと」とか、「今ちょっといいですか」などと言っただけで、「なぜ今すぐ要件を言わないのだ」とムッとするようになる。昼ごはんも10分で食べてしまうようになる。
相手が医療関係者ならまだしも、患者さんに対してはせっかちがばれないよう、麻酔科医はみな気をつけているはずではあるが、隠しきれないものはある。術前診察でやたらと早口だったり、逆に患者さんの話をちゃんと聞いていなかったりすることは、どうしてもあるだろう。不愉快に思われる患者さんもいらっしゃるはずだ。全世界の麻酔科医を代表して、この場でお詫びします。
ところで、麻酔科医がどうして例外なくケチなのか、このなぞはいまだ解明されていない。
2013.3.20
|
|
医者に殺される?
|
またまた物騒なタイトルの本がベストセラーになっている。「医者に殺されない47の心得」という本である。こうやって、医師を殺人者に見立てることによって荒稼ぎをしているこの本の著者が医師だというのが、せつない話である。
以前とりあげた「医療とかかわるな」と同じく、難くせをつけてみたい。本を買うと著者がもうけてしまうから、例によって中身を見ないまま、書評等の資料から内容を想像していく。
この著者は以前から、日本のガンの診療を否定する本をたくさん出している。ガン検診は無意味だし、ガン治療は寿命を縮めるだけだ、とのことである。
これを完全に否定することはできない。部分的には本当だからだ。
医師が過剰医療という悪弊に陥る場合はある。
ある種のガン検診には、寿命を延ばす効果がないということが分かってきている。
ガンの治療をしたために、死期を早めてしまうケースがあるのも確かである。たとえばガンを取る手術を行った結果、腸の縫合不全を起こすなどして亡くなる方がおられるのは事実である。またこの著者がよく攻撃の対象としている抗癌剤治療であるが、その副作用による死亡もたしかにあるだろう。
だが一方で、多くの患者さんが、治療の結果完全治癒を手に入れておられることを無視されてはたまらない。著者の持論として、「本物のガンはどうせ切っても治らないから、放置するのがよい」とまで言っているようなのだが、そうすると何ですか、私が常々目にしている、たとえば大腸がんを切除して完全に普通の生活を取り戻している人たちの姿は、夢まぼろしだとおっしゃるのだろうか。それは取らなくても良い「がんもどき」だったのだとおっしゃるのであれば、大腸がんの発見、治療が遅れて腸閉塞になり、苦しみ亡くなっていく人たちの姿は、やっぱり私の夢まぼろしなのだろうか。
要は、ガンとわかった場合に治療を受けたほうが得か、損か、その兼ね合いなのだ。治療の損得は、ガンの種類と進行度によって全く違ってくる。患者さんには難しい判断ではある。
良心的な医師は、治療の得ばかり説明するのではなく、損の部分(治療のリスク)も提示した上で、最善と信じる方法を患者さんに勧めるはずである。それを取るかどうかは患者さんの選択である。医師の言っていることを鵜呑みにすることはない。もし、その医師の良心が信じられなければ、今はセカンドオピニオンという制度がある。検査結果持ち出しを要求し、他の病院で他の医師に見せて意見を求めることができるのだ。自分の命がかかっているのだから、それくらいのことはしてもよい。
これでも、ガン治療は悪、医師は殺人者だと思われるだろうか。
参考までに、あるガン治療の例を挙げてみたい。
私が研修医の頃、胃がんが腹膜に達しているものは治療不能だった。手術で開腹してみて、ガンが腹膜に浸潤していれば、まったく何もせず閉腹し、手術を終了していたのである。胃がんに効く抗癌剤はなかった。その人の余命は、長くて半年である。
現在はどうか。胃がんが腹膜に達しているどころか、穿孔まで起こしていても、胃は切除する。その上で抗癌剤治療を行う。胃がんに効く抗癌剤が出たのである。その結果、少なくとも数年生きておられる患者さんがたくさんおられる。おそらく、完全治癒と言える人も多いだろう。医学はたしかに進歩している。それを利用しないのはもったいない。
結論としては、医療機関を上手に利用してくださいということである。あたりまえのことすぎて、そんな本を出しても売れないから出さないだけだ。
この本の著者は、医療を必要以上にけなすことで患者さんの治癒の機会を奪っている可能性がある。自分が「患者を殺している」かもしれないと、この人は考えたことはあるのだろうか。言葉がどぎつすぎるかもしれないが、こんな言葉を使っているのは著者自身なのだ。
2013.3.17
|
|
麻酔科の品格
|
高校生の息子に、麻酔科医の仕事について解説をした。
父:「ま、医者の中でも人に頭を下げることはあんまりない科やね」
息:「え!とうちゃん、いっつも外科医に頭下げてるん違うの?」
父:「なんでやねん、何で頼まれる側が頭下げなあかんねん。手術をコントロールしているのは麻酔科や。麻酔科医の中には、外科に対していばるのが仕事やと思ってる人もいるくらいや。ワシはそういうのは嫌いやけどな」
息:「えー、でも麻酔なんて誰がかけても同じなんと違うの?」
父:「あほか、普通の状態ならともかく、患者さんの命がかかった時なんかにこそ麻酔科医の腕の見せどころがあるんやで」
息:「ほんまかなー」
どういうわけか、力を入れて説明すればするほど、息子の目はどんどん細くなり、疑いを深めていくのであった。少なくとも、父親の仕事に対する尊敬の念は感じられなかった。
思うに、家庭での私があまりに「謙虚」なので、手術室をさっそうと仕切る父親の姿が想像できないのだろう。実際、仕事中の私は「さっそう」というより「もっそり」だから、半分当たっているところがくやしい。
それにしても、麻酔科医の家族がこれでは、麻酔科医の地位が世間一般で認知されていないのも当然と言える。この状態を少しでも改善するために、まず足下を固める必要がある。給与振込口座をおさえるのは無理にしても、テレビのチャンネル権くらいなら奪えるのではないか。
うーん、それも無理だな。
2013.3.16
|
|
「救う」
|
テレビで子供が、「将来はお医者さんになって患者さんを救いたいです。」などと発言することがあるが、それはちょっと言いすぎだろうと思う。医師は病気を治して命を救うというより、患者さんが治るのを助ける、と言ったほうが当たっている。
たとえば、敗血症(菌が血液に乗って全身をかけめぐり、多臓器に障害を与えている状態)の患者さんがICUに入室されたとする。医師は、人工呼吸と昇圧剤で患者さんの生命維持に努め、抗生物質で菌を叩く。しかし、その状態から立ち上がるのは患者さん自身のからだである。患者さんが自分の力で治るまで、なんとか生命を維持するのが医師の仕事である。
何より、「救う」という言葉が私からすれば重すぎる。自分の身を危険にさらしても人を助ける、という意味合いがあると思うのだ。消防士が燃えている家の中に飛び込むイメージである。医師はそこまで覚悟しているだろうか。強いていえば、時々「寝不足」という健康面の危険を冒しているくらいである。コンピュータいじりやビールダラダラ飲みでも夜ふかしすることはあるわけだから、寝不足くらいで威張ることはできない。
今はもう絶版になってしまったが、新潮文庫に「シンドラーのリスト」という、事実に基づく小説があった。第二次世界大戦中、あらゆる困難を乗り越えて自分の工場にユダヤ人を雇い続け、ナチスによるユダヤ人絶滅計画の狂気から多数のユダヤ人の命を救った、実在のドイツ人の物語である。後にスピルバーグ監督により映画化された。
映画では、自分の工場に安い労働力を導入したいという実利的な目的がことの発端であったように描かれている。しかし、原作では違う。シンドラーはナチス党員でありながら、ナチスの所業を心底嫌悪し、ユダヤ人を救うことを最初から明確に意識していた。このため、「ユダヤびいき」として2度逮捕され、下手をすると自身がアウシュヴィッツに送られる可能性もあったという。まさに、自身の命を危険にさらしていたのである。
このように書くと、シンドラーが聖人君子のような人物であると思われるかもしれないが、実体は逆である。浪費家であり、女性にだらしないプレイボーイであり、その妻によれば「戦争前も、戦争後も、何一つ見るべきことをなしえなかった」人間なのである。そういうどこかネジがゆるんだ人物だけが、その狂気の時代にまともな目を持ち続けられたのだと思うと、興味深い。私のように自分のネジをしめるのが苦手な人間にとっては、まことに都合の良い例である。
小説の冒頭に、タルムードというユダヤの聖典のことばが引用されている。
「一つの命を救うものは全世界を救う」
「救う」という言葉は、シンドラーのような人にこそふさわしい。
2013.3.2
|
|
麻酔における方言の研究
|
術前診察などで患者さんとお話しするにあたり、標準語を使ってさしあたり困ることはないが、もう少し親密さをかもし出そうとすれば土地の言葉は欠かせない。
関西弁が便利なのは、敬語が使いやすいことだ。何にでも「はる」をつければ無難に会話をやわらげる効果がある。
「普段、お買い物なんかは自分で歩いて出かけてはりますか?」
ただし、関西と言っても広いので、敬語の使い方も地域によって微妙に異なる。京都では「こんな映画をやってはる」、「犬がおしっこしてはる」などと、人でないものに対しても過激に使用されるが、神戸だと敬語の使用範囲は狭く、言い方も違い、「血圧の薬をのんどってですか?」などとなる。私は「はる」で間に合わせているが、ほんとの神戸人は「はる」は使わない(と思う)。
静岡の病院に赴任した時、せっかくだから静岡の言葉をマスターしようと思った。大体標準語に近く、習得も簡単だろうと思っていたのだ。だが、静岡弁は存在した。ナースたちが「あわてて走ったもんで、こけてしまったっけだよ」、「なにやってるのかしん」、「そんなことあるらー?」などと言っているのを聞いて、私は自信を失った。これを自分が普通の顔でしゃべるようになるには5年かかると思った。残念ながら、静岡には2年しか居られなかったので、私の完敗であった。
ただ、静岡の人がやたらと連発する「もんで」(だから)だけは、真似るのは簡単だった。
「明日麻酔を担当するもんで、ご説明にきました」
「これで麻酔の準備は終わったもんで、これから麻酔がかかるだよ」(「だよ」はちょっと勇気がいる)
残念ながら、静岡の人は「もんで」が方言とは思っていない様子だったから、私の努力はまったく人には知られずじまいである。
命令文ならば、わが広島弁が世界最強だと信じている。広島では、たとえば母が子にいう。「お風呂にはいりんさい」
こんなに優しく命令されたら抵抗できない。
お風呂に入りなさい(標準語)、お風呂にはいりや(関西)、お風呂にはいらないかんがや、さっぱりワヤだがね(名古屋の人にはすみませんが、想像です)、など、思いつく他の言葉ではまったく表せない優しさが、「んさい」にはある。
「手術すんだけえ、起きんさいや」
「喉に痰があったら、出しんさいよ。貯めちょったらいけんのんよ」
もし麻酔で広島弁を使えたら、こんなふうに優しく命令してみたいのだ。
2013.2.17
|
|
閉所恐怖症
|
私には閉所恐怖症の傾向がある。エレベーターやトイレが怖い、というほどではないが、身動きできないほど狭いところはいやだ。地震か何かで生き埋めになって死ぬ、という状況を想像するだけで息が苦しくなる。そんなのは誰だっていやだろうが、わざわざそういう状況を1ヶ月に1回くらいの頻度で想像して勝手に冷や汗をかいているのだから、ちょっとおかしいと思う。
私の知る範囲では閉所恐怖症は欧米では大変ポピュラーな病気である。どうも、死人を棺桶に入れて土葬する習慣から来るものらしい。棺桶の中で息を吹き返してしまい、地獄の苦しみを味わいながらまた死ぬ、という恐怖をみんなで共有していたようである。
たとえばリルケ(ドイツ)の「マルテの手記」には、主人公の父親の死後、本人の生前の希望で、医師に心臓への処置をしてもらったというくだりがある。棺桶の中で間違って生き返らないようにしたい、ということだろう。
また、エドガー・アラン・ポー(アメリカ)の代表作の「黒猫」と「アッシャー家の崩壊」はいずれも閉所に閉じ込められた者の恐怖が主題になっている。どう考えても、ポー自身が生き埋めの恐怖におののいていたとしか思われない。
墓場や棺桶などとはおよそ縁のなさそうなイメージのアンデルセン(デンマーク)も、やはり閉所恐怖症だったようだ。毎晩寝る前に、枕元にメモを書いておいたという。自分は寝ているだけであって、決して死んでいないから、早まって棺桶に入れないようにと。そのメモを、毎朝家政婦さんが読みもしないでくずかごに捨てていたとか。
現代の日本には土葬の習慣は残っていないから、閉所恐怖症が少ないのかというと、私の印象ではそうでもない。たとえば、CTは狭くて怖いから絶対にいやだと言われる患者さんは結構いらっしゃるし、トイレのドアは少しあけておくという人もいる。何か理由があるのだろうか。
あるとき術前診察で患者さんと話していると、自分は閉所恐怖症だと言われる。麻酔って、何かに閉じ込められるような感覚はないんですか、と心配しておられた。私はそんなことはありませんと説明し、少しでも気分をほぐすことができたらと思い、自分のことを告白した。
「私も閉所恐怖症なんですけどね。どうも小さい頃、兄にさんざん布団蒸しにされて死ぬほど泣いたので、そのせいじゃないかと思うんです」
するとその患者さんははたと膝を打ち(たぶん)、
「そう言えば、私も学生の頃、寮でよく布団蒸しにされて、いやでいやでしょうがなかったですわ。先生に言われて思い出しました。私の閉所恐怖症はそのせいかもしれませんな」
かくして、日本の閉所恐怖症の根源は布団蒸しだったことが明らかになった。症例数2。
2013.2.16
|
|
医学部体育会礼賛
|
どの大学にも医学部体育会といって医学部生だけの運動部というのがあり、いわゆる本学の運動部とは独立して活動している。もちろん、医学部体育会のほうがレベルは低いのであるが、そのかわり初心者でもそれなりに試合に出て活躍できるので、勉強優先でやってきた青白い若者にとって大変ありがたい制度である。私も大学に入ってから卓球を始め、近畿3位に入ったりもしたが何のことはない、「近畿医科学生の3位」であるから看板に偽りありである。
この医学部体育会にとって最大のイベントが、毎年夏休みに行われる西医体(西日本医科学生体育大会)、東医体である。多くの者にとって、学生時代最良のあるいは最悪の思い出になっているはずである。私にとっては特に6回生時の最後の西医体が思い出深く、団体戦3位決定戦の単複で勝った時の自分の試合については、25年経った今でもラリーの内容を鮮明に思い起こすことができる。私の一生の財産である。
今思えば、西医体、東医体ほどアマチュアスポーツの理想に近い存在はないかもしれない。すなわち、勝利への渇望と、勝利から何の見返りも求めない潔癖さである。
まず、伝統ある大会であるから選手は真剣に勝つことを求める。直前合宿では昼間の苦しい練習と夜の苦しいゲーム大会(連想ゲームとかドボンとか)に明け暮れる。大会前夜は宿の一室にレギュラーが集まり、綿密に作戦を練る。敵はどういうオーダーを組んでくるか、敵の弱点は何か、敵エースの交際相手はだれか、その名前を試合中に敵にささやくとどれほどの効果があるか、など、真剣な議論は数時間に及ぶこともある。その結果、相手が食中毒かなにかでやられることを真剣に祈ったものである。他大学との親睦とは名ばかりである。
一方、努力や作戦が実ったり、祈りが通じたりして勝ったらどうなるか。得られるのは名誉と自己への満足のみである。金品、他チームへの移籍話、意中の異性のハートなど、現実的なメリットは皆無である。また、どうせみな医者になるのだから、西医体で勝つことと将来のキャリアとはまったく関係がない。だからこそスポーツ本来の楽しみを味わえるし、そこに医学部体育会の魅力がある。
当時大阪医大の絶対的エースだったN氏が、われわれの大学の部誌「多苦究道」に寄稿してくれたことがある。その中の一文がわれわれの気持ちのすべてを表している。
「勝ち負けは一時のことにすぎません。しかし、感動は一生つづくのです。」
同じアマチュアでも有名学校の有名スポーツになると、こうはいかないだろう。勝つことに学校の宣伝、自分の進学や就職などの目的が混入するから、選手以外の者が勝ち負けに介入してくる。これは苦しかろう。羊飼いのお兄さんがオリンピックのマラソンで優勝した昔と違い、現代のスポーツで一流になるためには自分の24時間をそれに捧げなくてはならない。1ヶ月のうちの24時間ならまだしも、1日のうちの24時間である。才能を持つ者が頭角を現すほどに周囲からの期待を集めるのはめでたいが、ヘタをするとその人のスポーツ以外の可能性を閉じられてしまいかねない。もし本人の意思によるものではないとしたら、気の毒としかいいようがない。しごきや体罰なども、選手以外の者が選手に勝利を求めるところから発生するのではあるまいか。
テレビに映るほどのスポーツには全て、このようなある種の「残酷さ」がつきまとうように思う。「感動をありがとう」などとはなかなか言えるものではない。
アマチュア精神という言葉は死語になってしまったが、プロ選手もセミプロ選手も、その部分は残して欲しいと願っている。彼らには自分自身の楽しみのために競技生活を送る権利があり、観客にも国家にも監督にも両親にも、それを奪う権利はない。
2013.2.3
|
|
麻酔と体罰
|
大阪の高校からはじまった体罰問題が世間を騒がせている。
わたしの場合、生まれてこの方、体罰というものを受けたことがない。この点に関して、両親、教師、クラブの先輩、そして妻には感謝をしなくてはならない。体罰を受けて喜ぶ自分、体罰によって向上する自分というものを想像できないからだ。
ところで、麻酔科の中でも体罰による教育を実践する人がいると聞く。失敗したり、指示を守らなかったりすると、ぽかんと殴ったり、押したり、蹴ったりするらしい。医師になるためにさんざん自分を律してきたであろう者を相手に、暴力への恐怖を利用した教育が果たして有効なのか、極めて疑わしい。そういう指導者が、ほんとに効果があるのだと思ってやっているのだとしたら、今どき医学研究の定番となっている前向き無作為化研究をしてみたらいい。被験者は研修医、体罰ありの場合となしの場合とで、知識や技術の身につく程度が違うかどうかを調べるのだ。もちろん書面による同意が必要だ。
次のような会話が予想される。
指導医:麻酔の教育にあたって体罰に効果があるかどうかを調べたいから、被験者になってくれないか
研修医:体罰はちょっと勘弁してください
指:ちょっと頭をこづくだけにするから
研:いや無理っす
指:じゃあ、失敗したら肩もみ、というのはどうだ。もちろん、肩もみするのは私の方だ
研:それも別の意味で無理っす
指:どうして私のいうことがきけないんだ。同意書にサインしないと殴るぞ。サインすれば、殴られる確率は二分の一ですむ。さあどうする
…
自分で言い出しておいて何ですが、こんな研究、誰が信じるか。
2013.1.27
|
|
麻酔科最強定理
|
敗血症治療の国際的ガイドラインである、"Surviving sepsis campaign" のガイドラインが4年ぶりに改訂された。意外に大きな変化はなかったが、細かい所では多数の変更が加えられている。以前は強く推奨されていたことが、なんとなく自信を失った書き方になっているところもある。ここからも、医学に絶対的真実はなく、日々改善を重ねるしかないということがわかる。
改善を重ねていけば、いつか真実にたどりつけそうなものだが、どうやらそれも怪しい。たとえば、輸血は最小限にすべきかたっぷりすべきか、血糖は低めに保つべきか、高めの方がいいか、ステロイドはどうか、といった問題に関しては、同じところを行ったり来たりしており、いつまでたっても数年周期の振り子運動をやめられない可能性がある。
他の自然科学も似たようなものだと思うが、数学だけは別だ。どう見ても間違いのない公理から出発して、誰が見ても間違いのない論理を使い、定理を導きだしていく。だから、一度確立したことは基本的にはひっくり返らない。ヒポクラテスの医学を現代にあって実践している人はいないだろうが、ピタゴラスの定理は中学生がみんな学んでいる。うらやましいことだ。
せめて医学にも、公理のようなものはないのだろうか。たとえば、「人は必ず死ぬ」というのは絶対的真実のように思える。ここから出発して、どんな定理が導けるだろうか。
「人はどうせ死ぬ。早いか遅いかの違いしかない。」
「たいていの人は、死ぬのは遅いほうがよいと思っているから、医学の目的はいろんな健康の危機にあって死なないようにしてあげることだ。」
「また、生きているといっても痛みがあったらイヤから、痛みをとることも医学の重要な目的だ。」
「したがって、その2つの願望を叶えるプロである麻酔科医は、究極の医学の実践者である。」
「麻酔科は最強だ。」
2回ほど読みなおしてみたが、この論理にはまったく破綻がなく、完全に正しい定理が得られたことがわかった。偶然にも、自分の仕事に関係する結論だった。
だが、本当に人はかならず死ぬのだろうか。もしかしたら何万年も生きつづけている人がいるかもしれず、我々が知らないだけという可能性は否定できない。たとえば空海は、たしかまだ奥の間にはいって修行中のはずである。誰も奥の間を覗いていないから、どうなっているのかわからないのだ。もし、これまでの人間が200年以内に全員死んでいたとしても、将来の人間は寿命が1万年を超えるかもしれず、そうなると本当にいつか死ぬのかどうか、証明がむずかしくなる。
前提が怪しくなったので、「麻酔科最強定理」は崩れた。惜しかった。
2013.1.25
|
|
テレビドラマと麻酔科医
|
医療ドラマは苦手だ。3分に一度は現実にはありえないことが起こるので、見ていてからだに悪い。診療内容、業務のシステムなどもいいように歪められているが、一番現実と乖離しているのが登場人物の言動である。医師といえば、傲慢とゴマスリと熱血の3種類のキーワードに白衣を着せて歩かせているだけのペラペラのキャラクターばかりだ。とてもあのような方々とは、私はチームを組めそうな気がしない。
先日、食事中にスーパードクター系ドラマを見ていると(私にチャンネル権はない)、あるシーンでごはんをのどに詰めそうになった。主人公の女性外科医が手術中に麻酔科医になにごとか要求し、麻酔科医が断ると、
「はい、麻酔科チェーンジ。XX先生呼んできて」
と言い放ったのである。
麻酔科医は外科医のシモベだと思い込んでいる脚本家が多すぎる。外科医をスポーツ選手に例えれば、麻酔科医はダブルスのパートナーである。選手が試合中にダブルスのパートナー交替を要求するだろうか。
でもって、その外科医のキメゼリフがまたすごい。
「わたし、失敗しないもん」
手術を、鶴の折り紙か何かと間違えていないか。手術は常に危険を伴うものであり、いかに完璧な手順を尽くしてもよい結果が得られないということはありうるのだ。野球選手が打率十割を自慢していたとしたら、信用する人がいるだろうか。
警察、教師の方々も、同じ被害に遭っておられると推察する。悪徳警官、正気とは思えないはみだし刑事、情けない日和見校長が出てくるドラマを、よりによって自分の家族が笑って見ているのではありませんか。
同志のみなさん、腐らずに、強く生きて行きましょう。
2012.12.22
|
|
オッド・マン・セオリー
|
小説の話は、事実や実体を伴わない論議になるのでなるべく避けてきたが、たまには例外もある。
「アンドロメダ病原体」(1969年)は、映画ジュラシック・パークの原作などで知られるSF作家の故マイケル・クライトンの出世作である。宇宙から来た、100%近い致死率を持つ未知の病原体と戦う科学者たちの物語であり、今読んでも新鮮な驚きに満ちている。で、この物語の中心になるのが、ある科学実験に基づく「オッド・マン・セオリー」である。
すなわち、組織が危機的状況に陥ったとき、もっとも正しい判断を下せるのはどのような人物かを実験により調べたところ、それは「独身男性」だったという。このため、科学者チームの中にひとり加わった独身男にある重要な鍵が託されるのであるが、物語のクライマックスでこの男が誰も予想しない面でオッドマンぶりを発揮し、チームを破局から救うのであった。ここにおいてオッド・マン・セオリーはその正しさを自ら証明したことになる。
小説の中では、このセオリーが具体的な数字や表をもって紹介されており、結論もなんだかもっともらしく聞こえるので、実在の理論をこの小説家が拝借したのであろうと、私は思い込んでいた。普通、SFのような架空の小説ほど、リアリティーを持たせるために土台のところは現実世界のものを使うものなのだ。ところが、このオッド・マン・セオリーもクライトンによる完全な創作らしい。すっかりだまされたではないか。
ここから何が言えるかというと、
-
人間は統計、数字、図表、出典など、科学的な雰囲気を漂わせたウソにだまされやすい。
-
これは、人をだましたいときに使えそうだ。読者の方は、前回の「BGMの効果」について、ちょっとはだまされていただけただろうか。
-
ただ、科学よりも自分の感覚を重んじる人には通用しないかもしれない。「40歳の独身男なんて、気持ちわるーい」など。幸か不幸か、この種の人間は人口の約半分を占める。
-
男は一匹狼的な要素にロマンを感じる。独身男がうらやましい。
-
このような口からでまかせだけで財をなしたクライトンがうらやましい。
2012.12.16
|
|
BGMの効果
|
最近の論文によると、手術室で流す音楽により、手術のスピードが変わるという (Eurasian J Anesthesiol 2012; 35:125-9)。いろんな音楽を試した結果、ヨハン・シュトラウスのワルツがもっとも効果的で、皮膚縫合に要する時間が12%短縮したとのことである。これは、手術終了前にこっそり部屋の温度を上げるよりも高い数字であった。やはり、三拍子に乗って無意識に運針が進むのであろう。
というのは根も葉もないつくり話である。
ごめんなさい。
2012.11.4
|
|
「ちょっと」の効用と乱用
|
患者さんに点滴するときなど、「ちょっと痛いですよ」というのが医療関係者がよく使う定番フレーズである。さらにやさしい言い方を目指すならば、「ちょっとチクッとしますよ」などという。ところがそう言っておいて、ちょっとどころではなく痛いことをするというのが、病院でよく見られる光景だ。
言い訳がましいが、それもやむを得ない事情というものがある。
かつての同僚で、そのような欺瞞をいさぎよしとせず、「それでは針を突き刺しますよ」と言う医師がいた。それも、どこのナマリかしらないが、「き」にアクセントが来るのである。そばで聞いている私でも、「ああ、痛そう」と思ったものだ。痛いことをする場合でも、お互い嘘とわかって「ちょっと」をつけるほうが、やはりやさしいと思うのだ。
都合のよいことに、「ちょっと」という言葉は、文脈によっては強調を意味することがある。
「あの人の能天気ぶりはちょっとすごい」
「あれ以上能天気な人はちょっと考えられない」
などである。だから、「ちょっと痛い」がまったくの大嘘であるとも言い切れないのだ。ただ、おのずからなる語調というものがある。医療機関で処置を受ける人は、「ちょっと」の微妙なアクセントから、次に来るものの危険度を察知して欲しいと思う。(勝手なお願いで申し訳ありません。)
研修医など若い人のなかに、この「ちょっと」を乱用するものがときどきいる。無意識に、何にでもちょっとをつけてしまうのだ。
「ちょっとお顔にマスクを当てますよ。」
「ちょっとね、お胸に心電図のシールを貼ります。」
など、「ちょっと」をつければとりあえず穏便にことを進めることができると思っているらしい。(ついでだが、「お胸」もやめてほしい。)ひどいのになると、
「ちょっと手を強くにぎってください。」
とか、
「ちょっと大きく深呼吸をしてください。」
などと明らかに矛盾したことを言い出したりする者がいるから、びっくりする。「ちょっと」の便利さに甘え過ぎだ。
ちょっと猛省を促したい。
2012.10.7
|
|
おなら問答
|
小学校4年くらいのころ、家に遊びに来たKくんが突然、こんな問いをかけてきた。「どういうときにおならがたくさん出るか、知っちょるか」
当時私は理科大好き少年を自負していたが、この問題には答えられなかった。Kくんの答えは、「うんこが出る前じゃ。」であった。
俗説に、芋や豆を食うとおならが出るというが、自分の実感として、それが正しいと思ったことはない。しかし、Kくんの答えはまさに、言われて見ればそのとおり、全く反論の余地を残さないものであった。彼は俗説やおとなの常識にとらわれることなく、自らの消化管機能への冷徹な観察を通して、この問題と回答を導き出したのであろう。図鑑とか、ナゼナニ博士の問答集などをたくさん読んで得意になっていた私には、とてもできない発想だった。自分の見たものしか信じないというその態度は、医学のあるべき姿を体現しているようにも思われる。
今度は私から出題を。麻酔科医が仕事中におならを催したらどうすべきか、おわかりだろうか。Kくん説に基づくならば、朝トイレに行き損ねた日などが危険、ということになる。
これは、手術室の構造がわかっている人には容易な問題である。
手術室の空気は常に流れている。部屋の隅から空気を取り込み、HEPAフィルターを通して清浄化し、天井から送り出す。部屋の空気が1時間に15回以上入れ換わるのが、一般的な手術室の基準である。(日本手術室医学会、手術医療の実践ガイドライン参照)
すなわち、当該麻酔科医は空気取り込み口の前にさりげなく、所在なげに立つ、これが正解である。

2012.9.25
|
|
医療関係者のための Linux の勧め
|
パソコンをお持ちの皆さん。OS(オペレーティングシステム=基本ソフト)としてウィンドウズかマッキントッシュOSをお使いのことと思う。しかし、どちらも使えば使うほど、悪名高い独占主義者たちをさらに富ませるだけのことである。ちょっと人と違うものを使いたい方に、Linux をお勧めしたい。Linux にもいろいろな製品があるが、私は Ubuntu (ウブントゥ)というものを使っている。
Linux は無料のOSである。タダより高いものはないと言われるが、この場合それはあてはまらない。Linux は企業などでも使われる、極めて信頼性の高いものある。タブレットPCやスマートホンのOSであるアンドロイドも、Linux をベースとしている。このように社会のなかにしっかり根付いているから、消滅する心配はない。そこが、これまで、私に愛好されたばかりに消えていったものたちと違うところだ。(IBM OS/2 の末路は悲惨だった。)こういうものを無料で開発して無料で公開する、奇特な人たちがいるのである。世の中、捨てたものではない。
Linux がはじめてという人には、専門的知識がなくてもとっつきやすい Ubuntu がおすすめである。Ubuntu はインターネットで入手できるが、初心者はCD-ROM と解説つきの雑誌を買われたほうがよいだろう。Ubuntu Magazine Japan (アスキー)、Linux100%(晋遊舎)などがある。ウィンドウズが載っている普通のパソコンなら、ほぼ間違いなく動かすことができる。CD-ROM から立ち上げてちょっと試してやめることもできるし、ハードディスクにインストールして、ウィンドウズと切り替えながら使うこともできる。
Ubuntu についてさらに詳細を述べていくのにやぶさかではないが、私がどのようなソフトウェアを使っているかを紹介したほうが、心ある医療関係者の参考になるだろう。
-
Libre Office: ワープロ、表計算、プレゼンテーションがひと通り揃っている。よほどマニアックな使い方でない限り、機能的には何の問題もない。たしかに、マイクロソフトのパワーポイントのほうがさまざまな視覚効果を備えているが、そんなものに数万円払うくらいなら、私はタダのソフトを使って中身で勝負する。(勝負はするが、勝つとは言っていない。)
-
Gedit: エディター、つまり文字を入力編集するソフトである。この「麻酔科パラダイス」の html 書きも、プログラミングもすべてこれでやっている。(このサイトのレベルが低いのは、エディターのせいではない。)
-
Python: お手軽なプログラミング言語。C言語ほどややこしくないので、とっつきやすい。手術室用カウントダウン-カウントアップタイマー、手術室の自動麻酔記録装置のデータから日本麻酔科学会への年次報告を作成するツール、研究で出てくるデータを解析するツールなどを作って面白がっている。もうすこし技を磨けば、手術申し込みの時に虚偽の予定時間を入力しようとする外科医にキーボードから電気ショックを与えるツール、疲れた時に肩を揉んでくれるツールなどが作れるようになるかもしれない。ちなみに、C言語もタダでついている。
-
Kigo: 囲碁対局ソフト。まじめにやれば勝てるが、油断すると負けるという、わたしにとってはちょうどいいレベル。私の石を攻撃してくることはあっても、私の人格を攻撃してきたりしないところが、ネットで対戦する人間と違う。
-
Truecrypt: ドライブ暗号化ソフト。USBメモリー、ディレクトリからハードディスク全体まで、何でも暗号化できる。医師のパソコンには、患者の姓名などは入れないように気をつけているはずだが、どうしても患者に関する情報は入ってしまう(今日どんな手術があったなど)ので、万一盗まれたら大変である。たとえデスクトップパソコンのハードディスクでも、データファイルは暗号化ドライブに入れて、パスワードで鍵をかけるべきだと考える。(Win版もあり)
-
Physionet の PhysioToolkit (http://www.physionet.org/physiotools/): 時系列データの解析に関するツールがたくさん置いてある。アカデミックな分野ではもっとも広い基盤を持つ Unix と、そのパソコン版である Linux だからこそ、このようなツールが使えるのだと実感できる。
-
R(「アール」): 統計ソフトといえば非常に高価なパッケージを買わなくてはならないと思っていたが、探してみたらちゃんとタダのものもあった。まだ解析すべきデータが揃っていないが、いつかこれを使って研究をまとめたいものだ。(Win版もあり)
これらのソフトはすべてタダであり、インストールも簡単である。もちろん、この他にも、メール、ウェブブラウザ、音楽・動画プレーヤーなどが最初からついている。
欠点もある。ブルーレイビデオの再生、地デジの受信など、ライセンスの絡むものはほぼできない。また、iPod, Sony Walkman, 電子書籍プレーヤーなど、パソコンとの接続に特別なソフトを使う機器は、ウィンドウズでなくてはむずかしい。というわけで、私も週に一度くらいはパソコンをウィンドウズで起動して使わざるを得ない。
しかし、独占主義者ども(しつこいか)の囲い込みの腕をかいくぐり、自由な OS を自由に使うことの喜びに比べたら、多少の不自由は私は我慢できる。
いかがでしょうか。
2012.9.16
|
|
ジョギングの時代
|
ジョギングが流行っている、ように思われる。街には走るおじさんやおばさんが溢れている。私もその一人だ。
中学高校の頃、冬になると体育の授業で長距離走をやらされたが、これを好きというものはただの一人もいなかった。苦しいばかりで何の楽しみも見いだせなかったのだ。若者にはあれほど不人気なスポーツが、なぜ大人に好まれるのだろうか。例によって、箇条書きしてみよう。
-
お金がかからない。若い頃は、大人の遊びというとゴルフとか高級バーとか金のかかるイメージをもっていたが、自分が大人の遊びにふさわしい年齢になってみると、とんだ見込み違いだった。おじさんの楽しみのために金をかけてもいいと思っている人は、周囲に誰一人としていないことがわかった。
-
長生きできそうな気がする。少なくとも私には、妻より長生きするという目標がある。その理由はここでは書けない。走っていると交通事故や心筋梗塞のおそれもあるが、それでもいい。結局、どっちでもいい。
-
相手がいらないので、やりたいときにできる。卓球などの練習においては、もっともエネルギーを要するのは相手とのスケジュール調整だ。その点、あらゆる人間関係を排除できるのがジョギングの魅力である。(ただし、洗濯物が増えることに関連して、特定の人間関係については緊張を増す)
-
勝負事ではないので、人に負けるくやしさがない。もっとも大会に出ると、多少周りの人が気にはなる。しかし、私くらいのレベルになると、他の選手は敵ではない。最大の敵は、関門での時間制限と脱落者回収バスである。
-
走っているときは苦しい。息切れ、膝の痛み、気持ち悪い汗(おじさんの汗は自分でも気持ち悪い)、そばを疾走しているつもりなのに逃げずに座っている猫などに苦しめられ、それで頭がいっぱいになる。ところがそのおかげで、日常生活の終わる見込みのないストレスを忘れられるのだ。ゆったり温泉につかっていたら、こうはいかないだろう。お湯の中で余計なことを思い出し、ギャッと叫んだことのある人は多いはずだ。
これほど込み入った「大人の事情」の上に成り立つジョギングの楽しみ、若いものには理解できないのは無理もないことだ。
2012.9.9
|
|
本当に効くのか
|
Gigazine というサイトがある。パソコン、ジャンクフード、旅行など、オタクが好きそうな話題を手当たりしだいに集め、まったく自由な立場からリポートを行っている(ように思える)。この中に、あるノートパソコン用冷却台を取り上げた記事があり、実際にどれくらいの効果があるのかというデータを紹介している。(2009年08月28日 「温度によりファン回転数を自動調整できるノートPC冷却台「X-Wing」、実際にどれぐらい冷えるのか?」)
この冷却台にはファン回転数自動制御、温度監視、メディアプレーヤーコントローラ、USBハブなど、目のくらむようなさまざまな機能が詰め込まれているが、肝心のノートパソコンのCPU(心臓部)の温度はほとんど下がらない(たかだか1℃か2℃)のだ。これには驚いた。
だいたい、パソコンの底から風を当てているのだから冷えそうなものだし、効果があるからこそこうやって売っているのだろうと思われるのだが、これらが勝手な思い込みであったと気づいて驚くのである。
機械という、効果が簡単に検証できるような分野でも、このような思い違いが発生するのである。健康産業においては、もっとすごいことになっているはずである。なぜなら
1. 健康を願う人の数は、ノートパソコンが熱くならないことを祈る人よりもはるかに多く、当たれば儲けが大きい
2. 商品に本当は効果がないとしても、それを立証するのはむずかしい。何人もの被験者で、使用した場合とそうでない場合の差を調べなければならないから、消費者の手に負える仕事ではない
3. そもそも、それらの商品に効果があるとは売る側は言っていない。ただ単に、CMの出演者がぐるぐる膝を回したり、八千草さんなどの美しい老人が夕日を見たりしているだけである。仮に消費者側が商品に効果がないことを証明しても、「それが何か…」という返事が待っている
実に見事なやり口ではないか。
2012.9.2
|
|
麻酔科のすすめ
|
今年はまだ、当院麻酔科に後期研修医(3年目の医師で、ここから専門の科を決めて研修を始める)の候補者が現れないのは、どうも気がかりである。気がかりであるが、この病院ではまだ、麻酔科に後期研修医が入った実績がないので、別に驚いているわけではない。
当院のような、心臓外科麻酔を経験できない病院は、どうしても若い人を獲得しにくい傾向があるが、それにしても何とかならないものだろうか。このサイトを作ったのも、これを見た研修医が麻酔に興味を持ち、どういう風の吹き回しか当院の麻酔科に来てくれるという僥倖を祈ったからであるが、これまでの感触では瀬戸内海でマグロを釣るほうがまだ簡単ではないかという気がする。
だが、まだ可能性はゼロではない。研修医に麻酔科入りを決意させる殺し文句を無造作に並べてみる。
「麻酔科に入ったら、こんなにいろんな劇薬を使うことができるんだよ。」(「劇薬」という言葉よりも、その先生がほんとにうれしそうな顔をしているのが印象に残った。)
「外科医は土管掃除をしているだけや。(そのとき大動脈瘤の手術をしていた。)手術の痛みを止めてあげることの方がよほど上等な仕事をしとる。」(何か言いがかりのような文句だが、助教授の言葉なので説得力があった。)
「麻酔科の売りはクオリティオブライフや」(ある大学教授の言葉。主治医として患者を持つ他の科と違い、当番でない限り夜間や休日は確保されることを強調している。立場の上からは、少しでも安全な麻酔を目指して、とか、研究に人生を捧げるとか、美辞麗句を並べそうなものだが、麻酔科の実利をストレートに表現したのは、さすがS先生。)
「麻酔科のメリットは、自分のやっていることの効果がすぐに目の前で確かめられることね。」(気の短い人にはぴったりだ。)
「麻酔中、状態が安定していると暇でしょ。手術が終わるまでこうやってぼーっとしているのが好きな人にはお勧めですよ。」(なんと、気の長い人にもぴったりだ。)
「君のような、ちょっと変わった人には麻酔科は向いている。」あるいは、「君のようなまともな人こそ、麻酔科に必要だ。」(やはり、すべての研修医に勧められる)
あとは、マグロがかかるのを待つだけだ。(メールください)
2012.8.20
|
|
学術雑誌
|
日本麻酔科学会は20数年前から英文雑誌 "Jounal of Anesthesia" を発行している。雑誌といっても日本の週刊誌のようなものではなく、ほぼ学術論文ばかりである。息子に聞かれたから答えておくが、決して、ダジャレコーナーもないし、芸能コーナーも息抜きコーナーもない。
創刊当初は日本人の論文がほとんどであったが、近年はだいぶ国際化してきて、さまざまな国から投稿されるようになってきた。よろこばしい限りである。
この雑誌にイランからの論文が掲載されていた。帝王切開後の鎮痛に、ある種の神経ブロックが非常に有効であったという論文である。イランといえば、核開発をめぐり、欧米を中心とする国際社会から冷たい目でみられているが、この論文からには、あの覚えにくい名前の大統領につきまとううさんくささはみじんもない。この論文を読めば、以下のことがわかる。
1. イランの医師たちは世界とのコミュニケーションを図るため、英語という国際語を使っている。すくなくとも、戦時中の日本のように、英語を敵性語として憎む雰囲気は感じられない。
2. 男性優位という印象があるイスラム国家においても、女性のための術後鎮痛法が医学の課題として取り組まれている。
3. 医学の研究において必要なのは適切な条件設定と統計学であり、神の力や核武装論が登場する余地はない。
少なくともイランの医師たちは、他の国の医師と同じ価値観をもっている。現代の医師像とはおそらく、職業的親切心を持った合理主義者であり、決してカリスマ的指導者やシャーマンなどではない。このことは国籍や宗教とは無関係であろう。
ちょっとほっとした。
2012.7.22
|
|
心のプロ
|
面接についてもう一題。
総合病院における面接では、精神科の医師がしばしば動員される。心のプロだから、われわれの見えないところを見てくれるのではないかという期待が込められているのであろう。
ある病院での後期研修医採用試験の面接でのことである。最後の受験者が少し変わった人だった。何がおこっても慌てなさそうな大人物の風格が、採用面接なのに全面的に表に出てくるという点で、そこにいた人はみな、違和感を持っただろうと思う。ちょっと話してもらっただけで、ちょっと変わった印象を与える人だということは、たくさん付き合えば相当変わった人だとわかってくる可能性がある。会場の空気が微妙に緊張してきた。
すると、それまで他の受験生のときには全く無言を通してこられた精神科の部長が、はじめて口を開き、彼に質問をした。特殊な内容ではなく、上司にそう言われた時自分はどう感じたの?、といった質問だった。それに対する返事にも、別段変わったところはなかったように思う。少なくとも私には、彼の人物を知るうえで参考になるようなやりとりではなかった。
受験者が退室したあと、副院長が精神科部長に聞いた。「どうしてあの質問を?」すると、精神科部長は、
「ここは私の出番かと思いまして」
とだけ答え、再び口を閉ざした。
受験者は合格した。残念ながら他院に就職したが、しっかり活躍されていると聞く。
精神科部長はあのとき、一体どのような判定を下したのだろうか。今でも少し知りたい気がする。
2012.7.1
|
|
体力自慢
|
ある病院で研修医の採用のための面接に立ち会ったことがあるが、受験者の多くが申し合わせたように、「体力には自信があります」と主張するので驚いた。とくに、運動部出身のものにその傾向が強かった。つまり、体力が医師としての能力の一つであり、体力のあるものの方が採用に有利であると考えているようなのだ。
医師に体力のあるほうがいいのは確かだが、それがどういう種類の体力なのかはなぞである。
たぶん、筋力は必要ない。(整形外科は除く)
心肺機能も普通は問題にならない。(院内救急発生時、階段を5階分昇り、すぐに点滴取ったり気管挿管したりする場合を除く。)
一方、医師が持っていると絶対有利なのが、寝不足に強い、徹夜明けでもばりばり働けるという体力だ。医師が不眠不休で働くことは、かっこいいことでもほめられることでもないが、時にそのような状況に立たされることがあるのも現実であるからだ。
しかし、運動部で体を鍛えたからと言って、そういう能力が鍛えられるものだろうか。本当に勝負に徹する運動選手であれば、勝つためにしっかり眠る技術こそ必要であって、寝不足でも戦える能力などはそもそも不要であろう。
もしも面接で「仕事に役立つ」体力をアピールしたいならば、次のような主張をするとよいかもしれない。
「学生時代は特に部活もせず、ぶらぶらしていましたが、麻雀の誘いは断ったことがありません。それほど強いわけではないのですが、なぜか徹夜になると必ず勝ちます。また、学生時代は主にカップラーメンで三食をまかなっていましたが、風邪一つひきませんでした。したがって、患者の気持ちがわかる医師になれるかどうか、微妙なところです。」
面接する側としては、判で押したような体力自慢をくりかえし聞かされるよりは、このような話を聞ける方がよほどありがたいのである。ただし、採用に有利かどうかは保証の限りではない。
2012.5.27
|
|
ラスイチ問題
|
麻酔科医室の入り口に、お菓子置き場を設けてある。ここに置いてあるお菓子は、誰でも問答無用で食べてよいことにしている。誰が持ってきたものかは一切気にしないで食べるのがルールである。もちろん、礼などいう必要はない。
 そうやって礼節無用を奨励しているが、そこが日本人の悲しさ、お菓子がラスト一つになるとぴたっと手が止まるもののようである。その結果、写真のように各種のお菓子が一つづつ残って膠着状態になってしまうこともまれではない。
そうやって礼節無用を奨励しているが、そこが日本人の悲しさ、お菓子がラスト一つになるとぴたっと手が止まるもののようである。その結果、写真のように各種のお菓子が一つづつ残って膠着状態になってしまうこともまれではない。
これをラスイチ問題といい、地図塗り分けの4色問題、天体の運動が計算不能になる3体問題と並ぶ難問となっている。(2は思いつかなかった。)これを数学的に解決する方法はないかもしれないが、医学的にはそうむずかしいことではない。
私が咀嚼し、嚥下することで問題は解決する。
2012.5.4
|
|
マニア道
|
このホームページを作る上で私がお手本にしたのは、「卓球王国」という雑誌が作ってるサイトの中の、「奇天烈逆も〜ション」というブログである。書いているのはある卓球愛好家で、有名選手でもなんでもなく、家電メーカーの技術系会社員である。このおやじが、卓球だけでなく宗教とか音楽とか、あらゆることに好奇心を向け、いかにも理系人間らしい合理主義をふりかざすものの、根本にあるのは卓球に対する不合理なまでの情熱と「どこかずれてて笑えるもの」への渇望であり、結果として毎回わけのわからないオチがつくのである。まことに奇天烈なブログである。ひそかに師と仰ぎ、わがホームページをそのレベルまで近づけたいと願うものの、いまだまったく足元にも及ばない。
このブログの最近の話題を少し拝借。この卓球おやじ、同僚の中に花火マニアがいることを知った。「花火鑑賞士」という資格を持つ彼に対し、「花火の歴史上、もっとも革命的な出来事は何だったの?」と聞いてやったという。これがマニアをもっとも喜ばせる質問なのだそうだ。花火鑑賞士が口から泡を飛ばして縷々説明したのは言うまでもない。愛好する対象は違っていても、マニアの道というのはこういうところでつながっているのだと、感心した。
さて、麻酔科医も程度の差はあれ、麻酔マニアである。麻酔科医に同じ質問をしたら、どんな答えが返ってくるだろうか。
全身麻酔薬(エーテル、笑気)の発見は、麻酔そのもののはじまりだから、除く。私ならば、麻酔の歴史の転換点を二つあげさせてもらいたい。
一つ目は陽圧換気の発明である。それまで行われていた、自発呼吸下のエーテル吸入では、可能な手術や対象となりうる患者は非常に限られていたはずである。たとえば開胸手術は不可能だし、呼吸器疾患のある患者の麻酔もむずかしかっただろう。陽圧換気により、手術の適応は一気に拡がったと思われる。自分の目で見たわけではないが、生物の歴史に例えれば、カンブリア大爆発に相当するのではなかろうか。
二つ目はパルスオキシメーター(動脈血酸素飽和度モニター)の普及である。それまでは呼吸を確実にモニターできる方法がなく、呼吸トラブルの早期発見がむずかしかった。麻酔科医は自らの寿命を削りながら麻酔管理を行っていたが、パルスオキシメーターの登場で麻酔の安全性は飛躍的に高まった。術中術後の患者の潜在的な死亡リスクを劇的に減らし、麻酔科医の寿命を劇的に延ばした。
これらの詳細について、語れと言われればいくらでも語るけれども、誰も読まないであろうから割愛する。
あなたは、何の歴史について語りたいですか?
2012.4.21
|
|
カルシウムチャネルの秘密
|
私が大学在職中に研究していたのは、血管平滑筋のカルシウムチャネルである。カルシウムチャネルといえば、電位依存性カルシウムチャネルがよく知られているが、私が着目したのはカルシウム透過性陽イオンチャネルであった。このチャネルは当時まだほとんど注目されていなかったが、私は血管収縮においてはこちらも同じくらい重要な役割を果たしているということに気づいた。私はこの成果をまとめ、自信を持って世に発表したところ、現在もまだまったく注目されていない。
まったく、世の中の人は、カルシウム透過性陽イオンチャネルのことを知らないまま、よく自分の血圧をコントロールできているものだ。驚いたことに、他人の循環制御を職業とする麻酔科医ですら、このチャネルのことを知らないものがいる(私以外のすべての麻酔科医)。そんなことだから彼らは麻酔中の患者さんの血圧を下げるときに、電位依存性カルシウムチャネルの拮抗薬を喜んで使っているのである。私も同じ薬を使っているのだが、それは陽イオンチャネル拮抗薬がないからであり、いやいや使っているところが違う。
学問や芸術が先進的過ぎると世の中から理解されず、埋もれてしまうことがあるのはよく知られているとおりである。整数の平方根が分数で表せないことを発見したピタゴラスの弟子などは、埋もれるどころか、ピタゴラスから死刑を宣告され海に沈められてしまった。今のところ私は誰にも命を狙われているようには思えないので、幸運なほうなのかもしれない。
現在は研究生活から足を洗い、臨床に明け暮れる毎日である。私はおそらく、カルシウムチャネルの秘密を知る世界でただ一人の麻酔科医であるが、そのことを他人にひけらかしたりしたことは一度もない。ひけらかしても「何それ」という顔をされるのがオチだからである。かりに頼み込んで説明を聞いてもらうところまでこぎつけたとしても、「ふーん」以上の反応は期待できない。心の傷が深くなるだけだ。
これからも、「早く生まれすぎた陽イオン専門麻酔科医」として生きていく覚悟である。
2012.4.14
|
|
別れの言葉
|
異動の季節になった。
私の周囲でも,医師,看護師、事務の人、いろんな人が部署を変えた。隣の病棟に移るだけの人もいれば,遠くの病院に移る人もいる。
去る方は、「お世話になりました。ありがとう」でよかろうが、見送る方はどう言えばいいのだろう。「寂しくなる」とか、「あなたなしでやっていけるだろうか」とか、心にもないことはなかなか言えないものだ。「あなたがいなくなっても、次の人が来るし、なんとかなるでしょう」などと、本当のことはもっと言えない。以前紹介した老外科医の「壮健で!」はかっこいいが、この一言だけでぴたっと止めるには、相当のダンディズムの持ち合わせが必要だ。
最近気に入っているのは,「また、ご縁があったらご一緒しましょう」という言葉である。永遠の別れになるとは限らないから、お互い気にしないようにしましょうや、というわけである。何を言っているかわからないが、そのあいまいなところがいい。
この季節,私が一番苦手なのは,送別会の終わりに送られる人が出口に陣取って、帰る客に一言ずつ挨拶を交わす、あの儀式である。とっさに逃げ場を探すが、他の出口はすでに手回し良くふさがれている。しぶしぶ行列に並びながら、冷や汗をかく。本当に何をいっていいのかわからない。「すみません」と謝って済むものなら謝りたい。
もし私が異動する側になった場合、そういう送別会は勘弁して欲しい。残される人に冷や汗をかかせたり、送別会の会費を払わせたりするだけの価値が、自分にあるとは思えない。私の理想の立ち去り方は、「蒸発」である。ちょっとコンビニに言ってくる、などと言って財布だけ持って病院を出て、そのまま帰ってこなかった、というのがいい。そして私がいなくなったことに誰も気がつかなったとしたら、最高である。
その日のために、いてもいなくてもどっちでもいい、透明感あふれる麻酔科医でいられるよう、こころがけておこう。
2012.4.6
|
|
あきれたベストセラー
|
何やら単行本のベストセラーランキングの中に、「大往生したけりゃ医療とかかわるな」という本が入っているようだ。とても買って読む気にはなれないが、ここまで挑発的なタイトルをつけられると放置もできないので、ネットで紹介文だけ読んでみた。
どうも、癌にかかっても治療をうけないほうが痛くないし、苦しまない自然な死に方ができる、と言いたいらしい。たぶん,もうこの世に思い残すことのない人ならば,癌と分かったら延命治療をせずに運命を甘受すべきというのが著者の主張なのであろう。
だが、世の中には、治る癌と治らない癌がある。切除すれば確実に治る癌だと知ってもなお、治療を拒否する人は多くはないだろう。治る癌かそうでないかは、病院に来てもらわないとわからないのである。「医療とかかわるな」というのは、その見極めから放棄せよということなのだろうか。
癌も治療をしなければ苦しまない,というのもおかしい。癌の種類にはよるだろうが,治療をしようがしまいが、痛い癌は痛い。現在の医療は,治癒の見込みのない癌に対しても,「緩和医療」といって痛みなどのつらい症状を緩和することに積極的に取り組んでいる。「医療とかかわるな」というのは、緩和医療も拒否せよということなのだろうか。
著者は医師であり、自分が多くの癌患者の最期を看取った経験からこの本を書いたという。その人が、「医療とかかわるな」というのは、おかしくないか。
そう、問題の元凶はこの書名にある。たしかにインパクトはある。だがめちゃくちゃだ。
延命治療の放棄を「医療とかかわるな」という過激な表現に言い換えることによって,人の目を惹こうという魂胆が丸見えなのである。
延命治療の問題点については、すでにさまざまな人がさまざまな場で論じている。死が避けられないときに延命治療を拒否するのは、患者さんの当然の権利である。しかし、「尊厳死」とか、「リビングウィル」とかいう言葉がすでに地味であり,多くの人の関心を呼んでいるとは言いにくい。しかしだからといって、人の目を惹くために何をしてもいいというものではない。
医療が人の死をめちゃくちゃにしているといいたそうなその口ぶりも私の神経を逆撫でするが,一番心配なのは,このような書名がベストセラー欄に載りつづけることで,病院を受診しなければいけない人を病院から遠ざけてしまわないかということだ。
からだのどこかにしこりや痛みを抱えつつ,仕事が忙しいからとか,癌と言われるのが怖いからという理由で病院を受診しない人はけっこういる。それで手遅れになってしまう人も残念ながらいる。そういう人が、こんな本がベストセラーになっていると知ると,病院に行かないことの口実になってしまうのではないだろうか。その結果,まだ死にたくない人が死に,完治できるはずの人が死ぬだろう。
出版社は売上げを伸ばすことしか考えていないからこんな書名をつけるし、著者はおこづかいを増やすことしか考えていないから、医師でありながら、自分の本にこんなタイトルをつけられても平気なのである。この書名が一人歩きした結果、癌による死亡が増えたとしても、彼らには興味のないことだろう。
ささやかながら、彼らに、この本の正しい書名を教えたいと思う。「死んでもいいと思っている人は医療とかかわるな」
ベストセラーにはならないだろうが、それが世の中のためである。
そして出版社と著者にはこう言いたい。「あなたがたは医療とかかわるな」
2012.3.21
|
|
リーダーの条件
|
大学時代、医学部卓球部のキャプテンを1年間務め、さまざまな失敗を犯した。今思い出しても冷や汗が出る。ただ一つの収穫は、自分にはリーダーは向かないということがわかったことだった。
クラブで,職場で,さまざまなリーダーを見てきたが,すぐれたリーダーになるためには、やはりそれなりの資質が必要だと思う。
まず、考え方の異なる者に自分の意見を受け入れさせなければならない。説得,強要、感化いろいろな手段があるが、どれも私には無理そうだ。現在,部下と自分の意見が食い違う場合は,自分が意見を変えることでことなきを得ている。ただ、二人以上の部下の間で意見が分かれたときは問題だ。私にできるのは、「おろおろする」ことだけだ。
また、リーダーは部下の能力を適切に評価し、適材適所で仕事を割り当てなくてはならない。こういうときに必要なのは,自分のことを棚にあげる能力だ。自分にできないことを人に要求できるのが、すぐれたリーダーの条件だからだ。自分が部下達に範を示すなどといった無駄なことは、しないほうがよい。
ただし、このタイプのリーダーになるためには、「そんなにいうなら自分でやれよ」などといった批判を跳ね返すだけのカリスマ性が必要だ。これは、わたしにもっとも欠けた資質である。
そんな私が,何かの間違いで,ある大病院の麻酔科の長を任命されたことがある。(幸い1年だけだったが。)ここのポストは激務で有名だったので,この話が決まったころ,私は家に帰って弱音を吐いた。
「大学医局のいろんな人が、ぼくのことを心配してくれてるみたいやで」
すると、それを聞いた我が家のリーダーは、こう言った。
「あんたはアホか。自分が人の上に立つ器じゃないことくらい、わからんのか。それをうれしそうに、こんな話を受けた自分が悪いんや。」
弱っている人をこんなふうに叱りつけることのできる人,こういうのが本当のリーダーだと思う。やっぱり私には無理だ。
2012.3.3
|
|
進化
|
昨年、日本の女子サッカー「なでしこ」チームが世界を制したが、彼女達と欧米の選手の体格差は際立っていた。程度の差はあっても、あらゆるスポーツにおいて体格のよいほうが有利であることは、スポーツを知る者の暗黙の認識であろう。彼女らがその体格差をはねのけて優勝したことは、真に称賛に値すると思う。
卓球においても,かつては日本がド根性(死語)と技術の正確さで世界の頂点に君臨していたが、やがて筋力がものをいう時代に入り、日本人が勝つのは難しくなっている。
しかし、日本人のからだが小さいことにも、何か理由や利点があってもよいのではないだろうか。
進化生物学の世界では、「島嶼化」という言葉があるらしい。島という、食料の限られる環境で独自の進化を遂げていくと、うさぎより大きな生物は小さくなっていくという。
人間も、その例にもれないかもしれない。インドネシアのフローレス島では、1万2千年前まで、身長1mあまりしかない人類が住んでいた。その正体はまだはっきりしないが、原生人類よりずっとまえにアフリカから出て広がっていった人類の末裔で、島嶼化により小さくなったのだと考えられているようだ。日本人のからだの小さいのも、島嶼化とは言えないまでも島国での生活に適応したからではないかと思うのだ。
しかし今、地球を、資源や食料の限られた一つの島と考えると、人類も全体で島嶼化したほうがいいのではなかろうか。体がちいさくなって少食になれば、人間の活動の地球への負荷もそうとう小さくなるだろう。とりあえず島嶼化の目安である「うさぎ」の大きさを目指すのがいいだろう。かつて、日本人はうさぎ小屋に住んでいると言われ(1979年ECの「対日経済戦略報告書」)、くやしい思いをした人もいるかもしれないが、あれは進化の先端を走る日本人への賞賛の言葉だったのかもしれない。
だが、いろいろと関門がある。
人間島嶼化を志す国やグループは、オリンピックの金メダルはあきめた方がいいだろう。今でも金メダルを取る日本選手がいるのは奇跡に近いのだ。からだがうさぎの大きさになってしまっては、さすがの北島康介も金メダルはとれないだろう。あるいは、すべての種目において柔道のような体重別クラスを設けてもよい。
生物学的には、お母さんのからだが小さくなりすぎると、人間にとって何より大事な脳が、お母さんの産道を通れなくなる可能性がある。帝王切開でやっていく方法もあるが、頭蓋骨を縦長にすることで対応可能であろう。
一番の問題は、背の高いほうが異性にもてやすいという社会的要因だ。阿部寛とか、向井理とか、背が高くて顔の小さいほうがもてる(=生殖に有利)という、意味のわからない今の女性の趣向がつづくと、人間がみな北極クマくらいの体格になり、夕食にアザラシ1頭食べるようになるかもしれない。そうなったら、人類は終わりだ。
世の中の女性にはぜひ、背の低い、晩ご飯にはニンジン2本も出せば喜んでくれる、頭が細長い男性を愛して欲しいと願っている。
2012.2.19
|
|
夢の続き
|
夢といえば、麻酔中にも夢を見る人は、少数ながらいる。なぜか、ほとんどがいい夢のようである。
たとえば、主治医と一緒に酒盛りをしている夢、バレーボールをして遊んでいる夢、ひさしぶりにヤクザしている夢、タコと一緒に水槽に入っている夢などである。そういう夢を見たと、目覚めた直後に患者さんがなごりおしそうに言われることがあるのである。ヤクザやタコがいい夢かどうか、よくわからないが、すくなくともご本人は満足そうであった。
さらによいことに、麻酔中に夢を見たことを、患者さんはしばらくすると忘れてしまうようである。普通の睡眠時の夢でも、醒めた直後は覚えているが、昼になるまでにはたいがい忘れているから、似たようなものだろう。
何かの小説に書いてあったが、最高の目覚めとは、すばらしい夢をみて、しかも目覚める瞬間にそれをすべて忘れてしまうことだそうだ。
私たち麻酔科医も、すこしは役に立つ仕事をしているわけだ。
2012.2.15
|
|
危険な物質
|
ある研究によれば、地球上には恐ろしいガスが存在する。人間がそのガスを吸うと、わずか 0.00001% の濃度でも数分で死に至るという。意外にも21%のほうが毒性は少ないが、それでもこのガスは数十年かけてからだをむしばみ、緩慢な死をもたらす。しかもこれがありふれた場所に存在するというから油断できない。(出典:大学時代の法医学か何かの講義)
だが、残念ながらわれわれはこのガスから逃がれることはできない。これは酸素だからである。酸素が緩慢な死の原因であるということに疑問を抱く方もおられるかもしれないが、酸素はもともとあらゆるものを酸化して傷めてしまう猛毒ガスであり、酸素下で暮らす生物は強力な解毒システムによって酸素を解毒しながらかろうじて生きているのだ。何ともご苦労な話である。嫌気性菌がうらやましい。
酸素で死ぬのは寿命だからあきらめるとしよう。だが、地球上には他にも危険な化合物が存在する。(あ、途中で読むのやめないでください。)この化合物は酸性雨の主成分であり、末期癌患者の腫瘍内部からも検出されている。また、この化合物が大量に蓄積している場所があり、そこに立ち入って窒息してしまう人が跡を絶たない。(出典:N.D. Tyson著、「ブラックホールで死んでみる」)
その化合物の名前は一酸化二水素といい、もう少し耳慣れた言葉でいうと水である。
地球がこんなに危険な場所だったとは知らなかったでしょう。
2012.2.3
|
|
麻酔の夢
|
夢にもいろいろあるが、私にとって、麻酔を受ける夢ほどいやなものはない。手術中麻酔が浅くて目が覚めてしまっているとか、夫の手術中なのに妻が遊んでいたりとか、麻酔の夢はろくなことがない。そんな夢を定期的に見るのである。
夢といえば、若いころは人並みにフロイトやその弟子のユングの精神分析に興味を持ち、随分本を読んだものである。夢からその人の無意識の世界が読み取れるというのが、精神分析の大前提である。夢判断をきっかけに、心の病やつまづきから立ち直った例が、本の中ではたくさん紹介されている。もちろん、私も自分の夢を解読しようと試みたが、本に書いてあるような説得力のある解読はついに一度もできなかった。
あくまで私の経験から身も蓋もないことを言わせてもらうと、夢とは脳内の記憶のどんちゃん騒ぎにすぎないように思う。そこから意味を読み取るのは無理というものだ。まして、夢の分析が問題解決の役に立つなど、思いもよらないことである。
そういう立場から、あえて自分の麻酔夢を分析してみよう。
自分の関心事が夢に出てくるのは当然である。日中ゲームに熱中したりすると、その夜ゲームの画面が夢に出てきたりする。そこに象徴とか代償とか、むずかしい理屈はないだろう。実生活では麻酔をかけるほうだが、夢ではかかる方に廻ってしまうという倒錯も、ありそうなことである。さて問題は、麻酔がかかったら意識がなくなるのが本当なのに、そこが夢の世界の浅はかなところで、夢のなかでさらに意識を失うという器用なことができないというところである。したがって必然的に、手術を受ける自分が見えてしまう、麻酔中なのに意識があるという苦しい事態を自ら招くことになるのである。
だから、麻酔を受ける夢はかならず悪夢であり、眠りを職業とする麻酔科医というややこしい存在の宿命なのである。(労災認定は無理だろうか。)
なんとも夢のない話でした。
2012.1.15
|
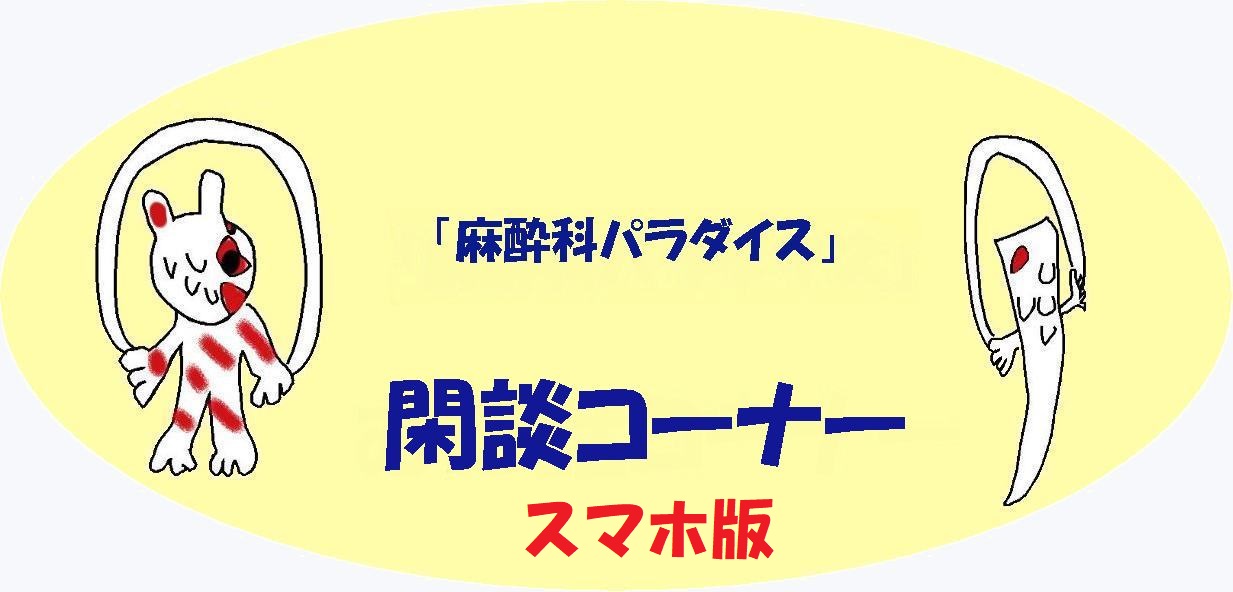
 私も、自分の子供に麻酔科医の仕事を理解させるのに苦労した。
私も、自分の子供に麻酔科医の仕事を理解させるのに苦労した。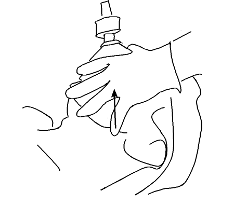 「介抱講座」で述べたように、舌根沈下による気道閉塞に対しては、「下顎挙上」がもっとも有効な手段となる。麻酔においても、全身麻酔をかけてから気管に呼吸のための管を挿入するまでの数分間、下顎挙上が必要になるが、麻酔科医はこれを左手小指の先端だけで行っている(図参照)。万一この指を失ったら、他の指では代用がきかないのである。たとえば、左薬指や右小指ではだめなのである。
「介抱講座」で述べたように、舌根沈下による気道閉塞に対しては、「下顎挙上」がもっとも有効な手段となる。麻酔においても、全身麻酔をかけてから気管に呼吸のための管を挿入するまでの数分間、下顎挙上が必要になるが、麻酔科医はこれを左手小指の先端だけで行っている(図参照)。万一この指を失ったら、他の指では代用がきかないのである。たとえば、左薬指や右小指ではだめなのである。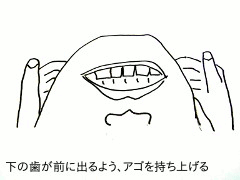 目の前で泥のように眠っている課長、舌根沈下を起こしてすごいいびきですが、ときどき気道閉塞に陥っているようです。普通に眠っている人でもそういう人はいますが(睡眠時無呼吸症候群)、アルコール、薬物、脳卒中などによる気道閉塞だとしたら呼吸が再開しないでそれっきりになる可能性があります。どうすれば舌根沈下を防ぐことができるでしょうか。
目の前で泥のように眠っている課長、舌根沈下を起こしてすごいいびきですが、ときどき気道閉塞に陥っているようです。普通に眠っている人でもそういう人はいますが(睡眠時無呼吸症候群)、アルコール、薬物、脳卒中などによる気道閉塞だとしたら呼吸が再開しないでそれっきりになる可能性があります。どうすれば舌根沈下を防ぐことができるでしょうか。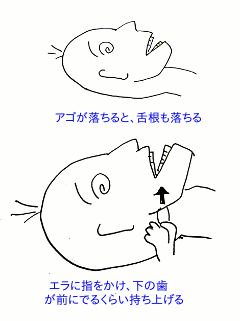 コツをつかめば、これが指一本でできるようになります(下の図)。これが、「指一本で人の命を助ける方法」なのでした。かっこいいでしょう。麻酔科医は麻酔導入時にこれを左手の小指でやっているので簡単にできますが、一般の方はすこし練習をする必要があるかもしれません。家族にいびきのひどいオヤジなどいれば、練習台にしてやりましょう。
コツをつかめば、これが指一本でできるようになります(下の図)。これが、「指一本で人の命を助ける方法」なのでした。かっこいいでしょう。麻酔科医は麻酔導入時にこれを左手の小指でやっているので簡単にできますが、一般の方はすこし練習をする必要があるかもしれません。家族にいびきのひどいオヤジなどいれば、練習台にしてやりましょう。 結局、課長の意識がない、呼吸しているかどうかもわからない、という時は救急車を呼んでもらうしかありません。救急車には呼吸モニターと気道確保に精通した救急救命士が乗っていますから。
結局、課長の意識がない、呼吸しているかどうかもわからない、という時は救急車を呼んでもらうしかありません。救急車には呼吸モニターと気道確保に精通した救急救命士が乗っていますから。 しかし、理系の人間ならば違和感を覚えるはずだ。37℃の水蒸気それ自身にはエネルギーや化学的な活性はほとんどない。繊維の側も、燃焼などの化学変化を起こしているのではないだろう。その両者が合体して熱を産み続けるわけがない。エネルギー保存の法則に反している。発熱現象はおそらく溶解熱の一種だろうが、いずれにしてもごく一時的なものに過ぎないはずである。(ネットで調べた所では、ものの3分。)
しかし、理系の人間ならば違和感を覚えるはずだ。37℃の水蒸気それ自身にはエネルギーや化学的な活性はほとんどない。繊維の側も、燃焼などの化学変化を起こしているのではないだろう。その両者が合体して熱を産み続けるわけがない。エネルギー保存の法則に反している。発熱現象はおそらく溶解熱の一種だろうが、いずれにしてもごく一時的なものに過ぎないはずである。(ネットで調べた所では、ものの3分。) そうこうするうち、ケロちゃんは原因不明のけいれんに悩まされるようになった。いよいよ弱ってきたとき、明るいところに連れて行こうとすると、最後の力を振り絞って抵抗した。そして、とうとう望み通り暗いところで真夜中に息をひきとった。妖怪になる前に仏様になってしまったのである。
そうこうするうち、ケロちゃんは原因不明のけいれんに悩まされるようになった。いよいよ弱ってきたとき、明るいところに連れて行こうとすると、最後の力を振り絞って抵抗した。そして、とうとう望み通り暗いところで真夜中に息をひきとった。妖怪になる前に仏様になってしまったのである。 それが当たっているかどうかは別にして、このような、帽子の中から鳩が飛び出すような離れ業を目の当たりにする瞬間が、なんとも言えない。
それが当たっているかどうかは別にして、このような、帽子の中から鳩が飛び出すような離れ業を目の当たりにする瞬間が、なんとも言えない。
 小柄ながら筋肉質、まゆが太く、メガネのフチも太く、見た目は頑固な偏屈おやじであったが、実際にはとても気さくでやさしいひとであった。(いやなやつだったら、そもそも私の文章には登場しない。)ICUで撮った胸部写真を見てもらった時、とても親切に読んで下さったことは忘れない。胸部外科の医師からも激しく愛されていて、肺やリンパ節をどこまで切除すべきかを、手術中にしばしば相談されていた。
小柄ながら筋肉質、まゆが太く、メガネのフチも太く、見た目は頑固な偏屈おやじであったが、実際にはとても気さくでやさしいひとであった。(いやなやつだったら、そもそも私の文章には登場しない。)ICUで撮った胸部写真を見てもらった時、とても親切に読んで下さったことは忘れない。胸部外科の医師からも激しく愛されていて、肺やリンパ節をどこまで切除すべきかを、手術中にしばしば相談されていた。 画像診断は囲碁、将棋に似ている。これらは「完全情報ゲーム」といって、競技者がすべての情報を知りうる状況にあり(麻雀やポーカーは違う)、したがって勝敗は運よりも「読みの深さ」で決まるというものである。
画像診断は囲碁、将棋に似ている。これらは「完全情報ゲーム」といって、競技者がすべての情報を知りうる状況にあり(麻雀やポーカーは違う)、したがって勝敗は運よりも「読みの深さ」で決まるというものである。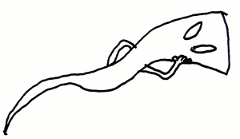 薬物依存から離脱するのはむずかしいが、依存症にならないようにすることは極めて簡単である。「試してみようと思わないこと」である。ある薬理学の教授の言葉を借りれば、「人間は薬には絶対に勝てない」のである。一度だけ試して、すぐにやめよう、という考えは、薬物という魔物には通用しない。自分を買いかぶってはいけないのである。
薬物依存から離脱するのはむずかしいが、依存症にならないようにすることは極めて簡単である。「試してみようと思わないこと」である。ある薬理学の教授の言葉を借りれば、「人間は薬には絶対に勝てない」のである。一度だけ試して、すぐにやめよう、という考えは、薬物という魔物には通用しない。自分を買いかぶってはいけないのである。 2つほどの雑誌から拒絶された論文を持て余したときのことである。私はこれをイギリスのややマイナーな雑誌に投稿し直したが、数ヶ月経ってもまだ受け取りの通知が来ない。しかし私はあえてこれを放置した。1年を過ぎたあたりでそろそろかと腰を上げ、問い合わせの手紙を送ったところすぐに返事が来た。論文を見落としていた、すぐに査読に回す、とのことであった。この時点で、私は「これは行ける」と思った。相手が恐縮しているのを感じたからである。論文はすんなり受理された。
2つほどの雑誌から拒絶された論文を持て余したときのことである。私はこれをイギリスのややマイナーな雑誌に投稿し直したが、数ヶ月経ってもまだ受け取りの通知が来ない。しかし私はあえてこれを放置した。1年を過ぎたあたりでそろそろかと腰を上げ、問い合わせの手紙を送ったところすぐに返事が来た。論文を見落としていた、すぐに査読に回す、とのことであった。この時点で、私は「これは行ける」と思った。相手が恐縮しているのを感じたからである。論文はすんなり受理された。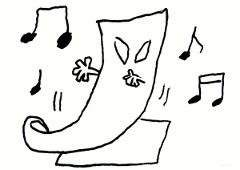 「わし、尊敬してたのに、残念やな。はは。」
「わし、尊敬してたのに、残念やな。はは。」 気迫に押された麻酔科医は、今度は何とか穿刺し、麻酔を成功させたのであった。
気迫に押された麻酔科医は、今度は何とか穿刺し、麻酔を成功させたのであった。 ガーゼカウントというのは、手術終了時に体内にガーゼが残らないよう、使用済みのガーゼを集めて数える作業であり、どんなに忙しくても、清潔ナースと声を合わせて数を照合しつづけなくてはならない。一旦数が合わなくなると、いつどこで無くしたのか、追跡不能になるのだ。
ガーゼカウントというのは、手術終了時に体内にガーゼが残らないよう、使用済みのガーゼを集めて数える作業であり、どんなに忙しくても、清潔ナースと声を合わせて数を照合しつづけなくてはならない。一旦数が合わなくなると、いつどこで無くしたのか、追跡不能になるのだ。 後にこの人が結婚すると聞いたとき、美しい人でもあったので、相手の男性をうらやましく思うと同時に、同情の念も禁じえなかった。お釈迦様の手から孫悟空が逃れられないのと同じくらい、こういう人の目はごまかすことはできないからだ。
後にこの人が結婚すると聞いたとき、美しい人でもあったので、相手の男性をうらやましく思うと同時に、同情の念も禁じえなかった。お釈迦様の手から孫悟空が逃れられないのと同じくらい、こういう人の目はごまかすことはできないからだ。
 そうやって礼節無用を奨励しているが、そこが日本人の悲しさ、お菓子がラスト一つになるとぴたっと手が止まるもののようである。その結果、写真のように各種のお菓子が一つづつ残って膠着状態になってしまうこともまれではない。
そうやって礼節無用を奨励しているが、そこが日本人の悲しさ、お菓子がラスト一つになるとぴたっと手が止まるもののようである。その結果、写真のように各種のお菓子が一つづつ残って膠着状態になってしまうこともまれではない。