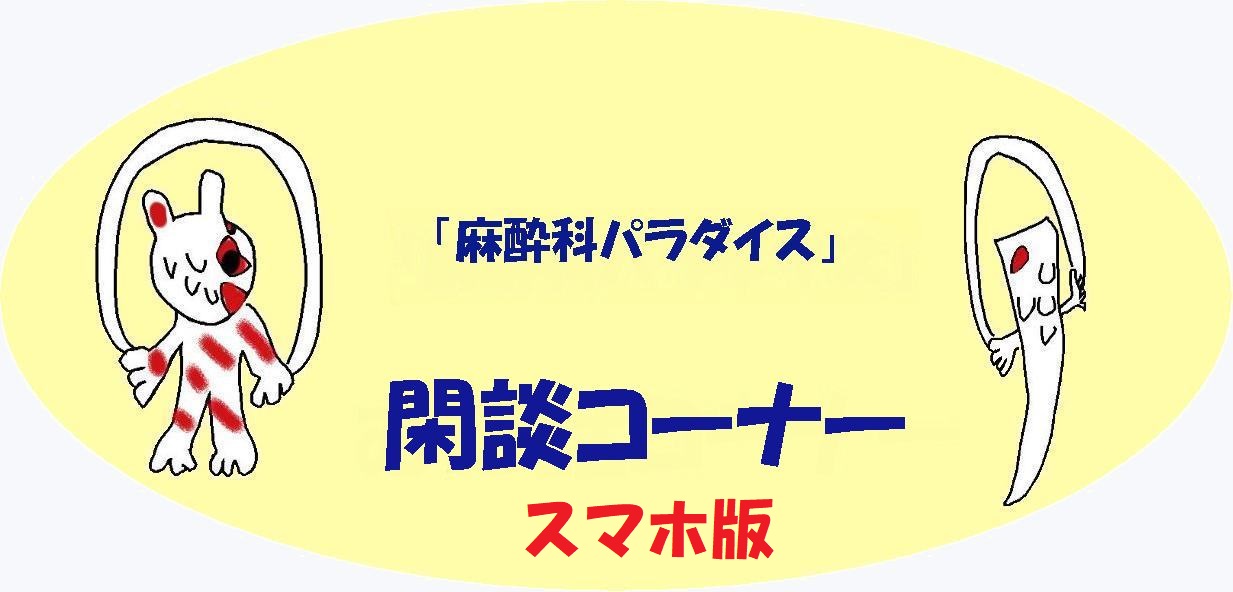|
手術室忘年会挨拶
|
この1年間の麻酔件数は約2,200件で、過去最高を更新しました。
(会場拍手)
えー、ここは全然喜ぶところではありません(笑)。麻酔科医3人と非常勤の先生とで何とかやってきましたが、麻酔科医ひとりあたりの麻酔件数は関連の病院と比べても最多レベルです。さらに来年は退職者もあり、ヘタをすると麻酔科医は私一人になってしまう可能性がありました。そうなったら、私もフラッと旅に出てみようかな、と思っていました。しかし、いろいろな幸運もあり、来年も何とかなる見通しです。
みなさん、よかったですね。
さて、私の院内PHSの着信音はゴジラのテーマにしていますが、どういう意味だかお分かりですか。招かれざる客が来た、という意味ですよ。外科のみなさんが私に電話をかけるたびに、電話の向こうでゴジラが鳴っていることを、どうぞお忘れなく。
来年もくれぐれも、お手柔らかに。
2011.12.31
|
|
外科医列伝(6)
|
外科の緊急手術というのは、ほとんどが腸管の病気である。イレウス(腸閉塞)では腸が内容物でパンパンに膨れ上がっているし,腸穿孔では腹腔内に腸内容物がもれている。腸内容物と言うと深刻さに欠けるが、ハッキリ言えばこれは大便である。頭側にいる麻酔科医ですら、嗅覚と視覚へのダメージはかなりのものだが、外科医は距離が近いし、さらに触覚の脅威にも耐えなくてはならない。仕事とはいえ,ご苦労なことだと思ってきた。
あるとき、イレウスの緊急手術中、外科の主治医が腸管から大量の「内容物」を絞りだしながらこう言った。
「ほんとはね、外科医はこういうの好きなんですよね」
すると、一緒に手術をしていた外科部長があわてて、
「おいっ」
といって、かすかに首を振って見せたのを私は見逃さなかった。それは、仲間の秘密をもらしそうになった者への警告に違いなかった。
ハハーン、そういうことか。いままで同情してきて、損をした。それ以降は「腸内容物操作」に取り組む外科医に対して同情どころか,軽い羨望すら覚えるようになってしまった。
大事な秘密を教えてくれた功績を讃え,私の外科医列伝に加えたいと思う。だが、本人は別にうれしくはないだろう。すでに以前,「手術大成功」(列伝2)で「すごい外科医」に列せられている先生だからである。
2011.12.23
|
|
麻酔と念仏
|
仏教では、念仏さえ唱えていれば成仏できるという宗派があるようだ。(浄土宗でしょうか。)それも、沢山唱えれば唱えるほどよいという。大学の近くに百万遍というお寺があったが、これも、念仏を百万回唱えたら何とかなるという話だろう。つまり、苦行とか善行とか少し力のいる仕事をせずとも、念仏というごく簡単な作業でも数を重ねれば同じくらいの効果があるということだ。なかなか便利な考え方である。この発想は、麻酔にも生かしてみたい。
麻酔の仕事では、この医師でなくてはできない、という業務はあまりない。ときには、麻酔科医のとっさの機転、とっておきのカミワザが威力を発揮することもあるが、そういう場面は多くはない。だから、他科の医師から見れば、退屈な仕事に映っていると思う。しかし、誰でもできるような麻酔症例でも、それをたくさんやること自体に意義があるはずだ。念仏を唱えれば極楽浄土に行ける。では、麻酔をいっぱいするとどんなご利益があるのか。
かつて日本の麻酔科医の草分けのような先生が,引退講演で次のような話をされたらしい。自分の生涯麻酔管理件数は1万件(だったかな)、そのうち、死亡事故が2件あった、と。どのような事故かはわからないが、この時代の麻酔で生涯事故数がこれくらいというのは、すごいことである。その2件以外はひたすら無事に麻酔症例を積んでこられたのである。このすごさは普通の人にはわからないだろう。この先生は、自分の業績を理解できるのは麻酔科医のみであろうことを知っておられたと思う。その上で、淡々と数字を挙げて見せたのである。
麻酔科医というのは、キャリアの終点に立ったときに初めて自らの偉業を語れる、そういう仕事をしているのかもしれない。念仏と同じように、愚直な積み上げが聖に通じる、それが麻酔百万遍のご利益ではなかろうか。たぶん。
そんなふうに思えば、これといって変哲のない麻酔症例でも、今日はいっぱいできたと喜んで家に帰ることができるだろう。
南無阿弥陀仏。
2011.12.18
|
|
外科医列伝(5)
|
以前、「手術に必要なのはゴッドハンドではなく、しっかりした手術チームである」と断言した私であるが、替わりのいない外科医というのはたしかにいるし、この外科医でなければ成功しない手術というのがあることも認めなくてはならない。サッカーと同じだ。手強い敵と戦うとき、ディフェンスを含めた組織力がないと試合にならないが、その上で最後に勝負を決めるのは点取り屋の天才のひらめきだったりする。
私が大学病院の研修医だったころのことである。その日、肝硬変合併肝癌の切除術が行われていた。肝臓は大小の血管のカタマリであるから、肝切除は出血との戦いである。肝硬変ではとくに止血が難しく、術中大出血がしばしば発生した。このときの手術でも夕方に差しかかったころ、癌は取れたものの出血が止まらなくなった。執刀していた講師(外科のナンバー3)が途方に暮れているのが、研修医の私にも見て取れた。しかし、麻酔科医にできるのはせっせと輸血して命をつなぐことだけだ。極めて危険な状態であった。
するとそこに、小児外科担当の助手(ヒラの教官)が現れ、「ちょっと休憩してください、その間私が時間をつなぎます、」と言ったか言わなかったか、とにかく講師と交代した。そして、鮮やかな手際で出血地点をつぎつぎと制御していき、ものの1時間もたたないうちにすべて止めてしまった。講師が休憩から帰ってきたときには、手術の重要なところは終わっていた。あ、この人は間違いなく、人の命を一つ救った、と思ったものだ。
この助手こそが、のちに大学に創設された移植外科の初代教授に就任したT先生である。この人の腕がなかったら生体肝移植が大学で軌道に乗ることはなかったし、日本で医療として定着することもなかっただろう。どこから見ても普通の人だし、ちっとも威張らず気さくな人だし、メスさばきも華麗というのではない、的確な処置をひたすら着実に積み重ねて、一歩も無駄足を踏まずに最短距離でゴールにたどり着く。その普通さにこそ、この天才のすごみがある。
大衆受けを狙うテレビでは、ちょっとお目にかかれないタイプですね。
2011.12.13
|
|
麻酔と戦争
|
いつのころからか、麻酔の雑誌とか学会のシンポジウムなんかで、「○○に対する治療戦略」などというタイトルをよく目にするようになった。方針、方略とでもすればよいところを、わざわざかっこつけて戦争用語を引っ張り出すところが気に入らない。こういう言葉を使う人は、戦争にかっこよさを感じているのだろうか。医療は病気との戦いだから、戦略という言葉もあながち的はずれではない、という声も聞こえてきそうだが、私は医療を戦争になぞらえるような品のないことはしたくない。
医学の進歩がしばしば戦争によって促されてきたことは確かだろう。出血に対する輸液の理論は、ベトナム戦争で傷ついた軍人の治療の必要性から大きく前進したと聞いたことがある。しかし、人を助けるという自分の仕事は、人を殺傷する行為からなるべく離しておきたいというのが私の心情である。
医学が戦争に近寄るのも怖いが、もっと怖いのは医学の軍事利用である。
9年ほど前だったか、チェチェン人のゲリラが多人数でモスクワ劇場を襲い、人質をとって立てこもった。これに対し、ロシア軍は劇場内に麻酔薬を充満させ、意識をうしなったゲリラを射殺した。このとき使用された麻酔薬は、当時の新聞報道によると、ハロタン(揮発性吸入麻酔薬)とも霧状にしたフェンタニル(全身麻酔用麻薬)とも言われるが、軍事機密であるから薬の正体は結局のところ分からずじまいである。(Wikipedia "KOLOKOL-1" 参照。)さらに悲惨だったのは、人質たちにも多くの犠牲者が出たことである。麻酔薬による呼吸抑制で窒息死したものと考えられている。これは麻酔薬の性質から考えて当然予想されることであるから、軍が劇場に突入する際、気道確保に経験のあるものを同行させ人質の救出に当たっていれば、多くの命が救われたはずである。
731部隊の例もある。オウム真理教は仮谷さん殺害に麻酔導入剤のチオペンタールを使用した。医学が人を傷つけるために利用されれば、最悪の武器となる。だから平和な時にあっても、医療と戦争とは遠ざけておいたほうがいいと思うのである。
2011.11.26
|
|
手術と笑い
|
手術関係者にとって、笑いは鬼門である。
手術室に入った患者さんの多くは、緊張のためコチコチになっている。ここで一発冗談でも言って、患者さんの緊張をほぐしてあげたいと思うのが人情である。ところがこれが、うまくいかないのだ。
たとえばこんなことがあった。看護師さんが、麻酔を受ける直前の患者さんの気分をやわらげようと、「緊張されてるんですか,大丈夫ですよ,ふふふ」と笑ってみせたところ、「看護師に笑われた。」と患者さんが激怒したのである。この人は術後も,「こんな病院くるんじゃなかった」とまだ怒っていた。こんなので切れる患者さんがいるのだから、つまらないギャグなど言ってすべってしまったら、「不謹慎な医者の不用意な発言のためにトラウマを負った」と訴えられてもおかしくない。
私も、訴えられるまではいかないが、笑いで失敗したことが何度かある。だから、「おもしろい人」になりたいのはやまやまだが、患者さんの前では、「やさしい、まじめな人」になる。
ただ一人、手術室で冗談をいうことが許される人がいる。患者さん本人だ。
「麻酔科の先生、気持ちええやつ、うってや」(40代男性)
「ぼく怖くないよ、男の子だもん」(70代男性)
「じゃ、私は寝るけど、みんなはがんばってねえ」(60代女性、麻酔で眠るまぎわに)
外国映画のヒーローは、窮地に追い込まれても冗談を言えるところにカッコよさを表現するであるが、日本にもカッコいい人はたくさんいるのである。
2011.10.1
|
|
外科医列伝(4)
|
9年前、小さな療養所病院に1年間勤めたことがある。そこの胸部外科の先生が懐かしく思い出される。
もう定年間近の、ひょうひょうとした老外科医であったが、昔はずいぶん怖い先生で、よく怒鳴って看護師さんを震え上がらせていたらしい。そういえば眼光の鋭さは、浅田二郎の小説にでも出てきそうな老侠客のそれを思わせるものがあったが、私の見たのは、ガーゼをうっかり控え室のゴミ箱に捨てたり、手術申し込みの内容がいい加減だったりで看護師さんに叱られる姿ばかりであった。ご本人は全くそれを意に介していなかったが。
ある時、手術中に突然、前後に何の脈絡もなく、
「わしはつねに、土のことを考えておる」
と述べられた。菜園が趣味、というより生きがいらしかった。
私が、大学の人事により病院を去るとき、その先生のところに挨拶にうかがった。新しい任地では、はじめて麻酔科の長として部下を持つことになるのが心配だ、と言ったところ、
「なーに、自分のやりたいようにやったらいいんだ。誰が何と言おうと、気にするこたあないよ」
と的確なアドバイスをしてくださった。自分もそうしてきた、ということだろう。そして別れ際の最後の言葉は、ただひとこと、
「壮健に」
であった。
まことに、絵になる老外科医であった。
2011.7.14
|
|
「ゴッドハンド」
|
テレビのある種の医療番組の中で,名医とやらの仕事ぶりを紹介するものがある。そういうところで麻酔科医が決して取り上げられることがないのは、まあいい。問題は,そうした番組で一部の外科医が「ゴッドハンド」などと持ち上げられることである。そのような、視聴者の心をくすぐる番組を流すことが、日本の医療に対していかに迷惑なことであるか,テレビ局はわかっているのだろうか。
そういう番組を見ると,普通の人たちは,自分ならあんなふうな神の手を持つ外科医に手術をしてもらいたいと思うだろう。それならば成功まちがいなしと思うだろう。しかし、手術というのは外科医の器用さだけで決まる,そんな単純なものではないのである。
まず、本当の手術というものを一般の人たちに理解していただきたいと思う。本当の手術というのは,標準的な医療を間違いなく実践することに他ならない。今や多くの手術は疾患ごとに術式がほぼ決まっており,天才でなくてはできない手術などというものはほとんどない。そういった手術を成功させるのは,術前術中術後(周術期)の患者管理に関わるすべてのスタッフの熱意と努力である。外科医はもっとも重要な要素ではあるが、あくまでもそのチームの一員にすぎない。もしもあなたが手術を受けなくてはならなくなったとしたら,周術期チームがしっかり機能している病院を選ぶべきである。(もっともそれをどうやって知るかは難しい問題だ。)
手術をチーム医療として考えるならば、ドラマなんかにありがちな、手術はうまいが独善的で周囲ともめごとばかり起こす外科医には、所詮よい手術はできない。よい外科医に必要なのは、手術全体を見通す構想力、さまざまなトラブルを予想し対策を練る力,その予想を越える事態が起こっても落ち着いて次の手を打てる怜悧さと柔軟性、周囲のスタッフの力を引き出せる協調力、などなど、天才のイメージとはちょっと違う地味な資質であろう。「ゴッドハンド」などと、外科医の力を手先の器用さのみに矮小化するような言葉自体が間違いなのである。
そもそも、まともな外科医が,自分のことを「ゴッドハンド」と持ち上げるのが分かっているテレビ番組に平気な顔で出られるわけがない。手術に絶対の成功はないことを知るものならば、自分の技術を神格化されることには耐えられないだろう。
テレビでは,たいしたことのない普通の手術を,この医師でなくてはできない手術だったかのように作って見せているのである。「ゴッドハンド」という幻想を演出するテレビ番組のウソを、世間のみなさんにどうか知っていただきたいと願うばかりである。
2011.7.10
|
|
留学生たち
|
ちょっと前にエジプト人留学生について書いたが,京大の麻酔科や薬理学教室は他にもいろんな国の留学生を受け入れていた。
タイからきた女性麻酔科医のBさんは、微笑みの国という母国の形容詞にぴったりの、感じのよい笑顔を絶やさない人だった。その微笑みの国で、後年、赤だの黄色だののグループが果てしない抗争を続けることになるとは思いもよらなかった。
中国から来たCさんは、とてもゆったりとした温厚な人だったが,研究室の引越しの時に突然頑張り始めた。新しい研究室の自分の机の周りにいろいろな所から集めたサイドテーブルをくっつけ、あれよあれという間に広大な領土を築きあげてしまったのである。これが中国三千年の実力かと刮目したものであるが,助教授の先生に怒られ,C王国は一夜にして崩壊した。
韓国から来たKさんは、すばらしく頭の切れる人だったが,同時にまた、会う人誰にも信頼感を与えてしまう紳士的な人だった。唯一の欠点は,奥さんがたまに来日したその次の日に,研究室をにんにく臭くすることくらいだった。本人は最後まで気づいていないだろうけど。
なかには困った留学生もいた。V君は研究する能力がどうこういう以前に、やる気というものをまったく持ち合わせていなかった。それなのに、学位を取らなければ国に帰れないから何とかしてほしいと言う。仕方なく論文を作ってやり、学位の申請、審査会の準備、すべてを私が代行してやらなくてはならなかった。その間、彼は勝手に心臓外科に出入りしはじめ、麻酔科にはよりつかなくなった。そして、学位をとるとさっさと帰国していった。国際問題になると困るからその人の国籍は明かせないが,あれ以来私はなぜか、生春巻きとかフォーとかいった料理を食べられなくなってしまった。
ま、いろいろあったが、英語に関しては彼らに感謝しなくてはならない。彼らの英語はたいていひどくいい加減だった。文法も発音もめちゃくちゃだったが、そのおかげでこちらもそれ以上にめちゃくちゃな自分の英語を恥じる必要がなく、自分の思っていることは何とか相手に伝えられるくらいにはなれた。とくにV君には、英語で相手をののしるという貴重な経験をさせてもらった。
そうやって身につけた英語は海外旅行で役に立った。ホテルの部屋が気に入らないから替えさせる、ホテルのランドリーサービスに出してゆくえ不明になったシャツを取り返すなど、妻のむずかしい要求を曲がりなりにこなすことができるようになったのは、ひとえに彼ら留学生のおかげである。
2011.4.30
|
|
敬語
|
先日、夜10時ごろ、緊急手術のため病院から呼び出され,出勤することになった。今度小学校6年生になった娘が、
「目上の人に、頑張ってとか、お疲れさま、とか言うたらあかんのやてね。」
という。塾で敬語を勉強しているらしい。
「どう言うたらええんやったっけ。ええと、ええと、そうや」
思い出した娘は、軽く手を床についてこう言った。
「お疲れの出ませんよう」
目上の人を励ますときのために、こんなまわりくどいほど奥ゆかしい,優雅な言葉があったとは知らなかった。誰も聞いたことも言ったこともない、言わば死語が、受験国語ではまるで博物館のように適温適湿で保存されているわけである。お受験も、無意味なことの詰め込みとばかりは言えないと思った。
今、職場でいろんな人に言って回っている。「なあ、目上の人を励ますときの正しい日本語知ってるか。小学生でも知ってるで」
2011.4.10
|
|
冥福
|
さきのニュージーランド地震で亡くなった人の中に、前の病院の手術室で一緒に働いていた看護師さんがいる。たいへん明るくかつ有能な看護師であった。この2つを兼ね備える人はなかなかいない。どんなに怖い外科医をも笑いながら叱り飛ばせる看護師は、この人くらいであったろう。彼女を知る人たちと同様、私も、彼女がもう亡くなっているとはどうしても実感できない。まだどこかで笑いながら仕事しているような気がして仕方がないのである。
人は2度死ぬという話があって、肉体的に死ぬのが第一の死、死者を知る人たちからその記憶が消えていくのが第二の死だということだそうだ。その考え方でいくと、彼女はまだ、われわれの中で生き生きと生きていると言えるだろう。
よく、亡くなった方の「ご冥福を祈る」と言うが,その意味を私はよく知らずにいた。ごく最近,たまたま気になって辞書で調べたところ,冥福とは死後の幸福のことだという。広辞苑にもそれ以上の説明は何もない。死んだ人に幸福や不幸があるのか。少し驚いたのだが、私はいい言葉だと思う。
亡くなった本人が幸せを感じているかどうかは、もう誰にも分からないが、遺された人たちの中でまだ生きているその人が幸せそうにしていられるなら、それが死者の幸福ということではないだろうか。だから冥福を祈るとは、亡くなった方とのよい思い出を大事にするということに他ならないように思う。
ニュージーランドと東日本の大震災で亡くなられた方々のご冥福を祈りたい。
2011.4.7
|
|
ムーサさんの思い出
|
エジプトで騒乱が起こっている。エジプトといえばピラミッドしか思いつかない日本人は多いだろうが、私は違う。もう一つ思いつく。ムーサさんというエジプト人である。
大学病院に勤めていたとき、エジプトからムーサさんという留学生が麻酔科にきた。来る前から、彼を日本に受け入れるためのいろんな手続きをEメールで依頼され、あつかましい人だなあと思っていたが、実際に来てみるとこれ以上ないくらい、柔和で上品な人だった。半年の滞在中研究を指導し、論文を一つ一緒に作った。
イスラム教徒と接するのは初めてで、面食らうこともあった。夕方決まった時間には実験を中断し、床に布を敷いてお祈りをしなければならない。彼は麻酔科医であるが、手術中にお祈りの時間が来たらどうするのだろうかと思った。これは最後まで聞きそびれた。食べ物の制限も非常に厳しい。一度ムーサさんをうちに招いて夕食をもてなすことになったが、何を出したらいいかでたいへん困った。
イスラム教徒の食事に豚がだめなのはよく知られている通りである。では牛や鳥なら良さそうなものだが、所定の儀式で命を奪ったものでないと食べられないという。寿司もだめである。イスラム教徒は酒も禁じられており、酒から作られる酢も口にできないのだそうだ。ちょっとくらいよさそうなものであるが、ムーサさんのようないい人を堕落の道にひきずりこむわけにも行かず、どうしたらいいのと怒る妻とイスラムの板ばさみになった私は窮地に追い込まれた。結局、魚と野菜で沖すきを作って食べてもらい、ことなきをえた。日本で厳格なイスラム教徒をもてなす場合は沖すきに限るという私の苦しい結論を、どうか他の人も参考にしていただきたいものである。
しかし、イスラム教のすばらしい面もたくさん教えてもらった。
私の同僚にとても仕事熱心な人がいて、休日でもかならず出てきて何か仕事をしている。ムーサさんはいつもそのことを心配して、「イスラムの教えでは、休日は家族のためにある、とされている。彼は働きすぎではないか。」といっていた。本人もエジプトに残した奥さんと子供たちをどれだけ大切にしているか、ことばのはしばしに感じられたのである。イスラム教というと男性優位で、女性はただ従うのみというイメージが強かったが、そうでもないと初めて知った。ちなみに、一夫多妻についておそるおそる聞いてみると、4人までは妻をもつことはできるが、普通そんなことはしない。一人で充分だという。(私も別の意味で同意見だ、いや一人でも充分過ぎるかもしれない)
ムーサさんが帰国するとき、日本語版コーランをくれた。ただし、この本の上に何かを乗せるようなことは絶対にしないようにと釘をさされた。私にとってはありがたいのかありがたくないのかわからないおみやげであった。コーランは本棚の一番上に置いて、まだ一度も開いていないが、ムーサさんからはその後もときどきメールが来た。改宗の決心はついたかと。
ムーサさんはもちろん、今回の国民の蜂起を支持しているようだ。エジプトの人たちにこころから声援を送りたい。
2011.2.16
|
|
マイナー比べ
|
世の中にはマイナー指向、反メジャー、脇道好き、そういうジャンルの人たちがいる。もちろん私も、その一人である。大学は関西、クラブは卓球、プロ野球はカープ、ビデオはベータ、トドの詰まりは職業が麻酔科医である。
蛇の道は蛇というが(その意味はよくわからないが)、麻酔科に入って見ると似たような人がたくさんいることに気がついた。なかでも1年上のS先生とは、自分のマイナーぶりを自慢し合い、競い合う仲になっている。
しかし弁の立つS先生とマイナー度を競っても、勝つのはむずかしい。どちらも中国地方出身だが、こちらは広島あちらが鳥取であることを利用して、「さすが、高等裁判所のある県は違いますよね。やっぱり広島県人はメジャー指向ですよね。」と攻撃してくる。
さらにS先生は自分がこだわりの強いコンピューターの話を持ち出して来て、「そんなこと言って Windows 使ってるんだから、ほんとは先生はメジャー好きなんでしょ」などとたたみかけてくる。彼は20年来の Mac 派なのだ。
しかし最近は風向きが変わってきた。Mac を作ってる Apple 社が iPhone とか何とかですっかりメジャーになってしまったのである。一方私は、Windows に別れを告げて Ubuntu という、Linux の一種を使うようになった。その筋では有名な、Windows よりはるかによくできたOSであるが、パソコンにおけるシェアは1%あるかないかである。先日会ったときこのことを指摘すると、弱気になっていたS先生、めずらしく反論してこなかった。
これで、どちらが真の弱者かということに決着がついたようである。あとは Ubuntu がメジャーになりすぎないよう祈ることにしよう。
2010.12.25
|
|
悲観と楽観
|
研修医に麻酔を教えていて思うのは、麻酔科医というのはつねに最悪の事態を想定していなくてはならないということだ。今一番起こってほしくないことは何か、ということをいつも考えている。
たとえば手術が終わって手術台からベッドに患者さんを移すとき、患者さんが急にあばれて転落しないか、麻酔が充分覚めていなくて呼吸止まったりしないか、ナースが渡してくれた酸素マスク、ほんとに酸素が出ているのか、麻酔科医はそんなことを心配しているのだ。スタッフが一番ほっとしがちな瞬間だけに、よけい気をつける必要がある。心配するのが仕事みたいなものだ。
こうしてみると、麻酔科医には悲観主義者が向いているようにも思えてくる。ものごとのネガティブな面に目が向いてしまう彼らの性格は麻酔科医にぴったりなのではあるまいか。しかし、私に言わせるとそれは間違いだ。悲観主義者ほど麻酔科に向かない人はないというのが私の持論である。
もともと麻酔というのは、患者さんの病気にいいことは何もしない。患者さんのからだに悪いことをしないのが仕事という、それ自体がネガティブな面を持っている。ネガティブ思考の人がそういう仕事をすると、とても持たないんじゃないだろうか。
悲観麻酔科医は、今日麻酔をかけた患者さんが今頃病棟で急変しているのではないかとか、明日麻酔をかける患者さんが心臓が悪いので何か起こるんじゃないかとか、心配しはじめるときりがなくなる恐れがある。それでは心の休まる暇がない。麻酔のために不幸な生活に陥らざるをえない。完璧な麻酔科医であろうとするあまり麻酔が嫌いになるはずだ。そうやって麻酔科を辞めざるをえなくなった人を、私は見たことがある。
麻酔科には楽観主義者あるいはちょっとユルい人の方が向いているし、実際、そういう人の方が多いように思う。心配だらけの麻酔科稼業の中に、自分だけの楽しみをこっそり見つけられる人のほうがいい。麻酔科医が幸せに仕事ができるということが、患者さんとっても幸せだと思う。ただし、小さな悲観主義者を心の中に持てるだけの知性は必要だ。
2010.12.13
|
|
「地球にやさしい」(2)
|
最近図書館で偶然手にした「人類が消えた世界」という本は面白かった。これは、なんらかの原因で人類だけがある日消滅したとしたら、残された地球はどうなるかということを、科学的に予想したものである。それによると、コンクリートで固められたニューヨークの大都会もほどなく植物に侵食され、野生動物(しかいなくなるが)が我が物顔で歩き回るようになるという。この本は他にも、家畜の運命、プラスチックのゆくえ、原子力発電所はどうなるか、などをしつこく描写している。
とにかくこの本の面白さは、人類滅亡と地球滅亡とは全然違うと確認できること。人類などいなくなっても、地球はちっとも困らない。むしろ、人類などいないほうがよほど「地球にやさしい」のではあるまいかと思えてしまう。
おどろいたことに、まさに「地球のために」人類はみずから身を引きましょうという主張をする団体があるそうで、自発的に全世界で子供を作るのをやめませんかと呼びかけているのである。いわば、種の自殺である。なんともすごい発想だが、やはり絵空事としか言いようがない。そんなことができるなら、人類全員が息を止めて自殺するほうがまだ簡単だろう。それに、彼らはそのような穏健でそれゆえに実現不可能な方法を提唱しているが、その思想が核とかウイルスなどありえなくもない手段を使った過激な人類絶滅計画などと結びつかなければよいが、と心配である。
このように「地球にやさしい」ことをとことんつきつめてしまうと、恐ろしいことになるから要注意である。普通に「人間にやさしく」したほうがよさそうだ。
2010.11.28
|
|
「地球にやさしい」
|
地球温暖化が問題になりはじめて以来、商品の宣伝などで「地球にやさしい」という言葉が合言葉のように唱えられるようになった。化石燃料を使わない、二酸化炭素を出さないということが地球にやさしいのだという。しかし、それはおかしいだろう。
地球と生命は、これまでの50億年でもっとすさまじい気候を生きのびている。数十億年前には地球は最低2回は全球凍結(スノーボールアースといって、太陽熱をほとんど反射してしまい、氷りっぱなしになる)していると言われるし、恐竜のいた時代は二酸化炭素が現在より10倍も濃く、気温は10℃以上高かったらしい。それでも生命は途絶えることはなかったのである。
今問題とされている程度の温暖化は、地球にとっては37度程度の微熱ですらないと思われる。放っておいてもいずれは氷河期がくるし、逆に地球上に氷のない激暑時代もくるかもしれない。人類は絶滅するだろうが、ゴキブリだか細菌だかがなんらかの形で生命をつないで行くに違いない。地球にとって、生命を宿すということに多少の意義はあるだろうが、それが人間でなくてはならない理由はない。人間ごときが多少の温度変化を防いだくらいで、「地球にやさしく」していますなどと言われるのは、地球にとっては片腹痛いことであろう。
温暖化を防ぐのは地球のためではない。人類が少しでも長く生き延びるためである。どうせ人類はほとんど自分のことしか考えていないのだから、それを正直に認めたらどうだろう。生き延びることは、それはそれで、生きものとしてのもっとも重要な使命であるから、そんなに恥ずかしがることではないはずだ。
2010.11.28
|
|
外科医列伝(3)
|
外科医列伝(1)で実例を挙げたように、すぐれた外科医というのは手術が速いものである。一般の方は、じっくりていねいに進めるのがよい手術と思われるかもしれないが、そうではない。相手はいきものである。芸術品をこしらえているのではない。さかな一枚おろすのに1時間かかる板前さんを、「ていねいですね」とほめる人がいるだろうか。
よい手術は速い。遅いけどよい手術だった、などということはありえない、そう思っていた。その肝臓外科医に出会うまでは。
その先生はとにかく遅い。たしかに肝臓の大手術を手がけるのだから長くなるのは仕方ないが、毎回のように朝から夜10時、11時くらいまでやられてはちょっとぐったりである。ある麻酔科医は彼の手術を、「世界有数の遅さ」と評していた。
しかし、何例か手術につきあうと分かるが、彼の手術は術中も術後も、驚くほどトラブルが少ない。出血を抑えるために時間と労力を使うのを、まったくためらわないからである。遅いといっても、手術の方針が定まらなくて遅いのではなく、ぶれない遅さである。たまたま肝臓の手術というジャンルが、彼のまじめで執念深いキャラクターに適合したのであろう。
私は、自分が肝臓癌の手術を受けるならその先生の手術を受けたいと思った。同業の方なら分かると思うが、これは麻酔科医が外科医に贈る、最大級の賛辞である。
2010.11.23
|
|
手術室の音楽
|
昔は、手術室に音楽を流すなどはもってのほかのご法度だった。その理由はというと、仕事する者の気が散るからだとか、心電図の音が聞こえなくなるからだとか言われていたが、本当の理由は、音楽を聞きながら仕事するのは不謹慎だという古い倫理感が手術室を支配していたからだろう。
現在ではたいていの病院で手術室に音楽を流していると思う。患者さんの緊張をほぐす効果はもちろん大きいし、スタッフにとっても気分をリフレッシュさせ、停滞しがちな仕事の流れをよくするための絶好の道具である。
有線があれば飽きが来なくて理想的だが、そんな恵まれた環境で仕事をしたことがない。たいがい、スタッフが持ち寄ったCDを流している。問題はどんな音楽を流すかである。
患者さんに麻酔がかかる前は、もし患者さんのご希望があればその曲を流すし、ご希望がなければ、あたりさわりのなさそうな静かな曲を流す。しかし、あたりさわりがなさそうな曲の中に、意外に縁起の悪い曲が含まれているから要注意だ。
平井ケンの「大きな古時計」。これは時計が壊れる話かと思ってよく聞けば、おじいさんの寿命が尽きる話である。
チャイコフスキーの「白鳥の湖」。バレリーナ扮する白鳥が弱って死んでいく。
ざわわ、ざわわ、の「さとうきび畑のうた」。鉄の雨の中でお父さんが死んだ。
お、これは軽快な行進曲、と思ったらベルリオーズの交響曲第4楽章「死刑台への行進」
こういう曲が麻酔導入時に流れてしまうと、患者さんが気にしなければよいが、とひやひやする。取り越し苦労だとは分かっているのだが。
音楽で気が散るというのはこういうことか。
2010.11.14
|
|
外科医列伝(2)
|
ある病院の外科の先生、とてもいい人で、手術がおわって麻酔から目を覚ましたばかりの患者さんに向かってかならず声をかけるのである。
「◯◯さん、おわりましたよ。手術はね、大成功」
しかも満面の笑みを浮かべてである。一刻もはやく安心させてあげたいという気持ちなのであろう。
一度大成功などと言ってしまうと、あとで術後合併症などがおきたときに、説明がむずかしくなる。「あのとき大成功って言ったじゃないですか」と言われると困るのである。だからふつうは、
「今のところは予定通り、順調にいっています」
と、すこし低めの声で言うものである。あんなふうに早々に成功を宣言する外科医を、わたしは初めて見た。
しかし、手術がいつもうまく行くとは限らない。そういうときはどう声をかけるのだろうと、私はひそかに心配していた。やがてその時が来た。癌が進行していて、取りきれなかったのだ。するとその先生、目を覚ました患者さんに向かっていつも以上のえびす顔で、
「手術大成功ですよ!」
と声をかけた。
すごい外科医もいたものである。
2010.10.22
|
|
なぜ疑問文形式のタイトルが横行するのか?
|
私は書店でぶらぶらするのが好きだが、新書コーナーだけは要注意だ。どうも怪しいタイトルが多いのである。とくに疑問文形式のタイトルは不愉快である。
「なぜ日本人は劣化したのか」
「出世する男はなぜセッ●スがうまいのか」
などというのを見ると、いい加減にしろと言いたくなる。「日本人が劣化している」、「出世する男はセッ●スがうまい」などという聞いたこともないような、しかも聞き捨てならぬ命題を突きつけておいて、その真偽を通り越してなぜそうなのか、とたたみかけてくる。つまりその命題が真であることが自明であるかのような錯覚を起こそうとしているのである。気の弱い人がそのタイトルを見て、
「え、日本人は劣化していたのか。知らなかった。どういうことだ」
と慌て、その勢いで本を買う、という線を狙っているのだろう。人をバカにしたやり口である。そんな本に中身などあるわけがない。
本を買うか買わないかは別にして、普通の日本人や男であれば、そういうタイトルをみて不快、不安を覚えるだろう。人を不愉快にしてまで中身のない本を売りたいか。
論文や学会の演題にも、疑問文のタイトルがある。さすがに「なぜ」で始まるものはないが、「揮発性麻酔薬は術中心筋虚血を減らせるか」などといった疑問文のものはちらほらある。「揮発性麻酔薬は術中心筋虚血を減らす」と書けばよさそうなものだが、そう書くと、読者は「ああそうですか」と一瞬で分かった気になってしまって中を読まない恐れがある。疑問文だと、答えを知りたくなって本文を読む気になるはずだという狙いだろう。
それでも本文の中にちゃんと答えが用意されていれば、ある程度納得はできる。しかしなかには、答えがどこにも見当たらない論文がある。この場合は、その疑問文の答えが筆者にもわかりませんでした、とでもいいたいのか。もしそうだったら、読者の期待を裏切ってごめんなさい、くらいは書いてほしい。
学術の世界でもやはり、疑問文のタイトルには何か底意が感じられて、すこし品が落ちる気がする。
本でも論文でも、中身に自信がないなら人目につかないようなタイトルをつけ、人目につかない場所に置いておいてもらったほうが、世の中のためだ。私のこの雑文のように。
2010.10.22
|
|
外科医列伝(1)
|
麻酔科医となると、しかも私のように転勤の多い麻酔科医となると、いろんな外科医とお手合わせしている。彼らの悪口のタネにはこと欠かないが、これはすごい、と思わずうならずにはいられない外科医もいる。おいおい紹介し、ほめたたえたいと思う。
ある整形外科の先生、とにかくおしゃべりで、手術中ずっとマシンガンのようにしゃべっている。まるで、声を出さずに息を吐くのがもったいないとでも思っているかのようだった。そういう口数の多い外科医は手術の方は今いち、という場合が多いが、この先生は手の手術というもっとも繊細な分野を専門としながら、手術がうまくてしかも速い。神経縫合など、むずかしい手術になるほど予定時間より早く終わってしまう。これまでの麻酔科医としての私の常識を破る外科医であった。
本人には聞けないことを、同僚の整形外科医に聞いて見た。
「あれだけしゃべってて手術が速いんですから、黙ってやったらどれだけ速いんでしょうね。」
その答えは、
「さあ、黙って手術してるところを見たことありませんからねえ。が、たぶん、黙ってたらストレスで手術が遅くなるでしょうね。」
すごい外科医もいたものである。
2010.10.16
|
|
三たび、「お疲れさまです」について
|
つまらないことにこだわるのはみっともないとは思うが、気になるのだからしかたがない。
院内ですれ違う人に、真っ昼間から「お疲れさまです」と妙な挨拶をされることに対し、私も「こんにちは」で切り返すことでやや心の落ち着きをとりもどした。これはすでに書いたとおりである。ところが、敵もさる者、次第に電話の世界に入り込んできた。これにはお手上げである。
PHSが鳴るので取ってみると、「総務でーす、お疲れさまでーす。今よろしいでしょうか。5時から会議がありますので出席お願いしまーす。」などと来る。
廊下を歩いているときならば、変な挨拶をされてもじっとこらえる心理的余裕はある。しかし電話というのは仕事の真っ最中に飛び込んでくるのである。緊急手術の申し込みかも知れないから、作業中でも手を止めて取るのである。そこに「お疲れさまでーす」とやられる。これは必要ないだろう。その3秒を返せと言いたい。
ついでにいうと、「お忙しいところすみません。」もいらない。ほんとにそう思うなら、あえてその一言を省略して欲しい。
こういうとき、私としては電波に乗せて「抗議の念」を送るしかないのであるが、それで不機嫌なことは通じてもその理由まで伝わるはずもなく、単に無愛想なおっさんだと思われるのが関の山だ。
どうやったらわかってもらえるだろう。
2010.10.12
|
|
このホームページのゆくえ
|
なんという理由もなく、このホームページの更新を3ヶ月休んでしまった。どなたか何かの間違いで私の文を読んでくださっている方がいたとして、この空白を心配してメールで励ましてくださったりするのだろうかと、別に期待はしていないものの漠然と考えていたのであるが、これまでと同じようにただの1通も読者からのメールをいただくような光栄には恵まれなかった。これはもう、このホームページには検索ロボット以外の定期的読者はいないと考えるほうが自然であろう。ロボット君だってファンレターくらい送れそうなものだが、彼らには私の文章のよさはわからないものと見える。
さてこのホームページの目的の一つに、これを見た若い人が感激して麻酔科を志し、私の部下となって私を楽にしてくれるという野望があったのであるが、それもはかない夢だったようだ。このホームページを見たよと誰かに言われたこともないし、ましてそのために私の弟子になりたいなどと志願する人は、この1年半、皆無であった。
そういうわけで、更新を再開するつもりになったものの、サイトの運営方針は変えることにしようと思う。
まず、新人獲得という不純な動機は棄てる。このため勤務先の公開も不要になる。これまでは私の素性もほぼ白状していたようなものだが、これからは誰が書いたか分からなくなるので、思いきったことが書ける。つまり、いままでいい加減などうでもよいことばかり書いてきたが、もっとどうでもよいことを書くことができる。
また、麻酔と縁のない人たちにも麻酔科医の仕事について理解してもらえたら、という目的もあったが、これもあまり考えないことにする。どうせ誰も読んでいないのだからもう少し自由に書いてみたい。
これまでは、世のため、麻酔科のため、自分のため、という意識が少しはあり、それに沿うようホームページをデザインしたつもりだったのだが、前の二つが消えてただ自分のため、となると、それは「ブログ」になってしまう。私はこれまで、「麻酔科医のひとりごと」とか「麻酔科医のつぶやき」とかいうブログのタイトルを見て、人に見せるためのものを作っておいて「ひとりごと」や「つぶやき」はないだろう、と思ってきたくちであるが、これからは人のことは言えなくなる。
自分が見ておもしろいものが書ければ、それでいい。
2010.10.10
|
|
看護師の名前
|
新しい病院に転勤したら、まず手術室の看護師の名前を覚えることを最優先する麻酔科医がいる。新しい職場に馴染み、仕事を円滑に進めるためには、看護師さんを名前で呼ぶことがもっとも重要なポイントなのだそうだ。名簿かなにかを手に入れ、一晩で覚えるのだというから、とても真似できない。
私も転勤を繰り返してきた人間だが、あえてそうした努力はしないことにしている。たまたまその日印象に残った人がいればその名前を覚えていき、名前で呼んでも不自然でないくらいに慣れたころ、名前で呼びはじめる。自分が名前を覚えた順番を思い返してみると、けっして美人度とか仕事の能力とかとは関係なく、あとから考えても理由がわからないところが、われながらおもしろい。そういうところも、転勤の楽しみである。
以前いた巨大病院では、看護師が手術室に40人、ICUに50人いた。私の流儀だと、毎日仕事する手術室でも全部覚えるのに1年かかるし、当直したり患者さんをおくったりするだけのICUだと、なかなか半分も覚えられない。困ったことに1年かかってうろ覚えに覚えた矢先、看護師さんたちは勤務交替である程度入れ替わってしまうから、この記憶率はこれ以上はあがらない。もっと困るのは、彼女らがしばしば結婚して名前が変わってしまうことだ。新しい名前を覚える前に、旧姓を忘れてしまう。いまさら名前を忘れたとは言えないから、知っているふりをするしかない。
大きな病院はなかなか大変である。
2010.07.12
|
|
麻酔科医失格
|
わたしのようなだらしない麻酔科医にも、麻酔科医としてこうありたいとう願望はある。心身ともにタフで、物事に動じず、むしろピンチに陥ったときにこそ本当の力を発揮する、そんな理想像である。日々の仕事の中でこうした理想像が多少のダメージを受けることはしばしばあるが、それは仕事の中で取り返せることが多い。しかし、家庭の中でそうした理想像に反する失敗を犯したほうが、回復への道のりはむしろ厳しい。
最初の子供が生まれる時のこと、産院の病室で妻の陣痛が規則正しく訪れるようになってから、戦いは夜を迎えた。苦しむ妻に向かって、わたしはこう宣言した。
「おれを誰だと思っている。麻酔科医だぞ。徹夜のひとつやふたつはいつものことだ。陣痛がくればいつでも背中をさすったる」
しかし、その2時間後には私はソファーの上で夢を見ていた。陣痛に苦しむ妻の姿がときどき夢と交錯したが、それは夢だということにして、ふたたび本物の夢の世界に帰っていった。麻酔科医たるもの眠気ごときには負けぬ、という願望はくずれさった。
その子供が7才の時のこと、真冬におとずれた遊園地で、子供とカヌーに乗った。ところが子供のこぎ方があまりにへたくそだったので、係員に禁じられていたにもかかわらず、私はおもわずカヌーの上で立ち上がった。子供にこぎ方を教えなくてはいかんと思ったのである。カヌーはあっという間に転覆し、2人とも真冬のプールに投げ出された。子供は、がくがく震えながら「あうっ、あうっ、お父ちゃん、なんちゅうことを」と言ったまま絶句した。麻酔科医たるもの、いかなる事態にあっても冷静沈着であるという願望もくずれさった。
これらの事件により失墜した麻酔科医像を、自分自身の中で取り戻すのに多少の時間はかかったのだが、家族の中では地に落ちたまま回復の見込みは立っていない。
2010.07.09
|
|
麻酔科の地位
|
一般の人にとって、麻酔科医というのは馴染みが薄い存在だ。医者といっても、自分が運悪く手術を受けるハメにでもならない限り、縁のない人間だと思われているだろう。しかし、病院にとっては麻酔科は案外重要だ。麻酔科は多くの場合中央手術室と集中治療室の責任者、あるいは実質上の管理者となっている。中央管理部門という、病院の心臓部を握っているとも言えるのである。
もし麻酔科部長が権力欲に取り付かれたよこしまな人間だったり、とんでもなく無能力なぼんくらだったりしたらどうなるか。すべての科の手術の円滑で安全な遂行が妨げられ、重症患者の治療がとどこおり、そのため各病棟の重症患者管理が破綻し、病院は大混乱に陥るだろう。麻酔科部長の影響力の強さは、他の科の比ではない。私も、病院が自分なんかを信用して心臓部を預けてしまって大丈夫なのだろうかと心配になるくらいだ。
しかし、だからといって麻酔科が王様のように君臨するというのとは、またちょっと違う。そうしたがる麻酔科医もいるかもしれないが、麻酔科は他科の診療を支えるという立場にある以上、病院が麻酔科医に求めるのは王様ではなくて公平かつ無私という資質であろう。(実際にそうであるとは限らないが。)そういう面では麻酔科は水や空気に似ている。実際、たいがいの病院で、会議の席も電話番号表も、麻酔科は最後尾のあたりである。放射線科や病理といった他の中央部門も似たようなポジションだ。
そういう扱いに不満をもつ人もいるようだが、私はまあ、それでいいじゃないかと思っている。よい酒は水の如しである。あるいは金持ちけんかせず、とも言える。ただ、医師のなかには麻酔科を、栓をひねれば水のじゃんじゃん出る水道と勘違いしている人もいる。そういうのはご勘弁である。限りある資源、大切に使ってもらいたいものだ。
2010.06.26
|
|
病院の怪談
|
また怪しい話で恐縮である。
テレビのオカルト番組などで、古戦場とか交通事故現場とかに霊が出るという話がよく出てくる。しかしながら、現代にあって人が亡くなる数ということなら、病院という場所の右に出るものはちょっとないのではないか。もし死者の霊魂のようなものが亡くなったその場所に漂うのだとすれば、病院のあらゆる場所で多数の霊魂がその持ち場を守っていることになる。ところが私にはそれが見えたことも感じられたこともない。スタッフや自分が異動するときは仕事場で記念写真を撮るのだが、何か妙なものを写してしまったという経験もない。
病院の怪談というのは聞いたことはある。当直室の前で人が行ったり来たりする足音がして、数えてみるとちょうど13歩で往復していたとか、まあそういうたぐいの話である。どうもそういうのは、霊感の強い人でないと感じられないものらしい。私は感度不足というわけだろう。
亡霊が見えてしまうくらいなら我慢すればよさそうだが、一部の怪談にあるように、死者が病人を自分の世界に引っ張り込んだりするようだと困る。医師として見逃すわけにはいかない。しかし、身の回りでそんな話は聞かないのである。
だいたい、死者が生者をねたんだり、自分のところにひきずりこんだりするものだろうか。ひきずりこまれた被害者は、恨むとすればその死者を恨むはずで、そうなると幽界で霊魂同士が戦うのだろうか。それはちょっとつじつまが合わなさすぎないか。
死者はもう少しやさしいものだという気がする。
2010.06.12
|
|
知り合いの知り合い
|
たまに知り合いなどから、「今度自分の親戚(とか知り合いとか)がお宅で手術受けるので、よろしく」と頼まれることがある。これはなかなか難しい要求である。何をしてほしいのかがよくわからない。特別扱いしてほしい、ということなのか。
一応、どんな患者さんに対しても仕事はきちんとしているつもりである。たしかに一昔前までは、麻酔科医が術後鎮痛にはあまり関与していなかったので、その辺でサービスすることはできたかもしれない。しかし、現在はそれも当たり前になっているので、知り合いの頼みだからと言って、特別なことをしたくても別段することがないのである。無理に特別なことをしようとすると、害を加えてしまう可能性もある。
私は、「わかりました、しっかりやります」と答え、1分後には忘れることにしている。これなら、言ってきた人も、「プレッシャーをかけておいた」と患者さんを安心させてあげられるだろう。
麻酔科医に知り合いのいない方、ご安心ください。医療の中でも特に手術室は、医療者がその患者さんのためだけに自分たちの技術と時間を注ぎ込む場である。手抜きはない。患者さん全員、特別扱いである。
2010.04.29
|
|
イカと蛾
|
精神科医でもある作家の加賀乙彦氏に「頭医者ことはじめ」という自伝的小説がある。この中で、ある先輩医師の言葉が紹介されていて面白かった。
それによると、人間というのはイカ型と蛾型に分けられるのだそうだ。普段はこの2種の区別はつかないが、ピンチに陥ったときにその本性が現れる。イカ型はボーッとなって動けなくなり、蛾型はばたばたと大暴れしてめちゃめちゃにしてしまうのだ。どっちもどっちだが、麻酔科医にもこれがある程度当てはまるように思う。
手術中の平穏無事を誰よりも願っている善良な麻酔科医にも、緊急事態はふりかかってくる。血圧が突然低下した、人工呼吸ができなくなった、原因不明の低酸素状態になった、気管内にチューブを入れる作業がどうしてもうまくいかない、などなど、このままでは患者さんの命があやういという事態である。このような、麻酔科医の力量を試される場面にあっても、イカ型の行動をとってしまう人と、蛾型の行動をとってしまう人とに分かれると思うのである。
イカ型麻酔科医はまず立ち止まり、動揺を悟られぬよう平静を装いつつ、そこから脱出する方法を探る。手数が少ないため、一発で解決できればさすがだが、うまくいかないと悪くなるのを指をくわえて見ているだけと思われかねない。一方、蛾型麻酔科医はいきなり走り始める。いろんな思いつきをつぎつぎと口に出し、鱗粉をまきちらしながら周囲を巻き込んでいく。その収拾策のどれか一つがヒットすると事態は突然収束に向かうが、うまくいかないと現場を大混乱に陥れるだけになる可能性がある。ま、すべての道はローマに通じると言われるように、どっちのアプローチにしても、要は問題が解決すればそれでよいのである。
私は若いときから典型的なイカ型で、蛾型の人を見るとうらやましくて仕方がなかった。何か事が起こるとどうしたって蛾型の方が主導権を握ってしまい、気がついてみると自分の担当症例なのに後からきた蛾型の人の使い走りをさせられているのである。そうやって、蛾型が手柄を持っていくのであった。
それにしても、本当にイカといういきものは、ピンチになると動けなくなるのだろうか。それが疑問だ。
2010.04.25
|
|
「お疲れさま」対策
|
院内ですれちがう職員から「お疲れさま」と声をかけられるのがストレスになっている話を以前書いた。
その後研究を重ねた結果、「お疲れさま」に対しては「こんにちは」と返事をするのがベストであるという結論に至った。一見まじめにあいさつを返しているようであるが、相手と違うことを言って違和感を倍返しにしようという作戦である。
「朝っぱらからお疲れさまなどというもんじゃない。こんにちはだろうが」という指導もかねている。
やってみると、相手と違うあいさつを返すのは意外にむずかしいが、慣れてしまえばなんでもない。むしろ快感である。
ただし、相手は何も感じないか、変なオヤジと思うか、どっちかだろう。
2010.04.04
|
|
緊張
|
患者さんが手術室に入ったら、まず血圧を測る。病棟で測った血圧より30mmHg くらい高くなっている人も多い。これはやはり、緊張のせいだろう。
私は手術を受けた経験がないので、手術直前の患者心理というのは想像するしかない。
自分のからだを他人に預けてしまうというのは、緊張の最大の要因だろう。たとえばジェットコースターに乗ってしまうと自分ではもうどうにもならないわけで、機械にからだを預けるという異常な事態に身も心も硬直せざるを得ないのだが、あれに似た緊張感ではないかと想像する。ついさっきまでなら逃げ出すこともできたのに、ここに至ってはもう遅い、という後悔の念は緊張をますます高めるだろう。「安心してくださいね」と言われてもできるわけがない。
もう一つ、自分だったら緊張するだろうなと思う要因が、自分一人のためにこれだけの人が集まっているという事実である。
ちょっとした手術でも、外科2人、看護師2人、麻酔科1人、計5人は最低必要である。もう少し大きな手術だと、それぞれ一人ずつ増えて8人になる。心臓外科の手術はもっとすごい。これだけの人たちが結集し、自分の時間をこの人のために何時間分も提供するわけである。このようなことが他にあるだろうか。
散髪、タクシー、マッサージなどは、1名のプロの時間を自分のために使ってもらうことになる。わたしにはこれだけで結構なストレスであり、なるべく利用しないようにしている。なるべくならベルトコンベアーに乗せてもらって流れ作業でさばいてほしいと思うくらいだ。まして2名以上のプロの時間を一人で消費したことがこれまでの自分の人生であっただろうか。心当たりがないのである。そんなことされたらつい、「すみません、適当でいいです」、と言ってしまいそうだ。
努力したわけでもないのに、その場の主役になってしまっている。ここにいるみんなが自分に関心を持っている。しかも自分のよい部分ではなく、悪い部分が注目されている。血圧も上がろうというものだ。
2010.04.04
|
|
手術室看護師
|
手術室の看護師というのも、一般の人にはイメージしにくい仕事ではあるまいか。
看護師さんといえば、医師と患者さんの間をとりもち、やさしく患者さんの面倒を見る人と考えられているだろう。手術室でもそれは同じだが、医師の介助という看護師のもう一つの側面がより強く求められる。外科医や麻酔科医の仕事を支えるために、物品を間違いなく揃え、手術や麻酔の介助をする。しかし、「介助」という言葉では、手術室看護師の機能は十分には言い表せない。
優秀な看護師は、事前に患者の状態や手術の内容を理解し、麻酔や手術の進行を予測し、刻々と変化する状況を的確に把握し、何が起こっても最短時間で対応してくれる。ここまでくると、手術を支配していると言ってもよい。医師はその手の上で踊っているだけだ。医師がサッカー選手だとすると、看護師は監督である。どっちがえらいかは、いうまでもない。
手術室看護師は医師の能力を評価するという点ではまったく情け容赦がない。その医師がどんなにイケメンであろうが、やさしい人であろうが、手術室では関係ないことを知っているからだ。手術を成功させるためには、外見や性格はどうであれ、腕の良い医師が必要だ。そして、医師の腕を引き出す看護師の手腕ももっと必要だ。たとえば手術中に外科医が困難にぶつかって立ち往生してしまった場合、看護師は当の外科医が助けを呼ぶ前に勝手に別の医師を呼んでしまう。誰を呼べば事態が打開できるかもよくわかっている。立ち往生した外科医のメンツなど一顧だにされない。
このように、外科医の能力を見極めることは、手術室看護師としてもっとも重要な能力であるといって良い。最初は医師や先輩に怒られつつ仕事を覚えるのに精一杯だった新人看護師たちも、だんだんこの能力に目覚めてくる。職務に忠実たらんとすれば、目覚めざるをえなくなってくる。彼女ら/彼らが外科医の悪口を言い始めると、その手厳しさに私もうろたえてしまうほどだ。私のいないところではさぞかし麻酔科医の悪口も言っているだろう。
このように怖くて頼もしい手術室看護師。仕事のパートナーとしては最強ですね。
私の問題は、帰宅してもそこに元手術室看護師がいることである。私は毎日値踏みされ、毎日評価を下げ続けている。
2010.03.21
|
|
因果律
|
世の中、原因があって結果がある。すくなくともそう思われている。逆に言えば、何かが起こったのであればかならず原因があるはずだ、ということになる。これを因果律というらしい。しかし、そんなに単純なものだろうか。
ブランコを押すと動き始める。どうしてそう思うのかというと、これまでかならずそうなったからである。ブランコを押したら向こうから10倍の力で押し返してくる、といったことは起こったためしがないのである。科学はこの「再現性」を信じるところから始まる。厳密に言うと、明日もそれが成り立つ保証は何もないが、それは言わないでおこう。
このように因果律というのは、何度やってもそうなるという前提が必要なのだが、実際の世の中はブランコのように何度でも試せるというものは少ない。私たちが日々向き合っている臨床医学はまさにブランコの対極にある。
糖尿病と狭心症と認知症を患っている80歳の老人が、転倒して大腿骨を骨折し、手術の段取りをしているうちに肺炎になり、抗生剤治療しているうちに腎不全になり、心臓の動きも悪くなって不整脈と心不全を併発したとしよう。この複雑に絡み合い、もつれ合う現象のかたまりから、因果関係の糸を拾い上げるのは簡単ではない。もちろん医師たちはそれぞれの問題点のリストを作り、その原因と思われるものに対して治療を行っていくのだが、あくまでもそれは作業仮説である。結局、なにが原因で、なにが結果だったのか、最後まで分からないことも多い。そもそもこのかたまりの中に因果関係を見出そうとすることに意味などないような気もしてくる。探すことに意味がないとすれば、それは存在していないと言い換えられるのではあるまいか。
人間の病気のような多くの因子が絡み合う複雑な現象になると、再現性は確保できなくなると、私は思う。それぞれの因子を分離できるのであれば、科学の手法で分析することは可能だろう。しかし因子同士は影響しあっているから、分離はできないのである。むりに分離すれば、間違った推論を導く恐れがある。かといって、まったく同じ条件を再現して実験を行うことも不可能だし、よく似た症例を探して参考にしようとしてもどうしてもちょっとずつ違う。再現不能である。
どの患者さんも二人といないからだで一度きりの人生を歩んでおられるのである。一回きりの現象に対して、因果律は通用しない。宇宙が誕生したことに、原因があるのか。私が私に生まれたことに、原因があるのか。どんな現象にも原因があるという考え方は間違っているのではないか。
そんなことを言っていては医学の進歩に背を向けるような態度と思われるかもしれないが、科学は万能ではないということを認める謙虚さも、医師には必要と思うがどうなんだろうか。すくなくとも、原因の究明よりも、そのご老人の残り少ない人生をどう過ごしてもらえるのかを考えるほうが大事だろう。
2010.03.04
|
|
カップ麺
|
私の昼食はカップ麺が多い。二十余年の麻酔科生活の到達点がこれである。これにはいろいろ理由がある。
1. 豪華な昼食を取るにはおこづかいが足りない。
2. 若いもんに麻酔を担当させているので、食堂には行けない。食堂にいて緊急事態その他で呼ばれてしまった場合、注文した食事をきっぱり見捨てなくてはならず、それだけの勇気を示す自信がない。
3. 短時間で食べられる。若いもんには30分の食事休憩を与えているが、自分にはそれだけの時間を与えてあげられないことが多い。
私は味にはこだわる男なので、食べるのはいわゆる定番ラーメンにほぼ限られる。サッポロ一番の「味噌ラーメン」と「塩ラーメン」、エースコックの「ワカメラーメン」である。よく飽きませんねと言われるが、さすがに毎日同じものを食べているわけではない。ちゃんとこの3種でローテーションを組んでいる。
そんなものはからだに悪いでしょう、ともよく言われる。だが、カップ麺がからだに悪いと、誰が決めたのか。自分の子供たちは休日の昼はほぼかならずカップ麺を食っており、それでもそれなりに成長している。
たぶん大丈夫だろう。
2010.03.04
|
|
ダウジング
|
麻酔科医の行う作業を物理学的側面から見ると、そのほとんどが「管に管を突っ込む」作業である。静脈にカテーテルを入れる、気管にチューブを入れる、などである。その管が目に見えるものであれば作業は比較的容易であるが、見えない管を攻めるとなると難度が急上昇する。たとえば中心静脈(深いところを走る太い静脈)、動脈あるいは脊髄腔の穿刺がそうである。
こういうものは触診したり、周囲の構造物をたよりに入れていくのであるが、それだけにやはり習得に時間がかかるものである。自分は長年の経験でなんとなくできてしまうのだが、どうしてできるのかを説明しろと言われてもできないし、その微妙なところを若い人に教えるのもむずかしい。「心眼を使え」とか、「針の気持ちになってごらん。血管にもぐりこみたくなるはずだ」とか言って、研修医を困らせるのが関の山である。なにかよい方法はないか。
地下の水道管や水脈を探すのに、ダウジングという方法があるそうである。テレビで一度だけ見たことがあるが、水道局の人がL型の針金を両手に持ち、「犬も歩けば」の要領で歩いていくと、水道管の埋まっている場所で針金が反応するのである。インターネットで調べると、これには科学的な説明はまだできておらず、そういう意味ではオカルトまがいの技術ではあるようである。
さらに調べると、反応するのは針金ではなく、持っている人の筋肉が反応しているのだとか。つまり、水道管に反応しているのは人間であり、針金はその反応を増幅する道具に過ぎない。古いところでは、諸国で井戸を掘り歩いたという空海の杖がそのダウジングロッドにあたるのだそうで、偉いのは杖ではなくて空海だというわけである。
オカルトでもなんでもいいから、これを麻酔の技術に応用できないものか。血管穿刺用の針にダウジングの機能をもたせ、目的物に反応して人間をそこに誘導するのである。麻酔科医は針と一身同体となり、邪念を捨てて、針の向かおうとするところに進んでいけばよい。上記の理論によると、それを扱う人間にもダウザーとしての能力と修行が必要とされるが、そこを省略できるなら金を払う価値がある。(払うのは病院だが)
だれかこれを読んで真に受けてしまい、製品を開発してくれたりしないだろうか。だがまず、このホームページを読んでいる人がいない現状では、望みは薄い。せいぜい空想を楽しむほか仕方がない。
2010.01.28
|
|
すいかの種
|
いわゆる盲腸、正確には虫垂炎だが、これの原因がすいかの種だとかはぶらしの毛だとか、そういう話を聞いたことがある。しかし、たくさんの虫垂切除術に立ち会ってきた私も、摘出した虫垂からすいかの種が発見されたというのは、見たことも聞いたこともない。何か根拠のある話なのか、迷信のようなものなのかわからないが、かといって本などで調べるほどの話でもない。
いつの日か、摘出虫垂を調べている外科医が、
「ついにすいかの種を発見したぞ」
と叫んで、アルキメデスのように走り出したとしたら…
いくらか胸のつかえが取れるかもしれない。
2010.01.09
|
|
励ましの言葉
|
人を励ますのはむずかしい。私のもっとも苦手な分野である。
「いま頑張れば、結果は必ずついてくるゾ」とか、「まあ、ぼちぼちやりましょか」とか、どう言い方を工夫しても、なんか相手に見透かされそうな気がして仕方がないのである。自意識過剰なのかもしれないが、その時点で既に、「励まし役」としては失格である。
考えた挙句、「ま、頑張ってください」と、月並みな言葉で済ませてしまうことが多いのである。
逆に、自分が励ましてもらってよかった思い出というのも多くはないのであるが、ひとつだけ、ひどく印象に残った言葉がある。
すでに書いた、研修医1年目の暗黒時代のこと、どうも自分は仕事がうまく覚えられないとへこんでいたら、ある人がこう声をかけてくれた。
「自分で自分を励まさへんかったら、誰が励ましてくれるん?」
その人は同期の研修医であるが、到底同僚を暖かく励ましてくれそうな感じの人ではなかったので、これには驚いた。その、ストレートでない励ましの言葉がいかにもその人らしく、要するに自分の問題は自分で解決しろと突き放しているわけだが、その底には励ましたい気持ちも感じられ、それもそやな、と気を取り直してしまったから不思議である。
これ以上は考えられない、絶妙な励まし方であった。
それ以降も、むずかしい事態に陥ったとき、この言葉を思い出しては勇気を奮い起こしているのである。
2010.01.09
|