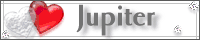

昼休み。
二年生の教室が並ぶ廊下を、頭ひとつ分背の高い男がゆっくりと歩いてゆく。
目当ての教室を見つけると、念のためドアの上に掲げてあるクラス表示を確認した。
「あ、キミ、すまないが海堂を呼んでくれるかな。3年の乾だけど」
手っ取り早く、目の前を通り過ぎて教室に入ろうとしていた生徒を捕まえ、抑揚のない声で乾が言った。
「あ、はい、……海堂、ですか…」
一瞬困ったような顔をしたその男子生徒は、小さく溜息をつきながら教室に入っていった。
程なくして出てきたその男子生徒は、頭を掻きながら「いないみたいです」と乾に告げた。
「どこに行ったか分かる?」
「あー……いえ……あんまり話したことがないんで……ちょっと……」
「…ありがとう。手間をとらせて悪かったよ」
無表情のまま礼を言ってから乾は溜息をついた。
「教室にいないとしたら、やっぱりあそこしかないか…」
ぼそっと独り言を呟くと、乾はテニスコートへと向かった。
「ちゃんと食休みは取った?」
「!」
一人でストレッチをしていた海堂は、いきなり背後から声をかけられ驚いた。
「……ちす」
小さくそれだけ言うと、立ち上がって乾と向き合う。
「だいぶ気温が変わってきたからね…来週の分のトレーニングメニューを作ったよ。いる?」
「はい」
乾はポケットから四つに折ったレポート用紙を取り出した。
「それと、これはおまけ」
海堂に手渡したレポート用紙の上に、小さな白い箱をポンと乗せた。
「………なんスか」
「チョコレート」
「………」
「アミノ酸が入っているから、ランニングの前に食べると良いよ」
海堂はしげしげとチョコの入った箱を眺めると、小さく頭を下げて「すんません」とだけ言った。
「今朝は大変だったみたいだね」
「え……っ?」
「越前が、なんかやらかしたみたいじゃない?」
「あ………ああ、まぁ…」
ホッとしたように視線を外す海堂に、乾は小さく苦笑した。ちょっとカマを掛けただけで、『何かあった』のが越前ではなく海堂自身であったことが窺える。
「ねえ、海堂」
「なんスか」
「…ちょっと部室で探したいものがあるんだけど、一緒に来てくれないかな。俺はもう引退しちゃってるから、部外者が一人で入るわけにもいかないだろう?」
海堂はちょっと怪訝そうな顔をしたが、素直に頷いた。
海堂の後ろについて部室に入ると、乾が溜息をついて微笑んだ。ちょっと来ない間に、あんなに入り浸っていた部室がもう自分の居場所ではなくなっている気がした。
「探し物ってなんスか」
海堂が振り返って乾に尋ねると、乾は「ちょっとね」と言いながら、ドアをロックした。
「先輩……?なんで鍵……」
「俺が怖い?」
驚いて乾の顔を凝視する海堂に、表情を消して乾が言った。その言葉に海堂の目つきが変わる。
「…なんだと?」
「探したいものは……海堂、お前の中にあるんだ」
「え?」
乾がゆっくり海堂に近づくと、海堂は後ずさることなく、乾を睨み付けたまま身構える。
「ここに、ね」
乾は海堂の左胸に、トンと人差し指を当てた。
「………どういう意味っスか」
「海堂は俺のことをどう思ってる?」
「……………先輩……っスよ」
「それだけ?」
「…………」
海堂は乾から僅かに視線を逸らすと、黙り込んでしまった。
「まだ…好きにはなってくれてないんだ?」
「………アンタも俺も、男だろ………好きもへったくれもねぇ」
真っ直ぐ睨み付けてくる海堂の瞳を受け止めて、乾は小さく溜息をついた。
「でも、一緒にいると楽しい、くらいは思ってくれていた?」
「……………はい」
「そうか………よかった。嫌われてはいないみたいだね」
乾のその一言に、海堂が一瞬瞳を揺らすが、すぐにまた睨み付けてくる。
「アンタにはいろいろ世話になったし……尊敬も……してます」
「でも、恋愛感情じゃないんだよね……仕方ないのかな……」
乾が海堂から離れてホワイトボードの前に立った。
海堂は乾を見ずに視線を足下に落とす。
「そろそろ……ケリをつけないとならないかもしれないな…」
「ケリ?」
海堂が振り返ると、乾が海堂を見つめて微かに微笑んでいた。
「先輩…」
「ねえ海堂、………また…キスしてもいいかな」
「!」
海堂の顔が一気に赤く染まる。
「…これで最後にするから」
「え…」
乾は素早く海堂を抱き寄せると、有無を言わさぬ勢いで口づけた。
薄く開いた海堂の唇から舌を割り込ませ、逃げようとする舌を絡め取る。
「ん…」
苦しげな海堂の表情を時折見つめながら、乾はこみ上げる感情のままに甘くてほろ苦い海堂の唇を貪った。
「……海堂……」
「っ!」
甘い吐息に紛れて、耳に唇が触れるほど近くで名を囁かれ、海堂の身体がビクッと震える。
「……すまなかったね、海堂…」
乾が優しく呟いて身体を離そうとすると、海堂が咄嗟に乾の肩を掴んだ。
「先…ぱ……っ」
「…………ん?」
小さく身体を震わせている海堂に優しく笑いかけ、乾は真っ赤になっている海堂の顔を覗き込んだ。
「……感じちゃった?」
「…………っ」
さらに頬を真っ赤に染めて目を逸らす海堂の髪を、乾は優しく撫でる。
「いいよ。これで最後だから…またイかせてあげるよ」
もう一度口づけながら、乾は海堂の短パンの中へ手を滑り込ませた。
「う、……あぁ……先輩…っ」
「…………気持ちいい?」
言いながら乾が海堂の短パンを膝まで下着ごと下ろす。
「うっ…」
乾は海堂の前に跪くと、何の躊躇いもなく海堂の熱塊を口に含んだ。
「先、……ぱ…いっ」
絶妙な舌使いで、乾は海堂を追い上げてゆく。
乾がこんな風に海堂に触れるのは初めてではなかった。
昨年最初の校内ランキング戦で乾がレギュラーの座を失い、マネージャーのようにレギュラーたちの体調管理や練習メニューを組み始めたあの頃から、一人で頑張る海堂が乾の気にとまり、何となく個人的にその世話をするようになった。そして二人はどんどん親密になった。
学校での練習以外でも乾の作成した朝晩の練習メニューを一緒にこなしたり、「たまには生き抜きもメンタル面に必要」と乾が言えば、二人で買い物をしたり映画を見たりもした。
乾の家でテニスについて夜遅くまで語り合ったりもした。そのまま泊まってしまった海堂の『朝の生理現象』に乗じて乾が海堂に手を伸ばした。
(あの時にちゃんと拒絶してくれればよかったのに…)
乾はチラリと海堂の表情を盗み見る。
きつく目を閉じ、唇を薄く開いて甘い吐息を漏らす海堂の姿があまりに扇情的で、乾は慌てたように視線を外す。
初めて海堂の身体に触れた日、乾は自分の海堂への感情が『恋愛感情』なのだと気づいてしまった。
だが相手は海堂だ。想いが成就することなどあり得ないと、すでに乾は諦めてしまっている。
それでもこうして海堂の傍にいるのは、海堂が拒絶しないからだ。
乾はさらに海堂を追い上げながら、Tシャツの下に隠された引き締まった身体に直接触れてみた。
途端に海堂の熱塊が反応し、硬度が増した。
「先輩……っ、もうっ、……もたねぇっ」
乾は無言のまま海堂を絶頂まで連れてゆく。
「離せっ、出…るっ!………くっうっ!」
海堂の身体が硬直し、熱塊の先から熱い飛沫が噴き出した。
すべてを口内に受け止めた乾は熱い液体をそのまま嚥下した。
「なっ……アンタ、飲んだのかっ!?」
乾は口元を拭いながら立ち上がると、小さく微笑んで海堂の短パンを引き上げてやった。
「最後だからね………味わっておきたかったんだ」
海堂の目が見開かれる。
「ねえ海堂、最後だから、もう一つ、したいことがあるんだけど」
「………」
「キスマーク、つけていい?」
「なっ!?」
海堂がまた真っ赤になって乾の身体を押し返した。
「もちろん、目立たないところにするから……だめ?」
「………っ」
「嫌なら嫌だって言ってくれ……いいなら何も言わなくていいから…」
自分を受け入れてくれなくても、拒絶まではしないと言うなら、ほんの少しだけ海堂の優しさに甘えよう、と乾は思った。
Tシャツの襟元を押し下げて、乾はむしゃぶりつきたくなる衝動を宥め、滑らかな鎖骨の下にきつく跡を残す。
「…っつ!」
微かな痛みに海堂が小さく声を漏らした。
乾がもう一度、海堂の引き締まった身体を抱き締める。
「………ありがとう、海堂」
「あ………」
乾は一瞬腕に力を込めると、海堂の身体を解放した。
「じゃあ、もう行くよ。チョコをくれた彼女によろしくね」
「……え」
そのまま乾は部室から出ていった。
残された海堂はしばらく呆然と佇み、しばらくしてからそっと鎖骨のあたりを指で辿った。
練習に集中できない自分を自覚して、その原因がよく分からず海堂は戸惑っていた。
何とか気合いを入れようと顔を洗って戻ってくると、『目障りな後輩』に呼び止められた。
無視するわけにもいかないので黙って彼の方を向くと、いつも余裕タップリなはずの大きな瞳に、微かな苛立ちの光を見つけて海堂は内心「何かあったな」と感じた。
「何でチョコレート、受け取ったんスか?」
「………あぁ?」
突然の質問に、真意を測りかねて鬱陶しそうに海堂が返事をする。
「今朝、部室を出たところで女子から受け取っていたじゃないっスか、チョコ。見られてないと思ったんスか?」
「…………」
海堂は内心ギョッとした。ほんの一瞬の出来事だったし、周りには誰もいなかったはずなので、誰も知らないと思っていた。
だが見られていた。しかも一番見られたくないヤツに。
そこまで考えて、そういえば乾も「知っていた」ことを思い出す。
(まさかこいつが………)
「てめぇにゃ、カンケーねぇだろ」
微かな心の動揺を悟られないように、そして乾に余計なことを告げたことへの多少の怒りを込めて、いつものようにつっぱねてみる。
「カンケーはないけど、参考に聞いてみたいんスよ。決まった相手がいるのに、何で他の人から『気持ち』を受け取れるのかなって」
「…………」
そう言えば乾が以前、手塚と越前の関係を自分に仄めかしたことがあったな、と海堂は思い出した。
それを聞いたときは正直言ってビックリしたが、二人を見ているうちに、その関係はひどく自然なものに思えてきていた。
(手塚先輩と何かあったのか……)
海堂は、急に目の前の後輩に親近感を覚えた。その『親近感』がどこに起因したのかは分からなかったが、とにかくこの後輩が自分を茶化すために呼び止めたのではないと知り、海堂は真面目に答えてやろうと思う。
「………嬉しかったからだ」
「え?」
ちゃんと真面目にテニス以外のことを話すのは初めてなような気がして、海堂はなぜか湧き起こる気恥ずかしさに、目の前の後輩から視線をずらした。
「人の想いってもんは大事にしなきゃなんねぇ。その人が俺のために一生懸命作ってくれたもんを無下にはできねぇだろ」
海堂は本音を言った。
今朝チョコレートを渡してくれた女子生徒は、真っ赤な目をしていた。きっと夜中までチョコを何度も失敗しながら作ってくれたのだろうと、海堂は感じ取った。そしてそれを自分に渡す勇気を奮い立たせたであろう彼女に、差し出されたチョコレートを突っ返すことは、海堂には出来なかった。
「……でも、それで先輩の気は済むだろうけど、先輩のことを想ってるあの人がどう思うか考えないんスか?」
その一言に、海堂は一瞬息を飲んだ。
(こいつ……知ってる…?)
そしてその表現が、まるで恋人を裏切った人間に向けられたもののような気がして、海堂は語気を強めてしまった。
「俺は後ろめたいことはしてねぇ!モノは受け取ったが、彼女にはきっぱり断りを入れた」
(そうだ……先輩は恋人じゃねぇ………ただの……先輩なんだ)
反発しながら、海堂は自分の胸に訳の分からない苦い想いが広がるのを感じた。
何かが自分の中で変化してゆくようで、苛立ちと不安に、つい目の前の後輩に矛先を向けてしまいそうになる。
だが、いつもはそんな自分のきつい瞳を受け流すその後輩が、今日に限って同じように自分を睨み返してきた。
「だからって、アンタを好きなあの人が嫌な気分になっても良いって訳?」
(俺たちが付き合っていると思ってやがるのか…こいつは…)
その時急に、昼休みに乾が見せた最後の表情が海堂の脳裏を掠めた。
ほんの少ししか見えなかったが、あんなに切ない乾の表情は初めて見た気がする。
それでも、だからといって、情に流されるのはごめんだ、と海堂は思う。
「…俺は俺のしたいようにする」
自分の行動はすべて自分の責任になる。相手の感情に流されて、そうしてつらい思いをしたときに相手のせいにすることは絶対にしたくなかった。
これ以上自分の心を掻き回されたくなくて、海堂は隣のコートに足を向ける。…と、突然後輩が妙なことを言った。
「海堂先輩、今日は胸のボタン全部締めておいた方がいいっスよ」
「?」
後輩の言った言葉の意味がわからなくて、海堂は怪訝な顔をして振り返った。
するとその後輩は自分の襟元を指さしてニヤリと笑った。
「!」
部室で乾につけられた『痕』のことを思い出し、突然後輩の言わんとする意味が理解できた海堂は慌ててボタンを締めた。そうすることでその『痕』の意味を肯定してしまうことになるのだが、この際それは気にしないことにした。
それでもやはり自分に向けられているだろう、からかうような視線が気になり、肩越しに後輩を振り返ってみる。
しかし、振り向いた先にいる後輩は切なげに瞳を揺らしながら大きく深呼吸をしていた。
(こいつもこんな顔をするのか……)
常に余裕を持ち、飄々と何でもこなしてしまう『目障り』な後輩。
なのにその後輩が今、誰かに想いを馳せ、悩み、切なげに瞳を伏せている。
真実を確かめるのが怖くて、でもそんな自分に嫌気がさして八つ当たりしてきたのかもしれない、と海堂は思った。
同性という最大の障害に、きっと何度も不安を感じてきただろう。それに昨年は手塚が負傷して東京を離れていた時期もあった。
(それでもこいつはずっと『自分の想い』と向き合ってきたのか…)
海堂は視線をコートに向けた。
(俺はどうだ?俺は『自分の想い』と向き合ったことがあるのか?)
そう考えてからハッとする。
(自分の、想い……だと?)
海堂は目を見開いた。
自分は今までどうして気づかなかったのだろう、と愕然とした。
(俺の、……想い………)
「オラ、マムシ!ボケッとつっ立ってンじゃねぇよ!」
「…んだとコラァ…っ!」
思考を妨害した桃城をギラッと睨み付けると、その背後のフェンスの向こうに見慣れた人物を見つけた。
「おい」
また深呼吸をしている後輩に向かって声をかける。
訝しげに視線を寄こした後輩に、向かいのフェンスを顎で示してやった。
示された方を見た後輩の表情が、ほんのりと明るくなるのを海堂は見逃さない。
「回りくどいコトしてねぇで、てめぇで確かめろ」
後輩に背を向けて、相手に聞こえるギリギリの声で海堂は言った。
(いつまでもウダウダしてんじゃねぇ。……てめぇらしくねぇだろっ)
ささやかなエールのつもりだった。
そして自分にも、同じ言葉をぶつける。
(てめぇで……確かめろ……)
海堂は大きく息を吐くと、コートの向こうにいる桃城に向かって叫んだ。
「おい、タコ野郎!そこにいるなら相手しやがれっ!」
「誰がタコだっ、このマムシ野郎っ!さっさと打てよ!ボザボサしてんじゃねぇっ!」
「うるせぇっ!殺すぞっ!」
叫びながら海堂がサーブを打った。
桃城とのやりとりが、今は心地よかった。
家に帰り着いた乾は、着替えを済ませてからパソコンを立ち上げた。
しかし画面を見つめる乾の瞳は、何も映してはいなかった。
「俺も結構女々しいな…」
もう随分前に諦めていたはずだった。
自分の中に芽生えたこの想いは、相手には届かない、届くわけがない、と納得していたはずだった。
なのに今日、またもや迂闊に触れてしまった海堂の感触が、自分の唇に残っている。
乾は自分の唇に指で触れようとし、しかし触れる前にその手をギュッと握りしめた。
(もうよそう……今日で終わりだ…)
自嘲気味に微笑んで溜息をつくと、ふと、時計を見た。
(そろそろ部活が終わった頃だな……)
もう一度溜息をついて、気持ちを切り替えようとしたその時、玄関のチャイムが鳴った。
家には自分しかいないので、ゆっくりと立ち上がった乾は玄関に向かった。
インターフォンには出ずに、そのままドアを開ける。
「!」
「うっ!」
開いたドアの前に、乾の予想しなかった人物が立っていたので、乾は咄嗟に言葉を失ってしまった。
その訪問者もいきなりドアを開けられてひどく驚いたらしく、言葉を出せずにいた。
「……どうしたの海堂?メニューに分からないところでもあった?」
「…………あ…………いえ」
海堂が口ごもって俯く。
「…入る?」
「…いえ……すぐ帰るんで………ちょっと、外で…………いいっスか?」
「わかった。ちょっと待ってて。上着を取ってくるよ」
部屋に戻り上着に袖を通しながら、乾は複雑な心境になった。
「まいったな……」
期待してしまいそうになる自分の心に苦笑する。
大きな溜息をひとつついてから、乾は海堂と共に近くの公園に向かうことにした。
「そう言えば部活は?早く終わったの?」
「あ………竜崎先生が、今日は急用ができたからって……いつもより30分早く切り上げました」
「なるほど」
公園に到着すると、乾はベンチに腰掛けた。
「座れば?海堂」
「いや、いいっス」
「………で?話って何?」
普段より心なしか口数の少ない海堂に、話しやすいように乾が話を切り出してやる。
「………今日、アンタは俺に言った………自分をどう思っているのかって」
「うん」
「俺も聞きたいっス。………アンタは俺のこと、どう思っているんスか?」
「……言っても困らない?」
海堂は真っ直ぐに乾を見た。少し間をおいて、小さく頷く。
乾は溜息をつくと、海堂を真っ直ぐ見上げた。
「……海堂が好きなんだ。友達とか、後輩としてとか、そう言う意味じゃなく、キミに恋をしてる」
海堂はあまり驚かなかった。乾の言葉を聞き終わると、小さく頷いて「そうスか」と呟く。
「海堂?」
その反応が乾の予想していたものとあまりに違ったので、乾は不審に思って海堂の顔を覗き込んだ。
乾の顔が接近した途端、海堂が驚いたように一歩後ずさる。
その行動を見た乾は、今度こそ完全に拒絶されるのだと覚悟を決めた。
「わざわざトドメを刺してくれるのかい?いっそ、その方がすっきりするかもしれないな」
乾はそう言って微笑むと、ゆっくりと立ち上がった。
「じゃあ、俺ももう一度聞くよ。海堂は俺のこと、どう思っている?」
「………」
答えてくれない海堂に、乾は溜息を漏らした。
「………わかった。じゃあ、元気でね」
海堂に背を向けて歩き出す乾に、海堂の叫びが突き刺さる。
「何が『わかった』だ!アンタは何も分かっちゃいねぇ!」
乾は足を止めると、ゆっくりと振り向いた。
「海堂…?」
振り向いた先の海堂は、頬を真っ赤に染めながらきつく睨んでくる。
「何なんだ、アンタは。最後最後って連発しやがってっ!そんなに最後にしてぇのか!」
「!」
「終いにゃ、俺の返事を聞きもしないで勝手に結論出しやがって!いい加減にしろっ!」
乾は身体ごと海堂に向き直ると、眉をきつく寄せた。
「返事?」
「…………っ」
海堂はいきなり口を噤むと、乾から目を逸らした。
「海堂?」
「……怒鳴ってすんません………後ろ………向いててもらえないっスか?」
「………こう?」
乾は訳が分からないまま、とりあえず海堂に背を向けた。
「すんません」
海堂が深呼吸を始める。
乾は、今度は結論を急がずに海堂の言葉を待った。
「………アンタをどう思っているか聞かれて、部室で言ったことは本当っス。アンタは尊敬できる先輩で、一緒にいると結構楽しかった」
ゆっくりと紡ぎ出される言葉に耳を傾けながら、乾はそっと両手を握りしめた。
「初めてアンタの家に泊めてもらったとき………いきなりあんなことされて……すげぇ、ビックリした………でも…」
海堂がそこで一瞬押し黙った。乾の心拍数が上がり始める。
「……でも、もっとビックリしたのは………アンタの手が………全然嫌じゃなかったことだ……」
「海堂…それは…」
「黙って聞けっ!」
乾の言葉を、海堂は慌てたように遮る。
「その後も……何度も同じようにアンタにイカされて………でもアンタは何も言わないし、自分の欲求を俺に押しつけても来なかった」
「……」
「アンタがどういうつもりで俺にあんなことをするのか分からなかった……退屈しのぎに使われているんだと思った。…でも俺のカラダは、どんどんアンタの感触を覚えちまって………アンタに飽きられたらどうなるんだろうと………それが、怖かった」
乾は目を見開いた。握りしめた手に、汗が滲む。
「なのに、アンタはいきなり『今日で最後だ』と言った。何度も何度も『これで最後だ』って……。それでもいいのかもしれねぇって…さっきまで俺も思ってた」
言葉を止めて、海堂がまた大きく息を吸い込んで吐き出した。
「…でも…アンタが……ちゃんと俺のこと好きだって言うの聞いたら………俺も…今の自分の気持ちがはっきりした」
ドクンと、乾の鼓動が大きく鳴った。
「悪いが、アンタのこと、アンタが俺を好きなのと同じように好きかどうかはまだわからねぇ。でも、『今日で最後』ってのは納得がいかねぇ。もっと……一緒に………いて欲しい」
「また……俺にあんなことされてもいいの?」
今度は海堂が言葉を遮ってこなかった。
しかし一向に返ってこない返事を待ちきれなくて、乾は海堂を振り返る。
乾の眼鏡の奥の瞳が、真っ直ぐな海堂の瞳を捕らえた。
いや、乾の瞳が、海堂の瞳に魅せられ、捕らえられた。
「俺は嫌なことは嫌だと言う。だが………卑怯かもしれねぇが……嫌じゃないことに頷く勇気が、まだ出せねぇ……」
「いいよ、それで」
乾は海堂を抱き寄せた。
海堂はおとなしく乾の腕の中に捕らわれる。
「………これは『嫌じゃない』んだね」
「…………」
「じゃあ、キスは?」
「…………」
黙ったままそっぽを向く海堂の顔を自分に向けさせると、乾はそっと唇を重ねていった。
「…嫌じゃ…ないんだ?」
唇を少し離して乾が囁くと、海堂の身体がビクッと揺れた。
乾の胸に甘い疼きが広がる。
もう一度深く口づけてから、乾は海堂の身体をしっかりと抱き締めた。
「……俺の家においで。今、誰もいないんだ」
「………っ」
海堂の体が小さく揺れた。だが、拒絶の言葉は、海堂の口からは聞こえてこない。
乾はクスッと笑うと海堂の身体を離し、その手を引いて自分の家に向かって歩き始めた。
「……手……」
「え?」
海堂が真っ赤になりながら小さな声でぼそっと言った。
「手は…離せ」
「………これは嫌なんだね?」
海堂が小さく頷く。
「分かった。ゴメン」
「いちいち謝ってんじゃねぇよ……」
解放された手をポケットに突っ込みながら、独り言のように海堂が呟いた。
乾は微笑むと、海堂の温もりが残る右手をポケットにしまい込む。
「……今日もテニスの話をしようか。ちょうど新しい雑誌も買ってきたし。夕飯もうちで済ませるといい」
「……どの雑誌スか?俺も昨日買ったヤツ、持ってるんスけど」
「本当は明日発売のヤツだから違う雑誌じゃないかな。一日早く販売する本屋をこの前見つけたんだ」
「いいっスね、それ。近くの本屋っスか?」
「今度連れていってあげるよ」
「はい」
何気ない会話が、乾には嬉しい。諦めてしまっていた想いが堰を切ったように胸に溢れてくる。
暗くなった空を見上げると、ひときわ大きく輝く星が、乾の目に留まった。
「大きいな、あの星…」
「木星、じゃねぇかな…」
「木星?」
「…クラスの科学部のヤツがそんなことを言ってたと思うんスけど…」
「ネットで調べてみようかな」
「そっスね」
「今夜はやることが多いね。時間を有効に使うために………また泊まってく?」
海堂は目を見開いて乾の背中を凝視した。何か言いかけたが、すぐに口を閉じた。
「………じゃ、いいんだね?」
少し俯いた海堂の顔がみるみる赤く染まってゆく。
しばらく返事を待ったが何も聞こえなかったので、乾はクスッと笑ってからまた夜空に輝く大きな星を見上げた。
(言葉じゃ伝わらないものもある……)
言葉で伝えることも時には大切なことかもしれない。
しかし、言葉になる前の『想い』を伝えるためには、本当は言葉なんていらないのかもしれない。
乾は立ち止まって、言葉を紡ぐのが苦手な想い人を振り返った。顔を赤くしたまま真っ直ぐ見つめてくる海堂に微笑みかける。
「やっぱり何でも粘らないといけないね」
海堂は一瞬キョトンとした表情をしたが、小さく溜息をつくと、ふっと笑った。
「諦めたら終わりっスよ」
「そうだね………もうしばらく粘ることにするよ」
「………俺も……ちゃんと答えが出るまで……妥協はしねぇから…」
「まあ、俺もただ粘るだけじゃなくて、どんどん攻めていくからね。覚悟はしておいた方がいいよ」
「………か、覚悟って…」
再び火が出そうなほど顔を赤くした海堂が乾から視線を外して俯いた。
「木星が…」
呟くように乾の口から出た言葉に、海堂がふと視線を乾に戻す。
「木星が太陽の周りを一周するまでには…いい結果が出ていると良いけど…」
「………一周?」
「12年かかる」
「12年………っスか」
「長い?短い?」
海堂はふぅっと息を吐くと乾を真正面から見つめた。
「長いか短いかは関係ねぇ。重要なのは、その12年をどう過ごすかじゃないんスか?」
「…そうだね」
「常に自分のベストを尽くせば、自ずと結果はよくなるっスよ」
「じゃあ、俺を拒絶しなかったことは、今の海堂にとってベストなことなんだね」
海堂はまた頬を染めると、乾を軽く睨み付けた。
「アンタ、誘導尋問がうまいっスね」
「ガンガン攻めるって、さっき言っただろ?」
海堂は溜息をついて頭をガシガシと掻いた。
「今日の俺の選択がベストかどうかは、『結果』に現れて来るんスよ」
「………なんか矛盾してないか?」
「う………俺は頭で考えるのが得意じゃねぇから………」
「じゃ、身体で一緒に考えようか」
「…………なっ!!!」
真っ赤になって狼狽える海堂が可笑しくて、楽しくて、嬉しくなって、乾が声を立てて笑った。
『惑いの星』と書いて『惑星』と読む。
自分を惹きつけた、空に輝くあの大きな星は今の海堂に似ている、と乾は思った。
END
2003.2.13
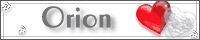
■不二×菊丸Side■

■Novelsトップへ■
|