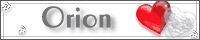

朝練でのリョーマの重大発言を知って、菊丸は大笑いをした。
「あははっ、さっすが、おチビだにゃ〜」
「後で手塚の感想を聞いてこようかな」
「うんうん、それも楽しそうだにゃん!」
「ところで英二」
「うにゃ?」
不二はスッと菊丸に顔を近づけると、真顔になった。
「今日の夜はダメって、どういうこと?」
「あは………」
菊丸が笑顔のまま凍り付いた。
ジッと見つめてくる不二の瞳を受け止めかねて、菊丸がしゅんと肩を落とす。
「…だってさ………久しぶりに親父が休み取れてさ……みんなで鍋でも食べようって言うから……家族が揃わないと可哀想だから…」
菊丸の父親は休みもろくに取れずに仕事で飛び回っているため、たまに休みが取れたときには家族とゆっくり過ごしたがるらしい。
「親父がさ、母さんと買い物にも一緒に行って材料仕入れて来るって言うんだ。母さんも張り切っちゃってて………」
「…………」
不二も家族を大切にする方なので、菊丸の気持ちは分からなくはない。だが、家族と恋人を天秤にかけるとすれば、不二の場合は少しだけ恋人の方に傾いているのだ。
昨年のクリスマスもそうだった。
菊丸の父親の休みが急に取れたからと言う理由で、クリスマスイブを一人で過ごさなくてはならなかった不二だ。手塚に八つ当たりしてみたものの気が晴れるはずもなく、むしろそんな自分が情けなくなって、最後には手塚たちにちょっとしたクリスマスプレゼントまで贈ってしまったほどだ。
「………わかったよ英二。もういい…」
「不二……っ」
「あ、別に怒ってないよ。英二とはいつでも一緒に過ごせるもんね」
「……う、ん……ごめん」
不二にニッコリと笑いかけられて、菊丸は申し訳なさそうに小さくなった。
「明日はいいの?」
「うん!明日はずっと一緒にいられるにゃっ!」
嬉しそうに断言する菊丸の笑顔に、不二もやわらかな微笑みを返す。
「そう。よかった。………あ、じゃあ、チョコレートも明日でいい?」
菊丸は一瞬「うっ」と言ったが、小さな溜息をひとつついて、不二に笑いかけた。
「不二だって我慢するんだもんね。俺も我慢するにゃ」
「大丈夫、チョコレートは腐ったりしないし」
「そだね」
二限目開始のチャイムが鳴った。
「じゃあね」
「うん」
三学期になって少し離れてしまった席へ、不二がゆっくりと歩いてゆく。その不二の後ろ姿を見送りながら、菊丸はそっと眉を寄せた。
昼休み。
不二と菊丸はいつものように二人で昼食を済ませ、暖かな窓際でのんびりとしていた。
「あ、そうだ、辞書借りないと…ついでに手塚に感想聞いてこようかな」
「じゃ、俺も俺も〜!」
二人で1組の方へ向かおうとしたその時、教室の後ろの方から菊丸にお声がかかった。
「お〜い、菊丸、ちょっとこっち来いよ〜」
「え〜今から用があるにゃん」
「まーいいからいいから。ちょっとだけ。不二、菊丸貸して!」
不二は菊丸にニッコリ笑いかけると「手塚の感想、うまく聞き出しておくよ」と囁いて、一人で廊下に出ていった。
「不二………」
菊丸はキッと振り返ると、自分を呼び寄せた本人の所に足早に歩み寄った。
「も〜、なんだよぅ。せっかく楽しいコトしに行くとこだったのにぃ〜」
「え?不二とヤラしいこと?」
「違うよ、バカっ!」
「怒るなよ。冗談だって。ほら、お前にお客さん」
「へ?」
菊丸が指さされた方に目を向けると、頬を真っ赤に染めた下級生らしい女子生徒が廊下に立って俯いていた。
「う………」
「やっぱテニス部はモテモテだよな〜いいな〜いいな〜」
いくら禁止という校則があっても、やはり「こっそり」チョコレートを持ち込む女子生徒はいるものである。
「参ったにゃ………」
菊丸は小さく呟くと、不二が出ていった方のドアを見つめた。
手塚に辞書を借り損ねた不二は、仕方なく隣のクラスにいる大石に借りるべく、廊下に出た。
何気なく廊下の窓から見える非常階段に目をやると、4階と3階の間にある踊り場のところに菊丸の後ろ姿を見つけた。
「英二……?なにやって………」
不二は一瞬呼吸を止めた。菊丸の陰に頬を染めた女子生徒が見えたのだ。
女子生徒は遠目でも分かるほど緊張していて、今にも泣き出しそうな顔をしている。何度も菊丸に頭を下げて、必死に何かを頼み込んでいるようだ。
菊丸がぽりぽりと頭を掻いている。
受け取れないと断る菊丸に、女子生徒がどうにか受け取って欲しいと頼んでいるように、不二には見えた。
(英二好みの可愛い子だね……)
不二が微笑んで視線を外そうとしたその時、菊丸が大きく頷いて、彼女の肩をポンポンと二回叩いた。
(英二……?)
不二の切れ長の目が大きく見開かれる。
菊丸が女子生徒から、小さな箱を受け取ったのだ。
(英二………)
不二はそのまま、予鈴がなるまで、そこに立ち尽くしていた。
「不二!一緒に帰るにゃん!」
「…ゴメン、英二。今日はちょっとテニス部を覗いてから帰るよ」
「………ん、わかった。明日は10時にいつものとこでいいかにゃ?」
不二はニッコリと微笑んで頷いた。
「明日、楽しみにしてるよ」
「うん。………今日はホントにごめんにゃ。じゃ、明日!」
「じゃあね、バイバイ、英二」
「おチビによろしくにゃ!」
鞄を担いで教室を飛び出してゆく菊丸を見送ると、不二はそっと瞳を伏せた。
(とうとう英二は何も言わなかった……)
非常階段にいたときの菊丸の後ろ姿がふと思い出される。
(どんな顔してあの子からチョコを受け取ったの?)
不二はそっと目を開けると、机の上の鞄を手にした。
図書室に寄って、少しだけ時間を潰してからコートに向かう。
部員に気づかれないように校舎側の木の陰からそっと様子を伺ってみようとして、そこに先客を見つけた。
「……あれ、手塚?」
「不二…」
「もしかして、王子様のお迎えがてら、見に来たの?」
手塚は「まあな」とだけ言うと、視線をコートに戻す。
「………今日は振られたのか?」
「え……」
突然の手塚の言葉に、不二は少しだけ驚いた。
「仮面が外れかかっているぞ。……まあ、そんなものはつけていない方がいいんだが」
「なんだい、それ」
不二はいつものように笑おうとして、なのに、頬が強ばって綺麗な笑顔が作れない自分に気づいた。
「………まいったな……」
「いっそのこと、さらけ出してしまえばいい」
「……他人事だと思って簡単に言わないでくれる?」
仮面の外れかかった不二の瞳は、相手を突き刺しそうなほど冷たく鋭い。
手塚は軽く溜息をつくと、不二の冷たい瞳と視線を合わせた。
「不二、以前お前が俺に言った言葉をそっくりそのまま、今のお前に返してやろう」
「え?」
「『嫉妬もできないようじゃ、本気だとは言えない』だ」
不二は大きく目を見開いた。
「菊丸を信じてやれ。『不二周助を本気にさせた男』だろう?」
「手塚……まるで何か見ていたような口振りだね」
「…図書室に向かう途中で、非常階段に女子と一緒に出ていく菊丸を見た。そしてお前のその様子。……だいたいのことは分かる。」
手塚から視線を逸らして不二が溜息をついた。
「さすが、元生徒会長にして青学テニス部最強の男、だね」
「茶化すな」
「そうじゃないよ……そうじゃなくて………」
不二の冷たかった瞳が翳りを帯びて切なげに揺れた。
「キミには偉そうなことばかり言っているけど、自分のことになるとダメなんだ。英二に……拒絶されたら、って……」
「………」
「英二が僕の傍からいなくなるかもしれないって考えただけで、息が出来なくなる……いや、そうなったら、自分が英二に何かしでかしそうで…怖いんだ……」
手塚は不二の横顔をしばらく見つめると、もう一度視線をコートに戻した。
「俺が信じろと言ったのは、菊丸とあの女子とのことじゃないぞ」
「え…」
不二が顔を上げて手塚を見た。
「菊丸の、お前への想いを信じろと言ったんだ」
「手塚……」
「あいつもお前も、お互いのことに関しては度が過ぎるほどに一途だ。そんな菊丸の真っ直ぐな瞳は、すでにお前の『本性』なんか見抜いている。それでも、あいつはお前の傍に、今もいるだろう?」
「そう、………かな………」
すっかり仮面の剥がれ落ちてしまった不二は、手塚の言葉ひとつひとつを噛み締めながら素直に心にしまい込んでゆく。
しばらく沈黙した不二が、静かに深呼吸をして、クスッと笑った。
「キミたちより僕達の方が先につきあい始めたのに………何だか教えられることが多いや……」
手塚はコートを見つめたままふっと笑った。
「…俺たちも…いろいろあったからな…」
「…うん…そうだったね…」
乾いた冷たい風が、二人の足下の枯れ葉をさらっていった。
「……ありがとう、手塚。ちょっと、落ち着いたよ」
手塚は無言で不二を見た。
「今日はもう帰るね。越前くんによろしく。じゃ…」
「ああ」
不二は、いつもの笑顔を浮かべると手塚に背を向けて歩き出した。
向かい風が、不二の色素の薄い髪をすくい上げる。
(キミが傍にいないと……凍えそうだよ……英二……)
不二は目を閉じると、向かってくる風を胸一杯に吸い込んだ。そしてそれを一気に吐き出すと、ゆっくりと目を開ける。
(強引に奪ってしまえたら…楽なのにね…)
それが出来ない自分をもどかしく思いつつも、一方では、いつか菊丸の自由さえ奪いかねない危険な自分を嫌悪する。
(逢いたい……)
逢うだけでいい、と不二は思った。
たとえ菊丸の輝く瞳が自分を映していなくても、その姿を自分の瞳に映せればそれだけでもいい、と。
「英二……」
不二の切ない囁きが、風にのって上空へと舞い上がっていった。
「はぁ〜、お腹いっぱいにゃ〜っ!」
一家揃って楽しい夕食を終えた菊丸は、満杯の腹を撫でながら幸せそうに言った。
「さ〜て片づけ片づけ!」
「あ、姉ちゃんたち、俺がやるからさ!早く彼氏に電話してあげたら?」
「な……何言ってんのよあんたはっ」
「そ、そうよ、別にあたしは…」
恥ずかしそうに頬を染める姉たちを見て、菊丸がニッコリと笑った。
「いいからいいから、ほら、早く!」
「……うん……ごめん、頼んでいい?」
「まっかしてにゃん!」
「ゴメンね、英二」
エプロンを菊丸に渡してそそくさと携帯を手に持ち、二階へ向かう姉たちを見送りながら、菊丸は腕をまくり上げた。
「ラブラブな親はほっといて、っと!よーし、超特急で片づけにゃんっ!」
鼻歌を歌いながら、菊丸が食器を洗い始めた。
片づけを終え、自分のベッドで雑誌を捲っていた菊丸は、自分の名を呼ばれたような気がしてふと顔を上げた。
「兄ちゃん、何か言った?」
「ん?何も言ってないぞ」
「………」
バサッと雑誌を乱暴に閉じた菊丸は、上段のベッドから一気に飛び降りた。
「こらっ!英二!飛び降りんなって言ってるだろっ!」
「ゴメン兄ちゃん、緊急出動要請にゃん!」
「はぁっ!?」
菊丸は真顔になってジャケットをひっ掴むと、部屋を飛び出していった。
菊丸家の前で、不二は通りを挟んだ電柱の陰から明かりの灯る二階の窓を見上げていた。
家にいても何も手につかず、ついここまで来てしまった。
だが他人の家を訪問するにはすでに遅い時間のため、目の前のインターフォンを押すことは出来ない。
せめて、想い人がひょっこり窓から顔を出してくれればと、不二は儚い望みを抱きつつ、すでに一時間以上この場に佇んでいた。
冷たくなった手をポケットの中で握りしめて、不二は溜息をついた。
(これじゃ、ストーカーみたいだ………)
目を伏せて、今日はやはり諦めよう、と思ったその時、目の前の玄関のドアが勢いよく開いた。
「!?」
「…不二、おまたへ〜っ!」
「え?」
あまりの驚きに何も言葉が出てこない不二の傍に、菊丸が軽くスキップをしながら近づいてきた。
「気づくのが遅くなってゴメンにゃ〜。寒かったよね」
菊丸が不二の両手を掴んで一纏めにして握り込んだ。
「うわっ、冷たっ!………大丈夫?不二……」
「英二………なんで………僕がここにいるって……」
不二はずっと二階の窓を見ていたから分かるのだ。菊丸が自分の姿を『見た』わけではないことを。
「不二の声が聞こえたにゃん。何度も、何度も………呼んでくれたでしょ?」
不二は目を見開いた。自分はここに来て、一言も声を発してなんかいない。
「どうして……」
菊丸は不二にそっと抱きついた。頬を摺り合わせて「ほっぺも冷たいね」と呟く。
不二もゆっくりと菊丸の身体を抱き締め返した。
「英二はあったかいね………」
「何でだか分かる?」
「え……?」
菊丸はそっと身体を離すと、不二の瞳を覗き込んだ。
「俺があったかいのは、今、不二が寒いだろうな〜と思っているから。不二をあったかくしてあげたいな〜と思っているからにゃん」
「!」
「不二が寒かったら俺が暖めてあげる。お腹空いていたら、俺がご飯を作る。………逢いたいって思ってくれたときは、緊急出動するにゃ」
不二は大きく目を見開いたまま、何も言えなかった。呼吸すら忘れたように、ただ菊丸を見つめる。
そんな不二にニッコリと微笑みかけると、菊丸はそっと唇を重ねてきた。触れるだけのキスをして、不二の身体を抱き寄せる。
「大好き、不二……」
「………え……い…じ…」
不二は菊丸の背にしっかりと腕をまわすと、きつく抱き締めた。
「不二……?」
菊丸の肩口に顔を埋めて小さく肩を震わせ始めた不二に驚き、菊丸はオロオロとその背をさすってやった。
「な……泣いてるの?不二???」
「ううん、泣いてないよ………嬉しいだけ……」
「不二が泣いたら俺も泣くよ…」
「うん……だから泣いてないよ……英二の涙なんか、見たくないもん…」
さらに深く菊丸の身体を抱き締めながら、不二が熱い吐息を漏らす。
「このまま……ずっと一緒にいたい………ダメ?英二……」
「うーんと………」
菊丸はちょっと悩む素振りをした。不二はそっと苦笑する。
「ワガママ言ってゴメン……英二が優しいから、甘えたくなっちゃった…」
菊丸がクスッと笑う。
「不二に甘えて貰えるとすっごく嬉しいにゃ。もっとワガママ言っていいのに」
「え……」
「あのね」
菊丸が真面目な顔で不二の顔を覗き込んだ。
「俺の家と不二の家、どっちで一緒に過ごす?うちでよければすぐに暖めてあげられるけど、今日は兄ちゃんがいるし…」
「………」
「あ、べ、別に、兄ちゃんがいても良いんだけど………今日はバレンタインだもんね……本当は二人だけがいいよね…」
不二はやわらかく微笑むと、菊丸に深く口づける。
艶やかな水音をさせて唇を離すと、菊丸の耳に触れそうなほど近くで囁いた。
「僕の家、今日は誰もいないよ」
「……え?」
不二は瞳を揺らしながら、菊丸の瞳を覗き込む。
「母さんは父さんのところにチョコレートを渡しに行っちゃってるし、姉さんは今夜は彼氏と一緒なんだ」
不二の言葉の途中から菊丸の頬が赤く染まり始める。不二が話し終わる頃には暗がりでも分かるほど耳まですっかり赤くなってしまっていた。
「………ちょっと待っててにゃ。今から不二のところに『お泊まりする』って言ってくる」
「大丈夫?」
「不二が『一人じゃ怖くて眠れない』って泣いて頼むから、って説明するにゃ」
「ひどいな。一人じゃ眠れないって言うのは本当だけどね」
小さく笑う不二に菊丸が「待ってて」と笑いかけ家の中に入っていった。
「……二人で一緒にいたら、ますます眠れないかもしれないけどね……」
そっと呟きながら、不二が夜空を見上げた。冴えた輝きを放つオリオン座の三ツ星が目に留まる。乾いた冷たい空気を吸い込んで、ゆっくり吐き出した。
(ほら、やっぱり……キミが傍にいるだけで、空気まで暖かく感じるよ……)
ほんの十数分前とは別人のように穏やかな表情をして、不二が甘い溜息を漏らした。
程なくして現れた菊丸が、にっこり微笑んで「OK貰ったよん!」と言った。
二人で並んで歩きながら手を繋ごうとして、不二は菊丸の手がふさがっていることに気づいた。
「あれ?それは………」
「あ!これはまだあとで!先にこっち!」
菊丸が左手に持った箱を隠して、右手の紙袋を不二に差し出す。
「なに?」
「まだ日付は変わってないにゃん」
「え?じゃあ……」
「菊丸印のハートミルクチョコにゃん!」
「すごい、作ったの?」
菊丸は「エッヘン」と胸を張って見せた。
頬を染めて受け取った不二は、紙袋に口づけながら「ありがとう」と言った。
「それとね」
菊丸が隠していた左手を出す。
「なんか変わったもの貰っちゃったんにゃ」
「変わったもの?」
菊丸の左手には、例の非常階段で貰った箱が乗っている。
「チョコじゃないの?」
「チョコはチョコなんだけど………」
勿体ぶっているような菊丸の口調に不二が怪訝な顔をする。
「このチョコ、俺たちに、って貰ったんにゃ」
「俺たち?」
「うん、そう、俺たち」
ちょっと困ったような笑顔を浮かべる菊丸に、ますます不二は首を傾げた。
「これをくれた子がね、つらいことがあったときに、俺たち二人の笑顔を見ていたら、すっごく心が楽になったんだって」
「そう…」
「でね、俺たちが別々にいるときの笑顔じゃダメなんだって。一緒にいるときの二人の笑顔に癒されるんですって言ってた」
「だから、僕達二人に?」
「うん。後で一緒に食べよ」
不二が微笑みながら「そうだね」と頷いた。
「ねえ英二、どうして学校でそのチョコのこと言わなかったの?」
「ん?だって……不二に一番最初にチョコをあげたかったから……この子に先を越されるのは嫌だったにゃ」
不二はちょっと驚いて目を見開いた。そしてすぐに、とびきり嬉しそうな微笑みを浮かべる。
「英二…」
「ん?……あっ」
不二が菊丸を抱き締めた。
「チョコレートより甘い時間を過ごそうね、英二」
「………うん」
チュッと音をたててキスをすると、二人は微笑み合って歩き出した。
オリオン座の三ツ星が、微笑んだかのようにキラリと瞬いた。
END
2003.2.9
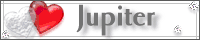
■乾×海堂Side■

■Novelsトップへ■
|