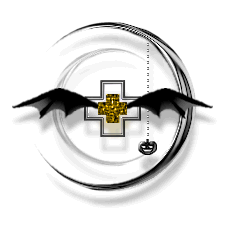
Trick or treat or LOVE
<2>
全国大会を終え、青学が輝かしい栄光を手にした影で、手塚はまた腕の故障を再発させてしまった。
試合終了後、祝勝会に向かうメンバーと別れて、一人でかかりつけの医師の元を訪れた手塚は、はっきりと宣告された。
「奇蹟は、二度は起こらないよ」
医師は手塚に「引退」を促したのだ。
「これ以上続けても、君は試合では通用しない身体になるばかりだ。テニスが好きで、ずっと関わっていたいというなら、選手としてではなく、別の道を選んだ方がいい」
完全に腕が動かなくなってしまう前に、と医師はその瞳で語っていた。
「………考えてみます」
どこか覚悟はしていた。
だから驚きはなかった。
ただ、専門家の立場からはっきりと言葉で言われると、やはり、心が激しく揺さぶられた。
(もう、テニスはできない……)
自分の世界が変わってゆく気がする。
今まで何もかもがテニスを中心に回っていた自分の世界が、音を立てて、崩壊する。
「………」
病院からふらりと出てきた手塚は、色褪せてしまった視界の中で、唯一の、鮮やかな色彩を見つけた。
「……リョーマ…」
「………」
「迎えに、来てくれたのか?」
リョーマは何も言わずに小さく微笑むと、そっと手塚の腕を引いて歩き始めた。
数週間前、約束通り全国大会に間に合わせて帰還した手塚を、リョーマは嬉しそうに迎えてくれた。そしてあの甘い口づけを、何度も交わした。
そうして大会中、試合を終えるたびにリョーマから口づけを求められ、何度も何度も、甘く舌を絡め合った。
不思議なことに、リョーマと口づけを交わすと、試合の疲れが吹き飛んだ。
好きな相手と触れ合うことがこんなにも心身共に影響するものなのだと、手塚はどこか感心しながらリョーマの唇を貪った。
だが今回の怪我は、リョーマの口づけでは、どうにもならないだろう。
それはわかっているが、手塚は沈んだ心だけでもリョーマに救って欲しいと思う。
「ねえ、部長。……今日、祝勝会のあとで、アンタの家に行きたい。いい?」
「……ああ、構わない」
無理矢理小さく微笑んで応えると、リョーマがじっと手塚を見つめてきた。
「……なんだ?」
「病院で何か言われたんスか?」
「………」
手塚はリョーマから目を逸らして溜息を吐いた。
「奇蹟は二度は起こらない、と」
「………ふーん」
小さく溜息を吐いて、リョーマは手塚から目を逸らした。
「アンタ、無茶ばっかするからだよ」
リョーマの口から小言を聞かされてしまい、手塚は苦笑する。
「そうだな」
「ばか」
「そう、だな……」
胸の痛みで、手塚は思わず立ち止まってしまった。
「リョーマ…もうお前と、テニスができないかもしれない」
「………」
苦しくて、思わず吐きだした言葉を、リョーマは平然と聞いている。
「それで?」
「え?」
静かに聞き返されて、手塚は小さく目を見開いてリョーマを見た。
「……それで、医者から『もうテニスするな』って言われて、でも、アンタはどうしたいわけ?」
「俺…?」
「アンタの意志が一番大事なんじゃないの?」
睨むようにじっと手塚を見つめてリョーマは言う。
「アンタは、どう、したい?」
本音を言えと、リョーマがその大きな、強い瞳で促してくる。
その瞳の前で、手塚は嘘や建前を言えるはずもなかった。
「俺は、まだテニスを続けていたい。プロになって、世界中の強い相手と戦いたい」
「うん」
リョーマがふわりと微笑む。
「じゃ、とりあえず祝勝会に行こうよ。みんな心配してるし、アンタが行かないと、意味ナイでしょ?」
「リョーマ…」
手塚が力無く苦笑すると、リョーマはまた笑った。
「大丈夫。アンタはまたコートに立つよ」
「…え?」
予言めいたリョーマの言葉を聞くのはこれで二回目。
一度目にその言葉を聞いた時には奇蹟が起きた。
だが今度は。
「奇蹟は、二度も起こるものなのか?」
「さあね」
大きく傾いた陽の光に、リョーマの瞳が煌めく。
「アンタが何を奇蹟って呼んでるのかは知らないけど、それが奇蹟じゃないんなら、何度でも起きるんじゃないの?」
「え…」
クスッと微笑み、リョーマがまた手塚の手を引いて歩き出す。
「奇蹟なんて、カミサマが起こすものでしょ?………オレは、カミサマじゃないし…」
背を向けているリョーマの表情はわからないが、その声はどこか硬く、微かに自虐的な響きすら感じられた。
「リョーマ?」
「………」
それからリョーマは何も喋らなかった。
ただ手塚の手だけはずっと離さず、真っ直ぐ前だけを見つめ、歩き続けた。
祝勝会を終えて、そのまま、手塚はリョーマを家へと連れ帰った。
祝勝会の間中、リョーマはずっと手塚の左側に座っていた。
それはまるで、自分の痛めた左腕を庇ってくれているようで、手塚は胸が熱くなった。
「今、何か飲み物を持ってくる。何かリクエストはあるか?」
「べつに」
部屋の中を見回しながらリョーマが答える。
「では適当に選ぶが、あとで文句は言うなよ?」
「はーい」
リョーマは興味深げに、棚に並ぶ本のタイトルに目を走らせている。そのリョーマを見て小さく微笑んでから、手塚はキッチンへと向かった。
「母さん、何か飲み物を頂けますか」
「ええ、今用意したところよ。はい、これ、どうぞ」
手塚の母・彩菜が差し出したのは濃い赤紫色のグレープジュースだった。
「それね、とっても美味しいから気に入ってくれると思うんだけど」
「?…はい、ありがとうございます」
今までグレープジュースはあまり出されたことがなかった手塚は、内心首を捻りながらも、「きっと店で試飲して気に入ったのだろう」と思い、気にしないことにした。
「あ、それから、母さんちょっと出掛けるから、しばらくお留守番してて?」
「今からですか?」
「ええ。…そうね、二時間くらいはかかるかしら。越前くんに『ごゆっくり』って言っておいて」
「わかりました」
不審に思いながらも、敢えてそれ以上は追及せずに手塚は部屋に戻った。
「待たせたな」
「んー」
リョーマは壁に飾ってある大きな山の写真に見入っていた。
「ねえ」
「ん?」
トレイを机に置き、リョーマの横に並んで立つ。
「この山の写真、いつ撮ったの?」
「………さあ……いつだったか…」
「……ま、いいや」
リョーマは視線を手塚に向けて小さく微笑むと、ふと、机の上にある二つのグラスに気づき、目を輝かせた。
「それって、グレープジュース?」
「ああ」
「もらっていい?」
「どうぞ」
微笑んで頷いてやると、リョーマは嬉しそうに机に走り寄り、グラスを二つ手にした。
「はい、アンタもドーゾ」
「ありがとう」
グラスをひとつ手渡され、手塚は笑みを深くして礼を言う。
「カンパイ」
リョーマが軽く音を立ててグラスをぶつけてきた。
「青学の勝利に、か?」
「まあね。それと、オレたちの未来に?」
「………ああ…」
未来、と聞いて手塚は表情を曇らせた。
自分が今まで思い描いていた未来への道は、もう閉ざされかかっているのだ。
「ん、おいしい!ワインみたいに芳醇」
「……知ったようなことを言う」
一気にグラスを空にしてしまったリョーマを見て、手塚は表情を和らげる。
「アンタも飲みなよ。ホントに美味しいから」
「ああ」
頷いて、手塚もグラスを口に運ぶ。ジュースを一口飲んで、手塚も小さく目を見張った。
「……確かに、これは美味いな」
「でしょ?日本の葡萄で作ったのかな」
「さあ」
甘い芳香を放ち、とても豊かな味わいのグレープジュースは、グラスを光に翳しても透けないほど濃く鮮やかな、赤みがかった葡萄色をしている。
「美しい色だ」
「オレ、グレープジュースって、大好きなんだ」
「そうか」
「だってほら、ちょっと血の色みたいで」
「え?」
「ねえ部長」
リョーマがグラスを机に置いて、手塚の傍に歩み寄る。
「キスの先、したくなった?」
「え……」
茶化すわけでもなく真剣な瞳でじっと見上げられて、手塚は微かに動揺した。頬に熱も集まってくる。
「アンタの中で、オレは、やっぱりキスの先に進みたくなるような対象じゃない?」
「それは……」
言い淀む手塚から、リョーマは視線を逸らす。
「アンタがしたいと思わなきゃ意味がないんだ。オレばっかりサカってても……」
直接的な言葉に手塚の頬がさらに熱を増す。
だがふと、手塚はひとつのことに思い当たった。机に飲みかけのグラスを置いて、リョーマを冷静に見下ろす。
「お前……俺を慰めるつもりなのか?」
「え?」
探るようにリョーマを見つめると、リョーマが小さく眉を寄せて手塚を見上げた。
「なにそれ」
「落ち込む俺の心を、救ってくれようとしているのか?」
「は?」
リョーマはさらにきつく眉を寄せる。
「なに?アンタ、オレの身体で憂さ晴らししたいの?」
「そんなことは考えていない」
逆に聞き返されて手塚は即座に否定する。
「俺はもうずっとお前のことを欲しいと思っている。初めてお前とキスした時から、俺は、お前のことで頭がいっぱいになっていた」
「…ホント?」
「ああ」
今度はリョーマから探るような瞳で見つめられ、だが手塚は、その瞳を真正面から受け止めた。
「もうずっと、俺は、お前と、キスの先へ進みたいと考えている」
リョーマの表情が和らぎ、ふんわりと頬が赤らむ。
「……でもね、部長……キスの先に進むなら、アンタに言っておかなきゃならないことがあるんだ」
「え?」
「心の準備がいるって前に言ったでしょ?」
頬を紅く染めたまま、しかしその瞳に暗い光を宿して、リョーマは言う。
(あれはリョーマ自身のことではなく、俺の方の心の準備だったのか…?)
訝しく思って手塚が口を閉ざしているとリョーマがじっと見つめてくる。
「部長、オレのこと、好き?」
「ああ、好きだ」
「ホントに?」
「どうやって証明すればいいんだ」
手塚が眉を寄せて尋ねると、リョーマは寂しげな瞳のままクスッと笑った。
「今から話すことをアンタが信じる信じないは自由だけど、もし、信じてくれないなら、オレはアンタの前から姿を消す」
「なんだって?」
「だから、ちゃんと最後まで聞いてて。オレの、話」
切なげに揺れながら、リョーマの瞳は真っ直ぐに手塚に向けられている。その瞳を見つめながら、手塚は深く頷いた。
「………」
リョーマは、ひとつ深く息を吐いてから、意を決したように、改めて手塚を真正面から、見た。
「オレ、普通の人間じゃないんだ」
「え……?」
「普通の人間には『ヴァンパイア』って呼ばれてる」
「!」
手塚は大きく目を見開いた。
すぐには信じられない話だ。
だがリョーマの瞳は、強い光を宿したまま、真っ直ぐに手塚に向けられている。
「……血を、吸う、のか?」
「吸わないよ」
ほんの少しだけ表情を和らげて、リョーマは続ける。
「オレたちが普通の人間と一番違うところは、寿命が長いってこと」
「寿命?」
「死なないワケじゃないみたいだけど、自分から死なない限り、一族の中では今まで病気とかで死んだ人って聞いたことない」
「………」
「血を吸うって思われているのは、何か別のバケモノと混同されているらしいってことと、あとひとつ、性的に興奮して、その興奮がピークに達すると、………その……牙みたいなのが伸びてきて、相手に噛みついちゃうから、それを『血を吸う』って勘違いされるみたいなんだ」
「噛みつく?」
リョーマは上目遣いで手塚を見つめながらコクンと頷いた。
「そして、その興奮状態のヴァンパイアに噛みつかれた傷口から唾液が直接その人の血液に混ざると、その噛みつかれた人も、似たような体質になっちゃうんだ」
「似たような?…ヴァンパイアになるわけではないのか?」
「ならない。……けど…」
「けど?」
「その人は、一生、定期的にヴァンパイアの体液を血液に混ぜないと、すぐに細胞が老化して、死んじゃうんだ」
「…どういうことだ?」
「オ
レたちの身体は、死なないように、体内にウィルスが入って来られない性質だし、怪我しても驚異的なスピードで回復するようにできているんだ。だから、一度
『ヴァンパイアもどき』になった人が、血液の代謝でヴァンパイアの体液が排出されてその性質だけ残った状態になっちゃうと、制御機能が働かなくなって、細
胞が暴走して老化しちゃうんだって」
「……まさか、俺の肩が治ったのは…」
「うん。オレとキスして、アンタが一時的にほんの少しだけヴァンパイア化したからだよ」
あの甘い唾液が、手塚の身体にそんな変化をもたらしていたのだと。
「………そうだったのか…」
手塚は、やっと謎が解けたような心境になって頷いた。
不思議と、リョーマを疑う気も、恐れる気も、手塚には湧いてこない。
「……アンタ、信じる?オレの話、全部」
リョーマが縋るような瞳で手塚を見上げてくる。
手塚はそんなリョーマをじっと見つめてから、ふわりと微笑んだ。
「信じよう」
「え!」
手塚の言葉が心底意外だったらしく、リョーマは大きな目をさらに大きく見開いた。
「ウソ!ホントに?」
手塚の腕を掴み、食い入るように見つめてくるリョーマに、手塚は大きく頷いてみせた。
「ずっと不思議に思っていたんだ。かかりつけの医者には重症だと言われた肩が、治療先についてみれば軽傷に変わっていた。あんな短期間でコートに戻って来られたのは、全部お前のおかげだったんだな」
「ぶちょう……」
「それに、俺の身体がベストコンディションを保てるように、大会中もずっとキスしてくれていたんだろう?」
「ぁ……」
「ありがとう、リョーマ」
「…っ!」
微笑んで礼を言うと、リョーマの瞳からポロポロと透明な雫が零れ落ちてきた。
「リョーマ?」
手塚が慌てて涙を拭ってやると、リョーマは倒れ込むように手塚の胸に身を寄せてきた。
「お礼なんて……オレが、言いたいのに……」
「え?」
「アンタみたいな人、初めて逢った。……こんなに優しくされたの、初めて……」
「リョーマ…」
「オレのこと、どんなに好きだって言っても、本当のことを話すとみんな疑って怒り出したり、怖がって逃げていったりした。なのにアンタは逃げないどころか、お礼なんか…言っちゃって……っ」
「俺の素直な気持ちなんだが……困るのか?」
小さく震える髪を撫でてやりながら優しく問うと、リョーマがコクリと頷いた。
「困るよ……アンタのこと、本気で好きになっちゃった……」
「今まで本気じゃなかったのか?」
俯くリョーマの前髪を優しく掻き上げて顔を覗き込むと、リョーマがチラリと濡れた瞳を向ける。
「だって……本気になって、また逃げ出されたら、やってらんないよ」
「そうか……そうだな……本気になることが、恐かったのか…」
「ん…」
「ならば、俺のことは、本気になってくれるのだろう?」
「………」
「俺では役者不足か?」
ブンブンと、リョーマが首を横に振る。
「好きに、なっていい?」
潤む瞳に見つめられて、手塚の胸の奥で甘い焔が揺らめく。
「ああ」
「アンタの体質、変えちゃうかも…」
「そうしてくれないと困る。俺はお前と、ずっと一緒にいたい」
「ぁ……」
ぐっと強く腰を抱き寄せて吐息混じりに囁けば、リョーマは甘い声を漏らした。
「キスの先へ、進んでいいか?」
額に口づけてやると、新たな涙を零しながらリョーマが笑う。
「………うん」
「リョーマ…」
堪らなくなってギュッと抱き締めてやると、同じくらい強く抱き締め返された。
普通の人間ではないと言われて、確かに最初は驚いた。
だがリョーマの話を聞いているうちに、心の奥に、むしろ歓喜が込み上げてきていたことに、手塚は気づいている。
(普通の人間の寿命では、お前を愛し尽くせそうにないからな)
「……明かりは、消した方がいいのか?」
リョーマの耳元で愛を囁くように尋ねると、リョーマの身体がビクリと揺れた。
「ん……ホントは、明るいのはあんまり得意じゃないんだ…」
「そうか」
だからリョーマはいつもキャップを目深に被っているのかと、手塚は日常の細かなことを、ひとつ納得した。
「これならいいか?」
手塚はベッドサイドにある小さなライトを点け、部屋の照明を落とした。
「うん……」
リョーマは手塚から視線を逸らして俯いた。
「リョーマ?」
「ぁ…の、オレ………キスの先は、初めてだから、その……」
「俺も初めてだ」
微笑んで、優しく囁きながら抱き寄せると、華奢な身体は可哀相なくらいに緊張していた。
「リョーマ、俺を見てくれ」
「………」
手塚の言葉に、リョーマはゆっくりと顔を上げる。
「好きだ、リョーマ」
胸に込み上げてくる想いを何の飾りも付けずに告げると、リョーマの瞳が大きく見開かれた。
「オレ、も……」
「リョーマ」
そっと両手で柔らかな頬を包み込み、ゆっくりと唇を重ねてゆく。
睫毛を微かに震わせるリョーマの表情を盗み見ながら舌を絡め、手塚は一枚一枚、リョーマの服を剥いでゆく。
やがて全ての服を取り去り、真珠のような肌が露わになると、リョーマはギュッと手塚にしがみついてきた。
その背中に、肩に、脇腹に、腰に、そして柔らかな双丘に両手を滑らせ、また這い上がらせて頬を包み、唇にも額にも瞼にも、口づける。
そうしてまた深く舌を絡め合い、艶やかな水音をしばらく室内に響かせてから、手塚がリョーマを抱き上げた。
「わ」
「リョーマ…」
そっとベッドにリョーマを下ろし、そのままのし掛かる。
「リョーマ……リョーマ……」
「ぁ……ぶちょ……ぁ、ん」
顔中に口づけ、首筋に舌を這わせ、そのまま滑り降りて鎖骨を吸い上げ、小さく尖った乳首に辿り着く。
「あっ、ぁ、んッ、や、ぁ、んッ」
舌先で蕾を転がし、コリコリと優しく歯を立ててから、思い切りきつく吸い上げる。
「ぁあんっ」
途端にビクビク痙攣を起こすリョーマの身体を強く抱き締めると、すでに熱く変化を始めたリョーマの雄が、手塚の腹に当たった。
「もう感じているのか?」
「だっ……て……気持ちいい…」
「ああ……気持ちいいな……」
眼鏡を外してベッドサイドのローボードの上に置き、リョーマの胸に頬を擦り寄せて瑞々しい肌の感触を楽しみながら、手塚はそっと手の平を滑らせてリョーマの性器に触れる。
「あっ、んっ」
途端にリョーマの身体が強ばり、大きく揺れる。だがその身体はすぐに甘く解けだし、ゆっくりと、大胆に、開かれてゆく。
「あっ、あぁ…ぶちょ……っ」
「名前を、呼んでくれないのか?」
「……ダメ、名前は……アンタが、……あっ」
何か言いかけるリョーマの言葉を手塚は口づけで封じ込める。
「んっ、んっ」
強弱をつけてリョーマの雄を扱いてやると、手塚の舌先に触れるリョーマの犬歯が少しずつ尖り始めた。
「リョーマ…」
「あぁ、んんっ」
吐息混じりに名を呼べば、リョーマの性器も、「牙」も、さらにグンと尖る。
「あ……あ……」
リョーマが瞳を潤ませて手塚を見つめる。
「……もっと……奥に触れて欲しいのか?」
「ん……」
コクコクとリョーマが頷く。
「…ちょっと待っていろ」
手塚はゆっくりと身体を起こしてベッドから降り、机の引き出しの奥から、今の季節は使っていないハンドクリームを取り出した。
ベッドに戻りながらチューブのフタを開け、手の平に出して指先に馴染ませる。
「ぶちょ…」
「ん?」
ベッドに乗り上げて、微笑みながらリョーマを見下ろしてやると、リョーマも小さく微笑んだ。
名を呼ぶだけで、名を呼ばれるだけで、互いの想いが伝わってくる。
「リョーマ…」
「ぶちょ……ぁ…」
クリームで滑る指先でリョーマの秘蕾を探ると、リョーマの身体がまた少し強ばる。
「怖がるな…ゆっくりするから…」
頷くリョーマに微笑みかけ、手塚は言葉通り、ゆっくりゆっくり、中指を秘蕾の奥へとめり込ませてゆく。
「ぁ……っ」
「痛いか?」
フルフルと、リョーマが首を横に振る。
それを確認して、手塚はさらに深くまで、中指を押し込んだ。
「ん…っ」
リョーマの頬がさらに赤く染まり、唇から甘い吐息が零れる。
手塚はゆるゆると指を回し始め、リョーマの熱い腸壁を撫でてやる。
「ぁ……ぁ……あ、んっ」
リョーマの腰が微かに揺れだし、呼吸が乱れてゆく。
一旦指を引き抜き、人差し指も添えて再びリョーマの胎内へ埋め込む。
「ぁ……は、んっ」
痛がる様子がないのを見て取り、手塚はさらに薬指も添えてリョーマの腸壁を嬲った。
「あぁ、あ、んっ」
リョーマの腰がユラユラと揺らめく。その中心では、固く尖った性器の先端から、トロトロと蜜が零れ始めていた。
手塚はリョーマの胎内を嬲りながら、その尖った性器を口の中へと招き入れた。
「あっ」
リョーマの腰がビクビクと痙攣を起こす。
「ダメ…っ、気持ち、いい……っ」
トロトロと湧き出てくるリョーマの蜜を舐め取ると、手塚の身体が熱くなり、腕の違和感がゆっくりと退いていった。
「唾液よりも効果覿面、か…」
そっと呟いた手塚の言葉は、きっと今のリョーマには届いていない。
「あっ……やっ……もっと……っ」
「ああ、もっと、気持ち良くしてやる」
手塚は再び身体を起こし、リョーマの熱い視線を感じながら、ゆっくりと衣服を脱ぎ捨ててゆく。
そうしてリョーマの目の前で、固く立ち上がった自分の性器にハンドクリームを塗りたくり、緩く扱いて見せた。
「あ……あ……ぶちょ……っ」
「挿れてもいいか?」
リョーマにのし掛かりながら問うと、潤んだ瞳を嬉しそうに細めてリョーマが頷く。
だが手塚はリョーマの後孔に先端を宛ったところで動きを止めた。
「ぶちょ…」
「俺の名前、知っているだろう?」
「ぁ……」
「名前を呼んでくれ」
「ゃ……そんな、こと、したら、アンタが……」
「俺の心がお前のものになる、か?」
潤んだリョーマの瞳が、目一杯大きく見開かれる。
「知ってたの…?」
「ああ。そんなことだろうと思っていた」
頑なに自分の名を呼ばないリョーマに、何か理由があるとは思っていた。
おそらくリョーマの一族は、その長い歴史の中で、子孫を残すために、自然とそのような『術(すべ)』を身につけていったのだろう。
相手を意のままに操り、心もカラダも自分のものにし、歴史を繋いできたのだろう。
普通の人間たちに受け入れられなかった彼らの、それはとても悲しい術だと手塚は思う。
「俺の心がお前のものになるなら本望だ。だが俺は、そう簡単にはお前の思い通りにならないぞ?」
「え…?」
「俺の想いの強さを、お前はまだ知らないだろう?」
「ぁ……」
潤んだリョーマの瞳から、一粒の大きな雫が零れ落ちる。
「俺の名を呼んでみろ、リョーマ」
「……」
「お前が好きになった男は、誰だ?」
「ぁ……」
リョーマがおずおずと手を伸ばして手塚を引き寄せる。
「く、に…」
「ん?」
「くに…みつ…」
リョーマの震える指先が、手塚の髪に触れる。
「国光……国光……オレを……愛して……」
震える声で囁かれ、手塚は心いっぱいに溢れ出す恋情に、苦しささえ感じた。
「国光……」
「ああ、愛している。とっくの昔から、だ」
クスッと微笑んでやると、リョーマが目を見開いた。
「国光……平気、なの?」
「今言っただろう?俺はもうずいぶん前からお前を愛しているんだ。今さら愛せと命令されたところで、そんなものでは、俺の心は拘束できない」
「ぁ……」
見開いたリョーマの瞳からポロポロと雫が零れ落ちてゆく。
「リョーマ、もっと俺の名を呼んでくれ」
「国光…」
「そうだ。もっと……」
「国光、国光、国光!」
「リョーマ」
「あぁっ!」
一気に奥まで、手塚は尖りきった雄をリョーマの胎内に突き立てた。
「あっ、あぁぁっ!」
グッと締め付けられたと感じた次の瞬間、リョーマは勢いよく熱液を噴き上げていた。
ピクピクと小刻みに身体を痙攣させ、リョーマが堪えていた熱をすべて吐き出してゆく。
「く…っ」
目一杯締め付けられ、危うく手塚も達してしまうところだったが、歯を食いしばって何とか堪えた。
はぁはぁと胸を大きく上下させて、リョーマの身体は一気に弛緩してゆく。
だがその中心では、未だ芯を持った雄が柔らかく尖って天を向いていた。
「リョーマ…」
「………」
荒い呼吸のまま、涙で濡れたリョーマの瞳が手塚を捕らえる。
「リョーマ…」
手塚がゆっくり腰を揺すり出すと、リョーマは小さく眉を寄せて唇を噛み締めた。
「リョーマ…」
「んっ……あっ」
次第に動きを大胆にし、抉り上げるように腰を回すと、リョーマが小さく叫んで仰け反った。
「ああ……リョーマ…っ」
目の前に晒された白い喉に唇を寄せ、舌を這わせる。
「ぁ…っ」
「リョーマ…」
自分の呼吸が乱れていくのがわかる。
狭い器官に締め上げられ、熱い腸壁にまとわりつかれ、そのあまりの快感に我を忘れそうになる。
「リョーマ…っ」
深く繋げた身体を、もっともっと深く溶け合わせたい。
「あっ、あっ、あ、あ、…っ、やっ、スゴ、イ……っ」
「う、あっ、リョーマ…リョーマ…っ」
夢中で叩きつける手塚の腰に、リョーマの脚が絡みついてくる。
「あぁっ、んんっ、あぁっ、やぁぁっ」
ガクガクと揺さぶられ、甘い嬌声を上げ続けるリョーマの口元から、尖り始めた「牙」が見え隠れする。
「もっと……もっと……」
「ああ…もっと……リョーマ、もっとだ……っ」
奥へ奥へと何度も抉り込み、最奥で腰を大きく回してやる。
「ひっ、ゃ…ぁ、あぁっ、んっ、あっ」
「気持ち、いいか……?」
抉り上げながら問いかけると、リョーマは涙を零しながら譫言のように「イイ」と繰り返した。
覆い被さって口づけると、リョーマの「牙」は完全に尖りきっていた。
「…イきたいか?リョーマ」
「あ……ヤ、ダ……っ」
ポロポロと涙を零し、頬を、いや全身を紅く染め上げ、手塚の動きに合わせるように腰を振りながら、リョーマは首を横に振る。
「やっ……いや…だっ」
そんなリョーマの様子に、手塚の心が甘く軋む。
(俺をその牙で犯したくない…と…?)
こんな状態でありながら、尚、自分のことを気遣うリョーマに、手塚の胸が熱くなる。
だが。
「あぁぅっ!」
腰に巻き付いていたリョーマの脚を引き剥がして大きく左右に広げ、繋がり合う部分がリョーマからよく見えるように腰を持ち上げてやる。
「見えるか?……お前はもう、俺のものだ」
深く打ち込んでいる肉剣を緩く出し入れしてみせると、リョーマが目を大きく見開いて接合部分を見つめ、さらに頬を紅くしていく。
「ぁ……ぁ……」
「……なのにお前は、俺をお前のものにはしてくれないのか?」
「………っ」
大きな瞳がゆっくりと動き、手塚を捕らえる。
「俺を、お前と同じものに、してくれ……リョーマ」
「ぁ……」
新たな涙がリョーマの頬を伝う。
「俺を一生、離さないでくれ」
「国光……」
「俺は、お前だけ愛せればいい」
「国光…」
「それだけでいいんだ」
ギュッと抱き締めてやると、リョーマもギュウと抱き締め返してくる。
「国光っ」
「リョーマ…っ」
見つめ合い、互いに引き寄せ合うようにして夢中で口づける。尖りきったままのリョーマの牙の裏側を舌先で舐め上げてやると、リョーマの胎内がヒクヒクと痙攣した。
「あぁ……国光……大好き……」
「リョーマ…」
見つめ合いながら深く繋げた身体を揺らし合う。
「ぁ……ぁあ……っ」
リョーマの首筋に口づけ、まるで血を吸い上げるようにしてきつく痕を残す。
「ぁあんっ」
リョーマの身体が快感に痙攣する。
「リョーマ」
「やっ!」
手塚はリョーマを抱きかかえて身体を起こした。
深く手塚を銜え込んだまま向かい合わせに座る形になり、リョーマの胎内へ、さらにぐっと肉剣がめり込んでゆく。
「ひ……あ……っ」
「くっ」
ベッドを大きく揺らしながらガツガツと突き上げてやると、リョーマは声すら発することができないように、口を大きく開けて喘ぐような呼吸を繰り返し始めた。
「リョーマ…っ」
「……っ、…っ!」
細い腰をしっかりと掴み、リョーマのスイートスポットに剣先が当たるように角度を変えてやると、リョーマが叫び声に近い甘い嬌声を上げた。
「やぁあぁ…っ、あぁぁっ、あぁっん、あぅっ」
抉り込み、突き荒らし、間断なく揺さぶり続けるうち、固く閉ざされていたリョーマの瞳が徐々に開き始めた。
大きな声で喘ぎながらも意識が朦朧としているのか、その瞳の焦点が合っていない。
(瞳の、色が……)
普段の茶褐色から金色に近い色に変わって見える。
手塚は突き上げ続けながら、リョーマの目の前にわざと自分の首筋を晒すように見せつけた。
「ぁ……あぁ……っ」
はっきりと、リョーマの瞳が金色に変わった。
その次の瞬間、手塚はリョーマの「牙」が自分の首筋深くめり込むのを感じた。
「あぁ……」
「………」
不思議と痛みはなかった。
それよりも、牙を打ち込まれた場所から甘い痺れが全身に広がり、今まで味わったことのない強い快感に支配されてゆく。
「ん……」
リョーマの身体がぶるりと震え、手塚の腹に熱い液体が掛けられた。
手塚の首筋に噛みついたまま、リョーマは達していた。
「あ……リョーマ……っ」
手塚の首筋から離れないリョーマを包み込むように抱き締め、手塚はゆっくりと身体を倒してリョーマの身体をベッドに深く沈める。
「んっ」
その体勢のまま、奥へ奥へと腰を揺すり、リョーマの最奥のさらに奥を抉るように腰を回すうち、キツイ射精感が込み上げてきた。
「リョーマ……出すぞ…っ」
リョーマの耳元で熱く囁くと、リョーマの牙がさらに深く手塚の首筋に食い込む。
「あぁ…っ」
全身が燃え上がるような快感の中で、手塚はリョーマの奥へと熱い飛沫を叩きつける。
「…っう、くっ……ぅ、あっ」
長く尾を引く絶頂の中で、手塚は何度も楔を打ち込んで、リョーマの胎内を熱い精液でたっぷりと満たしてゆく。
「ん……ん……」
腰を打ち込まれるたびリョーマが甘えるような声を零してギュッと手塚にしがみついてくる。手塚もさらに締め上げられ、また新たな快感に射精が止まらない。
それでもゆっくりゆっくりと絶頂の波が退いてゆき、リョーマの奥深くで最後の射精を終えた手塚は、きつくリョーマを抱き締めたまま、深く息を吐き出した。
「……リョーマ?」
少しだけ呼吸が整い始めた頃、腕の力を緩めてリョーマの顔を覗き込むと、すでにリョーマの牙は消えていて、犬歯が正常な長さに戻っていた。
「………」
「……リョーマ?」
「……ごめん…」
涙声で、リョーマが呟く。
「どうして謝るんだ?」
「だって……」
リョーマは手塚の首筋にくっきり残る傷を見つめ、そっと舌を這わせる。
「ん…」
手塚が声を零すと、ハッとしたようにリョーマが顔を上げた。
「痛い?」
「違う」
ふわりと微笑んで、手塚はリョーマの髪を撫でてやる。
「『感じた』んだ」
「な……っ」
リョーマの頬が再び真っ赤に染まる。
「い、痛くないの?」
「ああ、痛くない」
「ウソ」
「じゃあ、お前のここは、痛いか?」
そう言ってまだ繋がり合っている腰を揺らすと、リョーマが小さく声を上げて身体を震わせた。
「……痛く、ないよ」
「良かった」
髪を撫でていた手をずらして頬に触れ、そっと唇を寄せるとリョーマは素直に手塚を迎え入れてくれた。
しっとりと舌を絡ませ合い、互いの唇を柔らかく噛み合う。
しばらくそうして口づけ合っているうちに、リョーマにやっと笑顔が戻ってきた。
「国光……大好き…」
「俺もだ……愛してる…」
「ぁ……よかった…傷、治ってきた…」
そう言ってリョーマが、傷があったはずの手塚の首筋に口づける。
「ならば、もう一度つけてくれないか?」
「え…?」
吐息とともにリョーマの耳元で囁くと、リョーマが驚いたように手塚を見つめてきた。
「ぇ…でも……あ、んっ」
答えを待たずに腰を揺らせば、すぐにリョーマがしがみついてきた。
「ぁ…あっ、やっ、出てくる…っ」
手塚がゆっくり肉棒を出し入れすると、リョーマの胎内から手塚の放った精液が溢れ出してきた。
「…お前の中にも、俺の体液が染みこんだか?」
「………えっち」
クスッと笑ってリョーマが手塚の胸に顔を埋める。
「こんなんじゃ足りないよ。もっと…もっといっぱい…オレの奥に出してくれないと……」
「ああ。俺も足りない。もっと…お前の牙に貫かれたい…」
囁き合い、口づけ合い、再び込み上げてくる情欲に逆らわず、二人はベッドの上で深く繋いだ身体を揺らし合う。
「あぁ……国光……」
「リョーマ……お前は最高だ……」
「国光…っ、ぁあんっ」
グチャグチャと、接合部分から大きな粘着音が響く。
尖り始めるリョーマの牙を見つめながら、手塚は満ち足りた笑みを浮かべた。
 エピローグへ→ エピローグへ→
掲示板はこちらから→
お手紙はこちらから→

20071101
|