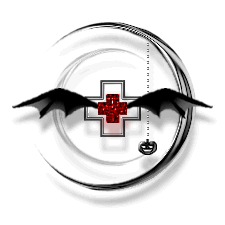
Trick or treat or LOVE
<エピローグ>
二人が結ばれてから二ヶ月が過ぎた。
今日はハロウィン。
魔物が堂々と街を闊歩する祭。
「Trick or treat!」
部活を終えたリョーマが、たぶん真っ直ぐ手塚の家にやってきた。
「あらあら、元気ねぇ」
手塚とともに玄関までで迎えに来た彩菜が、リョーマにキャンディーの入った小さな巾着を渡す。
「わ、オバサン、ハロウィンのこと知ってるんスね」
「ええ、知っているわよ。楽しいお祭りですもの。越前くん、ごゆっくりね。後でグレープジュースをお持ちするわ」
「アリガトございます!」
シューズを脱ぎながら礼を言うと、彩菜はニッコリと微笑んでキッチンへと姿を消した。
「そう言えば、いつもあのジュースどこで買うのか聞き忘れちゃうんだ。あとで訊いてみようかな」
「あれは、フランスでワイン工場を経営している友人に送ってもらっているそうだ」
「え、じゃあ、普通には売ってないんだ?」
「ああ」
なーんだ、と唇を尖らせるリョーマを微笑みながら見つめ、手塚はそっとリョーマの肩を抱き寄せる。
「部屋へ行こう」
「うん」
うっとりと見上げてくるリョーマの額にチュッと軽く口づけ、手塚はリョーマを連れて自室に向かう。
部屋に入るとすぐに彩菜がジュースを持ってきた。
「越前くん、オバサンね、ちょっと出掛けてくるから、ゆっくりしていってね」
「ぁ、はい」
「よかったらお夕飯もどうぞ。今日はカレーにしたの」
ニッコリと笑いかけられ、リョーマも「はい」と言って微笑み返す。
「もう外暗いから、オバサン、気をつけてね」
「あら、ありがとう。大丈夫よ、私、こう見えても強いから」
コロコロと笑って彩菜は部屋を出て行った。
「こんな時間からどこ行くんだろ?」
「さあな」
リョーマが家に来ると度々母は姿を消す。
以前行き先を尋ねてみたが、母は「お友達の家」と答えるだけで、詳しいことは教えてくれなかった。
もしかしたら自分たちに気を遣ってくれているのではないかと手塚は思う。だからこの頃は、母の行き先を尋ねるような無粋なことは、もうしない。
「強いって、何か習ってンの?空手とか?」
「いや?」
早速ジュースを飲みながら不思議そうに訊ねてくるリョーマに微笑んで答え、手塚もグラスを口に運ぶ。
「オバサンて、何か不思議な感じ」
「そうか?」
「うん。フランスとか、海外にはよく行くの?」
「俺はまだそれほど多くは海外へ行ったことはないが……あの人はいろいろな国を回ったことがあるらしい」
「へえ。意外」
「お前の両親も、今までいろいろな国を巡ってきたのだろう?」
「うちはいろいろって言うより、日本とアメリカの往復が多いみたいだけど………いや、うちと比べたってしょうがな…」
言いかけて、リョーマは急に表情を変えた。
「まさか……オバサンって……?」
目を見開くリョーマに、手塚はクスッと笑ってみせた。
「お前の一族とは違う系統だが、な」
「ちょっ、待って、じゃあ、アンタ……」
「…残念なことに、母の一族は『感染』はしないんだ。だが、愛し合う相手を同じ体質に変えることは出来なくても、その子どもには、かなりの確率で『遺伝』する」
「!」
言葉を失くすリョーマに、手塚はさらに微笑みかけた。
「お前を一目見た時に、母にはお前の血筋がわかったらしい。だから、このグレープジュースを出したそうだ」
「え……?」
「お前の一族は昔からごく稀に吸血行為をする者が出るそうだ。だから、その衝動を抑えるためにも、お前の一族には赤ワインを好んで飲む者が多いと」
「だから、オレには、ジュース……?」
手塚は頷いて、また美しい赤紫色の液体を一口飲む。
「何で言ってくれなかったんだよ……最初から言ってくれたら、オレ……」
「俺も最近になって一族のことを知らされたんだ。だが、俺はどうも半端に母の血を受け継いだらしくてな……軽い予知能力があることと、運動能力には長けているが、肉体は普通の人間と変わらないんだ。だから、怪我で苦しんでいたのは本当だ」
「そ……なの?」
「ああ」
頷いて、手塚はリョーマを引き寄せる。
「だから、お前には本当に感謝している。俺を好きになってくれてありがとう、リョーマ」
そっと額に口づけると、リョーマが甘い吐息を零しながら胸に顔を埋めてくる。
「………だから、アンタはこんなにいい匂いがするのかな…」
「ん?」
手塚の腕に包まれながら、リョーマがじっと見上げてくる。
「最初に電車の中で逢った時、アンタからすごくいい匂いがしたんだ。だからすごく気になって……そうしたらアンタもオレのこと追いかけてきてくれて……嬉しかった」
「そうか」
「うん」
互いの中にある、似たような『何か』が引き寄せ合ったのか。
それとも、これこそが『運命の出会い』だったのだろうか。
(どちらでも構わない)
リョーマを抱き締めながら、手塚は思う。
運命であれ、必然であれ、単なる偶然であれ、こうしてリョーマを腕の中に抱くことができる現実が、手塚には何よりも重要で愛しい。
母親から一族のことを告げられた時、「本当は話さないつもりだった」とも告げられた。
遺伝により歴史を繋いできた母の一族には、ごく稀に、一族の血を引きながらその能力や体質を全く受け継がない者が生まれ出でる。
(それが俺だったというわけだ)
一族として生まれながら、手塚は普通の人間と全く変わらない肉体で生まれたのだ。だから母は、一族のことを知らずに生き、普通の人間として生を全うできるならその方がいいと思っていたのだと話してくれた。
(でも俺は、リョーマと出逢った)
誰よりも、何よりも、大切で愛しい存在に出逢った。それが、長い時を生きる宿命を負った、リョーマだったのだ。
そして、二人の関係に気づいた母は、手塚に一族の話をする決意をした。
母によれば、契りを交わさずとも手塚の肩が治癒したのは、リョーマの一族の血と母の一族の血との相性が抜群に良いかららしい。だから、リョーマの体液が手塚の血液でなく、体内に取り込まれただけで、軽いヴァンパイア化が起こったのだ。
つまり、手塚の肉体は父と同じ「普通の人間」であっても、そこに流れる血は、まさに母の一族のものだったのだろう。
今思えば、リョーマに名を呼ばれても魂を奪われることがなかったのは、想いの強さ以外にも、この血のおかげもあったのかもしれない。
「お前のおかげで、俺は永遠に、愛する相手と一緒にいられるんだ。こんなにも幸せなことはない」
「国光…」
「ありがとう、リョーマ」
「大好き、国光…」
互いに唇を寄せ合い、チュッと音をさせて口づけ、見つめ合い、微笑み合い、そしてさらに深く甘く、舌を絡め合ってゆく。
「そろそろお前が足りなくなってきたんだ。また、お前が欲しい」
「週末にあんだけ補充したじゃんか」
クスクスと笑いながらリョーマが言う。
本来ならば、「体液の補充」は、月に一回程度で充分なはずだった。だがそんなに間隔を空けていたら、リョーマを求めすぎる手塚の心が干からびてしまうだろう。
「お前が足りなくて死にそうだ。助けてくれ」
本当は毎日でも、いや、ずっと身体を繋げたままでいてもいい。
耳元で甘く囁くと、リョーマの身体が小さく震え、その愛らしい唇から甘い吐息が零れた。
「…ばか」
二人でベッドに移動し、甘く見つめ合う。
「リョーマ」
「ん?」
額を擦り合わせて名を呼ぶと、リョーマが微笑みながら答えてくれる。
「Trick or treat…」
囁きながら、リョーマの甘い唇にそっと口づける。
「…… or Love」
リョーマが手塚の首に腕を回す。
「Love…please…」
「……リョーマ…」
きつく抱き締め合い、二人の艶やかな吐息が部屋を満たしてゆく。
「……そう言えばリョーマ、お前本当は何歳なんだ?」
「ナイショ」
魔物が街を闊歩する祭の夜。
ここには、二人だけの時間が流れていた。
HAPPY ENDLESS

掲示板はこちらから→
お手紙はこちらから→

20071102
|