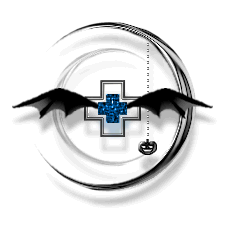
Trick or treat or LOVE
<1>
その少年は唐突に現れた。
そうして、その場にいた全ての者の目を惹きつけ、心を捕らえた。
「ねえ、うるさいんだけど」
乗客の少ない電車の中。
大声で騒ぎ、あまつさえテニスのラケットを取り出して振り回していた一団に向けて、その少年は声を掛けた。
少し離れた座席から彼らの様子を見ていた手塚は、浮き上がりかけていた腰をゆっくりと下ろした。
少年が彼らを注意しなければ、自分が声を掛けにいこうと思っていたのだ。
相手は高校生くらいと思えるが、年上だろうが年下だろうが、他の乗客の迷惑になることを平然と行う人間を、手塚は放置できない。
だが手塚が出ていくまでもなく、その少年のおかげで、彼らは静かになった。
少年は小学校高学年くらい。身体の線は細く、だが、ハーフパンツから伸びる脚は、ただ細いだけでなく、鍛え上げられ、引き締まった綺麗な筋肉を纏っていた。
彼の身長ほどもありそうに見える大きなバッグの中には、たぶん、テニスのラケットが入っている。
そのバッグやシューズと同じメーカーのキャップを目深に被り、ひと騒動済んでから、彼は立ち上がった。
向かいにいた「騒がしかった集団」が一瞬身構えたが、少年は彼らには目もくれず、こちらに歩いてきた。おおかた、駅に着いた時に階段に近い扉で降りられるように、車両の中を移動しているのだろう。
少年が近づくにつれ、その顔立ちがしっかりと見えてきた。
(ずいぶんと……)
綺麗な顔立ちをしていた。
真っ直ぐ前を見つめる大きな瞳、長い睫毛、スッと通った鼻筋、仄かに色づくぽってりとした唇。
テニスをしているようなのに日焼けは見られず、その肌はまるで淡く発光しているかのように真珠のような輝きを放っていた。
その大きな瞳が、チラリと、こちらに向けられる。
「!」
手塚は表情には出さなかったが、その視線を向けられた瞬間、呼吸も、鼓動も、時間も、全てが停止したような錯覚を覚えた。
そして、自分たちだけが、異質な空気に包まれるような感覚。
(……なんだ?)
だがその錯覚や感覚は、少年の視線が手塚から外れるのと共に、一斉に消し飛んだ。
ふいに異世界から現実世界に戻されたように、手塚は軽い眩暈を覚える。その眩暈を振り切って顔を上げた時には、少年はすでにホームに降り立っていた。
(今のは…?)
手塚は自分でも気づかぬうちに立ち上がり、締まりかけた電車のドアからホームへと飛び出していた。
(あの少年は…?)
ホームを見回すが、少年の姿がない。
慌てて階段を駆け下り、改札に向かうが、そこにも少年はいなかった。
(見失った…か)
諦めて帰ろうと思った手塚の目の前を、先程の「お騒がせ集団」が横切った。
「今日は弱っちいヤツばっかだから、俺なら楽勝だぜ」
「さっすが佐々部、言うことがデカイなぁ」
「優勝したら奢ってくれるんでしょ?」
相変わらず人目をはばからず大音響で騒ぎながら歩いてゆく一団を見送り、手塚は小さく溜息を吐いてから、ふと思い出した。
(そう言えば、さっきの少年もテニスバッグを…)
もしやと思い、手塚はその騒がしい集団の後に付いていった。
再び少年を見つけたのは、敷地の外れにあるコートの中だった。
騒がしい集団が向かったのは柿の木坂テニスガーデン。今日はそこでジュニアテニストーナメントが行われていた。
試合が行われているコートを片っ端から見て回ったが少年を見つけることはできなかった。
(ここにはいないのか…)
当てが外れたのだと思い、本来向かおうとしていた場所へ行こうと歩きかけ、手塚は立ち止まった。
(音…)
誰かが、練習用のコートでボールを打っている。片方は抜群にいい音をさせ、もう片方は並の上、といったところか。
(練習用コートで、試合…?)
何となく興味を引かれ、手塚はその音のするコートへと向かった。
「…!」
そこに、先程の少年がいた。
しかもやはり先程電車の中で騒いでいた連中のリーダーらしき男とコートで向かい合っている。
(試合、なのか?)
正式な試合ではないのでスコアはわからないが、短いラリーを見ていて、大体の試合展開が手塚にはわかった。
いや、二人の表情や雰囲気からしても、どちらが優勢であるのかは明確だった。
(いいショットを打つ…)
華奢な見た目からは想像もできないような強い打球を、少年は平然と打ち込んでくる。息も乱れていない。
長身の相手がネットに出られないようにわざと深いショットを打ち込むあたりも、なかなか冷静に見える。
だが。
「待てよ!今のアウトじゃねーの?」
相手プレーヤーの仲間の一声で、場の空気が澱んだ。
セルフジャッジなのをいいことに、少年が放つライン際の深いショットを、悉くアウトと言い始めた。
(見苦しい…)
手塚は自分が出ていって審判を務めようかと身を乗り出したが、思い留まった。
コート内には見知った顔がいた。
(竜崎先生?)
なぜ自分の学校のテニス部顧問である竜崎がそこにいるのかはわからないが、どうやら少年とは知り合いらしく、時折頷きながら少年を黙って見守っている。
(…さあ、どうする?)
確かに、少年がどう対処していくのかが、見てみたくなってきた。
手塚もゆっくりと腕を組み、状況を見守る。
少年は深いショットをやめ、少し浅めに打つようになった。すかさず相手がネットに出てくる。だが少年はそれを待っていたかのようにロブを上げ、まんまと相手を出し抜いた。しかも、ボールにスライス回転をかけ、ライン上でわざわざ止めて見せている。
「やるな」
フッと小さく笑いながら手塚は呟いた。
(格が違いすぎる)
この試合はたぶん相手の男から吹っ掛けたのだろうが、少年だと侮ったあの男はどこまでも浅はかだと手塚は思う。
あの少年の実力は、おそらく、こんな小さな大会を制しただけで満足するようなレベルではない。
(うちのレギュラーにも引けを取らない)
いや、「引けを取らない」どころか、上回るかもしれない。
何年か先には、あの少年の名を知らない者はテニス界にはいなくなるだろう。
手塚がそう確信を持った時、そのアクシデントは、いや、その事件は、起きた。
男が、上がったロブを打とうとして手が滑ったかのように、少年に向けてラケットを投げつけたのだ。
(なんてことを……っ)
またラケットが人を傷つけるために使われてしまった。
手塚の胸に、苦い想いが込み上げる。
少年の姿が、二年前の自分とダブって見えた。手塚も先輩にラケットで左腕を殴られ、負傷した経験がある。今もその傷は、心身共に手塚を苦しめ続けているほど深い。
だが少年の様子はあの時の手塚とは違うようだった。
明らかに額から出血しているのに、少年は平然と試合を続けている。
しかも。
「あれは……ツイストサーブ…?」
少年はキレのいいツイストサーブを、相手に向けて連発した。
そうして少年は、呆気なく年上の男に勝利した。
竜崎に声を掛けられて二言三言話した少年は、ジャージを着込み、あの大きなバッグを担いでコートから出てきた。
先程出血していたのを思い出し、手塚はコートから離れたところで少年を呼び止めた。
「君…」
「え?……ああ、見てたの?」
少年はまるで知り合いにでも会ったかのように小さく笑って手塚の前に立った。
「さっき同じ電車に乗っていた人、だよね?」
少年が自分を覚えていたことに内心驚きながら、手塚は頷いた。
「怪我は…」
「べつに」
「見せてみろ」
「わ」
コートに血が滴り落ちていたというのに「べつに」どころではないだろうと思い、手塚は少し強引にキャップを取り、少年の額を覗き込んだ。
「?」
確かに少年の額には血を拭き取ったような痕は残っているが、どこにも傷はなかった。
「すまない、出血していたと思ったんだが……怪我は、していないのか?」
「してないよ」
そう言って、少年はクスッと笑う。
「心配してくれたんだ?」
「ぁ……ああ……」
今度は逆に少年に顔を覗き込まれ、手塚はなぜか微かに狼狽えた。
少年の整いすぎる顔が近づき、ふわりと綻ぶ。
「アリガト。優しいんだね」
「………」
「ねえ」
さらにぐっと顔を近づけられ、手塚は少し後退った。
「アンタ、なんか、いい匂いするね」
「え?」
「じゃあね」
少年がスッと離れ、クルリと踵を返した。
「俺は手塚国光という。君は?」
少年はどこか意外そうな顔で振り返り、だがすぐにまたふわりと微笑んだ。
「越前リョーマ」
「どこかのテニスクラブに所属しているのか?」
「べつに」
「俺は青春学園中等部のテニス部に所属している」
「は?」
「竜崎先生とは知り合いなのか?」
「りゅうざきせんせい?」
越前リョーマと名乗った少年は暫し考え込み、「ああ」と思い出したように頷いた。
「あのオバサンの名前か。なんか聞いたことあると思った」
「竜崎先生はうちの部の顧問をしている」
「へえ」
「うちの部に……青春学園に、来るのか?」
自分でも驚くほど目の前の少年に執着していると、手塚は思う。
このまま別れてしまいたくなかった。
何か繋がりが、欲しかった。
「青春学園……か」
リョーマはそう呟いて、また暫し考え込んだ。いや、考え込む振りをして、チラリと手塚に視線を向けてきた。
「どうしよっかなー」
クスクスと笑いながら、リョーマが手塚の方へ近づいてきた。
「……ねえ、オレにまた逢いたいの?」
「え…」
心を見透かされて、手塚は表情に出さずに狼狽えた。
「オレに、逢いたい?」
「………」
「正直に言わないと、オレ、別の学校に…」
「逢いたい」
リョーマが言い終わる前に、手塚の唇が動いた。勝手に言葉が出たような感覚があった。
「逢いたい。また逢いたい。もっと、君を知りたい」
次々に言葉が出てくる。初めて口にする慣れない言葉たちに、手塚の心がオーバーヒートを起こす。
「アンタ、真っ赤」
またクスクスとリョーマが笑う。だがすぐに笑みを消し、リョーマはじっと手塚を見つめてきた。
「あんまり長居する気はなかったんだけど、アンタ、いい匂いするし、面白そう」
「え?」
「じゃあ、四月からよろしくね、セ・ン・パ・イ」
そう言ってリョーマは背伸びして手塚の首筋に口づけた。
「な…」
「バイバイ」
はっきりと動揺して手塚が後退ると、リョーマは笑いながらクルリと背を向け、軽やかな足取りで去っていった。
リョーマの背を見送りながら手塚はリョーマの唇が触れた首筋にそっと手を当ててみる。
(熱い…?)
口づけられた首筋が熱い。
首筋だけでなく、頬も、いや身体全体が、熱くなっている。
(なんだ…この感覚は……?)
戸惑う手塚の髪を、柔らかな風が揺らした。
それから数週間後、越前リョーマは本当に青春学園に入学し、手塚の目の前に姿を現した。
最初に出逢った時の印象とは違い、青学に入学してきたリョーマは、至って「普通の中学生」に、手塚には見えた。
もちろん「テニスの実力」に関しては中学生どころかプロでも感心するほどのレベルだったが、手塚を魅了した、あの滲み出るような妖艶とも言える輝きは、ほとんど見られなかった。
他の部員や同級生たちと普通に話をし、時折笑み、口数は多くはなかったが、部活動を含め、普通に学校生活を送っているようだった。
手塚の予想通り、四月からいきなりレギュラーの座を獲得し、徐々にリョーマの名は世間に知れ渡っていった。
だがリョーマの出場した公式戦は最初から波乱含みで、リョーマ自身も地区予選では瞼を切る怪我を負ったが、地区予選も、地区予選後の試合でも、青学レギュラー陣に怪我人が続出した。
極めつけが自分自身の怪我だったと、手塚は思う。
関東大会初戦、氷帝学園と対戦した青学は辛くも勝利を手にしたが、手塚は肩を負傷し、戦線離脱を余儀なくされた。
『オレ、疫病神かもしれないっスよ?』
以前、リョーマがふざけ半分にそんなことを言っていた。
周りのレギュラー達は冗談と受け止めて笑い飛ばしていたが、手塚は複雑な心境になった。
べつにリョーマのことを『疫病神』と思っているわけでは、決してない。むしろ手塚にとっては、自分に幸福を与えてくれる神々しい神のように思えたこともある。
だがリョーマは、他の者と、どこか違う、と感じる。
何がどう、どこがどう、とははっきり言葉にできない。
いや、はっきり言えることがあるとすればたったひとつ。
リョーマは、怪我の治り方が異常に早い、ということ。
手塚がそのことに気づいたのは、あの、地区予選でのリョーマの怪我。
相手選手の技にかかり、自分のラケットで自らを傷つけることになってしまったリョーマの傷は、端で見ていた手塚も顔を顰めるほど、パックリと皮膚が割かれていた。
なのに、一週間もすると、その傷が跡形もなく治ってしまっていた。
周りの人間は「きっと見た目ほど深い傷ではなかったのだ」といって納得していたが、手塚にはそうは思えなかった。現に、あの傷を間近で見た大石も、しばらくは首を傾げていた。
だがその時の手塚は、そんなリョーマのことを「特異体質なのかもしれない」と思うことにし、それよりも気にかけていたリョーマの内面の問題の解決を図った。
リョーマの瞼の傷が癒えてすぐに、手塚からリョーマへ試合を申込み、リョーマの中に埋もれていた「テニスへの情熱」に火をつけることに成功したのだ。
それ以来、リョーマのテニスの実力は、まるで固かった蕾が一気に開花してゆくかのように急速にレベルアップして行き、誰もが目を見張った。
そしてもうひとつ変わったことは、リョーマが手塚の傍に居着くようになったことだった。
練習の時も、試合の時も、気がつくとリョーマは手塚の隣にいた。
だがリョーマは、特に親しく言葉を掛けてくるわけでもなく、ただ傍にいて、手塚と同じ場所に立ち、同じものを見ようとしているようだった。
そんな二人の関係が変わったのは、手塚が試合で痛めた肩の治療で東京を離れることになった時だった。
治療先へ出発する前の晩、リョーマがふらりと手塚の家を訪ねてきた。少し話がしたいと言われ、手塚はリョーマを連れて近くの公園へと向かった。
晩と言っても遅い時間ではなく、未だ西の空は沈んだばかりの太陽の名残に薄く照らされている。
その西の空がよく見えるベンチに、二人は並んで腰を下ろした。
だが、手塚を呼び出したリョーマは一向に口を開かず、じっと足下を見つめたまま、口を閉ざしている。
美しい夕空のグラデーションが、リョーマの目に映る前に藍一色のグラデーションへと変化していった。それでも手塚は黙ったまま、リョーマが話し始めるのを待った。
そうして辺りがモノトーンになり始めた頃、漸く、リョーマは口を開いた。
「ねえ」
「ん?」
視線は相変わらず足下に向けたまま、リョーマは、どこか硬い声で言う。
「部長……前から肘を痛めていたって、ホント?」
「………ああ」
「それなのにテニスを続けてたのはなんで?」
「テニスが好きだからだ」
「………」
リョーマはさらに深く項垂れるようにして小さく溜息を吐く。
「そんな状態だったのに、なんでオレと…全力で、試合して……」
「俺が全力でやらないと、意味がなかったからな」
「でも、なんで、そこまでしてくれんの?」
震えるような声でリョーマが言う。普段のリョーマからは想像もできないような、か細い声だった。
(「なんで」…?)
手塚は黙り込み、暫し考え込んだ。
確かに、自分は青学の未来を考えて、そのために自分の意志を引き継いで青学を支えてくれるだろうリョーマに期待をかけた。リョーマが覚醒してくれるなら、いくらでも、どんなことをしてでも、手助けしたいと思った。
すべては、青学の未来のために。
受け継がれてきた「夢」を実現させるために。
だが、それだけだっただろうか。
(ああ………そうか……)
手塚は自分の心の奥に押し込めていた想いに、やっと気づいた。
「好き、だからだ…」
「え………テニスが?青学が?」
顔を上げ、潤んだ瞳でリョーマが手塚を見つめる。
「お前が」
言ってしまってから手塚は我に返り、バッと口元を押さえた。
言うべきではないことを、言ってしまった。
初めてリョーマに出逢った時のように、唇が勝手に言葉を紡いだ。
「部長……?」
「いや……俺は……」
リョーマから目を逸らし、手塚は慌てて立ち上がった。
「部長…」
「今のは忘れてくれ」
「………」
「すまない」
その場から立ち去ろうとする手塚に、リョーマが後ろから抱きついてきた。
「越前…っ」
「ヤダ。今の、もう一回、ちゃんと言って!」
「………」
ギュッとしがみつかれて、手塚は大きく目を見開いた。
(まさか……)
そんなことがあるのだろうかと、思う。
だがリョーマの様子は、どう考えても「拒絶」しようとする者のそれではない。
「もう一回、言ってください」
手塚にしがみつくリョーマの手が微かに震えている。
その手に、手塚は自分の手を重ねた。
手の平から伝わってくるリョーマの温もりに、手塚はふっと、肩の力を抜く。
「………」
「部長……」
手塚は目を閉じてゆっくりと深呼吸をし、静かに目を開いた。
「越前………お前が好きだ」
ビクリとリョーマの身体が揺れ、そうしてまたギュッと強くしがみつかれた。
「部長……それって、恋愛感情、ってこと?」
「ああ」
ほんの少しだけリョーマの声音が変わった気がしたが、手塚はあまり気にしなかった。
「ホントに?」
「本当だ」
「じゃあ、部長、今すぐキスして」
「!」
リョーマが、手塚の前に回り込んで見上げてくる。
「オレに、キスして、部長」
「えち…」
「そうしたら、オレ、部長のこと少し助けてあげられるから!だから、キスして」
(助ける?)
手塚は疑問に思ったが、目の前の誘惑に心を奪われた。
潤む大きな瞳が、そして何より、薄く色づいている唇が手塚を誘っている。
「いいのか?」
「うん」
大きな瞳が、ゆっくりと閉ざされてゆく。クッと顎を突き出し、睫毛を震わせるリョーマの表情が、そして、仄かに色づいている唇が、手塚の胸に激しい恋情を呼び起こした。
「越前…」
甘く名を囁き、手塚はそっと唇を触れさせる。それだけで離れようとすると、リョーマが薄く目を開けた。
「ダメ……もっとちゃんと……オトナのキスがいい……」
そう言ってリョーマが舌の先で手塚の下唇を舐めた。
「…っ!」
堪らなくなった手塚は、噛みつくようにリョーマに深く口づける。
「ん……ん…っ」
誘い込むように開かれたリョーマの口内へ舌を滑り込ませると、途端にリョーマの舌が手塚の舌を迎え入れるように触れてきた。
躊躇いなくリョーマの舌を絡め取り、口蓋を舐め上げ、少し離れてリョーマの下唇に甘く歯を立てる。
「ぁ……もっと……」
リョーマが口づけを強請る。求められるだけ、手塚はリョーマの唇が腫れ上がるほど口づけ続けた。
「越前…」
長い長い口づけを終えてリョーマの身体をしっかりと抱き締めると、リョーマは甘い吐息を零して手塚の胸に顔を埋めてきた。
「……やっぱ…こういうことだったんだな……」
手塚の腕の中でリョーマが呟く。
「え?」
何のことかと手塚が聞き返すと、リョーマは笑って「なんでもない」と言った。
「部長……いつ戻ってくるんスか?」
リョーマの問いかけに手塚は一瞬口を噤んだ。
とにかく早く戻りたい。
戻ってみんなと一緒にコートに立ちたい。
だが、肩を診てくれたかかりつけの医師には、そう簡単には完治しないだろうとはっきり言われた。肩だけではなく、肘の古傷も危うい状況だ。
(すぐには戻れないかもしれない)
手塚の胸に、焦燥感のような、虚脱感のような、そんな負の感情が湧き上がりそうになる。
だが。
「全国までには、戻る」
青学に入って、大和部長と出会い、信頼できる友と出会い、心に芽生えた青学への愛情。そして、夢。
その夢の実現のためには、戦力としても、精神的な支えとしても、自分は必要になるはずだ。驕っているわけではなく、自負があるわけでもなく、客観的に見て、シンプルにそう思う。
だから早く戻ってきたい。
肩も肘も、全てを完璧に治すことができなくても、戦える身体になって、早く、戻りたい。
その願望を、手塚は確かな約束のように、口にした。
「うん」
その手塚の決意にも似た強い意志をわかっているかのように、リョーマは頷く。
「大丈夫っスよ。アンタはすぐにまた、コートに立つから」
励ましとは違う、と手塚は感じた。
リョーマの言葉は、まるで予言のように聞こえた。
ろくにサーブも打てないほど痛めつけられた肩を目の当たりにしたはずなのに、「すぐに治る」と、確信のようにリョーマは言うのだ。
(それほど俺を信じていると、言うことか?)
それだけではない気がする。
だが、その意味を追及しなくてはならない必要を、手塚は感じなかった。
「ああ。俺は絶対に、お前たちと、お前と、一緒に全国で戦う」
「うん」
リョーマは微笑み、また手塚の胸に顔を埋めてくる。
「……越前」
「なんスか?」
うっとりとしたように甘い声でリョーマが応える。
「俺が好きなのか?」
「そうみたい」
どこか他人事のように言うリョーマに、手塚は小さな不安を感じる。
「いつから?」
「ん?……たぶん、一番最初に、アンタと電車の中ですれ違った時から、かな」
「え…」
意外なことを言われて手塚は目を見開いた。
「そんなに前から……?」
「…オレもずっと気づかなかったんだけどさ……あの時アンタを見て感じたものは、やっぱ、こういうコトしたくなる相手、だったんだなって、今わかったから」
「こういうこと…」
ふわりと手塚の頬が熱くなる。
「部長……」
リョーマが手塚の腕の中で、じっと見上げてくる。
「ん…?」
柔らかく聞き返すと、リョーマの頬が紅くなった。
「オレ…男だから…部長がソーユー気になるかはわかんないけど……キスの先がしたくなったら……心の準備とかいるから、先に言ってね」
(キスの先……)
「………」
軽い眩暈のようなものを感じて手塚は目を閉じた。
心の中が燃えるように熱くなっていくのがわかる。
「ぶちょ?」
「ん。わかった」
ただそれだけ言ってリョーマをきつく抱き締める。
(今すぐにでも、キスの先に進みたくなる)
きつく抱き締めながら、リョーマの髪やこめかみに何度も口づけていると、クスッと笑われた。
「ぶちょ……もっと、こっちに、キスして…」
「………」
つんと尖らされた唇に誘われて、手塚は自分の欲望に抗わずにリョーマの唇を貪る。
(甘い……)
深く絡め合うリョーマの舌はとても熱く、甘かった。
そのリョーマの熱が手塚にも伝わり、全身が熱くなるような感覚がある。
「リョーマ…」
唇を触れさせながら名を囁いてやると、リョーマの身体が微かに震えた。
「ぁ……ぶちょ…」
リョーマがうっとりとした目で自分から唇を寄せてくる。
「アンタのキスって……気持ちいい……」
甘い吐息を零しながらリョーマが囁く。
「ああ……俺も気持ちがいい…」
手塚も囁き、また深く唇を重ねる。
胸の奥に、後から後からリョーマへの熱い想いが溢れてくる。それは手塚の心をいっぱいにしてもまだ滾々と湧き出で、まるで出口を求めるように狂おしく渦巻き始める。
青学のために、自分の夢のために、怪我を早く治して戻りたいと思う。
だがそれと同時に、リョーマの元へ少しでも早く戻ってきたいと、強く願う。
「…お前の元に、俺は戻ってくるから…」
呟くように、だがしっかりとした口調で言うと、リョーマは腕の中で小さく「うん」と言って頷いた。
そうして、密かに起きていた奇跡に気づいたのは、治療先で診察を受けた時だった。
「……少し熱は持っていますが、特に問題はありませんね」
「え?」
診察した医師の言葉に手塚は目を大きく見開いた。
「問題、ない?」
「ええ……まあ、多少は肘と肩の関節周辺に炎症の名残が見られますので、すぐに長時間の酷使は厳禁ですが、明日まで様子を見て、明後日からリハビリを始めても大丈夫ですよ?」
「そ……そうですか……よろしくお願いします」
何日かかるのだろうと、不安でいっぱいだった心から一気に力が抜けてゆく。
「念のため、塗り薬を出しておきますから、今日と明日はこれを一日三回程度塗布してください」
サラサラとカルテに何か書き込みながら医師が淡々と言う。
「紹介状にはだいぶ症状が重いと書いてありましたけど……短期間のうちにここまで回復したのかなぁ…」
ボソボソと呟く医師の言葉に手塚自身も内心首を傾げる。
(そう言えば、もう肩の違和感がなくなっている…)
特に何をしたわけでもないのに、怪我のことを忘れるほど、肩の違和感がなくなっていたのだ。
医師も手塚も、まるで煙りに包まれたような表情をして診察を終えた。
(だが、これで早々に帰れそうだ)
薬局で薬を受け取りながら、手塚は身体同様心までも軽くなってゆくのを感じる。
(リョーマ、お前の元へ、すぐにでも帰るから…)
小さな疑問よりも、リョーマの元へ還る日が早まったことへの歓喜で、手塚の胸はいっぱいになる。
(こんなにも、お前のことを想っていたのか、俺は……)
気づいたばかりの恋情の大きさに手塚自身驚く。
「リョーマ…」
待合室の窓辺に立ち、雲のない空を見上げる。
(早く、お前と……)
深く重ね合った唇の感触を思い出し、手塚はそっと自分の唇に指先で触れてみる。
(そう言えば…あの時、妙なことを言っていたな…)
『オレに、キスして、部長』
『そうしたら、オレ、部長のこと少し助けてあげられるから!』
あの時はそれほど気には止めなかったが、今になって思うと、手塚の肩が軽くなったのはあの日の帰り道からだった気がしてくる。
リョーマの言葉とキス。そしてあの予言のような言葉。
『大丈夫っスよ。アンタはすぐにまた、コートに立つから』
「………」
まさか、とは思う。
リョーマとキスを交わしたことが怪我の回復を促すとは思えない。
なのに、「もしや」と思う気持ちを拭い去ることはできない。
(特異体質というものは、伝染したりするのだろうか……)
「………」
しばらく思考を巡らしてみるが、自分が考えているだけでは明確な答えなど出ないと思い、手塚は別のことを考えることにした。
(とにかく、少しでも早く復帰しなければ…)
そうして手塚は、身体の故障だけではなく、精神的な障害も数週間後かけて乗り越え、青学に復帰した。

掲示板はこちらから→
お手紙はこちらから→

20071031
|