|
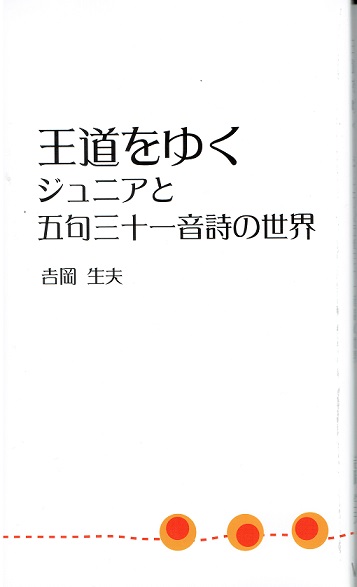 |
|
|
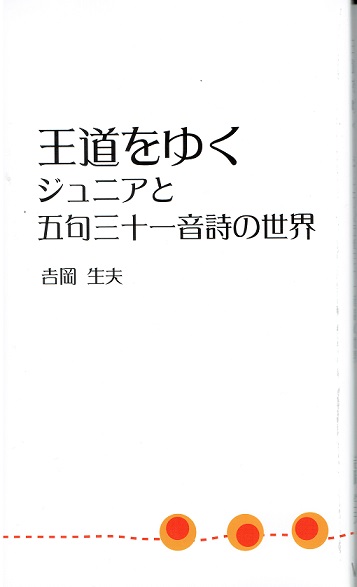 |
|
| 王道をゆく ジュニアと五句三十一音詩の世界 | ||||
| はじめに | ||||
| 本書は「短歌」と呼ばれる短詩型の発生から現在までを俯瞰しようとする試みの一書です。正確にいえば俯瞰するための「概念」を提唱する一書ということになります。 そのためには見直さなければならないことがあります。たとえば「短歌」以前は「和歌」だということになっていますが、そうでしょうか。あるいはそれだけでしょうか。ためしに『現代短歌大事典』(三省堂)で「和歌」を引くと、次のように始まります。 「からうた=・唐歌・漢詩」に対し、日本固有の「倭歌=やまとうた」をいう。『万葉集』では「和歌」とは贈歌や問歌への「和(こた)ふる歌」のことだが、『古今集』に至って「和歌=やまとうた」の概念が確立した。以後、短歌、長歌、旋頭歌、仏足石歌、片歌の五種の歌体が「和歌」として認識されるが、広義には和歌史の趨勢(すうせい)を形成した短歌のみを「和歌」という。(後略)。 本論で詳しく触れますが「和歌」とは「概念」なのです。しかも「和歌」は後に登場する「狂歌」を含みません。二重にも三重にも俯瞰を困難なものにしています。 では「概念」とは何か。『デジタル大辞泉』は「 物事の概括的な意味内容」と「形式論理学で、事物の本質をとらえる思考の形式。個々に共通な特徴が抽象によって抽出され、それ以外の性質は捨象されて構成される。内包と外延をもち、言語によって表される」を載せています。どうやら「概念」とは絶対的なものではなさそうです。そこで「概念」と反対語の「実体」にこだわることによって新しい「概念」を求めました。 そのために焦点を当てたのが名称の変遷と五七五七七また三十一文字でした。 次にツールとしての言葉に着目しました。 『万葉集』の時代、私たちは固有の文字を持ちませんでした。万葉仮名は日本語を表記するために漢字の音や訓を借りてきたものです。言文で整理するなら話し言葉すなわち「言語体」です。日本人が固有の文字を獲得した平安時代は「言文一致体」です、十四世紀になって言文は二途に分かれます。このとき平安時代の言語体系の外面を真似たのが「文語体」です。逆に内面を選択したのが「言語体」でした。当時の日常語としての話し言葉です。前者が和歌の「文語体」、後者がはっきりと姿を現すのは近世の狂歌でした。 このうち『万葉集』の時代の言語体、平仮名の生まれた平安時代の言文一致体、言文二途の時代における狂歌の言語体の流れを本書では王道と呼んでいます。 王道とは物事が進んでいくべき正統な道、また方法であり、手段をいいます。 今一つ、スタンダードツールとスペシャルツールという用語を採用しました。言文二途の時代はダブルスタンダードの時代です。ところが近代に入って言文二途の「文」がスタンダードツールとして君臨し、歌壇外の動きと裏腹に言文一致体は特殊という意味のスペシャルツールとして隅に追いやられました。これが周回遅れながら、ドラスチックな変化を遂げる、そのさまをジュニアの作品によって明かそうとするものです。 ちなみに言文二途の時代をくぐり抜けた「文語体」は、その内実において破綻していると考えるべでしょう。安田純生は『現代短歌のことば』(邑書林)所収の「文語と〈文語〉」において平安時代の言語体系を意味する文語と、言文二途の時代における文語を区別しています。すなわち後者を〈文語〉として、次のように述べています。 室町時代や江戸時代の〈文語〉には、誤用が頻出する。平安時代の文語と室町・江戸時代の〈文語〉を同一視し、〈文語〉を証拠にして正しい文語であると主張したりするのは、いささか問題がある。〈文語〉が文語であることが、〈文語〉によって証明されたりはしない。 明治三十八(一九〇五)年の文部省告示第百五十八号「文法上許容すべき事項」(本邦書籍『新聞集成明治編年史 第十二巻 日露戦争期』)において「教科書の検定又は編纂に関し、文法上許容すべき事項」とした十六項目があります。 参考に例示を除いて抜粋すると「一、『居り』『恨む』『死ぬ』を四段活用の動詞として用ゐるも妨なし」「二、『シク・シ・シキ』活用の終止言を『アシシ』『イサマシシ』など用ゐる習慣あるものは之に従ふも妨なし」「三、過去の助動詞の『キ』の連体言の『シ』を終止言に用ゐるも妨なし」「四、『コトナリ』(異)を『コトナレリ』『コトナリテ』『コトナリタリ』と用ゐるも妨なし」「五、『……セサス』と云ふべき場合に『セ』を略する習慣あるものは之に従ふも妨なし」「六、『……セラル』といふべき場合に『……サル』と用ゐる習慣あるものは之に従ふも妨なし」「七、『得シム』といふべき場合に『得セシム』を用ゐるも妨なし」「八、佐行四段活用の動詞を助動詞の『シ・シカ』に連ねて、『暮シシ時』『過シシカバ』などいふべき場合を『暮セシ時』『過セシカバ』などとするも妨なし」「九、テニヲハの『ノ』は動詞、助動詞の連体言を受けて名詞に連続するも妨なし」「十、疑のテニヲハの『ヤ』は動詞、形容詞、助動詞の連体言に連続するも妨なし」「十一、テニヲハの『トモ』の動詞、使役の助動詞、及受身の助動詞の連体言に連続する習慣あるものは之に従ふも妨なし」「十二、テニヲハの『ト』の動詞、使役の助動詞、受身の助動詞及時の助動詞の連体言に接続する習慣あるものは之に従ふも妨なし」「十三、語句を列挙する場合に用ゐるテニヲハの『ト』は誤解を生ぜざるときに限り最終の語句の下に之を省くも妨なし」「十四、上に疑の語あるときに下に疑のテニヲハの『ヤ』を置くも妨なし」「十五、テニヲハの『モ』は誤解を生ぜざる限りに於て、『トモ』或は『ドモ』の如く用ゐるも妨なし」「十六、『トイフ』と云ふ語の代りに『ナル』を用ゐる習慣ある場合は之に従ふも妨なし」の十六項目です。 国がお墨付きを与えたとしても〈文語〉が文語にならないことは先に引用したとおりですが、これに加えて擬似古典語の問題があります。安田純生は「現代短歌のことば」(『歌ことば事情』邑書林)で次のように述べています。 明治以後に作られた、近代詩歌語とでも呼べるものがあります。(略)。少し例をあげれば、「眼裏(まなうら)」「晩夏(おそなつ)」といった名詞、「寂しむ」「まぶしむ」といった動詞、「さはやけし」「ひそけし」といった形容詞などがそれに当たります。 さらにシニアのスタンダードツールに属する用語ですが、その中の代表格といってもよいでしょう、「祖父」「祖母」を意味する「『おほちち』『おほはは』が短歌で使われ始めたのは、大正年間であろうか」(『現代短歌のことば』)というのですから驚きます。 かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな 若山牧水の明治四十三年の作品です。彼ら近代の歌人を取り巻いていた言文の状況はどうであったかというと、先の「文法上許容すべき事項」は文語文を「普通文」と呼んでいます。それでも教科書の言文一致を推進してきた言文一致会は明治四十三(一九一〇)年に所期の目的を達成したとして解散をします。新聞が言文一致に踏み切るのは遅く大正十(一九二一)年、公用文は昭和二十(一九四五)年の敗戦後だそうです。 内実はどうであれ、言文不一致の環境では文語体に拠ることを説明する必要はなかったでしょう。しかし言文一致を意識さえしない今日においては話が別です。文語文法の習得の困難さもさることながら、そもそも文語体である必要があるのか、主体的に自問さえすれば答が出ているというのが、短歌愛好者の大方であろうと思われるのです。 五句三十一音詩史すなわち三十一文字(みそひともじ)の歴史に日本語の歴史を重ねたときに見えてくる風景、それはシニアの信奉するスタンダードツールがコペルニクス的展開を迫られているということです。 証言するのは私たちがジュニアと呼ぶ未来人なのです。 |
||||
| 目 次 | ||||
| はじめに 3 第一章 名称を巡る考察 15 第一節 対抗軸にみる変遷もしくは同一形式のせめぎ合いの中で 17 第一項 『万葉集』~短歌と長歌~ 17 第二項 『古今和歌集』~和歌と漢詩~ 19 第三項 狂歌~和歌の鬼子に救われる形式の危機~ 20 第四項 近代短歌~和歌と狂歌の行方を問う~ 25 第五項 国歌~国学の勃興とその影~ 36 第六項 結語 39 第二節 歴史を俯瞰するための名称を探る 40 第一項 三十一文字 41 第二項 五七五七七 44 第三項 五句三十一音詩 46 a 三十一言 47 b 三十一音 49 c 歌か、詩か、その分岐点 50 第四項 結語 52 第二章 ツールとしての言葉の歴史を俯瞰する 55 第一節 言語体~『万葉集』の時代~ 59 第二節 言文一致体~平仮名と『古今和歌集』~ 59 第一項 文語とは何か? 60 第二項 試みに『土佐日記』を読んでみましょう 62 第三節 言語体~言文二途に見る狂歌の位相~ 68 第一項 狂歌人の歌論 71 a 由縁斎貞柳(ゆえんさいていりゆう)(一六五四~一七三四) 71 b 栗柯亭木端(りつかていぼくたん)(一七一〇~一七七三) 73 c 九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい)(一七二三~一七六七) 74 d 永日庵其律(えいじつあんきりつ)(一七二六~一七六一) 76 e 山中千丈(生没年不詳) 77 f 二松庵万英(にしようあんまんえい)(?~一七八〇) 78 g 仙果亭嘉栗(せんかていかりつ)(一七四七~一七九九) 80 h 木室卯雲(きむろぼううん)(一七一四~一七八三) 82 i 元木網(もとのもくあみ)(一七二四~一八一一) 85 j 朱楽菅江(あけらかんこう)(一七三八~一七九八) 86 k 唐衣橘洲(からごろもきつしゆう)(一七四三~一八〇二) 87 l 大田南畝(おおたなんぽ)(一七四九~一八二三) 89 第二項 狂歌の言語体 97 第四節 周回遅れの言文一致体 105 第一項 スタンダードツール 106 第二項 スペシャルツール 108 第五節 結語 109 第三章 ジュニアに学ぶ五句三十一音詩 111 第一節 古代語 102 第二節 近代語 116 第三節 現代語 119 第一項 現代学生百人一首(東洋大学) 120 a 二〇一二年編纂 現代学生百人一首 120 b 二〇一三年編纂 現代学生百人一首 123 c 二〇一四年編纂 現代学生百人一首 126 第二項 SEITO百人一首(同志社女子大学) 129 a 31音青春のこころ2012 「SEITO百人一首」の世界 130 b 31音青春のこころ2013 「SEITO百人一首」の世界 133 c 31音青春のこころ2014 「SEITO百人一首」の世界 136 第三項 契沖顕彰短歌大会(契沖研究会) 139 a 第九回(平成二十四年二月四日) 139 b 第十回(平成二十五年二月三日) 142 c 第十一回(平成二十六年二月二日) 145 第四項 ―ふれあいの祭典―兵庫短歌祭作品集(兵庫県歌人クラブほか) 148 第五項 感じて短歌(加古川市中学校国語研究部会) 152 第六項 兵庫県高校生文芸集(兵庫県高等学校文芸部会) 158 |
||||
| 第一章 名称を巡る考察 | ||||
| 『古今和歌集』(小学館『日本古典文学全集7』)の仮名序に「三十文字(みそもじ)あまり一文字(ひともじ)はよみける」というくだりが登場します。真名序では「三十一字の詠(うた)あり」に該当します。その後「みそもじひともじ(三十文字一文字)」「みそじひともじ(三十一文字)」「みそひともじ(三十一文字)」とも呼ばれます。また「五七五七七」という呼び方もあります。十世紀後半の成立がいわれる歌学書『倭歌作式(わかさくしき)』(『日本歌学大系』第一巻』)には「択字定三十一」があり、「抑(そもそも)五七五七七、一文之中予有四病」も見ることができます。 三十一文字も五七五七七も定型詩としての要件を規定する名称です。 この二つに対して和歌も狂歌も短歌も、他のジャンルとの競合ないしは同一形式との差別化に由来する名称にほかありません。和歌はさらに曖昧な性格を帯びます。 『日本国語大辞典』『大辞林』『デジタル大辞泉』『広辞苑』の見出しが「和歌・倭歌」となっているのには拒否反応を禁じ得ません。『日本大百科全書(ニッポニカ)』から「和歌」の冒頭部分を引用します。書いているのは藤平春男です。 「やまとうた」すなわち日本の国の固有の歌を意味するが、その概念は平安時代の『古 今和歌集』の成立によって確立したので、具体的な和歌の歌体としては、その当時固 有の歌体として認められていた短歌・長歌および旋頭歌(せどうか)・仏足石歌(ぶ っそくせきか)体をさすことになり、それが現代に至るまで狭義の和歌の範囲となっ てきている。(後略)。 この「和歌」という用語を『万葉集』まで遡及させない、名称の変遷を実体に即して、つまり『古今和歌集』以後の五七五七七に限定して検証することにします。 |
||||
| 第一節 第一節 対抗軸にみる変遷もしくは同一形式のせめぎ合いの中で | ||||
第一項 『万葉集』~短歌と長歌~ 『万葉集』では五七五七七が単独で登場するときは「歌」と表記されます。例えば「君を思ふこと未だ尽きず、重ねて題(しる)す歌二首」(八六六・八六七)といったふうにです。詞書に「後(のち)の人の追和」とある八七二も目録では「後の人の追和する歌一首」となります。長歌とセットで登場するときは短歌と表記されます。例をあげると八八六から八九一は詞書に「熊凝(くまごり)のためにその志を述ぶる歌に敬(つつし)しみて和する六首」(長歌一首、短歌五首)とありますが目録では「山上臣憶良、熊凝の為に志を述ぶる歌に和する一首并(あは)せて短歌」となっています。その次が有名な詞書「貧窮問答の歌一首并せて短歌」(八九二・八九三)の作で、これは目録も同じです。基本的パターンといってもいいでしょう。 つまり『万葉集』に出てくる五七五七七は和歌ではないのです。巻第五に「書殿にして餞酒する日の倭歌(やまとうた)四首」(八七六・八七七・八七八・八七九)がありますが、小学館の『萬葉集二』(『日本古典文学全集3』)の校注では次のように説明されています。 倭歌は漢詩に対していう。目録では諸本とも「和歌」となっているが、天平初年に、国名としてのヤマトや日本を、「大和」「和」と書いた例はない。目録の作成年代が少なくとも天平宝宇元(七五七)年以後であることの一つの証であろう。 これをもって『万葉集』も和歌だとすれば、あとの四〇〇〇首を越える短歌はどうなるのでしょう。間尺に合いません。漢詩との関係が顕著になるのは次の時代なのです。 第二項 『古今和歌集』~和歌と漢詩~ 『万葉集』の成立年は不明ですが、最後の作品が天平宝字三(七五九)年正月の〈新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事(よごと)〉(大伴家持)ですので、それ以降ということになります。大伴家持(七一八頃~七八五)の生きた奈良時代は奈良(平城京)に都のあった和銅三(七一〇)年から延暦三(七八四)年をいいます。 『古今和歌集』は醍醐天皇の勅命により紀貫之・紀友則・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)・壬生忠岑(みぶのただみね)が撰して延喜五年(九〇五)に奏上しています。成立年については諸説ありますが、桓武天皇による長岡京遷都が延暦三(七八四)年、平安京遷都が延暦十三(七九四)年、すでに一世紀以上が経った頃です。この間を占めるのが国風暗黒時代です。弘仁五(八一四)年の『凌雲集』、同九(八一八)年の『文華秀麗集』、天長四(八二七)年の『経国集』と立て続けに勅撰の漢詩文集が出ています。国風暗黒時代とは漢風全盛時代なのです。しかし風が変わります。あるいは風が変わったからなのか。寛平六(八九四)年に遣唐使が廃止されます。こうして初の勅撰和歌集が出たのです。仮名序では「やまとうた」が一回、「三十文字(みそもじ)あまり一文字(ひともじ)」が一回、あとは「和」のない「歌」です。もちろん歌集名は、 すべて千歌二十巻(ちうたはたまき)、名づけて『古今和歌集』といふ です。これが真名序では「和歌」が十四回、「三十一字」「反歌」「短歌」が各一回です。先に一時代を画した漢詩文を意識した用語であることはいうまでもありません。 第三項 狂歌~和歌の鬼子に救われる形式の危機~ 狂歌とは和歌が否定した世界、書き継がれることのなかった幻の短歌史です。これを狭義の狂歌とすれば宮廷歌壇の外で作られる五七五七七もあったでしょう。また宮廷歌人といえども用語や素材から自由に作歌したいこともあったでしょう。これを含めた概念が広義の狂歌と考えられます。今川文雄訳『訓読明月記』(第一巻、河出書房新社)の建久二(一一九一)年閏十二月四日に用語としての狂歌が登場します。定家は三十歳です。 相次で一条殿に参ず。昨日の仰せに依りてなり。夜に入りて、百歌を読み上げらる(御歌・入道・予。三百首なり)。事畢(をは)りて当座の狂歌等あり。深更に相共に家に帰る。 次に同第四巻より健保三(一二一五)年八月二十一日、定家五十四歳の記事です。 日入る以後参内し、鬼の間に参ず。少時にして頭弁参入。又右武衛参ず。此の間に、治部重長来たりて予を召す。御前に参ず。俄にして人々を召す。各々参入し、連歌を始む(人名草を賦す)。一両句の間、雅経朝臣参入。按察参ずべき由、女房之を申す。忽ち連歌を抑へて(五十句の後)、狂歌合せ有り(両の方、各々の体を詠ず)。評定了りて按察参ず(夜半なり)。賦物を改む(魚河の名)。又五十句訖りて各々退出す。已に暁鐘なり。 次は二条派の重鎮として活躍した歌僧、頓阿(とんあ)(一二八九~一三七二)の『井蛙抄(せいあしよう)』(『日本歌学大系』第五巻)巻第六、雑談からの引用です。 六条内府被語云、後鳥羽院御時、柿本、栗本とておかる。柿本はよのつねの歌、是を有心と名づく。栗本は狂歌、これを無心といふ。有心には、後京極殿、慈鎮和尚以下、其時秀逸の歌人也。無心には、光親卿、宗行卿、泰覚法眼等也。水無瀬和歌所に、庭をへだてて無心座あり。庭に大なる松あり。風吹て殊に面白き日、有心の方より、慈鎮和尚 心あると心なきとが中に又いかにきけとや庭の松風 と云歌よみ、無心の方へ送らる。宗行卿 心なしと人はのたまへどみみしあればききさぶらふぞ軒の松風 と返歌を詠じけり。耳しあればが、なまさかしきぞと上皇勅定ありてわらはせ給ひけり。 六条内府は六条有房(ろくじようありふさ)(一二五一~一三一九)です、これとの関連を思わせるのが『訓読明月記』第二巻、建永元(一二〇六)年八月十日の記事です。定家は四十五歳です。 和歌所の輩ヲ狂連歌に籠め伏すべき由、結構す。下官・雅経等、尋常の歌詞を以て之に相挑(いど)む。此の事三度許りに及ぶ。事、叡聞に達し、彼方の張本等を召し抜く。長房卿・宣綱・清範(本儀ハ此の方なり。仰せに依り彼方に渡さる)・重輔、之を以て無心の衆と称し、態々(わざわざ)狂句を出す。中納言(公)・雅経・具親、御方に候す。之を以て有心と称す。 どうやら頓阿の時代には和歌=柿本=有心と狂歌=栗本=無心の並立が図式として出来上がっていたようです。では狂歌が一人歩きを始めると、どうなったでしょうか。 くげたちのゆみやもとらぬごくつぶしなどゆきしもときえもうせぬぞ 詠み人知らず 乗り物の上下の者は歌人にてなかなる我にはぢをかかする 黒田月洞軒(くろだげつどうけん) 死んで行く処はおかし仏護寺の犬の小便するかきの本 桃縁斎(とうえんさい)(芥河(あくたがわ))貞佐(ていさ) 一首目は戦国時代の始期がいわれる明応二(一四九三)年に起きた明応の政変また正覚寺合戦が舞台で、『金言和歌集』(『狂歌大観』第一巻)に収められています。〈公家達の弓矢も取らぬ穀潰しなど雪霜と消えも失せぬぞ〉。どうして雪や霜のように消えていかないのだ。時代の主役が貴族から武士に移ったことによる変化を表しています。 二首目の「乗り物」は籠、「上下」は前後、「歌人」が二人して狂歌人である「私」に恥じをかかせるといっています。しかし狂歌を作る「私」が籠にのり和歌人に籠をかかせているところに注目すべきでしょう。黒田月洞軒(一六六一~一七二四)は千二百二十石を知行する徳川譜代の旗本です。『大団(おおうちわ)』(『狂歌大観』第一巻)の一首です。 三首目は、一見すると犬が狂歌人である「私」の墓に小便をかけています。しかしよく見ると「かきの本」すなわち柿本の和歌人の墓なのです。だから「おかし」いのです。三句の「仏護寺」は現在の本願寺広島別院。作者の芥河貞佐(一六九九~一七七九)は広島の酒造家でした。『狂歌二翁集』(『近世上方狂歌叢書二十六』)に収録されています。 『万葉集』の短歌と長歌も、次の時代の和歌と漢詩文も異なる形式を意識した名称でした。それに対して狂歌と和歌は同一形式内での差別化ないし対立が生んだ名称といえるでしょう。そして近世において和歌が力を失っていくのは和歌そのものの中に原因が求められます。つまり狂歌をインフォーマルかつ言い捨てにしなければ楽しめなかった、その制約こそが力を削いでいったのです。反対に用語においても素材の選択においても一切の制約を排除した、その自由の中にこそ狂歌は求心力を高めていくのです。 第四項 近代短歌~和歌と狂歌の行方を問う~ 現代の「短歌」が生まれる過程を辞典(事典)で調べようとします。すると「和歌」や「旧派和歌」「新派和歌」は出てきても「狂歌」が登場することはありません。しかし振り向けば和歌と狂歌がある。そのことを指摘しているのが安田純生です。平成九(一九九七)年に刊行された『現代短歌用語考』所収の「はかないことば」から引用します。 漢語や話しことばの採用、破格の語法など、用語の面のみに着目すると、狂歌は現代の文語体短歌や話しことば調短歌に近いものを有している。少なくとも江戸時代の正統的な和歌より狂歌のほうが、いっそう現代短歌と近い関係にある。これを逆にいえば、現代短歌は、歌人が意識しているか否かにかかわらず、用語の面で江戸時代の狂歌を継承しているということである。 では、ほんの一部ですが、実際の作品に当たってみましょう。 火の用心の声あはれなりさよしぐれぬれて夜番のひとり行くらん 油煙斎貞柳(ゆえんさいていりゆう) 出づるより西へいるまで時付けのときをちがへぬ月の御船 満永 久かたのあめの細工やちやるめらの笛のねたててよぶ子鳥かも 九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい) 態(わざわざ)申すよつて詠むるさくら花一枝をくりたてまつり候 安親 花に来てはるかの谷の山ざくら咲きものこらずちりもはじめず 永志 吹く風の手にやははきをつかふらん山を木の葉のちり塚にして 石田未得(いしだみとく) すゑに名のくちせずもああ忠臣はくすの木やなる大石ならん 山果亭紫笛(してき) 一番の風の手なみに霜氷川しもさして雑乱雑乱雑乱雑乱(さらさらさらさら) 生白庵行風(せいはくあんこうふう) 一首目は現代短歌に多い初句七音です。『家づと』(『狂歌大観』第一巻)に収録されています。貞柳には〈秋たちて幾(いく)日あらねど朝さむござる小袖かさばや七夕の空〉のような作品もあります。上句の「朝」の帰属に迷います。「幾(いく)日あらねど朝/さむござる」と「幾(いく)日あらねど/朝さむござる」、むしろ破調と解した方がいいのかも知れません。 二首目は結句六音の例です。『銀葉夷歌集』(『狂歌大観』第一巻)よりの引用です。「つきのみふねぞ」で七音ですが、やはり確信犯なのでしょう。三句「時付け」は到着の時刻などを書き記すことをいいます。空の御船の発着は乱れがないというのです。 三首目は変則の枕詞です。初句は「天」や「雨」に掛かりますが、それを同音の「飴」に掛けています。『狂歌野夫鶯(やぶうぐいす)』(『近世上方狂歌叢書十三』)から引きました。正岡子規の〈久方のアメリカ人(びと)のはじめにしベースボールは見れど飽かぬかも〉(岩波文庫『子規歌集』)が有名ですが先行する「久方の」は多くあります。他の枕詞では『狂歌我身の土産』(『近世上方狂歌叢書十一』)に養老館路産(ようろうかんろさん)の〈あし引きのやまとめぐりの留主の間を長々しやと待つて居ました〉があります。初句「足引きの」は「山」に掛かりますが、それを同音の「大和」に掛けています。父親の路芳(ろほう)を迎えに出ての作です。参考ながら返歌は〈たとへにはもるる親なり可愛い子に留主をばさして旅をして来た〉でした。 四首目は候文、手紙歌です。詞書は「花の枝送るに添へて」。また諸橋轍次の『大漢和辞典』で「態」を引くと国訓として「わざわざ」があるのでルビを補いました。初句七音で「ほかのついでではない」となります。二句「因って」は漢文訓読に由来し、「そういうわけで」となります。下句は句またがりです。『銀葉夷歌集(ぎんよういかしゆう)』から引用しました。 五首目は、謡曲『鞍馬天狗』の一節「(今日見ずは悔しからまし花盛り、)『咲きも残らず散りも始めず』」が口を衝いて出たものです。『狂歌大和拾遺(やまとしゆうい)』(『近世上方狂歌叢書二十』)の一首です。謡曲や狂言また流行歌(語)は見落としも多いことでしょう。 六首目は『歌ことば事情』でも取り上げられている「風の手」(「風のてのひら」所収)の古い用例です。これを収録する『吾吟我集』(『狂歌大観』第一巻)は刊年不詳、「序」は慶安二(一六四九)年です。ちなみに『かぜのてのひら』は俵万智の歌集名です。 七首目は感動詞「ああ」の用例です。『狂歌かがみやま』(『近世上方狂歌叢書一』)所収、題は「大石勇士の五十回忌に」です。〈忠臣は楠やなる大石ならん〉で「や」は反語。「あの楠の木が大石に変じたか。正成以来の忠臣は内蔵助だろう」と読みました。 八首目はルビのある歌です。詞書は「立春風」、「一番」は春一番、「風の手」の応用編が「風の手なみ」となります。結句のルビを濁音で読むと聴覚でズームイン、清音で読むと視覚でズームアウト、二つのイメージを重ねると風景が立ち上がってくるようです。収録する『後撰夷曲集』(『狂歌大観』第一巻)は寛文十二(一六七二)年の刊行です。 再び安田純生の指摘に戻りますが、平成二十五(二〇一三)年三月一日発行「樟蔭国文学第五十号別刷」の「和歌から短歌へ」からの引用です。 狂歌は、いうまでもなく和歌から出た一つの流れである。しかし中世近世を通して、和歌の流れとは異なる流れを成していた。それが、近代になり、用語の面において、和歌の流れが狂歌の流れを取り込んだこともあって、新派和歌が生れたともいえそうな気がする。比喩的にいえば、平行して流れる和歌の川と狂歌の川とがあって、和歌の川の水量が減少してきたので、和歌の川の方から強引に水路を掘って、狂歌の川に繋ぎ、狂歌の水を和歌の川に導いたのである。それゆえにか、和歌の川の水量は回復して豊かになり、近代短歌の大河になった。そんなふうにもいえるのではなかろうか。つまりは、狂歌は和歌に取り込まれてしまったのである。そして、このような見方に少しでも妥当性があるのならば、近代短歌の歴史を顧みるとき、狂歌の流れを視野に入れる必要があるはずである あと最後のところからも引用します。 また、江戸時代の狂歌を読んでいると、用語の面だけでなく、内容的にも近代短歌の世界を思わせるような作品が散見している。そういったことに関しても、未だ十分に検討されているとはいえないのではあるまいか。 ということで、『近世上方狂歌叢書』(近世上方狂歌研究会)から該当しそうな作品を拾い出すことにしました。まず題を外しても支障のない歌、次に掛詞の少ないことを条件にピックアップしました。どちらも近代が遠ざけたものです。最後の篩いとして自我の発露であるとか個人の心情とおぼしきものが出ているといったものを並べてみました。但し、作中の「私」が作者であることは保証しないということです。これは文芸の本質とも関わりますし、逆にいえば近現代短歌への批評が含まれていると思われます。 なかなかに田舎の水のすみよくて淀川のぼる気はござんせぬ 寺沢還愚稿 かやり火のふすべる闇の独りねに悋気(りんき)で去つたつま思ひ出す 栗果亭木端(りつかていぼくたん) さびしさは土瓶の下に火気もなしひとり坊主の庵の夕ぐれ 僧 一英 一ィ二ゥ三ィ四めいりまへの振袖のちぎれる程に手まりをぞつく 無為楽(むいらく) 是は祖父是は祖母のときるもののむかし話になりし虫ぼし 先賀 弁当のむすびをほればなつく犬の手をくれるまで遊ぶ春の野 鼠虫軒睦丸 紙袋あたまへ着せりや煤掃きに後ずさりしてふきまはる猫 破睡軒辻丸 仕事するそばには毒な火鉢ぞや得てはつゐ手のあたる物から 英果亭桂雄(えいかていけいゆう) 叱りたる子供よゆるせ今朝の春まつにほたへたきのふ一昨日 栗本軒貞国 暮れさうでくれぬといひし春の日に庭から灯す梅のはつ花 童亭源土器 脱ぎかへし布子の事も忘れてはさがす袷の袖たばこいれ 鬮丸 行燈に羽織を着せて今宵先づ手にふれそむる吾妹子が乳 橙果亭天地根(とうかていあまちね) 一首目の「なかなかに」は『狂歌大和拾遺』の一首です。作者は現在の徳島県小松島市の人です。息子は京都に住んでいます。老親を心配した息子から京都で隠居しないかという手紙がきます。それに対する返信なのです。結句は気が「ない」の叮嚀語です。 二首目の「かやり火の」は『狂歌かがみやま』の一首です。妻に逃げられた男の独り寝を詠っています。二句の「燻べる」には「煙らす」「悋気する」「煙で責める」の意味があります。妻の嫉妬に得意顔の夫、許容範囲を超えた妻の怒り、そして現在の侘びしい鰥夫の独り寝が重なります。ふすべられているのは蚊ではなく「私」なのです。 三首目の「さびしさは」は『狂歌気のくすり』の一首です。四句は「ただ一人の坊主」と「一人ぼっち」の両意なのでしょう。俳人ですが井上井月、種田山頭火、尾崎放哉といった系譜が思われます。残念なことに作品はこの一首しか見当たりません。 四首目の「一ィ二ゥ三ィ」は『狂歌落穂集(おちぼしゆう)』の一首です。手鞠の際の「ひいふうみい」の「よ」に「嫁入り前」の「よ」を重ねて活発な女性像を描いています。作者の無為楽は一方で〈ひえるはず石の地蔵も綿ぼうし召されてしのぐけふの初雪〉のような静かな、石地蔵を擬人化しているからでしょうか、温もりのある叙景歌も残しています。 五首目の「是は祖父」は『狂歌ことばの道』の一首です。三句の「着るもの」は「着物」三音の字数調整というよりも、文脈の調整だったと思われます(「着物」だと「着物を巡る昔話」等で非定型となります)。初句の「祖父」は「そふ」、二句の「祖母」は「そぼ」、洋服が普段着になる以前は、こうして異世代を繋ぐ着物だったことが分かります。 六首目の「弁当の」は『嬾葉夷曲集(らんよういきよくしゆう)』の一首です。二句は「結びを放れば」、四句は「私」が「お手」を要求して、犬がそれに応えてくれるまででしょう。行楽のシーズン、当時の言葉なら「野遊び」で弁当を広げているところに近づいた犬との交感です。 七首目の「紙袋」は『狂歌かたをなみ』の一首です。飼い主にいたずらをされた猫が紙袋の中でネコ科の野生を見せています。結句は「吹きまわる」、これに煤掃きですので「拭き回る」を掛けているでしょう。紙袋と猫なら、もう一首あります。〈猫も来ば袋に入れて鞠に蹴ん山寺淋し秋の夕ぐれ〉。作者は永田貞也、享和三(一八〇三)年刊の『和歌夷』収録の一首です。当時の手鞠唄「山寺の和尚さんは/毬がお好きで毬はなし/猫を紙袋へへしこんで/ポンと蹴りゃ/ニャンと鳴く/(略)」を下敷きにしています。 八首目の「仕事する」は『狂歌栗葉集(りつようしゆう)』の一首です。二句の「毒」は「ためにならないもの」、三句の「ぞや」は古く響きますが「だなあ」と詠嘆的強調を表します。四句の「得ては」は「ともすると」、火鉢が一般家庭から姿を消すのは燃料が炭から電気・ガス・石油に取って代わられてからですから、まだまだ実感した世代も多いと思われます。 九首目の「叱りたる」は『狂歌家の風』の一首です。三句は元旦のことです。四句は「待つにほたえた」(「ほたえた」は「ふざけた」「じゃれた」等)、正月が待ち遠しくて落ちつかなかったのでしょう。結句「一昨日」は「おとつい」と読みました。 十首目の「暮れさうで」は『狂歌手毎(てごと)の花 四編』の一首です。春は日中の時間が長い、初二句はそのことをいっています。まだ灯篭に火は入っていません、気がつくと梅の木に今年初めての梅の花が咲いていた、四句の「庭から点す」が発見の叙景歌です。 十一首目の「脱ぎかへし」は『狂歌千種園(ちぐさのその) 夏』の一首です。衣替えに取材した作品です。初夏に着る袷の袖を探っても煙草入れがない、実は木綿の綿入れである布子から入れ替えるのを忘れていたのです。煙草入れは刻みタバコを入れる携帯用の袋をいいます。和服から洋服へ、また時代は移っても、日常身辺に起こる小事件は変わりません。 十二首目の「行燈に」は『狂歌一燈集』の作品です。二句の「羽織を着せて」は照明を落としたのです。その灯りが艶めかしく逢い引きの場面を演出しています。結句の「乳(ちち)」からは与謝野晶子の〈乳ぶさおさへ神秘のとばりそとけりぬここなる花の紅ぞ濃き〉や〈春みじかし何に不滅の命ぞとちからある乳を手にさぐらせぬ〉が連想されます。 なお『現代短歌大事典』(三省堂)で「短歌」を引くと『万葉集』から説明して現代短歌に及んでいます。『日本大百科全書(ニッポニカ)』も同様です。漠然とした印象ですが、近世までを「和歌」で説明し、明治以降を「短歌」で説明しようとする従来の立場が一つあるようです。もう一つは現在にシフトして「短歌」で、この形式を概観しようとする立場です。「和歌」に広義と狭義の「和歌」があり、「短歌」にも広義と狭義の「短歌」があり、広義の「短歌」が広義の「和歌」を併呑し、こうして用語が多義性を帯びていくことは決して好ましいものとは思えません。いらぬ混乱を招くことにもなりましょう。また、どちらも「狂歌」を見ていない、見えていないというのも不思議なことです。 第五項 国歌~国学の勃興とその影~ 『万葉集』の短歌と長歌、『古今和歌集』の和歌と漢詩、このように異なる詩型を意識した名称がありました。反対に和歌と狂歌という五七五七七の形式を共有しながら異なる名称の時代がありました。それぞれの歩みを眺めてきたのですが、ひとり対抗枠を持たない名称が気になります。国歌、その屹立する名称とは何だったのでしょう。 寛保二(一七四二)年に成立した荷田在満(かだのありまろ)(一七〇六~一七五一)の『国歌八論』(小学館『日本古典文学全集50』)を開いてみましょう。但し、この歌論の中に「国歌」という言葉は一度も登場しません。連想されるとすれば「敷島の道」です。 思ひきやわが敷島の道ならで浮世の事を問はるべしとは 二条為明(『太平記』巻第二) だが在満は、その翫歌論(がんかろん)で「中古以後の官家(くわんか)の人は、天下の政務の武家に移りてわが閑暇なるままに、ひたすらに歌のみを好みて、終(つひ)に『わがしきしまの道』と称す。これ歌の本来を知らざるのみならず、道といふ事をも知らざるからの妄言」と一蹴しています(「官家」とは堂上貴族です)。では「国歌」の出所はどこか。平凡社ライブラリーの『日本語の歴史5 近代語の流れ』の第六章「言語の学問としての国学」を開くと「近世の国学者自身で、その学問を〈国学〉と呼んだ人に、荷田春満(かだのあずままろ)があるといわれるけれども、ふつう国学者のあいだでは、むしろ、〈倭学〉の名が用いられていたようだし、本居宣長にいたっては、皇国のことを研究するのに〈倭学〉と呼ぶのは不適当だとこれを退け、むしろ、〈古学〉と呼ぶべきことを説いている」とあります。在満は春満(一六六九~一七三六)の養子ですから、この「国学」を背景として「国歌」が出てきたのでしょう。 国学や国歌と聞けば幕末の尊皇攘夷をイメージしますが、時代は十八世紀、ここは記紀歌謡を含んだ古典研究といったほどの意味合いなのでしょう。やはり翫歌論ですが「歌の物たる、六藝(りくげい)の類にあらざれば、もとより天下の政務に益なく、また日用常行にも助くる所なし。古今の序に『天地(あめつち)を動かし』『鬼神(おにがみ)を感ぜしむる』といへるは、妄談を信ぜるなるべし」と明解です。六藝は中国の周代において士以上の必修とされた技芸です。 次に『明治歌論資料集成』(立命館出版部)を開くと「国歌」を標題に含む歌論が二編あります。どちらも明治二十五(一八九二)年に発表されています。一つは佐藤誠實の「国歌の韻」です。文中に一度「国歌」が登場しますが、『日本書紀』から起筆していますので、概念としては荷田在満と変わらないでしょう。もう一つは旗野桜坪の「国歌の韻を読む」は佐藤に対する自説を展開しています。「国歌」が四回、ほかに「支那詩」や「和詩」も登場しますが、記紀歌謡を含めて「国歌」の一語で代表させているようです。 なお明治三十六(一九〇三)年に出た『国歌大観』(昭和二十六年、角川書店より復刻版が出ています)の正篇は『古事記』『日本書紀』等を収録し、昭和六(一九三一)年に出た『校註国歌大系』(昭和五十一年、講談社より復刻版が出ています)の第一巻は「古歌謡集」ですので、どちらも右の流れの「国歌」と思われます。逆に昭和五十八(一九八三)年から平成四(一九九二)年に出版された『新編国歌大観』(角川書店)は記紀歌謡を含みませんが、名称を引き継いだところはその影響下と見るべきなのでしょう。 第六項 結語 以上、五七五七七の定型詩を名称の変遷に着目して眺めてきました。 その鳥瞰図を広げれば、五七五七七の定型詩は名称を変えつつ時代の波をくぐり抜けてきた、先行する五七五七七の衰退があり、それを受けた復活劇があった、このように整理できると思います。同じ歌体でありながら名称の分かれた狂歌と和歌の時代を補足するならば新興の連歌、俳諧の連歌へと和歌人口は流出したことでしょう。これに代わって表舞台に登場したのが狂歌なのです。形式が選択した自己防衛といえなくもありません。 近代短歌の形成については、まだ未解明な部分が多くあります。その解明を困難なものにしてきたのは歌人が無意識のうちに封印している、狂歌という存在なのです。 |
||||
| 第一章 第二節 歴史を俯瞰するための名称を探る | ||||
| 第一節で取り上げた名称の核は「歌」、これに対峙させる詩型によって短歌、和歌、狂歌と変化するのが近世以前でした。それらは、しかし用語としては万全でありません。詩型の要件をダイレクトに表さないということもあります。歴史を俯瞰しようとするときに複数の名称は妨げになります。とりわけ多義性を帯びた用語はなおさらです。たとえば概念としての和歌があります。これだけでも十分にスイッチの切り替えが必要ですが、「はじめに」で取り上げた『現代短歌大事典』は『万葉集』にない片歌を含めます。定義としては第五項で取り上げた国歌に近似します。『日本大百科全書(ニッポニカ)』はこれを含めずに説明します。定義としては広義の和歌といっておきましょう。以下『日本国語大辞典』『大辞林』『デジタル大辞林』『広辞苑』が国歌に与しています。これに広義の短歌という概念が絡んでくるのですから、歴史も観察者次第、一様ではありません。 もっと直截に、この詩形式を指し示す用語を私たちは知っています。主観や思い入れ、また好悪によって曇らされることのない、形式の要件だけを表す三十一文字であり、五七五七七です。この用例から入って、現在における有効性を検討してみましょう。 第一項 三十一文字 「三十文字(みそもじ)あまり一文字(ひともじ)」「三十一字」「三十文字一文字」「三十一文字」などと呼ばれる名称は、この形式の容量を表しますが、まずは和歌の用例です。 藤原公任(ふじわらのきんとう)(九六六~一〇四一)の『新撰髄脳(しんせんずいのう)』(『日本歌学大系』第一巻)は「歌のありさま、三十一字、惣じて五句あり」という一文で始まっています。 源俊頼(みなもとのとしより)(一〇五五~一一二九)の『俊頼髄脳(としよりずいのう)』(『日本古典文学全集50』)に旋頭歌について「例の三十一字の歌の中に、いま一句を加へて詠めるなり」、また混本歌のところでも「例の三十一字の歌の中に、いま一句を詠まざるなり」ともあります。 藤原清輔(ふじわらのきよすけ)(一一〇四~一一七七)の『奥義抄(おうぎしよう)』(『日本歌学大系』第一巻)の「序」に「出雲の八雲の詞より、やまと歌みそぢひともじにさだまる」とあります。 次は狂歌における用例を引きます。 寛文六(一六六六)年刊『古今夷曲集(ここんいきよくしゆう)』(『狂歌大観』第一巻)の「序」に「すさのをの尊(みこと)三十文字(みそもじ)あまり一もじによみ給ひてぞ和歌となれりける」とあります。このあと「しかはあれども人の代となりても」と展開し、「よの口遊(くちすさひ)を狂歌にいひかふるたよりにもとて千歌十巻(ちうたとまき)なづけて古今夷曲集(ここんいきよくしう)といふ」とあります。 寛文十二年(一六七二)年刊の『後撰夷曲集』(『狂歌大観』第一巻)中「夷歌式目録」の「六躰事」に「長歌とは三十一文字一首也」とあります。このあと「又古今集(に)短歌とかける部の事書きに長歌とありてかへしうた一首あるあり反歌なきあり」と続いて「未練(みれん)のものの心得にくき処なり」とあります。前者は著者不明の『新撰和歌髄脳』(『日本歌学大系』第一巻)の「和歌六義体」中「一者、二五三七。五七五七七 三十文字餘り一文字なり。是を長歌といふ」を指すと思われます。ちなみに「二者、五七五七、多少いくらもただ人の心なり。是を短歌といふ」とあります。後者は『古今和歌集』巻第十九の「長歌」とあるべきところが「短歌」になっていることを指します。雑体(ざつてい)として長歌・旋頭歌・誹諧歌を集めていますが、未熟者には了解しがたいというのです。 享保十五(一七三〇)年刊の『狂歌乗合船(のりあいぶね)』(『狂歌大観』第一巻)中「狂歌式愚案条々」に著者の永井走帆(ながいそうはん)(一六六一~一七三一)は「歌の五句は人の五体に象(カタド)る。初めの五文字を頭といひ、二の句を胸といひ、三の句と四の句の間を腰と云ふ。五句めを足とも裙(スソ)共云ふ也。此の五句三十一字の中に心の備はる事人の五体に心性の備はるがごとし。三四の間はなれたる歌を腰折とて嫌ふ也」と書いています。 次は作品に登場する「三十一文字」の一例です。 梅咲いて大木小木の花ながめあぶるかき餅みそじ一もじ 豊蔵坊信海(ほうぞうぼうしんかい) 出典は『信海狂歌拾遺』(『狂歌大観』第一巻)です。詞書は「弟子留主の淋しさに」。作者の豊蔵坊信海(一六二六~一六八八)は京都府八幡市にある石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)豊蔵坊の社僧です。豊蔵坊は幕府の祈祷所ということもあって江戸下向の旅は信海にとっては生活の一部だったでしょう。今はその仕事も弟子が代わり、老境の平穏な日々というのでしょうか、欠き餅をあぶり、庭の梅を見ながら狂歌を捻っているというのです。 第二項 五七五七七 三十一文字が歌の容量を示すとすれば、五七五七七は歌の構造を示しています。どちらも形式そのものの名称でありますが、後者は歌の分析に威力を発揮します。 まず和歌の用例です。 『新撰和歌髄脳』の「和歌六義体」の続き、箇条書きに「和歌六義体」をあげたあとの解説に該当する部分です。「第一に二五三七。五七五七七と云ふは、三十文字余り一文字なり。是を長歌といふ」。行を改めて実作を例示「いかるがや富の緒川の絶えばこそ我がおほきみの御名は忘れめ」。再び改行して「と詠み給へるをはじめとして和歌はひろまりにけるなり」とあります。『新撰和歌髄脳』は平安後期の成立とされていますが、『古今和歌集』巻第十九の逆で、短歌とあるべきところ、用語の混乱があるようです。 承元三(一二〇九)年成立の藤原定家(ふじわらのていか)(一一六二〜一二四一)著『近代秀歌』(小学館『日本古典文学全集50』)に「かの本歌を思ふに、たとへば、五七五の字をさながら置き、七々の字を同じく続けつれば、新しき歌に聞きなされぬところぞ侍る」とあります。 次に狂歌の用例です。 生白堂行風(せいはくどうこうふう)(生没年不詳)編『後撰夷曲集』(一六六五年)に「夷歌式目録」があります。その「六体事」に「所詮短歌とは五七五七とつづけ五句めに七文字にて果つべきところを」とあります。これに続けて「五文字にいひなし、それよりはいかほども心に任せて作り。結句は七七にてはつと心得(う)べき歟(や)」とあるのは『古今和歌集』巻第十九(小学館『日本古典文学全集7』)の長歌とあるべきところを短歌とある、そのことへの詠嘆の籠もった疑問でしょう。頭注には「誤りであろうが、古来明解がない」ということです。 九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい)(一七二三~一七六七)の撰になる『興歌老の胡馬(こば)』(『近世上方狂歌叢書二十三』)中「興歌五義之事」に遍序題曲流の各字を大きく掲げて、その下に「遍 一句目かしらの五文字也。あまねしと読み五句へ渡る詞置所也」「序 二句目の七文字也。上の句を受けて次の題を出す序詞也」「題 三句目五文字也。ここにて其の題を顕はしていふ所也」「曲 四句目七文字也。ここにて何ぞ何一曲有る事をいふ所也」「流 五句目七文字也。やすらかにいひながしたる詞をいふ也」云々と続きます。 第三項 五句三十一音詩 容量としての三十一文字も、構造としての五七五七七も、すでに『倭歌作式』(『日本歌学大系』第一巻』)に「択字定三十一」「抑五七五七七、一文之中予有四病」という形で登場しています。そしてその後の展開を見るに「五句三十一字」「三十一字の歌」という用語もありました。つまり短歌・和歌・狂歌といった抽象的な名称でなく、また命名者の主観や価値観の表明ともとれる名称ではなく、形式の要件のみを正面から捉えた名称として「五句三十一字の歌」すなわち「五句三十一字歌」の成立が想定されます。 なお「三十一字歌」は『明治歌論資料集成』の伊藤武一郎の『歌の律呂(リズム)』(明治二十六年)と大西祝(おおにしはじめ)の『国詩の形式に就いて』(明治二十六年)で実際に出ています。 また、この『明治歌論資料集成』には明治十五(一八八二)年から三十(一八九七)年までの代表的な歌論五十二篇が収録されています。「解説」には「明治の新派和歌は二十七八頃に誕生して、三十三年には確立するわけにいたつたのであるが、明治の歌学歌論はそれに先立つてつぶさに生みの悩みを経て来たのである」とあります。 この資料を追跡することから始めましょう。 a 三十一言 少し遠回りしますが坂野信彦の『七五調の謎をとく――日本語リズム原論』(大修館書店)の「第一章 音律の原理」の「1 日本語の音」を開くと「日本語の音(おん)は一音一音が明確に等時的なので、音の数を容易にかぞえることができます。(略)。それゆえ、かなで書いて字数をかぞえれば音数をかぞえることにもなるわけです。短歌のことを『三十一文字』(みそじひともじ・みそひともじ)と称したのも、文字数がそのままま音数を示すものであったからです」とあります。なるほど、また『日本国語大辞典』で「文字」を引くと「(2)特に日本語の、音節を表わす仮名。また、音節、音節の数」とあって用例の第一に「*古今〔905〜914〕仮名序『うたのもじも定まらず、〈略〉素戔嗚尊よりぞ、みそもじあまり一もじはよみける』」がでてきます。「字」と「音」は地続きなのでした。とはいえ「字(文字)」が「音」に代わるのは何時からなのか、見届けねばなりません。資料に当たっていくと「字(文字)」が揺らぎ始める現場に遭遇します。 明治十七(一八八四)年、末松謙澄(すえまつけんちよう)の『歌楽論』に「国歌ノ境界ノ狭少セシハ第一ニハ世人ノ熟知シ生モ屡々論ゼシ如ク重(おも)ニ三十一言ノ繊巧ヲ争ヒ思ヲ長歌ノ結構ニ費スモノナキニ至リシニ因ル」とあります。まずは「字」から「言」です。 明治二十一(一八八八)年、佐々木健(信綱)の『和歌のはなし』にも「我が国の短歌は三十一言にして、意味単純なるが故に、人情複雑、文化発達せる当時は、いかにも三十一言にては言ひつくしがたきことあるを以て、今様(七五七五と句を重ねたるもの)をいくつもつづけたるもの(今の新体詩と称するもの)を用ひて、泰西(たいせい)の詩(ポエトリー)の如く、よく人世の情慾を写し、美術壇上にたたんこそねがはしけれ」とあります。 同じ年、「三十一字」の元になる「五七五七七」にも変化が生じ、佐々木弘綱の『長歌改良論』に「上代は長短あれども、大方は、五言と七言となる物にて、古くは、先五言よりいひはじめて、七言につづくが、定りなり」と出てきます。 実作の場面ではどうなのか。筑摩書房の『現代短歌全集』で追ってみましょう。明治三十六(一九〇三)年に出た佐佐木信綱の第一歌集『思草(おもいぐさ)』(第一巻)を開くと「おもひ艸の序」(源高湛)に五度、「佐佐木君歌集題詞」(寧斎主人)に一度、「三十一言」が使われています。なお源高湛は森鴎外の別名、寧斎主人は漢詩人の野口寧斎(のぐちねいさい)と思われます。大正五(一九一六)年に出た新井洸(あらいあきら)の第一歌集『微明(びめい)』(第三巻)の序文は佐佐木信綱が書いていますが、そこにも「三十一言」が一度登場しています。 b 三十一音 明治三十二(一八九九)年、八杉貞利(やすぎさだとし)の『和歌壇の革新に就きて』に「三十一文字(綴音)」が一度登場、括弧の取れた「三十一綴音」が二度登場します。後者は「三十一綴音は我国語が多少純潔なりし時代に発達して、七綴音若くは五綴音の重畳は支那語の上に発達せし詩形なり」また「起(たて)や明治の青年歌人、たとへ卿等(けいら)が住地は区々たる三十一綴音の間に過ぎずとも、せめて卿等が思想を以て世界を横行せよ」とあります。この歌論で注意したいのは「三十一綴音」のほかに「三十一字詩形」が二度、「三十一字詩」が三度登場することです(一方では「三十一文字」もあって定まらないのですが…)。 実作の世界では、どうでしょうか。大正十一(一九二二)年に刊行なった石原純(いしはらじゆん)の第一歌集『靉日(あいじつ)』(『現代短歌全集』第五巻)の「歌集に関することども」に「歌の各首の書き方は今日では句読も何もなしにのべつに一行若くは二行に亘りて書くのが普通であり、私たちもその方を見慣れてはゐますが、等しく三十一音であり、又五、七、五、七、七音の連続であると云ひましても、実はそのなかに多様の韻律を含んでゐるのであつて、連作短歌の単調の感じを与へないのも之に依ると私は思つてゐます」とあります。 c 歌か、詩か、その分岐点 近代短歌の黎明期の歌論を中心に見てきましたが、「五句三十一音」までは史的事実として確認できました。では百年をタイムスリップすることにしますが、歌論の帰着するところであろう、現在の辞典は「短歌」をどのように規定しているのでしょうか。 『現代短歌大事典』には「五・七音節の短長句を五七五七七と五句組み合わせた歌体」とあります。『日本大百科全書(ニッポニカ)』からは冒頭の「ほぼ7世紀ころから現在までつくられ続け味わわれ続けている、各句五または七音節で五七五七七の五句からなる、日本固有の叙情詩形」を引いておきます。『デジタル大辞泉』は「五・七・五・七・七の5句31音からなる歌」、『大辞林』には「和歌の一体で,最も普通の歌体。五七五七七の五句三一音を原則とする」とあります。『日本国語大辞典』には「和歌の一体。長歌に対して、五七五七七の五句から成るもの」ですが「和歌」を引くと「長歌・短歌・旋頭歌・片歌など五・七音を基調とした定型詩であるが、歌体の消長に伴って短歌が和歌を意味するようになった」とあります。『広辞苑』は「和歌の一体。長歌に対して、五・七・五・七・七の五句体の歌」と「近代詩歌の一ジャンル。五・七・五・七・七からなる定型の詩」の二意をあげますが「音」は出てきません。ただ「和歌」を引くと「長歌・短歌・旋頭歌・片歌などの総称」とした上で「狭義には31音を定型とする短歌」とあります。 「短歌」は紛れもなく「歌」ではありますが、それでも「叙情詩形」「定型の詩」「定型詩」といったかたちで説明もされています。なぜなら「短歌」とは一方で「短詩型」として俳句や川柳と歩みを共にしているからです。また「定型詩」として俳句や川柳・漢詩・ソネットなどと共に自由詩、不定型詩と向き合っているからでもあります。 歴史を俯瞰する名称としての「五句三十一音」は、その一歩手前、「歌」と連結もできるし、「詩」とも連結できる、そうした分岐点にあるといえそうです。 第四項 結語 断っておかなければならないのは、ここ百年をタイムスパンとした話なら「短歌」で十分なのです。わざわざ「五句三十一音詩」を振り回すこともありません。同様に『万葉集』の時代なら短歌、『古今和歌集』以降なら和歌、近世なら和歌と狂歌でいいのです。しかし千四百年にわたる五七五七七の歴史を展望するときの名称となると別でしょう。 広義の和歌であっても、逆に広義の短歌であっても十分ではありません。 五句三十一音詩を提唱する理由としては、 一、混乱を招く多義性と無縁の、形式の容量と内容に直結する名称であること。 二、通時的には「五句三十一音」、共時的には「詩」で対応できること。 三、ツールとしての日本語を考えるときに狂歌なしの「史」は考えられない。 以上です。和歌と狂歌の対立は雅俗などではありません。変化する日本語と、どう向かい合ってきたのか、あるいは向かい合わなかったのか、そこに尽きるのです。 |
||||
| 第二章 ツールとしての言葉の歴史を俯瞰する | ||||
| この章では一般に口語と文語あるいは口語体短歌とか文語体短歌といわれている言葉のスタイルを扱います。但し、用語としての「口語」と「文語」は基本的に使用しません。第一に「口語」と「文語」が多義語であるため、そこから来る混乱を避ける狙いがあります。たとえば明治書院の『日本文法大辞典』で「口語」を引いてみましょう。 ①話しことば。音声言語。口ことば。書かれたことば(written language)に対して、話されることば(spoken language)の意。②現代語。明治以降の日常生活に用いられることば。この場合には書かれたものも含めて「近代口語文」「口語文法」「口語に訳せ」のように用いる。以上の二つの意味がある。①の意味が本来のもので、文章語・文語に対して、「当時の口語では」のように用いる。ところが、明治以降、古典にみられる書記言語・雅語や、明治普通文・雅文などに用いられる語体系を「文語」と呼ぶのに対して、当代の話しことばおよびその語体系に基づく書記言語を「口語」とよび、その文法を「口語法」「口語文法」といったことなどから、②の意味に用いるようになった。 次に反対語となる「文語」も引いておきます。 ①書きことば。文字言語。話されることば(spoken language)に対して、書かれたことば(written language)の意。②古典語。日本語の場合、平安時代中期の文章(当時としては話しことばを写したもの)が一種の完成を示し、鎌倉時代以後、話しことばの変化にかかわらず、文章には平安時代中期の語法を基礎とした表現をとるようになって、明治中期にまで及んだ。この、平安時代中期の語法に、その後の若干の語法の変化をとり入れ、さらに若干の奈良語法をも含めた語体系を、明治以後の現代語を「口語」というのに対して、文語というのである。現代では短歌・俳句の創作などに残っている。「近代文語文」「文語文法」「文語は歴史かなづかいによる」「『べき』は文語的表現だ」のように用いる。文語文という場合、使用語彙も無視できない要素であるが、主として語法によって口語文と区別している。「古語」はある単語に関していう場合が多い。 以上のように、使用に際して①か②の確認を要すること自体が問題でしょう。なお本書の場合は終始①の立場に拠っています。現代語における口語あるいは現代語における文語です。同様に古典語における口語また古典語における文語といった具合です。文法なら現代語文法(現代文法)、対する古典語文法(古典文法)です。用語として採用しない理由の第二は、②の場合ですが、「口語」(現代語)と「文語」(古典語)はフィフティフィフティなのだという誤ったメッセージを伝える恐れがあるからです。スタンダードツールの現代語に対して古典語はその習得の困難さからいってもスペシャルツールなのです。 「口語」と「文語」に代わる用語としては、固有の文字を持たなかった『万葉集』の時代の言語体、固有の文字である平仮名を手にした『古今和歌集』の時代の言文一致体、その後の言文二途の時代における言語体と文語体、近代における言文一致運動の成果としての言文一致体、このように区分して歴史を俯瞰することにします。 なお言語体という用語は耳慣れない言葉ですが、先例がないわけではありません。言文一致に功績のあった二葉亭四迷の追悼文に幸田露伴の「言語体の文章と浮雲」(岩波書店『露伴全集』第二十九巻)があり、奇しくも本稿とテーマを同じくしているのです。 |
||||
| 第二章 第一節 言語体~『万葉集』の時代~ | ||||
私たちが固有の文字を持たなかった時代の『万葉集』は漢字を利用して、漢字だけで書かれています。たとえば音仮名(漢字の音を借りて日本語の音節にあてたもの)や訓仮名(漢字の訓をその意味とは無関係に日本語の音節に当てたもの)、また正訓(漢字本来の意味に基づいた訓)や義訓(漢字漢語の意義によって訓を当てたもの)を利用して和文が綴られているのです。先の「口語」でいえば①の「話しことば。音声言語」、「言文」でいえは「文」を欠きますので、これを「言語体」と名付けることにしました。 |
||||
| 第二章 第二節 言文一致体~平仮名と『古今和歌集』~ | ||||
平安時代の初期に至って、私たちは固有の文字を持ちます。それが平仮名です。先の「口語」でいえば①の「話しことば。音声言語」に対応する「文語」の①「書きことば。文字言語」が登場するのです。「言文」の「文」を手にしたのです。ところが厄介なことに「口語」と「文語」のそれぞれ①の意味が後退を始めます。明治だから近年のことです。 第一項 文語とは何か? ここでいう「文語」とは先の『日本文法大辞典』の②すなわち古典語を意味します。では「古典語」とは何か。『日本語の歴史4移りゆく古代語』(平凡社ライブラリー)の「第三章 古典語の周辺」の「三 散文の世界に照明をあてる」から引用します。 平安時代の散文ことに和文は、言文一致であったということである(平安時代の散文に女流の手になる物語や日記のみならず、男性のがわにみられる漢文や変体漢文の日記・記録をもふくめて、一様にこれを言文一致とみることにはなお異論があろう。いまそれについてくわしく述べる余裕がない)。 次に歌人で学者、歌言葉の専門家として知られる安田純生の「文語体と口語体」(「白珠」平成二十二年七月号)からの引用です。 文語は平安時代の日常語なのですから、その時代の和歌は、特有の歌語を交えることはあっても、また、音数律に合わせて表現するという、日常語にない特殊性はあっても、基本的には言文一致歌でありました。万葉時代でも、おおよそは、そういえます。 言文一致歌を書き表す平仮名については山口仲美の『日本語の歴史』(岩波新書)に「和歌を詠む時は、男性だってひらがなを用います。『古今和歌集』に収められている和歌の多くは男性作者ですが、もちろん、ひらがなで書かれています」とあり、また、 ひらがな文は、自分たちの日常使っている話し言葉を基盤にする文章です。日常使っている話し言葉で文章が書ける、こんなすばらしいことが到来したのです。 とも述べています。「文語」(古典語)は従来の「言」に加えて平仮名という「文」のツールをも得たのでした。換言するならば言文一致は五句三十一音詩の原点なのてす。 第二項 試みに『土佐日記』を読んでみましょう 最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』編集の中心として「仮名序」を執筆した紀貫之(八七〇頃~九四五)は同時に仮名文日記文学の先駆とされる『土佐日記』の作者でもあります。後者には言文一致歌の機微を如実に語る場面があって注目されます。 御船(みふね)よりおふせ給(た)ぶなり朝北(あさぎた)の出(い)で来(こ)ぬ先に綱手(つなで)早曳(はやひ)け 紀貫之は延長八(九三〇)年に土佐守となっています。任国土佐の国府を後にしたのは承平四(九三四)年十二月二十一日、右に抄出したのは承平五(九三五)年二月五日、場所は「和泉の灘」(大阪府泉南郡泉町)です。さて抄出した五七五七七ですが、 「船疾(と)く漕(こ)げ。日のよきに」と催(もよほ)せば、楫取(かぢと)り、船子(ふなこ)どもにいはく、「御船より、おふせ給ぶなり。朝北の、出で来ぬ先に、綱手早曳け」といふ。この言葉の歌のやうなるは、楫取りのおのづからの言葉なり。楫取りは、うつたへに、われ歌のやうなる言(こと)いふとにもあらず。聞く人の、「あやしく。歌めきてもいひつるかな」とて、書き出(い)だせれば、げに三十文字(みそもじ)あまりなりけり。 御船(紀貫之)の意向を受けた船頭が水夫に与えた指示だったのです。それが五句三十一音詩のように聞こえたというのです。朝北は朝のうちに吹く北風をいいます。 『土佐日記』には、このほかにもジュニアの五句三十一音詩が登場して注目されます。作者は紀貫之だろうということですが、そうしたシチュエーションがあっても不思議でなかった、また必要としたからこその場面であり、少年や少女だったのでしょう。 次のような作品です。 ゆく人もとまるも袖の涙川みぎはのみこそ濡れまさりけれ 或(ある)人の子の童(わらは) 承平五年一月七日、船は大湊(おおみなと)(未詳)に停泊しています。大湊は物部川河口の西と推定されていますから距離的にも国府の近くです。差し入れに来る人も多いのです。初二句の「ゆく人」は都に帰る人、「のこる」は土佐に残る人また国人も含まれるでしょう。三句の「涙川」は川のように流れる涙、漫画のような比喩ですが目頭に当てる袖が川のようだというのです。四句の「汀」は陸地と水の接するところをいいます。乗り物は船ですから別れる場所、その縁語にもなっています。ちなみに『日本国語大辞典』は「みぎわ優る」で「(汀の水が増すというところから)涙がとめどなく流れる」意を上げています。 まことにて名に聞く所羽(はね)ならば飛ぶがごとくに都へもがな ありける女童(をむなわらは ) 一月十一日。「ありける」は「例の」「以前の」ですから作者は「或(ある)人の子の童」となり、「童」は少女だったことが分かります。羽は現在の高知県室戸市羽根町、羽根岬があり、この歌が歌碑になっています。結句「もがな」は終助詞「もが」と「な」の重なったもの、格助詞「へ」を受けて願望を表します(「飛ぶように都へ帰りたいなあ」)。 立てば立つゐればまたゐる吹く風と波とは思ふどちにやあるらむ 女(め)の童(わらは) 一月十五日、場所は現在の室戸市室津です。室戸岬を回れずに十一日から二十日まで十泊を重ねるところです。二句の「ゐる」は『日本国語大辞典』に「植物や無生物の場合」として「(ふくらみのあったものが)平らになる」を上げています。「風が立てば波も立つ、風が収まれば波も平らになる、風と波とは仲のよい友だち同士なのかしら」。 漕ぎてゆく船にて見ればあしひきの山さへゆくを松は知らずや 年九(としここの)つばかりなる男(を)の童(わらは) 一月二十二日、場所は「夜(よる)べの泊りより、異泊(ことどま)りを追ひてゆく」海上、「はるかに山見ゆ」といったところです。歌意は「乗っている船から見ると山も一緒に進んでいる。あの松は自分たちのたっている山が動いていくのを知っているのかな」でしょう。 わたつみの道触(ちぶり)の神に手向けする幣(ぬさ)の追風(おひかぜ)止(や)まず吹かなむ 在る女(め)の童 一月二十六日。作者の「在る」はそこに「居合わせた」、海賊が追ってくるというので夜中に出港しているのです。二句は「旅の安全を守る神に」、四句の「幣」は麻・木綿・紙などで作った供え物、道祖神の前でまき散らして手向けるのですが、海上ですから「幣に吹く追い風」となります。結句は期待で「止まずに吹いてほしい」となります。 ところで気になるのが影の主役と呼んでもいいでしょう、舞台である船のことです。一月「十二日。雨降らず。ふむとき・これもちが船の遅れたりし、奈良志津より室津に来ぬ」から一行は三隻と想像されます。帆は備えているようですが、使ったのは二十六日「漕ぎ来る途(みち)に」「風のよければ、楫取りいたく誇りて、『船に帆を上げ』など喜ぶ」の一度きりなのです。あとは人力で漕ぐか、陸が近ければ二月一日「今日は箱の浦といふ所より、綱手曳きてゆく」という按配で引き船となります。船に何人が乗っていたか、記載はないので、ざっと拾ってみました。「女(日記の作者)」「或人(前の守・船人・船君・船の長・御船)」「翁人」「専女(たうめ)」「稚き童」「或(ある)人の子の童(ありける女童(をむなわらは))」「母(昔へ人の母)」「女の童」「年九(としここの)つばかりなる男(を)の童(わらは)」「在る女(め)の童」「淡路の専女(淡路の島の大御(おほいご)・淡路の御)」「或童」「或人」「或女」「人人」「女これかれ」「つきて来る童」「郎等」「楫取り」「船子」などです。重複する部分があるとしても、複数の「郎等」や「船子」を入れて数十人が乗っていたのでしょう。構造物としては船屋形と船底が出てきます。前者は船上に設けた屋根付きの部屋で、この時代は船が小さいこともあって一階造りだったようです。後者は「まして女は、船底(ふなぞこ)に頭(かしら)を突き当てて、音(ね)をのみぞ泣く」(一月九日)「『都近くなりぬ』といふを喜びて、船底より頭をもたげて」(二月六日)とあり、窮屈この上もなかったと思われますが、居住空間として使われていたことが分かります。 祈り来る風間(かざま)と思(も)ふをあやなくもかもめさへだに波と見ゆらむ 或童(あるわらは) 二月五日、「和泉の灘より小津(をづ)の泊りを追ふ」。小津は大阪府泉大津市が推定されています。初二句は「祈ってきた甲斐があっての風の絶え間だと思うのに」、三句は「いわれもなく」、下句は「なぜ鴎さえすら波に見えるのだろう」となります。「風波(かぜなみ)止まねば、なほ同じ所に泊れり」(一月十六日)、「なほ同じ所にあり、海荒(あら)ければ船出(い)ださず」(一月十八日)、二月二日「雨風(あめかぜ)止まず。日一日(ひひとひ)、夜(よ)もすがら、神仏(かみほとけ)を祈る」、三日「海の上、昨日のやうなれば、船出ださず」、四日「楫取り、『今日、風雲(かぜくも)の気色(けしき)はなはだ悪(あ)し』といひて、船出ださずなりぬ」、こうした調子で泊を重ねていくのですから鴎が波に変化(へんげ)してもあながち不思議でもありません。あるいは強迫観念に近いものでしょうか。 二月十五日に下船、『日本古典文学全集9』(小学館)に載る「土佐日記の旅程」によると十六日の帰京までに五十三泊を要しています。そうした中、船を舞台にして、少年や少女が歌を披露できたのはそれが日常語の延長だったからに外ありません。 |
||||
| 第二章 第三節 言語体~言文二途に見る狂歌の位相~ | ||||
この節で扱う「言文二途」とは「話しことばの表現と、書きことばの表現とが一致していないこと。二つの文体に分かれていること」(『日本国語大辞典』)をいいます。 『日本語の歴史4移りゆく古代語』(平凡社ライブラリー)の「第三章 古典語の周辺」の「三 散文の世界に照明をあてる」中、小見出し「平安時代は言文一致の時代」は、 平安時代の散文を言文一致であるとして、それなら言文が二途に分かれる契機をどこに求めたらよいかという問題が、ここにでてくるはずであるが、それについて、国語学者の亀井孝が興味ある見解を提出しているので、それを紹介してみる。 で終わります。亀井孝は『日本語の歴史』の三人いる編集委員の一人ですが、続く小見出し「言文二途に開ける」の出だしの部分を読んでみましょう。 はじめに、そこから結論らしきものを要約してみれば、彼は《徒然草》に、言文二途の開きをみるというのである。もちろん、彼は慎重な態度をとって、そこから一般論をみちびきだそうとはしていないし、むしろ、《徒然草》の時代に、文語と口語をへだてる壁が、いまだそれほど高くも厚くもなかったとさえ推定している。しかし、そういうことよりも、《徒然草》の時代に、文語と口語とのあいだに境界線があったこと、さらには、いつの時代にもあるはずのその境界線が越えがたい壁になってゆく過程にこそ問題があることを、はっきりと指摘しているのである。 なお『徒然草』は一三三〇年から一三三一年頃の成立、室町時代は一三三六年から一五七三年です。日本語は文法史的には大きく古代語と近代語に区分されます。鎌倉時代と室町時代は長い過渡期にあたるそうです。この点、一般の時代区分と異なっています。 言文二途の壁とは、現代語の話し言葉と書き言葉の関係であった平安時代に対して、両者の乖離が進んだ結果、現代語の話し言葉と古典語の書き言葉という組み合わせが出来てしまっていることでしょう。これに五句三十一音詩史を重ねるならば、当代の言語体に拠る狂歌に対して前代の文語体に拠る和歌という近世の位相が見えてきます。 活力という点では比ぶべくもないでしょう。時代の前線に躍り出る狂歌に対して後退戦を余儀なくされる和歌、それは決して雅俗の問題ではありません。変化する日本語と、どう向き合うのか、この一点です。そして歌の原点は狂歌に引き継がれたのです。 第一項 狂歌人の歌論 狂歌集に見ることのできる歌論のうち、ツールとしての言葉に触れたものを引用します。読みやすさを考慮して漢字表記への変更、句読点等を施しました。 a 由縁斎貞柳(ゆえんさいていりゆう)(一六五四~一七三四) 貞柳の十七回忌にあたる寛永三(一七五〇)年刊『狂歌手なれの鏡』(栗柯亭木端撰)に「柳門狂歌十徳」(跋文)があります。署名は栗柯亭人、木端の門葉という意味でしょう。貞柳といえば『続家づと』(一七二九年)の「箔(はく)の小袖に縄帯(なはおび)したる姿によみ出づる外に別の習ひ候はず」が知られていますが、その高弟である木端一門で喧伝されたのが次の十箇条でした。 本歌物語の詞を用ゆれば歌人(うたびと)も口ずさみ 古詩本語を用ゆれば詩人もまた吟弄(ぎんろう)し 俗諺(ぞくげん)俳言(はいごん)を用ゆれば児女(じじよ)のたぐひ牧童(ぼくどう)樵夫(しようふ)のともがらも耳近くて心得易し 梵漢の語も其のままに用ゆれば詞広くして詩歌にいひ残す情も述べやすし 詞長うして俳諧の句に云ひ尽くし難き趣意もまた云ひ叶へ易し ことば聞こえやすくて教戒の助に成り易し 流行り歌、流行り言葉の拙きも此の道に用ゆれば優しくなれり 即席の詠に興を催しやすし 余力なき人も学び易し 和歌の本意を忘れねば箔の小袖に縄帯の言葉の海に簸(ふ)の川上の流れを堪へたり 一の「本歌物語」は『伊勢物語』や『大和物語』などの歌物語をいいます。二を例示すると木端に〈無心なる雲にもあらで我は今朝くきの城下をたちいでにけり〉があります。これは陶淵明の『歸去來兮辭』の一節「雲無心以出岫」を用いたものです。「岫」は山の峰、但し四句は「九鬼の城下」(三田藩)で同音異語となります。三の「俗諺」はことわざ、「俳言」は俳諧に用いて和歌や連歌などには用いない俗語や漢語などをいいます。四の「梵漢の語」は「梵語」(サンスクリット語。仏典の音写を通して日常語になった言葉に塔婆、閻魔、袈裟、夜叉、奈落などがあります)と「漢語」(字音語)をいいます。言葉に関しては次に七の「流行り歌、流行り言葉」が注目です。十の「簸(ふ)」は動詞で「箕(み)で穀物などをあおって、もみがらやごみなどを除く」(『日本国語大辞典』)意、「堪へたり」は「湛へたり」の誤りでないかと思われます。貞柳自身の言葉としては先の『続家づと』に「もし他をそしるの落首をよみ候はば和歌三神の御罰(ごばつ)を蒙り信海法印(しんかいほういん)半井卜養(なからいぼくよう)二仙の教へにはづれ本意に背き候べし」があることも注意したいところです。 b 栗柯亭木端(りつかていぼくたん)(一七一〇~一七七三) 宝暦八(一七五八)年刊の『狂歌かがみやま』の序文より抄出します。 狂歌の狂の字を思ひ違(たが)へ、狂乱の人の詞(ことば)に等しく、あらぬ由無し事を云ふと心得し人も少なからず。此の狂の字は柿の本に詠み慣れざる方の詞をも栗の本に憚りなく詠み出だせる違ひある故、強いて借り用ひたるまでなり。たとへば商人(あきびと)の取り扱ふ扛秤(ちぎ)となんいへるものの軽重の少し違ひたるを狂ひたると云ふに同じ。大いに変はれるを云ふにはあらじ。 要点は「柿の本に詠み慣れざる方の詞をも栗の本に憚りなく詠み出だせる違ひ」でしょう。狂歌という名称は和歌から与えられたものですが、素材の選択においても用語においてもフリー・ハンドであるならば、この名称を捨てるという選択肢もあったわけですが、そこのところが近世という時代なのでしょう。「扛秤(ちぎ)」は桿秤(さおばかり)の一種をいいます。 c 九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい)(一七二三~一七六七) 刊記なし、宝暦元年未臘月(ろうげつ)の序がある『興歌老の胡馬(こば)』から抄出します。なお宝暦元(一七五一)年の朧月(十二月)は『日本暦西暦月日対照表』(日外アソシエーツ )によると新暦では一七五二年になります。さて鈍永ですが「当意即妙の風情をつらね、樵夫牧童の耳目までも喜ばしむ、まことに詞の雅俗は選ばざれど和国の風俗にして疎ならぬ道なんめり」(「序」)と述べ、本文の「本歌興歌の大意」では次のように展開しています。 興歌は心詞あたらしく、ただ物に任せて興を述べ、言ひ慣はしたる諺あるひは時里巷歌謡の類まで嫌ひなく一首に仕立つる也。されど述ぶる情は一つ也。月は月、花は花、雪は雪と目に見、耳に聞くもの貴賤の差別なし。この道の広きこと本歌に詠まれぬ詞まで用ひ、当意の妙、本歌に劣ることなし。 「時里巷歌謡」の「時(じ)」は「さだ」で盛時(の歌謡)、「里巷(りこう)」は村里(の歌謡)の意で解しました。「嫌ひなく」は「差別なく」、「本歌」は「和歌」のことをいいます。 d 永日庵其律(えいじつあんきりつ)(一七二〇~一七六一) 延享三(一七四六)年刊の『狂歌秋の花』より序文を引用します。このときの其律は満で二十六歳です。周囲の信頼や期待も大きかったことが思われます。 やまと歌は人の心を種として万(よろづ)の言の葉となり、狂歌は世俗の言葉を綴りて人の耳を喜ばしむ。禁色の道因殿と聞くほどに、引銀瓶のはての可笑しさとは知らぬ、雲居の流行り事にして定家卿の戯(たはぶ)れとなん。賤(しづ)・山賤(やまがつ)の木こり歌まで三十一文字に詠みなせるは、全(また)く栗の本の言葉にこそあなれ。 ただ「禁色の」から「戯れとなん」は意味を把握できませんでした。「禁色の道因殿」は『古今著聞集(ここんちよもんじゆう)』(岩波書店『日本古典文学大系84』)巻第五の「敦頼入道大納言実国(さねくに)を訪ひ和歌を応酬の事」を指すと思われます。短いので全文を引用しておきます。 馬助敦頼、出家の後、すなはち大納言実国のもとへまうでたりけるに、扇にかきつけられ侍ける、 むらさきの雲にちかづくはし鷹はそりてわかばにみゆる也けり 返し、道因法師、 はし鷹のわかばにみゆときくにこそそりはてつるはうれしかりけれ 一首目の「逸りて」に対して二首目は「剃りて」となります。次の「引銀瓶」は白楽天の諷喩「井底引銀瓶(せいていいんぎんべい) 淫奔(いんぽん)を止(とど)むるなり」(日本図書センター『白楽天全詩集』第一巻)でしょう。「題義」に「女子の淫奔を戒めた詩」とあります。要所は、しかし、この部分を除く「狂歌は世俗の言葉を綴りて人の耳を喜ばしむ」と「賤(しづ)・山賤(やまがつ)の木こり歌まで三十一文字に詠みなせるは、全(また)く栗の本の言葉にこそあなれ」に落ち着くでしょう。 e 山中千丈(生没年不詳) 明和四(一七六七)年刊の自詠集『狂歌鵜の真似』の「序文」の一節です。 常にもて扱ふ世話詞を以て、三十一字に続けて、見る事思ふ事心に任せて云ひ述べんとて書き集められしより年頃も十年(ととせ)に余れり。 「世話詞」は「世話言葉」で『日本国語大辞典』に「日常用いることば。通俗のことば。俗語」とあります。「年頃」は「年来」でしょう。六十余歳の作者が旧作の処理について相談した友人の答を紹介したものです。その友人、津田千里が跋文を寄せています。 f 二松庵万英(にしようあんまんえい)(?~一七八〇) 天明四(一七八四)年刊の遺詠集『狂歌月の影』から「序文」を抄出します。「跋文」(二松庵清楽)によれば「幸ひに作り置かれし文章」を始めに置いた由です。 狂歌の詠み方は、ただ有りのままを詠み出だし、雅俗の言葉にも関はらねば、其の式もやや難しからず。卑賤の人の耳に入りよく、詠み出づることもまた易ければ上下の情相感じ易し。狂歌の体は古事記日本記(ママ)等には夷歌といひ、詠歌本記(ママ)には和歌の八体を題して戯歌と名付け、八体のうちの一体に備へられき。さるから万葉集には本歌狂歌の分かちなく国々傍人(ぼうじん)の歌なんど多く載せられたり。古今集には詞花を専らに撰りて、その俗語なるものを分かちて誹諧歌の部類をたてられたる也。其の後、俊成定家の両卿の頃に至りて専らに是を狂歌といへるにや。 当時、共有されていたであろう、オーソドックスな狂歌史が述べられています。うち「詠歌本紀」は『先代旧事本紀大成経』という本に収められています。これは近世初期に成立、聖徳太子撰を詐称した神道書でした。注目したいのは「雅俗の言葉にも関はらねば」また狂歌の出自への全幅の信頼といったものでしょうか。もう一箇所、引用します。 後鳥羽上皇は殊に敷島の道に愛で愛し給ひ、其の妙を極め給ひしも、上下の情相感ずるに至りては狂歌の徳多きことを知ろしめし給ひ、水無瀬の和歌所にも柿本栗本とて二もとを置き給ひけるとなん。 こうした歴史認識が主流となって狂歌史が形成されていきます。仮に栗本の狂歌と呼ぶならば、彼らと対照的な天明調狂歌については後に触れることになります。 g 仙果亭嘉栗(せんかていかりつ)(一七四七~一七九九) 浄瑠璃作者としては紀上太郎(きのじようたろう)、本名は三井高業(たかなり)、三井六本家の一つ、京都の南家に生まれています。寛政四(一七九二)年刊の『狂歌栗下草(くりのしたくさ)』の「後序」から抄出します。 和歌は万(よろづ)の言種(ことぐさ)のさまざまこころごころに詠み出づるといへども、詞は三代集のうちを出でずとかや。仮名遣ひも定まりたる格式ありて、そを学ぶも又たはやすからず。わが狂歌の道には俗語俚諺はもとより和歌に詠み慣れざる字音をも其のまま云ひ出づれば、敷島の道の外に、四声開合直音拗音の仮名をも字書韻鏡によりて諦めざれば、懐紙短尺等にも仮名の折れ合ひ平頭同韻の用捨に詳しく、筆を取りがたきやうなり。されば和歌の道よりもなほ言葉広く事繁きに似たり。しかはあれど、その事知り顔に難しく詠み出づるにはあらず。かく心得て、さて事に当たりて口軽(かろ)く心床しく詠むを道を得たりといふべし。 文中の「字音」は漢字の発音をいいます。「四声」は漢字の韻による区別、「開合」は開音と合音、「直音」は「いっさいの字に直音と拗音があるという抽象的な言語理論に立って、仮名一字で表わされる音」(『日本国語大辞典』)、「拗音」は仮名二字で表わされる音をいい、「字書」は字典、『韻鏡』は中国の音韻図を指します。「折れ合ひ」は「折り合ひ」(連句用語で止めの字が同じになること)、「平頭」は「平頭の病」(上句と下句の始めが同字であるもの)の略、「同韻」は「同韻相通」(同母音を持つ音が互いに通用すること)の略と思われます。和歌と狂歌の優劣論ではなく、分析し、比較するところに主眼があります。要所は「俗語俚諺はもとより」「字音をも其のまま」あたりでしょう。 h 木室卯雲(きむろぼううん)(一七一四~一七八三) 以下、江戸の狂歌論です。 年代的には山中千丈の『狂歌鵜の真似』(一七六七)以後の上方狂歌と並走するかたちとなります。江戸狂歌でいえば卯雲以前に半井卜養(一六〇七~一六七八)と豊蔵坊信海(一六二六~一六八八)の遺髪を継ぐ黒田月洞軒(一六六〇~一七二四)がいます。 安永五(一七七六)年刊の編著『今日歌集(きようかしゆう)』の「凡例」より抄出します。 狂歌の狂の字、今、花洛には興ずるを専らとなせばとて六義の興の字を用ひ、浪花には本歌と狂歌は秤目の狂ひのごとく僅かの違(たが)ひを取れりと狂の字を用ひる由、東都に其の沙汰なし。ただ雪月花に狂ふの狂の字を用ゆ。取り敢へず祝し、取り敢へず事を述ぶるなれば今日歌と云はんも然(しか)るなるべしや。 文中「花洛」云々は九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい)(一七二三~一七六七)、「浪花」云々は栗柯亭木端(りつかていぼくたん)(一七一〇~一七七三)のことで、二人とは京都で会い、歌を交わしています。 京の旅やどりへ芦田鈍永初めて来りし時 浅づけのおし小路から来た人は京で興歌の大かうのもの かへし 鈍永 浅づけの浅からぬことのはあたりや一しほかげんよき御歌なれ おなじ頃なにはの木端叟尋ね来まして閑談時うつりしに 木端 心をばふかく染めたる江戸むらさき知恵の浅黄のいろの恥づかし かへし 難波江の水の浅黄のきれいさに江戸むらさきはみさめ((ママ))恥づかし 一首目。鈍永の姓は蘆田、仁和(にんな)寺(京都市右京区)の寺侍で、このときは押小路に住んでいました。結句「大かう」は「大剛」に「だいこ」(「大根」の音変化)を掛けたものでしょう。二首目は二三句「ことの葉」に「言の葉」、四句「一入」に「一塩」を掛けています。三首目の「叟(そう)」は老人を敬っていう語、「来まして」も木端に対する敬意を表すでしょう。三句の「江戸紫」は江戸染め、江戸を象徴する染め色とされています。四句の「浅黄」は緑がかった薄い藍色ですが、ここでは挨拶として浪花の不粋とか野暮の意味を重ねているでしょう、四首目の二句「水の浅黄」(水浅黄)は水色をいいます。 また鈍永は四十五歳で若死にするわけですが、やはり『今日歌集』に、 鈍永が終の別れをいたみて 終に行く道へ旅出の九如館きのふけふとはおもひ木や町 初めは押小路に有り後木や町へ居をうつし死せり という挽歌が収められています。「木や町」は「木屋町」、一首は在原業平の〈つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを〉(『古今和歌集』八六一)を下敷きとしています。結句「おもひ木や」は「思ひきや」を重ねているでしょう。 こうして眺めて見ると木室卯雲とは前期江戸狂歌の流れと後期江戸狂歌の流れが交わる潮目に立っているようです。前者については右の逸話が十二分に物語っています。後者についていうならぱ「凡例」の「雪月花に狂ふの狂の字を用ゆ」が、その分岐点を示しています。鈍永の「心詞(こころことば)の新しさ」でいえば、少なくとも「詞の新しさ」(歴史)を放棄したのが右の「狂」(今日)にほかならないからです。ちなみに「心詞」とは「歌の内容と用語。素材観照の心とそれを表現することば」(『日本国語大辞典』)をいい、「新しい」は「旧来のやり方を改めている」(『大辞林』)や「今までにはなかったものである。現代的、進歩的などの意を含めても用いる」(『日本国語大辞典』)を意味するでしょう。 i 元木網(もとのもくあみ)(一七二四~一八一一) 天明三(一七八三)年刊の狂歌論『狂歌はまのきさご』から抄出します。 狂歌に法なしといへども、歌にすがりて詠み、歌の式に拠るべし。ただ常の言葉を三十一文字に言ひ続くるなり。しかしながら歌の古き言葉を借りて新しき狂言を入れて詠むべし。 「歌」とは本歌、和歌のことです。元木網のいう「常の言葉」が日常語をいっているのでないことは、これと次の「歌の古き言葉を借りて」で分かります。「狂言」は戯れ言でしょう。「言葉(詞)は古いツールを使いましょう」、そう言っているのです。 j 朱楽菅江(あけらかんこう)(一七三八~一七九八) 天明七(一七八七)年刊の狂歌論『狂歌大体』から抄出します。 近来、鯛屋貞柳(油煙斉)・半井卜養などいへるやから時々流行の詞をもて蒙昧の耳目を驚かせり。あらぬ風情を求めて、歌のさまに関はらず、軽口などいう類にて座客におもねり、笑ひを求む。然るを当世の児女これを狂歌のさまと心得、まことの狂歌を知らず。浅ましくなん侍る。 文中「やから」(輩)に恫喝の響きが籠もりますが貞柳は一七三四年没、卜養は一六七八年没ですから、これを「近年」とするのは疑問です。本来なら木端や鈍永を槍玉にあげなければならないのですが、それでは役不足なのでしょう。源頭の二人に矛先を向けています。しかし何を怒っているのか。おそらく「蒙昧」人や「児女」にも分かる歌が頂けないのでしょう。ちなみに卜養は幕医として最上位の典薬頭(てんやくのかみ)を務めています。その卜養に歌を所望する人が「蒙昧」とは一般的でありません。住む世界は異なりますが、貞柳も事情は同じで、このあたりの事実誤認は承知の暴論を展開しているのです。したがって「真の狂歌を知らず」はブーメランとなって菅江に戻っていきます。言文二途の時代にあって和歌と狂歌を分かつ究極の壁とは心詞の詞、言葉なのです。古典語に拠るのか、日常語に拠るのか、これ以外にありません。菅江は頑迷にも旧ツールに拠る歌人でした。 k 唐衣橘洲(からごろもきつしゆう)(一七四三~一八〇二) 寛政二(一七九〇)年刊の狂歌論『狂歌初心抄』から抄出します。 近き頃、半井卜養などすこぶる小手の利きたるに任せ、席上にて人々の求めを塞ぐとてあらぬ事を多く詠めるも余儀なき事也。 卜養に対する評価は否定的ですが「余儀なき」(やむを得ない)と一定の理解を示しています。但し、即興が身上の卜養にとっては余計なお世話というものでしょう。 では言葉についての認識はどうなのか、「狂歌の大意」から抄出します。 俚(り)は鄙俚(ひり)と続きて卑しと読む也。狂歌はいかにも和歌に詠まぬ俗語もて綴り侍れど、楽天が俗にして俚(り)ならずといふ所、肝要なり。 楽天は中国の詩人、白楽天(白居易)です。俗語は日常語ですから、そこのところを確認したいのですが逃げられる感じです。目次の「心を先とし詞を先とする事」に期待して読み進めるのですが「人のいまだ詠まざる風情をやすらかに艶(えん)なる詞にて続くべき也」また「いかにも相応の詞もて晴着とすべし」等、どこまで追っても、つかみ所のない表現で終始します。畢竟、旧ツールに属する穏健派といったところなのでしょう。 l 大田南畝(おおたなんぽ)(一七四九~一八二三) 寛政七(一七九五)年刊『四方(よも)の巴流(はる)』の「狂歌堂に判者をゆづること葉」から抄出します。署名は四方山人、四十七歳。田沼意次の失脚後は表舞台から退いています。 銀葉夷歌の頃より底金(そこがね)の響きも移ろひたるに、言因とかや言ひし痴れ者いかなる由縁の侍りしや、雲の上まですみのぼる烟の名を立てしより、その流れを汲み、その泥(ひじりこ)をあぐる輩(ともがら)・京わらんべの興歌などいへるあられもなき名を作りて、はてはては何の玉とかいへる光なき言の葉も出できにけり。 「銀葉夷歌」は生白堂行風(せいはくどうこうふう)(生没年不詳)の編著『銀葉夷歌集(ぎんよういかしゆう)』(一六七九年)のこと、「底金」は雪駄(せつた)の踵の革が減るのを防ぐために打ちつけた金、「移ろひたるに」は「消えたのに」となります。「言因」は永田貞柳の実名ながら初期の号です。こんなところからも悪意が伝わってきます。「痴れ者」とは愚か者とか馬鹿者をいいます。次の「由縁」は南都古梅園の大墨が御所に献上されたときの作〈月ならで雲のうへまですみのぼるこれはいかなるゆゑんなるらん〉(『家づと』)が評判となり、以後「油煙斎」(由縁斎)と改名したことをいっています。「その泥(ひじりこ)をあぐる」以下を含めて朱楽菅江に輪を掛けて高圧的、しかも内容はというと、ただ罵詈雑言を重ねているに過ぎません。興歌を謳った歌集には鈍永撰『興歌老の胡馬』(一七五一年)、一好(いつこう)詠・梅好(ばいこう)撰『興歌帆かけ船』(一七六八年)、山居撰『興歌河内羽二重(きようかかわちはぶたえ)』(一七七六年)、繁雅撰『興歌野中(のなか)の水』(一七九二年)ほか数多くあります。「何の玉」は一本亭芙蓉花(いつぽんていふようか)(一七二一~一七八三)の逸話ですが、南畝の『俗耳鼓吹(ぞくじこすい)』(岩波書店『太田南畝全集』第十巻)より全文を引用します。 浪花の一本亭芙蓉花は狂歌に名あり。ことし(壬寅)あづまに下りて、浅草観世音の堂に一つの絵馬をささぐ。自ら宝珠をゑがきて、かたはらに狂詠をそへたり。 みがいたらみがいただけはひかるなりせうね玉でも何の玉でも ある日何ものかしたりけん、一首の落書をおしおけり。 みがいてもみがいただけはひかるまじこんな狂歌の性根玉では 京都にても落書あり。 ひかろかのこんにやく玉も藍玉もたどん玉でもふぐり玉でも 壬寅(みずのえとら)は天明二(一七八二)年、江戸下向のタイミングにも恵まれませんでした。 それでは太田南畝に代表される天明調、天明振りとは何だったのでしょうか。 一。南畝の『四方の留粕(とめかす)』(日本名著全集刊行会)から『狂歌三体伝授跋』を引用します。『四方の留粕』の出版は文政二(一八一九)年、但し『狂歌三体伝授跋』の執筆は寛政六(一七九四)年が思われます。先の「狂歌堂に判者をゆづること葉」に「寅の年のはじめ、河原崎の翁わたしとともに三体の伝ことごとく伝へぬ」とありますが、直近の寅年が寛政六年です。同席者は不明ですが、河原崎が歌舞伎劇場の河原崎座のことなら狂号「花道のつらね」即ち五代市川団十郎(一七四一~一八〇六)が浮上してきます。 夫(それ)狂歌には師もなく伝もなく流義もなく糸瓜もなし。瓢箪から駒がいさめば花勝見を菖蒲にかへ吸ものの紅葉をかざして師走の闇の鉄炮汁恋の煮こごり雑物のしち草にいたるまで、いづれか人のことの葉ならざる。されどきのふけふの今参りなどたはれたる名のみをひねくり刷り物のぼかしの青くさき分際にては此の趣をしること難かるべし。もし狂歌をよまんとならば三史五経を采の目に切り、源氏万葉伊勢すり鉢世々の撰集の間引菜ざくざく汁のしる人ぞしる狂歌堂の主人真顔に問ふべし。其の趣をしるにいたらば暁月房雄長老貞徳末得の迹を踏まず、古今後撰夷曲の風を忘れて初めてともに狂歌をいふべきのみ、いたずらに月をさす指をもて絵にかける女の尻を摘むことなかれ。これを萬載不易の体といふべきかも。 狂文から伝わってくるのは、南畝のいう狂歌は栗本の狂歌史と絡まないだろう、という印象です。江戸狂歌の潮目と評した卯雲の「今日歌(きようか)」(狂歌)が思い出されます。 次いで天明四(一七八四)年刊の『狂歌すまひ草』から作品を引きます。題は「西上人の人にはくずの松原といへる言のはのうらをかへして」、西行著とされていた説話『撰集(せんじゆう)抄(しよう)』(『続群書類従・第三十二輯下 雑部』)第九「南都覚栄僧都事」に出てくる辞世〈世の中の人には葛の松原とよばるる名こそうれしかりけれ〉のパロディです。 世の中の人には時のきやう歌師とよばるる名こそをかしかりけれ 四方赤良 題の「~葉の裏を返して」が葛の縁語と一首のモチーフを表明して巧みです。ところが翌年の『徳和歌後万載集(とくわかごまんざいしゆう)』になると、これが「述懐」に変わります。我こそは伝説の狂歌人、そんな自己演出が臭います。南畝にとっての狂歌史は「狂歌堂に判者をゆづること葉」にある「鳥が鳴く東振りはわづかにはたとせばかり此の方わがともがらよりもて囃して」からしても『明和十五番狂歌合』(一七七〇年)あたりを創世記としたはずです。 一。梅本高節(うめもとたかのり)(一八六二~?)の『狂歌師伝』(『江戸狂歌本選集』第十五巻)から「天明振狂歌師伝」を抄出します。先と同様で長くなりますが核心を衝く部分です。 江戸風狂歌の勃興せる原因は、他にも有るであらうが、黄表紙と称へる、小説の流行が、確に其の原因の一である。黄表紙は、宝暦より安永の初までは、極めて幼稚なるので、児童の玩弄物であつたのが、安永の中葉から、春町、喜三二、全交、京伝等の戯作者が相踵いで起り、滑稽諷刺を主として、著作せるのみでなく、有産階級を揶揄したり、智識階級を翻弄したのが、当時の江戸人の意気に適つて、大流行を来したのであるが、江戸風狂歌は、殆、黄表紙と同時に勃興したもので、前に挙げた黄表紙の作者等は、孰れも狂歌師を兼て居たから、一部の黄表紙を圧縮したものが、三十一文字の江戸風狂歌となつて、世に顕はれたのだとも云ひ得ると思ふ。 なるほど南畝は洒落本(しやれぼん)から後には黄表紙(きびようし)を執筆し、朱楽菅江も洒落本と川柳に関わっています。天明調の狂歌が狂歌史に根を下ろしていないのは出自が違っていたのです。異質としか思えない元木網・智恵内子(ちえのないし)・節松嫁々(ふしまつのかか)・頭(つむり)の光・宿屋飯盛(やどやのめしもり)・蔦唐丸(つたのからまる)・酒上不埒(さけのうえのふらち)・尻焼猿人(しりやけのさるんど)といった狂号のオンパレードも、これで分かります。大流行したという天明調狂歌とは、通時的ではなく共時的、同時代の戯作文学(げさくぶんがく)を母胎としていたのでした。 最後に巷間に流布する「狂歌三大家(たいか)」について一言しておかなければなりません。先の梅本高節は同文の中で「狂歌四大人(うし)」について述べています。「大人」とは「師匠、学者や先人などを尊敬していう語。先生」(『日本国語大辞典』)です。「大家」は「その道で特にすぐれた人。巨匠」(『日本国語大辞典』)ですから「大人」より格上でしょう。 狂歌師の多い中にも、唐衣橘洲は、江戸狂歌中興の祖と仰がれ、此人の外に、四方赤良(蜀山人)、元杢阿弥、朱楽菅江(漢江とも書く)を合して、世に狂歌四大人と称へた。奇々羅金鶏(ききらきんけい)の著『闇雲愚抄(やみくもぐしよう)』に、 大江戸にてもてはやせるは、天明のはじめ、四方赤良、唐衣橘洲、元杢阿弥、朱楽漢江のすき人々、明くれ口とくよみ出しより、今はいにしへぶりまなぶものはまれに、よもつ国の人までも、大江戸のふりをなんしたふめるは、此よたりのいさほしにぞありける。と あり。又、喜多村節信(きたむらときのぶ)の著『嬉遊笑覧(きゆうしようらん)』に、 其後暫廃れしが、安永ごろ又流行だして、菅江、赤良、橘洲、木網((ママ))を始めとして、其徒あまた出来ぬ、皆慰みわざとして、点料など取る事なし、其後これをもて業としたる者は真顔也。とある。 一方、野崎左文(のざきさぶん)(一八五八~一九三五)は「狂歌の研究」(昭和六年『岩波講座日本文学』)で「後の狂歌三大家と云はれた小島謙之(唐衣橘洲)、大田南畝(四方赤良即ち蜀山人)山崎景貫(朱楽菅江)等が居て」と述べますが典拠を示していません。いつから元木網を外したのか、加えて「大家(たいか)」に昇格したのかが知りたいところです。『江戸狂歌壇史の研究』(汲古書院)の石川了(一九五〇~)は「狂歌三大人」で通しています。直接に言及するところはありませんが、「第一章 天明狂歌をめぐる諸相」の「第六節 『天明狂歌』名義考」で例示される豊富な資料を眺めていると、『闇雲愚抄』(一八〇〇年)や『嬉遊笑覧』(一八三〇年)に替わる「後に」も推測可能です。一名減は早くて一八九一年です。「大家(たいか)」は古風な「大人(うし)」(近世の国学者が復古趣味から使い始めた語)を忌避したのかも知れません。あるいは「大人(うし)」ではなく「先生・師匠・学者などを敬っていう語」(『日本国語大辞典』)の「大人(たいじん)」から類音の「大家(たいか)」に落ち着いた可能性も考えられます。ただ江戸時代の主流語「天明調」「天明風(ぶり)」に替わって幕末に生まれた「天明狂歌」の呼称が定着するのは昭和二十一年以降だそうですが、それと呼応するかのような肥大化(昇格)の印象は拭えません。肝に銘じたいのは「狂歌四大人」にしろ、「狂歌三大人」にしろ「天明の」という冠詞がついてまわることです。これが外れると言葉は一人歩きを始めます。巷間に流布する「狂歌三大家」は、その最たるものでしょう。朱楽菅江から「やから」呼ばわりされ、「時の狂歌師」の増上慢としか思えないのですが、大田南畝から「痴れ者」「その泥(ひじりこ)をあぐる輩(ともがら)」と罵倒された彼らは、しかし言文二途の時代にあって「文語体の和歌」対「言語体の狂歌」というダブルスタンダードを実現してみせたのでした。すなわち『万葉集』『古今和歌集』以来の王道が未来に接がれたのです。 第二項 狂歌の言語体 うさいわうよろこびあれや年の暮れにさらばこがねの鈴を参らしよ 半井卜養(なからいぼくよう)(一六〇七~一六七八) 『卜養狂歌拾遺』(『狂歌大観』第一巻)。題に「歳暮に蜜柑贈るとて、ふる年も早たち花と祝ひ参らせ、一折ささげ申し候。黄金の鈴とも世人申すならば繁るまま目出たく幾久幾久」とあります。「一折」を「一折り」と読んで進上物、「一折れ」と読んで舞の一差しとなります。両意を掛けていると思われます。初句「于思翁(うさいおう)」は能「翁」に出てくる白髪の老翁、四句「然らば」は「それでは」の意、次の比喩「黄金(こがね)の鈴」が美しく響きます。結句「しよ」は「せむ」の音変化「せう」を発音のままに書いたものでしょう。 御使ひかはいらさんせい入りさんせいふみばこそこにおかさむせいなう 豊蔵坊信海(ほうぞうぼうしんかい)(一六二六~一六八八) 『豊蔵坊信海狂歌集』(『狂歌大観』第一巻)。詞書は「三清と云ふ法師文箱もちて使ひに来にけるを門外にて逢ひて」。そこで親しく声をかけたという場面です。もとは遊女語「さんせ」は動詞の未然形につく助動詞「さんす」の命令形、丁寧の意を含んだ尊敬表現です。語尾の「い」は話し言葉の現場を反映また法師の「三清」とも一致します。 あさ夕はどこやら風もひやひやとお月さま見て秋をしりました 黒田月洞軒(くろだげつどうけん)(一六六〇~一七二四) 『大団(おおうちわ)』(『狂歌大観』第一巻)。月洞軒は知行高千二百二十石の旗本で、狂歌は豊蔵坊信海に師事しています。年上の貞柳は弟弟子にあたります。題は「初秋月」。二句の「どこやら」は何となく、しかし確かにそうだという感じを表します。三句「冷や冷やと」は初二句を受けますが、これに納得するように四句「お月さまみて」と続きます。 国はなんの都はなんのうかれめの一たびゑめば銚子かたぶく 由縁斎貞柳(ゆえんさいていりゆう)(一六五四~一七三四) 『続家づと』(『狂歌大観』第一巻)。「題しらす」ですが「傾城」(「一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く」)をモチーフとしています。初句と二句の「何の」の受け流したような、意に介さない口吻は、次に何が傾くのか戦々恐々とするのですが、実のところは銚子なのです。傾城は美人また遊女の意、ここでは後者でしょう。 むかしむかしの話となりてさるの尻まつかうくさふなる親仁達 栗柯亭木端(りつかていぼくたん)(一七一〇~一七七三) 『狂歌ますかがみ』(『狂歌大観』第一巻)。題に「翁の述懐の歌とて 祖父(じい)は山へしばしが程に年老いてむかしむかしの話こひしき と読めりしに寄りて」とあります。「翁」とは貞柳です。「祖父は山へ」の歌は『家づと』(『狂歌大観』)の一首です。四句「真っ赤」に「抹香」を掛け、さらに副詞「真っ斯う」(全くこう)を重ねています。 みる人が楊貴妃よりはうつくしくせつかく咲いたはなはひしげた 木室卯雲(きむろぼううん)(一七一四~一七八三) 『今日歌集』(『江戸狂歌本選集』第一巻)。題は「美人花ニ勝ツといふ題に」です。初句「見る人」が美人、二句「楊貴妃」には梅のほかに桜もあるようです。もちろん中国は玄宗皇帝の妃から来ている命名が下句に強い印象を与えていることはいうまでもありません。結句「鼻がひしげた」は「鼻が凹んだ」、この「鼻」に「花」を掛けています。 方円の器のなりにしたがふて水にちよつぽり、(テン)のなすわざ 九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい)(一七二三~一七六七) 『興歌野中の水』(『近世上方狂歌叢書十五』)。題は「氷」。上句は成句「方円の器に従う」(水は容器次第で四角にも丸にも形を変える)を使っています。四句「ちょっぽり」は「ちょっぴり」、続けて「水」に読点のルビ「テン」が付いて「氷」、これも三句「従うて」の範囲だというのです。四句からして表面を薄い氷が覆っているのでしょう。 語りあうた中はあかなき湯の山を別れの涙しぼる手ぬぐひ 永日庵其律(えいじつあんきりつ)(一七二六~一七六一) 『狂歌秋の花』(『近世上方狂歌叢書三』)。題は「勢州菰野(こもの)へ湯治せし時、逗留中語りあひし人々山口までおくり出しわかれに」。初句はウ音便、二句「あかなき」は「垢なき」に「飽かなくに」(残り惜しいのに)の意を重ねています。修辞としては言文混用、しかし地である言語体は動きません。三句は湯ノ山温泉、今の三重県菰野町が舞台です。 手はしかう鎌をかけても麦秋はやとふ人さへあちらむきやす 山中千丈(生没年不詳) 『狂歌鵜の真似』(『近世上方狂歌叢書十一』)。題は「麦秋怱」(「麦秋」は麦を取り入れる初夏の頃、「怱」は慌ただしい意)。初句は「手はしかく」のウ音便、「はしかい」に「痛がゆい」と「機転がきき敏捷である」の両意を託しています。結句の助動詞「やす」は四句「雇ふ人」への軽い敬意、しかし雇い主も忙しくて振り向けないのです。 土産とて下されました伊勢桜おはらひさまよりなほ有りがたい 二松庵万英(にしようあんまんえい)(?~一七八〇) 『狂歌月の影』(『近世上方狂歌叢書十』)。題は「土産桜」。二句は「下される」(頂戴する)の連用形に叮嚀の助動詞「ます」の連用形そして過去の助動詞「た」の終止形となります。三句「伊勢桜」は伊勢神宮の境内に咲く桜の花、四句「御祓様」とは伊勢神宮で授ける御札をいいます。「花より団子」ならぬ「御札より花」というわけです。 しやうがいにかみのみやうがもごさんせうたうからしれたゆくすゑのさち 手柄岡持(てがらのおかもち)(一七三五~一八一三) 『我(われ)おもしろ』(『江戸狂歌本選集』第十巻)。題は「山椒茗荷柚生姜蕃椒の画の扇にめでたき歌書いてとあれば」。初句に「生姜」と「生涯」、二句に「紙」の「茗荷」と「神」の「冥加」、三句に「山椒」と「御座んせう」、下句に「蕃椒(とうがらし)れた柚くすゑのこと」と「とうから知れた行くすゑのこと」が同居しています。「柚」(ゆ)は江戸の俚言、二つの意味が同時進行して巧みです。言語体ではありませんが、記号入りの狂歌も散見します。風水軒白玉翁(ふうすいけんはくぎよくおう)(一六五三~一七三三)以来と思われますので参考に挙げておきます。 金銀のあまたあつ○身の上は井ま福とくの三年めかも 題は「越後屋の手代の役替を祝ひて」。「手代」は丁稚の上、「役替」は役目や役割の替わる「役替わり」と解釈しました。一首は暖簾印「丸に井桁三」を入れています。下句の「(いま)福徳の三年目(かも)」は思いがけない利益を得ることをいいます。 暮れ限り錠前ぴんと箱根山四角四面にさしたものじやな 仙果亭嘉栗(せんかていかりつ)(一七四七~一七九九) 『狂歌辰(たつ)の市(いち)』(『近世上方狂歌叢書五』)。題は「関路夕」。初句は暮れ六つの規則通り。二句の「ぴんと」は錠前を掛ける音、役人が関所の門を「箱根」の箱よろしく「四角四面に差した」のです。「じゃ」は断定、「な」は詠嘆。嘉栗は三井家の南家第四代当主、幕府御為替御用名前(おかわせごようなまえ)は次郎右衛門です。江戸勤番のための下向か、上京の折りの作品でしょう。三井高陽編『嘉栗研究』(三井家蔵版)の「三井嘉栗略年譜」によると安永八年「三井家旧制復活の計画をなす」(三十三歳)、安永九年「三井家旧制復活につき計画」(三十四歳)、天明元年「三井家家譜を編集完成す」(三十五歳)、しかし寛政八年「三井家内紛のため徳川家より取潰しの危機に会ひ、一身に罪を負い重追放大津に移る、これにて三井家潰滅を免る」(五十歳)とあり、経済人としての波乱の人生がかいま見えます。 |
||||
| 第二章 第四節 周回遅れの言文一致体 | ||||
正岡子規(一八六七~一九〇二)に有名なベースボールの歌があります。 久方のアメリカ人(びと)のはじめにしベースボールは見れど飽かぬかも 『子規歌集』(岩波文庫) 初二句のイレギュラーな枕詞の用例を手繰っていくと朱楽菅江(あけらかんこう)(一七三八~一七九八)が「やから」(輩)呼ばわりした半井卜養(なからいぼ゛くよう)(一六〇七~一六七八)の、 久かたのあまのじやくではあらねどもさしてよさしてよ秋の夜の月 『卜養狂歌集』(『狂歌大観』) に行き着きます。詞書は「八月十五夜月曇りて出でざりければ」。「天」の字ながら「天の邪鬼」、囃すように「差してよ差してよ、お月さま」となります。また大田南畝(おおたなんぽ)(一七四九~一八二三)が「しれもの」(痴れ者)と呼んだ由縁斎貞柳(ゆえんさいていりゆう)(一六五四~一七三四)から『貞柳伝』の著がある仙果亭嘉栗(せんかていかりつ)(一七四七~一七九九)に至る歌論は正岡子規(まさおかしき)の「生は和歌につきても旧思想を破壊して、新思想を注文するの考にて、随(したが)つて用語は雅語、俗語、漢語、洋語必要次第用うるつもりにて候」(「六たび歌よみに与ふる書」、『歌よみに与ふる書』岩波文庫)を連想させます。しかし決定的に違ったのは前者が言葉のツールを古代語から近代語にシフトした言語体、これをスタンダードツールとしたのに対して、後者は旧ツール、用語以上の展開は望めませんでした(なお松陰女子学院大学国文学研究室編「文林」第十二号に大谷篤蔵の翻刻本『貞柳伝』が収録されています)。 第一項 スタンダードツール 正岡子規に限らず、言文二途の「文」をスタンダードツールとする歌人が圧倒的な近代にあって、青山霞村(あおやまかそん)(一八七四~一九四〇)は異色でした。あるいは出色でした。 露霧でいつしか深うなつて来た草に熟柿を踏む山の秋 ものをいふその目が好かつたばつかりに田舎に老いて菊作りする 泣いて来た人はいなすにいなされず炉で栗焼いて霜夜を守る 六日見ぬと七秋みない恋しさに雪の今日でも逢ひに来たとよ 搗き上げた臼の小餅は児の多い裏のおさよにまづちぎらして 右の五首は明治三十九(一九〇六)年に出版された霞村の第一歌集『池塘集(ちとうしゆう)』(筑摩書房『現代短歌全集』第一巻)に収録されています。二首目には青年である霞村の夢見た恋愛が老後の「私」を通して語られています。三首目もそうですが、作中主体としての「私」は現実の「私」から独立してドラマを生きている。これも近代短歌の特色と大いに異なるところでしょう。話を本来のツールに戻しますが、この「自序」に、 誰でも日本の国語国字に就て多少考へたものは其不統一不完全不便利を認めないものはありますまい。あの羅馬字会といひ言文一致会といひ漢字廃止若くは制限論といひ皆これが為起つたのではありませんか。私は久しく詞賦を研究して居るので詩歌の上にも可成言と文とを一致せしめたいといふ願が切なのであります。 とあります。文中の羅馬字会は日本語表記をローマ字にしようと主張する団体で明治十七(一八八四)年に発足、言文一致会は明治三十三(一九〇〇)年に発足しています。またその最後を「近頃ある批評家も将来の詩歌は言文一致だといはれたさうですが私は口語の詩が日本の詩国に一境地を拓き得ることを確信して疑はないのであります」と結んでいます。山田美妙や二葉亭四迷に始まる言文一致運動からすると周回遅れとはいえ、青山霞村の願いと確信は当時に比較すると格段の広がりを見せています(詳しくは本書と姉妹版をなす『ゆたかに生きる 現代語短歌ガイダンス』を参照願います)。 第二項 スペシャルツール 今後の予想としては、旧ツールと書きましたが、言文二途の「文」に拠る歌人は、言文一致体の凌駕を受けて少数化することでしょう。すばらしいことです。 残るのは古典に憧憬する専門家集団です。で、あるならば少なくとも明治三十八(一九〇五)年の文部省告示第百五十八号「文法上許容すべき事項」(本邦書籍『新聞集成明治編年史 第十二巻 日露戦争期』)以前の水準に戻ってもらいたいものです。一例を挙げれば「暮セシ時」「過セシカバ」に違和感を覚える歌人であってほしいのです。 ツールの仕分けは破綻に瀕している言葉を洗浄し、蘇らせ、詩型そのものをも活性化させるのです。座右に置くならば「現代短歌の〈文語〉が、どのように文語と相違しているかを知るのも、実作者として決して無駄なことではあるまい。本書をまとめた目的も、そこにある」という安田純生の『現代短歌のことば』(邑書林)、またそれに続く『現代短歌用語考』(邑書林)・『歌ことば事情』(邑書林)、これは必携の三部作でしょう。 |
||||
| 第二章 第五節 結語 | ||||
| 第二章第二節第二項で取り上げた『土佐日記』を思い出しください。楫取りが船子に話していた普段の言葉です。紀貫之や登場する少年や少女も同じ日常の言葉で詠っていたのでした。現代人ならば現代語、その中にミューズが宿り、そして微笑むのです。 私たちシニアは、むしろジュニアから学ぶべきでしょう。タイトルの「王道」とは五句三十一音詩という詩形が生まれてから今日までを貫く一大法則なのです。辞書を引くと『広辞苑』には「最も正統な道・方法」とあります。『明解国語辞典』なら「最も正統な道」、『日本国語大辞典』なら「物事が進んで行くべき正当な道」、これしかありません。 五句三十一音詩史すなわち三十一文字(みそひともじ)の歴史に日本語の歴史を重ねたときに見えてくる風景、それはシニアの信奉するスタンダードツールがコペルニクス的展開を迫られているという事実です。証言するのは私たちがジュニアと呼ぶ未来人です。 |
||||
| 第三章 ジュニアに学ぶ五句三十一音詩 | ||||
| 第三章 第一節 古代語 | ||||
| 『日本国語大辞典』は「古代語」を「古い時代の言語。日本語では、主に中世以前のことばをさす」とあります。平凡社ライブラリー『日本語の歴史4』は「移りゆく古代語」の副題を持ちますが、表紙に「古代と近代とをつなぐ〈古典憧憬〉の時代―そういう眼で中世をとらえるならば、言語の歴史のうえにも中世はあった。そこでは、古代語の残照が美しく光る水面の下に、はげしい底流となって渦巻き流れる近代語の露頭をみることができる」とあります。本節では、その古代から中世の作品を採録しています。 神な月時雨ふるにもくるる日を君まつほどはながしとぞ思ふ 人のむすめのやつなりける『後撰和歌集』(冬、四六一) 『後撰和歌集』は天暦五(九五一)年、村上天皇の勅命を受けた『古今和歌集』に次ぐ勅撰和歌集です。題は「おやのほかにまかりておそくかへりければ、つかはしける」。天永三(一一一二)年頃に成立した源俊頼の『俊頼髄脳』では「十月ばかりに、母のものへまかりたりけるに」云云とあります。保元三(一一五八)年頃に成立した『袋草紙(ふくろぞうし)』(上巻)も同内容です。言文一致だから、こうした母恋の歌も可能だったのです。 つつめどもかくれぬものは夏虫の身よりあまれる思ひなりけり うなゐ『大和物語(やまとものがたり)』(四十段) 「髫髪(うない)」は幼年期の髪形です。「童(わらわ)」ともあって、おませで大胆な子供が想像されます。以下「桂のみこに、式部卿の宮すみたまひける時、その宮にさぶらひけるうなゐなむ、この男宮(おとこみや)をいとめでたしと思ひかけたてまつりけるをも、え知りたまはざりけり。螢のとびありきけるを、『かれとらへて』と、この童にのたまはせければ、汗袗(かざみ)の袖に螢をとらへて、つつみて御覧ぜさすとて聞(きこ)えさせける」に続く、十世紀半ばの歌物語です。 鶯よなどさはなくぞ乳やほしきこなべやほしき母や恋しき 乳(ち)のむほどのこども『俊頼髄脳』 源俊頼(一〇五五~一一二九)は「これは、幼きちごの、父(てて)が、継母(ままはは)につけておきたりけるほどに、土して、小さき鍋のかたを作りたりけるを、継母が子にとらせて、この継子(ままこ)にはとらせざりけるを、欲しとは思ひけれど、え乞はぬ事にてありけるに、鶯の鳴きければ、詠める歌なり。乳なども欲しかりける程にや。幼き人も稚児どもも、むかしは歌を詠みけるとみゆるためしなり」と述べています。同歌は『袋草紙』にも登場します。 竹のむまはふしかげにしていとよわし今夕かげにのりてまゐらん 壬生忠見『袋草紙』 藤原清輔(一一〇四~一一七七)の歌学書『袋草紙』に壬生忠見(みぶのただみ)(生没年未詳)「幼童の時、内裏より召有る、乗物なくて参り難きの由を申すに、而らば竹馬に乗りて参るべきの由御定(ごじよう)有り。仍りてこの歌を進(たてまつ)る。/(略)/忠見は貧敝にて田舎に住む者なり」とあります。「ふしかげ」は竹馬を臥した鹿毛(かげ)に喩えています。「ふし」に竹の「節」です。「夕かげ」は「夕影」に馬の毛色「木棉鹿毛」を掛けて夕方参上の意としています。 ふたつもじ牛の角もじすぐなもじゆがみもじとぞ君はおぼゆる 延政門院『徒然草』(第六十二段) 作者は後嵯峨天皇の皇女、悦子内親王(一二五九~一三三二)です。本文は短く「延政門院いときなくおはしましける時、院へ参る人に御言(おんこと)づてとて申させ給ひける御歌(おんうた)、(略) こひしくおもひまゐらせ給ふとなり」とあります。「院」は御所、父と娘は別に暮らしているのです。「ふたつもじ」は「こ」、「牛の角もじ」は「い」、「すぐなもじ」は「し」、「ゆがみもじ」は「く」、合わせて「こいしく」です。「こひしく」が「こいしく」ですが音韻変化で「ひ」を「い」と発音しています。これをハ行転呼音といいます。著者は吉田兼好(けんこう)(一二八三頃~一三五二以後)、『徒然草』は鎌倉時代後期の随筆です。 雪降りて寒き朝(あした)に文(ふみ)読めと責めらるるこそ悲しうはあれ 西園寺実俊(さねとし)『竹むきが記』 貞和五(一三四九)年成立の『竹むきが記』は日野名子(めいし)(?~一三五八)の女流日記です。北朝の暦応三(一三四〇)年、後の右大臣実俊(一三三五~一三八九)六歳の作です。父公宗(きんむね)が処刑されたときは母名子の腹の中でした。「雪の朝に、日毎の所作なる文を、人々読ませ聞(きこ)ゆるに、詠み給へる」とあります。名子には〈わすれじよわれだに人の面かげを身にそへてこそかたみともせめ〉(『新千載和歌集』一六〇三)があります。 霜月に霜の降るこそ道理なれなど十月に十はふらぬぞ 藤原家隆『清巌茶話』 正徹(しようてつ)(一三八一~一四五九)の『清巌茶話(せいがんさわ)』に「家隆卿稚き時、(略) とよみ給ひしを」とあります。但し藤原家隆(ふじわらのいえたか)(一一五八~一二三七)と時代を同じくする順徳天皇(一一九七~一二四二)の『八雲御抄(やくもみしよう)』にも「家隆卿がをさなくて、『など十月に十はふらぬぞ』とよみたるこそ、山口しるくめでたけれ」とあります。「山口」は前兆。霜月は陰暦十一月、十月は神無月、ここだけ漢字が数字になっています。先行歌学を集大成した『八雲御抄』は承久の乱(一二二一年)以前から執筆、佐渡の配所でまとめられました。 |
||||
| 第三章 第二節 近代語 | ||||
| インターネット辞書・事典検索サイト「ジャパンナレッジ」の見出しで「近代語」はヒットしません。しかし平凡社ライブラリー『日本語の歴史5』は「近代語の流れ」の副題を持っています。表紙に「中世の終り、底流に渦巻いていた近代語は、この時代に入って、にわかに水面に露呈し、滔々たる水流となる。きびしい封建体制下、上方と江戸の地方差、武士と町民の身分差を反映しながら流れつづける近代語の波頭に、芭蕉や西鶴が新しい発想と芸術を展開する」とあります。本節では、その近世の作品を採録しています。 はらからの娘がしぼんだ花とつてふくらかすかの里の朝がほ 佐藤少女萩『狂歌かたをなみ』 『狂歌かたをなみ』(近世上方狂歌叢書二十九)は玉雲斎(ぎよくうんさい)社中詠、刊記に寛政八(一七九六)年とあります。掲出歌の題は「里朝顔」。作者は佐藤さんちの少女、萩さんです。初句の「同胞」は兄弟姉妹、その娘とは嫁いだ姉の子、姪でしょう。以下「萎んだ花とって脹らかす」は幼児の姿です。「かの」は遠称の代名詞、「里」は村落。歌集中に佐藤魚丸(蝙蝠軒、旧路館)と佐藤女鶴江が出てきます。おそらく両親と思われます。 あたご山しぐれの桜それ過ぎてゆきの花ちるけふのさむけさ 嘉栗孫十歳 世根女『狂歌辰の市』 嘉栗は仙果亭嘉栗(一七四七~一七九九)、『狂歌辰の市』(近世上方狂歌叢書五)は寛政十(一七九八)年の刊です。掲出歌の題は「山雪」。歌意は「愛宕神社に参詣の途次ですが時雨桜を過ぎた頃から雨が雪に変わりました。時雨の秋から雪の冬、今日は本当に寒い日です」。二句と四句が対句構造になっています。堪忍舎二字守に〈愛宕山山麓の桜時雨てふ名を得てくもる春の月の輪〉(『狂歌手毎の花 初編』同十六)があり、春と秋が同居する「時雨桜」が桜の一品種で、愛宕山山麓の実景であったことが分かります。 家ごとの屋根一面にしら雪のつもりて見えぬ瓦町すぢ 幼童 辻行雲『狂歌後三栗集(ごみつぐりしゆう)』 『狂歌後三栗集』(近世上方狂歌叢書八)の撰者は百尺楼桂雄(ひやくしやくろうけいゆう)と橙果亭天地根、刊記に文化十一(一八一四)年とあります。掲出歌の題は「市中雪」。結句「瓦町」は瓦を焼く職業の家が多い町の意、ここは現在の大阪市中央区瓦町が舞台と思われます。二句の「屋根」と呼応した「瓦町」であり、「一面に~見えぬ(瓦)町筋」でもあります。「ぬ」は文語の打ち消しの助動詞「ず」の連体形が口語の終止形・連体形になったものです。 |
||||
| 第三章 第三節 現代語 | ||||
平凡社ライブラリー『日本語の歴史7世界のなかの日本語』の巻末「事項索引」を見ても「現代語」は登場しません。そこで「ジャパンナレッジ」で「近代語」を「全文」検索すると「日本語を大きく古代語と近代語とに区分する時」(『国史大辞典』の見出し「文法」)、「日本語の歴史は、(略)。文法史的にみると、十六世紀と十七世紀との間に大きな変化があり、『古代語』と『近代語』とに二分される」(『日本大百科全書(ニッポニカ)』の見出し「日本」)などがヒットします。ただ本稿のテーマは文法ではありません。五句三十一音詩と言語体ないし言文一致体です。そこで本節は「現代語」としました。 『日本国語大辞典』で「現代語」を引くと「過去の時代の言語に対して、現代人が、自分のものとして用いる言語。日本語では一般に明治以降の言語をいうが、特に、第二次世界大戦後の言語に限定していうこともある」云々と出てきます。 第一項 現代学生百人一首(東洋大学) 東洋大学創立百周年の記念事業として始まったという「現代学生百人一首」は二〇一四年で第二十八回目を迎えています(編纂は翌年)。選考委員として参加している歌人は花山多佳子・光栄堯夫(二〇一二年編纂)、鮫島満・中川佐和子(二〇一三年・二〇一四年編纂)です。記念冊子(過去の作品抄)もあって史的貢献の大きさが思われます。 a 二〇一二年編纂 現代学生百人一首 母ぐまの後をおいかけ街に出たまいごの子ぐま早くおかえり 北嶺中学校二年(北海道) 齊藤明良 13歳 熊がエサを求めて人里に下りてくる、あるいは人に危害を加える、そんなニュースを耳にすることの多い昨今です。掲出歌は、しかし迷子の小熊の身を案じた歌で、「私」の思いがよく出ています。今ひとつ、言葉の巧みな連鎖反応に注目です。「母ぐま」「子ぐま」の対句はもちろんですが、「おい」「まい」や「かけ」「かえ」の類音、回文的な「まいごの子ぐま」(「まぐこのごいま」)などが小熊物語に優しい光りを添えているのです。 まっくらの計画停電あった夜あの日の夕食今でも言える 東松山市立南中学校三年(埼玉県) 新井晴乃 15歳 上句は、二〇一一年三月十一日に発生した東日本大震災の影響によって東京電力の電力供給能力が大幅に低下したため、同月十四日から一都八県で実施された計画停電(『デジタル大辞泉』)、その夜のことをいっています。たぶんロウソクかランプの光りで夕食を囲んだのでしょう。印象としては、やはり「まっくら」、その中での下句に思いを致したいところです。表現としては「あ」音や「い」音が響いて調子を整えています。 飲みかけのラムネのビンを傾けるガラスのなかで揺れた夏空 女子学院高等学校一年(東京都) 山内志織 15歳 くびれのある緑のラムネ瓶といえば夏のイメージです。ただ外の清涼飲料水と違って、売られている場所は限られると思われます。では「私」はどこでラムネを手にしているのでしょうか。縁日もしくは海の家を想定してみました。三句「傾ける」のは飲むため、瓶は逆さ、「私」の視線は四句の「ガラス」(ガラス玉・ラムネ玉・ビー玉)に注がれます。くびれの底から瓶の口まで転がってくるとき、たしかに夏の空は揺れたのです。 中庭に座ってみると大きくていつもの校舎がどこか頼もしい 佐世保市立中里中学校三年(長崎県) 岡田みずほ 14歳 初句の「中庭」は周囲の建物が、ここは校舎ですが、壁のようになりますから見上げる角度は自然と大きくなります。座れば尚更でしょう。池か花壇があって、ベンチが置かれているのでしょう。憩いの場所ですが、窓から眺めることはあっても、庭に立つこと、ましてベンチで過ごすのは希でしょう。だから余計に三句の印象を強くしたと思われます。それは普段は思いもしなかった景として下句、「私」の感慨を深くしたのでした。 秋の空イワシがたくさん泳いでてとなりのネコがひるねをしてる 佐世保市立中里中学校三年(長崎県) 阪口啓介 14歳 上句の「イワシ」は「鰯雲」の略、空に白い小さな雲が、魚の鱗のように群がり広がっているところです。下句は、「私」の隣で昼寝をしている猫、でしょう。諺に「猫を追うより魚をのけよ」「猫に魚の番」があるように、近くは「サザエさん」の歌詞が「お魚くわえたどら猫」で始まるように、猫は魚に目がないという「常識」を逆手にとってユーモラスです。ベランダからの空の景色でしょうか、読者を幸せな気分にしてくれます。 b 二〇一三年編纂 現代学生百人一首 今までは寒く感じたスーパーも職場となれば長袖めくる 北海道帯広農業高等学校三年(北海道) 古家杏奈 17歳 食品売り場でしょうか。それでなくともスーパーマーケットの室温は低く設定されているものです。したがって「寒い」と感じる客も少なくない。上句から「私」もその一人だったことが分かります。四句の「職場」は、将来を見据えたものかも知れませんが、アルバイトの設定で読みました。結句の「長袖めくる」が、この作品のハイライトでしょう。用心してのことでしたが、売る側に回った活気とやる気が袖をめくらせたのです。 ベランダにゆれるわたしのユニホームプレッシャーなしの軽いリズムで 県立松山女子高等学校一年(埼玉県) 西原好美 15歳 学校の運動部に所属しているのでしょう。上句は洗濯したユニホームがベランダに干されて、風に揺れている風景です。下句は、そこから触発される「私」の思いを重ねました。ユニホームを身にまとうとき、とりわけ試合となれば、それはプレッシャーの代名詞にもなるのですが、なんと結句「軽いリズム」で風を受け流しているのでしょう。三句と結句から卓球・テニス・バレーボールといったネット型の競技を思ったことでした。 好きですとメールで届く告白文直接言えよ草食男子 県立横浜平沼高等学校三年(神奈川県) 曽田夏希 18歳 上句の腰が引けたような「好きです」メールが愉快です。もしかしたら三句「直接言えよ」と、背中をどやしてくれそうな女子生徒だからこその選択かも知れません。結句の造語「草食男子」は二〇〇九年の流行語大賞を取っていますが「協調性が高く、家庭的で優しいが、恋愛やセックスには積極的でない」(『現代用語の基礎知識』)男性をいいます。これに対置されるのが肉食女子、自分にないところに惹かれたのかも知れません。 先輩の仕込んだ酒を一滴もこぼさぬようにびんに詰めゆく 県立田布施農工高等学校(山口県) 中原諒子 18歳 田布施農工高等学校のホームページを覗くと食品科学科の専門科目に「酒類醸造」があります。「学校案内」の「その他」では瓶詰め作業や酒造室の軒先に吊された杉玉(酒林)の写真も掲載されています。昭和三十三年からの酒造りということですから酒造業界また関連会社に進んだ先輩も多いのでしょう。一首は、そうした伝統の中に置くと、いっそう味わい深いものがあります。まさしく、そうした「私」たちの一首なのです。 就活の車窓に見える案山子から試験頑張れとエールをもらう 県立諫早農業高等学校(長崎県) 立石亮介 18歳 初句「就活」は就職活動の略、求職活動全般を指しますが、四句に「試験」が出てきます。ここは「就職試験を受けに行く」意だと分かります。二句は、その「車窓」です。「案山子」は農業高校の生徒である「私」には身近な存在なのでしょう。下句は、まるで親戚の叔父さんのように立っています。あるいは学校の農場なのでしょうか。受験するのは県内か、県外か、遠ざかる案山子が次第に郷里そのものに変貌していくようなのです。 c 二〇一四年編纂 現代学生百人一首 しがみつく夢のはじっこ布団ごと母にはがされ無念の起床 青森県立八戸工業高等学校三年(青森県) 西村和輝 17歳 比喩が巧み且つユーモラスです。『現代日本語方言大辞典』(明治書院)で「端」を引くと「はじっこ」の栃木や神奈川等、「はしっこ」の富山・三重・奈良等に分けられますが、「私」が暮らすのは前者の圏内ということになります。初句「しがみつく」のは「夢のはじっこ」ですが、同時に三句「布団」の「はじっこ」でもあるのでしょう。その夢と布団「ごと」を四句「母にはがされ」るという、おきまりの朝がやってきたのです。 四分休符下から上へ書いてゆく空へ飛びたつ翼のようだ 聖ウルスラ学院英智小・中学校九年(宮城県) 根來怜菜 15歳 初句「四分休符」は四分音符「♩」と同じ長さの休止を表わす休符、こんな形をしています。五線譜に四つある間の一つ目から書き始めて四つ目の途中で書き終わります。つまり二三句「下から上へ書いてゆく」のです。そして出来上がった記号を見ていると下句「空へ飛びたつ翼のようだ」とは上手くいったものだと感心します。まるで未来の「私」たちを象徴するような「翼」、すでに大空を翔る姿にも見えるのでした。 「いきます」と上げた右手が震えてもバーの向こうの空を見たくて 宮城県宮城第一高等学校一年(宮城県) 須田琴乃 16歳 陸上部、競技種目は走り高跳びでしょう。大きな大会が思われます。初句「いきます」は審判の競技開始の合図を受けて、呼吸を整えます、そして今から「いきます」と右手を上げたのでしょう。スタンドから見ているような臨場感です。三句から「私」の緊張感が伝わりますが、下句は「私」の勇姿また「私」の夢や希望でしょう。その意味で「空」は比喩、比喩としての「バー」を背面跳びで超えていく青春が見えるようです。 ドッカーンとどろきわたるカミナリと家路を急ぐ自転車集団 駒込学園駒込中学校二年(東京都) 紀井大武 14歳 光るのと鳴るのが、ほぼ同じであることが初句のオノマトペ「ドッカーン」から分かります。またこれを含む「ドッカーンとどろきわたるカミナリ」と下句「家路を急ぐ自転車集団」が接続助詞の「と」ではなく、並立助詞の「と」で結ばれていることにも注目しました。〈カミナリがドッカーンとどろきわたると自転車集団家路を急ぐ〉の「と」では生ぬるいのでしょう。実際そのとおりで、衝迫の下校風景が活写されています。 あとひとつアウトが取れぬ苦しさにホームベースにかげろうゆれる 滋賀県立高島高等学校二年(滋賀県) 藤原みな美 17歳 野球を素材とした作品は珍しくありませんが、作者名からして女子のようです。したがってソフトボールの試合と考えて間違いないでしょう。では作中の「私」のポジションはどこか。ピッチャーを想定するのが無難ですが、上句「あとひとつアウトが取れぬ苦しさ」は九人が共有するものです。そういう意味ではキャッチャーを除く八人が下句「かげろうゆれる」「ホームベース」に向かい合っている、その一体感に醍醐味を見るものです。 第二項 SEITO百人一首(同志社女子大学) 短歌コンクール「SEITO百人一首」は二〇一四年で第十三回目を迎えています(受賞作品集は翌年刊)。歌人では安森敏隆(同志社女子大学名誉教授)と梅内美華子が選者に名前を列ねています。作品には作者の二百字前後のコメントが掲載されています。また座談会・選者講評・応募状況の公表・「英語短歌の書き方」などに特色を見ます。 a 31音青春のこころ2012 「SEITO百人一首」の世界 スパイスのむせかえるほど香り立つアラブの市の物売りの声 明石華乃 同志社女子高等学校(京都府)一年 アラブ人の国は西アジアから北アフリカまで広がっています。さて「私」が旅行したのはどの国だったのでしょう。子供にも『アラビアン・ナイト』で馴染みの深い国、その現地詠です。三句までの嗅覚が四句を修飾し、結句で聴覚に変換する、この体言止めも見事で完成度の高い作品となりました。作者は「香りは記憶を呼び起こすことができる、と聞いたことがあります」と書き起こしてチュニジアの香辛料市場だと明かしています。 「なぁ聞いて?」いつものように父に語る返事は来ない仏壇の前 成行亜優 観音寺中央高等学校(香川県)三年 いいお父さんだったんだと思います。そして娘さんのことを誰よりも大切に思っていたんですね。作品の構造としては初句が起、二三句が承で、四句が「どうして」と読者に思わせる転、結が謎の解ける結句となります。いつも黙って聞いてくれる三句の「父」は「私」の中で生き続けているのです。コメントによると仏壇が来てからの日課で「入選の知らせをした時は、いつもより線香の火が明るかったように感じました」とありました。 じいちゃんの役に立とうと考えた春から私看護学生 長船里咲 観音寺中央高等学校(香川県)三年 初句「じいちゃん」は闘病生活を余儀なくされているのでしょう。歌の構造は三句切れの鑑賞もありますが、ここは「じいちゃんの役に立とうと考えた(春から)私看護学生」とカッコで挿入の無句切れで解釈します。句またがりの「私/看護学生」に決意や喜びといった思いが込められ、来春の桜の季節が思われるのです。おじいちゃんっ子のコメントには「おじいちゃんをはじめ、多くの人の力になりたいです」とありました。 帰り道悪口言い合う小学生それでも一緒にならんで帰る 清水恵理奈 さくら国際高等学校(長野県)一年 二句の「悪口」は「悪態」とか「憎まれ口」、言い換えても核心に近づけませんが、一種の言葉遊びなのでしょう。このまま大人になれば『日本国語大辞典』が収録する悪口仲間(遠慮なく気軽に悪口を言い合うことのできる親しい仲間)になるのでしょう。しかしその困難さを「私」は知り始めているのです。コメントによると三人連れ、美しい下句ですが「その場面がなんだか懐かしいような、微笑ましく思いました」とあります。 父の部屋いまだにずっとおいてある昔にあげた父の似顔絵 園田理恵 大阪女学院高等学校(大阪府)二年 三句の「おいてある」とはどのような光景なのでしょう。額に入れて「掛けてある」という本格的なものではない。かといって机の上に置いたままでもない。室内に入ると目に立つところに立てかけてあるとか、そんな置かれ方を想像しました。下句、「私」の「あげた父の似顔絵」は初句「父」にとっては永遠の宝物なのです。コメントには「久しぶりに父の部屋に入ると、壁に私が小さい頃にあげた父の似顔絵があった」とあります。 b 31音青春のこころ2013 「SEITO百人一首」の世界 桃は好きその一言で冷蔵庫桃で埋まった犯人は祖母 浅野君江 清水谷高等学校(大阪府)二年 初句の「桃は好き」の助詞「は」は相対的な嗜好に過ぎないでしょう。たとえば「桃が好き」よりも「好き」の絶対度は低い。しかしその「は」に反応して三四句「冷蔵庫」が「桃で埋まった」。意表を突くのが結句の「犯人」ですが新鮮に響きます。犯意は「私」への愛情ですから再犯は免れないでしょう。コメントには「こんなに買わなくてもいいのに、という少し複雑な気持ちを“犯人”という言葉で表現しました」とあります。 一斉に青に変わった信号機前に進めと言われた気がした 角辻麗衣 同志社高等学校(京都府)一年 直線道路に設けられている信号が、初二句「一斉に青に変わった」と理解しました。少しずらすのが一般的と思われますが、管理する道路によって要件も異なるのでしょう。ともあれ見渡す信号は同時に青、それを「私」は下句「前に進めと言われた気がした」つまり肯定と励ましのサインと感じたのでしょう。コメントには「交差点に何個かある信号が一気にぱっと青に変わって、そんな光景を見たのは初めてなので」とありました。 夏の午後蔦のカーテンすずしげにトカゲの影もゆっくり進む 菊地亜希 女子学院高等学校(東京都)二年 二句「蔦のカーテン」から連想するのは「学生時代」の歌詞の一節「蔦のからまる/チャペル」ですが、「私」の見ている風景はどうなのでしょう。三句「すずしげに」とありますが、やはり夏です。下句と初句が対応しています。また四句の「影」も蜥蜴の影ともいえるし、蔦の影を進む蜥蜴そのものともいえるし、なかなか巧みです。コメントは「グリーンカーテン越しに外を見た。葉陰の向こうに広がる庭は」と続いていました。 寂しさは例えばビターのチョコレイトひとりになりたい夜だってある 北村早紀 京都光華高等学校(京都府)三年 上句、「私」が手にしている「ビターのチョコレイト」あるいは口にした「ビターのチョコレイト」、たとえばこれが「寂しさ」だといっています。ストレートにいえば寂しいのは「私」、だから下句が来ます。あるいは下句だから上句に帰結します。「ビター」の苦み、「チョコレイト」の古風な表記、CMに登場しても不思議でない世界です。コメントは「甘くないチョコをおいしいと思えるくらいには、私も大人になったんだから」。 ちびっ子と夢中ではしゃぐ好きなヒトふとこっち見て笑うの反則 三宅萌瑛 狭山高等学校(大阪府)二年 上句は「好きなヒト」も「私」も参加するボランティアの場面という設定で読んでみました。その「好きなヒト」が「私」の心を見透かしたように、四五句「ふとこっち見て笑う」、それを「反則」といっています。恋をしている「私」、その「私」を客観視する「私」からのイエローカードなのでしょう。コメントは「友人と〝キュンとするシチュエーション〟について話していた時、私が一番共感できたものを歌にしてみました」でした。 c 31音青春のこころ2014 「SEITO百人一首」の世界 授業中カーテン丸く膨らんで私の心秋の風にのる 藤田朱音 セントヨゼフ女子学園高等学校(三重県)二年 窓を開けての授業です。教室は二階か三階でしょう。二三句「カーテン丸く膨らんで」とは、たとえば直線のウォータースライダーを裏返したように閃いているのでしょう。斜めになれば下句の「心」も膨らんで、「秋の風」に乗れそうな、さわやかな時間です。そうした景色を一望できるところに、「私」は座っているのでしょう。コメントには「私は廊下側の席に座っていました」「どこか旅行にいきたいという思い」とありました。 相撲部屋みたいな京の宿でした三日続けて鍋の夕食 後藤のはら 横手高等学校(秋田県)二年 修学旅行でしょう。上句が単刀直入、気分は肉襦袢に髷のカツラというわけです。しかし何を形容したのだろう、疑問と興味を膨らませての下句に納得かつ笑ってしまうのでした。学校側の予算で決まってくる部分また旅館側の人手不足もあるのでしょうが、なにしろ「京の宿」です、四句の三日連続には辛いものがありす。コメントに「大広間にずらっと並んだお膳の夕食を想像していたのに、部屋食とのこと」と悲哀が綴られます。 表札の明かりにヤモリいつもいる人来ると逃げる我が家の門番 河合萌子 同志社高等学校(京都府)三年 初二句「表札の明かり」は照明付き表札か表札を照らす表札灯なのでしょう。三句は昆虫を補食するためです。しかし「明かり」(人)=「いつもいる」(ヤモリ)の優しい関係か浮かび上がります。さらに「ヤモリ」は「家守」とも書きますが、その名前に似ず「人来ると逃げる我が家の門番」とユーモラスに、その生態を描きました。コメントに「近づくとすぐ隠れつつ、顔だけ出したりして(略)、癒されていました」とあります。 夏の夜縁側で切ったわたしの爪パチンと飛んで三日月になる 落合志野 ノートルダム清心高等学校(広島県)二年 「奇想天外」というのは「奇想天外より落つ」の略ですが、これは「奇想天外へ飛ぶ」面白さが身上です。いわば初句「夏の夜」の夢語りなのです。二句と三句が字余りですが下句で纏めました。また二句を含めて三度の「ん」の音がアクセントになっています。コメントは「幼稚園の帰り道、母が私に言いました。『三日月って爪の白い部分みたいって小さい頃思ったよ』」「たったそれだけの事が私にはずっと忘れられませんでした」。 めんこいなぁぶたねこかかえてばあちゃんがくもった窓から舞う雪見つめる 山田千聖 真室川高等学校(山形県)二年 初句「めんこい」は「かわいい」「愛らしい」の東北方言ですが、発語者は三句「ばあちゃん」ですから、「めんこいなぁ」は下句の「雪」が「小さくてかわいいなぁ」となります。しかし一方で「めんこい」のは「ばあちゃん」という文脈も「私」や読者の中に成立するわけで、二つの「めんこい」が重なってメルヘンの世界を作り出しているといえそうです。コメントに「私の祖母と飼っている猫をモデルにしました」とあります。 第三項 契沖顕彰短歌大会(契沖研究会) 毎年、後援の園田学園女子大学大講義室で開催されています。選者は吉原栄徳会長のほか田岡弘子・中野昭子・安田純生といった歌人があたっています。歴史的仮名遣いの発見で知られる古典学者・契沖(一六四〇~一七〇一)は尼崎市の生まれ、このため研究会の活動も市内における歌碑の建立や契沖音頭の普及と幅広いものがあります。 a 第九回(二十四年二月五日) スクールバス思ったよりもせまかった八年前は広かったのに 尼崎市立南武庫之荘中学校二年 藤田耕平 八年前の「私」は幼稚園の園児、今の「私」が乗っている幼稚園のスクールバスを利用していたのでしょう。つまり卒園生ということになります。なぜ、そういうことになったのか。前後の作品から推して中学二年生が職場体験を通して地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の一環として添乗したものと思われます。引率者用シートから幼児用シートを眺めていると、そのまま八年の歳月が上句と下句の対比として蘇ってくるのでしょう。 万羽鶴(まんばづる)死者の数だけ折りました東北の地に願いをこめて 尼崎市立小田北中学校三年 中川謙 千羽鶴とはいいますが、一般的に万羽鶴とはいいません(鹿児島県の出水(いずみ)平野には一万羽以上の鶴が飛来することから、これを万羽鶴というそうですが)。東日本大震災の死者は約一万六千人、万羽鶴は自然の成り行きだったでしょう。二三句「死者の数だけ折りました」からは「私」だけでない多くの指先が見えてきます。古来より鶴は吉兆、死者だけではなく、被災地とそこに生きる人たちへの祈願と慰安が込められているのです。 空を飛ぶ鳥のようにはいかないが見えないつばさ僕にもあるさ 尼崎市立尼崎双星高等学校一年 宇治菜留美 歌意は「鳥のように、見える翼ではないけれども、きっとあるはずだ。僕にも」ですか。気になるのは「僕」が女子ではないかということです。精神科医で作家のゆうきゆうがネット相談で「僕」には「少年のような未成熟で純粋な印象」があり、女性の一人称にはない言葉だということを書いていました。なるほど、昔、シンガーソングライターの森田童子が「僕」で歌っていたことが思い出されます。人称の選択にも詩がありました。 授業中消しゴム一つおっこちて笑顔でキミがかえしてくれた 尼崎市立尼崎東高等学校二年 香山祐也 四句の「キミ」と作中主体である「私」は、どのような関係なのか。すでにつきあっている、つきあっていないが好感を持っている、いろいろなケースが考えられます。あとは読者の想像力次第というわけで、核となるものが読者の中で広がっていく醍醐味があります。その一つ「ころがっていった消しゴムが運良くといおうか、気になっている君のところで止まった。すると思いがけなく」と恋を予感させるシーンを選択してみました。 おい、おかん元気すぎるで無理しなやおかんの娘でうち幸せや 兵庫県立武庫荘総合高等学校三年 前田歩未 四句の「おかんの」まで作中主体を男子とばかり思っていました。するといきなり「娘」ですから驚いたやら、慌てたやら、しかしこの裏切られ感は愉快でした。すべてが予定調和では面白くありません。ちなみに「おかん」は「おかあはん」の変化した語、関西系方言とか中流以下の町家などで多く用いると辞書にあります。「うち」は自称、これも関西地方で主に女性が用いると辞書にあります。初句の「おい」が目くらましでした。 b 第十回(二十五年二月三日) いつもならここにあるはずいえのカギ見つからなくてひやあせが出た 尼崎市立園田東中学校二年 浅野友之 家人が家を留守にする場合に、家族にだけ分かる鍵の保管場所がある。今日も「私」は疑わずに手を入れてみた。おかしい。初二句「いつもならここにあるはず」は、このようなシチュエーションでしょう。四五句は「探して鍵が出てきた」「保管場所が変わっていた」「ほかの事情で家に入れた」など、いくつかの例外も考えられそうですが、玄関が開いてホッとした気持ちが出ています。登場しない家族との絆でもある鍵の歌です。 一人旅電車にゆられてガタガタガタ今日はちょっぴり大人の気分 尼崎市立園田東中学校二年 髙森萌恵 初句「一人旅」とは、どんな旅なのでしょう。二句から新幹線や飛行機を使う距離ではなさそうです。三句の「ガタガタガタ」からは一両編成か二両編成の電車が想像されたりします。さらに踏み込めば行き先は祖父祖母の家とかで、宿泊の心配もない、そんなシチュエーションに「私」を置いてみました。親の監視もない、頼り合う友人もない、すべては自己責任の、しかし窓の風景を楽しむ姿に下句がびったりと収まっています。 こわごわとテストの点数見せたけどふーんと一言心配してよ 尼崎市立常陽中学校三年 石井美羽 初句「こわごわと」から「私」は叱られるかも知れないと思っています。それと同時に点数そのものに「私」が満足していないことも語っています。「私」の実力は、こんなものではない。ところが親に見せると「ふーんと一言」、逆に憤慨せざるを得ないのです。四句のリアクションは父か、母か、ここからは読者が組み立てていくことになります。その「一言」を共有して「一言心配してよ」、結句に「私」の真情がこもっています。 自転車で2人乗りしてきみがこぐその背中から愛が伝わる 尼崎市立尼崎双星高等学校一年 奥園侑奈 自転車の二人乗りは久しく見かけません。禁止されているからでしょう。デートを想定しても実際的でありません(だから歌の素材になったのかも知れませんが)。自転車で通学する「きみ」とバスか徒歩の「私」、荷台に横座りして腰に手を伸ばしているという設定読みました。ペダルを漕ぐ「きみ」の体温が伝わってきます。途中で注意されないとも限りません。禁止された二人乗りに「禁じられた恋」のイメージが重なります。 鍋用のハゲの皮むきむずかしく冷たい水にかじかむ両の手 兵庫県立錦城高等学校二年 小川祐貴 作者の通う錦城高等学校は明石市にある公立定時制高等学校です。港近くには明石市公設地方卸売市場と明石浦漁業協同組合共販所があり、程なくのところに鮮魚店が軒を列ねる魚の棚商店街があります。こうした環境の中で「私」は働いているのです二句の「ハゲ」は「カワハギ」(まるはげ)のことでしょう。慣れない手つき、また秋から冬が旬ということで、調理場の厳しさに鍋を囲む客の姿がオーバーラップして見えてきます。 c 第十一回(平成二十六年二月二日) 新品のノートを使う最初の日いつもの字よりていねいに書く 尼崎市立成良中学校二年 矢野花苗 ノートが古くなれば字も乱雑になるというのではないでしょう。普段から丁寧な字そして大切にノートを扱っているのだろうと思われます。だからこそ手つかずの白がモチーフに選ばれてくるのです。一首の構造は三句までが場の提示、名詞止めとなっています。四句以下が、その後の展開で動詞で終わっています。新しいノートを使い始めるときの、引き締まるような気持ちが、こちらも丁寧に五句三十一音詩として綴られています。 参観日親はまだかと待ちながらきょろきょろしてて注意をされる 尼崎市立小園中学校二年 中村雄介 二句の「親」は両親なのか、あるいは父親なのか、母親なのか、つまるところ参観の対象が不明です。ただ二三句「まだかと待ちながら」に加えて四五句「きょろきょろして」からは良好な親子関係が見えてきます。また授業にも積極的で臆していない、当てられるまでもなく、手を上げるタイプなのでしょう。おまけのように先生から結句「注意をされる」羽目になっていますが、「私」にとって晴れの日の高揚感が伝わってきます。 憧れの高校生になったんだ固いローファーまだ慣れない 奈良県立法隆寺国際高等学校一年 今田晴香 中学生のときはズックかビニール製の運動靴だったのでしょう。それが高校生になると四句の「ローファー」になる、革靴ですから、大きな変化です。紐や留め具のないカジュアルな靴ですが、しかし上句「憧れの高校生になったんだ」を実感させてくれる代表的なアイテムなのです。下句は素材である靴の質感を表現し、加えて高校生活に「まだ世れない」という、毎日が新鮮な驚きの連続の、そんな初々しさを重ねているでしょう。 明石浦漁業共同組合十七歳魚(さかな)に埋(うも)れてがんばっている 兵庫県立錦城高等学校二年 重野泰輝 作者は前年の「鍋用の」の作者と同じ高校に通っています。昼間は明石浦漁業共同組合mで働いているのでしょう。初二句「明石浦/漁業共同組合」(五/十一)で十六音ですが、勢いですから、気になりません三句以下は「六/八/七」音になります。移動販売や通信販売、もちろん事務の仕事もあるのでしょうが、掲出歌は競りをする施設内での勇姿が思われます。下句は十七歳の自画像ともなっていて、その充足ぶりが魅力です。 使い道なんてないのに財布には去年の映画のチケット二枚 兵庫県立锦城高等学校二年 田村綺映 財布に入っているのは使わないままに終わった映画のチケット、それも二枚です。好きな人と行くつもりだったチケット、もしかしたらそれが初めてのデートになるはずだった二枚です。いえずに終わったのか、いって断られたのか、そこのところは分かりませんが使わずに終わった映画のチケットが、そのまま財布の中に残っています。行きたくて、行けなかった、そして年が明けても処分できない「私」の青春の余情を漂わせて。 第四項 ―ふれあいの祭典―兵庫短歌祭作品集(兵庫県歌人クラブほか) ーふれあいの祭典ー兵庫短歌祭は毎年行われていますが、平成二十四年十二月十五日、アステ川西のアステホールで開催された―ふれあいの祭典―兵庫短歌祭の作品集から抄出します。この年のみですが、主催団体である(公益財団法人)兵庫県芸術文化協会・川西市・兵庫県歌人クラブの選で「ジュニア短歌百首抄」が掲載されているのです。 見上げたらヒコーキ雲がまっさおな空にひとすじ夏が始まる 三木市立星陽中学校 清水朋瑛 空はキャンバス、二句は「飛行機雲」ではありません。カタカナの「ヒコーキ雲」であることによって、ぐんぐんと伸びていく、いかにも白い航跡に目を奪われます。三句から四句の句またがり「まっさおな空」も透明感があって見事な背景です。そして一気の四句切れ、さて次に何を持ってくるのか。それによって歌が生きもするし、死にもするのです。息を呑む瞬間ですが、異なる文脈から、季節を用意して画竜点睛としたのでした。 宿題を計画的にやりたいが頭の中は計画停電 姫路市立坊勢中学校 前田紗希 東日本大震災以後、節電が叫ばれ、計画停電も云々されました。そうした時代背景を取り入れた歌、二句と結句が対応してユーモラスです。実際の場面としては夏休みの宿題がはかどっていないのでしょう。言葉遊びの世界ですから「計画停電」の中身を追求しても意味がありません。ただ単に高校野球のテレビ観戦中かも知れません。四句「頭の中」から漫画チックにアイデアが閃いたときの電球マークを連想するのも一興でしょう。 コープでの店内放送緊張しマイクの前で何度も練習 宝塚市立西谷中学校 松田航 兵庫県には中学二年生が職場体験を通して地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」があります。作中の「私」は生活協同組合、コープ(COOP)の店舗で体験学習に参加しているのでしょう。受け持ったのは店内放送、話す内容は事前に分かっているわけですが、それでも不安です。何しろ校内放送と違って一般社会とダイレクトにつながるわけです。下句の練習風景に、その緊張の度合い、また真剣で健気な姿がよく現れています。 船乗り場あいさつをしてゆっくりと遠くなるのはあなたの背中 南あわじ市立辰美中学校 堀大輝 連絡船で通学している男子生徒を思いました。挨拶した相手は女子生徒、ここまで一緒に来たのでしょう。「さようなら」「またね」。そしてその後を甲板に立つ「私」が陸を歩いて遠ざかる女子生徒の後ろ姿を見やっているのでしょう。結句からは「あなた」への淡い思慕が伝わってきます。その視線を女子生徒も背中に感じていることでしょう。但し、シチュエーションは一様ではありません。読者の中でドラマは育つのですから。 足の指全てにマメがあるけれどこれがバレエの努力の証 三木市立緑が丘中学校 丸川こころ 二句の「マメ」は漢字で書くと「肉刺」、見ているだけでも痛くなります。トゥシューズでつま先立ちをするからなのでしょう。両足の指だと十個の豆のような水膨れができている、その症状からは過酷な日々の練習が思われます。ただ下句から推して、肉刺ができて潰れて、その繰り返しの中で胼胝になりつつあるのではないでしょうか。決して美しいとは思っていないけれども、勲章のような結句「努力の証」を眺めているのです。 第五項 感じて短歌(加古川市中学校国語研究部会) 歌集『感じて短歌』は兵庫県加古川市内十二校の中学生の、おそらく三年生と思われますが、作品五四〇首が収録されています。平成二十四年五月から翌一月まで月ごとの題詠となっています。いきいき表現プラン推進委員会の編集、発行は三月一日です。 選と批評は茅花短歌会の代表、前田昭子が担当しています。 弟と母を見舞って帰るバス肩を並べて雨の音聞く 加古川市立両荘中学校 木下和厚 弟は中学生あるいは小学校の高学年と思われます。四句「肩を並べて」二人は立っている。坐っているとしたら横向きシートでしょう。どこまでもシチュエーションにすぎませんが、前向きシートだと雨に対して遠近が生じます。等距離しかもその先の車窓を流れる雨滴を見やっている。普段は父よりも母と過ごす時間の方が多い。したがって影響は直接かつ不安は心身両面に及ぶ。だから寡黙となり、雨音の中に立ち尽くすのです。 公園の灯りの下でボール蹴る自分ももっと輝くんだと 加古川市立平岡中学校 中岸良介 四句の「自分」は一人称の人代名詞、意味的には「僕」「俺」「私」と同じですが三音となると「私」、二者択一で身体感覚にフィットする「自分」が残り、次の「~も」が来ます。この係り助詞「も」(自分もまた)が指し示すのはどんな選手なのでしょう。運動神経抜群のライバルかも知れません。あるいは本田圭佑・香川真司といった憧れの選手が走っているのでしょう。公園の灯りの下は歓声で渦巻く夢のピッチなのです。 妹とお風呂に入り比べ合う背中に残った夏の思い出 加古川市立氷丘中学校 足立祥子 スーパー銭湯のような日帰り入浴施設を想像しました。水着で覆われる部分と露出していた部分、その白黒のコントラストが鮮やかな姉妹です。日焼けを気にする女子、気にしない女子、むしろ日焼けをしたい女子、このように分類するなら間違いなく「勝った、負けた」の三番目に入るでしょう。だから「夏の思い出」なのです。それでも日焼け止めを手にするときがやってくる。今、青春へアイ・エヌ・ジーの「私」と妹なのです。 長い髪二つ結びが暑いから後ろにまとめてお団子一つ 加古川市立中部中学校 藤木琴子 二句の「二つ結び」は別名をツインテール、調べると長い髪を左右の中央あるいはそれより高い位置でまとめて肩に垂らしたものをいう、とあります。結句は「お団子」ヘア、三句「暑いから」一つにまとめたのでしょうが、手間は半分とはいかないでしょう。つまり、お洒落を忘れていないのです。このあたりは男子生徒の髪型と対照的です。作品は「二つ」と「一つ」という数詞を対応させて単純かつ髪型の名称にも親しみを覚えます。 似合うやん浴衣の君に言えなくて「馬子にも衣装。」言って後悔 加古川市立別府中学校 藤原拓海 国語辞典は「馬子」を「つまらぬ者」や「誰でも」の意味で説明しています。遠い昔の諺だから仕方ありませんが、馬子とは馬をひいて人や荷物を運ぶことを職業とした人のことです。近い昔、タクシードライバーを雲助と呼んで訴えられた漫才師がいました。それはさておき本音「似合うやん」が、照れからでしょう、口をつくと「馬子にも衣装」の逆説表現となる「僕」の後悔に同情ないし共感する男子も少なくないと思われます。 運動会足をつないで1,2、1、2、心もつないでみんなでゴール 加古川市立氷丘中学校 近都麻衣 四句に「みんな」とあるので二人三脚でない、ムカデ競争でしょう。五人一組か、十人一組か、また男女混合か、女子だけなのか、あるいはトラックを走るのか、グラウンド内の直線コースなのか、このあたりは読者に委ねられた世界です。ただ三句の元気な掛け声と揃った足並みが目前を過ぎていく。手かせ足かせというが、その足かせに自由を与えるのが四句の「心」です。チームワークを体現したようなリズムが聞こえてきます。 真っ白な体操服によく映えるクラスカラーの青いハチマキ 加古川市立平岡南中学校 繁原実沙 「私」の現在地はどこか。たとえば鏡に向かってハチマキを締めながら思ったのか。入場行進あるいは整列して壇上の話を聞きながら思ってのことなのか。それともトラックの外周に沿うクラスの席から応援しつつ思ってのことなのか。逆にトラックの中から思ってのことなのか。そのいずれとも決めがたい。またそのいずれの場合にもフィットする。清潔な白と空の色に通うクラスカラーがいやが上にもクラスを一つにさせるのです。 コーナーを曲がると視界が広がってつなぐバトンに力がこもる 加古川市立平岡南中学校 小林駿一 体育大会。種目は学級対抗リレー、男女混合として読みました。トラックは二百メートル、何番目の走者かは不明ですがバトンを受け取ってからは一列の力走でしょう。抜きにくいし、抜かれにくい。まもなくコーナーに差し掛かる。二句「視界が広がって」のとおりチャンスであり、またピンチである。それぞれのコースの向こうには次の走者が手を振っている。クライマックスそしてバトンを手渡したあとの達成感も伝わってきます。 将来の話をすると父親がオレの進路を熱く語った 加古川市立平岡中学校 洋谷友治 思わず吹き出してしまいました。父親にすれば息子に託す夢があるのでしょう。分身としての息子そして時間を遡るならば系統樹のように未来は可能性に満ちていた。そこでの選択の一つ一つが他の可能性を封印する。もしかしたらあり得たかも知れない「私」の人生を重ねているのかも知れない。「オレ」が立派なのは、そんな「父親」を拒絶していないことです。他人事のように描く三句以下にユーモアの源泉を見る思いがします。 カレンダーめくって時間が戻るならまたもう一度中3の夏 加古川市立平岡南中学校 木曽幹也 十一月の「自由課題」詠です。ほんの二、三ヶ月前の夏または夏休み、充実した季節を振り返っています。「僕」と同じようなことを考えたのが藤原俊成(ふじわらのしゆんぜい)(一一一四~一二〇四)です。文治六(一一九〇)年〈けふ暮れぬ夏のこよみを巻きかへし猶春ぞとや思ひなさまし〉と、こちらは惜春です。いみじくも八〇〇年の歳月を隔てた大歌人との交感また競詠です。三句の仮定形「なら」で一休止、そのあとの展開も心地良い仕上がりです。 第六項 兵庫県高校生文芸集(兵庫県高等学校文芸部会) 兵庫県高等学校文芸部会は平成二十四年度に発足したばかりです。そのせいもあってでしょう、初年度の応募は一校十三首でした。翌二十五年度は七校四十六首です。また第二号から短歌部門の助言者として歌人の吉岡生夫が関わらせていただいております。 次の作品は、その第二号からの抄出です。 テディベア机の上で座ってる友だちと買ったおそろいのもの 兵庫県立社高等学校一年 中田夏生 初句の「ディ」を準拗音とすれば一音、計四音で字足らず、助詞「は」を補いたい衝動に駆られます。しかしそうすると形は整っても、何か力が削がれると作者は感じたのでしょう。何かとは何か、縫いぐるみの「ベア」(熊)が「ペア」(二つで一揃いのもの)であること、これを類音といいますが、意味以外の要素で主張していることでしょう。初句で場面と主題を提示、クローズ・アップして、そこに三句以下の思いを込めました。 |