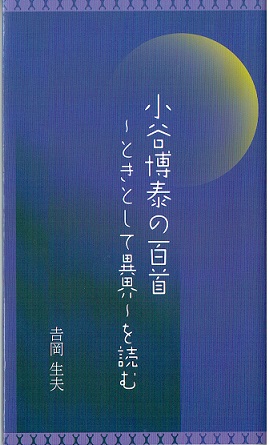| 小谷博泰の百首~ときとして異界~を読む |
病院の廊下のはてに行き暮れて死にしものらといる遊戯室 第一歌集『たましいの秋』四八頁
著者は小谷水彦(おたにみずひこ)、現代仮名遣いである。歌集の「あとがき」に「私にとって、詩歌は現実の仮象を超えるためにある。現実以上に実在的な真実世界の虚構こそ望まれるものである。(略)。うたは魂の贄(にえ)である。」とある。三句は「行く途中で、日が暮れること」(日本国語大辞典)、死んでいない〈私〉であろうか。四句は具体的にはわからない。死者が見えているともとれるが、私は死が充満した空間として読んだ。
まちがへてエレベーターでたどりついた病院地下の霊安室前
たとえば右のような作品(第六歌集『海辺の街から』二一頁)であるが、異界を詠う姿勢は一貫して変わらない。一九八三年、歌集刊行時、著者は三十九歳であった。
|
他界よりきこゆるごとく響(な)りている夜をはるけきひとつシグナル 第一歌集『たましいの秋』一九七頁
結句の「シグナル」、ここでは鉄道の信号機であろう。四句「はるけき」だから空間的に遠く隔たっている。それが上句しかも夜である。初句「他界」とは自分が属さない世界もしくは死後の世界(あの世)をいうが、シグナルが警告音であることを思えば、後者と考えるのが自然だろう。いつの日かは分からないけれども御迎えのある世界である。
夕暮れに来てはどろ田をつつきゐるあの細きわが過去世のものら
第三歌集『さようならやま』(二二頁)に載る。掲出歌が来世とすれば、これは前世の縁を詠っている。その前生において〈私〉はサギだったというのである。過去世のことはともかく、今生においては自分が属さない世界つまり他界を詠っていることになる。
|
地下鉄の廃坑にひと飼われいて日ごと夜ごとに気のくるいゆく 第一歌集『たましいの秋』二一四頁
二句の「廃坑」というのは廃棄された鉱山や炭坑のことであるから、「地下鉄の廃坑」というのは意味の上からも解せない。また地下鉄道のためのトンネルを廃棄する、そんな無責任な工事などあり得ない。しかし、それをあらしめるのが異界なのだ。なぜ、閉じ込められたのか。すなわち「ひと飼われいて」とあるが、飼っているのは何者か、もわからない。ただ飼われているのは読者の私であるかも知れない。そんな不気味さだけは伝わってくる。作中の〈私〉もいない。おそらく語り部のような位置付けだろう。
拷問をされてうめいているような声が地底の奥から聞こえ
二〇一八年刊の第十一歌集『季節の手毬唄』(一五八頁)に、こんな歌もあった。
|
この山の枯木は首をつるしおり何千とあるすべてわが顔 私家版歌集『タタの星祭』九頁
第二歌集『みずいろ迷宮』五七頁にも載る。鳥山石燕著『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫)に「人面樹」(にんめんじゅ)がある。「しきりにわらへば、そのまま落花すといふ」とある。水木しげるの『日本妖怪大全 妖怪・あの世・神様』(講談社文庫)は「じんめんじゅ」で解説が詳しい。掲出歌の顔はたぶん笑っていない。第一歌集『たましいの秋』の口絵は人の顔を大量に入れた箱だった。手も見える。墓場のようでもあった。結句は作者の強迫観念であろうか。第三歌集『さようならやま』には次の歌がある。
人の顔に似る花たちの咲いてゐる道を帰りぬ塚多き村(五〇頁)
ルドンに「沼の花」だったか、似た作品がある。さしずめ、こちらは「塚の花」か。
|
田のもなかに小さき森のありてまたきのうわらべの入りてもどらぬ 私家版歌集『タタの星祭』一三頁
神隠しの森を詠っている。「やまと」四十二首の一首(第二歌集『みずいろ迷宮』なら「夕もや峠の」七十首の一首、六〇頁)である。両歌集とも、これ以上の情報はない。「あとがき」の(追記)に「私の住んでいるあたりには、古墳や墓地がやたら多い。おかげで、住宅地の近くで、畑に桃が咲き、田に鷺が飛び、池に鴨が鳴く。夜は静かで暗い。古墳の横の小道を夜に歩いていたりすると、私のような唯物論者にとっても、さすがに不気味である」とあるが、その不気味さの中にこそ「神隠しの森」も存在する。三四句「またきのう」とあるから一度や二度でなく異界の扉が開いたのである。第三歌集『さようならやま』(一二〇頁)に次の作品がある。人の怯えよりも犬の怯えが本能的、説得力がある。
犬おびえほえしがのちはただ黒く夜の古墳のしづまりゐたる
|
蛙鳴くと思いて寝るにいつしかも蛙となりてわれの鳴きいる 私家版歌集『タタの星祭』一四頁
二句「思いて寝るに」とあるから三句以下は〈私〉の夢を詠っているともいえる。夢の中で〈私〉が蛙となって鳴いている。だが印象は違う。夢ではない。夢からさまよい出た、あるいは脱け出た魂が蛙となって鳴いている。イメージとしては、こちらの方が強い。
同じ一四頁に次の歌がある。いずれも「やまと」四十二首の一首である。「われの鳴きいる」声は、小さな一団から時空を超えた「太古の声」となって響かせるのである。
この星に生きつぐあかしかいかいと太古の声で蛙はなくも
「蛙鳴くと」は第二歌集『みずいろ迷宮』六〇頁、「この星に」は同六一頁に収録されている。タイトルは「夕もや峠の」七十首、別の意図で再編集しているのであろう。
|
峠越えてきたれど出会うものたちの先の部落に似たる顔々 私家版歌集『タタの星祭』二六頁
「タタにて 30時76分」五四首の一首である。プロローグに「地球に接してTATAという異空間があるという。ある種の人々がそこに出入りできるという。地球の一時間はTATAの一日の三分の一、TATA星時間の33時間33分33秒という」とある。峠を越えても「似たる顔々」とは不思議である。これを何と呼べばいいのたろうか。インターネット上に「実用日本語表現辞典」という辞書サイトがあり、試しに「平行世界」(別表記「パラレルワールド」)を見ると「あらゆる選択の上に現在自分のいる世界が成り立っているとして、選択を違えた『もしも』の数だけ存在すると考えられる別の世界を意味する語」とある。これだろう。〈私〉はどこかでパラレルワールドに迷い込んだのである。
第二歌集『みずいろ迷宮』(三八頁)にも収録されているが、タイトルは「蟬の木過ぎて」五四首、作品の数は同じだが、配列は全く別、作品も一致していないようである。
|
くちびるのような花びら開かせてとげとげの木が夢にたたずむ 私家版歌集『タタの星祭』三九頁
「タタにて 30時76分」五四首の一首である。花びらを花唇という。また美人の唇も花唇と呼ぶ。あるいは諺に「美しい花にはとげがある」ともいう。「ような」と比喩表現だが上句の肉感的な捉え方と四句の「とげとげ」が効いている。夢にでてきた「くちびるのような花びら」とはどんな花だったろう。三句がセクシーに迫る。「ニュー・フォーク地帯」(六三首)の六十頁には次の歌が載る。二句からは柘榴や通草を思い出すが、あれは木の実か。上句と下句の対比、とりわけキツネの前世を思わせる四句に味わいがある。
草の実がくちびる裂けて笑いあう夕べひと恋うきつねにて候(そろ)
「くちびるの」は『みずいろ迷宮』の六一頁、「草の実が」は二八頁に載る。
|
魚らあまた水族館の円筒の壁のまわりを死ぬまでめぐる 私家版歌集『タタの星祭』七五頁
第十三歌集『河口域の精霊たち』の最後に「著者略歴」があり、「歌集・歌書」の欄があるが、『タタの星祭』は含まれていない。第十二歌集『カシオペア便り』には「小谷博泰歌集・歌書」欄があるが、やはり含まれていない。第十歌集『シャングリラの扉』も同様である。第二歌集『みずいろ迷宮』の「あとがき」に「あの歌集は、発行部数が少なすぎて」云々とある。二五〇部である。しかし、『みずいろ迷宮』に収録された作品はいい。収録されなかった作品はどうなるのか。たとえば掲出歌も、その仲間と思われる。
一読、イワシの大群を想像した。しかし初句「魚らあまた」とあるだけで、種類は特定されていない。また沢山といっているだけだから、どんな魚でもよいことになる。円筒形の規模にも因るだろう。メインは下句とりわけ結句であろう。事実に違いない。その事実によって、人間も含めて、存在の無意味性が問われているような気がするのだ。
|
逝きたりし者らのどかにつどいいる二次元世界またはまんだら 第二歌集『みずいろ迷宮』一六八頁
「顔白き者ら」六〇首の一首。上句が、どのような曼荼羅をいっているのか分からない。もしかしたら浄土曼荼羅であろうか。さらに気になるのは四句の「二次元世界」である。古典的名著の誉れ高いエドウィン・アボット・アボット(一八三八~一九二六)の『フラットランド たくさんの次元のものがたり』(講談社選書メチエ)は二次元の世界の住人が三次元また多次元に目覚めたが故にフラットランドの議会に逮捕される物語であった。掲出歌の結句も縦と横たけで高さのないフラットランドである。しかし描かれているのは三次元の世界である。いくつもの三次元の世界が描かれている。世界大百科事典で「異次元」を引くと「三次元空間の集合が四次元であり,四次元空間の集合が五次元となる」とある。つまり曼荼羅図とは四次元の世界を二次元の世界で表しているのである。方向性としては『フラットランド たくさんの次元のものがたり』とは逆の豊穣さにある。
|
澄みわたる水にかじかの声のして百一階の屋上庭園 第三歌集『さようならやま』一八頁
「五月はきつね(東京にて)」二十三首の一首。一連には〈宵をともす明かりの下に商ひてゐるものたちの人にはあらぬ〉(一九頁)もあって表題がすべてではない。掲出歌も同様で日本に百一階の建物はない。あべのハルカスで六十階、横浜ランドマークタワーで七十階、その百一階の屋上庭園でカジカガエルを飼育しているというのだが、美声を人工衛星にでも聞かすつもりなのか。上句「澄みわたる水」以下の対比の妙に惹かれた。
遠足で地下百階の公園の池のほとりで弁当食べた
第十二歌集『カシオペア便り』中「カシオペア便り」十二首の一首(一六一頁)。舞台は地球ではない。しかし「遠足」「公園の池」「弁当」と限りなく懐かしい未来である。
|
水になくはわがたましひと思ひつつ手もとのよわきあかりを消しぬ 第三歌集『さようならやま』五九頁
『タタの星祭』(一四頁)の〈蛙鳴くと思いて寝るにいつしかも蛙となりてわれの鳴きいる〉について「夢からさまよい出た、あるいは脱け出た魂が蛙となって鳴いている」と書いた。だが、この歌は「夢」ではない。初句「水に鳴く」は蛙だろう。それが「わが魂と思ひつつ」と詠っている。魂が二つあるのでは、たぶん、ない。魂が脱け出たから下句「手元の弱き灯りを消しぬ」と空っぽの身体を眠りに就かせるのである。
かいかいと蛙のなきて雨ふれり街のざわめき絶えしたまゆら
『α階のS』の七〇頁にある。『タタの星祭』(一四頁)の〈この星に生きつぐあかしかいかいと太古の声で蛙はなくも〉と同じく、蛙は「かいかい」と鳴いている。
|
かうもりが塔を飛び立つあのなかのわが遺伝子を分けし一群 第三歌集『さようならやま』七二頁
「惑星間ステーション」十六首の一首。地球滅亡後の世界のようだが、コウモリと人間の〈私〉の関係が、下句「わが遺伝子を分けし」とあれば「子」ではないのか。しかも、その「一群」が塔からいっせいに飛び立つというのだから信じられない光景である。
はるかなる塔見え誰も行きつかずゆきつかぬまま今日も暮れゆく
つぎつぎと塔の上よりとびおりてをれど地面に誰もとどかぬ
一首目は『さようならやま』(一四二頁)の歌、但し「風、または京都」十二首の一首である。二首目は第四歌集『α階のS』(二九頁)の「洪水の予感」七首の一首である。片や距離、片や高さ、ともに永遠の未到達という不思議な塔の世界を詠っている。
|
なめくじにふるには足らぬ量をもてわが食ふ飯に塩をふりをり 第三歌集『さようならやま』八三頁
ご飯に塩を振るときに「なめくじにふるには足らぬ量をもて」などと思うだろうか。絶対に思わない。そして絶対に忘れない歌である。願わくは、ご飯を食べるときに甦らないでほしい。そう思うだけだ。しかし鈴木棠三の『日本俗信辞典』を開くと、どうか。「ナメクジを焼いて食べると声がよくなる」「痔には、ナメクジを食べる」「淋病には、ナメクジを生きたまま呑む」「胃病には、ナメクジを丸呑みにする」「ナメクジの焼いたものは疳の虫に効く」「痰が出るときは、生のまま呑む」「風邪にはナメクジを煎じて飲む」等の夥しい民間療法の歴史を重ねるとき、上句も驚くにあたらないのかも知れない。但し、日本大百科全書は病気が治るとかいった「迷信があるが、場合によっては寄生虫の感染のおそれもあるし、一般に不潔な所で生活をしているので、このようなことは避けたほうがよい。現在のところナメクジによる確実な薬効は証明されていない」としている。
|
うすあかりともる社のしろじろとして狛犬の目のふと動く 第三歌集『さようならやま』一二一頁
二句「社」(やしろ)は神社であろう。三句「しろじろと」は明け方の意味ではない。初二句「うすあかりともる」本殿を受けて、白く見えると解釈した。そして誰が見ているのか、四五句「狛犬の目のふと動く」というのだ。その「狛犬」とは何か、世界大百科事典によると「聖域を守護し,邪悪の出入を禁ずる目的をこめて置かれた鎮獣と考えられる」とある。しかし歌から伝わってくるのは真逆とはいわないが怪異で気味が悪い。
真夜中となりて座敷のひな壇の人形たちの目が光りたり
『うたがたり』(一四六頁)に載る。家人も眠る丑三つ時、それが救いであろう。雛人形には汚れを祓う呪具としての歴史もある。ただ単に綺麗、豪華なだけではない。
|
夕暮れの時計台ゆがんで立つ空の裂けめより青き魚の飛び来る 第三歌集『さようならやま』一五一頁
「北の青」二十首の一首。「夕暮れの~立つ」は時空のゆがみをいっている。さらに驚くべきことは「空の裂けめより」以下である。たとえば映画館の大画面を見ているような迫力である。「空の裂けめ」で繋がったのは海(湖・川)だったのだ。これを読んで〈山の上を過ぎつつありし飛行機のにはかに雲にまかれ消えたる〉(四二頁)を思い出した。雲の中に飛行機が入った、と読んだ。しかし掲出歌とは逆に「空の裂けめ」にのまれたのではないか。向こう側の世界に消えたのではないか、と思うようになったのである。
ひと行かぬ沼地に青き花が咲きあの世の風のごときがかよふ(一五二頁)
同じ「北の青」の一首。「ごとき」と詠うが結句「通ふ」、繋がっているのである。
|
またたかぬ目玉ひとつがうたたねの夢の奥までのぞきこみをり 第四歌集『α階のS』二七頁
「二〇XX年」二首の一首。もう一つは〈ベルリンの壁が崩れて五十年たつたがどこもかも壁のなか〉である。作られたのは「一九九六年」(目次)、ベルリンの壁崩壊は一九八九年、したがって比喩としての「壁」になる。片や夢。ゲゲゲの鬼太郎の目玉おやじと違って、こちらは無言で身体を持たない。その目玉だけが「夢の奥まで」だから、おぞましい。「壁」に囲まれた生活、心奥まで監視されている「二〇XX年」であるか。
いままでに食べたさかなの目玉らが奈落の底でにらみつづける
『季節の手毬唄』(一四三頁)に載る。「奈落の底」と今を生きている〈私〉を結びつけるのは、やはり夢か。三句の「ら」は鳥や牛の目もか、成仏していないらしい。
|
夏の夜とびこんできたかなぶんはお座敷犬がばらばらにした 第四歌集『α階のS』七四頁
「ほの明るみて」六首の一首。「座敷犬」は「ざしきいぬ」、「愛玩犬」は「あいがんけん」、辞書を引いて意外な気がした。その「お座敷犬」の玩具にされてしまった不運なカナブンの登場である。もとより昆虫であり、前足で弄んでも、血を流したり、汁を出さないところ、その金属光沢が注意を引いたか。結句に珍しいものに対する興奮が見える。
土に降りて女王蟻となるはずの羽蟻を犬が食べてしまつた(二〇五頁)
食卓にこがね虫たちのしにがらを並べてあきの静けさにいる
一首目は『α階のS』、不運な将来の女王蟻だが、これは犬の本能だろう。二首目は『たましいの秋』(一六九頁)、お座敷犬の飼い主であっても、不思議でない人物である。
|
すみれほどの小さき山羊があらはれて机上の本をかじりてゐたり 第四歌集『α階のS』八八頁
「パラレルワールド」二十首の一首。〈私〉の机の上に、突然といったかたちで現れた生きもの、およそ似つかわしくない山羊は、どこからやってきたのか。初句に「すみれほどの」とある。高さ十㎝ぐらいであろうか。こちらの世界なら足元に咲く花、その紫ごと口に運んでいるかも知れない大きさである。パラレルワールドと知ってか、知らずか、その山羊は〈私〉の机の上の本を囓っているというのである。比喩が美しい歌である。
本当の父と母とが居るごとし山辺の家に明かりともれる
同じ「パラレルワールド」の一首(八四頁)。ひっそりとした「山辺の家」そして懐かしく、優しい明かりを遠望していると、上句のような幻想が湧いてきたのであろう。
|
めのまへを電車の通る下宿屋に女と暮らすあさきゆめみし 第四歌集『α階のS』一〇四頁
「昭和エレジー」十首の一首。エレジーを辞書で引くと悲歌、哀歌、挽歌と出てくる。結句で夢だと断っているが、この「女」と「私」の恋は実ることはないのだろう。そして連想するのは「同棲」という言葉である。上村一夫の「同棲時代」が昭和四十七年から四十八年、その四十八年には梶芽衣子・沢田研二主演でテレビドラマ化、続いて由美かおる・仲雅美主演による映画が上映されている。なお映画の主題歌は大信田礼子である。また南こうせつとかぐや姫の「神田川」も昭和四十八年である。翌年、関根恵子・草刈正雄の主演で映画化されている。いわば同棲ブームを背景とした「あさきゆめ」なのだ。
第七歌集『夢宿』(六四頁)に再び登場する。由美かおるのヌードが衝撃的だった。
遠き日の夢にてあれど線路わきの安アパートに女と暮らす
|
誰にでもいのちの終はりが待つといへば安らぐといふものでもない 第四歌集『α階のS』一一七頁
「ひたすらに」五首の一首。下句とりわけ「ものでもない」の六音が響く。死は未知の世界しかも死んでいくのは個人、〈私〉一人で死んでいかなければならないのである。このあたりの心情を詠ったものがないか、探したが拾えなかった。〈命などいつか終はると思へどもさとるは難(かた)しわが身となれば〉(『海辺の街から』一八頁)が、やや近いか。
しらじらと夜はあけはじめやがて俺のゐないあしたがやつてくるのか
長く続く廊下のはてのドアを出て戻ってきたものだあれもいない
一首目は『夢宿』(一五頁)、「あした」は「朝」かつ「明日」(未来)でもあろう。二首目は『シャングリラの扉』(四三頁)、客観的あるいは比喩的に描いて巧みである。
|
冬の日の小便小僧 小便をしてをらざればなほさら寒き 第四歌集『α階のS』一四七頁
日本国語大辞典で「小便小僧」を引くと「ベルギーのブリュッセル市に建つ、小便をする裸の男児の像。また、それを摸して噴水などにとりつける像」とある。珍しくないわけであるが、掲出歌の像は六甲高山植物園のものだろう。冬はマント着せ行事があるらしい。私の訪れた二〇二〇年六月にはマスクをしていた。やはり小便はしていなかった。
雨の日の心さむきにここちよげに小便をするせうべん小僧
春まひる小便小僧のしょうべんの音を聞きつつベンチに眠る
一首目は第七歌集『夢宿』(三二頁)、二首目は第九歌集『うたがたり』(一五〇頁)、季節によって小便小僧も微妙に変化する。そして、ここは〈私〉の居場所でもある。
|
灯台の霧笛がきこえてゐるやうなわが人生の夕暮である 第四歌集『α階のS』一六九頁
「北の大地」二十八首の一首。北海道が舞台である。感傷といわれると、それまでだが、その感傷が悪くない。すでに第三歌集『さようならやま』に〈人生もすでに日暮れとどしやぶりのあと雷鳴の過ぎて行きたり〉(一一九頁)という人生即日暮れ観を吐露した作品が見られたが、類似の歌が、現れては消え、消えては現れる。そこを追ってみた。
人生の夕暮れ近きうすぐもりふはりふはりと雪がまひをり
人生も引け時かなと遠くきて路面電車に揺られて思う
一首は第五歌集『冬の昼顔』(一〇七頁)に載る。場所は不明、自宅か。二首目は第九歌集『うたがたり』(二六頁)に載る。長崎の路面電車に揺られているのである。
|
聖地へとむかふ正義の十字軍ほど迷惑なものはなかつた 第四歌集『α階のS』一七五頁
「正義(Ⅱ)」二首の一首。「イミダス2018」で「十字軍」を引くと「十字軍はキリスト教徒にとって聖地奪還を掲げた聖戦だったが、次第に教皇の政治的野心や、諸侯の領土獲得などに目的がすり替わり、イスラームにとっては略奪と虐殺の侵略戦争にほかならなかった」とある。「植民地」化をいう辞典もあり、迷惑とは、このことだったろう。
正義とはいかなるものぞポルポトに紅衛兵にかがやく正義(一一八頁)
アメリカにとりてはパールハーバーの報復なりしやヒロシマ・ナガサキ(一八三頁)
一首目は「正義(Ⅰ)」、二首目は「正義(Ⅲ)」の作。ポルポト(カンボジアの政治家)、紅衛兵(文化大革命)そして原子爆弾、共通しているのは夥しい死者の数である。
|
しあはせは時の浪費をすることと昼のターミナル水割りを飲む 第五歌集『冬の昼顔』一四頁
第三歌集『さようならやま』の「あとがき」に「神戸から奈良へ八年間かよった。やっと奈良へ転居して、やれやれと思っていたところ、一年で勤め先が神戸に戻った。今度は奈良から神戸に九年通った。乗り換え乗り換えしながらかよっていると、帰りには疲れて駅で缶ジュースを飲んだりする。そのうち、乗り換えの鶴橋で酒を飲む。やがて、大阪駅でも飲む。神戸で飲み、大阪で飲み、奈良に帰ってまた飲み、となると立派なアル中である。転居して神戸に戻ったが、まだアルコールは脱けない」とある。神戸から奈良へ八年、奈良から神戸へ九年、計十七年の長距離通勤が残した習慣は、第五歌集に至っても変わっていないようである。次の歌は第四歌集『α階のS』一三一頁、神戸に転居後である。
ターミナルの中二階なる喫茶店 黒ビールなど飲みゐてだるし
|
ゴッホの絵の居酒屋なぜかなつかしくたぶん私がかたすみにゐる 第五歌集『冬の昼顔』一七頁
「入院を控えて」九首の一首である。ゴッホの絵とは何だろう。私は「夜のカフェ」(「夜のカフェテラス」ではない)を想像した。『ゴッホの手紙(テオドル宛)中』(岩波文庫)から拾うと「この絵は今までに僕が描いたうちで最も醜いものの一つだからだ」(二一八頁)また「僕は《夜のカフェ》の絵で、カフェとは人が身を滅ぼし、狂人になり、罪悪を犯すような場所だということを表現しようとした」(二二六頁)などに拠った。
よくもまあ今まで生きてきたものと思へば酒を飲まずにをれぬ
一連に、こんな歌(一六頁)もある。「思へば」までは分かる。しかし「酒」以下の展開は作者にしか説明できないだろう。結句「をれぬ」は祝杯というには複雑である。
|
看護婦ら湯灌のやうにわがからだぬぐうてをれどああ勃起する 第五歌集『冬の昼顔』二三頁
「病院へ行かう」二十一首の一首である。「湯灌」は死体を棺に納める前に湯で洗い浄めることをいう。「あとがき」(二〇〇八年四月)に「この歌集の、はじめには頸椎の手術があった」。これであろう。「二年後に、今度は、前立腺癌だときた」。進行していないので「頸椎のときの倍の三年間、治療を引き延ばした」「現在は、ここらで年貢の納め時か、という心境になってきた」とある。二〇一三年刊の第七歌集『夢宿』(一〇九頁)の次の作品が、その一首だという確証はとれないが、そうであっても不思議ではない。
勃起せるわがからだ拭く若きナースふいにとまどふやうに黙りき
自分の意思とは無関係に「ああ勃起する」のだろう。悪意や、湯灌からは遠い。
|
あぢさゐの花まりの青 奥透きて逝きし者らがちやぶ台かこむ 第五歌集『冬の昼顔』六三頁
「心の遠景」十五首の一首。但し『α階のS』の「昭和エレジー」(一〇三頁)に、その原型とおぼしき〈土間があるちやぶ台があるうす暗いあかりのしたに黙々と食ふ〉がある。「ちゃぶ台」は「卓袱台」と書く。デジタル大辞泉には「和室で用いる、足の短い食卓」とある。「卓袱台返し」というのもあった。「(腹を立てた者が、食事の途中で)ちゃぶ台をひっくり返すこと」とある。「腹を立てた者」というが父親以外に誰がひっくり返すだろうか。ダイニングテーブルでは考えられない。ひっくり返す皿も少ない。卓袱台をかこむ家族の距離も近かった。掲出歌は、その家族に対する深い思いを、紫陽花の青の奥に描いてみせた。『昼のコノハズク』(四七頁)では、不滅の家族を、こうも詠う。
ちゃぶ台をかこむ一家がふと見えて時空ぶれゆく深夜の電車
|
港にも雨ふりをらむ山頂の展望喫茶で飲む白ワイン 第五歌集『冬の昼顔』八八頁
歌集の「あとがき」に「この歌集の、はじめには頸椎の手術があつた」「二年後に、今度は、前立腺癌ときた」。これは「三年間、治療を引き延ばした」が「二年前から勤め先で役職について、これまた精神衛生によくない」とある。さらに歌集の名前を『神戸』にしようかと思った話から「一月にバラが咲いたりして亜熱帯に近い感じの市街地と、北海道南部の気候というのが歌い文句の六甲山上との距離は、ケーブルカーでたった十分である。/精神衛生のためにと、ここ二年間はよく六甲山へ行った」と背景を語っている。
ケーブルカーで十分というのは、六甲ケーブル下駅から六甲山上駅までの時間である。約一・七キロメートル、高低差四九三・三メートルだそうだ。さて掲出歌であるが、四句の「展望喫茶」とはどこか。とりあえず六甲ガーデンパレスとしておこう。六甲有馬ロープウェーの山頂駅も近い。そして有馬温泉も神戸市北区有馬町、神戸市なのである。
|
桜さく谷間の空に祝日のロープウエイは満員である 第五歌集『冬の昼顔』一一一頁
どのロープウェイだろうか。まやビューラインと六甲有馬口ロープウェーの、どちらかであろう。表六甲線は休止後の歌と考えた。で過日、摩耶ケーブル駅と平行する上野道を登って摩耶山上・掬星台まで歩いたがロープウェーは見えなかった。今度は六甲摩耶スカイシャトルバスと六甲山上バスを乗り継いで六甲山頂駅へ行った。六甲有馬ロープウェーから有馬温泉駅へ向かう。往路には気づかなかったが復路、六甲山頂駅が近づいて下を見ると人が歩いている。あの人たちの目から見たら掲出歌になる、と勝手に解釈した。
谷あひの温泉町にバスが来て人を降ろした夕暮である(一一二頁)
同じ一連の歌。温泉街までは徒歩かタクシーだと聞かされて、復路に飛び乗った。
|
どしやぶりの日にひとり来て海の家で缶チユーハイを飲んでをつたよ 第五歌集『冬の昼顔』一二〇頁
「海の七月」六首の一首。場所は須磨海岸を想定して読んだ。〈私〉の居場所の一つだろう。なにしろ「どしやぶりの日」しかも「ひとり来て」、よく店も開いていたと思うが「海の家」で「缶チユーハイを飲んでをつたよ」なのだ。泳ぎに来たわけではない。
若者がおでんを運んできたりしが外くらきまで雨のはげしき(一二〇頁)
同じ一連の作である。おそらく同じ時の歌であろう。下句からして客は他にいない。何が〈私〉を駆り立てるのか。雨の日だけでない。〈海の家はたたまれて何もない浜に石ころひとつ拾ひあげたり〉(『α階のS』一〇一頁)と、いわば季節外れの海岸も出てくる。思索の散歩としては、こちらがふさわしかろう。やはり掲出歌の情熱は謎である。
|
木々すべて死に装束となりてをりケーブルカーの窓に雪ふる 第五歌集『冬の昼顔』一二九頁
歌集の「あとがき」に恰好の解説文があるので引用したい。すなわち六甲山は「観光シ
ーズンの晴れた日曜日などは、人やくるまが多くて、下界とあまりかわらず、登山をする
わけでもない私には、うれしくない。が、四季にかかわらず霧が吹く日がある。霧が濃い
日には、人のほとんどいない結界状態のようになる。また、冬は雪が積もって、行けばそ
こは異郷である」という。掲出歌のケーブルカーはその結界、異郷に向かうのである。
霧の奥にやうやく見えてケーブルカー ライト二つが這ひのぼりくる
天空の駅のごときに霧のなかケーブルカーは徐々に近づく
第七歌集『夢宿』(三四頁)と第八歌集『昼のコノハズク』(八六頁)から引いた。
|
風の日の実在ひとつウインドサーフイン沖にくつがへりをり 第五歌集『冬の昼顔』一四二頁
「神戸だより」四首の一首。神戸市でウインドサーフィンといえば須磨海岸だろう。下句は「沖に覆りをり」(沖で転覆している)、風のコントロールで明暗が分かれる。その風が強い日とあれば、考えられるケースだ。さて、どうするのか。身の危険と隣り合わせなのだ。見ている〈私〉は、それを初二句「風の日の実在ひとつ」と詠ったのである。
サーフィンのトンボの羽のような帆が海に散らばり真夏すぐそこ
第十一歌集『季節の手毬唄』(二四頁)に載る。初句「サーフィン」とあるが二三句でウインドサーフィンのことをいっているのが分かる。「帆が海に散らばり」で、こちらは海面を滑走しているのであろう。結句からも平穏な初夏の海が描かれている。
|
ほととぎす雨後をなきをり山道にしてわがからだ消えゆくやうな 第五歌集『冬の昼顔』一五一頁
「しののめ」十六首の一首。他の作品から六甲山の山道が念頭に浮かぶ。二句切れ。三句以下は「わがからだ消えゆくやうな山道(にして)」の倒置法であろう。消えてゆきそうなのは体だといっている。そして心だとはいっていない。心の方は、とっくに消えている。いや雨後のホトトギスの声に溶け込んでいるのである。そういうことだろう。
時空ずれるようなひととき公園のあちこちでないているホトトギス
『昼のコノハズク』(三一頁)に載る。初二句とりわけ「ずれる」だが、公園にいると〈私〉でない、ホトトギスの時間と空間に入り込んだような気分だ、というのだろう。掲出歌ならホトトギスあるいは山道という大自然の一部でしかないという感覚と解した。
|
青年の日をうとうととして思ふバスの窓にはただ雪の降る 第五歌集『冬の昼顔』一六二頁
「雪がふる」十四首の一首。十四首中十二首に「雪」、三首に「山」が登場する。「し
んしんと雪ふる山を越えてバス行く」(一六一頁)もあって掲出歌は六甲山を走っている
印象である。上句「うとうととして」、下句「ただ雪の降る」は、〈旅先のモカコーヒー
のにがくしてゆるり増えつつあらむか癌は〉という厳しい現実の歌も混じるが、こと「青
年の日」に関していえば、慰藉されている、その空間に身を委ねている感じなのだ。
暗かりしわが青春のかなたなるベトナムの炎ビートルズの曲
『さようならやま』(一三頁)に載る。ストレートな初二句である。ベトナム戦争とい
えばベ平連(小田実)が思われる。ビートルズの東京公演は一九六六年六月だった。
|
飛行船が浮かんでゐるよ麦秋の神話のやうな青空にして 第六歌集『海辺の街から』九頁
「よしなきことを」八首の一首。初二句は眼前の事実を詠っている。だが二句の最後にに添えられた「よ」の意味は小さくない。確認するような気分そして感動がこもる。巨大なガス袋に小さなゴンドラ、効率の悪さはそれだけではない。動きは鈍重で、天候にも左右されやすい。しかし歴史は飛行機よりも古い。「麦秋」は初夏の頃、人類の憧憬の向こうからやっきた飛行船にはふさわしい季節であり「神話のやうな青空」、好天なのだ。
いずこから来た飛行船 街空の奥にただよいいずこへ向かう
第八歌集『昼のコノハズク』(七〇頁)に載る。三四句からも飛行船の速度が推察できる。なお有人飛行船は、この歌の当時は一機のみで、飛行船広告をしていたらしい。
|
地下鉄にゐる顔顔顔のどこか違ふパラレルワールドあるいは名古屋 第六歌集『海辺の街から』一二頁
「日常の駅」十四首の一首。うち、この歌を含む四首が一つの固まりとして独立しているから名古屋編であろう。同じ地下鉄に乗っても、文化圏が違うと雰囲気も違う。いや、そのような気がするものである。それを「パラレルワールドあるいは名古屋」といった。この「パラレルワールド」が効いているが「イミダス 2018 」で引くと「【文学】空想科学小説で、現在の世界と次元が異なる世界があると仮定すること」とある。
プロムナードと言へど四十六階にひとり歩けば来世に似たる(一三頁)
ネットを検索していたらスカイプロムナードという施設が出てきた。地上二二〇メートルの散歩道、名古屋の街を三六〇展望できるとあれば必ずしも大仰でもない、か。
|
英語にてアナウンス聞く京都駅うちらあほらしおすとは言はず 第六歌集『海辺の街から』一六頁
「日常の駅」十四首の一首。うち、この歌を含む四首が独立している。京都編として読んだ。〈私〉は京都駅構内でアナウンスを耳にしている。英語である。訳すと「うちらあほらしおす」とはいっていない、というのである。だれにでもわかっていることだ。しかし、こうして下句に収まると、上句と同様に存在を主張し始める。その「うちらあほらしおす」から、どのような人物を想像するだろうか。私には祇園の芸子さん、舞子さんと重なって、観光都市・京都の一大ターミナル駅が立ち上がってくるのである。
バスの中やはらかさうな物言ひで男の評価するむすめたち(一六頁)
「やはらかさうな物言ひ」だが「評価」には遠慮がない、手厳しいというのだ。
|
ノックする音を聞きしは夢の中はつと目覚めてのちは眠れぬ 第六歌集『海辺の街から』二〇頁
「入院前」五首の一首。次の一連が「わが癌病棟」を考えると神経が昂ぶっているのかも知れない。さらにその次の「退院して」には〈あの世から追ひ返されてきた我か耳鳴りをきく夜のわが部屋〉(二三頁)があるから「あの世から」のノックだったのかも知れない。しかしネットを散策していたら「ホーンティング」の記述がある。明治大学情報コミュニケーション学部教授石川幹人氏によると「ホーンティングとは、ある特定の場所において生じる特異現象であり、『幽霊が憑依した家』などという形で現われ、散発的に長い時間に渡って現象が起きる。例えば、幽霊の姿や火の玉が見えたり、何者かの存在感があったり、ノック音や足音が聞こえたり、ドアや窓が開閉したり、温度の急激な変化があったりする」(メタ超心理学研究室)というのだ。掲出歌は「夢」と断っているが、他の歌群の解釈を含めて「何者かの存在感」「ノック音」は一つのキーになると思われる。
|
誰かいまおじぎして過ぐ昼間から焼酎飲んで寺町行けば 第六歌集『海辺の街から』七〇頁
お辞儀をしたのは教え子だろう。場所は兵庫県尼崎市、阪神の尼崎駅の周辺で飲んで寺町を歩いていたと読んだ。尼崎なら〈私〉のテリトリーであるし、学生、また卒業生も多いことだろう。同じ歌集に〈寺町で弘法大師といふ焼酎飲みをり窓なき蕎麦屋にひとり〉(九八頁)がある。寺町に蕎麦屋があるのか。それとも寺町は寺町周辺の意味か。ともあれ焼酎の名前がよかった。〈何に暗き命ぞまたも寺町の夜を逃げいし夢さめて闇〉(『タタの星祭』八一頁、『みずいろ迷宮』三四頁)。これは奈良の寺町であろう。四句までが、夢だから当然といえば当然だが、状況が分からない。『冬の昼顔』の〈夢暗く駅は寺町 終電で降りてしまうてタクシーもない〉(五六頁)はどうか。寺町という駅があるのは広島である。焼酎の弘法大師を作っている賀茂鶴の本社があるのも広島である。四首の寺町の歌では、酒気帯びでひょうひょうと歩く掲出歌の「先生」の姿が微笑ましい。
|
客すくなきシアターなれど指定席 ポップコーンのかすかに湿る 第六歌集『海辺の街から』七五頁
「秋」十三首の一首。また〈映画館でポテトチップスを食べながら見てゐたあの日 客は僕だけ〉(九八頁)もある。ポップコーンにポテトチップスと常連客である。しかも第三歌集『さようならやま』(七六頁)には〈秋の地下のミニシアターに外国の昔の美女らいさかふ寒さ〉もあって年季が入っている。四句は老優で「昔は美女」の意だろう。
ベイルマンの映画だったか雨上がりの路地裏が見えただけの一コマ
第十二歌集『カシオペア便り』(一二頁)に載る。初句「ベイルマン」はスウェーデンの映画監督(表記はベルイマンが一般的)である。結句は、前後を忘れて印象に残っている一コマという意味だろう。「雨上がり」も「路地裏」も小谷短歌に似つかわしい。
|
さらはれし女(め)わらべたちがさやさやと笑ふ声して夜の谷川 第六歌集『海辺の街から』八一頁
日本大百科全書で「人さらい」を引くと妖怪、妖魔だが「薄暮に跳梁(ちょうりょう)すると信じられてきた俗信の所産で、『神隠し』の伝承とも相通ずるところであろう」云々とある。三四句は妖怪の声とも、また実際にも「女(め)わらべ」の声とも、あるいは単に川の音のようにも聞こえる。川原にいるとおぼしき人物を含めて不気味な空間である。
夕暮れがきたりて寒し地下都市へ今日も人らがさらはれてゆく
するすると火の見櫓へ縄梯子おりてきて子どもがまたさらわれた
一首目は第五歌集『冬の昼顔』(一三頁)の歌、二首目は第八歌集『昼のコノハズク』(一四五頁)の歌、片や未来、片や過去と異なるが「人さらい」への関心は深い。
|
ああ今日も首なし地蔵が立つてゐる鉄路のしたの暗きトンネル 第六歌集『海辺の街から』一〇三頁
「月日」九首の一首。四句「鉄路」は高架になっている。二句「首なし」の事情は不明、遠くなら廃仏毀釈、近くなら高架化の際の保管の不手際も考えられる。小松和彦は『妖怪文化入門』(角川ソフィア文庫)の中で「地蔵菩薩という仏が辻や峠に立つことになったのには、地獄に堕ちた人びとを救い出して極楽浄土に導くという思想の浸透した結果であるが、さらに地蔵がこうした境界性を帯びた仏であるということをふまえて、地蔵が立っているところはどこでも、あの世とこの世の境界と見なされるようにもなったのである」と述べている。次の歌は第九歌集『うたがたり』(一〇二頁)に載るが、掲出歌の首なし地蔵の立つトンネルであっても少しもおかしくない。光と影が交錯しているのだ。
自転車の後ろに子どもを乗せた影 高架下の壁をすべりつつ行く
|
うつすらと霧の向うに見えてをりふもとの街が異界のやうに 第七歌集『夢宿』三三頁
「山の上」八首の一首。眺望だけなら摩耶ロープウェーの星の駅に隣接する展望広場「掬星台」であるが、一連からは六甲ケーブルの六甲山上駅から東、六甲ガーデンテラスの間のどこかという感じてある。生活のある麓、神戸の街に霧がかかっているのが異界のようだという。距離は近いが標高差のある六甲山独特の景観が織りなす感慨であろうか。
ツツ鳥がなく中をゆくケーブルカーあの世の景色が見えてきたりして
第五歌集『冬の昼顔』(一一六頁)の「窓の新緑」十六首の一首。筒鳥は夏鳥として飛来し、山地に棲息する。ポポ、ポポと鳴くとある。その中をケーブルカーは六甲山上駅に向かっている。下句「あの世の景色が見えてきたりして」、変化が激しいのである。
|
小春日のとろとろねむき駅に聞く人身事故といふアナウンス 第七歌集『夢宿』四一頁
「小春日」六首の一首。初句「小春日」は、十一月から十二月上旬の頃の、暖かく穏やかな日をいう。〈私〉は電車を待っている。遅い。なかなか来ないと思っているプラットホームに「人身事故といふアナウンス」が流れているのだろう。人身事故といっても、ホームからの転落、線路内への立ち入り、ほかいろいろ考えられるが、掲出歌の人身事故は自殺と読んだ。二句「とろとろねむき」とあるが、乗客の同情を買わない事故である。
待ち合わせの人らに多き少女たち薄化粧して夕暮れの駅
『うたがたり』(二一頁)の「北の旅」十首の一首である。平和で長閑な駅風景が魅力だが、線路に飛び込んだのは、もしかすると彼女らと同世代かも知れないのである。
|
鼻も口もべつたり乳がふたぎゐてもがいてをつたけつたいな夢 第七歌集『夢宿』五七頁
「フラッシュバック」九首の一首。フラッシュバックをデジタル大辞泉で引くと、まず「映画・テレビで、瞬間的な画面転換を繰り返す手法」がある。九首の作品相互の関係に当てはまるだろう。ただ掲出歌に関していえば次の「過去の出来事がはっきりと思い出されること。逆行再現」だろう。なおフラッシュバックはタイトルにしか登場しない。
夢を見ているのは立派な大人である。大人であるはずだ。その〈私〉が、なぜ赤ん坊よろしく乳房に覆われているのか。大きな乳房に鼻も口も塞がれて、あがいているのか。方言によって作品が生き生きとしている。とりわけ結句の「けつたいな」は絶妙である。
歌集名『夢宿』は〈遠き日の夢にてあれど線路わきの安アパートに女と暮らす〉(六四頁)ほか一首からきている。造語だろうが、夢を宿とする人、夢が宿る人の物語だろう。掲出歌もまた、乳房の主の顔も見られないという変則な夢宿の〈私〉を詠っている。
|
連れてきた子を屋根裏で遊ばせてをつたら警官が踏みこみよつた 第七歌集『夢宿』五八頁
「フラッシュバック」九首の一首。先の「鼻も口も」の次に並ぶ。人さらいの歌があった。神隠しの歌も出てくる。そしてここに現代の誘拐犯を登場させる。とことん追求せざるを得ないのだろう。小松和彦の『神隠しと日本人』(角川ソフィア文庫)に「高度成長期以降、『神隠し』の話は日本人の間から急速に姿を消していくことになる。人びとが神を信じなくなり、また異界を信じなくなったからである」とある。人さらいも同様だろう。妖怪の事典では「隠れ婆(ばばあ)」「隠し神」「隠れ座頭」などの項目で説明される。掲出歌だが、初句に「誘拐した」とはいっていない。二句「屋根裏部屋」は怪しいが、三四句「遊ばせてをつた」から身代金の要求はしていないと思われる。危害も加えていない。いわば単純な連れ去りで、犯人の実況中継のとおり、無事に解決もしている。だから読める。なお先に方言と書いたが播州弁(ウィキペディアの「小谷博泰」)か?作品の魅力である。
|
二年間教へただけの生徒らの壮年となりゆく同窓会 第七歌集『夢宿』五九頁
二〇一二年の作である。作者は一九四四年生まれだから、このとき六十八歳であろうか。職歴をたどると奈良教育大学教育学部講師・助教授を経て甲南大学教授となる。ただ『冬の昼顔』の「あとがき」に「姫路や奈良に勤めを持ったことがあり」ともある。
休学せる生徒を見舞いに行くことの間遠になりて学年かわる
『たましいの秋』の「夜学」七首の一首(七三頁)で、「姫路」とあるのは、これだろうか。生徒が「壮年」には該当する。また大学生を「生徒」と呼ばないだろう。決めがたいが、教員生活を通じた教え子は多い。〈誰かいまおじぎして過ぐ昼間から焼酎飲んで寺町行けば〉(『海辺の街から』七〇頁)。ちなみに現在は甲南大学名誉教授である。
|
猫は屋根の上を跳ねつつ半月の半円くぐり向うへ消えた 第七歌集『夢宿』七九頁
「村」六首の一首である。初二句「猫は屋根の上を跳ねつつ」は三句以下への布石であろう。問題は、その次である。「半月の半円」すなわち弦月は見る時間によって少し傾いている。「くぐり」だから下弦の月の弦の下その闇を潜ったのだろう。だから結句「向こうへ消えた」、「向こう」とは「月の向こう」にほかならい。大ジャンプの趣である。
黒猫がくはへてきたもの蜥蜴、鳩、土竜(もぐら)、死んでゐる黒猫自身(一一二頁)
同じ歌集の「さかな」九首の一首である。一連には〈黒猫と子どものわれが暮らす小屋ねるまへ蠟燭の明かりを消して〉という作品もある。猫の習性から「蜥蜴、鳩、土竜(もぐら)」はあるだろうが、さすがに下句「死んでゐる黒猫自身」になると頭が混乱してくる。
|
大画面のテレビにハイレグの美女がゐて体操してゐるよき朝である 第七歌集『夢宿』一〇六頁
NHKのテレビ体操であろう。今なら午前六時二十五分から六時三十五分である。注目したいのは〈私〉が体操をしているわけではないことだ。大画面に映し出されるハイレグの美女たち、アシスタントと呼ぶらしいが、その体操をしているところを眺めているのである。ちょっと意味合いが違ってくるが、それを結句「よき朝である」といっている。
ゆかの下にこほろぎのなく朝あけの寝覚めてもなほただよふごとき
よき夢はつねに遠くへころがりて目覚めればくもの巣が張つてゐる
ただ「よき朝」でもあることは他の朝の歌を見ればわかる。一首目の第四歌集『α階のS』一〇八頁、二首目の第五歌集『冬の昼顔』七二頁の、いずれも体調不良である。
|
枝先に垂れたザクロの実がわれを見下ろしてにやりと笑ふ細道 第七歌集『夢宿』一一一頁
「さかな」九首の一首。ザクロは子供の頃に食べたことがある。自生だった。いま食べたらわからないが、スーパーに並ばない点でも、アケビとともに懐かしい果物である。ところが掲出歌の印象は違う。三句の「われを」は「我を」に「割れ(を)」だろう。そのザクロが「見下ろしてにやりと笑」っている「細道」なのだ。いくら「通りゃんせ」(通りなさい)といわれても、とてもではないが「行きはよいよい」とはいかない。
柘榴の樹に黒きざくろの実が垂れて割れおる無惨すでに三月
『河口域の精霊たち』(三九頁)に載る。〈柘榴(ざくろ)の木に黒ずんだ実の裂けており冬枯れ急ぐ公園の隅〉(同一四頁)もあった。掲出歌の柘榴も同じ公園のものかも知れない。
|
井戸の水がときどき枯れてざわめきが奥の方から聞こえたりする 第七歌集『夢宿』一一三頁
「さかな」九首の一首。とある民家の庭先にある井戸を想定した。地下数メートルぐらいの浅井戸である。日照りが続いたりして地下の水位が低下して枯れたのだろう。三句以降は雨が降るなどして地下の水位がもどってきた、その兆候と思われる。但し、それが「ざわめきが」以下を十分に説明しているとも思えない。枯れたから、枯れると「奥の方から~」と読むこともできるからだ。それは得体の知れない不安ないしは恐怖でしかない。
つぶれたる家に三本の井戸ありて一本はなお現世へ続く
『昼のコノハズク』(一四一頁)に載る。廃屋に三本の井戸、一本が現世なら、残るは前世と来世となる。井戸が入り口であり出口だ。さて、この廃屋はどこにあるのだ。
|
今日は田螺が沼でいい声で鳴いてゐる星も見えない闇夜となつて 第七歌集『夢宿』一一三頁
「さかな」九首の一首。春の季語に「田螺鳴く」がある。もちろん鳴くはずもないが、歳時記を開くと河東碧梧桐の〈田螺鳴く二条御門の裏手かな〉が載っていたりする。掲出歌は「いい声」で、しかも「闇夜」に鳴かせている。先行する田螺の歌を二首引く。
とほき世のかりようびんがのわたくし児田螺はぬるきみづ恋ひにけり
今生(こんじょう)の某(それがし)もとは田螺にて水田の畦をいま照らす月
一首目は斎藤茂吉の『赤光』に載る。迦陵頻伽は極楽浄土にいるという想像上の鳥である。田螺は、その迦陵頻伽の私生児だといっている。二首目は岡部桂一郎の『一点鐘』に載る。作中の「私」は田螺の生まれ変わりという。まとめて田螺の三歌人と呼ぼう。
|
年月ははやく流れて樺太犬タロも剥製になつてしまうた 第七歌集『夢宿』一二五頁
「北国のカフェ」十一首の一首。世界大百科事典で「樺太犬(からふといぬ)」を引くと「原産地が樺太(サハリン)の橇(そり)犬。(略)。酷寒地の重労働に耐え,筋骨たくましく」「また58年第3次南極観測隊によって連れ帰られた〈タロ〉〈ジロ〉の話は有名である」。その「タロ」「ジロ」もデジタル大辞泉プラスに載る。「タロ」は「一九五六年、南極地域観測隊、第一次越冬隊とともに南極に同行した樺太犬のオス。第二次越冬隊が越冬できずに帰国したため、合わせて一五頭の犬だけが昭和基地に取り残された。一年後に兄弟の『ジロ』とともに生存が確認、日本中で話題となった。その後一九六一年に帰国。一九七〇年死亡」とある。一九五一年生まれの私もかすかに覚えている。一九四四年生まれの作者にすれば、はっきりと覚えているだろう。それが初二句の表現となっていると思われる。なおタロの剥製は北海道大学植物園、ジロの剥製は上野の国立科学博物館で展示されている。
|
先斗(ぽんと)町のあたりうろつき結局はチェーン店にて食べるラーメン 第七歌集『夢宿』一三五頁
四条大橋のたもとに中京警察署の四条交番がある。東側に四条大橋、鴨川が流れている。土手にはアベックが等間隔に坐っている。背後に納涼床が北へ続く。影はうすいが下を、みそそぎ川が流れている。その四条交番の西側に「先斗町通り」の立て札が立つ。「先斗町通は三条通南から四条通間に約五〇〇m続く京都において文化・遊興の中心地として発展し、品格と賑わいを合わせ持つ通りである」云々、道幅は二メートルぐらいである。江戸時代から続く花街の一つである。一見さん、お断りの看板はない。金額も、さほど高いものでもない。と思いつつ先斗町歌舞練場まで来てしまったので、西側の木屋町通りを南へ歩く。高瀬川が流れ、角倉了以翁顕彰碑が立つ。やがて賑やかな四条通に出た。掲出歌であるが「チェーン店」と「先斗(ぽんと)町」、入りやすさという点では比較にならないだろう。ちなみに、この日の私が遅い昼食を取ったのは阪急電車の十三駅の構内であった。
|
どしやぶりの舗道にやせた迷ひ犬あいまいに尾を振りたり 寒し 第七歌集『夢宿』一四〇頁
三句は首輪からの判断であろう。野良犬はいない。仮にいたとしても、このようなときの居場所を知っている。ところが屋根のない舗道である。しかも迷ったのは昨日や今日のことではない。二句「やせた」状態は、自力でエサを求める手段を知らないからだ。かくて哀れな犬は、目の合った〈私〉に尾を振る。結句「寒し」は気持ちの問題である。
移り住み十年かりそめならざると連れてきたりし犬をはうむる(一五八頁)
夜明け前の暗闇の中でさっきから布団のチワワが寝ごと言うとる(二二頁)
一首目は『さようならやま』、二首目は『昼のコノハズク』に載る。無能な犬であるが、飼われる側として人を見る目はある。だから尾を振った。それが「寒し」なのだ。
|
雨はげしき夜明けまへなり病棟の一部屋のみが灯りてゐたる 第七歌集『夢宿』一四〇頁
「つはぶき」十三首の一首。二句「夜明けまへなり」ということだから自室というのが常識的な見方だろう。そうではないという情報をもたらす作品も一連にはない。そこから三句の「病棟」が見えるのである。そして結句「一部屋のみが灯りてゐたる」という。ただごとでない患者の部屋なのだろう。初句「雨はげしき」と天候も急を告げている。
あの部屋で死ぬのもよしと病院の窓のあかりを見てゐる夜だ
第五歌集『冬の昼顔』(四五頁)に載る。「街並み」九首の一首である。順序としては、こちらが先にあるわけだが、掲出歌と同じ病院として読んだ。初句「あの部屋」とあるから、そこだけが灯っているのであろう。消灯後である。重篤の患者が思われる。
|
太鼓橋を渡るとき景色がかわりたり向うから来る少年のわれ 第八歌集『昼のコノハズク』一三頁
ドッペルゲンガーを思った。大辞林は「自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種。自己像幻視」と説明している。歴史的人物についても報告されているし、文学では、たとえば日本なら芥川龍之介の「二つの手紙」がある。掲出歌も、この範疇で理解しようと試みたが、如何せん、年齢が異なるなど、作中人物は必ずしも既成語の中では動いてくれない。
着ぶくれた少女ら自転車で去つてのち杖ついて来るあしたの私
池のむこうに立っているのは百年後の時間からきた僕かもしれぬ
一首目は『海辺の街から』(四八頁)、二首目は『河口域の精霊たち』(一三六頁)に載る。少年であったり、少し未来の老人であったり、百年後の〈私〉だったりもする。
|
神隠しにあった子どもが灯しゆく明神様へつづく燈籠 第八歌集『昼のコノハズク』一八頁
「木隠れ村」六首の一首。小松和彦は『神隠しと日本人』(角川ソフィア文庫)で神隠し事件を四つのタイプに分けている。無事に発見されて失踪中の記憶があるタイプ、無事に発見されたが記憶にないタイプ、行方不明のままのタイプ、死体で発見されるタイプである。三句の「子ども」は現在行方不明である。それをナレーターとして語っている〈私〉の存在、「子ども」の落ち着いた様子などが印象に残る。あるいは明神様が隠し神か。
つむじ風に枯れすすきひくく揺れており木隠れ村が消えて久しい(二〇頁)
「木隠れ村」は辞書で調べても出てこない。作者の造語だろう。仙境、理想郷、人外境をいう隠れ里の一種を想像した。但し、「木隠れ村」は「子隠れ村」でもあったろう。
|
タクシーをとめて坐れば飛ぶように夜の奥へと連れられてゆく 第八歌集『昼のコノハズク』五〇頁
「夏の終りに」八首の一首。手をあげてタクシーをとめたのは〈私〉である。乗り込んで行き先を告げたのも〈私〉である。運転手の反応はどうだったか。三句まではいいだろう。しかし四句あたりから怪しくなってくる。結句になると完全に主客逆転の趣である。乗るまでは客である〈私〉、乗ってからは運転手の手に委ねられていることを思えばそうなのだが、それでも「夜の奥へと」「連れられてゆく」。いったい、どこへなのか。
タクシーに乗りて夜深くもどりしがすべておぼろの酒宴の終り
第五歌集『冬の昼顔』(一八頁)に載る。先の答の一つが、これである。連れられてきたのは呪われた家でも何でもない。取って食われる心配もない〈私〉の城だった。
|
地酒飲んでたこ焼き食べて昼まえの港で過ごす一人の時間 第八歌集『昼のコノハズク』五九頁
「三都好日」の一首。居場所の一つとしての神戸を想定して読んだ。「地酒」を日本大百科全書で引くと「地方で醸造される酒。清酒の主産地で、ナショナルブランドの多い灘(なだ)(神戸市)や伏見(ふしみ)(京都市)の酒に対し、それ以外の地方でつくられる清酒」云々とあって困るが、灘五郷以外の酒として読んでおく。自足の時間である。
コップ酒を飲みつつひとり蛸食えばわびしい昼の港が見える(五〇頁)
雨の降る島のさびれた食堂でたこ焼きを食ふ焼酎を飲む(『夢宿』六二頁)
一首目は「夏の終りに」八首の一首(神戸か)。二首目は「島」五首の一首(場所不明)。掲出歌と同じ自足感に加えて背景の漁港、昼酒かつ肴のB級なところに惹かれた。
|
ああいやな夢を見たなと目覚めたがそこはまた次の夢の中にて 第八歌集『昼のコノハズク』六三頁
嫌な夢から醒めてよかった。しかしそう思うのも夢の中だった、という作品である。だれしも似たような経験をするものだ。ただ普通人との違いといえば変だが、作者の場合は夢の占める意味が違っている。夢は異界てあり、その異界を放浪するのが日常なのだ。
夢さめてまた別の夢にいるかとも思いつつ昼のひげをそりおる
夢のなかで夢を見るといふ夢をまた見てゐたといふやうな夢
一首目は私家版歌集『タタの星祭』七八頁(第二歌集『みずいろ迷宮』二三頁)の歌、初二句は掲出歌と同じ構造である。二首目は第六歌集『海辺の街から』(一〇九頁)の歌、「夢」が四度出てきて構造はさらに複雑というべきか、面目躍如とした趣である。
|
あちこちに桜が咲いて新幹線の窓から見える平和いつまで 第八歌集『昼のコノハズク』七六頁
「曳き舟」六首の一首。他の五首との関連でいえば、いきなり「桜」がきて、いきなり「新幹線」がきて、いきなり「平和」がきたような一首である。しかし歌集を超えて小谷短歌を眺めるとき、必ずしもそうではない。結句の思いは様々な場面で登場する。
顔よきもむくろとなりて積まれをり帝都空襲の写真一枚(六四頁)
夜空ひくく過ぎゆきし音そのあとは四方八方火の手があがり(六四頁)
走りゐてたふれしならむ黒こげの子どもの死体 戦争の朝(六四頁)
第五歌集『冬の昼顔』中「戦争の朝」三首も、そうだ。昭和二十年三月十日未明の東京大空襲であろう。二時間半の爆撃によって廃墟と化した下町一帯の写真に拠った。
|
ヘリポート付きの高層ビルの群れが窓に見えすでに未来ではない 第八歌集『昼のコノハズク』八六頁
「ビワと鴉」九首の一首。ヘリポート付きの高層ビルが建つようになったのは、火災のときに梯子車が届かないなどの、災害時の想定によるらしい。しかし実際に使われた例は寡聞にして知らない。四句「窓に見え」は何処といってないが、東京スカイツリーや東京タワー、あべのハルカスもその一つだろう。たしかに四五句「すでに未来ではない」。
病院にヘリコプターが降りてゆくいつか日常となりし風景(九三頁)
同じ『昼のコノハズク』の「季節の中で」十二首の一首である。掲出歌と違ってドクターヘリの活躍はニュース、ドキュメンタリー、テレビドラマでもよく目にするところである。ネットで見ていたら神戸赤十字病院にも屋上ヘリポートの写真が写っている。
|
口を開け眠る乙女のもも白し夏の終りの湖畔の電車 第八歌集『昼のコノハズク』一一八頁
「出雲路」八首の一首。乙女とは何歳ぐらいをいうのだろう。デジタル大辞泉に「年の若い女。また、未婚の女性」とある。掲出歌は、口を開け、連鎖的に両足も緩んだ女性、私は十代を想像した。湖は宍道湖だろう。「もも白し」が三句で陣取っているのもよい。運動部で日に焼けた学生でも「もも」は「白し」なのだ。晩夏を詠って絶品である。
二、三センチずり上がりゐしミニスカのよかりしやあの白きふともも
ふとももの白き少女が過ぎてゆく夏の幻影ならぬ街かど
一首目は第五歌集『冬の昼顔』(一二二頁)、四句の「や」は間投助詞の詠嘆と解釈した。二首目は第七歌集『夢宿』(一九頁)で、下句とりわけ「幻影」が生きている。
|
おさなごは地震以前の家に居てときにこの世の夢にあらわれ 第八歌集『昼のコノハズク』一五四頁
「神戸その後」三首の一首である。座敷わらしを連想したが、座敷わらしには家がある。また人前に現れる(という)。掲出歌の「おさなご」に家はない。また人前にも現れない。遺族の思い出の中で生きている。その「おさなご」に地震で潰れる以前の家そして人前に現れるための夢という二つの居場所を提供したのは、この歌の功徳にほかならない。
黙々と人ら来る道かはら散り電線は垂れガス漏れてゐる(一二七頁)
またここもくづれし家がふさぎをりサイレンの音まちを過ぎ行く(一二八頁)
『さようならやま』の「地震ののち」から引く。生々しい。平成七(一九九五)年の阪神・淡路大震災の死者六四三四人、掲出歌の「おさなご」も、その一人である。
|
ふと違う世界が見えた戻るとき車両のドアを一つ間違え 第八歌集『昼のコノハズク』一五六頁
「四万十川まで」十一首の一首。一連からは土佐くろしお鉄道の中村駅が想像される。他の歌に登場する「入り江」「汽水」とも合致するからだ。停車している特急であろう。下句によって上句すなわちパラレルワールド(「空想科学小説で,現在の世界と次元が異なる世界があると仮定すること」イミダス 2018)を連想したのだろう。ただ四万十川でなければならない理由はない。新幹線や他の路線の特急でも味わえる世界である。
それぞれの人生ありて通勤の電車の客らおし黙りいる(一〇七頁)
同歌集の歌。掲出歌の世界は通勤電車においても起こりえるだろう。パラレルワールドに迷い込んだ乗客とは別に、迷い込まれた側の乗客を思えば、こうなるに違いない。
|
どなる声を聞きつつそっと受話器おく無言電話の犯人わたし 第九歌集『うたがたり』四八頁
「オフタイム」十首の一首。この作品の前後に〈ずたずたに傷つきそうでさようならしてからなおさらずたずたの日々〉〈親からの着信音あり何もかも捨てようスマホのリセットをして〉がある。展開としては、よく分からない部分もあるが、「ずたずたの日々」「何もかも捨てよう」の間に潜り込んだのが「無言電話」への誘惑であったかも知れない。
いづこかであざわらひをりゆふぐれにまたかかりくる無言の電話
ところで様々な〈私〉を登場させている作者を考えるとき、右の第四歌集『α階のS』(二〇二頁)で無言電話を取る〈私〉を描いてから、この『うたがたり』において無言電話を掛ける〈私〉を描くまての歳月というか、広がりにも興味を惹かれるのである。
|
せみがチッとおしっこをしてとんでった母さんどこかへ行ってしまった 第九歌集『うたがたり』五〇頁
「くまの子たろう」十首の一首。絵本に『クマの子 太郎』がある。母熊を殺された子熊の物語であるが、この一点のみ共有する連作である。「おしっこ」をかけられる「たろう」の可愛らしさは人間の子供を連想させるが、自然の中、一頭でたくましく成長していく。しかも詠い手は「たろう」である。誰もが肩入れせずにはおれない魅力がある。
山の上のお花畑をころがってくだればはるかにけむりがのぼる(五一頁)
子をつれて母さんぎつねがとおる道むこうに麦の畑かがやく(五二頁)
絵本と違って人間は登場しない。魚の群れを追いかけても収穫は一匹だけ、そんな「たろう」も、ここより遠くへ行こうと考える。「母さん」が呼んだ気がしたからである。
|
知恵の輪が不意にはずれるようにしてドアから向うの世界へ落ちた 第九歌集『うたがたり』五三頁
「廃墟」十首の一首。知恵の輪は子供の頃に遊んだ記憶がある。難易度は低いものだったろうが、外れるときは、いつも「不意に」だった。しかし三句「ようにして」以下は、斬新だがギブアップである。仕方ないので落ちた「向うの世界」を想像してみた。
地球といふ異界への戸をあけにしが一億年がたつてしまうた
丑三つとなりて人々うごきだす洛中洛外の絵の昼の町
一首目は『海辺の街から』(七二頁)に載る。〈私〉は今ではエイリアンであるらしい。すでに人類の滅んだ地球と思われる。二首目は『うたがたり』(一二六頁)に載る。丑三つの洛中洛外図の前、さらに飛び越えて洛中洛外図の絵の中であるかも知れない。
|
若き日の妻のからだを思い出すわれに彼岸が近づいたのか 第九歌集『うたがたり』六〇頁
「季節」十一首の一首。上句とりわけ「若き日の妻のからだ」としかいっていないが、読者には「美しい」「みずみずしい」といった形容が湧いてくる。相手が「若き日の」夫すなわち〈私〉なら、印象は、それほどでもなかっただろう。お迎えも遠くないと思っている年齢の〈私〉だからこその賛嘆といってもよい。つまり、そこには〈私〉の失った歳月が横たわっているのである。そして賛嘆は現在の〈私〉に対する嗟嘆でもある。
まだ若い妻が呼んだのは夢のなか起きればとなりに老いて妻寝る
『季節の手毬唄』(五八頁)に載る。「思い出す」のではなく、〈私〉を呼んだのだ。あの素晴らしい日々、あの輝かしい日々が、と思ったのも束の間の夢の中なのだ。
|
壁に掛かる古き絵の中の家にしてときどき人のいる気配する 第九歌集『うたがたり』七〇頁
「青い蝶」七首の一首。絵が掛かっているのは〈私〉の家、美術館、公共施設、ほかにも考えられるが下句「ときどき人のいる気配する」といっている。これは眺める機会が多くなければいえないことである。窓の灯りがついたり、消えたりするのであれば話も早いが、あくまでも気配というのが難しい。画家の呪いがこもった一枚でもあろうか。
壁の絵の窓からわれを少女見る 実在するのは我か少女か
第七歌集『夢宿』(一三二頁)に「美術館」五首の一首で載る。描かれた少女は窓から〈私〉を見ている。〈私〉は美術館で絵を鑑賞している。下句の答えは明白である。ただ四句で「実在」という言葉を使っているのがミソであろう。掲出歌との違いである。
|
縄とびの波のしだいに速くなりころがって出たわれは白髪 第九歌集『うたがたり』八五頁
「私が住んだいくつかの町」十六首の最後に置かれた一首である。『海辺の街から』の「短歌関係略歴」を見ると一九四四年「神戸市兵庫区に生れる。以降、四〇歳代ころに奈良市に住んだ十年ほどを除いて、兵庫区、長田区、須磨区、兵庫区、垂水区、須磨区、灘区と転々としながらも、神戸市に住んでいる」とある。一連には、こんな歌がある。
濁りいる運河の船から高校へ通うか制服の少女出で立つ(八二頁)
突き当りのうどん屋がまだやっている暮らした町の商店街で(八四頁)
こうした作品を背景にすると、掲出歌の上句は時間の比喩となり、下句は現在の〈私〉となろう。もちろん単独作品として読むときの映像も、また見逃せない魅力である。
|
街かどにあれども気づくことはなし異界につなぐ電話ボックス 第九歌集『うたがたり』一〇四頁
「電話ボックス」十二首の一首。〈あの世での四十余年は夢のような幸せでしたとあの人の言う〉という歌から始まるが、「あの人」とは誰か。氏名不詳だから「あの人」か、それとも夢の中の登場人物か。また〈生きゆくは修羅にて長しひとり来て子どものころの海を見ている〉という歌もある。電話ボックスとは「あの人」と「あの世」をつなぎ、また〈私〉と「子どものころ」の〈私〉をつなぐもの、だから「気づく」人もいない。
他界より声をつたえて地下道の闇にひとつの無届け電話
『タタの星祭』の三三頁、『みずいろ迷宮』なら四六頁に載る。両歌集とも一連の中では単独感の強い歌であるが、長い歳月を経てタイトルへと昇華、熟したのであろう。
|
なんとなく自分が自分でないここち見た夢忘れてしまった朝の 第九歌集『うたがたり』一〇五頁
「電話ボックス」十二首の一首。「見た夢忘れてしまった朝」は「なんとなく自分が自分でないここち」がするという。逆にいえば、見た夢を覚えている朝は、自分が自分である、というのだ。そしてその夢が登場する歌は実に多い。作者は夢の歌人なのだ。
見し夢をまた忘れたりコスモスの花も終りの寒き雨ふる
第二歌集の『みずいろ迷宮』(一七一頁)に載る。二句「また」とある。大概の人が「また」で、気にしない。しかし、作者は違う。結句「寒き雨ふる」は心象風景でもあろう。そして、営為、夢の歌を歌い続けて「また」の数は劇的に減っていったのだろう。夢の歌人は、夢という他界を歌う歌人なのだ。この点でも記憶されて然るべきであろう。
|
まりをついている童女ありこの道を行けばあの世と教えてくれた 第九歌集『うたがたり』一〇八頁
「森の植樹祭」七首の一首。初二句の鞠をつく童女は、この世の者なのか、あの世の者なのか。小松和彦は『妖怪文化入門』(角川ソフィア文庫)の中の「境界」論で「『生』と『死』の境界が、もっとも人間にとって根源的で普遍的な境界であるということがわかるはずである。当然のことながら、そうした『境界』は『怪異』の発生しやすい領域であった」と述べている。歩き始めて、振り向くと、童女の姿はないのかも知れない。
紫陽花が色づきはじめぽつぽつとあの世への道てらしてゐるよ
第五歌集『冬の昼顔』(一二一頁)の「霧吹く日に」六首の一首。六甲山で取材した歌と思われるが、この山も、霧が濃くなれば結界、異郷、異界の表情を見せるのである。
|
女子プロの美人レスラー血まみれとなって客席静まりかえる 第九歌集『うたがたり』一一四頁
「プロレス伝説」六首の一首。連作である。美人レスラーのモデルは安川惡斗であろう。対して〈血まみれの顔をつかんで拳(こぶし)にて殴りに殴る女レスラー〉は世Ⅳ虎である。〈あとは引退試合が待つというけれど視力失った美人レスラー〉〈八百長ではなかっただろうリングから救急車へと運ばれて行き〉と続く。その後だが安川惡斗は女優・安川結花として、世Ⅳ虎は世志琥でプロレスラーとして、ウィキペディアが、その活躍を伝えている。
白人を空手チョップで傷(いた)めつけわきにわかせたモノクロ時代(一一五頁)
プロレスと聞いて、作者の帰っていくのは力道山であろう。街頭テレビの時代だった。〈力道山刺されて死んでしまったと昭和レトロな暗い伝説〉、一九六三年である。
|
爺さんと婆さんが湯に浸かっていた山のかなたは今ダムの底 第九歌集『うたがたり』一三三頁
「山の彼方に」十三首の一首。石坂洋次郎に『山のかなたに』があるが、私が思い出すのはカアル・ブッセの「山のあなたに」(上田敏訳『海潮音』)であり、三遊亭歌奴の「授業中」である。「山のあなたの空遠く/『幸(さいはひ)』住むと人のいふ。/噫(ああ)、われひとゝ尋(と)めゆきて、/涙さしぐみかへりきぬ。/山のあなたになほ遠く/『幸』住むと人のいふ」。「爺さんと婆さん」は山を下りたのだろう。そして家屋敷は「今ダムの底」なのだ。
鉄道会社の古き社員寮ものほしでギターを弾いたり酒を飲んだり(一二九頁)
カカカカカ 四方八方に鳴いていた蛙の声も消えてしもうた(一三三頁)
作品は、いろいろな傾向を含んでいるが、掲出歌のイメージの周辺で選んでみた。
|
あの僕は鏡の中の僕であるもはやこちらへ出てはこれない 第九歌集『うたがたり』一六五頁
「鏡とマネキン」八首の一首。冒頭に〈婦人服売り場の鏡に写っている僕は青ざめた貴婦人である〉(一六四頁)とあり、〈僕〉はマネキンであるらしい。そして二首置いて掲出歌となる。鏡の世界に閉じ込められた〈僕〉なのだ。下句に「もはやこちらへ出てはこれない」というが、出てくること自体あり得ない。そして、その次に〈売り子らは薬をお茶に入れてまぜ最後の客の僕に勧める〉と二人目の〈僕〉が登場して、やや混乱する。
こなごなに鏡が砕け散ったとき何百となく僕の飛び散る(一六六頁)
「売り子らは」の次の作品。なぜ割れたのか、あるいは割られたのか、何の説明もない。鏡に幽閉された〈僕〉が「何百となく」飛び散った破片に写っているかのようだ。
|
黒馬が萌え出た草をむしり食う先垂れている黒き男根 第九歌集『うたがたり』一八一頁
「南相馬へ」七首の一首。三句まで読んだ時点では、牧歌的な風景を連想するが、あに図らんや、ズームインして立派な一物が主役となる。一連には〈山畑をならし積み上げた黒いもの汚染土入りのビニール袋〉(一八〇頁)がある。また「南相馬へ」の前は「マロニエの並木」十首であるが、最後は〈麦秋も終わる季節の旅を来て福島の駅、今日のにぎわい〉(一七八頁)である。『昼のコノハズク』を開くと「福島」十三首があり、〈二年たってまたおとずれた福島のすっかり違う駅のにぎわい〉(八八頁)で始まり、南相馬の旅が詠われる。『夢宿』の「夏の旅」十三首は福島(九四頁)から塩釜(九六頁)の旅を詠う。話を戻して「南相馬へ」の次の「レクイエム」十三首は、次の歌で終わる。
震災のあとの神戸に咲いたケシここにもさらに美しく咲く(一八六頁)
|
ぴったりと男と女がくっついて電車の中で何してくれんねん 第十歌集『シャングリラの扉』七六頁
第三歌集『さようならやま』にも〈ふとももの白き女と髪長き男がじやれる昼の電車に〉(一六六頁)があり、どの電車でも、よく目撃する光景である。しかし掲出歌が抜きん出ているのは下句とりわけ「何してくれんねん」であろう。思わず笑ってしまった。しかし、そうした視線を意識しての「じやれる」であり、「ぴったりと~くっついて」なのだろう。良くも悪くも注目される電車は彼らの舞台なのだ。見られることは快感に違いない。
駅のすみに若い男女がおしだまりなんのトラブル朝の大都市(一三九頁)
同じ『シャングリラの扉』に載る。電車の中ではない。「駅のすみ」に注目した。出勤時間帯だろうか。夫婦ではない。恋人か、恋人未満か、駅はドラマに満ちている。
|
とびだした弟めざし青空からタカの一羽が近づいてくる 第十歌集『シャングリラの扉』一四六頁
「こぎつねコン子」一五首の一首。連作である。「母さん」狐の膝下にあった子狐たちが成長し、やがて住み処の穴を出る物語である。語り手は「コン子」、姉狐だろう。〈母さんに連れられて見る村里のかがやいていた菜の花畑〉〈母さんがつかまえてきた野ネズミはひめいをあげて逃げてしまった〉〈じゃれあっていた兄弟は強くなり母さん言っても聞かない弟〉〈母さんは待っても来ない 穴の中で育った兄弟ばらばらと去る〉、このあと稲刈り、遅くまで灯る水車小屋、荷車に積まれた米俵が詠われて〈月沈み与作が夜あけの道を来るわらじになぜか母さんのにおい〉から悲運に見舞われたことがわかる。さらに山里の人形芝居に泣く村人、与作の嫁取りで賑わう冬があって、コン子の歌で終わる。
弟も妹もどこかでねむるだろうこよい粉雪がふるともなくふる(一四九頁)
|
遠い旅を来た商人から買った鏡このごろ映る知らない小部屋 第十歌集『シャングリラの扉』一五〇頁
「鏡の中で」八首の一首。下句の「このごろ映る知らない小部屋」が不気味である。二首目は〈鏡にはどこかの町が映りいて男が夜回りの拍子木たたく〉と「どこかの町」に変わり、ここを舞台に物語が進行する。〈むこうから立ち食いそば屋がやってきて橋の近くで屋台をとめた〉〈夜回りの男がそば屋の前に立ちそばを食べつつよもやま話〉〈髪ほどけた女が道をやってきて助けてくれと男にすがる〉〈夜回りの男が女と立ち去ってそば屋もそそくさと行ってしまった〉〈夜回りの男あたふた駆け戻りそば屋の屋台をさがしつつ去る〉。そして最後の歌である。男が女に変わったのかと驚き、やがて作者の性即作中の性という先入観に毒されている私に気がついた。「買った鏡」から女で決まりなのだ。
鏡には切られた女が映りいてあっとおどろくわれの顔なり(一五二頁)
|
車窓過ぎる瀬戸内海の島々の一つ仙界へ通じているか 第十歌集『シャングリラの扉』一六一頁
「高松にて」八首の一首。初句「車窓」は先に快速電車とあるので瀬戸大橋線からの眺めである。地図を見ても周辺に多くの島が散在しているが、全体では、どれだけあるのか。世界大百科事典によると「島(満潮時の周囲〇・一㎞以上)の数は約七〇〇(うち有人島は約一五〇)である」という。下句の「一つ仙界へ通じているか」の連想が楽しい。
エレベーター揺れてとまりぬ壁をふと押せば向こうは地図になき町
右は『昼のコノハズク』(一四〇頁)に載る。事例が唐突、不似合いな気もするが(但し、岩黒島と馬島は瀬戸大橋の橋脚にエレベーターが設置されているらしい)、「仙界へ通じている」とすれば上下だろう。場所は瀬戸内海だから下に島、上に仙境となる。
|
樹々さやぐベンチにおれば五月はやホットパンツの少女の歩む 第十一歌集『季節の手毬唄』一五頁
「シャボン玉」十五首の一首。初句「さやぐ」は「木の葉などがざわざわ音を立てる」(小学館全文全訳古語辞典)ことをいう。三句「はや」は「強い感動・詠嘆を表す」(同)、ベンチの前を歩む少女は、さながら初夏を律しているように〈私〉には見えるのだ。
胸豊かな少女がぼうしを顔にのせ砂に寝ており太陽ま上(二四頁)
冬さなかといへどふとももまるだしで若い女らゆく戎橋
一首目は掲出歌と同じ『季節の手毬唄』に載る。顔を帽子が覆っているから胸と太陽がクローズアップされて夏の主役さながらである。二首目は『海辺の街から』(三六頁)に載る。コートを着て寒そうに歩く大人と対照的、ミナミを御している若さである。
|
エレベータに消えたあいつを追いかけてすぐに扉を開けたら空っぽ 第十一歌集『季節の手毬唄』一八頁
「街の風景」十五首の一首。二句の「あいつ」は何ものか。親しい関係ではない。追いかける理由を含めて謎である。エレベータの扉が閉まる。指で「開」を押す。扉は開くが空っぽ、奥の鏡に〈私〉だけが映っている。この摩訶不思議だけは誰も動かせない。
デパートのエスカレータを上りゐしはずが地下街に迷ひてゐたり
パジャマ着て歩く男がすたすたとエレベーターにはいって消えた
一首目は『さようならやま』(一〇四頁)に載る。エレベータとエスカレータの違いはあるが、化かされた市民こそ気の毒である。二首目は『うたがたり』(一二二頁)に載る。結句「消えた」で、またか、と思うが「病院にて」六首の一首、心配ないだろう。
|
ディスプレイの中でなじみの道を行く妻も子どもも眠った夜更け 第十一歌集『季節の手毬唄』一九頁
「街の風景」十五首の一首。家族が眠った深夜、一人でパソコンを見ているのであろう。しかし、そのように読んでしまうと味も素っ気もない。なにしろ〈パソコンの菜の花畑の壁絵からかすかな香りがただよう深夜〉(第十歌集『シャングリラの扉』一三頁)なのだ。そして「なじみの道」とは〈わが心の内にある村わが心の内にある町ありてさびしき〉(『昼のコノハズク』一六八頁)に違いない。ただ「さびしき」だけでは何かが足りない。
長ズボンの猫など前から来るような気がする暑き西日の道に
第十歌集『シャングリラの扉』(二八頁)に載る。道を行けば誰かと出会う。いや何か、である。それか猫しかも長ズボンで直立二足歩行する猫であってもおかしくはない。
|
クーラーの下で午睡の覚めるときありありと誰か立ち去る気配 第十一歌集『季節の手毬唄』四四頁
「ヘリコプター」十首の一首。こういう歌を解釈せよ、といわれても困る。できないからである。しかし惹かれるのも事実だ。似た経験があるような気がしないでもない。
真夜中に目ざめるときに誰かゐて襖のあひから見てゐたけはひ
うしろから誰かが見張っているようで振りむく前に消えた人影
ただ作者にとっては、これが初めてのことではない。一首目は『海辺の街から』(五九頁)、二首目は『カシオペア便り』(六一頁)に載る。考えてみるに、解釈できないのは、現実の生活に発想の根拠を求めているからに違いない。先に触れたホーンティングの「何者かの存在感」(石川幹人)に求めれば、理解できるし、作品との距離も近くなる。
|
樹の下に弁財天の祠あり扉の中はいずこへ続く 第十一歌集『季節の手毬唄』七三頁
「古都の時空」十六首の一首。京都市右京区嵯峨野神ノ木町に神ノ木弁財天があるが、これだとすると、二〇一七年の台風二十一号で三本の榎のうち一本が倒れ、鳥居も破損したとある。歌集の制作時期と重なって微妙ではあるが、観音開きの扉の向こうに神春竜神と神ノ木龍神が祭ってある。下句「扉の中はいずこへ続く」という想像力が楽しい。
扉あき中はからっぽ突風が過ぎたか調布の路地裏の稲荷(五二頁)
「雨宿り」十三首の一首。舞台は東京都調布市の路地裏にある祠だろう。稲荷信仰の盛んな地域だったらしい。ただ初二句「扉あき中はからっぽ」では何をかいわんや。扉が閉まっているからこそ掲出歌「扉の中はいずこへ続く」という深遠な謎を生むのである。
|
押入れの穴から知らぬ部屋が見え声なく笑いあう老人ら 第十一歌集『季節の手毬唄』一四二頁
「裏通り」二十二首の一首。古びたアパートだろう。押し入れに穴があいている。最初からの穴かも知れない。あるいは入居者の誰かがあけたのかも知れない。ありそうな話である。そして穴があれば覗く。ふつうは〈私〉と同じ一人部屋が見える。ところが違うのである。二三句の「知らぬ部屋」とは、そういうことだろう。どんな部屋か。読者は想像するしかない。ただ「声なく笑いあう」が不気味だが「老人ら」の複数形も妖しい。
あの廊下のつきあたりにある姿見の奥からこわい顔でにらんだ(一四二頁)
一連には、このような作品もある。やはりアパートのような集合住宅あるいは病院を舞台にした怪奇現象だろう。〈私〉の後ろに人がいるのではない。鏡の中なのである。
|
X字エスカレーターですれ違ったあれは俺だよ もう見えないが 第十一歌集『季節の手毬唄』一四三頁
「裏通り」二十二首の一首。初句「X字」の「X」は上りと下りのエスカレーター、アルファベットの文字で比喩としたところが凄い。この交わるところで三句「すれ違った」のである。こういうのをドッペルゲンガーという。デジタル大辞泉で引くと「自分とそっくりの姿をした分身。自己像幻視」とある。次は、そのバリエーションである。
一両ごとに我がすわっているような 今過ぎて行く快速電車
ベンチごとに老人ひとり坐っていてどれか一人が僕のようだよ
一首目は『カシオペア便り』(五四頁)、「一両ごと」である。二首目の『河口域の精霊たち』(五〇頁)はベンチごとに坐っている「どれか一人」というから掲出歌に近い。
|
タクシーがひとりを拾い去ってゆく落葉ひとひら字幕は出ない 第十一歌集『季節の手毬唄』一六三頁
「ノスタルジア」一八首の一首。この「ノスタルジア」をデジタル大辞泉で引くと「異郷にいて、故郷を懐かしむ気持ち。また、過ぎ去った時代を懐かしむ気持ち。郷愁。ノスタルジー」とある。ナレーターがいて、遠景に主人公を乗せて走り去るタクシー、近景に「落葉ひとひら」の配置とくれば、これは映画以外の何ものでもない。たっぷりとノスタルジアに浸って席を立つはずだったが、結句「字幕は出ない」、まさかのどんでん返しである(ナレーターを恨むまい。私たちの生活も瞬時を捉えれば立派なシネマなのだ)。
玉垣に名前が彫られすでに世になき人々と消えた会社と(一六〇頁)
一連には、このような作品もある。神社の玉垣に時代の推移を見ているのである。
|
一本のビニール傘で男二人なかよくもなく通りすぎたり 第十二歌集『カシオペア便り』五三頁
「遊歩道にて」八首の一首。傘がないので、どちらかが入れてもらったのだろう。入れてあげた方も本来の雨傘は持ってきてなかったのでコンビニで買ったのかも知れない。会社の同僚、昼ご飯を外で食べるために出てきたのかも知れない。あるいは会社にもどる途中かも知れない。そんなところだろう。四句「なかよくもなく」が言い得て妙である。
ウイスキーのびんをそなへて橋の下いつも二人の男ねむれる
第五歌集『冬の昼顔』(三二頁)の一首。こちらも男二人、しかしホームレスらしい。ビニール傘の代わりはウイスキーの瓶、「そなえて」は「備えて」だろう。仕事の仲間か。若者による襲撃事件もあるので、二人連れの方が心強いに違いない。そして酔える。
|
ボッスの絵の地獄の場面を抜け出して画廊のソファーで飲む缶ジュース 第十二歌集『カシオペア便り』七九頁
「超熱帯夜」十四首の一首。「ボッス」はヒエロニムス・ボッシュ、日本国語大辞典に「フランドルの画家。悪の諸相や怪奇な幻想・妖怪、あるいは地獄の情景を描出。代表作は『快楽の園』『聖アントニウスの誘惑』など。(一四五〇頃~一五一六)」とある。二句は「快楽の園」の三枚セットの右側だろう。地獄から抜け出してホッとしているのだ。
ドアのない画廊のなかで服を脱ぎヒエロニムス・ボスの絵のなかに立つ
『季節の手毬唄』(二〇頁)に載る。「快楽の園」の中央だろう。人間の愚かさと罪が描かれているらしい。夥しい裸の人物の一人になろうとして服を脱いだが、脱衣室がない。それが上句だろう。絵の中を往来するという発想に、特異な画家への共感が見える。
|
サイボーグ秘書の私は長生きだ、死にたい歳を申請して来た 第十二歌集『カシオペア便り』一三四頁
「ドロシーのあくび」六〇首、三部作その三部の一首である。「アンドロイド」(人造人間)「クローン」(クローン人間)「サイボーグ」(改造人間)「エスパー」(超能力者)「コピー」(コピー人間)、時代は未来と分かるだけで、ストーリーもあるらしいが、想像を超えたものである。なにしろ「原種の人間」が「一億を切った」(一三四頁)世界なのだ。それでも〈自分の手に入らないもの自分自身、雨降る道にくるまを走らせ〉(一二四頁)のように心にとまるものがある。掲出歌も、そうだ。改造人間も、心は手つかずなのであろう、下句の事務的な手続きが面白い。同じ『カシオペア便り』の「ロンサム・ジョージ」から引く。こちらは人造人間、「死ぬほど退屈」といっても、死ねるのだろうか。
いつまでも死ねないままに二百歳越えて死ぬほど退屈である(六七頁)
|
青春が俺にあったか無かったかゆっくりゆっくり沖を行く船 第十二歌集『カシオペア便り』一三六頁
「八月の終わりに」九首の一首。三句切れ、二句と三句の「か」は並立助詞だろう。自らの青春に懐疑的である。四句から実景で、沖の船に問いかけるように遠望している。距離があるから動くのは「ゆっくりゆっくり」である。通して読むと四句が微妙に上句を受けている気がするから不思議である。結句は「沖を行く船(考えている)」だろう。
青春はにがく過ぎたり楡の木のたつ下に来てこもれびあふぐ
樫の木が春のあらしに揺れておりみじめに過ぎし俺の青春
一首目は『さようならやま』(一五三頁)、二首目は『うたがたり』(一六八頁)に載る。掲出歌に呼応するのは「にがく過ぎたり」であり、「みじめに過ぎし」であろう。
|
アッ先生と言う声聞いたのはこの駅かベルト緩めて便所出るとき 第十三歌集『河口域の精霊たち』四一頁
女子学生だろうか。「アッ先生」と声に出たが、駅のトイレから出てくるところ、しかもベルトは最後まで締まっていない。悪いところで会った。無防備な姿に挨拶は遠慮して、人混みに紛れたのだろう。事実かどうかは知らない。しかし事実であっても不思議でない趣である。作品ではないが『夢宿』の「あとがき」に「思いがけぬことから、今年一月以来、兵庫県歌人クラブに関わりを持つことになった」とある。定年と聞き、断られるのを覚悟で代表の私からお願いした。二〇一二年六月三十日には川西市文化会館で講演会を開き、講師をお願いした。これは地元有志によるものだ。演題は「万葉集に見る場と想像ー虚構と述懐ー」だった。参加者四十九名、会費五百円、講演料は一万円だった。十一月には兵庫県歌人クラブの『年間歌集』の編集をしてもらった。断られないのをよいことに、大先輩を随分と安く使ったものだ。掲出歌を読みながら、そんなことを思い出した。
|
わが家だけが存在しているかのような夜の暗闇 雨音ざんざ 第十三歌集『河口域の精霊たち』四七頁
「汽水」十八首の一首。家を包んでいるのは雨の音だけ、結句「雨音ざんざ」で「わが家だけが存在しているかのような」、そんな「夜の暗闇」(布団の中で聞いているのだろう)を「私」はどんな思いで過ごしているのだろう。一般的な事例で考えると、川の氾濫や、土砂崩れといった具体的な脅威がなければ、また停電やモノが飛んでくるという心配がなければ、残るのは高揚感だろう。安心を保証されている非日常と呼んでもよい。
カーテンを開ければ雨といふやうな街にしばらく暮らしてみたい
第六歌集『海辺の街から』(一二二頁)に載る。「しばらく」の限定つきだが結句に落ち着くところを見ると、生活上の不便は仕方ないが、やはり雨が好きなのだろう。
|
べっぴんが通ればいまも振り返る三十年たっても直らない癖 第十三歌集『河口域の精霊たち』一一二頁
「奈良町あたり」十二首の一首。「三十年」前の『みずいろ迷宮』に「べっぴん」は登場しない。ただ「あとがき」に、美人の教え子から秋篠寺の伎芸天まで、美とは何か、について語られていた。掲出歌だが初句の親近感がよい。『昼のコノハズク』には〈うしなったカンガルーの皮の眼鏡入れベッピンさんがくれた思い出〉(一七九頁)がある。
しげしげとながめをりしかうるはしきお顔がついと横をむきたり
笑ひやめてすましたときの一瞬がこはくなるほど美しい人
一首目は『冬の昼顔』(八八頁)、二首目は『海辺の街から』(一七頁)、別嬪さんには目がいく。横を向かれてもこりない。何しろ三十年来の「直らない癖」なのだ。
|
睡蓮の葉にふる雨は目に見えず水面(みなも)の雨は輪をえがきいて 第十三歌集『河口域の精霊たち』一四〇頁
「六月のひぐらし」二十七首の一首。札幌を舞台にした連作ないし群作の最後に置かれている。睡蓮と似た蓮の葉は、雨が降ると表面張力で水滴となる。撥水性があるからだ。睡蓮には、これがない。しかも水面に浮かんでいるから、雨に濡れていることは分かるとしても、水滴としては目には見えない。その浮かんでいる葉の周辺は、すなわち下句にあるとおり「水面(みなも)の雨は輪をえがきいて」で、目にも見えるので好対照となっている。
街灯の照らす範囲にふる雨と闇に見えずに降っている雨
第十二歌集『カシオペア便り』(四〇頁)に載る。街灯が照らす範囲は雨が見え、闇の部分は雨が見えない。撥水性と光との違いはあるが、おもしろい風景を詠っている。
|
| 項目別に歌集および「あとがき」を見る |
一、序数歌集
第十三歌集『河口域の精霊たち』の末尾に「著者略歴」があり、「短歌」「歌集・歌書」「研究」「研究論文(上代韻文関係を抜粋)」に整理されている。このうち歌集だけを取り上げると、次のとおりである。
第一歌集『たましいの秋』
第二歌集『みずいろ迷宮』
第三歌集『さようならやま』
第四歌集『α階のS』
第五歌集『冬の昼顔』
第六歌集『海辺の街から』
第七歌集『夢宿』
第八歌集『昼のコノハズク』
第九歌集『うたがたり』
第十歌集『シャングリラの扉』
第十一歌集『季節の手毬唄』
第十二歌集『カシオペア便り』
第十三歌集『河口域の精霊たち』
但し、第一歌集と第二歌集の間に歌集『タタの星祭』が出ている。奥付には「昭和62年3月25日発行(250部限定)」とあるのみである。第二歌集の「あとがき」に「第一章から第三章までの作品の多くは、かつて私家版で出した『タタの星祭』に収めたものである。あの歌集は、発行部数が少なすぎて、教え子たちの一部に送ったあとは、ごく少部数を白珠社や歌壇の方々に送っただけであったが、思いがけず、新聞や結社誌、同人誌や単行本にまで取りあげていただき、感謝している」とある。
第十一歌集『季節の手毬唄』も「あとがき」に「毎年一冊の自費出版では、さすがにかなわないので、私家版(非売品)として、二五〇部を出版することにした」とあり、奥付でも「私家版(非売品)」とある。しかし、こちらは第十二歌集『カシオペア便り』の末尾の「歌集・歌書」欄で私家版のまま第十一歌集として位置付けられている。
『カシオペア便り』も『季節の手毬唄』に同様である。奥付は「私家版(非売品)」であるが、「あとがき」及び「歌集・歌書」欄には第十二歌集となっている。
二、著者名
第一歌集『たましいの秋』と私家版歌集『タタの星祭』の著者は「小谷水彦(おたにみずひこ)」、第三歌集『みずいろ迷宮』以後が「小谷博泰(こたにひろやす)」である。
三、仮名遣い
第一歌集『たましいの秋』 現代仮名遣い
私家版歌集『タタの星祭』 現代仮名遣い
第二歌集『みずいろ迷宮』 現代仮名遣い
第三歌集『さようならやま』 歴史的仮名遣い
第四歌集『α階のS』 歴史的仮名遣い
第五歌集『冬の昼顔』 歴史的仮名遣い
第六歌集『海辺の街から』 歴史的仮名遣い
第七歌集『夢宿』 歴史的仮名遣い
第八歌集『昼のコノハズク』 現代仮名遣い
第九歌集『うたがたり』 現代仮名遣い
第十歌集『シャングリラの扉』 現代仮名遣い
第十一歌集『季節の手毬唄』 現代仮名遣い
第十二歌集『カシオペア便り』 現代仮名遣い
第十三歌集『河口域の精霊たち』 現代仮名遣い
現代仮名遣いでスタートし、第三歌集から第七歌集の四冊は歴史的仮名遣い、第八歌集以降は再び現代仮名遣いにもどしている。
四、歌数
第一歌集『たましいの秋』 三八八首(「あとがき」に「約三九〇首」)
私家版歌集『タタの星祭』 二一〇首(「あとがき」に「二一〇首ばかり」)
第二歌集『みずいろ迷宮』 四七一首
第三歌集『さようならやま』 三九〇首(「あとがき」)
第四歌集『α階のS』 四四二首(「あとがき」)
第五歌集『冬の昼顔』 四五二首
第六歌集『海辺の街から』 三一四首
第七歌集『夢宿』 四〇一首(「あとがき」)
第八歌集『昼のコノハズク』 四一三首(「あとがき」)
第九歌集『うたがたり』 四二六首(「あとがき」)
第十歌集『シャングリラの扉』 五〇七首(「あとがき」)
第十一歌集『季節の手毬唄』 六一一首(「あとがき」)
第十二歌集『カシオペア便り』 五七九首(「あとがき」)
第十三歌集『河口域の精霊たち』 六二一首
歌数としてはカウントしていないが『たましいの秋』にはプロローグとしての五句三十一音詩が十一首、『タタの星祭』にも一首あることを、参考に記録しておく。
第二歌集『みずいろ迷宮』の「あとがき」に「第一章から第三章までの作品の多くは、かつて私家版で出した『タタの星祭』に収めたものである」とある。そこで計算すると「暗転ののち」七四首中六六首、「蟬の木過ぎて」五四首中五三首。「夕もや峠の」七〇首中五六首、計一七五首となる。残る『タタの星祭』は三五首である。
これも参考だが、全歌数としては六〇五〇首という数字が残る。
五、発行部数
第一歌集『たましいの秋』 記載なし
私家版歌集『タタの星祭』 二五〇部
第二歌集『みずいろ迷宮』 未記載
第三歌集『さようならやま』 未記載
第四歌集『α階のS』 未記載
第五歌集『冬の昼顔』 未記載
第六歌集『海辺の街から』 未記載
第七歌集『夢宿』 四〇〇部
第八歌集『昼のコノハズク』 未記載
第九歌集『うたがたり』 四〇〇部
第十歌集『シャングリラの扉』 四〇〇部
第十一歌集『季節の手毬唄』 二五〇部
第十二歌集『カシオペア便り』 未記載
第十三歌集『河口域の精霊たち』 未記載
第七歌集『夢宿』の「あとがき」に「今回は、発行部数を四〇〇部に抑えた」とあって、第六歌集までの「未記載」の発行部数を、いくらかでも推測できるのである。
六、出版社
短歌新聞社 第一歌集『たましいの秋』
和泉書院 私家版歌集『タタの星祭』
ながらみ書房 第二歌集『みずいろ迷宮』
和泉書院 第三歌集『さようならやま』
青磁社 第四歌集『α階のS』
和泉書院 第五歌集『冬の昼顔』
短歌新聞社 第六歌集『海辺の街から』
和泉書院 第七歌集『夢宿』
いりの舎 第八歌集『昼のコノハズク』
いりの舎 第九歌集『うたがたり』
いりの舎 第十歌集『シャングリラの扉』
ブイツーソリューション 第十一歌集『季節の手毬唄』
ブイツーソリューション 第十二歌集『カシオペア便り』
和泉書院 第十三歌集『河口域の精霊たち』
中で目立つ和泉書院は「日本文学・日本語学・日本史学と上方文化本の図書出版」を専門とする大阪市天王寺区にある出版社である。和泉書院のホームページで小谷博泰の名を検索すると『日本語文法の原理と教育』『木簡・金石文と記紀の研究』『上代文学と木簡の研究』『木簡と宣命の国語学的研究』『木簡・金石文と記紀の研究』『日本語文法の原理と教育』『上代文学と木簡の研究』『木簡と宣命の国語学的研究』がヒットする。
また第十三歌集『河口域の精霊たち』の「あとがき」に「出版を和泉書院にお願いすることにした。ちょうど研究書の小谷博泰著作集全四巻の出版が和泉書院のお世話で進行中であり、この歌集はたぶんその第四巻に前後してできあがるだろうと思う。和泉書院の廣橋研三社長はじめ、皆様のご厚情に感謝申しあげる」とあって縁が深い。
七、刊行年月日
一九八三年十月一日 第一歌集『たましいの秋』
一九八七年三月二十五日 私家版歌集『タタの星祭』
一九九二年七月二十三日 第二歌集『みずいろ迷宮』
一九九六年九月一日 第三歌集『さようならやま』
二〇〇三年二月一日 第四歌集『α階のS』
二〇〇八年六月二十五日 第五歌集『冬の昼顔』
二〇一一年五月二十五日 第六歌集『海辺の街から』
二〇一三年三月十五日 第七歌集『夢宿』
二〇一五年九月十日 第八歌集『昼のコノハズク』
二〇一六年十一月一日 第九歌集『うたがたり』
二〇一七年九月一日 第十歌集『シャングリラの扉』
二〇一八年四月三十日 第十一歌集『季節の手毬唄』
二〇一九年二月二十日 第十二歌集『カシオペア便り』
二〇二〇年一月二十五日 第十三歌集『河口域の精霊たち』
第七歌集で、ややスピードをあげるが、第九歌集からの凄まじいとしか言いようのない加速には目を瞠るものがある。
八、歌論
歌は魂の贄(にえ)
「私にとって、詩歌は現実の仮象を超えるためにある。現実以上に実在的な真実世界の虚構こそ望まれるものである。生活綴り方の断片を書くのなら、何もこのきゅうくつな表現形式による必要はない。雑駁な日常は散文にまかせておけばよい。うたは魂の贄(にえ)である。」(第一歌集『たましいの秋』の「あとがき」)
私の短歌に私の現実は登場しない
「私の短歌に私の現実は登場しない。短歌はしばしの虚妄を美とし、わずかの調べを命とするものである。」(私家版歌集『タタの星祭』の「あとがき」)
古典和歌の歴史
「小説でも詩でも、作者は作者、作品は作品として、作者と作品は一応、切り離して考えることが多いのだが、短歌では、作者と作品を一体のものとして考える傾向があるようだ。/五七五七七の表現形式がそれを要求するというのなら、一〇〇〇年以上に渡る古典和歌の歴史は何だったというのか。/そこで気がついたのたが、私の目の前には、少数の方々を除き、ほとんど人が手を入れていない広大な沃野、作者からは自立した作品を生むべき沃野が残されているのである。まずは、自分でここを耕してみよう。なんせ、ほとんど未開拓の土地である。今までの歌集でもすでに作りはじめてはいたが、意識して作り出すと、次から次へといろいろな傾向の作物ができてくる。去年の十一月ごろにはじまって、半年ほどで、意外な数の作品ができてしまった。」(第九歌集『うたがたり』の「あとがき」)
視点人物の転換
「常に作品の『我』=『作者』とするには、作品の『我』=『作者』という図式を常に実体化しなければならない。そのためには視点人物を作者、あるいは作者とするもの以外の者に置くことは常にタブーとし、『われ』=『作者』であると完全に条件付け、あるいは設定しなければならない訳である。しかし、私のこの歌集では、そのような条件付けははずしてあるので、作品ごとに読者に判断をしていただくことになるかもしない。」(第十歌集『シャングリラの扉』の「あとがき」)
九、エピソード
引っ越したら
「神戸の須磨から奈良の高畑にある勤め先へ八年間通った。九年目に、とうとう奈良へ引越した。ところが、引越してから半年たって、今度は神戸への転勤が決まった。(略)。/神戸からすると、奈良は異郷である。大阪を越え、生駒山のトンネルを列車が通過するころ、軽い耳なりのすることがあった。トンネルのこちらとあちらでは、いささか風景が違っている。トンネルを出ると、そこは雪国であったこともある。この一年は、奈良に住み奈良に通う。来年になれば、今度は奈良から神戸へ通っていることであろう。」(私家版歌集『タタの星祭』の「あとがき」)
ボディー・チェック
「私の住んでいるあたりには、古墳や墓地がやたら多い。おかげで、住宅地の近くで、畑に桃が咲き、田に鷺が飛び、池に鴨が鳴く。夜は静かで暗い。古墳の横の小道を夜に歩いていたりすると、私のような唯物論者にとっても、さすがに不気味である。/散歩によくでかけるところに、大きな池がある。その芦原に、種々の水鳥が生活している。ある日、たまたま、私のつれあいと池のまんなかに通っている細道を歩いていたら、どうしたわけか、ふだんは見かけない何匹も何匹もの大きな蛇にであった。ゆうゆうと、かま首をあげて、こちらを見ていたりする。/大きなる蛇、聞きて、高く頭をもたげて、女の顔をにらみ、蛙を吐きて放つ/という『日本霊異記』の一節を思いだした。/また、ある日のこと、古墳と古墳との間の細道を一人歩いていたら、二人の労務者ふうの男にいきなり前後をはさまれ、なんと、警察手帳を見せられ、ボディー・チェックをされた。ドスのきいた声をかけられたときは、わけも分からぬまま、思わずあやまってしまいそうな気になった。二時間余りの散歩のあいだ、ずっと見張られていたようで、トランシーバーで連絡を取っていたが、私はそのとき、ふと何十年かののちに来るかも知れない社会を幻視したのであった。/ある隠れ里の昼さがりのことである。」(私家版歌集『タタの星祭』の「あとがき」の追記)
帰神
「三月に奈良から神戸へ引っ越しした。本当は一年早く引っ越しするつもりでいたところ、地震のおかげで今年になってしまった。(『あすは廃墟の港か知れぬ』と詠んだときは、まさか半年後にその光景が目の前に広がるとは思いもしなかった)。のびた一年は、えらくしんどい一年であった。そのクライマックスに父親が死んだ。思えばしんどい年月の前後にはきっと誰かの死や、私の転居や、転職・転勤があった。運命?は連れもってやって来るということか。今回はまだ転職はないが。」(第三歌集『さようならやま』の「あとがき」)
アルコール
「神戸から奈良へ八年間かよった。やっと奈良へ転居して、やれやれと思っていたところ、一年で勤め先が神戸に戻った。今度は奈良から神戸に九年通った。乗り換え乗り換えしながらかよっていると、帰りには疲れて駅で缶ジュースを飲んだりする。そのうち、乗り換えの鶴橋で酒を飲む。やがて、大阪駅でも飲む。神戸で飲み、大阪で飲み、奈良に帰ってまた飲み、となると立派なアル中である。転居して神戸に戻ったが、まだアルコールは抜けない。」(第三歌集『さようならやま』の「あとがき」)
病気
「この歌集の、はじめには頸椎の手術があった。ちょうどアメリカ・イラク戦争の始まった日であった。開戦のニュースを見損ねた。いや、あぶなく、体ごとあちらの世界へいくところであった。/二年後に、今度は、前立腺癌だときた。さいわい良性で、まだ進行してはいなかったが、ふつう、初期でも精神衛生に悪いからと言って、治療する、つまり切り取ってしまうらしい。しかし、頸椎の手術でこりた。セカンド・オピニオンの医師の話も聞いて、さしあたっては治療しないことにした。/治療しないが、三、四か月に一度、血液検査と診察を受ける。当然、医者は治療を勧める。なるほど、精神衛生に悪い。/頸椎の場合は、頸椎なんとか症で、この『なんとか』の所はとうとう覚えられなかったが、今回はなんせ『がん』である。前立腺がなんたるかはよく分からなかったが、この『がん』は、泣く子も黙るというしろもの。なるほど、コトダマとはこういうものを言うのであろう。言葉からして精神にこたえる。それでも、頸椎のときの倍の三年間、治療を引き伸ばした。しかし、二年前から勤め先で役職について、これまた精神衛生によくない、ストレス多き二年間を送ったためか、血液検査の数値が少しながら進んだ。現在は、ここらで年貢の納め時か、という心境になってきた。」(第五歌集『冬の昼顔』の「あとがき」)
歌集『神戸』
「さて、ヒトとしての私のテリトリーは、神戸にある。歌集の名前も『神戸』としようか、と思ったぐらい、今回はご当地の短歌が多い。いや、多そうである。テリトリーの東は芦屋、西宮、大阪の梅田、西は明石あたりであろうか。大阪をもっと越えて南へ行けば、母方の祖先の墓のある岸和田、貝塚あたりへ行き、明石を西へ行けば父方の祖先の墓のある加古川、高砂あたりへ行く。が、そこまで行くとテリトリーからは外れる。姫路や奈良に勤めを持ったことがあり、そこらも、年に二、三度、行っているようである。/言うのもいまさらながらだが、神戸は東西に長い町である。その南北を図式化すると、人工島、港、工場地帯、商店街、住宅地、山脈、温泉町と新興住宅地、と並ぶ。実際にはこれらが入り混じっており、しかも長い年月で考えると、ダイナミックに流動してきた。/ところで、一月にバラが咲いたりして亜熱帯に近い感じの市街地と、北海道南部の気候というのが歌い文句の六甲山上との距離は、ケーブルカーでたった十分である。/精神衛生のためにと、ここ二年間はよく六甲山へ行った。この山、観光シーズンの晴れた日曜日などは、人やくるまが多くて、下界とあまりかわらず、登山をするわけでもない私には、うれしくない。が、四季にかかわらず霧が吹く日がある。霧が濃い日には、人のほとんどいない結界状態のようになる。また、冬は雪が積もって、行けばそこは異郷である。/現在の神戸の市街は、たとえばマンガの『神戸在住』(木村紺著・講談社)に詩情をもって描かれているが、これを見ると、私が住んでいるのは、心理的には今より少し古い神戸かなという気がする。なんせもう、歳も六十代である。などと言い出すと、愚痴っぽくなるので、これでおしまいにする。」(第五歌集『冬の昼顔』の「あとがき」)
引っ越し魔
「一九四四年(昭和一九年)、神戸市兵庫区に生れる。以降、四〇歳代ころに奈良市に住んだ十年ほどを除いて、兵庫区、長田区、須磨区、兵庫区、垂水区、須磨区、灘区と転々としながらも、神戸市に住んでいる。」(第六歌集『海辺の街から』の「短歌関係略歴」)
暴走する短歌
「予定とか予想とかは、はずれやすいもののようである。今年、つまり二〇一二年三月末日をもって定年退職をした。そもそも定年いっぱいまで勤めるというのが予定外であったが、それはともかく、退職すればあれもしたい、これもしたいと思うことはあった。ところが、短歌ができはじめた。短歌などというものは、初心のころはともかく、たいていは、締切りにせまられてできるようなものである。それが、締切りを無視してできる。それでも退職後、二か月くらいは何やかやと用事があった。それが過ぎると、なんと、短歌が暴走しはじめた。いつもの何倍もできてしまうのである。結果、この一年間の作品数を合計すると、三年分くらいになるであろうか。」(第七歌集『夢宿』の「あとがき」)
|
| あとがき |
一 執筆の動機
本書の執筆の動機は暴走する小谷短歌を受け止め、私なりに整理する必要に迫られたことによる。愛唱歌・注目歌が、どこにあるのか、押さえておきたかったのである。
二 出会い
小谷さんとの出会いは同人誌「鱧と水仙」(藪の会)の創刊時のメンバーとしてだから平成五(一九九三)年である。但し、私は平成二十二(二〇一〇)年に藪の会を退会している。兵庫県歌人クラブとの関係については一一二頁に触れたとおりである。その縁もあって二度ほど散策する機会を得た。
一度目は平成二十六(二〇一四)年四月十三日である。兎月庵日記より引く。
「白珠」の小谷博泰さんと「短歌人」の髙井忠明さんと私の三人で源氏まつりを見る。 といっても今年は懐古行列が能勢口周辺である。それだけでは面白くないので、朝、雲 雀丘花屋敷に集合、バスで満願寺に行く。そのあとは歩いて多田神社、再びバスで能勢 口にもどって昼食、十四時前後に能勢口駅前を通る行列を見て解散した。
川西は清和源氏発祥の地である。多田神社付近に居館を構えていたとされる。満願寺は源氏の祈願所であり、頼光四天王の一人、坂田金時(金太郎)の墓がある。通常、懐古行列は多田神社から出発する。源頼光らによって退治された酒呑童子も、見られる。
二度目は平成二十七(二〇一五)年五月十五日。やはり兎月庵日記より引く。
「白珠」の小谷博泰さん、「短歌人」の髙井忠明さんと私の三人で伊丹の荒巻バラ公園 を散歩した。十時半、阪急電車の中山観音駅で下車、高井さんの車で連れていってもら う。昼食は山本駅近くの「花やしき」、その後、清荒神をお参りして散会(次は神戸あ たりをなどといいつつ)した。
この荒巻バラ公園には地下ホール(瞑想空間)がある。公園には何度か来たことがあるが、階段を下りるのは初めてだった。私には、異界のような空間であった。
三 書名
本書の書名は『小谷博泰の百首~ときとして異界~を読む』である。初めの「執筆の動機」からいえば『小谷博泰の百首を読む』でもよかったわけである。しかし個人的には最大の特色である「異界」は外せない。いや外したくない。私の、こだわりである。そこで各歌集に「異界」という言葉は登場するのか。不安なので調べてみた。
第一歌集『たましいの秋』。「異界」は登場しないが「他界」が一五四頁、一九七頁、二二九頁に出てくる。意味は、自分の属さない世界とも、来世とも取れる。
私家版歌集『タタの星祭』。「異界」は登場しないが二二頁のプロローグに「異空間」が登場する。「他界」が三三頁と五二頁に登場する。
第二歌集『みずいろ迷宮』。一〇四頁に「他界」が登場する。
第三歌集『さようならやま』。巻頭に「異界の神々」五首が置かれている。
第四歌集『α階のS』。一〇六頁に「他界」が登場する。
第五歌集『冬の昼顔』。一二四頁に「他界」が登場する。一五七頁に「異界」が登場する。作品に、この語が登場するのは初めてということになる。
第六歌集『海辺の街から』。七二頁、八三頁、一一九頁、一三二頁の四カ所に「異界」が登場する。
第七歌集『夢宿』。三三頁、一〇九頁、一三五頁の三カ所に「異界」が登場する。
第八歌集『昼のコノハズク』。二八頁と一三二頁に「異界」が登場する。なお九八頁に「異世界」が登場するが、文学ジャンルの意味で使っている可能性がある。
第九歌集『うたがたり』。七一頁、一〇四頁、一一八頁、一九一頁の四カ所に「異界」が登場する。
第十歌集『シャングリラの扉』。三〇頁と八一頁に「異界」が登場する。
第十一歌集『季節の手毬唄』。「異界」という言葉は登場しない。但し「他界」が三四頁に登場する。
第十二歌集『カシオペア便り』。六二頁に二カ所、六三頁、七〇頁、一三七頁、一七六頁の計六カ所に「異界」が登場する。
第十三歌集『河口域の精霊たち』。七五頁と九八頁に「異界」が登場する。なお七九頁に「異世界」が登場する。
では「異界」とは何か。大辞林によると「人類学や民俗学での用語。疎遠で不気味な世界のこと。亡霊や鬼が生きる世界」である。しかし、これでは小谷短歌の半分しか掬い取ることができない。日本国語大辞典で引くと「日常生活の場所と時間の外側にある世界。また、ある社会の外にある世界」という。幅のある、こちらに拠ることにしたい。
四 クローン、アンドロイド、サイボーグ…いうならSF短歌について
さて「日常生活の場所と時間の外側にある世界」であるが、私家版歌集『タタの星祭』に「タタにて 30時76分」五十四首がある。そのプロローグに、
地球に接してTATAという異空間があるという。ある種の人々がそこに出入りできる という。地球の一時間はTATAの一日の三分の一、TATA星時間の33時間33分33秒 という。
とある(ちなみに小松和彦の『異界と日本人』によれば、浦嶋太郎の訪問した龍宮の三年は、人間世界の七百年以上の歳月に相当するという)。
第三歌集『さようならやま』には「惑星間ステーション」十六首が収められ「ロボット」「クローン」「サイボーグ」が登場する。第九歌集『うたがたり』の「プラネット」十首には「アンドロイド」が登場する。第十歌集『シャングリラの扉』に「星の女王さま」一連があるが、第十二歌集『カシオペア便り』の「星の女王の孫娘」一連へと続く。同じく第十一歌集『季節の手毬唄』に「ドロシーの一日」一連があるが、これは第十二歌集『カシオペア便り』の「ドロシーのあくび」一連、また第十三歌集『河口域の精霊たち』の「ドロシーのデータ」一連へと続く。いうならSF短歌が数を増し、工夫が重ねられていく過程を眺めることになるのである。作者は第十二歌集『カシオペア便り』の「あとがき」で虚構詠について「柿本人麻呂などが長歌と反歌によって成し遂げた『歌語り』(歌による物語り)を、短歌の連作によって試みたものであり、いわば日本の詩歌の伝統にのっとったものであった」とする。そのとおりなのだろうが、なにかしら補足する具体例がほしい。そんな思いで関連する書籍を見ていたら、これが、あったのである。
西尾光一校注『撰集抄』(岩波文庫)である。「はじめに」で「『撰集抄』は、古来西行自著と信じられて広く愛読され、漂泊の歌僧西行の文学像形成に大きく寄与してきている。しかし、現存本の『撰集抄』が西行の自著ではなく、西行自記の体裁に仮托してつくられた書物であることは、明治以降今日までの研究で、ほぼ明らかにされてきた。」また「たとえ西行の自著でなく、仮托の書であるにしても、一三世紀の半ば頃に成立し、鎌倉室町期以来ずっと西行のものとして一般に読まれ続けてきた享受の歴史の持つ重みは、動かし得ないものがある。」という代物なのだ。
その中から「西行高野ノ奥ニ於テ人ヲ造ル事」(巻五第一五)を引用する。
おなじき比(ころ)、高野の奥に住みて、月の夜ごろには、ある友だちの聖(ひじり)ともろともに、 橋の上にゆきあひ侍りてながめながめし侍りしに、此聖「京になすべきわざの侍る」と て、情(なさけ)なくふり捨ててのぼりしかば、何となう、おなじ憂き世を厭ひし花月の情(なさけ)をも わきまへらん友こひしく侍りしかば、おもはざるほかに、鬼の、人の骨をとり集めて人 につくりなす例(ためし)、信ずべき人のおろおろ語り侍りしかば、そのままにして、ひろき野 に出(いで)て、骨をあみ連(つら)ねてつくりて侍りしは、人の姿に似侍れども、色も悪(あし)く、すべて心 も侍らざりき。聲はあれども、絃管(げんくわん)の聲のごとし。げにも、人は心がありてこそは、 聲はとにもかくにも使はるれ。ただ聲の出(いづ)べきはかり事ばかりをしたれば、吹き損じた る笛のごとくに侍り。
おほかたは、是程に侍るも不思議也。さて、是をばいかがせん、破らんとすれば、殺業(せつごう) にや侍らん。心のなければ、ただ草木と同じかるべしと思へば、人の姿也。しかじ破ら ざらんにはと思ひて、高野の奥に人もかよはぬ所に置きぬ。もし、おのづからも人の見 るよし侍らば、化(ばけ)物なりとやおぢ恐れん。
さても、此事不審に覚えて花洛に出侍りし時、教へさせおはしし徳大寺へ参り侍りし かば、御参(さん)内(だい)の折(おり)節(ふし)にて侍りしかば、空しくかへりて、伏見の前(さき)の中納言師仲の卿のみ もとに参りて、此事を問ひ奉り侍しかば、「なにとしけるぞ」と仰せられし時に、「そ の事に侍り。廣野に出て、人も見ぬ所にて、死人の骨をとり集めて、頭(かしら)より足手(あして)の骨 をたがへでつづけ置きて、砒霜(ひさう)と云薬を骨に塗り、いちごとはこべとの葉を揉みあはせ て後、藤もしは絲なんどにて骨をかかげて、水にてたびたび洗ひ侍りて、頭とて髪の生(を) ゆべき所にはさいかいの葉とむくげの葉を灰に焼きてつけ侍り。土のうへに畳をしきて、 かの骨を伏せて、おもく風もすかぬやうにしたためて、二七日置いて後、その所に行(ゆ)き て、沈(ぢん)と香(かう)とを焚きて、反魂(はんごん)の秘術を行ひ侍りき」と申侍りしかば、「おほかたはしか なん。反魂の術猶日あさく侍るにこそ。我は、思はざるに四條の大納言の流をうけて、 人をつくり侍りき。いま卿相にて侍れど、それとあかしぬれば、つくりたる人もつくら れたる物もとけ失(う)せぬれば、口より外(ほか)には出(い)ださぬ也。それ程まで知られたらんには教 へ申さむ。香をばたかぬなり。その故は、香は魔縁をさけて聖衆をあつむる徳侍り。し かるに、聖衆生死を深くいみ給ふほどに、心の出(いで)くる事難(かた)き也。沈と乳(ち)とを焚くべきに や侍らん。又、反魂の秘術をおこなふ人も、七日物をば食ふまじき也。しかうしてつく り給へ。すこしもあひたがはじ」とぞ仰せられ侍り。しかれども、よしなしと思ひかへ して、其後はつくらずなりぬ。
中にも土御門の右大臣のつくり給へるに、夢に翁(おきな)のきたりて、「我身は一切の死人を 領せる物に侍り。主(ぬし)にものたまひあはせで、なんぞ此骨をばとり給ふにや」とて、恨む るけしき見え給へりければ、もし日記を置く物にしあらば、我子孫つくりて靈にとらは れなん、いとど由なしとて、焼かせ給ひにけりと聞くにも、無益(むやく)のわざと覚え侍り。よ りより心得(こころう)べき事にや侍らん。ただし、呉竹の二子は、天老と云(いふ)鬼の、頴川(えいせん)のほとりに てつくりいだせる賢者とこそ申傅(つた)へたるなれ。
これに竹取物語や織女星と牽牛星の話を重ねれば、往時の「クローン」「アンドロイド」「サイボーグ」また「惑星間ステーション」を、垣間見る思いがするのである。
五 歌人・小谷博泰の功績
大層なタイトルになったが、この本の冒頭で「小説でも詩でも、作者は作者、作品は作品として、作者と作品は一応、切り離して考えることが多いのだが、短歌では、作者と作品を一体のものとして考える傾向があるようだ。/五七五七七の表現形式がそれを要求するというのなら、一〇〇〇年以上に渡る古典和歌の歴史は何だったというのか」をプロローグの形で引用しておいた。第九歌集『うたがたり』の「あとがき」であるが、さらに「そこで気がついたのだが、私の目の前には、少数の方々を除き、ほとんど人が手を入れていない広大な沃野、作者からは自立した作品を生むべき沃野が残されているのである。」と続く。これも歌論のところで引用しておいた。もともと「私にとって、詩歌は現実の仮象を越えるためにある。」(第一歌集『たましいの秋』)や「私の短歌に私の現実は登場しない。」(私家版歌集『タタの星祭』)という発言からも、出発の当初から一般の作者と違っていた。第九歌集『うたがたり』に至って劇的な変化が到来したわけではない。そうした意味においては沃野と信じて、未開の土地を一人で耕してきた、その作物、私の数えたところでは六〇五〇首を、歌人・小谷博泰の功績としてあげることに躊躇しない。
「一〇〇〇年以上に渡る古典和歌の歴史は何だったというのか」。と、いうことは近代短歌の歴史を見直すということでもある。私の問題意識とリンクさせるならば、日本語の歴史(古代語と近代語)、歴史的仮名遣い(定家受難の仮名遣い)、和歌と狂歌(戯作文学としての天明狂歌は含まない)が議論の機会を待っている。
時代は変わりつつある。いや変わらなければならない。
六 さいごに
百首の歌を鑑賞することにした。本文に引用した作品を含めて二百首以上になった。それでも十分ということはない。何度も捲っていると迷う歌も多い。チェックしたが、付箋を貼らなかったばかりに埋没して、出てこない歌もある。逆に付箋を貼りすぎて、わからなくなった作品もある。「あとがき」を書いていて、そんな歌と出会った。優柔不断な思いを記念して、一部だが、ここに書き留めておくことにする。
このとびらひらけば村のはずれにて過去世の妻がはたを織る音
第二歌集『みずいろ迷宮』九三頁
舌だけが生き残りたりいま磯をなめてゐるのはわが舌である
第四歌集『α階のS』一七七頁
なお、この原稿をチェックしているときに第十四歌集『時をとぶ町』が届いた。第十三歌集『河口域の精霊たち』の奥付を見ると今年の一月二十五日である。いやはや凄い。新歌集に追い越されてしまった。というわけで既刊歌集を網羅する鑑賞本ではなくなったが、第一歌集から第十三歌集までの鑑賞本として、お読み頂ければ幸甚である。
令和二(二〇二〇)年九月二日 兎月庵 𠮷岡生夫
|