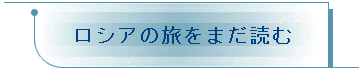部屋に戻ると、一人客が乗ってきていた。アゼルバイジャン人のセイドである。年は30程度であろうか。国後島で兵役訓練をしてきた帰りだと言う。この列車では私と同じイルクーツクまで行き、最終的には彼の故郷であるアゼルバイジャンの首都、バクーへ行くらしい。セイドは英語を喋れないので、以後バディムにより訳してもらうことになった。
部屋に戻ると、一人客が乗ってきていた。アゼルバイジャン人のセイドである。年は30程度であろうか。国後島で兵役訓練をしてきた帰りだと言う。この列車では私と同じイルクーツクまで行き、最終的には彼の故郷であるアゼルバイジャンの首都、バクーへ行くらしい。セイドは英語を喋れないので、以後バディムにより訳してもらうことになった。
列車はハバロフスクを後にする。街外れでシベリア号は全長 2.5キロに及ぶ長大な鉄橋に差しかかる。そう、アムール川である。日本にも冬になると流氷がくるが、それはこのアムール川から流れ出る大量の淡水によってもたらされる。凍りついて一面真っ白の川を望んでみてもまるで海のようである。老朽化もささやかれている1916年製のアムール川鉄橋をシベリア号はゆっくり渡り終えると、急にスピードを上げた。
単線だった橋を渡り終えて複線に戻ると、ウラジオストク方面へ向かう貨物列車が一本の線路上に3~4本数珠繋ぎで信号待ちしていた。シベリア鉄道は貨物輸送が主体だが、単線のこの橋が輸送力アップのネックになっているという噂は確かに合点が行く。
小さな駅ビラを17時57分に発車するとシベリア号は急に山深い所へ分け入るようになってきた。これからイルクーツクあたりまで鬱蒼としたタイガ(針葉樹林体)の中を進むことになる。
陽が暮れて山の端が赤く染まっている。手前の空はすっかり暗くなっているが、黒と言うよりはコバルトブルーである。それらを水滴の凍り付いた二重窓のガラスを通して見ると、絵画のように思える。腐り掛けた木の窓枠も、この時ばかりは幾星霜も年月を重ねた額縁のようにさえ見えるから不思議である。
次のアルハラに着くころにはモスクワとの時差は7時間から6時間に縮まるので、時計を1時間戻しておく。1時間得した気分である。この作業はウラジオストクからモスクワに着くまで7回繰り返される。1日1時間時差が縮まり、終点モスクワでその差は当然だが0時間となる。なんとなく旅をしている気をかきたてられる。
夕食はバディムがご馳走してくれた。メニューはパサパサのソバの実と、パン、チキン、それにおばあさん手製の大きいピクルスであった。ピクルスは美味しかったが、ボソボソなそばの実などはロシアの現状を現しているのでような気もする。
アゼルバイジャン人のセイドは音楽好きだ。コンパートメント備え付けのBGMのボリュームを上げて、エレキギターを引く真似をして見せたりするから騒々しいのなんの。おまけに僕に
「パスポート見せてくれ」
「日本の金はどういうのだ。できれば札がいい」
とか言ってくるのでこちらも多少の警戒心を抱きつつあった。諸外国同様、ロシアでも日本人は狙われるんだろう。後でバディムに
「日本では平和だろうが、ロシアは違う。金やパスポートを見せろと言われても、そんなものない、とシラを切るんだ。絶対見せないように」
と念を押された。
〈危機一髪〉
日付は変わり3月3日午前0時。ベッドの通路側に腰掛けていると、通路から刃わたり10センチを越えるナイフがスーッと出てきた…。
「ウォーッ!!! ヤバイッ!」
心の中で叫んだ。声にならないとはこういう事なのか。ついに覚悟する時が来たようだ。その間一秒に満たないだろう。しかし、最悪の場合の対応策についてずいぶん思いを巡らしたように思う。と、次の瞬間セイドが顔を出して、ニターッ…
「キタイスキー、キタイスキー」(キタイスキー:中国製の意)
とハシャぐ。多分ポリスから借りてきたのだろう。
「おい、てめえー。ざけんなよっ!」
心の中でつぶやいた。冗談にしては強力すぎた。その晩は厳戒体制で就寝。
〈ボラれ自慢〉
3月1日、9時30分起床。今日も白銀の大地が眩しい。スコボロディノに10時07分到着。スコボロディノはフライパンという意味だとバディムが教えてくれた。ホームへ買い出しに降りてみる。
シベリア鉄道では長距離列車が駅に着くたびに近所のおばちゃんがピロシキやジュース、ふかしたジャガイモを売りにくる。必ずどこの駅にもアイスクリームがあるので、ロシア人はかなりのアイスクリーム好きだろう。ペリメニと呼ばれるロシア風水ギョウザがあったので購入する。本当はジュースも買いたかったが、バディムが値段を聞くと九〇〇〇ルーブルという答えが返ってきて、
「普通の街の店ではあんなの五〇〇〇ルーブルだ。買わないほうがいい。飲み物はぼくの 紅茶でも飲んだほうがいい」
と言う。ロシア号では驚くほどに食べ物、飲み物の所有が明確でない。他人の飲み物も食べ物も結構勝手に飲む(アゼルバイジャン人のセイドだけかも知れないが)。元来、歓待好きの気質もその所以だろうか。しかし、まだその感覚に慣れない僕は自分の飲み物を確保しておきたい。日本から持参したコーヒーはスティックタイプだったので、セイドに数回飲まれて無くなってしまったし。
ペリメニはまずかった。ご丁寧にペリメニ1個につき1個の割合で小石が混ざっている。バディムも1個食べたが、
「おばあちゃんのペリメニの方が美味しい」
と一言。
ペリメニだけでは腹の虫が収まらず、私は一人食堂車へ向かった。食堂車では昨日と同じおばちゃんが注文を取った。昨日と同じ食べ物を、という意思を何とか伝えると
「サラダはどうか?」
とおばちゃんが勧める。野菜はこちらへ来てから食べていないので、躊躇せずに頼んだ。 決して上等とは言えないが、スープはボルシチだった。サラダも思ったよりは新鮮なレタスが盛り付けられていた。勘定を済ます時、ついでに近くにあるペットボトルに入ったジュースも買おうとした。おばさんは「それよりこっちがいい」という感じの手招きをして、冷蔵庫から冷えてるジュースを出した。9000ルーブルと高いがやむを得ない。
部屋へ戻ると、バディムが
「食堂車の領収証を見せてくれないか」
と言う。何のことかわからないが見せてみると、バディムは「やっぱり」という表情を しながら言った。
「昨日の昼に食べたのと同じ料理は正規料金だが、今日付け加えたサラダの料金は完全に高く取っているよ」
と言う。確かにサラダの値段が他のメニューより一桁多い。さらにバディムは私の買ってきたジュースについても「飲ませてくれないか」と言ってきた。差し出すと、まず蓋がすでに開いていることを示した。続いてジュースを飲んでみて、
「ケイーチ、これもそうだ。蓋が開けてあるから不審に思ったけど、やっぱり水で薄めてある」
と言う。なんだか探偵気分になってくる。
バディムは誤解無きよう僕の日露辞典を示して言葉を選びつつ
「同じロシア国民として、君たち外国人旅行者をだまし嘲笑う者がいることを恥じ入っている。申し訳ない。今後、買い物や食堂車に行くときは僕もついていくから」
と言った。昨日の昼食でバディムが食堂車へつきあってくれたときも、彼は何も食べずにメニューばかり見ていた。それはこんな事態を予期してのことだったのだ。
14時半、エロフェイ・パブロビチを出発すると、おすましちゃんが掃除機を引きずってやってきた。掃除の時間である。椅子の下も念入りに掃除してくれる。その後、バディムがオレンジをくれた。ビタミン不足の折り、その甘さもまた格別だった。
アマザル16時18分着。デッキに立つ列車乗務員と思しき男女のところに人だかりができた。闇両替か? 写真を思い切り撮ったが、咎められなかった。ただの商売か?
17時半、ふと線路際のモスクワ起点のキロポストを見ると6951キロとなっている。ウラジオストクからモスクワまで9297キロ。やっと4分の1に達したわけだ。
一時、曇が出てきたが空は再び晴れて夕焼け色に染まりつつある。今日は、車窓から地平線を望むことも無く、ひたすらタイガの中を走り続けてきた。もうすぐ一日が暮れる。
モゴチャ18時12分到着。高台の駅からは町並みが見渡せるが、どこかに似ている。バディムが
「ここでは金がたくさん取れる。産出量はロシア全土の4分の1にも達する」
と教えてくれた。
この雰囲気は炭鉱住宅の立ち並ぶ夕張と似ていたのか…。
15分間の停車中にバディムと一緒にパンを買い、今後は食堂車を避けることにした。
ところで冬は夜長という感があるが、どうもこちらでは違う。この日は19時半を回った頃にやっと日没となった。今日もまた、美しい夕焼けであった。
〈そして、バイカル〉
明けて3月2日、グウタラを払拭して8時前に起床した。バディムと一緒にチタ駅で散歩をしようと言っていたのだ。窓から外を眺めると、もう町中に入っている。時折、小さな駅を通り過ぎるが、ホームには通勤客が溢れている。まだ陽は昇ってなく寒そうだ。誰もがコートをしっかり身にまとっている。時折、車窓に建築中の家が見える。バディムが「Good
life is good house. Bad life is bad house. 」
と話した。当たり前と言ってしまえばそれまでだが、ロシアは貧困の差が著しいらしい。
ニューリッチと呼ばれる富豪は日本人でさえも想像のつかない豪勢な生活を送っている。当然、ニューリッチを狙った殺人も大幅に増加しており、依頼殺人という事件も珍しくなくなっている。こうした状況に彼も不安を感じているのだろうか。
8時2分、チタに到着した。厳密には「チタⅡ」という駅で、「チタⅠ」はバディムによると軍事関係のトップシークレットの駅のようである。そのような街にあるチタⅡ駅で写真を撮っていいのかバディムにたずねると
「そんなの、全く問題ない」
と言う。ロシアの駅での撮影禁止も過去の話しとなったようだ。
薄曇りのチタはとても寒い。と言ってもマイナス二〇℃くらいのようだ。今回の旅はマイナス四〇℃近くを覚悟していたので、やや拍子抜けとも言える。薄暗い地下道を抜け、駅前へ出る。さすがに人影はまばらで、大きな電光掲示の時計がモスクワ時間を示しているのが目立つのみ。薄氷が地面を覆い、マンホールの蓋はなぜか半開き。ロータリーには車が意外と数多く停車しているが、内陸部に入ったこともあって日本車はないようである。 さすがに、バディムも寒いらしく急いで退散した。
チタを発車してしばらくすると日が差してきた。右手には氷結した湖が広がり、多くの人が氷に穴を開けて釣りに興じている。バディムに湖があることを知らせると、とても小さい湖だからと関心を示さない。とは言え、日本ならば大きい湖だ。
おすましちゃんが掃除にやってきた。掃除している写真を撮らせてもらうと、
「東京から写真を送ってもらわなくちゃね」
と言って、いつもの高笑いではなくクスクスッと笑った。
車窓はなだらかな丘陵が続く。夏は一面の麦畑になるとバディムが教えてくれる。とその時、貨物列車が擦れ違う。
「ケイーチ、タンクだ!」
擦れ違う貨物列車には数台の戦車が積載されている。彼は私の露和辞典を開いて「市民紛争」という単語を指差し、肩をすくめた。
列車内の生活も飽きがくる。バディムは中国製テトリスを貸してくれたり、ロシアのことを話してくれた。シベリア鉄道のチャイコフスカヤ駅やメンデレエボ駅はそれぞれチャイコフスキーとメンデレエフに由来するとか、ロシアの民族は
150を越え、各々が言語を持っていること、オイミャコンでは氷点下73℃の世界最低気温の記録を持っており、窓ガラスも
割れてしまったこととかを教えてもらった。僕も富士山や味噌汁のことを話した。「ケイーチ、君は富士山登ったことはあるの?」
「いや、ない。頂上はあんまり綺麗じゃないみたいだしね」
などと登ったこともないのに、知ったかぶっていた。
そうした話題のうち唯一、彼が理解できないことは僕がなぜ冬のシベリアを選び旅をしているかということだった。余計なお世話だと言いたいところだが、同じ部屋になった仲間だし教えてあげよう。
「北国へは冬に、南国には夏に行く。それが俺のモットーだ!」
言おうとして気付いた。こんなの日本人にしか通用しない「さすらいの旅人」系の理由だ。彼に通じそうにない。
『世界一長距離を走る列車に乗るために来た』『ロシア美女に会いに来た』『傷心旅行だ』『男を磨く旅だ!』
瞬時に浮かんでは消えていき、ついに口から出た言葉は
「シベリアは冬が一番きれいだからだ」
しかし、バディムは
「夏の方がずっときれいだ」
と言い、冬に来たとは気の毒だ、という感じである。同情しなくていいよぉ。
そうこう話しているうちにモスクワとの時差は5時間に縮まり、14時14分シベリア号はペトロフスキー・ザボードに滑りこんだ。ここでパンを買うことにする。駅のキオスクで、
「ケイーチ、車掌からパンを買ってきてくれと言われたんだけれど、申し訳ないが彼女らの分を立て替えてくれないか」
と言うので、1200ルーブルを立て替えた。
列車へ戻ると、すぐにおすましちゃんがコンパートメントへ来て、一言
「ドルーグ!」
ニコッと笑みを浮かべてキッチリ一、二〇〇ルーブルを返してくれた。ドルーグとは日本語で言うと「親友」にあてはまるようだ。これから彼女のことを「おすましちゃん」ではなく「親友」と呼ぼう。
16時。ウラン・ウデが近づいてきた。ウラン・ウデはブリャート自治共和国の首都であり、モンゴルの首都ウランバートルを通り中国へ抜ける鉄路とのジャンクションでもある。植生もそれまでのタイガからステップへと変わり、モンゴルの草原を彷彿とさせる大地を列車は行く。窓に額をつけて列車の先頭を見ると機関車が見える。軽快なレールを刻む音を聞きながら、ふと列車も広大な平原を走る馬のように思えた。
16時34分、ウラン・ウデ到着。ここブリャート自治共和国住民の多くはブリャート人と呼ばれるモンゴロイド系民族で構成されており、一見して日本人と見分けることは難しい。そんな妙な雰囲気のホームで車内食用のインスタントラーメンを購入する。ふと金色の硬貨を出された。ロシア硬貨との初めての出会いである。
100ルーブル未満は切り捨てられることが多かったが、初めて50ルーブル硬貨と出会った。激しいインフレの中、硬貨は金属であるから、額面より実質価値の方が高く、多くが潰されてしまったのであろうか。
コンパートメントへ戻ると、新たに客が増えていた。人の良さそうなロシア人青年である。
へぼロシア語で挨拶した。
「ズドラーストヴィチェ。ヤー ケイイチ。ヤー イズ ヤポーニィ(始めまして。ケイイチって言いますす。日本から来ました)」
彼はニコッとうなづいてからロシア語を話した。以心伝心なのか、「上手だ」と聞き取れた。
彼はランディン=アレキサンドル。徴兵中の身だが、休暇を利用してノヴォシビルスクの友人に会いに行くと言う。見せてもらった兵役登録手帳のようなものから1970年生まれとわかる。私より2歳年上である。残念ながら英語は喋れない。しかし、バディムに教えてもらったトランプゲーム「ドラーク(馬鹿者の意)」をやりながら楽しい一時を過ごす。
夕日もかなり暮れた19時半、セイドが賑やかにコンパートメントに戻ってきた。車窓右手にバイカル湖が現れたのである。この時ばかりは普段部屋に閉じこもり気味の他の部屋の客もバイカル湖を見ようと通路に出てきた。バイカル湖が見えてくると下車するイルクーツクはもうすぐだと思ってしまうが、イルクーツクまであと5時間はかかる。さすが世界最大の湖である。
外が闇に包まれると、さすがにそれ以上見てもいられない。再び、トランプに興じる。しばらくして、セイドがバディムとアレキサンドルに何やら相談し始めた。そしてバディムが「セイドへ4000ルーブル払ってくれ」と言う。さすがになぜ払うのかを聞き返すと、これからロシアの別れの儀式をするという(儀式は大袈裟だが)。「ナ・ポソショーク」と呼ばれ、シャンパンなどで乾杯をするそうである。割勘でシャンパンを買い、それぞれのコップに分けて、最後の夜に乾杯となった。
22時、バイカル湖畔の町、スリュジャンカ到着。ホームへ降りると満天の星空が広がった。オリオン座を見つけ、
「オリオン座から見ると、僕の移動した距離なんてわずかなものだろうな…」
とふと考えてしまう。こんな夜遅くでもホームにはバイカル湖で獲れたと思われる魚を売りにおばさんたちが集まっている。しかし、売れ行きは芳しくないようである。きっと生魚なのが原因だ。車内で食べられないしね。
20分停車の後、列車は次のイルクーツクへ向けて走り始めた。客車の通路からアレキサンドルと一緒に外を眺める。バイカル湖が遠ざかり列車は徐々に勾配を上がっていく。眼下には暖かそうな明りの点った家が時折一軒、二軒と現れては消えていく。それはどこかで昔見たような、あるいは夢の世界で出会ったのかもしれない、心暖まる風景だった。アレキサンドルも無言でその家々を目で追っている。彼の気持ちもまた、言葉は交わさなくとも何となくわかった。
部屋に戻りしばらくすると、ポリスのスラヴァが、
「ケイーチ、Stand
up! drink Vodka.」
ウォッカを飲もうと誘ってきた。バディムは心配そうだが、スラヴァに断るのも悪いかな、と思い、バディムに日露辞典で『ごまかす』という単語を見せて部屋を出た。
ポリスの部屋にはスラヴァともう一人の警官、そしてセイドの3人がいた。まずはナ・ポソショークに従ってシャンパンをグラス一杯一気飲みとなった。あまり、ガンガン飲むとロクなことがなさそうなので、「僕は酒だめっす」という感じで一気飲み後に咳込んでみせた。しかし、逆にそれが受けてしまい宴は盛り上がっていった。
ウラジオストクからずっとニコリともしなかったもう一人の年配の警官が珍しくニコニコしながら、
「Where are you from? 」
とか聞いてくる。しばらくは平和だったが、空気が徐々に怪しくなってきた。スラヴァが「ケイーチ! 君の100US$を僕のルーブルと交換してくれ」
と言ってきた。ついにやってきた闇両替。しかし、当然法律違反なので
「出国時に両替のレシートを提示しなくてはならないので、闇両替はできない」
と鉄則を述べ断った。しかし、それでもなお彼は引き下がる。大体、警官と闇両替なんて聞いたことがない。ひょっとするとオトリ捜査かも知れない。ロシアで逮捕されたらタイガの奥地に抑留されそうだし、たまったもんじゃない。
セイドが最悪のタイミングで
「日本円を見せてくれ」
と言ってくる。しかし、この状況で見せたらスラヴァが
「USドルじゃなくてJapanese Yenでもいい」
などと言うに決まっている。
「僕は日本円など持っていない」
と言うと、セイドは
「この前、日本の金を見せてくれたじゃないか」
と突っ込んでくる。しまいには時計の交換を求められ始め、徐々に袋小路に追い込まれる。バディムの忠告に従っていれば良かったかも知れない。話題を切り替えようとはぐらかしても、スラヴァが
「Keiichi, listen to me.」
と唾を飛ばしてくる。やがて、
「お前らいい加減にしろ」
バディムが現れた。
「ケイーチ、カモン!」
助けられるとは我ながら情けないが渡りに船である。バディムは
「結構、酒を飲んだだろ。飲みやすいけど40度位あるんだぞ」
と言いながら僕をデッキに連れていき
「深呼吸しろ」
と促した。
バディムに「寝てるフリしてろ」、と言われ横になっていると、「親友」とペアで乗務している車掌がやってきて、
「もうすぐイルクーツクよ」
と言ったのかわからないが、ニコリと切符を返してくれた。
日付が変わり3月3日午前0時40分、列車はイルクーツクに到着した。ここでもトランスファーを頼んだのだが、バディムは深夜到着のイルクーツクでトランスファーが来なかった場合、一人でホテルまでホテルまで歩くのは危険なことこの上ない、と繰り返していたし、迎えにくるであろうインツーリスト職員のことも信用していないようだった。幸いにもしっかりとしたインツーリスト(旧国営旅行社)職員が出迎えてくれた。バディムも「彼はグッドマンだ」と安心してくれた。僕もホッとした。
アレキサンドルとスラヴァ、セイド、そして大変世話になったバディムに握手をして別れを告げる。スラヴァやセイドとは「My
Friend」などと言って別れた。やや腹のたっていた僕はあまり言葉を交わさなかったが、不器用な彼らを徹底的に憎むことはできなかった。「親友」の車掌は就寝中のようで、さよならを言えず心残りだ。
クセのある連中ばかりのシベリア号の3泊だった。地下道へ降りる重い木戸を開けながら少し振り向き別れの手を上げた。
インツーリストの黄色いバスに乗り込んで待っていると、2人の同い年くらいの日本人男女が来た。ウラジオストク駅で見かけた二人だったが、シベリア号で別の車両に乗っていたようである。久々に「こんばんは」と交わすと、やっと緊張感が緩んだ。
その晩は「ホテル・インツーリスト」に泊まった。ホテルの窓を開けると冷たい外気が入ってきた。深夜のアンガラ川は湖のように水を湛え、水面に街灯がゆらめいている。イルクーツクの空気は透き通っているようだった。