











決戦は金曜日〜SIDE:V〜
君に一番近い場所












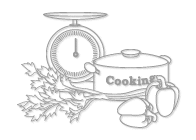
聖なる夜に、永遠の愛を誓い合った二人が、今、また危機を迎えようとしていた。
「どうしよう」
「どうしたらいいんだ」
二人は別々の場所で、同時に同じような言葉を口にしていた。






喧嘩をした。
些細な喧嘩だった。
学校近くの公園でいつものようにリョーマが部活を終えるのを手塚が待ち、束の間の甘い時間を過ごしている最中のことだった。
バレンタインデーを前にしての週末を、どちらの家で過ごすかという話になり、二人は相手を自分の家に招くと言って譲らなかったのだ。
「いつも国光の家だから、たまにはオレの家に泊まってよ」
「母がお前に会いたいと言っているんだ。それに…」
言いかけて口籠もる手塚に、リョーマは不審げな視線を向ける。
「それに?何?」
「…………」
少し躊躇い、口を開き、またひき結んで、手塚は低く唸った。
「……来てくれればわかる」
「なにそれ」
リョーマはつんと唇を尖らせた。
「オレの家に泊まりたくないんスか?」
「そう言うわけではない……とにかく、いつものように、来てくれないか」
「ヤダ」
上目遣いで手塚をじっと見てから、リョーマは立ち上がった。
「リョーマ?」
「今日は帰るっス。明日から校内戦あるし」
「………」
溜息を吐いて黙ったまま立ち上がる手塚を見上げ、リョーマは眉を寄せた。
そのまま、ほとんど口もきかずに別れて家に帰ってから、リョーマは少しだけ後悔した。
(なんか……オレに見せたいものでもあったのかな……)
恋人として手塚と深く付き合うようになって、リョーマは手塚が思った以上に不器用であることに気付いた。
思っていることをなかなか口にしないのはしょっちゅうだし、自分で何でも片づけようとするところも、ある種の不器用さだと思う。
甘い時間を過ごしている時は赤面するような台詞をサラッと言うくせに、困っていたり、怒っていたり、そして悲しんだりしている時、手塚はその想いを滅多に口にはしない。
(でもオレだって……たまにはアンタに……)
ベッドに仰向けになりながらリョーマは唇を噛んだ。
日本のバレンタインデーは、なぜか『女性から男性へ愛を告白する日』とされているが、アメリカ育ちのリョーマの中ではバレンタインデーはシンプルに『愛の日』であって、様々な愛と感謝の気持ちを、大切な人に贈る日である。
だから。
手塚を家に招いて、寛いでもらえたらと思っていた。
そのために、従姉の菜々子から少しだけ料理も習った。
手塚が泊まりに来てくれている間は、すべて自分で、手塚のために動きたかった。
「だって、いつも貰ってばっかだし……」
手塚にはいろいろなものを与えられていると思う。
愛情、と簡単に一言で言い表せないような温かな深い想いを、逢うたびに手塚は、惜しげもなくリョーマに注ぎ込んでくれる。
二人の始まり方がよくなかったせいか、本当の意味で想いが通じ合っている今、手塚は悉くリョーマを甘やかす。
それが嫌だとは思わないが、あまりに大事にされすぎて、時折怖くなるのだ。
もちろん、手塚の想いが、ではなく、自分自身の手塚への想いが。
大事にされすぎて、大事にされることに慣れてしまったら。
手塚はもう二度とリョーマを離さないと誓ってくれた。二度と、傷つけたりもしない、と。
だがそんなぬるま湯のような日々にリョーマは戸惑う。
手塚の優しさに、どっかりと胡座をかいてしまっていいのだろうか。
与えられる分の愛情を自分も手塚に与えてやりたいのに、その方法が、リョーマにはわからない。
日々の喜びを、ささやかなことへの感謝を、そして何よりもどんなに手塚を愛しているかを、どうすればきちんと手塚に伝えられるのかわからないのだ。
だからせめて、一日だけでも手塚のために、食事も、身の回りの世話も、すべてを自分の手でしてやりたかった。
「国光……」
愛しい名を口にした途端、リョーマの心に寂しさが湧き上がる。
「もっと……ちゃんと話して……わかってもらえばよかった……」
リョーマはそっと自分の唇に指先で触れてみる。
(今日は…キスもしてない…)
「………どうしよう…」
切なくて、堪らなくなって、リョーマは勢いよく身体を起こした。

リョーマと別れて家に帰り着いた手塚は、少し投げやりに鞄を投げ出し、どっかりとベッドに腰を下ろした。
(言い方が…まずかったのか…)
深く溜息を吐いて、制服のまま後ろに倒れ込む。
「怒らせてしまったな…」
自分が常日頃から言葉が足りないのは自覚していた。だが、そのことがこんなふうにリョーマとの関係に影を落としてしまうなんて思っていなかった。
「また……傷つけただろうか……」
そう呟いて、手塚はきつく眉を寄せる。
リョーマが愛しい。
愛しくて堪らない。
ただそれを伝えたいだけなのに、最初に深く傷つけてしまったこともあって、どこかで少し躊躇いがある。
二度と不安にさせないように真摯な想いを伝え続けようと思うのに、想いを伝える前に、熱い欲望のままにリョーマを抱いてしまう。
「言葉にせずに、行動に出てしまうとは……つくづく俺はケダモノだな……」
小さく苦笑して目を閉じる。
バレンタインに、リョーマに知らせたいことがあった。
べつにバレンタインデーを意識して狙ったわけではなかったが、ちょうど時期が合ったので、便乗することにした。
驚くリョーマの顔が見てみたかった。
そして、すぐに喜びに微笑んでくれるのを、見たかった。
そんな些細な演出を企んだ自分が、何やら情けなくなってきた。
別れ際の、リョーマの表情を思い出すと、胸が痛い。
こんなにも愛しているのに、リョーマの想いを受け取ろうとしなかった自分が嫌になる。
「どうしたらいいんだ」
正直に話せば、リョーマは許してくれるのだろうか。
「リョーマ…」
愛しい名を口にすると、想いが急激に膨れあがった。
逢いたい。
今すぐに逢って、ちゃんと話がしたい。
そうして微笑みながらあの柔らかな唇で名前を呼んで欲しい。
「………っ」
手塚は勢いよく身体を起こした。
迷ったがために、リョーマを失いそうになったあの日のことを、急に思い出してしまったのだ。
「俺はもう、迷ったりしない」
手塚はスッと立ち上がると、風のように部屋を出て行った。

あと数日で満月になりそうな月明かりの下を、リョーマは息を切らして走った。
手塚の家に行くと、「さっき急いでどこかに行っちゃったの」と言って、彩菜が苦笑していた。
リョーマは礼を言ってすぐに踵を返した。
たぶん。
手塚は自分に逢いに行こうとしてくれている。
同時に同じことを考えた二人は、同時に行動し、擦れ違ってしまったのだ。今頃手塚もリョーマの家で不在を告げられているかもしれない。
(アンタも…オレと話したいって、思ってくれたんだね…)
リョーマは嬉しくなって小さく微笑んだ。
「そうだ、携帯………あ」
何も考えずに家を飛び出したリョーマは、携帯電話の存在もすっかり忘れていたようで、ポケットには薄い財布しか入っていない。
「どうしよう」
このまま家に引き返しても、手塚と逢える可能性は低いかもしれない。
立ち止まってしばらく考えて、リョーマは答えを出した。
「あそこだ」
ひとつ深呼吸してから、少し向きを変え、『あの場所』を目指す。
(たぶん、アンタは来てくれる)
確証なんてなかった。
ただ、二人の心が通じ合っているなら、手塚も間違いなく『あの場所』に来てくれると思う。
「俺たちの始まりの場所だ…」
闇が濃くなると同時に温度を失ってゆく冷たい風の中を、リョーマはただ手塚のことだけを想いながら走り続けた。

春野台、高架下の区営コート。
もちろん人影もなく、今はコート入り口に鍵もかかっていて中には入れない。
「国光…」
息を切らしながら、リョーマは呟いた。
フェンス伝いにコートをぐるっと回ってみるが、手塚の姿がない。
「国光……国光!」
叫んだリョーマの声は、ちょうど通りかかった電車の音に掻き消された。
(いない………?)
リョーマはフェンスに縋りつき、そのままズルズルとしゃがみ込んだ。
「国光のバカ……っ!」
「こら」
蹲っているリョーマの耳に、大好きな声がするのと同時に足音が聞こえた。
「…………」
ゆっくりリョーマが顔を上げると、缶コーヒーを二つ手にした手塚が立っていた。
「まだ夜は冷えるのに、そんな薄着で…」
缶コーヒーをひとつ差し出しながら言う手塚をじっと見上げて、リョーマは、すん、と鼻を鳴らした。
「アンタも薄着じゃん」
受け取った暖かな缶コーヒーを両手で包んで、呟くようにリョーマが言う。
「そうだな」
小さく笑ってから、手塚はリョーマの横のフェンスに寄りかかった。
手にしたコーヒーを飲もうとはせず、二人とも手の中でコロコロと転がしている。
しばらく沈黙が続いたあとで、手塚が溜息を吐いた。リョーマの身体がビクッと震える。
「………すまなかった」
「……ううん、オレも、我が儘言った」
二人は顔を見合わせて、同時に「ごめん」と言った。
手塚がホッとしたようにふぅっと息を吐いて、リョーマの隣に腰を下ろす。
「……寒くないか?」
「アンタといれば気にしない」
「そうか」
クスッと小さく笑って、手塚は缶コーヒーの封を開けた。
一口飲んで、口を開く。
「……お前に、見せたいものがあるんだ」
「………え?」
「持ち運びが出来ないものだから…お前に家に来て欲しかった」
「………うん」
リョーマは内心「やっぱりそうだったのか」と思いながら、小さく頷いた。
「オレはね、アンタにオレの傍でのんびりして欲しかったんだ。菜々子さんに、ちょっとだけ料理も習ってさ……食べてくれないかなーって…」
「料理を?」
手塚が驚いたようにリョーマに視線を向ける。
その手塚をチラッと見遣って、リョーマは恥ずかしそうに俯いた。
「そんな…スゴイモノじゃないよ?パスタとか……トロトロのスクランブルエッグの作り方とか…」
「リョーマ……」
「ぁ…の、さ……だから、いつもアンタに嬉しいことばっかしてもらうから……たまにはオレも、アンタが喜ぶようなこと、したいな、って思って……」
口籠もるリョーマを見つめて手塚はふわりと微笑んだ。
「リョーマ」
そっと名を囁き、片手でリョーマの頭を引き寄せる。
「……ありがとう……リョーマ…」
「国光…」
リョーマは手塚をそっと見上げて微笑み、その肩に頭を乗せる。
「だから……オレのはいつでもアンタにしてあげられるし……今度の週末は、アンタの家に行くよ……行ってもいい?」
「もちろんだ……それに、それなら俺の家に来てから作ってくれないか?」
「ぁ……そっか…」
リョーマの髪を撫でながら手塚がクスッと笑ったので、リョーマは怪訝そうに手塚を見遣った。
「食材を二人で買ってから俺の家に行こう。金曜の夜から、来るだろう?」
「………うん」
「決まりだ」
手塚はぐっとリョーマを引き寄せて、小さく溜息を吐く。
「よかった…」
心底ホッとしたように言う手塚を、リョーマは不思議そうに見遣る。
「国光?」
「愛してる」
甘く囁きながら額にしっとりと口づけられる。
「だめだよ、国光」
「………え?」
拗ねたように言うリョーマに、手塚は小さく目を見開いた。
「恋人同士のキスは、マウス・トゥ・マウスでしょ?」
上目遣いに小さく睨まれて、手塚はほんのりと頬を染めた。
「………そうか……今日はまだしてなかったな…」
「……うん」
リョーマもほわりと頬を染める。
「愛してる、リョーマ」
「くにみ……」
名を呼ぶ途中で口づけられた。
そっと重ねられた唇はひどく冷たくて、もしかしたら手塚はもうずいぶん前からここにいたのではないかと、リョーマは思った。
何度も啄まれ、リョーマがもどかしげに甘い吐息を零すと深く口づけられた。
熱っぽく入り込む手塚の舌を奥まで迎え入れ、リョーマからも熱く舌を絡ませていく。
そのまま飽くことなく舌を絡めていると、堪えきれなくなったように手塚がそっと唇を離した。
「……これ以上はだめだ。理性が保たない」
「うん……」
リョーマも同意して小さく頷いた。
さすがに2月の夜に、こんなところでキスの先まで進むわけにはいかない。
「週末までお預けだ」
「ホントだね」
額を摺り合わせ、二人はクスクスと笑った。
「…アンタが何を見せてくれるのか、楽しみにしてるっス」
「ああ。期待していてくれて構わない」
「うん」
それからまた何度も口づけて、理性の限界を超える前に二人は身体を離した。
金曜の夜からの二人の時間を思えば、今は、何とか我慢できる。
そうして二人はゆっくりと立ち上がり、手をしっかりと繋いで歩き始めた。
「じゃあ、また明日」
「うん」
リョーマの家の前で、二人はそっと触れるだけの口づけを交わす。
「愛してる」
「オレも、愛してる」
微笑み合い、見つめ合ってから手塚が背を向けて歩き出す。
見えなくなるまで手塚の背中を見つめていたリョーマは、胸に込み上げる甘い幸福感に溜息を吐きながら、部屋に戻った。






金曜日。
部活を終えてから落ち合った二人は、そのままスーパーで買い物をして手塚の家に向かった。
「ちょっと待っていてくれ」
玄関にリョーマを立たせたまま手塚だけ奥に消えてゆく。
リョーマは少し怪訝そうに首を捻りながら、再び手塚が戻ってくるのを待った。
「いらっしゃい、越前くん!」
手塚よりも先に彩菜が顔を出し、いつものように満面の笑顔でリョーマを出迎えてくれる。
「またお邪魔します」
「ええ、もう、いつでも大歓迎よ!……国光、このまま行くの?」
背後の手塚を振り返って彩菜が問う。手塚は「はい」と頷いて、またシューズを履き始めた。
「えっと、どっか行くんスか?」
「ん。すぐそこだ。では母さん、また夕食の折に、こちらに戻ります」
「はいはい、ごゆっくり」
ニコニコと彩菜に見送られ、リョーマはまた怪訝そうに眉を寄せる。
玄関を出た手塚は、そのまま庭の方へ回り、その奥へと歩いてゆく。
(こっちの方に来るのは初めてだ…)
手塚家へは頻繁に訪れるものの、敷地全体がどれほどの広さなのか、リョーマは知らない。
手塚家は、実はとても由緒のある家柄で、遡れば将軍家に近しい位にあった武家の流れを汲んでいるらしかった。
そのことは何となく聴いてはいたものの、こうして庭の広さを実感すると、さすがのリョーマも圧倒される。
キョロキョロと周りを見回しながら手塚について歩いてゆくと、すぐに小さな家屋が目に入った。
「ここだ」
「え?なに、ここ」
「代々道場として使っていたところなんだが、祖父も、もうここは使わないと言ったんで、改装してもらった」
「改装?」
手塚が鍵を開けてドアを開けた。
「わ」
中に足を踏み入れ、リョーマは瞳を輝かせた。
「トレーニングルーム?」
ドアを開けてすぐ、板張りの、20畳もありそうなほど広い部屋に、様々な筋力トレーニングのための器具が置かれている。
手塚は頷いてさらに付け加える。
「この奥には10畳ほどの部屋もある。その奥にはキッチンも、シャワー付きの風呂も、トイレも、すべてついているぞ。茶室もあるしな」
「え」
「今すぐここで生活できるほど、すべて揃えてある」
手塚を見上げて、リョーマは大きく目を見開いた。
「国光……」
手塚の説明を聞きながら、リョーマの胸にあるひとつの想像が浮かんでいた。
それはとても幸せで、どんなに願っても、実現するのはもっとずっと先だろうと思っていたこと。
「まさか…」
「いつでも二人の生活を始められるぞ」
「あ………」
手塚はふわりと微笑んでから、シューズを脱ぎ、一段高くなっているフロアに上がった。
「もちろん、今すぐというわけにはいかないだろうが………俺の方の準備は出来た。いつお前が来ても構わないように、な」
「国光…」
「さあ」
手塚に手を差し伸べられ、リョーマは夢を見ているかのような心地でシューズを脱ぎ、手塚の手を取って、その横に立つ。
「コートだけはさすがに作れなかったが、壁打ちならこの裏で出来るようにしてもらった。どうだ?」
「すごい………」
そう言ったまま、リョーマは言葉を失った。
クリスマスの雪の夜、手塚と愛を誓い合ってから、ずっと夢に見ていた。
二人だけの時間を過ごせる、二人だけの場所。
それがこんなにもあっさりと手に入ってしまい、リョーマは夢でも見ているのではないかと、徐に頬をパチンと叩いてみた。
「いたっ」
「リョーマ?」
笑いながら手塚に覗き込まれ、リョーマは瞳を揺らしながら手塚を見上げる。
「どうしよう……」
「ん?」
「嬉しすぎて、なんて言ったらいいのか、わかんない」
呆然とするリョーマに、手塚は嬉しそうに微笑みかけた。
「少し早いが、俺からの、バレンタインの贈り物だ。気に入ってくれたか?」
手塚の言葉に頷き、だがリョーマは溜息を吐きながら俯いてしまった。
「………どうした?」
手塚が、少し慌てたようにリョーマを覗き込む。
リョーマは困ったふうに微笑んで手塚を見つめ、また溜息を吐いた。
「こんなスゴイモノ用意されちゃったら……オレがアンタにしてあげたいことなんか……全然……」
手塚は一瞬目を見開いてから、すぐにふわっと微笑んだ。
「……ばか」
優しくリョーマの身体を抱き締め、額を摺り合わせる。
「俺の方こそ、お前からいつもたくさんの幸せを貰っているのに、こんな形でしか感謝の気持ちを表現できなくて……すまない」
「何言ってンの」
リョーマは手にしていた荷物をそっと床に下ろし、手塚を抱き締めた。
「ありがとう、国光。二人で、もっと、幸せになろうね」
「………ああ」
手塚がぐっとリョーマを抱き締める。リョーマもさらに強く、手塚を抱き締め返した。
「愛してる、リョーマ」
「国光……国光……大好き……愛してる…」
二人は自然に唇を重ねてゆく。
チュッと音をさせて離れ、微笑み合い、また深く口づける。
「奥に行こう」
「………うん」
二人でぴったりと寄り添い合って、奥にある部屋へと向かう。
短い廊下を渡り、部屋に入って明かりを点けるとそこは洋室になっていて、部屋の隅にはセミダブルのベッドが置かれている。
ドアのすぐ横の壁は一面がクローゼットになっているらしく、タンスの類は視界には入らないようになっていた。部屋のさらに奥にはカウンター付きのキッチンまで設えてある。
たぶんキッチンの横のドアの向こうには洗面所や風呂などのある空間に繋がっているのだろう。
元々は武術の鍛錬の場であった道場だとは思えないほど、何もかもが洒落た造りになっていた。
だがそんなことは、今の二人にはどうでもよかった。
熱く見つめ合い、剥ぎ取るように互いの上衣を脱がせ、真新しいシーツに倒れ込む。
「リョーマ…」
「ぁ……国光……」
想いを交わし合う深い口づけが、互いの情欲を煽るそれに変わってゆく。
「リョーマ……もう……こんなに固くして……」
ズボンの上から優しく雄を撫でられてリョーマが身悶える。
「だって、早く欲しい……国光は……?」
「ああ、俺もお前が欲しい」
熱い吐息とともに口づけられ、リョーマのズボンのファスナーが下ろされる。
「ぁ………」
柔らかく、直に握り込まれてリョーマがビクビクと小さく痙攣を起こす。
そんなリョーマを見下ろしながら、手塚は嬉しそうに微笑んだ。
リョーマに触れると、今でも手塚は最初にリョーマを抱いた日のことがチラリと胸を掠める。
無理矢理抱いたわけではなかったが、リョーマにひどい傷を負わせた。身体にも、心にも。
それ以来手塚は、どんなにリョーマが欲しくても、どんなに切羽詰まっていたとしても、決して性急に身体を繋げたりはしない。できるだけローションを使ってリョーマの後孔を柔らかく解し、ゆっくりと身体を進めるのだ。
愛しくて、大切で、自分自身でさえ、リョーマを傷つける者は許せなかった。
だが最近、手塚は気付いたことがある。
身体を重ねるようになって間もない頃は、こうして組み敷くたびにリョーマの身体が少し強ばった。それはやはり「痛み」に対する本能的な恐怖で、本人もあまり自覚しないところで手塚を警戒していたのだろう。
しかし、何度も身体を重ねているうちに、リョーマの身体から強ばりが完全になくなっていた。
むしろ、手塚が触れるだけで甘くとろけるようになった気がする。
自分の身体に馴染み、妖艶になってゆくリョーマが、手塚は愛おしくてならなかった。
「も……いいよ、国光……早く……おねが……っ」
頬を上気させ、呼吸を乱しながらリョーマに強請られると、手塚の理性は崩壊を始める。
手塚が身体を起こしてズボンのファスナーを下ろし、きつく締め付けていた下着をズボンとともに押し下げると、解放された熱塊が勢いよく跳ね上がった。
リョーマの熱っぽい視線が、手塚の雄に向けられる。
「国光……」
リョーマは息を乱しながら身体を起こし、吸い寄せられるように手塚の熱塊に口づけた。
「リョーマ…」
「んっ、んっ」
鼻にかかった声を小さく漏らしながら、リョーマが手塚を口内で愛撫し始める。
舌を絡めるように先端を舐め回され、時折きつく吸い上げられ、淫猥な音を立てて口内を出し入れされると、手塚の理性は跡形もなく消し飛んだ。
「もういい、リョーマ」
「ぁ……」
リョーマから自身を取り上げ、手塚はすぐにリョーマを押し倒してその両足を担ぎ上げ、後孔に肉剣を突き立てた。
「ああっ」
ローションの滑りに助けられて一気に奥まで捩り込むと、リョーマが身体を仰け反らせてひくりと痙攣した。
「リョーマ…っ」
緩く腰を回し、リョーマが痛がらないことを確認すると、手塚の動きが熱っぽく大胆になる。
「あっ、あぁ、ぁっ、やっ、あ、んっ、あぁんっ」
手塚はリョーマの表情を見つめながら先端から根元までの抽挿をリズミカルに何度も繰り返し、時折意識して突き込む角度を変えてやるとリョーマの喘ぎが艶を増した。
「や、ぁんっ、いい……気持ち、いいよ……国光っ……ああっ」
「ああ……俺も…いい……リョーマ……」
リョーマの腰がベッドにつく暇も与えないほど突き上げ、抉り回し、音を立てて腰を叩きつける。
「やぁっ、あぁっ、あ、すごい、気持ちいいっ、いい……っ、国光っ……ひあっ」
「ん……っ」
奥深くまで捩り込んだところで一旦動きを止め、手塚は肩に担いでいたリョーマの脚を片方だけ下ろしてのし掛かった。
「あぁうっ!」
これ以上ないほどの奥まで手塚が届き、リョーマが艶めいた声で叫ぶ。
そのまま手塚がグリグリと腰を押しつけ、最奥を掻き回すように抉ってやると、リョーマは声も出せずに身体を痙攣させた。
そうしてさらに体重をかけて手塚が奥を抉り回してやると、リョーマは堪えきれずに激しく痙攣しながら熱液を噴き上げた。
「く…っ」
きつい締め付けに眉を寄せながら手塚がリョーマの耳朶に口づける。
「もう…イったのか?リョーマ…」
熱を込めて囁くと、リョーマが小さく声を発しながら身体を震わせ、最後の熱液を吐き出した。
「ごめ……国光……すごく……感じて……」
頬を真っ赤に染めて見つめてくるリョーマに、手塚の情欲が跳ね上がった。
手塚がまた大きく腰を振り始めるとリョーマは苦しそうに喘ぎ出す。
「すまない……止まらない……っ」
「ああっ、あぁっ、やっ、もっと……もっと…っ」
達した直後で弛緩しきっていたリョーマの身体が、手塚に突き上げられてすぐに快感を追い始めるのがわかった。
手塚の腹に押し潰されそうになりながら、リョーマの雄も完全に固く変形している。
「…どうした…?…いつもより、感じる…のか?」
突き上げ、抉り回しながら手塚が尋ねると、リョーマはうっすらと目を開けて、喘ぎながら恥ずかしそうに目を逸らした。
「んっ……感じる……だって……ここは……オレたち、だけ、の……あぁんっ」
「くっ」
リョーマにきつく締め上げられ、強い射精感が込み上げるのを、歯を食いしばって手塚は堪える。
「国光も……」
「え…?」
何とか射精を堪えた手塚の首に、リョーマが腕を回してきた。
「国光も、オレの中に…いっぱい出して……」
「…っ!……ばか…っ」
「え?…ああっ、やぁっ、ひ、あっ!」
どうしようもない激情が込み上げ、それに逆らうことなく手塚は激しくリョーマを揺さぶり始めた。
ガツンガツンと音をさせながら腰を叩きつけ、最奥を抉り回し、角度を変え、体位も少しずつ変えながら、思う様リョーマの身体を味わい、溺れる。
激しく揺さぶられ、腰をぶつけられてリョーマがまた熱液を迸らせる間も手塚の猛攻は収まらず、淫猥な粘着音と喘ぐような荒い呼吸音が部屋を満たし続けた。
手塚が肉食獣のような獰猛な瞳でリョーマの表情を覗き込むと、すでに意識の飛びかけているリョーマが、強い振動にガクガク揺れながら幸せそうに微笑む。
「国光…」
「リョーマ……」
ケダモノのようにリョーマを求めていた手塚の心に、苦しいほどの切なさと愛おしさが一気に込み上げた。
「リョーマ…!」
手塚があらん限りの力でリョーマを抱き締める。
「あぁっ!」
リョーマの艶めいた叫びを耳元で聴き、手塚の雄がリョーマの胎内で限界まで膨らんだ。
「くっ、あ……リョーマ、出すぞ…っ」
苦しげに宣言してから、手塚はリョーマの最奥で思い切り力み、射精し始める。
「んっ、ん……あぁ…っ…!」
「あ…国光……すごい……いっぱい、出て……」
自分の最奥で何度も力み続ける手塚の熱塊を、その動きに合わせてきつく締め上げてやりながら、リョーマはうっとりと嬉しそうに微笑んだ。
リョーマの直腸を自分の体液で満たし、長い長い絶頂が漸く収まった手塚は、深く息を吐きながらリョーマの上に倒れ込んだ。
「……大丈夫か?」
まだ荒い呼吸を整えようともせず、手塚がリョーマの耳元でそっと尋ねる。
「ん……大丈夫だけど……大丈夫じゃないかも…」
「え?」
リョーマの言葉に手塚が顔を上げ、心配そうに眉を寄せてリョーマを見つめた。
「……すまない……どこか、痛むのか?」
リョーマの胎内から自身を引き抜こうとする手塚を、リョーマは静かに引き留める。
「だめ……もっとしてくれないと、オレ、死んじゃうから……」
「………」
「このまま、もっと、して、国光…」
リョーマの言葉に目を見開いて、手塚が頬を染める。
「…こんなヤラシイオレは、嫌い?」
恥ずかしそうに頬を真っ赤に染めながら、リョーマは手塚から視線を逸らした。
「最初はちょっと怖かったのに……今は、もう、アンタに触れて欲しくて堪んない……いつも、アンタとこうすることばっか…考えちゃって……」
手塚は一瞬沈黙してから、ふわっと嬉しそうに微笑んだ。
「…まだまだ新婚だからな、俺たちは」
「し、新婚って……」
さらに頬を真っ赤にして小さく睨んでくるリョーマに、手塚は優しく口づけを贈る。
「ケダモノなのは俺だけじゃなかったと…思ってもいいのか?リョーマ」
「…うん、いいよ」
クスッと笑うリョーマに、手塚はもう一度口づけた。今度は、先程よりも深く舌を絡めて。
「んっ」
「…リョーマ…」
甘い声で名を呼ばれ、腰を動かされると、胎内を満たしている手塚の精液が攪拌され、泡立って溢れてくるのがリョーマにもわかった。
「あ……ぁ、国、み…つ……」
手塚に合わせてリョーマも腰を揺らしてやると、手塚の唇から熱い吐息が零れた。
「……あとで俺が風呂に入れてやる。食事も、向こうの家から運んできてやる。……だから、もっと……続けていいか?」
「…続けてくれないと、オレが死んじゃうって、言ったじゃん」
クスクスと笑っていたリョーマの微笑みが、妖艶な挑発を含み始める。
「大好き、国光……だからもっと…」
「もっと……?」
チュッと音をさせて口づけ、唇が触れるほど近くで手塚が尋ねる。
「もっと……どうして欲しいんだ?」
「ん……もっと……オレを溶かしてみせて……」
「……わかった」
手塚が深く口づけてくるのを、嬉しそうに微笑みながらリョーマが受け止める。
深く甘く舌を絡め、ほんの少し唇を離して見つめ合い、また口づけ合う。
繋がり合ったところから熱が広がり、二人は会話もせずに、自分からその熱に身を任せていった。
何度目かの吐精のあと、リョーマは微笑みながら意識を失うように眠りについてしまい、手塚は愛おしげにリョーマの髪を撫でながら飽くことなく恋人の寝顔を眺めていた。
しばらくして、ベッドサイドに置いてある電話が内線での着信を告げた。
手塚は時計を見て、内心「しまった」と思いつつ、リョーマを起こさないようにそっと腕を伸ばして受話器を取る。
「はい」
『国光、ご飯、テーブルの上に用意しておいたから、キリのいい時に取りに来なさい。そっちで食べるんでしょう?』
「あ、はい」
キリのいい時、と言われて手塚はドキリとする。
『いくら嬉しいからって、二人ともやりすぎはだめよ?』
「え?」
『特に越前くんは身体が細いんだから、無理させちゃ可哀相でしょ?』
「あ、あの…?」
『二人とも若いから夢中になっちゃって、時間も忘れて続けたいのはわかるけど、ご飯はちゃんと食べないと身体によくないわよ?』
「か、母さん!」
『なあに?』
何でもないことのように話す母親に、とうとう手塚は口を挟んだ。
「さっきから……何を……」
母親にはすべてがバレているのかと思い、手塚は全身から血の気が引いてゆく思いがした。
『何をって……貴方たち、夢中でトレーニングしているんでしょ?』
「は………?」
『あら、違うの?』
「いえ、そうです。二人でいろいろ話しながら、夢中でトレーニングをしています」
『そうでしょう?もう今日は遅いんだから、いい加減にしておきなさい。明日の朝もゆっくりでいいから、ちゃんと寝なさいよ?』
「はい」
『じゃ、お休みなさい』
「はい。ご心配おかけしてすみませんでした。おやすみなさい」
少しして切れた電話を置いてから、手塚は改めて時計を見上げた。
「11時か……」
リョーマとここに来てから、ザッと計算してもたっぷり五時間以上ノンストップでSEXしていたことになる。
(母さんは変に思わなかったんだろうか……?)
いくら新しいトレーニングルームを作って嬉しいからと言っても、夕飯もとらずにそんなに長くトレーニングしていると、本気で信じてくれているのだろうか。
(そういえば…)
電話が切れる直前、受話器の向こうで母がクスクスと笑っていたような気がする。
(まさか………やはり………)
リョーマを失いそうになった手塚に喝を入れてくれたのも母・彩菜だった。
あの時は深く考えはしなかったが、あの時点ですでに気付かれていたなら、手塚がここを自分用に改装して欲しいと願い出た『意味』もわかっているはずだ。
「……敵わないな、あの人には……」
深く溜息を吐いて苦笑すると、リョーマがもぞもぞと動いた。
「起きたのか?リョーマ?」
「……………」
手塚が覗き込むと、リョーマは静かに寝息を立てて眠っていた。
(今のうちに食事を運んでおくか……)
小さく溜息を吐いて静かにベッドを降り、手早く衣服を身につけて手塚は本宅へと向かった。
裏口へ回り、鍵を開けて直接キッチンに入った手塚は、テーブルの上に用意された大きなトレーの傍に手紙を見つけた。
その手紙に目を通して、手塚は小さく微笑む。
『疲れた時には甘い物がいいと思い、添えておきます』
トレーに視線を移すと、綺麗にラッピングされた小さな箱が隅の方に置いてあった。
包装紙には『 Happy Valentine 』の文字。
「ありがとうございます、母さん」
寝室の彩菜には聞こえないとわかっているが、静かに口に出して感謝を述べたくなった。
慎重にトレーを運び、手塚が部屋に戻ると、リョーマがゆっくりと身体を起こした。
「起きたか、リョーマ」
「………」
黙ったままじっと見つめてくるリョーマに、怪訝そうに眉を寄せながら手塚が近づく。
とりあえずトレーをキッチンへ運んでから、手塚は足早にリョーマのいるベッドに戻った。
「どうした?」
「…………」
「……怒っているのか?」
リョーマはふいっと手塚から視線を逸らしてベッドに潜り込む。
「リョーマ?」
チラッと手塚を見遣り、リョーマはボソッと呟いた。
「……また急にいなくなったら、離婚する」
目を丸くする手塚に、もう一度視線を向けてリョーマはほんのりと頬を染める。
「…なんてのは、ウソだけど、またやったら怒るから」
「………すまなかった」
どこか嬉しそうに微笑みながら謝る手塚に、リョーマはグッと言葉を詰まらせ、唇を尖らせる。
「夕飯を運んできたぞ。食べるか?」
「うん」
「待っていろ、今温めてやるから」
「…うん」
キッチンに向かう手塚を目で追っていたリョーマは、そっとベッドから降りて、上衣だけを羽織った。
だがすぐに戻ってきた手塚が、シャツ一枚羽織っただけでベッドに腰掛けているリョーマを見て眉を顰めた。
「なんて恰好をしているんだ」
「え?」
「風邪をひくぞ?」
「大丈夫。…なんスか?」
手塚が何かを持ってきたことに気付いて、リョーマは小さく微笑みながら手塚を見上げた。
「ん?ああ……母からこれを貰った」
「なに?」
手塚から手渡された小さな箱と手紙を見て、リョーマはほんのりと頬を染める。
「疲れた時、ね」
「………疲れた時、だ」
「開けていい?」
「ああ」
リョーマがラッピングを綺麗に剥がして箱を開けると、そこにはハート形のチョコレートが5つ入っていた。
「半分コ出来ないね」
「そうか?」
「だって…」
手塚はクスッと微笑んでリョーマの隣に腰を下ろし、箱を覗き込んだ。
「お前が二つ、俺が二つ」
「ほら、一個余るでしょ」
「一緒に食べればいいだろう?」
「え?」
リョーマが不思議そうに手塚を見つめると、手塚は箱からチョコレートをひとつ摘んで自分の口に放り込んだ。
「こうすればいい」
チョコレート含んだまま手塚がリョーマに口づける。
「ん……」
絡まり合う舌の間にチョコレートが転がり、互いの熱で溶かされてゆく。
チョコレートがすっかり解けてしまうまで舌を絡め合っていた二人は、そっと唇を離して微笑み合った。
「ねえ」
「ん?」
「他のも今みたいに半分コしたい」
上目遣いで見つめてくるリョーマに、一瞬目を見開いてから手塚はクスッと笑った。
「飯のあとで、な」
「うん」
リョーマの額にチュッと口づけてから、手塚はまたキッチンに入ってゆく。
手塚の背を見送り、もう一度手の中のチョコレートが入った箱を見つめて、リョーマは微笑んだ。
「もう、何もかも、大丈夫だ…」
リョーマを、いや、二人を不安にさせる物は、もう何もない。
二人の心がしっかりと結ばれていることはもちろんだが、自分たちを見守ってくれる存在がいることが、ひどく心強い。
例え、お互いがいれば他には何もいらないと思っていても、自分たちはまだまだ未熟で、二人きりでは乗り越えられない問題が、いつか必ず目の前に立ちはだかるのだろう。そんなときに、理解してくれる人がいると思うだけでも、何十倍もの心の力になるはずだ。
(幸せになるって、自分たちだけじゃなくて、周りのみんなごと、一緒に優しい気持ちになれることなんだ…)
「リョーマ、温まったぞ。こっちに来られるか?」
「ぁ、うん」
シチューのいい香りに腹の虫が目を覚ます。手にしていた小さな箱をそっとベッドサイドに置き、リョーマは手塚のもとへ小走りに向かった。
「国光」
後ろから手塚に抱きつくと、手塚が小さく笑う。
「ね…」
「ん?」
「…幸せだね」
呟くようにリョーマが言うと、手塚は穏やかな顔で振り返り、じっとリョーマを見つめてから、静かに頷いた。
「…感謝、しなくてはな。支えてくれる、たくさんの人たちに」
「うん」
多くを語り合わなくても、手塚が自分と同じことを思っていたと知り、リョーマは嬉しそうに微笑んだ。
「大好き、国光」
「ああ。愛してる、リョーマ」
見つめ合い、微笑み合って、そっと唇を寄せる。
「さあ、ずいぶん遅くなったが、夕飯にしよう」
「もうほとんど『夜食』だね」
「そうだな…これを食べたらもう少し頑張れそうだ」
「………えっち」
冗談か本気かわからない手塚の言葉に笑い合いながら、二人は暖かな夕食にありついた。
「今日って満月かな」
「いや、まだ少し欠けているだろう」
食事を終え、夜空を見上げなから二人はそっと寄り添う。
「ずっと、こうしていたいね」
「いや……それは無理かもしれないな」
「え」
手塚の言葉に驚いてリョーマが視線を向けると、そこには優しくて、熱い瞳があった。
「今すぐにでも、俺はお前をベッドに連れて行きたいんだが?」
「あ…」
頬を染めるリョーマをそっと抱き締めながら、手塚は熱い吐息を零す。
「………だめか?」
「だめじゃないよ」
二人は身体を離し、見つめ合い、微笑み合い、ゆっくりと唇を寄せてゆく。
本気で好きになれる人がいて、
その人も自分を好きでいてくれて、
周りに自分たちを支えてくれる人がいるからこそ
二人で寄り添って生きていくことが出来る。
こんなにも幸せなことがあろうか。
「愛してる、リョーマ」
「愛してる、国光」
月明かりに照らされた部屋の中を、二人の熱い吐息が満たしてゆく。
溢れるほどの幸せの中で、二人は飽くことなく互いを熱く求め合った。
その後、プロとして世界各地を飛び回ることになる二人だが、日本での生活は、すべてここで過ごすことになる。
だが二人にとって本当の『終の棲家』となったのは、互いの傍であったことは、言うまでもない。
完
掲示板はこちらから→
お手紙はこちらから→
20060216
ちょっとバレンタインには間に合いませんでした・・・