僕が小学校高学年だった頃、白熊と言われた熱血教師がいた。彼はテレビの学園ドラマに出てくる熱血教師のように熱かった。我が校では月に1度月末に清掃コンクールというものが開かれ学年ごとに教室のきれいさを競い、生徒会の審査を受けて最もきれいに部屋を掃除したクラスには賞状が贈られることになっていた。審査の日に、白熊はクラスのみんなを集め作戦を立て、窓のサンや黒板、教室の隅などの重要ポイントをいかにきれいに見せるかを話し合い、クラスみんなで清掃コンクールに向けて志気を高め、一致団結して掃除に取り組むムードを高めていった。当然、私達白熊のクラスは毎月のように優勝し、教室の掲示板に張られるクラスの賞状は増えていった。学年の最後にはずらっと並んだ10数枚の賞状が妙に誇らしかった。
 また、同じ学年の別のクラスには、うすのろと呼ばれる先生がいた。彼は清掃コンクールに向けてクラスを団結させ志気を高めることもなく、ホームルームの時間には、うすのろが一言、
また、同じ学年の別のクラスには、うすのろと呼ばれる先生がいた。彼は清掃コンクールに向けてクラスを団結させ志気を高めることもなく、ホームルームの時間には、うすのろが一言、
「さぁ、どうしよう。みんなどうしたい?」
と言ったっきりクラス全体が静まったまま長い沈黙が10秒・・20秒・・30秒・・と1分近く過ぎることもあり、生徒の誰かが何かを言うまで黙ったままのことが多かった。生徒の誰かが「コンクールなんてばかばかしい」と言えば、「そうか」と小さくつぶやいて、いつも通りの清掃しかしなかったり、誰かが「みんな頑張ろうよ」と言えば、「そうか、じゃあ、頑張るか」とつぶやいたり、とにかく自分の意見がない奴だった。
白熊のクラスはいつもイベントの主役だった。修学旅行先でのクラス対抗カヌー大会、飯ごうでのカレー対決、運動会や文化祭、白熊が仕切ってクラスが団結して動けば、いつも無敵だった。夏休みには毎日のように学校に来て、運動会の組体操の練習をした。隊列を組み、きちっと並んでの入場行進から始まり、横1列に並び、一糸乱れぬラインダンスをするため、朝9時半に集合し、朝10時から2時間練習をした後、1時間の昼食を入れて、夕方の4時まで練習が続いた。夏休み中の登校は正直きつかったし、登校のない日はひたすら夏休みの宿題に明け暮れた。塾の夏期講習に行かせようとしていた父母からは文句が出たが白熊は
「幼いうちからの偏差値教育や詰め込み教育は良くない!」
と、持論を展開しそれなりに上手く乗り切っていたようだ。夏休みが終わってからも、夕方6時まで残され行進やラインダンスの練習をさせられたのはかなりきつかったが、運動会本番では父母以外に地元の新聞社のカメラマンが何人か来て、大きな拍手をもらい先生や新聞社の人にほめられたのは嬉しかった。
うすのろのクラスも夏休み中、時々は白熊のクラスや他の同学年のクラスと共同でラインダンスの合同練習をしたが、塾があるとか忙しいとか親の手伝いとか家族旅行とかお腹が痛いとかで比較的簡単に休むことが出来た。白熊のクラスがほぼ全員参加している練習にうすのろのクラスは半分ほどしか参加していなかったため、みんなが一致団結してと言うよりもは4・5人の仲良しグループがいくつか集まってる雰囲気だった。
白熊は、自分が担任持ちの教師から、学年主任、教頭、校長にステップアップするための勉強にも熱心だった。資格試験を受け、人脈を広げ、不良少年の生活指導係をかってでて、小・中・高の生活指導の先生方による交流会・勉強会にも出席し、教職員の労働組合である日本教職員組合の活動にも熱心だった。当時、日本史の授業で太平洋戦争などをやっていると、与謝野晶子の詩などを引用しつつ、
「この時代には君たちぐらいの年齢の若者が戦争にかり出されて死んでいったんだ。この頃は『御国のために死んでこい』と言って君たちを戦場に送るのが良い親であり良い先生だとされたのだが、もし再びそのような時代が来ても先生は君たちに戦場を勧めない。その時には憲兵という軍人が学校の中にも入ってきて、先生の授業を教室の横のところに立って観ていて、もし、『戦争反対』とか『生きて帰ってこい』とか言ったら、すぐに飛んできて、ひっつかまえて、教壇から降ろされて、教師の免状剥奪されるんやけど、そんな状況になっても『人殺しは良くない』『君達は行かなくて良い』と言い続けて君達を守るぞ。だから、君達は天皇のための歌など歌わなくても良いし、旧日本帝国軍の旗など掲げなくても良い。」
と熱く語っていた。
職員会議などでも白熊は、君が代の斉唱や日の丸を上げることに対する反対運動の先頭に立っていた。そして、職員会議でよくつるし上げを食らっていたのは、うすのろだった。
「我が校の教職員は一致団結して日の丸や君が代に反対していく。その姿勢でほぼ決まっているのに反対しているのはあなただけだ。あなたは一体なにを言いたいんだ。」
白熊につるし上げられ、席を立ち1人孤立したまま何か発言をしようとしているうすのろは、いつもドモリがちだ。
「このような問題は・・・非常にデリケートな問題であり・・いちがいに・その・・なんと申しますか・・皆様方、個人としての心情もあることですし・・・・わたくしのような者が・・と申しましても・一概にその・・・非常にまあ・・こんなんな・その・わたくしといたしましては・・慎重の上にも慎重に・判断を差し控える所存で・・考慮させていただくという・・」
正直言って何を言ってるのか良く分からないし、物事をはっきり言ってる白熊の方が何十倍も筋が通ってる。うすのろが、うすのろと呼ばれるゆえんだ。
その頃までは卒業式に、君が代も日の丸もなく、校歌と校旗だけだったし、それが普通だったのだが、少しずつ状況は変わっていった。その年には文部省から各小・中・高校に卒業式や入学式には君が代を歌い日の丸を上げるよう指導が入った。卒業式の日、歌いたくない人は君が代を歌わなくて良いと指導した教師と、その教師を支持した教師13人が小学校を首になり、訴訟が起きていた。日本教職員組合の力が低下し、日の丸・君が代に反対する教師が徐々に隅の方に追いやられていった。
僕が小学校を卒業して3年後、白熊は日の丸・君が代推進運動の先頭に立ち、学校に日の丸と君が代を定着させた業績を買われて教頭になった。そして、うすのろは相変わらずヒラの教職員で、職員会議では白熊につるし上げを食らっている。
「我が校の教職員は一致団結して日の丸と君が代を推進していく。その姿勢でほぼ決まっているのに反対しているのはあなただけだ。あなたは一体なにを言いたいんだ。」
白熊につるし上げられ、席を立ち1人孤立したまま何か発言をしようとしているうすのろは、いまもドモリがちだ。
「このような問題は・・・非常にデリケートな問題であり・・いちがいに・その・・なんと申しますか・・皆様方、個人としての心情もあることですし・・・・わたくしのような者が・・と申しましても・一概にその・・・非常にまあ・・こんなんな・その・わたくしといたしましては・・慎重の上にも慎重に・判断を差し控える所存で・・考慮させていただくという・・ですが、様々な緊急を要する諸懸案につきましては、わたくしと致しましても・・緊急に検討をせざるをえない・・非常にいかんともしがたく・・。」
![]()
1993年冬。1955年から38年間続いた自民党政権がつぶれ、国会に新進・日本新党・さきがけの連合政権が誕生する。連合政権発足後、テレビ朝日の報道が与党自民党を批判的に扱い、日本新党や新党さきがけ、新進党などの新党ブームをあおったとの指摘が自民党から発生し、 報道局長が国会で証人喚問される。
「ニュースステーション」「朝まで生テレビ」「ドラえもん」この三つがテレビ朝日の看板番組だ。この三つの番組はどれもひどいものだが、特に偏ってるのが、ドラえもんだ。まったく、ドラえもんの現場をとらえていない。日常ぼく達は、テレビや雑誌、新聞といったマスコミを通じて情報を得、それが正しいことを前提に日常生活における判断を行っている。この事実は、マスコミが偏った情報を流し続けると、ぼく達の判断がいかに狂ってくるかを示している。
ぼくはごく普通の小学四年生だ。そしてほとんどの小学生がそうであるように、ドラえもんの身長が低いことに、何の疑問も持たず生活してきた。頭でっかちで、腰の低いドラえもんが、大きな顔をして歩いている。それが当然だった。
でもね、ドラえもんの背はじつはあんなに低くなかったのさ。だって不自然だろ?ドラえもんだけあんなに背が低いなんて!
そう。むかしのぼくなら、こんなことは言わなかった。あんなに頭が大きいと体が不安定なんじゃないかとか、逆さまにされるとあの短い手足じゃ自分で起き上がれないだろうとか。そんなこと考えもしなかった。ただそこに君がいて、金曜日の夕方になればいつでも会うことが出来る。そのことがまだ幼かったぼくにとって、とても自然なことに感じられた。ただ、それだけなんだ。
でも、今のぼくは違う。今のぼくは君の頭の大きさ、構造上の欠点、有り得るはずもない身体機能、これらは全部メディアによって伝えられるイメージだが、そういったことの矛盾を全部指摘できる。あのデカすぎる頭じゃ、のび太くんの家の狭い階段で頭がつっかえてしまうんじゃないかとか、頭に重心があると朝起き上がるときかなりの腹筋が必要だとか、あのままの手じゃ四次元ポケットまで手がとどかないんじゃないかとか、そういったテレビやコロコロコミックじゃ伝えられていない現実のドラえもんの姿をぼくは知っている。
現実を知らされていない人達というのは、ある意味幸せかもしれない。ぼく達にもそんな幸せな時代はあったし、ずっとあの頃のままでいた方が良かった。そういう指摘もあるだろう。けれども、ぼくはもう小学四年生だ。上級生としての大人の責任で、現実を知らされてない人達に、事実を伝えていく責任がぼくにはある。だから、多少耳の痛い話にはなるけど、みんなにも知ってもらいたいんだ。メディアは信じたくない事実よりも、信じたくなるような幻を伝えることもあるってこと。事実と幻が食い違っていたとき、どちらを信じれば良いのか。事実が幻を作ったのか、幻が事実を作ったのか。
例えば、メディアの中のドラえもんと現実のドラえもんが食い違っていたとき、どっちの君が本物で、どっちの君を信じれば良いのか、正直言って分からなくなる。ドラえもんを演じようとする君と、君を演じさせるメディアの中の君。合わせ鏡というより、スキャンダラスな私生活を演じる女優のどこまでが演技でどこからがプライベートな私生活なのか分からなくなった状態に似ている。真面目な銀行員を演じきれなくなった銀行員、良き母良き妻を演じ切れなくなった女性。きっと君はもう自分を演じれなくなったんだよね。
思えば、君とぼくとは長い付き合いだった。カベに はった、君のポスター。日に焼けて端の方が黄色く変色している。君の映画を観に行った日、パパが買ってくれたお気に入りの一枚サ。こいつは今でもぼくの宝物なんだ。
ぼくが小学校にあがる日、ママが買ってくれた「小学一年生入学準備号」に、君のミニチュアが付いていた。君は手をバタバタ上下に動かし、目を白黒させながら、おどけて机の上を走ってくれたよね。あの日のぼくはもう小学四年生になりました。
夏になれば、ゆかたを着て、うちわをあおぎ、打ち上げ花火を眺めながら、「夏だ一番!ドラえもん祭り」に酔いしれた。パパはビールを片手に、ぼくはコーヒー牛乳を飲みながら、君の一挙手一投足に、一喜一憂したものだ。夏が終わり、秋になれば、「秋だ一番!ドラえもん祭り」。秋が去り、冬が来れば、「冬だ一番!ドラえもん祭り」。冬がすぎ、春が来ると「春だ一番!ドラえもん祭り」。一年は、君を中心に回り、君と一緒にすぎて行くんだよね。
君とぼくとはまるで兄弟のようにして大きくなった。そう、ぼくらは幼なじみだったんだ。君はいつもぼくのそばに入てくれた。それがとても自然なことのように思えた。
あの日、ぼくはどうかしてたんだ。突然、本物の君に会いたくなった。ぼくは君に会いに行った。初めてだった。あんなにぼくは君に会ってたのに、直接、生で会うのは初めてだった。こんな思いをするために、君に会いに行ったんじゃないし、会わなけりゃ良かったと思うときさえある。でも、いまは、これが二人にとって一番良かったのだと信じてる。本当の君に出会えたことで、マスコミのうそも、世間の偽善も見えたような気がする。こんなぼくだけどちょっぴり大人になれたのかな・・・・・・なんてね。
これまでの君は、テレビ朝日と小学館によって語られるドラえもんだった。マスコミによって語られる、作られたドラえもん像だ。メディアによって報道されるひとつの完結したイメージでしかなかった。
ぼくが見た本物の君は、身長が二メートル近くもあり、頭は大きいが、手足も長く、むしろスマートな印象さえあった。君は無言で一言もしゃべらず、体は金属的、機械的なロボットというより、布地、とりわけタオルケットに近い気がする。指は片手に五本、両手に十本あり、デパートの屋上では、幼稚園児達と一緒に遊び、中には学生アルバイトのお兄さんが入ってる代物だった。
![]()
ある晴れた日曜日、私は街を歩いていた。
「ドロボー!」
突如、女性の叫び声。彼女からハンドバッグを引ったくり、走って逃げる男の姿。気がつくと、私は走って泥棒を追いかけた。
「こらっ、ドロボー待てぇー。」
私は周囲の人間に注意をうながしながら走り続けてる。
「こらっ、ドロボー、ハンドバッグを返せー!」
こんなことを叫んでいても、泥棒が素直にハンドバッグを返すわけがない。どんどん走って逃げている。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
大声でこう叫び、泥棒を追いかける。こんな時はみんなで捕まえるのが、一番なのだ。
泥棒は走って、どんどん逃げている。その先を歩いている人達が私の声に気付き泥棒とすれ違う瞬間、泥棒にぶつかって腕を捕まえるが、泥棒はうまく腕を振りほどき人混みをかき分け逃げていく。それを捕まえ損なった人達が、
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
と集団で叫んで、泥棒の進行方向にいる人達に注意をうながし、みずからも泥棒を追いかけ出してる。その先を歩いている人達も、その声に気付き泥棒に身構え、走ってくる泥棒にぶつかって捕まえようとするが、なかなかどうして泥棒は、さらに深く人混みの中をすり抜けすり抜け入り込む。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
みんなしてそう叫び、泥棒を捕まえようと追いかける。泥棒を追う人混みが増え、私も必死になって追いかけているが泥棒も必死で逃げている。泥棒を追う人混みの先頭に立ち、泥棒まであと3メートルの距離まで来た。泥棒までの距離が、あと2メートル。私の後ろからはさっき泥棒を捕まえ損ねた人達が一緒になって走ってくる。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
泥棒を追う集団から一歩抜けだし、あと1メートルで泥棒に追いつく。走れ、走れ、走れ、走れ。泥棒を捕まえるため全力で走る。あともう少しで手が届く。大通りの十字路を、泥棒は右に曲がろうとする。正面の信号が赤だからだ。私も泥棒を追いかけ右に曲がる。
と。
そこに泥棒の姿はない。石段に腰かけ、ちぎったパンをハトにあたえている老人とポカポカした日差しの中で昼寝をする赤ちゃんを乗せたベビーカーを押した若奥様とおそろいのポロシャツを着た若い旦那さんの手に引かれて歩く黄色い子供服を着た四・五才の男の子がハトの群の中にダァーーッと走ってていっせいに飛び立つハトを見て喜ぶ子供に、うろちょろしないでちゃんと歩きなさいと軽くしかって子供の手を引っ張る若夫婦の微笑ましい光景。テニスラケットを持った若者、公園でゲートボールをする老人。一瞬、時間が止まったようないつもの街の風景。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
後ろから走ってくる大勢の人達。私は再び走り出す。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
後ろを振り返ると大勢の人達が必死の形相で走ってきている。私も全力で走りはじめてる。とにかく捕まってはならない。走れ、走れ、走れ、走れ。
私はこの街を全力で走っている。疾走し続けていると言っても良い。この街を駆け抜けたその先に何があるのか?どこを目指しているのか?どこかたどり着くべき場所があるのか?そこで私はどんな目にあうのか?そんなこと、分かる訳が無いし、分かるすべもない。けれども私は走り続けている、走らずにいられない。後ろから大勢の人間が私をぶちのめしに押し寄せてくる。奴等に捕まってはならない。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
私が叫び始めた時には七・八人だった人数が、二・三十人に増えている。彼らは必死の形相でこっちに向かって走ってくる。敵意むき出しのぶち切れた人達が、集団で私をぶちのめしに来る。彼らに捕まってはならない、捕まったら最後、もみくちゃにされ、ボコボコに殴られて、まちじゅう引きずり回される。息は切れ、呼吸はあがり、体は疲れ切っている。けれども走らねばならない。この場を逃げ切らなければ、大変なことになってしまう。
私は市街地を抜けると、街の大通り、人ごみでごった返す休日の歩行者天国に入って行った。通りには重低音鳴り響くバズーカ型のラジカセと、そのラジカセから流れるヒップポップに合わせて踊る高校生ダンスサーが男女合わせて七・八人、そしてその見物客が二・三十人、路上で銀細工のアクセサリーを売る外国人とどれにしようか選んでいる女子高生三人組み、路上のオープンカフェでくつろぐ人々。赤や黄色にペイントされた白いミニバンの屋台が三台、クレープとハンバーガー、アイスクリームが来ている。もう少し先には、たこ焼きと大判焼き、ラーメンとおでんの屋台が出ている。普段は車道として使われている遊歩道に設置されたイスとテーブル、そしてパラソルの下、ところせましと人々がごった返し、アイスにハッシュドポテト、ジュースにクレープを食べている。人を隠すには、人ごみの中。あの中にまぎれ込めば、逃げ切れるはずなのだ。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
後ろから飛んで来る罵声。人々の注目が私に集まる。高校生ダンスグループのリーダーらしいのが、「捕まえろ!」と言ったのを皮切りに皆一斉に、私に襲い掛かる。私は歩行者天国の人ごみの中、人をかき分け突き進み、何とか人ごみにまぎれ込もうとする。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
後ろからの声に、私を追う集団も増える。さっきまで踊っていたダンスグループとその見物客、路上で指輪やペンダント・銀細工を売っていた露天商の外国人、それを眺めていた茶パツで長髪の日に焼けた女子高生三人組み、街頭でマイクを持ち政府の税制政策について批判を力説していた人間まで、同じことを口走って一方向に走り始めた。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
カフェテラスの人々。ホコテン広場の飲食者。白塗りの大道芸人。おもちゃ屋のプラカードを持ったジャイアントパンダ。私を追う人の数は膨大に膨れ上がり、歩行者天国に居た人全員が私を捕まえようと襲い掛かってくる。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
足が重く、汗でベタ付いたズボンが太ももにまとわりつく。息も苦しく、これ以上走れそうにない。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
追っ手はすぐ後ろまで迫っている。捕まると何をされるか分からない。けれども私はもうこれ以上走れそうにない。息が切れ、呼吸が苦しい。追っ手の集団の先頭を走る男が私のすぐ後ろ、もうあと三メートールの位置まで近づいてきている。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
集団パニックか、ヒステリーか?私をぶちのめそうとする男が私のもうすぐ後、今にも手が届きそうな位置にまで来ている。集団の先頭を走る男まであと二メートル、一メートル。あらゆる意味でもう潮時だった。これ以上走れない。私は捕まり、もみくちゃにされる覚悟をした。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
そう叫び、群れの先頭を走る男が私の肩をグイとつかみ、後ろに引き寄せ、私をドンと後ろへ突き離し、そのまま私を抜き去って行く。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
そう叫びながら、その男は一人、私の前を走り去っていった。私は呆然としながら、自分の前を走り去って行く幾人かの先頭集団を見送り、そして、そのすぐ後、膨大な人数の人ごみが自分の真横を通り過ぎて行くのを見送った。さっきまで、あれほど注目を浴びていた自分がまるで存在しないかのように、無視され続けている。
人々の流れとは逆に、私は一人、さっきの歩行者天国まで戻ろうとしていた。アイスクリームが食べたかったのだ。疲れ切った体で、とぼとぼとうつむいて歩いている横を多くの人が熱狂して走り去って行く。
「ドロボー!ドロボーだぁー、あいつを捕まえろ、あいつは悪人だ。」
もとはと言えば私が言い始めた言葉だった。責任を取れと言われても、そんなつもりで言い始めたわけじゃないし、こうなるとは思ってもみなかった。私はただ、歩行者天国の広場に戻って、アイスクリームを食べながら疲れた体を休ませたい。そう思って広場に向かう。
広場には人気は無く、風にあおられてカラカラと転がる空き缶と、持ち主に捨てられたままヒップポップを流し続けるラジカセ、人ごみに倒された路上のオープンカフェのイスとテーブル、そしてパラソル。パラソルは風にあおられてガガガガガと路上を滑って行く。露天のバーガー屋にもアイスクリーム屋にもクレープ屋にも人影は無く、屋台もレジも食べ物も置きっぱなしだ。
と、そこに一人だけ私以外の人影を発見した。さっき夫人からバッグをひったくっていった泥棒だ。店員の居ないのを良いことにハンバーガーからポテトから好きなだけ食いまくっている。泥棒の方も私に気づいた様子で軽くこちらに会釈をすると、そのまま優雅に食事を続けた。私もまた無断でアイスを食べ始める。私は疲れていて今すぐアイスを食べながらゆっくり休みたい、なのに金を払おうにも店員が居ないのだ。
![]()
高校で古文の時間に「めり」という助動詞を習う。
「婉曲・推量の助動詞で、・・・のようだ、・・・のように見えるという意味を持っています。」
と習うのだが、婉曲なんて言われても「婉曲」という言葉の意味自体が分からないし、推量の助動詞には「む・むず・らむ・けむ・べし・らし・まし・めり」と八種類もあり、他の推量とどこが違うのかよく分からない。「めり」は頭に「め」が付いている分だけ、「視覚的に・・・のように見える」という意味であり、ビジュアル的な推量なのだが、これを暗記してもすぐに忘れてしまい試験直前になってまた一夜漬けするハメになる。そこでこういうモノは文脈の中で覚えた方がより頭に残るし、細かいニュアンスも分かる。何も小難しい古文の中で覚えろと言うわけじゃない。ちょっとした小話で良いんだ。
☆
大学の国文学科の男の子が、助手席に同じく国文の後輩の女の子を助手席に乗せて、高速道路を走っていた。ポテトチップスとか食いながら、男の子が
「ポッキーいる?」
とか言って、女の子が缶ジュース飲んで、男女で、たわいもない話しながら走ってたわけだ。
そしたら、向こうの方にさ、変な建もんがあって、なんか、田舎のたんぼの真ん中に自由の女神とかパルテノン神殿とか、建ってるわけで。話題が
「あれ、なんかな?」
とか、いう話になって、女の子が、
「ラブホテルちゃう?」
とか、言うから、男の方が
「そうかなぁ、ラブホテルかなぁ?」
とか、言って、まあ、走ってたわけで。
したらさ。なんか突然、女の子の方が、
「あれは、ラブホテルだ!ラブホテルに違いない!私には分かる!」
って、叫んで、男の方は、そういうの無視して、黙ってニヤニヤしながら運転してたわけ。
そしたら女の子が、ちょっと下向いて恥ずかしそうに
「ラブホテルめり。」
って、言った。
って話なんだけど。
☆
ん?
これだけじゃ、なんのことか分からんって?
わからん分は想像力働かせるか、なんかして埋めて欲しいんやけど、無理やったらしゃぁーない。
じゃあ、男の方を主人公に心理描写を入れて。
もう一度。
☆
一応まあ、俺が国文科の大学生やとするやん?で、俺の左側の助手席に、同じ国文の後輩の女の子を助手席に乗せて、高速道路を走っていて、まあ、ポテトチップスとか食いながら、
「ポッキーいる?」
とか、言って、缶ジュース飲んで、女の子とたわいもない話しながら走ってたわけだ。
そしたら、向こうの方にさ、変な建もんがあって、なんか、田舎のたんぼの真ん中に自由の女神とかパルテノン神殿とか、建ってるわけで。話題が
「あれ、なんかな?」
とか、いう話になって、俺は、実家の方で、これと似たような風景を見ていて、まあ、その実家の風景を思い出してたわけやね。
ある日、突然、今まで何も無かった田んぼの真ん中に、ハッデェーーーな紅の鳥居が建って、近所の人達が、新興宗教やと思って、反対運動起こして、署名活動してた時期があって、自分も「署名してくれ」言われて、まあ、変な宗教団体来ても嫌やし、どう考えてもあの色とデカさが異常やったし、名前書いたんやけど、後でそれが、地元のラーメン屋が客寄せに造ったってのが分かって、ま、それやったら良いかって感じで落ち着いたんやけど、それ思い出してたから、安い土地買い取って、そこに何の役にもたたん様な派手な建造物、記念碑とか、馬鹿でかい塔とか、五階建てぐらいのデカさの銅像とか造んのって、新興宗教ちゃうん?とか思ってて、
したら、彼女が、
「ラブホテルちゃう?」
とか言うから、俺は、
「そうかなぁ、ラブホテルかなぁ?」
とか言って、まあ、走ってたわけで。
したらさ。なんか突然、あいつ、
「あれは、ラブホテルだ!ラブホテルに違いない!私には分かる!」
って叫ぶから、なんかなぁ、とか思って、「ラブホテルだ!」って断言するんやからなぁ、「私には分かる!」と、まで言うんやから当然、入ったことあるんやろなぁー、って思うやん?あんな所、一人で行くわけないから、とうぜん誰かと行くわけで、誰と入ったんかなぁー、とか思うわけでさぁ。最近、仲良い**かなぁー、とか、でもコイツR先輩ひとすじやったはずなんやけど、R先輩にはA子先輩いるし・・・とか、こんなこと心の中では思ってるけど、コイツとA子さんじゃ、勝ち目無いのコイツも分かってるやろうし、なんて、口に出してこいつに言うわけにもいかんやん?バイト先で彼氏できたんかなぁー、とか思ってる その間、結構会話停まってんよ。口に出して言えんようなこと考えてたから。
確か、駅前のハンバーガー屋やったよなぁ、こいつのバイトって。・・・マックの奥でハンバーグ焼いてんの中年ばっかりやん?まあ、中年ゆうたら悪いかもしれんけど、30代なかばの人やったし、でも、むこう社会人やし、金は持ってるわなぁ・・・・正直言って俺には勝てん。そうだよ、社会人って金もってんだよなぁ、っったくよぉ、どうすりゃ良いんだよ、援助交際とか売春とかっってのは、雑誌とかテレビの世界だと思ってたのによぉ、こんな身近にさぁ・・・とか思って、
ふっと助手席見ると、ふっくらほっぺのガキが、ポッキーおいしそぉーに食べてるやん?それはないかぁ。って思って、ちょっと安心しつつ、やっぱ、サークル系で言うと、**かR先輩か、・・・・辺りかなぁ。って。
カーステレオの曲が一曲終わって次の曲行ってたりさ、最近ゼミも始まったって、言ってたし・・・なんか、わからんけど、どっかの誰かと上手くやってんだろなって、思いながらニヤニヤしてたら、彼女が、ちょっと下向いて気恥ずかしそうに
「ラブホテルめり」
って、言ってん。
☆
ん?
これだけじゃ、なんのことか分からんって?
わからん分は想像力働かせるか、なんかして埋めて欲しいんやけど、無理やったらしゃぁーない。
じゃあ、女の方を主人公に心理描写を入れて。
もう一度。
☆
あたしが後輩の女の子だとするとぉ、こんな感じで彼の左側に座って、高速走ってたの。ポテトチップスとか食べながら、
「ポッキーいる?」
とか言いわれて、おクチ開けて「あーん」とかしてたら、運転手がこっち向いて、何してんの?ここ高速だぜ?って顔してるんで、ちっきっしょー、A子先輩にはデレデレするクセにぃーー!とか思って、右手握り拳状態で、むかぁーっときて、ほら、前みて!前!って目で言い返しながら、自分で缶ジュース飲んで、まあ、男の子とたわいもない話をしながらドライブしててん。
そしたら、向こうの方にさ、変な建てもんあるのよ。なんか、田舎のたんぼの真ん中に自由の女神とかパルテノン神殿とか、建ってるねんな。
「あれ、なんかな?」
って彼が言うから、まあ、高速降りてすぐの、こんな所にド派手な建てもん建てるのっって、ラブホテルに決まってるやん?だからあたしは、
「ラブホテルちゃう?」
って言ったら、先輩は
「そうかなぁ、ラブホテルかなぁ?」
とか言うから何か変やなぁーーおもって。・・・だってこんな所にある非常識な建てもんってそれしか考えられへんやん?なのに、そんなこと聞いてくるってことは、ほんんんんとにラブホテルかなぁ?とか言い出してさぁ、ちょっと試しに見に行かへん?とか、なんか気になるしさぁ、確認してこよ、とか言って、突然彼、高速降りて、「自由の女神」の地下駐車場入るやん?これ、ほんまにラブホテルかなぁ、ちょっと中入ってみぃーひん?とか言って あたしの手を引っ張って中入って行くやん。2人して部屋入ってさ、へーーぇ、これがラブホテルかぁーー、とか部屋見渡しながら言ってさ、すげぇーーー、おれ、こんな所くんのはじめて!とか言いながら、上着ハンガーに掛けたりし出しててさぁ、どうせやったら、シャワーだけでも浴びてかへん?とか言われて、そのままズルズル・・・・ってパターンが あたしの頭ん中に突然浮かんだわけよ。先輩、絶対それをねらってる!って。したらさ、浮かんだ瞬間。
「あれは、ラブホテルだ!ラブホテルに違いない!あたしには分かる!」
って、思わず叫んじゃって・・・だってそうやん。はじめからラブホテルやって分かってるんやから、確認しに行かんでも良いやん。だからあたしは「あれはラブホテルだ!」って断言してんよ。そしたら、一瞬「しーーーーん」って沈黙が続いて、何か気まずいなぁーーー、早くなんかしゃべってくれへんかなぁ、思うんやけど、しゃべってくれへんやん。
ふっと、横見たら、みょうーーにこっち見ながら、黙ってるわけやん。ニヤニヤしてるわけやん。
あ、これ、ひょっとして、この人、始めからラブホテルに誘う気なかった?なのに、あたしが勝手に余計なこと言ったばっかりに・・・完璧に誤解されてる!あたし、別にラブホテルに誘ってるわけじゃなくて、その・・この人カン違いしてるーーーぅ。そんな・・・ひょっとして あたしは自分から男の子をラブホテルに誘うような おんな?そういう おんなって やっぱり おとこの人から見ても可愛くない?そ・そんな・・甘く見ないでよ!あたしだって本とーぉに行くって決めたら、ちゃんと作戦立てて、遠回しに、ムード作って・・・違う、そうじゃない、そうじゃなくって、あたしが言いたいのはそういうことじゃなくって・・そんな目で見ないで、あたしは別に、ホテルに行こうだなんて、一言も言ってもいないし思ってもいないのに・・・何でこうなるのぉーー。って状態で思わず、
「ラブホテルめり(ラブホテルのようだなぁ、ラブホテルに見えるなぁ)」
って、言ったわけ。

ボクは精神病院にいる。理由はまだない。ボクは精神科医に会って、精神診断を受ける。ボクがここにいる理由はそのとき作られる。
昨日学校から電話があって、「精神科医に会わないか?」と言われた。これといった理由が無く、親はこれに同意した。これといった理由が無く、ボクはここに強制連行された。おかげで彼女とのデートはキャンセルになった。
ボクは精神病錬の中の、医務室に連れてこられた。その中には驚いたことに、白衣を着た猫がいて、気難しそうにカルテをみていた。
猫は言った。
「これが何に見える?」
「さあ。」
ボクは答える。実際、何にも見えなかった。
「わかりません。」
と答えると、
「多少時間がかかっても良いから、思いついたことを言いなさい。」
と言われた。
ボクは、これについて考えていた。そう、これは確か、小学校に入学して一年が過ぎ去ろうとしていた小学一年の三月、入ってすぐの頃はお母さんと一緒に教室まで来て、教室で母親と別れるときに泣いてる女の子がクラスに一人いて、きっと彼女は幼稚園に通ってなかったに違いない、だから母親と離れるのが怖いのだろうと初めて幼稚園に行った日にも、泣いていた子が何人か居たのを思い出しながら、眺めていたそんな小学一年が終わろうとしている冬の日の寒い朝に、いつもよりも早く学校に来て誰も居ない教室に一番乗りし、妙に静かでガランとした空っぽの教室の中で手袋を外して一年二組の石油ストーブの石油を運ぶ係、つまり日直になっていたのがボクで、そのために寒かったにも関わらず、いつもよりも早く目覚ましをかけて起きて、いつもより二十分以上も早く家を出て、人っ子一人居ないはずの教室に来たのに、先客がもう既に二人ほど来ていて、・・・・・・。
「何か言いなさい。どうです、何に見えます?」
猫は、ボクに何かをうながした。
「どうして猫なのですか?」
ボクは言った。猫は不思議そうに首をかしげる。
「猫って何ですか?」
「猫で無ければ、クマで良いです。」
ボクはクマのことを「猫だ」と言ったのを恥ずかしく思った。こんな大きな猫がいるわけ無いじゃないか。ボクはこれをクマと呼ぶことにした。
「クマです。」
「クマに見えますか?」
クマは少し驚いた様子だった。
「他に何に見える?」
「プーさん。」
むかし「クマのプーさん」というアニメがウォルト=ディズニーのアニメであったことを思い出した。黄色い肌をしている。ハラが出ている。黄色いガウンを着ている。ハチミツが好きだ。ハチが嫌いだ。トリッキーな運動をする。トロッキーは運動をする。クロッキーは指を動かす。クロポトキンは知らないが、スナフキンは語らない。
「劣等民族を殺したいと思う?」
今度はボクがプーさんに質問した。自分が何に見えるかなんて、見ず知らずの人間に聞くなんて、ナルシストかボクに気のある女の子ぐらいのものだ。そして、ナルシストはいつも、劣等民族を絶滅させたいと思っている。劣等民族は美しくないからだ。もし、この質問で答えがノーならば、彼はボクに気のある同性愛者だ。
「これで決まりだな。」
さっきまで持っていたロール=シャッハテストのパネルを机の上に置くと、プーさんはカルテをのぞき込んで「もういいよ」と手で合図をした。
ボクもいいかげんこの退屈なゲームにうんざりしてたので、部屋から出ると、待合室の長椅子に座った。椅子には見るからに無口そうな、そして、少し神経質そうな女の子に出会った。
「空が青いね。」
ボクは言った。空を見上げると、病院の待合室の上には真っ青なコンクリートの天井が広がっていた。
「海は白いわ。」
彼女は言った。彼女の目の前に広がる精神病院の壁は確かに、まるでどこまでも広がる真っ白な海のように白く広がっていた。
「コカコーラは赤いよ。」
ボクも言った。
「ヤスは黒よ。」
彼女は言った。
「ポートピアだね。」
ボクも言った。
「ポーランドではないの。」
彼女は言った。
「ポーランドは赤だよ。」
ボクも言った。
「赤は嫌いよ。」
彼女は言った。
「どうして?」
ボクも言った。
「ポーランドではないの。」
彼女は言った。
「ポートピアだね。」
ボクも言った。
「そう、連続殺人事件。」
彼女は言った。
「犯人はヤスじゃない。」
ボクも言った。
「むかしのことよ。」
彼女は言った。
「これだ!」
ボクはいま、頭の奥底に引っかかって、どうしても思い出せなかったある事実を思い出した。そう、すべてはむかしのことなのだ。これは確か、小学校に入学して一年が過ぎ去ろうとしていた小学一年の三月、入ってすぐの頃はお母さんと一緒に教室まで来て、教室で母親と別れるときに泣いてる女の子がクラスに一人いて、きっと彼女は幼稚園に通ってなかったに違いない、だから母親と離れるのが怖いのだろうと初めて幼稚園に行った日にも、泣いていた子が何人か居たのを思い出しながら、眺めていたそんな小学一年が終わろうとしている冬の日の寒い朝、登校中の通学路の水たまりに氷が張っていて辺り一面真っ白に霜が降りてて、氷の上に乗ってパリパリ氷を割りながら学校に行って、いつもよりも早く学校に来て誰も居ない教室に一番乗りし、妙に静かでガランとした空っぽの教室の中で手袋を外して一年二組の石油ストーブの石油を運ぶ係、つまり日直になっていたのがボクで、そのために寒かったにも関わらず、いつもよりも早く目覚ましをかけて起きて、いつもより二十分以上も早く家を出て、人っ子一人居ないはずの教室に来たのに、先客がもう既に二人ほど来ていて、取りあえず「おはよう」とあいさつして、「いつもこんなに早いの?」って聞いたら、「いつもはもっと早いよ」って言うから、何しにこんな早く来るのだろう?と思いながら、ボクは用具室に行って石油の入ったポリ容器を教室に運んで、教室にある大きな石油ストーブに石油を入れていた。いや、もっと正確に言うと、石油を入れるふりをしていた。ボクは心から石油を注ぎたいと思ったわけで無く、成り行きの中で、周囲との関係の中で偽善的に、石油を入れざるをえない状況になっていた。とはいえ、当時の僕をそんなに責めないで欲しい。端的に言うと、怖かった、そう、怖かったのだ。この石油を注ぐという行為、これは当時のボクに対して課せられた一つの義務であり、責任であり、決して逆らうことの出来ない強制労働であった。そしてこの行為を強制する大人達というのは、当時まだ七歳の子供であったボクにとって、恐ろしくわがままな生き物であった。彼らは私達に学校へ行くことを強制する、そしてみづからは学校へ行かない。このことに対して怒りを感じていた人は多かったはずである。なのに、何人の人が大人達と闘争できたであろう。むしろ、なんの闘争もなしに学校へ強制収容されていた人の方が多かったのではないだろうか。恥ずかしながら、私もまたそのうちの一人であったのだ、・・その役目をこなしていた。これは石油を入れていたというより、石油を入れてるふりをしていると言った方が正確だった。何しろ当時のボクは心から石油を入れたい、入れずにいられないと思ったことは一度もなかったのだから。そんな、石油を入れるふりをしていた朝の六時五十二分、ボクは朝の会の司会を務めるふりをして、一時間目の授業を受けるふりをして、友達と遊ぶふりをして、二時間目の授業を受けるふりをして、回し手紙を回すふりをして、小学校の中庭に出るふりをして、そこでボクが友達のふりをしている智弘と、ボクの友達のふりをしている中里と敷島と掘之内と三嶋でドッチボールをするふりをして、休み時間を過ごすふりをして、三時間目の授業を受けるふりをしていたとき、先生は確かにこう言ったふりをした。
「これ・それ・あれ・どれ、この四つをこそあど言葉と言い、これは指示代名詞です。」
そう、確かに「これ」は指示代名詞だった。ボクは思い出した。思い出したふりではなく、思い出したのだ。これは指示代名詞。これは指示代名詞。ボクが記憶している限り、これは指示代名詞なのだ。かつてこれが先生によって指示代名詞だとされたように、いまも、そしてこれからも、これはボクの記憶している限り指示代名詞であり、指示代名詞であり続けるのだ。決してこれは、指示代名詞のふりをしているわけじゃない。
「ありがとう。これを取り戻すことが出来たよ。」
ボクは言った。
「これって?」
彼女は言った。
「これは見えない。けれど信じる。これはボクの周りにいつもある。そう信じるんだ。」
ボクは言った。彼女は唖然としている。
「ボクの周りに在るのがこれ。そう信じて。」
ボクは言った。
「うん、信じる。」
彼女は言った。
「君の周りに在るのがそれ。そう信じて。」
ボクは言った。
「うん。信じよう。」
彼女は言った。
「僕達の周りに無いのがあれ。あれはボクからも君からも離れていて、手が届かない。信じられる?」
ボクは言った。
「信じられない。」
彼女は言った。
「じゃあ、信じなくても良い。ついでに言っとくと、どこにも存在しないのがどれ。」
ボクは言った。
「あれが在るなんて信じられない。」
彼女は言った。
「あれが在ることを証明するのはむずかしい。信じる人の心の中にしかないのだから。」
ボクは言った。
「それがあるのは信じられる。それって、それでしょ?」
彼女は言った。彼女が手のひらで指し示した方向には、確かに「それ」があった。少なくともボクはそう信じる。
「そうだよ。」
ボクは言った。
「でも、それだらけで『あれ』がひとつも無いわ。」
彼女は言った。彼女の右手が指し示した方向には確かに「あれ」が無く、それでいっぱいだった。少なくともボクはそう信じる。
「あれなんて本当に在るのかしら?」
彼女は言った。
「あれだよ。」
ボクは廊下の遠くの方を指差して行った。
「どれ?」
彼女は振り向いた。彼女は振り向いてあれに近づいて行ったとき、あれはそれになり、あれでなくなった。ボクはどれがあれなのか分からなくなり、
「いや別に。」
と言った。
ここには無い、つまり存在を確認できないなにか記憶創作的なもの。指示代名詞の「これ」とかプロレタリアの楽園とか見えざる神の手とか歴史的必然とか異常と正常の境界線とか他人と自分との境界線とか、そういった前提をあると思い込む病と喪失する病。そのどちらかを患った者が患ってないボクをここへ収容したがるようである。
![]()
一人暮らしの午前二時四十二・三分 深夜テレビが砂嵐になり 一人 壁に囲まれたまま 眠ることも出来ず天井を見上げたまま 沈黙がおそろしく耳障りな時間帯 今すぐ誰かと話そうにもこの時間に話せる相手はそうそう居るものではなく 午前三時十五分前に起きている一人暮しの友達 もしくは一人暮しでなくても家族共に午前二時三時に電話がかかってきて当然だと思っている誰か・・など居るわけもなく ふとんの中でうずくまり 手応えのない布団をパスパス殴りながら 掛布団の中に顔を埋め 僕は深い気だるさの中に沈み込んでいた・・・何が僕を深く沈み込ませているのだろう・・・・・心当たりをひとつひとつさぐっていく なぜ/いつから/どのようにして沈み込み 何が僕を解決するのか 例えばそれは自分にとって必要なものと不必要なものを分ける一つのきっかけか答えにでもなるのかもしれない 何かが変わるわけでも 何も変わらないわけでもない 日常生活を受け入れる決意をした時から・・という解答 これも有り得る答えのうちのひとつ と、いうよりむしろ いや きっとそれが原因で きっとそれからの僕は 深く落ち込んでいるのだ スパイ映画の主人公や特撮戦隊物の変身ヒーローのように 日常生活の向こう側に跳ぼうと暴れ回ってた僕は いまさらのように冒険活劇のマフィアやテロリストにあこがれる年齢でもない自分自身の年齢の存在に気が付き 生活世界の向こう側に跳べないことに気付いて 暴れることを止めてしまった・・重苦しい鋼鉄の重圧によって抑圧された過剰なエネルギーが シリンダーの中で暴動を起こし 爆音と共に走り出す二十四気筒のシャフトを高速回転させた七百五十ccの鉄の塊が どんなに遠くへ逃げたつもりでも 暴発したエネルギーはシャフトの同じ部分をグルグル回り続けるように きっとそこはそこに住む人にとっての生活世界で 昨日と同じ夜の首都高を旋回し続ける 数年後のタクシー運転手もしくは白バイ警官隊・・・・・・どんなに異常な出来事を起こしても 驚きは始めの瞬間にだけ凝縮され 出来事の継続は あらゆる種類の薬物が耐性を持つように 反復が非日常性を日常化し 初めは事件であった出来事にも人間は慣れ親しみ 退屈をおぼえる。 繰り返しを余儀なくされた遊戯は いつしか義務感と共に汗まみれになり足取りを重くしていく どのような壮大な話もまた 自分の職場と住みかの往復である日常世界の外側に連れ出してはくれず 職場や住みかから少しばかり離れた場所にある何かについては マスコミからの伝聞を通じてしか知ることが出来ず 自ら確かめる手段を持たない そんな自分の生活世界が 学校とアパートの往復 それにいくつかの駅周辺を加えた程度のものに過ぎないように どんなスーパースターも・・例えば仮に自分がロックスターに成れたとして・・ホテルとライブハウスとの往復ツアーや 事務所とテレビ局との往復のくり返しの中でしか生きてはいけず その間にあるのはせいぜい渋滞に巻き込まれた自家用車での移動や 六畳ほどの待合い室で過ごす本番二時間前の待ち時間でしかない そんな物になるための努力だなんて まるで捨てられるために生まれてくるガチャガチャのプラスチック容器 熱狂することによって 非日常の世界に跳ぼうとする僕は ゲームかスポーツにでも熱狂するだろう 王を詰み ボールをゴールすることに 意味を感じられない僕は 宗教か政治にでも加わるかも知れない 窓枠に金網を張り スピーカーを乗せた黒いバンに乗り込み 国体を左右するお偉方の事務所に乗り込み 様々な抗議行動の一環として時には バリケードを築き上げ 火炎瓶を投げ 毒ガスをばら撒くだろう それは深い変革への意志と共に 熱狂が一時的にでも僕を陶酔で満たすかも知れない でも いまの僕は火炎瓶や毒ガスに熱狂できても そこに意味を見出すことは出来ず 無意味に気付いた心は すぐに熱狂を僕から消し去る・・・・僕は熱狂を捨て 冷めた日常生活に戻るつもりだ・・・一見無意味に思える作業 朝目覚し時計と共に目を覚まし 朝食と着替え ちょっとした旅行気分で通勤を終えると 社訓と社歌 校歌を斉唱 今月の目標と朝の挨拶にラジオ体操 帰宅後の着替えと風呂とビールと夕食 ビールに巨人戦が唯一の楽しみ そんな規則正しい日常生活のくり返し・・・・上の子が今度小学校に上がるので ランドセルを買ってあげなくちゃいけない 下の子は幼稚園の運動会で努力賞をもらった 学芸会の出し物は森の熊さんで 森に咲くチューリップの役をするので休日はビデオカメラを持って観に行かなくてわ そして子供達もいつかは大人になり 自分達の知らない場所へ行ってしまう・・・・さして熱くも激しくもないスケージュールの中で ささやかな幸せと不安 最寄りの駅までバスで二十分 歩いて行くには少々遠く 車で行くにも駅前に駐車場が無く バス停でわ 二十分に一本のバスを待ちながら 駅に着いたら 三十分に一本の快速を待ち 地下鉄を乗り継いで会社に着くと 就業時間が来るのを待ち 上司の指示と決定を待ち 休憩時間が来るのを待ち 取引先からの連絡を待ち 部下の仕事が上がるのを待ち 同僚と飲み会の約束を交わすと 終業時間が来るのを待ち 待ち合わせ場所で同僚を待ち 仕事が遅れているとの連絡を受けると 先に飲みに行って飲んでる先で同僚からの連絡を待ち 店の中では携帯が入らないと店を出入りしてみたり 外で連絡を待ってみたりしながら 長引いた飲み会の終わりには 終電は合っても終バスに間に合うはずも無く 長蛇の列が出来ている深夜タクシー乗り場でタクシーを待つ そんな待ち時間と移動時間と付き合いをくり返し。静かに冷めた心は 何かに乱されることも 何かに満たされることもなく ただ何事にも動じない。清流で作られた透明なレンズのように あるがままの矛盾と不条理を受け入れ 時には同じような生活をする仲間達と愚痴をこぼし お偉方をののしりながら それを解決する力を持つわけでもない。終わらない時間 始まらない時 繰り返され続ける会話と無意味な笑い ゼンマイ仕掛けの腕時計を毎日同じ時間に同じように巻き続ける 一分一秒も狂わないように そして時計が止まりさび付いて動かなくなったとき初めて その持ち主の死に気が付く そんな カフカのような公務員的人格になりたい。そういう思いを抱き始めてから 少しづつ じわじわと無気力な脱力感と 理由のない気怠さ・・失業中のフランス人没落貴族が 有り触れたどうってことのないゼネラルストライキに沸くごく見なれた街中の風景を 屋根裏のロフトの窓辺から 頬杖をついて見下ろしているようなアンニュイな気分が・・・・・・・別にどうだって良い 規則正しい生活を繰り返してやる。
そう思ってふっと顔を上げ 時計を見上げると 時計の秒針が長針と重なったまま動かない。時計が壊れた・・・いや 電池が切れたのか? とにかくいまこんな時間であるはずがない。僕が物思いにふけ 沈み込んでから 四時間・・・・いや四時間もたっていれば辺りはもっと明るくなっていて良いはず・・少なく見積もっても二時間はたつはずだ。そういえば 二時間前この時計を見たときも この秒針は止まったままだった・・・かもしれない・・ような気がする。まずい、早く敏速に時計か電池を買い換え いまの正確な時間を確認し 一刻も早く規則正しい日常生活に戻らなくてはならない。そう思った僕が時計に手を伸ばすと ゆっくりと・・それは本当にゆっくりとであったが・・長針と重なりあっていた秒針が動き始めた。規則正しく・・正確に。止まっていたのは 時計ではなく 時間の方だった。
![]()
私が彼と出会ったのは近所のスーパーからの帰り道だった。車のワゴンに夕飯の材料を詰め込み車を運転していたところ、急カーブの道路脇に「止まれ」の標識を高く掲げた男が立っていた。赤い逆三角形の「止まれ」の標識だった。細身で長身、ロングコートを着てブーツを履いた全身黒ずくめのちょっと格好の良いやさおとこだった。赤い「止まれ」はそれがちょうど正式の標識であるかのようにごく自然な位置、ごく自然な高さで配置されていた。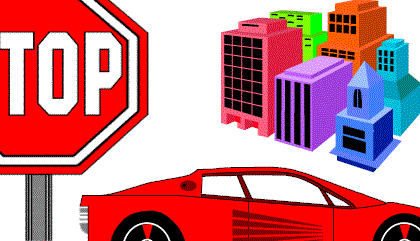
次に彼を見かけたのは街のメインストリートでだった。二車線の道路が十字に交差する一角に彼はまたしても赤い「止まれ」の標識を掲げて立っている。街の風景に溶け込む黒い棒状の人影がちょうど良い高さに、「止まれ」を掲げていた。彼は頭上に掲げたままで老婦人に話しかけられ、親切にポケットから市街地図を出して老婦人に道を教えていた。老婦人は深々と丁寧に頭を下げると横断歩道を渡り向こうの方まで歩いていった。その間ずっと彼は左手で高々と標識を掲げ、もう一方の手だけでポケットから地図を取り出し開いて道を教えたのち、もう一度たたんでポケットにしまっている。かなり慣れた手つきであったし二・三日で身に付く技術とは見えなかった。彼は道路標識の常連なのだ。
三度目に彼に会ったのは雨の日だった。いつものように限りなく黒に近いモノトーンのグレイ一色に身を包み、ロングコートにブーツ、手袋といったファッションであったが、今回は雨ということもあってかビニールの防水加工を施したシルクハットをかぶっており、雨から髪や顔を守っていた。私は彼に近づき
「大変ですね。」
と声をかけてみた。彼は
「仕事ですから。」
と笑って見せた。もちろんこんな仕事などあるはずがない。精神科医の務めとして私は彼の病状を診断し御家族に報告し、症状によっては精神病棟に入院してもらうことになるかも知れない。さいわい、彼は見たところ症状は軽く「止まれ」の標識を掲げて路上に立つのを仕事だと思ってる以外はこれといっておかしなところはない。周囲に危害を及ぼすわけでなく、自殺の可能性も少ない。周囲に害を与えず患者自身にも害を与えないのなら今のところ実害はないわけで入院させる必要はないが、念のため詳しくカウンセリングしてみる必要がある。私は彼に
「仕事はいつ終わるのですか?」
と尋ねると、
「社会秩序が完成するまではまだ当分かかるでしょう。」
と答えるので、
「いえ、そうではなくて今日の仕事を終えて帰宅されるのはいつですか?」
と聞き直すと
「実際のところ本人にも分からないのですが、用事があるようでしたら今日はこれで切り上げましょうか?」
と言うので
「そうしていただけると有り難いです。」
となった。
☆
彼はその精錬された服装とルックスに見合わず薄汚い小さなボロアパートに住んでいた。家庭もなく一人暮らしの二十代後半無職、自分の世界に閉じこもり幻想を持つには十分な条件がそろっている。おそらく現在の彼の状況を指摘する友人もいないだろう。都市での一人暮らしとはそのような物だ。
「あなたはどうしてこのような職業に就こうと思ったのですか。」
と私は質問する。彼の強迫観念の原因を抽出するのだ。
「何者かと思ったら、プレスの人間か。普段はマスコミ関係者はお断りなんだが、君は特別だ。運が良かったな。」
彼はそう言うとフライパンを取り出し、コンロに火を付けながらさらに言った。
「ハムエッグで良いかい?」
コーヒーでなく、いきなりハムエッグなのは彼の自己中心性から来ている。外来客を迎える常識が欠如し、単に自分の食べたい物を相手も食べたいと思い込む。ここは彼に話を合わせて親密になっておいた方が後々カウンセリングもし易い、
「ありがと、ちょうどお腹が空いてたところなんだ、うれしいよ。」
と言って私は席に座る。ボロアパートに不釣り合いなコートとブーツとシルクハットが壁に掛けてある。おそらく制服のつもりなんだろう。彼は鼻歌混じりに料理をしている。
「どうして道路標識を掲げるようになったのかそろそろ話してくれないか。」
と私が言うと彼は昔を懐かしがるように語り始めた。
「君は何年生まれだい?・・そうかだったらおぼえているだろう。僕たちが小さかった頃は街にはまだ道路標識人があふれていた。電信柱だって人間だったんだ。そう、道路標識機械化法案施行以前、まだすべてが輝いていた時代だ。街のストリートには十メートルおきにモノトーンのコートに身を包んだ長身の電信柱人が台の上に立って電線を掲げてた。地平線の向こうまでずらっと並んだ電信柱人の姿は壮観だったな。彼らは皆、細く長身で美しかった。街の人達とのコミュニケションも取れてて、街の人気者だった。美しく上品なエレベーターガールのような物だ。けれども合理化の波はまず電信柱人を排除して無機質なコンクリートの塊にしてしまった。電信柱人の大量解雇、彼らの多くは道路標識人に流れたが、道路標識の機械化も時間の問題だった。適切な場所、適切な時間に、適切な道路標識。いまでも技術的には機械に負けてないつもりだ。ただ、人力ってのはコストがかかるんで、誰も俺を雇っちゃくれない。始めから分かり切ってた事なんだが、雇用者がいないってのはそれなりにこたえた。だが、俺を必要とする人間がいなくなっても俺は街に立ち続ける。雇用者との関係の中で必要のない存在でも、街を歩く人達は俺を必要としてくれている。それが街に立ってると痛いほど感じるんだ。」
「友達は君のことをどう言っている。」
私は彼を現実の世界に引き戻せるよう質問形式で誘導していく。私が彼に現実を教えるのではない。彼自身が彼自身の力で気付くように誘導尋問をとるのだ。
「ともだち?ああ、始めはみんな馬鹿にしたよ、そんなことおまえに出来るわけがないって。いまに成功して、もう一度やつらの前に表れてやるのさ。」
駄目だ、聞く耳を持ってない。少し質問を変えてみる。
「いまは親友と言えるような友達はいないのかい?」
「こっちに越してきてからは何かと忙しくてね。」
「彼女は?」
「いない。」
周囲に人間関係が無い、完全に孤立している。強迫観念が巨大化する環境がすでに出来上がっている。私は彼に彼自身の姿を気付かす他人の視線として唯一の切り札を出した。
「親はどう言ってる?」
多少嫌な言い方だが仕方がない。このまま行けば彼はドンドン深みにはまって取り返しのつかないことになる。
「もちろん勘当さ。」
彼は笑って言った。ハムエッグを盛りつけて出してくれてる。
「親ってのは自分の息子にはちゃんとした雇用者のいる会社に入って安定して欲しがるもんなんだ。うちの家庭もご多分に漏れなくてね。」
「けれど雇用者がいないんじゃ生活していけないだろう?」
と私が言うと
「あまり言いたくはないんだが、バイトもやってる。早朝と深夜がメインだから、道路標識との両立もできるし、何より社会勉強になる、(目で「止まれ」の標識を指しながら)こればかりやってると視野が狭くなってね。」
パラノイア、偏執狂と言うのだろうか、彼の中では体系的一貫性を持っているのだが、現実と解離している。要するにこの世の中には道路標識人などという職は始めから無かったのだと彼に教えなければならない。彼自身に気付かせる作業に比べて多少乱暴だが、必要な作業だ。
「正直に言おう。私は君のカウンセラーとしてここに来た。君は青年に特有の強迫観念を持っている。誇大妄想だと言っても良い。君の言う『道路標識人』などという職業は過去においても現在においても存在していない。君の頭の中だけの存在なんだ。」
彼は予想したよりおだやかな表情でこう言った。
「なるほど、君もそうか。」
彼は何かを思い出したかのように突如吹き出して、
「いや、精神科医でもないのに何故こんなところに来たんだろってずっと気になってたんだ。いや、失礼した。精神科医なら良いんだ。」
「分かってくれたんなら嬉しい。とにかく私は君の担当医だから信頼してくれ、全面的に信用してくれてかまわない。そして、道路標識も電信柱も昔から人間ではなかった。分かるだろ?」
多少乱暴な言い方だが、このぐらいでないと彼は自分の間違いに気付かない。
「おいおい、君は本当に精神科医か?精神科医ならもっと慎重に患者を扱うべきだぞ。このような症状の場合、いきなりいままでと違う世界観を与えては患者はアイデンティティクライシスに陥る。事実を少しづつ小出しにしていって患者が自然に気付くのを待つんだ。いきなり事実を突きつけたら、いままで患者が信じてた世界が壊れて、かといって医者の言う世界観も急には信じられない。最悪、信じられる世界を失った患者は不安に怯えて自殺する。君は精神科医だろ?精神科医ならカウンセリングを受けたことがあるだろう。その時患者はいかに医師の・・。」
「いや。カウンセリングを受ける方はまだ。」
「なんだ無いのか。残念だな。じゃ、僕をカウンセリングしてくれたお礼に僕が君をカウンセリングしてあげよう。」
この手の誇大妄想狂は大抵尊大であり、多少なりともこういうところがある。そして、これを受け入れなければ彼もまた私のカウンセリングを受け入れなくなる。
「結局のところ、君は私がうらやましいのだ。私のようにやるべき仕事を持ち、抱えるべき標識を持った人間をうらやましく思い、君は私に嫉妬してここに来る。そして私に道路標識を掲げることを止めさせようとする。けれど私は止めない。そんな私を見て君はより私に嫉妬する。君に必要なのは私のカウンセリングではなく、私と共に標識を掲げることではないのか。」
そう言われた私は、次の日から彼と共に街頭に立ち一緒に「止まれ」の標識を掲げている。もちろん彼の方が先輩であり私はまだ未熟者だ。
![]()
AM2時半の八王子駅。終電もなく、始発までは時間がありすぎる。こんな時間でも駅前には、待ち合わせをする女の人が結構いる。なぜ誰がこんな時間に、こんな場所で、誰を待っているのか、尋ねてみたい気もする。駐車場には、車が並び、今度は男が、誰かを待ってる。駅の方から手を振ってあらわれた女の人を車に乗せて、どこかへ走り去る。電話ボックスには誰かに電話をかけるお姉さん達、壁の隙間にはうずくまってる女の子。壁と壁の間では人目につかない。あんな場所では普通、待ち合わせをしない。何をしてるのか分からない、雨混じりの風をしのいでるようにさえ思える。一人でいるのも退屈だろうから、声をかけてみようとも思うが、なんて言って話しかければいいか思いつかない。夜更かしを楽しむガキどもの群れには、ポリも声をかけない。
深夜営業のラーメン屋はいつも満員だ。飲み屋には会社の同僚やサークル仲間といった団体客が多いが、なぜかラーメン屋にはアベックが多い。商店街の交差点では、脱色した髪が腰まで流れる白い毛皮の姉ちゃんと、同じく、脱色した髪が腰まで流れるシルバーグレイの毛皮を着た姉ちゃんが、ガードレールに腰掛けて煙草に火を付ける。通りの向こうから、くたびれた背広を着た酔っぱらいが、
「ねーぇちゃんら、どっから来たんや!」
とでかい声で話かける。白い毛皮は戸惑いながらも
「あなた達?」
と、聞き返す。シルバーグレイは、
「お金あるの?」
と尋ねるが、酔っぱらいは胸を張って
「二千円しか無い!」
と叫ぶ。酔っぱらいの声は夜の商店街にこだまする。
「お約束は?どちら様でしたっけ?どこかで出会いましたか?」
毛皮の姉ちゃんは見かけによらず丁寧な話し方をする。よれよれの背広は
「ここで会った。」
と大声を出す。酔っぱらいの同僚が、
「すいません。」
と頭を下げて、向こうの方に連れていく。毛皮は
「くだらねー!」
とつばを吐く。しばらくすると、胸のポケットから赤いスカーフを垂らしたグリーンのソフトスーツで決めた男と、首に紫の唐草模様のスカーフを巻いた赤いソフトスーツの男があらわれる。ふたりは毛皮に話しかけ、毛皮はショルダーバッグを掛け直し、ソフトスーツのセダンに乗って、どこかに消える。
「テレクラでの出会いなんてこんなものかな」て気分と、「会う時の目印になる服や小物は伝えてるはずだから、いくら何でもよれよれの背広をソフトスーツの彼と間違うことはないだろ」って気分と、「女の方が先に来て待ってるシチュエーションと、酔っぱらいに対する言葉使いからして、テレクラじゃなくて、デートクラブかな」って気分と、「エコロジーブームと動物愛護運動の広がりで、毛皮を着るのがダサクなってる」という記事と、去年のパリコレのテレビ中継で注目を集めてた人工毛皮(エコロジーブームとの関連からか、紫や緑と言った明らかに人工毛皮と分かる毛皮が流行りらしい)と、ソフトスーツ=ニュートラ(ニュー・トラディショナル)=田中康夫の「なんとなくクリスタル」という図式と、こんな「ファッションは嫌われる」という女性週刊誌の特集で、ソフトスーツが嫌いな人76%、好きな人13%、嫌いな理由の一位が、「遊んでるように見える」であったことが、ただ何となく頭の中を流れていった。
風が強く、雨もぱらつきだしたので、コンビニに入ろうとすると、広場のベンチで一人座って本を読む女性がいた。午前四時前、こんな嵐の中でハードカバーの本を、なぜ読んでるのか事情が気になったが、話しかけれるはずがない。いまどきこんなカッコをしているのは漫画家か手塚治虫氏ぐらいだろう的なベレー帽にめがね。民族衣装ぽいワンピースの上に、ベストとカーディガンを着ていた。うつむいた顔はクールに決めていたが、断続的に横から突風が吹き、そのたびに大粒の雨がバチバチ当たる。あくまでも冷静を装い本のページをめくる姿と嵐の中にいるという状況が異常な光景を生み出していた。
コンビニに入ると、真っ先に「カラー軍手」という手袋を買った。手が寒かったからだ。が、手袋をはめるより、素手同士で暖めあった方が早く暖まることに買ってから気が付いた。手が暖まると、雑誌を立ち読みし始める。ビッグコミックに連載中の「音楽畑でティータイム」だ。コンビニの中には有線で「ナインティーンナインスリー」や、「純愛ラプソティー」が流れてる。突然入り口の方からオペラのような声が聴こえる。振り返ると、浅黒い肌の外国人ホステスが、祖国の歌をうたっている。両手を広げて異国の歌を歌うホステスは、酒が入ってて僕に気付いていない。一緒にいた二人の外国人が聞いたことの無い言葉を交わしながら、店に入ってくる。マニラかブラジルか中東かは知らない、英語でも日本語でもない言葉を話す人であることだけ分かる。3人の水商売系の人が店内に入ってきて、狭いコンビニは香水の臭いで満たされる。頭がぼーーっとして妙に気持ちがいい。歌を歌ってる人が僕に気付き、歌いながらこっちに歩いてくる。僕はぼーっとしたままその人を見ている。長いマニキュアの指が僕のほほに触れ、あごから首筋に向かって撫でる。
「おにいさん、あたしとあそばない?」
なれた日本語にどう反応していいか分からず、なにごともなかったかように、本に目をやり、立ち読みを続ける。プライドを傷つけられた彼女は、怒ったようにミドルヒールのかがとをカツカツ鳴らして、向こうに行ったが、また機嫌よく祖国の歌をうたってる。少し惜しいことをしたと思いつつ、このような時はどうすればいいのだろうと考えるが、何も浮かばない・・・そうだ今度先輩達に会ったら聞いてみよう・・・まだ頭がぼーーっとして気持ちがいい。
午前五時には店も閉まり仕事から解放された彼女らは、早朝出勤のサラリーマンを眺めつつ、屋台のラーメンを食うらしい。屋台でない方のラーメン屋に行くと、彼女たちのはげ落ちた化粧品の臭いがラーメン屋の湯気で増幅され、地獄のような吐き気がする。しかも屋台と違って、湯気も臭いも薬品も、店の中に充満する。あのドクターペッパーのような臭いは、なれるまでかなりきつい。彼女たちの多くは猫と暮らしているのだそうだ。僕は猫を飼う人間が嫌いだった。いまでも嫌いかもしれない。猫とのコミュニケーションの中で、自分の寂しさをまぎらわせる、そんな人間の弱さが嫌いだった。人とのコミュニケーションの中に、埋められない何かがあることを、認めるのが嫌だった。人とのコミュニケーションの中で埋められない何かが、猫とのコミュニケーションで埋められるということを認めるのが嫌だった。水商売の女性の多くは猫を飼っていて、猫の話ができれば彼女たちにもてるのだそうだ。彼女たちの多くは男性の世話にはならず、自分一人で生活してる、もしくは自分一人で生活していける、そんな強い人たちだ。強い人がなぜ猫を飼うのか?なぜ、人間ではダメなのか?彼女たちは男に生活させてもらうような弱い女性じゃない。男は女を自分のそばに置いておきたがる。自分と同じ夢をみて、自分と同じ目標に向かって汗を流し、自分の夢が叶ったら、一緒に喜んでくれるような女性を求めてる。大抵の女は世間の目と男の経済力・・これって、組織的というか制度的というか、個人の力じゃないんですよね・・に負けて、夫と同じ夢をみてるふりをする。本当は夫が課長になるよりも、夫の給料が増える方が嬉しいし、出世のために接待ゴルフをする休日よりも、家族で楽しくすごす休日の方が大事だと思っているのに・・・。彼女は強い女性だったから、夫の夢が自分の夢だとは思わなかったし、彼氏の目的達成のために自分が何かをしようとも思わず、そのふりさえしなかった。自分は自分の夢を持ち、自分の目的達成のために努力してきたのだ。男たちは「君は僕がいなくても生きていけるんだね」とか「君なら一人で生きてゆけるよ」とか言い残して彼女らの前から姿を消していく。もちろん「やらせてくれ」とか「愛人にならないか」とか「彼女になってくれ」とか、言い寄ってくる男性はあらわれはするのだが、つきあいだすと、「午前七時には朝飯つくれ」とか、「俺が帰る頃には、風呂と飯を用意しておけ」とか言い始める。だからって、彼女たちの仕事が終わる午前五時に晩御飯を作って家で待っててくれたり、出勤前の午後3時に朝御飯とシャワーを準備してくれてるわけじゃない。「家事ができないなら水商売は止めろ、おまえ一人ぐらい俺が食わしてやる!」彼女たちは強い人間だから自分の夢を捨ててまで誰かと一緒になろうとは思わなかった。入れ替わり立ち替わりする男性客の中に、いつもそばにいて優しく見守ってくれる人なんていなっかった。なのに、この仕事に彼女たちがこだわり続けるのは、やっぱり、すてきな男性に会うチャンスというわずかな可能性を捨て切れてないからなんだよな。時間を共有できて・・自分のスケージュールに合わせてくれて・・家で大人しく待っててくれる人・・の代用品として猫がこの部屋にいるのだと思う。午後三時に起きて、午前五時に帰る生活に合わせる男性なら、彼女たちとの共同生活もできるのだろな、きっと、たぶん。
午前六時前、コンビニから出て、屋台のラーメンを食う。目の前を七・三眼鏡ネクタイの集団が流れていく。早朝出勤のサラリーマンが、駅の売店で菓子パンを二つ買っていく、この時間に出勤するのでは、奥さんも朝御飯を作ってくれない。駅のホームが賑やかになりだすと、高校生もぼちぼち電車に乗り始める。
「ヨネっちと、相川あやしくない?」
「あやしいよね、あのふたりぃーー」
「うそ?かなりブルー入ってるよ、それ!あたし的には、けっこダークじゃぁん?」
「本人に、きいてみたんさぁ」
「したら?」
「相川の奴、シカトしてやがんの(笑)」
「て、ゆぅーーか、あの二人ぜってぇーだっつーの!」
の集団と、深刻な顔で単語帳をにらみつけてぶつぶつと・・・アバンダン=捨てる、アドマイヤー=感嘆する、アドミット=承認する、アドバンス=進歩した/発展した・・・と呪文を唱えてる集団は、着ている制服が違う。制服をみれば偏差値が分かるというが、みなくても十分分かるし、偏差値が低い方が幸せそうに思える。
帰宅時に、たこ焼きやフランクフルトを買って食う制服と、英単語でしりとりをする制服。駅のプラットホームはアリとキリギリスの通過点だ。駅前の屋台で午前六時にラーメンを食う自分たちはキリギリスで、早朝出勤をするサラリーマンはアリなのだろう。朝六時、徹夜、眠い、この日、僕は本当に、学校に行くのだろうか。
![]()
多摩ニュータウン。新宿=内環状線まで電車で四・五十分のこの街は、日本最大のベッドタウンだ。バブル崩壊と共に住民の居住率が急減したニュータウンの象徴的存在であり、かつ住宅公団という公共団体が都市計画の一環として作り出した人工都市である。イギリスのサッチャー元首相から「うさぎ小屋」とののしられた建築物。それは金のある人にも、ない人にも平等に、安価で住み心地の良いコンクリートの箱を与えようという社会主義的配慮。統一規格の大量生産品。ぼくたちはこの都市を徘徊しながら、多摩ニュータウンに流れる都市設計の思想に触れたいと思う。
新宿駅から電車で四十分、京王多摩センター駅にたどり着く。地上五メートル、駅ビルの二階に位置する改札口を出て左手には幅広い大通り。天井は吹き抜けで、左右の壁も肩までしかなく、眼下には二階の歩道を垂直に横切る車道とバスターミナル。歩道と車道が立体交差しているにも関わらず立体交差点の印象を与えないのは、改札口が既に駅ビルの二階に位置しているため階段を上り下りする負担を歩行者に与えていないのと、幅広く日当たりの良い歩道が、そこが二階であるという印象を僕たちに与えないためである。歩道の下にある日当たりの悪い地上には車道と駐輪場とバスターミナル。あくまで歩行者優先の思想が見て取れる。
空中庭園のように宙に浮いたその歩道は、さらに階段を積み重ね、地上との距離を広げながら、左右に広がる他のデパートの二階・三階へと続いていく。歩行者は階段を上り下りすることなく、その歩道と同じ高さのフロアへ移り、そこからデパートのエレベーター=エスカレーターで移動すればいい。高齢者や身体障害者に優しい作りになっていることは、新宿や他の駅での歩道橋だらけの立体交差点と比べれば一目瞭然だ。そこが二階であることを忘れるほどの空中歩道をまっすぐに突き抜けると、だだっ広い広場と大木、小さな木々と植物、左手には地中海をイメージしたという白と青のメルヘンチックな建物。日曜日には大道芸人達がやってきて、パントマイムと一輪車、火のついたこん棒でお手玉して、棒状の風船をねじって犬の形にする。母親に手を引かれてやってきたよちよち歩きの乳児は、白塗りのピエロを見ておびえ、泣きだし、ピエロに握手され、犬の形をした風船をもらって泣き止み、ほほえむ。時間が来ると右側の時計台から、人形が出てきて演奏が始まる。広場には子供が好きなだけ走り回れるスペースがあり、母親も安心して子供の手を離し、子供の好きにさせる。広場の真ん中に大木が生えてるだけに気付かないのだが、ここはあくまでも二階であり、宙に浮いた空中広場なのだ。子供が走り回るそのすぐ下には車がびゅんびゅん走っているのだ。もちろんその車が広場の子供をひき殺すことは有り得ない。ぼくはこの広場の設計者に、その思想に、最大限の敬意を表したい。
その広場をさらに突き抜けると、高く積み上げられた階段の上に真っ白なパルテノン神殿がそびえ立つ。夜にはこの建物が暗闇の中でライトアップされ、さらに荘厳な空気を帯びるのだが、ここにきて建築物の意味、設計者の意図が突然見えにくくなる。多摩に、パルテノン神殿、略してパルテノン多摩。この建築物はギャグではなく、ごく普通に、パルテノン多摩と呼ばれている。建物の中は、いくつかのホールから成っており、地元の市民グループによる絵の展覧会や、地元高校・大学の吹奏学部による演奏会、つかこうへい主催の「熱海連続殺人事件」の公演や、「シェリー」など比較的マニアックな映画の鑑賞会など、地元文化の交流に使われている。新宿のコマ劇場などと違い、主婦が繁華街に出ることなく、子供や夫の夕御飯の準備の心配をすることなく、家事のあいまにごく自然に立ち寄れるのが、住宅地の真ん中にあるホールの特徴だ。コマ劇場などの場合、新宿まで電車で四十分、駅から歩く時間も考えると往復で二時間はかかる。帰りの時間がラッシュアワーと重なることを考えると四・五才の子供を連れて新宿に出るのも一苦労だ。かといって子供の世話を同居している姑にまかせるのも気が引ける。これがいつも買い物をしている多摩センターなら、夫や姑の目も気にせず、思う存分文化を堪能できる。客層も新宿なら、結婚していない二十代か、子離れした四・五十代に二分され、特定劇団の熱狂的お取り巻きが主流となるところだが、四・五才の子連れや若夫婦が目立つのもパルテノン多摩の特徴だ。周りが子連れだから、子供が泣き出したりぐずり出しても、その子を抱えてホール外の待合い室へ出ていく両親に対する周囲の目も温かい。友達感覚の夫婦、結婚しても恋人でいようねと言い合ったニューファミリーの理想がここでなら実現出来そうな気がする。夜の九時半頃、闇夜にライトアップされたパルテノン神殿から青やピンクのドレスを身にまとった夫人達がキャッキャはしゃぎながら駅側へ押し寄せてくるのを見るとベルサイユのバラ、もしくはシンデレラのワンシーンを見ているかのような錯覚にとらわれる。二階であることを忘れさせる空中広場の演出とはうって変わって、広場とパルテノン多摩をつなぐ道を細めの並木橋にすることで、自分の立つ位置が大地に根ざした地上ではなく、どこか浮足だった場所であること、そして白い照明でふち取られた橋を渡り、現実の向こう側に歩いていこうとしていることなどを無意識の中で感じとれるようになっている。そのように思えた頃には悪趣味に見えたパルテノン神殿も、夢と幻想を提供するごく自然な建築物に見えてくる。
パルテノン多摩を抜けると、みどり広がる多摩中央公園が広がっている。この手の公園は犬の散歩に欠かせない。パルテノンのわきにある人工的な湖風の池と芝生。夏にはここがビアガーデンになる。休日にはビニールシートをひいて親子で日なたぼっことフリスビー。夜、親の目を盗んで家を抜けてきた高校生が集まって語り合うのもこの芝生の上だ。湖風の池、止まってしまった噴水、月の光と街灯が池の水面で揺れている。空を流れる雲のすき間からまるで宗教画のような一条の光、月光、それとも真夜中の太陽、光は左右に揺れながら、地上を照らす。UFOに違いない。光が照らす方向にぼくらは走り出す。光に導かれる昆虫のように、動物として本能が光に向かって走らせる。多摩中央公園の端、街灯のない方向に誘われる。サーチライトは人気のない暗闇にぼくを誘う。けもの道の先にあるのは鳥居。神も霊も信じないぼくさえも鳥居をくぐるとき、不吉な死者の視線を感じ、首すじがぞくっと来た。
白山神社の境内を抜け、たどり着いた先にはUFOも神の啓示も奇跡もなく、空を照らすサーチライトと小さなコンクリートの建築物。多摩クリスタルと書かれた看板。光はサーチライトによって作られたファッションヘルスの広告だと判明し心のドキドキも終わりを迎える。合法的に本当に若い女を抱きたいと思えば、入学シーズンの学生街の風俗に限る。この辺りは共学・女子大共に多く、売り手も買い手も何万人単位でいる。しかも短大の場合二年、四大でも四年で新陳代謝をする。売り手も買い手も毎年三月、四月で三分の一程度が入れ替わる。それだけ需要と供給の新規開拓がスムーズでかつ市場もでかい。野猿街道沿いのT字路で見かける多摩クリスタルの捨て看板やこのサーチライトのリース料も月五十万は下らないだろう。立地条件的に見て、日本で最も稼いでるファッションヘルスの一つだと思われる。
公園を抜けたこの辺りは都市開発計画の範囲に入っていない。周囲には古くから在ると思われる一戸建ての家、公団が作った建て売りの大量生産品ではなく、統一感のない歴史を感じさせる家屋。ぼくたちはそこを迂回してさらにその奥、ニュータウンの奥地に入っていこうと思う。
郊外の閑静な夜の住宅地。歩いていて妙に落ち着くのはなぜなんだろう。ニュータウンはすべて高層ビルばかりかと思うとそうでもない。庭付きの一戸建ての集落もある。車が一台入るガレージに、芝生付きの庭、二階建てのオシャレな建て物。それは日本の古い木造家屋ではなく、ヨーロッパのレンガ作りをたぶんに意識した作りで、三角形の出窓にレースのカーテンもしくはブラインド。すだれやしょうじ、のれんの類は顔を出さない。芝生の上には犬小屋か子供用のブランコ、もしくはガラス張りのカフェテラスか、キャンプ用のバーベキューセット。まかり間違えても庭沿いに縁側を作ったり、井戸や池を掘って盆栽を並べ、日本庭園にしてしまってはいけない。あくまでアニメ「メイブルタウン物語」のパームタウン編に出てきたような街並みでなくてはならないのだ。そこにあるのはカミュやアラン=ドロンに代表される地中海文化に対する憧れ。アメリカやイギリス・フランスでなく、地中海というところから、カミュやアラン=ドロンにあこがれ、六十年代に青春を過ごした太陽族による設計であると思われる。さらに駐車場や車道をなるべく端に追いやり歩道と自転車道をメインに持ってきたところも人に優しい街作りという点でさきほどの空中広場と同じ思想を感じる。出窓、洋風の一戸建て、自転車と並んで高級感を出しているのは、このなだらかな坂道だろう。高級住宅地にはなぜか坂道が似合う。平地の直線で仕切られた街並みでなく、やまあいの扇状地に作られた曲がりくねった道となだらかな坂こそが、高級住宅地に良く似合う。一つは山の手と下町という言葉の語感から来る錯覚かも知れないが、敗戦後の焼け野原から復興した沿岸部の三角州と、高度成長後、余裕を持って開発された扇状地=山あいという差もあるだろう。戦後すぐの建坪率で建てられた市街地と先進国の仲間入りを果たしてからの建坪率で建てられた住宅地の差は大きい。住宅公団の物件でありながら、高級感あふれる低層住宅を抜けると、今度はテニスコートや野球場の設備を完備した公園が見えてくる。緑の中のランニングコースを走るおじさん。テニスコートにはダブルスをするアベックと若夫婦。そして老人用にゲートボールのコースも用意してある。マンションのすぐ前にベンチと共にあるのが嬉しい。歩き疲れてベンチに座る。今夜はここで野宿だ。
集会所の伝言板にはパッチワークに生け花、英会話とテニスとその他多くの二十八種にも及ぶサークルの活動時間と場所が書かれている。新興住宅地には地域社会と近所付き合いがないといわれる。けれども古い地域社会には何十種にも及ぶサークルは存在しない。これは単純に人口密度の差による物だろう。庭&ガレージ付き一戸建て建築の人口密度ではパッチワークだの俳句だのといった趣味のつながりよりも物理的距離が優先されるのに対し、人口密度の高い高層マンションでは物理的に近い人すべてと付き合うのは時間的に不可能なので近所に住む大勢の人の中からさらに自分に近い趣味を持つ仲間に人間を絞り込んで近所付き合いをする。例えば一つのフロアに二十八世帯分の部屋があり、それが三十階建てで、そのビルが十個近所に建ってるとして、単純計算して二十八掛ける三百、八千四百世帯分のご近所が存在するわけで、その八千四百世帯すべてと平等の時間を割いて近所付き合いをするのは不可能なので、第二・第四水曜日の午後一時から四時まで集会所の第二学習室に集まる編み物サークルの人達との近所付き合いが中心になってくる。これは付き合う相手を物理的距離によって決められるのではなくこちらの趣味によって選択できるシステムなので一見良いことのように思われるが当然欠点もある。どの集まりにも参加できない人、参加しない人が生まれてくる可能性があるのだ。
どの集まりにも参加できない人、しない人、特に高層マンションの高い階に住む老人などの場合事態は深刻である。エレベーターでなければ外に出られない、家へ帰れない。高齢のため外に出るのがおっくうになる。けれども自分達の子である若夫婦と住んでるわけではないので、食料品の買い込みなどは自分でやらなければならない。息子夫婦と暮らそうにも公団の3LDKでは二世帯でなど暮らせそうもない。一人暮らしの御老人などの場合、何らかの事故で亡くなっても発見されるまで結構な時間を要すこととなる。
いま、多摩ニュータウンを始めとする公団住宅の居住率が下がっているという。居住率二・三十パーセントの建物の中のある特定の階、例えば十八階には二十八部屋ある中で入っているのが一部屋だけで、高齢の老夫婦が二人、後はみんな空室という例もある。防犯や治安の面からも老夫婦の精神衛生面からも不安定要素が多い。バブル崩壊後の地価下落でより安い一般住宅に移り住んだのが若い人達で、引っ越しをする体力のない老人だけがゴーストタウン化した高層ビルのより高い階に住んでいるというのは、ちょっとしたジョークだ。
公団住宅の居住率の低下について新聞は「バブル崩壊以後、若い人達が狭くてもより会社に近い環状線沿線に住まいを求めたため」と説明している。住宅公団は明らかに人口構成比を読み間違った。いまの日本で最も人口の多い年代は第一次ベビーブーマー世代=団塊の世代と、その子供達=第二次ベビーブーマー世代だ。団塊の世代は六十年代に地方から東京の大学に出てきて、四畳半のアパートに住み、四畳半フォークを聴きながら火炎瓶を投げ、ある者は高度成長期のモーレツ社員として、別の者は植木等ばりの無責任男としてサラリーマンになり、身を固めて、「夫婦お断り・子供お断り」のアパートから追い出される形でベッドタウンへ移り住んだ。年功序列で給料が上がり、一戸建てのマイホームや株券や土地を買い八十年代のバブル、そして崩壊。団塊の世代の何割かは、このバブル前後に公団住宅からマイホームへ移り住み、その子供達である第二次ベビーブーマー達はまだ、社会人になったばかりで、ベッドタウンに住む年齢に達していない。ベッドタウンが生涯の中である一時期を過ごすための物であるとするなら、市場と需要の縮小はあらかじめ予測できたはずである。
結局、公団のミスなんてのは、ぼくらにとってどうでもいい。第二次ベビーブーム世代のぼくにとって、親の世代:第一次ベビーブーマー/団塊の世代ってのは、一つの有力なサンプルなわけで、ぼくとしてはそんな親たちの世代が作った都市開発計画なり住宅なりを観て、何をまねて、何を直すかって辺りが、その・・ねむい。一睡もしてないのに周りが明るくなってくる。午前四時の青い光が降りてくる。明け方だ。今日もまた、夜が壊れて、朝が始まる。幼い頃みた夜明けがまた繰り返される。
犬の散歩をしている婆さんが気安く声を掛けてくる。しわくちゃの体に露出の高い黒と赤のラメの入った原色の服。どのようなコミュニケーションを求めてますか。超高層のビルは老体にこたえますか。都市のコミュニケーションは老人に冷たいですか。そんな思いが何年後かの自分宛てに、そのまんま繰り返され続けている。
トップヘ BGM「憧れ」作曲:森田博美