 採用分
採用分フリッパーズギター結成10周年を記念してflippaMLの加藤さんを中心に作られた非公認ミニコミ。某ページに転載されました。
パーフリのデーターを持ってるわけでもなく、関係者でもないのに推測と妄想だけで長々と書いてしまいました
 採用分
採用分
いま、フリッパーズギターのファンを名乗っている人達のほとんどが、解散後に彼等を知った、もしくは解散後に彼等を好きになった人達だ(少なくとも私がMLを通じて知る限りでは)。その好きになるきっかけは、解散後のソロ活動であったり、ポストフリッパーズと言われるバンドの活躍であったり、様々なのだが、当時の邦楽シーンを知る人達にとって、やっぱり彼等は早過ぎたバンドだったと言うのが正直なところではないだろうか。
今でこそ、フリッパーズギターはファッションリーダー的存在だったとか、彼等のボーダーシャツはモラトリアムの象徴だとか言われるが、バンドブーム末期のあの時期、彼等のファッションは非常に奇妙なものに見えた。
あの時代、モラトリアムの象徴はボーダーシャツではなく、逆立てた赤髪と破れたGパン、そして白のTシャツとGジャンもしくは皮ジャンだった。ミュージシャンと言えば、みな髪を染めたり、立てたりし、髪のトサカの高さや形を競い、顔には必ずメイクを施していた。あの時代、ライブとは日常から非日常へ跳ぶための行為であり、異常な姿をした異常な人を見に行く見世物小屋がライブハウスであった。
あの当時、見世物小屋の見世物であるミュージシャンに求められたのは、異常さ、派手なパフォーマンス、政治的メッセージだった。「俺は高木ブーだ!」と叫んだ筋肉少女帯、「ドブネズミみたいに美しくなりたい」と叫んだブルーハーツ。ツアーごとにコンセプトを決め、衣装からダンスから照明からセリフ・ストーリー構成まですべてをコンセプチャルにみせた米米クラブ。そして、有象無象のビジュアル系・ホラーロック・シアトリカルロックバンド達。それらの元になっていたのは、ステージの上で幼児に見立てた人形を切り刻んだアリス=クーパーだったり、口から血や肉を吐いたオジー=オズボーンだったり、火炎放射器付きのベースで火を吹いていたキッスだったり、ピコピコシンセに合わせてロボット振りをしたクラフトワークやディーボだったわけだ。
そこへ、フリッパーズギターが普段着で登場したのだ。髪を染めてるわけでもなく、声高に何かを主張するわけでもなく、ごく普通の人がごく普通にごく普通の曲を演奏したのだ。その時の言いようのない違和感というのは、例えばハロウィンの仮装パーティーで、みんな何らかの仮装をしてくる約束になっているにも関わらず、普段着で登場した二人組が悪びれもせず「ぼくたち、普通の人のコスプレをしてますから」と言って入ってきた時の何かこう・・ねじ曲がった違和感。異常な格好をすることが義務付けられてる場において、普通の格好で登場する事がいかに異常なことなのか。異常が普通で普通が異常である時の「普通」とは一体何を意味するのか。
もちろん、パンキッシュな歌詞で大人達や学校や体制を攻撃することが美徳とされたビートパンク全盛期にも、それに対するカウンターカルチャーとしてのネオアコースティックシーンは存在した。それは、フリッパーズギターを真似た音やファッションを意味する今日的ネオアコではなく、当時の主流であるビートパンクと対立する事によってその存在をより分りやすくしたネオアコースティックだった。当時のネオアコのキャッチフレーズは「いまの騒々しい、電子音に疲れた人へ」とか「優しい」「癒しの」なんて言葉が飛び交い、ビートパンクへのカウンターである事をまず表明する。また、服装は極めてフォーマルで白のブラウスに蝶ネクタイや棒タイ、黒のベストにサスペンダーとおでこ靴。女性の場合はベレー帽もしくはフェルト系の帽子でアートな雰囲気を醸し出し、服は露出の少ないワンピース。楽器はクラッシック系の弦楽器や管楽器に時々オカリナを混ぜてみたりする。プロモーションビデオのロケ先は森か高原か草原か湖で、小人や妖精や天使に出会う歌を歌う。ビートパンクとは別な意味の非日常へ連れて行くのが当時のネオアコースティックなのだ。
当然、都市における学生のなにげない日常を歌ったパーフリの歌や、今ではネオアコの象徴にもなったボーダーシャツは、この当時のネオアコースティックシーンの中に存在しない。「さようならパステルズバッジ」のプロモーションビデオは、高原でも癒しでもない東京の地下鉄での撮影だし、音はかなり激しいロックだ。ライブCD「オンプレジャーベント」の「カメラ×3」を聴くと当時のビートパンクバンドそのままな音で、妙に懐かしい。フリッパーズギターが一番最初に受けた商業誌のインタビューは「DOLL」ってのも、彼らのわからなさ加減がよく出てる。だって、DOLLって血だるまの死体とか、スキンヘッドの暴動とか、暴力的で汚い写真の載ったハードコアパンク雑誌だぜ。アマチュア時代の唯一のオフィシャルライブの時、対バンバンドがロックンロール系だったこともあって、客席にはポマードベトベトの皮ジャン&レザーパンツのこわおもての人しか居なかったってのも、笑えるエピソードだし。ネオアコなのに高原とか癒しから一番遠い位置に居るじゃん?
フリッパーズギターの伝説の中で、音楽誌でなく、ファッション誌に広告を打った。というのがある。フリッパーズギターがいかにオシャレなバンドであったのかを示す伝説なのだが、実際のところ、広告を打とうとした時に、消去法で真っ先に音楽誌が消えてしまったのが実情ではないだろうか。当時の音楽誌というのは、音のクオリティー云々よりも、まずコンセプトやメッセージの目新しさ、映像の派手さに目が行っていた。音は雑誌では伝えられないが、コンセプトやメッセージは活字で伝えられるし、映像は写真で伝えられる。編集者にとって扱いやすいのは映像と活字なのだ。着ぐるみの衣装を自分達で作っているバンドやカラフルな色の髪をなびかせているバンドの中に混じって、普段着を着たバンドの写真というのはどうしても色あせてしまう。けれど、当時のファッション業界は装飾を省いたミニマリズム・・マキシシングル「カメラ×3」で二人が着てる服・・が流行でむしろそのミニマルなファッション雑誌の中にいる方が馴染みやすかったのが当時のフリッパーズギターだった。
ジャケット写真をめぐる謎
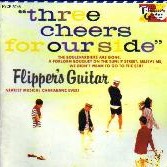 じゃあ、その異常なまでに普通だったパーフリは本当に普通だったのかというと、やっぱりどこか異常だった。例えば、ファーストアルバム「海へ行くつもりじゃなかった」
じゃあ、その異常なまでに普通だったパーフリは本当に普通だったのかというと、やっぱりどこか異常だった。例えば、ファーストアルバム「海へ行くつもりじゃなかった」のジャケット写真。特別異様な格好をしているわけじゃない。火も吹かないし、血も流さない。なのにどこか変だ。海へ来たのに、砂浜なのに誰一人として水着にならないし、泳ごうともしない。五人が五人とも別々の方向を見て、しかもなぜか腕を組んでうつむいたりして、革靴をはいたまま海に入ろうとしている人すらいる。この人達は海に来たのに泳ごうとしない。では何をしに来たのだろう?アルバムのタイトルは「海に行くつもりじゃなかった」だから、目的を持って海に来たわけじゃなく、気がついたら海にいたということか。これなら水着にならないのも納得できる。じゃあ、一体どこへ行くつもりだったのだろう。何をするつもりだったのだろう。タイトルがそのまま謎かけになっているが、答えはどこにも示されていない。目的地とは違う場所に来て、そこから目的地に向かうわけでもなく、いったん家に帰って出直すでもなく、海で、てんでバラバラに呆然としてる人たち。
 裏ジャケットを見ると、砂浜で三つのビーチパラソルの下で、みんな海の方を見て、一人は腕を振り上げている。五人が同じ方向を見ている、しかも砂浜に座ってる。表のジャケ写真がアルバムの始まりだとしたら、アルバムの終わりにふさわしい写真だ。バラバラの方向を向いて歩いてる集団から、一つの方向を向いて座る・・ある種の秩序と方向性、安定感が出てきている。目指す方向は海。砂浜に座る事は、その姿勢=方向性がある程度の長時間維持されることを意味する。始め、海に行く事は不本意だったが、最終的には海に来てよかった。海に出ることに意義を見出した。というストーリーがそこに現れる。でも、そんなすっきり物事を解決させてくれるほどパーフリは甘くない。このビーチパラソルはどこから持ってきたのだろう?もしも家から持ってきたのだとすると、海に来るつもりがないのに彼等はビーチパラソルを持ち歩いていた事になる。普段からビーチパラソルを持ち歩く五人組、しかも三本も。
裏ジャケットを見ると、砂浜で三つのビーチパラソルの下で、みんな海の方を見て、一人は腕を振り上げている。五人が同じ方向を見ている、しかも砂浜に座ってる。表のジャケ写真がアルバムの始まりだとしたら、アルバムの終わりにふさわしい写真だ。バラバラの方向を向いて歩いてる集団から、一つの方向を向いて座る・・ある種の秩序と方向性、安定感が出てきている。目指す方向は海。砂浜に座る事は、その姿勢=方向性がある程度の長時間維持されることを意味する。始め、海に行く事は不本意だったが、最終的には海に来てよかった。海に出ることに意義を見出した。というストーリーがそこに現れる。でも、そんなすっきり物事を解決させてくれるほどパーフリは甘くない。このビーチパラソルはどこから持ってきたのだろう?もしも家から持ってきたのだとすると、海に来るつもりがないのに彼等はビーチパラソルを持ち歩いていた事になる。普段からビーチパラソルを持ち歩く五人組、しかも三本も。
もう少し普通に考えて、海の家から借りてきたってのはどうだろう。海の家というのは、人がにぎわう海水浴場ではでは絶対に必要な存在だ。けれど、表のジャケ写真にあるようなひとけのない浜辺の場合どうだろう。ひとけのない砂浜というのは、季節はずれの海、もしくは海水浴ができない何らかの理由、波が高いため非泳遊区域に指定されているとか、そういう場所だ。そんな人のいない砂浜で海の家が営業しているだろうか。人のいない砂浜で店を開いている海の家と、そんな場所に不本意ながらもたどり着いてしまった五人の若者達。妙にシュール過ぎやしねぇーか?それに、裏ジャケの右端にあるデレクターズチェアはどうなる?これも海の家から借りたのか、それとも普段からこれを持ち歩いているような人達なのか。
ジャケ写とジャケ写の間にある歌詞カード、ここに問題を解くカギがある。彼等は車で海に来ていた。車にきっとデレクターズチェアも積んであったのだろう。ひょっとするとビーチパラソルも車に積んであったのかも知れない。去年の夏にビーチパラソルを三本、車のトランクに入れてそのままになっていたのが、偶然海に出てしまった際、役に立ったと。でも、この写真に載ってる車ってのは、四人乗りの小型車、ビーチパラソル三本も入るだろうか?やっぱり、パラソルは海の家からの借り物か?と、いうより、四人載りの小型車に乗って五人は来たのか?そりゃこの車も、無理すりゃ五人乗れなくもないだろうけど、大型犬連れてんジャン?犬どうすんだよイヌ!犬だけ車につないで走らせるってワケにもいかねぇーだろ。車の隣に古い型のスクーターが一台停まってて、それにボーカルの小山田君が乗ってるから、残り四人と大型犬一匹が小型車に乗る。無理すりゃ不可能じゃないんだけど、結構きゅうくつそう。しかも、レトロな色合いの旧式の車に四人と一匹を乗せて走る馬力はあるのか?言っちゃ悪いが、砂浜とか坂道では上手く走れなさそうな気がする。
いや、それよりも何よりも、最大の問題はここだろう。バラバラの方向を向いてうつむいて歩いてた五人が、裏ジャケでは一つの方向に向いて座っている。これは一見ハッピーエンドに見えるが、彼らは一つの方向に向かって進んでいない。一つの方向に向かって座っているのだ。バラバラの方向に向かって歩いていた五人が、一つの方向に向かって座る。歩く=進む=行動する事をやめて、座る=見る=見守る事を始めた彼ら、その視線の先には何があるのだろう。片手を振り上げる彼は何かを応援しているかに見える。一体何を?普通に考えれば彼らの視線の先は海だ。その海で何が起こっているのか。ここで、このアルバムに収録されている最後の曲を思い出して欲しい。レッド・フラッグ。ある決意=赤い旗をなびかせて船は海に向かって進む。海では幾多の困難が予想される。けれども船は進む。どこか、パーフリのラストアルバム「ヘッド博士の世界塔」と似てないだろうか?「逆巻く波間の小舟でさらに1000年/ジョークのつもりがほんとに降りれない」となげく二人のフリッパーズギターと、旗をなびかせて進む船を見つめる五人のフリッパーズギター。そういえば、五人のうちの一人は「小山田圭吾=パーフリのボーカル=現・コーネリアス」のマネージャーになり、コーネリアスのツアーではドラムを担当している。当時キーボードを担当していた別のパーフリは音楽評論家として活躍中で「小沢健二=パーフリのギタリスト」参加の「マービン=ゲイ トリビュート」に好意的なコメントを寄せ、オザケン告発本「前略小沢健二様」(当初、小沢健二の悪口をかつての旧友から引き出す目的で編集された。最終的には悪口以外の様々なコメントも載って出版される)にはノーコメントを貫き、告発本の編集部からさえ「うーん、正しい。」と言われたりしている。つまり、五人のフリッパーズギターが見守る先には、二人のフリッパーズギターが居る?
でも、やっぱり、海に行くつもりじゃなくて、どこへ行くつもりだったのかはよく分らないし、何をするつもりだったのかもよく分らない妙に謎だらけのジャケット写真であったりする。この分り難さが、あまりにも分りやす過ぎた当時の演劇的ロックシーンの中に「普通なのに異常」というポジションを築き上げる。
早過ぎたバンド
CDジャケット一つとっても分りにく過ぎたフリッパーズギターは、あの時代すぐには大ブームにならなかった。当時ラジオから流れてきたフリッパーズギターを紹介するDJの声はこんなものだった。
「これはね、フリッパーズギターつって、いまラジオDJ業界ではすごい事になってるんだけど、一般の人にはまだ届いてない音で、一応ね、英詞バンドなんだけど、日本語でも歌う、メンバーも自分が会った時は男の子ニ人組みだったんだけど、ジャケットでは五人になってて、クレジットも五人なんだけど、本人達に聞くと、人数もメンバーもまだ決まってないという非常に謎の多いバンドで・・」
興奮気味に紹介されるその声から、本気でフリッパーズギターが好きだというのが伝わってきたが、バンドの実態は一切分らないままだった。たぶん、五人から二人になった経緯を説明するのを面倒くさがった二人が、いつもの様にインタビュアーの質問をはぐらかした結果だろう。その紹介後に流れた英詞曲は「ノイジーなギターサウンド」と「パンキッシュな歌詞」が合い言葉だった時代の流れとは無縁の、耳障りの良いポップスで、選曲を主な仕事とするラジオDJ業界の厚い支持があるということは、その曲がCMやドラマのサントラに多く使われる可能性を示していた。(実際知名度の割りに多くのタイアップがあった)
派手な仮装と演劇的なコンセプトで始まったバンドブームも、そのブームを支えたバンドが、ブームの加熱に嫌気がさし、徐々にメディア露出を減らす一方、より過激な仮装をした・・けれど音的にはクオリティーの低い新しいバンドが次々とデビューし、テレビ・ラジオ・有線からは、派手な映像の・・けれどクオリティーの低い音が溢れ返る。ブームは確実に終息していくが、次の新しい音は見えない。そんな時期にフリッパーズギターは解散する。
その後に来たブームが、Being系ブームである。CMやドラマの主題歌とタイアップしたバンドが、ライブやメディア露出を一切せず、バンドの集合写真はおろか、正式メンバーの人数や名前すら公開せずに、大量のスポットCMを打ってCDを売る。この時、もしもフリッパーズギターがいれば、Beingを超える流れを作ってくれたのでは?・・と、ちょっと思った。フリッパーズギターへの再評価は、解散からずいぶん経って、元パーフリメンバーのソロ活動と、パーフリフォロワーが渋谷系という名で活躍し始めてからだ。
ボツネタ
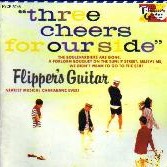
一般にフリッパーズギターのサイケデリックアルバムといえば3rdを指すのだが、実は1stで既にその傾向が出ている。注目はフリッパーズギターのロゴ。カラフルな色の渦巻きとフリッパーズギターの文字。このデザインだけで既にサイケデリックっぽいのだが、このデザインの元ネタと思われるのが、ビートルズのサイケデリックムービー「マジカル・ミステリー・ツアー」のロゴ。まさにそのままなデザインなんだけど、史上最大のサイケデリックアルバムといわれた「サージェント・ロンリー・ハーツ・ペッパーズ・クラブ・バンド」の製作後、LSDでぶっ飛んだまま撮られたこの映画は、ストーリーらしいストーリーも無くバスツアーするビートルズが雲の上で下界を見下ろしたり、セイウチになったり、突然踊り出したり・・まあ、そういう映画でそのサイケデリックムービーのロゴからパクって来てる辺りが、この頃既にパーフリはサイケデリックな資質を持ってたのではないかと言えるんだな。
インタビューを読む限りだと、フリッパーズギター文学部門担当のオザケンにその傾向が強いらしく、サンリオSF文庫のウイリアム=バロウズなんかを高校時代愛読していたらしい。
で、それだけで、パーフリとサイケデリックを結びつけるのもあれなんで、もう一つ出すとこのジャケットでパーフリの連れてるドギードック。白地に黒ブチの彼の文様がもろ「101匹ワンちゃん」byウォルト=ディズニーで、70年代のヒッピーの間じゃLSDをキメてディズニー映画ってのは割りとトレンドだったんだけど、その中でも101匹ワンちゃんは格別で、ディズニー自身のコカイン疑惑が出るぐらい、特にオープニングがぶっ飛んでるんだな。真っ白な白地がしばらく続いて、突如黒い斑点が出る。斑点がバババババっと増えると、そこにペンが現れて斑点の間に境界線を描いてって斑点の一部が犬の絵になる。次から次に犬の輪郭が描かれ、そのかしこにあった斑点すべてが犬になって動き出す。始め斑点に見えたものはすべて犬の集団の文様であった事が分ると今度は真ん中の犬にカメラが寄って行きどんどんズームになって犬の斑点にカメラが寄って、斑点が画面全体に広がって画面が真っ暗になるとそこから突如反転。真っ白な元のキャンパスがそこにある。ってな感じの、マジでディズニーが薬キメて作ったんじゃねぇーのと思えるような特殊効果=ダマし絵の連続。そうそう、この映画に出てくる悪役の女性毛皮商も変なパイプ吸ってて紫色のけむり吐いてるし。もちろん、ディズニーが薬使わなきゃだまし絵の一つも作れないような貧しい才能の人だったとは思えない。だって、それを言い出したらマルグリットはただの薬中で、サルバトール=ダリはただの精神異常者になっちまう。ただ、ほんと、ヤバイんじゃねぇーの?って思えるぐらいの視覚効果がこの映画にはあって、わりとLSD(麻薬の中でも幻覚作用に長けている)と結びつけて語られる事が多くて、その映画から実写の犬を引っ張り出す辺りがパーフリ成りの視覚効果。
だって、あのドギードック見たとき、初対面なのにどこかで観たことのあるような変なデジャヴーに襲われなかったか?どこかで観たのだけれど、どこで観たのかわからない。売れない画家がキャンパスに向って筆が進まないでいる。白いキャンパスにインクが飛んで斑点が生まれる、斑点に筆が輪郭を書き込み犬の絵になり、絵が実物の犬になってキャンパスから飛び出してくる。そんなアニメの犬をアニメから実写に飛び出すよフリッパーズ世界で初!なんだから。
もういっこ、いっけん上品に見えるパーフリが意外とワイルドなんじゃねぇーのという一例で、ネオアコの代名詞にもなったボーダーシャツ。ボーダーシャツの快進撃はこのCDジャケットから始まるんだけど、この頃のボーダーって、線が太めでさぁ、しかもシャツの上にトラッドなジャケット羽織ってるでしょ、ズボンはズボンで、中途半端に半ズボンだしさぁ。これもまた、極端な推測なんだけど、線が太いボーダーシャツって、欧米の囚人服じゃん?で、監獄から逃げてきた五人が囚人服を隠すためのジャケットをどっからかっぱらってきて着て逃げてる。本当は囚人なんだけどそれをトラッドなジャケットで隠して看守から逃げてきた。で、海に出るつもりじゃなかったのに、海に出てしまった。
これ、音楽的にいうと元々は刑務所で流れてる監獄ロックだった。刑務所で囚人達がやってるロックンロールパーティーが最高潮に盛り上がって、そのドサクサにまぎれて逃げ出してきたパーフリがトラッドな服に着替えてリゾート地に来ている。いま自分達はロックンロールではないような服を着てリゾートミュージックという場所にいるのかも知れない。でも、リゾートミュージックになるつもりは無かった。アマチュア時代の唯一のオフィシャルライブがリーゼントに皮ジャンの人達の前で行なわれたこととか、小山田君はああ見えても中学時代メタルキッズで、高校時代はガスマスクをつけてハードコアパンクバンドをやっていたとか、パーフリに影響を与えたネオアコバンド、アズティックカメラやオレンジジュースなんかもパンクロックの洗礼を受けて、パンクの後にパンクではない形で出てきたバンドだった事とか考えると、上品な上着を着ているけど、下地はJail‘s Rockだった、もしくはJail’s Rockを覆い隠すような新しい上着を仕立てるんだという意気込みを示しているとか・・うがった見方過ぎるか。
最後に、ジャケットに書かれた英語、普段目にしているけどあまり意味を気にしない奴を訳しときます。
まずは、右上のロゴから。「最新の音楽劇 フリッパーズギター キャラバンはどこまでも!」
次にタイトルのスリーチアーズは「賞賛を我等に」。辞書を引くまで知らなかったがスリーチアーズで、万歳三唱の意味がある。
その下に書かれたセリフが「街路の人々は通り過ぎて行った。サンリッツ大通りに見捨てられた花束。僕を信じて、僕等は海に出るつもりじゃなかった!」
これが、実は裏ジャケにも書かれているから、単なる気まぐれで書かれたセリフじゃないって事ぐらいはよく分かる。しかも面白い事に、「街路の人々は・・」のセリフは歌詞カードを開いて見開きの右端、どのページにも書かれてる。お祭り騒ぎの後に残る切なさみたいなのを上手く表現した言葉なんだけれども、この過ぎ去ってった街頭の人達ってのが、時期的に僕にはバンドブームのお祭り騒ぎに感じられるんだよね。して、道端に捨てられた花束がフリッパーズギターで、海ってのはメジャーデビュー。「バンドブームは終わった。路上にほっとかれたフリッパーズギター。でも、僕達はメジャーに行く気はなかったんだ。」ここまで来ると、翻訳でなくて、シドニー=シェルダンの超訳、もしくは創作にになっちゃうんだけどさぁ。
でも、こういう事を割りとストレートに書けるのも、英語=外国語だからなんだよね。だって、あのひねくれたオザケンやコーネリが、自分達の目の前を通り過ぎて行く人に、「僕達は道端に捨てられた花束なんです。どうか拍手を下さい。」なんて言うか?やっぱ外国語だから言えるんでさぁ、ほら、ニューヨークで「I LOVE NY」なんて胸元にデカデカと書かれたTシャツ来てるの、観光客だけじゃん。俺、浅草で胸元にデカデカと「浅草」と書かれたTシャツ着た外国人見てさ、「I LOVE NY」着るのやっぱ非英語圏だけだよと、つくづく思ったもん。
収録曲の中から、英語じゃなきゃとても言えないなって歌詞をちょこっと抜き出すと、一般的には当時の彼等が大好きだったバンド名&レーベル名を並べた曲と言われる「さようならパステルズバッジ」。収録曲中唯一ライブでの演奏がなく、レコーディング時に急きょ作られたこの曲。メジャーデビューによってロリポップソニックから別のバンド名に変えられる時の、複雑な心境を語ってると思われる個所が、そこかしこにあるんだよね。「それはある種のハッピーバースデイ」と言ってみたり、大好きなバンドを羅列した後「can’t die=死んだりしない」と言ってみたり、大好きなバッジを上着=アノラックから外して、「引出しの中にしまっておこう」と言って、「引出しの奥から、いつでもまた取り出せるさ」とうそぶいたニュアンスを残したり、「あの気持ちを決して忘れないと」誓ったり、最後なんかはもっとストレートに「そうだ、僕らのロリポップは何か純粋なものだった/だから今は 大好きなシャツを脱ぎ捨てて」と、フリッパーズギターのアマチュア時代のバンド名、ロリポップソニックを思わせる単語や、ロリポップソニック時代の唯一の音源、favorite shirtsを思わせる単語がストレートに出てくる。こういうレーベルに対する不満ってのを含んだ表現ってのは日本語でしちゃうと角が立つしさ、どうせ誰も意味を気にしない外国語って形式にすることで初めて出来る手法だと僕は思うんだな。
「カメラは暴力だ!」と上岡龍太郎は言ってたけど、その暴力の犠牲者になったとき、被害届の一つも出す権利がないのが芸能人だ。ちょこっと最近の例を出すと、松田聖子が再婚時の結婚式の映像を撮るのは良いけど放送してはいけない、もし放送する時には出演料を要求するってな契約を各テレビ局に突きつけた物だから、テレビ局サイドが怒って共闘を組み、松田聖子をTVで使わない事に決めちゃったわけだ。まあ、CMだけはスポンサーあってのものだから局側も柔軟な対応で見逃したんだけど、それでもメディア露出の減少は聖子の出演CM一本にまでCM契約を減らさせ、TVでプロモーション活動できなくなった聖子のシングルCDは、売上が二万枚にまで落ち、聖子が折れる形で決着がついたと言われるんだけど、メディア露出が自身の売上にも関わってくる芸能人にとって、カメラの暴力に対する手段は泣き寝入りしかないらしくて。
で、パーフリだ。1stを作る事で、プロモーション活動を余儀なくされたパーフリが、カメラの被写体にされる事も多かったはず。「カメラ トーク」というタイトル自体、プロモーション活動の中心である写真撮影&インタビューを意味してるわけで。その撮影&インタビューをこなしていれば、多感で賢い彼等の事、すぐにカメラの暴力性に気付かないわけがない。だって、写真を撮られる本人達には、その写真にどんなタイトルがつけられるのかさえ知らされてないんだから。
道端を歩いていていきなりパシャリとシャッターを切られると、普通の人なら怒る。でも、芸能人なら怒るに怒れない。プロモーション期間中のミュージシャンだって似たようなものだ。彼女と一緒に居るところとか、機嫌が悪くて怒ってることろとか、そういう撮られたくないような写真の方が、見る側にとって面白いし、撮る側にとっても金になる。撮られた時の対応も人様々だ。カメラマンを捕まえて殴る武闘派も居れば、その写真を使った出版社に殴り込んだアウトロー派も居るし、裁判を起こした合法派も居るし、頭脳派だと、夜の車中で女の子といちゃついてるところを正面からカメラ向けられたので、ライトをつけたなんてのも居る。ライトをつけると逆光で写真が写らないのだ。いま、一番一般的なのは、カメラマンを捕まえて、フィルムを没収するというパターンで、カメラマンもカメラを二台持ってって、撮ってない方のカメラを渡して新品の生フィルムを没収させるのが標準らしい。そうそう、フィルムを没収しようとしたら、カメラと一体型だと言われ、「そのカメラと同じ物買ってあげるからフィルム返して」と言ったサッカー選手もいたなぁ。
で、ひねくれポップなフリッパーズギターがカメラの暴力に対して取った行動は、2ndのジャケットでCDの購入者にいきなりカメラを突きつけるって手法だ。「アンタが僕達を見ている様に、僕等もアンタを見ている」とジャケットは言う。ダウンタウン風に言うと「お前は俺を見てるかもしれん。けど、俺は俺を見ているお前を見ているよ。」ってことだ。
 視線が客から芸能人に向って一方通行である時、客である僕等は一方的に商品=芸能人を品定めし、点数や○×を付ける。けれど、物を言わない被写体=静止画であったはずの彼等に、「僕もあんた達の品定めをするんだよ」と言われた時の驚きと暴力性は僕達に反省をうながせる。ひょっとして僕らは芸能人を高見から一方的に裁いてなかっただろうか?彼等に不可能な要求を突きつけてなかっただろうか?彼等も英雄である前に一人の人間であることを僕らは忘れていたのではないだろうか?自分のようなファンを彼等は好きでいてくれるだろうか?カメラを突きつけられることによって急激に甘くなって行く採点と評価。そう、彼等はカメラの暴力がカメラマンから発せられるのではなく、むしろ現像されたフィルムを安全な位置から見る閲覧者から発せられることを知っていたのだ。
視線が客から芸能人に向って一方通行である時、客である僕等は一方的に商品=芸能人を品定めし、点数や○×を付ける。けれど、物を言わない被写体=静止画であったはずの彼等に、「僕もあんた達の品定めをするんだよ」と言われた時の驚きと暴力性は僕達に反省をうながせる。ひょっとして僕らは芸能人を高見から一方的に裁いてなかっただろうか?彼等に不可能な要求を突きつけてなかっただろうか?彼等も英雄である前に一人の人間であることを僕らは忘れていたのではないだろうか?自分のようなファンを彼等は好きでいてくれるだろうか?カメラを突きつけられることによって急激に甘くなって行く採点と評価。そう、彼等はカメラの暴力がカメラマンから発せられるのではなく、むしろ現像されたフィルムを安全な位置から見る閲覧者から発せられることを知っていたのだ。
カメラマンを殴るのも捕まえるのも訴えるのもすべて、カメラという暴力の根源とは闘っていない。カメラマンは、有名人を見たいと願う消費者の欲望の代行者でしかないのだ。オーディエンスの手先であるカメラマンと無意味な闘いをすることを飛び越え、パーフリは無邪気に、笑顔で一般消費者にカメラを突きつけ、シャッターを切り、フラッシュを焚きつけてきた。それは明るくポップな仕草を装っているが彼等特有のそしてお得意の悪意とイタズラがうかがえる。CDジャケットをもう一度見て欲しい。こちらに向けられたカメラはいままさにシャッターを切られている最中なのだ。青緑色のブレとシャッター付近の集中線がそのことを端的に示している。
ポストフリッパーズの代表者として大々的に売り出されたロボショップマニアのジャケットを見ると彼等もまたパーフリと同じようにある道具を使って視線を演出している。だが彼等が決定的に違うのは、手にした虫眼鏡をそのCDを手に取った客から少ぉーーしだけ外しているのだ。パーフリからアイドル的&王子様的要素だけを引き継いだ彼等、パーフリの悪魔的イタズラ精神は引き継がなかった彼等、視線の暴力性に気付いた上でファンに気を使ってしまった彼等は、お客さんに虫眼鏡を通して視線を投げかけ、無邪気なフリして拡大鏡でファンのあら探しをするなぁーんてことはせずに、別の何かを覗き見ている。アイドルとしては非常に正しい選択。
じゃあ、その小悪魔的なパーフリのカメラ×3のジャケットをもう少しロボショップマニア寄りに、敵を作らない正当派アイドルっぽく解釈出来ないだろうか。ジャケットに描かれてるカメラのレンズにはカメラを構えた二人のパーフリがこっちを見て写真を撮ろうとしてる姿が写っている。鏡に映った鏡と、鏡に映った鏡の中の鏡・・的な合わせ鏡な状況だけど、ジャケットに描かれたおおもとのカメラ。これは明らかにCDの消費者に向けられたカメラ=視線だ。そのカメラの中に居る=写ってるのは、当然CDの購入者であるはずなんだけど、何故かジャケットではカメラを構えたパーフリの二人なんだよね。つまり、CDの購入者とパーフリが入れ替わっている。CDを手に取っているパーフリファンと、このジャケットの中に居るパーフリは同一人物だよと。このCDジャケットと向き合ってる君も僕も私もフリッパーズギターの一員なんだよ、パーフリにカメラを向けている側の人ではなく、パーフリにカメラを向けている誰かと向き合ってるこちら側の人間なんだよ、と、このジャケットは言ってるわけで。
そう解釈すると、なんだパーフリ良い奴じゃん。ひねくれポップとか言ってるけど、わりとサービス精神もあるし、結構素直な良い人達だよ・・って。うーーんと、まあ、このように考えるとアルバムタイトル「カメラトーク」の名の通り、様々な解釈の成り立つカメラジャケットはかなりしゃべってますね。ここまで饒舌に自己主張するカメラも少ねぇーぞってぐらいに。
そういえば、ソロになったコーネリアスがHEY!×3に出たとき、いきなりビデオカメラを回しながら登場し、司会のダウンタウンが引いていたなんて場面もあった。言葉を失ったダウンタウンにコーネリアスが気を使って話し掛けるんだけど、場の空気に飲まれたダウンタウンは黙ったまま。「これ、まだ買ったばかりで使い方分らないんですよ。」「さっきここへ来る途中で買ってきて・・」あの異様な空気を作り出したかと思うと普通にしゃべり出すコーネリアスをみて、TVのこちら側でも私は言葉を失ってました。
その後、元レベッカのNOKKOがやはり同じことをしてダウンタウンに「そんな登場の仕方されてみ。こっちの身にもなってみぃーや。」と言われてましたね。
最後に、ジャケットに書かれた英文の訳を載せときます。「“カメラトーク“もしくは 若者の無秩序なロマン主義。ダブル ノックアウト コーポレーション フリッパーズギターからのより偉大な目録から出展」
この「より偉大な目録」原文だとモア・グレイト・リストなんですけど、何と比べてより偉大なのかってぇーと、やっぱ2ndだから、1stと比べてなんでしょうけど、過去の作品集よりも新作、過去の作品には触れないでくれといった、オザケンの過去が消えていく傾向も実はこの頃から既にあったと思われる?
また、ここで出てくるロマン主義。ですが、文学の世界ではゲーテの生み出した三つの概念、若き天才・インスピレーション・夭折なんて語とセットで出て来るんですね。パーフリというバンドが、若き天才として学生時代にデビューし、大学の卒業と共に解散=夭折する。ってのがこの時、既に決まっていたかのような完璧なキャッチコピーですね。ロマン主義ってのは、学生が趣味=インスピレーションでやっていたことが、偶然社会に認知され職業として成り立ってしまうものであって、社会人が計算の上で成り立つ職業として職人的生産活動を行なうってのとは丸っきり別物ですから。そういう意味で、パーフリの活動というのは美しく華麗なロマン主義時代に限定されたものだったと、そしてそのようなロマン主義の当然の帰結として、卒業後の二人がすぐに音楽活動に入るのではなく、生計を立てる手段として音楽を選ぶのか選ばないのか考えるのに2・3年という時間を必要としたって部分まで含めて、パーフリの活動期間とロマン主義的概念の間に幸福な一致があった事がこのコピーからもうかがえるわけです。
最初に、歌詞カードに書かれた英文の訳から入ります。
まず、歌詞カード一発目のアジテーションから『コントロール出来なくなる事をおそれるな・・・だってコントロールは僕等のゲームの名前でしかないんだから――ジャック=ター』『ヘッド博士の世界塔』
次に爆発を示す記号の上に書かれているのが『フリッパーズギター――イカしたポップスター』
次はパレットの様にも人の顔のようにも見える抽象的な記号の上に書かれたセリフ『フリッパーズギター――精神異常の油絵画家』
次はナイフとフォークの記号で、高速道路でみかけるパーキングエリアを示す記号や、新幹線の中で見かけるビュッフェを示す記号っぽい記号で『フリッパーズギター――偏執狂的レストラン』
次に世界地図・・というより地球儀?の下に書かれたセリフ『フリッパーズギター(限界)――超近代的観光』ちなみにこのウルトラモダンってのは、時としてファシズムを意味するんだよね。
最後にフリッパーズギターの頭文字「FG」を中心に、エネルギーの循環を示す矢印、黒の矢印が循環してストライプの矢印になり、ストライプの矢印がまた黒に戻る・・生死の循環を示してるようにも、もしくはエコロジー的な資源のリサイクルを示しているようにもみえる・・そして、その上から危険を示す黄色で、バッテンを加えられることで核燃料リサイクルの記号にも見える・・そんな記号の横に小さく書かれた言葉『商標』カタカナで書くと「トレードマーク」。
何かこう、全体としてイカにもパーフリ的なアジテーションに、複数の解釈が可能な記号を加える事で、解釈そのものを拒絶しているようなデザインに仕上がっている。
始めの、アジテーションについて書くと「制御不能になることをおそれるな。制御なんてのはゲームでしかない」と言ってるジャック=ターと、頭脳や理性の象徴であるヘッド博士ってのは明らかに対立してるわけだ。ヘッド=頭脳博士の世界塔ってのは、バビルⅡ世なんかに出てきたタワー状のスーパーコンピューターで、あらゆる物を効率よくスムーズに動かす官僚組織とか、なんかそういう物を連想させる。
対するジャック=ターは「理性博士=ヘッド博士による制御なんて要らない。そんなのは遊戯でしかない。」と言い切っている。ここで言うゲームってのは、フィクション=架空のものであるのと同時に、野球やサッカーなどのボールゲームに代表されるような数値による勝ち負けをも意味する。CDの売上枚数だとか、リクエスト数だとか、少ない費用でより多くの売上を上げようとする費用対効果だとか、そういう数値のゲームは要らない、理性による制御なんて要らない。そう言い切るジャック=ター(Jack Tarr)とは何者なのか?
一般にJack Tarが水夫を意味する所はよく知られていて、世界を管理するヘッド博士に対する、現場の人間、実際に世界の中にいる人、ぐらいの意味だと思うのだが、だったら、Jack TarrのRは一つで良いはずなんだよな。tarは「汚名を着せる」「名声を汚す」の意味で動詞として用いられ、その時の過去形・過去分詞形への変化がtar tarred tarredと、Rを二つ重ねた形態を用いる。ただの水夫でなく、「汚名を着せる」「名声を汚す」を意味する動詞を連想させる様にわざとRを二つ重ねた。そう考えるのはわりと普通の事だと思うんだけど、その際、tarを連想させる事で、「Jack Tarr=汚名を着せるジャック」になるのか、tarredを連想させる事で「Jack Tarr=汚名を着せられたジャック」になるのか、このへんも重要なポイントでありながら、どちらが正しいのか決定不能なまま提示されている。
で、一度CDジャケットの写真に目をやると、一組の男女が写っている。明らかにフリッパーズギターでない人達(実はパーフリ本人によるコスプレなのだが)。男の方は「フーテンの寅さん」や小津安二郎の映画に出てくるような、1950年代以降みなくなった古臭い帽子をかぶっている。坂口安吾や東条英機がかけてたような古い真ん丸の黒ブチ眼鏡。首にはタオルを巻いてる。ここまでだったら、明治大正から戦後にかけての典型的日本人像なのだが・・タオルは当時高級品で手ぬぐいが主流だったってのだけ微妙に違うけど・・着てる服がアロハで首からカメラと双眼鏡をぶら下げて、双眼鏡で何かを見てる・・って辺りが、日本人旅行客の典型、カリカチュアライズされた、アメリカ映画に出てくる日本人旅行客。古い日本を引きづりつつ、手ごろに買えるアメリカを着てる黄色人種をみすぼらしく表現してる。
 もう一方の女性はマリリン=モンロー張りの金髪パーマのかつらをかぶり、フレンチなファッショングラスをかけてスカーフは水玉模様、服もいかにもパリコレで発表されてすぐのファッション性の高いおしゃれなデザイン・・どことなく3rdでパーフリの二人が着てる服と似ている・・なんだけど、いかんせん着てる本人の胸がない、ウエストが太い、手肌が荒れてる、顔が引きつってる。金髪なのに肌は白人じゃないし、頭に巻いたスカーフの巻き方も、なんか田舎の農業労働者が農作業中に頭に手ぬぐい巻いてるような巻き方だし、防空頭巾とかさ、なんかそっち系のダサい巻き方、せめて首の後ろで縛ったらカッコ良いのにさぁ・・。そう、さっきの男性が外国旅行中の日本人旅行客のカリカチュアライズだとすれば、こちらの女性は欧米帰りの日本人のカリカチュアライズ。舶来品を身につけ、いっぱしの白人にでも成ったかのような気になってる日本人の格好悪さを表現している。
もう一方の女性はマリリン=モンロー張りの金髪パーマのかつらをかぶり、フレンチなファッショングラスをかけてスカーフは水玉模様、服もいかにもパリコレで発表されてすぐのファッション性の高いおしゃれなデザイン・・どことなく3rdでパーフリの二人が着てる服と似ている・・なんだけど、いかんせん着てる本人の胸がない、ウエストが太い、手肌が荒れてる、顔が引きつってる。金髪なのに肌は白人じゃないし、頭に巻いたスカーフの巻き方も、なんか田舎の農業労働者が農作業中に頭に手ぬぐい巻いてるような巻き方だし、防空頭巾とかさ、なんかそっち系のダサい巻き方、せめて首の後ろで縛ったらカッコ良いのにさぁ・・。そう、さっきの男性が外国旅行中の日本人旅行客のカリカチュアライズだとすれば、こちらの女性は欧米帰りの日本人のカリカチュアライズ。舶来品を身につけ、いっぱしの白人にでも成ったかのような気になってる日本人の格好悪さを表現している。
さあ、なんでこんなカッコ悪い日本人がオシャレなパーフリのCDジャケットになってるの?2ndアルバムでは本場イギリスのミュージシャンとセッションしたパーフリが、歌詞カードの中ではフレンチなサングラスを頭に差して、ファッションモデルさながらのポーズをとってる小山田圭吾と、アンディー=ウォーホル張りの白髪かつらをかぶったカッコイイオザケンが二人並んでるのに、そのままヴォーグの表紙飾れるぐらいのカッコイイ服着て三面鏡の中にいる二人なのに、どぉーして、ジャケットはパーフリの二人でなく、ダサい日本人観光客なの?私にはどぉーしても、パーフリの一人ツッコミにしか見えないんですね。「カッコイイことはなんて、カッコ悪い事なんだろうbyジャックス」的な汚名を着せられたパーフリによるパーフリ自身への一人ツッコミ。
さて、3rdアルバムのジャケットで人のバックにある水玉模様。これについても、考えてみたい。白地にドット絵だとリキテンシュタインの影響だとか、スーラの点描だとか言って終われるんだけど、黒地なんだよね。カラーコピーの場合、色の三原色+黒の四色を白地に塗って仕上げるんだけど、黒地ってことは印刷じゃなくって、ブラウン管の可能性が高い。テレビのモニターなら、黒地+光の三原色ですべての色を表現する。でも、色を見ると白抜きは三原色すべて発光させてる部所を示してるとして、それ以外が四色なんだよな。光の三原色と色の三原色を足してかぶってる部分を引いた四色がこのジャケットの巨大ドットに使われている。もちろん、余った一色は三原色のうちの二色同時発光で作った混合色だから考えなくて良いんだよと言われりゃそうなんだけど、既に三色同時発光の白も出てるんだけど、だったら、三原色+三原色の二種混合色で計六色ドットが使われてても良いはずなんだよな。でも、実際には光の三原色+色の三原色というこの取り合せになってる。もしこのジャケットの示すところがブラウン管でもカラーコピーでもないとしたら、ヘッド博士の世界塔そのものじゃないかと思えるんだよね。
1stアルバムのジャケットにはパーフリが写っていて、歌詞カードの中にはパーフリの連続写真がフィルム状に並べられている。つまり動いているパーフリがフィルム状に記録されている。2ndになるとパーフリを見るカメラ=認識・記録媒体がジャケットに成っている。1stで動きのあるフィルムであったり、広がりのある風景であったりした物が、2ndでは動きのあるフィルムの一瞬を切り取ったカメラ、広がりのある風景からその風景を封じ込めるカメラに変わり、3rdではついにそのカメラのレンズの奥にあるデジタルな認識・記録媒体の拡大図にまでズームして行く。世界を認識するフィルムやテープや神経細胞や視覚中枢も結局のところ赤や青や黄色や緑のドットでしか見てないのではないか。デジカメも眼球も世界を赤や青の点に分解して認識してるに過ぎないのじゃないか。head=頭脳を顕微鏡的に描くことで、それがそのままheadの究極と限界を指し示すようなスタイルに成ってます。
このアルバムは音的には小山田のコラージュ趣味が炸裂し、詞的には小沢のサイケデリック趣味が錯乱している。サイケな薬物が人の記憶と知覚を一度バラバラに分離して脈絡のない形で再構成するのと、コラージュ的手法がテーマとして上手く合致している。そして、知覚・記憶というテーマとデジタルなドット絵、「永遠」や「1000光年」という語を使いながらも閉塞的な終末感漂う音楽と、三面鏡という閉塞的な無限に囲まれたパーフリの写真。三面鏡という閉じた無限とサンプラーの織り成す無限ループ音。音楽のテーマとジャケット・歌詞カードの写真の主題が見事に合致しているコンセプチャルなCDジャケットです。