|
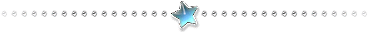
■ 最強の恋人たち ■
〜『ラブ・ストーリーは突然に』その後のお話〜
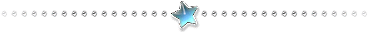
部屋の中を艶めいた呼吸音が満たし、ゆっくりとしたリズムでベッドが軋む。
「ぁ……あっ……そこ…っ」
「ん……こっち、か…?」
「あっ、んっ、いい…っ」
薄く開いたカーテンの隙間から月の光が差し込み、ベッドの上で揺れ合う恋人たちを仄かに照らし出す。
「も…っと……ぁ……もっと深く……あっ」
「こう、か?」
「あぁ、んっ」
ベッドの軋みが激しくなってゆき、艶めいた呼吸がさらに乱れて喘ぐような声が混じる。
「あっ、んっ、あ、あ、あっ」
二人だけの部屋。
二人だけの家。
マンションの東隅にあるこの一室は、手塚と、リョーマのための、住まい。
だからリョーマは、自然に生まれる艶声を、抑えようとはしない。
「ああっ、あっ、そ……そこ、いいっ、もっと……あ、んっ、は…っ」
「あぁ………リョーマ……っ」
パンパンと肉を打つ音が部屋中に響く。
「ああぁ、あっ、ああぁぁっ」
間断なく突き上げられて、リョーマの嬌声も止まらない。
与えられ続ける強い快感に、リョーマの思考は、もう形を成さない。
たったひとつ、リョーマの胸にあるのは。
「好き………国光……好き…っ」
「リョーマ…っ、好きだ…、好きだリョーマ……っ」
「あ、あぁっ、んっ…スゴ……い……っ、気……ち…い…い…っ」
リョーマの頬が、肌が、快感に紅く染まっているのが月明かりに映し出され、手塚はさらに熱い衝動を覚えてリョーマの奥深くをメチャクチャに突き荒らした。
「リョーマ……リョーマ……っ」
「国……くに…み、つ…っ」
愛しくて、愛しくて、ただその名を呼ぶことしかできなくなってくる。
ベッドを激しく軋ませ、大きく弾むように二人の身体が揺れる。
「あッ、あッ、あぁ、イクっ!」
「出すぞ…っ、リョーマ…っ、っあ、…っ!」
「う、あっ、あぁぁ……っ」
全ての音が、一瞬、消える。
「っく、……っは、ぁっ」
手塚が何度も息み、その度に緩くベッドを軋ませて腰を揺する。
腹の奥底が熱いもので満たされてゆく感覚に、リョーマは身体を時折痙攣させながらうっとりと陶酔する。
「…………」
「…………」
やがて、荒い呼吸音に満たされた空間が、ゆっくりと落ち着きを取り戻してゆく。
「……リョーマ…」
「………ん?」
額や頬に優しく口づけられて、リョーマはゆっくりと目を開いた。
「……大丈夫か?…痛いところはないか?」
「うん………気持ち良かった……もっとして…」
手塚の身体を引き寄せ、その胸に頬を擦り寄せると、リョーマの胎内に埋め込まれたままの熱塊が、ビクリと脈打って質量を増した。
「…いいのか?」
「だって……これから試験だから…あんまり出来ないんでしょ?……だから…」
「…………」
手塚は一瞬何かを言いかけ、だがすぐに小さく微笑んでリョーマに口づけた。
今は、言葉よりも、互いの熱を伝え合う方を優先する。
「リョーマ……愛してる……」
「ぁ……国光……」
手塚がゆるりと腰を動かすと、何度も吐き出された手塚の精液がリョーマの蜜壺から溢れ出し、シーツをしっとりと濡らしていった。
「え?なに、それ?」
翌朝、学校へ行く支度をしながらリョーマが目を丸くした。
「試験を頑張ればいいことがあるって……アンタがなんか『ご褒美』でもくれんの?」
「いや……努力は報われるということだ」
「?」
手塚は歯切れ悪く口籠もったが、疚しいことがあるわけではないらしい。
「ふーん、ま、いいや。…アンタがそう言うんだから、頑張ってみる」
「ああ」
ふわりと微笑み、手塚がリョーマを引き寄せて口づける。
「今日から部活も出来なくなるから…学校では逢えないな」
「うん…」
小さく頷いて、リョーマは背伸びして手塚に口づけた。
「でも帰ってきたら、いっぱいキスしてくれるんでしょ?」
「………それなんだが……今日から学校帰りに大石たちも呼んで勉強会をしようと思うんだ。…いいか?」
「え……」
リョーマは一瞬眉を寄せたが、スッと手塚から目を逸らして小さく溜息を吐き「ここはアンタの家なんだから好きにすれば」と呟いた。
三年生にとって一学期の期末テストは重要だ。
いくらエスカレートで進路が決まっているとしても、そのデータが高等部で重要視されることは間違いない。
しかし、手塚が今回の期末テストに拘る理由は、それだけではなかった。
三日ほど前、手塚は母・彩菜からの電話で、軽いショックを受けた。
「工事が……終わるんですか…?」
リョーマとの同居生活を始めるキッカケにもなった家のリフォームや、あの放火魔に焼かれた裏の勝手口の修理も終わり、いよいよ引き渡しが行われるというのだ。
『あらあら、そんなガッカリしたような声を出して……やっぱりまだリョーマくんと暮らしたいわよねぇ』
「……いえ……我が儘を言うわけには……」
ぐっと眉を引き寄せながら、手塚は思うことと反対の言葉を、無理矢理理性で搾り出した。
『そうねぇ。ウチもそんなに余裕があるわけじゃないし…今から息子を独立させるのも…ね』
「………はい」
初めから期限が決められていたことなのだ、と手塚は何とか諦めようとするが、感情が言うことをきかない。
『でも国光は、まだそこでリョーマくんと一緒に暮らしたいわよね?本当は』
「……はい」
正直に答えると、電話の向こうで彩菜が笑った。
『本当にリョーマくんのことが好きなのねぇ。………わかったわ、ひとつ条件を出しましょう』
「条件?」
『もうすぐ期末テストでしょう?だから、あなたは、まあ、現状維持。リョーマくんの成績は良くわからないけど、今よりもアップしたら、あなたが卒業するまで、そこにいていいわ』
「え!」
思わず大声を出しそうになり、手塚は慌てて自分を落ち着けた。
「それは……本当ですか?」
『ええ。だって、そこにいるから成績が上がった、っていうことになれば、向こうの親御さんもリョーマくんがそこにいることをダメだとは言えないでしょう?』
ふふふ、と笑う母の声を聴きながら、手塚は自分の母親が案外策士であることを再認識した。
「わかりました。アイツの成績が、上がればいいんですね」
念を押すように問うと、彩菜がまたクスッと笑う。
『でも、この約束のこと、リョーマくんには言っちゃダメよ。こんな条件が付いているんだって知ったら、リョーマくん、俄然、頑張っちゃいそうだし』
「…そうですね」
それはそうだろうと手塚は思う。この先もしばらく二人で暮らせるかどうかが懸かっているなら、リョーマは何日徹夜してでも、成績アップのために努力を惜しまないだろう。
「わかりました。その条件も呑みましょう。でも、俺がアイツの勉強を見てやるのは、もちろん構わないと言うことですよね?」
『ええ、もちろん』
そうして手塚は彩菜との秘密の約束事を成立させた。
(なんとしてもお前にはこの『勝負』に勝ってもらわなければならない)
隣を歩くリョーマにチラリと視線を向けながら、手塚は自分自身に気合いを入れ直した。
一方、手塚のそんな思惑を知らないリョーマは、昨夜、母・倫子との電話で、気づきたくないことに気づかされてしまい、心が沈んでいた。
『手塚さんのお宅、もうすぐ工事が完了するみたいよ』
いつか来る日だとは思っていたが、リョーマは手塚との甘い生活が終わってしまうことがどうしようもなくつらい。
手塚との生活は、リョーマにとっては楽園のようで、そこを追い出されたら自分は死んでしまうような気までしてくる。
(アンタと一緒にいられなくなるなんて……)
学校でも授業どころではなく、教師が「ここは試験に出るから」と言っても、まるで頭に入ってこなかった。
それでも、リョーマがそんな状態であることは手塚には知られないようにしようと思い、手塚の前では至って普段と変わりなく振る舞ってみせた。
その分、ベッドの中では思い切り甘えた。
もうすぐこうして肌を重ねる機会もなかなか取れなくなるのだと思うと、少しでも長く、手塚を感じていたいと思うようになった。
なのに。
(先輩たちを家に呼ぶなんて……)
勉強を効率的に行うには、それぞれ苦手な分野を補い合いながら一緒に進めるのはいい方法だと思う。
だが一分一秒でも長く、手塚と二人きりで過ごしたいリョーマには、苛立ちが募る時間でしかない。
勉強どころでは、ないのだ。
「オレ、なんか飲みモン買ってくるっス。先輩たち、何がいいっスか?」
「ウーロン茶」
「炭酸」
「100%オレンジ」
「コーヒー」
いろいろなリクエストが飛び交うのを苦笑しながら聞き留め、リョーマが玄関に向かうと手塚が追いかけてきた。
「俺も行くか?」
「ぁ……でも…」
リョーマがチラリとみんなのいる居間に視線を向けると、手塚は小さく笑ってリョーマの頭をポンと軽く叩いた。
「すまない、みんな、俺も買い出しに付き合ってくるから。ちょっと待っていてくれ。すぐ戻る」
「ほーい」
菊丸の陽気な声が帰ってくる。それに紛れて「ごゆっくり」という不二の声も聞こえた。
「行こう」
手塚に肩を抱かれ、リョーマが嬉しさを隠しきれずに微笑んで見上げると、手塚も目を細めて微笑んでくれた。
思いがけず二人の時間が出来て、リョーマは心がウキウキとしてきた。
「階段?エレベーター?」
玄関から外に出た途端、リョーマは表情を和らげて手塚に尋ねる。
「階段をゆっくり下りよう」
「うん」
ニッコリと微笑んで頷き、リョーマはそっと手塚の手を取った。
「繋いでいい?」
「もちろんだ」
手塚がしっかりと握り返してくれて、リョーマは嬉しさに頬を染める。
(ずっと、こんな日が続けばいいのに……)
そっと手塚に身体を寄せると、手塚は繋いでいない方の手で優しく頭を撫でてくれた。
「……やはり、家に呼ばない方がよかったか?」
「え?」
心を読まれてしまったのかとリョーマが驚いて顔を上げると、手塚は優しく微笑んでリョーマを見つめていた。
「お前と二人きりでいると、お前に触れたくて堪らなくなるんだ。……だから、みんなを呼べば、俺の理性が保つと思った……俺の都合で、すまないな」
「ぁ……」
リョーマの頬が真っ赤に染まる。その頬の熱なのか、あまりの嬉しさなのか、リョーマの瞳が潤む。
「ごめ……そうだよね、ちゃんと勉強しなきゃ……オレ、すごく自分勝手なこと考えてた……ごめん」
「……リョーマ」
階段の踊り場で、手塚がリョーマをしっかりと抱き締めた。
「国光…」
「離したくない……ずっとお前を抱いていたい……だがそれでは、俺たちは大人たちに認めてはもらえないんだ。……わかるか?」
「うん」
手塚の胸に頬を擦り寄せて、リョーマは頷く。
「……オレも、ちゃんと勉強する。やれることは全部やってみる。…アンタと一緒にいるから成績下がったなんて、絶対に、言わせないから!」
「え…」
彩菜との約束がばれたのかと手塚は一瞬驚いたが、今の台詞は、リョーマの性格が生み出す当然の言葉だとすぐに気づいた。
「俺もそう思って頑張っている。……一緒に、頑張ろう、リョーマ」
「うん」
チュッと、唇を触れさせるだけのキスを交わして、二人はまた階段を下り始める。
「アイスも買おうね」
「ああ」
微笑みを交わし合い、二人はゆっくりと階段を下りていった。
いよいよ期末試験が始まった。初日も二日目も、二人は着実に勉強の成果を出し、手塚に至っては、何科目か満点を取れたのではないかという手応えまで得られた。
残すところ、あと一日。三教科。
だが三日目にはリョーマの苦手な国語があった。
最終日は比較的得意な科目だけになったという手塚に時間を割いて教えてもらったが、今まで以上の点数が取れる自信はない。
「今日で終わりだ。気を引き締めていこう」
「油断せずに行こう、じゃないの?」
二人で朝食を摂りながら、そんな会話を交わして微笑み合う。
「今日は練習あるんスよね」
「ああ。今までの分を取り返さないとならない」
活動休止中とはいえ、部員たちは皆それぞれ自主的に筋力トレーニングは行っていたはずだが、コートに立っての練習は約一週間ぶりになる。
手塚とリョーマも朝と晩のランニングをこなしてはいたが、コートに入ることはしなかった。
「…じゃあ、今日は目一杯練習、っスね」
リョーマが肩を竦めて小さく溜息を吐くと、手塚も溜息を吐く。
「そういうことだ」
二人とも、練習が嫌なのではないことは互いにわかっている。
ただ、もう一週間もまともに触れ合っていないせいで、かなりカラダの熱が溜まってきているのだ。
毎日触れ合っていた二人にとって、この一週間は、長く、つらかった。
「ぁの…国光…」
「ん?」
「今日………ぁ、いいや、なんでもない……最後の三科目、頑張るから」
「……ああ。お互い頑張ろう」
ふわりと微笑まれて、ただそれだけなのにリョーマのカラダの奥が疼く。
(絶対に、いい結果を出して今夜は……)
じっと手塚を見つめていると、気づかれた。
「…そんな顔をするな」
「え?」
「いや…」
そう言って小さく苦笑すると、手塚が静かに立ち上がった。
「一昨日と昨日の結果がよくても、今日がダメでは全てが水の泡だ。…気を引き締めなくては、な」
「……うん」
大きく頷き、リョーマも立ち上がる。
二人で食器を片づけ、支度をして家を出た。
とてもいい天気だった。
手塚から、彩菜との秘密の約束事があったことをリョーマが聴かされたのは、部活を終えた帰り道だった。
今日の出来があまりよくなかったのだと、ボソボソと手塚に言うと、小さく溜息を吐いた手塚が、そっと教えてくれた。
「そんな……そうなら言ってくれれば、オレもっと頑張ったのに…っ!」
「お前には何も言わないというのも条件のひとつだったんだ」
静かにそう言われ、リョーマは唇を噛み締めた。
(ダメかも、しれない)
リョーマは生まれて初めて、結果が出る前に「負け」を感じた。
論説文の問題については手塚に解答を見つけ出すコツを教えてもらっていたので、何となく出来たとは思う。
漢字の書き取りも、まあ、出来ただろう。
問題は、「文法」や「四字熟語」や「ことわざ」に関しての設問。
特に「四字熟語」や「ことわざ」に関しては生徒の知識の深さを測るつもりなのか、授業では一切教えてくれなかった問題が次々と出された。
(あんなの……サギだし…)
「あのさ、国光……『情けは人のためならず』って、どーゆー意味?」
「…人に情けをかけると、巡り巡っていずれは自分のためになる、という意味だ」
「うわ…っ」
リョーマがガックリと肩を落とす。
「じゃ、じゃあさ、『青菜に塩』って言うのは鮮やかになるって意味?」
「違う」
「………マジ……」
他にもいろいろ尋ねてみたが、リョーマの「ことわざ」に関する正解率は10%にも満たなかっただろう。
「ほぼ全滅……」
頭を抱え込むリョーマを見て、手塚は小さく苦笑する。
(やはり、世の中そううまくは行かないか……)
「ごめん、国光……」
「謝らなくていい。……それに、俺たちの関係が終わってしまうわけではないんだ。そんなに気を落とすな」
「でもオレ……ずっと国光と二人で暮らしていたい。オレたちの家がなくなるなんて……」
「リョーマ……」
手塚を見上げるリョーマの瞳が切なげに揺れる。思わず抱き締めそうになり、手塚はギュッと唇を噛み締めた。
その手塚の視界に、キラキラと光るものが目に入った。
「?」
そちらに視線を移すと、商店街の一角、通りの反対側に飾られた笹飾りを見つけた。
「……あれに、頼んでみるか?」
「え?」
手塚の視線を追いかけてリョーマも振り返る。
「七夕様…」
「行ってみよう」
二人はさりげなく手を繋いで、笹飾りのもとへと近づいていった。
「ご自由にどうぞ、だって」
笹飾りの近くに会議用の机が置いてあり、平べったいアルミ缶の中に、短冊と鉛筆が入っていた。
「ぁ……最後の一枚だよ?」
缶の中を覗き込むと、用意された短冊はほとんどなくなっており、薄い水色の短冊が一枚だけ入っていた。
「国光……」
リョーマはその短冊を手に取り、手塚に視線を向ける。
「ああ……二人の願いだ。一緒に書こう」
「うん」
鉛筆を持つリョーマの左手に、手塚も左手を重ねる。
そうして二人で願い事を書き、手塚が手の届く最も高い位置に、しっかりと括り付けた。
「これでいい、か…」
手塚が振り返ると、リョーマが笹飾りに向かって手を合わせている。
(好きな人と一緒にいられないつらさを知っているなら、どうか、お願いします。オレたちを…引き離さないでください……っ)
神頼みなんて今までリョーマはしたことはなかった。
だが今回ばかりは、こうして祈らずにはいられない。
(国光と、一緒にいたい…っ)
ふとリョーマが目を開けると、手塚もリョーマの隣で手を合わせていた。小さく眉を寄せ、真剣な表情で祈っている。
「国光…」
「……不二たちに見られたら笑われそうだな」
短冊を見上げて小さく微笑む手塚を見て、リョーマの胸に苦しいほどの愛しさが込み上げる。
「笑われてもいいよ。アンタと一緒にいられるなら、オレは……」
互いに相手だけを映す瞳が切なく揺れる。
「……そうだな……」
ふわりと微笑まれて、リョーマも微笑み返す。
「帰ろう。俺たちの家へ」
「うん」
商店街にはまだ人がたくさんいたが、二人は身体を寄せ合い、そっと指先を絡めて歩いた。
「待って、待っ……あっ」
部屋に入るなり、いきなり玄関でリョーマは後ろから手塚に抱き締められた。
二人のバッグがほぼ同時に足下に落ち、リョーマの身体が壁に押しつけられる。
「ぁ…待っ……お風呂…シャワーでもい……部活…汗……っ」
「待てない」
服の上から身体をまさぐられ、リョーマはまともに言葉を紡げない。並べられた単語から伝わるリョーマの主張を、手塚はひと言ではね除けた。
「ぁ…っ」
言葉で抵抗はしたものの、リョーマが本気で拒絶するはずもなく、自分の首筋に顔を埋める手塚の髪を愛おしげに梳いてやった。
「ね……鍵…しめた?」
「……ああ」
吐息紛れに尋ねると、手塚がリョーマの首筋に口づけながら応える。
性急にベルトが外され、ズボンのファスナーが下ろされる。
「あっ」
すぐに下着の中に滑り込んできた手塚の熱い手に優しく握り込まれ、リョーマは声を上げて仰け反った。
「もう…先が濡れている」
「だっ…て……オレだって……国光……欲し…っ」
「リョーマ……っ」
熱い吐息とともに耳元で名を囁かれ、リョーマの全身に甘い電流が走る。
リョーマの先走りで濡れた手塚の指先がスルリと後ろに回り、慎ましく閉じた蕾の淵を撫でる。
「あ…」
固さを確かめるようにつつかれ、少しだけ力を込められて指先が入り込む。
「い…っ」
リョーマの身体が一瞬強ばり、手塚の動きも止まる。
「………っ」
「ごめ……いい、よ……痛くしてもいいから、挿れて……」
手塚の喉がゴクッと音を立てる。
リョーマのズボンがずらされ、背後で手塚がベルトを外す音が聞こえる。ファスナーの音を聞いたと思ったすぐ後、リョーマの後孔に熱い塊が押しつけられた。
「あ……っ」
リョーマがギュッと目を閉じる。襲い来るであろう強い痛みに身構えていると、あの熱い塊がリョーマの後孔に何度か擦りつけられ、そのままぬるりとリョーマの袋を押し上げた。
(え……?)
「脚を閉じろ」
「………」
言われた通りに脚を閉じると、きつく閉じた股の間で手塚の熱塊が抽挿され始めた。
「く…国光…っあ、んっ」
手塚の熱い吐息がリョーマの耳にかかる。
何度かそのまま股を使われ、すぐに熱塊が引き抜かれた。
「…っく」
「ぁ……っ」
リョーマの後孔に熱い飛沫がかかる。
たっぷりと出された熱い粘液は、リョーマの後孔から内股を伝って滴り落ちてゆく。
「国…」
手塚の指先が粘液を掬い取るように動き、すぐにリョーマの後孔に滑る指先が埋め込まれた。
「ぁ…っ」
「痛いか?」
余裕のない声で、手塚がリョーマの耳もとに囁く。
リョーマはすぐに首を横に振った。
「大丈夫」
「ん」
すぐにもう一本指が差し込まれ、広げられて解され、手塚の指がさらにもう一本増やされた。
「あぁ、んっ」
「リョーマ…」
熱く名を囁かれ、引き抜かれた指の代わりに熱の塊が捩り込まれる。
「あ……ぁっ!」
強い圧迫感に、リョーマは小さく顔を歪める。
「あぁ………」
手塚が感じ入った声を漏らす。
「あ……ぁ、ん、……や……っあぁっ!」
リョーマの奥まで手塚の熱塊が入り込んだ瞬間、リョーマは呆気なく弾けた。
「リョーマ…?」
「ぁ………ん…」
射精の余韻にうっとりと身を委ねていると、手塚がリョーマの耳もとでクスッと小さく笑った。
「…挿れただけだぞ?」
「………国光だって…すぐイッちゃったくせに…」
「限界だったからな」
「ぁ…っ」
ゆっくりと腰を回されてリョーマの身体が痙攣する。
「いつも以上に感じやすいな…」
後ろから回された手でシャツのボタンが下から外され、全て外す前に滑り込んできた手に胸の突起を摘まれてリョーマが震える。
「ぅ、あ……っ……やっ」
「…そんなに締め付けるな…」
甘く甘く、耳から注ぎ込まれる手塚の艶めいた声に、リョーマはすぐに音を上げた。
「や、だ……早く…奥…突いて……っ」
「………」
手塚が堪らなくなったようにリョーマをギュッときつく抱き締め、深く、奥まで押し込むように腰をゆっくりと揺らめかせる。
「あぁ……あ……っ」
「リョーマ……」
壁に押しつけられ、徐々に激しく突き上げられ、リョーマはうっすらと笑みを浮かべて嬌声を上げる。
「あぁっ、い…い、よ……国…光…っ、あっ、あっ、あ…っ」
腰を抱え込まれ、パンパンと音を立てて肌がぶつかり合い、手塚の熱塊が奥深く何度も叩き込まれる。
「あぁ、んっ、あっ、やっ、あ、スゴ…っ、あっ、ぁんっ」
次第に力の入らなくなってゆくリョーマの身体を、手塚は抱え上げ、廊下に俯せにさせた。
「あぁっ」
さらに力強く奥を抉られ、リョーマの背が思い切り撓る。
二人ともシューズを履いたまま、衣服もほとんど乱さずに、露わにした下半身だけで繋がり合う。
それほど二人には余裕がなかった。
この一週間、けじめをつけるためだと言って、二人は頑なに身体を繋げようとはしなかった。
それでも、どうしても相手が欲しくなった夜には、お互いの性器に手を伸ばし、熱く見つめ合いながら熱をいなした。
だがそれで満足できるはずもなく、二人は今日の、この瞬間を、胸が痛くなるほど待ち焦がれていたのだ。
「あぁ……リョーマ……堪らない……リョーマ……っ」
「あっ、はぁっん、あっ、あぁ、んっ」
グチグチと、粘つく水音が大きくなり、二人の息遣いもひどく不規則に乱れる。
「国光……イク……も、イク…っ!」
「リョーマ…っ」
手塚がリョーマの腰を抱え込み、下から抉るように突き上げる。
「やっ、だめ…っ、イク………っぁあっ!」
「…っく、ぅ…」
硬直するリョーマの身体をなおも揺さぶりながら、手塚が呻く。
きつくきつく収縮する腸壁をこじ開けるように、無理矢理剛直を出し入れし、一気に込み上げてきた射精感に逆らわず、手塚もリョーマの奥深くで息む。
「……っく、はっ……あっ」
手塚は息を荒げながら、リョーマの尻朶を変形させるほど己の熱塊をグイグイと限界まで深く捩り込み、最奥めがけて熱い濁液を叩きつける。
「……っう……くっ……っ」
痙攣するように手塚が腰を押しつけるたび、リョーマの身体も敏感に反応し、淫らに揺れる。
やがて全てを出し切った二人は、深く息を吐いてその場に重なり合うように崩れ落ちた。
「………すまない……止まらなかった」
「うん……オレも……すぐ…欲しかったから…」
荒い呼吸に胸を弾ませながら、リョーマが嬉しそうに笑う。
手塚はそんなリョーマに蕩けそうな微笑みを向け、ゆっくりと身体を起こした。
ズルリとまだ芯を残す熱塊が引き抜かれ、リョーマが「ぁ」と艶めいた声を漏らす。
手塚は少し下げていただけの下着を引き上げ、前髪を掻き上げてから、リョーマのシューズを脱がせてやる。
脱げかけのズボンに足を取られてなかなか起き上がれないリョーマを見て、手塚は優しく「ちょっと待っていろ」と言った。
「国光…」
「ん?」
自身もシューズを脱いだ手塚は、手際よくリョーマのズボンと下着を全て脱がせ、そのまま抱き上げた。
「く、国光」
「さあ、どっちに行きたい?」
「え?」
目を丸くするリョーマに、手塚はふわりと微笑みかける。
「風呂に行くか?それとも、ベッドで続きをするか?」
「ベッド!」
即答したリョーマに、手塚はわかっていたとばかりに深く口づける。
「……いい答えだ」
「ばか」
手塚の胸に顔を埋めるリョーマをさらにギュッと抱き込み、手塚は真っ直ぐ寝室のベッドへと向かう。
時折待ちきれずに口づけながら全ての衣服を脱ぎ去り、二人はやっと肌と肌を合わせて微笑み合った。
「国光…」
そっとベッドに押し倒されながら、リョーマは手塚をじっと見つめる。
「ん…?」
手塚が優しく問い返すと、リョーマは泣きそうな顔で笑った。
「ねえ、やっぱ、ムリ……オレ、アンタと離れて暮らすの、ヤダ……っ」
「……リョーマ…」
手塚が大きく目を見開く。
「好きだよ、国光……どうしよう……スゴイ、好き……っ」
ギュッと抱きついてくるリョーマの身体を優しく抱き締め返しながら、手塚も小さく眉を寄せる。
「ああ……俺も、……お前が好きすぎて、どうにかなりそうだ……」
「国光…」
「リョーマ……愛している」
「離れたくない…っ」
小さく呟かれたリョーマの切ない声に、手塚はギュッと目を閉じて込み上げてくる不安を抑え込む。
(離せるものか……絶対に……)
それでも、まだまだ非力な自分たちは、大人たちの決断に従うしかない時がやってくるのだろう。
「リョーマ……今は……忘れよう…」
こうして抱き合える今だけは、互いのことだけを想い合おう、と。
「ん……大好き、国光……」
リョーマの言葉が手塚の唇に吸い込まれてゆく。
その夜、二人は明け方近くまで身体を繋げ、何度吐精しても込み上げてくる愛しさに、際限なく互いを貪り合った。
疲れ果てて眠り込んだリョーマを見つめ、手塚は狂気に近い自分の恋情を再認識して小さく苦笑する。
「離れられないのは、むしろ俺の方だ、リョーマ」
今は届かない言葉をリョーマの耳もとでそっと呟き、手塚も静かに目を閉じる。
(俺たちを……離さないで欲しい……)
意識が途切れるまで願い続け、祈り続けた。
翌日から期末テストが順次返却され始めた。
一番最後に、一番気になっていた国語のテストが返され、その瞬間、リョーマは愕然と目を見開き、肩を落とした。
(やっぱ、前より点数が低い……)
1点だけではあったが、前回の中間テストの時よりも点が低かった。
(ごめん……国光……っ)
放課後、部活が始まる前に、誰もいない部室で手塚に報告をした。
「………そうか…」
「国光はクリアしたよね?」
「ああ」
しっかりと頷く手塚を見つめ、リョーマはまた肩を落とす。
「だが、今回お前はよくやった。国語の問題をみせてもらったが、あれはかなり難易度が……」
そこまで言って、手塚は急に押し黙った。
「国光?」
「………大石が来たら、先に部活を始めるように言っておいてくれ。急用を思い出した」
「え?」
「頼む」
それだけ言い、手塚は珍しく慌てたように部室を飛び出していった。
「国光……?」
リョーマは手塚の出ていった部室のドアを呆然と見つめ、やがて深く溜息を吐いた。
その日の夜に、手塚とリョーマは、彩菜と倫子をマンションに呼んだ。
「これが今回のテストの結果です」
テーブルに二人の答案用紙を広げてみせると、二人の母親は「まあ」と口々に呟いて答案用紙に見入った。
「すごいわね、手塚くん、満点が三教科も……他も全部90点以上じゃない!」
倫子が心底驚いた風に目を丸くする。その母を見て、リョーマは小さく溜息を吐いた。
「リョーマくんも、英語はさすがね。いくら外国で育っても、テストになるとてんでダメって言う子もいるのに、リョーマくんは綴りの間違いがひとつだけだなんて、すごいわ」
「ありがと、オバサン」
力無く微笑むと、彩菜が怪訝そうに首を傾げた。
「リョーマくん、元気ないわね。……他がダメだったの?」
優しく問われ、リョーマは頷いた。
「国語だけ……前よりダメだったっス」
俯くリョーマに、彩菜は優しげな視線を送る。
「リョーマくん……そんなに国光と暮らしていたい?」
「え……そりゃ……もちろんっス!」
バッと顔を上げてリョーマがはっきり言うと、彩菜と倫子は顔を見合わせてクスッと笑った。
「でもね、リョーマくん、オバサンは国光と約束をしたのよ。成績が下がった時は、ここを出て、それぞれの家に帰るって」
「………わかってます」
シュンと肩を落とすリョーマをチラリと見遣り、手塚が口を開いた。
「その件ですが、母さん、これを見てください」
「え?」
彩菜と倫子の目の前に、手塚は一枚のプリントを広げて見せた。
「なあに、これ?」
彩菜が穏やかに尋ねると、手塚は少し身を乗り出した。
「一年生の、一学期の定期テストの総合結果表です」
「一年生の?」
「こちらは中間テストのデータ。こっちは今回の期末のものです」
手塚が指をさすごとに視線を移動させながら、二人の母親は頷く。
「よく見てください。この、国語のデータを」
「え?」
訝しげに声を上げたのはリョーマだった。今さらそんなものを二人に見せてどうするのか、と。
「前回の中間テストの平均点はこれ。そしてこれが今回の平均点です」
「あら」
「ふぅん?」
二人の母親は、同時に意外そうな声を漏らした。
「ずいぶん今回は低いのね。平均点が10点以上低いなんて、今回はよほど難しかったのね」
「その通りです。でもコイツの点数は、1点しか下がっていません」
その場に、一瞬沈黙が流れた。
「………まあ」
最初に、手塚の言いたいことに気づいたのはやはり彩菜だった。
「そう。じゃあ、リョーマくんも条件クリアね」
「えっ」
リョーマが心底驚いたように身を乗り出した。
「平均点がこれだけ下がったのに、リョーマくんは1点しか下がっていないのよ?すごいじゃない。文句なく、条件クリアよ」
隣に座る倫子に「ね」と同意を求めると、倫子も満面の笑顔で頷いた。
「よく頑張ったわね、リョーマ。やっぱりあなたは手塚くんの傍にいて、変わってきたみたいね」
「母さん……」
「べつに私たちの手の届かないところに行くワケじゃないんだし、このままあなたは手塚くんと一緒にいた方がいいのかもしれないわ」
「じゃあ……っ」
リョーマが瞳を煌めかせて二人の母親たちに視線を向けると、それぞれが優しく微笑んで頷いてくれた。
「合格よ。国光が卒業するまで、ここはこのまま、あなた達二人で使いなさい」
「やったぁ!」
思わずリョーマが立ち上がり、ガッツポーズを取る。
「ありがとうございます」
手塚も嬉しさを隠しきれずに頬を染めて彩菜に礼を言った。
「二人とも頑張りやさんだから、きっとこうなるとは思っていたけど、本当によく頑張ったわね」
感慨深げに彩菜はそう言って、静かに立ち上がった。
「越前さん帰りましょうか」
「え?ぁ、ええ、そうですね」
彩菜と倫子に続いて手塚とリョーマも玄関まで来ると、彩菜が振り返って手塚に真っ直ぐな視線を向けた。
「今回は合格を出したけど、あなた達の学校生活や部活動に支障が出るようなことがあったら、いつでも不合格を言い渡しますからね。それだけは心しておきなさい」
「はい」
手塚とリョーマが声を揃えてきっぱりと返事をすると、彩菜の表情が和らいだ。
「じゃ、またウチの方にも遊びに来てね、リョーマくん」
「はい」
「手塚くんも、ウチに遊びに来て」
「はい、伺います」
それぞれの母親たちと約束を交わし、四人は微笑み合って「会議」を終えた。
ドアが閉まった後も、手塚とリョーマはしばらく無言のまま、その場に立っていた。
「……国光…」
「……ああ…リョーマ」
ゆっくりと視線を交わし、破顔する。
「やった!国光!ずっと一緒だよ!」
「ああ、リョーマ。本当によかった…」
歓喜の言葉を口にしながら、二人は固く抱き締め合う。
「国光、国光……離れないですんで…よかったね…」
「ああ……リョーマ……これからも、よろしく頼む」
「こっちこそ」
身体を少しだけ離して見つめ合い、堪らずに口づける。
「嬉しい」
「ああ、本当に…」
唇の隙間で呟き、また深く口づける。
「七夕さんたちが…オレたちの短冊見てくれたのかな」
「そうなのかもしれないな」
微笑み合い、抱き締め合い、また口づけ合う。
「リョーマ…」
「国光…」
見つめ合う視線に艶めいた輝きが生まれ、二人は何も言わずに寝室へと向かう。
やがて明かりの落とされた部屋は、微かな衣擦れの音と、甘い嬌声に満たされていった。
「どうして言わなかったんですか?とっくに部屋の契約は延長していたって」
駅に向かいながら、倫子は胸に抱いていた疑問を彩菜に問うてみた。
「それを言ってしまうと、世の中そんなに甘くはないのよって、説得力がなくなっちゃうから」
「ぁ、それもそうですね」
二人の母親たちは、顔を見合わせてクスクスと笑う。
「でも手塚さん、本当によかったんですか?うちの子、男の子ですけど」
「ウチこそ申し訳ないですよ、国光ったらあんな素敵な息子さんを独り占めしちゃって」
ふふふ、と笑みを交わして、ふと、二人は黙り込む。
「そりゃあね、孫のこととか、夢見なかったと言えば嘘になりますけど……あんなに想い合っているところを見せつけられたら鬼にはなれませんよ」
「ああ、あの短冊ですか…」
苦笑する彩菜に、倫子も小さく苦笑しながら頷いた。
数日前、手塚とリョーマが商店街の笹飾りに短冊を飾っているところを、彩菜と倫子は見ていたのだ。
時折二人でお茶する間柄になっていた彩菜と倫子は、偶然二人の姿を見つけて、声を掛けようとして思い留まった。
「あんなに…切なげなあの子の表情、初めて見ました」
「ええ、私も」
あの日の二人の表情を思い出しながら言う彩菜に、倫子も同意して頷く。
二人が立ち去ったあとで短冊を見に行った彩菜と倫子は、その願いの切なさに胸を打たれた。
『離れませんように』
ただその一言だけが書かれた短冊は、笹飾りの一番高いところで、風に揺れていた。
多くは望まない。
ただ二人が、このままずっと一緒にいられればいい。
純粋で、必死な想いが、その短冊から母親たちの胸に届いた。
「帰ってからが大変だったんですよ。ウチの主人ったら『なんで国光だけ戻らないんだ』ってしつこく言うから、いろんなコト言って、言いくるめちゃった」
ふふふ、と笑う彩菜に、倫子はまた苦笑する。
「ウチの旦那は、テニス以外はうるさくないから……今まで以上にテニスが出来る環境ならなんでもいい、とか言ってましたよ」
「まあ」
二人の母親は、声を合わせてコロコロと笑う。
「あの子が好きになった人が、手塚くんでよかった」
「いえいえ、こちらこそ、あの子がリョーマくんを選んだこと、誇りに思いますよ」
「これからもよろしくお願い致します」
「こちらこそ、末永くよろしくお願い致します」
頭を下げ合って、また笑い合う。
二人の母親たちを見下ろす空には、いつの間にか大きな月が出ていた。
「ぁ、七夕って明日だよね。今年は晴れるかな?」
「…晴れるといいんだが」
未だ熱の冷めないカラダを持て余し、ベッドの中から窓を見遣って二人は少しの間黙り込む。
「…天の川見えないね」
「月が、明るすぎるんだろうな」
それでも、明日の晩も晴れてくれるなら、空の二人もこうして甘い時間を過ごせるのだろう。
「ね、あとでまたアイス買いに行こ?」
「あとで、か?」
「うん。あとで」
「じゃあ、いいのか?」
ギシッとベッドを軋ませて、手塚がリョーマに覆い被さる。
「…アイスより甘いヤツなら、いいよ?」
見上げてくるリョーマの瞳は、天の川よりも美しく、生き生きと煌めいている。
「甘いだけじゃない」
優しくリョーマの舌を絡め取り、唇を離して手塚はふわりと微笑む。
「濃厚で、熱いヤツを」
「……ホント?」
リョーマがうっとりと目を細めて手塚を見つめる。
「お前だけが味わえる…」
「ん…」
自然に重なり合う唇から、二人だけの特別な夜が、また始まる。
「愛してる、リョーマ。これからもずっと…」
「オレも、愛してる、国光。これからも、ずっとずっと…」
『このまま、離れませんように』
言葉にはしない二人の願いが、甘い吐息とともに闇に紛れてゆく。
変わることのない二人の願いも、願うだけでは叶わぬ祈り。
だが願わなければ叶わぬ想い。
本当に願いを叶えるのは、他の誰でもなく自分たち自身なのだと。
いつか、そのことに気づけた瞬間、二人は何にも揺るがぬ、最強の恋人たちになる。
その瞬間は、きっともうすぐ。
終
20070707
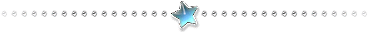
そしてこのあとに続く言葉をどうぞお聞かせください…
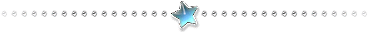
掲示板はこちらから→
お手紙はこちらから→
|